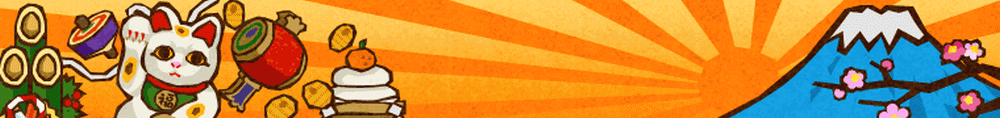2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年11月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
百人一首の指導・待たない
間をあけないためのポイントは、一つ。 待たない!ということです。 1ゲーム終了。 対戦相手変更。 意識のある子は、さっと代われます。そして、札もすぐに置いて準備完了。 ところが、意識の薄い子。声だしお手つきを思わず出してしまうような子ほど、さっきのゲームの感想を言ったりして、なかなか準備できません。 私の場合、交代の時間は、20秒とっています。「20,19,18・・・・」とカウントダウンしていきます。 明らかに、その子たちの責任ではなく、間に合いそうになり場合は、「3,2,1・・・0.9,0.8」というように時間を調節しますが、普通は待ちません。「1,0」と同時に、札を読み始めます。 当然、「待ってよぉ。」と言う声が最初のうちはあがりますが、待ちません。 かまわず読んでいきます。 待たないと、間に合わせようとして、交代も早くなります。 そして、交代の時に喋ることもなくなってきます。 スムーズに、無駄なくゲームが始められるわけです。 ただし、まだ準備ができていない組があるのがわかっていて、待たずに始めた時の1枚目の札は、ゆっくりと読んであげます。 ゆっくりと読んでいる間に、準備ができるように・・・です。 ここんとこ、けっこう大切な配慮です。
2005年11月30日
コメント(0)
-
百人一首の指導 間をあけない
リーグ戦になると、勝ち負けがよりシビアーになってきますので、またまた声だしお手つきの指導が必要になってきます。 これについては、思わず声を出してしまうお調子者の子が何度か注意を受けている間に静かになっていきます。 私のクラスの場合、問題は、読み手が読む間、1ゲームと1ゲームの間、リーグの班が変わる時に話してしまう子がいることです。 特に、ゲームとゲームの間、リーグの班が変わる時に喋ってしまうのです。「やった。勝った~。」「よし、これで9班や。」と言うような感じです。 ここで、喋ってもお手つきというようなルールにする手もあります。 それは、それでいいのですが、何となくクラスの子どもたちにあっていないような気がしました。 あまり、禁止事項を増やす気にもなれなかったのです。 では、どうするのか。 ポイントは、一つ。 間をあけないということです。
2005年11月29日
コメント(0)
-
リーグ戦の導入
初日は、生活班の中だけで、時間許す限り繰り返しおこないました。(・・・の続きです)「まぁ、今日は試しのゲームだから、あまり気にしなくてもいいんだけど・・。」と言いながら、何勝何敗か聞いていきました。 すると、1回も勝っていない子が何人か。「そうか、がんばってたのにねぇ。」と慰めながら、一言。「じゃぁ、0勝の子同士でやってみましょう。」 まずは、全員教室の後ろに行かせました。「0勝の子、こちらへ来て。」 0勝の子は1班のところに来させました。何回も何回もやっているので、0勝だった子は、3人。 とりあえず、その3人は1班のところに。「逆に、全部勝った子いますか?」 これは、ちょうど4人。 9班に座らせます。 このような感じで、負けの多い子を2班、3班に。 価値の多い子を8班、7班に座らせていきます。 このようにしていくと、ちょうど、勝ったり負けたりの子が残りますので、後は適当に空いている席に。 これで、ほぼ同じ勝率の子が同じ班に集まったというわけです。(この時点の勝率=その子の実力ではありません。たまたまいた班が強い子ばかりだったり、逆に弱い子ばかりだったりするからです。) そして、1セット(3ゲーム)やってみます。 ここで、またストップ。「その班の中で、一番勝った人、立ちましょう。勝った人は、一つ上の班にいきます。」 当然、9班の上はありませんので、9班の子はそのままです。「次に、一番負けちゃった人、立ちましょう。その人は、一つ下の班にいきます。」 これも、当然1班の下はありませんので、1班の子はそのままです。 このようにして、1セットごとに人の入れ替えをおこなっていきます。 これによって、ほぼ同じ強さの子が同じ班で戦うことになります。 これが、リーグ戦です。 やってみると、リーグ戦の方が楽しいのですが、いきなり強い子、こっちとか言うとやる気をなくしてしまう場合があります。今回のような導入方法が無理なくていいです。 ちなみに、リーグ戦のやり方(システム)自体は、法則化運動で学んだものです。
2005年11月28日
コメント(0)
-
百人一首第1歩・3
生活班というのは、座席が近くのものでつくっている4人単位の班のことです。 給食なども、この班で机をくっつけて食べています。 まずは、隣どおしが机を向かい合わせにして、勝負。 1字決まりの札7枚を机の上に出していきます。 いずれは、源平合戦形式でしょうと思っているのですが、最初はただ単にたくさんとった方の勝ち・・という方が単純でわかりやすいので、並べ方は特に指定せず。 きちんとそろえて並べるところもあれば、バラバラのところもあり。 それはそれでいいことにしました。 で、勝負が始まります。「一人勝負」では、「声だしお手つき」を意識できていても、いざ、対戦相手がいると「おっしゃ、とった!」「よしっ!」など声が出てきます。 すかさず言います。「はい、その場にしゃがみなさい。」 勝負する時は、椅子を机に入れて、立っておこなっています。 一度、ゲームがストップしているんですよ・・・ということを意識させるためにも、ここでしゃがませるわけです。(座らせるだと、またイスを出さないといけません。だから、しゃがませるなのです。)「今のように、声を出してしまうと、お手つきでしたね。今回だけはおまけします。」 ここで、声だしお手つきの確認をするわけです。 ゲーム再開。 しかし、この後も、お調子者の男子なんかは、何回も声を出してお手つきになります。「まぁ、今は試しのゲームですからね。」と、フォローを入れながらも、しっかりと1回休んでもらいます。「またかぃ」などとつっこみを入れながら、笑いをとって、越えだしお手つきの徹底をしていくわけです。(といってもそんなに簡単には徹底しませんが) 1ゲームを終わったら、班の中で、勝ったもの同士、負けたもの同士で試合。 2ゲーム目を始めます。 2ゲーム目も、声だしお手つきを中心に指導。 2ゲーム目が終わったら、3ゲーム目。 班の中で、まだやっていない子と対戦です。 これで、一通り終わるわけです。 わたしは、これを1セットと読んでいます。 3ゲームで1セットというわけです。 初日は、生活班の中だけで、時間許す限り繰り返しおこないました。 すると、1回も勝てない子が出てきます。 そこで、リーグ戦へと移行していくわけです。
2005年11月27日
コメント(0)
-
百人一首第1歩・2
クラスで百人一首をする場合、何と言っても押さえておかなければいけないのが、 声だしお手つきです。 ここんところを、しっかりと指導していると、楽しく、スムーズに百人一首ができるわけです。 だから、自分の机の上に札をおいて、自分でとるという「一人勝負」の時に、はっきりとさせておくのが一番いいわけです。 対戦相手がいないわけですから、子どもたちも比較的冷静にできます。 声だしお手つきがない状態が簡単にできるわけです。 ここで、もちろんほめておきます。 この「一人勝負」を2回ぐらいおこないました。(クラスの実態によって、変えていいと思います。) そして、次はいよいよ対戦です。 まずは、生活班で始めました。
2005年11月27日
コメント(0)
-
百人一首第1歩
7枚の一枚札ができたら、それぞれ、自分の机の上に広げさせます。 初めて、百人一首に触れる子もいますので、ここで説明です。 私が、使っている百人一首は、表には下の句のみ(これは普通の百人一首といっしょ)、裏には上の句と下の句がのっています。 とりては、表を机の上に置き、読み手は、裏を読めばいいようになっているのです。 さて、説明です。「百人一首は、上の句と下の句からできています。(ここで、百人一首について、簡単に説明しますが、略)・・・では、じっさいにやってみましょう。」 私のクラスの場合、1年生の時に五色百人一首をやっていたようですので、とりあえずやってみることにしました。「先生が、今から読みますので、実際にとってましょう。まずは、試しのゲームです。対戦相手はいないから、絶対にとれますよ。」 ほとんどの子がルールを理解しているとはいえ、転校生など、初めの子もいます。 ゆっくり始めることにしました。 まずは、一句。「むらさめの・・・」 早い子は、すぐに反応します。 そして、「やったー。」「とったどぉ。」というよけいな反応も。 うるさい。 けれど、そのまま、次の句へ。「せをはやみ・・・」「はいっ。」「おっし。」 またまた反応。「聞こえません。」「もう一回。」 うるさい声に対して、このような反応も。 待ってました。 ここでお手つきの指導が入ります。「違う札をとった時はお手つきといいます。次の回には休みになります。それと、さっき、とったどぉ・・とかの声で他の人が聞こえなくて、困っていたでしょ。これもお手つきにします。先生が、読んでいる間に声を出したら、1回休みです。」 そして、次からしっかりと声だしお手つきをとっていきます。 まず、ここんところをしっかり押さえるのが重要です。
2005年11月27日
コメント(0)
-
百人一首の指導のツボ
百人一首をする。と、まぁそれだけでも、それなりに子どもたちは熱中するのですが、何事にもそれなりのツボというものはあるようでして、そのツボのいくつかを紹介していきたいと思っています。 まずは、一つ目のツボ。 百人一首は全員に持たせる。 子ども(親)に負担させるのもなんだし、教師が毎年使うと言うことで、自腹を切って、クラスに何セットか用意して、とりあえずやってみようか!・・・でも、まぁいいんですが、実際に私も今までそうだったんですが、やはり、それぞれの子がマイ百人一首を持っている方が何倍もいいです。 かといって、やはり子ども(親)に負担させるもの気が引けるし、かといってクラスの全員分自腹を切って買ってあげるほど余裕もないし・・・という方がほとんどだと思います。 では、どうするのか? 自作の百人一首をつくっちゃえばいいんです。 これなら、必要経費は、画用紙代のみ。 なんとかやっていけるでしょ。 まずは、一字決まりのカードのみつくっちゃいます。 わずか7枚。 印刷もすぐにできます。 1枚、1枚に名前をしっかり書かせます。 これで、マイ百人一首のできあがりです。 私は、数年前に、東京で百人一首の指導の名人&鬼・・いや、とにかくすげーっ人(と私が密かに呼んでいる)から、この自作百人一首の元をいただきました。 無作為に100枚を何セットかに分けるのではなく、一字決まり、二次決まりというようなコンセプトでカードをセットに分けていくという発案者でもあります。 大変多くのことを学ばせていただきました。 今年、満を持して、ありがたく使わせていただいています。
2005年11月24日
コメント(0)
-
あ~飽きっぽいな。反省!
11月第2週。 金・土・日と仕事関係で家を空けて、更新しなかったのを皮切りに、なんか進みませんでした。しかも、大好きなレスラーの死もあり、ショックで何も手がつかず・・・(というのは大げさ) 気がつけば、もう22日。 えらい長い間更新していなかったんやなぁと反省しながら、今うってます。 この間も、国語で言えば「一つの花」の授業が「省略」というキーワードを軸に順調に進んでいたり、理科では巨大空気でっぽうで子どもたちに拍手喝采させたり、社会では自勉から出発したパトカーのハテナで盛り上がったり、そして、百人一首は相変わらずの盛り上がり、一字決まりの札なんかは、大人でも勝てないぐらいの猛スピード・・・など、それなりに学校では楽しく有意義に進んでいました。 それにあわせて、私の飲み会も順調に有意義に進み、ますます更新から遠ざかる始末。 でも、まぁ、いつまでもそう言うわけにはいかないので、またがんばります。 懲りずにおつきあい下さい。
2005年11月22日
コメント(2)
-
つがわ式記憶法2
具体的なことは、現時点ではあまり書こうとは思っていないのですが、いやはや面白かった。 斉藤一人 池谷裕二のお二人の著書を初めて読んだ時と同じぐらいのインパクトがありました。 ・・・というのも、今まで書けなかった「薔薇」という漢字が書けるようになったんですよぉ。(書けなかった一番の理由は、書く気がなかったというのが一番なのですが。) しかし、それでも一瞬で覚えてしまいました。 これは、凄いんじゃないかい? ちょっと、授業の中でも使ってみようと思いました。 一度、実践をくぐらせてまた報告していきたいと思っています。 お楽しみに。
2005年11月07日
コメント(0)
-
つがわ式記憶法
つがわ式記憶法って、ご存じですか? とりあえず、知っていて損はないと思います。 世界最速「超」記憶法 津川博義 講談社α文庫 本屋に行けば、たぶん、すぐに見つかるはずです。(平積みしていると思います。) この中に次のような記述があります。 覚えているうちに繰り返せ そう言えば・・・と思い返してみると、凄く納得。 このような内容がけっこう入っています。 実際に、授業でも使えそうなものも多数。 お薦めです。
2005年11月07日
コメント(0)
-
不思議の国 ニッポン
ラーメンズのライブで一番面白かったのが、 不思議の国 ニッポンというネタでした。 これは、ある国の学校で、日本の都道府県の特徴をレクチャーしていくというネタで、その中でそれぞれの県のことを面白おかしく茶化していく・・・といったものです。 例えば、三重県のことを「さんじゅう」と読んだり・・・、各地の名産品を絡めて笑いをとったりということです。 そう、あの名曲。 県庁所在地ロックンロールにつながるものがあるわけです。 各県の名産品としては、キリン一番搾りのプレゼントなんかもネタとして使えます。 テレビばかり見ているようでも、常に頭の中は教育のことでいっぱい・・・のたわせんでした。(笑)
2005年11月06日
コメント(0)
-
ラーメンズ遭遇
いやぁ、遅ればせながらラーメンズに今日初遭遇。 自分のつぼにズバッ入ってしまいました。 吉本のコテコテも好きだけど、あぁいうネタもいい。「不思議の国日本」のネタなんか、5年社会科の勉強にも使えそう。 ただし、このネタで笑えるのには、けっこう知識量が必要。 有田氏も言っていましたが、「知識がないと笑えない。」というのは、本当です。 単元の終わりにこのビデオを見せて、笑っているかどうかで、知識の定着を評価する。なんて、できそうです。 もちろん、本当にはしませんけどね。
2005年11月05日
コメント(0)
-
百人一首、学年でブレイク中!
私の学校では、担任がクラスだけを見るのではなく、もっと多くの目で子どもを見ていこうと、担任同士も授業を交換しておこなっています。 私と学年を組んでいる先生は、新卒2年目。・・ということで、教科の交換は、この先生が持ちたい教科を優先しておこなうことになりました。その結果、理科と体育の授業を交換することに。元気いっぱいのこの先生は体育を、元気が抜けて来だした私が隣のクラスの理科を持つことになりました。 さて、ここからが本題。 私が面白いと思うことは、隣の先生も面白いと思ってくれているようで、当然、隣のクラスでも百人一首をおこなっています。 これが隣のクラスでも、大ブレイク。 非常に喜んでいるようです。 今日の理科の時間。 縦割り活動のため、教室に帰ってくる時間がバラバラに。 なかなか全員がそろいません。 そんな時には、百人一首。 ただし、対戦バージョンは手間がかかります。 一人勝負 自分の机に札をおいて、とる練習をしていきました。 これなら、遅れてきた子も途中からでも自分の席でおこなえます。 1分あればできます。 一人勝負・・・今年、思いつきで始めたものですが、けっこういい。 お薦めです。
2005年11月04日
コメント(0)
-
天国言葉と地獄言葉
斉藤一人さん関係の本より 天国言葉と地獄言葉 要するに、プラス思考的な言葉を天国言葉。マイナス思考的な言葉を地獄言葉というわけですが、そのネーミングが凄い。 だけど、実際に子どもたちの言動を見てみると、地獄言葉までいかなくても、マイナス的な反応がおきることは、よくあります。 例えば、授業中、誰かが発表したときに、「え~っ、それはないわ。」「それはおかしいで。」というつぶやきが聞こえてくるようなことです。 これなんかは、地獄言葉までいかないでしょう。むしろ、友だちの発表をよく聞いているからこそ、出てくる反応ではあります。 しかし、それでも発表者にとってはマイナス的な反応であるのは確かです。 発表者にとっては、ちょっと嫌な気持ちになります。と言うわけで、このような場面が出ると、 マイナス反応はするな!と、私の一言が必ず入ります。 反対意見を持つのはいいのです。反対意見なら、その子の発表が終わった後、正式に発表すべきなのです。 つぶやき・・という形で、他の人が話している間に、反対意見を述べるからいけないわけです。 ただし、「そう、そう。」「俺もそう思う。」のようなプラス反応的なつぶやきはオッケーです。これは、発表者にとって、応援メッセージになっているからです。
2005年11月04日
コメント(0)
-
百人一首始めました
11月となり、2学期も残すところ、後2ヶ月。・・・ということで、百人一首を始めることにしました。 まずは、一字決まりの札、7首のみを画用紙に印刷。 それを子どもたちに配りました。 表には、下の句のみ。裏には、上の句と下の句どちらとも書いたものです。裏面を黄色に塗らせてできあがり。 一字決まりの黄色札が完成します。 このクラスの子の半分は1年生の時に、五色百人一首を経験していますが、もちろん、初めての子もいます。 そこで、まずは一人勝負。 机の上に、7枚の札を置いて、とる練習。 対戦相手はいません。 自分が作った札を自分がとるわけですから、他の人にとられる心配はありません。 最初は、この一人勝負を私の解説を入れながら、何回かしました。 これで、初めての子も百人一首のやりかたがわかったようです。 そして、次は、対戦。 一対一で勝負です。 7枚ですから、すぐに決着がつきます。 何回も何回もおこないました。 もう、子どもたちは、百人一首に夢中です。
2005年11月02日
コメント(0)
-
手と心で読む9
秋山君の言っていることは、もっともらしいのですが、何となくそれは違うだろ!・・という感じがします。 それは、聞いていた子どもたちもそう思っていたようです。 いろいろと反対意見が出ました。が、結局のところ、次のような意見としてまとめることができます。「1825年にルイ=ブライユがつくった点字」と「今、世界で使われている点字」は同じである・・・と考えれば矛盾はなくなる。 実際、そうでしょう。 しかし、秋山君のように感じる子がいても仕方がない、記述かもしれません。(というか、この点に気づいた秋山君の視点は凄いと言えるかもしれません。) だから、「それ」が指しているものの答えとしては、秋山君が反対したように「1 今、世界で使われている点字」は不親切です。 となると、どの答えがいいか? 1 今、世界で使われている点字 2 世界で使われている点字 3 点字 4 フランスのルイ=ブライユという人が考え出したもの 実は、この4つ、そこまでズバリといいのはないのです。○はあるけど、◎まではいかない・・といったところでしょうか。 当然、「では、◎の答えはないの?」と言う質問が出ました。 私の解は、次のようになります。 フランスのルイ=ブライユという人が考え出した点字 3と4の合体!です。(4の意見が子どもの話し合いで消えかかったときに、()で囲んだだけなのは、このような理由からです。) 以上、一つの発問で3時間の討論の概略を終わります。 ふぅ~、疲れた!
2005年11月01日
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-

- ♪~子供の成長うれしいなぁ~♪
- ☆クライミングロープ☆
- (2025-11-21 22:01:34)
-
-
-

- 子連れのお出かけ
- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…
- (2025-11-07 07:53:33)
-