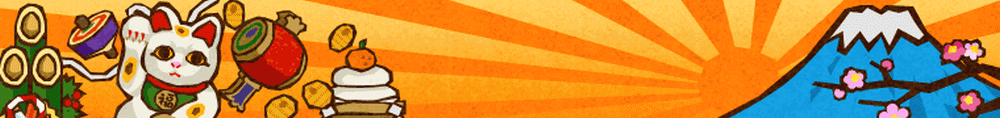2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年10月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
手と心で読む8
「日本で点字が使われたのは、1890年頃でしょ。今というのは、2005年だから、もし、「今」というのが正しければ、2005年にならないと日本の点字ができないと言うことになってしまうからおかしい。」 この秋山君の説明を私が解説することにしました。 「今、使われている点字を組みかえて使ったというのなら、日本で点字が完成したのは、今になると言いたいんですよね。でも、実際は1890年に組みかえて使っているのだから、今・・・と言うのが入るのはおかしいと、秋山君は言っているわけです。」 まぁ、こんな感じで話をしました。 実際は、黒板に図を書いたりして説明しましたので、文だけで読むよりも、もう少しわかりやすかったと思います。 ほとんどの子どもが意味がわかったと言いました。 しかし、意味がわかっても、反対!と言う意見は当然出ます。 実際、秋山君の意見には抜けている視点があるのです。 つづく
2005年10月31日
コメント(0)
-
手と心で読む7
いやぁ~。 阪神がロッテに4連敗。 ショックで仕事に手もつかず・・・というのは嘘ですが、続きを始めます。 いろいろと確認、横道にそれながらも、「今」の検討に入りました。 秋山君は次のように主張しています。「2005年、世界で使われている点字」を、日本では組みかえて使っているのなら、それまで日本では点字が使われていなかったことになっておかしいと思う。」 なるほど! 私には、彼の言いたいことがわかりました。 しかし、説明不足です。 他の子は、きょとん?としていました。「えっ、わからへん。」と言う声があがります。 念のため、聞いてみました。「今の秋山君の意見、意味がわかった人?」「意味がわからない人?」 私は、よく次のようなことを言います。「言っている意味がわかる=賛成 ではありませんからね。言っている意味はわかるけど、その意見には賛成できない、と言うことは当然あります。1+1=3と誰かが言ったとき、かれは一つものと一つのもをあわせたら、三つになると言っているんだなというのはわかりますよね。でも、その意見には、反対ということってあるでしょ。だから、意味がわからなければ、もう一度聞き返すんですよ。」 案の定、この時、意味のわかった子は皆無でした。 もう一度、秋山君に説明をしてもらいました。「日本で点字が使われたのは、1890年頃でしょ。今というのは、2005年だから、もし、「今」というのが正しければ、2005年にならないと日本の点字ができないと言うことになってしまうからおかしい。」 この説明で、唯一長州君だけが「アッ」という声を上げました。 他の子は、相変わらず?顔です。 そこで、私が解説をすることに。 続く
2005年10月31日
コメント(0)
-
手と心で読む6
アッ・・、一つ書き忘れていました。「世界で使われている点字」と「日本で使われている点字」は違う。と言うことが確認された後、「じゃぁ、これもおかしいな・・・。」と反対意見が出たものがありました。 3 点字です。 これでは、どちらの点字かわからないからです。シンプルすぎるというのです。 『それ』に『点字』を当てはめてみて、説明する子もいました。 今、世界で使われている点字は、一八二五年、フランスのルイ=ブライユという人が考え出したものです。日本では、『点字』を五十音に組みかえて使っています。 なんか、変?・・・というのです。 感覚的にもおかしい・・・と言うことで、3番の考えも( )で閉じてしまいました。
2005年10月26日
コメント(0)
-
手と心で読む5
「世界で使われている点字」は「日本で使われている点字」ではない。と言う確認はできました。 しかし、ここからが本番。 秋山君が続けます。「もし、今が入るのだったら、それは2005年に世界で使われている点字ということだから、日本でそれを組みかえた・・というのはおかしい。」「えっ?」と言う顔が数人。 後は、「わけわからん?」という感じです。 ほとんどの子が、秋山君の真意がわかっていないようでした。 こういうことでは、一番得意の長州くんが、「ちょっと、待って。意味がわからない。」と言っていたぐらいでした。(この後も、めずらしいことに、人一倍発表好きの長州君は一人発表せず。ずーっと考えて込んでいました。)つづく
2005年10月25日
コメント(0)
-
手と心で読む4
「ぼくは、1の『今』と言うところに反対です。」 続けて、こう言いました。「今・・ということは、2005年に世界で使われている点字と言うことだから、それをそのまま当てはめるとおかしくなると思う。」 ほとんどの子が、はてな顔でした。「今の発表の意味がわかった人?」 手が上がりません。「わからなかった人?」 ほとんどの手が上がります。あがらなかった子は、今、一生懸命考えてます・・と言う表情でした。 そこで、今回は、私が、一つ、一つ確認することに。「なるほど、この今というのは、いつか考えたわけですね。実際にこの文章が書かれたのは、もう少し前ですが、わかりやすく2005年としておきます。これはこれでいいですか。」 ここまでは、簡単。 問題はこれから。「まず、秋山君が注目した『世界で使われている点字』なんだけど、これは『日本で使われている点字』と同じものですか。それとも違うものなのですか。」 違うもの・・と言う答えが返ってきました。「そうです。『世界で使われている点字』は『日本で使われている点字』と違うわけです。ここは、けっこう大切ですよ。」「あっ。」と言う声が聞こえました。 この確認ができただけでも、秋山君の意見はお見事でした。 意識しないで読んでいるものにとっては、どれも同じ点字と認識していたはずだからです。 つづく。
2005年10月25日
コメント(0)
-
手と心で読む3
さて、4の意見のどこが問題になったかわかりますか? いろいろと、賛成、反対意見が出たのですが、結局主張したいところは1点。 4 フランスのルイ=ブライユという人が考え出したもの 「もの」では、わからん! もしかしたら、ブライユさんは、他のものも発明してたかもしれないじゃないか。 フランスのルイ=ブライユという人が考え出したやかんかもしれないということです。 なるほど!と言う子が大方を占めました。・・・ということで、この4の意見は、「4はおかしいということですね。」と言って、( )で囲みました。(5の意見は、黒板消しでスパッと消しています。こちらの方は、( )で囲んだだけ、実は私には思うところがあって、そうしたのですが、子どもたちは、この意見も消えた・・・と見ていたようです。) そして、この後のちょっとしたこだわりの意見から討論が長引いたのでした。「ぼくは、1の『今』と言うところに反対です。」 つづく
2005年10月23日
コメント(0)
-
手と心で読む2
3時間の討論を書き出すのと同時に、3日連続の飲み会が始まり、なかなか続きが書けませんでした。・・というわけで、話を戻します。 今、世界で使われている点字は、一八二五年、フランスのルイ=ブライユという人が考え出したものです。日本では、それを五十音に組みかえて使っています。 「それ」が指しているものはなんですか。 1 今、世界で使われている点字 2 世界で使われている点字 3 点字 4 フランスのルイ=ブライユという人が考え出したもの 5 小さな点のうき出たところ 5の意見というのは、「手と心で読む」の一番はじめの段落にある文章です。 点字の説明の部分を抜き出して持ってきたのでした。「だって、点字のことをわからない人がいるかもしれないから、こちらの方がわかりやすい。」 当然、この意見には反対が集中しました。「逆にわかりにくい。」「当てはめてみると、「日本では、小さな点のうき出たところを五十音に組みかえて使っています。」・・・になります。やっぱり、わかりにくい。」「それが指すところは、そんなに前にはないと思う。」「この文を読んでいる人は、この部分から急に読み出すことはない。前のところも読んで、ここまで来るはずだから、点字自体の説明は必要がないと思います。」 やっぱり、5は違います。 この意見はすっぱりと消しました。 次に問題になったのは、4の意見でした。 つづく
2005年10月23日
コメント(0)
-
手と心で読む・討論
3時間の討論は次の場所でおこりました。 今、世界で使われている点字は、一八二五年、フランスのルイ=ブライユという人が考え出したものです。日本では、それを五十音に組みかえて使っています。 ほんの2つの文章のみ。 ここだけで、3時間の討論になったわけです。 発問は、至って単純。 「それ」が指しているものはなんですか。 なんのひねりもない問題です。 最初、次の5つの意見が出されました。 1 今、世界で使われている点字 2 世界で使われている点字 3 点字 4 フランスのルイ=ブライユという人が考え出したもの 5 小さな点のうき出たところ まず、標的になったのは5の意見。 反対意見が集中しました。 続く
2005年10月20日
コメント(0)
-
指示語一つで3時間。
いやはや、大変なことをしてしまいました。 指示語がどの言葉を指すのか。 説明文の授業では、よくあるパターンの課題。 テストでも必ずと言っていいほどでてくるお約束の問題。 ちょっと遅れ気味の進度にもかかわらず、討論の内容が私にとって、非常に面白かったので、子どもたちが意見がきれるまで聞いてみようとほっといたら、3時間もかかってしまいました。 さすがに、これ以上、引っ張るのもどうかと思い、今日決着をつけたのですが、なかなか面白い討論が続きました。 教材は、4年生「手と心で読む」。 最後のページの文章です。 引用します。・・・と思ったら、教科書を持って帰ってくるのを忘れました。 詳細は、明日に。
2005年10月18日
コメント(0)
-
1週間って早いなぁ
気がつけば、月曜日。 ホント、1週間って早い。 運動会も終わり、実習生の実習も終わり、日常が戻ってきたはずなのに、1週間がアッという間に過ぎていってしまいます。 これは、年をとったせい? いやいや、充実しているからでしょう。・・と、無理矢理納得をさせ、久々の日記。 しかし、日常が戻ってきたせいか、クラスは落ち着きを取り戻しつつあります。 にぎやかな中にもしっとりとした感じもでてきだし、自分の理想のクラスの雰囲気に一歩一歩近づいています。 だいたい6月10月というのは、クラスが崩れ始める時期。(学級崩壊を起こすクラスでは、この辺の時期に始まることが多いようです。要注意の月なのです。) それが、逆にまとまってきた。・・・・ウン、いい感じだ。
2005年10月17日
コメント(0)
-
否定ができない2
なぜ否定できないのでしょうか? 不安だからです。 教材研究不足による教材解釈の不安。 子どもを否定すると、子どもとの距離が遠くなってしまうのではないかという不安。 このような不安があるから、否定できないのです。 では、どうすれば、否定できるようになるのでしょうか? 教材解釈の不安に対しては、「しっかり教材研究をしろ!」としか言えません。ただ、自分一人で考えるのにはどうしても限界があります。だから、本を読む。人と会う。人に聞く。・・・ということが大切になってくるわけです。 学び続けるものだけが、教える資格があるということです。 子どもとの距離が遠くなってしまうという不安。 まず、一つ目は気持ちの持ち方です。実習の先生には次のように言うことが多いです。 子どもを好きになろうとするのはOK!ただし、子どもに好かれようと思うな。 子どもに好かれようとすると、子どもにこびを売るような感じになる場合があります。子どもって、けっこうこういうのには敏感です。これではいけません。 二つ目は、否定できない人ほど、肯定もしていないのです。 普段から、子どものいいところを見つけ、しっかりほめている人。子どもたちの個性を認めている人。つまり、肯定している人は、ここぞという時にしっかり否定できるようです。 このような人は、子どもたちを否定する場面があっても、その1回や2回で子どもたちとの距離が遠くなることはありません。 つまり、子どもとの距離が遠くなってしまう・・という不安もなくなるというわけです。
2005年10月13日
コメント(0)
-
否定できない。
実習生の授業、休み時間の子どもたちとの過ごし方を見ていて、気になることがありました。 否定ができない。 例えば、国語の授業での場面。 課題に対して、いくつかの意見が出ます。 そして、討論。 討論慣れしている私のクラスでは、けっこう意見も出て、話し合いも続きます。 しかし、何やかんや言っても、やはり4年生。 論がおかしかったり、明らかに間違っていたりすることもあるのです。 ところが、一生懸命発表している子を見て、あるいは間違っていると指摘されたらかわいそうという気になって、もしかしたら教師の教材研究不足から、ダメな意見を否定することができないのです。 これは、休み時間でも同じ。 何かいけないことをしていても、何となく流してしまう。 こういうことが何回かありました。 否定できない。 これは、新任の先生、またはやる気のないベテランの先生にも言えることです。 では、なぜ否定できないのでしょうか? どうすれば、否定できるようになるのでしょうか? 続きは、次回。
2005年10月12日
コメント(0)
-
流行廃り・・・ふぉ~
子どもの世界では、流行廃りが非常にはっきりしています。 1学期、あれだけ流行っていた「あるある探検隊」。 今では、誰もやっていません。 今、流行っているのは、 ふぉ~ そう、レーザーラモンHGが一番人気です。 昔、昔、彼が吉本新喜劇の端役で出ていた頃から注目はしていたのですが、まさか、小学生にまで浸透するような芸人さんになるとは思いもしませんでした。 一発屋で終わるのか? それとも、藤井隆のように、際物で出発しながらも生き残るのか? どうなる、ふぉ~!
2005年10月12日
コメント(0)
-
ふぅ、一段落・・・(^_^;)
先週は、鬼ような忙しさでした。 まず、一番の誤算は、9月末が締め切りだった研究紀要の原稿を完璧に忘れていたこと。 催促され、大慌てで執筆。 社会科 地域教材 A4 40文字×40行 6枚 しかし、地域教材は最近はやっていません。 昔の資料を引っ張り出すのに一番時間がかかりました。 次に、実習生の指導。 最後の週、力も入りました。 涙を誘うお別れ会もでき、めでたしめでたし。 また、社会見学などもあり、 ラストは、小学館の原稿。 笑育流 保護者会の原稿 こちらも6ページ。締め切りは、週末。 一応締め切りぎりぎりセーフに、とりあえずメール送信! 構想は前々からできていたのですが、ライフワーク的な原稿ですので、これに一番エネルギーが注ぎ込まれました。 そして、3時間の睡眠で、週末は千葉へ・・・ 3日間、研修会に参加。 昨日の夜遅く帰ってきました。 とにもかくにも、ふぅ一段落です。・・・・(^_^;) 3日連続の研修会参加。
2005年10月11日
コメント(0)
-
二重目標 ドラゴン桜より
前回、前々回で書いたことと同じようなことをドラゴン桜の中でも見つけました。 どこかで使えそうな気もしますので、とりあえず引用(紹介)しておきます。 阿院先生が井野先生に話しているシーン 目標を立てるときは二重に準備するといいのでヒ・・・ 普通は誰もが「○○を○○だけやるぞ」と目標をたてます 「物理の問題を毎日15問解くぞ」というようにね でも大抵は三日坊主で終わる なぜなら目標がただの願望になっていて昨日できなかったから今日は倍やるぞなどと無理を重ねてしまうから そして一つ失敗するとすべてがダメだと思って諦めて投げて出してしまう これを防ぐために目標を二重にするのでヒ 最低限なしとげたい目標と・・・ もしできたら理想的な目標の二つを用意するのでヒ モーニング 2005 No・43
2005年10月03日
コメント(0)
-
美味しいところから
前回、次のようなことを書きました。 とりあえずの最低ライン(エイサー)をクリアーしたので、理想のラインまで行こうと、時間をかけた感じです。 実は、この手法、私はよく使います。 運動会の表現などの場合、まずメインの踊りを完成させる。そして、もし時間的、精神的な余裕があればその前後を凝る。または、+αの演技を付け加える・・・といったことをするのです。 それを、入場から順番に指導していくと、メインを指導する頃には時間がない!飽きている!といったことになったりして、せっぱ詰まった状況になってしまう恐れが出てきます。 美味しいところ(大切なところ)からおこなう。 大本、中心さえしっかりしていれば、細かいところなんてどうでもいいわけです。 これは、運動会の表現の指導だけでなく、他でも使える原則でもあります。
2005年10月02日
コメント(0)
-
運動会終了!
運動会が終わりました。 エイサーも気合いの入った踊りを見せてくれたようで、大成功!「4年生が一番よかった。」と、いっしょに仕事をしていた6年生が何人も話していました。 さて、今回の運動会の練習、時間をかけました。 ここ数年で一番かけたはずです。・・・と言っても、子どもたちがうまく動かないから、踊らないなから、時間がかかったというのではなく、むしろ、その逆。 エイサーの踊り自体は、2週間前には完成していました。 まぁ、ぶっちゃげて言うと、 毎日踊りたかったからなんです。 あと、メインのエイサーが早く仕上がったので、入場なんかも凝ったりもしました。 とりあえずの最低ライン(エイサー)をクリアーしたので、理想のラインまで行こうと、時間をかけた感じです。 おかげさまで、楽しい練習をすごすことができました。(リレーの練習もかなりできましたし・・・) そう言えば、昔はどれだけ短い時間で指導ができるのかばかりが気になっていました。短い指導時間の方がいい指導・・・というイメージがあったのです。 もちろんダラダラとか、無計画な指導で指導時間が長くなるのはいけませんが、濃くて楽しい指導が続くのなら、そちらの方がいいのに決まってますよね。
2005年10月02日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- 障害児と生きる日常
- 特別支援学校で段ボールの車制作。
- (2025-11-19 21:40:51)
-
-
-

- 子連れのお出かけ
- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…
- (2025-11-07 07:53:33)
-
-
-

- 子育て奮闘記f(^_^;)
- ☆チューブ式ブロック☆
- (2025-11-23 13:59:29)
-