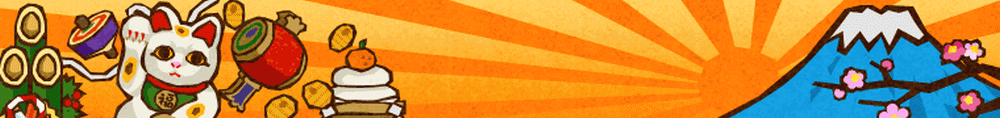2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年06月の記事
全53件 (53件中 1-50件目)
-
プラスαをほめまくる
今日、習字をおこないました。 みなさんも、自分の習字の時間を思い出していただければわかりますが、4年生ぐらいの場合、気をつけていてもかなりいろいろなところに墨をとばします。 たわせん学級も、ご多分に漏れず、床を汚したりする子がいます。 こぼした子は雑巾を急いでとってきてふいています。 ところが、問題は、誰がこぼしたのかわからないもの。 気がつけば、床に墨の後が・・・というパターンです。 片づけている時にこぼしたのでしょう。 たぶん、こぼした本人にも自覚がないと思います。 そんな時、どうするのか? まず、教師が動き出します。 雑巾をとって床を拭くのです。 教師がしていると、次のような子が何人か必ず出てきます。「手伝おうか?」 もちろん、手伝ってもらいます。 2,3人集まってきたら、後を任せます。 廊下に出てみると、廊下にも墨の後が・・・ 片づけが終わって、ぼーっとしている子に声をかけます。「雑巾を持って、ふくの手伝ってあげて。」 最初に、何人かが自主的にふき始めているので、これらの子も私が思っていたより、すっと動きはじめました。 こんな感じで、習字の片づけが終わった子は、何らしかの後かたづけの手伝いをする状態に持ち込みました。 そして、授業の最後に次のようにいって締めます。「床に落ちた墨をふいたり、自分から進んで片づけたりした人手をあげてください。すばらしいですね。先生から言われてからした人も手をあげてください。これらの人も、嫌な顔をせずに手伝ってくれていました。このようにプラスαの動きができると、みんなが居心地のいいクラスになりますね。これからもがんばってください。」 まず、さっと動き出した2,3人を特にほめる。 4年生ぐらいだと、他の子も「よし、俺も・・」という気持ちになって、いい動きをまねします。 そして、それでも動き出さない子には、教師が無理にでもさせて、(無理にさせているのにもかかわらず)後でほめるのです。こうすると「やらされた。」という感じよりも「ほめられた」という印象が強く残りますので、次のいい動きにつながりやすくなるのです。 とにかく、ほめて動かす。 教師も気分がいい。子どもたちも気分がいい。 いいことずくめです。
2005年06月30日
コメント(0)
-
力を伸ばすには、チェック
漢字テストがあります。 ここで、子どもたちにいい点を取らせる(つまり、漢字を覚えさせる)時の一番のポイントは、教師のチェックです。 以前にも書きましたが、子どもたちは意外と自分の書いた漢字が間違っていても気がつきません。 一生懸命、間違った字を練習してきたりします。 だから、その間違いをチェックして、訂正させるのです。 これだけでも、点数は大きく関わってきます。 私のクラスでは、漢字のテストがある場合、前日にテスト練習の宿題が出ます。 そして、朝一番にそのノートを提出させています。 子どもたちが朝の会をしている間に、全力でノートチェック。 間違って練習している子にはやり直しをさせます。 ちなみに、この漢字練習の宿題を忘れた子にはテストは受けさせません。(テストは、放課後残って受けることになります。みんながテストをしている時間に練習をして、放課後居残りというわけです。やっぱり居残りは嫌なようで宿題忘れも減るし、練習もせずにテストを受けるということもなくなるしで、一石二鳥です。) これは、漢字だけの話しではありません。 子どもたちの力を伸ばすには、いかに、いいタイミングで教師がチェックをして、いいアドバイスができるかにかかってきます。 算数の計算でも水泳でも絵の指導でも調べ学習でも全て同じなのです。
2005年06月30日
コメント(0)
-
「プロレスから学ぶ学級経営」のその後
4日間にわたって、再録した「学級経営に大切なことのほとんどは四角いリングから学んだ」も、前回でとりあえず終了。 この「プロレスから学ぶ学級経営」というテーマはけっこう自分ではお気に入りでした。 そして、その続編として考えたのが、 つんく♂から学ぶ高学年女子とのつきあい方 難しいお年頃の女子とどう接していったらいいのか? これに失敗すると1年間やな雰囲気のクラスになったりします。 上手なつきあい方・指導の仕方を、モー娘をうまくプロデュースしていたつんく♂から学ぼうというものです。 なんとなくコピーがいい感じでしょ。 さらに、考えたのが、これ。 吉本新喜劇に学ぶボケとつっこみの授業術 まぁ、これも当時ノリで考えただけなのですが、実は、これが現在の笑育の元になっています。「笑いを育てる」「笑顔に育てる」といった「笑育」の概念につながっているのです。 つまり、「プロレスから学ぶ学級経営」があったからこそ、「笑育」があるというわけです。・・・と、うまくまとまったところでこのシリーズは終わります。 長い間おつきあい下さり、ありがとうございました。
2005年06月29日
コメント(0)
-
受けの美学4
ここまでは、対戦相手を「子ども」に置き換えて、教師から見た視点で考えてみましたが、今度は、これを「子ども→子ども」に置き換えてみます。 つまり、 相手の技をうけても平気なだけの基礎体力 対戦相手に対する信頼感 相手のいいところも引き出そうという気構え そしてもちろん自分自身を主張できるだけの技術の「対戦相手」のところを「(クラスの)友だち」というように置き換えてみるんです。 こうなります。 友だちの技をうけても平気なだけの基礎体力 友だちに対する信頼感 友だちのいいところも引き出そうという気構え そしてもちろん自分自身を主張できるだけの技術 このような学級を創っていきたいなぁと思っています。 みなさんは、どのような工夫をされていますか? お教え下さい。・・・という感じで終わっています。 この発表の後、研究会で参加者の方々から意見をいただいているはずなんですが、ほとんど記憶に残っていません。(笑) 友だちの技をうけても平気なだけの基礎体力 のところで、「自分自身に対する自信をつけさせなければならないと思っています。」と話したことと、仲間内から「これは面白い!本になったら(誰が買うねん!)絶対買うよ。」といわれたことだけは覚えています。 おしまい。
2005年06月29日
コメント(0)
-
受けの美学3
(前の続きです) 子どものいいところをも引き出そうという気構え この場合は、「いいところをも」ではなく「いいところを」の方がいいですね。 何と言っても、主役は子どもなんですから。 では、「いいところを引き出す」のには、どうすればいいか。 私の場合は、まず子どもを見ることを心がけています。 ただ、漠然と「見」ようとしても、なかなかできるものではありませんので、ちょっとした工夫はしています。 例えば、学級通信です。 例えば、座席表です。 がんばりファイルというのをした年もありました。(現在の俵原学級では、各月ごとの自己評価と、すげぇーチャンプというもの中心にしています。すげぇーチャンプについては、またいずれお話しできると思います。) そして、もちろん自分自身が主張できるだけの技術 これは教師はあまり必要ないかと思います。(といいながら、音楽会では金ぴかの衣装を着て、マツケンサンバなどを歌ったりしているのですが・・・) つまり、勝敗にこだわってはいけないと言うことです。 勝敗にこだわって、相手の技をよけるボクサー型になってはいけないのです。 勝敗にこだわらず、相手の技をドーンと受けるプロレス型の教師にならなければいけないのです。(つづく。・・・次でたぶん終わります。)
2005年06月28日
コメント(0)
-
受けの美学2
「相手の技をうける」と言うことは、次のことができていないといけないのです。 相手の技をうけても平気なだけの基礎体力 対戦相手に対する信頼感 相手のいいところも引き出そうという気構え そしてもちろん自分自身を主張できるだけの技術 ざっとこれだけのことができていないといけないのです。「相手の技をうける」ということ、一つとっても、このことが如何にプロでないとできないことかがわかると思います。 そして、これだけのことが教師にできているか? 対戦相手を子どもに置き換えてみるとわかりやすくなります。 やってみましょう。 子どもの技をうけても平気なだけの基礎体力 例えば、授業で言えば、子どもがどんな発言をしようとも、受け止めるだけの教材研究ができているのか・・ということです。 もちろん、生活の場面でも同じことが言えます。 平気なだけの基礎体力がないと、子どもの言動に思わず「カッ」と感情的になってしまいます。 こういうときは、思わず反則技が飛び出してしまい、大変なことになってしまいます。 子どもに対する信頼感 プロレスの技にボディプレスというものがあります。 前座の若手も使うほんの基本的な技です。 相手を抱え上げて、背中からリングにたたきつけます。頭からではありません。そんなことされたら死んでしまいます。いくら鍛えても、頭や首はきたえようがないからです。 しかし、レスラーは相手を信頼して体をあずけていきます。 こういうことです。 無条件に相手を信頼するということです。・・・・この後もつづく
2005年06月28日
コメント(0)
-
受けの美学
・・と、研究紀要には書いたのですが、実際の発表の際には次のように続いていました。 紀要では、ごちゃごちゃと書いたのですが、結局、プロレスから学んだことは、次の7点にまとめることができます。 1・受けの美学 2・自分のキャラクターを確立する。 3・常に観客を意識する。 4・自分の大技を持つ。 5・技と技をつなぐ基本も大事。 6・時にはヒール。時にはベビーフェイス 7・想像力で楽しむプロレスファン。 では、上の事柄から、1の「受けの美学」について、補足してみます。 プロレスとはつまるところ、「受けの格闘技」です。(注・格闘技という言葉につっこみたい人もいると思いますが、あくまでも日本では格闘技・・ということで。) これは、「相手の技をうける」という意味の他に「観客に受ける」という意味も含んでいます。「相手の技をうける」ということも、実をいうと観客のことを意識しているからこそ、出てくる発想なのです。) つまり、プロレスとは(1)相手の技をうける格闘技(2)観客に受ける格闘技といえることができるのです。 この後もまだまだ続きます。
2005年06月27日
コメント(0)
-
学級経営に大切なことのほとんどは四角いリングから学んだ3
発表紀要の原稿前回の続きです。(学級経営での必要な知恵は、大学の教育学部という山のてっぺんにあるのではなく、大阪府立体育館の四角いリングにあったのである。私は、そこで何を学んだろうか。) 盛り上がる試合には、ある法則性があるということ。 対戦相手が、コーナーポストに上ったら、相手の技をよけずに受け止めてあげること。 リングを広く使うこと。 2階席のお客まで、意識して試合をすること。 ロープに振られたら、素直に走ること。 そして、戻ってくること。 対戦相手を尊重しなければ、いい試合はできないこと。 レフェリーは、必要以上に目立たないこと。しかし、試合のできを左右するのはレフェリーだということ。 同じ技を出しても、使う人によって、その説得性が違うこと。 その日の興業の出来不出来は、メインイベントで決まること。 対戦相手のよさを引き出すこと。 いっしょになって、盛り上がること。 ベストコンディションで試合にのぞむこと。 決して、最後まであきらめないこと。 悪役ほど、実はいい人であること。 何年か先を想像しながら、前座の試合も真剣に見ること。 基本が大切だということ。 いいレスラーは、自分の決め技を持っていること。 地道な技も大切だということ。 いい試合は、リズムがいいこと。 覆面レスラーの正体は、知っていても、だまされてあげること。 明日もがんばろうという気にさせてくれること。 決して、相手が、次の日、試合ができなくなるような危ない反則はおこなわないこと。 プロレスラーという職業にプライドを持つこと。 常に、観客に向けて、何かを訴え続けること。 24時間、プロレスラーであること。 教師として知っていなくてはならないことは、ほとんど、この中に何らかの形で触れてある。ここには、人にしてほしいと思うことは自分もまた人にたいして、そのようにしなさいというマタイ伝の教え、いわゆる「黄金律」の精神や、多くの学級経営での心構え、はたまた授業の基本は述べられている。 この中から、どれとなりと項目を一つ取り出して、教師向けの言葉に置き換えてみれば、きっと、そのまま通用する。 明快で揺るぎない。・・・・という感じで、以下、具体的に実践につながっていくのでした。 パチパチパチ。
2005年06月27日
コメント(0)
-
学級経営に大切なことのほとんどは四角いリングから学んだ2
発表紀要の原稿をまず、きりのいいところまで再録します。 ある時、次のような言葉を耳にした。「教室というのは、子どもたちの学習の場であり、そして、生活の場である。」 そうだ。 その通りである。「学級経営が大切なんだ。」 そして、私はプロレス会場に行った。 あるSF作家の言った言葉が、頭の中に浮かんだ。「プロレスは人生の縮図である。」 と、そこで私は、充実した楽しい学級経営をするために必要なことは、すでにあらかた知っているのだと言うことに思い至った。しかも、それはそんなに難しいことではない。わたしには、わかっている。もうずっと前からわかっていた。なら、わたしはそのわかっているところに従っておこなっていたか、となるとこれは、また話しが別だけども・・・・・。目から鱗が落ちて、私はこう考えた。 教室で教師は、どう生きるか、どのようにふるまい、どんな気持ちで日々を送ればいいか、本当に知っていなくてはならないことを、私は、ほとんど、四角いリングから学んだ。学級経営での必要な知恵は、大学の教育学部という山のてっぺんにあるのではなく、大阪府立体育館の四角いリングにあったのである。私は、そこで何を学んだろうか。 (つづく)
2005年06月26日
コメント(0)
-
学級経営に大切なことのほとんどは四角いリングから学んだ
昨日、部屋の整理をしていたら、10年ほど昔、ある全国的な規模の研究会で発表した原稿が出てきました。 教師誌や研究会などでちょこちょこと論文を書くことも多いのですが、その中でもお気に入りの論文です。 ファイルを無くし、原稿自体を探していたのですが、探しているときにはみつからず、他のものを探しているときにふっと出てきたのです。 久しぶりに読み返してみたのですが、これが結構面白い。 発表タイトルは、「学級経営に大切なことのほとんどは四角いリングから学んだ」です。 あのベストセラー「人生に必要な知識は全て幼稚園の砂場で学んだ」(ロバート・ブラハム)のパロディです。「四角いリング」というのは、当然プロレスのことです。 つまり、プロレスから学んだ学級経営・・・と言う内容の論文です。 今から思えば、よくこんなふざけた内容のものを発表させてもらえたものです。 主催者の梶田叡一さんに感謝。 また無くさない前に、研究紀要の原稿をこのブログに再録しようと思います。 ほとんど、自分のための自己満足ですが、おつきあい下さい。 再録は、次回と言うことで・・・
2005年06月26日
コメント(0)
-
天丼で定着2
35+29=64をつかって、35万+29万を計算しましょう。と言う問題。 どうしてもわからない子を「天丼」でできるようにさせる。 こんな感じです。 念のため、もう1回します。 35 + 29=64と板書して、「35万+29万は?」と言いながら、万の所を書き加えます。 反応の早い子が手をあげます。「64万です。」「正解。すごい!わかった人(手をあげて)」と聞きながら、64の後ろにも万を書き加えます。(この時点では、手をあげていない子がまだ何人かいます。) 35万+29万=64万と書かれています。すぐ、その下に次のように書きます。 35万+29万=64万 35 +29 =64「念のため、もう1問。35億+29億は? 3秒でできないとダメです。」「わかった~。」 さっと手が上がります。万の時と同じように35の後ろに億を書いていきます。「正解。いいねぇ。できた人?」(まだ、この時点でも1人)「もうやらなくてもいいけど、念のため、問題です。」「え~っ。」と言う声があがるが、顔は笑顔。「35兆+29兆は?」 黒板には、同じように書いていきます。 テンポ良くおこないます。 黒板を見ると今までの式と答えが残っています。 何となく雰囲気はわかります。 ここで、一番「?」だった子の手が上がりました。「64兆です。」「お見事!でも、念のため、もう1問。」 念のため、もう1問・・・に反応して、その子も笑っています。 もう大丈夫。 でも、しつこく、まだまだやりました。「4年生のレベルを超えた問題です。35京+29京は?」 実は、レベルは全然越えていません。 ノリと勢いでこの後、どんどん桁があがっていきました。 ほんの10分ほどの時間です。「天丼」・・・繰り返しで定着させた実践でした。
2005年06月25日
コメント(0)
-
天丼で定着
同じパターンを繰り返して、笑いをとることを専門用語で「天丼」と言うそうです。 この天丼は、知識の定着にも非常に効果的です。 1回よりも2回、2回よりも3回練習した方が身につく・・というのは何となくわかりますよね。 さらに、ここに笑いが加われば恐いもの無し。 楽しく意欲的に学習活動に取り組むわけです。 35+29=64をつかって、35万+29万を計算しましょう。と言う問題をしました。 ノーヒント、さっと読んだ時点でわかる子は、クラスの30%いればいいでしょう。じっくり読んで、一生懸命考えて(ちょっとヒントあげて)また30%。 答えを聞いて、友だちの解説を聞いて後20%。 残りの子は、「??????」という感じでした。 さて、ここからが教師の出番。 教師の説明が入りますが、最後の1人はまだ「?」の顔。 こうなれば最終手段です。 理由がわからなくても、とりあえず解けるようにする。 後になって、意外と理由もわかってくる場合があるのです。 また、こういう子には、問題が解けた・・と言う達成感を味合わせることが大切だからです。 で、結果を先に述べると、この子はしっかりと解けるようになりました。 それも、楽しみながら。 その指導法は、天丼です。 具体的な事例は次回の日記で・・・(お出かけの時間が迫ってきました。すみません。)
2005年06月25日
コメント(0)
-
最終回見た?
4月から始まったドラマもいよいよ最終回を迎える時期になりました。 現在、4年生担任なのですが、これぐらいの年の子どもたちはその成長度合い、興味の方向がけっこうバラバラで、月9を欠かさず見ている子から、ムシキングが大好きな子までいろいろなパターンに分かれています。 昨日、最終回だったアタックNo,1。 見ている子は、見ているが、興味のない子は全くなし。 私が猪熊監督のまねをしてもわかっているのは、一部の子のみ。(けっして、似ていないからではないと思うのですが・・・) でも、それでいいと思っています。 わかるやつだけわかればいい! わからなくても、何となく雰囲気で笑ってくれています。 まぁ、笑いってそんなものですね。 ちなみに、私が今、一番はまっているドラマは、仮面ライダー響鬼です。
2005年06月24日
コメント(0)
-
声が落ちる
音読をする際、姿勢について注意することがよくあります。 背筋を伸ばして。 胸を張って。 などなど・・・・ 基本的には歌を歌うときの姿勢と同じなんですが、音読の場合、 目線が下がることがよくあります。 暗唱している場合は別ですが、教科書を見て(読んで)音読の場合、どうしても視線が下がってしまうことが多いのです。(歌の場合は、指揮者の方を見るので、普通は目線が下がることはありませんよね。) 実際、目線が下がると、声が落ちる感じがします。 顔を下げるな。 下を向かない。 音読も人生もいっしょです。(少し大げさかな?)
2005年06月24日
コメント(0)
-
算数でも音読
一石二鳥作戦は、水泳だけではありません。 算数でも、音読をおこないます。 姿勢を正し、声を大きく出します。 まずは、算数の教科書音読。 私が音読した後、続いて子どもたちにも読ませていきます。 声がそろわなかったら、もう1回。 何回かおこないます。 特にしつこくするのが、教科書の太字、つまり、定義の部分。 ここは、声がそろっていても何回もおこないます。 算数が苦手な子は、どうしても算数の時間は受け身がちになります。 ところが、音読をするとなると、どの子も主体的に取り組まないといけません。この意識の違いだけでも、算数から遠慮したいなという子には大きな効果があります。音読をすることによって、ぼーっとしている時間が少なくなっていくのです。脳の働きも活性化していきます。 とにかくいいことずくめです。 どの教科でも、音読。 お薦めです。
2005年06月23日
コメント(0)
-
息継ぎのコツは、いいカッパ
水泳が始まりました。 私の担当は、水泳が苦手な子。 具体的に言えば、息継ぎができない子ということです。 さて、この息継ぎのコツですが、一番のポイントは次のことです。 水の中で息を吐ききる。 泳ぎが苦手な子ほどこれができていません。 そして、この「水の中で息を吐ききること」の大切さもわかっていません。頭でわかったからと言って、すぐにできるようになるものではありませんが、理解した上で練習するのと、訳のわからないまま練習するのとでは上達度も違ってきますので、なぜ、これが大切なのかの説明もしました。「柔らかいペットボトルを水の中でつぶしてぺちゃんこにして空気を出します。水の外に出すと、空気が勝手に入ってきて元に戻るでしょ。これなんですよ。 つまり、水の中で空気をはききると、顔を上げて口を開けただけで空気が入ってくるんです。 ところが、水の中で空気をはいていないとどうなるか? 1・口を開ける 2・息を吐く 3・空気を吸う 3つのことをしないといけないんです。 すでに水の中ではいていると、空気を吸うこともしなくていいんです。口を開ける・・・の1つの動作のみ。 どっちが楽かわかりますよね。」 子どもたちは一生懸命聞いていました。 「それでね。頭の中では次のように唱えるんです。 水の中で息を吐きながら、「いいカッ」 顔を上げて、口を開けながら「パ」 いいカッパ・・です。」 プールサイドで、音読開始。 水にはいる前に、みんなそろって言いました。「いいカッパ!」
2005年06月23日
コメント(0)
-
プールでも暗唱
水泳が始まりました。 この時期の水泳で一番つらいのがシャワー。(みなさんも、身に覚えがあるでしょ。) 誰が名付けたのかしりませんが、毎年この時期のシャワーは、こういわれています。 地獄のシャワー ほんと、シャワーの水がむっちゃ冷たいんですよね。 だから、子どもたちは申し訳程度に体をぬらし、すぐに外に出ようとします。 しかし、教師の立場として、それは阻止せねばなりません。 10を数えさせたり、「頭ごしごし、腕ごしごし・・・」と言わせながら、いっしょに入って指導したり・・・・。 いろいろな方法を今までとってきました。 で、今年の方法は・・・と言うと、タイトルの通りです。 寿限無を唱えさせたのです。 学年のほとんどの子がすでに暗唱しています。 と言うわけで、現在、暗唱をすることが好きな子が育っています。 だから、普通に数を数えさせるよりも、子どもたちも一生懸命やります。 結果的に、楽しく地獄のシャワーを浴びることができるのです。 そして、暗唱の力も伸びる(?) まさに、一石二鳥。 しかし、シャワーを浴びながらみんなで寿限無を唱える姿・・・。 一歩離れてみてみれば、ちょっと異様かも(笑)。
2005年06月22日
コメント(0)
-
お笑い研究クラブ2
昨日のお笑い研究クラブで、4年生のネタを見た6年生の一言に、こんなのがありました。「下ネタはダメ。」 下ネタと言っても、小学生の下ネタですから、「おしり」とかのかわいいものですが、なんか6年生の本気度にはビックリしました。 本気度と言うより、本格派指向というべきかもしれません。 実は、6年生だけが、クラスではしゃぐお調子者タイプではないのです。(でも、そう言うタイプの方が最終的に本物になるんでしょうね。) 本当にお笑いのことが好きなんでしょう。 実際、この6年生、けっこういいセンスをしています。 批評の一つ一つが的確なんです。 私が最後に言おうとしていたことをきっちりと話してくれます。 今回は、6年生の批評をうけて、次のように話して終わりました。「ネタについての細かいつっこみどころ、演じている人の動きについては、また作り直したり、練習していけばいいんだけど、先生から見ていて、これだけは一つ気をつけてほしいことがありました。 6年生も言っていた やっている者が笑っている ということです。 これは、直してほしいです。 やっている者が楽しむのではなく、見ている人に楽しんでもらうのがお笑いの基本です。 笑いながらしているのは、自分たちだけが楽しんでいて、まわりのお客さんに意識がいっていないと言うことです。 それではいけません。 まわりのことを意識して演じてください。」
2005年06月22日
コメント(0)
-
お笑い研究クラブ
お笑い研究クラブ2回目。 何をしているのかというと、いたってノーマル。 グループごとにネタを考えて、披露。 それをお互いが批評しあうというもの。 普通と言えば普通なのですが、これを小学校のクラブ活動でやっていると言うところが、ちょっと普通ではない。(笑) 今日は、4年生のグループがネタ披露。 グループ名は、「ハイオク」。 この名前から、予想できると思いますが、あきらかに「レギュラー」のパクリネタ。 当然、5,6年生からの批評はきつめ。「オリジナリティがない。」「そのままあるある探検隊やん!」「やりながら、やっている本人が笑っている。」「端にいる子が何もやっていない。」 う~ん、するどい! いい評論家になれそう。 実際、児童集会などで披露するには、充分なのだが、夢のM-1に出るにはほど遠い。 そう、どこまで本気かどうか知りませんが、この4年生、M-1に出る気なんです。 もちろん、ある程度のレベルまでいかなければ出させません。今の段階ではとうてい無理です。 しかし、夢を持つのはいいことです。 果てさて、どうなる事やら!
2005年06月21日
コメント(0)
-
復活!!
体調を崩し、しばらくご無沙汰でしたが、本日、復活。 また、四方山話におつきあい下さい。 さて、今日の笑育です。 本日、クラブ活動がありました。 私の担当は、「お笑い研究クラブ」 小学校のクラブ活動としては、全く、嘘のようなクラブです。 たぶん、全国的にも珍しいんじゃないでしょうか? 私の学校は、毎年子どもたちの希望をきいて希望人数によって、その年のクラブが決定します。(もちろん、いろいろなきめ細かい取り決めはありますが、大雑把に言うとこんな感じです。) 最初に、どんなクラブをつくりたいか・・・と言うアンケートを採ったときに目にしたのが「お笑い研究クラブ」。「誰が、こんなクラブに入るねん。」と一人つっこんでいたのですが、ふたを開けてみると、9人ほど希望。 意外にも、見事、クラブ成立。 びっくりしました! 本日は2回目。 いよいよ本格的なクラブ活動のスタートです。
2005年06月21日
コメント(0)
-
教室風水?
今年は、まだ全然やっていないのですが、ある年に、ちょっとおもしろがってやっていたのが、教室風水。 まぁ、全くのしゃれでやっていたのですが、教室の運気を高めるために、「水のもの(主にお魚の入った水槽)はこの方角に。」「緑はこちらに。」などをやってみました。 特に変わったことはしていません。 私に専門的な知識はありませんので、入門書を見てお家の風水をそのまま教室に持ち込んだだけです。 ただ、教室風水という言葉の響き(私の造語だと思いますが)が、妙に耳に心地よく、まわりの先生に話していたことを思い出します。 その効果は・・・というと、全然わかりません。(笑) 自分の中の風水ブームの終焉と共に、教室風水もすたれていきました。 ・・・と書いているうちに、今年もまたやりたくなってきました。 やってみようかな?
2005年06月16日
コメント(0)
-
暗唱ファイル第2期の目玉
暗唱ファイルは、5つの内容で1期という事にしています。(今後どうなるかわかりませんが・・・) 1つは、名文。2つは、春の七草のように2行程度の短いのを2つ。1つは、言葉遊び的なもの。そして、最後の1つが「譲二の言葉」のように、普通の暗唱詩文集では絶対にのらないようなもの。・・・という感じです。 子どもたちがやはり食いつくのは、最後の一つ。 そして、今回の目玉は、迷ったあげく次のようになりました。静まれ、静まれぇ。~Be still , be still.~この紋所が目に入らぬか! ~Look at this family crest.~ ここにおわすお方こそ、前の副将軍・水戸光圀公にあらせられるぞ! ~The man who's standing here in Shogun's uncle , the great lord Mitsukuni Mito . ~頭が高い。控えおろう!~Bow your heads , down your knees . ~ そう、水戸黄門です。 ちょっとひねったのが、英訳つきと言うところです。 子どもたちが日本語を読み、教師がすぐ後に英語の部分を洋画の予告編のように読んでいきます。出典は、水戸黄門大学からでした。
2005年06月15日
コメント(0)
-
学年そろって、譲二の言葉
いつものように、朝の会終了直後、暗唱文集の1~5を全員立って姿勢を正した上で声をそろえて暗唱していました。 譲二の言葉の所はいつも、全員で声をそろえた後、上の句(しまったしまったの所、本当は上の句ではないのですが、子どもたちはそう言ってます。)と下の句(島倉千代子のところです。)を、「最初は上の句男子、下の句女子。」「次は、逆。」という感じでバリエーションをつけて楽しんでいます。 ところが、この日は、うちのクラスが上の句を言った後、隣の教室からなんとなく下の句が聞こえてくるのです。 これは、面白い。「よし、全員で上の句を言おう。1組が下の句をかえしてくれるかも・・・」 クラスの気持ちが一つになりました。 全力で上の句を叫びます。「あいきゃん のっと」 一瞬の間が空いた後「能登半島」 壁を隔てて聞こえてきました。 もう、子どもたちは大喜び。 最後まで一気に譲二の言葉の上の句を叫びまくりました。 そして、一通り終わった後は、もちろん、1組が上の句を・・・ 学年そろって、アホなことをする・・・というのもいいものです。(笑)
2005年06月15日
コメント(0)
-
勝ち負けにこだわれ!
休み時間に、学年でドッジボールをしました。 1組対2組という学年対抗の形です。 白熱したいいゲームでした。 僅差で1組の勝ち。 ゲーム終了後、少し話しをしました。「勝ち負けにこだわるな・・・と言われたことがあるでしょ。でも、勝ち負けにこだわってもいいんです。 いや、むしろ勝ち負けにこだわらないと力は伸びていかないものなんです。負けても、ニヤニヤしているような野球チームは決して強くなりません。負けた時に、思いっきり悔しがるようなチームが強くなるのです。 でも、こだわり方を間違えると、力を伸ばすどころか力を落とす結果になります。 相手のチームがずるいことをした。運が悪かった。相手が強すぎた。味方のチームのあいつがミスしなければ勝てた。・・・というように自分自身以外の所に負けた原因を探すようなこだわりをするとダメなんです。 本当は、自分の力不足なのに、いいわけをつくって自分を甘やかしているわけです。これでは、自分は伸びません。 原因を自分自身の中にふりかえっていく人は伸びていきます。 メジャーのイチロー選手は、人一倍勝負にこだわる人だったらしいです。しかし、そのこだわりはいつも自分自身にむいていたそうです。だから、あれだけの選手になれたんですね。 先生の言いたいことは伝わりましたか。君たちは、もう4年生だから話しました。低学年には少し難しいかもしれません。だから、低学年の場合は、勝負にこだわるな・・・と先生も話します。君たちだから話したのです。」 すごく真剣にきいていました。 ちなみに、イチローの話しはもしかしたら間違っているかもしれません。どこかできいたのですが、どこできいたのかはっきり覚えていないものなんで、正式な論文などの引用するときはしっかり調べた後お使い下さい。(使わんわな。)
2005年06月14日
コメント(0)
-
10マス計算バリエーション
子どもたちから笑い声が起こる10マス計算バリエーション。 一番簡単でお約束なのがこれ。 ベタですが、ベタであるが故、うけます。「よ~い、スタート。・・・といったら始めるんですよ。」 次に、じゃんけんで勝った人からスタート。もちろん、教師は同じ手しか出しません。(グーならグーばっかり) この時、タイムを計るのは、最後の子が計算を始め出してからにします。 すると、どうなるか。早く勝った子のタイムは0秒となるわけです。 10マス計算のタイム0秒。この響きに子どもたちは大喜びです。 また、10マス計算は普通、上から計算していくのですが、子どもたちが慣れてきた頃を見はからって、下から計算をさせていくこともあります。 視線の移動が上から下の逆になるだけでタイムも落ちます。ちょっとマンネリになってきた子どもたちの気持ちに火をつけることができます。下から上だけでなく、「一つとばしで計算して、下までいったらとばしたところをする」や「一番上→一番下→2番目上→2番下・・・」というようなバリエーションもあります。 クラスの中で大きくタイム差が出ているときに早い子だけこのパターンでさせるということもあります。 以上、上のバリエーションは杉渕先生から教えていただいたものです。 あの先生は、すごいです。
2005年06月14日
コメント(0)
-
10マス計算
10マス計算て、ご存じですか? 100マス計算とは、違います。 読んだ字のごとく、100マスでなく10マスで計算をしていくのですが、これがすごくいいんです。 100を10にしただけのように思えますが、やってみるとその効果には歴然の差があります。 まず、10マス・・・つまり10問だけですので、集中力がとぎれない。 また、クラスでやる場合は、一気に100問だと早い子と遅い子の時間差がすごく大きくなりますが、10問だとそれほど差ができない。早くできた子も待つことができます。 他にも、いろいろと効果があるのですが、「間違いを自覚させる」のに10マス計算はいい働きをしてくれます。 10マス計算をやっているお子さんの横に立って、ちょっとつまったところ(すごくつまったところ)を見てあげます。 そして、10問終わった後にこう言います。「つまったところを赤鉛筆でかこみなさい。」 これで、自分の苦手な九九が自覚できます。 自覚した後は、その九九を集中練習するわけです。 なお、10マス計算について、もっと詳しく知りたい方は、検索で「10マス計算 杉渕鉄良」といれるとけっこう当たるはずです。(杉渕鉄良という方が子の10マスの生みの親であり、実践の第1人者です。) 10マス計算のドリルも少し大きな本屋さんなら3社から販売していますので、比較的手に入り安いはずです。 以上、今回は前の流れから笑育とは関係のない方向に行ってしまったように感じますが、実は10マスを飽きないようにするためには、笑いも必要なんです。 そのへんのバリェーションは次回にて紹介します。
2005年06月13日
コメント(0)
-
間違うことでダメになる2
九九の続きです。 とにかく九九の場合、一度間違った答えを覚えてしまうと、後々すごく苦労します。修正が非常にききにくいのです。 何度も何度も同じ間違いをしてしまいます。 そして、その子はこう思います。「自分は、算数が苦手だ。」 苦手でもがんばろうという意識があればいいのですが、普通はこう続きます。「算数は、嫌い。」 こうなると、けっこうやっかいです。嫌いという意識が前に来ると、自然にやる気がなくなってきます。そして、ますますわからなくなるのです。 しかし、よく考えてみると、九九ができないと言っても、81個ある九九のほとんどができないわけではないのです。 九九を習い始めたときは、人生の中でもけっこう算数に燃えていた時期のはずですので、現在、算数が嫌いな子でもそれなりに練習をしていたはずです。だから、すっと出てこない九九は、本人が思っているほど多くないはずです。 そこで、まず、そのあやふやな所をはっきりさせることから始まります。 そのチェックのためにもいいのが、10マス計算です。(念のため、100マス計算ではありませんよ。) 続く
2005年06月13日
コメント(0)
-
間違うことでダメになる
間違うことでかしこくなれば、間違うことでダメになる場合があります。 それは、どんな時でしょうか? 前回にもそれらしいことを書いていますが、それは、 「間違い」を自覚していない時なんです。 一番具体的でわかりやすい例が漢字と九九です。(1番といいながら2つ出していますが、ご容赦を。ここがつっこみどころです。) 例えば、漢字。「明日、漢字のテストがあるから、家で練習しておいで。」という宿題が出ることがあります。 その時、たわせん学級では、「自分で○つけをすること」も宿題のセットになっています。 これは、なにも教師が楽をしようとしているのではありません。 練習をした際に、すぐに答え合わせをしていないと、間違った字を書いていた場合、それが正解である・・・と、脳が覚えてしまうからです。これが、間違いを自覚していない悪いパターンなのです。 だから、すぐに○つけをして、間違っていた字を書いていたら、その場で訂正をして、覚え直す必要があるのです。 漢字の苦手な子ほど答え合わせもしっかりできていないことが多いです。教師は、宿題が提出された際、○つけがあっているのかどうかを点検しています。 この時、間違っているのに○をつけている子、自分で○つけをしていない子にはやり直しをさせます。 だけど、本当のことを言うと、書いたすぐ後に自分で点検ができるようになるのが一番なんです。 子どもたちには、次のように言うことも多いです。「漢字の○つけがきちんとできる子は、漢字の力は伸びていきます。」 九九も同様です。 九九の場合は、2秒ほどで思い出さなければ、すぐに正解を見させます。「う~ん。」と考える時間もとってはいけません。 一瞬で出来なければ、九九を使いこなすことができないからです。
2005年06月12日
コメント(0)
-
間違うことでかしこくなる2
昔の人は、よく言ったものです。「聞くは、一瞬の恥。聞かぬは一生の恥。」 本来の意味は、「恥ずかしがっていて聞かないと、ずーーぅっと知らないままで一生恥をかくよ。」という意味ですが、「一瞬の恥」が、「強烈なインパクトを生んで、一生忘れない」という風にここではとってみます。 けっこう「一瞬の恥」を嫌がる子というのは、多いものです。 例えば、「間違いを赤鉛筆で直しなさい。」と指示しているのにもかかわらず、先生の目を盗んで消しゴムで消し、黒の鉛筆で書き直している子なんかがそうなんです。 こういうことをしていると、自分が正解だったのか間違いだったのかがはっきり頭の中に残りません。最初から、正解だったのなら、次に同じ問題をやっても、正解になるでしょう。逆に、間違えていた子は、次に問題をやった場合、とりあえず間違えたということは意識しているので、悪くとも同じ間違いはしないでしょう。(多くは、正解になるでしょう。) ところが、ごまかしちゃう子は、正解、不正解の意識がはっきりしないままに終わっています。(ごまかしたという意識のみが残っているかもしれません。)不正解の答えを正解だったと思ちゃう場合もあります。 どちらにしても、3タイプの中では一番よくありません。 また、ごまかす癖がつくと、勉強の場面以外でも問題が出てきます。 では、このようなタイプをなくすのは、どうしたらいいのか? 結局は、クラスの雰囲気なんです。 間違っても、みんなに笑われない。 万が一、笑われたとしても、それが「おいしい」と感じる。 だから、笑育なんです。(ちょっと、強引)
2005年06月12日
コメント(0)
-
間違うことでかしこくなる
「紫式び」のように、間違うことで印象が強くなり記憶が定着。 結果的に、かしこくなるということがあります。 実は、教師というものは、わざとまちがえて、子どもたちの意欲を引き出すと言うことをよくするものです。「わざとまちがえる」「わざと知らないふりをする」事によって、子どもを熱狂の渦に引き込むわけです。 わが師匠の有田和正氏は、この分野も名人芸。 有名なポストの授業は、まさにボケの波状攻撃です。「この紙でポストをつくりたいんだけど、できるよね。」「紙で、できるはず無いやん。」「なんで、紙の方がつくりやすいでしょ。」「紙だと、雨が降るとぬれて壊れるでしょ。本物は鉄みたいにぬれても大丈夫なもの。」「そうか。じゃぁ、今日はこれを鉄だと思って考えてね。(まるめて)はい、できた。」「だめ~。上があいている。」「アッ、本当だ。」・・・という感じで、ポストのことについて学習を進めていくわけです。 中学年までは本気で先生が知らないと信じている子が多く、「全く、うちの先生は何も知らないから、私たちがしっかりしないとね。」としたり顔で話しているほほえましい風景をよく見ることになります。
2005年06月11日
コメント(0)
-
源氏物語の作者は?
「藤波くん、源氏物語の作者は?」 社会の授業中、ちょっとよその世界にいってそうな藤波君(どこのクラスにも1人や2人いますよね。)に、いきなり指名。 答えを求めました。(たぶん)他のことを考えていたであろう藤波君は大いに焦り、立ち上がります。「源氏物語ですよ。源氏物語。」 ちょっと意地悪にプレッシャーをかけていきます。「むらさき しき・・・・・」 この日に限って、なぜかすっと出てきません。(別に私も怒り心頭という顔ではなく、どちらかと言えば、にやにや。←これがいかんかったのか!) それほど、よその国に行ってたのでしょうか?「あーーっ。」 どうやらわかった模様。「よし、では、藤波君どうぞ!」「紫式び!」 これは、想定外でした。 思わず、吉本新喜劇のように崩れ落ちてしまったぐらいです。 しかし、「紫式び」のインパクトのおかげで、このクラスの子どもたちは、「源氏物語の作者は?」のテストは完璧でした。 一生、紫式部のことを忘れないでしょうね。 ありがとう!藤波君。
2005年06月11日
コメント(0)
-
顔色をうかがえない子どもたち
たわせん学級では、よく「空気を読め」という表現を使いますが、最近、大人の顔色をうかがえない子供が増えてきたと思いませんか? 目の前で先生が今にも怒り爆発直前という感じでも、素知らぬ顔。 スーパーなんかでも、お母さんの顔が明らかに怒っているのに気づかず騒いでいる子。 最近よく見かけるような気がします。 一昔前なら(う~ん、こういう表現をするというところが年をとった実感)、「大人の顔色をうかがって行動する」というのは決してほめ言葉ではなかったのですが、なんか最近なら、これすらほめ言葉に聞こえてきます。 それぐらいまわりが見えてないんでしょうね。 ヒデのように広い視界が持てるといいんですが・・・(ワールドカップ出場記念的表現でした。)
2005年06月10日
コメント(0)
-
空気が読めないやつは、お笑いをするな。
クラスの中に、一人や二人はいるお調子者の男子。 彼らは、大いにクラスを盛り上げてくれ、楽しい学級づくりのためのいいムードメーカーにもなってくれるのですが、やはり、そこは、まだまだ子ども。 静かになるべき所で騒いでしまったり、笑いをとろうとしていきすぎてしまったりなど、調子に乗りすぎることもしばしば・・・ そんな時に言ったのが、タイトルの言葉。「空気が読めないやつは、お笑いをするな。」「今は静かにする」「相手が嫌がっている」という空気が読めないやつは、人をわらかそうとしてはいけません。人をわらわせるということは、すばらしいことだけど、空気が読めないでおこなうとその行為はマイナス以下になるもんです。・・・と、言うようなことを話しました。 子どもたちは、真剣な目で聞いていました。 しかし、「お笑いをするな。」がこんなに効果があるとは。 後で考えてみると、なんかおかしかったです。
2005年06月10日
コメント(0)
-
関西人の基礎基本
関西人の基礎基本とでたところで、思い出したのが、吉本興業の社長の言葉です。「関西人の基礎基本は、読み書きそろばん、ボケつっこみや。」 う~ん、納得! 10年ほど前の話しです。 私の友人の一人が、めっちゃきれいな娘とつき合っていて、結婚間際だったのですが、なぜか急に破局。 その理由の一つが、「自分がボケても、つっこんでくれへん。」というものでした。 一生共にすごす相手がつっこんでくれない。 これは、確かにつらいかも・・・(ちなみに、東京の友人にこの話をしたところ、全員信じられないという反応。関西の友人は、一同納得という反応でした。当時の西と東でのお笑いに対する執着心がよくあらわれている反応でした。今では、少し傾向も変わっているかもしれませんけどね。)
2005年06月09日
コメント(0)
-
声に出して読みたいチューイングボーン
最近、音読・暗唱に力を入れる先生方が増えてきました。 独自に、音読集や暗唱詩文集などをつくり、子どもたちに名文などを音読、暗唱させるという実践が多くの学校、クラスでおこなわれています。 たわせん学級も同様です。 2005年バージョンは、今週から始まりました。 ファイルに、音読、暗唱させたい文章や詩などをとじて活用しています。 まず、第1期として、5つ。 最初は定番の「寿限無」から始まり、「春の七草」「秋の七草」。 そして、「付け足し言葉」と続き、最後はちょっと(かなり)お遊びで、「譲二の言葉」をいれてみました。 関西人なら誰でも一度は聞いたことがあるはずのあの「譲二の言葉」です。「譲二の言葉」(吉本新喜劇より) あいきゃん のっと 能登半島 なんのこっちゃ 抹茶に紅茶 しまった しまった 島倉千代子 ひさしぶりぶり ブロッコリー 困った困った コマドリ姉妹 そうです。ぱちぱちパンチで有名な「吉本新喜劇」の島木譲二です。 これこそ、関西人の基礎基本です。(笑)
2005年06月09日
コメント(4)
-
ドキドキワクワク日番くじ
日番の話が出たので、ちょっと横道にそれますが・・・ 普通、日番といえば出席番号順に回っていくことが多いものです。 が、たわせん学級では、ここでもちょっとひねりを加えています。 ドキドキワクワク日番くじ 割り箸に、出席番号を書いてくじをつくります。 それをその日の日番が終わりの会にひいて、次の日の日番を決めていくのです。 当然、出席番号順に決まっていきません。 その日の日番(仮に出席番号5番とします)の子が引いたくじが23番なら、次の日の日番は、23番の子になるからです。 ただ、日番をする順番が出席番号順ではないだけで、結局全員が日番をすることにはなります。 それでも、次の日は誰になるかわからないドキドキ感を子どもたちは満喫しているようです。「盛り上げCD」で、ドラムロールのBGMを流しながら、「明日の日番は・・」と、声がかかると、「8番、8番。」や「俺、当ててくれーーっ。」などいろいろな声があがります。 さらに、ポイントを一つ。 実は、このくじの中に「あたり」を一つ入れておきます。「あたり」が出れば、もう1回。 次の日も日番が出来るという特典です。(「あたり」が出れば、高学年は他の子が大喜び。低学年では、あたった子が大喜び。どちらにしても、大盛り上がりです。 )
2005年06月08日
コメント(0)
-
ハッスルTシャツでハッスル、ハッスル
毎日、日番が「さようなら」のあいさつをします。 基本パターンは、「明日も元気で、さようなら。」というものですが、原則的に言う言葉は、最後に「さようなら」さえ入っていれば、何でもOK。 つまり、日番任せと言うことにしています。 女子が日番の時は、比較的ノーマルにいくことが多いのですが、お調子者の男子の場合、プラスαの何かを入れたがります。 その時、一番多いのが、これ。「3、2、1。ハッスル!ハッスル!」 私の教室には、ハッスルTシャツが常備しています。 このTシャツを着て「さようなら」のあいさつをおこなうのです。(ただし、私のものなので子どもたちが着るとぶかぶかです。) ちょっとした小物に凝ってみると、子どもたちの動きが変わってきます。
2005年06月08日
コメント(0)
-
授業で使える面白グッズ2
ピンポンブーでは物足りない、セレブなあなたには、これ。「早押しピンポンブー」 6人参加の早押しピンポン。 6班対抗のクイズ合戦や九九合戦など、班対抗で盛り上がる際にはうってつけ。 いち早く押した番号が光ります。 もちろん、正解の「ピンポン」不正解の「ブー」もしっかり鳴ります。 お値段はちょっとお高く、税別で6500円。 東急ハンズなどで売っています。
2005年06月07日
コメント(0)
-
授業で使える面白グッズ
東急ハンズなどのパーティグッズコーナーを見てみると、授業で使えそうな面白グッズがたくさんあります。 その中でも一番のお薦めは、「ピンポンブー」 正解の音「ピンポン」と間違いの音「ブー」が簡単に出せて、税別980円。 値段も手頃でお買い得です。 使い方も簡単。「次の問題が解けた人は、ノートを持ってきなさい。」というような指示をして待っておきます。 こどもがワヤワヤ・・とやってきます。 ノートを見て、正解なら○のボタンを押して「ピンポン!」 間違いなら、×のボタンを押して「ブー。」 この間、教師は一言もしゃべりません。(しゃべらない方が効果があるのです。) 教室は、熱狂の渦に巻き込まれます。(ちょっと大げさかな・・・)
2005年06月07日
コメント(0)
-
「ヒロシです。」でお天気キャスター CDを使った授業
CDを使った授業で、一番ピタッとはまったのが、5年生、理科での天気図を読みとる内容のものでした。 天気図を見て台風の進路予想をするという内容のものを、お天気お姉さんや石原よしずみさんになったつもりで、天気予報番組風にして発表しよう・・・と少しひねりを加えてみました。 まず、それらしくまじめに発表原稿を書きました。 ここでCDの登場です。 正当派のキャスター向けに役に立ったのが、「盛り上げCD」 効果音を付けだけで雰囲気が出まくります。 正当派の原稿が早くできた子は、おふざけバージョンもつくらせました。関西弁のキャスター、コギャル風のキャスター、ハム太郎風のキャスターなどなど。これも喜んでつくっていたのですが、ここで大活躍したのが「ガラスの部屋」のCD。「ヒロシです。本日21:00,九州に大型の台風が上陸するとです。」のような感じで、大受けでした。 ちなみに、理科の演示実験の際には、手品の音楽がバッチリ合います。
2005年06月07日
コメント(0)
-
授業で使える面白CD
「合体漢字」の時、ターミネーターのテーマを口ずさむだけでもいいのですが、この時ターミネーターのサントラCDを流すと、効果倍増。 盛り上がり度は違います。 同じように、授業や朝の会、終わりの会などで使うと効果的なCDを2つ紹介します。「盛り上げCDスペシャル」1500円(税別)「カウントダウン」「拍手」「問題を出す際の音楽」「手品の時に流れる音楽」などたくさん入っています。東急ハンズなどで簡単に手に入ります。おすすめNo.1。「僕たちの洋楽ヒットVol.4」2500円(税込み)「ヒロシです。」のバックに流れている曲「ガラスの部屋」が収録されたアルバム。普通のCD屋では入手困難。インターネットショッピングがお薦め。 具体的に、これらの曲をどのように使ったのかは、また明日紹介します。 おやすみなさい。
2005年06月06日
コメント(0)
-
へんとつくりの学習は、合体漢字で・・・
IQサプリに出てくるような凝った合体でなく、とーっても単純な合体でも、あのターミネーターのテーマを口ずさみながら、「合体!」というだけで、もう子どもたちは楽しい気分になっちゃいます。 へんとつくりなどの勉強が、この「合体!」で、とても楽しくできるのです。 例えば、次のような感じになります。「イ(にんべん)」と合体して出来る文字は、どれですか? 「木」「口」「立」「日」 一人指名して、前に来させます。 そして、「イ」の横に、自分が答えだと思う文字を書かせるのです。 この時に、教師が言います。「合体!」 そして、ターミネーターの曲を口ずさみます。 テレビのように、特別なCGがなくても、黒板にチョークでけっこう盛りあがるものです。子どもたちの頭の中では、目の前の黒板でおこなわれていることがCG化して流れているのです。「合体!」と言う言葉とテーマ曲。 これだけのことですが、ノリが全く違います。 やる気が200%アップするのです。
2005年06月06日
コメント(0)
-
現在、子どもたちが好きな知的な番組
今でも、トリビアはやっています。 だから、何かの調べ学習をして、「へぇ」と思ったことがあれば、どんどん投稿してもいいのですが、現在、子どもたちが好きな番組で、かつ、知的なもの、そして投稿も出来るものの一番手といえば、「IQサプリ」ではないでしょうか? 子どもたちに考えさせるなら、「合体漢字」がいいでしょうね。 問題がつくりやすいので、喜んで取り組みますし、ちょっぴり漢字の学習にもなります。 すごいのが出来たら、投稿。 投稿するという事実が、さらにやる気を倍増させます。
2005年06月06日
コメント(0)
-
人気テレビ番組から
2年前の水産業の調べ学習の際、「トリビアの海」と称して、自分たちが調べたことをトリビア風にまとめさせたことがありました。 例えば、「マグロは一生眠らない。」とか「オーストラリアの競りは静か」のような感じです。 子どもたちは、燃えました。「みんながつくったトリビアは、実際に応募するからね。」と、前もって話していたからです。 もう勉強が始まる前から、子どもたちの頭の中は、賞金の使い道でいっぱいでした。(「クラスでパーティをしよう!」ということになっていました。) でも、最終目的がはっきりとしているというのはいいことですね。 子どもたちのやる気が俄然アップします。 ちなみに、2年後の現在も採用通知はありません。 残念!!
2005年06月05日
コメント(0)
-
クラスの子どもたちが何に興味を持っているか?
「子どもたちが何に興味を持っているか?」 一番、手っ取り早いのが、本人に聞くという方法です。 しかし、この方法は、あまりにも直接的すぎます。 何気ない会話の中で、「えっ、先生、そんなことまで知ってるの?」「なかなかやるやん。」と思わせるには、前もってある程度、その子たちが興味を持っているであろうものをリサーチしておく必要があります。 そのような一般的な傾向を知りたい場合のいい参考文献を紹介します。「小学館発行 小学○年生」 その学年の子どもたちが今興味を持っているテレビ、文化などがこの1冊でよく分かります。 また、スーパーなどのおもちゃ売り場、文具売り場、CDショップなどをうろうろするのも一つの手です。 ただし、変な人と間違われないようお気をつけ下さい。(笑)
2005年06月05日
コメント(0)
-
意味のない会話
以前、心理カウンセラーの講演会で聞いた話です。 会社の社長、お母さん方などなど、いろいろな人が来るそうです。 自分がいる集団(つまり、会社であり、クラス、家庭などということです)がうまくいかないという相談を受けたときには、次のように答えると言っていました。「意味のない会話をしていますか?」 例えば、お母さんがお子さんとうまくいっていないと相談に来たとします。 たいてい、次のように会話が続くのだそうです。「お子さんと、会話をしていますか?」「はい、していますよ。」「どのような会話ですか?」「えぇ、早く起きなさい・・とか、晩ご飯は何がいい?・・とか。」「お母さん、それはご自分の仕事(家事)を能率よく進めるために聞いているものであって、事務連絡のようなものです。大切なのは、仕事とは全く関係のない意味のない会話なんですよ。」 意味のない会話で、集団がまとまる。 考えてみれば、友だち同士の会話の多くは、そうですよね。(井戸端会議のお母さんたちの会話も、居酒屋のお父さんたちの会話も) どの集団でも、いわゆる馬鹿話って、大切なんですね。
2005年06月05日
コメント(0)
-
共有する話題を持っていますか?
「笑いには、他者と笑いを共有する意識がないと、笑いそのものが成り立たない。(ターザン山本!)」ということで、クラスの子どもたちと共有する話題をいくつお持ちでしょうか?もちろん、「645年には、大化改新があったねぇ。」というような話題ではありませんよ。 実は、一見意味のないようなものこそ、子どもとの共有感には大切なのです。「クラスの子どもたちが、興味を持っているのは何か?」 それをつかんだ後、教育の場にうまく持ち込もうというのが、先に述べたTV番組からのパクリ(笑)シリーズです。 以上、ちょっと理論武装してみました。 もちろん、このパクリシリーズはこれからも不定期に続きます。
2005年06月04日
コメント(0)
-
人気番組からちょっと拝借2
授業で「ファイナルアンサー」を使う時、たいていセットになっている言葉があります。 番組は違ってくるのですが、それは「中間ジャッジ」という言葉です。「ファイナルアンサー」が最終決定の意見というのに対して、途中の意見という意味合いで使っています。 子どもたちは、途中の意見と言うことで、比較的気楽に自分の意見が決定できます。そして、みんなの意見を聞いた上で「ファイナルアンサー」ということになります。 ちょっと言い回しを変えるだけで、ドキドキ感や楽しさが違ってくるようです。
2005年06月04日
コメント(0)
-
人気番組からちょっと拝借
授業で使えるネタは、「いいとも」以外にもたくさんころがっています。 何と言っても、簡単に使えるネタは、「ファイナルアンサー?」 これは使い勝手がいいです。 教師が、みのさんのように演じると、面白さも倍増。 グーーーッと、ためるだけためて、「正解!」「残念!」「健介くん、答えは? はい正解です。」というように、答えを子どもたちに聞いているのは同じなのに、言い方一つで、盛り上がり方は雲泥の差です。 ちなみに、のりのいい子どもたちは、これをすると、ライフラインも使いたくなるようです。 もちろん、使わせます。「フィフティフィフティ」は、2拓問題に。「オーディエンス」は、クラスの他の子に挙手させて答えを聞く。「テレフォン」は、筆箱を電話のように耳に当てて、誰か一人に相談。・・という感じです。「テレフォン」が好きな子が多いです。相談された子が答えようとしたときに、教師が「はい、時間切れ。」と切ってあげることが面白さをアップさせます。)「ファイナルアンサー」、ご家庭でも使えるネタだと思います。
2005年06月04日
コメント(0)
-
今日は、何の日?エピソード1
授業の最初、黒板に日付を書くとき、その横にその日の記念日などを書いていきます。 ただ普通に書いても、子どもたちの知的好奇心をくすぐってくれるのですが、ちょっとしたクイズ形式にすると、さらに盛り上がった数分間をクラスに提供してくれます。 授業が始まる時間、きっかりに初めて、2~3分おこないます。 楽しくワイワイやっていくうちに、少し、授業に遅れてくる子も激変します。 毎年、名解答、珍解答が続出します。 今日は、そのエピソードの一つを紹介します。「4月17日○○○○○の誕生日。さて、○にはいる言葉は?」 普段は、おとなしめの女の子。 なぜか、この日は大張り切り。「はーい、ブッシュです。」「いや、5文字なんですけど・・・」「う~ん、ブッシュ(首を傾けてカワイク)。」「いや、ブッシュの後にハートをつけられても・・・ ヒント1 3つ目の文字は、ゴ。そして、ヒント2日本人です。」 彼女は、しばらく考えた後、自信満々でこう答えました。「メカゴジラ」 確かに、メカゴジラは、日本製ですが・・・。 正解は、ムツゴロウ(さん)でした。
2005年06月03日
コメント(0)
全53件 (53件中 1-50件目)
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆
- (2025-11-16 21:36:26)
-
-
-

- 子供服ってキリがない!
- 【3,300円福袋】クロミ ハッピーバッ…
- (2025-11-24 05:06:53)
-
-
-

- 軽度発達障害と向き合おう!
- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…
- (2025-11-17 06:15:32)
-