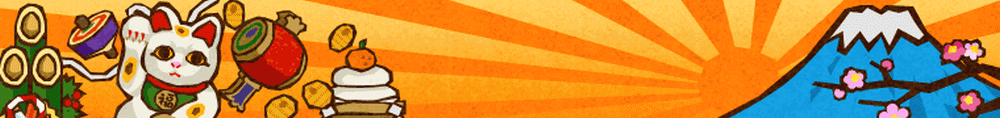2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年12月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
2005年ももう終わりかぁ
以上で、兵庫県の導入の授業は終わりです。 3学期の社会科はこの続きから始まります。 そして、2月10日の実践発表会へと続くのです。 昨年は、1000名もの方が参加してくださりました。 今年は、もう少し規模を縮小して(1000名もだと対応できれない面も出てきましたので)・・と考えているのですが、それでも500名は越す研究会にはなりそうです。 私は、もちろん、社会科の授業を公開します。 昨年の発表では、担任を持っていないかったため、クラスを借りておこなったのですが、納得のいかない授業になってしまいました。 今年は、自分のクラスで、リベンジ。 今、その構想を練っているところです。 あと、頼まれた算数の原稿(学事出版)やずーっと先延ばしにしている組合の原稿もあるのですが、この授業構想を練ることが、冬休みのメインの仕事になりそうです。
2005年12月31日
コメント(0)
-
兵庫県導入の授業3
(前の続き) 5つの地域を合体させて、黒板に少し大きめの兵庫県の白地図ができる。 この作業は、子どもにやらせました。 パズル遊びみたいな感じでおこなえるので、大喜びです。 次は、自分たちの住んでいる市の確認。 以外にも、3人が間違えていました。やはり、こう言うのもたまにはしていかないといけません。 そして、いよいよこの授業のラスト。 兵庫県には、全部でいくつ市があるのですか? 都道府県は47個あります。では、兵庫県の中にはいくつあるのですか・・・ということです。 副読本の84ページには次の記述があります。「兵庫県は、22の市と66の町からなりたっています。」 他にも各地域ごとに市の数が書かれているページもあります。それを一生懸命たしている子もいました。 もちろん、子どもたちの答えは 兵庫県に市は22個ある。になります。 さぁ、いよいよファイナルアンサー。 ためるだけ、ためて正解を言いました。 残念! 実は、平成の大合併で市の数が変わっているのです。副読本のデータは古い物なのです。(そのための改訂作業が冬休み明けにあります。あ~、忘れてたそれまでにその原稿も書かなくては・・・。編集委員なんです。) 教室の中は、大ブーイングの声。(こういうブーイングは気持ちいい) 答えはもちろん言いません。 オープンエンド。3学期への布石を打っておいて2学期最後の授業を終えたのでした。 冬休みに調べる子もいるかなぁ?
2005年12月31日
コメント(0)
-
兵庫県の導入の授業2
全部でいくつ都道府県があるか確認した後、第6問目を出しました。 兵庫県は、神戸・阪神 但馬 丹波 播磨 淡路の5つの地域に分かれています。 第6問目は、但馬の白地図を見せたわけです。 これには、さすがに混乱。 子どもたちは都道府県が続いていると思っているからです。「難しいですね。引き続いていきます。」と、続いて、丹波・播磨・神戸・阪神・淡路と提示していきました。 この途中で、勘のいい子はこれは県ではないと気づきます。 すると、どこだ!ということで教科書を見出すのです。 副読本を見て、発見。 これは、県ではない! う~ん。4月に比べると格段の進歩だ。 客観的資料を見ることなんかなく、自分の思いが最優先の子どもたちだったのに・・・。(涙) まぁ、とにかく、最後の淡路で、ほとんどの子がこれは淡路だと気づきました。 そして、答え合わせ。 但馬 丹波 播磨 神戸・阪神 淡路と一気に正解を述べます。 副読本を見せて、それぞれの地域の読み方と位置を確認。全員で指さし。(←基礎基本の徹底) そして、「合体!」 合体漢字のテーマを口ずさみながら、それぞれの地域を一つにして、兵庫県に。「答えは、兵庫県でも○にします。」 まだもう少し続きます。
2005年12月30日
コメント(0)
-
オールザッツ漫才で徹夜
う~ん。 関西ローカルのオールザッツ漫才を最後まで見てしまって、徹夜してしまいました。 いつもこの時期、吉本の若手芸人がたくさん出て、一晩中おこなわれる番組なのですが、ついつい見てしまい、毎年、この日を境に冬休みの生活リズムが崩れます。 みなさん、規則正しい生活をしましょう!と、とりあえず言っておきます。 もう10年目になるのですが、ストリークの野球ネタがおもしろかったです。来年、プチブレークするかも。 漫才のうまさという点では、とろサーモンがよかったです。
2005年12月30日
コメント(0)
-
産経新聞の取材 兵庫県導入の授業
(前の続き) 2学期の社会科ですることは一応終わっていましたので、前倒しして、3学期の兵庫県の導入をすることにしました。 冬休み自主勉強で兵庫県について調べてくる子がいたら儲け物です。 導入は、都道府県あてクイズ。 都道府県の白地図を見せて、それがどこかあてるというものです。 これは、師有田先生の実践の追試です。 1問目は簡単。北海道の地図を見せました。「わかった~。」 もう大騒ぎです。 次は、少し難しくなります。滋賀県です。琵琶湖に気づけば簡単なのですが、気づかない子は気づかない。「ヒントです。」 琵琶湖の部分を青チョークで塗りました。 これで大丈夫。 この辺から地図帳を見て答える子も。 それとなく、ほめておきました。 3問目は、石川県。これも、少し難しいですが、能登半島に気づけばわかります。地図帳を見ている子も多かったので、けっこう簡単にクリアー。 4問目は、静岡県。形だけ見ていると、これはけっこう難しい。しかし、地図帳の4ページを見ている子に簡単。そこには、「金魚みたいな形をしているね。静岡県は・・というキャラクターのせりふがあるからです。 そして、ラスト5問目は、青森県。 これを逆さまに提示。 そうしてみると、なんとなく鹿児島県に似ている。 有田先生の実践でも、ここでかなりの子が引っかかる。 ところが、なんと、「うわぁ、たわせん。いじわる~。」「はっは~ん、そういうこと。」など言いながら、逆さまであることにほとんどの子が気づく。 みごとに担任の性格をつかんでいる。 かわいくねぇ~。 ちゃんと引っかかってくれた子は2人のみ。(嬉しくて、思わず握手。) 簡単に青森県と正答が出た。 全部でいくつ都道府県がありますか?「47都道府県」 一応、それぞれがいくつあるか確認。 実は、これは、都道府県はいったん終了しましたよっという教師からのわかりづらいメッセージでもあった。 授業は、まだまだ続く。
2005年12月29日
コメント(0)
-
産経新聞の取材
冬休み前の月曜日。 放課後に、校長室にお呼び出し。 何かと思っていって見ると、産経新聞の記者が。 どうも、教育の欄で学校紹介のコーナーがあって、私の勤務校を紹介したいのだそうだ。 全国的な実践発表会をおこなって、今年で5年目。 ということで目にとまったのだろう。 で、第1回目からずーっといて、かつ、研究推進担当の私に声がかかったわけである。 いろいろ(前半は学校の研究について、後半は私の授業について)と話しているうちに、授業の写真がほしいと言うことになりました。 そんなの今までの写真を渡せばいいわ・・・と思っていたら、実際の授業を参観して、記者本人が写真を取らせてほしいとのこと。 えーっ!?後、学校って3日しかないで。それも明日は社会の用意持ってこさせてないし、明々後日は終業式やし。 で、結局、終業式の1日前に、社会科の授業を公開することになったのでした。 2学期の社会は一応終わってたのにねぇ。
2005年12月29日
コメント(0)
-
仕事納めでサプライズ
いやぁ~。 今日は、2月の実践発表会用の研究紀要を印刷屋さんに渡さないといけなかったので、朝からその原稿書きや表紙に使う写真選びや息やら心臓動かしたりやで、けっこう忙しかったのですが、何と、ビックサプライズが! 校区にすんでいる阪神の○○選手が校庭で自主トレをしているではありませんか! さっそく、阪神ファンの先生方何人かと、校庭へゴー!! もちろん、ミーハーにもサインをゲット。 いっしょに写真なんかも撮らせてもらいました。 なんか、得したぁ。 嫌な顔せずつきあってくれた○○選手。 ファンサービス、ばっちり。 阪神タイガースは永遠に不滅です。
2005年12月28日
コメント(0)
-
あいさつする子は、ねらわれにくい。
先週の「たかじんのこんなんいって委員会」で橋下弁護士が言っていたことです。 番組の中で、幼児誘拐の話題になった時の言葉。 そのような誘拐犯が、刑務所の中で書いた手記のようなもので、目を見てあいさつする子はねらいにくいと書いていました。あのような人は、気が小さい人が多いので、しっかり見つめれると逆にダメなんでしょうね。と言うような感じの話でした。(細部の言い回しなどは違うと思いますが、本筋は間違いない) なるほど。 まぁ、一概にオールマイティな武器にはなるとは思えませんが、あいさつも大切な一因なんですね。
2005年12月27日
コメント(0)
-
あ~、冬休み!
本来なら、冬休みが一番のんびりとできるものですが、今年はなんかやることが盛りだくさん。 昨日も、学校に出て一日中何やかんやしていました。 研究紀要の原稿 兵小社(兵庫県の小学校社会の研究会)の冊子の原稿 学校の1~6年生までの授業時数の総計 2学期におこなった総合的な学習の総括 特別活動のまとめ 「聞く」指導の事例 机の整理 お昼ごはん おしゃべり チョコのつまみ食い 息 心臓動かすこと などなど 最後の方は、小学生が言うようなことも書いてしまいましたが、まぁ、こんな感じです。 さぁ、今日も息して、心臓動かしながら、やること、やるべし!
2005年12月27日
コメント(0)
-
Mー1最高!
昨日のM-1、めっさよかった。 出る組、出る組。ノーミス、完璧な演技。 まるで、荒川か村主か・・・という具合の気合いの入り具合。 感動で涙流しまくり。 それでもやはりよかったのは、優勝したブラックマヨネーズ。 紳介が高評でも言っていたけど、4分の使い方がめっさうまい。 静かに入っていって、どんどん盛り上がっていく。 クライマックスが来て、オチ。 ばつぐん。 授業もこうありたい物です。 さて、私事ですが、3学期は私の学校でも全国規模の授業発表会があります。 冬休みの真っ最中ですが、ネタづくりに奔放中。 4年社会でおもしろいネタを見つけています。 後は、45分の使い方を考えて・・・っとぉ。 さて、どうなることやら?
2005年12月26日
コメント(0)
-
北海道だけ、なぜ「道」?・・・2
さて、娘に受けて調子に乗った私は、続いて第2説を・・・。 もう一つの説は・・・。 柔道や剣道、華道や茶道なんかもあるやろ? 実は、北海道の「道」というのは、それと同じ意味合いのもん何や。 昔、北海道に住んでいた民族がつかう「ホッカィ」という武芸をきわめることを「ホッカィ」道と読んでいたことに敬意を表して、その地を「ホッカィ道」と呼ぶことにした。 それは、どんなものなん? スターウォーズのフォースのようなもんみたい・・・かな?・・・これも、娘に「よくもまあ、そんなでまかせが次から次へと・・・。」と、半ばあきれられながらも受けたのでした。 おしまい。
2005年12月11日
コメント(0)
-
北海道だけ、なぜ「道」?
この間、娘に聞かれました。「北海道だけ、なぜ「道」なの?」 東京都は、日本の都と言うことで「都」というのはわかる。 大阪府、京都府も、昔、日本の中心だった、太宰府があったとかでわかる。・・・だけど、北海道は?・・・・というのです。 実際に、東京都、大阪府などがそのような理由なのか私も知りませんが、(この後調べようと思っていますが)とっさの質問に次のように答えました。 あれは、道ではなくて、本来は「DO」という意味やってんで。 クラーク博士という人が、昔、北海道の地に来た時に、北の海で「するべし」・・と言う意味で 北海「DO!」と言ったのが始まり。 北海「DO!」→北海どぅ→北海どう→北海道と言うわけ。 そして、その後、田原俊彦の名曲「恋=DO」を歌ったのでした。 娘には受けました。
2005年12月11日
コメント(2)
-
百人一首の指導・伝えたいことは・・・
百人一首をやっていると、そのゲームの途中で、子どもたちに伝えたいことが出てきます。 例えば、次のような場合です。 声だしお手つきのことです。 いくらダメだとわかっていても、特に最後の1枚を取り終わった時には、その瞬間に、「勝った~。」だの「よし、これでうえにあがれる!」だのいろいろな声が思わずあがります。 早い子は、上の句の1文字だけで勝負がついてしまいます。 だから、そのような子はいいのですが、下の句まで聞いて初めて取りに行くような子にとっては、おかげで下の句を読んでいる声が聞こえにくくなる場合があります。 これは、当然、声だしお手つきです。 最後にとった1枚を提出させます。 これがペナルティになります。しかし、このようなお手つきはない方がいいのです。 だから、前もって指導しておきます。「下の句まで読み切るまでに、声を出したらお手つきですよ。」と言う具合に。 しかし、 しかしです。 やはり、最後の1枚では声が出てしまうのです。 では、どうするのか? 最後の1枚を読む前に言うわけです。「ラスト1枚。最後まで静かにしていないとお手つきですよ。」 これで、一気に静かになります。 他にも、同時にとった時にどうするのか、移動の時に時間がかかりすぎるのが気になるなどなど、何か話したい時には、ゲームとゲームの間に話すよりも、ゲームの途中・・・つまり札を読む間に話す方が静かにしっかりと時間のロスなく聞けるものです。 ちょっとした違いですが、やってみるとその効果の違いに驚くと思います。
2005年12月07日
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- シングルマザーの子育て
- もうどうしたらいいか分からない
- (2025-11-14 23:09:22)
-
-
-

- 子育て奮闘記f(^_^;)
- ☆チューブ式ブロック☆
- (2025-11-23 13:59:29)
-
-
-

- ミキハウスにはまりました
- 下着色々入荷されてます
- (2025-11-23 17:40:08)
-