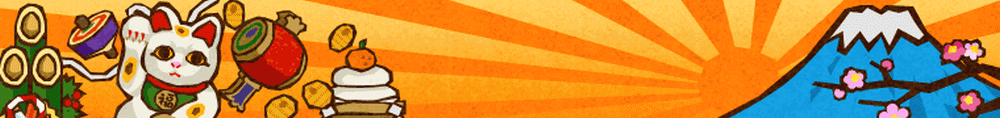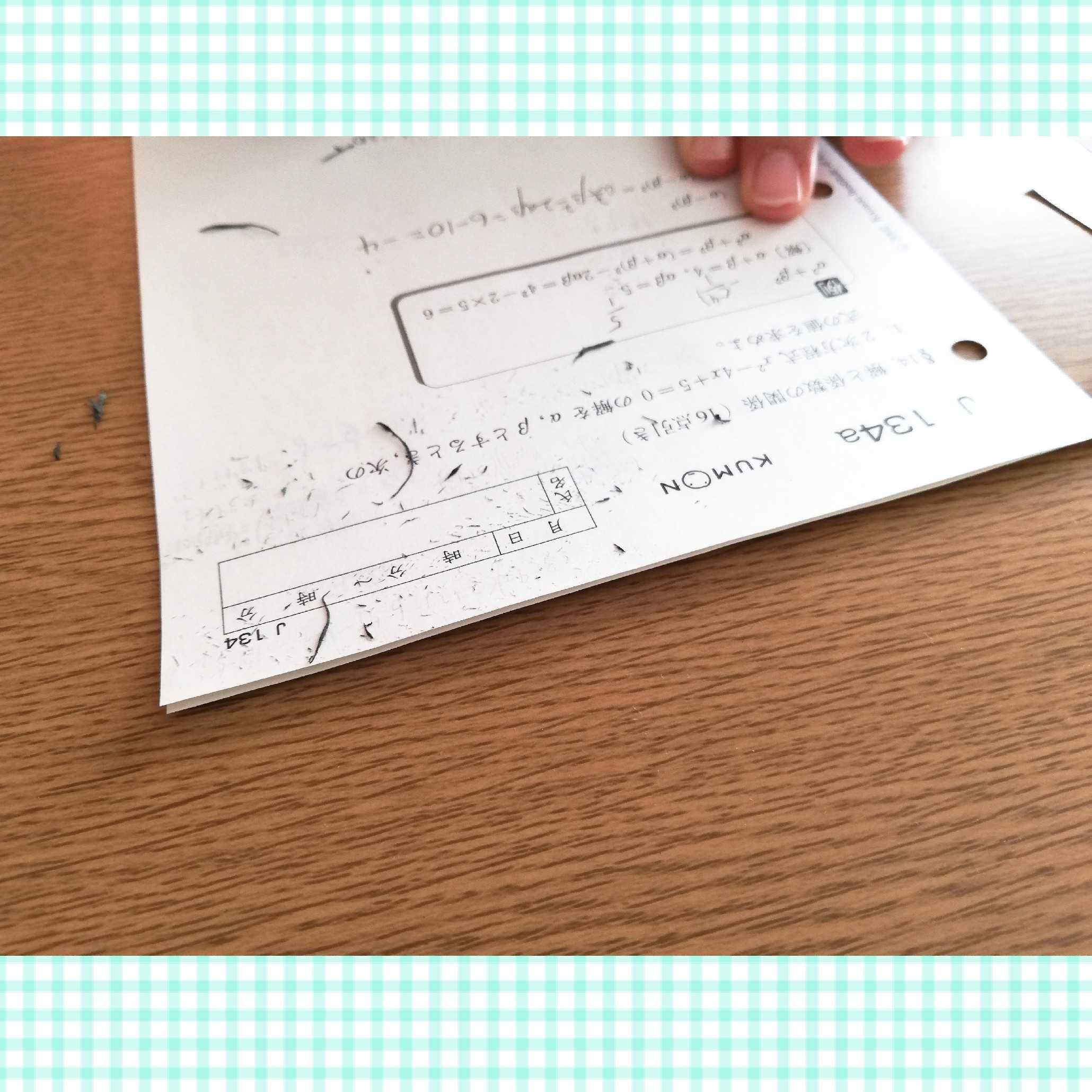2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年10月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
読み方なぁーに3
では、昨日の答え。 魂消た~たまげた 毳毳~けばけば UFOをみて、たまげた・・・・となるわけです。子どもたちは、そのまんま「魂消えた(たましいきえた)」と読んでいました。つまり、UFOに乗っている宇宙人に、魂が吸い取られると考えたようです。 もう一つの方は、「あっ、君のセーターに・・・・がついているよ。」という例文を出しました。これがなかなか難しかったようです。昨日は、時間がなかったので問題を出しただけで終わりました。たぶん珍解答が続出するはずです。楽しみ。 この日は、後4問、問題を出すだけ出して終わりました。 不味い 疾っ疾と 雀斑 若気る 答えは、上から「まずい・とっとと・そばかす・にやける」です。とりあえず、読み方なぁ~には、これにて、いったん終了。 次は、反対語に行く予定です。
2006年10月31日
コメント(0)
-
読み方なぁ~に?2
昨日の続きです。 これも、最近はあまり目にしないものですが、子どもたちの解答がけっこう楽しいので。 父は冬場には湯湯婆をてばなさない。 答えは、「ゆたんぽ」ですが、まず間違いなく「ゆばぁば」と読みます。 あの「千と千尋の・・・」の「ゆばぁば」です。「ゆばぁば」をてばなさい父って・・・。 いややなぁ。 魂消た 毳毳 この2つもなかなかの珍解答続出。 答えは次回で。
2006年10月30日
コメント(0)
-
読み方な~に?
読み方はなぁに? 以前、ブックオフで、平成教育委員会の本を見つけました。 1冊100円。 やすい! 思わず、3冊大人買い(笑) その中から、小学生にでも解けそうな、そして、楽しめそうなものをチョイス。 ちょっとした時間に問題として出しています。 今回は、読み方問題。 河馬 海豚 土竜 これは、比較的簡単です。 正解は、上から「かば・いるか・もぐら」ですね。 次は、ちょっと難問。 日本人はやっぱり御御御付が好きである。 最近の子は、「おみおつけ」という言い方を知らない子も多いです。そういう意味でも難問。でも、家に帰ってお家の人に出してごらん・・・と、ふればオッケー。 3問目は、子どもも知っているので大丈夫。 子どもの頃使った御虎子を見つけた。 正解は、「おまる」 いろいろと珍解答続出。 なんやかんやとつっこめば、さらに盛り上がります。 でも、なぜ虎なんやろ? 虎のイメージ無いよねぇ~。 このシリーズは、まだまだ続きます。
2006年10月29日
コメント(0)
-
ヒーローショー最高!
遊園地などに行って、ヒーローショーなんかやっていると、娘が見たくないと行っても必ず見ることにしています。 かなり勉強になるからです。 最近のヒーローショーは、 怪人がやってきて、それをヒーロ-がやっつけて、お終い。という感じではなく、とちゅうにお客をステージにあげてトークをしたりしています。 つまり、 お客のいじり方・場の盛り上げ方を学ぶいい教科書になるわけです。 コンサートやライブなどでももちろん学ぶことが多いのですが、金がかかっていない・・・言い換えれば、手作り感いっぱいと言うところが、実際に現場に役立てやすいのです。・・・と、またまた無理矢理理論武装。 以前も、プロレスをみた後、このようなことを書いていたような気がします(笑)。
2006年10月29日
コメント(0)
-
自己新記録達成
昨日、ある学校の研究会に参加しました。 総合の授業です。 カレーライスにぴったり合うお米を作ろう 何種類かのお米をブレンドして、そして、それを近くのお米やさんで販売してもらおう!という、スケールの大きな楽しい勉強でした。 学校に行ってみると、カレーのかかった4種類のお米を試食させてくれました。 もちろん、おいしく完食。 実は、日曜は、夕飯、カレー。 その後、木曜まで、毎日、朝はカレー。 そして、この日の昼。 これで、日曜から1日1食ずーっと、カレーを食べています。 自己新 よし、今日のお昼も、カレーを食べにいこ。
2006年10月28日
コメント(0)
-
木が4つで、ジャングル。では、木が5つでは?
先週末、教育の鉄人さんの学校公開があったので、参加させていただきました。 その鉄人さんから教えていただいた漢字クイズに次のようなものがあります。「木が2つで?」「林です。」「さすが。第2問。木が3つでは?」「森です。」「次は、難しいよ。木が4つで?」「・・?」「ジャングルです。」「ハハハハハ」「教科書の後ろに載ってるよ。」 あわてて探す子が何人か。「嘘に決まってるじゃん。」 ここまでが鉄人さんに教えてもらったクイズです。 で、この後、私はよけいなことを付け加えてしまいました。「では、さらに・・・木が5つでは?」「アマゾン」「凄いジャングル」「森林(しんりん)だよ。な~に、とんちぶってんだか。2年生でも読める漢字だよ。(スケバン京子風に)」 このネタ、いろいろな子や人で試しているのですが、ジャングルで、一度頭がそっちの方へ行ってるので、ほとんどの子がひっかかります。(今日も、授業の前に、保健室の先生に試してみたのですが、予定通りひっかかってくれました。大人の場合は、今まで100%の成功率です。) お試しあれ。
2006年10月26日
コメント(1)
-
あいさつ3連発 クラスのお気に入り
あいさつ3連発。 いろいろなバージョンの指示カードのとおり、「さようなら」を言うあいさつ3連発。 今、クラスで一番のお気に入りが、「関西のおばちゃん」。 日番が、このカードを引くと、みんな大喜び。 ジェスチャーつきで、「ほな、さいなら。」と言うのですが、これがジェスチャーからばっちりシンクロ。 気分良く学校から帰ることができています。 後、サークルのメンバーの音読プリントから教えてもらったのが、「欧米か!」 次のようなものです。 グッバイ! 欧米か! これは、私の今のお気に入りです。 それでは・・・ 明日も元気で・・・ さようなら。(大きな声) ほな、さいなら。 グッバイ!欧米か!
2006年10月26日
コメント(2)
-
インテル入っている?
明日までにしなければいけない仕事が・・・っ。 仕事がたまってくると、いつも思うことがあります。 あぁ~あ。 インテルが入っていたらなぁ。 いつまでもドラえもんの秘密道具がほしくなるのと一緒。 今、まさにその状態。 明日までにしなげればいけないことがたくさん。 さぁ、思いこもう。 思考は現実化する。 ピポパポ インテル入ってる。
2006年10月19日
コメント(0)
-
大名行列を横切っていい職業は?
社会の時間の迷解答。 大名行列を横切ると「無礼者!切り捨てごめん!」と、切られたそうです。 しかし、大名行列を横切っても切られなかった職業があります。 その職業とは何でしょう? 正解がわかったら、私だけに聞こえるような小さな声で答えをいいに来させました。「農家の人。」 ブー。 ピンポンブーで、正誤を判定してあげます。「医者。」 おしい・・・。 そんな感じで続いていったのですが、思わず笑ってしまったのが、これ。 ゴジラ うん。 確かに、ゴジラが横切っても、切り捨てできひんわな。 っていうか、逆にやられるやん! ちなみに、答えは産婆さんでした。
2006年10月18日
コメント(0)
-
貯めるときは貯める
以前も紹介した元WWEのディーバ鈴木浩子さんのブログより。『これだけ耐えての出発だ。どうせ飛び立つなら絶対に成功したい』『これだけ考えてのアイデアだ。現すからには絶対ものにしたい』こうして、更に、慎重に、鉄壁に、確実に旅立つための《地ならし》を始める。今すぐ逃げ出したい。それも耐える。楽な方を、無難なところで妥協もしたくなる。それも耐える。これが、第一歩。そのうち、やりたいことが見えてくる。今すぐその行動を起こしたいのもとりあえず耐える。イラつく。きついけどそれも耐える。こうなれば、あともう一歩。ここまで来ると、逆に慎重に《時》を見るようになる。そして風が吹いた時、その時こそ一心不乱、スピード勝負。一気に仕掛ける。これが健想の学んでいる哲学なのだ。大成功をしている先輩方も、口を揃えて《スピード》という。今のこの情報社会の中では、スピードがものをいう。タラタラやっていたのではもっていかれてします。だからこそ一気に仕掛けられるように、準備をしっかりをしなければいけないというわけ。《スピード勝負》だからといって、焦ってはだめ。貯めていないものを小出しにしていったのでは元も子もない。 スピード勝負といっても、中途半端はいけない。 なるほど。 なんか凄くよくわかります。 貯めるときは貯める。 貯まっているのは、皮下脂肪ばっかりですが・・・。
2006年10月17日
コメント(0)
-
ルパン酸性~っ。
6年理科。 リトマス紙を使った実験をしました。 青いリトマス紙が赤くなるのが、酸性。 赤いリトマス紙が青くなるのが、アルカリ性。 変化なしが、中性。なんですが、どっちがどっちだったか覚えにくい子もけっこういます。 そこでの暗記テクニック。 ルパンのジャケットの色は? 赤(緑もあるけど、こっちは無視) そうです。 赤になるのは、ルパ~ン酸性。 あまりものくだらなさがグッドでしょ。 ちなみに、アルカリ性の方の覚え方は、 あっ。ルカリオ! ルカリオの色は? 青 そうです。 青になるのが、アルカリ性。というもの。なんのこっちゃと思うのでしょうが、実はルカリオという青色のポケモンがいるんです。大人的にはルパン酸性の方が、圧倒的にいいのですが、子どもにはこちらのほうもけっこううけます。
2006年10月17日
コメント(0)
-
シュワルツネガーの話
まだシュワルツネガーが、知事になる前。 ターミネーターの前。 シュワちゃんなんて言われる前。 つまりは、ボディビルダーとして出てくる頃の話です。「アーノルド・シュワルツェネッガーの鋼鉄の男」というビデオでの彼の言葉。 辛くないことを何度繰り返してもダメだ。身体は苦痛を通して鍛えられる。筋肉は痛みを通して発達する。その繰り返しが筋肉をたくましくする。チャンピオンの分かれ道もそこにあるんだ。苦痛に耐えた者だけがチャンピオンになれる。多くの人に欠けているのは、何事にもめげずに突き進むガッツだ。ジムでの痛みのあまり気絶してもボクは恐れない。吐いたこともあるが、すべて自分のためだ。 すごいなぁ。 芸能活動を中断して、アメリカに武者修行に旅立った赤西くん・・・じゃなかったなかやまきんに君にも捧げたい言葉です。 もちろん、辛いことが嫌いな自分にも。
2006年10月16日
コメント(0)
-
祝タイガース優勝!!
少々(?)締め切りが終わりましたが、やっと、原稿ができました。 急いで本局まで行き、速達で送る。 これで、一つ仕事が片づきました。 次は、小学館の原稿。 こちらは、7ページ。 最初の1ページは扉なので、原稿話で、6ページ。 テーマは、「ほめ方・しかり方」。 締め切りは、今週末。 書く内容はあるので、後はどのように料理していくか・・・ということになります。 さぁ、ちょっと(たくさん)休憩して、書き始めるか!・・・と、ネットを見てみたら、ついにタイガース優勝! やったぁ。 ・・・と、言っても阪神ではなく、デトロイトの方。 まぁ、今年は、それで我慢しとくか。
2006年10月15日
コメント(0)
-
未来とは~。
ターザン山本氏のブログからの引用です。学級指導で使えそうです。そして、何より、すぐに流されてしまう自分を反省!「やる」と宣言しながら実行しない人がいる。それはまずい。流されて生きる。そうなると未来は絶対に見えてこないのだ。未来とは今とは違う自分のことなのだ。流されながら生きていると、未来にも今と同じ自分しかいないことになるのだ。
2006年10月13日
コメント(0)
-
コンピュータ室には行かせない。
今、論文の下書きをおこなっています。 次のようなものです。 すでに、締め切りは過ぎていて・・・がんばらねば。 例えば、次のような課題で調べ学習をおこなったことがある。「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。この3人のうち、1人応援演説することになりました。あなたは、誰を選びますか?」 1人選んだ後、立ち会い演説会(討論会)をおこなうことを告げた。 まずは、織田対豊臣。どちらの応援が説得力があったのかは、徳川を選んだ子どもたちが判定する。 残りの対戦もおこない、総当たりの応援演説リーグ戦をおこなうのである。 討論の好きな子どもたちである。 この仕掛けに、子どもたちは燃えた。 討論に勝つには、自分が選んだ人物のいいところや相手が選んだ人物の悪いところを調べる必要がある。「先生、コンピュータ室に行ってもいいですか?」 子どもたちは、すぐにコンピュータ室に行きたがった。 そう、最近の子どもたちは、すぐにインターネットで調べたがるのである。 しかし、インターネットでお目当ての資料を見つけるのは、大人でもけっこう難しいものである。 下手をすれば、1時間コンピュータと向かい合って、成果無し・・・なんてことも出てくる。(というか、特に指導なしでおこなえば、多くの子がこうなるはずである。) しかも、インターネットの資料の場合、多くは大人向けのもの。 いきなり、マニアックになっても仕方ない。 まずは、基礎基本的な内容を調べさせたいものである。 そして、基礎基本的な内容を調べるのに、一番適して調べツールといえば、やはりこれ。 教科書である。 いきなりコンピュータ室には行かせない。 まずは、教科書(資料集)で調べる内容をクリアーさせるのである。「最初は、教科書(資料集)で調べます。それがクリアーして、まだ時間があったら、コンピュータ室や図書室に行ってください。」 もちろん、クリアーしているかどうかのチェックは教師がおこなうのである。
2006年10月11日
コメント(0)
-
さて、来年の応援団は?
先週末、民舞研究会のメンバーで、今年おこなったそれぞれの学校の運動会の表現運動のビデオ上映会をおこないました。 同じ組体操でも指導する先生によってずいぶん違うものです。おこなっている技については、そんなに変わらないのですが、流れる音楽、隊形、演出など全然違いました。ちなみに、私の学校は、迷曲ゴーゴーカリートにあわせ、アップテンポな感じで組体操がはじまり、最後はダンス隊による恋のペコリレッスンのダンスの後ろでタワーができあがるという何ともあわただしいもの。 さて、ついでに応援合戦も見てもらったのですが、これも大受け。「こんな応援合戦見たこと無い。」「趣味丸出しやな」と、大絶賛(?) 調子に乗った私は、来年度以降の計画も話しました。「応援団の反乱は、第1話で、来年以降も続くんやで。」 そうなんです。 一度、小芝居をおこなうと、子どもたちも期待します。 スターウォーズサガならぬ、応援団サガが続くわけです。 ちなみに、エピソード1は、今年おこなった「応援団の反乱」 エピソード2は、平和な運動会に突如現れた黒組という運動会をじゃまする悪の組織を応援団長を中心になってやっつける話になります。(細部は、子どもたちと相談して決めるので、多少変わりますが・・。) 以後、応援合戦で何かが起こるという伝統ができあがるのです。(ちなみに、私が昨年度までいた学校はそうなっています。新任の頃からそこにいる先生は、応援合戦はそういうものだと思っていたようです。)
2006年10月10日
コメント(0)
-
24を見た。
久しぶりに24を見ました。 昨夜からシーズン4の放送が地上波ではじまったのです。 シーズン3は見ていないのですが、まぁ大丈夫だろうと、見てみたのです。 相変わらず、CTUは忙しそうです。 あれを見たら、私たちの仕事なんて・・・。 忙しいなんて言ってられません。 相変わらず、ジャックバウアーは働き者です。 彼を見たら、自分がためてる仕事なんて・・・。 うん。もっと働かなくちゃ。 締め切り間際の教育書の原稿があります。 ジャックを見習い、今から、がんばります。
2006年10月09日
コメント(0)
-
バリエーションカード2
バリエーションカード、子どもたちはいたくお気に入り。 授業が終わった後、私の机の周りに集まり、自分達で新たなカードを作りだし始めました。 宇宙人のように 周りながら ピカチュウのように などなど しかし、ピカチュウのように・・って。「ピカ、ピカ、ピカチュ~」 ピカチュウって、ピカしかいわへんやん! でも、おもしろいから採用。 私が独断で、採用、不採用を決めました。 練習風景は、なんかガラスの仮面っぽくて、楽しいです。
2006年10月08日
コメント(0)
-
音読バリエーションカード
やっと国語の教科書が下に入りました。 現在、扉の詩「希望」を、班ごとに群読練習をしています。 一人で読むところ、二人で読むところ・・・と、班ごとに相談工夫して読み方を変えておこなっているのです。 これは、これなりにがんばっているのですが、ちょっとお遊びでもうひと味加えてみました。 バリエーションカード トランプ大の大きさの紙に、「大きく」だとか「小さく」だとか「悲しそうに」とか書いておきます。 それを音読する前に1枚引いて、その指示通りに読むというものです。 どのような指示が出たのかは、他の子にはわからないようにします。 他の子がその子の音読を聞いて、カードの指示がわかれば、オッケー。うまい!・・・ということです。 初めてのこの日、かなり盛り上がりました。 そこで、帰りの「さようなら」もこのカードを使うことに。 出たカードは、「小さく」「とびながら」「大きく」の3枚。 楽しく最後の一日を終えたのでした。
2006年10月07日
コメント(2)
-
新しいノートにイラスト
ある教育書に、子どもが新しいノートを持ってきたら、毛筆を使ってその子の名前を書いてあげる・・・という文章が載っていました。 子どもたちは大喜び。 ノートを大切に扱う。のだそうです。 この実践をまねしたわけではないのですが、私も似たようなことをおこなっています。・・・といっても、私の場合、達筆ではありませんので、毛筆は使いません。 子どもが希望するイラストを一つ描くということをしています。 子どもたちが今何が好きか・・・という実態把握にも一役買っています。 現在、たわせんクラスで、リクエストの多いのは、男子ではブリーチ、女子ではチャオ関係のものといったところです。
2006年10月06日
コメント(0)
-
やる気パワー
小芝居は、前日の仕上がり具合によってはやらない。といいましたが、実際練習したのは、前日の30分のみ。 ただし、シナリオは、私が以前使ったのをたたき台にして、6年生と相談して3日前に制作。 役決めをした後、残りの2日で覚えるように指示。 5年生に、小芝居をすることを教えたのも、前日。 3,4年生に至っては、運動会当日の応援合戦の30分前。「おもしろそう。」「わくわくする。」 子どもたちがやる気を出したときのパワーはすばらしいものがあります。 結局、教師の仕事というのは、そのやる気のパワーを引き出すことにあるんだなぁと、今回、再確認しました。
2006年10月04日
コメント(0)
-
小芝居は、当日まではシークレット
さて、後半戦。 ここでは、6年生にがんばってもらいます。 前半で、かなり声は出てきました。 6年生なしでも、大丈夫なぐらい自主性も出ています。 そこで、後半1日目は、6年生は別行動。 違う部屋で、開会式の言葉や応援合戦の打ち合わせをしました。(この間、5年生以下は体育館で練習) ここで、開会式の言葉と小芝居をおこなうことに決定。 きっちりとしたシナリオなどは、別の時間に考えると言うことに。団長・副団長と相談し、でき次第暗記してもらうことに。 ここでのポイントは、一つ。 小芝居は、シークレット。誰にも秘密。 これが、応援団の一体感を高めます。(この時点では、知っているのは6年生のみ) それと、付け加えるのなら、 小芝居は、前日の仕上がり具合によってはやらないことも告げておきます。別になくてもいいことだからです。 しかし、子どもたちは、この小芝居やりたくて、やりたくて仕方なくなっています。セリフなど必死に家で覚えてきます。当然、練習にも熱が入るというわけです。
2006年10月03日
コメント(0)
-
自分達だけでも練習する。
応援団の練習は、本番2週間前からはじまりました。 練習時間は、昼休み。 そして、前日の準備の時間の30分ほど。 昼休みは、だいたい20分。それが10回。 20×10+30=230 だいたい4時間弱の練習時間です。 その練習時間で、・団長などの役決め・応援団の心構え・エール・3・3.7拍子・2拍子・レッツゴー応援・応援歌・開会式の呼びかけ・応援合戦(小芝居をのぞく)・応援合戦(小芝居)をしなければいけません。 こうやって書くと、よくできたなぁと言う感じもしますが、ポイントさえはずさなければ大丈夫。担当教師は焦ることなく、運動会を迎えることができます。 最初の一週間は、上で言う開会式の呼びかけまでの部分を練習します。 この部分さえできていれば、最悪でもあと(呼びかけや応援合戦など)は、6年生の応援団長・副団長だけでもなんとかなります。 この前半のポイントは、練習のシステムを作ると言うことです。 つまり、 教師がいなくても、練習ができるということになります。 もう少し付け加えるのなら、6年生が来ていなくても、5年生中心に練習ができる。5年生が来ていなくても4年生中心に、3年生しか来ていなくても3年生だけで・・・ということです。 お昼休みの練習時間、運動会の練習が延びて、給食終了が遅れる場合があります。すこしでも練習時間を確保するために、そして、自主的に動けるようにするため、ここんとこは重要です。「本番でも、5・6年の騎馬戦の時は、4年生が中心になって応援しないといけません。プログラムによっては、5・6年の演技の次が4年生の演技と言うこともあります。その時は、3年生だけで応援しないといけないのです。だから、昼休み、体育館に来た時6年生がいなくても、来た人から練習を始めてください。」というようなことを話しました。 各学年ごとに一人団長を決め、笛も渡しておきます。 このシステムがうまく機能すれば、後半の練習もぐっと効率が上がります。
2006年10月02日
コメント(0)
-
応援合戦シナリオ
ミルマスカラス効果のおかげか、昨日の運動会は大成功。なかでも、応援合戦は今までにはないパターンだっただけに、子どもにも大人にも新鮮だったようです。まずは、そのシナリオを紹介します。応援合戦シナリオ20061*入場 (赤・白) 太鼓の合図で、その場に整列!2*赤組の応援(赤組) (白組は、体育座り) 「たらこの色は何だ!」 「赤だ!」 「太陽の色は何だ!」 「赤だ!」 「勝利をつかむのは!」 「赤だ!」 「赤組、優勝するぞ!」 「オーッ!」 この後、3・3・7拍子、2拍子、レッツゴー応援、応援歌をおこなう。3*白組の応援(白組) (赤組は、体育座り) 「ごはんの色は何だ!」 「白だ!」 「体操服の色は何だ!」 「白だ!」 「勝利をつかむのは!」 「白だ!」 「白組、優勝するぞ!」 「オーッ!」 この後、3・3・7拍子、2拍子、レッツゴー応援、応援歌をおこなう。4*エール交換(赤・白)赤組A 「それでは、白組の健闘を祈って、エールを送ります。」 (全体練習ではエール交換をしておしまい。) 5*本番バージョンでは、ここで反乱が起こる。赤組・A それでは、白組の健闘を祈って、赤組・B ちょっと、待った! わたしたちは、白組にエールを送りたくない。赤組56年 オーーッ。赤組・B 優勝するのは、赤だ!赤組56年 オーーッ。放送 MJ おーっと、これはどうしたことでしょう。赤組応援団が、 エールを送りたくないと言い出しました。 どうですか? 解説のOYさん。解説 OY いけませんね。○小はじまって以来の事件ですよ。放送 MJ さぁ、これに対して、白組はどうするのでしょうか。白組・A もちろん、白もエールを送らない。白組56年 オーーッ。白組・A 今年も勝つのは、白だ!白組56年 オーーッ。放送 MJ さぁ、大変です。白組もエールは送らないと言ってます。解説 OY 売り言葉に買い言葉ってやつですね。 <「猪木ボンバイエイ」の曲が流れる。> 赤組、白組、曲にあわせて、戦う(最初赤組3歩前に出て、パンチ。白組大げさに倒れる。その後、白組。4拍子のリズムに合わせて、踊る?)。 赤白団長 お待ちなさい。 <「盛り上がりCDからオープニング」の曲が流れる。>放送 MJ 応援団長です。応援団長の登場です。解説 OY 派手に登場しましたねぇ。 (実は、応援団長はエールの交換がはじまると、後は副団長に任せて、本部席の方へ移動、白団長はマツケンサンバの金の衣装。赤団長は赤の衣装を着て、隠れている。)放送 MJ そうです。この騒ぎを止めることができるのは、もはや応援 団長しかありません。がんばれ、応援団長。応援団34年 フレーフレー団長。フレーフレー団長。フレーフレー団長。白団長 けんかはいけません。赤団長 そうです。みんなは忘れたのですか? <このあたりから、「青春アミーゴ」が流れる。>白団長 開会式で、「正々堂々 戦おう」と、誓ったことを。(赤組、白組5,6年応援団ガックリとうなだれる。)赤組・B そうだ。「正々堂々 戦おう」だ。赤団長 正々堂々 戦おう!応援団 56年 戦おう!(小さな声で)赤団長 正々堂々 戦おう!応援団 56年 戦おう!(大きな声で)白団長 やっと、分かってくれましたね。赤団長 さぁ、エールの交換をしましょう。放送 さすがは、団長です。さぁ、みんなもいっしょにエールの交換をしましょう。赤組・A 白組の健闘を祈って、エールの交換をします。フレーフレー、白組。以下・応援合戦のプログラムにもどる。「応援団、退場します!」退場 赤・白太鼓の合図で、駆け足で退場応援合戦の練習では、小芝居の部分はやっていませんでしたので、低学年の子どもたちは、本当にけんかが始まったのかと、どきどきしていたそうです。応援団長が朝礼台の上に登場したときは、歓声(&笑い声)があがりました。
2006年10月01日
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1