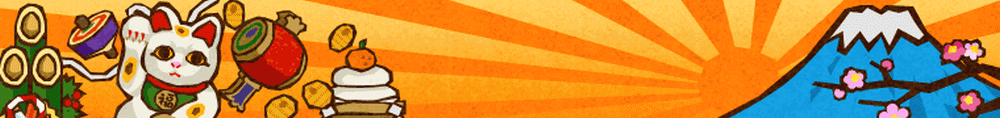2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年11月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
予想外だ!
「それでは、野田さんに答えを発表してもらいましょう。」 タッタラタタッタラタタッタラタタ~。「ハリネズミ。」「予想外だ!」 今週になって、やたらたわせん学級で流れている「タッタラタタッタラタタッタラタタ~」は、AUでおなじみのプロコフィエフ/バレエ組曲「モンターギュ家とキャピュレット家」です。 ただただ、みんなで「予想外だ!」を言いたいがために、ゲットしました。 もちろん、子どもたちには大受けです。 ベストクラシック100の1枚目の14番目「モンターギュ家とキャピュレット家」がそれです。けっこうツタヤにもありますので、おすすめです。
2006年11月30日
コメント(0)
-
教師色気論
最近、ちょっと多いのですが、またまたターザン山本!氏からの引用。ターザン氏の教師論。なるほど、色気ね。何となくわかるような気もします。教師に一番、必要なものは色気だ! ・あこがれと尊敬。そういう目で生徒から見られている教師。それが理想である。その部分で生徒が満たされていると…。学校で今、いじめの問題が起こっている。それについてはいろんな見方があるが、一つ言えることは教師(先生)が子供(生徒)から見て魅力的な人間であること。これがすべてのような気がする。あこがれと尊敬。そういう目で生徒から見られている教師。それが理想である。その部分で生徒が満たされていると、いじめは起こらないかも。そんな気がする。これはきわめてボクの楽観的な見方である。じゃあ何がどう魅力的なのかとなる。そう言われるとボクもこたえにくい。ただ子供もバカではない。直感という武器がある。彼らは瞬時にしてそれを判断してしまう。教師というのは意外と生徒からジャッジメントされる存在なのだ。そこでボクが考えたのは色気のある教師という概念である。人としての魅力は色気があるかどうかに尽きるのではないか?それは簡単にいうと利益、利害、損得、計算を超えた「何か」を持っていること。それが色気の条件となる。その「何か」は謎でなければならない。だから色気とは謎、不思議さ、求心力のことをいう。そういう教師や先生はいなくなったのかなあ。その存在が形而上的であること。そうでなかったら教師とはいえない。そういうハードルの高さがあって人は初めて教師になることができるのだ!
2006年11月28日
コメント(0)
-
ごめんね。うん、いいよ。
今回も、ターザンさんのブログより引用。 途中からの引用なので、意味がわかりにくい点があるかもしれませんが、自分のメモ用という意味が非常に強いので、お許しを。 まったく便利な方法だ。これはもしかすると日本人の得意技かもしれない。もともと神道では罪という概念はなかった。「けがれ」と「はらい」の世界ですべてが処理されてきたからだ。薬物疑惑の事件はいわゆる「けがれ」である。だったらその「けがれ」は「はらい」ですませればいいのだ。日本人は不滅だ。ボクはこの考え方をある部分で支持する。(と中略)でもボクのまわりにも心の苦しみをかかえている人は非常に多い。ボクが思うにそれって忘れることの自由を失った人たちだと思うのだ。こうなると悩みは泥沼化する。その解決方法を始めから知らない民族だからだ。思い出して欲しい。君たちがかかえている「けがれ」は「はらえ」ばいいってことを。悩むな。はらいなさいである。されば救われんである。 なるほど、「はらい」ですか。 罪という概念は、古来の日本にはない。 どこかで使えそうです。 少し話は変わりますが、小学校の子ども社会では、「ゆるす」というキーワードは、けっこう重要です。「ごめんね。」「うん、いいよ。」 謝りさえすれば、けっこう簡単に子どもたちは許してくれます。 なんかわざとらしい・・・・と、大人は感じてしまうのですが、実は、これはかなり重要なことなのです。 しっかり「ゆるす」という練習を小学校時代に学習しているわけです。
2006年11月27日
コメント(0)
-
明治時代は四字熟語4
さっきのは、ほんの空き時間用なんですが、がっつり授業もおこないました。 並び替えゲームです。 明治時代を表す上で重要なもの。 さらに年号のはっきりとしているものを12枚選び、黒板にバラバラに並べました。 一番古いのは(明治時代ではありませんが)、「黒船来航」。 一番新しいのは、「韓国併合」。「さぁ、途中を並べかえましょう。」という具合です。 子どもたちは、年号も付け加えて、ノートに書いていきます。 これで、明治時代の大きな流れがざっとわかります。 具体的な細かい内容はこの後、入っていくわけです。 ちなみに、これ、ゲームでも何でもないですが、何となく楽しくなるでしょ。 雰囲気、雰囲気。
2006年11月26日
コメント(0)
-
明治時代は四字熟語3
厚紙(だいたいA4サイズ)にきれいに書かれた四字熟語。 最終的にはファイルにとじて、明治時代四字熟語辞典をつくろうと考えています。 が、使い道はいろいろとあります。 一つ目は、基礎基本定着用。 つまり、フラッシュカードとして使うのです。 ステップ1は、教師が読んだ解説を聞いて、何の四字熟語か当てるというもの。 ステップ2は、その逆。 こういうのを、ちょっとした空き時間にやります。
2006年11月26日
コメント(0)
-
明治時代は四字熟語2
次の日、社会の時間なのに、習字の用意。 まずは、ずらーっと黒板に書かれた明治四字熟語の中から、一つずつ担当を決めました。 次に、その担当した四字熟語の解説をうすい緑色の紙にネームペンで書かせました。 解説といっても、教科書、資料集に載っている用語解説の丸写しです。 10分ぐらいできあがり。 これを厚紙の裏に貼ります。 当然、表は毛筆。 さぁ、習字の時間の始まりです。 厚紙は、高価ななため(笑)失敗は許されません。 半紙に練習をしました。 別に、毛筆指導が目的ではないので、鉛筆の下書きをありにしました。 修正ペンでの修正もオッケー。 みんな、けっこうきれいに仕上がりました。 まずは、鉛筆で下書きをする。 毛筆指導の革命かも!(笑)
2006年11月25日
コメント(0)
-
明治時代は四字熟語
ある時、社会の教科書を見ていて、ふっと気づきました。 明治時代は、四字熟語が多い。 そうなんです。明治時代のプロローグとも言える「黒船来航」から始まって「日清戦争」「日露戦争」まで明治時代のキーワードはほとんど四字熟語であらわせます。 まずは、教科書、資料集から四字熟語を見つけ、発表させました。 大政奉還 明治維新 富国強兵 地租改正 四民平等 文明開化 廃藩置県 版籍奉還 憲法発布 帝国議会 韓国併合 西南戦争 日清戦争 日露戦争 官営工場 郵便制度 足尾銅山 条約改正 ・・・などなど(順不同) まずは、ここまで1時間。 次は、調べ学習と習字とのコラボ。 翌日に続く・・・・となりました。
2006年11月23日
コメント(0)
-
551の豚まん4万年分!
今日、何のきっかけか忘れましたが、松坂の話になりました。 そこで、トリビア的知識はなぜかよく知っている高田君の一言。 松坂の60億って、551の蓬莱の豚まん、朝昼晩と毎日食べても、4万年分らしいで! この事実に、みんなびっくり。 まさに、驚愕の事実。 でも、朝昼晩1個ずつやったら、たらへんわ! おいおい、びっくりするところはそことちゃうやろ!
2006年11月21日
コメント(0)
-
特殊相対性理論を唱えた人
最近おこなっている学校が多いのですが、本校でも朝、読書タイムというのをおこなっています。 で、さらに、時々、その時間に、地域の人がボランティアで本の読み聞かせに来てくれます。 先週は、うちのクラスに来てくれました。 読んでくれたのは、「モモ」。 時間泥棒の話です。 読み聞かせが終わった後、なぜこの時期に「モモ」を聞かせてくれたのか・・・自分の考えをノートに書かせました。 そして、全員発表。「卒業までの、残り時間を大切に扱ってほしいからです。」というようなことを言っていました。 合格です。 次に、話はずれて、特殊相対性理論のこと。「時間というのは、一定に流れいないんだよ。」 一人ぐらいは知っているだろうという期待の元、次の質問。「この特殊相対性理論を唱えた人は誰か知っている?」 唯一のヒントは、外国の人というもの。 予想通り、元気な男子が手を挙げます。 100%違うだろうなと予想しつつ、いつもすてきな(?)解答を答えてくれる篠沢君を指名。「はい、モナリザです。」 予想外だ(笑)
2006年11月20日
コメント(0)
-
司会ウィーク!
思い起こせば、ここ1週間、やたら司会をしています。 先週の土曜・日曜は県の教研集会、自治的諸活動の分科会の司会。 月曜日は、勤務校の全校朝会の司会。 水曜日は、司会ではないですが、5年目の先生方の指導助言。ちょっと会の進行が気になり、司会っぽいことも。 金曜日は、研の社会科県大会3年生分科会の司会。 土曜日は、音楽会の反省会の司会。 昨日、音楽会の反省会の司会をしていて、ふっと気づいたのです。「なんか、司会ばっかりしてないか?」 軽いものから、重いものまで、いろいろとありますが、こんな週ははじめてです。 この1週間で司会の経験値がかなりアップしています。 レベルアップにまでは、至っていませんが・・・。 何の役にも立たない情報ですが、自分にとって珍しかったもので、お許しを・・・。
2006年11月19日
コメント(0)
-
ブシオネアで基礎基本2
4拓問題、ブシオネア。 まぁ、4拓といっても解答に、どの問題にも「俺様」や「マウリシオ ショーグン」などのボケがあるので、実質は3拓問題(問題によっては、2拓)なのですが・・・。 問題自体は、すべて教科書レベル。 教科書を音読して、キーワードに線を引かせているのですが、ほとんどの問題はそこから出ています。・・・で、一つの単元(6ページから8ページ)で20問。 こんな感じで問題はつくられています。 4拓問題でもあるし、答えはほとんど教科書に出ていますので、どの子も自習でも宿題でもできるというわけです。 まず、ブシオネアのプリントをします。 そして、次の日、テスト。 テスト問題は、ブシオネアと全く同じです。 ただし、選択問題ではなくなります。 しっかりと覚えとかないと解けません。これがあるから、ブシオネアが単なるお遊びプリントではなくなるわけです。 一応、テストは2回しました。 合格点は80点。 2回目で合格しなかった子は、再テストとなります。(ほとんどいませんが・・・。)
2006年11月19日
コメント(0)
-
ターザン山本!の教師論
今日もターザン山本!さんから引用。今回は、教師論。使えそうな文がいっぱいです。教師と生徒の関係について。 ・尊敬とあこがれの心がなかったら人は誰も学ぼうという気にはならない。子供たちにはその考えが非常に強いのだ!「教育基本法」が衆議院を通過した。 国家が教育の現場に介入することはNOといって野党は反対したが、結局は与党の押し切り勝ち。 教育に関しては教師の免許制度を見直そうという動きも出ている。 教育とは「初めに教師あり」なのだ。 生徒からすると先生が魅力なかったらつまらないだろう。そんなものは退屈に決まっている。 教育とは、これはもう徹底した「現場主義」に尽きるのだ。 生徒VS教師の真剣勝負のことである。 こんな真剣勝負はほかにないと思うんだけどなあ。 それは学ぶ側の生徒の気持ちを考えたらよくわかることである。 尊敬とあこがれの心がなかったら人は誰も学ぼうという気にはならない。子供たちにはその考えが非常に強いのだ。 楽天の野村監督は「一流プレーヤーが一流プレーヤーを育てる」と言い続けている。 その一流プレーヤーを教師という言葉に置き換えたらわかりやすいのではないか? 「立派な教師が立派な生徒を育てる」 つまりは影響力のことである。悪いことはものすごい伝染力を持っている。 それは一気に感染していく。この伝染力と感染力は止めようがない。これに対して人の内面性にかかわるポジティヴな影響力は、少数派の中でしか起こらないのだ。 参考になるかどうか知らないがボクの教え方はこうだ。 生徒全員に平均的な視点に立って平等に教えていこうとは思わない。 自分の頭の中で理想的生徒を想像して、その想像の中の生徒に向かって授業をする。 それが現実に目の前にいる生徒のひとりだったりすることはある。 特定したひとりの生徒に向かって講義をするのだ。絶対にこの方がいいのだ。 教師も生徒からの特別な視線を感じた方がいいからだ。 このやり方には快感と快楽と自己満足がある。 想像の中の生徒と現実の生徒の両方を相手にしているからだ! ターザンカフェより
2006年11月18日
コメント(0)
-
ブシオネアで基礎基本
以前、子どもにミリオネア風の問題をつくらせていると書いたことがありますが、今年は先生も基礎基本を身につけさせるべく、ミリオネアをつくっています。 ちょうどやり始めたのが、武士の始まりからでしたので、コードネームはブシオネア。 今回は、その中から江戸時代の第1枚目を紹介します。 学年全クラス使ってくれているのですが、誰がつくったのかはバレバレのようです。☆4拓問題ですが、しっかり覚えるためにも記号で書かずに、答えはていねいにしっかり書き写しましょう。1・江戸幕府は、全国の200以上の大名を厳しく支配していました。では、「徳川氏の親類の大名」を何といいますか?A 親藩 B 譜代 C 外様 D 審判「ストラィ~ク!バッターアウト」 アンサー( )2・では、「古くからの家来の大名」は?A親藩 B譜代 C外様 D譜面台 アンサー( )3・では、「関ヶ原の戦いのころ、家来になった大名」は?A親藩 B譜代 C外様 D俺様 アンサー( )4・家康の孫、19歳で3代将軍になった人物とは?A徳川家康ジュニア B徳川家光 C徳川綱吉 Dマウリシオ ショーグン アンサー( )5・江戸幕府が決めたきまりを何と言いますか?これにそむいた大名は厳しく罰せられました。A 十七条の憲法 B慶安の御触書 C武家諸法度 Dピザハット アンサー( ) 必ずぼけが入っているのがポイントです。 ただ、このぼけがわかりにくい。 マウリシオ ショーグンなんて、クラスで一人しか知りませんでした。(ちなみに、ブラジルの格闘かです。) 答えの解説より、ぼけの解説に時間がかかります(笑)。
2006年11月17日
コメント(0)
-
失敗を笑えるクラス
昨日は、教職5年目の先生の研修会に、指導助言として参加しました。 そこでのレポートに次のような文章が。 間違いを笑う雰囲気はないか。安心して話せる雰囲気づくり。 なるほど、なるほど。 その通り。 大切なことです。 ただ、たわせん学級は、もう一ランク上をねらっています。 間違いを笑い飛ばせるクラス つまり、失敗を笑えるクラスです。 失敗しても、友だちにうけたからオッケー。 あいつは、あほな間違いもするけど、でも、好きやなぁ。 こんなクラスづくりを目指しています。 ただし、一歩間違うと危険な状態になります。よい子(教師)はまねしないでください。
2006年11月16日
コメント(0)
-
これ、いいわぁ。
愛国心というと、微妙な問題も含んでくるので、軽々しく発言などはできにくいのですが、いつも引用させていただいているターザン山本!さんの愛国心論は、納得。 これ、いいです。 愛国心とは日本語を愛すことだ! ・愛国心という言葉を聞いた時、ボクなんかはすぐに国境という言葉を思い出す。自分の国を愛すということは…。与党、自民党はどうやら教育基本法の改正に関して強行採決をする腹のようだ。どうなるかわからないがそういう気配がある。教育基本法の改正について一番の問題になっているのが、愛国心である。学校教育の中で愛国心を教えていく。それが自民党の考えだ。じゃあ、愛国心とは一体、何なのか? それを定義する必要がある。物事を定義しないのはすべてまやかしであるというのがボクの考えなのだ。定義しないことでごまかす。だます。利用するというやつだ。愛国心という言葉を聞いた時、ボクなんかはすぐに国境という言葉を思い出す。自分の国を愛すということは自分の国を守るということなのだ。なぜなら人類の歴史は国と国が戦争を起こし続けたという事実がある。それはもう間違いないのだ。そうするとその国境と戦争という概念は、人類の中に共通して遺伝子としてみんな組み込まれている。だから愛国心とは必然的に仮想敵国を意識することなのだという定義に落ち着いてしまうのだ。これはやばいだろう。逆にいうと仮想敵国というイメージがなければ愛国心という言葉は成立しない。そこでボクが考えた愛国心とは日本人にとっては、「日本語」を愛することだと思うのだ。日本語の中にあらゆる宇宙がぎっしりとつもっている。そこはボクたちにとって感性の宝庫でもあるのだ。人々が日本語にもし敏感になったら「いじめ」は起こらない。日本語は我々が生きる上で精神的プレッシャーを与えてくれるパワーを持っている。それを見逃している。わかっていない。日本語を好きになること。日本語に愛着をおぼえること。それなくして愛国心を叫ぶこと自体が、日本語に鈍感な人の言い方だとボクはそう考えているのだ!
2006年11月15日
コメント(0)
-
解答は、作文にして~星期天って何?~
中国語を日本語に の続きです。 中国語の辞書を持ってきたこのおかげで、一部の男子で中国語のブーム。 私も、せっかく辞書を持ってきたのだから、そこから出題することにしました。 そのうちの一つがこれ。 星期天「ヒントは、ほとんどの人が好きなものです。先生も好きです。たぶん、君たちも好きでしょう。」 今までは、答えをこそっと話させに来たのですが、この日は趣向を変え、作文を書かせてみました。 意味はわからなくても、意味を予想して、作文に書くわけです。 ちなみに、答えは「日曜日」です。(前々回の答えは、コンビニ・UFO・ロボットです。)「私は、昨日、星期天をたべました。」「居酒屋で、星期天のおかねをはらいました。」などなど。 正解を知っている私と、池谷君だけは大受け。 答えの発表の後、「へぇ~。剛田君は日曜日を食べるんだ?」「日曜日って、居酒屋で売ってるの?すげぇ。」など、つっこみを入れました。 楽しい時間が過ぎていきます。
2006年11月14日
コメント(0)
-
ターザン山本!のいじめ論
ターザン山本!さんのいじめ論。先週の金曜日から、3日間。出張で家を空けていました。いじめの話等々、協議会で討議をおこなって、疲れて昨日晩に帰宅。いつものブログを見てみると、ターザン山本!さんが、いじめについてコメント。元週刊プロレスのカリスマ編集長の考え、参考になると思います。「いじめ」の問題はやっかいだ。 現時点ではなんの解決にもなっていない。相当に根が深いと考えるべきだ。 しかしどんなこともシンプルに考えると、わかるべきことがわかってくるのだ。 なぜいじめは起こってしまうのか? 起こるという点ではいつの時代にもいじめはあった。 「なかった」のではないのだ。その部分はまずきっちり押さえておく必要がある。 だからいじめそのものを否定するのではない。そこも重要なことなのだ。 いじめは「ある」という視点に立って、そのいじめが深刻な実態を生んでいること、そのことを我々は考えなければならないのだ。 いじめそのものが絶対的に悪いと考えたら、それはナンセンスなのだ。 要はいじめがあった時、それにブレーキをかけるべきプレッシャーを与える人がいるのか? あるいはいじめにあった人をそっと救える人がいるのか? そこである。 つまりその両方の人がいないわけだろう。アクティブに助けられる人。マイルドに救える人。 ということは、傍観者だらけなのだ。 じゃあなぜ人は傍観者になってしまうのか? ずばりその答えは「私的正義感」がないからだ。 正義感とは一般的には「公的正義感」のことだとみんなそう思っている。そんな公(おおやけ)の正義感などあるはずがないのだ。 正義感はすべてその人個人にとっての内的な世界のことをさす。 それを称して「私的正義感」と呼ぶ。 それを現代人は失ってしまったのだ。正義感とは自分の心の中にしかないものだというそういう理屈がわからなくなっているのだ。 仮に公的正義感というものがあるとしたら、そんなものはまさしくウソっぱちだ。 内的なものに関するものは全部、私的なことにかかわってくるからだ。 その人の中にしか存在しない私的正義感の空洞化が日本の現代のいじめを起こしている最大の原因なのだ! ターザンカフェより)
2006年11月13日
コメント(0)
-
手紙って何?
読み方なぁ~に?の第2弾。 次の中国語を日本語になおせ。をやっています。 これも、前回同様、授業がはじまるちょっとした時間にやっています。 第1問は、けっこう有名なこの言葉。 手紙 これは、クラスの中でも一部の子は知っていました。 正解は、トイレットペーパー(ティシュペーパーでもオッケー)です。中国の友だちに、「今度、手紙送るで。」といったら、変な顔をされますよ・・・と補足。 第2問以下は、これ。 ・方便商店 ・幽浮 ・机器人 ヒントは日本語というとすべてカタカナ。 方便商店は、郵便局ではありません。 何と次の日、お父さんに聞いてくる子一人。 中国語の本を買ってもらった子一人。 国語とは、直接関係ありませんが、知的好奇心を揺さぶっていることは確かです。
2006年11月09日
コメント(0)
-
どこのけんぽう?
じつは、正解は、少林寺拳法。 少林寺拳法の理念なんです。 お粗末様でした。
2006年11月07日
コメント(0)
-
どこのけんぽう?
憲法第9条を世界遺産に・・・という本を読みました。 なかなかおもしろい。 意外にも、宮沢賢治の話も出てきて、これもやまなしの授業で使えそう。 そういえば、2年前におこなって憲法の授業で、 どれが日本国憲法でしょう?という問題を出したことがあります。 誤答もいくつか出したのですが、その中の一つがこれ。 これは、どこのけんぽうでしょう? あたったら、すごい! 半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」 ・・これが???の理念を表した宗 道臣のことばである。技術を身につけることで、イヤなものはイヤと言える自信と勇気を手に入れ、なおかつ、人と人とが協力し合うことの楽しさと大切さを学ぶことに修練の目的がある。
2006年11月07日
コメント(0)
-
いじめは許さない byターザン山本
今日は、私の大好きなターザン山本!さんのブログより引用。 考えさせられます。 今、いろいろと「いじめ」が社会問題になっているが、昔から「いじめなるもの」はあった。しかしそれによって不登校になったりひきこもったり自殺することはなかった。 ボクが教師だったらいじめは許さない。そういうプレッシャーを生徒に向けて発信する。だいたいそういうことは日頃から注意していれば勘でわかる。 いわゆる自信に満ちた強い教師がいなくなったのだろう。そうとしか考えられない。 もし自分のクラスでいじめがひどい形で進行していたら教師として恥だ。 あるいは世の中の人々が休みもなく勤勉に働いていたら、そういう社会ではいじめは起こらない。勤勉さによる共通認識が出てくるからだ。「心という生態系」。それを忘れてしまっている。 心と心が社会のもう一つの生態系を作っているからだ。 みているといじめの問題について心の生態系という発想がないのだ。それはだめでしょう。心の生態系という考え方をしたら、それは人事ではなくなるからだ。結局は人なんでしょう? それ自体が大問題である。
2006年11月06日
コメント(0)
-
戦後○○年
我が師匠有田和正先生の実践に、「戦後○○年」という授業があります。 ○○年というのは、第2次世界大戦から何年という意味で、今年授業をするのなら、「戦後61年」と言うようになるわけです。 授業の流れは次のようになっています。「戦後とはどういうことですか?」 第2次世界大戦後ということ。「第2次世界大戦に参加した国、つまり戦争をした国は何カ国ぐらいあったでしょう。」 答えは、60カ国。 参加しなかった国は、スウェーデン、アイルランド、スイス、スペイン、ポルトガルの中立国5つのみ。「第2次大戦後、どんな戦争や内乱があったでしょう?」「何回くらい、あったと思いますか?」 正確な数はわからないが、300回以上はあったらしい。 そして、メイン発問。 この300回以上の戦争や内乱に、一度も参加していない国は、どのくらいあるでしょう? 今、独立国は191カ国あります。 フィンランド、スウェーデン、スイス、アイスランド、ブータン、日本が着色した世界地図を配る。そして、聞く。「一度も参戦していない国を調べて、ノートに国名を書きなさい。」 どうして戦争をするのだろうか・・・とつぶやく声をうけて。「日本以外の5つの国が、61年間戦争をしなかった理由がわかる人はいませんか?」「日本が戦争をしていないのはなぜですか?」 以上で、授業は終わりです。 自衛隊派遣で、最近の日本は微妙なところなのですが、歴史の授業が終わり、次の憲法の授業への橋渡しとして、ばっちりの授業です。 20日には、この実践を元にした授業をおこなう予定です。 もちろん、笑育っぽい味付けをして。
2006年11月05日
コメント(0)
-
客の前でする・・・。
いつもいつも引用したくなるような記事がいっぱいの鈴木浩子さんのブログから。 ちなみに、一応説明しておくと、鈴木浩子さんの旦那、鈴木健三さんはただいまプロレス修行としてメキシコに単身乗り込んでいます。 そういう背景の元に、次のような文章がありました。 《とにかく1試合でも多く試合をする》という《プロレス修行》で向かったメキシコだけに、これは願ったり叶ったり。レスラーはレスラーとして磨かれるには、どれだけリング外でトレーニングしたところで、どうしようもない。客のいるリングに少しでも多く上がって、試合をすること。それしかない。 さて、これをいつものごとく因果伝垂ではなく我田引水に、教師の職業に当てはめてみると・・・。 つまりは、教材研究や教育理論ばかりしていてもしかたない。 実際に客のいる前で授業して見ろ!ということになります。 客のいる前での授業。 業界用語で言う研究授業というやつです。 同業の先生や大学の教授などに見てもらい、授業の後、いろいろと討議してもらうあれです。 今年は、学校も変わり、学校の研究体制もかわりで、私自身まだ客の前での授業はなし。 ただ、20日に、他市で他のクラスに飛び込み授業。 今年初の客の前でする授業。 健三に負けないようがんばります!
2006年11月04日
コメント(0)
-
キャンディキャンディは強かった!
キャンディキャンディは、やはり偉大でした。 雀斑という漢字は始めてでも、 雀斑なんて気にしないわ~というヒントは、絶大な効果。 親に聞いてきた子は、その威力にびっくりしたようです。「ほんま、一発でわかったわ。」 まさに、記憶に残るアニメ主題歌。
2006年11月04日
コメント(0)
-
やはり御御御付けは知らなかった?
読み方なぁ~に?の答え合わせをしました。 御御御付け~おみおつけ やはり子どもたちは知りませんでした。 どこかで聞いたことがある・・と言う子はいましたが、それがおみそ汁だと言うことを知っている子は一人もいませんでした。 ちなみに、御虎子の方は、ほとんどの子は知っていましたが、やはり一部の子が。 今日は、雀斑を出したのですが、すべて当てずっぽう。 正解者無し・・・ということで、答えは言わず。 正解は、お家の人に聞いてごらん。 雀斑なんて、気にしないわ~。といえば、ほぼ100%わかるから・・・。と、教えました。 たぶん、これで正解者が出るはず。
2006年11月01日
コメント(0)
-
どこが、ハロウィンやねん!
昨日、10月31日は、ハロウィンの日。というわけで、我がクラスのイベント係が2週間前ほどからハロウィンパーティーを企画。教室の飾り付けをするなど、少しずつ準備を進めていました。そして、いよいよ当日。ハロウィンパーティー10時にスタート!それぞれのグループが家庭科室に行きました。おやつづくりです。この日のために、グループごとに買い出しにも行ってます。下準備をしてきている班もありました。それぞれのやる気がびんびん伝わってきました。みんな、手際がいい。私は、今年、家庭科を教えていないので、子どもたちの調理の様子をしっかり見るのは、はじめてなのですが、けっこうやるものです。つくっては、食べ。食べては、つくり。・・・という班もあったのですが、とりあえず12時前には調理終了。みんなで食べることに。できあがったおやつは、これ。・チョコレートフォンデュ・パンプキンケーキ・ホットケーキサンドそして、・たこ焼き(3グループ)3グループがたこ焼き。まさに、たこ焼き祭り。しかも、調理に時間をとられ、仮装しているものもなし。ゲーム的なものもできず。どこが、ハロウィンやねん!いかにも、関西なたわせん学級でした。
2006年11月01日
コメント(0)
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…
- 我が家の「沈黙の戦隊」
- (2025-10-24 09:33:10)
-
-
-

- 子連れのお出かけ
- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…
- (2025-11-07 07:53:33)
-
-
-

- ♪~子供の成長うれしいなぁ~♪
- ☆クライミングロープ☆
- (2025-11-21 22:01:34)
-