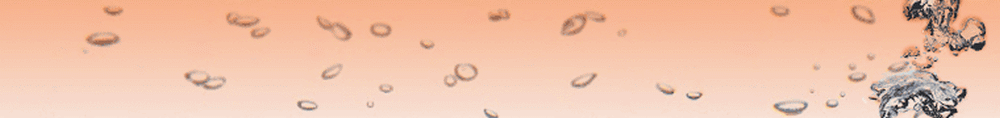2007年09月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
体育大会決行
今朝は小雨が降る中、我が息子の初めての運動会が決行された。せきとりに朝早く行ったときは、運動場はぬかるみ、先に席を取っていた保護者の皆様のシートがずぶぬれ状態だ。たまたま、居合わせた先生に聞くと「10時位にはやみますから、行ないます。」とのこと。なんと、間違った判断だ、と内心思いながら空いたテントの下に自分のシートを引いた。しかし、先生の判断は 正しかった。 本当に9時ころから雨がやみだして、昼ごろには青空が見え出したのだ。参りました。 さて、うちの運動会で面白いことに気がついた。それは、グランドが広いせいかもしれないが学校が要したテントの中にシートを引くというのが私の中の[運動会]のイメージだったが ここは、マイテント&テーブルを持参するのだ。子供の競技はそのテントからは見えにくいのだがとにかく、親がリラック出来る状態を第一優先のように感じた。見ていると、確かにゆったりと運動会をマイペースで楽しめる。自分の子供の登場のときのみ前に行って、ビデオをまわす。ほかの子供たちの演技は見ない。 時代の流れだろうね。まあ、おかげでシートの中で見れたのでよかったが・・・ 来年、テントを買うべきか否か?!
2007年09月30日
-
数百億を動かす男と会う!
まあ、すごい人が世の中にはいるもので・・・その人の話を最前列で聞いてまいりました。決断と入り口と出口を見極めること。この2点を学んだかな・・・億という単位のお金が身近なものに感じてしまう錯覚をおこしました。それと、もうひとつ。本当のお金持ちは(テレビなどで出てない方々)質素・倹約に努めているそうです。見栄を張りまくることはようない。大きく動かして普通を維持する。そんな、気持ちの持ちようを学びました。
2007年09月29日
-
変わらぬ味は、変えている
変わらぬ味を売りにする店がある。本当に変わっていないのか?しかし、季節やその日の天気によって調整をかけるところもあるときく。ということは、まったく変わらない味というものは売り手の思い込ませ方ということになる。基本的な部分はそのままに時代や世代に受けいられるように“マッチ”させてこそ「変わらないもの」が出来ているのだろう。 その前にスポーツ界を見てみると時代とともに変わってきている。根性論・精神論は洗練されたデータに基づいた勝負論に進化した。部活していたときにのどが渇いても水分はとるな!いわれていたが、今は逆に水分をとれという。体に水分補給をしたほうが良い結果をもたらす場合がある。 忍耐力や我慢することが犠牲になっている部分がその反面あることは否めないが、それをカバーするだけのメリットが何かしらあるのだろう。 さて、勉強面に目を移すとどうだろう。我慢強さや長期的な継続力は必要だと思うし、それをデメリットとする要素はないと僕は考えている。要はその伝え方を時代にマッチした形でどう落とし込むか、であろう。 変わらぬもののよさは変わりながら作られているのだ。 時代に流されていくのはいやだ。流れを読み、方向を決めるのは自分でありたい。
2007年09月28日
-
時は何を語るのか・・・
相撲界で激震が起こっている。17歳の若き力士の死亡の件だ。これが練習中によるものかそれ以外での要因であるのかは今後警察の調べでわかってくるだろう。さて、あるコメンテーターが言っていたが今の子達は甘やかされて育っているから昔と違って、厳しい練習に耐えられない者が多いという。行き過ぎの“指導”(?)はもってのほかだがそのように甘やかされてて育った才能ある若者をどこまでの範囲で「指導」していいのか兄弟子や師匠がわからなくなってきているような気がする。これ以上やったら死ぬだろう。その限界がぼやけている。昔はこれくらいでは大丈夫だった。しかし、今はそうではなくなった。まあ、朝青龍の件もそうだろうが・・・確かに、たくましく育ってほしい気持ちはわかる。だが、その希望に才能を持ったものがついてこれなくなってきている。そんな気がする。新たな育成方法が必要な時期にさしかかってきているのだろうか?いつの時代も変わらぬ教育方法というのはやはりないのだろうか・・・・時代が流れるとき、新たな方法を見つけ出すものが次のステージへすすめ、これまでの方法に固執する者が時代に潰される。そんな気がした。
2007年09月27日
-
昨日来てくれた君に・・・
何かを覚える時は、覚え方がある。例えば、泳ぎを覚える時はどうだったか?親や友達の兄ちゃんにドボーンと川や池に投げ込まれて必死になって、泳いで岸に戻った記憶がある。人前で泣くのは悔しいので、余裕のある表情で笑っていた。しかし、それ以来川や池で泳ぐことはなくなった。 恥ずかしながら、しっかりと水泳を覚えたのは学校の体育の授業だった。見よう見真似でそれまでは手足をばたつかせていたがどうにもうまく前に進まない。短距離走のように早く進めない。そのとき初めて、ひざを曲げてはいけないことを知った。これで、少しはスピードを上げて泳げるようになったが水泳教室に通っているものいはかなわなかった。彼らは「泳ぎ方」を学校で学習するより知っており、さらに、練習を積んでいる。泳ぎでは勝てん・・・・そんな挫折感を小学校の低学年の時に感じた。 成績を上げたければ「学び方」をいかに知っているかがカギだ。そして、それを使っての練習あるのみ。自分が何を知らないかをまず知り、それらをひとつ、ひとつ潰せ!時間をかけようがやるしかない。 プレッシャーもあろうががんばるといって、昨日来てくれた君に送ろう!
2007年09月26日
-
生き生きした姿
そろそろ、中間テストが近づいている。3年生はここで大きく踏ん張らないと後がない!先日のテストでもそうだ。得点を高くとっているものほど遅くまで残ってやり直しに時間をかける。やり直しの数が少ないにもかかわらず、時間をかけてくる。逆に得点がほしいのに、取れていないものほど手を抜いて帰る。その、やり直しノートは解答の丸写し的なものもいた。これではやっている意味がない。僕はいう。人の3倍努力して、結果が1.1倍でれば上等だ!結果を上げるとはこういうことをいうのだ。得点を上げたいものはそこに時間をかける。たまたまやったところがでたなどとは決していわない。あれだけやったから、取れて当然。そう思える勉強を残された時間でやってほしい。
2007年09月25日
-
人生最悪の最初の運動会
昨日、次男の幼稚園の運動会だった。彼の生まれてはじめての運動会である。気合十分!ハンディカムをもって臨む。が・・・本人は「ママがいい!」と泣き始め先生も手一杯でひとまず保護者席へ子供を預けた・・・・・周囲の子達でそこまで“甘え”ている子は誰一人いない。ワンワン泣きまくるわが子に切れてしまった・・・・・その場をさり、駐車場の車へと移る。「あれだけがんばるといったやろ!」もう3歳だが、毛布が手放せない。したがって、名札の横にその切れ端をはりつけているが、それで涙をぬぐう姿にまたもや、怒る。「もう、こんなのはいらん!こんなのがあるから泣くんや!!」そう叫んで引きちぎった。「もうがんばらんのか!」「もうがんばらん・・・」「がんばらん子は悪い子や!」「わるいこ・・・・」大声で初めて次男を叱り飛ばした。生まれて初めての運動会で生まれて初めて親父から怒られた、次男。1時間近くも鳴き通す。参加競技も2つすっぽかす。らちがあかなくなり、こちらも諦めて再び幼稚園へ戻る。子供を母親に預ける。見ると同級の子供も何人かは母親に抱きついて泣いていた。「・・・こなもんなんか。」 しばらくすると、息子の調子も少し回復し2つほど競技に出た。私は、ひどく落ち込んでいた。楽しそうに過ごす家族を見ているのがつらく、重く感じそのまま、塾へもどった。がんばったら、夕食は焼肉屋へ行く予定も「がんばってない」と本人も納得の上なので家でささやかな夕食だった。もちろん、ビデオで何もとらないままだ。 ビールを3本飲んでいつの間にか眠ってしまった。 夜中目が覚めて、それから目がさえた。よくよく考えてみると、がんばっていないのは自分のほうだった。次男があんな状態になるのは想定内であった。だが、私は[運動会]で次男を応援することをがんばろうと思っていた。間違いであった。私が本当にがんばらんければいけなかったのは「次男をいかに運動会に楽しく参加させること。」だったのだ。今頃気がついても遅い。馬鹿な親父である。本当にがんばらなければならなかったのは私自身であった。なぜ自分ががんばれないのか、3歳がわかるはずがない。ただ彼は自分が悪い子としているという自覚はあった。だから、「今日は運動会がんばらんやった。」家に帰ったとき次男がいったのだ。かれの人生最初の運動会を泣きながらでも、楽しくさせる努力を怠った私が“一番、がんばっていない”それに気がついた。 今朝は、彼はもうそのことをすっかり忘れたように元気に遊んでいる。そんな姿を見ながら、次こそは楽しい運動会になるように私自身も努力しないといけないと、心に誓う。
2007年09月24日
-
この季節だからこそ・・・
残暑が続く今日この頃。子供たちもまだ半そでを着ている。かくいう私もその一人だが・・・さて、通常はこの季節はもう長袖である。でも長袖は今年に関してはまだ着たくない。しかし、秋の訪れを待ちわびている昆虫君たちはそんなことはお構いなしにいつもの秋を満喫している。で、昨日発疹が出来て、病院にいって神経性の云々という話はしたがこれはどうも間違いのようだ。ネットで調べたら・・・この症状がぴったりだった。というか、これそのもの!「チャドクガ」確かに、椿の葉っぱにぎっしりいましたね。触りはしなかったものの、きっとそれが原因でしょう。 本来なら長袖で防げたものを、半そでのせいでこうなったんです。(か、かゆーい!) 皆さんも気をつけましょう。
2007年09月23日
-
24軍団
腕の湿疹はいまだ完治せず・・・さて、朝からがんばってきている自習軍団にご褒美だ。MRお奨めの「24」!!!ただ今より、視聴開始。 勉強のご褒美はお金やものではなく心に満足感と充実感のみを与えてくれるものでよいとおもう。彼らがわくわく・ハラハラしてしばしのあいだ、勉強の疲れを癒してくれたらそれでOK!
2007年09月22日
-
家族の波長
昨晩から妙に腕がかゆかった。見ると、発疹が右腕にぽつぽつぽっつ・・・「!」あやしいー!何か虫にさされたか、植物にまけたか、さらには食べ物にあたったか・・・とにかく、わからないが着実に時間とともに増えているようだ。何もわからないので、木酢を塗ってみた。「・・・・」まあ、少しはかゆみがひいいたきがした。 今日の朝。 「ちょっとこれ見て。」同じものが妻の腕にもある。長男にもでき始めているようだ。次男は・・・ない。 家族で同じものができている。いったい何、何や!!!!! すぐに近所の2時間待ちの皮膚科にいく。 「ああ、これはストレスや体調が落ちているときにでてくる、発疹ですよ。」 ・・・じゃあ、一家で一斉にストレスを感じているということかいな! とりあえず、へんな病気でなかったので安心した。 しかし、こうも同じように症状が出るとはそんなにストレスを同調して感じているのだろうか?
2007年09月22日
-
そういえば、僕もそうだった
このくそ暑い中、銀行にいってきたときの話。キャッシュコーナーからこちらーをジーっとみているかわいい女性!「まいったな・・・・・」勘違いぶちコキの私は誰とわからず営業(本音も入りいの)スマイル。「先生!」なんと教え子だった。「おお、ひさしぶり。」その子はキャッシュコーナーに戻って「ほれ、ほれ」といいながら後ろにいた自分の子供を僕に見せてくれた。「わああ、何歳?」「一歳半です。」「大きいね。お母さんにだね。」僕もそうだったが、お世話になった先生方に自分の子供をみせたいのだ。結構はなれたところだが小学校時代の担任の先生に長男を見せにいったことがあった。 彼女の子供をあやす姿は初々しいママ そのものだ。彼女はすっかりお母さんになっていた。 でも、僕はどう見ても彼女が中学時代からかわっていないようにしか見えない。(失礼な意味ではないよ)それは、中学時代の同窓会で初めは誰だかわからないが、名前がわかって急に、あの頃に戻ったようなそんな感じなのだ。ちなみに、僕はどうも本当に顔が中学時代から変わっていないらしいが・・・ただし、体系のほうは・・・・・・・・・ 「私の夢はこの子を先生の塾に入れること。」なんと嬉しいことをいってくれる。お母さんが通った塾にわが子も通わせたい。これまでがんばってきて本当によかったと純粋に思う。今後は卒塾生の子供たちが来てくれることをひそかに楽しみにしよう。
2007年09月21日
-
世界一となるための練習
谷亮子の金メダル獲得のあの瞬間は本当にすばらしかった。少々、話が古いが、そのときのインタビューで「世界一になるための練習をしました。」という一言がすごく印象に残っている。母親として一時は柔道から離れた。スポーツや芸術、勉強もそうだが継続は力なりで、その逆は力を失う。彼女は寝るときさえ、仰向けにならないそうだ。つまり、背中をつけない。そんな彼女も今回は「だめかな・・・」と私は思っていた。しかし、他に選手は違った。世界1位に何度もなった人間はなんと強いものか。あくまでも、自分の地位を持続させることに固執せず、さらに進化をしようとする。プレッシャーに弱い選手が口にする 「自分のためにがんばろう。」ではなく、「応援してくれる人たちのためにこたえたい。」と彼女はいう。ここが本物の一流選手たるゆえんだろう。生徒たちにもこの気持ちの部分を彼女から学び取ってほしい、人生の手本になる人間の一人である 。
2007年09月21日
-
読解力を伸ばすには
さて6年生もいよいよ、入試の足音が聞こえ始めてきた。外は9月ももうあと10日ばかりだというのに8月下旬の暑さだ。まだ夏のようだが、それに勘違いを起こさない様にしてほしい。さて、とある中学では朝の課外の時にみんなで一緒に「読解力の問題」を解くそうである。それに異議を唱えた人がいた。「入試で読解力の問題は特に時間との戦い。じっくり読んでじっくり考えるなんて、勝てるはずがない。うちは時間を決めて、その時間内で解かせてました!」まさにその通りである。陸上日本一を作った原田隆史先生は「100メートル10本走れ、の練習はしません。100メートル、10分です。」個人の目標にあわせその本数を各自で任せる。これでいいのだと思う。まさに、自立した個別指導だ。一斉の中での各自の目標に即した指導。ここがポイントになるように思う。 テストで読解力の問題をGETしたければ時間内でとく練習を心がける。○○○文字の問題を○○分で解く。この訓練を丁寧に継続しておこなうことがこれからは大切だ。
2007年09月20日
-
あなたは戦国武将でいうと誰?
結構、おもしろいかもね! ここ
2007年09月19日
-
自分の子供をそれでも信じる
走るのが速い奴は絶対に陸上部に入るのか?そうではない。それを生かして、野球やバスケにはいりそのほかの才能をも伸ばしていく。勉強だって同じだろう。勉強ができるからって勉強ばかりする必要はない。音楽いきたければ、いけばいいしスポーツの方にいきたければそうすればいい。しかし、だ。一概には言えないがレベルの高い学校に意外にスポーツや音楽に長けているものが多いことも事実だ。しっていたか?勉強できる奴はスポーツも音楽も芸術も本当によくできるし、それを楽しめる。 僕はそっちに進んでほしいな。 これまでの視野が数段広がるようだよ。やるもののレベルが数段上がるそうだ。 そして数倍も楽しめるし、おもしろい、ということ。 こればかりは、実際その学校に入学して体験してみないとわかんない。 勉強を苦しみながら部活をするのもいい。でも勉強を余裕を持たせ、楽しみを謳歌する。そんな高校生活を歩んでほしい。きっと、そんな姿を君の親は望んでいるんじゃないか?今は反抗してもいいけど、そんな君を君の両親は笑いながらそばで信じているはずだ。
2007年09月19日
-
ふるさとの味
この地に来てすでに20年以上が経過している。生まれた地は隣の隣の山越えたところだ。そこで幼稚園から高校時代をすごした。そこでの思い出はいっぱい。さて、昨日生徒と話していたら『前食べてた、たこ焼きが忘れられん!』という。『そら、俺の人生でアレだけの大きさのタコを入れて400円というのは、見たことないもんね。たこ焼きNO1やね。』彼らにとってのふるさとの味にしたいひとつである。そこで、今度のテストで先月より20点以上あげたら買ってしんぜよう。という約束をする。さて、いよいよ来週。どうなることやら・・・・
2007年09月18日
-
今日もきてるぜ!
朝9時にここに来ている生徒諸君。気分がすぐれないががんばってやってきたBさん。なぜ、ここまでやるのか?決まっている。来週のテストで努力の成果を出すためだ。やるだけのことを常日頃からやる!単にそれを実行して出るべき結果を出すのみだ。この塾ではここを教えたい。この方法はきっと大人になる過程でもなってからも、役に立つ。さあ、今日もがんばろう。
2007年09月17日
-
地獄と天国
我が師匠が言った。「いいこと半分、悪いこと半分。それしかない。」「いいことを言っていればいいことが訪れ、悪いこといっていれば、悪いことが訪れる。」今日まさにそのようなことが訪れた!ある方との出会いがそれまでの僕の中の一方通行の考えを両方向通行に変えてくれた。 自分の理念を持つ。それをぶれさせないことがもっとも大切なのだ。それ以外は小さい、小さい。小さいから、気にしないようにする。小さいことを気にすると、小さい動きしか取れなくなる。大切なことは理念がぶれそうになった時に自分の弱さを戒めることだ。 僕にはそれまでそんな考えがなかった。それが、心の中の言いたいことと言葉として出てくることとのズレになっていた。 さっきまで、曇っていた心の中がぱーっと明るくなった。
2007年09月16日
-
親の教育の結果
長年教育関係に携わっていても、理解しがたいことがでてくる。例えば・・・親のは子供の将来のために良かれと思う教育を施す。それは第3者が見てもある程度正しい教育だとしよう。しかし、問題ないとおもわれる教育をやっていてもそれはあくまでも大人の判断であって子供にどうその結果が現れるかが問題である。 大人が予想しきれない、結果が現れた場合どこに原因があるのだろうか? ここ最近、この点が私を悩ませている。 なんとなく共通因数的なものはわかるのだがその家庭や保護者の本質的な考えに踏み込めないので原因追求ができない。 ただ、ひとついえることがある。 大人はわかっていても、子供には理解しがたいことがあろう。よく「将来のために」といわれても大人ほど将来の予想を子供たちはできない。だから、楽なほうに流されやすい。そこを理解して上で、子供時代を生きている子供に如何にそれをリアルに伝えきるか。ここが最大のキモのような気がする。僕にもあまり『コレダ!』と断言できることはいえないが・・・・・大人の望む結果を理由をつけて子供に説明することだけはやっていこうと思っている。
2007年09月15日
-
あと20数回だろう
アイガモ農法の古野さんが言っておられた。「自分が田植えできるのもあと30数回しかない。」多くの失敗やチャレンジでやっとたどり着いた有機農法のひとつ。世界からも注目されている。この方のお子さんを運よく教えることができたことは僕にとってすばらしい経験だった。この方との会話の中で、「失敗はもう100も1000もやってきた。そう簡単に成功にたどり着けるはずはない。どれも手抜きなんかしていない。稲が作れるものあと30数回しかないからね。」 何度でも失敗をかせね、成功へと近づいていく。しかし、手を抜いた失敗は決してしてはいけない。全力で取り組んでの失敗こそが次に繋がるのだ。僕がこの塾から子供たちを羽ばたかせるのもよくよく考えると後20数回あるかどうかだ。成功するかどうかより成功するんだという気持ちをこめて全力で接していかねばとあらたに心に誓った。
2007年09月14日
-
椿の種笛
この季節になると、椿の種が道端に落ちてくる。小学校の頃、昼休みに何個かとってきて上のほうをコンクリートでこすりつけて穴を開け、中の実を名札の安全ピンの針で削り出し笛を作って遊んでいた。それを先日小学生にいうと「しらん」早速、近くの公園からとってきて1つ作ってやった。『ピーッ!』耳に響く高い音は子供たちの目をきらきらさせる。「へーーーー!」授業の後に数個ずつ子供たちに分けてやる。 ここまではよかった・・・・ 塾が終わって、外にでてお母さんたちを待っている子供たちは歩道でしゃがみこみ一斉に「シャリ、シャリ、しゃり・・・」と種を削り出してしまった!道行く人たちも何事だとかれらを見つめる。「おいおい、いえでやってくれ~」 迎えに来たお母さんやお父さんも「ほー。やったことないですね。」 なんか、ジェネレーションギャップを感じてしまった。
2007年09月14日
-
子供に携帯は不要
おもしろい記事が出ていた。電車の中や駅のホーム、自転車に乗りながら、車で運転中と携帯を話せない若者が実に多くなっている。何をそんなにやっているのだろうとちょっと見てみると、メールかゲームである。これは、携帯が普及している国は共通のような気がする。 しかし、これでいいのか???新世紀の新しい価値なのかもしれないがどうも個人的には受け入れられない。 子供の時期は家族との通信手段としてのみ使うのは結構だが、それ以外はあまり使わせたくない。定義が難しいが「正しい使い方」を誰か作ってはみないものか? 時代がそういう流れなら受け入れることが仕方がないが、子供の頃は公衆電話で我慢しろといいたいのは僕だけか?
2007年09月13日
-
小学校で全都道府県名と位置くらいは暗記を.....
「小学校で全都道府県名と位置くらいは暗記を」当たり前だろう!といえばそれまでだがこんなことくらい、塾では当たり前にやっている。 いったい今までの「ゆとり」はなんだったんだろう?詰め込みはだめだと、詰め込むものを極力減らし、弱体化した日本の子供をつくった「寺脇」君。この罪は重いぞ。
2007年09月12日
-
親・子の温度差(まっすぐに育つために)
ipodを子供に買ってやった。歴史や数学の公式を音楽とともに覚えるCDを入試のために全巻買い、それにいれ学校の行き帰りに聴いてほしいという親の願いだった。子供はそれに大好きなアイドルの歌を親に見つからないように、寝静まってから夜中にダウンロードして笑顔で聞いていた。 朝の1時間の親子の勉強時間が次第に、機能しなくなってくる。子供は眠くてたまらない。「どうして、いいもん買ってあげてるのに!」 さらに、親子ともども必死になって、塾での試験の順位上昇のためにがんばった。テレビも見せない。人気の週刊誌や月刊誌も買わない。ともに一生懸命がんばって結果を出していった。 日ごろから、こんなきつい思いをしているから親が御褒美に海外旅行やミュージカルに連れて行った。最前列に陣取り相撲も見せた。がんばったから! でも、子供はうれしくなかった。本当はあのアイドルのコンサートに行きたかった。3階の一番後ろでもいいので 自分の見たいものを見たかった。 次第に、子供は親の前では親の理想を演じるようになる。それが、その親の子としての「生きるすべ」ということを、自ら学習する。 でも、その子はその子なりに押さえつけられる自分の多くの欲望を解消しようと別の顔の自分が現れて、すべてをさまざまな形で満たし始める。そうしないと、その子自体が崩壊する。それは本能的行動だろう。 親の価値基準と子供のそれとは違う。きっと、大人の価値基準は正しい。それは音のあの時間が人生で長いからだ。それに見合った最善のものを選ぶ。その子も大人になると、親のすばらしい価値観に追いつき、感謝する。 でも、子供であるその子はその子の基準が満たしたかった。満たせないから、がんばって、怒られないようにしっかりと自分の価値を満たしていく。 そういえば、自分の子供時代もそうだった。 そうやって、大人の基準に近づいていく。大切なことはそれを大人が思い出してみることだ。そうして、黙って認めてあげること。認めてやることだ。それが、まっすぐに子供が育つ肥料となのだ。 まっすぐに育つために根っこはいろいろな方向へと伸びている。
2007年09月12日
-
親子の作用と反作用
昨日というか今日の午前1時30まで4者面談を行なった。内容は伏せるとして、勉強になったことを書こう。まず、小学生のころは子供って本当に親の言うことをきくものだ。聞かなければ力ずくでも聞かせることが可能となる。大人の価値観を子供に良かれと思って教えても、子供はそれがわからない。おそらくは、彼らが大人になって初めてそのありがたさに気がつくのだろう。しかし、子供の成長とともに「自我」が目覚めると話は変わってくる。大人の言うことを聞かなくなる。賢い子供は聞いたふりをして「いい子」を演じることを覚える。子供のころの大人がいいこといっていた自分を大人の目の前に表現する。しかし、実際はそうではない。大人のいうことを聞きながら脳がそうではない、自分のやりたいことを自分の欲求のままにやれと命令し、大人にばれないように、行動に出る。これが、成長だと僕は思う。大人の目を盗み、これまで否定されていた価値観を試しだす。OKだ!どんどんやれ!今まで、押しても押し返さなかった子供が、押し返すようになってくる。今度は大人が子供から押し返される番だ。われわれ大人はそんな脱皮中の子供に負けないで押し返さなければならない。大切なことは、押し過ぎもせず、押したりなくもなく。 彼らと同じ力で・・・・ここが大切だ。 反抗期の子供の力は強ければ強いほど押し返し甲斐がある。そして彼らを立派な人間へと成長させる。
2007年09月11日
-
休みの時
昨日、文化祭がおこなわれた学校があった。今日は振り替え休日だが、いったい彼らは何をしちるのだろう?勉強する姿はここでは当たり前の光景だ。しかし、太陽のもと汗を流しながら遊んでいる姿を想像できない。塾生以外の学校の友達とどんな会話をし、どんな格好で普通の中学生や小学生となっているのだろうか?すれ違った、中学生の背中を追いかけながらふと思う。 生徒たちとの勉強ばかりの共有時間も大切だが人間相手のこの職業。少しは勉強以外でもコミュニケーションの時間をこの秋は増やそう。
2007年09月10日
-
もう少し早足で
入試というものが5教科評価である以上その教科をあげる努力を惜しまずやるしかない。 野球でいうと打たれないような速球を投げる投手からヒットを打ちたければその投手の投げる速さ以上の球を打つ練習を数多くやればよい。 勉強も同じだ。不得意科目でも数多くやっていけば必ず「目」が慣れてくる。もうやる時期が来た。早く、早く、ここに来て夢に向かって努力しよう
2007年09月09日
-
ドラえもんとジャイアン
「わかる」と「できる」の違いを言うときの例。ドラえもんの顔はかける子が多い。どうしてか?小さい頃から何度もそれを見て、描く練習をしているからだ。さて、ジャイアンはどうだろう?顔を見ればわかるが、描けと言われてできるものは少ない。小さい頃から何度も見ているのに、描く練習はしていないからだ。スネオやデキスギ君も同じだ。“わかったつもり”とはこういうことをいうのだ。自分の手で生み出すことが《できる》ようなって初めて理解したこととなる。 君の勉強は「ドラえもん」まで達しているか?「ジャイアン」止まりか??
2007年09月08日
-
結果がくる
数学マン点者は予想より少し多かった。後はどれもケアレスミスで、わずかな得点を落とし、それが積もって10点や15点マイナスに繋がっている。 解けないもんだではない。要するに、気持ちの問題だ。ここの部分のコントロールが生徒にとっても我々にとってもこの時期課題になってくる。 常日頃、どのような問題を解くにしても本番のテストを受けうるが如くまたはそれをシュミレーションしておこなう訓練が必要だ。 さ、これをたたき台にして伸びていこうぜ!
2007年09月08日
-
おれは、ジャックバウアー
もう、これ最高! レンタルされまくりで、借りれん・・・
2007年09月07日
-
メンテナンスの重要性
メンテナンスを怠っていたため大切な時計や車がその機能を発揮しなくなった。いつも使っているから、その変化に気がつかなかった。その付けは・・・・ここでは言うまい。日頃使っているからこそ一旦、時間や距離を置いてその変化を見つけなければならない。メンテナンスという言葉があるが何事においても使ってたら、一度は専門家や自分でちゃんと機能をしているのかをチェックしなければいけない。さて、一番今まで使っていたもののメンテナンスを考えると・・・ そう!! 自分の体。 しばらくぶりにメンテナンスをしなくては!
2007年09月07日
-
親の心 ゴーン!
久しぶりに子供の空手道場へ足を運ぶ。もう、泣きはしなくなった。OK!下の子が大きな道場を端から端までダッシュしまくる。OK!白帯の中では親の目から見てもよく先生の話を聞いている。OK!ただ、組み手になると、よわい・・・ガードが甘く自分から攻めようとしない。母親は「あの子は性格が優しいから・・」という一方で、少しでも反撃をするわが子に「いけー!」と叫ぶ始末。 家に帰って、早速復習。「脇をしめて、相手の目を見ながら。ちがーう!」そう檄を飛ばしキックミットで受ける僕。それを見た母親いわく「がんばったんだから、もう少しほめてやったら。」そうだ・・・ストロークだった。 カルロス・ゴーンはわが子にサッカーを教えるときボールの蹴りの方を事細かにいわずまず、ここに蹴って来いとゴールを示し、そこにボールがはいるとおおいに子供をほめた。 わが子には感情が先走ってしまうが生徒たちに心がけているように接しなければいけない。まだまだ、指導に関して未熟さを感じた。
2007年09月06日
-
ストロークをうて!
人に「良い」ことを言うのは日本人はあまり良しとしない。「暗黙の了解」「阿吽の呼吸」という言葉があるように、古来より日本では「語らぬ文化」が発達したが、ここに原因があるようだ。 さて、子供たちを元気付けるにはどうしたらよいか?僕は子供たちがへこんだ時に、またはその前から「ストローク」を打つ様に心がけている。「ストローク」とはその人のいいところを見つけ褒めること。または元気付けることである。「おべっか」や「ご機嫌取り」とは似て非なるものである。まず、これらは自分のことが第一である。自分の利益をあげるために他人をいい気にさせるのである。一方、「ストローク」は基本的に相手の気持ちを元気付けてあげようというものが最優先である。相手の目を見て、言い分をうなずきながら聞いてやり、元気がでる言葉を与える。当たり前のことであろうが、このようなことも今の子供たちはいや、親もかもしれないがなかなか実践されていない。このような「心の環境」を整えることで実は成績は伸びていく。 知識だけを教え込むのは時代とともに、廃れていく。
2007年09月05日
-
強さを持つものは、よりやさしさを持つ。」
先日の空手選手権での挨拶で「強さを持つものは、よりやさしさを持つ。」というフレーズが今でも心に残る。子供の練習を見ていても、強いものは弱いものに対して、手加減を知っている。弱いものは、強いものに対して逆に手加減しない。それは失礼に当たるからだ。韓国の友人と焼肉食べたときもそうだ。おごるのは年上の私。年下のものがお金を払うのは向こうでは年上のものを侮辱する行為になるという。タイでもそうだった。持てるものは持たないものに施す。これは、当たり前である。空手の話に戻るが、「礼」を尽くすことによりあの痛いつきや怖い蹴りをもらっても、相手を憎むことはない。力の強い・弱いがあり、強きものは弱きものの力を受け、その痛みに耐える。組み手が終わり相手と握手というコミュニケーションをとることで、すべてが終わる。ノーサイドだ。さらに突っ込むと目上の人に、尊敬と敬意をはらい謙虚さを尊ぶ。という日本の古きよき伝統といってもいいものを学んでほしいと思っている。だから、かっこいいしわが子にも学ばせたいと思う。 強きものは、よりやさしさを持っている。 ところで今後、中学校の体育に「武道」が導入される。「中学校の保健体育で選択必修になっている武道(柔道、剣道、相撲など)を1、2年生の男女を対象に原則、必修化することを大筋で了承した。昨年12月改正の教育基本法に盛り込まれた教育目標「伝統と文化の尊重」の実現を目指す。この教育目標は「伝統と文化を尊重し、 それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養う。」ということを中教審で大筋了承されたとのこと。 さて、負ければリセットというゲーム世代の子達にどこまで「武道の精神」がきざみこまれるか・・・
2007年09月04日
-
ノートに書いた言葉
勉強から逃げてはいけない。君の目標はどこにある?人は一番ほしいものに時間を一番かける。逆に言うと、君が一番時間をかけていることが、本当に自分自身にとって大切なものか、最高にほしいものかそこを考えてほしい。人は弱いから誘惑に負け、苦しさから逃げようとする。しかし、そこをいかに歯を食いしばって打ち勝つか!その方法とやり方を君は知っているか?誰に習った? 知らなければここに来るといい。体に染みわたるまで教えてあげよう。
2007年09月04日
-
第5回世界チャンピオンと!
昨日、国際センターで全九州空手道選手権大会があったので、家族で見に行った。そこで、なんと何と、ナントあの第5回世界チャンピオン 緑 健児 代表とお会いすることができた!体は165センチくらいだろうか。この小さな体で、世界をとった男だ。DVDで見たこともある。感激である!!思わず、子供をだしに握手とサインをしてもらった。 さて、試合のほうだが特に注目した選手は「徳田 則一選手」だ。彼も背は大きくなく160センチだ。間近で後ろから見たが、小柄な女性のように華奢だ。しかし、試合場に立つと大きく見える。彼は惜しくも4位であったが、その応援は決勝戦のようだった。もちろん、私は彼を初めて見たが応援したくなる。 大きなものに、立ち向かう勇気と希望を彼は小さな体で、表現してくれた。 3位の選手は忘れたがこの4位の選手は忘れない。そんな印象を与えた試合だった。諦めない!彼の気持ちは見るものにストレートに伝わってきた。 押忍
2007年09月03日
-
毎日が真剣勝負を意識して体で感じろ
日ごろから、入試のそのときをシュミレーションして、何事にも臨めといっている。試験で喜びを感じたいのなら、日々どうすればいいのだろう。試験の日には朝食をバランスよくとれ。それは脳が活性化され、集中する時間が長いからだ。 ならば、日々それをやっておけ。 答案がすべて丸だと気持ちがいい。 ならば、どんな小さな試験でさえ、驕ることなく、気持ちを落ち着け満点を取れ。 試験のときに少し熱があっても休まない。 ならば、学校や塾にはその理由でやすまない、休ませない。そんな癖をつけてどうする! 合格発表の日、「やった!よっしゃ!!」と叫びたいだろう。 ならば日ごろから、目標達成したときにその言葉をはく癖をつけろ! 必ず、その目標は達成されるようになるだろう。 毎日、毎日が真剣勝負を意識して体で感じる癖をつけろ!!
2007年09月02日
-
9月開始!
いよいよ、秋の陣の到来だ。夏の疲れもあっという間に飛んでいった。 最高の贅沢が昼に大好きなビール様を飲んで、そのまま、お昼寝。 これも経験できたし家族サービス充電できただろう。 今日から9月。生徒に言う前に自分自身を気を引き締めておく。
2007年09月01日
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- 20%Pバック😀【1種類を選べる】メリ…
- (2025-11-25 19:30:04)
-
-
-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…
- 大宮科学技術高校
- (2025-10-20 13:16:42)
-
-
-

- ミキハウスにはまりました
- ミキハウス好き限定!10%OFF😀公式シ…
- (2025-11-27 15:50:04)
-