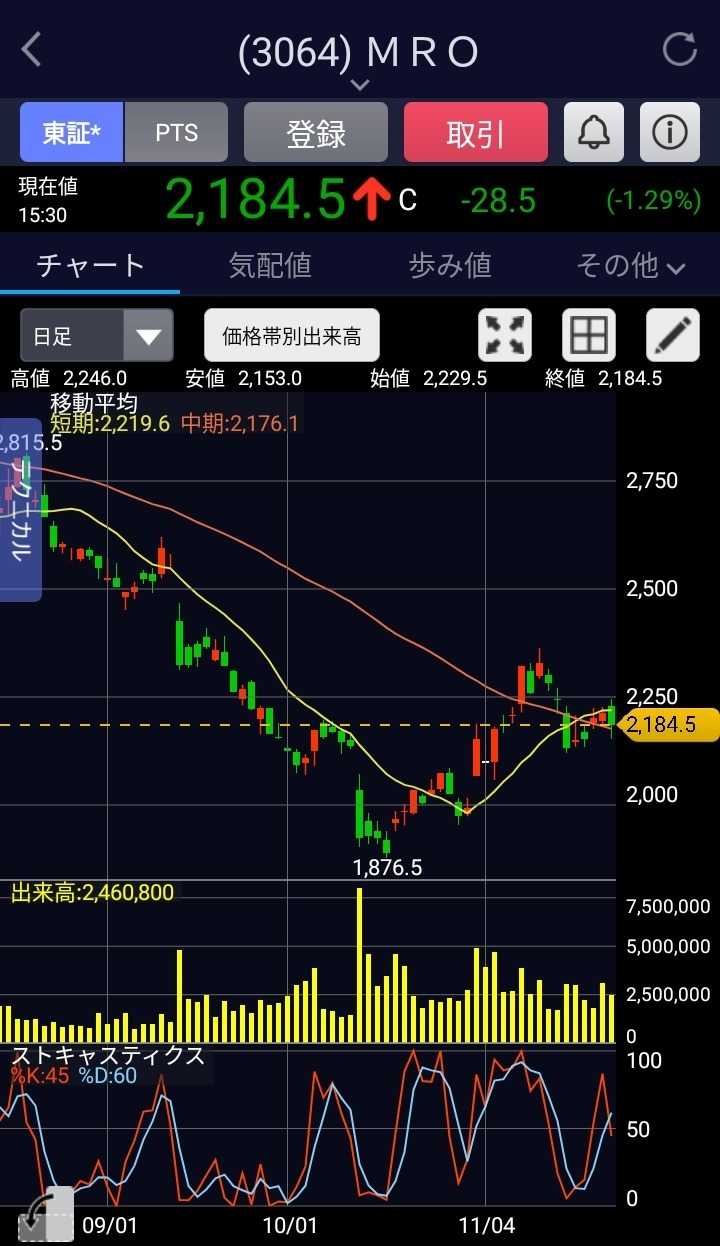2015年04月の記事
全72件 (72件中 1-50件目)
-
4月30日(木) 七等分の知恵
4月30日(木) 七等分の知恵 目の前にケーキがあったとします。そのケーキを七人で食べる時、うまく同じ大きさで取り分けるには、どのようなやり方があるでしょう。 アニメ番組『サザエさん』に、「七等分の天才」という題の話があります。サザエさんの弟カツオは、バームクーヘンでも、羊羹でも、メロンでも、何でも器用に七等分に切り分けます。 「手品みたい!」「定規を使ってるの?」と皆、不思議がりますが、「うちは七人家族だから、体が覚えているんだよ」と、カツオは得意気です。 番組の後半で、七等分の秘密が明らかになります。実は、カツオは普通に八等分に切って、そのうち一個をこっそり隠していたのでした。残りの一個は、後でこっそり食べるか、飼い猫のタマにあげていたのかもしれません。 悪智恵といえばそれまでですが、こうした機知が物を言う場面は、人生でも多くあるでしょう。固定観念を捨て、柔軟に物事に向かう時、カツオのように思いがけない妙手が生まれるかもしれません。 今日の心がけ◆知恵を働かせましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2015年04月30日
コメント(0)
-
4月29日(水) 充電の場
4月29日(水) 充電の場 今朝の目覚めはいかがでしたか。今はどのような気分ですか。今日一日、どのようなことを心がけて働きますか。昨日の疲れが残っていたり、十分な睡眠による爽快感がなければ、朝から気分も沈みがちになってしまうでしょう。 今日一日の働きを一段と活発化させるには、家庭における充電が欠かせません。憩いの空間で過ごす心の安らぎ、しっかりとした睡眠による精神の安定は、なくてはならない要素でしょう。 気力体力を充実させるために、家庭において大切なのは、住みよい環境づくりです。不要な物は捨てる整理や整頓を心がけ、毎日使う玄関や流し場、トイレ、風呂などは、清潔さを保って、落ち着ける場を演出したいものです。 寝室やクローゼットに物が山積みになっていては、安眠は望めません。ホコリだらけの部屋では、食事や会話も進まないでしょう。 家庭で過ごす時間も、一日の働きの一環です。職場に来てからの準備ではなく、家庭での陰なる努力も、働きの質を高める大切な取り組みです。 今日の心がけ◆家庭でも整理整頓を心がけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2015年04月29日
コメント(0)
-
4月28日(火)
4月28日(火) 何のために働くのか 新入社員のKさんは、「やる気に満ち溢れている」と社内で評判です。それは、という自覚が原動力になっているからです。 Kさんは早くに祖父、父親を亡くしました。今は祖母、母親と同居しています。奨学金制度で大学を卒業し、昨年就職しました。月々の奨学金返済に加えて、扶養家族である祖母と母親を養っていかなくてはなりません。 キャリアは浅いもののという秘めた情熱を燃やしています。業務に関する勉強を欠かさず、現場で体を使う働きにも一所懸命です。 私たちは何のために働くのでしょう。「お金を稼ぐため」という答えが多く上がるかもしれません。では、何のためにお金が必要なのでしょうか。 個人の趣味や夢のためにも、お金は必要です。しかし、もっとも清らかで、力強い意欲が湧いてくるのは「誰かのために」という目的ではないでしょうか。 Kさんは今日も家族のために仕事に励み、働けるありがたさを感じています。 今日の心がけ◆働く目的を見つめ直してみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月28日
コメント(0)
-
4月27日(月) 一本のドリル
4月27日(月) 一本のドリル 企業の繁栄に、取引先との信頼関係は欠かせません。信頼関係とはどのように育まれていくのでしょう。その一例を紹介しましょう。 Aさんは、機械工具の卸売りをする会社で営業を担当しています。得意先の営業にまわっているある日の夜、B社の社長から電話が入りました。「作業中にドリルが折れてしまったので届けてくれないか」とのことでした。 注文は一本数百円のドリルです。そろそろ帰ろうかと思っていた時の電話でした。と思いながらも納品に向かうと、「これで明日朝一番の仕事に間に合うよ。夜遅くにありがとう」と、満面の笑みでお礼を言われたのです。 その後も、Aさんの元には、同様の細かい注文が入りました。数百円の品物でも、その度に車を走らせました。 ある時また、B社長からAさんに連絡が入りました。「新しい機械の見積もりを頼むよ」と言われたのは、高額な大型機械の注文だったのです。 些細な仕事でも、大きな成果を生むことがあると知ったAさんでした。 今日の心がけ◆小さな仕事を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月27日
コメント(0)
-
4月27日(月) 一本のドリル
4月27日(月) 一本のドリル 企業の繁栄に、取引先との信頼関係は欠かせません。信頼関係とはどのように育まれていくのでしょう。その一例を紹介しましょう。 Aさんは、機械工具の卸売りをする会社で営業を担当しています。得意先の営業にまわっているある日の夜、B社の社長から電話が入りました。「作業中にドリルが折れてしまったので届けてくれないか」とのことでした。 注文は一本数百円のドリルです。そろそろ帰ろうかと思っていた時の電話でした。と思いながらも納品に向かうと、「これで明日朝一番の仕事に間に合うよ。夜遅くにありがとう」と、満面の笑みでお礼を言われたのです。 その後も、Aさんの元には、同様の細かい注文が入りました。数百円の品物でも、その度に車を走らせました。 ある時また、B社長からAさんに連絡が入りました。「新しい機械の見積もりを頼むよ」と言われたのは、高額な大型機械の注文だったのです。 些細な仕事でも、大きな成果を生むことがあると知ったAさんでした。 今日の心がけ◆小さな仕事を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月26日
コメント(3)
-
4月26日(日) 学生食堂の今
4月26日(日) 学生食堂の今 大学の学生食堂といえば、かつては大テーブルに相席が基本でした。最近は、一人用の席を設置する大学も増えているようです。 大東文化大学の東松山キャンパスにある学食内には、テーブルに半透明のプラスチック板が設置された席が作られています。この席に座ると、対面の人の顔は見えず、カウンターに座っているような状態になります。 これは、学食がサークルの集団などに占拠されがちなため、「個人利用の席を確保してほしい」という父母会からの要望を受け、設置されたそうです。大学は「スピード席」と命名しましたが、通称「ぼっち席」とも呼ばれています。 このニュースを聞いて、どのような感想を持つでしょう。「こういう席があるのはありがたい」「一人ぼっちだと思われるから座りづらい」「コミュニケーションの機会が失われてしまう」など、感じることは人それぞれでしょう。 これから先も、職場には、若い世代が増えていきます。どう指導し、どう受け入れるか。今社会で起きている出来事が、考えるきっかけになるでしょう。 今日の心がけ◆社会の今に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2015年04月26日
コメント(2)
-
4月25日(土) わからないからこそ
4月25日(土) わからないからこそ マネジメントの父と称され、多くの経営者の指針となった経営学者のピーター・ドラッカーは、「未来は予測しがたい方向に変化する」と記しています。 スペインの哲学者・オルテガは、「われわれは明日何が起こるか分からない時代に生きている」と述べ、だからこそ未来は、あらゆる可能性に向かって開かれていると著書で綴っています。 日常生活のあらゆる作業は、科学技術の恩恵によって支えられています。日進月歩で技術は進歩していますから、これから先、私たちの生活がどのように変化し、進歩するのかは誰も予測がつきません。 しかし、科学技術の進歩も、それを作り出すのは人間です。未来は予測できないからこそ、私たちの努力で、いかようにもなるものです。 変化興亡の激しい時代を生きるために、何が起きるかわからないからこそ、無限に広がる可能性に喜びを見出し、未来を肯定的に捉えて、今するべきことに取り組んでいきましょう。 今日の心がけ◆明るい未来を切り開きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2015年04月25日
コメント(0)
-
4月24日(金) 個性的な桜
4月24日(金) 個性的な桜 桜の木は、海外でも見られますが、ことに日本列島には、美しい花を咲かせる、いろいろな種類の桜が、集中して分布しています。 現代では、日本の桜のおよそ八割が「染井吉野」と言われています。「染井吉野」は、葉が茂るよりも先に、花が木いっぱいに咲きます。 成長が早く、植えてから十年足らずで立派な木になるため、江戸時代末期に作り出された新品種にもかかわらず、各地の堤防や公共施設に植えられました。 しかし、最近では「染井吉野」以外の、「山桜」や「八重桜」などの伝統的な桜が見直されています。伝統的な桜には、その花の色や、花弁の数、咲く時期や散り方などに違いがあり、それぞれに豊かな個性があるからです。 昔から日本一の桜の名所と言われている奈良県吉野山や、毎年テレビを賑わす大阪造幣局の通り抜けの桜も、「山桜」や「八重桜」などの伝統的な桜が、それぞれの個性のままに咲き、散りたい時に散ってゆきます。 「染井吉野」だけでなく、各地の個性的な桜にも注目しましょう。 今日の心がけ◆地方の特色を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。
2015年04月24日
コメント(0)
-
4月23日(木) 親孝行の会社
4月23日(木) 親孝行の会社 茨城県を中心に外食産業を展開するB社は、「親孝行」を経営理念に掲げています。お客様からも、社員やパートからも支持を得て、業績を伸ばしています。 B社が示す親孝行の「親」の字には、両親だけではなく、目上の人、上司、先輩など、お世話になっている人すべてを含みます。 その親に感謝の気持ちを持って生活するのと、そうでないのとでは、人生における滋味の豊かさに大きな差が出ると、B社の社長は強い信念を持っています。 働き手の確保に苦慮する飲食業界にあって、B社には、「親孝行がしたいので、この会社に入りたい」と、続々と若者が入社を希望してきます。 物心ともに豊かに生きたいと願っても、その手段を知らなければ、思いを遂げることはできません。B社では、親孝行の一つの形として、初月給から、いくらかの金額を、両親やお世話になった人のために使うことを奨励しています。 先人たちが編み出した「親孝行」は、より豊かに生きるために必要な心の持ち方を知る方法です。自分のためにも、親孝行をしていきたいものです。 今日の心がけ◆感謝の気持ちを忘れずに生活しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2015年04月23日
コメント(0)
-
4月22日(水) 得意と失意
4月22日(水) 得意と失意 苦難に直面し、失意のどん底にある時に、声をかけてくれた人のことを忘れることはできません。 S氏にも、そのような忘れられない人がいます。その日から二十年が経った現在でも、という思いは消えたことがありません。 仕事の失敗が続き、意気消沈していたある日、その人は「失意泰然」という言葉とともに、「仕事が思い通りにいかなくなっても、あせらず、くさらず、落ち着いて、堂々と構えることが大切だ」という意味を教えてくれました。 長い人生には、物事がうまくいく時もいかない時もある。得意と失意は交互にやってくる。気をつけなければ、どちらにあっても自分を見失ってしまう一。そう捉えたS氏は、冷静に自分を見つめることを心がけるようになりました。 その後、何かにつけて決断をしなければならない立場になった氏は、「失意泰然」という言葉が役に立っていることを実感しています。 今日の心がけ◆苦しい時こそゆったりと構えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2015年04月22日
コメント(0)
-
4月21日(火) お先にどうぞ
4月21日(火) お先にどうぞ 地方から都心の職場に転勤したTさん。しばらくは人や車の多さ、移動する人の歩行の速さについて行けず、戸惑うことばかりでした。 と思うことも、しばしばありました。 ある朝の出勤途中、Tさんは、同じタイミングでエスカレーターに乗ろうとした女性とぶつかりそうになりました。ぶつかるのを避けようと、一瞬立ち止まると、その女性は「お先にどうぞ」と譲ってくれたのです。 お礼を言い、先にエスカレーターに乗ったTさんは、ふと我を振り返りました。 仕事の面でも、新しい職場に慣れるにつれて、小さなミスが多くなっていることに気がつきました。初心を忘れずに、また、外を歩く時には「お先にどうぞ」と言える心のゆとりを持ちたいと思ったTさんです。 今日の心がけ◆心にゆとりを持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月21日
コメント(0)
-
5月12日(火) 楽しいことは六十四
5月12日(火) 楽しいことは六十四 ゴールデンウイークの休暇を利用して旅行をするなど、リフレッシュした人もいるでしょう。一方で、休み明けの反動か、やる気が出ない人もいるでしょう。 かつてSさんも、新人時代に、脱力感に襲われました。当時は、会社という新しい環境になかなか馴染めず、仕事の理想と現実のギャップに悩んで、心が暗く沈みがちでした。 様子を見かねた先輩が、声をかけてくれました。 「今は、新しい生活スタイルや人間関係を作り上げ、与えられた業務を必死にこなさなければならないから、辛い時期かもしれないね」 「でも、人生が百の数字だとすれば、楽しいこと(ワッハッハ)は八×八=六十四、悲しいこと(シクシク)は四×九=三十六だろう? 楽しいことは悲しいことの倍あるぞ。ワッハッハ」と笑いながら先輩は去っていきました。 先輩の豪快な話ぶりに、ふっと肩の力が抜けたSさん。やがて、脱力感からも抜け出して、職場でも私生活でも活発に飛び回っています。 今日の心がけ◆時々肩の力を抜きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月11日(月) 完結力と後始末
5月11日(月) 完結力と後始末 仕事をする上で、いくら良い企業であっても、成果に結びつかなくては意味がありません。そのためには、成果を得るまで緊張を緩めないことです。 Tさんは、企画力が抜群で、仕事の手際も良いのですが、完成間際で失敗することがあります。要領がいい分、最後に気を緩めてしまう癖があるからです。 そのようなTさんの仕事ぶりを見て、先輩が、ある助言をしました。それは、後始末を徹底することでした。 半信半疑だったTさんですが、まずは退社時に机を片づけることから始めました。散らかり放題の机を見て、一日の仕事ぶり、後始末の悪さを痛感しました。 その習慣を続けることで、Tさんは少しずつ、緊張感を持続できるようになりました。それが、結果的に、業績の向上につながっていったのです。 後始末は、1物や道具への感謝、2物事の区切り、3次のスタートの準備であると共に、物事を完結させる力を養う訓練にもなります。生活の一場面ごとの後始末をしっかり行ない、物事をやり遂げ、成果をつかむ力を養いたいものです。 今日の心がけ◆後始末に磨きをかけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月10日(日) 思わぬ手紙
5月10日(日) 思わぬ手紙 入社三年目のIさんは、毎日多忙です。帰りも遅くなりがちです。 その日も、デスクに溜まった書類を整理しながら、残業をしていました。すると、書類の間から、以前母親からもらった手紙が出てきたのです。 「また顔を見せてね。元気に頑張って」という短い手紙でした。一人暮らしの自宅に届いた手紙を会社で読んだまま、書類の間に埋もれさせていたのでした。 思いがけず出てきた手紙を読み返すと、心が温かくなりました。こうして忙しく働いている陰で、両親が応援してくれているのだと思うと、心が軽やかになり、いつも以上に仕事に打ち込むことができました。 その日の仕事上がりに、母親に一枚のハガキを書きました。感謝の気持ちはなかなか口に出せないので、文章にして伝えようと思ったのです。週末には久しぶりに実家に戻り、元気な姿を見せることもできました。 それにしても、なぜこの手紙が突然出てきたのかと、不思議に思いながらも、と思うIさんです。 今日の心がけ◆両親に手紙を書きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 9日(土) 休日は何のため
5月 9日(土) 休日は何のため 四月から五月にかけての大型連休を指す「ゴールデンウイーク」という言い方が広まったのは、昭和三十年代のことです。高度経済成長に伴い、連休に、レジャーやショッピングを楽しむ人が増えました。 連休に限らず、普段の祝日や日曜日なども、「いかに休日を楽しむか」という感覚が、現代では一般的でしょう。 一方、江戸時代までの日本には、基本的に「休日」という概念がなかったようです。特に、農家や職人などは「やることがあれば働き、なければ休む」という生活でした。働くことが主、休みは従という意識であったようです。 日頃何気なく用いている「労働」の「労」の字には、「ほねおり」「つかれる」という意味があります。働くことは疲れること、苦しいことだから、できることなら働きたくないという意味にも受け取れる言葉です。 人間が生きていく上で、働きも休息も欠かせません。休日を楽しみながらも、「休みのために働く」という意識になっていないか、点検してみましょう。 今日の心がけ◆働きの意識を再考しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 8日(金) ハガキの投函
5月 8日(金) ハガキの投函 Mさんは、取引先の担当者に、商談が成立した礼状を書きました。 ハガキを投函しようと席を立つと、上司から「これも出しておいてくれ」と、ハガキを渡されました。Mさんは、自分の書いたものと上司のハガキが確かにあることを確認して、ポストに投函しました。 その後、ハガキを投函したことを何気なく告げると、上司は「そうか、ありがとう」と、明るく返事をします。ポストに入れただけですから、特別に喜ばれることではありません。不思議に思っていると、上司はこう言いました。 「投函したことを報告してくれたのは、君が初めてだ。無事に投函されたかどうか、案外気になるものなんだ。人に頼んでおきながら、虫のいい話だけど」と、笑って答えたのです。 確かにMさんも、人に投函を頼んだ時、間違いなく投函してくれたかどうか、気になっても聞けないことがありました。 業務は、行なって終わりではなく、報告して完了すると心得ましょう。 今日の心がけ◆きちんと報告しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 7日(木) 芸人魂
5月 7日(木) 芸人魂 不意のトラブルで交通機関が乱れ、予定通りに目的地へ到着できない事態に遭遇することがあります。 Aさんが寒冷地に出張した時のことです。ターミナル駅に下車すると、大雪のため、多くの路線が止まっていました。改札口の前は、荷物を抱えた人で溢れ返り、困惑して佇む人、駅員に罵声を浴びせる人たちで騒然としていました。 すると、改札口前の広場の一角から、突如、歓声が聞こえてきました。乗客と見られる人が、大道芸を始めたのです。子供たちが大喜びする光景に、周囲の大人たちも穏やかになり、殺伐とした雰囲気が変わっていったのです。 その後、復旧を知らせる放送と共に、観衆は大道芸人を残し、一斉に改札口へ向かいました。自身も交通障害に巻き込まれたにもかかわらず、場を和やかにし、周囲の人を楽しませた芸人魂に、Aさんは深く感銘を受けました。 仕事にはそれぞれ本分があります。困った時こそ人を責めず、本分を自覚し、朗らかにサッと行動できる人でありたいものです。 今日の心がけ◆自分にできることを考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 6日(水) 私にできること
5月 6日(水) 私にできること 南米アシデスに、古来より伝わる『ハチドリのひとしずく』という物語があります。森に火災が広がってしまった時、ハチドリは、口ばしで水を運び、たった一羽で火を消そうとしました。 他の動物たちは、われ先に逃げ出し、「そんなことをして何になるんだ」と笑いましたが、ハチドリはこう答えました。「私は、私にできることをしているの」 ハチドリは、世界で最も小さな種類の鳥です。しかし、もしハチドリが数百万、数千万羽と集まったら、山火事を消すことができるかもしれません。 職場に山積する、一人ではどうすることもできない大きく複雑な問題も、小さな一歩から解決につながります。 と目を背けずに、を考えて行動を始める。そこには必ず応援者が集まり、大きな力を与えてくれるはずです。 まず、あなたが最初の一羽になりましょう。 今日の心がけ◆できることから始めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 5日(火) 五月は花の月
5月 5日(火) 五月は花の月 五月は一斉に花々が咲く月です。 「五月は好い月、花の月、芽の月、香の月、色の月、ポプラ、マロニエ、プラタアヌ、つつじ、芍薬、藤、蘇芳、リラ、チュウリップ、罌栗の月」。与謝野晶子の詩「五月礼賛」の一節です。 日本人は、花を愛でる民族といえます。伝統的な華道とは別に、花を愛でる文化が江戸時代に盛んとなり、園芸種の菖蒲や朝顔、椿や菊などの品種改良が行なわれました。 全国各地に花の名所があり、四季折々の花を観賞することができます。とりわけ、春に咲く桜の花を愛でる「お花見」は、国民的行事といっても過言ではないでしょう。自宅の庭やベランダで、草花を育てている人も多いはずです。 殺伐とした忙しい生活の中だからこそ、花を愛でる心の余裕を持つことは大切でしょう。一所懸命けなげに咲いている花々を見つめて、命の美しさとかけがえのなさを感じたいものです。 今日の心がけ◆花を愛でましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 4日(月) 自然に親しむ
5月 4日(月) 自然に親しむ 五月三日の「憲法記念日」、五日の「こどもの日」に挟まれた四日は、かつて「国民の休日」と呼ばれる祝日でした。 平成十九年からは「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを目的に、「みどりの日」として祝日に制定されています。 もともと「みどりの日」は、植物に造詣が深く、自然をこよなく愛された昭和天皇の誕生日である四月二十九日でした。その日が「昭和の日」に改められ、「みどりの日」は五月に移動されました。連休中に行楽などに出かけて、自然の中で過ごしたり、草花や動物に触れ合う人も多いでしょう。 自然に親しみ、その恩恵に感謝することは、どこか特別なところに行かなければできないわけではありません。皆さんの身の回りにはどれくらい緑がありますか。近所に咲く花、いつも通る道に並んでいる街路樹は何でしょうか。 身近な自然に関心を持ちましょう。生活の場の緑を増やして、その環境を大切に守ることで、豊かな感性を育んでいきたいものです。 今日の心がけ◆身の回りの自然を守りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 3日(日) 教えを守る
5月 3日(日) 教えを守る 戦後を代表する評論家であり、作家であった草柳大蔵氏の若き日の逸話です。 ある国務大臣の家に原稿を受け取りに行った際、応接間のソファに腰かけ、タバコに火をつけて待っていました。 大臣の妻に原稿を渡され、帰ろうとすると、「私の申し上げることは参考として聞いてください」と、よその家を訪問した際のマナーを教わったといいます。 「そこの主人が姿を見せるまでは腰をおろさず、立ったままで待つものですよ。そのために壁に絵がかかっていたり、花瓶に花が生けられているのです」 その後、氏は「応接間のソファには主人が見えるまで座らないで待つ」ことを三十年守り続けました。そういう人物であることが評価されて、「彼の取材なら受ける」と、仕事の成果に結びついたこともあったそうです。 若い頃、仕事で恥をかいたり、失敗したり、落ち込んだりすることは、誰にもあります。その失敗を素直に反省し、自分への教訓として生かしていく姿勢が能力を伸ばし、周囲から信頼を得ることにつながるのでしょう 今日の心がけ◆失敗を糧としましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 2日(土) 濃い顔
5月 2日(土) 濃い顔 昨年、インドの民族衣装で歌い踊る曲がヒットした歌手の平井堅さん。自らの発案で、頭にターバンを巻いて撮影したミュージックビデオが話題になりました。 かつて新宿でインドの人たちの集会に遭遇し、「こっちだ」と手招きされたことがあるほど、顔の彫りが深い平井さん。デビュー当時は、爽やかなイメージで売り出しましたが、なかなか芽が出なかったそうです。 その後、「むしろこの顔を使って、他のアーティストにはできないことをやってやろう」と、無精ヒゲを伸ばし、濃い顔をさらに濃く見せる方向に転換した途端、CDが売れ出したといいます。 人には誰でも、大なり小なりコンプレックスがあります。しかし、自分が思うほど、周りの人は気にしていないものです。気になって隠そうとするほど、人に見られているような気がして、暗い表情にもなりかねません。 「他人との違いは、むしろ自分を覚えてもらうチャームポイントだ」と捉えて、自信を持って、表情を明るくしたいものです。 今日の心がけ◆自分の特徴を魅力にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
5月 1日(金) 魂と共に
5月 1日(金) 魂と共に ある国の旅行者一行が、アフリカ大陸の砂漠を横断するため、現地の人をガイドに雇った時の話です。 出発してから一時間が経った頃、特に疲れた様子でもないのに、ガイドが「休憩したい」と言い出しました。十分間休んで歩き出すと、ガイドは一時間後にまた休みをとりました。その後も、歩いたり休んだりを繰り返しました。 その理由を尋ねられたガイドは、「私たちの歩く速度は速すぎた。魂はついて来ていない。それを待つために休んでいるのだ」と説明したそうです。 私たちの仕事においても、何時間も緊張感を持続させなければならない場面があるかもしれません。常に危険と隣り合わせの仕事に就く人もいるでしょう。 そうした仕事に携わる時、体はここにあっても、心ここにあらずでは、取り返しのつかないミスを犯すだけでなく、大事故につながることもあります。 休日や休憩時間を有効に使い、眼の前の業務に集中できるコンディションを保つことも大事な仕事である、と自覚したいものです。 今日の心がけ◆休みを有効に使って集中力を高めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月20日
コメント(2)
-
4月20日(月) 新人の力
4月20日(月) 新人の力 街のいたるところで、初々しい新入社員の姿を見かけます。 新入社員の皆さんは、一日も早く仕事を覚えて、会社に貢献することが求められています。いずれ社会に貢献できる人になってほしいと期待されています。 では、今の段階では、会社に何も貢献できていないのでしょうか。そんなことはありません。新人にしかない力があります。それは職場の空気を変える力です。 爽やかな風が舞い込んできたかのように、職場に新鮮な空気を吹き込みます。それによって、迎える先輩も新人時代を思い出し、新鮮な気持ちになれるのです。 その新人力を強みに、わからないことは堂々と尋ね、一つひとつの仕事を謙虚に身につけていきましょう。 また、これまで何気なくやっていた挨拶や返事を一音階上げて、明るいトーンに変えてみましょう。毎日意識すると、とっさの時に成果が表われます。 そんな新人を見習い、先輩社員はまた、新たな気持ちで仕事に取り組みましょう。まずは、一日のスタートとなる朝礼に臨む意識を新たにしたいものです。 今日の心がけ◆新たな気持ちで朝礼に臨みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。この「職場の教養」は書店で販売していません。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が、毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。
2015年04月20日
コメント(0)
-
4月19日(日)
4月19日(日) 緊張と喜び 祭事などの終了後、神様に供えた御神酒や食物を下げて、それを戴くことを「直会」といいます。これは「緊張した状態から元の状態に直り会う」が語源とされています。 古代社会では、神事など大切な行事を行なう際は、緊張感を持って滞らないようにしなければなりませんでした。神事が終了すると、公の正式な場はお開きとなり、酒席を設けて緊張を和らげたといいます。 同じ意味合いを持つ言葉に「宴」があります。「宴」は「歌い上げ」が語源とされ、神事が一致協力して終わった後、何事もなく終えられた喜びを皆で歌い合ったことが言葉のルーツです。 聖徳太子が制定した十七条憲法に「和を以って貴しとなす」と示されているとおり、皆で協力して大きな仕事を成し遂げ、成功したら喜び合うのが日本文化といえるでしょう。 言葉の語源に隠された日本の心に触れ、自身の生活にも活かしたいものです。 今日の心がけ◆日本の精神文化を知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2015年04月19日
コメント(0)
-
4月18日(土) 松陰先生の教え
4月18日(土) 松陰先生の教え 吉田松陰は、日本を代表する教育者であり思想家です。松陰が主宰した「松下村塾」は、後に明治維新を打ち立てた多数の志士を輩出しました。 松陰の教えが今も脈々と受け継がれているのが、故郷・山口県萩市にある明倫小学校です。明倫小の一日は、朗唱から始まります。 昭和五十六年から続いている朗唱には、松陰の詩歌や著書から、人の生き方や読書の大切さがわかる言葉が選ばれます。一年生から六年生までの全児童が姿勢を正し、教室のガラスがビリビリと振動するような声で元気よく朗唱します。 朗唱する言葉の意味をすべては理解できなくても、その言葉は児童たちの心に刻まれ、生き方の指針となり、意思決定の基となっていくのでしょう。 職場人にとっては、自社の経営理念や社是・社訓が、創業の精神を言葉に表わした重要な指針となります。 朝礼などで日々斉唱していると、ついマンネリになりがちですが、元気良く唱和し、経営者の思いを胸に刻んで、業務に邁進しましょう。 今日の心がけ◆声に出して心に刻みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2015年04月18日
コメント(0)
-
4月17日(金) 客ぶり
4月17日(金) 客ぶり 茶道の世界に「客ぶり」という言葉があります。 良い客ぶりとは、おもてなしをする主人側に対して、もてなしを受ける客側が、主人側を喜ばす所作や振る舞いをすることです。これにより「おもてなし」が完成し、主客ともに、和を満ちた時を過ごすことができるというものです。 私たちは普段、いろいろな店に足を運びます。その際、感じの良い店か悪い店か、客の立場から評価をします。これに対して、客である私たち自身が、客ぶりの良さを発揮しているでしょうか。 客ぶりの良さを発揮するのは難しいことではありません。品物を受け取り、代金を支払う時に「ありがとう」の一言を添えられるかどうかです。 お金を出すのは客側でも、商品を販売するお店があってこそ購入できるのですから、ともに感謝し合うのが本来の姿でしょう。 気軽に「ありがとう」を添えてみませんか。「ありがとう」は店側に好感を持たれるだけでなく、購入者の人柄や品性の高さをも感じさせる一言です。 今日の心がけ◆気軽に「ありがとう」を添えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。
2015年04月17日
コメント(0)
-
4月16日(木) 聞いていない話
4月16日(木) 聞いていない話 大病を患い、病院通いが続いているY氏。これまで通っていたA病院から、専門のB病院へ転院することが決まり、外来の日を決めるため、B病院へ連絡を入れました。 しかし、転院する話が、B病院の事務局には通っていない様子です。電話に出た事務員は「何も聞いていません」と、終始、冷ややかな対応です。 数日後、B病院から電話がありました。「主治医同士ではメールのやり取りをしていたものの、事務局で確認ができていませんでした」と、お詫びと外来日の連絡を受けました。前回とは同一人物とは思えないほど、丁寧な物腰でした。 不愉快な思いをしたY氏でしたが、かつて自分も、似たような対応をしたことを思い出しました。仕事に慣れてきた頃、「自分は聞いていない」とお客様に返事をして、嫌な思いをさせてしまったことがあるのです。 話の内容が伝わっていない用件に、対応せざるを得ない状況は起こるものです。特に電話の場合、お互いの顔が見えないだけに、謙虚に受け答えしたいものです。 今日の心がけ◆謙虚に応対しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。
2015年04月16日
コメント(0)
-
4月15日(水) 信頼の計算式
4月15日(水) 信頼の計算式 算数の計算式では、十-一=九ですが、信頼において同様の引き算を当てはめると、十-一がゼロになったり、時にはマイナスにもなってしまいます。 お客様に対するたった一度の失礼な態度や嘘偽りが、それまで築いた信頼関係を台無しにしてしまうことがあるのです。 逆に、信頼における足し算も、計算式には当てはまらないでしょう。マイナス十に一を足した時、それが一気にプラスに転じることがあります。 例えば、失敗やミスの後の丁寧な謝罪と応対が、顧客に感動を与え、それまでより、強い信頼関係を築くこともよくある話です。 信頼のもとは、サービスの内容もさることながら、最終的には、それに携わる人の誠意でしょう。それは数値には表われません。 信頼は、誠意の積み重ねによって築かれ、油断や妥協により崩されます。業務を全うする責任感と、真心を込めたサービスが信頼をさらに強固にするでしょう。 一人ひとりが業務に全力で励む姿勢こそ、企業の信頼を築く鍵です。 今日の心がけ◆小さなことにも全力で取り組みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。
2015年04月15日
コメント(0)
-
4月14日(火) 雨の日もウォーキング
4月14日(火) 雨の日もウォーキング 会社の健康診断で「軽肥満」の判定が出たMさん。保健指導で「あと三キロは痩せるように」と助言され、出勤前にウォーキングすることを決意しました。 一週間続けた朝、いつものように玄関の扉を開けると、雨が降っていました。とレインコートを着て、いつものコースを歩き始めました。そして、約一時間のウォーキングを終えて自宅に戻りました。 家に着き、濡れた体をタオルで拭いていると、ぞくぞくと悪寒がしました。慌てて体温を測ると、熱が三十八度あります。とても出勤できる状態ではなく、会社に連絡をして、その日は休むことになりました。 布団の中でうなされるMさん。傍らで看病してくれた妻からは、「あなたの目的はウォーキングじゃなくて、痩せることでしょう。雨の日は無理してあるかなくても、家の中でできる運動をしたらどう?」と言われました。 たしかに妻の言うとおりです。その日から、雨の日は家の中でストレッチやトレーニングを行なうようにして、少しずつ成果を上げています。 今日の心がけ◆目的を確認しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。
2015年04月14日
コメント(0)
-
4月13日(月) 家に社長はいない
4月13日(月) 家に社長はいない 私たちは一日の中で、様々な立場を使い分けています。 たとえば会社の中では、部下に対しては上司であり、上司の前では部下です。お客様に対しては、その会社の代表という立場にもなります。いろいろな立場で仕事をする度に、言葉や態度を変えていかなければなりません。 職場内のみならず、家族や地域の中での立場もあります。立場の自覚があれば、それに応じた働きができるものです。 もし、その自覚が薄れてしまうと、誰でも傲慢になりがちです。たとえ会社のトップでも、家族の一員であり、地域の住民です。家に帰って「俺は社長だ、言うことを聞け!」と言っても、子供はついてこないでしょう。 常に立場を自覚して働くためのポイントがあります。それは感謝する心です。と思えば、父親の自覚は深まります。と思えれば、上司としての自覚は深まっていくでしょう。 その場に、相手に、感謝の念を忘れずに、立場の自覚を深めたいものです。 今日の心がけ◆立場の自覚を深めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。この「職場の教養」は書店で販売していません。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が、毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。
2015年04月13日
コメント(0)
-
4月12日(日) 自己存在感の確立
4月12日(日) 自己存在感の確立 本誌発行元の倫理研究所では、家庭教育の大切さを伝えるフォーラムを全国各地で開催しています。 各開催地では、地元の教育にかかわる有識者や経営者が登壇します。コーディネーターと共に、それぞれの立場から、家庭のあり方や人材教育など、多岐にわたるトークが展開されます。 フォーラムを通じて見えてきたことの一つは、人間が輝いて生きるためには、乳幼児から高齢者にいたるまで、「自己存在感」を確立することが重要な要素になる、ということです。 自己存在感とは「私は必要とされている」という自覚です。たとえば「あなたのお陰で・・・」という一言は、「自分は役に立っているんだ」「ここにいていいんだ」と自己存在感を高める大きな力になるでしょう。 職場においても、互いの個性を活かし合い、存在を認め合う時に、マンパワーが増大します。自らの生きる力も強くなり、活力溢れる職場となるでしょう。 今日の心がけ◆互いの個性を尊重しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2015年04月12日
コメント(0)
-
4月11日(土) 失敗も一つの成果
4月11日(土) 失敗も一つの成果 小惑星探査機「はやぶさ」が二〇一〇年六月、小惑星「イトカワ」から微粒子を採取し、地球に帰還しました。このイトカワという名は、「日本の宇宙開発・ロケット開発の父」と呼ばれた糸川英夫博士にちなんだものです。 日本の宇宙開発の歴史は一九五五年、わずか全長二十三センチのペンシルロケットの水平発射実験から始まりました。この後、十年余りの糸川博士を中心としたロケット打ち上げ実験は、まさに試行錯誤の連続でした。 当時の新聞は、「糸川ロケットまた失敗」と、否定的な記事を掲載し続けました。しかし、常に最先端の技術を追求することに誇りを持ち、「失敗も一つの成果」とポジティブに捉え、次へステップアップする教訓を得てきたのです。 初号機だった「はやぶさ」の七年に及ぶ行程は、昨年十二月に打ち上げられた「はやぶさ2」への更なる教訓として、活かされていくでしょう。 日本の宇宙開発のごとく、職場のリーダーとは、いつでも希望に燃え、「どうしたらできるのか」を常に考えて好影響を及ぼしていく存在をいうのです。 今日の心がけ◆失敗を次へ活かしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2015年04月11日
コメント(2)
-
4月10日(金) 一流に触れる
4月10日(金) 一流に触れる 小説家の池波正太郎氏は、若い頃から様々な「一流」に触れることの大切さを述べています。いい店に行くこともその一つです。 「ただ食べるということだけではなくて、いろいろ相手の気の配りかたがわかれば、こっちの勉強にもなる」として、たとえ若くても、倹約してお金を貯め、その道の一流の店に行くことを勧めています。 一流に触れることは、仕事を上達させる秘訣でもあります。第一線で活躍する人の仕事に触れ、それを目指すことで、仕事に取り組む姿勢が変わり、今後の自分の仕事を支える財産になっていきます。 また、目標とする人の仕事ぶりや姿勢、所作を真似ることにより、技術だけでなく、そこに込められた想いも学ぶことができます。もし、見てわからないことがあれば、受身になるのではなく、積極的に尋ねて、話を聞きましょう。 一流の人を徹底的に真似て、学ぶことを続けていくと、やがてそこに自分の個性が加わり、独自の仕事ぶりが生まれていくのです。 今日の心がけ◆第一線の人から学びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月10日
コメント(0)
-
4月 9日(木) 三つの基本
4月 9日(木) 三つの基本 社会人として一歩を踏み出した皆さんへ。まずは、職場の雰囲気にとけ込み、仕事に慣れることが第一歩です。与えられた仕事が何であれ、喜んで取り組み、一所懸命に基本をマスターしていきましょう。 仕事に限らず、物事の基本となるものは、時代が変わっても変わることはありません。いつまでも大事に守っていくべきものです。 野球、サッカー、相撲などのスポーツも、書道や華道などの伝統芸術も、すべて基本の動作を大切にしています。基本を身につけなければ、いくら上辺のテクニックを磨いたところで、能力はなかなか向上しないでしょう。 日常生活の上でも、忘れてはいけない基本が三つあります。 1「おはようございます」と元気よく、自分から先手で挨拶を行なう。 2名前を呼ばれたら、「ハイ」と心を込めて、感じのいい返事をする。 3「ありがとう」という感謝の心で、すべての後始末をきちんと行なう。 「挨拶、返事、後始末」の三原則を実行していきましょう。 今日の心がけ◆基本を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です
2015年04月09日
コメント(0)
-
4月 8日(水) 美容師の原点
4月 8日(水) 美容師の原点 四月は新たな門出の月です。期待と不安が交錯する中、多くの人が新しい一歩を踏み出していきます。物事がスタートする月であり、それぞれに原点に立ち返ることができるのも、この四月ではないでしょうか。 美容師になり、十九年目となるA子さん、下積み時代は失敗も多く、何度も挫折を味わいました。その後、A子さんを指名するお客様も増え、お店にとっても、お客様にとっても、なくてはならない存在になっています。 A子さんが美容師を目指したのは、小学校五年生の時です。母親に連れられて、初めて美容院で髪を切ってもらったことがきっかけでした。緊張して硬くなっていたA子さんに、若くて明るい美容師が、常に笑顔で接してくれたのです。 切り終わった後に、「とっても可愛くなったわね!」と言われたことが心の底から嬉しく、「私も美容師になりたい」と強く思ったのでした。 かつては何度も仕事を辞めることを考えたA子さん。その度に原点に立ち返り、再スタートを切りました。今では喜んで仕事に打ち込んでいます。 今日の心がけ◆原点を振り返ってみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2015年04月08日
コメント(0)
-
4月 7日(火) 三冠達成
4月 7日(火) 三冠達成 今年一月、全日本バレーボール高等学校選手権大会において、男子は東福岡高校が初優勝を飾りました。 これまで頂点にはあと一歩届かないことが続いていた同校ですが、全国高校総体と、福岡県選抜としての国体の優勝を合わせて、みごと三冠を達成しました。 「土壇場で際どいところを狙って入るかどうかは、うまいか下手かじゃない。人間性だ」と説いてきた藤元聡一監督。選手各自が率先してゴミ拾いなどに取り組む中、「小さなゴミも見過ごさないことが、コートで一つのプレーを大切にする気持ちにつながった」と、アタッカーの古賀健太選手は語っています。 二人の言葉を職場人向けに意訳すると、どうなるでしょうか。 1ピンチの時や決断を迫られた際に、物を言うのは人間性である。 2普段からの整理・整頓・清掃が人間性を磨き、一つひとつの業務を大切にする心を養い、いざという時に力を発揮できる。 身近な実践で人間性を磨きながら、実力を養っていきたいものです。 今日の心がけ◆人間性を磨きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2015年04月07日
コメント(0)
-
4月 6日(月) 突然の依頼
4月 6日(月) 突然の依頼 仕事をする上で、一日の見通しを立てることは大切です。朝にその日の予定を立て、優先順位をつけてから、仕事に取りかかる人は多いでしょう。 ところが、予期せぬ仕事を突然上司からふられて、せっかく立てた予定が崩れてしまうことがあります。と、心の中で愚痴の一つも言いたくなるものです。 もちろん、手の離せない最優先事項がある場合は、きちんと上司に説明するべきでしょう。しかし、仕事に「予定外」はつきものです。 その仕事の量や難度や様々な状況を考えた上で、と信頼して頼まれているのですから、まずは「ハイ」と受けて、自分のできる最善を尽くしましょう。 と思うような仕事こそ、自分の力を引き出してくれるものです。予期せぬ仕事をこなした経験が、自分を成長させてくれたことに、いつか気がつくはずです。 今日の心がけ◆予定外の仕事でも引き受けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。この「職場の教養」は書店で販売していません。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が、毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。
2015年04月06日
コメント(0)
-
4月 5日(日) シルバー川柳
4月 5日(日) シルバー川柳 平成十三年にスタートした「シルバー川柳」は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が企画し、公募を行なっています。 毎年、高齢社会や高齢者の日々の生活をテーマにした川柳が集まります。「同時期にシュウカツをする孫と爺」という入選作のように、昨年は、孫や子供、家族をテーマとした、身内ネタの作品が多かったようです。 また、老化や病気はシニア川柳の定番です。「老いるとはこういうことかと老いて知る」「糖尿病甘い生活記憶なし」など、老いを実感し、病気とつきあいながらも、肯定的に受け止めようとする姿勢が、笑いと共に表現されています。 近年の傾向として、妻を題材としたものに比べて、妻が夫を詠む句が減っているそうです。また、「五輪」「スマホ」「シュウカツ」等の言葉から、シニア世代の関心事を知ることもできます。 人生の先達の言葉や体験には、様々な学びがあります。シニア世代の働きの上に今日の繁栄があることを思い、尊敬する気持ちを持ち続けたいものです。 今日の心がけ◆人生の先輩の言葉に耳を傾けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2015年04月05日
コメント(0)
-
4月 4日(土) 桜の季節到来
4月 4日(土) 桜の季節到来 日本の国花といえば、何の花だと思いますか。国花を法的に定める規定はないものの、日本人にもっとも愛されている花として、桜を思い描くでしょう。 桜はバラ科サクラ属に分類される落葉広葉樹です。四百種類以上ある中で、もっとも一般的で馴染み深いのは「㳃井吉野」です。 桜の図案は、昭和四十二年から現在に至るまで、百円硬貨に使われています。また、かつては電報の文面として、志望校に合格すると「サクラサク」、不合格なら「サクラチル」と用いられていました。 なぜ日本人に桜が好まれるのでしょう。理由はいろいろありそうですが、ぱっと咲き、さっと散っていくその儚さ、潔さに、諸行無常を感じ取り、人生を重ね合わせて好まれたともいわれます。 皆さんの住む地域では、今年の桜の開花はいつ頃でしょうか。会社仲間と、家族と、友人と、あるいは一人でも、ゆったりと花を愛で、英気を養ってはいかがでしょう。 今日の心がけ◆花見を楽しみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2015年04月04日
コメント(2)
-
4月 3日(金) 企業イメージ
4月 3日(金) 企業イメージ Mさんは、スマートフォンを新しい機種に買い換えることに決めました。 その際、携帯電話の会社も、A社からB社へ変更することにしました。最近は会社を変えても、今の番号をそのまま使えるサービスがあるからです。 手続きのため、A社の店舗を訪れたMさん。担当者は中年層の男性です。他社に乗り換えることを告げると、「まだポイントが残っている」とのことでした。 「手続き後にはポイントが失効してしまいますので、アクセサリー類の購入にお使いになりませんか」と勧められました。そして、店を出る際には「また当社に戻っていただける日を心よりお待ちしております」と、笑顔で見送られました。 Mさんは十年以上A社を利用していたので、と思っていました。しかし、店員の爽やかな応対に、その気持ちは払拭され、むしろと好感を覚えたのです。 その会社で働く人の言動は、企業イメージに直結します。特に、お客様が退会する時や契約が切れる時こそ、明るさが肝心です。 今日の心がけ◆最後まで真心を込めて応対しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。
2015年04月03日
コメント(0)
-
4月 2日(木) 「あれ」はどれ?
4月 2日(木) 「あれ」はどれ? 日本語では、近くを指して「これ・ここ」と言い、中間のものは「それ・そこ」と言います。遠くのものは「あれ・あそこ」、不確定のものは「どれ・どこ」などと表現します。 これらの指示語は、最初の一文字をとって「こそあど言葉」と呼びます。「こそあど」の部分を変えるだけで、様々な距離感を表現できる便利な言葉ですが、使い方によっては、話し手の意図が聞き手に伝わらない場合があります。 比較的近い対象について「これ・それ」と指し示せば、聞き手はすぐに理解できます。しかし、唐突に「あの件について」「あれはどうした?」と言われると、聞き手はすぐに理解できず、間違いや誤解も生じてきます。 「こそあど言葉」の中でも、「あれ・あちら・あそこ・あの」など、「あ」を使う際には、前後に説明を加えるなどの配慮が必要でしょう。 特に重要な事柄を伝える場合には、できる限り、具体的かつ明確な言葉を使って、用件が正しく相手に伝わるよう心がけていきたいものです。 今日の心がけ◆用件は具体的に伝えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2015年04月02日
コメント(0)
-
4月30日(木) 七等分の知恵
4月30日(木) 七等分の知恵 目の前にケーキがあったとします。そのケーキを七人で食べる時、うまく同じ大きさで取り分けるには、どのようなやり方があるでしょう。 アニメ番組『サザエさん』に、「七等分の天才」という題の話があります。サザエさんの弟カツオは、バームクーヘンでも、羊羹でも、メロンでも、何でも器用に七等分に切り分けます。 「手品みたい!」「定規を使ってるの?」と皆、不思議がりますが、「うちは七人家族だから、体が覚えているんだよ」と、カツオは得意気です。 番組の後半で、七等分の秘密が明らかになります。実は、カツオは普通に八等分に切って、そのうち一個をこっそり隠していたのでした。残りの一個は、後でこっそり食べるか、飼い猫のタマにあげていたのかもしれません。 悪智恵といえばそれまでですが、こうした機知が物を言う場面は、人生でも多くあるでしょう。固定観念を捨て、柔軟に物事に向かう時、カツオのように思いがけない妙手が生まれるかもしれません。 今日の心がけ◆知恵を働かせましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月29日(水) 充電の場
4月29日(水) 充電の場 今朝の目覚めはいかがでしたか。今はどのような気分ですか。今日一日、どのようなことを心がけて働きますか。昨日の疲れが残っていたり、十分な睡眠による爽快感がなければ、朝から気分も沈みがちになってしまうでしょう。 今日一日の働きを一段と活発化させるには、家庭における充電が欠かせません。憩いの空間で過ごす心の安らぎ、しっかりとした睡眠による精神の安定は、なくてはならない要素でしょう。 気力体力を充実させるために、家庭において大切なのは、住みよい環境づくりです。不要な物は捨てる整理や整頓を心がけ、毎日使う玄関や流し場、トイレ、風呂などは、清潔さを保って、落ち着ける場を演出したいものです。 寝室やクローゼットに物が山積みになっていては、安眠は望めません。ホコリだらけの部屋では、食事や会話も進まないでしょう。 家庭で過ごす時間も、一日の働きの一環です。職場に来てからの準備ではなく、家庭での陰なる努力も、働きの質を高める大切な取り組みです。 今日の心がけ◆家庭でも整理整頓を心がけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月28日(火) 何のために働くのか
4月28日(火) 何のために働くのか 新入社員のKさんは、「やる気に満ち溢れている」と社内で評判です。それは、という自覚が原動力になっているからです。 Kさんは早くに祖父、父親を亡くしました。今は祖母、母親と同居しています。奨学金制度で大学を卒業し、昨年就職しました。月々の奨学金返済に加えて、扶養家族である祖母と母親を養っていかなくてはなりません。 キャリアは浅いもののという秘めた情熱を燃やしています。業務に関する勉強を欠かさず、現場で体を使う働きにも一所懸命です。 私たちは何のために働くのでしょう。「お金を稼ぐため」という答えが多く上がるかもしれません。では、何のためにお金が必要なのでしょうか。 個人の趣味や夢のためにも、お金は必要です。しかし、もっとも清らかで、力強い意欲が湧いてくるのは「誰かのために」という目的ではないでしょうか。 Kさんは今日も家族のために仕事に励み、働けるありがたさを感じています。 今日の心がけ◆働く目的を見つめ直してみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月27日(月) 一本のドリル
4月27日(月) 一本のドリル 企業の繁栄に、取引先との信頼関係は欠かせません。信頼関係とはどのように育まれていくのでしょう。その一例を紹介しましょう。 Aさんは、機械工具の卸売りをする会社で営業を担当しています。得意先の営業にまわっているある日の夜、B社の社長から電話が入りました。「作業中にドリルが折れてしまったので届けてくれないか」とのことでした。 注文は一本数百円のドリルです。そろそろ帰ろうかと思っていた時の電話でした。と思いながらも納品に向かうと、「これで明日朝一番の仕事に間に合うよ。夜遅くにありがとう」と、満面の笑みでお礼を言われたのです。 その後も、Aさんの元には、同様の細かい注文が入りました。数百円の品物でも、その度に車を走らせました。 ある時また、B社長からAさんに連絡が入りました。「新しい機械の見積もりを頼むよ」と言われたのは、高額な大型機械の注文だったのです。 些細な仕事でも、大きな成果を生むことがあると知ったAさんでした。 今日の心がけ◆小さな仕事を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月26日(日) 学生食堂の今
4月26日(日) 学生食堂の今 大学の学生食堂といえば、かつては大テーブルに相席が基本でした。最近は、一人用の席を設置する大学も増えているようです。 大東文化大学の東松山キャンパスにある学食内には、テーブルに半透明のプラスチック板が設置された席が作られています。この席に座ると、対面の人の顔は見えず、カウンターに座っているような状態になります。 これは、学食がサークルの集団などに占拠されがちなため、「個人利用の席を確保してほしい」という父母会からの要望を受け、設置されたそうです。大学は「スピード席」と命名しましたが、通称「ぼっち席」とも呼ばれています。 このニュースを聞いて、どのような感想を持つでしょう。「こういう席があるのはありがたい」「一人ぼっちだと思われるから座りづらい」「コミュニケーションの機会が失われてしまう」など、感じることは人それぞれでしょう。 これから先も、職場には、若い世代が増えていきます。どう指導し、どう受け入れるか。今社会で起きている出来事が、考えるきっかけになるでしょう。 今日の心がけ◆社会の今に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月01日
コメント(5)
-
4月25日(土) わからないからこそ
4月25日(土) わからないからこそ マネジメントの父と称され、多くの経営者の指針となった経営学者のピーター・ドラッカーは、「未来は予測しがたい方向に変化する」と記しています。 スペインの哲学者・オルテガは、「われわれは明日何が起こるか分からない時代に生きている」と述べ、だからこそ未来は、あらゆる可能性に向かって開かれていると著書で綴っています。 日常生活のあらゆる作業は、科学技術の恩恵によって支えられています。日進月歩で技術は進歩していますから、これから先、私たちの生活がどのように変化し、進歩するのかは誰も予測がつきません。 しかし、科学技術の進歩も、それを作り出すのは人間です。未来は予測できないからこそ、私たちの努力で、いかようにもなるものです。 変化興亡の激しい時代を生きるために、何が起きるかわからないからこそ、無限に広がる可能性に喜びを見出し、未来を肯定的に捉えて、今するべきことに取り組んでいきましょう。 今日の心がけ◆明るい未来を切り開きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月24日(金) 個性的な桜
4月24日(金) 個性的な桜 桜の木は、海外でも見られますが、ことに日本列島には、美しい花を咲かせる、いろいろな種類の桜が、集中して分布しています。 現代では、日本の桜のおよそ八割が「染井吉野」と言われています。「染井吉野」は、葉が茂るよりも先に、花が木いっぱいに咲きます。 成長が早く、植えてから十年足らずで立派な木になるため、江戸時代末期に作り出された新品種にもかかわらず、各地の堤防や公共施設に植えられました。 しかし、最近では「染井吉野」以外の、「山桜」や「八重桜」などの伝統的な桜が見直されています。伝統的な桜には、その花の色や、花弁の数、咲く時期や散り方などに違いがあり、それぞれに豊かな個性があるからです。 昔から日本一の桜の名所と言われている奈良県吉野山や、毎年テレビを賑わす大阪造幣局の通り抜けの桜も、「山桜」や「八重桜」などの伝統的な桜が、それぞれの個性のままに咲き、散りたい時に散ってゆきます。 「染井吉野」だけでなく、各地の個性的な桜にも注目しましょう。 今日の心がけ◆地方の特色を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2015年04月01日
コメント(0)
-
4月23日(木) 親孝行の会社
4月23日(木) 親孝行の会社 茨城県を中心に外食産業を展開するB社は、「親孝行」を経営理念に掲げています。お客様からも、社員やパートからも支持を得て、業績を伸ばしています。 B社が示す親孝行の「親」の字には、両親だけではなく、目上の人、上司、先輩など、お世話になっている人すべてを含みます。 その親に感謝の気持ちを持って生活するのと、そうでないのとでは、人生における滋味の豊かさに大きな差が出ると、B社の社長は強い信念を持っています。 働き手の確保に苦慮する飲食業界にあって、B社には、「親孝行がしたいので、この会社に入りたい」と、続々と若者が入社を希望してきます。 物心ともに豊かに生きたいと願っても、その手段を知らなければ、思いを遂げることはできません。B社では、親孝行の一つの形として、初月給から、いくらかの金額を、両親やお世話になった人のために使うことを奨励しています。 先人たちが編み出した「親孝行」は、より豊かに生きるために必要な心の持ち方を知る方法です。自分のためにも、親孝行をしていきたいものです。 今日の心がけ◆感謝の気持ちを忘れずに生活しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2015年04月01日
コメント(0)
全72件 (72件中 1-50件目)