2007年02月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
中尾語録008 目的は考えるための指針となるものと、行動できる具体化したものが必要
中尾語録008 目的は考えるための指針となるものと、行動できる具体化したものが必要企業で言えば、目的というのは、企業理念にあらわされます。しかし、多くの場合、企業理念は曖昧で、抽象的に表現されます。そのため、企業理念の浸透が末端まで伝わることがとても難しいわけです。そこで、それを具体的にしたものをいかにTOPが伝えられるかが必要になってくるわけです。それにより、末端レベルの行動に落とし込まれ行動に変わるのです。これはあらゆることに共通で目的を考えたらそれを指針とし、行動に落とせるための具体化したもの言い換えれば手段かもしれません。これを示すことで、目標が、よりリアルに、より身近になり実現に一歩も二歩も近づけるわけです。抽象的で曖昧な目標だけでは一歩も二歩も遠ざかってしまいます。なので・・・ 目的は考えるための指針となるものと、行動できる具体化したものが必要
2007年02月28日
-
中尾語録007 ビジネススキルより、ヒューマンスキル
中尾語録007 ビジネススキルより、ヒューマンスキルビジネススキルとヒューマンスキルというのは車で言えば ビジネススキル:タイヤ ヒューマンスキル:エンジンというイメージでしょうか?まずはエンジンがあるから、車が動くタイヤがあるから前に進めるそんなイメージを人に当てはめるとヒューマンスキルがあるから人は動くビジネススキルがあるから、前に進める言い換えればヒューマンスキルがなければ人は動けないビジネススキルがなければ前に進めないつまり両方大事というわけです。しかしどちらが優先かといえば、エンジンですよね?人としての土台があるからビジネススキルが生きてくるわけです。先日発売された雑誌「SAY」の中でもお話ししましたが、様々なビジネススキルの根本にあるのはヒューマンスキル(雑誌の中では特に自立心としてますが)なんです。これは先日お話しした、心技体の順番と同じです。だから ビジネススキルより、ヒューマンスキル
2007年02月27日
-
中尾語録006 知識や情報をアウトプットできるようにすることが教育の本来の形
最近、読者の方からの感想がよく届くようになりました。お返事遅くなる場合もありますが、全部お返事しますので、ご遠慮なくメールをくださいね!今日の中尾語録はこちらです!中尾語録006 知識や情報をアウトプットできるようにすることが教育の本来の形学校教育では、今さかんに詰め込み教育が問題になって教育改革などと叫ばれるようになりましたがまだまだ今の学校教育はインプット中心です。学生と社会人の違いの中で、一番大きなものがココだと思います。今の学生は(前からですが)学校教育の中で、何かの課題には必ず答えがあって、既存の理論に基づき、一つの答えを導き出すことが中心になっています。ところが社会に出ると、課題に対して答えはいくつもあり、その中から自分なりの理論を考え、答えを作り出すことが必要になってきます。その理論になるための教育、それを使えるようにする教育つまりアウトプットできてこそ、教育が生きるわけです。この思考の転換が学生から社会人への意識の切り替えには、欠かせません。「これはこうだから、こうしなさい」ではなく、「これについてどう思いますか? その理由はなんですか?」こんな風に双方向のコミュニケーションが思考を切り替え、広げていきます。学校教育のようにインプットのみでは単なる評論家しか育ちません。インプット型からアウトプット型への意識転換そのためにはこれを忘れないことです。知識や情報をアウトプットできるようにすることが教育の本来の形
2007年02月26日
-
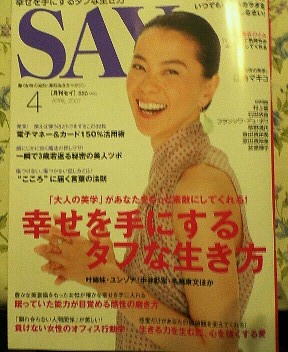
中尾語録005 目的を見失うと手段ばかりを考えて、方向を見失う
青春出版さんから「SAY」4月号が届きました!表紙は江角マキコさんです!先日ご紹介しましたとおり僕の記事が巻頭特集にでてます!!共演は、叶姉妹(笑)←この二人も出てるというだけです・・・まずは20ページ「美学のあるオフィスライフ送っていますか?」ということで、導入部分が僕のコメントから始まります!そのあとは「オフィスの美意識」チェックリストなんかも面白いのでやってみてくださいね!それから、24~25ページです!ここは「仕事とは『人の希望』を叶えること」として自分の夢と職業の関係、仕事とは?なんてことを短くお話しています!一番お伝えしたかったことはカットされてますが(笑)さて、前振りが長くなりますが、本日の中尾語録いきます!中尾語録005 目的を見失うと、手段ばかりを考えて、方向を見失う昨日の話しとほぼ同じですが目的の重要性です。たとえば、また不二家さんの例で申し訳ないのですが同じケーキをつくるでも目的が「いつまでに何個つくる」「この値段でケーキをつくる」「在庫を残さないようにつくる」などと誤った認識をもったばかりにその手段が「細菌がたくさんあっても決められた個数を出さなければいけない」「期限切れの材料を使ってでも、コストをさげなければならない」と違う手段を考えてしまうことになります。ケーキをつくる本来の目的は何だったのか?ケーキというのは誕生日であったり、何かの記念日であったり食べる人たちの幸せのひとコマに添えられるものだったりするわけです。ケーキをたべてるときのその笑顔のために作っているそんなことを考えると間違った手段は選択、つまり方向を見失うことはなくなるはずです。 目的を見失うと、手段ばかりを考えて、方向を見失う
2007年02月25日
-
中尾語録004 「目的意識をどれだけ持っているか?」によって、結果は大きく変わる
中尾語録4日目ですが、今日からようやく第一章に入ります!中尾語録004 「目的意識をどれだけ持っているか?」によって、結果は大きく変わる似たような話しで「目的なくして成果なし」というようなこともよく話します。これは教育に限ったことではありませんが何事も目的意識がなければただの作業になりそこに魂は入りません。以前、ホンダカーズ中央神奈川の相澤会長のお話をご紹介しましたが整備工にとって、ネジを締めるのが作業になってはいけないこれは、お客様の安全のために、ネジを締めているんだこういう目的意識を一つひとつにもっていればミスは起こらないそんな話しでした。私の本の中では、もうチョットくだけた事例でお話ししています。ご紹介しましょう。あなたは子どものころ、修学旅行や遠足で京都に行ったことありますか?地元の人は日光でも鎌倉でもかまいません。そのとき、お寺や仏像を見て楽しかったですか?ここで多くの人は「つまらなかった」と思います。では、大人になって行ったことはありますか?同じく楽しかったですか?すると今度はほとんどの人が「楽しかった」といいます。その違いってなんでしょう?それが、目的意識です。子どものときは、先生に決められたお寺や仏像を見せられていたからです。自らの意思で「何のために見るのか?」がなかったのでそこに楽しさは生まれません。大人になると、自分の意思で「アレが見たい」「歴史を感じたい」などとそれぞれに理由が生まれるからそこに行きます。これが目的意識です。これがあるから楽しいわけです。ですから、同じ京都に行くとしても目的もなく、行ったらつまらないですが目的があると、楽しい。ですから 「目的意識をどれだけ持っているか?」によって、結果は大きく変わる
2007年02月24日
-
中尾語録003 教育は最終的には1対1
中尾語録003 教育は最終的には1対1教育というのは、小学校のときから先生が1人で、生徒が多数という1 対 多 というのが基本というように無意識のうちに刷り込まれてきます。しかし、教壇に立つと分かりますが全員に対して満遍なく話しても全然伝わらないことに気づきます。一人ひとりをよく観察すると「この人眠そうだ」「この人、いま分かってないんじゃないか?」「このひとは集中力が落ちてるみたいだ」なんてことが見えてきます。それによって進め方を修正したりすることで一人ひとりが学べる環境ができてきます。それでも100%はカバーできません。だから終わってからのフォローが必要なのです。そのフォローの方法はまさに千差万別その人に合わせたコミュニケーションをとりその人の心にヒットするポイントをつく。やがてお互いに信頼関係ができてくると効果的な教育は1対1で行なうということが良くわかってきます。受ける方も、大勢の中の一人と思われるより自分のために教えてくれると思ったほうが何倍も吸収していくわけです。昨日の話につながりますが教える側と教えられる側がホンキになれるのが結局1対1ということです。家庭教師? のイメージを1対多の中でつくるそんな感じでしょうか?職場のOJTも同じでしょう。だから教育は最終的には1対1
2007年02月23日
-

中尾語録002 あなたが真剣にならなければ、新入社員も真剣にならない
中尾語録002 あなたが真剣にならなければ、新入社員も真剣にならない人は何かを学ぶときに、重要視する順番というものがあります。人それぞれだと思いますが私がこれまで社員教育を行なってきてわかってきたことは1 何のために学ぶか?2 誰に学ぶか?3 何を学ぶか?4 どのように学ぶのか?5 いつ学ぶか?6 どこで学ぶのか?で一番重要な、「何のため」というのは目的に当たるわけです。ですから、僕の本の中では一番最初にその部分のお話から入ります。そして意外に重要視されているのが「誰から学ぶのか」です。これはセミナーでも研修でもそうですが「講師が誰か」によってまったく集客力が違います。これは新人の育成にも同じことが言えます。つまり、育成担当者に「魅力」がなければならないわけです。「この人が言うなら間違いない」「この人から何か学びたい」そう思ってもらえなければ、学ぼうとはしてくれません。そのために一番重要なことが教える側が真剣に、ホンキにならなければならないということです。そのホンキ度に比例して、教えられる側のホンキ度も増していきます。ですから、 あなたが真剣にならなければ、新入社員も真剣にならない
2007年02月22日
-

中尾語録001 人によって起こった問題は人によって解決するしかない
昨日お話ししましたとおり、本日から、僕の本の中から一言ずつ中尾語録をご紹介します!!まえがきから順番に紹介していきます!中尾語録001 人によって起こった問題は、人によって解決するしかない職場でも、家庭でも何か問題があったり課題が生まれたとき、その多くの原因は「人」にあります。実際にいろいろな研修をしていると職場の課題解決の対策は???というと一番多いのはコミュニケーションによるものです。原因が人にあるならば、それは人にしか解決できません。システムやマニュアルを変えたって、人が変わらない限りは意味がないのです。たとえば、不二家さん・・・今回のような問題は、企業体質もあると思いますが根本的な問題は人にあります。これからいろんな企業が再生に向けて品質システムの見直しなどをやるとは思いますが、そんなものは今までだってあったわけです。不正をしてきた人自身が、意識を変えない限りは同じことは必ず起こります。飲酒運転が多いから罰則を厳しくしたって飲酒運転はなくなりません。一人ひとりの意識が変わらない限りは、罰則を倍にしようが3倍にしようがゼロにはならないでしょう。しかし、極論ですが、もしも一人ひとりの意識が本当に変われば罰則なんかなくたって、ゼロになります。僕の本で言えば新人の育成がうまくいかないのは育成する側にも問題があってその人が変わらなければ研修内容やプログラムを変えたって何にも変わらない・・・。そんな意識変革を起こしてほしいという願いをこめてこの一言を一番最初に書きました。人によって起こった問題は、人によって解決するしかない
2007年02月21日
-

中尾ゆうすけの本の中から、中尾語録を作りました
サイトをちょいといじくりました。追加したのはなんと「中尾語録」そんなに立派な格言めいたものではないですが僕の本に書いたことの中から「この一言がポイント」的なものを抜粋しました。数えてみたら、60個もありました。つまり・・・・厳選してません(笑)明日から、一つずつご紹介していこうと思います。本に書いたこととは違う、解説をつけますね!まぁ、中尾語録と言ってもいろんな人が似たようなこと言ってるし聞いたことある!というのもあるかもしれませんがパクリだと思わないでください^^それでは、乞うご期待!本の売り上げにつながるのも期待!(笑)
2007年02月20日
-

むすこの机を買いました
今年から、むすこが小学生になります。いろいろと買い揃えなきゃいけないものがあるのですがその中でもダントツに高いのが学習机(注:ウチの場合ですあくまで)で、今日届きました。これ僕のパソコンやら書棚やらもろもろ置いてある部屋だったのですがご覧の通りあけわたすことに・・・でも、子どもの学習机ぽくないでしょ?いつでも僕がのっとれるように(笑)大人っぽい渋いデザインの机にしました。むすこは、いかにも学習机っぽいのがよかったみたいですがそれだと長く使えないこともあり、僕でも使える=大人になるまで使えるものにしました。(高かったけど・・・)今の学習机って幅が100cmくらいしかないのね。住宅事情にあわせて小さくなったんでしょうね。それじゃぁ中学くらいになったら小さくなってしまう・・・。そのくせ奥行きはけっこうあるんですね。棚とかついてるし・・・。むすこを説得するのが大変でしたが・・・。僕の独断で幅の広いもの(130cm!!)で棚が前にないもの(書棚は別で一杯入るもの)を選びました。これでいつでものっとれます(笑)でも・・・デスクマットはポケモンです(笑)何年かしたら子どもにもパソコンが必要になるのでしょうね。ちなみに、僕のパソコンデスクや書棚は寝室に移動・・・。せまいっす(^_^;)
2007年02月19日
-
カフェがオープン
1/24の日記でお話ししたいとこのカフェのオープンが明日です。プレオープンということで、本日ランチをいただきました。JR中央線の日野駅近くのいなげやというスーパと花屋さんの間の道を入ってコインパーキングの隣です。むちゃむちゃ分かりにくいです(笑)店も小さいです。でも、味はバツグンにうまいです!ろうる(漢字が難しくて忘れた・・・汗;)という、ロールキャベツメインでロールケーキなんかもあります。ホームページは・・・まだないみたいです。
2007年02月18日
-
自分自身に原因がある
ピグマリオン効果の続きの話しですが、結局僕は、僕自身に期待もなかったし可能性も見出していなかったし人に好かれるわけがないと思っていたんです。それが自分自身にピグマリオン効果となって僕自身を僕自身が追い込んでいってしまった結果、人嫌い、対人恐怖症へとなってしまった本当の原因だと思います。これは今考えるとあらゆることに同じことが言えます。プレゼンがニガテだと思っている人はいつになってもニガテなままだし「だめだ今回の試験は受かるわけがない」と思ってると本当に落ちてしまうわけです。(実際にこれまでそれで何度も資格試験に落ちてます・・涙)何事もポジティブに考えればうまくいくって話しが一時期流行った(というのかな?)のももとをたどればこの原理じゃないかと思います。
2007年02月17日
-

ピグマリオン効果
昨日の続きです。ピグマリオン効果について本に書いたのですが、ご存じない方のために・・・これはアメリカのある心理学者の実験であるクラスで、テストをしたあと、先生に、こっちのグループは今後成績が伸びますと言いもう一つのグループはそれほどでも・・・ということを伝えるんです。しかし実はこのグループはランダムに分けただけ。そんなことは知らない、先生は無意識に優秀と言われたグループには期待を込めて接してしまいます。違うグループには期待をしていなかったわけです。結果的に、本当に成績がそのとおりになったという実験です。これは、期待を込めて接するとそれが伝わり期待にこたえるということです。逆に期待しなければ、そのとおりになってしまうのです。そんな話しを、新入社員に当てはめてもまったく同じだというお話しを書きました。 →この本話しを元に戻しましょう・・・。といいつつまたも 続く(笑)
2007年02月16日
-

自分をいかに受け入れるか?
昨日の続きです。結局こんな僕でも、結婚できたわけですよ。顔なんて関係ないんですよ・・・というと必ずしもそうではないかもしれませんし価値観は人それぞれ・・・ごにょごにょ(笑)僕の場合は自分自身が嫌いであったということが今思えば、一番の理由だったんじゃないかなと思うわけです。だって、自分が自分を好きでないのに他人がそんな自分を好きになんかなるわけがないですよ。自分を認められない人を他人が認めてくれるなんて、ないわけです。僕は自分の本の中で、ピグマリオン効果のお話しを書きました。続く・・・
2007年02月15日
-
マイナス思考
今だから昨日の日記のように、キズも受け入れることができていますが子どものころは、このキズがイヤでとても受け入れることはできませんでした。そして、何か人間関係でうまくいかないことがあると「自分は顔が悪いからいけないんだ」と、どんどん卑屈に考えるようになっていました。もちろん、子どものころは女の子にモテるわけもなくそれもすべて、顔のせいだと思っていました。当然一生独身なんだろうな・・・とマジで思っていましたね。でもね・・・・続く(笑)
2007年02月14日
-
対人恐怖症のトラウマ
ちょいとカゼをひいてしまいました。鼻水がダラダラです・・・(ToT)マスクは必須なのですがこの格好だと、みんなから「カゼ? 花粉?」とウザイくらい聞かれます。ほっといてくれ! といいたいのですがみんなが心配してくれているってことなんですよね。ありがたいですね。僕は子どものころ極度の人嫌いでした。理由はメルマガにも書いたのですが僕の顔には長さ6cm、幅2cmくらいのやけどのキズが2歳のときからあります。もちろん今もあります。僕にとってこれはトラウマだったのだと思うのですがこの傷について触れられる(聞かれる)ことが非常にイヤでした。でも・・・初めて会う人は必ず「そのキズどうしたの?」「かわいそう」子どものころはあらゆる人が初対面なわけです。それにうんざりして、人と会ったり話したりするのがイヤになりそのうちできなくなりました。今はもう、そんなこともなく克服しているわけですがそれでも時々「ほっといてくれ!」と思うことがあります。まだまだ修行が足りないんでしょう・・・。
2007年02月13日
-
サイトに情報追加しました。
サイトをビミョウに更新しました!http://www.hrt-i.comコラムを追加しました。
2007年02月12日
-
多くの人からの信頼とは?
最近のニュースで気になるのは、何といっても、踏み切りで女性を救った警察官の方の事故です。多くの方の祈りむなしく亡くなられてしまい、本当に残念でなりません。心よりご冥福を申し上げます。この事故以来、近隣の小学校から千羽鶴が届いたり、生前お世話になったたくさんの地域住民の方が、交番や事故現場を訪れているというのをニュースで見ました。世の中には、組織の末端で地位も名誉も人並みでも、溢れんばかりの人望を持った方がいます。今回の警察官の方は、本当に地域の方のためにご尽力されていたことがよくわかります。目立たない中で多くの人に認められる存在というのは、その人自身の生き方が、どれだけ多くの人に良い影響を与えて、生きてきた証を残すことができたか?ということだと思います。たとえば、私が育った小学校の近くにあった駄菓子屋さんのおばあちゃんは、地域の人や多くの子どもたちに愛されて、時にはケンカした子どもたちの仲裁に入ったり、人生における大切なことから、お金の使い方までたくさんのことを教えてくれました。1個10円の売り上げに心からの笑顔で「ありがとう」と言うその姿は幼いながらに私たちの心に何かを残してくれました。地位も名誉もお金もなかったおばあちゃんでしたが、亡くなったときに、ものすごくたくさんの方が葬儀にやってきました。 それを見て人は、人生の最後にその生き方が現れると、つくづく感じました。ご家族の方もさぞ誇りに思えたことでしょう。それは今回の警察官の方も同じだったと思います。時々、自分がもし死んでしまったら、どれだけの人が涙を流してくれるのだろう? と思うことがあります。そのたびに、自分は誰に何をどのように、貢献していけるのだろう?心を新たにします。
2007年02月11日
-
何マニア?(笑)
昨日の続きです。「意外にそういうの多いから気をつけたほうがいいよ」「他にもあるんですか?」「よくあるものだと・・・ この辺にある事務用品なら・・・ アロンアルファとか、 セロテープ、ホッチキス、 マジックなんかもそうだよ。 あと身近なものなら ウォークマンとか、サランラップとか、 万歩計も特定メーカーのものらしいよ」「え~・・・・普通に使ってますよ!!」「いんだよ。日常の中で通じるなら。 ただ、相手がそういうメーカーの人だったり、 公に出す文書などのときには気をつけないとダメだね」「変わりになんていうんですか?」「アロンアルファは、瞬間接着剤 セロテープはセロハンテープ ホッチキスはステープラー マジックはフェルトペン ウォークマンはヘッドホンステレオ サランラップはラップ 万歩計は歩度計だよ」 ※実際は調べながら言ってます^^「う~ん・・・難しいですね。 中尾さんはなんでこんなの良く知ってるんですか? 何マニアですか?」「論文の添削とか審査とかするとさぁ、 そういうのってチェックしなきゃ、外には出せないんだよ だから一時期かなり調べたことがあるよ」「なるほど、そうなんですね」とまぁ、結局は無しは落ち着きました^^そうそう、プリクラもそうですね。
2007年02月10日
-
口論のすえに・・・
先日ちょっとしたことで口論(ちょっとおおげさ)になりました。事務所にくる宅配業者さんはウチでは佐川急便さんを使っているんです。事務所の入り口はセキュリティー上、鍵がかかっているので扉の外に、「荷物あります」とか表示することで荷物があることを確認して、佐川急便さんが、事務所に電話したら荷物を出すというやりかたをしています。今回、その表示物を作りなおすことになったのですがあたらしく作ってくれたものにはこんな表示が・・・「宅急便あります。こちらへお電話ください! ****」シール紙に印刷したものを磁石のシートに貼って、結構手間のかかる作業です。しかし、それを見た僕は「宅急便って、クロネコヤマトさんのことだよ」「????」なんのことか分かっていないようです。「宅急便ってクロネコヤマトの商標で、 佐川急便ではその言葉は使わないんだよ」「え~そうなんですか? まぁ、別にいいんじゃないですかね?」「いやいや、作りなおしたほうがいいよ」「え~・・・だったらもっと早く言ってくださいよ」「いや、まさかそんな風に作ってるとは知らなかったし・・・」「だって、そんなの知りませんよ! みんな宅急便って言ってるしいいんじゃないですか?」僕は、宅急便=クロネコヤマト というのは常識かと思っていました。ところが周囲に聞いても誰も知りませんでした。なんか、僕が悪者みたいに・・・。「でもね、みんなが良くても、それを見るのは誰?」「佐川さんです」「佐川さんが、ライバル会社の名前をみたらどう思う?」「・・・」「いくら我々の大勢が許しても、対象となる一人が気分を悪くしたら それは、相手に対して失礼じゃない?」「・・・」「彼らは自社を誇りに働いてるわけだからさ、 違ういい方されたらいい気分はしないと思うよ」「う~ん・・・そうですね・・・」「たとえばさ、ビックカメラで『ポイントカードお持ちですか?』 って言われたときにヤマダ電機のポイントカードやヨドバシカメラの ポイントカードとか出したら気まずいじゃん!」「たしかに・・・」結局「宅急便」は、「宅配便」と一般名詞に置き換えられました。長くなるので、続く・・・。
2007年02月09日
-
コミュニケーションの影響力
昨日の続きですがどうしたら、内定者が自ら考え、行動できるか?その方法は、コミュニケーションの中からしか生まれません。一方通行ではなく、双方向コミュニケーションはキャッチボールこの大原則を忘れないことだと思います。僕がメールを送ると、返信が着ます。その内容によっては全体にフィードバックします。すると他の人も刺激を受けて、頑張ってくれます。その結果をまた報告してくれます。それに対しまたメールを送ります。深いコミュニケーションの中からしか、人の成長をサポートはできないと思います。
2007年02月08日
-
「やれ」ではやらない
昨日の続きですが、ではどうして僕のところにこうしてきちんと報告が来るようになるのか?何人かはできる人もいますが、ほとんどの人は初めからできるわけではありません。僕の場合は、キチンとできた人のメールをうまく使います。定期的に発信しているメルマガのようなものもやっていますがそのなかで、「先日一部の方から、レポート提出のご報告をいただきました。 計画的に進めているようで、とても安心いたしました」というようなことを伝えます。すると、次々に報告メールがきます。あくまでも、「報告せよ」とは言いません。報告をしてもらうことで、僕自身がどう思ったかを伝えただけです。報告していない人を責めるのではなく、報告した見本を伝えてあげることで、内定者は気づいていきます。そしてある程度報告がきたら「みなさんからご報告をいただきました。ありがとうございます。 テキストの○○ページにホウレンソウの重要性という項目が ありましたが、こうしてご報告いただけたということは、 みなさんが学んだことを充分にご理解いただけ、行動にまで うつせるようになったということだと思います。 社会人と学生ではいろいろと違いもあり、身につけることは たくさんあると思いますが、こうして一つひとつ成長している ことを心から嬉しく思います」まぁ、ちょっとしたリップサービスを入れつつ(笑)彼らに成長の自覚をさせてあげることがモチベーションをあげ、他にも学んだことで、できることはないか? と意欲もわいてくるわけです。
2007年02月07日
-
教育担当者の責任
先日、ある内定者からメールがきました。「通信制研修の課題を送付いたしました。今回は・・・を学び・・・」内定者研修に通信制の研修を行なう企業は多いと思いますがこうしてその都度報告がくるのは少ないそうです。たくさんの内定者からいちいち報告が来るのはうざい・・・じゃなかった(笑)大変でしょうが、大事なことは報告、連絡、相談・・・いわゆるホウレンソウをきちんとする習慣をいかにつけさせるか?これはとても重要です。なぜなら、多くの企業で行なっている内定者研修の中には、ほとんど必ず「ホウレンソウ」についての説明やその重要性が書かれている部分があります。とうぜんそこは勉強しているはずですが、こうして実践に移す人は、ごくわずかということです。僕は内定者研修は、テキストを送ってそのままにしているのはまったくの無意味で、お金のムダ使いだと思っています。学んだことをきちんと体現できるようにしていくのはテキストではなく、われわれ教育する側のやり方の問題です。
2007年02月06日
-
やっぱり心でしょ。
昨日の続きです。「心・技・体」の優先順位でなかなかまとまらないのですが原点に戻りました。そもそも、「人材育成において」という前提の話しでした。「どんなに教える技術があっても、教えようとする気持ちがなきゃ教えないでしょ?」「うーん・・・たしかに」「教えようとする気持ちがあっても教え方が分からなかったらダメじゃん?」「それも言える」「逆に学ぶ側からすれば、どんなに立派な教育でも、学ぶ姿勢がなきゃ、ザルに水でしょ?」「そうだな」「う~ん」「学ぶ姿勢があればさ、どんなにしょぼい教育でも、自分で学んでいくんじゃない?」「そうそう」「たしかに・・・」「だから教育には、まずやる気を起こさせること、その次に内容や教え方を考えるんじゃない?」「そうだな」「そうだな」ってなことで、やっぱり「心」が一番ということになりました。ちなみに「心」を押していたのが僕です^^
2007年02月05日
-
心・技・体の優先順位
先日こんな話題で盛り上がりました。人材育成において「心・技・体」の優先順位はどうなるか?意見は分かれました「やっぱ心でしょ」「なに言ってんだよ体だよ」「いーや技だ」「だって、どんなにすごいスキルがあっても、心がない人にはついていきたくないよ」「どんなに志が高くたって、5体満足じゃなきゃ何もできないでしょ」「それは、障がいを持っている人への差別じゃない? そんな人でも認められるのが技でしょ」「技を出すにも、それを制御してるのは心でしょ」「差別っていう意味でなくて、体が健康であることに感謝するって意味だよ」「なんだかんだ言っても技術があるから発展するんだよ」「極論だけど、技術ができて、核兵器ができて、それで幸せなの?」「核兵器ができてもそれを押す人さえいなければいいでしょ?」「それは極端だけど、技術のおかげでなんでもできるんじゃない?」「じゃぁさ、恋愛でいえばさ、やっぱ心でしょ?」「心はなくてもエッチはできるよ」「いやいや、どうせエッチするなら技が重要でしょ」「それに料理は愛情って言うじゃん!」「作る人がいるから食べられるんでしょ?」「心はなくてもレシピがしっかりしてればいいんじゃない?」などといろんな例えを出しつつ、なかなかまとまりません。続く・・。
2007年02月05日
-
2月になりましたが・・・
2月になってそろそろ花粉シーズンですね。でも今年はそんな話を全然耳にしません。暖冬だからでしょうか?そういえば、インフルエンザもちっとも耳にしませんね。温暖化のおかげ??(と言っていいのでしょうか??)えっと・・・今日は時間がないのであきらかに手抜きの日記ですね(笑)
2007年02月04日
-
働く理由2
続きです。管理職から経営層に行くと社会のために何ができるか?従業員のために何ができるか?そんなのが自己実現かもしれません。また、会社から独立し、自分のやりたいことができる人そんな人が自己実現者かも??でも、会社にいても役職につかなくても自分自身の意識次第で自己実現は充分可能です。ポストがない、上司が認めてくれないなどと嘆く前に、自分自身がどうなりたいのか?考えてみるといいかもしれませんね。
2007年02月03日
-
働く意味は人間の欲求から生まれる
昨日の続きです。「何のために働くの?」という質問に対し新人に近いほど「お金のため」という答えの割合が多いような気がします。まずは、生活をしていくことに一生懸命であることが、背景にあるのでしょう。学生時代の友人とのつながりもあるし、仲間はまだいます。所属したいという欲求は、働くことで解消する必要がないのでしょう。だから、早期の離職が多いのかもしれません。だんだん社会人経験が長くなると、離職率も減ってきます。家族を持ち、安定した生活を求めるのは安全欲求から生まれてるのでしょうね。辞めたら、その後の生活に不安があるからでしょう。また、それまでの人間関係を捨てにくくなり自分だけ逃げ出せないなどと思うのは所属欲求かもしれません。やがて、管理職などのポストを目指し、肩書きを求めたり、責任ある仕事をしたい権限を持って働きたいという世代になると承認欲求が生まれてくるころです。しかし、ここで終わる人がほとんどでしょう。権力に満足してる管理職は多いものです。その上から権力で動かされているのにね(笑)続く
2007年02月02日
-
働く理由
「なぜ働くのですか?」この質問に対しいろんな答えが返ってきます。「生きるためにはお金が必要だから」「食べるため」「家族を養うため」「将来に備えるため」「一人社会に取り残されたくない」「仲間がほしい」「社会に認められたい」「地位や名誉がほしい」「やりたいことをやりたい」「社会に貢献したい」すでにお気づきの方もいるかもしれませんね。そう、マズローの5段階欲求そのものです。 生存欲求 ↓ 安全欲求 ↓ 所属欲求 ↓ 承認欲求 ↓ 自己実現つまり、この質問をして、その答えを聞くことでその人が今どれぐらい、働くことに対して満足しているか?自己実現に近づいているか?そんなことが見えてきます。それから・・・時間がないので続く
2007年02月02日
-
愛妻の日
昨日1月31日は、「愛妻の日」だそうです。ターレス今井さんのメルマガで知りました!日本愛妻家協会というところがあるそうで、そこでは、愛妻の日に、「男の帰宅大作戦」というのを推奨しています。愛妻の日は早く帰宅して、午後8時、奥さんへ日ごろの感謝を「ありがとう」という言葉で伝えようというものです。この手の企画はこれまでも、同じ日、同じ時刻にみんなが一斉に打ち水をすると気温が下がるとか、一斉に消灯し、省エネなんていうのもありました。今回のものもなかなか面白い企画ですね。目に見える効果は分かりませんが、倦怠感の削減や、継続可能な夫婦環境をが狙えるとのことです。マイナーな企画なのでどこまで浸透するかわかりませんが年に1回でもこういう日があると家庭円満な家族がふえやがて、世の中全体が幸せになるかもしれませんね。
2007年02月01日
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 『君たちに明日はない』~垣根 涼介
- (2025-11-26 12:00:07)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?/…
- (2025-11-26 05:23:28)
-







