2007年06月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
中尾語録130 尊敬できる人のために働くということは、自分も尊敬される人になって、下から自分のために働いてもらえるような人材になるということ
昨日、めだかの孵化の話しをしましたがあわせて、カブトムシもどんどん孵化しています。今のところ見えているだけで15匹ぐらいは土の中からでてきてます。ところが・・・不思議なことにオスばかりメスはたった1匹しかいません。なんでしょうね??来年につながるでしょうか・・・??中尾語録130 尊敬できる人のために働くということは、自分も尊敬される人になって、下から自分のために働いてもらえるような人材になるということさて、今日の中尾語録は昨日の続きです。昨日は、上司のために働くというような話しをしましたがその真髄は自分自身が上司になったときに部下にそう思われるような人にならないといけないという意味でもあります。手前味噌で申し訳ないのですが、「中尾さんが言うことならなんでもやります」、「中尾さんのためにがんばります」、「中尾さんについていきます」、「中尾さんがいなくなったら会社を辞めます」こんなことを言ってくれる後輩や新入社員がこれまでも何人もいました。僕の場合部下というより、新人相手が本業です^^もちろん初めからそうだったわけではありません。いつのころからかと言えば、先日の中尾語録でもお話した、「何を教えるかよりも、誰が教えるかが重要」ということに気づいて、自分の行動を見直したころからです。 尊敬できる人のために働くということは、自分も尊敬される人になって、下から自分のために働いてもらえるような人材になるということ
2007年06月30日
-
中尾語録129 人は人の後姿に惹かれたときに自分から「この人についていこう」、「この人のために働こう」と思う
我が家で飼っているものでめだか がいます。このところ、産んだ卵がどんどん孵化しすごいことになっています。でも、やはり水槽の大きさに合わせて、結局は適正数に減ってしまいます。これは自然界でも同じなんでしょうね。中尾語録129 私自身、働く上で自分の給料(生活)のためとか、会社のため社会貢献のため・・・いろいろありますが、そのほかに「この上司のために働きたい」と思えることが重要だと思います。なぜなら、自分が働いた成果はそのまま、上司の成果でもあるからです。勘違いして欲しくないのは、これは上に向かってペコペコとするものではありません。世の中には上には良い顔をして、下には厳しい顔をする人もたくさんいますが、それでは誰もついてはきません。逆に「この上司のために働きたくない」となってしまったらどんなにモチベーションが高くてもやる気は失せてしまいます。この言葉の真髄は・・明日に続く(笑) 人は人の後姿に惹かれたときに自分から「この人についていこう」、「この人のために働こう」と思う
2007年06月29日
-
中尾語録128 指導する側と、指導される側の信頼関係がなければ、何を言ってもザルに水
何名かの方に、絵手紙をお送りしました!お申し込みありがとうございます!!無料で差し上げていますので、こちらからどうぞ!中尾語録128 指導する側と、指導される側の信頼関係がなければ、何を言ってもザルに水僕は、新入社員教育に携わった当初、自分の常識を世間の常識とし、常識のない新入社員に厳しく指導していました。しかし、言うことを聞く者も多いのですが、それは一時的なものばかり・・・。挙句の果てには、ウラで私の悪口、そんな状態でしたから信頼もなく、とても効果的な教育が出来るはずもありませんでした。そのときに気づいたことは、教育は何を教えるかの前に、誰が教えるかが重要なのではないか? ということです。それから僕は、新入社員が今何を考えているか?どう感じているか?何を求めているのか?何を知りたいのか?そんなことを感じながら臨機応変に指導内容から方法を変えていきました。すると次第に信頼関係ができ、それまでのようなことはなくなりました。 指導する側と、指導される側の信頼関係がなければ、何を言ってもザルに水
2007年06月28日
-

中尾語録127 レポートを読み進めることで嫌な思いをする方がいるだろう
僕の「新入社員劇プロ10倍活用法」のレポート内から中尾語録を拾っていますが、今日から第2章に入ります。中尾語録127 レポートを読み進めることで嫌な思いをする方がいるだろう僕は本もそうですし、このブログもそうですし自分のサイト内のコラムもそうですが・・・結構厳しいことを言ったりします。(でもそのウラには愛情を入れているつもりです)ですから、読んでいる多くの人にとって、耳の痛い話がたくさん出ます。かなり厳しいことも書くし、たくさんのダメだしと受け取れることも書きます。その結果、「中尾のヤツ生意気だ」「お前にウチの事情がわかってたまるか!」「そんなことは言われなくたって分かってる!」「そんなの理想だ!」「オレのやり方を否定する気か!」そう感じる人もいると思います。しかし、それでもあえて書きます。書くことで私が嫌われたり、避けられても構いません。その覚悟で書いてます。なぜなら、私は自分が好かれたいというより読んでる皆さんが何かに気づいてほしいというのが本心です。気に入られたいだけなら、もっと違うことを書きます。でもそれでは誰にも、何の気づきも生まれません。もしかしたらお怒りをかうかもしれませんが、それ以上に「もしかして私のやってきたことは、新入社員(や部下)のモチベーションを落としているのかもしれない」「私って何にも分かってなかったなぁ」「明日から部下への接し方を考え直してみよう」「私ってもしかして、信頼されてないかも・・・早速明日からこうしてみよう」などと感じて、決意をしてくれる人がいれば、嬉しいです。 レポートを読み進めることで嫌な思いをする方がいるだろう
2007年06月27日
-
中尾語録127 何を教えるかの前に、誰が教えるかが重要
ギリギリなってしまいましたが・・・ 生きているといろんなことが起きると思います。 つらいことや悲しいこと、 時には人のせいにしたり、八つ当たりしたり・・・ でも、必ずそこから脱出する突破口はあると思います。 しかしそれは、けして 偶然じゃない・・・。 すべての「結果」は引き寄せられているとしたら・・・ 自分自身で引き寄せられるとしたら・・・ そんな方法、知りたくないでしょうか?? すべての「結果」は引き寄せられている ~ 運命を決める「牽引の法則」~ 澤谷 鑛 著 (総合法令) http://www.kou-sawatani.com/hon.html 本日までキャンペーン中だそうです。 急がないと間にあわない! あっ・・・ 鏡の法則の野口さんも推薦しています!中尾語録126 何を教えるかの前に、誰が教えるかが重要何かを教わるということの大前提として人は人から教わると言うことがあります。「いや、本から教わる」という人もいると思いますがその本を書いているのは「人」です。たとえば、どんなにすごいノウハウでも「この人の言うことは聞きたくない」と思われたら、その人は何も学び取ってはくれません。学校の授業でも、先生が嫌いだから、その教科が嫌いになったという人は多いはずです。もともとその教科が悪いのではなく人なんです。もしも、教える立場であれば「この人から教わりたい」という人にならなければなりません。つまり、自分は絶対的な知識があるとか圧倒的なノウハウを持っているというだけではいけないということです。本も同じで同じテーマの本でもより信頼できる人の本を読むものです。 何を教えるかの前に、誰が教えるかが重要
2007年06月26日
-

中尾語録125 役に立たないのではなくて、役に立てなかっただけ
最強のマーケティングキーワード集が出ます!『Value Seeds100 ワーキングマザーが見つけたバリューのタネ 』こんな方におすすめです。----------------------------------------------・企画書をさらさらと書きたい・ビジネスのヒントがほしい・アイデアのタネがほしい・発想の仕方が知りたい・事象を端的にまとめたキーワードがほしい・主婦が見つけたバリューを知りたい・何気ない日常に価値を見つけたい----------------------------------------------ぜひキャンペーン(6/29~7/8)期間内にどうぞ先着プレゼント(300名)がほしい方は急いで!中尾語録125 役に立たないのではなくて、役に立てなかっただけ世の中に役に立たない本というのはない。そういうと「そんなことはない、役に立たなかった本はこれまでにたくさんあった」そういう方もいるでしょう。でもそれは本当でしょうか? 私はこう思います。役に立てるには目的を明確にして、その視点をずらさないこと。そして読みながら自分の日常の中に置き換えたらどうなるか?または自分だったらどうするか? というように読んでいくと、何かしらの気づきがあるはず。この気づきがなければ役立てることはできません。逆に言えば、どんなにすごい内容の本でも気づきがなければ「役に立てられない」のです「役に立たない」と言うことは「気づくだけの応用力がない」ということです。ですから正しくは「役立たない」ではなく、「役立てられない」なんです。 役に立たないのではなくて、役に立てなかっただけ
2007年06月25日
-
中尾語録124 ニートでも、自分自身でモチベーションをコントロールできれば、社会に出ようという気になる
成功したいと誰もが思っています。でもナカナカ成功する人は少ないですね。成功というのも一人ひとり違うと思いますがちょっと想像してみて下さい。たった一日のセミナーで成幸を確信できるとしたら・・。そのセミナー参加者の声です。 「今までは、成功とは、根性や気合だけがあれば、 手にできるものだと信じていました。しかし、この セミナーに参加して、心だけでなくからだや魂も 必要だということに気がつきました。 やっと自分の成幸を確信できました」 気になりませんか? そんな方はこちらへ! 中尾語録124 ニートでも、自分自身でモチベーションをコントロールできれば、社会に出ようという気になるニートにもいろいろなタイプがあると思いますがモチベーションが低いだけならモチベーションをあげればいいだけです。その方法は2種類周囲の働きかけで上げる方法もう一つは自分自身で上げる方法でも、大前提として忘れていけないことは他人と過去は変えられない、変えられるのは自分と未来ということ。だからニートの方が社会に出るために一番必用で、唯一の方法が自分自身でモチベーションコントロールすることなんでしょうね。 ニートでも、自分自身でモチベーションをコントロールできれば、社会に出ようという気になる
2007年06月24日
-
中尾語録123 コミュニケーション力が上がれば夫婦関係親子関係、ご近所付き合い、嫁姑問題・・・様々な日常の課題がクリアになる
顧客バリューアドバイザーの前田めぐるさんが書いた最強のマーケティングキーワード集が出ました。『Value Seeds100 ワーキングマザーが見つけたバリューのタネ』(前田めぐる著 カナリア書房刊 ¥1,260)こんな方におすすめです。----------------------------------------------・企画書をさらさらと書きたい・ビジネスのヒントがほしい・アイデアのタネがほしい・発想の仕方が知りたい・事象を端的にまとめたキーワードがほしい・主婦が見つけたバリューを知りたい・何気ない日常に価値を見つけたい----------------------------------------------めくるだけで企画脳が刺激され、企画書づくりがスイスイ進むことうけあいです。6月29日(金)~7月8日(日)に、購入された方は、前田さんのHPで応募すると、ハートのタネがプレゼントされるそうです。先着300名なので、急いでくださいね。中尾語録123 コミュニケーション力が上がれば夫婦関係親子関係、ご近所付き合い、嫁姑問題・・・様々な日常の課題がクリアになる研修をやっている中で「職場の課題は何ですか?」と聞くと、一番多いのが「職場のコミュニケーションが悪いこと」です。そのほかにも様々な課題はありますが「その課題を克服するために何が必要ですか?」と聞くとやっぱり「コミュニケーションの改善」となるんです。つまり、ほとんどの課題は「コミュニケーションの改善」で解決してしまうんです。これは会社における課題だけでなく、家庭内の課題も同じです。夫婦仲の問題もその原因のほとんどはコミュニケーション不足です。親子の問題も、嫁姑、ご近所付き合い・・・みんな同じです。 コミュニケーション力が上がれば夫婦関係親子関係、ご近所付き合い、嫁姑問題・・・様々な日常の課題がクリアになる
2007年06月23日
-

中尾語録122 コミュニケーション、自己啓発、モチベーションは、あらゆる職種や業種で必要な力
そうそう、サイトの更新をしましたと先日お伝えしましたが趣味のページへリンクも追加しました。前にチラリとお話ししましたが、最近、絵手紙をはじめました。前からやりたいなぁと思いつつなかなか一歩を踏み出せなかったのですが元まぐまぐのカリスマ編集者 ←勝手にネーミングA澤さまに背中を押され、始めました。まだまだヘタですが、それでもよければどなたかほしい方に無料でお送りします!サイトにはシステム上、50円と入れていますがお金は要りません!もらってくださる方はこちらから!そのうち、上達したら、切手代+材料代くらいもらえるかなぁ・・・。中尾語録122 コミュニケーション、自己啓発、モチベーションは、あらゆる職種や業種で必要な力ロバートカッツの理論という理論はご存知でしょうか人材育成をされている方や、それに係る方ならご存知だと思います。50年以上前からある考え方でその理論は普遍的でMBAの根幹の考え方にもなっているそうです。管理者に必用なスキルは大きく3つの分野があります。それが ・コンセプチュアルスキル ・ヒューマンスキル ・テクニカルスキルです。で、ややこしい説明はさておいて(笑)コンセプチュアルスキルは、管理階層が上がるにつれて必要度が高くなりテクニカルスキルは管理階層が上がるにつれて必要度が少なくなるんです。そしてヒューマンスキルというのは管理階層に関係なく総ての人に変わらす必要な能力と定義されています。そのヒューマンスキルというのが、いわゆるコミュニケーションスキルに代表されるものです。それを高めるの支えているのが自己啓発意欲とモチベーションなのです。 コミュニケーション、自己啓発、モチベーションは、あらゆる職種や業種で必要な力
2007年06月22日
-
中尾語録121 魅力や信頼で人は動く
先日コーチング研修を行ないました。対象は、管理職手前ぐらいの方で、部下もいるような、働き盛りの方たちです。で、そのアンケートを見ると「ティーチングとコーチングの違いが分かりました」「相手に考えさせるという手法が新鮮でした」「コーチングというものを初めて知りました」ん~???ビジネスにおいていうならコーチングって90年代初めにはアメリカから日本に入ってきたのですが今ごろ「初めて知った」って・・・(-_-;)ホントに部下がいて、管理職を目指そうと思ってる・・・?まぁ、そういう人がいるからコーチング研修があるんですが、もうちょっと勉強しようよ・・・。中尾語録121 魅力や信頼で人は動く昨日は、権力では人は動かないというお話しをしました。では、何で人は動くのか?答えは簡単^^魅力や信頼です。企業の中でも、新入社員のころは素直だったのに、なれてくるとまったく扱いに困るようになったということはよくある話です。家庭でもあるでしょう。逆にお子さんが大きくなっても、新入社員がベテランになっても、素直でいられる人もいます。この差はいったい何だと思いますか?じつはこの理由はまったく同じなのです。それはお互いの信頼関係です。子どもが小さいときは、親なしでは生きられないですから、言うことを聞くしかないわけです。つまり企業でたとえると、上司の権力に逆らえずとりあえず動くみたいな感じです。これは昨日お話しした権力です。ところが・・・信頼や魅力がある親の言うことは大きくなっても聞くものです。新入社員も同じです。子どもは親の背中をみて育つと言いますが、それは大きくなってきたときにわかることで現実は、幼いころは特に顔色をみて育つことがほとんどです。あなたの背中を見てもらうためには、信頼、魅力というものは欠かせません。社会人も同じです。 魅力や信頼で人は動く
2007年06月21日
-
中尾語録120 自立しはじめるともう、権力は通用しない
サイトを更新しました!人材育成コラムを更新しました。今回は、あまり大きな話題にはなりませんでしたが良識ある大人としての行動を考えさせられるニュースから話題をいただきました。中尾語録120 自立し始めるともう、権力は通用しない。人を動かす原動力には大きく二つあります。一つが権力もう一つが魅力です。権力というのは、立場における圧倒的な力により人を動かすものです。たとえば、社長に何か言われれば、新入社員はなかなか意見はできません。様々な不祥事がこのところ報道されますが、上司から指示を出されれば、断れない部下はたくさんいます。このような、悪いイメージだけでなく通常の業務命令などもこれになります。また、家庭でいえば、小さい子どもと親は、圧倒的な権力の差があります。学校で言えば、先生と生徒の関係も、権力差はあります。相手が動くための理由がそこにはあります。しかし、そのポジショニングが崩れたときたとえば、上司が移動したときや定年になったときもしくは降格したとき子どもが成長して自立したとき相手はそれまでのようには動いてくれません。動く理由がないからです。人事権のない元上司は、単なる他部門の人であったり自立した社会人であれば、親の言うことは絶対ではなくなるのです。そのとき、どう、人を動かすのか?それがもう一つの魅力というわけです。 自立しはじめるともう、権力は通用しない。
2007年06月20日
-
中尾語録119 現状の常識レベルを社会人の常識レベルに近づける
先日、ある研修の中で(僕が講師ではないのですが)企業イメージの話しがあった際に当然最近のコンプライアンスの問題が話題として出るわけです。某自動車会社さん某洋菓子メーカーさん某IT企業さん某生命保険会社さん ・ ・ ・すると研修アンケートの中に「家族が●●生命保険に勤めているので、聞いていてイヤでした」と書かれていました。たしかに・・・不祥事を起こした企業とはいえ、社員全員が悪いわけでもないし一生懸命まじめに働いている人もたくさんいるわけです。ごく一部の方のためにあたかもそこで働く総ての人が悪いような言い方は軽率としか言いようがありません。そういえば・・・僕もこのブログでかなり問題点を指摘してきたなぁ・・・一応そういうところを配慮して悪いことをしたことを指摘はしましたが基本的には、罪を憎んで人を憎まずをモットーにしたつもりです。でも、もしも、不快に感じる人がいたのならばこの場でお詫びいたします。中尾語録119 現状の常識レベルを社会人の常識レベルに近づける昨日お話しましたとおり、常識レベルは経験と学習を繰り返さなければ上がりません。たとえば以前、学生のときに起業して、5年経つという社会人に会いました。年齢は20代後半です。学生同士で起業し、その中でしか働いていない方でした。もちろんキチンとした教育システムもないのですがそれでも、IT技術を売りに頑張っているようです。最初に名刺交換をしました。しかし・・・名刺の受け渡し、扱い方・・・これは新入社員研修で通常学ぶのですが、彼らは自分たちで会社を起し、通常積んでくるであろう、様々な経験が不足していたのでしょう。まったくできていませんでした。それでも、名刺には、株式会社○○ 代表取締役 などと立派な肩書きがあります。そして言葉遣いもいわゆるタメグチでした。こっちは敬語、相手はタメグチ・・・・。通常20代も後半になれば、これぐらいはできて当たり前のはずです。それが学生の常識の中でしか育たなければ、どんなに立派な肩書きでも中身は学生なのです。ちなみに、ある高校の教頭先生と名刺交換をしたこともあります。官民交流ということで、ある企業に期間限定できていたんです。50を過ぎた方でしたが名刺交換がきちんとできない・・・やはり、経験をしていないことはどんなに歳を重ねても積み重なっていかないわけです。 現状の常識レベルを社会人の常識レベルに近づける
2007年06月19日
-
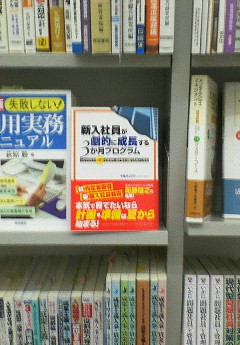
中尾語録118 本は読みながら、自分の仕事の中に置き換えながら読むことが重要
久しぶりに、八重洲ブックセンターに行ってきました。さっそく2Fのビジネス書コーナーの人事関係の棚に行くと・・・ありましたよ!!僕の本が!!注)この写真は去年発売当時の丸善さんの写真です。発売から1年になるのにいまだに棚に面置き(しかも目線の高さ)されていました!コツコツと出ていると思っていいんでしょうか?それとも営業の方の努力でしょうか?いずれにしてもありがとうございます!中尾語録118 本は読みながら、自分の仕事の中に置き換えながら読むことが重要僕は自分の仕事とはまったく違うジャンルの本を読んだりします。たとえば、こんな本ちなみにこちらの本、現在キャンペーン中です!http://www.kikidasu.jp/point僕自身はお店をやっているわけではないのですがこれを自分の仕事に置き換えていくといろんなことに応用できるんです。発想法の技術の一つに強制発想法←すいません名前はテキトーです(笑)たとえば、「今の課題と時計と関連付けると何が考えられるか?」というように、まったく関係ないものをぶつけて発想を新たにすると、今までに考えたこともない、アイディアが無理やりにでも(笑)生まれてくるわけです。それと同じで、お店をやっていない僕が「お店の売り上げを上げるという視点で人材育成を考えたら何ができるか?」「人材育成と顧客の視点を関連付けるとどんなことができるか?」こんな風に本を読むとジャンル違いの本も、必ず役に立つし、新しい発想やアイディアが生まれるものです。 本は読みながら、自分の仕事の中に置き換えながら読むことが重要
2007年06月18日
-

中尾語録117 あなたの応用力しだいで新入社員の成長が決まる
先日ある研修の過去の受講者から受講後の現状をアンケートで調査しました。300人くらいに送って75%の回収率ですから、任意のアンケートでは高いほうでしょう。すると、研修内容のアウトプットとして自分で書き上げた内容を覚えている人は60%いました。その中で研修が終わっても自分なりに内容を見直している人というのが60%つまり全体の36%は研修後もきちんと自分の行動に移しているということです。これはおそらく一般的にみたら、かなりの高さだと思います。そしてもう別の質問で、職場で実践しているか?という問いには同じように60%が活用し、そのうち60%はやり方を見直したりいました。これらをクロス集計してみると、ほとんどが一致しました。つまり、研修後に行動しなければ、必ず忘れるものである。ということです。さらにこんな質問をしました。「職場で成果につながりましたか?」この答えもなんと60%成果の大小はありますが、これもクロス集計すると同じ人が多いんです。つまり、研修はきちんと実践すれば成果につながるということが分かりました。何が言いたいのかというと、研修の見直しポイントは内容ではなく、いかに実践しようという気にさせるか? ということなんです。今日も前置きが長くなってしまいました・・・。中尾語録117 あなたの応用力しだいで新入社員の成長が決まるこれは僕の本を読んだ人へのメッセージです。何度も言いますが、本はあくまでも一例であり読んだ人が自分の落としこんで行ってはじめて役に立ちます。本は答えが書いてあるのではなく、参考書なんです。つまり、僕の本を読んだ方しだいで、新人の育成に大きく差が出るということなんです。 あなたの応用力しだいで新入社員の成長が決まる
2007年06月17日
-

中尾語録116 まずは人間的な力を身に付けさせ、後は自分で学習していくような人材にする
職場に保険屋さんが出入りしているところって多いと思いますがいかがでしょう?しかも担当の人って結構入れ替わりが早い!みんなすぐやめちゃうんでしょうか?そのたびに挨拶に来て同じような勧誘を受けるのですがあるとき、とても手ごわい・・・いや説得がうまい保険やさんがきて断れず契約する人続出というときがありました。たしかに保険というのは見直したほうがメリットがある場合は結構あるんです。特に多くの人は保険の知識がない・・・。そして多くの保険やさんはノルマのためにとにかく売りつけているから本当にお客さんのために設計してきたものはかなりの確立で、メリットがあるんです。職場の多くが「まいったなぁ」とか言いながら契約する中「中尾さんの入っている保険は、見直すところがないですね」と言わしめた僕ってすごい??中尾語録116 まずは人間的な力を身に付けさせ、後は自分で学習していくような人材にする僕は本の中で、教育は1対1というお話をしました。そうは言っても、社員教育において、講師1人に、受講者20人ということはごく普通のことです。特に新入社員に限って言えば、昨今の就職事情を考えるともっと多くなるのかもしれません。ではどうやって1対1になるのか?まずは、人間力をつけさせること。すると自分で学習するようになるので、教える側の負担(という言い方はよくないのですが)が減るすると一人ひとりに向き合う時間が作れるようになります。困ったときにいかにフォローできるか?そんなときに相手も心を開くからたとえ短時間でも深い納得感がうまれたりします。大勢に教えているときよりもあきらかに吸収力がちがうのです。 まずは人間的な力を身に付けさせ、後は自分で学習していくような人材にする
2007年06月16日
-
中尾語録115 仕事のやりかたをドンドン教えても、吸収する力や意識がなければ、どんなに詰め込んでも意味がない
今度ウチの職場の女性がテレビに出ることになりました。しかもナマ番組!!企業として働く女性への支援についての特集に、ゲストとして呼ばれたわけです。僕も人材育成か何かの特集番組に、出して欲しいなぁ・・・。中尾語録115 仕事のやりかたをドンドン教えても、吸収する力や意識がなければ、どんなに詰め込んでも意味がない俗に言う ザルに水、 暖簾に腕押しってやつです。本人に向上心や、やる気、モチベーション・・・これがなければ、どんなにに優秀な人が教えても何も吸収されず意味がありません。人にモノを教えることがうまい人というのは優秀な人ではなく人をその気にさせられる人なんですね。本気にさせてから教える。この順番が大事です。 仕事のやりかたをドンドン教えても、吸収する力や意識がなければ、どんなに詰め込んでも意味がない
2007年06月15日
-
中尾語録114 私のやり方が絶対ではなく、うまくできた事例の一つにしか過ぎない
金曜~土曜に子どもの学校公開がありました。最近は授業参観というのはないそうですね。全国同じでしょうか?僕らの子どものころは、決まった授業に親が来て後ろで見ていたものです。今は2日間学校を公開し、どの授業でも、休み時間でも、給食でも自由に見れるようになってるんですね。とはいえ、働くビジネスマンとしてはやはり平日は厳しい・・・。で、土曜に行こうと思ったら、急遽休日出勤!むすこよ、スマン。中尾語録114 私のやり方が絶対ではなく、うまくできた事例の一つにしか過ぎないうまくいく方法やノウハウはいくらでもあります。一つのテーマで、いろんな本読むと良く分かります。書いている人それぞれで違うやり方が書かれている。だから、きっと人それぞれに合ったオリジナルな手法があるのだと思います。そのヒントは本にあります。本はあくまでヒントでしょう。そこからそれが生きるか生きないか?それは本の中でいかにうまく誘導できるか?また、読んだ人の応用力にかかわるわけです。あえて言うなら著者は、自分のノウハウをカンペキとして語るだけでなく読者に応用できるように書いて欲しいところです。でも、多くの読者は、自分で考えないで、必殺のノウハウを探しています。版元もそのニーズに合わせるように必殺のノウハウのように見せて売ります。こんなことを書いたら怒られそうだな・・・。結局その本を読んだ読者は、「つかえない」と言います。出来ない理由を探すのはみんな同じですからね。 私のやり方が絶対ではなく、うまくできた事例の一つにしか過ぎない
2007年06月14日
-
中尾語録113 本を読んで「違う」と思ったことは、自分の価値観にあわせて変えてかまわない
先日、研修中に受講者が泡を吹いて倒れてしまいました。その場にいたわけではないのですが話を聞いて正直「またか・・・」と思いました。研修というのはなれない人にとってとても大きなプレッシャーがかかったり過度の緊張感、そして日常の疲労閉所恐怖症などの持病・・・いろんな要素があってときどきこのようなことは起こります。世の中に講師といわれる人はたくさんいますがこういうことを知らずにスパルタ式の講義などが行われるとこのようなことが起こり知らない講師ほどオタオタしてしまいます。僕が講師をやるようなときは必ず「今日の体調はどうですか?」という話をします。遠慮される方も多いのですが本当に具合の悪い方は手を上げるんですよね。それだけで安心感になるんです。すると、倒れる人がでなくなるんです^^前置きが長くなりました・・・。中尾語録113 本を読んで「違う」と思ったことは、自分の価値観にあわせて変えてかまわない昨日の話と同じですが手段はいろいろあります。それは考え方も一緒。たとえば、京都に旅行に行きたいという人が バスでいく 新幹線で行く 車で行くいろんな手段があります。その選択基準が人それぞれの考え方で 安くしたいからバス 時間がもったいないから新幹線 仲間でワイワイしたいから車ほとんどの本は何か目的に合わせて書かれているものです。その目的に惚れて本を買う人も多いでしょう。でもそこに書かれている内容は著者の考えや経験自分に合わないこともあるわけです。そのときは目的をずらさないように自分流にアレンジしちゃえばいいんです。そのほうが後悔もないし。 本を読んで「違う」と思ったことは、自分の価値観にあわせて変えてかまわない
2007年06月13日
-
中尾語録112 思いが一緒ならば、きっと共感される
久しぶりに、寝ていたら、足がつりました。いやぁ、夜中に一人悶絶し、誰にも助けてもらえないこの状況って結構ツライですね。 何年ぶりでしょう・・・。ん?? 話はそれますが、「久しぶり」というのは、「足がつった」に対してかかっているわけでけして「寝る」というところにかかっているわけじゃないですよ(笑)中尾語録112 思いが一緒ならば、きっと共感される人間の価値観はイロイロですから、時には「それは違うだろ?」と思うこともあるかもしれません。でもそれは手段の違いであって、目的は変わらないことも多々あるはずです。目的や、やろうとしたいことは同じ手段はいくらでもあるのですが考え方が違うと言って拒絶していたら何の得もありません。人と合わないことなどがあったり本を読んで「違うな」と感じたときは相手の本質を見抜いていくと思いは一緒かもしれません。それに気づくと、不思議に共感できるんです。 思いが一緒ならば、きっと共感される
2007年06月12日
-
中尾語録111 何もしないで本を読むだけでは、目的は達成できない
研修会社の取締役と話をしててまさにそのとおりと思ったのが・・・社員教育に500万かけて、全社員のモチベーションを上げるのと500万かけて一人採用するのとどちらが効果があるか?当然、研修である。ただしこれには条件が・・・研修内容がよいこと。たとえば、従業員100名に500万かけて研修を入れたら相当なことができます。10人なら、もっと凄いことができます。たとえ1000人でも、全員とは言わなくてもかなりの人のモチベーションを上げられるでしょう。同じ金額を出しても人を1人雇うとそのほかに雇用保険やらなんやらで年収500万でももっと会社の負担は大きく、仮に福利厚生や教育費通勤費などまで入れて1000万かかるとしたら、その1人がそれ以上のパフォーマンスを出さなければペイできません・・・。しかも、毎年・・・。でもたくさんの従業員が研修で上がったモチベーションで能力を発揮すれば500万はスグに元が取れます。今回は本文が短いので、前振りが長くなってしまいました・・・。中尾語録111 何もしないで本を読むだけでは、目的は達成できないこれまでの中尾語録で繰り返しお伝えしてきましたが本は読んでも役立たない。行動して初めて役に立つ。この一言に尽きます。当たり前すぎて、これ以上話が続きません(笑) 何もしないで本を読むだけでは、目的は達成できない
2007年06月11日
-
中尾語録110 応用力のある人ほど、本の価格の何倍もの価値に変えていくことができる
車検が近いので、ディーラーに見積もりに行きました。「どこか調子悪いところありますか?」「エンジン始動時になんかキュルキュルキュル・・・っていう音がします」「ベルト関係の可能性がありますので見てみます」 ・ ・ ・「ベルトが少し緩んでるようでした」「そうですか」「応急処置はしたので、大丈夫だと思いますが、車検のときにもう一度きちんとやりますので」「わかりました」で・・・全然なおってないんですけど・・・・(ーー;)中尾語録110 応用力のある人ほど、本の価格の何倍もの価値に変えていくことができる本って1000円~1500円ぐらいします。最近はネットで買う人も多く、送料や代引き手数料まで入れると1500円~2000円するわけです。けして安い値段ではないですよね。でも、それを安い買い物とするかムダ金にするかは本の内容も、もちろん必要かもしれませんがいかに自分に置き換えて身近なノウハウにできるか?だと思います。本に書いてあるのは、必殺のノウハウでもなければ誰でもうまくいく魔法の杖でもありません。あくまでも著者の経験や研究に基づく主観であるということです。それを自分の身近なものに応用してこそ活きるわけで100%本へ依存する人ほど、ムダ金になっていきます。応用力のある人は本の代金の何倍もの価値を自分自身で作っていきます。 応用力のある人ほど、本の価格の何倍もの価値に変えていくことができる
2007年06月10日
-
中尾語録109 本は所詮道具。道具である以上それが良いか悪いかではなくそれを使いこなすか、こなせないかで、道具の価値もあなた自身の価値も上がったり失ったりする
我が家の近所は坂が多い(>_<)自転車だと「きついなぁ」と思うときは押して上がるのですがその横を、腰の曲がったおじいちゃんが電動自転車で、スィ~と追い越していくのを見ると「いいなぁ~」と思わず買いそうです。中尾語録109 本は所詮道具。道具である以上、それが良いか悪いかではなく、それを使いこなすか、こなせないかで、道具の価値も、あなた自身の価値も上がったり失ったりする本は所詮道具です。本自身が何かをしてくれるわけでも何かを持ってきてくれるわけでもあなたの変わりに働いてくれるわけでもありません。パソコンも道具です。パソコン自身が勝手にメールを打ったり何かをくれたりしません。ただし、使いこなすことができればメールも打てるし、物も買えるし、売ることもできる・・・無限の可能性があります。でも、使いこなせなければただの鉄クズでしかありません。それと一緒で、実は「本の内容が役立つのか?」ではなく「本の内容を役立てられるのか?」なのです。主役は、モノではなく、人なんです!本は所詮道具です。使いこなせば無限の可能性がありますが使いこなさなければ、ただの紙クズです。本を読んで「使えない」と言う人は「あなたの応用力が足りないんでしょ?」っていう意味です。 本は所詮道具。道具である以上、それが良いか悪いかではなく、それを使いこなすか、こなせないかで、道具の価値も、あなた自身の価値も上がったり失ったりする
2007年06月09日
-

中尾語録108 あなたの役割・使命は何ですか?
10年前にかけた養老保険がもうすぐ満期を迎え結構な額が戻ってくるんですが・・・税金が19万だとか・・・・増えた分がそうとう消えていくんですけど・・・(涙)中尾語録108 あなたの役割・使命は何ですか?仕事をする以上、何らかの役割・・・使命ともいうべきものがあるはずです。それを知らずして、仕事は成り立たないはずです。ところが・・・「あなたの役割は何ですか?」と聞いてもなかなか答えられなかったりとんちんかんなことを答えたりそんな人はすごくたくさんいます。僕の本をそんな人が読んでもおそらく何にも成果にはつながりません。それは僕の本のレベルが高いとかじゃなくて役割の見えていない人には何をやらせても目的に達することはなかなかないからです。自分で言うのもなんですが、僕の本は「これはいい話だ」というのがたくさんあります。それを読んで、感心していてはいけないということです。内容に感心しても、その人の所にいる新入社員は成長しません。ほかにも、僕の失敗談を読んで「中尾はバカだなぁ、あっはっは!」と笑っていても誰も成長はしません。そのあとに「自分だったらこうするだろうな」これが必要なのです。その基準になるのが、自分の使命や役割なんです。だから、本の一番最初に問いました。 あなたの役割・使命は何ですか?
2007年06月08日
-

中尾語録107 結果を決めるめるのは本ではなく、内容をヒントに行動に移すあなたしだい
最近新しい趣味を・・・と、いつだったかお話ししましたが・・・ちょっと年寄りくさいかもしれませんが絵手紙を始めました。まだまだ始めたばかりで恥ずかしいぐらいヘタクソですがそのヘタなのを含めて、書きたまったころにご披露しますね。中尾語録107 結果を決めるめるのは本ではなく、内容をヒントに行動に移すあなたしだい書店に行くと「1億円稼ぐ!」みたいなタイトルの本が山のようにあります。それを読んだからといって、いきなり収入が1億円になるわけではありません。みんなタイトルに騙されすぎです(笑)でも、それをヒントに行動した人の中には、1億円になる人もいるかもしれません。そういう意味では、タイトルはけしてウソではないと思います。ただし、その違いと言うのは行動したか、しないか?それを続けたか、続けないか?自分なりの工夫や改善を入れたか、入れないか?本に書かれているのはあくまでも著者がうまくいった一例に過ぎません。うまくいくための必殺技だと思い込んでいる人は間違いです。その背景にある考え方や、指針みたいなものを読み取って自分に置き換えて初めて、そのノウハウが生きてくるし独自のノウハウとして根付いていくんです。そうでなければ単なるモノマネで失敗するだけです。僕の本も、3か月で劇的に成長するなどと書いていますがあくまで一例です。僕の本は考え方の本です。必殺のノウハウではありません。もちろんピッタリあう人もいますがほとんどは自分に落とし込まないといけません。場合によっては3か月でなく4か月、5か月かもしれません。逆に、2ヶ月かも知れないし、1ヶ月かもしれない。でもそれは・・・ 結果を決めるめるのは本ではなく、内容をヒントに行動に移すあなたしだい
2007年06月07日
-

中尾語録106 本というものは、読む人の視点で、どのようにでも変化していく
最近クールビズになったので、半そでのシャツで出かけたいのですが・・・先日のむすこの運動会で、真っ黒(と言うより真っ赤)に日焼けし腕の皮がボロボロです(涙)さすがにカッコ悪いし、見た目も見苦しいので長袖着てます・・・。そしたら、今日電車で座っていたらヘソ出しファッションの女性が僕の目の前に立ちました。目の前がちょうどヘソあたりですが皮がボロボロで汚い・・・。ファッションにこだわってる割にはこういうのはヘイキなんですね。僕はファッションにはこだわりませんがこういうのはダメです・・・。中尾語録106 本というものは、読む人の視点で、どのようにでも変化していく昨日のお話しは僕の本を「人材育成のPDCA解説書」と言ってくれた人のお話でした。実はこれまで、他にも 「コーチングの本」 「コミュニケーションの本」 「サービスの本」いろんな言われ方をされました。それは、読む人の立場や見る角度によってどのようにでも読めるということです。同じものを読んでも、感動する人もいればまったくそうでない人がいるように同じ本を読んでも気づきのポイントは人それぞれ。でも、それに気づかない読者もいます。そして「この本はダメだ」などとレビューを書く人もいます。とても残念ですがそれは、自分の見る角度が悪い場合もあるはずです。投資した本の代金をムダにしないためにこの考えを忘れずに! 本というものは、読む人の視点で、どのようにでも変化していく
2007年06月06日
-

中尾語録105 この本は育成のためのPDCA解説書
今日、別の部署の人に「中尾さんって前職は○○をやってたんですよね? 今度その分野でのソリューション事業を考えているんですが どなたかご紹介いただけませんか?」と聞かれました。でも・・・もう随分たちすぎて、すっかり人も入れ替わり連絡も取れない・・・。こういうのって、人脈っていわないんだろうな・・・。中尾語録105 この本は育成のためのPDCA解説書仕事のマネジメントサイクルとしてあらゆる業種・業態で使われている共通言語PDCA今更説明は要らないと思いますが何事も計画(Plan)を立てて実行(DO)し結果を確認(CHECK)し、改善(ACTION)するこれを繰り返すことで仕事の質が向上していくといものです。それは人材育成でも同じ。対象者をどのように育成するのか? 計画を立て実際に計画通りに育成し時々振り返ってはチェックするまた次のステップに向けて新たに計画をしていくこれを自然な形で本にまとめているんです。この流れをあえてPDCAという言葉では使っていません。しかし、読む人が読めばちゃんと分かってくれているんです。ぜひ手にとって確認してみてください!←宣伝(笑)新人育成のノウハウ本じゃありません。考え方の本なんです! この本は育成のためのPDCA解説書
2007年06月05日
-
中尾語録104 あなた自身が本気になって新入社員へ向き合っているか?
最近ケイタイをN904iにしたのですがハイスピードケイタイというだけあってメールの送信・受信がムチャムチャ速い!!びっくりするぐらい速いです。デザインもお気に入りです^^中尾語録104 あなた自身が本気になって新入社員へ向き合っているか?何をするにでも自分の行動は周りから見られています。そして、その行動はホンキか、そうでないか?見れば誰でもわかってしまうものです。もしも、自分が誰かにホンキになってほしいなら自分自身がホンキにならなければ誰もホンキになってくれません。だから、僕自身が新入社員に指導する上でいつも心がけていることは「本気とかいてマジ」←死語(笑)一所懸命な姿勢を崩さないことです。それが新人へ影響力を発揮していくのです。そして初めて、新人のスイッチが入ってホンキになります。互いがホンキになったとき、そして、そのホンキ同士が向き合ったとき大きなパワーを生み、大きな成長へつながっていきます! あなた自身が本気になって新入社員へ向き合っているか?
2007年06月04日
-

中尾語録103 リーダーシップとは「MVP Action」
最近、僕の本が、初めて(たぶん)●マゾンのの順位が10万位に落ちました。今日は14万まで落ちてました・・。まぁ、発売から1年近く、無名の僕の本がこれまで落ちないでいた方が奇跡なのかもしれません。どなたか順位を上げてください(ご購入)お願いします(笑)中尾語録103 リーダーシップとは「MVP Action」すみません、これは、僕の言葉じゃありません。(株)エンパワーリングの上村光弼先生に教わった言葉です。えっと、一般的にはパクリともいいます・・・。これは以下の言葉の頭文字をとっています。 Mission ミッション Vision ビジョン Passion パッション Action アクション つまり、リーダーとは、「己の使命を認識し、ビジョン(夢やあるべき姿)をかかげ、情熱を持ち続け、自ら率先垂範し、周囲に働きかけ、それを続ける人である」ということです。なるほど・・・・今日は上村先生の言葉のご紹介でした^^ リーダーシップとは「MVP Action」
2007年06月03日
-

中尾語録102 大事なのは読んでどうするか
最近は、ハンカチ王子だのハニカミ王子だのってやたら変な(強引な)ニックネームをつけてはマスコミの過剰な報道が目立っていますね。本人たちがどう思うか関係ないところがかわいそうです。僕だったら「ほっといてくれ!」と思いますね。特にゴルフなんて異常な過熱ぶり。ルールもマナーも何も知らない人たちで溢れるのは紳士のスポーツというゴルフが台無しです。そんな前フリまったく関係なく、今日もいってみよう!中尾語録102 大事なのは読んでどうするか本を読んで「面白かった」「感動した」「役に立ちそう」正直、このような感想は嬉しくありません。(イヤそんなこともないかな・・・)本当に嬉しいのは「○○に気づいたので、さっそくやってみました!」「○○をしたら、○○になりました!」こんな感想です。それは、僕の書いた本が何らかの影響を与えることができその方が行動してくれたからです。読んで知識として溜め込んでもなんにもなりません。行動してなんぼ。 大事なのは読んでどうするか
2007年06月02日
-

中尾語録101 あなた自身に成長していただきたい
さて、中尾語録も100回を超えます!もともと、僕の本の中から集めた言葉の数々でした。本のテーマにあわせ、人材育成に関するものが多かったと思います。次は、無名の僕が出版を実現したノウハウ(?)レポートからでした。レポートのテーマにあわせ夢を実現するとか人生を楽しむという言葉が多かったと思います。次は、僕の本を10倍役立てるレポートの中からご紹介します!!なので、自己啓発っぽい言葉が多いんじゃないかと思います!それではまずは、まえがきから・・・中尾語録101 あなた自身に成長していただきたい。僕は本を書くときに決めていたことがあります。それは、本を書いて有名になろうとか儲けようとかそんなんじゃありません。(そうなるに越したことはないのですが)読者の方に役立ててもらおうということでした。人材育成に関する本は2種類あると思うんです。一つは、ノウハウを学んでそれを発揮し、部下や後輩や新人を育成する本。目標管理とかの本なんかはこういうのに入ると思います。もう一つは、読んだ人自身を育成する本リーダーシップとかマネジメント論などはこの部類です。でも、僕が書きたかったのは読んだ人自身が成長することでその影響を受ける人自身も成長するという第3の本(コーチングなんかはこの部類かも・・・汗;)だから、新人育成のためのノウハウ本にだけにはしたくないと思ったわけです。読んだ人自身が自分を振り返り何かに気づき心に灯をつけ何か行動を起こしてくれるそんな本にしたいなぁと思いました。そしたらできるもんですね。←手前味噌(笑)総てはこの理由から・・・ あなた自身に成長していただきたい。
2007年06月01日
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月12日分)
- (2025-11-25 23:58:33)
-







