2008年11月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
賢い脳を育てる(4)
弟の姪っ子ちゃん達にひさびさに会ってきました。いろんなものを見つけてはリビングを素早くハイハイしてました。生まれてもう一年経ったんだと思うとほんと、時の経つのは早いものです。さてさて、お母様方とお話していると「なかなか勉強に気持ちが向いてないんです いつも遊んでばっかりなんですよね。 どうしたら、自ら進んでするようになるんでしょうか?」こんな風に聞かれることがあります。世間でも、運動ばっかりしてないで勉強しなさいとか、いいますよね。これ、世間である誤解の一つで運動しているときは、頭を使っていないこんなことは、ある訳なく頭が働かないと、運動もできません。これ、どういうことかというとひとは、入力→計算→出力という三つのサイクルで動いています。入力、入ってくる方は、感覚です。感覚から脳に入ってくるんですね。これを五感といいます。人によっては、第六感があるという方もいますけどいずれにせよ、感覚を脳に伝えています。そして、その感覚を脳で計算する考えたり、何かと繋げたりしています。そして最後に、出力、動きとして必ず筋肉の動きとなって出てきています。つまり、何かの情報が感覚として入力されそれを脳で情報を処理、計算、考えて筋肉など身体的な活動として運動、出力しているのです。逆に、出力の方から考えると例えば、姪っ子ちゃん達を例にするとハイハイしているとします。ちょっとでも動くと、外が変化したりしますよね。すると、感覚としてまた入力されます。あっちに行こうとハイハイして動くとその途端に、世界が変わるのでそれがまた、入力されてくるのです。どっかで音が聞こえてきたらそばにいけば、大きくなるし遠くにいけば、小さくなります。この三つのサイクルをぐるぐる回しながら脳はどんどんと育っていくんです。脳が育つとは、どういうことかというと先ほどの、ハイハイし始めた例で考えると目の前に靴があったとして動いていないと、大きさは変わりません。しかし、ハイハイで動いていくと目の前の靴が大きくなりますよね。その都度、世界は変わってくるのです。そして、靴をこっちから見ると、こう見えてあっちから見るとこう見えてと全部覚えてたら、頭は破裂してしまいます。だから、どういう風に見ていても変わらないというものが脳に残っていきます。そういうことを脳は勝手にやっています。そういう共通点を見つけ比較していく抽象化というのが、脳が育つということです。さらに、ここから解ることは入るところ、入力が小さいとどうしてもこのサイクルは全体に小さくなってしまうということです。人は体験・経験したことからしか学ぶことはできないというのは、こういうことです。やる気のスイッチが入るにはいろんな体験をすること自分の身体を通して入力→計算→出力のサイクルを回すことここに注目すると覚える、入力するということから見方が変わってくると思います。次回は、このことに関連して脳を育てるということを深めてみたいなと思います。
2008年11月30日
コメント(2)
-
第二印象力。
お洋服や家電製品を買うとき、即買いですか?それとも、一巡してから買いますか?そのとき、おまけをお願いしたり値切ったりしますか?何週間か前にTV番組で普段、負けてもらったりしたことのないふたりの主婦のうち、一方にだけある魔法をレクチャーすると好印象を与えることが出来て値引きやサービスOKになるという魔法を伝授していました。その魔法とは、『第二印象力』。具体的には、一度目の訪問では何も買わずそんなに愛想よくなくてもいいので、店の人の名前を確認したり、聞き出してきてで、しばらくたってから再訪問した時に、名前を呼んで声をかけるたった、これだけのことなんです。これだけで、おまけがついてくるし値引きもOKということでした。再訪問するタイミングは3分ほどが目安だそうです。これ、ほんとかな?と思ったのですがちょっと前に、ほしいものがあって1回目には、確認しただけだったのですがやっぱりと思って、数日後に見に行ったらお店の方が、自分たちの希望に合うようにアレンジのサービスをしてくれました。お店を出てから、『これが第二印象か』と気づいたのですがひとって、結構、この二回目の印象、大事にしますよね。初めていって、いい感じかと思ったけど二回目行ったら、ガックリしてしまったとか1回目ももちろんそうですが2回目の印象がいいところほど何でも長い付き合いをしているような気がします。先日、ディズニーのときにも書きましたが(11月23日)勉強も2回目からが勉強だと思っているのであえて同じことを繰り返したり2回目の印象を良くしたりしています。知っているものしか人は、理解できないということ繰り返せば、カンタンになるということすぐに、解りたいすぐに、結果がほしいという子にほどこの第二印象力が余裕やゆとりをもたらすこと教えてあげたいなと思っています。しかし、すぐわかちゃったり一目惚れするというのもまた魅力的ですよね。。。(笑)
2008年11月28日
コメント(8)
-
Time in Color
ここ数週間、受験生には定期テストや行事ごとが終わった子から過去問キャンペーンの第3弾、第4弾をしています。受験しようと思い立ったときが1回目で今年の春が2回目、夏が3回目で今回が、4回目。春に初めて設定した子は、3回目なんです。なんとか目標を超えた子もう少しの所までの子もちろん、いろんな子がいますがこれをしてあげるとみんな、目つきが変わってきます。実力テスト、模擬試験の偏差値というのも指標としてありますが過去問の方が、目標と現状の力がはっきりと数字で表れますし実力テストが計測しようとしているものと志望する学校が計測しようとするものが必ずしも同じだとは言えないのでこの方が、リアルになるのです。勉強に限らず、日常生活も人は、何かを選択・行動するときそこには、意識がありそれをする理由がありそこに何らかの役割を持たせています。それは、あまりにも無意識にしているように感じるので選択していることすら気付かないことが多いのですが自分にとって居心地のいい空間で大事だと重要性を感じることをしているのです。つまり、自分の周りにあるもの観るもの、聞くもの、感じるもの自分にとって重要なもので成り立っている自分にとって慣れ親しんだものでなりたっているということです。そして、自分たちは、このいい感じのなかでいい状態を発揮できるようにできています。だから、まだしたことがないことにも関わらず「いける」とか「いけない」とか「できる」とか「できない」とか解るんですね。そして、観ているもの、感じるものが自分にとって重要なものなのでそれ以外のやり方ってなかなか見えてこないのです。逆に、自分が本当に進みたい徹底的にほしいという未来を設定しそこに至るまでのプロセスを真似してみたり、疑似体験してみるといままで、合格点の取り方がほとんど、見えてこなかったのにその取り方が見えてきます。見えないものが見えてくるんです。つまり、現在が未来を決めるのではなく未来のゴールが、あるべき今を決めているということですね。そして、楽しく、仲良い状態や美味しい、嬉しい、楽しいといい感じの状態を繰り返し体験し、喜びを増やしていくと無意識がここに到達するように動き始めてくれます。ここで、重要なことは自分の周囲の環境をいきなり変えようとしないことです。こころの内側の意識を変えると周りの状況、外側は、それに伴って変わるのですから。これが、いわゆる引き寄せの法則ですよね。とにかく、自分が望むような状況幸せで、楽しく、仲良くいる状況そこに、馴染んで、親しくなって自分の心のなかに彩りがでてきたらそれがどんどん自分にとって重要になります。そうすると、いまあるべき姿が自然に、変化してくるんです。未来からの時間の流れのなかで現在あるべき姿、心地よい姿がリアルにカラーをもって意識し、働かし、動き始めると見えないものが見えてくるそんな風に思っています。『楽しむことを、あきらめない』昨日、モスに寄ったらこんな風に書いてありました。これ、お知らせですよね。今日の≪動画≫
2008年11月27日
コメント(6)
-
必死の『し』
ちょっと前に、日記のコメントのお返事に書いたことですが先日、小3年の女の子が 漢字の書き取りをしていて「「し」という字は、嫌な言葉だから ワタシ、この字覚えていないの。」というと 横に座った同じ学年の女の子が 「『し』という言葉、嫌だよね。 「必死」のだよ。これならいいよね。」 「あぁ、必死の『死』かぁ。 わかったよ。ありがとう でも。。。『必死』というのも あまりいい言葉じゃないよ。 余裕がないということだからぁ」 「いやいや、必死という言葉は 何かやりたい事や目標があって、 それに向かって 頑張るということばだから 必死というのは、いい言葉やねんでぇ。」 「必死は、余裕やゆとりがない ということなんだけどな。。。」 と話して、目で助けを求めていました。 余裕・ゆとりがないと答えた子には 合っているよと目でお話して 頑張ることは、いいことだ とお話している子には 「そうだねぇ」とお話して 余裕・ゆとりのお話をして もう少しじっくり時間をかけて 体験させていこうと思ったのです。このお話を昨日高校生にしたら「それ、小学生の会話じゃないねぇ」と話をしていて今日これを、ぽんぽこ先生にお話したら「必死を、素晴らしいと言っている子と ゆとりを素晴らしいと言っている子は 『頑張る』というものの捉え方が違うね。 前の子は、『自らが頑張る』 という意味の割合が多い意味で 後の子は、『他者に頑張らされる』 という意味の割合が多い意味で使っているね そして、頑張っている子は、 いまは、楽しいから、続けられるのだけど 頑張れなくなる時がくるから 上手に教えてあげてな。 そして、『ゆとりを持って』 という意識をもっていると 頑張る時よりも長くできるし疲れないし 楽しくできるよね。 そして、ゆとりを持つ意識を持っている方が 頑張るよりも、ずっと早くできるんじゃないかな?」と、話してくれました。続きをいろいろ聞かせてもくれたのですが授業になったので、また続きは書かせていただきますね♪
2008年11月26日
コメント(0)
-
美事な贈り物
ギャグを言ったりして特別面白いことを言っている訳じゃないのにクスっと笑うようなそんな魅力がある人なぜか応援したくなるような人っていますよね。丁寧で優しく、紳士的であることそして、ユーモアがあることそういう要素を多分に持っておられる人はその人と会ったり、その人を見るだけでなぜか元気が出てきたりエネルギーが上がってくるのを感じます。先週末のディズニーランドでもそんな出来事が沢山ありました。キャストの方が案内されるセリフにどこかユーモアがあるのです。「喫煙・飲食はご遠慮ください」ではなくボートで、川をめぐるジャングル・クルーズであれば「いま入った無線によりますと 先に出発した旅行者が アフリカゾウに襲われたそうです。 ワニ・ゴリラ・ゾウなどの動物たちは、 甘い食べ物の匂いによってきたようです。 動物たちに襲われないように ボートでは、喫煙・飲食はご遠慮ください。 特に、ポップコーンの甘い匂いに 動物たちは、寄ってきますので ボートに乗る前に、食べ終わるか ふたを固く締めておいて下さい。」とお姉さんが案内していました。また、ホーンテッドマンションでは「この館にいる幽霊たちは 3歳以下の子どもたちが大好きで、 いたずらしてくるかもしれませんから しっかり手を握ってください。」とか乗物に素早く乗ってほしい場面では「生きているのなら、テキパキと。」と話していました。これ、聞いているとクスッと笑えてくると同時に隣の人とかその台詞を復唱してその通り動いているのです。そして、これが何よりもすごいところだなと思うのですがこのセリフ(スピール)を聞いた人が喜んで、進んで行動しやすいようにゲストが行動するそのままの言葉を話しているのです。「遅れないで」ではなく「テキパキと」であり「手を離さないで」ではなく「手をしっかり握って」なんです。これ、神経言語学とか脳の理解の仕組みを学んでいると簡単なことのようでこの違いは、大きな違いなんだと出てくるのですね。「こぼさんといてや」とか「なくさんといてや」など意識していないと、人は知らず知らずに行動を禁止する言葉を発してしまうんです。そして、子供も大人も本当に理解してないと禁止された行動をまたやろうとしますよね。「だから、しないって言ったじゃない」こんな風になってしまうことが多々あります。危険だからとか不安だから余裕がないからそのキモチをそのまま禁止の言葉にしてしまうんですね。自分自身もこれに慣れるまで頭のなかで、一度思い描いて「『こぼさんといてや』は つまり『しっかり握ってね』だ。」とか「『なくさんといてや』は 『手にしっかり握ってね』か 『右のポケットにしまってね』だ」と、一つひとつ変換していました(笑)言葉ひとつで大きく変わりますよね。美事だなぁと思うような言葉「言われて嬉しかった台詞」 「言ってあげて喜ばれた台詞」って、ありますか?
2008年11月25日
コメント(4)
-
ハッピーマジック
「何か足りない」そんな風に思ったりすることありませんか?「なんで、うまくいかないんだろう?」そんなことを思ったりするときありますか?自分もこんな風に、思うときがありました。ひと月くらい前だと思うのですが今回の旅行を楽しみにしてた姪っ子ちゃんが旅のしおりを作ったりカウントダウン・カレンダーを作ったりしていると「ディズニーランドで働く人は どんなことを考えて どんなキモチで働いているんだろうね」ふと、そんな風に話してた時がありました。すると、つながるものでテレビ『ガイアの夜明け』(10月14日)でディズニーランドの人材教育が紹介され幹部社員の人がリゾート内を廻り素晴らしい応対をしている人にファイブスターカードと呼ばれるご褒美カードを渡していました。ちょうど、テレビ番組に出てた人が夏に、スティッチのランチショーを見たとき素敵な笑顔で応対してくれたあのお姉さんだったんです。「このお姉さん、覚えてるよぉ」と、話していました。ここディズニーリゾートにきて新人さんだなと感じる人ほど、表情が固くて頬の筋肉が強張っているんです。お客様にお話することと言えば走らないでほしいとか、こうしてほしいとかキャスト側からお客様に注意、お願い、禁止することですからこういう緊張するとき、必死なときって余裕がないので、こうなるものですよね。反対に、ネームプレート以外にバッジをつけているような人はほぼ全員が口角が上がり歯を見せていて頬の筋肉が、上に上がっているんです。さらに、あの人は♪と優れた人は必ず目を見て微笑んでお話してくれます。余裕があり、その人の目を見るから聞く人もその笑顔につられてうまくいっているんですよね。この笑顔であることと鏡を見ることはどうやら、自分への今回のテーマのようでホーンテッドマンションでも最高の贈り物は、物事の捉え方どんなマイナスなものでもそれを面白くすることだったしカヌー探検でも、お兄さんがカヌーを楽しみましょうではなく「楽しんで、見せましょう。」と、話していました。宿泊したマジックルームでもお部屋が絵本をきっかけに謎かけをしてあるのですがそのヒントは、笑顔と鏡でした。笑顔でいること、鏡をみることそういうことの大切さを知ると守られているもの一緒にいるものに気付きカタチとして見えるものは見えないものに支えられているそういうことを知ることができるんだなと、いろんなとこから改めて感じています。素敵な休日をお過しくださいね。
2008年11月24日
コメント(6)
-
Good fortune
「人生は、冒険のようなものだ。 何かに迷ったとき 何かを決断するとき そんなときは 自分のこころの奥にある 心のコンパスを信じて 心のコンパスに従っていけばいい。 人生の冒険の最高の宝物は お金や財宝ではなく、友達なんだ。」昨日、ディズニーシーに行ったらアラジンのコーストで船乗りのシンドバットがこれが、Good fortune(幸運のコツ)だとそんな風に話していました。夏に、ディズニーにやってきて(8月21日)あのときもそのときの心にピッタリのものを頂いたんてすが今回もそんな感じがしています♪今回は、夏に一緒に行った小3の姪っ子ちゃんがおばあちゃんを案内しているのですが3ヶ月前と同じにできるものは飛行機や宿泊場所、移動時間などできるだけ同じような感じにしてあるんです。すると、ライフコンパスというか頭の中に地図ができてたり 先を見通すこと予測を立てることができるので前回よりもイキイキしています。また、自分がエスコートするからといろいろ工夫しているようです。感謝のキモチで予測を立てると時間がどんどん増えること繰り返すと簡単になること人に教えるミニ先生になると得られるものは数段に変わることどれもお勉強と同じですね。連休なので入場制限がかかるくらいめちゃくちゃ人でいっぱいなのですがそれほど待つことなくなぜかスムーズにいろんな体験ができていますこれも、調和が取れてきたということなのかな?と思っています。今日は、ディズニーランドに行ってきます。また、何が聞こえてくるか耳をすませてみたいと思います。
2008年11月23日
コメント(2)
-
脳にいいこと。
「こんな美味しいものあるんだね。。。 ワタシは、ほっぺたが、落ちそうだよ♪ あの綺麗なお姉さんが プレゼントしてくれたの??」元教え子のゆみちゃんが差し入れに持ってきてくれたスイートポテトを食べている子たちがほっぺをウルウルにして、そう言っていました。高校卒業して3年にもなるのにやってきてくれたゆみちゃんこれからの仕事のこといまのことなどなど、いろいろお話して「自分のいいなと感じるものを たくさん増やしたり 進みたいなと思う所に足を運んで 自分のモデルとなるような人を見つけてごらん。 この人、『素敵だな』という人がいたら きっと、いい感じに開けていけるから。 いま、幸せであることが大切だよ。 これから、何にでもなれるよ。 そのための準備は、まだできるから。 美味しい、嬉しい、楽しいを増やして 余裕・ゆとりを持って 脳にいいことだけをしてね。」そんな風に話して送り出したら「リスタートするのに まず、先生のところに 行ってみようと思ったんだ」と、教室から後にしていました。茂木健一郎さんが翻訳したマーシー・シャイモフ著『脳にいいことだけをやりなさい』によると「脳にいいこと」を実践するときに法則の流れに乗れば、より効果的だそうです。(1)あなたを広げていくものが あなたを幸せにします。(拡大の法則)(2)宇宙はあなたを支えています。(支援の法則)(3)あなたが価値を認めるものが あなたの周りに増えていきます。(引き寄せの法則)思考や言動、自分の周りにある出来事は自分のエネルギーを増やすか減らすかでエネルギーを増やすと、より幸せになりエネルギーを減らせば、それだけ幸福感は減ります。すべての世界は、自分に優しくできているのですでに起こってしまっていることを嘆いたり変えようと後悔したりしないで自分の無意識(後ろの人)はいつも自分を支え、成長させてくれているそう信じることが自分と脳を成長させます。そして、好きになったものが自分の周りに集まってくるので好きなこと、いいなと感じること同じ考え方や行動を繰り返しているうちにわだちがしだいに道になっていくように神経回路がしっかり出来上がっていきます。ちょっと前に書いた(11月13日)『ミラーニューロン』を上手に活用して脳の神経回路がどうなっているかを確かめてまずは、幸せ度を高めるような新しい溝を作っていく考え方や感じ方や行動パターンを変えれば脳は、それに応じて自ら溝を変えていきますよね。木曜深夜に放送されていた『夢をかなえるゾウ』()で空を見るそんなときは下をみんと上を観る空は、心の鏡や。いろんなことを教えてくれる選ぶのが、怖くなくなる方法は自分だけは自分の味方ありのままの自分を好きでいる選んだ自分を否定しないと話していました。なんかゆみちゃんのおかげで自分もいろんなことがつながりました。
2008年11月22日
コメント(4)
-
continue
「なぁなぁ、せんせ 『どうするん?』 って1時間くらい お母さんと話したんだけど...」今週授業を始めようとしたら女の子が、そう話しかけてきました。「で、どういう結論になったんだ?」と聞くと「勉強しようということになった。」と肩を落としながら、答えました。「そうだね。」 そう言いながら微笑んだのが 彼女には不思議だったようで「せんせ、なんで、ニコニコしてるの。」と、上を見上げながら聞いてきました。で、座っている彼女と視線が同じになるように、しゃがんで「『勉強しよう』という言葉と いまの姿勢が、ぜんぜん違っていたから。 いまの『勉強しよう』は 策がないと言っているのと 同じように、先生には聞こえたよ。 『勉強しよう』って もっと具体的に言ったら、どうするの? いまの方法で、 結果が出ているものと 出ていないものがあるよね。 結果が出ていないものは、 何か変えないと、結果は変わらないよ。」と言うと、彼女は、上を見上げて何か思い出しているようでした。そんな姿を見ながら「実は、それが、いま不足していること。」というと、キョトンとしていました。「とにかく、多くの問題やって って焦っているでしょう。 一度やった問題は、 『これ、前にやったことあるし』 って、気持ちになるし 先生に、一度やった問題を もう一度しなさいって 確認テストしたりされると 一度やった問題ができないとき 『なんで、できないんだ』 って、腹が立ったりするでしょう。 それを超えて 『思い出す』時間を大切にすると 成績は、もうひと回り上がるよ。 せんせの授業を 思いだしたりする時間ある? まだまだ、やれるよ。 まだまだ、できるようになるよ。」と、続けてお話すると「そうか!」と上を見あげてペンを動かしながら、ニコニコしていました。今週から、早いところでは定期テストが始まっていますよね。「前日は、覚える時間ではなくて それまでに準備して、 思いだす時間にするんだよ。 時間はない、できないんじゃなくて、 時間は、作るもの、やるものなんだ。 前日に、思いだす時間を時間をつくれるか。 それまでに、やるかやらないか。 ただ、それだけなんだ。 誰かとの勝ち負けじゃなくて 続けてするか、しないかだけなんだよ。」定期テストを迎える子たちに最近、そんな風にお話し続けています。夕陽を見ながら、出来事を思いだしたり夜寝る前に、一日を思い出したりそんな時間をにっこりと迎えられたらとっても、幸せですよね♪(6月15日の日記)今日の≪動画≫
2008年11月21日
コメント(0)
-
ゆとりとプレッシャー。
ほんと、すごく寒くなりましたね。日本は、年末年始並みに冷え込むとニュースになっていましたがほんとに、今朝は冷えましたね。。。昨日、ぽんぽこ先生の所に行ってマッサージをして頂いてきました。自分がリラックスすること頑張りすぎることなく余裕とゆとりをもっていることそれが自分を喜ばすことでありひいては、教室の子供たちにつながる。そう考えているのですが昨日の日記(11月19日)に書いたみたいにぽんぽこ先生、ぬくもりのある手を背中に当ててマッサージしてくれて「やっと、いい感じになってきたなぁ どちらかというと、さださんはすぐに 『頑張ろう』とか 『なんとかしよう』とする方だからな。。。」と、笑っていました。「最近、ちょっと賢くなったんです(笑)」と言うと、ははとまた笑って「頑張ろう、しっかりしようとすると 人は、プレッシャーをかけてしまうんだ。 だから、プレッシャーを感じているときは ほんと、能力を発揮できないんだよ。 」「プレッシャーって、 上から押さえつけられるみたいですよね。 『世間では、プレッシャーに打ち勝って』 とか、言われたりしますよね。。。? 」と、聞くと、『頑張ること。怠けること。』(9月3日の日記)の続きを聞かせてくれました。「プレッシャーには、なかなか勝てないんだよ。 自分で自分に重しをしているんだから。 それに、プレッシャーに勝ったら 勝った方がやっかいなんだよ。 プレッシャーに勝った人は、頑固になるんだ。」「だから、余裕・ゆとりをもつ ということが大切なのですね。 『頑張る』という方向は 今までしてきたところだから どうすればいいか すごく解りやすいのですが 『頑張らないでおこう』とすると 『手を抜く』という風になりそうですよね?」「 そうそう。 『頑張ろう、しっかりしよう』として しんどくなったり、疲れたりするから 『休憩しよう』とするんだよね。 『手を抜こう』というのは 身体は、休んではいるけれど、 頑張る意識は、そのままなんだよ。 意識を変えないと、 楽にはならないし、解決しないよね。」と話してくださいました。 何かをするときいま自分は、どんな状態であるかそれを見ておかないと人は、知らず知らずに頑張ってしまうようです。うまくいく方向ではないと感じたらすぐに、休憩してゆとりがないと思って心のエネルギーを増やす。そうやってソフトで、楽しい意識仲の良い意識をもって楽しい、美味しい嬉しいをどんどん増やして楽しむと心のエネルギーって、増えますよね。写真は、堺のお部屋の玄関に飾ったピンクのクリスマスリースです。
2008年11月20日
コメント(2)
-
ぬくもりのある手。
先週の土曜日鎌田實先生の講演(11月16日)のあと姪っ子ちゃん親子と待ち合わせして『グッチ』先生こと芦屋カイロの中西先生の所に行きました。姪っ子ちゃんが、鼻が詰まって生活にも支障が出ているというので診てもらいました。自分も子供のころからアレルギー性鼻炎や中耳炎などを患いいろんな耳鼻科を転々とし高校を卒業してから市民病院に行って内視鏡カメラを使った治療をしてもらったり東京の大学病院で、治療してもらって初めてうまくいくようになりました。でも、東京医大の先生に「君の鼻はね、カメラで観て 目の前に持っていって 風を送っても 空気が通らないんだよ。」と言われて、困っていました。今からは想像できないのですが自分の鼻は、左に曲がっていました。曲がっているから風の通り道が塞がれていたんですねそんなとき、知ったのが頭蓋骨の整体。優しくソフトにそっと骨のバランスを整えてもらって鼻の位置を以前よりもまっすぐにして頂きました。すると、鼻がまっすぐになったこと以上にすごく呼吸がしやすくなったのです。というわけで、姪っ子ちゃんを連れていきました。すると、先生が優しく施術してくださるたびに鼻から、『プッスー』と空気が抜ける音がして帰る電車のなかで「どうだった」とお母さんが聞くと「すごく、鼻が通った。 息がしやすくなった。」と話していました。そして、施術の最後に中西先生が「寝る前に、右の肋骨の下あたり 肝臓の上に手を当ててあげてください。 なんにも考えなくてよくて ただちょっと、当ててあげてください。 それだけで、すごく落ち着きますから。」と、お話してくれました。姪っ子ちゃんにはこのお話がすごく響いたようで「母さん、せんせが、 手を当ててと言ってたやろ♪」と話して、当ててもらっていたようです。セロトニンの有田教授もお話していましたが(11月10日の日記)グルーミングやくっつこうとすることアタッチメントは、すごく人を幸せにします。子どもって、何かがあるわけではなくまさに、くっつくことそれ自体を目的としてくっつこうとするときってありますよね。赤ちゃん学の本などを読んでいるとこのアタッチメントの欲求というのは他のどんな欲求よりも強かったりするそうです。そして、初めてのものを目にしたり一人になったり身体の調子が悪かったりするなどして恐れや不安などを経験したときに養育者など、特定の人にしっかりくっつくことができまたその人から崩れた感情をうまく立て直してもらうことができたかによって子どものその後の人間関係も含めた社会性や性格の発達が少なからず左右されるという考え方もあるそうです。しっかりとくっつき感情の燃料補給をして安心感を取り戻すと再び養育者を安全な基地として勇敢に子どもは、出ていけるということなんでしょうね。リラックスする音楽を聴きながら背中に手を当ててあげたり自分一人のときは軽く身体全体をマッサージしてあげるそんなことだけでもすごく心のエネルギーが補給できるそんな風に考えています。日本は、全国的に年末並みの寒さになるそうですね。もし、時間があれば、そういう温かい時間作ってあげてください。写真は、和歌山の教室の壁に掛けてあるリースです。今年は、パープル、いろんな所でよく見ますね♪
2008年11月19日
コメント(6)
-
賢い脳を育てる(3)
秋が深まってきて、運動会・文化祭など行事ごとが、だいたいひと段落したので最近、保護者の方と少しずつ時間を取ってお話しています。学年も性別も、お子さんの状態もぜんぜん違うのでそれぞれに合わせてお話させて頂くのですが共通してお話させて頂くことそれは、局所的にみるといろんな状態があるけれどどういう感じに育っていってもらいたいかその望む方向・環境のものを目に触れ、感じるように増やしていくことそして、周囲の環境を自分に合わせて変えることではなく周囲・望む方向に合わせて自分を変えていくことさらに、その変化と言っても大きなものではなく小さな出力の積み重ねが、能力の向上につながること こんな感じのことをお話させて頂いています。 赤ちゃん学の先生のお話を聞かせて頂いていると人の脳というのは、生まれたときからかなり優秀なようで赤ちゃんの段階からかなりのことが脳ではできるのだけれどそれを表現する運動機能が育っていないのだそうです。また、運動機能を育てていくことで逆に、脳も大きく育ってくるそうです。実際に教室で、子供たちを教えていても思うように成果の出せていないお子さんはこの入力と出力のサイクルがうまく回っていないこのことが大きな原因であることが多いです。昨日の日記(11月17日)の『脳の回転スピードを落とさない』というのは言いかえると、こんな感じで知らず知らずのうちに、人には自分の当たり前というスピードがあるのでこの入力・出力の回転スピードを体験・経験のなかで上手に育ててあげることそれが大切かなと思っています。教えていていて、感じることですがこのテンポがゆっくりだと人は、頭のなかでより完璧な出力を求めるようです。そして、「理想とする状態」と「実際の自分のアウトプット」との間に大きなギャップが生まれ、苦しくなってしまいます。言葉に限らず入力と出力の間には一定のズレが生じます。勉強する上では、このズレ「もどかしさ」が大切なこともありますが大抵の場合、この苦しさが、行動意欲を減退させることにつながることが多いです。というわけで、入力・出力のサイクルとくに、出力の仕組みを作ってあげると大きく育ってくれると思っています。具体的には、赤ちゃんや幼児の時期であれば指や手足を積極的に動かす運動をさせること小学生のお子さんであれば身体をいっぱいに動かすことそして、一桁の足し算引き算、九九10~19までの数字と一桁の数字の足し算、引き算ここがスラスラ言える九九と同じレベルこうなると、後が楽だと思います。中学数学・高校数学は理論の部分、手続きの部分がわかれば分解すれば、この部分の結合でしかないからです。具体的な教材としては、『10マス計算』というのがあるのでそれを使うのがいいかなと思います。コツは、12-8などの10個の計算が10秒前後になって、スムーズになるまで書かないで、ひたすら、口で言わせることです。頭で考えるのではなく、口で出力するということですね。大人の方の場合は、見聞きしたものからそのものが解るいくつかのキーワードを拾いだしそのキーワードをもとに、それを誰かに話してみるこういうことでもいいと思います。頭の中の情報を上手に出力する自分の生産性が上がるパターンを身につけるって、とても大切なことだなと思います。不連続シリーズ『賢い脳を育てる』のバックナンバーは、ここです(笑)『賢い脳を育てる(1)』(6月15日)『賢い脳を育てる(2)』(6月16日)
2008年11月18日
コメント(4)
-
脳の引き込み現象。
国語を担当している先生が古文単語を覚えさせているのに「はい。これ10個ほど覚えてね。」と言って、中学生たちが覚えていました。黙ってもくもくと覚え始めたので「ちょっと待って。ちょっと待って。」と一旦止めて「『あやし』は、何かを見たときに 『あぁ』という感動の気持ちからでるから プラス表現なら、神秘的だとか不思議だ マイナス表現なら、見苦しい、お粗末だで 『をかし』は、センスがあるだから。 芸術的なものなら、『風情・趣がある』 容姿とか声なら、『見事である』で 『あさまし』は、 人の行動を「浅む」という所からくるから 予想外だと、驚きあきれるし、 行動とか身分だと、 『見下す』とか『ばかにする』なんだ。 『すさまじ』は、『興ざめである』 これ、枕草子に『すさまじきもの』 という段があるんだけど。 国司に当選確実を思って前夜祭していたら いつまでたっても、連絡がこない みんななんとなく感じてその家を去る こういうときに、『すさまじ』っていうんだね。」と、教えたら、なるほど、と覚えていました。自分が子ども達に教えるとき脳の回転数をなるべく落とさないようにというのを心がけています。丸暗記だと、脳に情報を書き込むまで忘れないように気をつける必要があります。だから、脳の作業場ワーキングメモリを上手に活性化しながらその場ですべて処理してしまうこれを心がけているのです。茂木健一郎さんの『脳を活かす仕事術』によると脳には、引きこみ現象というものがあって予測できる部分と予測できない部分のバランスが整った偶有性に満ちたものや相手が本気で言っているものには興味・関心、注意を向けるそうです。そして、相手の話にいったん引き込まれるとその状態が続いている限り集中力が持続しさらに、グーッと引きこまれていくんですね。脳の回転数を下げないコツはできるだけ、そのものが体感できるように、視覚化できるようにもっていくことです。『見えないはずの視線の先に』(8月29日)とか『思い描く力』(10月13日)とつながるお話だと思いますが言葉や音から、イメージ化する能力脳にある映像化する能力をフルに活用するとすごく能力がアップするのです。そして、ワーキングメモリを鍛える方法はちょっと前に、テレビ番組でしていたのですが適当な言葉を言ってもらって逆さま言葉をすぐ言う訓練を毎日10個くらいやり続けると短期記憶の回路がスムーズになります。今日も、教室のお母さんとお話させて頂いたときにお話させて頂いたことなのですが人って、その人の状態を見ながら光を当て、磨いたところが伸びてくると思います。
2008年11月17日
コメント(2)
-
鎌田實先生講演・いい加減がちょうどいい
昨日、諏訪中央病院の名誉院長であり、作家でもある鎌田實氏(かまたみのる)さんのお話を聞いてきました。鎌田實先生は、『がんばらない』『あきらめない』等 のベストセラーを立て続けに出し一躍、時の人になったドクターなのですが今回は、相愛大学の120周年シンポジウム「健康で長生きするコツ教えます」と題した講演をしてくださいました。いろいろお話をしてくださったのですが印象的だったところをいくつかご紹介させて頂くと最近、書かれた『いいかげんがいい』という本の中にも書かれたそうなのですが人の脳は、「頑張る神経」である交感神経と「休んでいいとする神経」副交感神経という二本の神経の加減をコントロールしていて長年、たくさんの人を見てきて人生の幸せは、この加減を失ったときに、不幸せになっているそうお話されていました。「人は、つい頑張りすぎてしまう傾向があり それがひどくなると、身体も心も悲鳴を上げます 反対に、副交感神経が刺激されると 血管が拡張して循環が良くなり リンパ球が増えて免疫力も上がってきます。 1日のなかで 緊張して、アクティブに活動する 交感神経が優位な時間と リラックスして、休む 副交感神経の優位な時間 この両方があって バランスを取ることが大切だから 健康であるために 一日の中に 「がんばらない」時間を作って欲しい。」そんな風にお話されていました。そして、鎌田さん、2006年の紅白歌合戦の特別審査員をされたそうなのですが楽屋で、木村拓哉さんとお会いした時に木村さんが初めて会うにも関わらずすごく丁寧に挨拶してくださって『容姿がカッコイイというのもあるけれど なるほど、だから みんなが、応援したくなる人なんだ。』とすごく納得したそうです。木村さんのお母さんとも対談したことがあるそうなのですが「木村さんには、3歳から包丁を持たせ 野菜嫌いだった木村さんの弟さんには 一緒に家庭菜園をして野菜を育てることで 命をいただくことを教えたと話しておられた 料理や野菜を育てることを通して 水加減・火加減・手加減を知るのですね。」と教えてくれました。そして、諏訪中央病院は介護を全国に広めたモデルケースだったそうなのですがそのきっかけが地域の医療費が一気に下がり長寿の人が増えて、役所のお役人が注目したことだったそうです。鎌田先生たちが地域のお年寄りを集めて5年かけて指導してきたことは(1)減塩・うす味であること 塩分過多で、病気にならないように(2)週5回の魚料理 魚からEPA・DHAなど イキイキする栄養を得るため(3)繊維のものを食すること これは、こんにゃく、きのこ 野菜、もずくなどの海藻など 繊維質のものならなんでもいい。 トイレに入ったら 自分のうんちを見る習慣をつける 水に浮くうんちだといい 繊維質を豊富に摂っている証拠だから(4)色素のものを摂ること 抗酸化力のある野菜の色素を摂ること かぼちゃや、ニンジンに含まれる 黄色のベータカロチンであったり トマトに含まれる赤のリコピンなど 野菜の色素に含まれる栄養を取ること(5)スロートレーニングをすること 深部筋肉を鍛え 転倒防止や、骨折にならない身体をつくること スロースクワットで 太ももの表と裏の筋肉を鍛えるとよいとお話されていました。そして、最後に楽しいことが一つあるだけでこの人の生活が変わる瞬間があります。1年に1つくらいやりたいことをやってください。こころにいい刺激を与えてくださいそうすると、やりたいことが変わり温かさは、連鎖するのです。とお話されていました。心を開放し「ほっ」とする時間を作ること。 そして、美味しい、楽しい、嬉しいを増やすことそして、最近大切だなと感じていたことをここでも、聞くんだなと不思議なシンクロに、ニヤっとしてしまいました。
2008年11月16日
コメント(10)
-
空白の時間。
「この空と白、続けるとなんと読むの?」小学校3年生と国語のワークをしていたらそう聞かれました。「『くうはく』だよ。」と答えてから『つながるものだな。。。』と、ニコニコしてしまいました。最近、一週間前の有田教授のお話がきっかけだと思うのですが「空白の時間を取ろう」と思っていたのです。『もっと時間があったら もっとお金があったら』と余裕・ゆとりを持とうとしていて心にゆとりが生まれリラックスして能力が上がったのに能力があがったものだからまた、頑張ってしまうこれでは、なんのために能力上げたか解らなくなってしまいます。これは、身体にも出ていてちょっと前に、電車に乗って座っているとなんだか苦しくなってきたと思ったらズボンのウエストがパンパンでおなかを締め付けていました(汗)というわけで、心と身体に、空白の時間を与えようと思い立ち朝、ストレッチ、スロートレーニングしたり何にもせずに、心を落ち着ける時間を取ったりそんなことをしています。1年くらい前に、ベビームーンのきよこさんから「さださん、忙しいんじゃないの? リラックスする時間ちゃんと取ってる? 私はね、朝、紅茶を入れて お庭に座る時間を取っているのよ。 いま、すごくいい花の香りがするの。 あの時間があるとないのとでは こころのゆとりが全然違うわ。」と、言ってもらった意味が最近やっとわかってきました。よくよく考えてみるとこんな風にしなければ何にもない『空白の時間』って取れていなかったんです。こうするようになって心地よく過ごす時間増えたような気がします。頭のなかをからっぽにするって、ほんと、大切ですね。リラックスタイム、空白の時間どんな風にとっておられますか?今日の写真は、玄関口にある赤い靴下です。
2008年11月15日
コメント(2)
-
調和の心。同調する脳。
昨日、家に帰ったら「臨床学会のお仕事に行ったらね。 ミラー療法というのを紹介していて 片方の手が動かない人が 鏡の入った箱のなかに、 動く方の手を入れて 鏡に映った手を見て 反対側の手の動きを脳に思い出させる バーチャルリアリティーの時空のなかで 錯覚を起こさせる治療法 というのを研究発表していたよ。」と、教えてくれました。昨日のミラーシステムを脳科学の分野で実践しているんだと『いい状態を目に入れること』の大切さを感じました。さて、子どもたちや相手にお話を聞いたりするときに『この子、わかっているのかな?』と感じることありませんか?こちらがお話しているのに「はい。はい。」ってとりあえずお返事していたり視線が違う所に向いていたりこちらが真剣にお話しているのにぜんぜん伝わっていなさそうなときって、ありませんか?また、真剣に書けば丁寧に書けるのに字が乱雑だったり、枠からはみ出たりそんなことって、ありませんか?「もっと、綺麗に、丁寧に描きなさい。」というと、「これ、どうみても読めるやろ。 読まれへん方がおかしいわ。」って、言いかえされたり。。。そんなことって、ありませんか?そんなとき、ちょっと前まで、自分自身の真剣さがあれば、思いがあればこのことが伝わるのだろうと思っていました。今週ちょうど、そんなことがあって「せんせと、いま、こころ通じている?」とお話したり「心を込めて書いてね。 これは、心が入っていないから せんせは、○できないな。。。」とお話しました。そして、子ども達と同じように紙に手順を書いてみて、彼らとテンポを合わせそのリズムやスピードや間が合ってきたらこちらが望むテンポにアップさせるとリズムの同調、雰囲気の一致とともに先生と心を通じさせること教材と心を通じさせることが以前よりもできるようになっていました。そういえば、横で教えていたひろみ先生はメトロノームを使って、メトロノームのリズムに同調させて子供のリズムを変えていました。 一生懸命したくてもその人がその気でなければぜんぜん、いいようにはなりません。人は、『わぁ嬉しい』と感じた瞬間にこころのエネルギーというのを一気に感じます。共感を生むような何らかの同調が起きたことしかそれを繰り返そうとはしないんです。このへんを利用したのが『引き寄せの法則』(7月8日)ですよね。だから、心地よい気分であること笑顔を生むことって大切なんですね。ゆとりがどれだけあるかって、大切ですよね。また、カウンセリングなどで相手と動作、言葉をオウム返しに合わせたりするミラーリングという技法をすることでラポール(信頼感・一体感)を作ることを重視しますがこれも、昨日の日記に書いた脳のミラーシステムを利用したものなんです。相手がある動作をしたとき相手に生じる脳の動きと同じ脳の動きが、私の中でも再現されます。反対に、心が同調していると私がある動作をすると相手の脳のなかでも私と同じように脳が動きます。そういう同調行動を引き起こす脳的な基盤があるからこそ動作の模倣ができるし相手の心も想像できるんですね。 自分自身は、一生懸命やっているのになぜうまくいかないのだろうというとき自分自身のこころのゆとり自分自身のこころのエネルギーに目を向け心の同調、リズムの同調雰囲気の一致を目指して、埋めていくと意識的にせよ、無意識的にせよ共感をサポートする同調が生まれお互い心からいい関係になりいい結果が生まれると思います。
2008年11月14日
コメント(2)
-
ミラーニューロン
野茂さんが、オリックスのキャンプに特別コーチとして指導したってニュースになっていましたね。大石監督がチームメイトだったというご縁で実現したそうですが最初このことが紹介されたとき一部のスポーツ紙は「野茂さんの日本時代を知る 若手はほとんどいなくて 首脳陣だけが盛り上げっていて、 いまの若手に、ピンとくるのだろうか? これは、オリックスの話題作りなのでは?」そんな風に書いていたそうです。今朝、出がけにニュースを見ていたら加藤選手は「3年間練習してきたものを、 ものの5分で超えてしまった」と語り直接フォークボールを伝授された大久保投手は「投げる際の意識の持ち方を教えてもらった。 いままで、いろんな人に聞きながら 自分なり試行錯誤でやってきたんですけど 今日ちょっとだけ教えてもらっただけなのに ほんとに、すごく落ちたので、びっくりしています。」と興奮気味に話していました。 ちょっと前から、ミラーニューロンという言葉が自分のなかで、ちょっとブームになっています。この言葉自体は、何年も前から知っているのですがたぶん、『脳活用100回スペシャル』(10月21日)を見たあたりからこの言葉をキーに考えるといろんなことがスッキリするようになってきました。 昨夜も、定期テスト前の中学生の子たちに「塾のワークであったり 教科書ワークであったり 解答を全部書き込んで、 どこから答えを導けばいいか ひとつずつ、確認していきなさい。 確認が終わったら、 コピーした何も書いていないもので それが、本当に、 マスターできたのか確認するんだよ。 最初は、時間がかかるから、 書かずに、指差し確認して声にだすの。 」って、お話しました。「テスト勉強しなさい」こう言われたところでどう覚えていくのが効率がよく結果につながりやすいのか解らないことが多いので本当に、自分が準備してきたことやり方、考え方、それをそのまま実演して、お話しました。テスト勉強とは、ノートをまとめたり問題集を解くものではなくてやり方も含めて、覚えちゃうマスターしちゃうことだこう言い続けてきてマスターできている子とできていない子がいたのですが今回、マスターできていなかった子が「プリントって、こういう風に ツールとして使うんだね。」と話すのを聞いてミラーニューロンミラーシステムの働きがあるから口で教えてもらってもなかなかできないことが見ればすぐできたり覚えられるんだなと感じました。 見ること、その場を共有することは、学ぶことで見ることは、ミラーシステムの作動を促しなにかを学ぶ上で、大きな力となるということですね。『天才を借りる』(10月20日)という日記を書いたことがありますがこれも、ミラーシステムにも関係がありますね。だから、余裕やゆとりなどもそっちがいいなと思う方向があれば望ぬ方向のものをたくさん見てください。そうすれば、自分の心地よい感覚コンフォートゾーン(6月25日)がぐっと、広がっていきます。人は、見ているものに大きな影響を受けるんですよね。楽しい、嬉しい、美味しい喜びが聞こえるものをどんどん増やすと心のエネルギーが増えて余裕やゆとりがでてくるって、そういうことなんだなと思います。 野茂さん、中学生のとき近所のダイエーでご家族でお買い物をするのをたまに見ていました。そして、近所の寿司屋さんで野茂さんの手形と自分の手を比べてたときに「昨日、野茂さん、食べに来ていたんだよ。 兄ちゃんの手の方が野茂さんよっか 指も手も大きいじゃないか。 野球やってたら、ひょっとするかもな。」と、褒めて頂いたのを今でも覚えています。やってみせて、真似をさせて褒めて、喜びを増やす久々に、野茂さんがボールを握っている姿を見てそんなことを思いました。教室をクリスマスっぽくしました。写真は、その一部です(笑)
2008年11月13日
コメント(2)
-
未来の色。
昨日の日記に書いたドラマの一場面とそっくりの言葉を本の一節から見つけました。「ちょっと想像してみてください」「ある晩、あなたが眠りについている間に 奇跡が起こってしまいます。」「そして、あなたが抱えている問題が 解決してしまったとします。」「さて、眠っているあいだに 奇跡が起こってしまったことを どのようにして知るのでしょう。」こうして「ミラクルクエスチョン」は、生まれました。「もしも、奇跡が起こったら・・・」「これまで、どうやって乗り越えてきたんだろう」「明日を3点だけ、ましにするのに 役立つのは、どんなことだろう?」こんな感じで書かれてありました。「明るくいこう」「楽しくいこう」「ガッツだぜ」「頑張ろう」そういう抽象的な言葉ももちろん役に立ちますがなかなか具体的な次の一手が見いだせないこともあります。そして、明るく、楽しくいるのがとってもいいことだと解っていても予定を思い描いたり未来を思い描いたりするときに暗い重い雰囲気がついてまわるようならわたしたちは、少しずつへこんでしまいます。こんなとき、未来は暗い色に包まれその色に影響されて、暗い気分になりますよね。その一方で、未来を描くだけで元気ハツラツ、るんるん気分になれるようなら私たちの日々は、明るいものになります。自然と、見えている世界も明るい色彩の穏やかな景色になります。なにが原因で、なにが結果なのか見当もつかないくらい問題が複雑化しているように見えるときそして、仮にその原因が解ったとしても簡単には、取り除けないことってありますよね。また、すでに、取り除けているのにまだ問題が解決していないときやその原因を取り除きたくない原因が別に存在しているしているときなどもありますよね。自分は、ずっと頑張ることでなんとかしようとしていました。でも最近ひとは、リラックスすることで能力があがるんだなと思うようになりました。頑張ろうとすると自分にプレッシャーをかけてしまいかえって能力が低下するので出来ればリラックスした方が元気になって能力があがるんだなって、体験経験のなかから実感するようになりました。子どもたちにも、頑張りたいなと思うとき未来の色を優しい色に思い描きリラックスしてほしいなと思っています。優しさは、素直さにであり、力だなと思います。
2008年11月12日
コメント(4)
-
ポッキーとタイムマシン。
今日は、ポッキーの日ですね。たぶん、教室でもそんな話題になると思いますがいつも教室に立つと「今日は、なんか、ピンクだね」とか「先週のパープルのやつの方がいいわ」とか「今日のせんせの黄色いネクタイ 実は、隠れミッキーなんだよね」とか「なんで、せんせ、上着着てるん?」などなど教えていると、ドキッとする発言をいうものでほんと、子どもは、よく見ているものです。授業をするたびに子ども達の目の前にあるのは自分の服だったりするので目の前の景色が変われば、気づくんでしょうね。 そんなこともあって、ここ数年毎朝、今日着るワイシャツを手に取る瞬間その日に教える子ども達の顔が、浮かぶようになりました。最初は、前回の授業と服装がカブることがないように。そんな理由だったのですが、いまは、伝えたいこと子どもたちに、マスターしてほしいこと授業の様子が一緒にパッと浮かんできてその時点で、今日は、「これをお土産に帰ってもらおう これをマスターして帰ってもらおう」そんなことが浮かびます。さっき、偶然見つけた藤子・F・不二雄さんの『パラレルワールド』(動画)で主人公の一人が「要は、信じるだけでよかったの。 もうすぐ、未来の私がやってくる 間違いないよ。 もうすぐ来る。」と言っていました。 イメージの世界って、不思議でその物事の最初と最後をイメージしてその通りしていくと意外とスムーズにいけるものです。うまくいかないときって実は、終わり方を明確にイメージしていないってこと多いですよね。そして、未来に向かっていくのではなく未来がこちらにやってくるエンディングがイメージできたらそこに到達するのは、容易ですよね。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』 子どものとき、あの映画が好きでした。タイムマシンに乗ったらまず、どこにいきますか?
2008年11月11日
コメント(0)
-
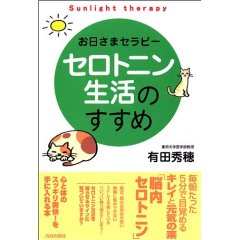
しあわせのリズム
11月4日に放送された日経スペシャル「ガイアの夜明け」『あなた 頑張り過ぎていませんか? ~サラリーマンに忍び寄る“心の病”~』という番組の録画を日曜日の朝、観たんですね。(放送内容は、こちらです。)トヨタ自動車や中国に進出している企業などを題材に「社員の心のケアこそ重要だ」とメンタルヘルス対策に取り組んでいる企業や精神科医の取り組みを取材したものだったのですが部下との対話を終えた支店長さんが「仕事は、どこかしら辛いもので ストレスは、みんなあるもので でも、こうして話をすることで ちょっとは解消すると思います。」と話していて寄り添う気持ちを大切にまず相手の思いを受け止めて聞く姿勢を持つこと。一人で悩みを抱え込まないで周りの人に話すこと話せる聞ける環境を整えること頑張りすぎない環境をつくることが必要それがひいては、会社の業績アップにつながると放送されていました。確かにそうなんだけど。。。なんかしっくりこないというか腑に落ちない感じがしていました。その後、お昼過ぎから大阪国際会議場で東邦大学医学部の有田秀穂教授のお話を聞いてきました。5年前に先生の『セロトニン欠乏症』という本を読ませて頂いて、その後、NHKの番組でお話を聞いていつか直接お話を聞きたいと思っていたのですが今回は、とてもいいお話をたくさん聞きました。それについては、おいおいまとめてみたいと思うのですが印象に残った所を書かせて頂くとちょっと前に(6月20日の日記)『しみじみとした気持ち』と書かせて頂いたように「 いろいろな要因があるけれど セロトニン神経が弱った状況が 心の病や、うつ病や自殺者の増加や キレる若者を生み出していて これは、昼夜逆転した生活や パソコンなど身体を動かさないこと ストレスのかかる状況など 現在の社会文明が起こしたものだ」とお話されていました。現に、文明があまり進んでいない地域ではこのようなことはあまりないのだそうです。セロトニンを活性化するのに3つのことが有効だということがわかっていて1)リズミカルな運動 歩行のリズム、咀嚼リズム、呼吸のリズム 2)早起き、日光を浴びること3)グルーミング 摩ったり、肌が触れ合うことがとても有効だとお話されていました。そして、特に、丹田呼吸、座禅の呼吸など深い呼吸はすごく有効だとしてお釈迦さまの入息出息法を紹介されていました。これも、少し前の日記につながるなと思い嬉しくなりました。(1月8日の日記)講演の最後に、「セロトニン神経は、筋肉と同じような感じで 毎日少しずつトレーニングしていると 鍛えることができます。 これによちすっきりした壮快感が得られ クールな覚醒を得ることができるのです。」とお話されていました。そして、帰りに久々に叔父さんの所に寄って有田先生から聞いてきた話をしたら「それは、そうだな(^v^) 脳にも、身体じゅうの細胞一つ一つにも みんなリズムがあって そのリズムを整える 指揮者みたいな役目が 脳にあるんだけど 朝の日光を浴びることで、 そのリズムがリセットさせるんだ。 だから、リズムを整えるって、大切なんだな。」と、その話の続きを話してくれました。いま、叔父さんは大阪府立大学で学生に生物や生化学を教えているのですがすごく楽しそうに教えてくれました。身体も心も元気になり楽しい状態が続くしあわせのリズムを上手に育てていきたいですね。
2008年11月10日
コメント(4)
-
食品の裏側
「さださん、この本、面白いと思いますよ。」『食品の裏側』という本を2年くらい前に美容院でカットしてもらうときに「待ち時間にどうぞ」と、読ませてくれました。その本は、食品添加物の元トップセールスマンが書いたもので食品添加物が悪者だと恐怖を煽るのではなく添加物の導入を決めた食品メーカーの人たちはどのような過程で、食品添加物を使うに至ったかが書かれていてそれは、それぞれに小さな悩みを解決することから始まったと書かれていました。安くて、簡単で、便利で、長持ちしそれでいて、見た目の美しく、おいしいものこれを経済効率的に求めていくことがいま現在の食品添加物の氾濫を生み出したそう書かれているように感じました。それ以来、食品を買うとき食べるとき裏の食品表示を読むようになってだいぶ食生活が変わりました。そして、昨日、その本の著者・安部司さんの講演会があると、新聞広告で知ったので自分なりの『ものさし』を確かなものにしたいと、聞きに行ってきました。自分が今まで知らなかったお話をいろいろ聞かせてくれたり実際にどうやって作られているのか実演をしてくださったのですが「何事にもメリット・デメリットがあるので 情報を聞いた上で、ご自身で決めてください」というのが好感が持てました。ネットでもいろいろ調べてみるとこの本や食べ物については、賛否両論あり食品添加物の危険性についてはいろんな本が出ているそうですが読んだことがないのでこれを機に勉強しようと思っています。自分の心や身体は自分が食べるものからできているということですね♪
2008年11月09日
コメント(6)
-
ストーリーテラー
『筑紫哲也さん死去…肺がん告白から1年半』学生時代、多事争論が始まるまで机に向かっていて多事争論が始まるとテレビに向かって筑紫さんの学生の自分にもよくわかる今の日本の見方、筋道たてた説明にこんな風に、ものは考えるのかと、いつも感動していました。ここ数年は、見れなかったのですが昨日のニュース23と今朝のフジテレビで彼の最後の多事争論を聞いてやっぱり、彼のこころにはぶれない心というか今の日本を語る上での“目盛の確かなものさし"があるんだなと思いました。ニュースに限らず、何事につけ人は理由を求めずにはいられないません。理由・原因・経緯・事情・バックグランドそういったものを知って「なるほど」と合点しなければ気が済まないものです。そして、できれば、意外性のある理由の方がリアリティーがあって納得がいくし事情を通じた人、知識のある人がいうとすごく納得がいきますよね。理由というのは、つまり物語です。昨日の小人の話とつながるものですが何かを記憶するときに自分の頭のなかで小人を登場させて映画を始めるというか物語を作ると、すごく記憶しやすいです。記憶できていないとか理解できない、覚えられないというのは物語になっていなかったりデタラメな物語、辻褄の合っていない物語になっているということですよね。頭のなかで、映画が始めるという体験ありませんか?
2008年11月08日
コメント(4)
-
こびとのくつやさん。
「さださんは、瞑想とかされていたり 右脳が拓けているんですよね? 私は、自分でしているので ぜんぜんイメージが見えないのです。」「小人のトレーニングとかある って、いうじゃないですか? あれ、本当ですか。。。? 」最近、よく聞かれたりするので「イメージは、見えないと思っているだけで 実は、みんな見えるし、できるんです。 意識が変われば いろんなことが変わってくるんですが ただ、その使い方が解らなかったり 『見えない、できない』と思いこんでいたり なんでもそうなのですが トレーニングすれば少しずつですが できてくるようになるんですよ。 最初は、できないことばかり思うので 『ごっこ遊び』みたいな感覚でいいのです。」そう答えています。『ごっこ遊び』と言えば、自分は、心の中には働き者の小人さんが住んでいる。と考えています。グリム童話の靴屋さんが眠っているうちに靴を仕上げてくれるあの小人の靴屋さんのように無意識のレベルで、その小人さん達が私たちの知らない間にいろいろな仕事をしてくれると考えているわけです。というわけで、テスト勉強をしている子ども達に「解らない、難しい問題が出てきたときには 解らないと焦ったり、 もういいやとすませるのではなく 上を見上げて『この問題について、考えておいてね。よろしく~』 と頼んでおいて、次の問題に進むといいよ。 働き者の小人さん達は ぜひとも試験で活躍してもらうようにしてね。」とお話しています。そうしておけば、他の問題を解いている時に無意識のレベルで、小人さん達が問題を解いてくれるのです。そして、ある瞬間に、ふと解答を思うつくときがあります。実は、フォトリーディングとかで本を読んだり、勉強したりする時に先に、ばーと目を通すと理解がしやすいというのも、実は、肝は、小人さんにあります。そして、「この子、ほんと、やる気が続かなくて」とか「締切りとかテストとかは ほんと、ギリギリにならないと やる気が起こらない」という悩みもよく聞くのですがそれは、小人さんに元気がないからなんです。また、逆の意味でいえば「何もしないで、ウダウダしている」と思っているときに、無意識のレベルで小人さん達は締切やテストに向けていろいろな下準備をしてくれているんですね。白雪姫が7人の小人と仲良く楽しくしていたときにその後に大きなお返しをくれたように元気がいっぱい、エネルギーがいっぱいだと結果をどんどん出してくれるんですね。だから、怒りがたまっていたり悩みがたまっていたり、ぜんぜんやる気がおこらなかったりこれ、全部、ゆとり・余裕・元気がないからなんですね。楽しく、仲良く、元気いようとして美味しい、楽しい、嬉しいと喜びを増やすとゆとり、余裕が生まれるというのも実は、小人さんの効果だと思っています。この成果は、すぐに実感できないと思いますが小人さんに質問する、上手にお願いする「あまり自分で考えない」という習慣をつけると自分自身でもラクになりますし成果も次第に感じられてくるとお思います。「わらかないときは、考えてもわからない」し「わかるときは、一瞬でわかる」のですから。いろいろなことを自分で自分に頼んであとは、放っておくそして、美味しい、楽しい、嬉しいを増やし幸せでいよう、仲良くいよう、楽しくいようと楽しい意識、仲の良い意識で過ごすとほんと、いろいろラクです。実は、この日記を書くときもずっと、何を書こうと考えているというより「今日の日記は、 こんな感じでいきたいんだけど。。。」と思ってから、「よろしくね~」と小人さんにお願いしてアイデアがでてきたら、それをどっかにいかないようにメモしているんです(笑)今日は、実に、ファンタジーな話になりましたね。小人、いるらしいのですが何人か観たことありますか?(笑)
2008年11月07日
コメント(9)
-
Yes, we can
オバマさんが大統領になることが確実になりましたね。ニューヨークのある新聞では「One man changes 」一人の男がこの国を変えていると見出しになっていたと報道されていました。 自分の最も好きなドラマの一つに『ホワイトハウス』という海外ドラマがあるのですがその中で、スピーチライターがスピーチ原稿を何度も推敲する場面が数多く出てくるのです。どの言葉を選び、どの言葉を捨てるかどの言葉を語ると、どの政策につながるのかそのひとつひとつを選びながらそして、どうしたら心が動かせるかそのことを事細かに考えて、相談して最後に、大統領にスピーチしてもらうのです。そんなドラマを見ていたこともあって朝起きてきて、新聞のスピーチ原稿を見て吸い込まれそうになってしまいました。そして、ニュース報道で彼の勝利演説を聞いて自分の国のリーダーではないと解っているのになんだかわからないけれど胸が熱くなり、心が打たれてしまいました。 実は、ここ数日、同じような言葉を聞いていました。「○○だから、私には、できないんです。 さださん、せんせ、どうしたらいいですか?」って。「いま『できない』ってお話されたことを されてみるというのは、いかがでしょうか?」とお話してみるけれど「それが、できないです。 だって、ムリなんです。 だから、困っているんです。」と答えが返ってくるんですね。それぞれは、ぜんぜん違う話なんですが本質的には、あまりにも似通った同じ話なのでこれは、『自分へのお知らせ』なんだろうなと思っていました。そこで、解ってきたことはランチメニューを決めるとかほんの小さなことでさえ、人というのは、新しい行動を起こすこと、変化を嫌う性質を持っていて0か100かの危険を伴うかけよりも70の満足を選択したがる性質をもっていること。そして、自分の能力が試されるような行動になると深層心理における恐怖感は倍増してくることでした。 なぜなら、うまくいかなかったらということを無意識に考えてしまって失敗する自分を見るのが怖かったり能力が足りていなかった自分を見るのが怖いのでいつにもまして、「でも」とそれらができない理由を探してしまうからです。 でも、面白いのは、それでも人は「○○ができたらいいな」「○○やってみようかな」と考えるのをやめないことです。新しいことを思いつくたびに「でも」「ムリ」「面倒くさい」と自分の発想を否定する考えが浮かぶのにやはり、人というのは、心のどこかに「もっと、成長したい」「もっとステップアップしたい」という前向きさを持っているのです。だから、現実と理想のギャップに悩むのですよね。 そして、もう一つ面白いことはじつは、「でも」「だって」「どうせ」という言葉を脳内で発したから「でも」「だって」「どうせ」という理由を考え始めたということなんです。客観的に、論理的にムリだと思っていることは実は、事実ではなくて、その人の習慣的な捉え方だったということですね。ということは、逆に自分にとって新しい物事が起こったときに「いいことありそうだな」「楽しみだな」「面白いな」という言葉を脳内で発して、それに続く「何ができるかな?」であったり「何を変えたらいい?」「何に変えたらいい?」「どのように変えたらいい?」という言葉を脳の中で会話するとそれに相応しいものが現われてくるんですね。 また、元気で、楽しく、仲良くいたり美味しい、嬉しい、楽しいを増やしていこういい気分でいようとただ思うだけで見えてくる条件は変わりいろんなことが解決してくるんです。 体験や経験のなかからこういう発想になった子は自然に、なりたい自分になっている教えていてそんな気がしています。 オバマさんは演説の一番最後で24万人の聴衆、テレビの向こうの人に熱くこう語っていました。「人々に仕事を戻し 子ども達にチャンスの扉を開き 豊かさを取り戻し、 平和を推進しましょう。 アメリカンドリームを唱え 基本となる真実を 確かなものにするときです。 大勢の中にあって 私たちはひとつなのだと 息をし続ける限り、 私たちは希望をもち続けるのだと。 皮肉や疑いに直面したとき 「できない」と私たちに語る人がいるとき 変わることのない信念で答えるのです。 『Yes, we can(私たちにはできる)』と。」オバマさんの演説からなにかヒントを得たように感じました。上の演説は、二番目の動画です。よかったら、ごらんください♪≪動画1≫≪動画2≫
2008年11月06日
コメント(4)
-
ラブ・ジェラ作戦。
苦手な食べ物を食べてほしかったり宿題や勉強を進んでしてほしかったりいろいろ願うことってありますよね。そして、子供のキライな食べ物の代表例といえばピーマン。「ちょっと。」と「ちょっと。」のお話(11月3日の日記)と同じで実は、これも大人が感じているピーマンの味と子供の感じるピーマンの味は違うんです。というのは、、、人間の舌は先端であればあるほど敏感で子供は舌先で味を感じるんです。しかし、年齢を増すにつれて味覚を感じる場所が奥に移り味覚に鈍くなってしまうんです。というわけで、ピーマンの苦味は子供の方が敏感に感じとっているんですしかし、ピーマンの栄養もぜひ摂ってほしいところですよね。「 どうしたら、苦手なピーマンを 食べることができるようになるか?」日曜日にテレビをつけたらそれを心理学的に解決しているそんな番組に出会いました。題して、『ココロの魔法・ラブ・ジェラ作戦』幼児から低学年位のお子さんをお持ちのお父さん、お母さんが子供達の前で美味しそうに食べるだけではなくいちゃいちゃしながら喜んで食べるすると、それを見ていたお子さん達はもうジェラシーめらめらで自らお口を開けて、ピーマン食べてました。番組の中で大学の先生も話していましたが仲間意識って、すごくあって楽しそうに、仲良くしていると自分もその場に入って体験したいんですね実は、学習やお勉強もこれと同じで「どうやったら、子供が自ら進んでやりますか?」このように質問を受けることがあります。子供は習慣を身につける時期だからエネルギーの高い子だと一人ででぎますが子供が完全にできるようになるにはある程度の時間と手助けが必要です。そして、なによりもお父様、お母様が楽しく仲良く勉強する姿を子供に背中で見せたり一緒にお勉強するとすごくうまくいくと思います。どんなことにチャレンジしておられますか?そして、ピーマン好きですか?
2008年11月05日
コメント(6)
-
ヘルシー野菜鍋とスロートレーニング。
昨日、東大阪にあるヘルシー野菜鍋おざわというお店で、野菜鍋を食べてきました。タレントさんがたくさん訪れるようでちょっと前に日記に書いた(10月7日)ナイナイの岡村さんとかたくさんのタレントさんの写真がたくさん貼ってありました。野菜鍋のほかに一品料理がたくさん出てきてこれ以上入らないというくらい食べました。で、帰りに、スーパー銭湯に寄ってお風呂上がりに体重計に乗ったのですが体重計に今まで見たことがない数字が並んでいました(汗)最近、久々にお会いした人に「さださん、ちょっと、ふっくらしたね。」と言われることがあったんですが体重計に乗ることなんてないから本人は、ぜんぜん気が付きませんでした(笑)今朝、起きてちょっと時間があったのでちょっと前に録ってくれていた『ためしてガッテン』を見ました。すると、いまのテーマにぴったりなんですね。それは、『脳をだます!ラクラク最新筋トレ術』内容は、ここにありますのでご覧ください。http://www3.nhk.or.jp/gatten/archive/2008q4/20081029.html要は、がんばったらダメだということなんです。素敵でしょう♪最近、この日記に書いてあることそのままじゃないですか(笑)スローなリズムの方がより成長ホルモンを刺激できるここにも通じるものがありました。続きをいろいろ書こうと思ったのですが授業の時間になってしまったのでまた次の機会に書かせていただきますね♪再放送、明日総合テレビで午後3時くらいからあるそうです。よかったら、ごらんください(^v^)
2008年11月04日
コメント(12)
-
「ちょっと。」と「ちょっと。」
昨日、デパートのエスカレーターを上っていたら小学3、4年生くらいの女の子を連れたお母さんが「服を見に行くから、 ちょっとついてきてくれる?」女の子を見て、そう話しかけていました。思わず、おかしくなって、ニコニコしているとその親子が通り過ぎてから「何が、そんなにおかしいの?」って、聞かれました。「女の子の顔を見ていて お母さんが言った『ちょっと』と 女の子が思ってる『ちょっと』は たぶん違うんだろうなと思ったから 」と言うと「女の子が、服やおもちゃの前で 『ちょっと見ていい』と聞いたりしたら お母さんは、ダメと言ったり 『ちょっとだけよっ』というだろうけど この『ちょっと』もまた違うんだろうね。」という話になりました。たぶん、もう7、8年前になると思うのですがNHKの教育番組で、『自閉症の子をどう育てるか』という番組のなかで自閉症の子は、抽象的な概念を理解するのを苦手とするから「ここで、待っていてね」と言われると「こことは、どこを指すか」不安になるし「ちょっと、待っていてね」と言うと「ちょっととは、どのくらいか」不安になるだから、「ここの椅子に座って、 時計の針が12になるまで これで、遊んでいてね。 お母さんは、お料理つくるから。」と伝えてくださいと紹介されていたことがありました。この番組を見た時に「これって、大人も子どもも みんな口にしないだけで同じだな」と思ったことを覚えています。それ以来、その子の行動を予想してその子自身が先を予測しやすいイメージしやすいそんな言葉を遣うように気をつけています。ほんのちょっとの工夫なんですがこれって、大きなことかなと思っているのですが言葉を遣ったりするときに工夫されていることありますか?
2008年11月03日
コメント(8)
-
ミの♭とレの♯。
「先生方の説明の時間が もうちょっとコンパクトに シンプルになったらと思うの。 授業の時間は、限られているから 授業の時間のなかで、子ども達に たくさん覚えたり、小テストをしたり たくさん演習をしてもらったりしてほしい って、先生方にお話しているんだけれど もうちょっと、うまく伝えたいのよね。」と、一緒にしている啓美先生とそんなお話をしていたことがありました。授業後も、教え方について相談し合ったりすごく熱心に準備してくださっているので教えている先生も教わっている子供たちももっと、楽に楽しく楽しみ、楽しませる関係であったらなと思っていたんです。そこで、授業準備を手伝いながら「わかるから、できるようになるために 大切なのは、誰が主役なのかということ やり方にバリエーション 工夫を持たせることだよ。 何を知っていれば それができるようになるのか たくさん説明をしようとせずに 手順・やり方をマスターさせてあげてね」と話をしました。昨日、名曲探偵アマデウス♯17の再放送をたまたま見て超絶技巧がアクロバットのように繰り返されるリストの「ラ・カンパネラ」は生涯3回、書き直されていて2回目から3回目に書き直す時に♭でいっぱいだったものを♯のものに書き直したと紹介されていました。これ、実は、リストの魔法でミの♭と、レの♯は同じ鍵盤をたたくのに♭だと、上から下りてくる感じ♯だと、上に突き上がる感じという演奏者の心のひだまで読みこんでテンポよく鐘を鳴らす状況をより演奏しやくしてあると、紹介されて難しいものを難しく表現するのではなく難しいものを簡単に表現してくことって、簡単なようですごいことだなと思いました。番組で放送されたのとは違いますが鍵盤の上で、飛び跳ねる『ラ・カンパネラ』よかったらぜひ、ご覧ください(^v^)(動画)
2008年11月02日
コメント(4)
-
引き算。
■「愚か者の誓い」中学教諭が生徒に強要…宿題忘れると7回(読売新聞 - 11月01日 03:04)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081101-OYT1T00024.htm宿題を忘れてきたり宿題をしてこなかったり勉強よりもお話をしてぜんぜん進まなかったりすべてがうまくいくわけではなくうまくいかないことってありますよね。こういうとき、真剣に怒ってみせていたり怒るのはよくないと思っておだやかに話をするというかどうやったら、解ってもらえるんだろうと思ったりするときもありました。子育てをされているお父さんお母さんとお話してもいろんな問題があって言うこと聞かないということがあるかと思うのですが実は、子供たちは、ほとんどが愛情に飢えている、余裕・ゆとりがないから無意識にそういう行動を起こしているということが多いんです。厳しい愛情があって「あなたのために言っているの。 あなたのために、 怒りたくないんだけど、怒っているんやで」と言ったとしても怒って直るものなら、怒る前に直るだろうしこうやって怒るときって子どもは、本当の意味で納得していないことが多いので子どもって、またやるんですよね。このへんのことは『反省するということ』(10月24日の日記)とつながるかと思うのですが重要だからとか真剣だからと自分自身がどうかということよりも相手が自分自身をどういう風に見ているかそのことが問題なんですね。そういう意味では、真剣さということよりも自分自身のゆとりがどれだけあるかでしかないのです。というのは、ゆとりがあれば、笑顔があります。ゆとりがあれば、知恵があります。すべては、知恵が自分自身の問題を解決しその知恵がたくさんあるかどうかは自分自身のゆとりがたくさんあるかでありそのゆとりというのは自分自身の心のエネルギーでその量がどれだけたくさんあるかどうかということにかかっているということなんですね。先日、失敗しちゃった子になぜそういうことになったのかその物事の因果というか説明をしていたら横に座っている子が「せんせ、おだやかに話しているけど 実は、怒っているよね。 せんせ、ちょっとくどいんよ。 もう、時間がもったいないじゃない。」と助け船を出していました(笑)なかなか難しいものです。心のエネルギーを増やしてあげることうまくいく仕組みを作ってあげることそれを本人が納得いくようにしてあげることハッピーを膨らませていく方法幸せを引き寄せる方法は何かを言ってきかせると教え込むことではなく怒りの感情や悲しみの感情の感情をどんどん引いていってその物事の流れをシンプルに見せる引き算かもしれないなと思うようになりました。宿題忘れとかミスとかどうされていますか?もしくは、どうされていましたか?怒ること、叱ること、どうされていますか?
2008年11月01日
コメント(6)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- ●購入物品お披露目~~●
- 【楽天】プロテインと桑茶で整えフラ…
- (2025-11-28 21:10:04)
-
-
-

- 高校生ママの日記
- モバイルバッテリーから煙が・・・(◎…
- (2025-11-28 20:43:35)
-
-
-

- 小学生ママの日記
- 衛生管理者1級を受験したい私
- (2025-11-28 17:00:07)
-







