2008年07月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
忘れものって、多い方ですか?
「忘れ物って、多い方ですか?」先日、高校生になったある女の子と話していたら「提出物忘れとか、忘れ物の多い子ほど、 小さい頃にお母さんに 手をかけてもらっていたんだなと思う子が多いよ。」と、話してくれていてよく見ているなぁと思いました。懇談をしていたり、他でもお話していると「自分から進んでお勉強してくれる子に なってもらえたらと思うのです。 どうしたら、自分から勉強する子になりますか? そして、勉強に限らず 自分から進んで行動していく子にするには、 どうしていけばいいですか?」こう質問されることが、よくあります。そこで、事情をよくよく聞いていると「ちっとも、勉強しないのです。」「今回、成績が急激に落ちてしまって。」という中高生の子の相談の場合から「何度言っても、こちらのいうことに 聞く耳を持ってくれないのです。」というお話や「朝が、いつもほんと一苦労で 『起きなさい』から始まって 『早く食べなさい』『歯を磨きなさい』 『準備をしなさい』と大変なんです。」というお話まで、ほんと、様々です。でも、ここには、『待ち切れない』という共通の心があります。待ち切れない人のアタマのなかに、お子さんに対して、なにか理想的なラインのような状態があってその状態に足りていないと減点方法で見てしまう心がそこには、あるんですね。『このままだと、時間に間に合わない』『このままだと、○○にはならない』というようなこと、ありますよね。自分も、そういう心あります。で、『なんで、しっかりしないの。』『なんで、ちゃんとしないの。』と手をかけてしまう、口を出してしまう怒ってしまうんですね。『しっかり』とか『ちゃんと』ではなく『どうしたら、うまくいくのか』その仕組みを教えてあげられたらなと思っています。子どもだから、ミスもするだろうし動きが遅いことも、たくさんあるだろうし同じことをしつこいくらい言ってもなかなか直ってくれないこともたくさんありますよね。でも、『怒られてしまうから』というのではなく『自分に必要なことなんだ』とか『こっちのほうがいいように歯車が回るのだ』と、子どもの心にほんとに根付いたときにはその子は、自ら動いてくれるようになります。だからこそ、こちらが、まず時間的にも心理的にもゆとり、余裕をもってこころがここにある流れのいい状態をやってみせて、教えてみせて手をかけずに、目をかける。自らを喜ばせることって、そういうことじゃないかな?と思います。授業は、9時からなのに7時に、教室に入ってきて自ら勉強している中学生をみてそんなことを思いました。
2008年07月31日
コメント(6)
-
なかよくいること。
私たちは、当たり前だと感じていること当然だと考えていることと自分のこころのなかの部分相手が話すことやすることに相違がある場合、違和感として「ネガティブ゙な感情」が湧いてきますよね。「なんで?」とか「こっちは、なかよくしよう と思っているのに。。。」 とか「なにが、悪いのよ。」「私は、ちゃんとやっている。」「私は、ぜんぜん悪くない。」「なんで、これがわからんか」などなど。夫婦間、親子間の日常の小さな出来事から大陸間、国家間に至る大きなことまで相違というのは、たくさんあります。もめようと思っていなくても人というのはなにか思って生きているので自分が思っている意見が正しいと思うほど、ぶつかってしまいます。しかし、ここに『なかよくいよう』という気持ちを持つといろんなことが変わってきます。『なかよく』というのは相手を思いやる行為相手を推察する行為なので穏やかに、ソフトな対応になってくるのです。これは、決して、言いたいことを言わないでおこうというのではなくて言いたいことを言っても相手を思いやる気持ちがあればその対応は変わってくるというわけなんです。そういう意味で穏やかで、笑顔を持ってというのは大切だなと思います。自分を大事にするのと同じように愛を持って考えているときは「心地よい感覚」が湧いてきます。だからこそ、『感情に気をつけなさい』って言われるんですね。なんにもなくても仲良くいられること。これが心地よければ同じ状態のものが引き寄せられますね。自分、家族、相手、過去、未来、勉強、仕事、夢などなどいま取り組んでいるものいろんなものと仲良くいれたらその世界は、どんどん広がっていきますね。なかよくいることって奥深いなと思います。
2008年07月30日
コメント(2)
-
流れを仕組み化する力。
「実力に明らかに 差がある場合は別として 実力にさほど差がない場合 準決勝以上くらいになると どんな準備をしているのか? どう流れを引き寄せるか? これが勝敗を左右するんですね。 野球って、ホームランやヒットなど 派手な面が、結果として表れ 取り出されますけれども その前には伏線があって 多くの場合は、四球やエラー 配球の選択ミスといった 自分達のミスがきっかけで 自分達が流れを手放したことで その結果が起こっているものなのです。 監督の仕事は、いま流れが どちらに向いているか見定め その流れに逆らわないようにすることと いろんな状況への準備を日々、確認して 周知徹底しておくことなんです(^v^)」一週間分のワイシャツをアイロンかけながら高校野球南大阪大会決勝近大付属VSPL学園を見ていたら元近大付属監督の解説の方が試合の途中で、そう話していました。ここ一ヶ月くらいの間に『プロフェッショナル』でヤクルトの宮本慎也さんと福川捕手のやりとり読売系列のスポーツ番組で埼玉西武の渡辺監督とバッティングコーチのデーブ大久保さんの指導方法カンブリア宮殿の録画で野村監督の野球理論とまーくん、山崎選手のやり取り一昨日の高校野球南大阪大会決勝の近大付属とPL学園の試合と同じテーマのものが見えてきています。自分が、そっちに意識を向けているから同じ趣旨のものをアンテナで拾っているというわけなのですが『流れを感じる力と それ、または仕事を仕組み化すること』『流れを確認し 誰でも運用できるように チェックシート化していくこと』これに、関係するものをたくさん拾ってきています。自分のしていることの流れ教室の流れ、いろんな流れを少しずつですが、シートにしていくとこんなことにも気がつかなかったのかという発見の連続です(笑)準備をしたら、準備をしただけの結果や余裕が生まれてくるものですね。もう少し追究していきたいと思っています♪
2008年07月29日
コメント(2)
-
最後の授業。
本屋さんに平積みになってずっと気にはなっていながら手に取らなかった本がありました。それが、『最後の授業』という、この本。以前、『ハーバードからの贈り物』というハーバード大学を退官する教授の最後の授業を集めた本があってこの本は、その本の二番煎じでは?と勝手に、思っていたからなんです。そして、今朝ネットで「最後の授業」の著者ランディ・パウシュ氏死去というニュースを知り、あの平積みになっていた本を思い出し余命半年と宣告された彼の『最後の授業』がyoutubeで観ることができると知って見てみたんですが、釘づけになりました。ご覧になったことがある方もたくさんおられるでしょうね。まだの方は、お時間があればぜひご覧になってください。ランディ・パウシュ氏 「最後の授業」上のページに行くと、右上の案内からyoutubeに飛べるようになっています。「私が、これからお話したいのは 子どもの頃の夢をどうやって実現できたか そして、他の人の夢の実現を どうやって助けたかについてです。 みなさんにも夢の実現を実践してほしい。 そして、人の夢の実現を手助けすることは とても楽しいものです。」と始まる、最後の講義はユーモアがあって至極の言葉がたくさん並んでいます。たくさん、メモした言葉があるのですがそのなかから、いくつか書かせて頂きますね。学生のころ、フットボールをしていた僕は、ある日、コーチに欠点を徹底的に直されました。何度も。何度も。何度も。終わると、コーチは言いました。「しごかれたね。 でも、それは、いいことだ。 間違いを正されるのは 期待されている証拠だよ。」謝りを指摘されない環境は自分のためにはなりません。 実は、子供たちにスポーツを習わせるということは『頭のフェイント』なのです。スポーツを習えば技術やルールなど多くのことが身につけます。でも、もっとも重要なことはチームワーク、忍耐力、スポーツマンシップ一生懸命立ち向かう価値逆境に立ち向かう能力です。このように何かを間接的に学ぶことを私は、『頭のフェイント』と呼んでいます。学んでいるときは理解できないがあとになってわかることを教えること。それが、『頭のフェイント』です。そして、『頭のフェイント』の達人は本当に教えたいことを、相手が気付かないうちに教えています。 夢をかなえる道のりに 障害(壁)が立ちはだかったとき「あんなに努力したのに」と言いたくなるとき、言っているとき僕は、いつも自分に、こう言い聞かせてきました。『レンガの壁が そこにあるのには、理由がある。 僕たちの行く手を阻むために レンガが、あるのではない。』 と。レンガがあるのは夢に対する思いの強さを証明するためなのです。 そして、幸運は、準備と機会がめぐりあったときに起こるものなのです。夢をいかにかなえるかが問題ではないのです。いかに人生を進めていくかなのです。正しい方向に歯車を進めれば運命が導いてくれます。そして夢の方から、あなたに向かってやってくれるのです。夢の実現を諦めてはいけません。 さっき、近所の本屋さんでDVD付きの本を買ってきました。もう一度、ゆっくり観てみたいと思います。そして、こんな素敵な先生に出会えたこととても嬉しく思います。ランディ・パウシュ教授天国でも授業をしていそうですね。
2008年07月28日
コメント(8)
-
いいことを考えると。
今朝、姪っ子ちゃんが北海道旅行に出かけて行きました。いま話題の旭山動物園などにいくらしく1か月前から、その話題で持ちきりで昨夜は、もう興奮気味でした。「旭山動物園にいる動物で 楽しみな動物、ベスト3は、何?」と、前に齋藤孝先生に教えて頂いた『3つあげる』(7月13日の日記)というのをやってみると「白クマ、ペンギン、アザラシ♪」と話していました。旅行って、旅行を準備している時から『楽しくなる』って、ほんと不思議ですね。いいことが起こるからではなくいいことを想像するだけで楽しく、幸せになれるんですよね。昨日の日記(7月26日)は、私たちが言葉を使って何かを話すときその話を聞いている相手は話し手が話す言葉を聞きながら、その人自身の過去の体験・経験に結びつけてその言葉を理解していて何か言葉を聞いた人は無意識にその言葉に反応するイメージを見たり、聞いたりしてしまうのでイメージしやすいようにカラーの映像や動画を見せてあげるとよいというお話でした。先ほどの「白クマ、ペンギン、アザラシ♪」であれば、何か映像がでてきますよね?また、『ハワイ』と言われたら、『白い砂浜』とか『フラ』『サーフィン』とか『青い海』とか映像が出てきますよね。そして、このどちらもすごく陽気な感じがしませんか?つまり、ここで大事なことは自動的にその言葉に関連したイメージをみてしまいイメージや音は、感覚や感情につながっているということなのです。逆に、愚痴など否定的な話を聞いていると知らず知らずのうちにそれに反応する否定的な映像を見てさらにその否定的な映像に反応する否定的な気持ちを感じてしまうことがあるのです。そして、その否定的な気持ちが繰り返されると否定的な現象を引き寄せてしまいます。先日起こった八王子で死傷事件に関連して今朝ニュースで、「事件の証拠として、容疑者の自宅から 容疑者が読んでいた本や漫画や 使用していたパソコンを押収した。」と報道されていました。このような理由からも何を目に触れ、何を聞きどんな環境に身をおくかは、とても大切なことだなと思っています。幸せでいよう、楽しくいよう、なかよくいようといい言葉を遣い、素敵なことを考えるという心のエネルギーを増やす工夫とできるかぎり、否定的なことを聞かない環境に身をおいて否定的なことをイメージしないで心のエネルギーを減らさない工夫は幸せを引き寄せる、大切な要素ですよね。「いいことがありそうだ。たとえば。。。」と、楽しみなことを些細なことでもいいので3つあげて”3ついいこと”を上げた後は「こんなとき、どんな自分でいたいかな?」「じゃぁ、そのために、今すぐできることは?」と、ただ思いを巡らせるだけでいろんなことが変わってくると思います。「いいことを考えると なぜいいことが起こるのか?」こんな風に思うのですがどう思いますか?
2008年07月27日
コメント(12)
-
絵で英単語とお祭り。
先週の土曜日、近所の神社のお祭りに行ってきました。いか焼きやたこ焼き綿菓子やリンゴ飴の夜店から香ってくるいい匂いが鳥居まで続いていました。ねじり鉢巻きに白いはっぴをきたおじさんたちがいてその横で、子どもたちがドンドコと太鼓を叩いていて一緒にいった姪っ子ちゃんはお賽銭箱でお参りをした後そのすぐ脇でやっていた金魚すくいとヨーヨー釣りに目をやりヨーヨー釣りに魅かれスティッチの青いヨーヨーを釣っていました。このことを次の日に思い出した時にちょっと前に読んだ神経言語学の本とつながって『これは、自分が体験したことだけど 相手に、これを伝えるとき この話を聞いた相手は、当然ながら 自分が見たお祭りの光景ではなくて 相手は、相手の過去の体験や 経験に照らし合わせて 想像しながら聴いているのだよな』って、思ったんです。これ、当然と言えば至極、当然なことなのですが私たちは、物事をありのままに見ているのではなく自分のフィルターを通して、自分なりのものの見方で見ています。だから、同じもの、同じ言葉でも人それぞれアクセスする体験や経験が異なるので捉え方も異なりそれに対する対応も異なってくるのですよね。『話が通じない』というのはこのへんが原因でもあります。そして、記憶は体験とともに記憶されるので『私たちは、言葉を使ったり 聴いたりするときに 言葉からイメージすることを 意識していくとぜんぜん違いますよ。』(2008年6月7日の日記)と、日記に書いてきたりお伝えしてきました。これ、自分ではこの重要性を解っていたのですが何度も何度も漢字や単語を書いても覚えることができなくて勉強自体が嫌になってきたり算数や数学の問題をたくさん解いているのにぜんぜん点数に跳ね返ってこなくて苦しんでいる姿を見るたびに自分が見ているアタマの中の映画館の3Dシアターのような情報空間を『この子にも、どういう風に 体験させることができるんだろう?』と思っていました。で、最初のお祭りの話に戻るのですがお祭りの話をしていたときにタコ焼きかイカ焼きの匂いやヨーヨーや金魚の映像太鼓のドンドコという音が聞こえてきませんでしたか?このように言葉を聞いた人は、無意識にその言葉に反応するイメージを見たり聞いたりしてしまうんです。意識的にイメージが作り出せればそれに越したことはないのですがその段階まで至っていないときには自分が見ているイメージを伝えるのではなくその人自身がイメージを形成しやすいように上手に誘導してあげたらいいと気付いたらすっとマスターしていくようになりました。具体的には、新しいものを覚えるときに「覚えなさい」とか「想像しなさい」ではなくてそのイメージのものをカラーの絵や写真で見せればいいと思い教室では、そこを意識した取り組みをこの夏は、特に重視しています。中学生には『絵で英単語』というのをしているんですがそこに出てくる動物の描写の絵をゲラゲラ笑いながら見ていてその単語だけではなくその単語に関連して入試で問われることも合わせてお伝えしているのですがこの取り組みを始めるまでは「これも、覚えなきゃいけないの どれだけ増えていくんだよ。。。」とか言っていたのに「これも合わせて覚えたらいいね」と、合わせて覚えてくれるようになりました。「『Banana』を『バナナ』ではなく あの黄色いイメージで覚えてもらいたい。」(2008年6月13日の日記)こう投げかけていたのが少しずつカタチになってきました。自分がアタマで見ている映像や脳内での会話に、意識を向けるとすごい空間が広がっていることにすごく気づくと思います。ぜひ、覗いてみてください♪明日は、今日のこのお話に関連して脳内の会話のこととか脳内イメージがもたらすもの肯定的な言葉がなぜいいのか?そんなことについて、書けたらなと思っています。『バナナのすじ』(2009年06月13日)
2008年07月26日
コメント(6)
-
本腰入れて。
「学校の授業は、50分なのに なんで、ここは60分なん? でも、ここで座ってると あっと言う間に過ぎるんだよね。」と、中3の男の子がいうとそれを聞いていた女の子が「学校で、授業受けているときに なんとか必死で起きて 先生の話を聞こうと思うけど 睡魔が襲ってくるんです。 どうしたら、いいですか?」と、聞いてきました。「眠いときって、机に肘がついて だんだん、そこに体重がのり 前かがみになっていない? 疲れや食後の満足感もあるけどそれがね、眠くなる原因なんだ。 腰が立っていないからなんだよね。」「『腰を立てる』って?」と聞くので、詳しくお話しました。腰を前にくっと入れて座ると骨盤に対して、背骨がうまく乗り長い時間いい状態でいられます。そして、深呼吸で呼吸を整えると脳にたくさん酸素も入るし神経の通りはよくなるし心も落ち着いてきますよね。教えている自分でさえ小学生の子どもたちが机に1時間座り続けているのは奇跡に近いことだと思います。勉強ができることへの基礎はいい状態でどのくらいの時間机に座ることができるのかここに、かかっているといっても過言ではないです。『本腰を入れる』って身体の使い方が脳の使い方物事の取り組み方にあったとても素敵な言葉ですね。今朝、新聞を読んでいたら話の『さわり』とは話の最初の部分ではなく話の核心部分の意味であって『檄を飛ばす』とは声をあげて、発破をかけるのではなく自分の考えを広めようとする意味だと、書かれてありました。ちゃんとした仕組みを知ると有機的に、物事を動かしていけますね。≪追記です。≫ミクシーにもこの日記を書いていたらマイミクの莞爾さんが「ゲキを飛ばす」の「ゲキ=檄」とは古代中国で役所がおふれを告げるために出した木札(文書)のことで、その檄文を急いで多くの人に回すことを「飛檄」と言っていたことから「檄を飛ばす」が生まれたそうです。この「檄」を激励の「激」と勘違いをしている人が多いのかも知れませんね。 と教えて下さいました。で、自分で『さわり』についても知りたくなって調べてみました。 『さわり』とは浄瑠璃のことばで 浄瑠璃は義太夫節が中心で そこに他の流派のいいところを取り入れることがあり、 その箇所(サビ)をさわりと言い他の流派の節のいいところ(サビ)にさわることが語源だとされているそうです。 その後、義太夫一曲のうち最大の聞かせどころの意となり、 さらには、一般の話や文章における 感動的な部分の意味となったんだそうです。 ところが、本格的にではなく手近な所に ちょっと触れるという「さわる」のイメージから 曲や話の最初の部分と結びつけられて 勘違いしているそうです。 深く詳しく知ると、嬉しくなりますね。
2008年07月25日
コメント(8)
-
怒りのコントロール。
午後の授業が終わって、3階の教室から2階の教室に移動しようと教材を揃えていたら廊下から、男の子の泣き声が聞こえてきて顔を真っ赤にした男の子が入ってきました。カラダをガタガタ震わせ肩を揺らし、全身で泣いています。この時点で、何があったかはだいたい想像は、ついていたのですが「どうしたんだ?」と、ぐっと両手を握っている彼を人がいないコピーの部屋に入れて尋ねました。「僕は、なんにもしていないのに K(年上の男の子)が蹴ってきて!」「そうか。。。 なんにもしてなかったのに Tは、蹴られたのか。。。。 蹴られる前は、何をしていたんだ?」「Kが携帯を見ていたから 『何、見てるん??』って覗いたの。 聞いても無視するから、また聞いて覗いたの そしたら、いきなり蹴ってきたんだ。 『蹴ることないだろう』 って、突進していったら また、ボコボコにつかまれて。。。 なんにもしていないのに 何回も何回も蹴ってきたんだ。」そう話す彼の腕を見るとTシャツから出ている左腕のところが手に爪の後がついて、真っ赤になっています。「腹が立つよな。。。」というと「腹が立つ、なんで、 暴力受けなきゃいけないんだ。」と震えていました。「ここに居てね Kとちょっと話してくるから。」と、2階に下りて、2階にいるKに「なんで、せんせが来たかわかるな?」と聞くと「わかる。」と話してくれたので「何があったんだ?」と聞くと「俺が携帯を見ていたら Tが『ナニみてんの?』と聞いてきて うっとしいなぁと思っていたら まだしつこく言ってきて、 携帯を取ろうとするから、 うっとおしかったから、蹴った。 」と話していました。「携帯って、プライベートなものだからな。 自分の部屋を覗かれるように感じて うっとしくなったから、蹴ったのか。。」そう話すと「実は、この休憩の前にもいろいろあって Tに、悪口を言われて、それもムカついていて。」と話してくれました。「悪口を言われたときは、堪えたんだな。 でも、携帯を覗かれて、嫌だったんだろう。 で、蹴ってしまったんだな。 これ、Kに限らず皆に言えることなんだけど 嫌なことをされたとき、 嫌だと胸がググッとするときあるよな その時、嫌だったからって その嫌な気持ち、傷つけた心を 相手も同じ分だけ傷つけと攻撃することないんだ。 面倒くさくても、嫌な気持ちは、説明しないと なかよくできないし、うまくやっていけないんだ。 いま、刺したり、人を轢いたり ホームから突き落としたり いろんな事件起こっているよな。 あれは、ほとんどのケースが 感情のコントロールができないから 起こってしまっているんだ。 自分の気持ちを説明できなかったり 面倒だから相手との交渉しなかったり ということが繰り返されて あそこまで、起こっているんだ。 やったことは、許されないことだけど 彼らも僕らと同じ感情を持った人間なんだよ。 でも、相手を傷つけてしまえば その人が大事にしているものを奪ってしまう。 だから、手を出してしまったら 被害を与えてしまったら 世の中では、先生たちみたいに 心のことまで見ることはなくて どちらがどちらに 外形的に被害を与えたか ここでしか見てはくれないんだ。 嫌な気持ちになるのは 今回のことだけではないだろうから 今回をきっかけに 嫌な気持ちをコントロールすること 嫌なことは、相手に説明する努力をすること。 そして、今回蹴ったことは 悪かったと思っているなら 謝りにいこう」と3階につれていきました。座っているTにKが真剣に謝りました。けれど、Tの怒りは治まりません。「蹴られて、殴られて、 『ごめんなさい』で、許されるか。 こっちも同じだけ殴らなきゃ気がすむか。 これで、許されるわけがないだろう。」と怒りが止まりませんでした。「でもな、やり返したら 攻撃が繰り返されてしまうんだ。 その怒りをぐっと握ってごらん。 この怒りを手放せることできる?」と聞くと「こんなんで、許されてたまるか。」と体をカチコチにしていました。その後、彼をそっとしていたんですが彼が握った怒りの玉が彼の手元から離れていくと机にうつぶせて寝てしまっていました。刑事政策とか被害者心理とか大学で学んだことを思い出したり感情のコントロールや怒りの感情の処理方法いろんなことがつながった一件でした。いろいろ書きたいのですが長くなったので、またまとめてみますね。
2008年07月24日
コメント(8)
-
自分のなかの自分。
「水分補給は、小まめに。 『ノドが渇いた』と感じたときは 実は、かなり手遅れの状態で そう感じないとき、体も、脳も、 ベストパフォーマンスがでるのです。」こんな新聞記事を読んで『そういえば、バレーボールの中継を見ても タイムアウトのたびにドリンク飲んでるなぁ』と思ってから意識して、お茶とか、水とか小まめに、水分を補給するようになりました。『疲れたから、一息いれよう』『なんか、のどが渇いた、飲みたい』というときは、快復するのに時間がかかっていたのに『ワタシのカラダは、水からできている』なんて思いながら、自分の状態について意識して観察しているとのどの状態だけではなく、体調や心の上でもずっと、楽しく、楽に過ごすことができるようになりました。自分で自分を喜ばすこと心を散漫させず、目覚めていくことは自分の心の動き、体の動き、言葉の動きを見守ること。だから、今何を考えているのか、心地よくいるのかを 気をつけなさいって言われるんですね。 自分で自分を楽に楽しく 自分で自分を幸せにする方法は自分のなかにいる自分に語りかけることなんですね。ではでは、9時から授業なので授業してきます(笑)
2008年07月23日
コメント(4)
-
右脳教育。七田眞先生教育講演会
昨日は、堺の産業創造センターであった『右脳教育で 将来リーダーとなる子どもを育てよう』と題した、七田眞先生の講演会を聞いてきました。七田先生のお話を聞かせて頂くのは去年のしちだコミュニティ以来で1年ぶりだったので、なんだか懐かしい気分でちょっとワクワクしていました。講演会の始めに、主催者である中百舌鳥教室の冨田先生が「みなさんに、七田先生をライブで 感じて頂きたいと思うと同時に 自分自身が、先生とお会いすることで 軌道修正したり、微調整したりするためにも 1年に1度お越しいただいているんです。」とお話されていましたが自分も今回の講演会は特にそんな気分になりました。七田先生が「朝の連続ドラマで いま『瞳』という番組が 放送されていますね。 あのオープニングで、 綺麗なトロンボーン演奏が 聞こえてくるのですが あの綺麗な音色を吹いているのは、 中川 英二郎さんといって しちだの卒業生なのです。」とお話してくれてその中川さんのお話を例に「勉強する前に深呼吸をして 呼吸を整えて、目を閉じて これからすることをイメージさせる それでは、目を開けて 『その通りに、やってごらん』 と中川さんも小さいころから 教室の先生が導いてきたんですよ。」と、右脳のイメージ力を活かした右脳イメージの学習法右脳の高速記憶法についていろいろお話してくださいました。何かを身につけようとすると時間がかかりますがイメージのなかで練習させそれから実際に練習すると驚くほど、速く高い水準の練習ができます。もうすぐ、オリンピックがありますがスポーツ選手が取り入れているように子どもにイメージ力を育ててイメージのなかで練習するバーチャルリハーサルをさせることはとても大切なことなことだと思います。そして、「いまの学校教育は理性教育ですが 右脳教育は、感性教育なのです。」と、数日前に、「感性の高い人」と日記に書いたことの一つのヒントを頂きました。「感性は、自分への愛、 他人への愛とで成り立っています。 どの人も愛がほしい、自由がほしい 幸福がほしいと思うものですが お友達もまた、同じように 愛がほしい、自由がほしい 幸福がほしいと思っている ということを教えています。 問題行動、犯罪、トラブルの大半は 思いやりをもつことができないことから 起こっています。 そして、子どもの問題行動は、 親の愛を求める無意識の気持ちから 起こっています。 だから、愛の気持ちを育てていくこと これを、大切にしています。 お父さん、お母さんから 愛をもらって育つと、子どもは安心ですよね。 愛を与えていくと 子どもの力は、どんどん発揮されるんです。」そう、柔らかく温かくお話してくださいました。素質をよくする。記憶力を育てる。ちょうど夏期講習を前にしていたので自分の原点を見直すような内容となりました。昨日聞いたことをアレンジして生徒たちとやってみていいものは、お伝えしていたいなと思っています。今日から、朝9時からから晩10時まで授業なのですが子どもたちからは、「なんで、そんなにニコニコなん? いつもよりも、ハイテンション ハイテンポだね。。。♪」なんて、言われています(笑)不思議なものですね。
2008年07月22日
コメント(10)
-
国語を読解する前に。
夏期講習など、講習会で国語をするときにちょっと大変だったりすることがあります。それは、課題文を読むこと。学校の国語の文章ならさんざん本読みをしているので読まなくても、問題の答えが解ったりするものなのでそういうことに慣れている子ほど初めて読む文章は、うまくいきません。説明文も小説文も課題文を読まないことには問題を解くことはできないのですが読むことを面倒くさがる子結構いますよね。「真剣に読みなさい。」とか「ちゃんと読みなさい。」と言ったところでなかなか読むようにならないしそもそもそんなことを言ってちゃんと読める子は、真剣に読んだ時の楽しさやメリットをしている子です。というわけで、言うことを聞いてくれなくなると「『ちゃんと、読みなさい』と言ったでしょう」と怒って、強制的に読ませるか「じゃぁ、せんせが読むから、聞いててね。」ということになるんですよね。自分も昔、そうでした(笑)でも、『読むから、読んでいてね』というときには子どものアタマは、違うところに意識が向いていて『ちゃんと、聞いていたのか??』と思うことが、しばしばでした。そんなとき、ちょっと前の日記にも書いた斎藤孝先生の「声に出して読みたい日本語」が一大ブームになったころ、テレビ番組で齋藤孝さんが、小学生たちと本読みをしていて「、」や「。」で交互に読んでいる姿を見ました。自分もそれを見てから本読みが上手じゃない子には交互に読んでみたりしています。自分の番がすぐにくるのでかなり真剣に本を読んでいます。子どもって、ちゃんとするとかじっとするというのが得意ではないのですが腹から声を出したりリズム・テンポに乗るのはすごく得意なのですね。そして、こっちのテンポやリズムにすごく反応してきます。昨日、姪っ子ちゃんのハワイアン・フラを見てきたんですが先生の鳴らすフラの楽器や掛け声に合わせて上手に踊る姿をみて、通じるものがあるなと感じました。リズムやテンポを整えることそのリズムやテンポをこちらがリードすることは楽しみをふくらますことになりちゃんとした状態を自然に伝えることになりますね。「勉強しなさい」というのではなく勉強とは、どうするか分からない子が多いから どうやって、勉強するのか どうやって、問題を解いていくのかその年齢、その年齢でやり方は異なるでしょうけどこの夏は、特に一緒にやっていけたらなと思っています。そして、ぜひ、いい文章を、親子で交互に読んだり読み聞かせしてあげたり子どもが読んでくれる本読みに細かく評価をしてあげたりしていいリズム、テンポを体感させてあげてもらえたらと思います。
2008年07月21日
コメント(0)
-
感受性が高い人。
昨日の日記(7月19日)にみさきよしのさんから『感受性豊かであるからこそ 見えないものが見えるのでしょうね。』とコメントを頂いて『感受性が豊かである』ということについて少し考えていました。感受性を豊かにするコツ自分で考えてみて3つあるのではないかと思います。1つは、みさきよしのさんに教えて頂いた『自分を観察すること』(2005年9月7日の日記)。目の前の現象ではなく自分の心の動きを見ることをみさきさんに教えて頂いてもう3年くらいになるんですがこれが大きなきっかけかなと思います。そうやって自分をみていることで自分の元気は、一定ではないということに気づき元気の素を見ていく(2008年7月9日の日記)と元気を増やすこと、減らさないことに意識して、工夫することができるようになりました。2つ目は、カラダをケアすること。自分のカラダをケアすることも自分に意識を向けることですし感受性が豊かな子どもほどカラダが柔らかいしリラックスしているんです。3つ目は、はじめは、花を見てキレイだと思わなくても空を見ていい天気だと思わなくても運がついてなくても「キレイ、いい気分、運がいい』と自分の口で言葉で声に出して自分自身に聞かせること。こうすることで、感受性って、どんどん高くなってくるんじゃないかなと思います。そして、いろんなことに、愛情をかけて笑顔で、ゆとりで接してあげることで感受性って、高まってくるなと思います♪幸せだと思った時から幸せは、始まりますよね。感受性が高いってどんな感じだと思いますか?
2008年07月20日
コメント(8)
-
見えないところが見える人。
昨日、子供たちに『あゆみ』や『通知表』を見せてもらいました。返ってきたテストを進んで持ってきたり通知表を自ら見せてくれるようになるって、とても嬉しいなと感じながら「よかったね。 ここ、褒めてもらったんだ。 できるようになったんだね。」と声をかけました。勝負の夏を迎える受験生に最近「いいものを持っているから この夏、本気で準備したら 大きいものが得られると思うよ。」と意識して声をかけているのですが今は見えないその人の今後を期待を持って見守ろうとすること背中を押すことはとても大切だなと感じています。昨夜、久々に前の教室で一緒に講師をしていた後輩の先生と食事をしました。「自分が楽しくいよう、仲良くいよう と思うものを増やしたらいいよ。 もっと、夢に携わる時間を増やしたらいいよ。 夢と携わっている時間が長くなると やっぱり、夢をかなえるんだよ。 そして、時間をかけたものは やっぱり、楽しくなるし 楽しくなるから、続けていけるものだよ。 いいもの持っているんだから もっと、頭を使って もっと、工夫していこうよ♪」と気付いたら彼にそう話していました。彼との話を帰りの電車で振り返ったとき自分も、小・中・高の学校の先生剣道道場の館長先生に「いいものを持っているね」と言われたり大学の教授や弁護士の先生右脳教育の七田眞先生や宝地図の望月俊孝先生に食事に連れていってもらったりしたときに「それ、いいね。いいものを持っているね。」と褒めてもらったなと思い出し自分もそういう年になったんだとちょっと可笑しくなりました。ないものを求め見えないところを見ようとすること。奥手なのではなく、慎重なんだ等と他人に対して、否定的な見方はせず肯定的に見る、想像力を働かせること。「いいものを持っていそうだから そのうち、化けるかもしれないよ」と見えないところをみて今は見えないその人の今後を期待を持って見守ろうとすること。見えないものが見える人。自分にも他人にもそういう人でありたいなそう思って、帰ってきました。
2008年07月19日
コメント(4)
-
復活の呪文。羽鳥ガリバー社長
大阪や和歌山の小中学校は今日で、学校が終了というところが多いですね。というわけで、夏期講習の準備をしています。 さてさて。。。。昨夜、月曜日に放送されたカンブリア宮殿の再放送をBSで見ました。今回のゲストは、中古自動車の買取をしているガリバーの羽鳥会長。道を車で走っていると黄色いバックに緑の字で『Gulliver』と書いてある看板をよく見かけますよね。「『買取専門』って よく聞くけれど、 こういうことだったのか?」と思いながら見ていたのですがガリバーという会社を1代で年商1900億円を稼ぐ中古車業のまさに巨人にした羽鳥会長のお話を聞いていると昨日書いた日記につながるお話がたくさん出てきました。そのなかの一つが、羽鳥さんが「プラス思考は、訓練でなれる。」と話していたこと。これ、羽鳥さんのお母さんから体験で学んだ話なんだそうです。羽鳥さんのお母さんは、羽鳥さんが子供のころ家に、どろぼうが入った時に入ってきたどろぼうに、食事を与えておにぎりまで持たせたんだそうです。そして、これには後日談があって数年後に、そのどろぼうが家に訪ねて来て「あのときは、ありがとうございました。 あれから、事業を興してそれが大成功し こんなにも、稼げるようになりました。」と、石炭を山積みにしてもってきたんだそうです。。まるで、日本昔話のような話ですよね(笑)そのお母さんの口癖が「よかった。よかった。 これで済んで、よかった。よかった。」だったんだそうです。自分も、この『復活の呪文』いつのころから口にするようになったのかすっかり忘れてしまいましたが「よかった。よかった。 これで済んで、よかった。よかった。 で、これから、どうしよっか? うまくいくには、 どういう仕組みにしたらいいかな?」というように何か、マイナスに感じる出来事が起こるたびにとりあえず、心に唱えるようになったら腹が立つこと、落ち込むことがほとんどと言っていいほど、なくなりました。そして、何よりも切り替えが早くなり次への一手が打ちやすくなりました。一見、マイナスに見える出来事となかよくするようになったからなんでしょうね。番組のなかで、村上龍さんが「毎度、毎度、『よかった。よかった。』 と言っていたら、バカみたいじゃないですか?」と、羽鳥さんに話していましたが「いや、いや、真剣に思っているんです。」と羽鳥さんは、答えていました。『心に笑顔を持つこと』(7月17日の日記)とは、こういうことですよね。人は、ついつい求めてしまう生き物で生きていると、こうあるべきという価値観をもってしまうものなので「なんで、なん?」と思ってしまいがちですが「よかった。よかった。」という言葉は心に余裕やゆとりを持たせる復活の呪文でみんなが探しているリセットボタンは、ここに隠れているようだ。と感じました。 「ええやんけ。」(7月4日の日記)と「よかった。よかった。」という、この二つの呪文。「この夏、自分を変えたい」と、飛躍の夏にかけている子供たちに、そして、自分に積極的に唱え続けていきたいなと思いました。
2008年07月18日
コメント(10)
-
ゆったりと心地よい空間。
昨日、今日、そしていつも日記に訪問して頂いているみなさまありがとうございます♪昨日、日記アップできなくて申しわけありません。懇談、夏の準備などなどやっとひと段落ついたと思ったときにはすでに、深夜1時を回っていました。(汗)もう一度、前回の日記を簡単に振り返ると『自分のなかにいる サブパーソナリティーに意識を向け そこへ、なかよく、楽しく、 ゆったりを語りかけると サブパーソナリティーが 喜んで、自分を手助けしてくれて 必ず何か変わると思いますよ。』というお話でした。さてさて、ずっと前から、ある人が目標を達成するどころか目標を立てるきっかけすら見つけられない場合勉強を教えるという以前に勉強するという気持ちが出てこない場合やる気を出しなさい、しっかりしなさいちゃんとしなさいと言われても本人は、本人なりにやっているけどうまくいかない場合どうしたらいいんだろう?と思っていたんです。ハングリー精神が必要?モチベーションが必要?いろんなことを考えていろんな本を読んでいろんな講座を聞いて前向きであること、ポジティブであること視覚的に思い描くこと、強い意志を持つこと肉体に覚え込ませること最終的な結果を感じること実際に計画を立てること紙に目標を書くこと感情を解き放つテクニックを持つこととにかく始めてみること・・・etcいろいろテクニックを知りどれも一定の効果がでました。それは、このどれもが今まで綴ってきた日記のどこかにあり(こんど、探してみますね。)それによって子どもが輝いてきたということからもわかるなと思います。しかし、このどれもが当人に『何かを達成しようとする心の準備がない』というやっかいな事実につきあたると目標を明らかにするエネルギーが維持できずその歩みが止まってしまうという問題が起きていました。みんな『頑張ろう』と思っているんだけれど『頑張る』ことが車輪を回すまでに至っていないんですね。『今年こそは』とお正月に誓ったこと『今度は、ちゃんとするから』と約束したこと決していい加減な意志では、なかったはずなのに心の奥底にまで至る深い願望にまで至っていなくていつも間にか止まってしまうということ誰しも一度ならず、経験がありますよね。前回のプラス思考、マイナス思考の話や人間関係の話、今日の夢や勉強、学力向上の話一見、ぜんぜん関係ないように見えますがじつは、根っこは、ひとつだったりします。それは、どういうことかというと自分の身に降りかかる問題は『過去どうだったから、 あのときこうだったから』という過去の記憶の再生にすぎないからなんです。そして、これらを心に笑顔をもった別の視点から見直すことで一つひとつの問題を試練と見なさず自然に、機会と捉えることができるんです。だから、思い込みを捨て去り、自分の内なる空間を楽しく、仲良くすることによってもたされるということを体験として実感してほしいなと思っています。なんか難しくなってきたのでごくごく、簡単にいえば問題が起きたときは問題は、『自分の外にある』と思っているから「ほら、そこにある!」とついつい思ってしまいますが問題は、そこには無いのです。何か問題が生じたとしても自分がハッピーであればそれは、問題でなくなってしまうからなのです。問題って、問題が自然発生するのではなく自分の心のエネルギーが下がっているから起こるものだからなんですね。つまり、自分の心がハッピーであれば自分の態度が変わるし、言葉が変わるし相手にそのハッピーは伝染するので問題が生じなくなるのです。これは、夢に対してもお勉強に対しても同じです。相手と仲良くなれない原因も自分の嫌な部分が嫌になる原因も夢が自分にちっとも近づかないように感じる原因も自分がハッピーじゃない心に笑顔がないからなんですね。自分の心に、ゆったりを教え心に笑顔を持っているイメージのなかで、自分がつながりたいものと自分のハートとそこがホースのようなものでつながったと想像しキラキラしたものを通してみる。これは、大きな効果があると思います。昔、右脳教育の七田眞先生が「学習にとって、人間関係にとって とくに親子関係において 一体化のイメージをもつと すごい能力が発揮されるんだよ」とお話されていて「世界史や数学の教科書や問題集と 一体化のイメージをもつ???」と思っていましたがそれが、やっと実感としてわかってきました。人生において望み得る場所は騒ぐ心を脱した彼方にあり平穏は、私とともに始まる。ゆったり、心地よい空間を自分の心のなかにもつことで心に笑顔を持つこと。自分をクリアにすればするほど自分もまわりまで、クリアになってくる。お昼にランチを食べているときに有線から『sweet home』の曲が聞こえてきてこんなことを思いました。
2008年07月17日
コメント(4)
-
サブパーソナリティー
「サブパーソナリティートランプ(SPトランプ) ってなんですか?これを、どう使えばいいんだ?」和歌山のジョブカフェ(若者の就業支援施設)で相談員をしている父から、こんなメールがありました。「こんどの休みに帰ったときに、 実際してみせて、説明するね。」とメールを返して、実家に帰ったときに、『よくもまぁ、 こんなレアなトランプを見つけてきたものだ』と感心しながら、父にセッションをしてひと通りの流れと、このトランプの意図を解説しました。自分の性格って、自分自身でもなかなかわからないもので几帳面でありながら、横着であったり怖かったり、やさしかったりしますよね。このトランプは、そんな自分のなかにいるサブ・パーソナリティー(自分のなかの子ども)を代表的なパーソナリティーをトランプのカードに見立てて自分のなかにいる子どもに気づきそれとうまくつきあっていくことを狙ったものなんです。このように、わたしたちの心のなかにはサブ・パーソナリティーが、いくつもいます。それを、『後ろの人』と名づけても『自分の中の子ども』と名付けてもどう名づけてもいいと思うのですがここに、光を向けると、いろんなことが変わってくるということが解ってきました。例えば、職業に就こうとかよりよく生きようとか自分自身がしっかり生きようとするときに人は、プラス思考の方がいいというのはみんなわかっていると思うのです。でも、なかなかプラス思考になれない。つい、マイナス思考になってしまいます。これは、なぜなんでしょうか?自分のなかに、扱い難いものがいるからなんですね。モジモジくんであったりマイナスくんであったりキレやすくんであったり。『頑張って』とか『しっかり』とか『まじめに』とか、思えば思うほどマイナス思考になってしまう。順風満帆でうまくいっている人はマイナス思考になりようがないのですが物事は、100%常にうまくいかないからそう思ってしまうのですね。そんなとき相手を責めたくなくても誰かを責めたくなくても『なんでなん?』『なんで、わかってくれへんの?』とか、思ってしまいます。しかし、問題が生じたとき相手にその問題を見るとき問題は、相手にあるのではなく実は、私たちは、自分の記憶や過去のデータをフィルターとしてそのフィルターごしに相手を見ているのです。そして、マンガの吹き出しのように『あの人が、こういうのは、こうだからだ。』というように、その状況を判定しています。つまり、問題は、それらにあるのではなく自分にあり、外にあるものなどあり得ないのです。だから、なにか問題が生じたときほど『この問題を生じさせた私の中で いったい何が起こっているのか?』『そして、自分のなかの問題を どうすれば、取り除けるのか?』と自分自身をきれいにして自分にゆとりを与えることゆとりを持って笑顔で接してあげたことをしたら答えは、自ずと出てくると思います。楽しい意識・・・仲良い意識・・・と自分のこころに『ゆったり』を教えてください。『ゆったり』をこころに教えていると私達が問題と思っていたことがどんどん消えていきます。 こして、自分のなかにいるサブパーソナリティーが愛され、褒められ、うまく行くと 喜んで、自分を手助けしてくれて必ず何か変わると思います。もっと、うまく詳しく書きたいといろいろ考えたのですがごめんなさい。授業の時間になりました。明日、続きを書きますね。続き(2008年07月17日)
2008年07月15日
コメント(4)
-
問題集の記憶法。
数週間前に三者懇談をした女の子から「せんせ、懇談したあと、 疑問が湧いてきたんです。 どうしたらいいか教えてもらいますか? 勉強していると、1回目で間違えたときに なんか、すごく落ち込むというか ムカムカと腹が立つんです。 これ、どうしたらいいですか? 」ちょっと前に、そう相談されました。「人間は、見たいものだけを見るからだよ。 Mちゃんは、『間違えたくない』 という気持ちが強いんだね。 Mちゃんは、1回でマスターするべきだ と思っているんじゃない? せんせは、ちょうどMちゃんの頃に 1回やって間違えた問題や 2回やって間違えた問題がテストに出てきて その問題をすることで ぐっと点数が良くなったんだ。 だから、間違えた問題を大切にしていたんだ。 1度目であった問題は、赤丸 2度目であった問題は、青丸 って、みんなにしてもらっているでしょう。 目の前が良い状態であってほしいと やっていると、いつでも全部 赤丸にしたいと思うものだけど 実は、青丸を大事にしたときに ぐっと成績が上がるものなんだよ。 あきらめたら、そこで終りなんだよ。」と答えました。問題集は、演習をするものではなく問題の解き方をインプットすること。問題集は、答えを見てもう一度解くことが極めて大切で文章問題などは、1回目は解かずに読みその直後、正しく記憶できているか確認するために解き直すことがとりわけ大事であることわかった状態と解けるというのは、違うことこれをもっと上手に伝えたいと思っていたんですがそう思っていたら土曜日に聞いた講演会(昨日の日記)で齋藤孝先生が、そのヒントをくれました。ここから下は、講演でお話されていたことです。何かを子供に身につけさせようとしたらそれは、紙に書いて貼っておいて音読させること。音読して、カラダを通すと身につきます。勉強ということであれば『問題集は、必ず3回やる。』と、ポイントを書いておいて音読すると、直ってきます。「問題集は、必ず3回やる。」と毎回必ず、一緒に音読し間違った問題に、印をつけて間違った問題だけ、もう一度やる。でも、子供の場合、最悪なのはやっちゃって答え合わせもしないという場合テストを受けたんだけど、答え合わせをしないよかった、悪かったと一喜一憂しているこれが最悪のレベルです。でも、こういう子多いですよね。次に、間違った問題というのをその場でもう一度解き直して理解するそこでやめちゃう子。ある程度できるんだけど伸びない子というのは、こういう子です。一番いい方法は、1週間後にできなかった問題をもう一度してあった問題は、OKとチェックを入れてできなかった問題は、また印をつけできなかったものを次の1週間後にまた、同じように確認することです。『問題集というのは、 3回やり直すためにある。』これをカラダで知っている子は強いです。1回やるというのは、やっていないに等しいです。どうやって問題集をやるかさえ理解していないことが多いのでそこのところを伝えるために紙に書いて、音読させてください。とお話していました。書いてしまえば、とてもシンプルで簡単なことですよね。前回の授業の復習テストなどいままでしてきたことをもう一度見直しひと手間加えて、紙に書いて、仕組み化してあげたらもっとやりやすくなるなと思い今日から夏に向けてその準備をしています。何でも、仕組み化すると面白いですね。そして、見える物事はすべて自分の幻想や投影にすぎず自分の影の部分を大切にすると自分にとって嫌なものが実は、自分を一番助けてくれるこれは、なんとも面白いコントラストですね。
2008年07月14日
コメント(4)
-
3つの力。齋藤孝先生教育講演会
『家庭学習で伸びる子どもの学力 「国語力」は、全ての学力の基本です』と題した明治大学教授・齋藤孝先生の講演会を昨日、大阪で聞いてきました。具体的で本質的なお話をたくさん聞かせて頂いたのですがまず、自分のカラダを通すことがマスターすることのコツだとお話して下さいました。以下は、斎藤先生のお話です。意外に、勉強ができる人ほど音読していてうまい人ほど、基本的な技を繰り返しています。そして、頭がいい、悪いといいますがカラダが動かないと意味がなく頭だけの人間ではなくカラダが伴うのが大切でこれが社会で通用する人間です。みんな仕事で通用する人間になりたいと思うものですが仕事ができる人とは、他人との競争ではなく自分が仕事ができる人間であること自分の周りの人も自分と一緒に仕事をすると楽しくなるようなコミュニケーション能力をもつそんな人が仕事ができる人ですよね。この対話能力・うまくやっていく力がないと能力があっても、縮こまってしまうのです。この対話能力は、国語力なのですがこれは、家庭で作り上げていくことが基本です。そして、国語力にとって最も大切な能力は『人の話を聞いて、要約して、再生する能力』です。例えば、「もう一回言ってみなさい」と言って、答えられないときは聞いていたとは言えない(死んでいた)ということです。人の話を聞くときはアイコンタクトが非常に重要で目を見る、ほほ笑むうなづく、相槌を打つ。これをしつこいくらい繰り返すことが大切です。『しつこい』というのが大事です。子どもは、しつこくないと言うことを聞かないですよね(笑)子どもに、この対話能力を育てるときはマンガでも、アニメでも何でもいいので、質問しまくることです。例えば、ドラえもん(2006年4月19日の日記)を一緒に見ていたとすると「ここで、なぜ、ジャイアンに対して のび太は、うそをついてしまったのでしょうか?」とか「なぜ、スネ夫は、このように言ったのか?」「スネ夫は、見栄っ張りだから。」というように、親との会話のなかで親が質問することで要約力を鍛えてほしいのです。考えながら、見ることをいろんなことで体験させることが重要です。欧米の人は、質問することが『相手のいうことを自分が興味があります』という相手に対しての誠意と考えているので質問することに、慣れています。日本人は、『質問する』という訓練をあまりしていないものなので子供の質問力を伸ばすには質問レベルが高い低いと評価しながら要約して再生して、的確な質問をするということを繰り返すと質問力のレベルは、どんどん上がってきます。この質問力を育てることは何も勉強するときだけではなく食べている時間も、何をしている時間もできます。子供は親と対話している時間が一番、脳が働くからです。自分と子供との間には言っちゃいけない言葉があってそれは、「え-」とか「うー」とか「わかんない」とかという言葉なのですが「どうだった?」と聞いたときに「特にない」「よかった」「普通」というのは親との対話を拒否と受け取る言葉だと話しています。子供の仕事というのは、「親と会話をすることなんだ」と中心にすえ「親の質問には、 ちゃんと答えなきゃいけない」と話をしていて「良かった、普通」という言葉は、情報量がない言葉で、会話が続かない言葉だから親との会話を拒否したと受け取るとお話しています。こんなやりとりを続けていると街のなかのあらゆることがチャンスになります。素敵ないい店があって「この店、いいね♪」という話になったら「この店が、いい理由を三つあげてみて」とか子どもに、「あの靴がほしい」と言われたら「なんで、好きなんだ?」と聞いています。「だって、ほしいんだもん。」と答えたら「じゃぁ、なんで、 ほしいのか三つあげてみて? この靴がなぜほしいのか 父さんを説得してみろ(^v^)」と、要求が通るためには、根拠が必要なんだということを教えています。3つ理由があることが大切なのではなくとにかく3つあげることやたくさんある理由の中から3つに絞るということが大切だということです。3つポイントをあげることを徹底的にやってほしいのです。3つあげていくと、思考が発展していきます。2つだけのポイントだと善か悪かという二元論で終わってしまうので1つ目は、すごく大事なもの2つ目は、まぁ大事なもの3つ目は、面白いものと、3つ上げていきます。何をみても三つあげる。これを繰り返していくと角度のある意見が言えるようになり情報の切り取り方が上手になってすべてのものには、意図があることに気づくようになります。「このCMには、コンセプトがない」なんてことを子供がいったりするのです。子供に、この力をつけさせるときのポイントは「この靴と、あの靴は、どう違うのだ?」と、比較するヒントを与えることです。こんな感じで、1時間ちょっとの時間演台から前に出て、ジェスチャーいっぱいでエキサイティングにお話してくださいました。要約力、質問力、コメント力この3つの力を鍛えていくこと本で、何度も読んだことだったのですが齋藤先生から直接お話聞くことですごく解りやすくなりました。カラダを通して理解することって、やはりすごいですね。いろんな問題をやっても それは、忘れてしまいます。 でも、何かを問われたら いつも3つで答える そして、それを立場を変え 視点を移動させて、コメントしてみる これが身につけば、社会に出た時に 必ず使えるワザになり大変大きな力になりますね。
2008年07月13日
コメント(4)
-
齋藤孝の相手を伸ばす教え力
昨夜、実家の本棚から五年前に買った本を取り出しました。『齋藤孝の相手を伸ばす!教え力』いまは、宝島社から文庫としても出版されているのですね。この本、年に一度くらいは手に取り、読み返し振り返っているのですが当時は、大事と思うところに蛍光ペンでラインを引いていたのでこんなことを考えていたんだなぁと、当時を懐かしく思い出しました。昨夜、本のなかにある言葉を読むとどれも今や自分のバイブルとなっていて『教える』『学ぶ』という関係は教える側がうまく上達する技術を持っていれば人間が誰かと関係していくなかでもっとも幸福な関係になる。そこには、教えられている側が感じる『伸びている』という充実感があるから。ということだったりうまい課題を設定してあげること。相手を上達させるために効果的に練習メニューをさせること。教える側がいま自分が伝えようとしていることや教える内容は、世界の中で面白いことなんだという雰囲気で、教える側の憧れを見せること。できない状態からできる状態に移るよう良いものとは何かが解っていること。良い状態を意識化させるために良いときに「いまのはいいよ」とコメントすること。など、ここからスタートしこれを発展させたものでいっぱいでした。今日、そんな齋藤孝先生の『家庭学習で伸びる子供の学力』という講演会を無料で聞けることになりました。この人に会って直接話を聞きたいそう思っていると、実現するものですね。どんなお話だったかそれは明日、書かせて頂きますね♪
2008年07月12日
コメント(8)
-
頭の中の出来事。
「いつもと違って、なんで南国風の音楽なん?」算数をしている女の子から、そう聞かれました。いつもは、散じている心をできるだけ整えてほしくてBGMに落ち着いた穏やかなクラシック(3月4日の日記)をかけているのですが学期終りのまとめのテストが近くその日のうちに、マスターしてほしかったのでちょっとテンポが上がるようなボサノヴァの曲を聞こえるか聞こえないかくらいでかけていたからなんです。『集中力がない、 なかなか進まない』という子の多くは意識が、いまここにないことが、多いんですね。計算をしたり、文章問題を読んだり問題を解いたりするときその問題と一緒にいる時間が短いのです。問題を読んだかと思うと鉛筆や消しゴムが気になったり明日のことが気になったり隣の子が気になったりしちゃうんです。『自分の意識がどこにいっているか』このことを、自分で観察できるくらい客観的な目を持つことができればそのことは、解決するのですが子供に、そのことを説明したところでなかなか理解してもらえませんでした。『これが解決すれば、いいのになぁ』と、前から思っていました。で、いろいろ理由とか原因とか考えたりしていたんですがことは、単純で、それが、嫌だからなんですよ(笑) 例えば、嫌な人と一緒にいるときのことを思い浮かべてもらえばわかるんですが人が、嫌な人といるときその人を持続的に感じることは、大きな苦痛になってしまうのである瞬間に「嫌だな」と感じるとすぐに気持ちを他へ移してしまうのです。そして、少しして、また一瞬だけ「嫌だな」と感じてまた直ぐに気持ちを移してしまいます。 意識があっちこっちに飛んでいる子供もこれを同じことを繰り返しているんです。反対に、好きな人といるときは時間を共にしている感覚はあるし頭のなかにもその人がいますよね。頭の中の空間にいるその人とも時間を共にし、寄り添っているものです。最初に書いた女の子は南国に良いイメージがある子なのでボサノヴァをかけたら、いい顔になってそのものと、寄り添っている時間が長くなりいつもよりたくさん進み予定していた所まで終えることができました。子供に教えていると、ついつい教えている事柄をなんとかして、伝えよう、マスターさせようと思ってしまいがちなのですがその子の頭のなかを想像してみるといろんなものが見えてくるなと感じました。そして、自分の頭のなかに見えている景色と相手の頭のなかに見えている景色が一緒でそれが調和がとれているとき自分とその人が、時間を共にしているという実感がでてきていい成果が出てくるなと感じています。そして、これこそが『ゾーンのチカラ』(2月25日の日記)だと思います。
2008年07月11日
コメント(2)
-
引き寄せ、創造するチカラ。
「せんせ、オレ、理科やばいで。」テストを前日に控えた男の子たちが若い女性の先生に、そう言っていました。それを横で聞いていたので「せんせをおどすな(^v^) 間際になって、焦る気持ちはわかる。 でも、それは、先生の責任ではないだろう? ほんの数日前までは みんな、のほほんとしてたじゃん。 自分の準備不足を 人のせいにしたらダメだよ。 これからできることは、何か。 もう少し心を落ち着けて、考えなさい。 そして、これが一番大切なことだけど 9月の実力テストのときに どういう気分でいたいのか? こんな気分ではなく いい気分でいるにはどうしたらいいか? 9月にいい結果になったとすると その前日には、どんな気持になるのか 細かく、細かく想像しなさい。」と話をしました。人は、途中でいきずまったり自分が望む状況ではないことを感じるとなんとか自分の責任ではないと思ってしまいがちです。出かけるちょっと前まで、ゆっくりしていたのに出かける間際になって、「なんで、○○がないんよ。」とか「なんで、ちゃんと 準備してくれてないんよ」と子供が慌てだすというのはよく観られる朝の光景ですよね。夏休みを前に、懇談したりと受験を控えた子供たちやお母さんとお話するとき「頑張らないで、楽しく、喜んで プラス志向、プラス志向とよくいうけれど それは、目の前に起こった出来事を プラスの方向で考えなさい とだけいっているのではなく 目の前のことと、なかよくいよう と思いやりの気持ちを持とうということだし 何か手に入れたいのならば、 実際に手に入れたとしたら どんな気持ちになるのか、 これから起こるであろう未来の出来事を 細かく細かく想像するということなんだよ。」とお話しています。右脳のチカラとかイメージとかシンプルにいえば一番のポイントはここで自分がしたいことを、すでに頭の中で想像する。それを喜びとともに、心地よい気持ちで味わい愛でる。アタマのなかで、リアリティーのある空間を造っていくそうすると、想像したことは創造するんですよね。自分が望む場所、望む時間に望む人と、望む状況で自分がしたいことをアタマの中ですでにしておく楽しい意識、なかよい意識をもって味わい愛でる。引き寄せる、創造するチカラってこういうことなのかなと思います。アタマのなかにそうやって世界が広がると夢は、必ず手に入るし実際に勉強するときにも勉強している内容がアタマのなかに世界を広げていくのでどんどんと、自分の望む状況とつながっていきますね。
2008年07月10日
コメント(2)
-
元気の素。
「なんで、しっかりしないのだろう。。。 なんで、ちゃんとしないのだろう。。。」これは、お母さんたちとお話しているととてもよく頂く相談です。そして、「私が見ていると、まだまだ余裕があるのに なんで、勉強しないのかと思うんですよね。」とも。ところが、子供たちに聞いてみると、そういう状態のほとんどの子供が「忙しい」「時間がない」って答えるんですね。子供たちの話を聞いていると確かに時間が無いようにも聞こえるしお母さんの達のお話を聞いているとそうでないようにも聞こえるんですね。で、「言い合いになったり、怒ってしまうのです。 どうして、この子は、頑張らないのでしょうか?」と相談を受けることが多いんです。実は、自分も子供たちを見ていてなんで、ダラダラするのかなんで、しっかりしないのかなんで、勉強しないのかと、ずっと思っていました。「そこまで、やらなきゃダメなん。」とか「自分の楽しみを減らされたくない」という言葉に『じゃぁ、チャレンジするの止めようよ もう夢見ることなんて、止めてしまおうよ』と喉まで出かかったことが過去何回かありました。でもね、やっぱり頑張るということは、疲れるんですよ。そして、『頑張ろう』というのは自分に元気がないときに頑張ろうと思うものなのです。だって、自分が心身ともハッピーな状態で元気いっぱいであるときに『頑張ろう』と思うことなんてありえないのですから。そして、この元気すごく元気であったりちょっと元気であったり朝昼晩で違ったり昨日今日でも違うものですよね。同じものを食べていてもどこで食べるか、誰と食べるかでもぜんぜん違ってくるものです。いままで、自分はそのことに気付いていなくて自分の元気は、一定でそのなかで、どうやって頑張るかと考えてたんです。そのくせ、風邪を引いたり熱が出たりするときに『今日は、元気がない』なんて思っていました。以前の日記(1月10日)にも書いたことがあるぽんぽこ先生に『元気は、一定ではない 自分の心のエネルギーが いまどのくらいか感じてごらん』と教えてもらってから自分の元気を気にしていると元気には、ほんと差があるもので自分自身に喜びがあると心のエネルギー、元気は増えるんです。わぁ、おいしいなというときにわぁ、楽しいというときに元気って、やっぱり増えるんですね。そして、悲しかったり『あの人どうなん!』とか『ここで、がんばらないと!』とか思うと元気は、シュワシュワと消えていくんです。ほんと、面白いものです。最初の話に戻ればお勉強にその子が今までどういうイメージをもってきたかそれによって大きく変わるとは思いますが一緒にやることで対象のイメージが変化して喜びが増えていったとき元気は、どんどん増えていきそれにともなって現象も変わってきます。楽しくて、穏やかで喜びがいっぱいあってしっかりしていないちゃんとしていない子なんていないと思うのです。自分のそして、相手の元気の量を量ることいい言葉を遣い素敵なことを思い楽しい意識、なかよい意識で喜びを増やすことこれが元気の素だなと思います♪
2008年07月09日
コメント(6)
-
気分のチカラ。
「ムカつく、腹が立つんよ。 ほんと、キモいわ。。。 もう、サイアク。。。 」と話していた女の子たちが「なんで、楽しくないかわからん。 なんで、うまくいかんかわからん。」と、話しているのを『いやいや、なんでそうなってしまうのか? 十分に 分かっていると思うんだけどな。。』と思いながら聞いていました。『キレる、ムカつく、キモい』という言葉があまりにも日常にあふれている言葉だからなかなか取り除くのは難しいのでしょうね。『なんで?訳わからん』という不快な気持ちが目の前のことの価値判断をしてしまい自分が正しく相手がおかしいという気持ちが言葉であったり、顔の表情であったりカラダの使い方に表れてきてムカつくとかキレるという感情になるのかなと思います。これ、どうしてこう思うのだろう?何が欠けているんだろう?と、ここ数カ月投げかけていたのですがひとつは、キレることによって自分の目の前が自分の思うように動くことが多いこともう一つは、楽しみを膨らますことで願いを叶えていく体験がないことではないかと思うようになりました。どんな小さなことでもいいから自発的にやったことで成功体験を持たせることこれが大切なことだということです。成功体験の喜びがないと脳の思考回路は変わってくれないんですね。いまここに、こころをおいて相手を思いやる気持ちをもつとうまくいくことこれから起こるであろう出来事を想像したり自分が望む方向に対する意識をもつと自分が取り組んでいることが面白くなってくることいい気分でいると、いい成果が出ることそんな体験をたくさんしてほしいなと思っています。私たちは自分が発したものを引きつけます。ネガティブな感情を、完全に消し去ることはできませんが絶望的だとか運に恵まれていないといった気もちよりも前に進めるキモチ、感謝の気もち相手を思いやる気持ちが大きくなる方が目の前の生活を、どんどん変えていきます。発するキモチが、かたちになって返ってくる。ほんと、単純な仕組みですね。楽しくなる工夫嬉しくなる工夫面白くなる工夫気分のチカラは大きいなと思います。
2008年07月08日
コメント(4)
-
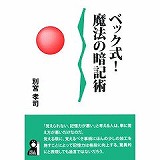
魔法の暗記術(2)
今日七月七日は、七夕で恋人の日らしいですよね。昨日、『ベック式!魔法の暗記術』など 数々の本を書いておられる別宮先生の講演会を聞いていました。記憶術の本や記憶術の講座などいろいろ読んだり聞いたりしてきましたがここまで体系立っていてかつ具体的な運用方法まで教えてくださる先生はそうそういないなと思いました。暗記しなくてもいい方法として昨日も日記に書かせていただいた思い出しやすくするためにはどうしたらいいのか?ということを軸に連想させて関連付けて覚える方法をたくさん教えてくださって例えば。。。同僚、明瞭、治療、寮という字を覚えるのに部首に注目して人の同僚、目に明瞭病を治療、ウチの寮テンポよく記憶していくほど記憶しやすいということや対象に対する印象を変えたり注目する点を変えることで記憶の定着度はまったく違ったものになる。というお話を実例を交えながらたくさんしてくださいました。今日七月七日は、1937年に盧溝橋事件があった日なんですが「盧溝橋の「盧」の字のなかには 『七』が入っているんですよ。」と話される別宮先生に『盧溝橋事件が1937年7月7日と 七並びとまでは、知っていたけれど 「盧」の字のなかに そんなヒントが隠れていたのか。。。 どこに注目するかって大切だな』と感動しました。「暗記なんて、 さっさと終わらせてしまって 暗記の、その先の勉強、 知的好奇心を呼び起こすような そんな勉強がしたいのです。」そう熱くお話される別宮先生はとても素敵な先生でした。大学のとき、刑事訴訟法の渥美教授が「歴史をただ覚えるのなら こんなことがあったと知るのなら 歴史を学ぶ意味など、何もない。 なぜ、そういう事件になったのか そのとき、人は、どう考えたのか その後、どう、動いていったのか そこを知ることで これと似たような現象を見たときに その後の流れを見るために 未来の流れを見るために 過去の歴史を学ぶんだ。」と話していたのを思い出しました。 いくさ長引く、日中戦争1937この語呂合わせも、もちろん載っている『ベック式!日本史ゴロ覚え』(学研)は 大学受験だけでなく、高校受験や小学生が歴史を勉強するときにもすごい威力を発揮してくれると思います。
2008年07月07日
コメント(8)
-
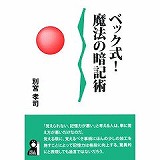
魔法の暗記術(1)
信号機の赤信号は、左にあるか右にあるかご存知ですか?毎日見ているようで、意識をしていないと意外に覚えていないものです。子供に漢字を覚えてもらったり英単語を覚えてもらったり算数や数学の計算問題の手順を覚えてもらったり勉強を進めていく上で、暗記は絶対に欠かせないものです。ただの記憶事項の暗記にとどまらず操作手順の記憶ということまで含めると勉強の9割は、記憶だと言っても過言ではありません。それほど、重要なものであるにもかかわらず「30回書きしなさい。」とか「覚えてきてください。」と指示されることがあっても「どうやって覚えていくのか?」といった暗記に関する技術的な側面が語られることは、ほとんどありません。。その理由は、記憶力が天性のもの固定的なものだと信じて疑わずその改善や向上など不可能だと信じ込んでしまっているからなのかもしれません。もちろん、コンプレックスが大きな影響していたり本人の記憶力の良い悪いはありますが他人と比較して「覚えられない、記憶力が悪い」と考えている人は覚える際に、覚えるべき事柄にほんの少しの加工を施すことによって記憶力は、格段に向上させることができます。何かを覚えて、小テストをしたときだったりあることを聞いて、「知らない」というとき問われたことの正解を聞いて「あぁ、そうだった。そういう意味だった。」ということは、ありませんか?『思い出す力』(6月15日)に書いたことでもありますが「そういう意味だった」と答えるということは忘れたのではなく、思い出せなかったということなのです。「思い出せない」という状態は、例えていうと家のなかにあるのはわかっているけれどどこにあるのかわからないとか書類に綴じられたファイルにタイトルやタグをつけずにどこかに紛れ込んでしまった状態といえます。記憶は、五感と密接に関連しているので記憶力を向上させるためには大切なのは、注意を払って、何かに関連付けたり意味をもたせたり、視覚化したり、音声化したりするとその容量は、何倍にも増えます。カセットテープに吹き込んでいたものから大型のHDDレコーダに録画するようにイメージファイルで簡単に取り出すこともできますよね。自分でもいろいろいい方法にチャレンジしてきたんですが今週ミクシーで記憶術で検索していたら 今日は、「ベック式!魔法の暗記術」という本や「日本史・世界史スーパー記憶法」など多くの本を書かれている別宮孝司さんの講演会が今日、たまたま枚方であると知りました。聞かせていただくお話から新しい発見をしてこようと思います♪最初に書かせていただいた赤信号ですが日本の赤信号は、左車線を走る車のドライバーにとって一番、視界に入りやすいように、一番右にあるんです。自分もこの話を聞いてから信号が違って見えるようになりました。意味をもたせると重要度が変わってくるって、面白いものですね。
2008年07月06日
コメント(6)
-
ベストプラクティス(2)スピーチ法
期末テストのテスト勉強で数学に追われている男の子達から「せんせが言うように、テスト前までに、 なんとか準備していこうとやってます。 でも、時間がなんぼあっても足りないです。 もう時間がなくなってきたので どれをやった方がいいか、○をつけてくれませんか。」と、ヘルプがでました。「じゃぁ、これやってみて。」というと「せんせ、苦手なとこをよく ピンポイントについてきますね。。。。」と言いながら、解いています。しばらくすると、手が止まっていたので「解答・解説をみてごらん」と解答集を渡すと「ここまでは、わかっていた」とかいろいろ言いながら自分達の解答と見比べていました。そこで、学年が下の子が隣で同じように数学の問題集を解いていたのでそれをちょっと借りてきて「この問題は、見た瞬間に解けるのが 自分自身でわかるでしょ。 こんな感じで、 こっちの問題ができたとき 使い物になるんだよ(^v^) 条件反射のように、思い浮かぶとき 初めて、ずば抜けた結果がだせるんだよね。」というと、「そんな風になるには、時間がかかりますよ」というので、「それは、問題は、自分で解くものだ と思いこんでいるからなんだよ。 ぱっと思い浮かぶようになるまで 解答・解説をしっかり読んで その問題を見た瞬間に その問題が、簡単に言えるようになったらいいんだ。 簡単に、手順を言えるようになったとき その問題は、計算間違いをしない限り 最後まで解けるよね。 これ、ザクっといったらどうなるの?」と聞いていたら、しばらくして「どんな風な感じでいうんですか?」というので、「これ、要は、Aを基準にした ハサミのような二つの三角形を考えて それをs対1-s、t対1-tとおいて 連立方程式を作って、求めると出るんだよね。 」と答えると、「そうです。 そんな風に考えるのですね。」と他の問題も取り組んでいました。自分がしていることをスピーチしてみる「要は。。。」とスピーチできるということは流れ、手順が解っているということですよね。何かをした直後に「要は。。。」と振り返りその直前にしたことを思い出すことは大変な武器になると思います。何かあったとき、学校から帰ってきたとき「どうだった?」と聞きながら、子供が話す言葉をそのまま返していって子供が「要は。。。」とか「要するに。。。」なんて、言葉を使うようになったらコミュニケーションも取れこれは、知力を上げるきっかけになりますね♪
2008年07月05日
コメント(4)
-
ええやんけ。中井政嗣(千房社長)
昨夜、地上波ではすでに6月30日に放送されていたカンブリア宮殿をBSで観ました。「部下を必ずやる気にさせる "人材育成術"教えます」と題してお好み焼きチェーン「千房」の中井 政嗣社長がゲストでした。そのなかで、新人さんを研修するシーンがあってとても面白いなぁと思いました。高校を卒業して今年四国から出てきた新人の小島くんに対してそごう横浜店・店長の椛島さんはこれからしてほしいことを2つだけ伝えるんです。「食器を洗うこと」と「残飯を片づけること」。そして、店長の椛島さん自ら手本を示しいい状態を繰り返し彼に見せます。しかし、小島くん残飯の入ったごみ袋であっちこっち、ものを倒すし食器を洗っていて手前のものを取ろうとするとその奥にあるコップを向こう側に倒してしまいコップを割ってしまうんです。テレビを観ているこっちが胸が苦しくなりそうです。「申しわけありませ~ん。」と大きな声で叫ぶ小島くんに店長の椛島さんは、小島くんの目をみて「小島、ええねんで。失敗は、誰でもする。 でもな、同じことを何度も繰り返したらあかん。」とだけ言うのです。「こら!!!」とか「なんで、なん?」とかないんです。割った後も、彼なりに一生懸命洗っている姿を後ろから観ては「小島、ええで、その調子やで。」って、声をかけるんですね。さらに、小島くんが最初に伝えた二つのことがきちんとできるようになると店長の椛島さん、今度は『サラダを作る』という役を与えます。そのときに店長の椛島さん、また「サラダを作るときは、必ず手を洗うこと。」「サラダのまな板を常にきれいにすること。」この二つのことだけを彼に伝えるんです。接客担当の人がサラダをお客さんに運ぼうとするとチラッと、小島くんの作ったサラダを見て店長の椛島さん、また「小島、ええやんけ。ええ調子やで」と声をかけます。そして、洗い場とサラダ場、この二つを小島くんが上手にこなせるようになったのを見ると「小島、いまここにある洗い物 いつまでにだったらできる?」と時計を見ながら聞くんです。すると、小島くん「45分まで、だったらできます。」と答えるので、店長の椛島さん「結構、かかんなぁ。。。」と笑いながら、また、時計を見るのです。その姿に、小島くん「40分までに、仕上げます。」と自分から宣言しちゃうんですね。すると、今までと同じ人かと思うほど彼の手の動きが格段にスピードアップするのです。「仕事辛いですか?」というインタビューに「朝から入って、お店が終わるまでいると 寮に帰ったら、クタクタで寝るだけということもあります。」と答えていましたが、その眼は、ごみ袋をあっちこっちにぶつけていた焦点の定まっていない目とは違いしっかり、相手を見据えていました。 教える側自ら、手本を見せそのコツを二つに絞って伝える。できていてもいなくても、些細なことを見つけて褒める。重要な役割を細かく与え小さな目標を自分で設定するようにもっていく。褒めるときは、できたねという励ましとできたことに対するねぎらいの意味で相手の目を見て、二度褒める。『これ思い当たる節ありまくりだな』と、自分と子供たちとのやり取りを思い出し子育てや教育にそのままつなげていきたいと思いました。「ええやんけ」って、いい言葉ですね。
2008年07月04日
コメント(14)
-
能力がアップするということ。
「なんで、ちゃんとしないんだろう?」「なんで、勉強しないんだろう?」「なんで、優しくないのだろう?」「なんで、仲良くないんだろう?」「なんでなん?」と思うことありますよね。これ、その子に、相手に問題があると思ってしまいがちですがあぁ、こう思うのは相手の問題なのではなくて自分の問題だったんだと、ここ最近よく思います。心理学の講座などでは何回も聞いた話なんですけどね。。。(笑)本当に大切なことはそう感じる自分自身が、ハッピーに生きることなんです。自分自身に余裕がなくて自分自身がハッピーでなくて相手のことを思っていたり相手のことをしている時には「せっかく、○○したのに。。。」と相手に恩を売ってしまいます。逆に、自分にゆとりがあると相手に恩を売らないだけでなく知恵が出てきます。そして、知恵が出てくるといろんなやり取りが考えられるしいろんなことが考えられ、覚えられますよね。ちゃんとしない、しんどいということはその人に『元気がない』ということで『元気がない』ということは楽しくない、面白くないということなんですね。ゲームをやっているとき子供は、勝手に『技』を習得しどんどん上達していきます。これ、楽しいからですよね。エネルギーがあって、元気があってそこに、ゆとりがあると何事もスムーズに運びます。物事を考えるにはこのリラックスしたゆとりが必要なんです。リラックスしているとき、楽しいとき早く動かそうと思わなくても自然に、早く動くものです。リラックスして、楽しく何かに取り組んでいるときしっかりしていないちゃんとしていないということは、ありませんよね。「しっかりしなさい」「ちゃんとしなさい」「なんで、ちゃんとせんのやろ」と、思うようなときは、物事が見えているようで視野が狭くなっているようです。自分自身がゆとりをもっていることリラックスしていることそして、望んでほしいと思う方向が楽しいと感じる環境を場を整えることこれが能力がアップするということにつながるんだなと感じています。
2008年07月03日
コメント(4)
-
思考の引き出し。
「わからん。わからん。」「こんなの習ってない。」「これどうしたらいいん。教えて。教えて。」という声に対して「『分からない。』ってばかり言ってないでちょっとは自分で考えてみたらどうなのよ。」こういう会話は、よくされますし自分もこういう状況に遭遇してきました。宿題をしていない言い訳かまってほしいときの言い訳といった、愛情不足、承認不足を訴えたものだったということももちろん多くありますが分からないという子供の頭の中で何がこの子には見えていて何が見えていないのでしょうか?「分からない」という子の見えているものについては『文章題のできる子』に書いたようにその子に絵を書かせたりその子のカラダの使い方である程度、分かってきます。そして、『見えていないもの』ですが誰しも、百%未知の状況では当然、判断が遅くなり、鈍くなります。逆に、百%分かっている状況ならストレスを感じることなく行動できます。そして、そのときの状況判断が正しければ正しいほどより効率的に問題を解決できますよね。だからこそ、分からない状況を少しずつより分かっている状況に近づけて判断の精度を上げると行動がしやすくなりますよね。人は、知っているものしか解らないのでさっき教えたのに『分からない』とかさっきとほぼ同じものなのに『教えて』という場合にはその子は、さっきした体験が『技』や『枠組み』といった簡略化されたものとしてインプットされていなかったり一つだけの法則で一定の単元が進めるそんな風に考えていることが多いです。何らかの概念や考え方を自分なりに束ね、整理して考えやすいもの覚えやすいものにするやったものを『技』という視点でみる『技(フレームワーク)』という思考はたくさんのことに応用できると思います。技の組み合わせでできていると捉えていくと『どの技が知らないから 解らないと言っているのか?』とその奥が見えてきますし多くの問題に当たって、その技が増えることは思考の引き出しが増えることになりますよね。そして、どの技をマスターしていないから『わからん。わからん。』というかというところに視点を置くとソフトに優しく接することができその技の習得を繰り返すことで自ら進んで学ぶ人、主体的な人になってくるそう思っています。
2008年07月02日
コメント(2)
-
ベスト・プラクティス(1)
「imagine (想像する)に関連して imaginary (想像上の) iamginable (想像できる) imaginative(想像力に富む) を語尾の意味に絡めて覚えておこうね。 確か、速読英単語の20番台前半の 左ページの下にあると思うんだ。」こう言ったら、「なんで、そんなこと覚えてるの?」と驚いていました。「そのくらいに条件反射になったとき 使い物になってくるんだよ。」とそのときは、答えたのですが英単語を覚えるということに限らず勉強とは、技や知識を覚えていくものそして、それを簡略化して考えどのような枠組みで構築されているかを把握しその全体を再構築できるようにする。つまり、プラモデルや折り紙の完成品を見てどのような手順で組み立てて立体化していくと、もとの姿に再現できるかこれが上手になったら勉強が苦しいものではなくなるのにと思っています。勉強をしている子供たちは大体同じような教材を使用していますが、その結果には大きな差が生まれてしまいます。多くの人が言うように、頭の良し悪しの問題にするのは簡単なことですが実はそうではないと思っています。それは、教材の使用方法と習得度に違いがあるんですね。「これ、やったことある!」という人は、たくさんいますが確実に身に付けるというところまで実行できていない人が非常に多いようです。いかにして、自分の頭脳の回路に学習内容を組み込むかここにかかっているなと思います。そして、ある情報を再現性のある形で分解し再構築できるかということがアウトプットの最大のポイントです。時間となってしまいました。もっと、噛み砕いたようなものを明日書きますね。
2008年07月01日
コメント(2)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 子育て奮闘記f(^_^;)
- 継続は力なり
- (2025-11-17 20:42:48)
-
-
-

- ●購入物品お披露目~~●
- 板藍根茶は苦手かも…“納得のど飴”を…
- (2025-11-19 21:10:04)
-
-
-

- ミキハウスにはまりました
- ミキハウス好き限定!30%OFF😀ミキ…
- (2025-11-19 15:40:05)
-







