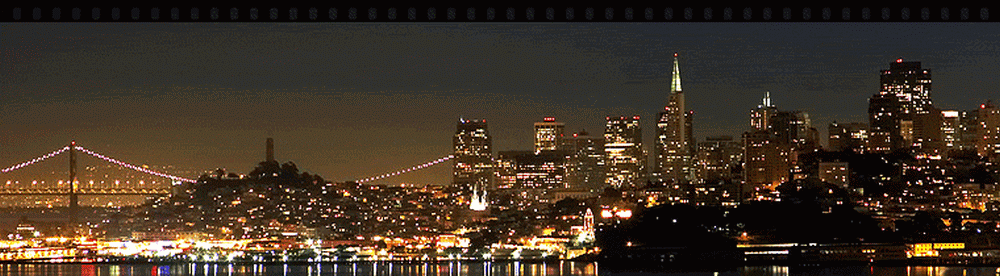2009年07月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
各国トップに見るゲームに対する温度差について(予告編)
表計算1級は今回スルーしてワープロ一級+DB2級に的を絞った管理人です。同時進行で表計算二級受験者用の対策問題を作成している本日のネタは予告編と言う事で、記事の紹介のみ。英ブラウン首相と米オバマ大統領、ゲームに対する姿勢はどう違う?(Gpara.com)>>ゲームに関する政治家の発言が、ゲーム業界の関心を集めるのは当然のこと。>>>> 例えば、英国のブラウン首相。ニュースサイト“Mirror.co.uk”との>>インタビューで、同首相は、議会の休会期間中、スコットランドの自宅で>>子供たちと過ごす時間を大切にしたいと語った。>>>> 2人の幼い息子をもつ首相は多忙のため、家庭では父親としての面目を失いがち。>>そこで、休暇中は息子たちのお気に入りのテレビ番組を見たり、>>コンピュータゲームをプレイしたりして、地位復活に努めるとのこと。>>首相は昨年も「『Wii Sports』で息子にボロ負けしたよ」と漏らしていることから、>>家族の憩いのひとときにゲームを活用しているのが伺える。>>>> 一方、アメリカのオバマ大統領はビミョー。ホワイトハウスの一室には、>>訪問する子供たちのためにWiiが設置してあるようだが、大統領自身は>>これまで再三にわたり、親に向けての演説で、ゲーム批判ともとれるような>>発言をしている。そのため、業界は少しばかり危機感を抱いているのだ。>>>> とくに先月、アフリカ系アメリカ人の家庭に向けたスピーチでは、>>「Xboxをしまってください」と、ゲーム機をはっきり名指し。>>「親は親の務めをしっかり果たし、子供と一緒にいる時間を増やすべき。>>子供の勉強をみてやり、夜更かしをしないよう気を配りましょう」と訴えている。この声明に対する業界の反応や管理人の考察に関しては、明日の更新にて。
2009.07.31
-
中国政府、ギャングを美化するオンラインゲームを禁止
DB2級の練習問題をやってみて、詰め込めば可能性が有ると見た管理人です。表計算のピボットテーブルの癖が未だに掴めない本日のネタは何かと騒ぎを起こす事で有名な中国からの報道で更新。中国政府、ギャングを美化するオンラインゲームを禁止(ITMedia)ネットゲームの取り締まり徹底=犯罪題材、青少年に悪影響-中国(時事コム)>> 中国政府は、マフィアを美化するオンラインゲームを呼び物にしたり、>>公開しているWebサイトを禁止し、違反者には「重罰を科す」としている。>>>> 文化省は、そのようなゲームは「わいせつ、ギャンブル、暴力を支持し、>>道徳や中国の伝統文化を損なう」と話していると、新華社は伝えている。>>>> 「これらのゲームは人民にだましたり、奪ったり、殺したりすることを奨励し、>>ギャングの生活を美化している。若者に悪影響を与える」と文化省の通知には>>記されているという。>>>> 「文化省は司法当局に対し、このようなゲームの提供を続けているサイトの>>監視を強化し、厳しく罰するよう命じた」と同紙は伝えているが、詳細な情報はない。>>>> ギャングは人身売買や麻薬取引などの不正な活動に関与しているにもかかわらず、>>台湾や香港で制作されるギャングものの映画やテレビ番組は、中国で非常に人気が高い。>>>> 中国政府は、オンラインのポルノや「低俗なコンテンツ」の取り締まりで>>数百のWebサイトを閉鎖している。場合によっては反体制的なサイトも対象になる。>>>> このキャンペーンは、10月の建国60周年に向けたメディア統制の一環だ。かなり細切れで分かりにくい内容になったので、↓に要点をまとめで簡単に解説。・中国政府は建国60周年を迎える為、メディア統制の一環として 暴力ゲームの規制を開始。・規制の背景には、最近再び増え始めたマフィア(ギャング)が再増加を始めた事が 原因。・映画やゲームではこういったギャング関係の物が人気が高いものの、 こういった状況が続けば、間違ってあこがれる若年層達が出てくると予想。 これらを禁止する事で、抑制しようと言う試み。・政府がこの施策についての通達後に、著名なオンラインゲームが相次ぎ閉鎖。 (未確認情報なので、真偽は不明)何か有る毎に規制をかけているが、段々反発が強くなる気がしているのは管理人だけだろうか?かつてのアメリカの禁酒法の様に、規制が強くなる程に地下で動く奴が存在し、それに誘引される様に、集まる集団も存在する。今の中国政府の行動は、タコが自分の足を食い千切って自滅する(※)姿によく似ている気がするが、それもまた一興なのかも知れない。※)タコはウツボ等に足を食い千切られた場合は、自己再生可能だがストレス等により自身の足を食い千切った場合は絶対に再生しないらしい。追記)管理人は犯罪を助長する気も無く、犯罪者を支援する気も無いです。ゲームや映画等の影響を受けて、そういう道に走る・走らないは本人の自由。ただ、映画等に流されて犯罪者になる輩が居たなら(自主規制)としか言えない。
2009.07.30
-
ドイツの「暴力ゲーム規制反対」署名、正式な嘆願書として認められる
ブログ開設当初の目的から離れた内容での更新が続いている管理人です。テスト鯖の応募をどうするか思案している本日のネタは、内容を変更して例のドイツの署名関係の続報が入って来たので紹介。ドイツの「暴力ゲーム規制反対」署名、正式な嘆願書として認められる(THE SECOND TIMES)>>7月8日(水)よりドイツで行われていた「暴力ゲーム規制反対」の署名が>>取りまとめられ、ドイツ政府に正式な嘆願書として認められた。>>>>現在ドイツ政府では、作中に暴力的な表現のあるゲームの開発・販売及び>>プレイの一切を禁止し、これに違反したゲームディベロッパーや>>販売に関わった流通関係者、ゲーマーに対し罰金と最大1年の懲役刑を課す>>法案を審議している。(詳細はコチラの記事)>>しかしこれにドイツのゲーマーたちが反発、7月8日よりネット上で>>ゲーム規制の見直しを求める署名活動を行っていた。>>ドイツでは5万人以上の署名を集めれば、それが正式な嘆願書として認められ>>法案審議の際に”国民の声”として効力を発揮、たとえ首相・大臣と言えど>>”適切な議論”をしなければならないとされている。この件に関しては、署名開始より1週間で達成されたのは記憶に新しい所だろう。(快挙!ドイツの「暴力ゲーム規制反対」署名、一週間で目標の5万人を達成)最終的には64,824人分もの署名が集まったらしく、インターネット上のみで集められたドイツ政府に対する署名としては過去最高の数値らしい。署名を集めた以上は、再審議は確定したものの、同じ結果で押し切られる可能性も含まれているだろうが、過去には↓の様な前例もある。>>ちなみにインターネット上だけではなかったものの、過去に>>「インターネット検閲法案」が審議された際は13万人分もの反対署名が集まり、>>結果的に同法案は廃案となった前例がある。現段階では再審結果がどうなるかは分からないが、廃案になる可能性は0では無い。個人的な感想から言えば、廃案になる可能性の方が高いと判断している。政治家=自分の利益確保に走る確率が高く、国民からの支持を得る為にはこう言った国民からの反論が大きい場合は、それに乗っかる可能性が高い。あくまで日本的な考えなので、ドイツは違う可能性も無い訳では無いが、管理人の偏見交じりの予想なので、当たるも八卦・当たらぬも八卦で。
2009.07.29
-
北斗の拳ONLINE HEROES ゲームサービス提供終了、享年1年2ケ月。
本日の午前中に、CS検定のワープロ&表計算2級&DB3級合格の通知が届き、ようやく一安心した管理人です。今回の資格を踏み台に上級検定に挑戦確定になった本日のネタは北斗の拳ONLINE休止に関する考察を。北斗の拳ONLINE HEROES ゲームサービス提供終了のお知らせ(北斗の拳ONLINE HEROES公式)>>日頃より、北斗の拳ONLINE HEROESをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 >>2008年7月24日(木)より正式サービスをスタートした「北斗の拳ONLINE HEROES」で >>ございますが、2009年9月30日(水)をもちまして、ゲームサービスの提供を >>終了させていただくことを決定いたしました。 >>>>本作は「北斗の拳」原作の世界観を出来得る限り忠実に再現した上で、 >>2008年7月24日(木)より正式サービスを開始し、これまで「北斗の拳」 >>ファンの方をはじめ、数多くのお客様にご愛顧いただき、様々なご意見、 >>ご要望をいただいてまいりました。 >>また本年3月には北斗の拳ONLINE HEROESとして戦闘システムの変更や新たな >>ヒーローシステムの機能追加など大規模なリニューアルを実施し、 >>ユーザーの皆様にお楽しみいただける環境作りに尽力してまいりました。 >>>>しかしながら、「北斗の拳ONLINE HEROES」が持つ独特の世界観や>>ゲーム システムを現在のオンラインゲーム市場に求められるニーズに>>マッチさせる ことが難しく、これ以上ユーザーの皆様にご満足いただける>>サービスを継続 して提供していくことが困難であると判断したため、>>誠に残念ではございますが、ゲームサービスの提供を終了と>>させていただくこととなりました。 この時期に終了を決定した理由として幾つか考えられる者が有るが、可能性としてはグランディアオンラインへのシフトに加えて資金回収関係、ユーザー離れ辺りが有力だと見ているのは、管理人だけだろうか?グランディアオンラインに関しては、ガンホーの稼ぎ頭増強の可能性も有り、かなり力を入れている気がする。資金回収に関しては、OBT時代からのシステム面やサーバーの挙動の不具合の影響で定着するユーザーも少なかったらしく、リニューアルの為に、一旦停止。初期広告費用に加えて、停止期間中の版権料やリニューアル期間の再開発費用等が加算された結果、現状の収益では回収しきれないと判断したのだろう。(MMO運営は3年で初期費用が回収出来れば御の字との話も…)「ユーザーのニーズに応えるサービスの継続が不能になった」と書かれているが、ユーザーの望むプレイスタイルを提供出来る環境が作れないと言う意味なのか、運営が一方的に見切りを付けたのかは分からない。やはり有名マンガの版権物をMMO化するのは無理が有ったと言う事なのだろうと考えつつ、本日のネタは締め。明日もMMO関係に関するネタで更新予定。
2009.07.28
-
女性がゲームをしないのは何故?ミシガン州立大学のチームが研究結果を発表
最近海外ネタしか扱ってない気がする管理人です orzニコ生見ながら更新している本日のネタも海外ネタなれど、興味深いネタなので紹介。女性がゲームをしないのは何故?ミシガン州立大学のチームが研究結果を発表(GameBusiness.jp)>>なぜ女性は、男性に比べゲームを遊ぶ時間が少ないのか?>>ミシガン州立大学のチームがこの原因を探るべく学生を対象に調査を行い、>>研究結果を発表しました。>>>>情報や通信の分野を担当するCarrie Heeter教授は、同大学の学生276名を>>対象に調査を実施。その結果、女子学生は男子よりも仕事や宿題などに>>費やす時間が一週間あたり16時間以上多く、一方の男子学生は、>>自分だけの自由な時間が二倍近く多いことが分かったそうです。>>>>「今回の研究結果は、女性が男性よりもゲームを遊ぶ時間が少ない>>理由の一つとして、彼女たちが義務的な活動で必要とされることが>>多いのを示しました。つまり暇な時間が少ないということです。」あくまでアメリカでの調査結果なので、国内でも当てはまるとは言えないが、ある程度参考にはなるデータでは無いかと思い、今回紹介してみた。確かに、女性の方が友人付き合い等が多い分時間に制約は有るだろうが、その辺りは人それぞれなので、時間の有る女性=ゲームに熱中すると言う訳でも無い。最近はミニゲーム系を中心として、ゲームに熱中する女性も増えている現状も有り、家事を放置してMMOにハマっている主婦もたまに見かける事も有る。上記リンク先では女性がゲームに興味を持たない理由の一つとして、「ゲーム業界で女性が活躍していないから」と言う話が書かれていたが、開発会社の社長が女性と言う例も有り、表には出てこないが女性開発者も実在する。総論すると、現在販売されているタイトルの大半は男性向けの物が多く、女性受けするタイトルが若干少なめで有り、ゲームに対する偏見も相まってプレイ人口が少ないと考えているのは管理人だけだろうか?
2009.07.27
-
M指定ゲームの広告を禁止するのは表現の自由を侵害する-米業界団体が交通局を告訴
市場調査用DB構築とショッピングサイトDB構築が近い気がする管理人です。だからと言って作成出来るスキルが無い本日のネタは海外の広告ネタで更新。M指定ゲームの広告を禁止するのは表現の自由を侵害する-米業界団体が交通局を告訴(GameBusiness.jp) >>米国のゲーム業界団体ESA(Entertainment Software Association)は、>>シカゴ交通局(CTA)を告訴しました。>>>>バスや電車でM(17歳以上)やAO(成人)指定ゲームの広告を出しては>>ならないとするシカゴ交通局の規則は、米国憲法で保障されている>>言論の自由を侵害するものだというのです。>>>>「シカゴ交通局の規則はエンターテイメントソフト産業の持つ>>憲法上の権利を侵害するものである」とESAのCEOである>>Michael D. Gallagher氏はコメントします。>>「合衆国の法廷はゲームが他のエンターテイメントと同様に>>合衆国憲法修正第一条の保護を受けられると決定したが、>>シカゴ交通局はこの確立した事実を認める気がなく、>>ゲームのダイナミズムと創造性、表現力豊かであることに>>不案内であることを示した。産業におけるクリエイティブの自由が>>侵害される時、我々は座視していない」との声明を発表しています。 コレを見ると以前の蘇民際ポスター騒動に近い気がするのは管理人だけだろうか?列車等の吊り込み広告の類は宣伝効果が高く、広告媒体としては非常に優秀なのは統計上でも実証されているので、今回の件は広告収入の面の問題も有る。しかし、最大の理由は審査団体が仕事怠慢でまともな審査をしていないと評価されたに等しい告知な事も有り、強硬手段に訴える可能性も有るだろう。確かに過激な広告があちこちに張られていたら問題だろうが、きちんと審査を通過して、問題が無いレベルなら試しに張るのも良いと思うのだが…。
2009.07.26
-
ゲームは“12歳の男の子向け”が多すぎる!ウィル・ライト氏の苦言
とある企画放送に参加していて更新が遅れた管理人です orz特急速度で更新している本日のネタは、現在のゲーム業界に対する苦言ネタで更新。ゲームは“12歳の男の子向け”が多すぎる!ウィル・ライト氏の苦言(Gpara.com)>> ビデオゲームがエンターテインメントとして広く受け入れられるようになって>>すでに久しいが、北米のゲーマーや業界関係者は、他の業界に比べ、>>いまだに世間の中で肩身の狭い思いをしているようだ。>>その理由について、シムシリーズや『Spore』の生みの親である>>Will Wright(ウィル・ライト)氏は、「一般の理解が足りないのは、>>ゲーム業界が、12歳の男の子向けのゲームを作り続けているからだ」と発言した。>>ライト氏は、「この20年間、ゲームに対して文化的な偏見が根強く残っているが、>>その多くは業界が自ら招いたことだと思う。いま作られているものを見ると、>>大半は12歳の男の子向けばかり。ゲームというフォーマットは、本来、>>それ以上の可能性を秘めているはずだ」と語った。 >>>> 「本当は、遊びこそが基本的な教育手段なのだが、私たちの文化は>>そのことを忘れてしまった。ゲームと共に成長しない大人は>>“遊び”という概念を、非生産的な暇つぶしととらえるようになってしまった」管理人も子供時代が有ったのは言うまでも無いが、多人数との遊びの中から暗黙のルールや協調性を学ばされた記憶がある。ところが、現在の状況を見てみると子供たちは親の操り人形になっているか、モンペに守られて無秩序な状況になっている事が多い。こういった事象を招いた背景には両親のゲームに対する価値観が起因している。「ゲーム=暇つぶし」ならまだ良いが、「ゲーム=悪」と言う極端な考え方は両親達が子供達を抑圧した結果論に過ぎないのでは無いだろうか?>> こうした現状に対する苦言は、若手のクリエイターからもあがっている。>>Thatgamecompany社のJenova Chen(ジェノバ・チェン)氏は、>>ライト氏の発言とほぼ時を同じくして、ゲーム開発者向けのカンファレンスで>>「ゲームの本質はこの20年間、ほとんど変わっていません。>>ゲームは人間の幅広い情緒を十分にかき立てておらず、未成熟です。>>大勢の大人が楽しんでいるのに、玩具として片付けられてしまう問題を>>はらんでいます」と訴えかけた。最近のゲームを見ているとどうしても演出>内容になりがちで、酷い例になるとネームバリューだけで中身がかなり酷いタイトル(某大御所の最新作)も有る。開発者サイドも「売れるゲームしか作らせて貰えない」と言う背景もある以上、集中的に攻める事は出来ないが、巡り巡れば各タイトルの売り上げの減少が要因の一つで有り、その背景にはマジコン等の違法DLロムの存在が有る。これらの悪循環を断ち切るには、違法DLロムの取締り等海賊版の縮小と同時に開発環境の変化も必要だが、一番大事なのは一般に認知される様な環境を築く事こそが肝要だと思うのは管理人だけだろうか?
2009.07.25
-
イギリスのテレビ局、オンラインゲームと仮想世界に関するドキュメンタリーを放送
採点終了後も連絡が無い所を見ると、どうやら合格したっぽい管理人です。一級試験の練習問題で頭から煙を吹いている本日のネタは、海外ネタで更新。イギリスのテレビ局、オンラインゲームと仮想世界に関するドキュメンタリーを放送(THE SECOND TIMES)>>イギリスの公共テレビ局「Channel Four Television Corporation」>>(Channel 4)が、オンラインゲームと仮想世界をテーマにした>>ドキュメンタリー番組「Another Perfect World」を放送した。>>現在YouTubeにて約30分のダイジェスト版が公開されている。>>>>Channel 4は知識層や若者、マイノリティに向けた番組を放送することで>>知られるテレビ局。「Another Perfect World」はオンラインゲームや>>仮想世界を開発・運営する人々やユーザーの姿を追い、仮想世界内での>>人付き合いからUGC、仮想通貨、仮想経済にも踏み込んだ構成となっており、>>番組中にはWorld of Warcraftやセカンドライフ、Metaplace、リネージュI&IIなど>>名の知れたサービスも多く登場している。YouTube動画URL:http://www.youtube.com/watch?v=NxZP_ur_Tvo管理人も動画を全部見終えてないので、今回は紹介のみで。明日は、少し長めの記事で更新予定。
2009.07.24
-
アカウントをBANされたゲーマーが運営を訴訟
市場調査用DB作成するにしても精錬値/属性/★個数等の処理がややこしくなりそうで頭抱えそうだなと思う管理人です。カード刺し後の処理も考えるとかなり厄介だなと思う今日のネタは昨日に引き続き、海外ニュースを紹介。『Resistance』でPSNのアカウントをBANされたゲーマーがソニーを訴訟-アメリカ(GameBusiness.jp)>>『Resistance: Fall of Man』のオンラインプレイでPlayStation Networkの>>アカウントを規制されたゲーマーが、苦痛を受けたとしてSCEA(※)を相手取り>>訴訟を起こしました。※)SCEA:Sony Computer Entertainment Americaかなりグダグダな訴訟内容だったので、下記にまとめて見た。・訴訟主は米国サンノゼ出身のErik Estavillo氏。・BANされた理由は『Resistance: Fall of Man』をプレイ中に問題行動を起こし、 SCEAのGMの判断によりPSNアカウントも含めて永久凍結に。・Erik Estavillo氏は広場恐怖症で有り、PSN上が唯一の社会交流の場だった。 しかし、今回の一件で米憲法修正第1条で保障された言論の自由を奪われ、 苦痛を受けたと主張し、同時にウォレット残額まで剥奪されたのは窃盗だと主張。 慰謝料として5万5000ドル(約515万円)を要求。この記事を見て先ず思ったのは「アメリカ的な発想だな」と「自業自得では?」と言うのが管理人の第一印象だったが、どんな発言をして凍結されたのかが不明と言う事なので、内容次第では情状酌量の余地は有るかも知れない。今回の件に関しては、国内でなら正直ウォレット残額の返金も難しいだろうが、仮想資産が認可されつる有るアメリカでは返金される可能性が無いとは言い切れない。この件に関して続報が入り次第、追って紹介予定。
2009.07.23
-
スウェーデン政府、仮想アイテム売買に課税検討
市場調査用DBを構築しようにも、構造設計の時点で苦戦しそうな管理人です。簡単に構築したとしてもテーブル5つは使いそうな気がする本日のネタは海外からのRMT絡みのニュースを紹介。スウェーデン政府、仮想アイテム売買に課税検討(THE SECOND TIMES)>>スウェーデンの「Stockholm News」の伝えるところによれば、>>スウェーデン国税庁は今後仮想アイテムや仮想通貨の売買における>>ユーザーの収入に課税することを検討しているという。>>>>スウェーデン国税庁は以前より電子商取引やオンラインカジノ、>>ポルノや有料の占いサイトなどで脱税が行われていないか調査していたが、>>その一環で14ヵ月に渡りオンラインゲーマーのアバターの取引も調査。>>すると、なんとその間に約6億6200万SEK(クローナ:スウェーデンの通貨)もの>>利益が上がっていたことが明らかになったという。>>しかしこの仮想空間内での収入を確定申告したユーザーは>>ほとんどいなかったとのこと。現在、各国で仮想通貨に対する法整備が検討されて来ているが、これらは全て「RMT容認」とも取れる気がするのは管理人だけだろうか?セカンドライフの様に運営公認のRMTが有るタイトルと同列に扱われて運営非公認のRMTも容認される流れになる危険性が十分に考えられる。この手のゲームをやった事の無い人間から見れば、どれも一緒に見えるらしく、「RMT」の問題について説明するだけでも小一時間はかかってしまう。もう一度、RMTの問題等について詳しく扱った特集記事も検討しつつ、本日は締め。
2009.07.22
-
マジコン不正利用者、未だに後を絶たず
仮にROの市場調査DBを作るとしたらデータテーブルやリレーションの設計で苦労しそうだなと思ってしまった管理人です。暇を見て設計試験的な物をExcelで作成してみようかなと考えている今日のネタはマジコン関係のネタで更新。山手線に“不正利用者”はこんなに居た!「マジコン調査隊」報告No.01(Gpara.com)詳しいことは上記リンク先で確認する事をお勧めするが、山手線利用客でDSで遊んでいる乗客のマジコン使用率を調査した結果は、調査対象215人に対して約1割にあたる20名が「マジコン」でゲームをプレイしていたとの事。あくまで目視確認で有り、、カバーでDS本体を覆っていた場合や、指でソフトカートリッジを隠していた場合等、目視確認できなかった分に関しては、カウントしていないとの事。サンプル献体が少ないので、確率的な偏りが有るだろうが、DSユーザーの約1割がマジコンを利用してDLしたタイトルを利用していたなら、かなりの損害だろう。個人的に気になったのは、下記の一文。>> また、「マジコン」の使用者は10代から30代が中心となっていることや、>>女性ユーザーも割と使用していることが判明している。最近ではP2P交換ソフトを利用してのDLソフトでのプレイを自慢した学生のブログが炎上した例や、「魚拓(※)写真」を取られた事に対して削除要請を行ったりする例も何件か有るらしい。管理人の感想としては『「不正行為=格好良い」と勘違いしてるのが増えた』としか、正直言い様が無い。モンペに保護されて甘やかされた若年層が今後もばら撒かれ続ける事を考えると正直気が重くなるのは管理人だけだろうか?ただでさえ、今のゲーム業界はかつて無い氷河期と言われている中で、現状が続けば倒産するメーカーばかりでは無く、ゲーム開発から撤退する可能性も十分に有る。開発・販売元も利益の出ない事業に投資を続けるほど甘くは無いのだから。
2009.07.21
-
SNSを狙ったマルウェアが急増 感染率はメールの10倍
連休中、カムバック対象垢が有ったもののほとんどプレイしていなかった管理人です。職業訓練先=訓練校の為、まだ暫く勉強出来そうなのでLuaかSQLでも少しかじろうかと思案している本日のネタは、セキュリティ関連ネタで更新。SNSを狙ったマルウェアが急増 感染率はメールの10倍(CNETJapan)>>Web 2.0サイトの特徴は、コラボレーション、ユーザーの参加にあり、>>そこに新たな攻撃が仕掛けられているとるとTanase氏は言う。>>たとえばYouTubeの動画の詳細情報や、Diggのコメント欄、Twitterの投稿、>>LinkedInのプロフィールにポルノサイトへのリンクが張られるといったものだ。>>>> なかでもソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を狙った攻撃は>>拡大を続けている。2006年から毎年2倍以上の増加ペースで、>>2008年は2万5000以上のマルウェアがSNSを介して広がったという。>>これらのマルウェアは2005年頃にまずOrkutで広まり、2006年からは>>MySpaceで急激に拡大した。2007年以降はFacebookを介したものも目立ってきている。Web2.0を利用したサイトを見てみると、 イギリスのF1チーム「Brawn GP」のサイト、ホワイトハウスのサイト、そしてローマ法王のサイトまで有る模様。Web2.0の最大の特徴であるユーザー参加やコラボ機能を悪用した形で、感染が拡大している例も何件か確認されている。>> SNSでの攻撃はメールを介したワームと酷似しているが、>>マルウェアの感染が成功する割合は、SNSを利用した場合が10%、>>メールを利用した場合は1%と10倍の開きがある。>>その原因は、SNSのユーザーは自らの友達リストにある人たちを信じる傾向にあり、>>深く疑うことなく、受信箱に届いたメッセージを受け入れてしまうという点にある。>>>> SNS特有のサードパーティ製アプリケーションも脅威となる可能性があるという。>>「Photo of the Day」という実験アプリは人気SNSが強力なボットネットと>>なることを実証した。このアプリはナショナルジオグラフィックのサイトから>>毎日違う写真を選んで、Facebookに配信するというものだが、>>裏側に仕掛けられたコードがユーザーをボットネット化し、DoS攻撃をさせる。上記の問題点をまとめるとシステム的な問題とユーザー側の問題が見えて来る。システム的なものはパッチの欠落や無認可のソフト利用、ユーザー側の問題はSNS経由のユーザーを鵜呑みに信用する点や個人情報流出等である。システム的なものは運営側の対策なので、今回は扱わないが、ユーザー側の問題は各個人が対策する事で被害は最小限に食い止める事が可能だろう。上記転載文にも有るが、「友人登録されている相手からのメールだから問題無い」と無防備に開けてしまうのも、問題では無いだろうか?例え、友人からのメールで有ったとしても、一度ウィルスチェックを行った上で開封する事が自分のみならず、送信者を守る事にも繋がる。仮にウィルス感染の踏み台にされた場合、本人に自覚が無かったとしても、追跡結果によって、本人からの感染が理由でとある企業で莫大な損害が出た場合、損害賠償が請求される可能性も有る上、最悪敗訴となる可能性も否定出来ない。(感染する企業にも問題ありと言わざるを得ない気もするが…)自分自身で自己防衛すると言う事は、周囲への被害を拡大する可能性を減らし、文字通り自身の身も守る事に他ならないと言うことを忘れてはいけないのだろう。
2009.07.20
-
「サーバー型」警戒 「電子マネー」利便性に落とし穴 (考察)
カムバックでROに顔出しした結果、東兄貴村に到着と同時に道兄貴の挨拶を見事に喰らった管理人です orz毎回、道兄貴と超兄貴に会ってる気がする本日のネタは昨日のネタの考察。簡単に電子マネーの特徴をまとめると下記の三点。・高い匿名性⇒匿名性の高さと銀行口座を経由せずに送金可能な為、資金洗浄が容易に可能。 中には電子マネー⇔現金の仲介業者も存在するらしい。・1600億円市場⇒本人認証せずに使える上に、コンビニ等で販売されたりなど利便性も高く、 年々利用率も向上し、本年度は1600億円を超えると言われている。・一向に追いつかない法整備⇒匿名性の高さや仲介業者の存在の為、振り込め詐欺の取引に使われる可能性や 最初に述べた資金洗浄が容易に行われる抜け道も存在している。(※)※昨日の記事でも紹介したが、知人の口座から預金を引き落とした後に、その預金を利用して電子マネーを購入、その後自身の電子マネー口座に入金させた。上記の事件で使われたのがウェブマネーウォレットの様に、ネット上に専用口座を設ける仕組みの物が使われた様だが、問題はコレだけではない。今回の情報元の記事によれば、RMTに上記の様に犯罪資金が流入した資金洗浄が行われたケースも確認されたらしい。この状態だと、数年内に最悪の環境が発生するのではないかと危惧している。RMTに直接関与していなくても知らない間に間接的に関わる環境が定着したならMMO業界ばかりではなく、オンラインゲーム業界全体の存亡に関わりかねない。正直、法整備にばかり期待せずに、ユーザー自身が現状を再認識して各自の行動を見直す所から始める必要が有るのかも知れない。
2009.07.19
-
「サーバー型」警戒 「電子マネー」利便性に落とし穴
無事に試験も終わり、一段落付いている管理人です。連休明けから、再び資格試験勉強と就活再開な本日のネタは、電子マネー関係のニュースが入って来ていたので紹介。「サーバー型」警戒 「電子マネー」利便性に落とし穴(産経新聞)>>本人認証を必要とせずに「財布」が持てる匿名性の高さや、>>入出金の容易さから、不当利得の資金洗浄(マネーロンダリング)や>>振り込め詐欺への悪用が指摘される。>>捜査当局は「金融犯罪の温床となりかねない」と警戒を強めるは、>>膨張を続ける仮想世界に、法制度が追いつかないジレンマもある。>>>> 今年春、京都府内の男(21)が府警ハイテク犯罪対策室に逮捕された。>>容疑は不正アクセス禁止法違反、電子計算機使用詐欺など。>>知り得た知人の銀行口座のIDとパスワードを使ってパソコンで>>銀行のサーバーにアクセスし、知人の預金を電子マネーの売買業者の口座に>>移すよう操作して電子マネー約30万円を購入、ネット上の男の財布に>>入金させたとされ、後に京都地検に起訴された。>>>> 府警は、男が不当に得た金を匿名性の高いサーバー型電子マネーに>>換えたことを重視し、ネット上の闇換金サイトを通じて現金化していたことも>>突き止めた。「電子マネーを使った明らかな資金洗浄だ」。>>取り締まりのリーディングケースになると目を光らせた。>>>> 組織犯罪処罰法の「犯罪資金の隠匿」など、地検とともに約2カ月間にわたり>>検討を進めたが、法務省サイドは立件には消極的な見解だったという。>>捜査幹部は「電子マネーの資金洗浄は法整備が脆弱(ぜいじゃく)だ。>>だが、さらに検討を進めて取り締まりたい」と話す。管理人の考察については、文章がまとまっていないので明日の更新にて。
2009.07.18
-
カメラを覗くとゾンビがいた! 携帯端末で遊べるゲームを米大学が開発
明日の残り二教科の試験が終わり次第、RO内に顔出しするか思案中の管理人です。今回の試験が終わっても、次の試験対策が始まる気がする本日のネタは海外初の拡張現実をゲームに応用した実例について紹介。カメラを覗くとゾンビがいた! 携帯端末で遊べるゲームを米大学が開発(Gpara.com)>> 現実世界にバーチャルな情報を重ね合わせる“Augmented Reality>>(AR:拡張現実)”。このコンセプトをゲームに応用する新たな試みが、>>米ジョージア工科大学の研究グループ“The Augmented Environments Lab>>(AEL)”の手で進められている。>>>> 同グループが開発中のゲーム『ARhrrrr!』は、カメラ付き携帯端末を使った>>ユニークなリアルシューティングゲーム。>>机の上のマップをカメラでのぞくと、マップ上にビルが立体的に建ち並び、>>ゾンビの群れが徘徊するのが見えてくる。カメラの向きを変えれば、>>3Dオブジェクトの向きも同じように変わり、高速のズームイン/アウトも>>可能とのこと。>>>> プレイヤーは、マップ上空を飛行するヘリコプターのパイロットとなり、>>街をうろつくゾンビを撃ち倒して、安全地帯に向かう一般市民を>>助けることになる。上空にいるからといってプレイヤーも決して安全ではなく、>>ゾンビが投げつけてくる“臓器”を回避できなければダメージを食らってしまう。>>>> また、マップ上にキャンディーを配置し、これを爆弾に見立てて>>利用することも可能。キャンディー爆弾を撃つと大爆発が起きて、>>複数のゾンビに大ダメージを与えられるのだ。某漫画にカードに描かれた絵を実体化させると言うシステムが有ったが、そのシステムの応用と考えた方が良いだろう。PS3でもこう言ったシステムのタイトルが有るらしいが、今回のは携帯版で有り、FPS形式の作りになっている点が、各方面から高評価を得ている様だ。管理人予想では10年以内にこの手のゲームが1ジャンルとして確立されると見ているがコスト面やゲーム市場が持つかどうかと言う点で考えると、難しいかも知れない。
2009.07.17
-
ココアと楽天が業務提携、meet-meの仮想通貨と楽天スーパーポイントの交換を開始
急に明日DB3級の試験を受ける事になった管理人です orz完全解答を狙う気でやれば何とかなる可能性が見えて来た本日のネタは過去に紹介した仮想通貨関係ネタの二の舞になりそうなニュースの紹介。ココアと楽天が業務提携、meet-meの仮想通貨と楽天スーパーポイントの交換を開始(THE SECOND TIMES)>>meet-meを展開する株式会社ココアと楽天株式会社が業務提携を行い、>>本日7月15日(水)よりmeet-me内の仮想通貨「MMP」と楽天スーパーポイントの>>交換サービスを開始した。>>>>「MMP」はmeet-me内で企業のアトラクションやイベント等への参加、>>土地代金の支払い金額に応じてユーザーに付与される仮想通貨。>>今回「楽天スーパーポイント」への交換サービスの開始により>>ユーザーは仮想空間内で貯めたポイントを楽天市場での買い物時に>>使用することが可能となる。交換パターンは以下のとおり。>>>>MMP → 楽天スーパーポイント>>1,100MMP → 1,000楽天スーパーポイント>>3,100MMP → 3,000楽天スーパーポイント>>5,100MMP → 5,000楽天スーパーポイント以前、中国でも同様のサービス(Q幣)が有ったが、現実の通貨価値より価値を持ち始めて経済が崩壊しかけた為に、廃止になった経緯が有る。今回の例もそこまで発展するかどうかは分からないが、可能性は十分に有る。一番怖いのが、これらのポイントに対するRMTやハッキングによる増殖だろうが、その辺りの対策は運営側が心配する事なので、しばらくは静観予定。
2009.07.16
-
快挙!ドイツの「暴力ゲーム規制反対」署名、一週間で目標の5万人を達成
何とか表計算2級に関しては目処が付いたものの、他二教科に関しては全く自信が沸かない管理人です orz盆明けまでAccess等の勉強が集中して出来る環境になりそうな本日のネタはドイツ発の規制に対抗する活動に関するニュースを紹介。快挙!ドイツの「暴力ゲーム規制反対」署名、一週間で目標の5万人を達成(THE SECOND TIMES)>>現在ドイツにて行われている「暴力ゲーム」規制に反対する署名活動が、>>開始からたった一週間で目標の5万人分の署名を収集した。詳しい経緯に関してはコチラでも書かれているものの、本文より転載。>>現在ドイツ政府では、作中に暴力的な表現のあるゲームの開発・販売及び>>プレイの一切を禁止する法案を審議している。>>もしこの法案が成立してしまった場合、「暴力ゲーム」を開発した>>ゲームディベロッパーや販売に関わった流通関係者、そしてプレイした>>ゲーマーとゲームに関係した全ての人間に対し罰金と最大1年の懲役刑が>>課せられることになる。>>この動きを受け、当初8月に開催される予定だったシューティングゲーム>>「カウンターストライク」のLANパーティイベント「Convention-X-Treme」など>>複数のゲームイベントが中止に追い込まれてしまった。>>しかしこれに対しドイツ国内のゲーマーが決起。>>「暴力ゲーム」への規制に反対するデモ行進を開催すると共に、>>ネット上で政府にゲーム規制の見直しを求める署名を行うよう呼びかけた。>>ドイツでは5万人以上の署名が集まると正式な嘆願書として認められ、>>審議の際に”国民の声”として効力を発揮する。署名の呼びかけが>>始まったのは7月8日で、当初は8月28日までに5万人の署名を集めることを>>目標としていたが、なんと呼びかけ開始からたった一週間で目標を>>達成してしまった。この規制が始まった理由は、非常にシンプルな構図で、告示した例は国内でも有る。今年3月にドイツ南部シュツットガルトにて17歳の少年が学校で銃を乱射し、自殺する事件が発生したのだが、この少年が「カウンターストライク」を所持していたことから政治家の間で「凶悪犯罪はゲームのせいだ」という声が上がり、上記の全面禁止法案が上がって来た模様。現在、世界各地で珍妙な法案が審議されたり、可決される例が多数確認されているが、正直ヒステリーを起こしたモンペ並の反応にしか見えないのは管理人だけだろうか?ろくに実態も調べない上、知ろうともせずに考え無しに規制・禁止をかけていく。その結果、犯罪率が向上したならどう言い訳するのか正直見物で有る。
2009.07.15
-
違法着うたサイト「着うたキングダム」、運営会社社長ら2名が逮捕
試験まで残り4日とせまってきたものの、今一つ確証が持てない管理人です。最悪ワープロ検定を切り捨てて、他二教科に集中しようか思案中の本日のネタはIASRAC絡みのニュースが入ってきたので紹介。違法着うたサイト「着うたキングダム」、運営会社社長ら2名が逮捕(CNETJapan)>> 岡山県警察本部生活環境課、生活安全企画課、岡山西警察署は7月13日、>>権利者に無断で携帯電話向けの音楽ファイルを送信可能な状態にしていたとして、>>ウインズコミュニケーションズ取締役会長の藤井功年容疑者と、>>代表取締役社長の隅川雅樹容疑者の2名を著作隣接権侵害の容疑で逮捕した。 >>>> 調べによると、この2人は共謀のうえ、岡山市内に設置されたサーバに>>「着うたキングダム」という名称のモバイルサイトを開設。>>エピックレコードジャパンとエイベックス・エンタテインメントが権利を持つ>>音楽ファイルを無断でアップロードし、不特定多数がダウンロードできる状態に>>していたという。着うたキングダムではこれまでにのべ95万4000曲が>>ダウンロードされていたとのこと。 以前に「第三世界」と言う個人運営の着うたサイトが摘発された例は有るが、法人運営の携帯向け音楽配信サイトでの摘発例はコレが初らしい。(ちなみに「第三世界」運営人は懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決。)この手のニュースは不景気になればなるほど大量発生している傾向が有り、著作権云々より利用者のモラルの低下が要因なのでは無いだろうか?(管理人の着信音は普通に公式から着メロDLする程度)管理人の予想では、この手の事件は年内に後2件は報道されると見ている。利用者も運営も金策に困ると、違法行為と分かっていても手を染める傾向に有り、善悪の判断が麻痺している可能性が非常に高いからである。
2009.07.14
-
深刻化する青少年の“ネット中毒”を解消する取り組み
取り敢えず、から練習問題を落として来たので、明日の昼休みにでも飯食いながら回答する予定の管理人です。解答も合わせて印刷したものの、同僚の分も印刷したら分厚くなるなと頭抱えそうになった本日のネタは、海外のネット依存症対策について。深刻化する青少年の“ネット中毒”を解消する取り組み (Computerworld)>> 中国各地の青少年リハビリテーション・センターでは、社会性に欠け、>>学業成績が振るわず、場合によっては精神的に抑うつ状態にある>>ティーンエージャーたちが、数カ月間の更正プログラムを受けている。>>>> 15歳から19歳が中心となる入所者たちは、規則正しい生活を送りながら、>>軍事教練、武術訓練、講義、精神科医との面談といったプログラムを受ける。>>入所期間は3カ月間程度だが、入所期間中の鉄則は「インターネットの利用禁止」だ。中毒状態から回復させるには、根源から完全に切り離した生活が一番と言うが、この状況なら、ネットと完全隔離された生活環境になるだろう。ただし、中毒症状になる理由は当人ばかりとはいえない様だ。>> タオ氏によると、ほとんどの若者は親から強制的に入所させられている。>>だが、そもそも入所者たちがインターネット中毒に陥ってしまった背景には、>>学校の成績などに関する両親からの強いプレッシャーがある、と指摘する。>>>> そのため、同センターの更正プログラムでは親の参加も義務づけられている。>>入所者と共に、精神科医との面談やバスケットボールの試合、ディベートなどの>>活動を行うのだ。>>「もっと子どもと対話を図り、あまり小言を言わないようにすることで、>>子どもたちをバーチャルの世界から引き戻すことができる」モンペが、周囲に毒をばら撒いているのが原因なのでは?と思ってしまったのは管理人だけだろうか?最近はモンペが異常増殖しているばかりでなく、モンペに甘やかされて育てられた子供の存在も問題になりつつある今、更に問題は悪化しそうだ。
2009.07.13
-
脆弱性対応が遅れる企業でマルウェア被害が継続、マカフィー調べ
試験対策用の問題集を探したものの、MOUS関係しか無かった管理人ですorz手持ちの教本のみで当日まで居残り確定になりそうな本日のネタはマルウェア感染系で気になるニュースが有ったので紹介。脆弱性対応が遅れる企業でマルウェア被害が継続、マカフィー調べ(ITmedia)>> マカフィーは7月10日、6月度のセキュリティ動向を発表し、>>既知の脆弱性を悪用するマルウェアへの感染被害が続いていると指摘。>>パッチの早期適用を呼び掛けた。>>>> 感染動向では、AdobeのAcrobatやReader、Flash Playerの既知の脆弱性を>>悪用する「Obfuscated Script.f」や「Exploit-ObscuredHtml」、>>Windowsの脆弱性を悪用する「W32/Conficker」が多数に上った。>>一方、これらのマルウェアに感染した会社数は、感染したマシン数や>>データ数に比べると少ないことが分かった。>>対策を施していない一部の企業で感染拡大が続いているという。…此処最近発生している運営会社のアカウントハッキングもこの件が絡んでいるのでは無いかと嫌な予想をしたのは管理人だけだろうか?過去を辿れば、ROのBOTが発生した根源は海外の運営会社のサーバーからGM巡回用のツールが流出したのが起因だった例も有る。「対策しているから大丈夫」では、いたちごっこで常に後手後手に回るだけなので常に相手の先を読み、先手先手で対策を講じる事が必要なのでは無いだろうか?明日以降、更新が途切れる可能性があるものの、タイピング練習も兼ねているので極力休まず更新する予定。
2009.07.12
-
MMORPGは社会性向上に有効 韓国の心理学者が発表
資格試験まで@1週間となり、正直焦っている管理人です orz休日返上+居残りで対策するしかないかなと思っている本日のネタは韓国発のニュースで更新。MMORPGは社会性向上に有効 韓国の心理学者が発表(THE SECOND TIMES)>>韓国延世大学のド・ヨンイム(Doh Young Yim)心理学博士が、>>MMORPGの中での経験は人間の社会性向上に有効であるとの研究結果を発表した。>>博士の研究によれば、ゲーマーはオンラインゲームの世界を>>「現実世界の延長線上にある世界」と認識しており、そこでの経験は>>自我の形成と公共心の育成に役立っているという。>>>>博士はゲーマーがゲームの中で自分自身をどのように認識するかをを>>調査するため、ネクソン社が運営するMMORPG「マビノギ」を対象に、>>計57個の行動質問項目を設定してマビノギユーザーに対し主な行動様式を>>評価するよう依頼した。>>その回答を集計・分析した結果、ユーザーたちは最初のうちは>>ゲームの世界を「現実とは違う仮想世界」だと思い、ゲームの世界と>>現実世界を分けて認識しているが、時間が経つにつれゲームの世界も>>他の人々と一緒に住む世界であり、社会的なルールと秩序、信頼と礼儀を>>守りながら生きていかなければならない場所だと受け入れることが>>明らかになった。また「ゲームプレイを通して問題解決力や自己統制力を>>身につけることができた」という回答もあったという。これはあくまで一例なので、今回の報告結果が全てと言い切る事は出来ないが、こういった一面も有ると言う例として紹介してみた。同じ様にMMORPGをやっていたからと言ってユーザー全員が同じ様に身に付くかと考えた場合、答えは「No」と言わざるを得ないだろう。「所詮ゲーム」と割り切って自由に暴れ回り続けるユーザーも居れば、ゲーム内でのローカルルールを守ってプレイするユーザーも居る。唯一の救いは、こういった研究で肯定的な意見を出せる学者の存在。頭ごなしに否定・批判を繰り返すより多角的な視点で結論が出る日が来ることを正直切に願いつつ、今日は締め。
2009.07.11
-
「トキメキファンタジー ラテール」でアカウントハック被害?
最近、仮眠時間が増えた樹がする管理人です orz前説ネタが正直怪しい本日のネタは、アカハック系のネタで更新。「トキメキファンタジー ラテール」でアカウントハック被害? 利用者はパスワード変更を(4Gamer.net)【重要】不正なログインの被害と対応について (ラテール公式)>>現在、一部のお客様のアカウント情報(ID、パスワード)が悪意のある第三者に>>利用されている被害に関しまして、ご案内いたします。>>>>■現在の被害・対応状況について>>第三者が何らかの方法で不正に取得したアカウント情報を用いてゲームに>>ログインし、そのアカウント内のキャラクターからアイテムを盗みだすという>>被害を確認しております。>>このような行為は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」をはじめ、>>弊社ゲームポットID利用規約における禁止行為、その他の不法行為にあたる>>可能性がございます。>>>>現在、パスワードの変更でお客様のセキュリティを強化していただく対策とは別に、>>弊社が提供しています全てのゲームタイトルのサーバー、ネットワーク、>>データベースの調査を徹底して実施しております。>>現段階におきましてはお客様のアカウント情報が漏洩した痕跡、事実は>>確認されておりません。>>原因究明と被害防止のため、いくつかの対策を弊社システム内に>>順次導入しております。ゲームポッドに関しては、先月中旬にもCABAL ONLINEにて同様の被害が発生している。この際も、強制的にパスワード変更するまでログイン不可で対応していたが、いまだに原因が特定されていないのが、実情で有る。管理人の記憶が確かなら、昨年のパンヤ公式サイト改ざんも含めれば、今回で3回目の被害になり、次はFEZが狙われるのではないか?との推測も。詳しいことは公式サイトでの告知に書いてあるので、心当たりの有る方は公式告知で確認を。追記)来週末の試験終了後、結果次第でワープロ検定&表計算1級+DB検定2級まで連続で資格試験を受けることになる可能性が浮上。
2009.07.10
-
米裁判所、著作権を巡る集団訴訟でYouTubeに有利な判決(考察)
取り敢えず、DB3級対策は必死に慣れるしかないなと痛感した管理人です。正直フォームとレポートのレイアウトの細かい修正は放置したい本日のネタは、昨日紹介した記事の考察で更新。簡単にまとめると、イギリスのプレミアムリーグの動画がYouTubeにアップされた件では有るものの、放送権を持っているMTV等との訴訟とは別件。今回の訴訟を起こした相手は 米国音楽出版社協会(NMPA)やBob Tur氏(※)ら。※:Bob Tur氏YouTubeを著作権侵害で訴えた最初の人物でも有り、有名な映像を多数報道したことで知られているジャーナリスト。今回の判決結果では、 英国のサッカーリーグの動画は外国作品で有る為、米著作権法の対象外であり、「適切な時期に登録されなかった外国および国内の全作品について法定損害賠償を禁じている」との事。しかし、Tur氏とNMPAの作品は、米国に拠点が有る為、米国著作権法の対象になるのではないか?と言う意見も上がっているらしい。ただ、冷静になって考えてみるとサッカーリーグ自体が国内に拠点を置いているならまだしも、サッカーリーグの映像がTur氏とNMPAの作品で無い以上、集団訴訟という形で参加したとしても、勝ち目は有ったのだろうか?「適切な時期に登録されなかった外国および国内の全作品について法定損害賠償を禁じている」と言うアメリカの著作権法だが、これで痛い目を見せられた影響で、著作権絡みの問題にうるさい団体が有る。あまり詳しく書かなくても予想は付くと思うが、某有名キャラの生みの親はかつてこの著作権法で泣かされて、莫大な損害を受けている。その被害の痛手により、故郷に帰る道中であのキャラを生み出した事は意外と知られていない。今一度、著作権とはどういった権利で何の為に有るのか、再度見直す時期だと考えているのは、管理人だけだろうか?
2009.07.09
-
米裁判所、著作権を巡る集団訴訟でYouTubeに有利な判決
DB検定対策の過去ドリルで見事玉砕した管理人です orz最新版は問題の記述方式が変更されているものの、自信の無い本日のネタは気力的な事も有り記事の紹介だけで更新。米裁判所、著作権を巡る集団訴訟でYouTubeに有利な判決(CNETJapan)>> 少なくとも3人の著作権保有者から著作権侵害訴訟を起こされている>>GoogleのYouTubeは米国時間7月7日、法廷でいくつかの小さな勝利を勝ち取った。 >>>> 今回の決定は、より大きな訴訟である、MTVやParamount Picturesの親会社>>Viacomが2007年3月にYouTubeを相手取って起こした訴訟とは無関係だ。>>しかし、Googleは、米連邦裁判所に対し、欧州のサッカーリーグによる>>法定損害賠償請求を棄却させることに成功した。 >>>> ニューヨーク州南部地区のLouis Stanton米地方裁判所判事は、>>英国のサッカーリーグであるPremiere Football Leagueの動画は>>外国作品であるため米著作権法の対象外となると述べ、>>懲罰的損害賠償請求も棄却した。 >>>> 同著作権法は「適切な時期に登録されなかった外国および>>国内の全作品について法定損害賠償を禁じている」とStanton判事は書いた。 今回の原告の背景や今回の判決結果による影響等に関しては、明日の更新にて。(3時間程度の仮眠から起きたばかりで脳が回ってない&情報整理が出来ていない為)
2009.07.08
-
PS2はOK、PS3はダメ――。イギリスの刑務所で最新ゲーム機の使用が禁止されたワケ
正直DB関係の試験に関して自信が持てない管理人です。模擬試験で馴らして確率引き上げる以外無いかなと思ってる本日のネタは少し前に入ってきた海外の刑務所事情で面白いネタがあったので紹介。PS2はOK、PS3はダメ。イギリスの刑務所で最新ゲーム機の使用が禁止されたワケ(ITmedia)>>イギリスのある刑務所では先日、服役囚たちが所内でプレイステーション 3、>>Xbox 360、Wiiなどの最新ゲーム機で遊ぶことを正式に禁じたそうです。>>ただしプレイステーション 2、プレイステーションといった>>前世代のハードは引き続きOK。>>>> 実は問題となったのは「ゲームで遊ぶ」という行為そのものではなく、>>これらのゲーム機が「ネットワーク接続機能を有していた」という点。>>>>同刑務所では服役囚がプレイステーション 3の無線LAN機能を使って>>刑務所のネットワークに接続、外部と連絡を取っていたことが>>確認されていたとのこと。刑務所内にゲームが持ち込める時点で国内では考えられない位の優遇だが、驚いたのはこの後の文章。>>これまでイギリスでは服役囚たちのゲーム代も政府が負担していたそうで、>>その額は年間5万ポンド(約800万円)以上にものぼっていたとのこと。>>今回の決定を受けて、イギリス政府は「ゲーム代は服役囚たちが>>自分で負担すべき」とする法案をただちに可決したそうです。多分、私設の刑務所だろうなと予想していたのが、国営の刑務所とは思わなかった。オマケに税金を使って服役囚に買い与えていたのには噴かざるを得ないかと。「真実は小説よりも奇なり」の実例と言う事で今日はこれにて締め。
2009.07.07
-
">「FFXI」米で5億円の集団訴訟 新作発表による八つ当たり説が浮上
気になる記事を見かけたので、少々フライング気味に更新している管理人です。試験まで取り敢えずOffice2003Personalでしばらく対応予定の本日のネタは、先日紹介したFF11関連の訴訟に関する推測記事を見かけたので紹介。「FFXI」米で5億円の集団訴訟 八つ当たり説も(ITmedia)一応、復習の意味も兼ねて訴訟内容の確認。>> 24日付の米紙「コートホース」(電子版)によると、ユーザー10万人を>>“代表”して同社を訴えたのはサンフランシスコ在住の中国系女性。>>この女性は、「FFXI」をオンラインでプレーする際、毎月支払う12.95ドル>>(約1250円)のプレー代金や、支払いが延滞した際の遅延金、未払いによる>>参加権利の制限やデータ消去などが不当なビジネス手法であり、>>ソフト購入時に十分な説明もなかったとしている。この件に関する評論家の意見の中に、訴訟の本当の理由らしき物があったので紹介。>> 「オンラインゲームは参加条件を規約で提示しており、同意することで>>参加できる。もちろん、FFXIは英語版も完備している。>>疑似世界であるオンラインゲームのユーザーは“のめり込み”が激しく、>>ゲーム上で不愉快なことがあるとメーカーに八つ当たりする傾向が強い。>>今回も、それに近いのかもしれません」>>>>「実は今月3日、新しいFF14が発表された。当然、大半のユーザーは14に移るが、>>それにより開始から7年間費やしたXIが廃れてしまうことに怒りを>>ぶつけているのかもしれない」と推測する。トレーラーサイトも掲載されていたので同時に紹介。正直、この画質でスムーズに動くPCとなるとi7以降でグラフィックボードも現行の最新版クラスで無いと厳しい気がする…と話が脱線しそうなので、切り替え。上記の推測に加えて、FF14の正式運営開始で、FF11が終了するのでは?と言う不安も混じっているのでは無いかと思える。どんなに良策のMMORPGでも何時かはサービス終了が来る事には間違いは無い。だからといって、運営相手にお門違いのクレームを付けるのもどうかと思う。(今回の訴訟の一件はRMTが絡んでいる気もするが、確証が無いので追求はしない)管理人としても、ネトゲの世界から足を洗う際は、異様な執着をする事も無く、跡を濁さずとは言わないが、静かに抜けられればと思っている。
2009.07.06
-
中国、PCへのフィルタリングソフト義務付けを無期限延期
最近、ブログの方向性を再度見直す時期かなと思い始めた管理人です。職業訓練が終わるまでに、再度方向性を見定めたい本日のネタはかなり放置気味だった例のフィルタリングソフトに関しての続報。中国、PCへのフィルタリングソフト義務付けを無期限延期(ITMedia)>> 中国政府は、同国で販売されるPCにフィルタリングソフトの搭載を>>義務付けるという計画を無期限に延期することにした。>>開始数時間前の、突然の撤回だった。>>>> この方針撤回は6月30日遅く、新華社が伝えた。同紙は、>>工業情報化省が「物議を醸しているフィルタリングソフト>>『Green Dam-Youth Escort』の新しいPCへの搭載義務付けを延期する」と報じた。この一件に関しては、国内外から猛反発を受けた事も一因している様だが、中国政府自体も実装に関して諦めた訳では無さそうだ。それを象徴するのが、下記の一説。>> 工業情報化省はコンピュータ企業の批判を受け入れたが、何らかの形で>>検閲が復活する可能性は残した。>>共産党がインターネットを依然として警戒しているのは確かだ。天安門事件を例にしても、政府にとって都合の悪い情報を隠蔽する体質は何処の国も変わらないのだろう。問題噴出時だけ、その場の対処で逃げている。本当に問題を解決するには、問題そのものを根本から解決するしかないのに、小手先の解決だけで、ガス抜きして延命させている様にも見える。これは各運営会社にも言える事で、不正者対策を行いますと言っている割に本腰を入れて対策を行っているのは一握りだけで、大半は放置していると揶揄(やゆ)されても仕方無いレベルの状況になっている。不正行為を行うユーザー側にも問題が有ると言えなくも無いが、BOT等に関してはユーザー間で解決出来ない以上、運営に頼らざるを得ない。不正行為を見かけても「どうしようもない」と諦めている中間層の多さにも、一因は有るのかも知れないが、これに関しては強要は出来ない。ただ、「見て見ぬ振りで問題は解決するのか?」と問う権利は残して置いて欲しい。
2009.07.05
-
小5男児800万円盗んで豪遊
資格試験まで@2週間を切った今、Office Professional Enterprise Edition2003を購入しようか思案している管理人です orz資格試験終了後も使う可能性を考えて、購入するか悩んでいる本日のネタは少し前に報道されたこのネタで更新。小5男児800万円盗んで豪遊(Yahooニュース/スポーツ報知)>> 今年5月に沖縄県石垣市の民家から現金約800万円が盗まれた事件で、>>八重山署は現金を盗んだとして、小学5年の男子児童(10)を児童相談所に>>通告したことが2日、分かった。通告は6月30日。>>>> 同署によると、5月7日午後、市内の男性から「家でタンスなどに>>保管していた現金約800万円が盗まれた」との通報があった。>>一方、男児は盗んだ金で、高額なテレビゲームを買うなどの遊興費として使っていた。>>>> 数日後、不審に思った父親が男子児童を問いただしたところ、>>民家に侵入し、現金を盗んだことを認めたため、同署に出頭。>>男性に謝罪し、弁償した。>>>> 盗まれた現金の大半は残っていたが、男子児童は小学校の同級生ら約20人に、>>最高で数十万円の現金を配っていたという。>>周辺では「お金の使い方がおかしい」などと、うわさになっていたという。…色んな意味でツッコミ所満載な気がするが、取り敢えず問題点をまとめると、1.父親が異常行動に気付くまで、数日かかった事。2.子供が盗みに対して罪悪感を持っていない事。3.周囲の同級生らが何の違和感も無く、現金を受け取っていた事。4.噂になっている時点で警察が気付かなかった点。出頭⇒通告までに約2ヶ月かかった点に関してもツッコミ入れられそうだが、面倒なので今回はスルー。1と2に関しては、両親の教育方針等に問題が有ったとしか言えないし、3に関しては、受け取った子供達の両親の育成に問題有り。4に関して言えば、「本当に調査してたのか?」と言う疑問も有るが、周囲から情報提供が無ければ、こう言った件は難しいので深く追求はしない。ともあれ、金銭感覚や罪悪感の無い若年層が増加している背景には、両親の無関心や無責任が有る気がするのは管理人だけだろうか?無論、やった小学生本人に責任が無いとは言わない。小学校5年なら十分善悪の判断が可能な年齢だと思うのだが…。
2009.07.04
-
ネトゲユーザー、借金返済のために仮想マネー横領
表計算二級に関しては、多少なりとも光明が見えた管理人です。試験終了⇒結果通知までは油断出来ない本日のネタは海外の話題で更新。ネトゲユーザー、借金返済のために仮想マネー横領(ITMedia)>> この事件が起きたのは、30万人以上の会員が月額15ドルで利用している>>EVE Onlineというオンラインゲーム。>>World of WarcraftやSecond Lifeに似たゲームで、プレイヤーは>>「遠い未来、人類が宇宙に植民した」という設定の世界で、働いたり、>>マーケットを運営したり、敵を殺したりしてお金を稼ぐ。>>>> 事件の中心となったのは、プレイヤーが運営する金融機関の中で>>最大のEBank。数千人の預金者を抱えている。>>>> 「犯人はしばらく前からEBankを運営しているメンバーの1人だった。>>彼は大量の(仮想)マネーを銀行から持ち出して、本物のお金に換えた」と>>このゲームを開発したアイスランドの企業CCPのネッド・コッカー氏は語る。コレを見てまず思ったのがRO運営の黒歴史たる「戸枝事件」。 共通点としては、共に借金返済が理由と言う点も有るが、どちらも仮想通貨を管理する立場(ゲーム運営と仮想通貨銀行運営)だった点。>> 彼は、ゲーム内で金を稼ぐよりも現金で仮想マネーを買いたいという>>プレイヤーと取引し、盗んだ仮想マネーを6300豪ドル(5100米ドル)と交換した。>>このような行為はEVE Onlineでは禁止されている。>>>> 彼は、仮想マネーと現金を交換するブラックマーケットサイトを宣伝する>>スパムが送られてきて、それを見て、家の手付け金や息子の治療費を支払うために>>仮想マネーを現金に換えようと思ったと話す。…赤字の部分が事実だとしても、罪状が軽くなる訳では無い。しかし、「自身の子供の命がかかっていた」と考えた場合、断罪出来るかどうか、正直な所、管理人でも悩んでしまうだろう。(だからといって、やっても良いと言う訳では無いが)
2009.07.03
-
“社交ゲームは協調性、暴力ゲームは攻撃性を伸ばす”との説に待ったの声
試験までにDB3級の出題範囲を網羅出来るか、少々不安な管理人です orz正直腹括るしか無いかなと思えて来た本日のネタは、少し前の海外ニュースから。“社交ゲームは協調性、暴力ゲームは攻撃性を伸ばす”との説に待ったの声(Gpara.com)>> 平和的な手段で問題を解決するゲームと暴力的なゲームを2つのグループに>>プレイさせ、そのあとで、無作為に選ばれたパートナーに対してパズルを>>出題してもらう。パズルは3つの難易度から自由に選ぶことが可能で、>>パズルを解いたパートナーは賞金10ドルをもらえるようになっている。>>>> この実験の結果、平和的なゲームをプレイした人はパートナーに向けて>>易しいパズルを、暴力ゲームをプレイした人は難しいパズルを出題する傾向が>>強かったという。上記結果を元に、「ゲームはその内容を見ながら善し悪しを決めるべきだ」と今回の実験を行った米ミシガン大学のBrad Bushman氏などが学術誌で紹介したらしい。ただ、上記の実験内容を見たが、単に「暴力的なゲーム=悪」と言う前提で今回の論文をまとめた気がするのは、管理人だけではなかった様だ。テキサスA&M大学のChris Ferguson教授は上記テストの結果に対して、>>「“ゲームと人の協調性・攻撃性は関係している”と端から決めてかかり、>>問題点を抱える研究例から都合のよい側面だけを取り上げている」>>「パズルの出題は現実の暴力とはまったく別物。判断基準にはならない」と、Brad Bushman氏達の説を一刀両断している。固執した考えを持つ事は研究者にとって最大の端だと聞いた記憶が有るが、今回の例はそれに当てはまるのでは無いだろうか?
2009.07.02
-
増える「ネトゲ廃人」 退学、退社、離婚…それでも「やめられない」
無事試験放送は終わったものの、資格試験は目前&DB検定は正直落とすかも知れない管理人です orz(まだリレーションを少しかじった程度)増える「ネトゲ廃人」 退学、退社、離婚…それでも「やめられない」【1】増える「ネトゲ廃人」 退学、退社、離婚…それでも「やめられない」【2】増える「ネトゲ廃人」 退学、退社、離婚…それでも「やめられない」【3】(参照元:産経新聞)少し気になる項目だけを抜粋して見た。>>ネットゲームにはまる人は子供のころからゲームに親しんできた>>10代後半~30代前半の男性や主婦らが多いが、最近は小学生が増えている。>>>> ゲームに没頭するあまり親のクレジットカードを使って高額のサービスを>>購入する子供もいる。>>>>「ネットゲームにはまる子供は、親が離婚しているケースも少なくない。>>どんなゲームで月にいくら使っているのか、親がきちんと見ていれば止められる」>>と指摘する。最後の一文はネトゲ廃人の著者、芦崎さんの言葉から抜粋。簡単に総論をまとめると、依存症=心の隙間を埋める為に行う行為と取れると思うのは管理人だけだろうか?上記の例を見ても両親の離婚がきっかけでネットゲームにハマる例も有り、他にも引きこもりの原因になる理由とネトゲのにハマる理由が見事に一致する点も、この考え方の根幹に有る。最終的にはネトゲ依存になる=両親が子供の事を本当に見ていない証明と言うには証拠が不足しているので、断言は出来ないが目安にはなる様だ。
2009.07.01
全31件 (31件中 1-31件目)
1