全285件 (285件中 1-50件目)
-
サクラ サク ・・・
2007.03.23
コメント(5)
-

グランドキャニオンの絶壁に片持ち梁の展望橋・・・part2
先日、3/9のweblogで書いた記事のグランドキャニオンの展望橋ができたようです。 マズは、完成予想図以下も資料と同じ写真ですから、迫力を見たければ資料を見て下さい・・ インデイアンの家もみえます・・・ 掃除も大変ご苦労さんです・・・ 足元が雲海?足場が組めないから、手前で組みそれを、前方に押し出し施工したのでしょう・・・いずれにしても足元がおぼつかなく、今後のメンテが大切だし、これも大変・・・しかし入場料が約\3.000-とは高い・・・それだけの価値があるのでしょう、落ちたときの保険も込み?・・・・
2007.03.22
コメント(0)
-

Frank Owen Gehry・・・・度々・・・
偶然ですが、NYタイムズの記事をわからないのに検索していると、建築家Frank Owen Gehry氏の設計した建物がNYにできました、先日美術館は米国ではじめてと書きましたが、Frank Owen Gehry氏の追っかけではないが、最近熱いです、Frank Owen Gehry氏が・・・・ しかし経過などを読むと、いままでの積み重ねから現在のFrank Owen Gehry氏にいたっています。 タイトルには、「Gehry’s New York Debut: Subdued Tower of Light 」とゲ-リ-NYデビュ-:和らぐ光の塔? 約10年かかったプロジェクトのIACのマンハッタン本社ビル、スカ-トを履いたようなデザインをガラスのプリ-ツで表現しています。 原文のHPです(Ny Times)
2007.03.22
コメント(0)
-

椅子・・・仕事・・・
日本での仕事の椅子といえばキャスタ-付きの椅子がメインであり、それが当たり前だと想っていたし、使い易いと考えていたが・・・ どうも使ってみると、座ったママでアッチコッチ動き動作的には不自由ないとも体感していましたが・・・ ある雑誌で家具デザイナ-氏が「仕事の椅子にキャスタ-?おかしんじゃないの?」とではどんなもの?と質問されると・・・「仕事といえども、やはり地に足のついた安定感のあるもの」と、またそれぞれの仕事にあわせて椅子を選択することが大切でまるで、座ることができれば、席があればイイという考えがマダマダ職場でまん延しています。 ある海外(スェ-デンのSAS航空)の本社では全ての社員に5種類の椅子を用意しており、各人の好みで選択できるそうです・・・・日本では余っているものを配給が多いのに・・・ そういえば、結構キャスタ-付きは、つい座ったママで用事をすませようとしているから、逆に疲れるのかも?適度に立つのがいいのかも、それに動くことで壁にキズが絶えないかも・・・ 本気で仕事をしようと思えば、上半身が自由になることで、ハイバックなんかは不可で背は高くしないように、肘掛は必要ですが手前に長すぎるのは不可、座は汗をかくからビニ-ルレザ-よりムク材がイイと・・・全く逆の考えでした。 そういえばアノガラス張りの長野県知事室の椅子はムク材(県材のカラマツ)を使っていたそうです。・・・今は観光協会の事務室らしいです。(田中前知事は仕事の姿勢に関してはいい考えだったのかも、知事と県民が同じ目線ということ) 肩書きで家具の差をつけるのは変です、みんなが対等という考えも必要かも・・・ 自民党総裁の椅子も以前見たが、やはり「エラソウ」ですが、たいしたことはないようです(政治上の椅子ではありません、家具での椅子です) 多分全ての日本の会社では「右へならえ」ですから、大体良く似た考えかも・・・ やはり、職種や使う人の感性で椅子は選びたい、何故ならデスクワ-クならその上でお金が出て行くわけだから、カタログから選ぶのではなく、自分の感性で選びたい・・・ いまある椅子は全て、メ-カ-が売るために開発された椅子であって、仕事における快適さなんてこれっぽっちも考えていないかも、モシ普通のサラリ-マンが「この椅子が快適でないから仕事の処理が遅い」と裁判になればキット、メ-カ-が負けるかも・・・ 家具の椅子一つを取っても、人間工学(高さ、奥行、巾など)も当然必要な要素ですが、何度も言いますが「感性」でしょうね。 資料 1、可変クッション椅子を用いた椅子の高適合化 2、人間工学的手法を配慮した椅子の開発(PDF) 3、家具工房デイスクリ-トチエア 4、建築家 故、宮脇檀氏も椅子の収集家でした
2007.03.22
コメント(0)
-
FM局・・・ながら族
いま日本の国の中でFM局は、地方にたくさんあります 学生時代はNHKと、関西ではFM大阪とかだけで、音がいいので良く聞いていました、ラジオが古く親父の真空管ラジオで聞いており、アンテナを合わしたり、ラジオの置く場所を部屋中アッチコッチに置き換えた覚えがあるのと、確か雑誌の「FMファン」でしたかそんなものがあったように想います。 私はいまでも・・・FMのファンです、密かに・・・ 城達也氏に「ジェットストリ-ム」なんか素敵でした・・・今でいう「癒し」 当時はFMを使って討論とか、対談などはもっての他というような空気でした、大変FMが貴重な時代だったようでした。 そのFM局が現在国内では、なんと現在運営しているのは約200局程度あります(資料) 勿論、天下のNHKとは比べ物にならないような、出力数ですが(ミニFMでは20w)NHKは1kw FM局を開設するのも、結構簡単にできそうです・・・ ミニ放送局の作り方 これだけFM局ができると、音楽限定なんかいえない時代だし、そこまで音にこだわるには別のツ-ルがたくさんあり、そういった時代に変わってきました。 そのラジオですが、古いツ-ルと思えわれていますが、音声だけの情報は結構人間の脳の活性化には有効らしいです。 現在のパソコン、TVだけなどではなく、ラジオ・・・耳から入る情報というのは、耳から入ってくる情報から脳を想像し、考えるというのが増えるらしいです。 音・・・側頭様 ~ 想像・・・前頭様 聞き取って想像、一方的に情報を入れるだけ例えばTVでは想像しない、全てをTVでは提示するから・・・ラジオは全てを提示できないから、聞いた情報で自分なりに整理する作業がいいらしい。 その中でもラジオドラマがいいらしい、私は好きです、今はNHKしかないかも(土曜日) 例えば・・・波の音を聞くだけだ色々なイメ-ジを膨らませる・・・波は人それぞれに色んな景色を持っている、そのプロセスが大切で訓練になるようです。 ニュ-スからメモをし、絵を書くそれによって脳の活性化にもなる 同時に二つのことをする(例のラジオを聞きながら何かをする)・・・認知症にいいらしい 同時に二つ認知症では不可能、老人ホ-ムの設計でもドアの開閉にレベ-を二つ設置することで、外に出ないようにすることもありました・・・それを耳・・・ラジオで行う 整理すると効果的な聞き方・・・聞いて想像、ニュ-スをメモ、絵に書く、聞き「ながら」族となる。 実際には医療にも使っているらしい(軽度の認知症)・・・和歌山の病院(医師、板倉徹氏) 母に教えますし・・・私は地で行っているから、将来大丈夫かな?パソコンと仕事とweblogと英会話とラジオを同時にやれば・・・・
2007.03.21
コメント(0)
-

休むということ・・・・
今日本では一体、一年365日のうち、祭日とか休日も踏めて何日あるのでしょうか?改めて・・・ 祭日などが・・・・15日 日曜日が・・・・・52日 有給休暇など・・・10日?・・・個人差あり としても・・・・・77日 77日の休みがあります、このうち本当の休日とはどれくらい、取れているのかな? モシ・・・ この日曜日は世界共通だから、この「52日」だけでも、地球上の人の活動を最小限に抑えることができるならば有限といわれる大切な資源がどれくらい後世に残せるのでしょうか? 勿論それには、おおきな各国、組織などが調整が必要に想いますが、本来はそんな考えとか必要なく、ただ人がヒュ-マンスケ-ルで動き生活するだけで達成できそうに思うのだが・・・・ 公共的に必要な病院とか警察、介護施設、交通手段などは、ある程度は犠牲が必要でんな~ 計算すると・・・52/365×100=14.26%・・・約14%の休止 わが国のエネルギ-需要は2005年の石油換算で、4.150.000.000kl(41億5千万kl)ですから そのうち、10%としても415.000.000kl(4億1千5百万kl)のエネルギ-が節約可能なのに ちなみに日本の国家石油備蓄は国と民間を合わせて約9000万kl(約80~90日) エネルギ-輸送も助かる?のに・・・ 一番手っ取り早く二酸化炭素を減らす方法だと想うのだが・・・ 甘い考えかな? COP3(京都議定書)の達成しようと思えば、もう枠を決めてしまいソノ中で需要というわけにはいかないのかな?家計簿からの延長上の考えなんですが・・・資料 このママでは、エネルギ-の悪徳金融会社の中にはまってしまいそうです。 語弊があってはいけませんが、休みということは何もしないことではなく、家族とユッタリ過ごすだけでこういったことが達成できそうですが・・・・ 昨年あった「打ち水大作戦」と同じ考えですが・・・
2007.03.21
コメント(0)
-

マッコ-ネル曲線・・・競輪
デイテ-ル(172号最新号)という建築の雑誌で「マッコ-ネル曲線」なるものがあり???ました・・・いわき平競輪場 このいわき平競輪場は昨年改修工事を終えて、ここではビルの3階にあたる所までバンクを持ち上げ、日本で唯一バンクの内側からも観戦可能な構造になっています。 全ての施設が完成するグランドオープンは2008年6月を予定のようです、私は自転車はいつも乗っていますが、自転車・・・競輪といえば中野選手だけしか知らなくまた、オリンピックで「競輪」が正式種目になったというくらいの知識ぐらいです・・・ 自転車競技・・・自転車文化センタ- その「マッコ-ネル曲線」はわからなく調べていると、どうも競輪の走路の曲線のようです、道路のクロソイド曲線はよく聞きますが、知らなかった~・・・ ※マッコーネル曲線とは現在、全国の競輪場において主流となっている緩和曲線の種類です。緩和曲線の始点および終点において、他の緩和曲線にくらべスムーズな走行が可能です。・・・小倉競輪ガイドより 他には・・・コーナーを設定された速度(50~55km/h)で走行したときにハンドル操作をすることなく走行できる立体曲線。曲線の始点及び終点において比較的スムーズな走行が可能。要は走路に垂直で自転車が進む曲線。・・・・・大宮競輪の競輪辞典より いわき平競輪のHP どうやら、三次元の曲線のようで、自動車のテストコ-スにも用いられているようです・・・・・参考(鹿島道路)・・・・・面白そうな施工機械です いま建築もCADが導入され、三次元の設計も使われだし(私は使えてナイ)デザインに多分利用されているのでしょう、あのフランク・Oゲ-リ-氏のデザインもそうなのかな?しかしあれはどのように曲線の数値を決めていくのかな? 建築はどちらかと言えば、幾何学数学を用いている事務所もあります ・・・ここまでくれば頭が痛くなりそうです マア、気持ちが良く、見て目にも素敵な曲線を描きたい・・・フリ-ハンドで なんか競輪も一度、現場を見てみたい・・・・言っているだけですが
2007.03.20
コメント(0)
-

中国・・・・中央美術学院現代美術館
Kenplatzより・・・ 磯崎新氏の設計です 所在地:中国北京 発注者:中央美術学院 設計者:磯崎新アトリエ 施工者:上海建工第七建築 竣工時期:2007年10月 延べ面積:1万4800m2 その他:11月オープン 設計協力:北京新紀元建築工程設計有限公司、中国建築科学研究院 磯崎新氏が以前設計した、奈良100年会館のボリュ-ムと良く似ています 内容を少し観てみると、外壁はスレ-トの「下見貼り」のようで、奈良百年会館では瓦を使ってました。 Casaという雑誌に、「建築家はニッポン最大の輸出品」とかいう記事がありました、確かに以前から日本人の建築家が海外コンペで勝ち抜く場面を沢山観てきました。 MoMA(ニューヨーク近代美術館)新館 谷口吉生氏 フランスの国際コンペ、ルーブル新館はSANAA(西沢氏&妹尾氏) ポンピドゥーセンター新館は坂茂氏 シンガポールの巨大ショッピングモール、台中メメトロポリタンオペラハウス、伊藤豊雄氏 WTC跡地のタワー4には槇文彦氏 中東アブダビ海洋博物館は安藤忠雄氏・・・これは選抜かな? ナド・・・・・・・ 他にもコンペ(設計競技)以外にもあるようですが、そういえば建築雑誌でも海外作品が増えてきました、ということは国内では飽和状態になってきているのかも・・・・ 当然海外に目を向けるのも流れでしょうか? どちらにしても、耐震偽造なども自戒し良い建築は世界で認められるし、今の時代の日本人がデザインするのは形は違った和風のようなものがあるのかもしれませんし、単に時代の流れというものだけで終わらせることのないようにすることとか、社会が要求しているものを的確に判断することにも長けているのかもしれません・・・
2007.03.20
コメント(0)
-

Weisman Museum of Art to get Gehry-designed addition
フランク・O・ゲーリーによって設計されたワイスマン美術館です。 ミネソタ大学のワイスマンArt博物館(以下WAM)は、USAでまだ無い、ゲーリーによって設計された唯一の美術館建築です、面積は約11000m2 内部には、3つのエリアがあるようです、この形状からは伺えませんが・・・ ●Creative CollaborationのためTargetStudio ●ア-トのワ-クショップのためのスペ-ス ●3つのギャラリーがあるCollection Wingcafとeacuteを収容するミシシッピー川の上に浮かぶ ようなThird Wing WAMは2007年の終わりまでに着工し、2009年に開館の予定です。 しかし、フランク・O・ゲ-リ-氏の形状は美術品より興味が大きいようですが、UAEにしても、この形状が多いですね・・・・外皮は多分チタンを使うのでしょう・・・それは、グッゲンハイム・ビルバオでは日本の技術でしたが、今回は如何なものでしょうか?
2007.03.19
コメント(0)
-
写真家 二川幸夫氏
二川幸夫氏は建築写真家としては日本に留まらず、世界で活躍されている写真家という枠では言えないような、尊敬する方です。 また日本に建築写真を根づかせた一人と・・・・ 二川幸夫氏自身でも「GA」という月間の建築雑誌を発行されているほどです、その雑誌は他とは違い鋭い観点から討論、対談は興味がつかないものばかりです、一時期個人で購入していましたが、氏に怒られそうですが少々高いので、モッパラ図書館か事務所か本屋で眺めています。 二川幸夫氏は多くの建築物の写真を撮るときは、フラッと訪れ、担当建築家とか事務所にアポイントを撮り撮影しだすとか・・・いつも若手の建築家に対し辛い批評をしますが、逆にいい課題点を周囲に与えているような気がします、そういった意味では対象となる建築を、損得なく観て感じてソレを写真とか文字で発することで、多大ないい影響を建築界にも与え、ある意味自浄作用のの一つかなと感じることもあります、勿論他の建築雑誌の影響もありますが、他はメ-カ-の写真が多い・・・・新建築など 海外でもスペインの雑誌 「el cropuis」の専属写真家でもあるようです。 ともすれば、建築設計というのはあまりにもア-トに偏ったり、自身の考えを押し付けたりします、自慰行為に近くよく先輩から「カクだけ、では駄目だ」といわれたものです。 だからある程度、自身で設計したものがそこそこ出来だすと、勘違いし「俺は偉いんだ」と想うときを頭から叩く廻りがいないと、それ以上いい方向へはまた廻りに認められる建築とまで、いかないでしょう。 だからそういった意味で建築雑誌の負う責任は大きいと・・・・ これからも建築写真、雑誌は多くの活躍、活動の場が広がっていることでしょう。 写真は勿論のこと、図面、文字、言葉で三次元を表現することの大切さ難しさを感じます 技術的な雑誌も大切ですが、現代の社会におけるデザインの方向とかを理解し長い時間その場に残る構造物を残す仕事にとって、全てとは言わないが、その場にいなくて写真だけでも「観る」ことにウエイトを置く大切さも考えさせられます。 実際はその場に自身の身を置いて感じることに勝るものはありませんが・・・・ いま海外でも活躍されている、坂茂氏(紙の建築)も若かりし頃、欧州を二川幸夫氏と写真撮影に同行されたと本で読み、ソノ中でも坂茂氏が二川幸夫氏から「時間があれば、沢山の建築を見なさい」と同行中叱られたシ-ンもあったようです。 しかし、ネットが活躍しだしてからは、観た、読んだ、知っているなどと・・・知ったかぶりも増えてきているように想います・・・ コレダハ・・・イケナイ・・・・「初心に還るです」
2007.03.19
コメント(0)
-

Santiago Calatrava・・・・Three Bridges over the Hoofdvaart
橋です、街と街を繋げる、人と人を繋げる橋です・・・ オランダはアムステルダムに2004年に完成した3つの橋です Bennebroekerweg橋: 全長: 148メーター(486フィート) Nieuw Vennep橋: 全長: 142メーター(466フィート) Toolenburg橋: 全長: 26メーター(85フィート) 建築家が橋をデザインすると面白いですが、どうもお金がかかるような感じがします、みてわかるようにデイテ-ルに凝るから?かな・・・・でも渡るのが楽しそうだ・・・・ でも橋は車でピュッ!と走れば、心には残りにくいが、歩けばシミジミするのかな、どんなもんかな?どうしても創り手側の想いになってしまうから・・・・普段橋を日常に使う方の想いは、どのようなものか聞きたい・・・
2007.03.19
コメント(0)
-
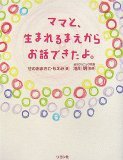
赤ちゃんを感じるとき・・・・
何時の間にやら、嫁の大切なお腹は、もう母親そのものになってきました その嫁に紹介された本で「ママと、生まれる前からお話できたよ」せのおまさこ、もえこ著 本屋さんには申し訳ないですが、立ち読みしました・・・・ 内容は読めばいいのですが・・・少し紹介しますと。 「胎話士」という胎児とお話できる人が居て、 お腹の中のやがて生まれてくる子供と沢山スケッチやらメモをしてに書き綴って出来上がった本らしいです、お母さんが自動書記によって胎児に代わって絵を描いたり、言葉を文字にしたり・・・ 勿論それが全て正しいとは想いませんし、お母さんの想いも多少ハイっているのかな?でも何か大切な神聖なものを感じました、涙が少し出そうかな? キット子供は生まれる前は神様と住んでいて、この地上に降りてくるときに、記憶を消されて地上に降りてきて、我々が預かり育てるのかな?そんな気分にもなります。 四六時中、覗いているような 家族になりたがっているのか、わからないが 男には決して、わからない、経験できない大切なものを大きなお腹の中にはつまっているようです。 色々考えると、目眩まではいかないが、生まれるのを待てないような そんな男にとって複雑な思いを抱かせる・・・戸惑いも?、涙もろい?ことさえも 吹き飛ばせるような 嫁のお腹です 普段といつもの一日とかわらないが・・・・
2007.03.19
コメント(0)
-

なごり雪・・・
「なごり雪」・・・イルカ 今朝、自転車で走っているとほんの少し「雪」が・・・ まるで、今年の冬の帳尻をあわそうと・・・ 丁度、いまぐらいのタイミングで降る雪をいうのかな~卒業シ-ズンだし 暖冬といわれながらも、年間を通じての気候は本当はその辺の人間が考えているより、もっと大きく、ユッタリと動いていると感じるときがあります、温暖化、暖冬と叫ばれて久しいですが。 たかが人間が住むところは必要な大気にしても、必要な地殻にしてもたかが薄皮一枚なのに 「なごり雪」は季節がいつも、知らないところで自然と耳をすませば、感じる心を持っているならばわかるのかもしれない たとえ、なごり雪でなくても、なごり雪がイイ 暖冬になっても「なごり雪」がいい 以前、5月の連休中に岡山と鳥取県の県境のブナの森を見にいったときに、フトンが落ちているとズット想っていたのが、近ずくと雪でした・・・これは「なごり雪」でなく「名残雪」なのかな?
2007.03.18
コメント(0)
-
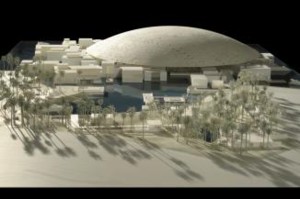
アラブ首長国連邦(UAE)
少し前ですが・・・UAEの首都アブダビでサアディアット島開発の一環として進められている複合文化施設の概要が公開されました。 日本からは安藤忠雄氏が海洋博物館を設計、ジャン・ヌーベル氏がルーブル美術館分館、あの曲面の建築家のフランク・ゲーリー氏がニューヨーク・グッゲンハイム美術館分館、ザハ・ハディド氏がパフォーミング・アートセンターを手がけるなど、さながら現代建築のエキスポ状態。 サアディアット島開発計画は、環境に配慮した世界有数の観光地にしようと、連邦政府が2004年から計画を進めてきた。同計画は、フランス国内の美術関係者からルーブル美術館分館建設が議論になるなど話題を呼んでいる。 パリ・ルーブル美術館から美術品の大量の貸与を受けることを認め、ルーブル美術館はルーブル・アブダビに対し、開館から10年間美術品を貸与し、美術館のコレクションや学芸員の養成に協力し、契約額は10億ユーロ (約1500億円) 規模です、ア-トは経済おも活性化します。 他の予定施設には、ホテルやマリーナ、ゴルフ場なども併設される。2018年に完成予定ですが、博物館や美術館は2012年から順次開館する予定です。 安藤忠雄氏は、ムハンマド・アブダビ皇太子らに計画概要を説明し、「経済都市のドバイに対抗し、アブダビを世界有数の文化都市にする試み。連邦の歴史をふまえつつ、未来に向けて海の大切さを考える機会となるよう設計に思いを込めた」と語った。以上一部読売新聞とかnikkeiよりです・・・・ 資料・・・Saddiyat Island Tdic ル-ブル、アブダビ美術館・・・ジャン・ヌ-ベル氏 海の博物館・・・・安藤忠雄氏 パフォーミング・アートセンター・・・・ザハ・ハデイド氏 ニューヨーク・グッゲンハイム美術館分館・・・フランク・ゲ-リ-氏 資料を見て下さい・・・・
2007.03.18
コメント(0)
-

忘れられない過去・・・・・
何をやっても どんな事を考えようが 仕事を一生懸命やろうが 楽しくても、苦しくても 幻を追っかけていても 忘れない過去が何処かに引っかかります 何をやっても どんな買い物をしても 旅行へ行っても どんな場所に自分を置いても 忘れない過去を引きずります 何をやっても 全てを赦しても 理解しても ノ-トに書こうが どこへ流れつこうが 忘れない過去が流れてくる 何をやっても 誰と付き合おうが 笑っていようが 泣いていようが 忘れない過去が擦り寄ってくる ただ、過去の事じゃないか と・・・言うが 過去も現在も未来も一つ 助けて~と年甲斐もなく叫ぶ もうイイジャないか もう帰ろうジャアないかと コノママ、大きな時間という海流に流される コノママ、いつまでもズット探し続ける いつまでも、いつまでも これからもズット・・・・いつまでも 誰かが顔を見てくれるだけで だれかが、何かが近くにいてくれるだけで 「ネエ」といわれるだけでもイイ 走りつづけ、歩きつづけ 流されつづけ、流れつづけ どこまでいくのだろうか 与えられた自由な意志をもって 乗り越えていきたい どこまでいけるのだろうか 行き着く先は・・・・・・・・
2007.03.17
コメント(2)
-
interesting scenes・・・・・
interesting scenes インドでしょうか、素晴らしい映像です・・・音楽と映像、素敵です・・・ 少し時間がかかるかもしれませんが・・・ スピリチュアルのことはあまりわかりませんが、感覚的に何かを感じます バレエのようでもあり、人が母の胎内にいるようでもある感覚になります・・・ あくまでも、私の感覚ですが・・・・・・・・ interesting scenes
2007.03.17
コメント(0)
-
普請道楽・・・・
やってみたい事に「普請道楽」を気兼ねなくやってみたい 19世紀半ばから20世紀前期までは、日本はもとより世界でも同時進行でヨク聞いたような気がします・・・そのあたりのハコモノが世界文化遺産?かな 財産を一代限りで消費しておれば、こういった普請道楽だけでなく、街まではは成立していないのでは。 これは箱物だけではなく地域のインフラ整備にも通じています。 時代を考えると経済的に強くない時代の方が堂々としたものができていたような気もします、まちの名所とか個性になるものが・・・・それが・・・現在ではいかがなものなのでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・ 身近なところで恐縮ですが・・・ 故郷の従兄弟に形は違えど「普請道楽」が一人健在しています、決して贅沢ではないが、何故か遊びに行く度に何か建築に対し、ドアを変えたり、アアヤロウとかコウヤロウと思惑まではいかないが、家をイジクッテます・・・でもそれは個人的なもの。 小屋を建てたり、納屋を壊したり、台所を増築したり、もう黒川紀章氏ではないが「メタボリズム」を地でやっていると、常々想っています。 普請道楽とは現代では役所がそういったことを行っているのかもしれません、いわゆる箱物? 美術館・図書館・官庁・集会所・屋内プ-ル・博物館などがそうかも知れません、昨年青森県で美術館ができこれで日本中に美術館が存在するようです、今後の経営が見所ですが・・・ 人一人が人生の中で一体何軒の建物を満足に建てられるか?果たして建築家でも何軒設計し建てようが、中々できないのに、一人の人間とはソレ程のチカラもないことをいつもいつもおもい知らされます。 普請道楽をしようとすれば、当然経済的に強力でないことには無理だし、人のエネルギ-も沢山いるものかなと・・・・ 英雄「色」を好むではないが、英雄「普請」を好むと 色気も素っ気もないかもしれませんが 普請道楽ともともと、日本では茶室とか離れなどを凝った造りにしたり、床の間や襖絵などを趣味にまかせて設え、人を招いては楽しんだことでしょうか? 今日のような経済状況では過ぎた道楽は許されないことであろうが、都であろうと、田舎であろうと、地域の風景をつくり、風格をつくってきたのは、そういう普請道楽の負うところも結構おおいのではないでしょう? 何故なら、地方でも都市部でも、そういった建物を迎賓館のように持ち有効に使っていたように想います、例えば旧財閥なんかそういった考えがあったのでしょう・・・ 本来の建築というのは、人を創り、仕事を創り、技術を創り、地域を創り・・・おおくの影響を与えるものかと想うしそれが今では一部の人間だけにその恩恵があるように感じます。 勿論、いまでも一軒家をたてると、建築士、工務店、土地家屋調査士、宅建取引主任技術者から現場では基礎から大工、ガラス、左官、家具、設備、電気・・・などピラミッド式に拡がりを持っているのは確かなのです。 特に役所関係の仕事にそういった想いを抱くこともあります・・・・ 建築に限らずこれからは、上記の時代ではないですが、拡がりをいかに持って仕事をすることが過去にも未来にも大きなポイントかなと・・・・普請道楽で考えた・・・
2007.03.17
コメント(0)
-

建築家 Michael Jantzen 氏
この、Michael Jantzen 氏は、 「HP」をみてもわかるように、ヤヤヤ~!という建築を扱って?います・・・Transformation House各パ-ツが回転し、太陽光、雨水などを用いて自己完結に近づけるようです。Wind Shaped PavillionWind Shade RoofWind Turbine Observation TowerWind Tunnel Footbridge以上は、上記のHP内にありますが、見れば見る程、また考えれば考えるほど・・・・でも感覚的には言葉には出来ないが、考えは理解できそうですが、使ったり住むのは 「チョット~」かな・・・
2007.03.16
コメント(0)
-
豊田大橋&スタジアム
2007.03.15
コメント(0)
-
廃線
2007.03.14
コメント(0)
-
言葉・・・文字・・写真・・・映像・・・・生身・・・・
いつも、想うことですが、人から発する「言葉」「文字」「映像」「写真」など二次元のものが、あらゆる人の社会に入っていき、色んな変化をし、影響を与えていると、時々思い出してはそう考え・・・ソウナンダ-とわかったようなわからないような顔をしています、突然が時々あります。 仕事での図面の提出もそう、自分がこう考えているが・・・相手にとっては気いらない 文字も表現するが・・・イヤコッチの言葉がイイ・・・ 捉え方も千差万別で、無限のごとくの解釈があります だから、たまにナンデ~と、自分の想うことが正確?に伝わらずに地団駄を踏むことも沢山あります。 それも経験なのですが・・・ だからこそ、以前にも書きましたが、言葉がコレだけあれば、国同士から国内の方言まであるならば、正確な言語ではなく、本来の持っている感情とか、心の訴えが一番誤解がないように想います。 しかし、そのように想っていても、宗教とか人のベ-スにあるものが違えば当然理解できないこともあります。 では何が一番共通する手段でしょうか? ンンンン~ 相手を受け入れる心と、赦すことかなと最近少し感じて実行していこうと思います。 個人から国同士、果ては惑星同士までいくかもしれませんが 人を受け入れ、赦すことは言葉では簡単ですが、「難しい」です・・・・ 闇雲に受け入れるのではありません 勿論、傷口に見合うバンソウコウと同じかなと思います
2007.03.13
コメント(0)
-
情報・・・・
情報が大切で、それが戦略にもなり、お金にもなるといわれて久しいですが その情報を扱う人間の方が、上手に扱っていないのが現代かも その最たるものがTVであり新聞などでしょう、捏造も最先端だし、ニュ-スが何時の間にやら偏った考えを発しているし、事実をありのママに表現するのは本当に出来ないのでしょうか? 偏った考えを提示するなら、必ずその反対の偏った考えも提示が必要だし、またそれの中間も必要だと想うのですが。 これもある意味デザインかと思います、建築の設計でさえ一つの物件があれば何案も提示し検討するのに・・・キットできると想うのですが。 勿論日々の情報が山積みの中で、咀嚼しそれを選択して提示する。 個人でさえ、Weblogを見たり、読んだりするときは様々な考えを読んで、自分なりの考えをもつのが楽しいのに・・・ メデイアの世界は、大昔から変わってないのか~!戦争中の新聞と変わらないのではないような気がします。 だから、末端のような私は新聞、TVからマスマス遠ざかるようになってきます。 個人で情報の嵐から、選択し、自分がある程度正しいというようなことをするのに、日本の新聞とかネット新聞などを読んでいても、妙に偏った意味ありげな表現が気になります。 もうそういった狭い世界ではないような気がしますが、世界の動きが広くなればなるほど、自身の国とか街を地元を大切にしようとする、反比例の法則のようです。 ・・・・私は、メデイアから遠ざかり、ツマラナイ情報ばかりを検索していますが、意外と他にはない自分なりの情報を得る手段が見えるときもあります・・・但し、時間が必要です。 本当は「声」にも「活字」とか「映像」などで表現が難しいものを取り上げをシテ欲しい。 それは何か?「アレ!」こんな情報があったのか、このような見方があったのか!というフウな驚きと尊敬のまなざしがあるような情報・・・・私はできない・・・ 以下そのつまらない?映像 Jet-vs-Porshe-vs-Yamahaのレ-ス 核兵器の恐怖 様々な着陸 Baseball中への不時着 PK戦
2007.03.12
コメント(0)
-
Tunami・・・Planet・・・Virus・・・Volcano・・・
BBC.Horizon-End Day パニックの映像と簡単には整理できないです、必要以上に脅すわけではないですが、今の時代に、ほんの少し間違いとか、偶然などが重なれば、また自然が少し変わるだけで・・・身近にあるような、身に迫る危険、危機、災害、かもしれません 人はいろんなことに備える必要があるのでしょうか?と思います、個人レベル、街レベル、国、地球と・・・・ 長いですので、時間があれば観てください・・・・ 再生をクリック下さい・・・英語です・・・
2007.03.11
コメント(0)
-
ヤットこさ、わかった詩・・・
石川セリさん が歌っていた曲です当時、NHKのドラマでの曲だったと想いますが、それ以上想い出せないがネット上で今までのどにつかえてたものが、スグに答えが出ました・・・ それは・・・・ 「遠い海の記憶」♪いつか思い出すだろう おとなになった時に あの輝く青い海と 通り過ぎた冷たい風を 君を育み見つめてくれた 悲しみに似た風景 追憶の片隅で そうっと溶けてしまうのだろう 今だ見つめておけ 君のふるさとを その美しさの中の 本当の姿を いつかおとなになって 君はふと気付くだろう あの輝く青い海が 教えてくれたものは なんだったのだろうと 以上ですが、曲は思い出したが、どうしてもその時のドラマのシ-ンが想い出せない・・・・・・・・・ 想い出せないママでいいのかも・・・
2007.03.11
コメント(0)
-

灯り・・・
建築やランドマ-クなど、また手元灯まで、灯りを自由にユッタリと演出のためのデザインは一昔前と大きく異なってきています。 「灯り」「光」は、人間の生活の全ての場面に深く、離れず根差しています。 現在の生活の中で、「光」なしでは暮らすことができませんし成り立ちません。 また、光は、あらゆる科学の領域から宗教や哲学までに浸透する、限りなく幅広い存在でありながら、エジソンが「光」の発明の一つの「照明」という狭い技術的な分野の中に、後世において人間が閉じこめてきましたように感じる時があります。 「灯り」「光」の手段である「照明」を、単なる冷たい技術だけでなく、より広範囲の「光文化」として考えて行くのが、この地球上の資源と地球の環境に向きあうことが大切かと想います。 ただの「灯り」「光」ではなく それに・・・「暗闇」も「あかり」の中の一つかと 闇がなければ明りが解らないというのと一緒だと・・・ ただ、明るければイイではなく 必要なあかるさ、必要な柔らかさと、場面の雰囲気・・・ 光のデザインには 1、透過光 2、直接光 3、反射光 の3つがポイントです、透過光は、行灯などの和紙を通して感じる光、直接光はあまり色気は無いが必要不可欠なもの、反射光は壁天井などを使い柔らかい光を廻りに提供します。 内外ともにそういった光を必要な場面に提供するならば、夜はキット素敵な違った世界が拡がるでしょう。 ランドマ-クデザインにしろ、本を読むときの、あかりにしろそこには目に優しく、環境に優しく、安心できるような・・・落ち着ける、あかりが欲しいもです。 日本にも、あかりを設計される方がいらっしゃいます・・・石井幹子氏・・・HP この方の手法までとはいかないが、模範にして「灯り」を楽しめるようになりたい。 単に照明器具のカタログから選択し貼っていくのではなく・・・ 明りに関する色んな団体など ・財団法人 照明学会 ・コンペ・TOKYO LIGHT 「TOKYO夢あかり」から・・・ ・日本光学会 ・他写真は light demension dezain さんより引用・・
2007.03.11
コメント(0)
-
土曜日の夜・・・
親父に会いたい こんな年になっても 親父は居ないが 何故か、会いたい 生前は何も話すこともなかったのに 親父もあまり話しはしなかったのに 何で会いたいのか いまの自分を見て欲しい 生前はユックリと話もしなかった 心配ばかりかけて ヒョットすると イマ会えばさらに心配 会えば話すことなんか、特にない 甘い考え 何処かで、いつも見いて欲しい希望 どんな時も 何処かにいて、存在を感じて 何処かに気配を感じて こんなこともあったヨ あんなこともあったヨ こんなになって あんなになって こうする、アアスル と、話を聞いて欲しい ウンウンと頷くだけでいいんだ 良い嫁も居てるのに 話を聞いてくれるのに 親父に会いたい 少しでいいから ほんの少しでいいから 土曜日の夜 ユッタリと
2007.03.10
コメント(0)
-
News・・・・Telepathy・・・
ニュ-スは最近はネット上でしか、見ていません・・・新聞を取ってないから、でも新聞があるところへ行けば、むさぼる様に読む自分が滑稽です。 ネット上は国内なら日経、海外ならウオ-ルストリ-トジャ-ナルとかBBC、NYtimes、などと最近わかったような振りをして、映像とともに観ています、それとNHKのネット(英語)など・・・ 国内の主要な新聞とか、あと地方の新聞は、新聞名以外ほとんど同じに見えます、他と違うのは観光とか、土産とか地域の情報程度でしょうか?まるで学級新聞かな?(失礼な表現ですがゴメンナサアイ、デモ活字としては尊敬しています、それと記者の方を個人的には尊敬しています)ただHPの構成を観てです。 東アジアの新聞のHPなど・・・このあたりは読むと「何で?!」という記事が多いです、ソリャ揉めるワア~と想うような記事ですから、目を薄く開けて内容半分で読むのがいいと・・・ しかし一番困るのは、結構時間がかかる・・・辞書を片手だから・・・(日本語は少ない) でも、外の世界を見ていると海外と日本国内との温度差とか、情報の扱いが全く異なっていることは、誰でも「ナンジャ、コリャ~」と気付くと想います。 例えば「日朝問題」についても他国の新聞、またグロ-バルにおいてもそんなに扱っていません、勿論それぞれの国での考えとか、戦略とか地域の関係もありますが、それにしてもメデイアの扱いの違いに時々ジンワリと驚きます。 だから、日本はいまだに東の果ての国です・・・・ 日韓、日朝、日中と色々な懸案事項はいくらでも湧いては消えずに増えていってます 一つは国民性もあると想いますが 過去は一体誰がどのように判断し決めるのでしょうか?ズット決めれないようです・・・ 私は今の状況が大切だと、バカ頭で単純に考えるのですが、その今の時間レベルが国レベルでも違うのでしょうか・・・ワカラン・・・・ 国連も役にたたない、というか有効活用していないし、国の駆け引きの場でしか見えないし、日本の国会も、国際的な質疑応答なのに、相変わらず野党は全然異なる質問しているし、一体誰がそのアタリを指摘し正すべきなのか・・・・ 一つは上記のメデイアが強く押さないといけないと想うのですが・・・これだけ地球規模での情報がこれだけ行き交っているのに、マスマス亀裂は増えるばかり やはり「言葉」が大きい壁かもしれない、こうなれば古代の「バベルの塔」を建て神様が怒り言葉を乱したことは大変なことであったのでしょう・・・ 言葉の壁はお互いを理解できない?ならばテレパシ-?
2007.03.10
コメント(0)
-

Standing tall・・・堂々と建っています・・・
下記の写真の建物の説明の原文を適当に訳すと・・・・(後日キッチリと修正します、ゴメンナサイ)I see no planners.....(私はこの建物のプランナ-を知らない) この奇妙なロシアの建物は、144フィート(約43m)にも達するような世界の中でも最も高い木造建築物の一つで内部は13階はあると言われています。 また、建物はこのように、ぼろぼろに崩れ、不完全であり、このニコライの15年のプロジェクトを終わらせるのを切望している市当局が撤去したいという、アル意味社会的に不安定な家です。 この共同のアパートの建設に骨を折った、ニコライがインスピレーションを出しながら、またひとりで孤独に感じながら工事を行い、今の状況になっています。 この建物の工事は、1992年に始まって、こんなに高くするようにとは当初想っていない事は、海外での日本やノルウェーの木造家屋を見る旅行で解ってはいました、しかし、彼は屋根裏を使用しながら、増築を続けていきました・・・ 彼がまず最初に3階を加えたのがキッカケで、その後彼は、床の増築を繰り返し、現在このような「幸運な偶然の出来事」という次第ということに終わっています。 確かに、彼にとって、この家は変わっています、彼自身も・・・(彼は、ゆすりで告発され刑務所で、4年を過ごしました)。 現在、無一文で彼の妻と共に彼の木造の丸太小屋の下部の4つの部屋で寒い部屋に住んでいます。 多くの隣人が、他のものが賛美された建物にもかかわらず、火災の危険と目障りなものにもかかわらず、またこれが建物でなくデコレーションであると主張する彼が言う2階の周りに屋根の増築を建設しただけと想っているようです。 なにかあのジブリの映画の「ハウルの動く城」のようなイメ-ジです、しかし近所にとってた迷惑なのかな?しかしヨクここまで雪の多い国で建てたと想います。 できるなら残してもいいのでは?でも建てたい欲望は「バベルの塔」かな?
2007.03.10
コメント(0)
-

夕焼け・・・・
夕焼けを眺める 夕焼けで、たそがれる 夕焼けを見て一日を想う、一年を想う 夕焼けを見て走り出す 夕焼けに向かって・・・・ 夕焼けはナントモ言えない、色、情景と朝日にはない、力を感じます 疲れであったり、どうし様もない事を考えたり 少し後ろ向きになったりと・・・・ あまり、明るくないかもしれないが、夕焼けは必要なシ-ンです その夕焼けが、永遠に見えるとなればどうします? たそがれも、夕焼けに向かって走るのも・・・そういったシ-ンが想えなくなる? そんな映像がありました「Eternal Sunset」 (永遠なる夕焼け) こんな、シ-ンいやだと言われるなら観ないほうがいいです・・・ちなみに世界中の夕焼けをWeb カメラで追っています。
2007.03.10
コメント(2)
-
改ざん・・捏造・・・・・
いまどの世界でも、改ざん・・捏造・・・俗にいうパクリ・・・が大流行です 個人から、仕事、そして国レベル・・・国同士の国際社会でも・・・まとめて「ニセモノ」 ニセモノは科学の世界、写真、紙幣、書類、歴史、weblog、各種製品、顔、身体・・・・・ありとあらゆるもの。 自分が潔癖で真実としても、タマニ間違えられるし、本当の真実を求めると逆に責められる場合もあるし、もう何が何かわからなくなる、例え真実だとしても、誰かに責められると、「アア、そうか俺が悪いんだ」とかヤケになり「もう、イイヤ-この辺で・・」とか、特に国際社会だとあいまいに出来なく、本来の思いやりとかが、泡と消えていつの間にか悪い方へなっている。 だから、ヒ-ロ-が出現しにくい世の中かも・・・ そのうち、国連なんかで「ニセモノ」をはっきりさせる部署も必要になってくるのでしょうか? 自分の立場をいかに訴え、廻りを引き込むという手段でした、生きていけないのでしょうか?そういうことならば・・・チョット、私のような、気弱?な人間では、狭い世界でした住めないのかな? でも、広い世界、自由に可能性が満ち溢れている世界がイイ となれば、やはり自分の大切な自由な意志を持っているならば、キットかなうはずだと信じています。 その写真もそう最近デジタル化しそれが素人でも可能になってきました、私でも何らかの形で学習すれば出来そうだし、まさか紙幣までと言うけど、これだけ、スキャンとかコピ-機などがバ-ジョンアップするならば、手軽?にできる・・・人間さえも・・・・ ブログだって考え様によれば、捏造も簡単と思います。(悪い考えです) 面白い例で、「捏造などを防ぐため?」:遠い知り合いに造幣局の方がいて、なんと入退場の度に裸になって、着替え「私は何も持って出たり入ったりしない証明」(聞いただけで、確かかどうか未確認)それをするとか・・・こういう方法もいいかも・・・単純で・・・ こういった「ニセモノ」は人間がいている限りはズ~ト存在続けるのでしょう、これを完璧になくすのはムツカシク、いかにどれだけ少なくできるか、が勝負かな? 私事で言えば、建築の設計の世界でも、昔は良いデザインと思えば、書き写し、ヤガテ写真で写し、そしてコピ-する、最近はデジタルだから簡単にenterを押せば、アラ~不思議ポケットに・・・ もうこんなことを書けば、何を信じていいのか解らなくなるが、結局それぞれの倫理観、道徳観・・・というところに行き着くのでは、それにはやはり宗教のチカラが大きいように感じます。 社会のシステムがソフト面もハ-ド面も変化が大きく、昔からあったシステムではもう太刀打ちできなくなってきているから、色んなところに歪みが出てきているのかもしれません。 それでもどの場面でも「真理は一つ」と信じていたいし、例えどうしても間違った道へ行ったとしても、だれでもやり直せる世界であって欲しい(但し極端な場合は考えます・・・)
2007.03.09
コメント(2)
-

グランドキャニオンの絶壁に片持ち梁の展望橋
グランドキャニオンの絶壁に片持ち梁の展望橋 米国アリゾナ州のグランドキャニオンに2007年3月28日,スカイウオークと呼ぶ展望橋が完成する。スカイウオークは張り出し長さ約21mの片持ち梁で,谷底を流れるコロラド川から高さ約1200m(4000ft)の絶壁に突き出す。 ・・ちなみにエンパイヤステ-トビルは1250ftです。 U字形をした2本の鋼製箱桁の上に,厚さ約10cmの強化ガラスの板を渡して通路にする。岩盤に埋め込む箱桁の長さは約14m。直径が最大で63.5mmある鋼棒やコンクリートなどで固定する。 ヨク観ると、完成予想図と実際の構造体を見ると、見かけに梁の高さが大分異なります・・・ 強度的には、約80km離れた地点を震源とするマグニチュード8クラスの地震のほか,谷底から吹き上がる秒速約45mの風にも耐えられるように設計した。一度に載ることができるのは120人までだが,設計上は約70tの荷重まで支えられるとあります・・・しかし、 国内法の法的根拠以上に、世界遺産の法令遵守が強く求められるはずのこの地に、何故このような人工構造物ができたのかが不思議なところです。その詳しいHPです・・・・資料 Usa Today の中でも紹介されてました・・・・インデイアンの後ろに工事中のデッキが少し見えてます。 そのうち、誰かがジャンプするのでは?パラシュ-トを持って・・・・ こういうのは、日本でも形は違いますが、本四架橋の大鳴門橋でも足元が・・・ココはガラス貼りで渦潮が見えるようになっているのですが・・・・でも元々、新幹線を通す列島改造論からあり、鉄道を通す部分だけが残っただけです、なぜならココにつながる明石大橋には鉄道が通りようにはなってないから・・・・変ですヨネ・・・案内HP でもケネゲに活用しています、本来の用途とか意味を忘れています・・・・本当に新幹線がきたらどうするのかな?
2007.03.09
コメント(0)
-

時刻表・・・・
子供頃、人には寿命がありそれがある場所ではロウソクを灯していて、そのロウソクの残りの長さが解ればそのロウソクの人の寿命がわかるというのを何処かで知って、押入で怖い日々を過ごしたことがあります。 ロウソクもそうですが、人それぞれに「時刻表」なるものがアルというのを以前から、何となくウッスラ感じていました。 その時刻表なるものには、出発時間・・・途中停車・・・分岐・・・特急・・・各駅停車・・・脱線・・・再出発・・・行き先変更・・・遅れ・・・乗り換え・・・・と・・・・様々な選択肢が用意され、時には廻りが演出し、そして自身が勝手に演出した時刻表を創り、進む時もあるのでしょう。 毎年々、時間を変更するJRとか私鉄の時刻表のように再々々発行し、その度に時刻表を見て、時間と列車と行き先を確認し列車に乗る・・・西村京太郎の世界のように、列車と飛行機を使ったり・・・ こんなことを書くと、何か変人と思われるかもしれませんが、最近たまに友人の不幸とか人生の転機を目の当たりにすると、そんな気分にもなってくるときがあり、何かに例えてしまいます。 ただ、この時刻表のうれしいところは、一つの時刻表を使いのではなく、自分だけの一つの時刻表しかないことですかね?寂しいときもあるが、その違いの良さに気付くまでかなりの時間がかかるかもしれません、廻り道をしてもそれだけの得る価値があるのでしょう、ロウソクの長さを測るよりおモットいいものが・・・・・ たまには、他人の時刻表を羨ましくなるが、いつも自分の時刻表を真摯に見る必要を感じます。
2007.03.08
コメント(0)
-

「(天津タワ-)・・・
Integra Architecture株式会社ブリティッシュコロンビアバンクーバー(カナダ)のドウェインSiegrist MAIBC MRAICによって、設計された「Tianjin's tower」で・・・工事は来年早々のようです。 クライアントはクライアントYoulan Zhiye Ltd.です。 内部はオフィスと住居を兼ね備え、立地は川沿いもあり、周囲からのロケ-ションを生かした建物のようです、でも最近海外の建築では中国関係が大変多いです・・・それも設計はUSAが多い・・・ その立地場所の地図です ・・・・・・・・・・・以上はWord Architecture より引用しました。(パクリです)
2007.03.08
コメント(0)
-
食事の回数・・・・1回・・・2回・・・3回・・・それ以上?
食事の回数が最近減ってきています、というか減らされています、今までは一日に3回は心の中では必ず取るのだと思ってはいましたが。 最近生活が仕事が自宅半分以上ということもあり、自転車に乗るのが唯一の運動かもしれませんが、どうも一日に2回の食事が身体に年齢に?合ってきているようです。 食事の食べ方は、以前嫁から、10代は腹イッパイ、20代は腹9分目、30代は腹8分目、40代は腹7分目、50代は腹6分目、60代は腹5分目、70代は腹4分目・・・と言うふうなことを聞きました。 その時は「ソンナ~と、ヤハリきっちり食べないと、勢いとか、仕事に対する情熱などがナイ!」と奥底で思っていましたが・・・最近、嫁のツワリもあり食事の回数が減っても何のことはない、動けるし、体重も減るし・・・イイ方向かな?とも感じるときもあります。 もちろん全てにこれがあてはまりませんが。 今、世界では12億の人が慢性的な栄養失調で毎年1800万人の方が亡くなっていると色んな情報から聞きます、食料が先進国に偏っているのは確かです、地球上の食料を均等に分ければ充分にまかなえるとも聞きます、「WTO」「WFP」「FAO」がソレを行おうと緊急的に対応したりしていますが、追いつかないし、たとえソレを行っても北朝鮮のように行き届かない状況のようです。 現実には、ビタミン欠乏症が多く、くる病(ビタミンD)、壊血病(ビタミンC)、かっけ(チアミン)など最近ではサプリをも配布するとも聞いています、特に南アジアとアフリカにて多いようです。 日本のような国も逆に「衣食住」においてもバランスがとれてなく、異常な国かもしれません、片やダイエットをし、片や日常的に残飯が、そして過剰に食料の輸入し、国内の自給率が40%と・・・ 食を減らせとは言いませんが、あまりにも食が過多かなと思います、「太るのなら、月に1回でも定期的に断食を正しくすればイイシ」食料も本来自給できそうな気がします。 もちろん、成長期に子供とか食べたいのに食べさせないのとは少し考えが違いますが・・・ 前にも書きましたが、イタリアでは農業従事者が4.6%で自給が80%です、ちなみに日本は農業従事者が3.8%で40%どこに違いがあるのでしょうか?「スロ-フ-ド」?(米国のファ-ストフ-ドに対抗しスロ-)日本にも日本の良き食材とか食生活があるのに矛盾しています(私もですが・・・) スロ-フ-ドの言葉だけが、一人歩きしているようですが(理念や考えなど)、スロ-フ-ド的なものも、本来の食生活に戻る一つの手段のようです。 ともかく・・・過剰な食を減らすことが一つの自給への道かもしれません。 「食事の回数 Frequency of meal」・・・・「たまねぎ地獄」さんから勝手にリンクしました
2007.03.08
コメント(0)
-
睡眠・・・レム・・・のんれむ睡眠
一般的に脳は午前中が活発で、思考力とか創造力などが必要な時は仕事や勉強に効率的だということが、今の時代は有力な説のようです。 実際私はその方だと体感します・・・が、色んな方いらっしゃるから、この学説はナントモいえませんが。 しかし睡眠で脳にある、記憶を保持し、想起させる必要な「シナプス結合」の可塑性を維持し、視覚や聴覚などを通じて脳に入ってくる情報を整理整頓し記憶として焼き付ける・・・ という説を、雑誌を通じて読みました・・・・報道ニッポン 3月号のコラム? 浅い眠りが「レム睡眠」、深い眠りが「ノンレム睡眠」で、その「レム睡眠」の時に記憶が整理整頓されて、脳に焼き付けられているとは・・・・ しかし、落とし穴があって、寝る前に、例えば「アア~仕事終わったとか、勉強終わった」と言って安心し、ヘラヘラとその後TVとかDVDとか、ワイワイガヤガヤしては他の情報が入ってきて、どうも、その「レム睡眠」の時に違う情報が入って、せっかく勉強しても・・・仕事をしても・・・いいこと?をしても忘れてしまうようです。 ななるほど、想い当る節がたくさん思い浮かびます。 どうも勉強、仕事をし、てすぐさまフトンに入るのが人類の成長にいいみたいです、母が言ってたことも、あながち嘘ではなかった・・・ 質の良い?眠りは人によるが・・・・6~8時間が最適?のようです。 この 「忘却曲線」を少しでも緩やかにするには、この睡眠がポイントのようです。 この忘却曲線によると20分後には42%を忘却し、58%を覚えていた。1時間後には56%を忘却し、44%を覚えていた。1日後には74%を忘却し、26%を覚えていた。1週間後(7日間後)には77%を忘却し、23%を覚えていた。1ヶ月後(30日間後)には79%を忘却し、21%を覚えていた。アア~そうか、そういう意味ではブログは、もの忘れに有効にになるのかな?しかし、ヒョットしたら過去に同じことを書いていて忘れているのかもしれない・・・・
2007.03.07
コメント(4)
-

建築家 フランク・ゲ-リ-氏
建築家 フランク・ゲ-リ-氏がNYにて、「先進技術を盛り込んだ世界企業の本社ビル――The IAC Building」が間もなく竣工するようです。KENPLATZによりますと・・・・ 約60社を傘下に収める世界企業の新本社で、フランク・ゲ-リ-氏がニューヨーク市で初めて手がけたオフィスビルだ。 市内の7つの事業所と400人の従業員が集まり、オフィス内は100%自然光が入ることになっており、現場でガラスパネルを曲げた世界初のガラスカーテンウオールや1階ロビーにある世界最大級の高解像度ビデオウオール、全フロアに設置されたテレビ会議施設など、先進技術が随所に盛り込まれた。 ・・・・・・この現場でガラスパネルを曲げた世界初のガラスカーテンウオールが少し気になります、どのように施工しているのか?・・・・・ちなみに日本では上記のHPでもあるように、神戸の「フイッシュ・ダンス」です(プロフィ-ルに使用) 所在地:米国ニューヨーク発注者:InterActiveCorp設計者:Gehry Partners,LLC施工者:Turner Construction竣工時期:2007年3月延べ面積:─その他:エンジニア:Desimone Consulting Engineers 、Cosentini Associates インテリア:Studios Architecture 他に、2/4のブログの「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」もそうです
2007.03.07
コメント(0)
-
国の考え・・・・
いま安部総理は国会の質疑回答に頑張っております、色んな意見があると想いますが、あの淡々と答える仕草は好きです、マアどのような総理、大臣であっても選ばれた限りは応援するというのが、私の考えです。 ・・・但し考えとか顔によります(顔はその方の想いを表していますから大切かと) いま揉めている「慰安婦」とかでも、約60年前の事で後片付けをしていなくて揉めていますが、別の考えから言えば、「充分している」また違う方向からは「モット、謝れと」・・・では一体どこめで?と悩みます、多くの考えがあってゼッタイにまとまらない・・・謝るにはきりがないです・・・ 野党の質問にも相変わらず言葉の端々だけを捉えた質問とかには、ショウとして観るのも、ネットが限度です、あれを延々と見る気は起こらないから、国政への関心も無くなるのでは。 そうなれば、ある時期集中して、仕事も同じなのですが、問題があれば徹底して調査し回答するしかないし、それでも違う意見が出るのは、特にこういった過去の問題には対応の限度を感じます。 当時の法律とか、時代背景なんかとてもじゃないが、今の世代では考えられない・・・ ならば、今の国の状態を見て頂くしかないのではないか?と 賠償とか補償もそうだと、相手に対しどれだけの補償をしてきたのか、そのアタりをキッチリ提示する必要を感じます、新聞社とかメデイアはいつも戦後のこととなると、政府を責めることしか知らなく、どれだけの犠牲を国を挙げて行ってきたかと言うのをモットnewsで挙げていただきたい。 それに何故メデイアは何か問題発言があれば「世界から孤立」だの「アメリカ議会では・・」との逃げ口上だけで、単なる自慰行為に近いようです、実際にアンケ-トなどで調べたわけでもないのに、メデイアの存在を危うくしているのは自身だとまだ気付いていないようです。 良いことも、悪いことも・・・・ だから、新聞離れ、TV離れをし海外逃避、ネット逃避・・・となるのに リンクしている 「アジアの真実」さんの記事で今日面白いのがありました。 「英BBCアンケートで世界への好影響は日本がトップ 」他のニュ-スでもたくさんありますが、こういった、情報を明示することで、また実績を提示することしか理解いただけないのでは、それでも駄目なら「無視するしかない」と思います。 しかし前提は「日本が行ってきたことは消せない」と「本当にあったことを限りなく明らかにする」と「間違いは間違いで正す」という姿勢は必要だと・・・・ 右翼とか左翼とかネオ保守とかの考えでも、一般市民の考えでもなく、自分の今の考えとして書いてみました。(当然のごとくまた変わります)
2007.03.07
コメント(0)
-

ホテル・プエルタ・アメリカ・・・・
ホテル・シルケン・プエルタ・デ・アメリカ(Hotel Silken Puerta de América) 2005年にできた、スペインのマドリッドに 「ホテル・プエルタ・アメリカ」というホテルがあります、当時世界で著名な建築家が13の異なる国々の18人を選び12フロアを異なる建築家がデザインを担当し、宿泊者が楽しめるように、この豪華な五つ星ホテルの、342の客室(各階30室)が出来ました。 それぞれ芸術や文化に基づく異なる眺望を表現するアイディアを生み出し発展させるため、自由な裁量を与えられ、 「夢見る場所」をテーマに、この多文化性を持つホテルは、芸術とデザインへのトリビュートを目的として作られたのです。 日本からは、10階を担当した磯崎新で、イメ-ジは繊細でリラックス感をあたえる日本的なテーマを強調した・・・と言われています。全体をフェリペサエス・デゴルドア(SGAエステュディオ)ハリエット・ボーン、ジョンサン・ベル庭園やホテルに隣接する公園などのランドスケーププロジェクトレストランは、クリスタン・リエーグルの設計。テレサ・サぺー氏は644台を収容の駐車場用サインのデザインエントランスロビーとレセプションルームはジョン・ポーソン ちなみに各階01st floor Zaha Hadid (ザハ・ハディド)02nd floor Norman Foster (ノーマン・フォスター)03rd floor David Chipperfield (デービッド・チッパーフィールド)04th floor Plasma (エバ・カストロ、ホガー・ケーン)05th floor Victorio & Lucchino (ビトリオ&ルチノ)06th floor Marc Newson (マーク・ニューソン)07th floor Ron Arad (ロン・アラッド)08th floor Kathlyn Findlay (キャスリン・フィンドレー)09th floor Richard Gluckman (リチャード・グルックマン)10th floor Arata Isozaki (磯崎新氏) 11th floor < Mariscal& Salas (ハビエル・マリスカル、フェルナンド・サラス)12th floorと正面 Jean Nouvel (ジャン・ヌーベル) 日本でも同様の事例 「IL PALAZZO」
2007.03.06
コメント(0)
-

ヤトロファ・クルカス・・・・・
ヤトロファ・クルカスという植物があり、種子は下剤や吐剤に利用され、また、種子からとれる油は石けんや機械油の原料にするなど、有用な植物です。 昔からアフリカでは生垣などに用いていたようですが、この「ヤトロファ・クルカス」さんが今注目されてきています、それはバイオ燃料の原料として、トウモロコシもそうですが、シカゴではバイオ燃料の原料であるこのトウモロコシが高騰してきております。 他にはサトウキビ・糞尿・木材・食用油・有機廃棄物・稲ワラ・菜種油・パ-ム油など こういった、植物系などを燃料として利用する場合、植物が光合成でCO2を吸収し、燃えるときはCO2を発生し、プラスマイナス0だと考えられています。 石油が有限であるのに対し、水と太陽があればいい植物は、より持続的利用が可能な燃料です。 硫黄酸化物の排出ゼロもに近く、一酸化炭素・炭化水素(すすや黒煙)が少ないなどの特徴があります、しかし、人体に有害なアルデヒド、窒素酸化物が増えるという欠点も持っており、これらの物質を無害化する触媒が必要である。 バイオ燃料はヨ-ロッパではかなりのウエイトを占めてきていると聞きますが、これによりアフリカが巨大な資源の大地に変わるとも言われています。 現在、世界では8億5000万台の自動車が走り、「7.5人にクルマ1台」という時代です、これから途上国にもクルマが普及し、例えば世界全体が「1.7人に1台」という日本並みになれば、37億台が世界の道路にあふれかえってしまいます。 ブラジルや米国ではバイオ燃料が普及し始め、大気中の二酸化炭素を吸収して成長する植物から作るバイオ燃料は、燃やしても二酸化炭素の総量は増えない。 最も有望視されるエタノールを木や草から作り出す技術も研究が進み、それにメドがつけば、バイオ燃料の「地産地消」が世界に広がり・・・ もう1つのアプローチは欧州が先進地である社会的な取り組みだ。独ミュンヘンでは都市の周辺までクルマで来て、その先は地下鉄などを使う「パーク・アンド・ライド」方式が定着した。パリでは昨年末に70年ぶりに路面電車が復活したりしています。 日本でも富山市の新型路面電車や神奈川県藤沢市の優先レーンを走る高速路線バスが好評だ。公共交通が復権すれば、環境への負荷軽減と便利さの維持が両立でき、都市の個性を磨ける。貨物ではトラック輸送の一部を鉄道や船に替えるモーダルシフト(輸送方式転換)が広がっています。ディカプリオ氏の選択 最後に私たち1人ひとりの考え方や価値観も大きな意味を持つ。米国では有名俳優のディカプリオ氏らがハイブリッド車などに乗って、アカデミー賞の会場に現れるのが例年の光景になった。「俳優たちは何台のクルマを持っているか」と冷やかすのではなく、「高級車よりも、環境によいクルマがかっこいい」というメッセージが、米社会にじわりと浸透しつつあることに注目したい。 温暖化の被害者は市民1人ひとりだ。二酸化炭素を排出するのも同じ市民である。被害者は同時に加害者でもある。「環境によいクルマを選ぶ」「燃費のよい運転を心がける」。こんな価値観や習慣が広がれば、恩恵はわたしたち全員に及ぶ。 常に技術革新と社会へのアプロ-チ、さらに個々人の価値観修正と考え方の革命、このアプローチをコツコツと積み上げるのが、いまできる唯一の現実的な道筋だと感じます・・・個人として。 仮にも今や車だけを取り上げれば、自動車先進国の日本は世界に範を示す「環境とクルマの調和」をめざし努力を重ねていくのが、一つの平和への道かも・・・ 快適と利便の代償。それは、人類が今後ガラスの地球上で継続して棲息できるか否かの分かれ目になる・・・モウヒタヒタと忍びよっています・・・ 今の拡大・成長路線を取るならば、「中国の路線」は確実に人類はある時点で「棲息破綻」がやって来る。エネルギーの枯渇・食料の絶対量の不足そして、絶え間ない民族・地域紛争(エネルギー・食料の獲得戦争)で滅亡するのである。 このことは、30年前の1970年代にローマクラブがデータで示した警鐘であった。殆ど、この警鐘が活かされなかったと言う「人類の性」である。 この30年一体なにをやってきたのかと感じます、本当に大切なもの、優先すべきものは目の前にぶら下がっているのに・・・・
2007.03.06
コメント(0)
-

古代出雲大社・・・・
出雲大社も巨大建築の一つであったようです・・・資料 以前、大林組がCGとかで復元しておりました、古代から人は高い所から見渡すことが好きであったしもちろん、出雲大社ならば神を向かえるため、宿る施設としての位置付けであったのでしょう。 いまでも、新築された庁舎なんかでは何故か展望フロア-を設け市民のサ-ビスとかの名目で公開していますが、これも?です赤字なのに何故ここまでやるのか?勿論、対外的に必要なのは分かりますが・・・神は宿りませんが「お上」は宿っています。 何時ごろから、こういった展望フロア-なるものが出来始めたのでしょうか? 天守閣に原点があるのかな~?・・・・安土城の復元 そういえば、建築家安藤忠雄氏が設計した大阪府の「近つ飛鳥博物館」もよく観れば出雲大社のイメ-ジににているような~(こらは私の独断と偏見ですが) 人が山があれば、登るように、高い建物とか、木があれば登りたくなるのは本能なのでしょうか? 宇宙が最たるものでしょう・・・ 地下にもぐるのもそうなのかな?地下街?地下鉄? ・・・・・・・・・・・・・・・ 話は全然違いますが、あの建築家黒川紀章氏が東京都知事に立候補の予定でマニュフェストが提示されてました(資料)・・・読ませて頂いてこれは、多分、黒川氏の建築とか都市計画に対するライフワ-クのひとつである意味、集大成のような気がしました・・・・今後どのような選択をされるのか楽しみです。
2007.03.06
コメント(0)
-
雑誌・・・写真の信用性・・・・
最近建築雑誌を買って、建築写真を見なくなりました雑誌の値段が高いこともありますし、近くの図書館で充分まかなえるからですモウ一つの原因はパソコン・・ネットですネットに繋げると、もうそこには最近の竣工写真が海外、国内問わず目の前に現れますしかし、その写真も本当に本物なのか?それも最近疑問に想うことがあります写真がデジタル化となり、例えば建物の見栄えに邪魔な電柱を消すことも可能になっているし、色の加工もできる、高さがおかしくプロポ-ポションまで修正することも可能となってきています。最近現場の工事写真で問題もありましたが・・・・勿論そこまで建築雑誌はしていないよな・・・と信じていますが でも考えてみると建築写真もそうですが、話は全く違いますが? 俗にいうグラドル(グラビアアイドル)なんかでも、谷間を大きく見せたり、多少細く見せたりはキット日常茶飯時に行われていると・・・?ということは、「美」を追求することは、暗黙の了解でヒョットしたら、編集側と読み手側で自然と行われているのかも・・・・ 建築のプレゼンテ-ションに用いられる完成予想図の「パ-ス」もそうです、あたかも緑があるかのように、また廻りの色彩も誤魔化し・・・と考えると以前から行われてきたことだと・・・今でも、マンションのチラシなんか見ると、青空で緑があり鳥が飛び・・・ともう何でもアリかもタイル面に水をまいたり、落葉を置いたり、なんかは許せますが・・一応「イメ-ジです」とは書いてますが・・・決してチラシには真実は無いと考えたほうがイイのいかもそれが、「YES」か「NO」かについては意見が分かれると想いますしかしこういった流れは、暗黙の了解のもとに、行われています単なるメデイアの問題ではなく業界全体の問題かもしれませんこれもある意味、捏造かもしれない・・・こうしないと「売れない!」ではミスコンの写真審査もそうかも?ソレを少しでもリアルに、正直にするためにはミスコンを例にとると、実物を見る、質問する、触る(これはマズイ)、臭う(これもマズイ)、プロセスの確認・・・など最近の耐震偽造もありますが、建築はこれから生の情報が要求され、そしてその「プロセス」を確認する方向になってきます、もうそう状態になっているように想います。これが大袈裟になる前に自主的にしないと、また蜂の巣をつついたようになるのでは?
2007.03.05
コメント(2)
-
オ-クションから・・・
オ-クションを私の廻りでやっています といっても「サザビ-ズ」とか 「クリステイ-ズ」とかでなく、Yahooオ-クションです 家のガラクタの中から、昭和30年代のおもちゃとか、使用済み切手、お菓子のシリ-ズ(パッケ-ジ)など、「エエ~こんなもん、売れるの~?」というと、出す人間は 「これが、コレガ、イインヤ~」と・・・ それなら実家に「スマップの学生服のポスタ-アルヨ、それもスマップがデビュ-前後カナア~」というと・・・「ソレ、それ高く売れる!」持っておいでと・・・ エエ~という感じ、前からお宝鑑定などと、知ってはいたが、モノの価値はわからない・・・ 結局自分が大切で好きなものがその時代に合えば、価格が上がるのかな? さらに違う友人はグラスが好きで、それも大正ガラス?とか言うもの・・・少し曇っていて、底にヘソが付いているもの・・・ナルホド・・・「そんなガラスだったら、この前学校の撤去で窓ガラスがたくさん出たけど・・・」そこでも・・・「オオ~ソレジャ、ソレジャ、どないにしたん?」・・・ それは、学校側も知っていたようで、新築の一部に使いましたが・・・ それ以来、私は素人として、骨董市なんかによく通ってましたし、少し田舎の金物屋とか骨董屋さんへ行けば案外価値がずれて、貴重なものがあることを知りました。 こういった骨董の部類に入るものは自前では持ってないが、ヤガテ時間が経てば値が自然と上がってくるのかも・・・ やはりものは大切にしないといけません。 しかし、最近のお宝を見ていると(あまり深くは知らなくて勝手なことを書いてますが・・)この時代にしか通じないような気がするし、サザビ-ズなんかでしたら、モットウンチクが多そうで楽しそうな感じがするのですが・・・ 古本もそうですが、モノがあふれると当然価値も下がるのでしょう、あの「切手収集もいい例かも・・・・骨董の飽和と経済の流れはリンクしているのかもしれません。
2007.03.05
コメント(0)
-

フランス ミヨ-高架橋・・・・
2004年 フランスのミヨー橋(ミヨー高架橋、フランス語:Viaduc de Millau、英語:Millau Viaduct)は、フランス南部アヴェロン県の主要都市、ミヨー近郊のタルン川渓谷に架かる道路専用の斜張橋である。フランス人橋梁技術者ミシェル・ヴィルロジュー(Michel Virlogeux)とイギリス人建築家ノーマン・フォスター(Norman Foster)の協力で設計されたミヨー橋は、主塔の高さがエッフェル塔や東京タワーよりも高い343メートルに達する、世界一高い橋として知られている。2004年12月14日に式典が行われ、12月16日より開通した。・・・『ウィキペディア(Wikipedia)』 ここでも、土木だけの技術者だけではなく、あの香港上海銀行、香港本店を設計した建築家ノ-マン・フォスタ-氏も協力したとのことです、日本の愛知県豊田市にも黒川紀章氏がデザインした豊田大橋もあります。(矢作川・・・豊田スタジアムもそうです) ・・・このミヨ-橋ですが、上記のようにかなり高度が高いためモヤが漂いなんとも幻想的と聞きましたが、霧がなくても中々素敵だと想います。 その工事中とかデイテ-ル(少し)などが動画で紹介されてました。(音楽もあり)・・・資料 橋は知らない街と街を繋げるものです、本当はすごく夢があふれているのかもしれません。
2007.03.05
コメント(0)
-

妖怪たち・・・・・・
妖怪たちは今色んな本を見て書き写しているだけですが、果たして自分がまた現代人間がそういった妖怪を見て感じ、創造・想像できるでしょうか?昔の人はかなりの考えを持っていたし、怖れとか畏怖の念を持っていたのでしょう、アニミズムという霊的存在が肉体や物体を支配するという精神観、霊魂観を大切にしていたのでしょう。 現代の人が忘れてしまったものでしょう・・・決してつまらぬ情報に踊らされていては感じることはできない、と思います。鳥山石燕 画図百鬼夜行 巻之中 明・・・より天井下(テンジョウクダリ)天井とは家の中の異界である、天井は安達が原もかくやと見がまう場所であり(「甲州の辻堂に化物がある事」)、女が夫の殺した愛人の首を持たされて監禁した場所である。天井を見せるとは、人を困らせるの意味、石燕の頃の流行語であったらしい。延宝五(1677)年刊「宿直草」巻二は何故か天井の怪異についての話が集中している。そういえば、忍者は天井にぶら下がっているが?大禿(オオガブロ)彭祖(ホウソ)は夏(カ)から殷末にかけて七百歳生きた人物、仙人であり、雨を司る神でもあった(「捜神記」巻一)周の穆王(ボクオウ)の枕を越えたという罪で流されて、配所で菊の露を呑んで不老不死の身となったのは菊慈童。日本では、那智は知らず、高野の大禿とは、俊寛の遺骨を納めて蓮華谷の出家となった「大童子」・有王のことであったか。日本にても那智高野には頭禿(こうべかぶろ)に歯豁(はあばら)なる大禿ありと云う。しからば男禿ならんか。中国で今度北京オリンピックに向け天候を人工的に変える実験とかもやっているようで、この大禿がいれば何とかなるのかな・・・・大首(オオクビ)平清盛が福原に遷都した時、夜、庭前の塀の上から一間に納まりきらないほどの大きな顔を出して笑った女、「面女(ツラオンナ)」がいた。(恋川春町画「妖怪仕内評判記」)。「面女」も「大首」の女も鉄漿(おはぐろに用いた液)を黒々とつけている。百々爺(モモンジイ)野衾のことだといいますが、石燕は無人の原野に現れる老夫の怪としている。普通は「ももんが」と「ももんじい」は同じ。草双紙「化物よめ入」には、ももんがとは化物の異名といい、市場通笑の黄表紙・天明元(1781)年刊「化物鼻が挫」は「ももんがじいはながひしげ」と読む。金霊(カネダマ)金(カネ)だまは金気(キンキ)也、唐詩に「不貪夜識金銀気」(むさぼらずしてよるきんぎんのきをしる)といへり。又論語にも「富貴在天」(ふうきてんにあり)と見えたり。人善事をなせば天より福をあたふる事、必然の理也。無欲善行の人に福がくるといっている。千葉県でいう金玉は空を黄色く光る玉が飛ぶというもので、それが飛んで行く方にある家は栄えるそうです。東京都でいう金玉は音を出しながら落下するもので、これが落ちた家も栄えるそうです。静岡県でいう金玉は夜に一人で歩いていると赤く光る玉が足元に転がってくるというもので、それを傷をつけたりせずに床の間に置けば金持ちになれます。しかし、もしも傷つけてしまうと家が絶えてしまいます。 『兎園小説』にも金霊のことが書かれています。1825年3月のある朝、千葉県で農民が田んぼの見回りをしていると、雷のような音とともに鶏の卵ほどの大きさの玉が落下してきました。農民はこれを金霊だと考え、家宝にしたそうです。参考・・・・もののけが集うホ-ムペ-ジ
2007.03.04
コメント(2)
-

Going green in the desert・・・・砂漠の緑、オアシスかな?
砂漠の国?クウェートのオフィス開発ですMIPIM賞(世界不動産見本市)で最終残ったプランです World Architecture より・・・・・ アトキンスバーレーンプロジェクトは2007MIPIM Architectural Review Future Projects Awardにおいてのものです。 この180mに及ぶタワ-の面積は56,400平方マイル。 この複合施設のビルは、仕事、レジャー、内外の空間を結合し、ビジネスのために持続可能で環境面で様々な生活の楽しみに、当てはまるようなシナリオを提供します。 中空の庭にはフードコートがあり、 オフィス空間には体育館、鉱泉、ヘルスクラブ、およびプールもありその上空には吊られた空間もあります。 外部は木の葉でカモフラージュし、リフレッシュするスペ-スを人々に提供し、ソーラー・パネル被覆加工はビルのエネルギー需要及び省エネに貢献するでしょう。・・・・トマアこのような紹介でした(訳は適当です)、ちなみに何時建設で竣工かは記載されていませんでした。 緑が外部廻りに植えていますが、施工はできると思いますが、後のメンテなんかどうなるのでしょうかネ、まあオイルマネ-でまかなうのかな?でも贅沢なプランです・・・仕事としては面白そうですが、生態系とか環境面を考えるならどうなのでしょうか、私は中東へは行ったことがないので分かりませんが、島国の感覚かもしれませんが・・・そういえば中東の国にはかなり素敵なホテルが建設されてます・・・・
2007.03.04
コメント(0)
-
優先順位・・・・・
人が生活を送る場合、仕事もそうですがそこには、必ずと言ってイイほどの「優先順位」がやたらメッポウ発生します。 朝起きて、「顔を洗おうか?」「歯を磨こうか?」「ネットをしようか?」「マダ寝ていようか?」「身体を動かそうか?「もう一度寝ようか?」ナドナド いつも選択肢があらゆる場面に登場しては消え、また登場するという日々の繰り返しです。 永遠に続く、アミダクジのようでもあり、迷路のようです。 それが日常何事もないように送っているということは、キットイイ状態なのかな? でもほんの少し選択、そして優先順位を間違えば、モウ大変・・・勇気アル撤退か、後戻り、方向修正など、それも何気なくやっている場合と、多少苦しみながらこなす、またモウ汗だらけになって頭を下げっぱなしでこなす・・・と色々あります。 でも結果はどのような状況でもついてきて、確実に時間が解決します。 そのように考えると何を優先し大切にするかで、人の人生の形を創られてきそうです。 勿論、良いもの、好ましいもの、徳高く、誉れがあり、それが称賛に値するなら・・・ナオ良しでしょうが・・・ これが簡単なようで、難しい、以前 「自然界のプロセス」でも引用しましたが、全てにプロセスがあり人は自由意志で決定したことに対して、全ての結果を被ります。 というフウに考えると、何を大切にし、守り、育むことが必要なのは、それぞれが心にキット思うことでしょう、そこで本当にイイ選択を多くの方げ正直にできるなら、どれだけ素敵なことでしょうか? 難しいことではないと思えば、キットできるはずです・・・・ 多くの仕事もそして、建築の計画、設計も施工も多くのプロセスがあり、選択しながら、また委任しながらものごとを完成する方向へ向かうという気持ちが一致すれば、モウ百人力、千人力でしょう。 だから優先順位を間違いさえしなければ、多くの場合ホボ、いい方向へと向かいのではないでしょうか? 私の場合?・・・まず「〇〇〇」「家族かな?」多分それができれば、全てはうまくいくような・・・・ そういえば学生時代にスポ-ツが出来て、学問も優秀なヤツがいましたが、万能ではなくある一つができるなら、他が出来ないのではなくて、それもできることでしょう、だから一事が万事とはよく言ったものです・・・これも優先順位の問題かな?
2007.03.04
コメント(0)
-

ファサ-ドデザイン
設計も何年か前イヤそれ以前からあったでしょうが、「ファサ-ド、デザイン」をやる方が出てきました、多分最初は日本ではカ-テンウォ-ル(ビルのサッシなど)なんかが出発で、それが街に与えるインパクトとか道路に面する方しか見えなくて、どうしてもその建物の「顔」を飾る、デザインする必要が当然発生してきます。 中途半端な建物でしたら、一方向だけイイカオにし、後の三面はマアと手抜きで素地そのママなどはよく見受けられます、勿論予算の都合もありますが、それに将来ヨコ、ウシロは建つだろうのもとに、計画し建ってますが、その思惑が外れ、居場所がないような建物も観られます。 そのファサ-ドデザインですが・・・東京「グッチ銀座店」ではファサ-ドデザインの先駆者、ジェ-ムズ・カ-ペンタ-氏が手がけておられます、ちなみに光の彫刻家といわれています。 GucciのHP この建物は、インテリアはグッチ・クリエィティブ・ディレクターのフリーダ・ジャンニーニとインテリア・デザイナーのウィリアム・ソフィールド、照明デザインはライティング・アーキテクトの豊久将三が担当しております。 このように分業化がかなり進み、では一体誰が統括し決めていくのか?丹下健三氏の時代とは少し趣きが変わってきています、勿論丹下健三氏の時代も色んな方とコラボはされていました、例えば彫刻家のイサム・ノグチ氏などです。 ファサ-ドデザインも一つの専門職となってきており、今後街中でのデザインを決めるのに大きなウエイトを占めそうです。 ちなみに昨年、11月にオ-プンしています、私はブランドの蚊帳の外ですが、建築など仕事に関わってきたならば、興味も出るのですが・・・・・逆にかかわりをもつようにすれば、関われるのかな?
2007.03.04
コメント(0)
-

天道白衣大観音・・・・・
宮城県は仙台にある 「天道白衣大観音」 建築面積は1020.72m2、延床面積は1509.44m2、主体構造はRC造(鉄筋コンクリ-ト造)、基礎は直接基礎・・・・ 外部は白色フッソ樹脂、内部は吹付タイルとなっており、その高さは約100mです。 また下部の龍をかたどった台座は直径33.75m、台座を除くと高さは92mです。 工事は1988年9月から1991年と約3年と2ヶ月という工期で、これが短いか長いかはわかりませんが。 これはもともと2mの彫刻から100mへと外形を整えていったらしく、その過程において技術的な躍進を開発していっております。 それは当時はこういった巨大人型建築は内部は鉄骨で下地を造り、表面をFRPとかRCで造っていくというパタ-ンだったのを、施工会社は(株)熊谷組と川鉄です、その施工会社が3次元のデジタイザ-で、原型の彫刻のデ-タを@150~300程度で作成し、数値化し、そのデ-タをもって、実際の型枠、鉄筋などに生かしたものです、(設計-施工支援システム「K-PACS」?)ですから簡単に言えばこの人型建築の構造は表面がそのママ構造体として成り立っております・・・・考えただけでも、型枠の図面作成、チエックは並大抵ではなかったのかと思います・・・ いまではそのあたりの図面は手元のパソコンで操作が可能となってきていますが・・・当時はフロンテイアであったでしょう。 型枠は合板を用いたようですが、FRPも使っております。 しかし写真で観るだけですが表面は美しいです、かなりの精度でのコンクリ-ト打設かと・・・恥ずかしいですが実物はまだ見ていません。 内部はエレベ-タとラセン階段、上部には展望台が配置されてます、このように巨大人型建築は、一部バブルの遺産のものもありますが、建築技術の進歩には「天道白衣大観音」のようにかなり貢献しているものもあるし、特別な技術ではなく、在来の技術の延長上で施工されているものもあります。 しかし、山の中とか、高原、街の中などスックト立つ姿はいつもそこに存在するということは、ある種不思議な感覚があります。 昔から人は巨大なものが好きだったらしいです・・・NYでは「自由の女神」日本では東京タワ-とか、太陽の塔、京都タワ-、各種回転レストラン、各種展望台、通天閣、突然ビルの中の観覧車ナドナド Nipponデハ、1793年(寛政5年)二月二十日から六十日間、南品川鮫頭海晏寺 で観音が開帳された時、境内の銀杏の大樹を心棒に身の丈、十六丈(約50m)?エエ~という感じですが・・・ また仏師光雲が造ったのは。大仏型見世物小屋、高さが四丈八尺(約14.5m)と今でいうと、4階建てでしょうか、仕上げは黒漆喰で下塗りで、青い色を塗り重ねるという手法で、マア張子のトラののようです、造ってから人気でしたが、暴風雨が襲い、表面を飛ばしてしまったようです。 下地は竹と丸太を組んで、土を塗り仕上げたようです・・・・内部、体内はかなりの暑さだと思います。 光雲の記載では明冶十八年(1885年)らしく、自由の女神が完成する前年のようです。 この巨大人型建築を今後機会があれば追っかけてみます。 なお奈良では壷坂寺の観音さん、有名な大仏さん、京都では京都タワ-・・・これはタワ-ですが人型?のようなもの・・・・奈良県、高市郡高取町の壷坂寺、下の写真は観音さんと涅槃像・・・西国33ケ所6番札所・・近くには、あの日本一大きな山岳の高取城があります。天竺渡来の大観音像とデカン高原(インド)の花崗岩で作造された大涅槃像。高さは20mで石は1200t使っているようです。
2007.03.03
コメント(0)
-

ベルギー・ブリュッセル
KenPlatzより228の窓に人物画が並ぶCDH政党本部へ――ベルギー・ブリュッセル ここはフランス語を話す有権者を支持基盤にする中道的な政党、CENTRE DEMOCRATE HUMANISTEの本部である。 1966年に建設された当時から、ファサードの全面は党のロゴタイプにも使用しているオレンジ色にデザインされていた。現在の党首、ジョエル・ミルクエット氏の強い要請があり、選挙活動にシナジー効果を吹き込むため、2006年に改装されたという。 228の窓枠が壁を埋め尽くす 年齢、職業、性別の異なる35人のイラストを作成。異なった色彩のバージョンをつくり、228を数える窓枠に収めたのが改装の主な内容だ。イラストがプリントされたプラスチックの粘着シートを窓ガラスに張っているが、内側からはこのイラストが見えないのが特徴だ。オフィスで働く人たちにとっては視覚的になんら影響がない。 景観と色彩に詳しい知人に、このビルについて意見を求めたら、「使われている色自体は調和しており、窓枠の形状と合わせて高いデザイン性が感じられる。周辺の建物を含めた町並みの景観という観点からは、賛否が分かれると思う」というコメントをもらった。 現地の市民の感想はどうなのだろうか。クリエーターのジャン・ラックさんに聞いてみると、「ベルギーの街は全体的にグレーの建物が多いのだが、この建築に関しての反感は皆無だった」と言う。改装が功を奏したのかCDH党は直前の選挙で議席数を多少ではあるが伸ばしたという。 ある日突然、東京・永田町界わいの政党本部のファサードがカラフルに塗り替えられたとする。相乗効果を得て、選挙結果にポジティブに反映するシナリオを連想してみたが、全くの夢ではないような気がする。問われるのはそのセンスであろう。 建物名:CDH Building Brussels所在地:41 Rue des deux Eglises 1000 Brussels Belgium設計者:Mccann europe/Jean-Luc Walraff/Sophie Norman こういった建物を日本に建てるとどのような意見がでるでしょうか? 非難?賛同?ジット見守る?
2007.03.03
コメント(0)
-
大工の弟子
萩原朔太郎の詩に 「大工の弟子」という詩がありました、今まで知りませんでした。 アノ・・・サクチャンです(「世界の中心で愛を叫ぶ」の・・・)大工の弟子 僕は都会へ行き 家を建てる術を学ぼう 僕は大工の弟子となり 大きな晴れた空に向かって 人畜の恐れるやうな屋根を造ろう ・・・・・・・・・・・・・・ 僕は人生に退屈したから 大工の弟子になって勉強しよう と・・・・・もう少し調べてから色々感じたいです、しかし 「僕は人生に退屈したから」とはどういうことだろう?参考・・・・・萩原朔太郎研究所HP
2007.03.02
コメント(0)
全285件 (285件中 1-50件目)
-
-

- 【日曜日(安息日)の過ごし方】
- 亀有キリスト福音教会_第一聖日礼拝_…
- (2025-11-03 07:39:23)
-
-
-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…
- ☆ビーズコースター☆
- (2025-11-21 22:50:42)
-
-
-

- 運気をアップするには?
- 座敷童(ざしきわらし)と同様の現象…
- (2025-11-21 23:26:05)
-








