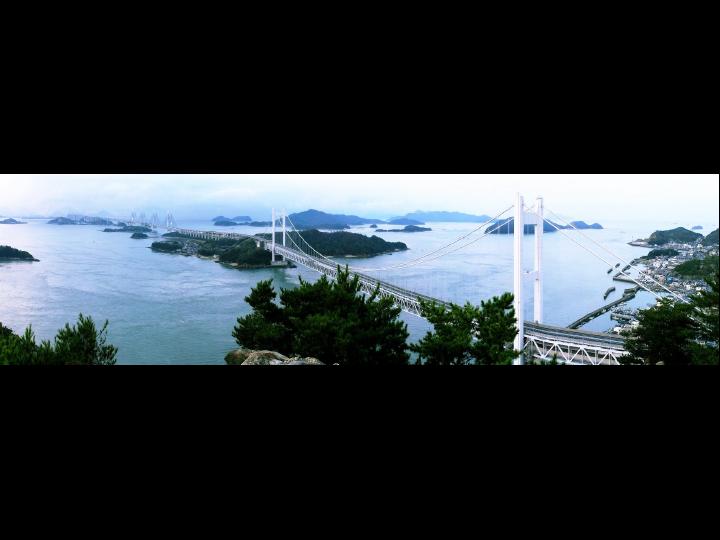2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年01月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

曇り空の日に鬱陶しいのは
曇り空の日に鬱陶しいのは・・・。 頭が重く何をするにも気力が湧かない、どんよりとした曇り空の日にはそんな状態でぼんやりとしている。これでも良くなった方なのである。鬱の状態であったので厄年も、更年期障害もその中に混じっていて自覚しなかった。更年期障害というのは何も女性の専売特許ではない。鈍感な男はあまり自覚しないだけ。雨がしとしとというのも少しは楽だが同じ症状を呈する。寧ろザーザーと降ってくれている方が開き直れて楽なのだ。 三十数年前車を車にぶつけられ整形外科へ半年ほど通院したことがある。二、三年して肩がこり頭が重く不眠で困ったのだが事故の後遺症くらいに思っていたのだ。だがこれはより深刻な問題の序章に過ぎなかったのだ。 私は医者ではないので専門的なことは分からないが三十数年前は鬱であるとは診断できなかったと言えよう。鬱病の存在は分かっていたが心の病くらいにしか思われておらず、日航機の機長が鬱なのに操縦桿を握り羽田をオーバーランをして認知されたというものである。脳神経外科へいけば脳波を取って筋収縮性頭痛と診断され薬を調合された。それを飲んでも一向に良くならなかった。整形外科へ行けばレントゲンを撮って首つりの機械で首をつられた。それも効き目はなかった。内科に行けば十二指腸潰瘍の注射を二十日間射れ飲み薬をくれたが駄目だった。この際専門医のはしごをしようと思い眼科、耳鼻科、泌尿科、肛門科、などあらゆる医院の門をくぐった。治療費の無駄だった。 私の周囲にも同じような症状の人がいて同病を哀れみ哀れんでいた。それは傷を舐めあっていたということだった。「あの人は横着者なのよ。一日中ボーとしていて何を考えているのかわかりゃしない。ヤクでもやっているのでしょうか」という声に心がさいなまれている人たちであった。その中の焼き肉屋の克つちゃんが、「何でも川崎医大に心療内科という科があるらしいのでみんなでいって見ようやないか」と言った。酒飲みのはしごと一緒でいくことにした。克つちゃんは川崎医大や倉敷中央病院に何度も入院して酒を飲み強制退院をしている猛者であった。何時もたばこ屋の巻ちゃんと魚屋の父の手伝いをしている敬子さんのところ入り浸りで焼き魚や刺身を食べながら想い人の敬子さんにつきまとっていた。店先の縁台に座って道行く車を眺めながら煙草の煙を吐き出していた。 克つちゃんと巻ちゃんと三人で川崎医大の心療内科を受診したのだ。待合いにはうつろな瞳を宙に投げて煙草をふかしている人たちが沢山いた。「そうですか、そんなに色々な医院を巡られましたか。みんなそうです、この病気は沢山の人が罹っているのですが世間では認識が不足しています。それに専門の医師でないと分からないのです」と診察を終えた若い精神科医は言った。処方箋の投薬をきちんきちんと飲み始めて頭は軽くなり眠られるようになった。何より頭に鉛をのせている様な症状がなくなったのが一番有り難かった。頭の重さがなくなってようやく思考が出来るようになった。だが、車に一人では乗れなかった。助手席に家人を乗せて短い距離を走る程度であった。「おい生きとるか」と尋ねてきたのが土倉さんだった。さんざんくどかれ原稿を引き受けざるをえなかった。どんなに今の体の状態を説明しても、「頑張れとは言わん。何時までも待っているから気長に書いてくれればいいから」またしても演劇の世界へ引きずり込まれた。家にいる分には不安発作は少なかったのでやけと道連れで書いた。何作書いたか覚えていない。演出もした。外に出ることで不安発作は軽減していった。 その頃舞台芸術財団演劇人会議のたちあげの実行委員になっていてその会議に東京まで行かなくてはならず一人で行動する恐怖はまだ残っていた。「いつかは死んで行く身、何処で果てよと定めかな、人の値打ちはただ長く生きるというものではむあるまい。ままよ今まで生きたがもうけもの」演歌の詩のような心境になってようやく参加した。 今年も国民文化祭の企画委員になって文句ばかり言っていたらお前のところがやれと言うことになり、一人芝居の「花筵」をやる羽目になった。時折気分が極端に高揚しいらぬ事を口走るときがある。その付けは意外としんどいものがある。 晴れのち曇りの人生を、頭抱えてケツまくり、生きる我が身の切なさは、巡る月日の草枕、何処で果てよと蝉時雨、きっと何かを拾うもの、明日の望みを考えず、今を生きると心に決めて、と心に言い聞かせているのです。「最近はどうなのですか」美しい声音が受話器の中から聞こえてきた。「今は怖いものがなくなりました」とだみ声で言う。「それはよろしゅうございました。案じておりましたの」「それはありがとうございます」「疣痔に切れ痔は大変でしょう」「はあ」 そんな間違い電話にも心安らかに身を置くことが出来るのです。 曇り空の時にはそうはいきませんが・・・。
2011年01月31日
コメント(1)
-

電話は午後にどうぞ
電話は午後にどうぞ。 午前中に私に電話をかけてくるのは友達にはない。友達なら私の生活を知っているから午後にかけてくるのだ。午前中は起きていないことを知っているのだ。寝ているところを起こすと機嫌が悪くぐずる幼児と同じできわめて愛想が悪い。会話が成り立たないのだ。頭が起きてなくて思考力はゼロに等しいのだ。そして、曇った日や雨の日にも決して架けてこない。三十五年ほど前にサイドに車のタックルを喰らうという交通事故で病院通いをし一応は治っていたのが数年して後遺症が出てそんな日は頭が重く何をするのも億劫なのである。そのことも友達は知っていて電話をかけては来ないのだ。自分勝手の横着者なのである。そんな私を見捨てずにつきあってくれている友達は神か仏のような心を持っていると思っている。後遺症から鬱という花が咲いたからどうしょうもない。二十年間つきあう羽目になった。別れようと何度も言ったが離れてくれなかった。悪妻のようなものだった。昼間はベッドに横になり頭を氷で冷やしていた。良くなった今でもケーキ屋が入れてくれる保冷剤をタオルの中に入れて頭に巻いて暮らしているのだ。この格好は何があろうがやめたことはない。新幹線の中でも、銀座を歩くときでも、お偉い先生方との会議でもタオルは外しをしないのだ。ターバンの様なものだ。鬱の名残のスタイルになってしまっているのだ。タオルはすり切れるので買わなくてはならない。保冷剤も劣化するので食べないケーキを買わなくてはならない、そんな生活を続けていたのだが最近保冷剤を売っている店を見つけてそこで買うことにしている。食べもしないケーキを買う必要がなくなったのだ。昔の知人からは時折電話がかかってくる。私の生活を知らない人たちなのだ。「しっとるか、小野君が内田百ケン賞の随筆賞を取ったこと」 午前十時頃杉原さんからかかってきた。「知りません。そうですか、それは良かった」「吉備の古墳のことを書いたらしい、目の付け所が違うな」 杉原さんは昔の同人誌の仲間で「文学界」の同人誌批評の今月のベストファイブに入ったほどの書きてであったが土地が高速道路に取られ億という金が入ってから小説は書かなくなり随筆、俳句などでお茶を濁していた。そのことは風の頼りで知っていた。彼は色々のところに応募してその近況を午前中に電話を入れて報告をしてくれていた。何処どの佳作に入った、とか賞に入った随筆の本を送ったからとか親切に言ってくれるが、私の頭は起きていないのだ。 そう言えば杉原さんと小野君のことでこのような事があった。 就業時間の終わった五時過ぎに小野君が血相を変えて飛び込んできてこの原稿を読んでくれと言った。二十枚ほどの短編に見えた。「杉さんがこのような作品は駄目だというのです」「あの人は誰の作品も斜めに読むからな」「今ここで読んで貰えませんか」「いいよ。暇だから」 読み終わってホーとため息が出た。「どうでした」「杉さん、これ読んでないよ。読めば作品の善し悪しは分かる人だから」「無責任ですね」「付き合いは君の方が深いでしょう」 二人とも市役所に勤務して良く話すらしいことは知っていた。「短編としては文句の付けようがない。良いできだ」「あの、ほんとうに・・・」「ああ、これなら何処の短編賞にだって応募しても受かると思うな」「ああ、胸が苦しかったのですが、今は大きく息ができます」「おばあさんの家の周囲に日に日に通勤の人たちの自転車が置かれていく・・・。おばあさんの心理描写が良いね。素晴らしい素材だと思うよ」「助かりました」小野君は胸をなで下ろしていた 小野君はその作品で中国新聞短編賞を受賞した。それを期に地方の賞をいくらか取っているはずだ。そして今回の随筆賞。 このような電話なら午前中でもどんどんかけて欲しいと思う。 朝の五時に眠ることにしているから夜は誰よりも強いのだ。 夜と言えば「女流文学賞」を取った梅内女史のことを思い出す。毎日夜の十時に電話がかかってきて午前六時過ぎまで私の家の電話は話中になった。かの名女優の杉村春子さんから弟子にならないかと言われた程の美貌と美声の持主の梅内女史の声が受話器から蕩々と聞こえてくるのだ。つまり彼女は受話器にむかって原稿を読んでいるのであった。主人を寝かし付けてから電話をかけ、起きる前に切ると言う、何時寝ているのだろうかと心配をしたものだが、エネルギッシュな人との付き合いで夜に強くなったのだと思っている。「あんたらなにしとるん。用事があってどちらに電話しても話し中やないの」 「歴史文学賞」を取った松本幸子さんに良くからかわれたものだ。 今は殆どがパソコンのメール、携帯は置いてるだけで持ち歩かない。電話も、「丸々化粧品ですが・・・」「××証券ですが・・・」「お金必要だったら貸しまっせ・・・」色々の勧誘電話ばかり、午前中なら、「いりまへん」と強く言ってガチャン。 今までの電話はこれからどうなるのか・・・。 遊び人の私に市の文化振興の企画委員とか国文祭の企画委員とかの要請がある度に午前中には電話をかけないで欲しいと一番に断りそれでいいのならと受けるのだ。
2011年01月30日
コメント(1)
-

書くわけ
書くわけ そこに山があるから・・・に通じて愉しいから書くのである。書く苦しさはあるが終わった後、出来不出来は別にして達成感と虚脱感の快い疲労は書いた者しか分からないだろう。 題材を決めて資料を漁り読んでからすべてを忘れるために若い頃はパチンコに行き喧しい騒音の波の中に身を置いていると今まで読んだものが頭の中から完全に忘れられたものだった。それらは体に入りとどまっていて書くときに自分の考えに変わって出てくれるのだ。パチンコには資金がいるしそんなことばかりしていたら家庭が破産するので深夜の映画館に行きポルノ映画を見ることで頭から忘れることもあった。蕩々とスクリーンに映し出される痴態をただ眺めているだけで何がどうなっているのか覚えてはいなかった。が、その方法も有効であった。だが書く前のプレッシャーを解きほぐすには馬鹿なことをして無駄な時間を浪費することであることに気づくのだ。読んだ本が頭に残っているとついつい生の資料を書いてしまうおそれがあったからそうしたのだ。その間に構成は出来、書き出しと終わりの1行が出来ていた。九十九パーセントが頭の中で出来、後の1パーセントが書くことなのだ。後は一気に書き上げていく、そこには降臨があって書いた物が自分の物ではないような感じを受けたものだ。書いて最低一ヶ月は何もせずにほったらかしておいて推敲をしなが書き直しをした。六月と十二月は応募原稿の締め切りなのでそれまでに四作づつ書き上げていた。万が一という考えはなかった。ただ書くことが愉しくてしょうがなかったのだ。その結果が応募であっただけなのだ。読んで書くそのことが面白く愉しかったのだ。そんな青春時代を過ごした人は全国で多くいただろう。書くことはいって見れば麻薬のような物だった。完全に書く中毒になっていたと言える。その楽しみの後には応募原稿が一次通過、二次通過、最後の十作へと繋がっていった。私の作品は暗くて重かった。人に読んで貰って喜んで貰える物ではなかった。考えて欲しいと思って書いたのだ。多分に自分のために描いた物が多かった。が、考える事のみを求める読者は少なく面白くて溜飲を下げることが出来ればいいという人たちが大半だった。それは分からないわけではなかった。この世知辛い世の中で金を出してまで人の苦しみを分かち合おうとする人はそんなにいなかったのだ。「もっと面白い売れる物を書く努力をしてください」と出版社へ電話すると編集長がそう言った。これは資質の問題でそう簡単に面白い物がかけるはずもなかった。出版社は賞を与えて雑誌に載せ評判が良ければ単行本にしてもうけるのだからそう言うのは当たり前であったろう。だが内容は重たく暗いが書く方は愉しかった。書いているとだんだん体が暑くなり昂揚して知らず知らずにパンツ一枚で書いているときがしばしばあった。 林芙美子さんが真冬に布団をかぶり裸で書いていたという逸話があるがそのことは真実だと理解できた。書いていると頭を血が駆け回り体はほてってそうなったのだろう。 文章を書くと言うことは頭脳労働であり肉体労働なのだ。物書きと言えば病弱な感じを想像するが今では健康そのものという肉体労働の人たちが多くなっている。精神が病んでいればいびつな物しか生まれないと言うことなのだろうか。深く物を考えていると精神は病んでくる、だが、今の物書き達は健康な肉体労働をしている人たちが増えたと言うことなのか。その方が健全だが。 昔の作家と言えば家庭のことはほったらかし、淫乱多情で、我が儘、偏屈、貧乏、病気持ち等々負の存在であった人たちが多かったのだが、今はそんなスキャンダルは聞こえて来ない。実生活が滅茶苦茶だが書いた物は清潔で道徳的だったという事が良くあった。それはまさに詐欺師なのである。きれい事を並べておいて反社会的な事をしていると言うことなのだ。なぜかそんな反社会的な作家の坂口安吾さんに惹かれ、彼の「堕落論」を教科書にしている矛盾を感じるのだが。人の世界はそんな物かも知れない。差別を否定している人たちが一番の差別者であるという事は良くあることなのだから。 私のことで言えば、鬱に罹って以来物事を突き詰めて考えるようになった。書くことが苦痛になっていたが快方するにつれて愉しく書けるようになり今までの文体が変わってきた。文章の短い人は循環器に傷害があるという説があったのだが、谷崎潤一郎さんの作品を読んでそれはただの仮説であると思った。彼は作品に依って文体を変えていたのだ。文体を持てと言う先輩がいたがその文体はテーマによって変わる物なのだ。だから文体など関係なく、自由に書くべきなのだと納得した。つまりテーマが文体を産んでくれるものと解釈している。そう思うと文体などに関わらずに書くことが出来る。 今読んでいる南木佳士さんの作品は私小説の色合いが濃いいが随筆と小説の文章は異なっている。それは彼の特質なのだ。 物を書く人の資質と言えば優しさと真実を持っているかどうかというものであると南木佳士さんを読んで感じた。 そんな物をこの私が持っているのかと問われれば、分からないとしか答えられないが・・・。
2011年01月29日
コメント(2)
-

猫への恩返し
猫の九太郎 九太郎という牡の猫を飼っている。 劇団員の少女が捨て猫を見つけてかわいそうだから飼ってもらえないだろうかと言うことで面倒を見ることになった。犬猫の獣医助手を目指す彼女に拾われたと言うことは捨て猫にとって幸運だった。が、飼う方には災難であることの方が多い。小さな泣き声であった子猫は大きくなるに従い猫の特性を遺憾なく発揮しだした。トイレにおしっこをしなくてくんくんとかぎ回り何処へでもおしっこを垂れ流しだしたのだ。マーキングである。猫のおしっこは犬と違い特別臭い。その臭いが家中充満した。家族に取っては耐えられるものではなかった。猫を飼うとこのようになると言う現実は充分に知っていたが猫には返さなくてはならない恩義があったのだ。恩のなんたるかを知らない家人は恐れ多くも、「また猫を飼うのですの。飼うのだったら去勢をしてくださいよ」 と平然と言ったのだ。恩義の有る猫にそんな動物である証の子孫を残すための行為に必要なものを除去出来るはずはないではないか、と言おうとしたが声が喉に詰まり胃袋に落ちたのだった。それは病気の所為ではなく去勢しろと言う家人の心理が怖かったのであった。九太郎を車で連れ出して二時間ほど走って帰り、「見事にたまたまを切除したぞ」と嘘を言ったのだ。それは妻に対する従順より恩義に対しての方が大きく重かったからなのだ。 三十年程前に仮面鬱病になったときに家の前のゴミ捨て場で三毛猫の雌を拾った。弱々しい声で泣いて哀れを誘っている猫に同情して夕餉のすき焼きの残りを食べさせてやった。お腹が減っていたのかおいしそうに食べる姿に感動しついつい家に上がらせたのであった。その猫に茶子兵衛と名付けた。 その頃肩がこり眠られず体が重たいし頭がボーとしていた時期であった。何軒も医院を訪ね診察を受け薬を調合して貰ってもいっこうに良くならなかった。おかしいと感じたのは県の青年大会の演劇部門で最優秀賞を貰い全国青年大会に出発する日に現れた。足がだるく息切れがして動けなくなったのだ。前日は興奮して眠れなかったので睡眠不足からくるものであろうくらいに考えて無理をして東京に行ったのだ。渋谷の参宮前駅で降り代々木オリンピックセンターまでの距離を歩いたのだが陸橋で立ち往生をしてしまった。どうしても階段が上れないのだ。階段を二三段上ると心臓は早鐘を打ったように鼓動し呼吸はぜいぜいと悲鳴を上げだしたのだ。一週間東京にいたが何がどうなったか定かに覚えていない。何度か医院のドアを開けたのは記憶しているが。そのほかは心臓病患者の様な不整脈と動悸の早さと喘息患者の様な息切れだけを記憶しているのであった。目黒公会堂での公演結果がどうであったか帰って聞くまでは定かではなかった。優秀演技賞と最優秀舞台美術賞を貰っていた。帰っていろいろな専門医に診て貰ったが正確に病名の診断を下す医者はいなかった。二階の書斎に上がる階段の途中で立ち往生をする事もしばしばであった。深夜とか静かにしているときに突然この世の終わりを告げられたような不安発作に襲われ何回も救急車で救急指定病院へ行った。着くと動悸は収まり息切れも治っているという状態が続いた。医者は何のために来たのかと言う顔をした。不安発作が鬱によるものとは判断できなかったのだ。 その頃茶子兵衛が現れたのだ。猫は心臓病と高血圧と精神の歪みの病気持ちに心の安穏を与えてくれる動物だと聞いていたのだがそれが真実かどうかはわからなかった。そう思って猫を飼ったのではなかった。捨てられた猫に我が身を重ねて哀れを感じたのであろうか。か弱い飼い猫がそばにいると言うことは精神を安定させる作用があった。茶子兵衛の動作を見ていると心がいやされた。同じ症状の焼き肉屋の旦那が迎えに来てくれ川崎医大の心療内科を受診した。貰った薬を飲むと体のだるさがなくなっていった。眠られるようになった。頭も軽くなった。肩がこらないようになった。不安発作も少なくなった。茶子兵衛はじゃれついて慰めてくれた。病名は仮面鬱病と診断されたのだった。医者の治療と茶子兵衛によってだんだんと恢復をしていったのだ。茶子兵衛は一日ボーとしている主のそばを離れず見守ってくれ見上げる目は心配そうで優しかった。いつも体のどこかへ尻尾をくっつけていて様子を見ていたのだ。テレビに対して話しかけ怒鳴る事しか話相手のなかったのだが茶子兵衛は話相手になってくれ独り言愚痴を聞いてくれた。その茶子兵衛は二年後に尿路結石による腎臓病でなくなった。もっと早く犬猫病院に連れて行ってやれば長生きが出来たであろうと後悔したものだ。 猫にはそんな思い出があり恩義があったのだ。 九太郎は何度か尿路結石になったがそのつど犬猫病院へ連れて行き茶子兵衛の撤を踏むこともなくなった。茶子兵衛のためにも九太郎を同じ病気で死なす事は出来ないと思っている。茶子兵衛の恩返しのためにその後三太郎を飼ったがその頃もまだ仮面鬱病は全治してなくいやされたのだ。元気になった今九太郎に手を焼きながらも面倒を見ているのは茶子兵衛と三太郎への愛情の印なのかも知れない。 九太郎を連れてきた劇団の少女は獣医の助手になり次男の嫁になって同じ屋根の下で生活している。今では双子の母である。
2011年01月28日
コメント(0)
-

道場破り
道場破り 私たちの若かった頃には何処の県にも何団体かの文芸同人誌があった。全国で言えば千は下るまいと思う。そのすべてが「文学界」「文芸」の同人誌批評にいかに取り上げられるかを目指していた。私も同人誌を二つばかり作ってはつぶした。編集責任者をしていて同人の原稿を編集委員と読んで協議して掲載作を決めていた。朝日、毎日、読売新聞「同人誌批評」や「文学界」「文芸」の同人誌批評に毎回取り上げられるという同人誌に育っていた。レベルは高かったと思う。同人の何人かは地方の文学賞をものにしていた。懸賞応募も盛んであったが殆どの人が二次三次まで残っていた。 そんなときに良く同人以外に原稿を持ち込んで読んでくれと言うことがしばしばあった。その人達を道場破りと呼んだ。 持ってきた人の前で原稿をめくる。殆どが一枚目でがっかりした。三枚も読めば作者の力量は読み取れた。そんな時に持ってきた人は私の目と手の動きに注視していたから格好だけでも真剣に読んでいる振りをするのだ。読みながら何か言わなくてはならぬ事にいらいらし疲労は全身に及ぶのだ。苦痛以外の何者でもないが前で真剣に見詰めているのでかわいそうになって読んでいく。三枚で作品の善し悪しは決まっているものを後何十枚も読まなくてはならぬ事は地獄以外の何ものでもない。「どうか忌憚のない意見をいただきたい。どんな批評にも耐える自信はありますから」と言われても小説の態をなしていないものをなんと言えばいいか困ってしまう。ここから持ってきた人と私の心理的なやりとりをしなくてはならないのだ。本人は素晴らしい小説だと考えているのか、これを小説と言っていいのか、何処を直せば良いのか、どのように書けばいいのか、どれに迷って持ってきたのかを判断しなくてはならなくなるのだ。心の底を観察する。どのように本を読んでいる人なのかは読めばある程度分かるのだが、本を師匠としている場合読んだ作品、作者の癖が出るものだからだ。読み進んで行く中でどこか良いところはないかとスケベー心が生まれてくる。優しいいい人を演じようとするのだ。 同人の場合には、特に掲載する作品にはとことんつきあい話し合い書き直しを要求するのだが、道場破りの彼らにそこまでする義理はないのだ。そんなとき私が何も分からずに原稿用紙にむかっていたときのことが頭をよぎるのだ。良い読み手がいてくれたのでどうにかこうにかやってこれたのだが、そのような人がいない彼らの良い読み手になってあげたいと言うのも資質の面から出来ないことが多い。つまり才能がないと言うことなのだ。努力して才能を芽生えさせると言う方法もあるが、文章はうまくても作品を誰に読ませたいか、何を伝えたいかというテーマがはっきりとしていないものが多かった。そんな人は多分に小学校の頃に作文が上手だと先生に褒められた人が多いのだ。作文がうまかったという人がプロの小説家になっている例はそんなに多くないのだ。 私は前に資質と言う言葉を使ったがすべての人は物書きに成れると思っている。本を読み砕いてもそれを生活の場で実践しなくては書き手としての血肉にはならないのだ。宗教に例を取っても聖書や仏典を読んでも生活の中でそれらを使いこなせなければ聖人には成れないと同じである。そこに勘違いがあると思う。つまり読んだものを何時までも覚えているのでなく生活の中で生かさなくては、唯面白かった、良かった、感動した、では駄目なのだ。それを文学的生活と言う言葉でやりとりをしていた。実践すると言うことは感性、雅性を作り、社会のあらゆる常識道徳を取り込み、自分の生き様を作り上げるというものなのだ。そこまでくると知らず知らずに文章は書けるようになる、テーマも自ずと生まれる。つまり降臨なのである。 そのような考えを巡らしながら読み進んでいくのだが何処にも目新しい表現には出会わなかった。良くある常套句の氾濫である。「銭にも棒にも引っかかりません。駄作ですと言うより作品以前です。ものを書くのは諦めて何か外に興味を見つけられたらいかがでしょう」こんな言葉は絶体に言えない。「大変だったでしょう」「はい。寝ずに書きました」「一日中書かれたようですね」原稿用紙だとペンにしても鉛筆にしても字の乱れが現れるもの、日を置くとそこから字は立ち上がってくるのでそう言った。「それでどうでしょうか」顔を引っ付けるように前のめりで聞いてきた。「この作品をどこかへ応募しようと思っておられるのですか」「はい」 言ってみれば殆どの文学青年はこの程度であった。 身辺雑記のようなもの、このような恋愛をしたいという願望もの、今までこのように生きた事をを書いたもの、苦労話、戦記物、そのほか色々様々な原稿を読まされた。道場破りの一本勝負で。「まあ、石の上にも十年と言います頑張ってください」三年を十年と言ってお帰りを願った。 道場破りには負ける事にしていた。同人になって欲しい人とは巡り会わなかった。 応募原稿を雑誌社の編集者が読まなくなったのは時間の無駄を省きたかったのではないか。一行三枚で判断して捨てる原稿が多すぎたのではあるまいか。今、応募原稿は下読みやが読んでいる世の中らになっている。「売れる原稿を書いてください」 私は若かった頃編集長にそう言われた。が、売れる原稿は書いたことがない。私にとっての必然しか書かなかった。 今、ブログにはあらゆる分野の小説が氾濫しているが良いものを書く人に出会ったのは五名程なのである。 一昨年、昔の同人誌仲間が「内田百けん文学賞」の随筆で受賞した。続けている仲間がいたことを喜んだものだ。 書くことが夢だとするとその夢を一生持って生きていくのも悪くないと思う歳になっている。
2011年01月27日
コメント(2)
-

文化講演会
文化講演会 最近は文化、文芸講演会の開催の情報を得ることはなくなった。昔のベストセラー作家は売り出し中の演歌歌手の様に全国を駆け回っていたものだ。それは本を売るためばりではなく国民の意識を高める上で効果的であった。今はそれをしないのは作家がテレビに出て半端なコメンテーターをしてお茶を濁しているせいか。それでは読者の心はつかめないだろうし読者のこんなものが読みたいという要求をつかめるはずもない。時代だと言ってしまえば終わりだが新人賞や直木、芥川賞を取った作家の本が売れないと言うのも納得がいく。書き手の必然が読者の必然と相い照らす事が出来なくなっているから売れないのは当たり前という物だ。作家では飯が食えないという時代であるが作家になりたがっている作家予備軍は多い。昔の様に文芸同人誌が多くなく減っているからそこで勉強をすることは出来なくなってブログに書いたり懸賞に応募するくらいになっている。満のいい人はブログに書いた小説が良い編集者に巡り会い芥川賞を取るという希有な人もいるがそれはあくまで希もので砂の中に金を見つけるより難しく殆どそういう恵まれた人はいないのが現実だ。百万円近く出して自主出版をする人も多いのだが出版界不況の中で良い商売になっていると言うことはそれだけ書いたものを本にしたいと言う希望があるからだろう。そのような人もプロの道は険しく殆どの人はプロにはなれない。プロでも注文の来ない作家がごろごろしているのだ。その人達はゴーストライターをして飯を食べている人が多い。林真理子は作家になる前に松田聖子のゴーストライターをしていたことは有名である。また、売れなくなると必ず「創作の仕方」「文章講座」などを書いて売れれば儲けだがそれより書き手が創作の原点に返るために書くことが多いようだ。書いた人で再起した人は殆どいないのはそれが徒労であると言う査証であろうか。 若かった頃、半年に一度はくる講演会に良く話を聞きに行ったものだ。皆な正装して拝聴していたのだ。インテリーの集まりの様に上品なのだが聞く作法を知らない。笑うところを笑わず手をたたくところでたたかない。さぞやりにくかったろう。開高健、曾野綾子、大江健三郎。井上光晴、野間宏、松本清張、水上勉、五木寛之、まだ沢山の作家や文化人の話を聞いたが、大江健三郎さんは我が子の話とほんの宣伝に終始し井上光晴さんは共産党をどんな経緯でいかにして離党したかを話した。殆どの作家は自作の本の宣伝が目的であり物見遊山もかねていろう。連載を沢山抱えていても地方に公演旅行をする余裕があったのだ。それだけでも今の作家とは違うと言える。その頃はまだファクスもなく出先で書いた原稿補を電話で読み上げて編集者が記述するというものと編集記者が原稿取りに行くという方法しかなかった。 心に残っていると言えば五木寛之さんと水上勉さんがある。 五木寛之さんは大学時代からテレビ創生期のの放送作家でありシベリア鉄道で北欧への旅をした。地中海沿岸の國にはあまり興味がなかったらしい。そこで国々を見て回り人にふれ歴史と文化を学び取った。後に「ソフィアの秋」「さらばモスクワ愚連隊」「蒼ざめた馬を見よ」「ガウディの夏」「ワルシャワの燕たち」などの作品を書く土壌を培った。直木賞を貰ったときに賞と同質の作品が五十作書きためて手元にあったという。みんな受賞をしても次作が書けないというのに五木さんは何年か分の作品を書いていたのだ。会場に集まった文学青年達からどよめきが起きた物だった。五木さんの自信に満ちた凜とした姿は忘れられない。それが「青春の門」に繋がった。還暦を迎えて大学に入り「浄土真宗」を学び新しい五木さんの活躍の場を広げている。それは計算された生き方でなくその都度何かを真剣に研究しなくては居られない五木さんの言ってみれば使命というべきものかも知れない。 水上勉さんは白い顔にかかる髪の毛をかき上げかき上げ少し激情して話をした。まだ「雁の寺」を書いて直木賞を貰う前のことだった。熊本の水俣で猫が飛び回っていると言う話を聞いた。水上さんは水俣へ飛んだ。そこには本当に飛び跳ねる沢山の猫たちがいた。何かの原因で、この有明の海で何か大変なことが起きている・・・猫にこのような症状が出ていると言うことはやがて人間にも・・・不安と怒りの中「海の牙」と言う推理小説を書き上げた。その話の間中涙を流し髪をかき上げ体を震わせて訴える様に語った。それは作家ではなく一人の人間の真実を露呈していた。 今、この二人の作家は私の心に大きな位置を確立している。沢山の公演を聞いたけれど二人の話が聞けたと言うことが何よりの果報であると思っている。 果たして今の作家にそのような怒りの軌道があるのか、人間を蹂躙する物に対して果敢と戦う姿勢はあるのか。注文が来ない、本が売れない・・・それは当たり前というものなのだ。大衆の心が分からなくて書いていて売れるはずもない。代議士と同じなのである。幸せというものに、生き甲斐という物に、夢という物になんの答えを持たずに明かりを与えない作家が書いて売れるはずもなかろう。怒りを忘れている作家にはもう一度土と戦って欲しいと思う。土が生み出す力こそ今人間が学ばなくてはならぬ物のような気がする。 今、信州は佐久平の病院医師南木佳士さんの随筆小説に親しんでいるが読むと沢山の答えを返してくれる。歳のせいか読んで薬になる物を好むようである。 生きとし生けるものことごとくみんな平等に逝くと言う安心感を根底において優しさと真実をつづる作家である。
2011年01月26日
コメント(1)
-

小説家は随筆を書くな。
小説家は随筆を書くな 小説家は随筆を書くなと言った小説家がいることを知ったのは小説家の南木佳士さんの随筆を読んだ時だった。その中で芥川賞受賞パーティーの席で開高健さんから言われたと書いている。何でも随筆一作で短編の材料を使うのはもったいないというような意味のことを言われて戒めたという。南木佳士さんは随筆を沢山書かれているが書いている時に常に開高健さんの言葉がよみがえってきて何か悪いことをしているという罪悪感に襲われたらしい。芥川賞の選考委員と言えば受賞者にとって雲の上の人、その人から声をかけられ将来を思い戒めの言葉を貰ったのだから分かるような気がする。南木佳士さんはそのことを何遍も書いているのは自分には医者として誰も書かけない小説を書く自信があることを小説のテーマーからも文章からも伺えるのだ。確かに随筆を書くときに少し突っ込んで書き進めれば短編になる物がある。開高健さん言いたかったのは小説家は本来小説を書く事を本業とし、随筆家は随筆を書くことで立つと言うことであったろう。 南木佳士さんには今は克服したが鬱という病気持ちで短編長編となると神経が持たないという事で頼まれて短い随筆を書いているのだろう。 南木佳士さんは大変なことを書いていた。彼が「文学界」に応募したとき一次も入らなかったが編集者から電話がかかり異質な世界の方で作品に光る物があり温かさを感じたので話を聞きたかったという物だったと。本来応募作品についてはお答えしないと言うのが定説なのだがこれは応募要項違反であるのだ。それが縁で編集者に作品の書き方を教わったという。文章や構成を学んだというのだ。「文学界」の新人賞を受賞したときにも応募する間際まで編集者と作品を推敲したと書いている。カンボジア難民救済医療団の一員として飛行場から出発する一時間前まで額をつきあわせて直したと言うことも書いている。これは真剣に作品を書き未来を夢見て応募する人たちにとって不幸なことである。編集者がその才を見抜き新人賞を取らせたと言っても過言ではないのだ。文芸春秋社の大いなる過失であり賞の価値はなくなる。私が応募した賞でも最終に残っていなかった作品が受賞した例はあるから何かの画策があったというほかない。選考に付いての問い合わせには応じられないとあるが、私が作品について聞きたいと電話をすると編集長さんが出て親切丁寧に答えてくれました。私はそこで問い合わせに応じられないという但し書きはみんなから問い合わせが来ているのだという意味なのだと感じた。この理解は正解であった。新人を発掘したい、偉大な作家を誕生させたい、希有な小説を世の中に出したいこれは編集者の仕事であるから時に型破りをするらしかった。 世の文学青年や文学老年達が南木佳士さんの随筆を読んで文芸春秋社に抗議をしたというニースに出会っていないのでそんなことはなかったのだろう。この話はもう時効だからと南木佳士さんは書いたのかも知れない。 徳のある人の人との邂逅は時に大きな花を咲かす事がある。そんな経緯があって南木佳士さんも今花を咲かしているのだ。 信州の佐久平の七百床もある病院の勤務医である南木佳士さんは呼吸器の専門医として特に肺ガンの治療に携わり多くの患者を見送ったのだ。それが元でパニック症から鬱になられた。自己診断も出来ずに病院の精神医にかかり治療を始められた。その病床にあってこれでは駄目だ何かしなくてはこのままでは死ねないと小説を書き始めたという。育ちは山奥でなにもすることがないので父の本を取り足りして読んでいたらしい。彼は言う、芥川の小説で一番良いのは「秋」だと。子供の頃から今までその思いは変わらないらしい。芥川の「秋」を出すくらいの深い理解力それが元になっているらしい。呼吸器系の診察から外して貰い人間ドッグドクターとして勤務して快方に向かったという。それに加えてこのままでは死なぬと言う思いと書くという彼の使命が支えたのだろう。 自宅から自転車で五分の通勤を続けておらせれると言う。 信州佐久平の病院は医療研修医に評判が良く全国から来るという。 私のかかりつけの耳鼻科の医師に尋ねるとよく知っていた。 今、勤務の傍ら日本百名山に登るという計画を立てるほどに恢復しておられる。山に生まれ山で育つた彼は人間の宿命とも言える生まれたところへ帰るという回帰本能が芽生えたというのでしょうか。 小説家は随筆を書くなと言う開高健さんの言葉を今どのように感じておられるのか。彼の随筆を読むたびに思うのである。彼の随筆は読む薬として広く処方されている。読者の層は広く浮気をしないらしい。作者の優しさと真実が読む者に心地良い癒しを与えてくれる。心の持ちようでなんとでもなるものだと感じ取らせてくれる。 彼は言う、どんな患者でも何処が悪くても奇跡が起こり治るのだと言う人が殆どだという。死なないと思っているという。が・・・。 人間はどんなに金持ちでも貧しくても平等に死を迎えるのだと。「あの憎たらしい奴が死なないのに俺が死ぬのは不公平だ」と言うことはないのだ。
2011年01月25日
コメント(1)
-

しのびよる声 6
しのびよる声 6 房江は後部シートにもたれて大きな寝息を発てていた。 電話はO駅の駅長からだった。「逢沢さんのお宅でしょうか。私はO駅の駅長の木村と申しますが、加藤房江さんはお宅のお母さんでしょうか」 ゆっくりとした丁寧な言葉使いであった。「はい。左様でございます。もしかして母がそちらに・・・」 育子は途中から気ずいたのか声がうわずった。「迷子と言うのもなんなんですが、迷われまして構内をうろつかれて、いいえ、歩いておられまして、階段に躓かれまして。怪我のほうはただ脛を擦りむいたと言う程度でして。今、私の部屋で休んで頂いておるのでございますが、このままずぅとお預かりしておくと言うのも何でございますから」 受話器を持って育子はいらいらしていた。「ご迷惑をお掛けしております。そちらにすぐに伺いますのでどうか宜しくお願いいたします」 育子は受話器を置き深々と頭を垂れた。が、「JRも親切になったものだわ。だけどもっと迅速に言葉を発車出来ないものかしら」 と言って逢沢に同意を求めてきたのだった。 駆け付けると房江は駅長室のソファに横になり眠っていた。「今日のところは何も聞かないでそーとして置いてあげてください。よくあることですよ。生まれ育った所へ帰りたいと言う願望があって、こうして駅までは辿り着くのですけれど、どのように行っていいのか分からなくなってしまって。故郷を捨てて子供達と一緒に町に出てきたのはいいのですけれど、年を取って参りますとなじんだ生まれ故郷の空気が恋しくなりまして、ついふらふらと自分でも分からなくなって足がその方向へ向くらしいのですね。つまり子供の家出のようなものかも知れません。癖が付くのです。こうして駅長をやらせて頂いておりますと、何十人と言う御老人とお友達関係になりましてね。総て、このおばあちゃんのようにして最初は巡り合うのですけれど、何度も、いいえ何十回と言う巡り合いを重ねている御老人もおられましてね。なにか、なにかが、間違っているんでしょうか。昔はこれほどでもありませんでしたが・・・」 駅長の穏やかな言葉が逢沢の胸を打った。 饒舌であった房江がだんだんと寡黙になっていくのだった。終日部屋から出ようとせずに、カーテンを開けてルート2を見入っていたり、庭の秋桜を食入るように見つめていたりしていた。「お隣の安井さんのように草花とか、刺繍にとか、絵とかに関心を示してくれればいいんですけれどね」 育子はお隣の老夫婦の生き方に共感していたから、羨ましげに言った。「義母さんは、今までに土いじりをした事があるのだろうか」「学校で生徒たちと稲を植えてどのように成長するかの観察をしたはずだわ。それ位しかないと思う。母さんにそんな余裕はなかったはずだし」「五年前だったかな、安木のお爺ちゃんが倒れられたときに・・・。退院しても殆ど動けなかったお爺さんを辛抱強く看病し、専門家顔負けのリハビリーをして、今ではご自分で殆どのことが出来るまでに回復させている、おばぁちゃんの愛情の深さかなって思うのだょ」「本当だわ。五年間二つの身体を一つの身体のようにして・・・お隣のお爺ちゃんおばぁちゃんが元気でおられたら、母さんも・・・」「夫婦ってほんとうに素晴らしいと思うよ。おまえさんが言うように・・・。年月が別々の肉体と精神を一個の肉体と精神に変えていくのだって事、そして、一つの物に同化しょうと働きかけていく、融合反応を起こしながな、徐々に一体化していくんだね。お隣さんの姿を見ていたらそう感じてしまった。義務感とか権利とかという制約が全く感じられずに、自分が今何をなすべきを、しなくてはならないかを自然の内に行なっているて感じだったね。心が和み潤うね」 「ええ、母さんどうにかならないかしら。何かいい方法がないものかしら」「今度、義母さんを連れて県北のきみが行ったという学校へ行ってみようか。民話の採取も兼ねてだがね」 「いいかもしれないわ。まだ少し紅葉には早いけれど、あの近くにはいい湯が沢山あるし・・・」「あるかないかわからないけれど、義母さんが初めて奉職したという学校も見たいし、そこに、原因があるとしたら現場に立ってみようじゃないか」「私は、母さんのことを書いているけれど、現場に立って確かめたことがないのょ。昭和十八年にかあさんを引き戻して・・・」「あの時言えなかったことをどんどん語って貰うんだ。心と身体にしみ込んだ思いの丈を存分に吐き出してもらおう。そして、これから義母さんが生きていくために何が必要なのかを引き出せるように考えてみようじゃないか」「私、漸く書けるような気がしてきたの。母さんの青春と子供達との交友、戦時下においての教育とその背景がどのように影響を及ぼしたかという童話。母さんは子供の瞳はいつも輝いていなくてはいけないてよく言っていたわ。だから、「あの瞳の輝き永遠に」という題にするわ」「これで漸く義母さんの後を継げそうだね」「ええ、この作品は母さんと共著、母さんを引きずっても連れていくわ。当時の状態のなかに再び掘り込んで、自分がなした行為を反省させながながら心に怒りを呼び覚ましてあげるわ」 逢沢は育子の義母と同化した義憤が創作への原動力に変わっていくのを羨ましく思えた。そこには、作者の必然が波打っていたからだった。「いい作品にきっとなるよ。期待している。私のことなど忘れて戦時下へタイムスリップして子供達の瞳の輝きを書き上げてほしいんだ」「今、各国で沢山の子供達が食料危機や自然の淘汰の前で、また戦争で尊い命を落としているわ。どうしてその子等の命を救えないの、助け合おうとしないの。日本が敗戦して母さんと母親が何を一番にしたかは、進駐軍に子供達への学校給食に力を貸してほしいという嘆願だったと聞いたわ。その貧困を経験している日本がどうして一番になって手貸し手を差し伸べようとしないの」 育子は腹立たしく言葉をそこら中に播き散らした。「その通りじゃ。子供らは飢えに苦しみ、目だけをギョロギョロとさせ、痩せこけて、腹の辺りだけが異様に脹くらんどったものじゃ。それらを知っとるこの国の国民がせんで誰が出来るというのじゃ。今のこの国にはそれが出来る。嘗てアメリカ軍が施してくれた脱脂乳とコッペパン、それでどれだけの子供達が飢えから救われたか愚かなこの国の国民は忘れたのじゃろうか・・・」 房江の声が障子の外でした。「かあさん、何時からそこえ・・・」 育子は声を弾ませて言った。「雄吉さん、育子さん、私はボケようとしたがボケられなんだ。ボケられたらなんぼか楽じゃろうと考えたんじゃが・・・・。そんなことで私がして来たことが心の中から消えるものではないって事がわかったから・・・。育子さん、明日から忙しくなるぞ、私の腹にあることをこの手で掴み出してぶち播けるからな。耳も目も使い過ぎて多少くたびれとるが、頭ははっきりしとる。『あの瞳の輝き永遠に』とか言う物語を、この私の生きてきた道、よたよたしながら転んだり躓いたりして通った道を、育子さんと遡ろうかね」「ええ、母さん。本当の生きた言葉で綴りたいわ」「義母さん、どうぞ入ってください」 逢沢の周囲に立ち籠めていた空気が何だか暖かくなったように思えた。その一方で、房江の抑制が外れたのだろうか、これからが本当の意味でのボケの始まりになるのだろうか、ふと逢沢の心の隅に生まれた不安は否めなかった。それをそーと隠すように頬を少し緩めた。 終わり
2011年01月20日
コメント(0)
-

しのびよる声 5
しのびよる声 5「義母さんは、教職を退いても戦争反対、憲法擁護の立場を貫き、教え子を戦場に送ったと言う体験をもとに日教のOBとして活躍してこられたんだ。それが言ってみれば義母さんの心の支えでもあったのだ。その支えがなくなったら心の中は空っぽになり、生きる意味が、目的がなくなって何も考えなくなってしまうんだ。それが怖いのだ。義母さんはタイムスリップをして昭和十八年の冬の終わりに帰り、長太君に合い『行くな』と言いたいのだ。そして、そのことで辛かった苦るしかった過去を葬りたいと考えているのだろう。が・・・」「判ったわ。・・・一度だけかあさんと県北の学校へ行ったことがあるわ。そこはかあさんが女子師範を卒業して最初に赴任した学校だったのよ。あれは、私が教育学部を卒業して県職に受かり教師として出発が決まったときの春だったのよ。その時、かあさんは定年を三年繰り上げて、私と交替のように退いた年だったわ。墓参りがしたいと言うかあさんを軽四の助手席に乗せて川ぞいを北に向かったの。幾つも山を越え、雪解け水が岩に砕けて白く砕ける細流を眺めながら、その流れに冬芽をはじかせた木々の枝葉が覆いかぶさるように垂れているのを見ながら、山と小川の細い径を進んだわ。小さな集落が幾つもあって山裾の辺りに校舎を見付けた時には、なんだか胸が熱くなっていたの。かあさんは目をつむって何かに耐えているようだったわ。山の頂きには残雪が白く光っていたの。校庭は雑草が生え方題、校舎はセピア色に変わっていて荒れ朽ち、かあさんは二宮尊徳の像のそばにある大きな楠を見上げていたわ。手の入っていない楠は枝が折れ傷ついていても新芽を吹き上げようとしていたの。かあさんが教え子達とその木を囲んで写真に収まっているのを見たことがあったわ。長い髪を編んで背に垂らし、白いブラウスの胸の辺りが窮屈そうに張り、真っ黒な顔をした子供達がまちまちな服を着て写っていたの。可笑しかった、かあさんまるで聖職を絵に描いたような顔をしていたんだもの。玄関戸は板でふさがれていたけれど、校庭に面した一つの教室を硝子の割れ目からじっと見つめていたわ。かあさん、なにかに一所懸命耐えているようだった。そこから、少し山に入った共同墓地にかあさんの教え子が眠っている墓があったの。かあさんはその前に額づいて立ち上がろうとはしなかった。話かけていた。色々なことを様々なことを話していたんでしょう。それは長い間だったわ。 帰ってから、退職教職員連絡協議会に入って反戦反核憲法護権の運動、環境問題、教育の改革へと生きている証として動き回っていたのよ。たけど、あんな気性だから妥協が出来なくて意見の対立が・・・。それからのことは、あなたも知っていてるわよね。自室に閉じ籠もり考えてばかりいた。苛立ち焦っていた。周囲の何もかもに腹を立てしゃべりまくっていた・・・。思うように進展しない運動に・・・。何時の間にか身の置き場がなくなってしまったのね。政治の駆け引きに我慢がならなかったのね、きっと。それから、心を閉ざし、貝殻のように唇を結んだの。・・・あなたの言っていることは本当のことよ。民話だって、誰に語るのでもなく自分自身に言い聞かせるために語ったんだと思うの。かあさんも心の中で繰り返し繰り返し自分が犯した過ちを・・・」 いつしか育子は頬に幾つもの流れを作っていた。「その運動を辞めさせてはいけなかったんだよ。なにがあっても今おまえさんが言ったように語り部として、聞いてくれようがくれまいが思いを言葉に変えて叫ぶことだったんだょ。たとえ会を辞めたにせよ、一人でもいい、辻に立ってでもいい生きている証として語ることだったのだょ。義母さんには、義母さんには体験に基づいた行動が取れる、それを語れる唯一の言ってみれば生き証人なんだから」「かあさんを見ていると・・・だって、いつまでいつまでも過去の足枷に縛られているようで・・・」「わかるよ。だけど・・・」「可愛そうだった。もうこれ以上苦しんで欲しくなかった。穏やかな老後を迎えさせてあげたかった。かあさんの苦しみを私が受け継いであげたかったのよ」 育子は泣いていた。声が膝に落ちて畳に広がっていた。「それは、おまえさんだけでなく生きているみんなが考えなくてはならない事なんだ。そのためにも・・・」「かあさんに、語り部として・・・」「いや、そうは言っていない。考える切っ掛けを作る立場にあって欲しいと言うことなんだ」 逢沢と育子は房江の失踪のことを忘れたかのように議論に熱中していた。 風が出たのか庭の木立ちが揺れ微かに泣いていた。開け放たれた硝子窓にルート2を行く車のヘッドライトの明かりが大きな星の流れのように映っていた。その明りの中に落葉がまるで花びらのように舞っていた。 湿っぽい空気の中に乾いたベルの音が鳴り響いた。 育子は我に返って玄関へ急いだ。
2011年01月19日
コメント(1)
-

しのびよる声 4
しのびよる声 4 逢沢の住む高台の住宅地には十家が様々の造りをして建っていた。O市とK市のほぼ中間にあって、交通の便は良かった。それに最近出来た空港へも三十分もあれば行けた。逢沢がここを買った時には隣に平屋が一軒建っていて、老夫婦が慎ましい生活を営んでいた。ブロック塀を造らなくて、腰の辺りに成長した柘の木がアトランダムに植えられていて、後は梅、柿、密柑、枇杷、夏目、花梨の木が南に面した部屋への日差を遮らないように植えられていた。アロエ、毒だみ、忍辱、雪の下、せんぶりが植えられていると聞いた。それらは、みんな民間薬草として夫婦が焼酎に漬けたり、果実酒にしたり、乾かして煎じて飲んだりするのだと言うことだった。「私が民間薬草に興味を覚えたのは、会社を退職してからなんです。それまで何の趣味もなくこつこつとただ働くことしか能がなくて、会社を辞めてからはただ呆然として一日を過ごしていたのです。それから、胃の調子が悪くなり、血圧が上がり、神経痛が出て、今まで構ってやらなかった身体が次々と文句を言うようになりましてね。それと言うのも、働いているときには心が張り詰めていたのでしょう少々ことはほったらかしていても自然に治癒していたんですがね。やはり病は気からと言うのは本当なんですかね。なにもしなくなると・・・。それからですよ、防御より先手を打って病気にならないように気を付け始めたのは。私は手近に出来る薬草に興味を見付け、それらを自分で作り飲むようになったのです。今では老人会の皆様に薬草のことを話したりしているのです」 安木老人は血色の良い赤ら顔を逢沢に向けて言ったのだった。薬草のことは逢沢も多少知っていた。民話の中に出てくるからだった。安木老人一家はそのためにわざわざ住馴れた家を処分してここに引っ越して来たのだと言うことだった。 逢沢は、対面の山の中腹にある女子短大に週に四日講義をしに通っていた。その外の日は、民話の研究に没頭した。育子は毎日、主婦としての雑用が済むと庭に面した部屋で原稿用紙を広げ童話を書くのが日課になっていた。 房江を引き取っても、二人の日課に大きな変化は見られなかったのだが、時折房江の奇行にてんてこ舞をすることがあった。時折、「沖へ行くにはどう行けばええんですかのう」 と言って山を下りたが、嘗て住んでいた所へ行きじっと佇んでいるのだった。そこはもう広い道路の一部になっていたのだった。 一度、房江を留守番にして採話旅行に二人で出掛けたのだが帰って見ると、房江は台所の冷蔵庫の中のものを引っ張り出して総て腐らし、何も食べてなく空腹のためにひっくり返っていたのだった。「これでは二人で出掛けることも出来なくなるね」 と逢沢が言うと、「御免なさい。もう少し非度くなったら特別養護老人施設へ入って貰うことにしょうと思うの」育子は逢沢に気が引けるのか声を落として言った。言葉はフロァーにべったりとひっついたようだった。「馬鹿なことを言うなょ。そんなことを考える時間があったら、義母さんの心の中に引っ掛かっている問題を原稿に書けよ。私は義母さんのこと何とも思っていないし、出来ることがあったら何でもするから、娘として二度とそんな下らない言葉を口にしてはいけないんだから・・・。それに、義母さんとはおまえさんを貰いに行った時にはっきり約束をしたのだから。老後は面倒を見ますってね。約束をしたからって言うんじゃないんだ。私には年寄りがいないから、義母さんのことは実の母のように思えるから。おまえさんの母親なら私にも母親なんだからな」 逢沢は少しむっとして言った。逢沢は四十二の厄年で、育子は三十九の厄年であった。結婚して十五年が経とうとしていたが、子宝には恵まれず、今に至っていた。子供でもいれば、また変わった風景が見られたであろうが、ただ平穏と言う事が幸せと言う毎日を繰り返していたのだった。まあ、二人に取って、原稿を書き、本を出版することが子供を産み育てると言うことに置き換えることが出来るのかも知れないが。 「育子さん、私の下着はどこにしまいましたかのう」 と房江は、持ってきた箪笥をひっくり返しながら大きな声で言った。育子は丁度物語の一番大切な所を書いていたのだ。「下着なら、二番目の柚き出しの中にあるでしょう」 育子が少々ヒステリックに叫んだ「ああ、ありましたありました」 と言う房江の声が逢沢のところ迄響いて来た。 逢沢は書斎で民話の分類をしていた。窓の外を何かがすーうと通り過ぎたのを見たように思ったのだが、この数日根を詰めて少々疲れていたのではっきりと確認できなかった。外は木立ちが風に煽られて泣いていた。 その日、房江はまるで神隠しにあったように姿を消したのだった。 下着は、新品を出して付けたらしい。包装していた紙が散乱する部屋の中から見っかった。着物もよそ行きを着て出ていた。高台に住む住人の中には房江を見掛けた人はいなかった。 逢沢と育子は、房江がいなくなったことを知っても、今は道路になっている元住んでいたところに行ったくらいにしか考えなかった。それは房江の何時ものパターンであったからであった。切りがついたら迎えに行けばいい、そう逢沢も育子も忙しいと言うことを口実にして、直ちに行動に移る事を躊躇したのだった。一段落して逢沢が駆けつけてみるとそこには房江はいなかった。その辺りの人に尋ねてみても房江を見掛けた人はいなかった。戦前から一年前まで住んでいたのだからここは房江に取ってホームグランドのようなものだったが、北風に乗って飛び発った落ち葉のように消息がなくなったのだった。辺りはすっかり夜の帖をおろし、空には存在を誇示するライトアップが放たれ、路線をヘッドライトの帯が交錯しながら流れていた。 逢沢は呆然と立ちつくしていた。善後策を考える余裕がなかった。頭の中は全くの白紙のようになっていた。その白紙の上に点が落ちて動き始め線となり形を作り始めた。それは段々と形を作り一つの抽象画を描いた。その絵が左右に震動し止まると、それは房江の顔になっていた。角ばった顎の線がまさに房江のものだった。「いないんだ。どこを捜しても見つからないのだ。なにか、義母さんの部屋に手掛かりになるような物が残っていないか捜してくれないか」 逢沢は近くの公衆電話のボックスから育江に連絡を入れた。「何を慌てているの。いない所にじっといても仕方がないでしょう。こちらに帰って来て頂戴。相談しましょう」 育子の落ち着いた声が受話器の中から沸いてきた。それは、妙に乾いた声だった。「おまえさんは・・・」「言いたい事はわかるは。それは後で聞きますからとにかく帰ってください」 ボックスの硝子が曇って辺りの風景を遮りヘッドライトの明かりだけが僅かに突き抜けてきた。「あなたが帰ってくるまでにかあさんの知り合いの方達に連絡をして聞いてみたんだけど、心当たりがないって言っていたわ」 育子は心なしか落ち着いた声で言った。逢沢は自分が一人で空回りをしているような感覚を持った。「それより、義母さんの部屋に何か手掛かりになるようなものがあるのではないのか」 逢沢は電話で話した言葉を繰り返した。「それは・・・一応捜したんですけれど・・・」「気丈な人だから、何も目的がなくてと言うことは考えられないのだ」「すっかりぼけてしまって・・・」「何を言うのだ。言って良いことと悪い事があるんだぞ。義母さんは決してボケてはいないんだ。こちらのぼけたと思う気持ちが義母さんをボケさせてしまうってことがあるんだから」「有り難いわ、そんなに言ってくれて・・・」「義母さんが、住んでいた家を引き払うとき教え子への戒めを解こうとしていたが、まだ拘っているのは確かだ。義母さんは一生懸命にその自責から逃れようとしているのも確かだ。が、その戒めを解いたら何もなくなって今度は本当うにボケてしまうことになるかもしれないんだよ。それが心配なんだ」 逢沢は心療内科の友人がボケになるパタンを語ってくれたことを思い出して言った。安心と平穏、拘りと自責がボケの治療には必要だと言うことを聞いていた。つまり適当に喜怒哀楽を繰り返すことがボケを防ぐと言うことなのだ。だけど、使命に対する責任が明確に生きる上にある以上まずボケることはあり得ないと言う事だった。それは、未来に希望のない人には難しいことであろう。 友人はある高名な精神医の言葉として語ったのだった。ー老人性痴呆疾患つまりボケを中心とする精神症状が始まる前段階として『抑制が外れる』ことがある。つまり心理的ブレーキが外れて、我慢の力が低下して抑えつけていたものがどっと噴き出して思っていた通りしゃべり、思っていた通りの行動するようになる。 抑制が外れたときになにをさすべきか、取り巻く家庭の人達は一早く症状に気ずかなくてはならないと言うのだったー
2011年01月18日
コメント(0)
-

しのびよる声 3
しのびよる声 3 引っ越しが決まって房江を車に乗せようとすると、房江は観念していた心を翻し家の中に駆けり込んだのだった。そして、仏間であった部屋に入って床の間の壁が白くなった辺りをじっと凝視していたのだった。そこには白井家の先祖代々の位牌を並べた仏段があったところであった。無論、房江の夫の位牌も祭られていた。夫の死の時も涙を流すことを許さなかった房江の自責への戒めは、そのとき外されかかっていた。逢沢と育子が部屋を覗くと房江は肩を奮わせていたのだった。「おかあさん!」 育子が曇った声を房江の背に投げた。 そのとき房江は、「もう許されてもええじゃろう。もう許してもろうてもええじゃろう。・・・辛いわねぇ、泣きたいときにも泣けんなんて。あんときに、長太君の遺髪の入った骨箱を見たときに、私は誓ったんよ、決してこれからの人生でどんなに嬉しいことも、悲しいことでも涙を流さないって・・・。それが、それだけが、私にすることが出来た償いのように思えて・・・」 房江は畳に両手をついて泣きながら言った。「お母さん・・・もういいって。お母さんの今までの生き様は・・・なんの楽しみもない、喜びのない、ただ子供達の幸せを第一に考えての人生だったことは、この私が一番良く知っているわ。だからお母さん・・・」 育子は房江の肩に手を置いてしゃくりながら言った。「お前は、私になんの相談もなくさっさと教壇を下りてしもうてからに・・・。私の苦しい苦い体験を・・・いいや、子供等を誰が守ってくれると言うんね」「判っているってお母さん、私は私なりに子供達の幸せのためにペンを握る決心をしたんだもの。現場ではどうしても、言いたいことも言えないし、やりたいことも出来ないから。今の私なら自由に何でも言えるし書けるんだから・・・」「だけど、あの時だって、知識人達は自分の考えを見失って、女子師範しか出とらん年端もない私等に本当のことを教えてくれなんだし・・・」「お母さん、あの頃と今は違うわ」 育子は逢沢を見上げて言った。「いいや、違うように思えん。本当に子供等のためを思うとんなら、あんなせせこましい教育はせん筈じゃ。日本語もろくにしゃべれん書けん教育があるもんかね。あの時にあの頃に返っていくように思われて・・・」 房江は何もない床の間を涙を流しながら食い入るように見つめて言った。 逢沢は、房江の考えが確りしていて、間違っていないことに共感し感心したのだった。その通りなのだ、文章を書かせてもまとまりがなく漢字を知らな過ぎると言う現実があった。それも、高校を卒業した短大生がしてそうなのだ。一体何を十二年間勉強したのか疑わしい子が多いいのだ。「それは・・・」 育子は答える言葉を失っていた。育子に取っても房江の言い分を否定することは出来なかった。「日本語を知らんから本を読まん、読まんから日本語が判らん、そんな子供等が果たしておまえの本を読んでくれるんかのう」 房江は言葉でギューと育子の首を締めた。この場は房江の勝利であった。そんな房江を宥め透かして、逢沢の家に連れてくるのは一苦労でも二苦労でもあった。 連れてきても、房江と育子はその問題で話し合っていたが、しまいには口論となり限りない平行線の結果、房江の勝利に終わった。育子は逢沢に助勢を求めたが逢沢はそれに取り合わなかった。母と子の、言ってみれば忌憚のない言葉のやりとりが二人の接点のように思われたからであった。逢沢は、そんな経験は全くないから寧ろ羨ましいとさえ感じていたのだった。「二人に取って良い頭脳の鍛練になると思うがね」「ええそうでしょうとも」 育子は頬をふくらましてすねたのだった。「何でも言い合えるって良い事だょ。母子っていいなーあて思うよ」逢沢は言葉を宙に泳がせた。「あなた・・・」 育子の声が小さく落ちた。逢沢の事が頭を掠めたらしい。それからは、育子は何も言わなくなった。その拘りが房江から消えると同時に、ボケらしい兆候が始まったのだった。 夏の日、真昼の余熱がまだ漂い淀んでいる時、房江が突然に逢沢の家から姿を消した。 逢沢と育子は、慌てて走った。房江の嫌いな逢魔が時が近ずいていたからだ。気付くのが遅かったと逢沢は後悔した。二人で今度出版する「民話における男と女」のゲラ稿に朱を入れていたのだった。房江は自分の部屋で昼寝をしていたのを育子が確認していた。その時刻が三時頃であった。校正が一段落付いたので、お茶でもと台所へ立った時に房江の部屋を育子が覗き声を掛けようとしたが良く眠っていたので踵を返したのだった。それから四時間、二人は仕事に夢中になっていたのだった。房江のことが心配になって声を掛けると居なかったのだ。庭に飛びだし、家の周りを探し回った。育子は、「おかあさん!」 と息をきらして汗を拭き拭き房江の名を呼んだ。声が薄暮の空に吸い込まれていた。「どうしたのです?」 二人の慌ただしい姿に隣に住む安木老人が声を掛けた「おばあちゃんがいないのです」育子が口をとがらせて言葉を蹴飛ばしたのだった。「ああ、おばあちゃんなら、沖に行くのはどちらですかいのう、と言って山を下りましたよ」「何時のことでしょうか?」 育子が咳込んで問った。「あれは私が洗濯物をしまっていた時でしたから・・・。五時頃でしょうか」「育子、今日は何日だ」 逢沢は育子に日時を確認するように問った。「ああ、今日はあの家を解体する日・・・」「そうなんだ・・・」 逢沢は車庫へ走った。「皆様御心配をお掛けしまして、すいません」 と言いながら育子も逢沢の後を追った。 車のエンジンを掛けるのももどかしく、二人は山を下りたのだった。 房江は、逢沢と育子が考えていたように、綺麗になくなった家の後に呆然と立ち尽くしていたのだった。家の残材は一かけらもなかった。その跡に山土が敷き詰められ、整地されていた。房江は、仏間があった辺りに立ち尽くしていたのだった。房江の頬を沈みかけた太陽が赤く染めていた。正に房江の怖がる逢魔が時が来ようとしていた。房江の顔は謡曲の「藤戸」の老婆、怨念を秘めて踊る痩せ女の面のように見えた。「おかあさん」 育子が小さく言葉を落とした。「やめておこう。そっと見ていてあげよう」 逢沢は育子を制した。房江の長い影が山土の上に伸びていた。その影が時折風に吹かれるように揺れた。だが、影も段々ん暗やみに呑み込まれていった。それは、逢魔が時に人が消えていなくなると言う言い伝えを肯定しているようだった。
2011年01月17日
コメント(1)
-

しのびよる声 2
しのびよる声 2 育子の父は、五年前に亡くなっていた。酔っぱらって帰りに道端で寝込み車に轢かれたのだった。「どじなお人じゃ。死ぬときくらい真面目に死ねばええのに」 とその時、房江は仏壇に向かってぽっりと言ったのだった。その言葉が夫への最大の餞のものであろうと、逢沢は心を振るわせたのだった。帝展に入選をして将来を嘱望された一人の画家の末路が哀れに思えたのだった。この義父も戦争で道を踏み違えていた。戦前戦中には、多くの人達が望む望まないに関わらず戦火へ追いやられ人を殺す道具として使われたのだった。シベリアから帰って来た時には、空っぽの財布のようになっていたと聞いていた。義父はその時から生きる行為を忘れたような毎日を送ったと言うことだった。絵筆を二度と持つこともなかったと聞いたのだった。義父は酒の中で泳いでいたのだった。「この手は汚れている」 と真顔の時に一度だけ逢沢は聞いたことがあった。それが逢沢が義父と交わしたただ一つの会話だった。その言葉を残してまもなく亡くなったのだった。まるで重い心の傷を自らが解き放つような行為で。 房江は戦前戦中の教育を悔いながら戦後の教育をした人であった。「教え子を再び戦場にやらない」「教え子を飢えさせない」「お母さんの身体を大切にしょう」 そう標榜する「母と女教師の会」の活動を定年退職まで続けたのだった。気丈と言う言葉が房江に誂えたように嵌まっていたのだった。 その気性は、育子に引き継がれているのだった。母子喧嘩は凄まじいの一言だ。そばで聞いていて、逢沢が身の毛もよだっ事も屡あった。そして、羨ましいとも思った。忌憚なく言葉を機関銃のように撃ちあえるのもやはり母子の絆故であると思ったからだ。逢沢の父は戦争中、内地にあって生物化学兵器の研究を強いられ、戦後C級戦犯として捕らえられ巣鴨で栄養失調のため命尽きたのだった。だから、父とは喧嘩をしたことがなかったのだった。哀れと言ば哀れである父であった。だが、それは逢沢だけでなく総ての人が何らかの悲哀と犠牲を強いられたのが戦争であったのだ。 逢沢が育子と会ったのは、「モーツアルトを語る会」に出席した時に隣同士になり、互いが気になる存在になり自然と行動を共にするようになったのだった。その頃、逢沢は大学院生で、育子は教壇に立っていた。その頃から育子は教師と言う職業に疑問を感じていて、弱音を吐いたものだった。「なに、昔から人間は人間を教育出来ないって言うじぁないか。それは、逆に言えば出来るって事なんだよ。もう少し考えてみたら。それに、教師だってなにか他のことを勉強しなくては・・・」「例えば」「童話を書くとかさ」「それに決めた!」 育子はいとも簡単に目標を決めたのだった。 逢沢は大学に残り「民俗学」の研究をしようか、野に下りて大学の講師になろうかと迷ったのだった。結局は、自分の好きな民話の研究の時間が自由になる短大へ職を求め、育子と結婚したのだった。 房江は童謡唱歌が好きだった。教え子とバラックの校舎で歌った記憶が蘇るのか、調子の良いときには縁側や庭に出て歌っていた。特に「赤とんぼ」が好きなのか一日に何度も歌った。その「赤とんぼ」に思い出があることを逢沢が知ったのは初秋の風が流れようとしている頃だった。黄昏が麓を覆い始めたと言うのに房江は庭から引き上げようとしなかった事があった。何時もなら、逢魔時が怖いと早々に自分の部屋に引き上げて、夕餉を待つのが日課になっていた。その日、育子が夕食を知らせに行くと部屋は空っぽで仏壇に線香が炊かれていたのだった。カーテンを引いて庭を覗くと房江が沈み行く太陽に向かってじっと佇んでいるのが見えた。育子は窓を開けて房江に声を掛けようかと思ったが、嗚咽と共に聞こえてきたのが「赤とんぼ」だったのだった。秋桜の花影に無数の赤とんぼがオレンジ色に燃える太陽に向かって飛んでいくのが育子の網膜に焼き付いたのだった。それはまるで童話の插し絵のようであった。ここに引っ越してきて十年になろうとしているが、このような光景を見たことがなかった事に気が付いた。 育子は幼い頃、房江に手を引かれ共に歌った事があった。そのときの太陽はとてつもなく大きく見え、夕焼けの鮮やかさに感動した事が心に蘇ったのだ。房江の手は何故か冷たくざらざらしていた。房江の周囲に漂うのはチョークの匂いだった。風の流れが運んできた秋長魚を焼く匂いが幸せな家庭を連想させた。「育子、かあさんは人殺しかも知れん」 何を思ったか房江は言葉を石ころだらけの道に落とした。「どうしたん」と育子は房江を見上げて問った。「教え子を戦場に送った」 房江の目は遠く西の空を見つめていた。「戦死をして遺髪となって帰ってきた」 赤とんぼが明かりの中で黒く見えていた。「相談を受けたとき、行くなと言えなんだ」 赤とんぼが太陽の中に溶け込んで行った。「あの時、私に勇気があれば、馬鹿なことを考えないで。もっと自分の命を大切にしなさいと言えたのよ」 房江の影は小さく見えた。そのとき育子は房江が犯した罪がどんな事か理解するには早かったが、自らが教師となって、房江の悔恨が良く分かり、教師の立場の重要性を教えられたのだった。 あの日、九月二十三日がその子の命日だったのだ。房江は庭に佇み夕日に染まりながら歌った「赤とんぼ」は、戦地に送った子への鎮魂歌であったのだろうか。 その事を育子から聞いた時に、逢沢は房江の細い肩にのしかかっている負荷の重さを理解できたのだった。人生の入り組んだ露地を見たように思えた。それだけに房江はゆるがない信念を持つことが出来たのかも知れないとも思った。夫との死別にも涙を見せなかった房江の心はその死よりもっと大きく深い悲しみの体験があったことを逢沢は納得したのだった。戦時下とは言え信条と真実を合い入れない教育が多くの子供達を戦地に赴かせた事の責任を房江は感じ、教育の怖さを知ったとき、自責と悔恨が心をじわじわ侵食したに違いない。気が狂わんばかりに放逸し、空虚と寂寥が生きる気力を奪ったのではなかろうか。だが、そんな感傷と休養を世間は許し与えることはなかったのが現状であった。教育の現場に戻され、教科書に墨入をれることから始まった授業、その行為がまた房江を泣かせたのではあるまいか。だけど、房江は子供が好きでおのれを殺してもその子等の幸せを願う事で、過去の過ちを償おうとしたのではあるまいか。「赤とんぼ」を歌う房江の心の中を探り、当時を想像し逢沢は思いを巡らせたのだった。
2011年01月16日
コメント(1)
-

しのびよる声 1
しのびよる声 1「お母さん今、たった今、ご飯を食べたばかりなのよ」 毎朝、逢沢雄吉は、妻の育子の声で目覚めるのだった。育子の声が日増しに甲高くなっていくのを感じていた。井戸に首を突っ込み死んで行く人を呼び戻すと言う風習があったと聞いたことがあるがまさに育子の声はその時に発せられるであろうと思えるものの様だった。 育子の母の房江を引き取って一年になるが、何度も同じ事を言っていたと思ったら、物忘れがひどくなっり、それに伴い耳が遠くなっていった。最初の頃は耳が遠くなったので聞き取れなくなったことが原因で意思の疎通が旨くいかずに奇行を繰り返すのかと思っていたが、この春の初めの三月に入った日、廊下で日向ぼっこをしていた房江が尿を失禁した。縁側の板場は水びたしになり、着物の裾は黒く濡れていた。「まあまあ、お母さん、お茶をこぼして・・・」 と言った育子の声が途中で強ばって氷ついたのだった。房江の前には茶器らしいものはなかったのに気づいたのだった。それは見事なほどの洪水だった。房江は知らん顔をして庭の桜の木を見つめててたのだった。「桜の木はパァと咲いてパァと散るからええのう」 育子の慌てふためく姿が目に入らないのか、ぽっんと言葉を濡れた膝の上に落とした。庭の隅にある桜はまだ裸木に近く蕾のひとつも付けていなかった。 育子は、何も言う気力もなくなったのか茫然としてその場に座りこんだ。「きっと、外の暖かさに比べて縁側は寒かったんだろう」 逢沢は肩を落とした育子に言葉を投げて、「ねえ、そうだったのでしょう」 と房江に言った。「暖かい日には、おじいさんと庭の草をよう抜いたわな。おじいさんは葉だけを毟り取る。根を抜いても生える強い雑草じゃと言うのに。おじいさんは一本もよう抜かん人じゃった。雑草のように生きるより、桜の様に咲いて散るほうがええんかも知れんな」 そんな日があって、房江は少しずつ坂を下るようにボケのような症状が現われてきたのだった。 房江の長年暮らた家が都市計画にかかって立ち退き勧告を受けたのは引き取る半年前だった。これをいい機会として逢沢は育子と語らって房江を引き取ることにした。逢沢が育子を嫁に貰いたいと申し出たときの条件は老後を看とって欲しいと言うものだったからだ。その話を育子が房江にすると、「あの話は、雄吉さんの心をはかるために言ったまでのことでな、本気にする人がありますかな」 と房江は育子を軽くあしらったのだった。「それより、ここに道がつくことを止めるように言うてくれませんかな、お金なんかいらんから。私はお爺さんが残してくれたこの家には、お爺さんと暮らした思い出が沢山有りましてな、思い出と一緒に残りの人生を過ごしたいのですのじゃ」 房江の言う分は至極当たり前のことなのだが、行政が決めたからには、いずれ土地収用法の適用に合わないとも限らない、困ったものだと逢沢は房江の心を思い遣り胸を痛めたものだった。 薄暗い仏間に柱と壁の隙間から一条の光線が差し込んでいて、仏壇の前に黄色い扇状の日溜まりをつくっていた。それは、育子の亡父が黄泉へ空間移動をするステーシュンのように見えたのだった。あまり広くない庭には、軒先に届くどんぐりの木が一本と背丈くらいの千両万両があった。それに楠と檜が成木していた。それだけでも南に面した部屋の日差しを遮るのに、一年前に十二階建てのマンションが建ち、小漏れ日のように届いていた陽を奪ったのだった。その時から、逢沢はそろそろ房江を引き取ろうかなと考えていたのだった。市から都市計画で房江の住む家が、新しい道路の予定地になっている言う報せが入った時には天の啓示かとも思えたのだった。 それまでは、房江は高台にある娘の家に時折来ていは、「良くもまあこんなところに住むわなえ。便利な家があるというのに」 と軽口を叩いては育子の顰蹙を買ったものだった。が、その事件が持ち挙がってからというもの、房江は家を出ようとはしなくなり、「体が怠いし、足が重たいしな・・・」 と弱音を吐くようになったのだった。 房江が訪ねてこなくなると心配になり、頻繁に電話のダイヤルを回す育子の姿があったのだった。口では嫌味の応酬をしていても根の部分ではしっかり結ばれている母と娘の絵図を逢沢はみていて心が和むのたった。、 逢沢も育子も十年前に買った高台の家で終日机に向かうか、採話旅行で集めた民話を分類し、カセットを回しながら原稿に起こすと言う作業をしていたから、房江が来ても一人ぽっちにすることもなく面倒が見られるのだった。 育子は房江の後を継ぎ女教師になったが、 「私には、可愛い子供達に序列を付けることは出来ないわ」と言ってさっさと辞め、童話の研究を始め、童話作家になっていた。少し悩んだあと踏切り良く割り切れたのは二人の間に子供がいないかったからだろうかと逢沢は考えたものだった。育子が眉を曇らせなながら答案用紙に赤ペンを走らせる育子の顔は、蛍光灯の明かりの下でまるで能の痩せ女の表情だったのだ。「私は、つくづく思うの。子供達の頭と心に理解させるようには教えることはできないって。つらいわ、どうすればいいと思う」と、育子は湿った言葉を逢沢の方へ鉛筆を転ばすように問ったのだった。「現今の教育のカリキュラムでは、置いてきぼりになる子がいても仕方がないのではないか。そのように教育しているんだから」「それが嫌なのよ。それは教育ではないわ。なぜ、なぜなの、どうして理解していない子がいるのに教科書のページを捲らなくてはならないのよ」「辞めたいのか」「ええ、辞めたいわ」「逃げるのかい」「逃げたいわ」「じぁや、そうしたらいい」「ええ、そうするわ」「何の解決にもならんぞ」「別の方法を考えるわ」「別の方法をねえ」 「あるでしょう、別になにかが」「うん、あるだろう」 逢沢は、だんだんと人相の悪くなっていく育子の顔を見るのが辛くなり、育子の行動に任せたのだった。現金なもので教師を降りた育子は溌剌とした身体と精神をと取り戻して年相応の容姿になったのだった。逢沢は近くの短大で日本文学を教えながら、民話の研究をしていた。原稿を書かないときには育子は逢沢の手伝いをした。民話の本を逢沢と育子の共著で何冊か出版していた。それが二人の子供のようなものであった。
2011年01月15日
コメント(0)
-

小さな善意の広がりが・・・。
倉敷も寒い日が続いています。歳とともに寒さはこたえます。私が少年のころにはもっと寒かったと思います。学校への行き来に川には氷が張っていましたし、麦畑には霜柱が白く土をこごらせていましたから。洗濯物も直ぐに凍っていました。晴れの國岡山のことです。 だけどストーブのない教室で鼻をすすり上げながら袖口で拭き、霜焼けやアカギレの手を擦りあわせながら息を吹きかけて勉強をしていたのです。 その頃に比べれはまだ暖かいと思います。 そんな生活をしていた人たちは高度成長社会の担い手になり頑張ったのです。団塊の世代の人たちです。 だけど今その苦しさを忘れているように思います。耐えて頑張ったのだから退職金と年金で悠々と暮らしている、それで本当にいいのでしょうか。みんな貧しかったから今は何の心配もなく過ごしているだけでいいのでしょうか。 私がそんなことを言えた柄ではないことを十分に承知しています。遊び人を通して過ごしたので退職金も年金などもありません。意志で本能のままに生きたのだからそれでいいのです。社会に参画してなくて、日本の成長に貢献していないのですから今の境遇は当たり前だと思っています。当たり前ですが税金はきちんと払ってきました。私は金銭より精神的な生活を本能として選んだのですから現状に満足しています。編集者として文学仲間と話し何人かのプロの作家を世に出し、演劇を通し沢山の青年達と話し舞台を創り、多くの少年少女とともに演劇を創ってきましたから、私の人生は充実していました。 金には縁がなかったけれど素晴らしい人たちと会い話す事が出来ました。公演の上がりのすべてを義援金として拠出しました。私の劇団の公演は何時もとんとんなので毎回という訳にはいきませんでした。それでもしたいという意志はありました。 今、世の中には、岡山では「桃太郎」とか「かっぱ」とかと言う名で品物を届ける人たちがいるのです。「伊達直人」現象の広がりなのです。ものを送ると言うことを善意と受け止めたい。が、何にも隠れてやることはない思うのです。堂々と差し出すべきではないかと思うのです。ネズミ小僧ではあるまいしと思うのです。 その人達は、昔貧しい中勉強した団塊世代の方であればいいなと思うのです。そう思いたいのです。 それなりの思いがその行為に走らせるのだと思いたいのです。 大きな車に一人乗って当てもなく走っているのは寂しすぎますから。 優しさが通じない世の中かもしれませんがその気持ちがあればまだまだ日本は暗くありませんから。金に執着する生き方からもう脱皮しなくてはならないときなのだと思います。 団塊の世代の方達は、海外旅行にうつつを抜かしている場合ではなくて、子供や孫達の為に金がなくても生きられる精神を後ろ姿で見せるときなのではありますまいかと思うのです。 私は子や孫に何も残せませんから、せめて生きて感じた言葉を残したいと思っています。金のないひがみではありません。 なぜに私が遊び人を通したのかそのことを一言の言葉にしてと思っています。
2011年01月12日
コメント(1)
-

星に願いを 5
星に願いを 5 ある年の冬のことでした。 大きな風と、はげしい雨が降ったのです。 ラルは小屋で震えていました。羊たちの事が気になっていたのですが、外には出ることが出来なかったのです。 ラルは一睡もしなくて祈っていました。「嵐はラルに試練を与え、ラルがどのように立ち向かってくるかを試そうとしているのじゃ。何が起こっても乗り越えなくてはならんのじゃ。人間にはその力があたえられておる」 おじいさんはそう言いました。 東の空が明るくなるころには風も雨も小さくなっていました。 ラルが羊小屋に行くと羊たちは寄り添うようにして固まっていました。 よく見ると羊たちは全部死んでいました。 それを見たラルは腰が抜けたようにその場に崩れおちました。 ラルは空を見上げました。 羊たちが次々と空に登って消えていくのが見えました。 ラルの涙があふれる目にはそのように映ったのです。「ラル、今日は羊たちの葬式じゃ」 おじいさんがラルの後ろに立って言いました。おじいさんは歯を食いしばっていました。 ラルとおじいさんはもう山に帰ってくることはありませんでした。 その後、ラルがどのように生きたかは分かりませんでした。 おわり
2011年01月08日
コメント(2)
-
新しい一年の始まりです。
物を書くと言うことは恥をかくことなのです。嘘を真実に見せることなのです。虚構で人の心を揺さぶることなのです。たいした知識の蓄積もなく半端な物で書き上げるのです。こうなりたいと言う願望を書き連ねるのです。でも、それが悪いことなのでしょうか。美しいと書くことが。見にくいと書くことが。人は真実の醜さを好みません。お話をほしがります。自分に出来ない夢を見たがります。ささやかだけれどその手伝いをしたいのです。手をさしのべてこういうのです。人間はまだ捨てたもんじゃないと。きっと望む楽園があると・・・。愛してもないのに、愛していると。平和のために嘘を言うのです。嘘がわずかの間しか有効でないことを知っていながら言うのです。寂しい事をあえてするのです。人間てそんな愚かしい事を平気でするのです。一人になって涙を流すのです。明日流す涙を今日流すのです。
2011年01月04日
コメント(1)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0930 勝つための準備
- (2025-11-16 00:00:12)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- やっと入れた楽天ブログ!これからの…
- (2025-11-09 16:30:43)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『異世界に召喚された(偽)聖女の私は…
- (2025-11-16 00:00:08)
-