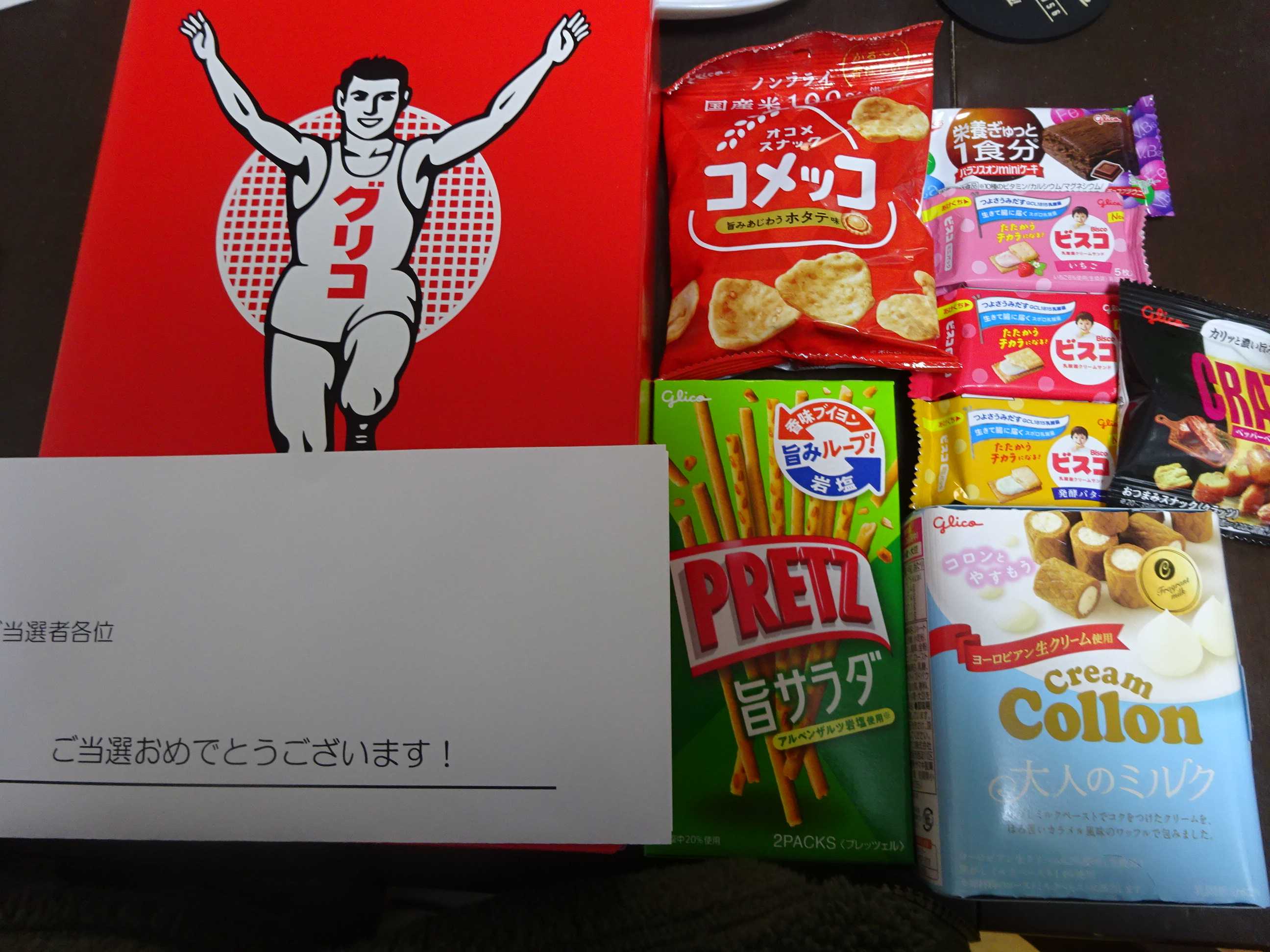2019年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

千葉マリンスタジアム~阪神ファンで黄色に染まる交流戦
横浜スタジアムに始まり、西武ドーム、東京ドーム、神宮球場と関東各地の球場を巡って来たが、今年は千葉ロッテマリーンズとの交流戦試合を千葉マリンスタジアムでやるので、意を決して幕張まで出張することになった。八王子千人同心の闊歩する多摩の奥地から、遥か佐倉藩領にほど近い海浜幕張まで、ほとんど旅行みたいなもんで、鉄ヲタとして京葉線の様子とかもいろいろ見ておきたかった。こんな訳で前日の夜はなかなか寝付けない。相変わらず子供みたいなもんだ。去る6月5日(水)~いよいよ現地へ向けて出発!東京駅乗り換えで京葉線に乗車。わざわざ窓際に立って車窓を眺める。湾岸に林立するタワマン、TDLやら物流センター、港湾施設や巨大なイオンモール幕張とか。海浜幕張駅なんか初めて降りたが、何かと乗降客が多い。明らかに阪神ファンと分かる人間の何と多いことか。海浜幕張駅から球場までそれなりに距離があるが、観光を兼ねてだから乗合自動車に乗らず歩いてみた。この界隈は全てが人工的である。地面から人工埋立地なのだから仕方無いが、定規で線を引いて作ったような街並みは、この年齢になって改めて見返してみると、もはや先進国でなく東南アジアの発展途上国にありがちだと感じるようになっている。競って高層ビルを建てるという発想がね、もうダサいんじゃない?丸を懲らしめろ!と思うのは広島ファンだけじゃない?マリーンズの交流戦ポスターが相手チームに挑戦的であると話題だ。パリーグ球団が何を言おうが気にもならんが、巨人だけはしっかりやっつけてもらいたい。隣島のカープ女子A子さんは、丸が凡退する度にざまーみろと大騒ぎしているらしい。丸のユニなんぞせいぜいメルカリ行きだろな。マリーンズストアミュージアム店にてさて、生暖かい湿った浜風を感じつつ球場前に着いた。球場の横にあるマリーンズのグッズショップに行ってみる。こういう所に入るのも全然抵抗感が無いというのが自分でも可笑しい。東京ドームなんか、敷地に入っただけで「ドイツ軍がソ連領に足を踏み入れた時の気持ちが分かる」みたいな(笑)。仕事の前任者がロッテファンなので、マリンスタジアムはいい球場ですよぉーぜひ愉しんで下さいと激励まで受けている。ヘンな話だが、パリーグのチームに敵愾心など微塵も無いから、東京ドームみたいに討ち入りという感覚が無い。店内の雰囲気が不思議なくらい違和感無いのは、マリーンズも阪神と同じタテジマだから?中には交流戦を記念した阪神とのコラボグッズまである。お店の中に資料館みたいな展示があって、オリオンズ時代の優勝旗や歴代ユニフォームとか飾ってあった。ここで前任者へのお土産のお菓子などを探す。ロッテなのだから、ロッテのお菓子ばっかりあるのかと思ってたら、なぜかロッテのお菓子が無い。クオリティー的に良さげな、とあるお菓子を買ったが、製造者は聞いたことも無い会社。後で前任者に「ロッテのお菓子が無いと意味無いじゃんかー」と言ったら、「それの何が不思議なの?」という表情。とりあえずお土産のお菓子をゲット。猫ピッチャーを貸してくれたY子さんにもあげなきゃね。ちなみにレジ係のお姉さんはみんな水兵の格好してて何とも可愛らしい。お店の細部に渡る作り込みセンスもなかなか。試合を前に小腹も減ったから、迷わずロッテリアに入ってフィッシュフライバーガーみたいなのを食べた。ロッテリアに入ったのは、札幌在住時代に地下鉄大通駅の店に入ったきり、久しぶりのことだ。これも前任者に言わせると「マリンスタジアムの愉しみ方分かってないッスよーやっぱ千葉県産の食べ物集めたフードコート千葉とかに行かなきゃ」とのことで、やたらと「ロッテ」に否定的だから可笑しくてしょうがない。パリーグの球団は、実業団野球みたいにとにかく親会社ありきのイメージでいたのだが、それは大きな間違いだったようだ。黄昏時の美しい夕陽を眺めつつ、いよいよスタジアムの観客席に入った。続きのお話はまた今度・・。
2019.06.24
-

昼食は阪神百貨店のモロゾフで、夕食は551の豚まん弁当で決まり!
神鉄粟生線小野駅から準急新開地行に乗って、そこから神戸高速を乗り継いで三宮に出る。すっかり日も暮れちまい、さんちかで夕食&職場へのお土産購入などでいい時間になってしまった。神戸市中心部の観光をする時間も無かったが、今回の旅行は神鉄粟生線に乗ることが大きな目標だったから、まあよし。今度来る時は神戸阪急ビルが完成した後になると思う。大阪への帰りの電車は、神戸三宮駅から阪神電車で大阪難波まで。阪神といえども実際に乗ったのは近鉄のクロスシート車だったので、帰りも少しだけ旅気分を満喫した。高架化が進む阪神本線、尼崎での梅田行電車との接続、そして旧西大阪線の風景、留置線に停車中の近鉄特急・・・いろいろ見させていただいて満足。平成最後の4月30日は、阪急の新型京とれいん「雅楽」に記念乗車。大型連休とあって、早くから並んでも座れたのは嫁さんだけだったが、車内で坪庭も見れた。お客さんがみんな楽しそうなので、株主として少しホッとする。関西私鉄の世界は競争が厳しい。京阪のプレミアムカーが予想外に好評なので、京とれいんの一編成くらいで対抗できるか不安だが、阪急京都線の特急は有料座席が必要なほどの乗車時間ではないし、梅田から座って乗れる可能性を考えると、敢えて指定席車を付ける必要は無いのだろう。この日の詳しい写真は→こちらからどうぞ。最後の愉しみは、梅田の百貨店巡り令和元年初日は、大阪から帰る日となった。親戚の皆さんに挨拶を終えて、最後は梅田の阪神百貨店や阪急百貨店で買い物とか食事とか。銀座の百貨店なんかわざわざ行く気もないけど、阪神百貨店と阪急百貨店は行くだけで面白い。阪神百貨店は、片側半分が既に完成している。全部完成したら壮観だろうなと期待も膨らむ。タイガースグッズを物色し、そしてモロゾフで昼食。新しいだけあって、全てがキラキラしている。サンドイッチとパフェのセットがお得感あったので、二人で同じものを食べる。このサンドイッチが美味い!こんな美味いサンドイッチ久しぶりに食べた。食塩も美味くて(笑)。パフェと共に出て来たコーヒーをマジマジと見つめる。なぜここのコーヒーは細かい泡が残っているのか。ドリップコーヒーを自分でやっているけど、さすがにカップに注ぐ際は泡が残っていないので、これはちょっと不思議だった。ちなみにこのお店は、となりの阪急百貨店やJR大阪駅がよく見える場所で、百貨店の建物も微妙に展望が効く構造になっているようだ。続いて阪急百貨店に移動する。コンコースを飾る宝塚の大きな広告を目にしたとき、昨年見に行ったエリザベートのことを思い出させた。あれは本当に素晴らしい思い出となっている。阪急百貨店の地下でコーヒー豆(阪急百貨店限定大阪ブレンド!)とか、新幹線で食べる弁当(551の豚まん弁当!)を買っておいた。この選択は正解だった。新大阪駅の混雑が尋常ではなく、売店のレジは長蛇の列を成していたのだ。全日程を終え、新大阪駅から東海道新幹線グリーン車に乗り込む。これから東京まで四時間の長旅である(?)。思えば行きはサンライズ出雲で岡山まで行って、九州新幹線車両に乗って広島まで行って帰って来て、神戸電鉄やら阪神やら阪急やら、そしてシメはこだま号で東京へ帰るという、怒涛の日々だった。付き合ってくれた嫁さんには改めて感謝。
2019.06.16
-

神鉄粟生線の旅~小野市そろばん博物館にて~そろばんと爪楊枝の関係性について考察したところで永遠に答えが出ない気もする
引き続き小野市そろばん博物館にて。時代を感じさせる古いそろばんの数々。と云うか、衝立に付属しているそろばんが理解し難い。常にご破算の状態となっているため、永久に計算が不可能なのだ。まぁ国際宇宙ステーションに持って行けば、無重力なのでご破算になることは無い。つまり、無重力状態の宇宙空間でのみ使えるそろばんと云うことになる。作った本人はちっとも意識していないのに、後で考えたら変にスケールがデカく感じることって結構あるものだ。続いて、様々な機能を持ったそろばんのコーナー。電卓付そろばんは、既に博物館級の一品になりつつある。そろばんは長きに亘ってビジネスパーソンの大事なアイテムだった。急に電卓が普及したところで、これまで愛用していた物を手放すことに不安を抱く人々が数多く存在したのである。電卓も押し間違いが起きては元も子もない。だからってそろばんで検算するのもある意味凄い。続いてこちらは「大きなそろばん」のコーナー。特大のそろばんは長さ3メートル近くある。国家予算も桁が違うであろう時代において、何を計算さすねんと云う感じ。ソ連の算盤コーナーも微妙である。なぜ表示がロシアではなく、もうこの世には存在しないソ連なのだろうか。これがかえって憶測を呼ぶ。旧ソ連時代、電卓の普及が西側諸国に追いつかず、代わりに近隣諸国の算盤を真似して使うしか無かったと云う説。あるいはロシアには元々算盤が存在したのだが、この博物館が出来たのが旧ソ連があった時代で、ソ連崩壊後もプレートが交換されることもなく今日に至ると云う説。以上二つの説が考えられる・・。人類は、計算していると背中が痒くなる生き物である(?)日中交流による中国そろばんの逸品特別展なるコーナーもあった。両国の国旗を担いでいるパンダが何とも不自然で不気味である。と云う拙者も「パンダ描け!」といきなり云われたら結構微妙になってしまうと思う。中国と云えば、普通それ食わねーだろって物を食べたり、そんなことを実践する必要が果たしてあるのかって事を敢えてやるような国だから、そろばん一つとっても、あっと驚くような珍品なんだろうと期待したところ、驚くと云うより、さっぱり意味分かんねーと云う感じ。この細長い棒みたいな品は、「そろばん付き孫の手」と云うやつ。なぜその組み合わせに至ったのかよう分からん!さらに表示板をよく見ると、「つまようじ入れが付いている」との説明が。はて?と思った。中国のことを笑ってられない。さっき見た日本製そろばんの展示を見直してみた。すると、「そろばん付きつまようじ入れ」と云う製品があるではないか!そろばんとつまようじ、何か切っても切れない縁があるのかと思案を巡らせてみたが、さっぱり思いつかない。拙者が意地悪な国語の先生だったら、「算盤と爪楊枝、この二つの品物の関係性について、諸君の思うところを自由に述べよ」と云う作文問題出したりして。小野市当局も、ここまで面白いネタを秘めていながら、なんかこう活かされていない現実を改められないのであろうか。観光客は嫁さん含めてたった二人~再び無人の商店街を通って神鉄小野駅へ戻ることにした。 旅の続きはまた次の機会に・・・連休中のネタがまだ書き終わらない。
2019.06.09
-

神鉄粟生線の旅~小野駅を降りてそろばん博物館へ
樫山駅徒歩8分にある喫茶店でアフタヌーンティーセットを食した後、次に来る普通小野行に乗った。先ほどは昭和の復刻塗装車であったが、今度の電車は最新型の6500系。田圃や畑が広がる粟生線に似合わぬ、超都会的なデザインだ。車内は誰が見ても阪急電車としか思えない意匠で、神戸電鉄が阪急系の会社であることを改めて印象付ける雰囲気である。電車は、やはり田圃の中をトコトコ走ること10分、終点小野駅に着いた。ここで乗客のほぼ全員が改札口へ向かう。この先はさらに運転本数が激減し、粟生駅に発着するJRの電車に接続するタイミングしか運転しない。粟生線の乗客が減るにつれて、最小限度の運転しか行えなくなった訳である。それでもこのような阪急電車を思わせる美しい電車が走っているだけ感激する。やっぱり縫いぐるみが運転席に鎮座しているし、もう神戸電鉄最高!駅名表示も阪急に類似したデザインだ。葉多はそのまま「ハタ」でいいらしい。関西は思わず首をひねるような駅名が多い。北海道生まれの嫁さんは粟生を「あお」と読めなかった。ビジュアル的に「くり?」と反応してしまうのだ。階段を上がって改札口を出たが、ここも無人駅である。それなのに、何と小野駅は立派な駅ビルがあるのだ。拙者は東京在住だが、最寄駅の駅舎とは比較にならないほど立派な駅である。人っ子一人いない、まるで人類滅亡後の地球小野駅を降りたのは理由があって、商工会議所内のそろばん博物館を見たかったからである。スマホで検索すると、商店街を通り抜けた先に、市役所や商工会議所があることが分かった。その通り進むことにする。あいにく雨も強く降って来た。商店街のアーケードがあれば助かる、と思って商店街に入口まで進んで、拙者は思わず息を呑んだ。なぜって、誰もいないからだ。アーケードは電灯も消えたまま。ほとんどの建物はシャッターが閉まっている。 全国的に商店街が寂れつつあるのは承知していたが、ここまでの寂れっぷりはどうだろう。シャッター通りなどという甘いもんじゃない。ほとんど廃墟としか言いようがない雰囲気。言葉を替えれば、人類滅亡後の地球みたいだ。 でも歩いているうちに、営業している店も見つけた。たばこ屋さん。中でおっちゃんとおばちゃんが阪神戦の中継を見ていた。恐らくサンテレビであろうか。1件、非常に立派な和菓子屋さんがあって、そこだけ明るくてキラキラ光っていた。いつお客さんがやって来るのだろうか。途中に、戦国武将と姫君の「顔の部分だけくりぬいて顔入れて記念写真撮るやつ」があった。ここは昔、城下町だったことは承知している。商店街をどうにか活性化しようと努力してみたものの、徒労に終わったと思えるところが痛々しい。廃墟と化した建物をよく見てみると、明治大正あたりからあったと思われる、古い商家の建物が時々見られた。歴史的な建物なのに、活用は出来ないのだろうか。むしろ暗くなるだけのアーケードなんか無くていいような気がする。あのような古民家を引き立てるのは、昭和30年代か40年代のアーケードよりも、青い空や赤い夕焼け空ではないのか。まぁ今現在はどしゃぶりの雨なので、アーケードの存在は有り難いのだが。商店街にこだわることなく、まず歴史的な景観を守ることを前提に、住宅への転用も容認し、とにかく空き家率を上がらないようにすれば・・・などと部外者が勝手なことを申し上げても仕方ないのであるが。 長い長い商店街を通り抜け、ようやく商工会議所があるであろう地点まで来た。雨はますます強く降っている。目の前の光景を見て、嫁と顔を見合わせた。なんか水没してへん? 駐車場らしき所へ来たら、大丈夫ここは水没してない。祝日のためか、駐車場もクルマが一台も無い。大きなそろばんのモニュメントがあった。「そろばんのまち 播州小野」~ロマンは感じるが少々苦しい。そろばんの良さは一部で見直されていることは承知しているが、もう主役にはなれない。電卓すら、パソコンのエクセルやスマホに仕事を奪われつつあるのだ。時代の流れが速過ぎる。 さて、我々は商工会議所の建物に入った。別に玄関から水浸しになっている訳でなく、結局あの光景は「そういう設計だった」としか云いようがない。で、玄関は真っ暗でトイレに入ったらそこも真っ暗。悪いけど電気つけさしてもらった。そろばん博物館なる部屋はかろうじて灯りが灯っていて、職員とみられる人が一人でパソコンを前にカタカタ仕事をしている。もちろん客は誰もいない。というか、さっきから観光客は拙者と嫁さんの二人だけなのだ。 一応、撮影の許可をもらって展示室へ入った。出迎えてくれたのは、そろばんを重ね合わせて作ったと思われる御神輿とお城。お城は小野藩の城郭ではなく、姫路城であるのが微妙なところ。そろばん玉五万個を使っており、二十三桁そろばんに換算すると四百三十四丁分になるのだという。さすがそろばん博物館だけあって、いちいち計算しているのである。そして、奥の展示室は大小様々なそろばんが並べてあった。案外突っ込みどころのある展示品の数々については、また次の機会で。
2019.06.06
全4件 (4件中 1-4件目)
1