2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
五臓のつかれ
今日は、忙しゅうございます。いろいろカキコにいきたいんですけど、やることいっぱいで。今日も山岡氏を書くつもりでしたが時間がないので吉川英治・新書太閤記に出てきた言葉を紹介します。明智光秀が本能寺の変まえに曲直瀬道三に言われた言葉です。************************************************肝・心・脾・肺・腎の五臓は、五志・五気・五声にあらわれ、色にも出で、肝を病めば涙多く、心をやぶれば悶々(もんもん)としてものに恐れ、脾をわずらえば事々に怒りを生じやすく、肺の虚するときは憂悶(ゆうもん)を抱いて、これを解す力を失う。また、腎弱まればよく喜び即座にまた悲しむ。************************************************わたしはこれを事務所のデスクにはってます。どれかあてはまるのあります?ほ~っておくとたいへんなことになりますよ~っ。
2006年01月31日
コメント(4)
-
-霞を食うて丸々と肥え、腹では泣いても顔では笑う-
私のブログもなんだかにぎやかになってきてすごく楽しくなってきました。やっぱり続けてみるのが一番のようですね。最近は、ブログの更新するためにまた本を読み漁っています。で、また教育ものですが、書いてみたいと思います。昨日の続きで竹千代が武道稽古で奥山伝心から大将の心得を教えられる場面です。************************************************(短気で困る....)と思うと、きびしい反省を見せたり、怒るかと思うと少しも怒らなかったり....ついこの間も、庵の向こうの菜畑で蝶を追いかけている竹千代を、今川家の家士の子供たちが大ぜい寄ってたかって罵っていた。「....三河のやどなし、性度なし、菜っ葉にそまっておお臭い」声をそろえてはやし立てるのをまるで相手にしなかった。とぼけた表情で振り返って、ニヤリと笑って見せるだけ。それは堪忍(かんにん)している顔ではなく、本当の阿呆に見えた。雪斎長老は見どころありといわれるし、奥山伝心はおもしろいという。が、祖母の身にしてみると何もかもが物足りない。「よろしい。今度は野駆けじゃ」と、突然伝心が立ち上がった。どうやら打ち込み五百回の練習は終わったらしい。「竹千代の体は胴が長すぎる。人間は自分の体くらい自分で作らねば相成らぬ。ケチな体にはケチな根性しか宿らぬもの。さあついて来なされ安部川べりまでじゃ」伝心は竹千代に続いて駆け出そうとするお側の少年たちを手で制して、自分ひとりで竹千代の後から門を出た。門を出ると何の遠慮もなくさっさと竹千代を追い抜いて、「安部川の味方あやうし、急げや急げ」あやしい抑揚(よくよう)を声につけて風のように駆けてゆく。竹千代はこれも慣れたものだった。相手がどのように早く走ろうと自分自身の歩速はみださない。もし途中で落伍したりへばったりすると、「....それが大将か」と、罵られるのをよく知っている。「遅いのう、もうちっと速く走れぬか」「.....」「それでは味方は皆殺しになるであろう。股(もも)を高く上げて、大きく手を振って、それっ、もちっと速く」ぴゅっと駆け抜けては、そこで足踏みしながら、伝心はあれこれと竹千代にからかいかける。だか、竹千代はへの字に口を結んだままで、伝心の顔も見ようとしないのである。上石町から梅屋町の通りをぬけ、川辺村へかかるころから、竹千代の顔には蒼さが加わる。うっかり口を開いて話してゆくと疲労は彼の足を止める。一度とまると、もう股もこむらも鉛がつまったようになって動かなくなってゆく。「それッ、今少しじゃ、早く!」竹千代は「くそっ!」と心で叫んだが、足だけは依然として同じ歩幅、同じ歩速でかけてゆく。ついに春の川面が見え出した。そこここにまだ桃や桜が咲き残っていて、その間を、菜の花の黄色があざやかに綴(つづ)っていた。川原へ出ても伝心は足をゆるめなかった。「やあやあ、遠からんものは音にも聞け、近くば寄って眼にも見よ。我こそは海道にその人ありと知られたる松平は名乗りは無しの竹千代なり」いいながらこらえにこらえて走ってくる竹千代を振り返って、「それッ、敵将は竹千代の姿を見つけてざんぶと川に馬を乗り入れた。追えや追えや....といってもこちらは馬ではない。それッ!」竹千代の疲労が極度に達していると知って、伝心はパッと着物をその場に脱ぎ捨てた。「それ、おぬしも早く脱ぐがよい。敵将を逸しては相ならぬ。今じゃ!今が竹千代の運命を決するときじゃ、それッ」伝心は川辺で足踏みしだした竹千代の着物を、むしり取るようにして脱がせてゆく。「敵....敵....敵将はだれだ!」たまらなくなって竹千代ははじめていった。丸い胸が波のようにゆれ、心臓の音がそのまま聞こえて来そうであった。「何という貧弱な体じゃ。このわしをみろ」伝心は岩くれに似た自分の胸をドンとたたいて、「敵少によっては追うに及ばぬというのだろう。そのような小賢しさは鍛えの邪魔じゃ。それ追えや追えや」いうや否や竹千代の裸の胸を抱き上げて、そのままパッと水の中へかけこんだ、そして冷たい流れが自分の腰を没したところで、目よりも高く竹千代を差し上げ、とうとうとした本流へ水音高く放りこんだ。「それ泳げ。泳げなかったら安部川の水くらい飲み干してしまうがいいぞ」浮きつ沈みつもがく竹千代を手をたたいてはやし立てた。竹千代はようやく背の立つところに来て、ほっと息を吸い込んだ。三月の水の冷えは駆けつづけてゆるんだ皮膚を、きゅんとするほど締め上げて、全身の筋肉が引きつりそうな感じであった。といって冷たさに音を上げるような竹千代ではなかった。この年もすでに寒中から冷水で肌をふきあげている。だが水勢と股の疲労は著しく、それに川底の水あかも彼の意思に反抗した。立つと一緒にくるりとすべって水をのみ、その水を吐き出そうとするとまたすべった。「あっはっはっは。呑め呑めもっと」伝心は竹千代の流されるだけ自分も下流に歩きながら、少しも揶揄をゆるめない。ようやくヘソのあたりの浅瀬までたどりついて、「敵将は......」「だ....だ....だれだ」「これは執念深い。討ち取ったのか、取り逃がしたのか」「取り逃がしたが....、だ....だ....だれだ」竹千代は早く陸へ上がりたかった。負けたといわず、参ったといわず、陸で体を干したかった。「敵将はな、おぬしと縁故浅からぬ織田上総介信長じゃ」「なに信長どの....それではやめた。追うのはやめた。竹千代が同盟軍じゃ」そういうと竹千代はのこのこ岸へ上がった。「考えたなこの奸物(かんぶつ)め」「奸物とはなんだ、信義を重んじて追わぬまでじゃ」「はっはっはっは。よしよし、では来い。のう竹千代。」「なんじゃ」「駆けたあと、泳いだあとは快かろう」「悪い気持ちではない」「おぬし過ぐる年に、この川原で石合戦を見たそうじゃの」「みた」「そのときに勝敗をいいあてたそうな。大勢の方には信がないゆえ負ける。少人数の方には団結があるゆえ勝つと...」竹千代は答えなかった。「わしはその話を雪斎長老に聞かされて、それからおぬしにほれたのだ。だが、わしのほれ方は少々荒っぽい。どうじゃ迷惑か」「迷惑と思わぬ」「そうか。フーン。そうか。ではこのあたりで中食(ちゅうじき)にいたそう。わしはちゃんと用意してきた。」二人はそこで着物を着た。そして川原へ並んで腰をおろし、伝心が腰へつけてきた小さな袋を開いた。「それ、これがおぬしの焼き米。わしは握り飯じゃ」ぽんと竹千代の膝に焼き米の袋をほうって伝心は自分だけ、うまそうに握り飯をパクつき出した。握り飯は梅干が入っていたし、別に赤い塩鱒が一切れあった。竹千代がうらやましげにチラリと見ると、「バカッ!」と伝心はどなった。「大将が家来と同じ美食などしてよいものか。これはおぬしの祖母がつくった中食じゃぞ」竹千代はうなずいてポリポリと焼き米をかじった。「大将の修行と雑兵の修行はおのずから違わねばならぬ」伝心は意地悪く舌を鳴らして塩鱒を賞味しながら、「どうだ竹千代も誰かの家来になっては」竹千代は答えなかった。「家来というは気楽なもんでな。生命も口も主人あずけだ。だが、大将となるとそうはいかぬぞ。武芸兵法はむろんのこと、学問もせねばならぬし、礼儀もわきまえねば相ならぬ。よい家来を持とうと思うたら、わが食を減らしても家来にひもじい思いをさせてはならぬ」「わかっている」「分かっていると思うのが間違いじゃ。まだおぬしなど何がわかっているものか。だいいちおぬしは痩せている」「.....」「それそれ、その目つきもいかんな。痩せておるのは美食をせぬためじゃといいたいのじゃろう。その考えがすでにいかん」「その考えとはどの考えじゃ」「美食をせねば肥えないものと考えるそのことじゃ。それは家来の考え方じゃ。大将の考え方ではない。大将というのはな....」「うん、大将というのは....?」「霞(かすみ)を食うてまるまると肥え、腹では泣いても顔ではニコニコ笑っている」「霞を食うてまるまると」竹千代が真顔になって首をかしげると、伝心の眼もぴたりと据わった。いつも冗談の中に真をふくませ、相手の心をひきつけて、疑問の的をずばりと貫く伝心の訓え方であった。「霞では血肉にならぬと考えるような人物では、大将はおろか、よい雑兵にもなれぬ。人間に賢愚の差があるであろう。竹千代はなぜじゃと思う?」「さあ....?」「霞の食い方ひとつにある。といってこれはおぬしだけではないぞ。おぬしの両親もよい霞....つまり正しい呼吸をしていなければ話にならぬが、たとえ両親が正しい呼吸をし、なに不足ない子を生んだとしても、その子の息が整うていなければれもまた話にならぬ。分かるかな?この大気はさまざまな宇宙の霊を含んでいる。この中から気息を整えて何を摂(と)るかで、その人の器の大小が決まっていくのだ」竹千代は何か分かるようで分からない節があった。伝心はそれと察して、またカラカラと笑い出した。「雪斎長老に公案を出されて困りぬいている。このうえ竹千代を苦しめまいかの。だが、雪斎長老は座禅を教えるとき、まず息から整えよといったであろう。息のみだれた奴には何も出来ぬ。苦しいときにも、悲しいときにも、嬉しいときにも、有頂天なときにも、同じ呼吸で宇宙の霊気を摂取する、そんな人物に仕立てようとしてご苦心なされていられるのじゃぞ」竹千代はポンと膝をたたいてうなずいた。伝心は近ごろ臨済寺で座禅しだしている竹千代に、一つの助言を与えようとしていたのだ。「さ、終わった。そろそろ帰るか」自分の握り飯がなくなると、伝心はさっさと立って歩き出した。竹千代はあわてて焼き米の袋を腰にはさんであとにつづいた。************************************************参考 山岡荘八・徳川家康3巻/雌伏の寅よりほんとはこの次が感動するところなんですけど、長くなりすぎるので明日の分にしようと思います。*この書き込みは営利目的としておりません。個人的かつ純粋にに一人でも多くの方に購読していただきたく参考・ご紹介させていただきました。m(__)mペコリ
2006年01月30日
コメント(0)
-
-教育-
今朝、なんぞの番組で今までの教育は子供に権利ばかりの教えて、義務を教えていないとか誰ぞがいっておりました。ライブドアの堀江氏。なぜすべでお金、ではならないのか?自分の子供に問われたら、どうかえそうかなぁ。とふと考えましたそこで今日は、また山岡氏から引用させていただきます。家康がまだ幼少(竹千代)時代、織田家から今川家へ人質交換で駿府へ行き、今川家の長老、大原雪斎から初めての訓育を受けたときの話です。*************************************************雪斎が竹千代に期待するものは人間として愛情以上に、法弟としての武将なのである。いや、もっと語を強めて言うならば、それは仏心によって新しい秩序をもたらす、一大政治家であり、救世の聖将なのである。「よかろう。では今日は手習い初めに入ろうかの」「はい」「竹千代は孔子という古い聖(ひじり)を知っているか」「はい。論語の孔子さま」「そうじゃ。その方の弟子に子貢(しこう)という人があった」「子貢....」「そうじゃ。その子貢があるとき、政治とは何でしょうかと孔子に尋ねたとき、孔子はこう答えられた....よいか。およそ国家には食と兵と信とがなければならんとな」竹千代は円い肩を堅くして、じっと雪斎を見上げている。それは知識に飢えた燐光をやどした目であった。雪斎は今まで竹千代の身辺に、いい加減な教育者のいなかったことの感謝と哀れさを覚えながら言葉を続けた。「すると子貢はまた質問した。よいか。何かの都合で国家がその3つを備えられない場合には、どれを捨てたらよいでしょうかと」「食と、兵と信の中の....」「そうじゃ。食は食べ物。兵は武備。信は人々の間の信じ合いとでも言うか。お許の松平家を例に取るならば、家中の士の間にそれがなくば、とうに崩れ果てていたであろうて....」雪斎はそういうと、また食い入るような竹千代の視線に微笑を誘われながら、「そこでお許の考えから先に聞こうかの。子貢のその3つが、ある事情でそろわないときには、まず何を捨つべきかという質問が、お許に向けて発されたとすると、お許はなんと答えるか」「食と兵と信....?」竹千代はもう一度口の中でつぶやいてそれから探るような表情で、「兵.....」と答えた。雪斎は意外な答えを得たおどろきで、またしばらく竹千代をながめやった。当時、大人の常識では武備こそ第一、武備は常にすべてにまさると考えられているときだった。「なぜ兵を捨てるかの?」「はい」と、竹千代は小首を傾げて考えて、「3つの中では兵が一番軽いかと....」いいかけて、今度は何か思いついたらしく、「人は食べ物がなければ生きられませぬ。が、槍は捨てても生きられまする」「ほほう!」雪斎はわざと驚いたように眼を丸くして、「孔子も竹千代と同じことを答えられた。兵を捨てよとな」竹千代はニコリとしてうなずいた。「ところが子貢はまた尋ねた。後に残った2つのうちまたどうしても1つ捨てねばならぬときが来たら、そのときは何を捨てたらよろしいかと。竹千代ならばなにをすてるの?」「あとは食と信....信を捨てまする。食がなければ生きられませぬ」意気込んで答えると雪斎は微笑した。「竹千代はひどく食にこだわるの。尾張で腹をすかせた覚えがあるな?」「はい、三之助と善九郎と....腹がすくと、みんな、機嫌悪く、あさましゅうなりました」雪斎はうなずいた。子供3人捕らわれの身の不自由さが目先に見えるようだった。「して、そのときに、何か食べ物が手に入るとお許はそれをどうしたな?」「まず三之助に食べさせました」「その次には」「竹千代が食べました。善九郎は竹千代が食べぬうちは食べませぬゆえ」「ほほう、善九郎は竹千代が食べぬうちは食べなかったか。」「はい。でも、それからは三之助も食べませぬ。善九郎のまねをしました。それゆえ、その次にははじめから3つに分けて、竹千代がまず取りました」雪斎は微笑しながら何かに祈りたい気持ちになった。この小さな政治家が、空腹を前に真剣に考えている姿が、ここでも目先にうかんで来る。「そうか。それはよいことをした。竹千代のやり方は正しかった。が.....孔子は子貢にそう答えなかったぞ」「すると、食を捨てよといわれましたか」「そうじゃ。食と信2つのうちでは、まず食を捨てよといわれた」竹千代は首をかしげて、「食を捨てて国がある.....それは孔子さまのお間違えでは」と低い声で探るようにつぶやいた。「竹千代」「はい」「これはのう、この次までお許にゆっくり考えてもらおうよ。なぜ孔子が食より信が大切かといわれたか」「はい。かんがえまする」「が、その考えのもとになること....それはお許の話にもすでにあったの」竹千代は不審そうに雪斎を見返して、また右に左に首をかしげた。「竹千代ははじめの時には三之助にまずやった。そして善九郎にもやったが、これは竹千代の食べないうちは食べなかったと申したな」「はい」「善九郎はなぜ食べなかったのだろうか。そしてその次には三之助もまた善九郎の真似をしたと申したの」「は....はい....?」「三之助はなぜ善九郎の真似をしたのか?それがお許にはわかるかな」「さあ....?」「その答えはこの次までにゆっくり考えて参るとして、わしの考えだけはいってみよう」「はい」「はじめ三之助は、まだ幼かったゆえ、竹千代にみな食べられて自分の分はなくなるかも知れぬ....と、そう思うたのであろう」竹千代はまばたきを忘れた顔でこくりとした。「ところが善九郎は、竹千代が一人でみな食う人ではないことを知っていた。竹千代を信じていた。信があったゆえ、竹千代が食べねば食べなかった....」雪斎はそこで言葉を切って、自分の眼光が竹千代の年を忘れて、雲水をたたくときの、きびしさに変わっていくのを意識した。「そしてその次には、三之助もまた、竹千代を信じてきた。黙っていても、後になっても一人でむさぼる人ではないと悟ったのだ。三之助は善九郎の真似をしたのではなくて、竹千代を信じ、善九郎を信じたのだ。よいかの、信があるゆえそのわずかな食は活きたの。3人の命をつなぎ得たの。ところが、その信がなかったらどうなってゆくと思うのか....」雪斎はそこで再び眼をなごめて、「善九郎が一人で食べたら後の二人は飢えていく。竹千代が一人で食べても三之助が一人で食べても同じことじゃ。だが人と人の間に信がなくなると、活用すれば三人とも飢餓を逃れたその食が、三人の争いの種となり、かえって三人を血みどろの切り合いに誘い込まぬものでもない」そこまでいうと竹千代はポンと自分の膝をたたいた。いつか体は文机の上に乗り出し、眼は満月のように見張られている。雪斎は、しかし、すぐに竹千代の答えを聞こうとしなかった。「よいかの。学問に早合点は禁物じゃ。この次までゆっくり考えての」「はい」「信じあう心......というよりも、信じあえるがゆえに人間なのじゃ。人間が作っているゆえ国というが、信がなければ獣の世界....とわしは思う。獣の世界では食があっても争いが絶えぬゆえ生きられぬ....さ、今日はこれまで。尼(祖母の源応尼)どのと一緒に戻ってな、諸将に回礼するがよい」「はい!」と、答えたが、竹千代の姿勢は以前のまま。雪斎は手をたたいて、次の間に待っている源応尼を呼び入れた。*************************************************参考 山岡荘八・徳川家康2巻/相寄る者より*この書き込みは営利目的としておりません。個人的かつ純粋にに一人でも多くの方に購読していただきたく参考・ご紹介させていただきました。m(__)mペコリ
2006年01月29日
コメント(5)
-
捻挫がなおらない
去年の11月末くらいにサッカーの練習中、トップスピードでサイドから突破してシュートをうつぞの体勢で左足を軸に踏み込んだら、足がパキッとかいって捻挫しちゃいました。あれから数ヶ月たつのですが、なかなか直りません。もちろん練習は続けていますが....だめですねぇ。歳を取ると怪我が増えるし直りにくいと来ます。疲労の回復も遅いし。最近は筋肉痛が2日後です。でも、サッカーはしたいし。やっぱり病院いったほうがいいかなぁ。
2006年01月28日
コメント(0)
-

わが子の成長
今日は、いつもと少し違う話題でいこうかな。 私の長男、和志君は只今小学校2年生。最近は掛け算の暗記をはじめており、家でも嫁さんと一緒に掛け算の暗記をしております。このごろは、何か叱っても、言い返すようになり最初は生意気な小僧め!!と思っておったのですが、最近は和志が言い返すのも理由があるのかな、と思うようになりあまり頭ごなしに叱らなくなりました。(でも叱ってはいますが....)この間、漢字の練習をしてて汚い字列でかいとるなぁと叱ろうと思ったのですが、よく見てみると、和志には和志の一定の法則で書いてまして、下敷きに四角の枠があって、その枠がうすくてよく見えずよく見える枠の左上にばかりあわせて書いてて、それで汚く見えてたのでした。客観的に見て、汚い字列ではあるのですが、自分の中で自分らしく法則を生んで書いていってるのを見たら、あまり大人の解釈で子供を押さえつけるような教え方は良くないのかなぁとおもってしまいました。
2006年01月27日
コメント(0)
-
-信仰観-
我が家は父の代から無信仰で、結婚してから嫁さんの実家がある信仰をしておりその生活観・死生観のギャップから精神的に非常に苦労したことがありました。そのときに、この本を読んで自分の信仰に対する考え方の参考にしたところを紹介します。豊臣秀吉存世中の大阪城大奥での話し。********************************************あるとき、そうした信仰のことに付き、大奥でひとつの議論に花の咲いたことがあった。秀吉や御伽衆(おとぎしゅう)を聞き役にして、「....神と仏と、切支丹のデウスとは、いずれが上位、いずれが下位であろうか?」と、いうのが、その日の論題だったらしい。その席に居合わせた小西行長の父の寿徳は、「....それは申すまでもござりませぬ」と、デウスを押した。デウスは絶対の存在で、他は人間のはかない願いが描き出した偶像邪心に過ぎないと。ところがこの議論はすぐさま仏教信者の女たちに手厳しい反撃を受けた。「....ではデウスだけが、どうして人間のはかない願いが描き出した邪心ではないという証拠があるのか」どちらもその意味では観念の所産であって、区別はない。それゆえ、各自がどの神仏を信仰するかは自由で干渉すべきものではない....と、いうのが一座の結論に近かった。秀吉は絶えずニコニコと聞いていたが、このときになって、同じように口をつぐんで聞いていた北の政所(まんどころ)・寧々に言った。「....政所よ。お身の意見は?」寧々は豊な微笑をたたえたままで、「....決まったことをお聞きなさるものではございませぬ」と答えた。「....決まったこと?」「....はい。それは天照大神(あまてらすおおみかみ)を仰ぐ日本の神々に違いないではござりませぬか」「....ほう、これは面白い。それをみなの納得するように説明できるか」「....できまする。日の神はこの世界をお作りなされた。万物をこのようにお生みなされてお育てなさる。人間も、仏も、デウスもみな日の神のお生みなされたもの。それゆえ、神々の中にも生んだものと、生んで貰うたものの差がござりまする」「....ほう、これは面白い!」重ねて秀吉は問いかけた。「....では、こなたは何ゆえ、弥陀(みだ)に称名(しょうみょう)し、観世音(かんぜおん)にぬかずくのじゃ」「ホホ....、それは人の子が、人間を生んで下された遠い祖先の神々よりも母親を懐かしむのと同じ気持ちからでござりまする。おわかりであろうか。仏にぬかずくもデウスに祈るも、そのずっと奥におわす天地を作られた日本の神々にぬかずいているのじゃと。それゆえ、どの門からおがもうと、それは人それぞれの自由でよいのじゃ」結論は信教の自由と同じところへ行き着くのだが、孝心までも信仰に連なるものと言い切ったこの卓説には、さすがの寿徳も歯が立たなかったという...***********************************************参考山岡荘八・徳川家康13巻/頂上よりこれを読んでから、少しばかり信仰に対する理解ができるようになりました。まぁ、いろいろありますが、じんさん的には無信仰な人よりも敬謙に物事に手を合わせられる信仰心のある人のほうがすばらしいと思います。ちなみに僕は、まだ無信仰ですが(笑)ようは何に手を合わせるかではなくて、物事に手を合わせる心があるかないかではないのでしょうか?あなたはご飯を食べるときに、心から手をあわせますか?ささいなことですが。*この書き込みは営利目的としておりません。個人的かつ純粋にに一人でも多くの方に購読していただきたく参考・ご紹介させていただきました。m(__)mペコリ
2006年01月25日
コメント(1)
-
-家風-
はぁ....やっとオークションの再出品がおわった。全部いっぺんに終わるようにしたから、まぁ大変です。でも、いっぺんに終わると管理しやすいですね。....と。今日も昨日に続いて本の内容でいこう(これから当ブログの方向はヒトリゴトとこれできまりっす)と思います。えー、また山岡本で、家康が秀吉に上洛を促され上洛する直前、家中に心構えをといた後の鳥居新太郎忠政とのやりとりです。***********************************************入念に心構えを調べていって、ふと家康はうしろに人の気配をかんじてふり返った。すでに次の間へ下がったものとばかり思っていた鳥居新太郎が、まだそこへ真四角に座ってじっと何か考え込んでいたのである。「新太郎、もう休んでよいと申したのが聞こえなかったのか....」「は....」新太郎はビクリとして前髪の顔を立てると、思いつめた表情で上半身をゆすった。「お先に休むなど思いもよりませぬ」「ほう、すると、わしが朝まで起きておれば、こなたも寝ぬつもりか」「お館さま!いよいよお館さまは、ご上洛なさるのでござりまするなぁ」「そうじゃ。そちも聞いていたではないか」「お願いがござりまする!」「ハハ....固くなって、何事じゃ」「この新太郎にも、是非ともお供をお許しくださりまするよう」「ふーむ。なぜじゃな」「もしご上洛と決まったら、お館さまの太刀持ちとして、おそばを離れてはならぬ。そのことを必ずお願い申してお許しを得ておくようにと....」「誰が申した?父の元忠か」「はい....それに、この新太郎も、そう思いまする。」家康は笑顔を納めて、ゆっくりと新太郎に向き直った。体はすでに大人であったが、ただ一基の燭台に照らし出された思いつめた表情の若さは、音を立てて折れそうな蒼白な緊張ぶりだった。「こなたは、上洛すればわしの身に危害を加えるものがある....と、思うておるのか」「いいえそうは思いませぬ」「ならば、何もこなたが、それほど固くなって案ずるほどのものはあるまい」「いいえ、それだけではならぬと思いまする」「なに、それだけではならぬ....?」「はいっ。お館さまは、さっき、ご城代に、そちはまだわしの思案の半ばしかわかっておらぬぞとおっしゃりました」「ほう、それを聞いていたのか」「私はその意味を考えました。そして父の言葉を思い出しました。」「なるほど」「たとえばご身辺に、何の危うさがないといたしましても、私は、やはりお側へきびしく座っていねばなりませぬ。相手に、さすがは徳川家のものども、一分の隙もない心構え....と、それを見せておくだけで、必ず後々のお為になる....父の申したことは、この油断のない心を養えよとの意味であったと察しました」家康はちょっと上目になり、それからしばらく黙って相手を見据えていった。作左衛門に念を押した一言が、まだ前髪立ちの新太郎にまで誤りなく受け取られている。「なるほど、それが新太郎の計算か」「お願いでござりまする。たとえ四刻、五刻(8時間、10時間)座り続けようとも、仰せとあれば身じろぎもいたしませぬ。祖父の忠吉、父の元忠に劣らぬご奉公がいたしとうござりまする。強(た)ってお供にお加えくださるよう、このとおりでございまする」そう言うと、新太郎は、おかしいほど真剣にたたみに落ちた自分の影へ額をつけてゆくのだった....「お館さま、なぜ黙ってでござりまする。この新太郎の考え方、まだまだ未熟と仰せられまするか」「されば、のう....」「父から祖父のことをたびたび聞かされておりまする。武人の勝敗はその時々よりも平素にある。平素に油断のないのが第一の心構えと」「........」「いや、家風というのは一代にしては成らぬもの。きびしく普段に培い(つちかい)伝えよと、これが祖父の口癖だったそうにござりまする。幸い我が家はここ三代お側はなれず....この新太郎のみ、大切なご上洛のお供が出来ぬとなりましては祖父に合わせる顔がございませぬ」憑(つ)かれたように言い立てられて家康はぐっと胸が切なくなった。若者の心の一途な切なさよりもその背後にある伊賀守忠吉や、彦右衛門元忠の庭訓(ていきん)のきびしさが胸をえぐって来るのである。「新太郎」「お許し下されまするか」「そちは三河武士の心構えを京大阪へ見せに行くというのじゃな」「はいッ。それが後々まで、秀吉に侮(あなど)られぬもとになろうかと」「ハハ....そう言われては連れて行かぬとも言えまい」「お連れ下さりまするか!?」「よし、連れて行こう。その代わり、われらと秀吉方の間に、どのような話が交わされようと、それにいちいち顔色を変えてはならぬぞ」「はいッ」「よいのう、いつもどっしりと、巌(いわお)のように控えておれるか」「巌のように....しかと、お約束いたしまする」「よしよし、いまのそなたの、その言葉、祖父(じい)の伊賀がどこぞて聞いて笑っていよう。用は済んだ。心の支度ものう....わしも休む。そちも休め」「はい。では、お館さまの寝息が聞こえましたら、火の元を見回って休ませていただきまする」「ハハハ....堅いこと堅いこと。よし、では、そちの思いのままにするがよい」すでに時刻は子(ね)の刻(12時)近い。シーンと静まり返った城内に物音はなく、遠く能見のあたりで犬の遠吠えがするだけだった。家康は立ち上がって、ゆっくりと背伸びをし、それから燭台の火を吹き消して床に入った。浜松を居城にしてから十六年目。久しぶりにやってきた岡崎城の秋のしじまが、そのまま無数の声となって話しかけてくるようだった。信康の声。築山殿の声。徳姫の声。石川数正の声。秀吉と家康。いったい誰が幸せで誰が不幸なのであろうか?そんなことを考えながら、しかし、家康はすぐに眠った。やはり彼は健康なのだ......************************************************参考山岡荘八・徳川家康12巻/三河の計算より*この書き込みは営利目的としておりません。個人的かつ純粋にに一人でも多くの方に購読していただきたく参考・ご紹介させていただきました。m(__)mペコリ
2006年01月24日
コメント(0)
-
-お椀の底が透けて見える味噌汁-
今日紹介するのは、僕が美味しいものが食べたくなったときにふと思い出す山岡本のくだりです。少し長くなりますが、そのまま乗っけてみようと思います。場面は、家康が小牧・長久手の戦後、京都から御用商人の茶屋四郎次郎清延を迎えて食事を出すところ。*********************************************茶屋四郎次郎は、うやうやしく膳の前で合掌した。相変わらず麦飯だった。それに椀の底の透けて見えそうな味噌汁と、香の物のほかには、いかにも塩辛そうに干からびた小鰯(こいわし)が一匹付いているだけだった。「時が移った。空腹だったであろう。遠慮はいらぬぞ。」「恐れ入ってございまする。では頂戴を。」茶屋四郎次郎は堺の町人の食膳と思い比べた。他人に出す食事といえば、どんなに粗末であっても、このほかに、なますと野菜の煮付けだけは付いて出る。(大納言にもなろうというのにいまだにこのようなお食事をなされている...)そう思うと、茶屋四郎次郎はあやしく目先がかすみかけた。46歳の家康が、なんと満足しきった箸の運びようであろうか。(厳しい禅堂での生活にも比すべきもの....)茶屋の知っている限りでは町人でも、このような質素さを守り通して、しかも生き生きと暮らしているのは本阿弥光二と光悦の一家くらいのものであった。光悦の母の妙秀は、厳しい日蓮信者で、他人に珍しい絹織物などを送られると、それを細かく袱紗(ふくさ)に分けて、出入りの貧しい妻女たちにわけてやり、一物も私しない。世間ではこれも時々「吝嗇(りんしょく)なのでは...」などと噂したが、自分ではいつも木綿ものしか着なかった。家康も、どこかそれに似ている。極端に消費を慎みながら、常に不時の入用に備え、考えているのは世の中のためらしかった。それでなければあの明るさは....と、思ったときに突然家康のほうから話しかけてきた。「茶屋、人間というものは、ちっとも油断のならぬものじゃぞ。」家康の言い方があまりに突然だったので、茶屋四郎次郎は、箸を持ったまま「は?」と答えて家康を見上げた。「時々のう、わしはうまいものが食べたくなる。」「は....それはもう、私なども」「しかし、その度にわしは反省するがの。この美味いものの食べたいときは、よく考えてみると自分がひどく疲れているときじゃ。」「ごもっともに存じまする。」「人間、疲れてはならぬ。」「確かに年を取りますると滋養の摂取が....」「茶屋、勘違いをするな」「は?」「わしが疲れるといったのは現身(うつしみ)の疲れをさして言ったのではない」「なるほど」「精神の疲れのことを申したのじゃ。美食がしたいと考えるようなときは、せねばならぬ仕事、つまり目的があいまいになっているときだと申したのじゃ。」「あ!そのこどでござりまするか」「そうじゃ。肉体はのう、どれほど美味を摂り、どれほど大切に寝ていてみたところで百歳まで生きられるものではない。衰えるときが来ればきっとおとろえる。しかし精神は死ぬまで衰えさせぬこどが出来る。」茶屋は思わずそっと箸を置いて姿勢を正した。そうせずにはいられない律儀さのせいもあったが、ただそれだけではなかった。やはり禅堂ですぐれた師家の前に座られているような気がしたからであった。「固くなるな。食べながら聞くが良い。」「は....はいッ」「わしはのう、他力のありがたさは十分に知って感謝している。が、また自力の効も忘れてはならぬものと思うておる。それゆえなぁ、わしが食膳に美味を並べておらなんだら、家康はまだ満々とした自信を持って、精神の疲れを知らず、目的のために働いているのだと思うてくれ」「あ....ありがたいことに存知まする。」「ご馳走をせなんだいいわけの、これがご馳走じゃぞ茶屋」「山海の珍味に勝る、ありがたき、心の滋味にござりまする。」「わしとてものう、美味いものは美味い」「ごもっともで」「しかし、わしは貧しい民百姓のある限り、それらに顔向けのならぬほどのおごりはならぬものと思うておる。人もわれらもみな、同じ神仏の愛し子じゃ」「仰せのとおり、と存じまする。」「それにのう、少しでもおごりを尽くしていると思うと、いつかそれが心の負い目になっての、大きな自信を失のうて行くものじゃ。どうじゃ、この膳ならばまだまだであろうが」茶屋四郎次郎は、はじめてこれが家康の自分の労をねぎらう答えであったと気が付いた。家康の無心はまた、なんと厳しい反省の上に立った無心であろうか。彦左衛門が無心は有心、有心は無心といっていたが、これはただの無心さではない。そう思うと、茶屋の目は自然に曇り、曇ったまぶたの裏で、家康とは、およそ対照的な秀吉の生活の豪華さが思い描かれているのだった。***********************************************参考山岡荘八・徳川家康12巻/無心有心よりぷはぁっながかったぁ。これからもこんなの書いてみよーかな。*この書き込みは営利目的としておりません。個人的かつ純粋にに一人でも多くの方に購読していただきたく参考・ご紹介させていただきました。m(__)mペコリ
2006年01月23日
コメント(0)
-
今日はなに書こうかなぁ。
今日は何のお話をしよっかなぁ。何も考えてません。でも、何がなくともこうやって書き込みをしたほうがいいのだと最近きずいてきまして。書いてるうちに広がっていく。今日は、納品やらお直しやら、なかなか忙しぃ。さっきお昼ごはんでカップラーメンにお湯入れたら「ピンポーン。ピンポーン」いらっしゃいませーっ汗接客終わったらすごいことになってました。一人はつらいですねー。でもたべちゃいましたからーっ笑.......やばっ話題が尽きる。やっぱり書き込む前に良く考えたほうがいいらしいです。サッカーのことも書きたい気がするけど..最近は、けっこう若い連中(22-23才)と練習してたけどみんな上手ですねー。僕らが若い頃のレベルよりかなりうえのレベルですね。足なんかぜんぜん太くないのに。僕らの若い頃は、上手なやつほど足が太いような気がしてましたが時代が違いますねー。今日は、近所の中学校でナイター練習だよーん。早くボールさわりたいよー。
2006年01月22日
コメント(0)
-
本日は謙信公の生まれた日
また歴史系の話題ですが、今日は上杉謙信が生まれた日でーす。えーーと謙信公は、吉川英治かな?僕が読んだのは。吉川英治氏はこれまたたくさん読みました。僕が高校時代に、まだマンガしか読んでなくって、小さい字の本が苦手だった頃に一番最初に読んだのが吉川氏の”新書太閤記”でした。学校の授業サボって図書室で昼寝してたらなにげに目に入って、ふと読み始めたのがきっかけです。あの頃はマンガの横山光輝・三国志にはまってて、そのマンガの原作が吉川氏の名前が付いてて、「あっ、この名前の人は三国志の原作の人と同じ人やん。」と読み出したのでした。そしたらおもろいおもろい。昔の候文やら、侍言葉などはマンガでも出てたので、すんなり読めて。今でも、あの竹中半兵衛重治が平井山で陣没するくだりなど、何度読んでもないてしまいます。(三国志の孔明・五丈原ばり)山岡氏は、哲学的、信仰的な書き方で、吉川氏は、文学的、描写的な書き方かな。二氏ともに、書き方のスタイルがわかり易く、理解しやすいので圧倒的に好きです。(はっきりいって二氏以外の本はあまり読みません。)読書と言うのは、著者の個性などを考えながら読んでいくと内容のみではなくって、もっと広く深い読み方が出来ると思いまーす。今度は本の内容についても書いていこうかなぁ。
2006年01月21日
コメント(0)
-

山岡荘八マニアです。
昨日は、夜9時30分ごろまで勉強会がありました。只今とてもねむねむです。コーヒー豆のサントスさんの瀬崎さん。車検のコバックの湯浅さん。うちとこの社長。同じく本店店長の5人でエモーショナルな販促に関しての勉強会。なかなか皆さんいろいろ知ってて勉強になります。このブログをはじめたのもその勉強会で啓発されたからです。で、最近なかなかブログが書き込めなくて何を書けばいいかなぁと聞いてみると歴史のことでも書けばいいじゃんといわれ今日さっそく書いてみようと朝から書き込みしてるのですが何を書けばいいのだろう。僕は歴史でも、ただの歴史小説を読むのが好きなわけではなくて、山岡荘八氏の人生の哲学的なものが好きなんです。その中で家康が大阪夏の陣の後、公武法度を出して江戸に帰る前、時の京都所司代板倉伊賀守勝重にのこしたことばで有名な”人の一生は、重荷を負うて遠き道を行くが如し 急ぐべからず”に始まるあれ系です。もう9年位前から山岡荘八氏の本を読んでますけど、何度読み返してもその時の自分の人間的器に応じて捕らえ方が違うので、何度も読み返してます。とくに徳川家康。家康君と言えば、他の著者は結構腹黒系で書いてるのが多いけど、山岡荘八氏はちょっと違う。信仰くさいというか、自分が過去に従軍記者として、太平洋戦争で多くの若者たちを戦場で送ってきて、「後を頼む。」と若者たちに将来を託され内地に戻ってきて、どうしたら恒久的な平和を築けるのかと言う視点から家康による太平の招来を書いたものなんだけど、その中で神仏に問い続ける真摯な家康の姿というのが、無信仰で戦争なんて関係もなにもない自分にとってはすごく勉強になるというか、心を動かすものがありました。そのなかでも今、一番気に入っている言葉が、”この身の道理をのぶれば天地に満ち 天地の道理を縮むればわが一身のうちにかくれる”です。この言葉の意味は理解するのに5年くらいかかりました。わかりますか?じんさん所持山岡本徳川家康全26巻伊達政宗全8巻徳川家光全4巻毛利元就全2巻源 頼朝全3巻柳生宗矩全4巻坂本龍馬全3巻高杉晋作全3巻(幕末維新史では彼が一番好きです。)
2006年01月14日
コメント(0)
-
あけましたおめでとう
今年もよろしくお願いします。エルガルディさんは、昨日からOPENです。じぇんじぇんやすめなかったよーん。でも、はっきりいって2日間することなかったし。早くお店に出たかったでーす。今年は、お客様に感動をテーマにと思っていたのですが、さっそくやってみました。今日、県外から1年ぶりに帰省ついでにスーツ作っていただいたお客様がいたのですが、お客様カードを見てたら今月誕生月ではないですか!?今ガルディさんでは誕生月の方にハガキご持参の場合、ネクタイをお誕生日プレゼントに差し上げているのですが、たぶんその方にもはがきが届きそう。マテマテ、県外住んでたらハガキが来ても再々戻ってこれんぞ。それでいいのか!?そういうわけで、出来上がり発送のときに一緒に送ることにしました。そのお客様にはナイショで。箱に包んで。きれいにラッピングして。一筆啓上つきで。忘れないようにもう発送の段取りまでしちゃいました。ネクタイは僕が選んじゃったけど。これで喜んでいただけたらいいのになぁ。
2006年01月03日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
-
-
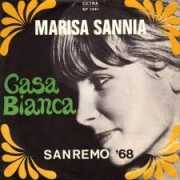
- 競馬予想
- ☆第42回 マイルCS*G1確定枠順&予想…
- (2025-11-21 09:39:54)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-






