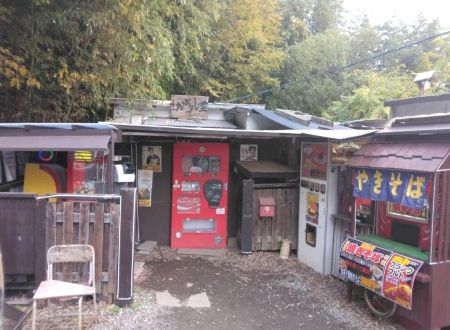2015年09月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
伝統を継続させる努力
9/27に行われた合唱コンクール中部支部大会で名古屋の男声合唱団クールジョワイエがコンクール復帰4年目にして全国大会出場を決めた。この合唱団は創立44年、1980年代後半は全国大会出場の常連で何回も金賞を受賞している、伝統も実績もある団体。この団体がなぜコンクールに復帰したのか?それは団員数を見れば明らか、1980年代は60~70人で参加していたのが、復帰してからは35人、明らかに伝統を継続させるためのコンクール復帰といえるのではないだろうか? ということで、ツイッターで「おめでとうございます。全国大会も頑張ってください」とツイートしたところ、その返信に感動してしまった。それは、「老体に鞭打って頑張っています」・・・さて、今の広友会は、このような言葉が言えるのだろうか?
2015.09.30
コメント(0)
-
常任指揮者によるヴォイトレ
昨日は、広友会常任指揮者の中館先生による第二回目のヴォイトレが練習前に行われた。今回の対象者はトップ1人、セカンド5人の計6人、時間は一人当たり約20分の合計2時間だった。私は、実際にヴォイトレを受けるわけではないのだが、先生がどのようなヴォイトレを行うか非常に興味があったのと、会場が地元だったこともあり、ヴォイトレの様子を見学していた。一回目のヴォイトレの話しを聞いて、興味を持ち同じように見学に来ていた方もけっこういて、これは良い傾向だと思った。 実際のヴォイトレは、まず簡単な発声練習を行い、その人の問題点を見極め、その人に合った方法で「余分なところの力を抜き、一定の息の流れを確保し、声の伸びや響き、音域を伸ばす」ものだった。今回は対象がテノールということもあり、いかに高音域を楽に、伸びやかに声が出るようにするかが主眼だったように感じた。 ここで個人的に問題点がそれぞれ異なるため、その解決方法も様々・・・例えばある人は、手を後ろに組んで若干後ろに反り返るような体制をとったり、別の人には、その逆で手を前に出させたり、いろいろな手法が行われた。このあたり先生の引き出しの多さに感心して見ていた。 発声練習である程度声が出るようになった後、残りの時間で現在歌っている曲の中で、本人が気にしている部分を取り出し、歌い方のレッスンが行われた。ここでの主眼は、言葉というか母音の発音の仕方に重点が置かれていた。これは、合唱を行うにあたって、邪魔になる声の排除が主眼、すなわち、ひらべったい声や息の当て方など、いかに合唱の邪魔にならない自然な発音で歌うかに重点が置かれた指導だったと思った。 このヴォイトレ、はっきり言って非常に有意義なのだが、問題はこれをヴォイトレを受けた本人がどう理解し基本として実際のアンサンブルで歌って行くかが重要。これを受けたからと言って、すぐに本人の歌が飛躍的に上達する訳ではない、まだまだ入口に立ったにすぎないと思う。時間が制約されていることもあり、基本的な歌う姿勢や感覚を指導されたにすぎない。もちろんこれなくして歌の上達のスタートはないのだが、まだまだこれから先に解決していくべき問題点が山積み・・・あとは本人がどれだけ勉強し実践していくか・・・何も考えず、なにもしなければすぐに元に戻るだけ・・・歌に対する根本的な経験や考えを「変えていく」ことから上達は始まるのではないだろうか?
2015.09.27
コメント(0)
-
オペラ演奏会鑑賞初体験
シルバーウイーク最終日、以前、SNSで知り合っていた方と久々にフェイスブックで再会した。その方はプロオケ専属合唱団でソプラノを歌っている方で、かなり以前になるが広友会の演奏会にも来ていただいていた。 で、その方の記事で、その日にオペラに公募の合唱役で出演するということで、なんとホールが地元葛飾シンフォニーヒルズ・・・ここなら歩いて行けるので、当日券があるようなら、チケットも手頃だったので聴きに行くことにした。 聴きに行ったオペラの演目は、「椿姫」・・・よく聴いたことのあるアリアも多く、合唱、重唱などなどとっても楽しめた。やはり主要配役はプロの歌い手で、きっちり歌いきっていたのは素晴らしかった。 ところで、このオペラの合唱と私が現在歌っている広友会での合唱、以前から違うということは実感していたのだが、今回オペラの合唱を聴くことによってその違いが明確になった。 それは、合唱団員各個人に人格があるかどうか・・・の違い・・・今回の「椿姫」での合唱は、女声が高級娼婦役、男声がそのお客・・・もちろん、一人一人にセリフがある訳ではないが、合唱を歌うときにその役柄が背景になると考えられる。 それと比較して、私が歌っている合唱には、合唱団員各個人の人格はない。人格のない一人一人が集まって一つの表現を作るという感じ。もちろん個人の声などある程度の役割はあるものの、オペラのような明確な役があるわけではない。 ここに大きな違いがあるのではないだろうか・・・
2015.09.24
コメント(0)
-
伝統を継続させていくということ
急性すい炎で入院中、特にすることもないので点滴をぶら下げながらテレビをみていると、創業600年以上老舗の和菓子屋さんの90歳を超えた女将さんが出ていた。そして、「こんなに長く続けていく秘訣はなんですか?」との質問に対して「それは、過去に固執することなく時代にあわせて変えていくことです」と平然と言い放った。話しは変わって、今回、広友会の広報を、ネットのSNSを利用して行おうとしたとき、自己紹介において「創立36年を超えた伝統ある男声合唱団」とHPに合わせて書いてあったのを、自ら伝統があると言うのはおかしく、ネットでは反発を買うという理由で削除した。このことに関して、団員のなかには気を悪くされている方もいるかもしれないが、今、広友会が「伝統」を継続させていくのに最も必要だと思われるのは、「変えていくこと」だと思っている。まず、合唱音楽自体の話しをすると、現在の広友会は、中館先生の圧倒的な指導力に引っ張られレベル自体はかなり上がっていると考えられ、その証拠は30回、31回定期演奏会で実証されていると考えられる。しかしながら、先生の指導力が強烈な分、団員が自ら音楽を作っていこうとする意識が薄いのではないか、「俺が、俺が」がモットーのトップを除いて、私には親鳥である先生から餌をもらおうと口だけ開けている雛鳥に見えてしかたがない。また、運営面の話しをすると、前例ばかり重視しそれを変えようとはしない。たしかに過去と同じことをやっていれば楽ではあるが、時代は流れており、もしかしたらその時代により強烈なしっぺ返しをくらう可能性は小さくないと思う。最後に私が広友会で聞くもっとも嫌いな言葉は、「畑中、北村時代は良かった。暗譜も当然だった」・・・これは、その時代を経験してきた方の「思い出」にすぎない。「思い出」とは、自分の「思い」が「出て」いって、昇華されたもの・・・現実を伴わないものは美しく感じられる。しかし、今一番大切なことは、「出て行った」ものではなく、現在ある「思い」ではないだろうか。
2015.09.23
コメント(0)
-
相澤直人作品個展Vol.1
を聴きに紀尾井ホールへ行ってきた。開場13:30と勘違いして四谷でゆっくりカレーを食べていたら、ツイッターで既に開場へ入っている人のツイートを見て、あれ?と思ってチケットを確認すると、開演が13:30・・・ひー、あと10分ちょっとしかない・・・ということでダッシュして会場へ、なんとか間に合った。指定席ということもあり、油断してしまった・・・汗・・・ 1ステージは、NHK東京児童合唱団ユースシンガーズの女声合唱・・・今回の演奏曲は全てアカペラ・・・若い女声のまっすぐな透き通った声と相澤先生の曲が良くマッチしてなかなか良いステージだった。ただ、やはり女声のアカペラだと低音が無いぶん、難しくもあり、聴く方にとっては音の厚みが物足りない感じは否めないが、これは構造上の問題で仕方ないか・・・それにしても「ぜんぶ」は名曲だということを、再認識させていただいた。また、ステージアンコールで、振り付きで歌ったのは、とても可愛くて良かった。おじさんはこういうのにとっても弱い。 2ステージは、harmonia ensembleにによる混声作品集・・・出だしは、harmoniaの美しいハーモニーが響いたのだが、いつもより若干、アンサンブルのバランスが悪かったように感じた。いつもは合唱の中で美しく響くソプラノの田村さんの声が、すこし飛び出して聴こえたのは残念。しかし、これは高度なレベルでの話しで、いつもよりという感じ・・・ 3ステージは、あい混声合唱団による相澤先生によるよく知っている曲の編曲集、もちろん指揮は相澤先生本人。よく知っている曲がほとんどということもあり、楽しく聴かせて頂いたのだが、ソプラノとテノールの高音処理が若干力任せになってしまったのは残念。まあ若さゆえということかな。 4ステージは3団合同演奏で、混声合唱のためのメタモルフォーゼ「詩ふたつ」 さすがに、合同演奏となると、harmoniaのソプラノ田村さんの威力が・・・ソプラノが締まって聞こえると、合唱全体のレベルが上がる。この曲は、けっこう長い曲だったのだが、観客を飽きさせることなく、なかなか良いステージだったと思う。そして最後はやはり「ぜんぶ」・・・楽しめた演奏会だった。
2015.09.22
コメント(0)
-
SNS広友会公式アカウント
私が所属するメンネルコール広友会正式アカウントができましたので、よろしくお願いします。フェイスブックは以下のURLです。https://www.facebook.com/MaennerchorKoyukaiぜひ、「いいね」をクリックよろしくお願いします。また、ツイッターも正式アカウントがありますので、広友会で検索していただき、フォローしていただけると嬉しいです。ちなみに、両方とも「中の人」を担当していますので、絡んでいただければありがたいです。よろしくお願いします。
2015.09.21
コメント(0)
-
中の人
という仕事をツイッターで担当した。当初は別の人がやる予定だったのだが、ツイッター初心者だったため、ネットコミュニケーションに全く対応が出来ない状況となったので、私が変わることになった。 私は、ブログやここのようなSNSに文章を書く場合、考察などけっこう長文が多いため、短文主体のツイッターは、ほとんど情報収集が目的で使っており自分からつぶやくことはあまり無かった。しかし、今後は「メンネルコール広友会正式アカウント」の中の人という役割でいろいろ情報発信をしていきたいと考えている。ツイッターをやっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ広友会正式アカウントをフォローしていただき、リツイートやコメントで絡んでいただけると嬉しいですので、よろしくお願いします。
2015.09.11
コメント(0)
-
「忘れる」という現象に関する考察
広友会は、前音楽監督の時代から言われ続けていることなのだが、練習で指揮者の指導によりその場で割と簡単に出来るようになるのだが、次の練習の時、その出来たことを「忘れ」て、また元に戻ってしまう。この「忘れる」ということに関して少し考察してみた。 まず、私自身がどうなのかということを考えてみたとき、基本的に私は「忘れる」ことはほとんどない。その証拠に私は指揮者の指示事項を一切楽譜に書き込まない。で、どうするかというとその場で全て出来るように努力する。もちろんそれは理想なのだが、なかなか全て完璧には出来ないがそれを練習録音を聴き込むことにより補完する。これを行うことにより楽譜に全く書き込みしなくても困ることはほとんどない。 ではなぜ他の人は「忘れ」てしまうのか・・・広友会では、高齢化で物忘れが多いことに逃げている人が多いが、これは違っていると考える。私の考えでは、まず「忘れる」という認識自体が違っているのではないか・・・ではなぜ前回練習で出来たことが今回練習で再現出来ないのか・・・これはその練習で実践はできるのだが、理論を理解していないのが原因だと考える。すなわち、「忘れる」のではなく「理解していない」のではないかということ・・・ 広友会はベテランの歌い手が多い・・・これにより指揮者の指導に身体が勝手に反応し出来てしまう。指揮者の指導の真意を理解することなく実践が出来てしまうのではないだろうか。指導の真意を理解していないから、時間が経過することにより同じことが再現できないということになるのだと思う。 実践を伴わない学校の授業などに置き換えると、授業で先生から習ったことを理解できなければ、当然試験で答えを導くことはできない。これが合唱の場合、頭を使わなくても出来てしまうが、それでは同じことの再現はできないということ。結局、その場では実践出来てしまうので、理解しようと努力することがないのではないだろうか・・・ 芸術全般そうなのだが、理論と実践の両方が揃わないとダメということなのだろう。なので、もう少し練習中に頭を使うことが出来れば、次の練習で再現することはできる。なぜ、ここはこのように歌う必要があるのかということを理解する努力が必要なのだと考える。
2015.09.09
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1