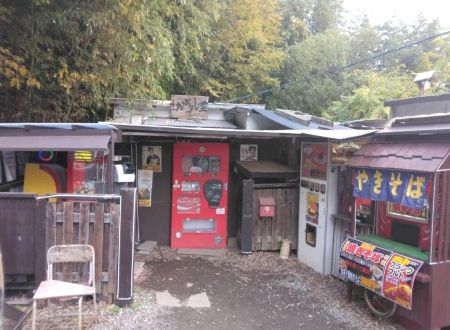2015年06月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
東西四大学合唱演奏会
昨日、すみだトリフォニーホールへこの演奏会を聴きに行ってきた。東西四大学とは、慶応、早稲田、同志社、関学の4っつの大学の男声合唱団、いわゆるグリークラブ・・・はっきり言って、超有名私学で偏差値もかなり高そう・・・で合唱はどうかというと、これも凄い歴史があり、地方大学である名古屋からは、とても憧れるグリークラブだった。今でも思い出すのが、慶応ワグネルが定期演奏会を名古屋の今は無き「愛知文化講堂」開いたとき、ちょうど大学3年でパトリだった私は、その演奏会を聴きに行き、木下保先生と畑中良輔先生に率いられた100人を超す大合唱を聴き、すごく感動し興奮したのを思い出す。もう35年も前の話・・・ さて、話を今回に戻すと、まずオープニングがエール交換・・・4大学の学生指揮者がそれぞれの大学の学歌を歌う。同志社と関学は歌詞が英語、早稲田はあの有名な「都の西北」・・・この演奏で各大学の特徴がうっすら現れた。私が一番気に入ったのは、慶応・・・コントロールされた理知的でセンスの良い歌唱だと感じた。 そして、それぞれの単独ステージ、まず最初は同志社グリーで指揮者は伊東恵司先生で歌ったのは千原作品「ラプソディ・イン・チカマツ」・・・この曲は、いろいろなパフォーマンスが入るけっこう派手な曲・・・ということは以前コンクールでこの曲を聴いておりしっていた。演奏自体はしっかりした演奏だと思ったのだが、すこし歌詞が聞こえにくかったのが残念 次のステージは、慶応ワグネルで指揮者は佐藤正浩先生、歌ったのがプーランクとサン・サーンスのフランス語曲・・・最初のエールの感じを裏切らず素晴らしい演奏・・・とってもカッコイイ・・・さすがは慶応ボーイというべきか・・・上品でフランスの雰囲気を十分感じさせる演奏で、私としては4大学の中で一番良かった。 3ステージ目は、関学グリー・・・指揮者は広瀬康夫先生で歌ったのは、トルミス作曲の3曲・・・これはもうトルミスらしく非常に迫力のある曲でこれも名演でないだろうか、とても良かった・・・ 4ステージ目は、早稲田グリー・・・指揮者は小久保大輔先生で歌ったのはカンタータ「土の歌」・・・そう終曲が「大地讃頌」という超有名曲・・・男声合唱でははじめて聴いた。で、私自身、早稲グリの演奏を聴くのははじめて・・・以前、上田真樹先生が「夢の意味」の男声合唱の初演が早稲グリで、「あそこの子たちは、綺麗に歌うというより熱く歌うという感じ」と言われていたが、まさにそのとおりの演奏で良かったのだが、一番最後のところでトップが大きすぎバランスを崩したのは残念・・・ そして合同演奏は、多田先生への委嘱初演曲・・・250人ほどの大合唱を、おえこらの山脇卓也先生の指揮で歌った。これは、はっきり言って合唱、しかも男声合唱で250人は多すぎ・・・繊細な表現ができなかったのは残念だが、まあこれは仕方ないところか・・・そして合同でのアンコールで多田作品を歌ったあと、エール交換の並びに戻り各大学が十八番のアンコールを歌う。4大学の中でも、関学の「ウ・ボイ」と早稲グリの「斎太郎節」は男声合唱をかじった者なら誰でも知ってる超有名曲でこれを生で聴けたのは嬉しかった。 社会人で男声合唱を復活させてから、本格的な大学グリーの演奏会を聴くのは初めてだったのだが、若いエネルギーて良いなあ・・・というのが率直な感想・・
2015.06.29
コメント(2)
-
吹奏楽部
最近、吹奏楽アニメにはまって、それが原因で中学時代の卒業アルバムを引っ張り出して見てみた。すると部活動のところで文化系として3年生が写真に写っているのだが、可愛らしいことに、マーチング用のユニホームを着て写っている。ユニホームのデザインは、セーラースタイルにベレー帽というまあありがちなものだが、今見るとけっこう恥ずかしい・・・ 写真に写っている3年生は合計で25人くらいで男女比はほぼ五分五分・・・今見ているアニメでは、男子は1割もいないので、女子の数が圧倒的に増えているようだ。なので、当時はほぼ金管楽器が男子、木管楽器が女子でサックスパートがちょうど境で男女両方だったように記憶している。そいうえば、パーカッションも男女両方いたかなあ・・・ 3年だけで25人もいるので、全体では70人超えって感じかあ、けっこう大所帯だなあ・・・文化系の他の部活なんかは、ほとんど活動していないなか、あきらかに異色・・・ユニホーム姿の写真を見ても明らか・・・朝練や休日練習もありかなりハードだったと記憶している。土曜日なんかは、グランド5周とか、腹筋とか、もうほぼ体育会系・・・バトン部が体育会系で写っているのが不思議・・・ただ、コンクールは出場していなかった。多分、当時からコンクールはあったはずなのだが、なぜだろう? ところで、今アニメでは主人公が技術的にとても苦労しているのだが、当時、私はそんな熱血に苦労した記憶がまったく無い・・・チューバは、当然はじめて扱った楽器なのだが・・・やはり音楽は得意中の得意だったのだろうか?合奏でも注意されたイメージはない・・・現在の合唱練習のトップテナーの方が先生からよく注意されるくらいだ・・・ また、ユーチューブなんかで当時演奏していたマーチを聴くと、チューバのパートの音をかなり記憶している。子供の頃、熱中してやっていたことはきっと記憶のどこかに残っているのだろう・・・まあ、懐かしく楽しい「思い出」って感じかなあ・・・
2015.06.28
コメント(0)
-
悔しくて死にそう・・・
もちろん私が言っているのではなく、嵌っている吹奏楽部アニメのユーフォニアム担当の主人公の女子高生のセリフ・・・コンクール府大会2週間前にユーフォに新しく難しいフレーズが追加され、一生懸命練習したのだが、結局そのフレーズはパトリ一人で吹いてくださいと言われ、その帰り道に「上手くなりたい、上手くなりたい、誰にも負けたくない・・・」のあとに橋の欄干で号泣しながら言ったセリフ・・・ ついに、このアニメも最終回を前にして熱血部活物語となった・・・ ところで、このようなセリフを言いながら号泣したことがあるかというと、実は私には記憶にある。それは、この主人公と同年代・・・公立高校受験を倍率1.10倍で落ちた発表後、家に帰るまでは我慢していたのだが、家に帰ったとたん・・・だったらしい・・・今では笑い話でよく両親に言われるのだが・・・ で、音楽でこんな思いをしたことがあるかというと、悔しいと思ったのは、大学一年で「枯れ木と太陽の歌」のソロで失敗したこと、広友会で大学グリー発声が通用せずダメ出しされたとき・・・くらいか・・・もちろん、死にそうにもならず泣きもしなかった。そしてすぐリベンジへ向けて動くって感じ・・・ やはり音楽とは相性が良いのかな・・・
2015.06.25
コメント(0)
-
ハルモニア・アンサンブル Nコンをうたう
を聴きに、先日の日曜日、私の家から歩いて行ける「かつしかシンフォニーヒルズ」へ行ってきた。会場は、ほぼ7割の入りで今年からプロ合唱団になったハルモニアの単独コンサートの出だしとしては、まずますの入りだったのではないだろうか・・・今年のNコン課題曲(中、高)も歌うとあって会場に中高生の合唱部員(だと思う)も多く聴きにきていた。 パンフレットを見るとメンバーの中にソプラノの田村さんの名前がなかった。あの輝く高音が聴けないのは残念だと思ったのだが、田村さん抜きでどんな演奏を聴かせてくれるかと思っていると、ステージがはじまり、最初の曲は、「気球にのってどこまでも」からスタート・・・メンバーは譜面を持たずに登場・・・おや、今回は暗譜かな?と思っていたら、手拍子があったためこの曲だけ暗譜、他は譜持ちの演奏だった。 演奏自体は、相変わらず安定したハーモニーで十分聴かせてくれる演奏だったと思う。Nコン課題曲集なので、そんなに高音や超絶技術も必要としなかったこともあるだろう。演奏された曲は、有名な曲が多くほとんど聴いたことがある曲ばかり・・・実際、私が広友会で歌ったことがある「信じる」「もう一度」も歌ってくれて楽しめた。今、歌っている「もう一度」は、Nコン課題曲当時は、アカペラ・・・今歌っているのはピアノ付きヴァージョン・・・このアカペラもなかなか良くて、定演のアンコールで歌ってもいいような感じ・・・まあ、決めるのは先生なのでどうなるかな・・・選びそうな気もするが・・・ そして、演奏終盤でサプライズとして作曲家代表で上田真樹先生が客席から登場し、いろいろNコン課題曲を作曲するにあたっての解説を、例の可愛い声でお話してくれたのは嬉しかった。 そしてアンコールは、震災ソングの「花は咲く」を会場と一緒に全員合唱・・・後ろから女子高生合唱部員の可愛い声と一緒に歌えて楽しかった。 それにしても、最後に歌った今年の高校課題曲の「メイプルシロップ」は難解な曲・・・詩を読んでみてもまったく意味不明・・・これをどんな解釈で高校生が歌うのかは楽しみ・・・ そして今後のハルモニア・アンサンブル単独の演奏会は・・・ 2015年8月16日(日)第6回定期演奏会・・・盆休み真っ最中・・・行こう・・ 2015年12月19日(土)クリコン・・・良かった、広友会定演と被らなかった・・・練習とかぶるけど行こう。 2016年3月25日(金)第7回定期演奏会・・・うーん平日・・・行きたいな・・・ 会場は全て渋谷さくらホール
2015.06.23
コメント(0)
-
タリス・スコラーズ東京公演
今日は、午後から健康診断だったため午前を有休にし会社をお休みにした。そして健康診断のあと、かかりつけの医者で月一の診察を受けその後タリス・スコラーズの公演を聴きに行くため、オペラシティへ向かい都営新宿線に乗った。時間的には2時間ほど早かったのでオペラシティにあるパブで一杯やってから行こうと思っていた。 地下鉄に乗っているところで、ある駅で外国人の方がけっこう乗ってきた。男女合わせて10人くらい・・・男女といってもなんかカップルの雰囲気はなく、観光ではなさそうな感じ・・・うーん何だろうと思って、あれ?もしかして・・・と今日の公演のチラシを確認すると、指揮者のピーター・フィリップスを含めたタリス・スコラーズのメンバーに間違いない。まさか地下鉄で乗り合わせるとは・・・話しかけようかとも思ったのだが、英語が全然話せないので諦め・・・当然のように皆さん初台で下車・・・電車移動で会場に入るんだ・・・ そして、演奏自体は、もう言葉にならないほど美しい・・・あんな美しい音楽は生まれて初めて聴いた・・・少人数アンサンブル(10人、ソプ4、アルト、テナー、ベース各2名)なので、私の周りのレベルでは、他の声を聞いて、合わせて、混じりやすい声で・・・なんて次元の演奏ではなく、一人一人が素晴らしい歌い手で、メンバー全員、楽々という感じで歌い、しかもその歌は美しく音圧もある。人間の声の美しさはこれほどまでのものか・・・ということを強く感じた。 なので、ほぼ満員の観客の反応の凄い、拍手が鳴り止まず、3回もアンコールを歌ってもらった。これほど拍手したのは私自身初めて・・・ この美しさ・・・さっそく次の広友会練習で真似してみよう・・・ちょうど練習曲は美しいロマン派の曲だしちょうどいい・・・
2015.06.16
コメント(0)
-
56回目
今日、6/15は私の56回目の誕生日・・・うーん、いよいよ還暦が近づいて来た訳なのだが、子供の頃想像していた還暦って、腰が曲がったり、けっこう老人って感じで隠居して縁側でお茶を飲んでいるようなイメージだったのだが、現状は全く変わってきている。会社でも60後半の方もけっこう働いており、今後の高齢化社会、出来るだけ仕事は続けて行きたいと思っている。 さて、合唱活動を縮小して歌う時間は短くなり、今月前半は特に合唱の演奏会も行かなかったのだが、後半は、まず明日6/16はオペラシティでタリス・スコラーズ、そして6/21は地元青砥でハルモニア、6/28はトリフォニーホールで東西4大学・・・それぞれ聴き応えがありそうなのだが、社会人になって大学生の演奏を聴くのはコンクールを除いて初めてなので、老舗私大の男声合唱はある意味楽しみ・・・現在の大学グリーはどんな演奏をするのかは、興味深々・・・ 明日は、健康診断で会社はお休み・・・午後からの健康診断後、オペラシティへ向かう・・・タケミツ・メモリアルホールも初体験でこれも楽しみ・・・
2015.06.15
コメント(0)
-
年齢から出る演奏の深み
「いろいろな人生を経験している年齢の方々だからこそ、演奏に深みがあり、感動を与える」という褒め言葉を広友会の演奏に対して頂くことが多い。また、前で指揮をされている先生も良く言われている。 しかし、これはいったい何だろう?いろいろな人生を経験すると歌のテクニックが上がるというのは、理由がわからない。最近の多田作品の練習でも、旋律に不慣れなセカンドやバリトンが歌っていると、ハミングをしながらイライラすることが多い。年取ったって、上手くならないじゃん・・・とずーと不思議に思っていたのだが、いろいろ考えてみると、もしかして次の仮説が当てはまるのかなと思いはじめてきた。 それは、ステージで演奏した数、経験値というのが言えるのかなあ・・・いろいろな曲、それぞれの状態、そして、その時の演奏における細かいテクニックや状況判断・・・これらの経験、引き出しが蓄積されて、自分であまり考えなくても、その曲の状況にあった表現ができるようになってくるのではないか・・・ これは、最近私が、大人数の男声合唱である広友会だけでなく、少人数のKFSやカンタート公募混声合唱などいろいろな経験を積んで、今までできなかったようなことが意識してできるようになって、それは練習録音を聴いても明らかにレベルアップしていることが伺えることから、この経験値の重要性を認識している。 ただし、これは進歩しようとする努力が不可欠・・・ただのんべんだらりとステージを経験しても、何も蓄積されないと思われる。そしてそれは、如実にメンバー間の実力差として現れるのだと思う。
2015.06.14
コメント(0)
-
頑張らない歌い方の重要性
これは、以前から先生がよく言われていたことだったのだが、最近、それができるようになってきたような感じで、この「頑張らない・・・」の重要性を非常に痛感している。 まず、なぜ「頑張って歌う」ことが問題なのかということを書くと・・・ ・いっぱいいっぱいで歌うため、他の声部をきくことができない。 ・ついつい身体に力が入り、音程が下がったり、響きがかげったりする。 ということで、この2点を見ただけでも重要性がわかっていただけると思う。 で、最近の私がどうなっているかというと、練習録音などを聴くと、以前より声の響きがアップしており、音程も安定してきている。他声部を聴くことができるため、アンサンブルでの出し入れが楽にできる。 やはり、音楽はある意味、冷静さが必要なのだろう・・・ で、この「頑張らない・・・」ができるようになった原因は何かと言うと、これはカンタート公募合唱団での経験が大きかった。カンタート公募合唱団は、基本的に栗友会や樹の会などの優秀な若い歌い手が集まってくる。そこに参加した私は、混声合唱初心者であったため、最初はついて行ければいいかな~というリラックスした気持ちで入っていった。これが逆に男声合唱のトップだとすると、対抗意識が働き、きっと頑張ってしまったことだろう。 で、ここで練習を重ねていく内、この頑張らない歌い方で最終的には内声テナーの重要なポジションになっていった感がある。 やはり、レベルアップを図るには、違った環境で歌うことも重要なのだと実感した。
2015.06.13
コメント(0)
-
なぜ、ソロをやりたいのか?
私の最近嵌っている吹奏楽部のアニメでは、コンクールに向けてオーディションが行われた。主人公の1年生が、2年生の先輩を差し置いて合格したり、トランペットの準主役の1年生が、3年生のパトリを差し置いてソロパートに決まったりした。そして当然いろいろ問題が発生するわけで、結局、トランペットのソロについては、ホール練習で再オーディションで部員全員の投票で決めることになった。 一見、部員全員の投票になると、人気のある3年生が有利に見えるのだが、ポイントは「ホール」・・・楽器でも歌でも同じだと思うのだが、細かいテクニックなんかは練習である程度カバーでき大きな差は生じないと思われるが、一番大きな差は、音量と響き・・・この差はなかなか一夜漬けの練習では埋まらない。そして大きなホールではその差が如実に表れ、いくら先輩に投票したいと思っても、あきらかに音に差がある場合、そんなこともできないだろうし、多分、投票の前に3年生が辞退するのかなあと想像しているのだが、さて来週が楽しみ・・・ それにしても、やはり「ソロ」ってやりたいものなのだなあ・・・なぜ、ソロをやりたいのだろう・・・と自分に置き換えて考えてみると・・・もちろん、観客を満足させるだけの自信がなければ立候補もできないのだが、なかなか自分の実力を冷静に判断するのも難しいようで、けっこうオーディションでは多数チャレンジするのだろうと思う。あと、やはり音楽をやっている以上、自分の実力を発揮したいという欲望なのだろうか?しかし、失敗したりするとなかなかダメージも大きいのだが・・・まあ、もちろん「目立ちたい」「良い格好したい」という気持ちも当然ある。そういうエネルギーも音楽の上達にはある意味必要なのかなあとも思う。
2015.06.11
コメント(0)
-
アンバランス
昨年の広友会定演のアンケートで一番気になったのは、「ベースが弱い」という感想・・・数年前までの広友会は、人数や技術的な面でもベース系の音圧は強かったのだが、ここ5年間の間に一気に音圧が落ちてきたようだ。その証拠に5年前のアンケートにベースが弱いなんて感想はほとんど見当たらない。 それとは逆に、トップの音圧が勢いを増してきている。で、この前の紅白合唱合戦でも「合唱のバランス」という面を気にする合唱人の方々からは、バランスが悪いという感想や、団員のお客さんであまり合唱を聞かれたことのない方から、右側の方が聞こえてこなかったという感想も聞いている。 最近の練習でも、非常に音響の良い閉ざされた練習会場などでは、ベースはけっこう響いているように聴こえるのだが、通し練習が終わったあとベースのある方から、トップが聞こえないという話が出た。前で指揮していた先生からは、少し頑張りすぎでトップの音を消していたようだというご指摘だったのだが、どうも根本的に今のベースは「そば鳴り」しているように感じられる。すなわち声が自分の周りで響くという現象・・・こうなると他パートの音は非常に聴こえにくくなる。 この「そば鳴り」がおこると、自分の周りだけで響いてしまうので、そこでエネルギーが消費され大きなホールなどでの演奏では声が客席に届かなくなる。これは定演や紅白での演奏の感想と一致するところ・・・ で、ここでトップはどう歌えば良いのか・・・バランスを重視しベース系に合わせて音圧を抑えるか・・・という選択肢もあるのだが、50人を超える大人数合唱団の広友会でそれをやると、音圧が物足らない、観客にしてみれば非常につまらない演奏になってしまうと思われる。実際、紅白でもステージ上でベース系が聞こえてこないのは判っていたのだが、あえて音圧は下げず歌いにいった。その結果、客席からの反応は非常に良く、作曲者の千原先生からも高評価のお話も伺っている。 定演までは、まだ6ヶ月もあるので、ここはトップは音圧を抑えることはなくいきたいと思う。先生のヴォイトレも始まることだし、ベース系の響きの復活を待つ。よしんば間に合わなくて多少アンバランスになっても、ステージ上だけのつまらない演奏だけはしたくないと思っている。
2015.06.07
コメント(0)
-
担当部署と性格
最近、吹奏楽部が主役のアニメにどっぷり嵌っている。ちょうどそのアニメの主人公は低音楽器を担当しており、そのパートの場面がよく出てくるのだが、私は中学時代に担当していたのも低音楽器のチューバ・・・そのアニメでは、チューバを担当している子のセリフで「チューバは影で支えるのが仕事」というのが出てくる。確かにそのとおり、ハーモニーの一番下を支えたり、リズムを打ってテンポを支えたり・・・とにかくほとんど脇役・・・ただ見た目は楽器が大きいので目立つのだが・・・ で、それを担当していた私の性格は、基本的に目立ちたがり・・・あまりリーダーシップはとれないのだが、とにかく目立つことが大好きだったようだ。そんな性格でよく2年半も中学でチューバを吹いていられたのだと思うのだが・・・一つの要因としては、すぐ上に先輩はいなくて、すでに1年の後半からチューバ担当が一人だったことがあるのかもしれない。上から押さえつけられることもなく、かなり自由で、地味な楽器とはいえ一人しかいなければ、ある意味、ソロ・・・まあ、もともと音楽大好きということもあり、けっこう頑張れたのだろう・・・自分では、当時よくわからなかったのだが、私の演奏はけっこう上手かったらしく、卒業した後もけっこう伝説(大げさ)になっていたと噂で聞いた。 そんな性格なので、男声合唱のトップテナーは性格にピッタリ、練習すればするほど上手くなるのは、楽しくて仕方ないという感じ・・・ で、カンタートでは混声合唱を歌ったのだが、混声テナーも役割的には内声パートなのだが、大人数で派手な曲の場合、内声とはいえ、けっこう自己主張しながら女声を支えられる・・女性大好きなので、これもなかなか良い格好が出来てけっこう楽しい・・・ しかし、子供の頃に形成された性格は、中高年になっても治らないということかな・・・
2015.06.05
コメント(0)
-
土日のこと
土曜日は、広友会の練習で先生によるロマン派・・・その練習の最初に、紅白合唱合戦で歌った千原作品について、千原先生から中館先生宛にお手紙が・・・内容は、紅白の録音を入手し聴いたところ、年齢は高そうなのだが、歌いまわしや表現に人生の重みや説得力がとても感じられじーんとしました。という嬉しいお話・・・うーん、頑張った甲斐があったというもの・・・確かに演奏後の観客席の反応はとても良い感じはしていた。まあ、まだまだ私自身の歌い方にはクリアすべき箇所は多々あったのだが・・・ その後練習開始でシューベルト、リストの2曲を練習したのだが、その真っ最中に地震・・・かなり長周期の揺れ・・・先週は月曜日に引き続き2回目となり、けっこうびびってしまった。そして練習後いつものように一杯やって帰ったのだが、地震の影響で京成線が15分ほど遅れていた。しかし、これままだ良かった方のようで、横浜方面の方はJRが軒並み止まってしまいかなり苦労された模様・・・ そして日曜日は、広島での「碑」の合同練習・・・そのため6時過ぎに家を出て成田空港へ向かう、成田から広島へLCC初体験・・・新幹線なら往復3万6千円くらいかかるものが1万3千円とほぼ1/3・・・しかも早い・・・そして余裕で練習会場に到着・・・午後1時から5時までの4時間、最後の通しも含めみっちり合わせ練習を行った。 その練習人数は80人以上100人近くいたような感じ、トップだけでも20人以上・・・広島メンネルコールは、広友会とほぼ同じ年齢構成、で指揮者の先生は、まだ若い先生だったのだが、明確な解釈にわかりやすい指揮、そして的確で効率的な練習をされており、とても良い練習だった。 それにしても、私の声は本当に百人程度の大合唱向きだということを実感した。ほとんどフルパワーに近い感じで歌ったのだが、録音を確認してもかなり良い感じで歌えている。やはり人数が多いと歌える人も多く「合唱」になっている感じがした。 そして帰りもLCCで夜9時過ぎに成田へ到着、帰宅したのが11時近く・・・ふう、疲れた・・・
2015.06.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1