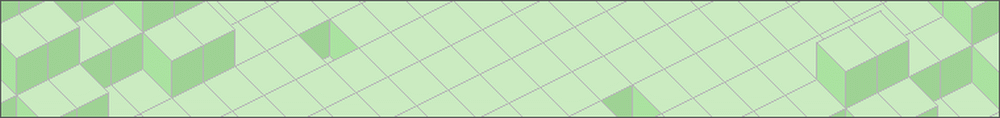2011年05月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
勇気と希望をもって毎日を過ごそう
人は誰でも、いくつかの短所があるし、悩みも持っている。 自分には 能力や才能がないからと諦めるのではなく、心をしっかりもって、心に 栄養を与えていけば成長して行くものと言われている。 毎日やることに決めことをしっかりと実行していけば、自然に成功への 道は開かれて行くものである。 毎日出来ることから、勇気と希望をもって、心に決めたことを確実に 実行し続ける努力の積み重ねによって、明るい未来を築き上げることに したい。
2011.05.31
コメント(0)
-
幸せにつての考え方
人の幸せについての考え方は、人間が成長していく過程において変わって 行くものと言われている。 一つ目は、人からやっていただく幸せである。 これは、人間が幼少のとき 親から色々なことをやってもらえる幸せである。 二つ目は、何でも自分でやることが出来るようになった幸せである。 三つ目は、人に対して何かをしてあげる幸せである。 以上のように大きく分けて三つになると言われているが、この中で最も大切な ものは、人に喜ばれることをしてあげることの幸せだと思う。 日常生活の中で 「人にしてもらいたい幸せ」 ばかりを求めているのであれば、 「人にしてあげられる幸せ」 をかみしめて、人がして欲しいことをするように 心掛けて行くべきではないだろうか。 人のため、世のためにすることは、 決して失敗することはないとの信念を抱きながら。
2011.05.30
コメント(0)
-
マラソン会練習会の情況写真
先週(2011-5-22日開催)の練習会のときのスナップ写真です。 ZKM大阪支部主催で実施された「大阪府舞洲」での近畿合同練習会 の模様です。皆さんの元気な姿を見ることが出来ます。
2011.05.29
コメント(0)
-
日頃のささやか事でも確実に実行して行こう
日頃のささやかな行動の中には、ちょっとしたヒントから悟りを開く道が多く 転がっていると言われている。 この様な簡単のことを実行して行くことに よって大事をなすことができるのではないだろうか。 私たちは、とかくすると、行為の前に難しく考えすぎて前進できない状態に 陥ってしまいがちである、そうではなくて、簡単な事でも良いから、基本を しっかりと身につけて、実行し続けるのが何よりも大切なことであると思う。 日常に起こる小事をしっかりと実行していけば、大事の成就に繋がる ものと信じている。
2011.05.29
コメント(0)
-
マラソンに関連するモニュメント
最近は国際ビジネスの関係から大阪から神戸まで出かけることが 多くなっている。 勿論 その移動には阪急電車を利用しているが、 往きも復りも疲れ切って、コックリコックリと眠りこけて人に迷惑を 掛けないようにすることだけはマナーとして守っているつもりである。 数え切れない神戸への訪問の中で新しい発見としては、神戸市役所 の前にあったマラソンのモニュメントであった。 日頃 マラソンを楽し みながら健康管理に努めている者にとって関心があったので、記憶に 残しておこうと思って以下にアップして見た。 他の地域にある モニュメンも機会があれば探索したいと思っている。 「日本マラソン発祥の地 神戸」 1909年3月21日 AM11:30 として表示されていた。
2011.05.28
コメント(0)
-
自分の輝きを表すための努力
梅や桜など植物は最も華やかな姿を表すための準備を充分することに よって、人の前に開花観賞の楽しみをつくり出してくれている。 我々人間も、自分の姿を輝きに満ちたものにするためには、その前の段階で の訓練が不可欠なことであると思う。 何事を行うにも、華やかさに繋がる裏にある、目にみえない努力を大切に して行きたいものである。
2011.05.28
コメント(0)
-
心豊かな生活
お金や物に恵まれていなくても、心が満ちておれは豊かな幸せな生活が 送れる考え方である。 人が幸せになるためには、家族構成や健康状態、保有財産、地位など によって、条件が異なるが、最も大切なものは、「心の安らぎ」と言われて いる。 しかしながら、この「心を安らかに」と口で言うのは簡単であるが、 これ程難しものはない。 どのように幸せに見えている人でも、それなりの 心の悩みや、苦しみがあって、心安らかになりにくいものとされているから である。 その原因としては、人の心の中に執着心があるからだ言われて いる。 心が凝り固まって、物事に固執することのようである。 それ故に、何事にも執着しないで、柔軟な心を抱くよう心掛けることに よって幸せな生活が送れると思う。
2011.05.27
コメント(1)
-
心に穴が空かないよう心掛けよう
人生の中で自分に係わる大きな事象が起きると、そのショックで心に 大きな衝撃を受けて沈んでしまうことが多いと言われている。一種の心の 病いで、対象喪失症ともいわれているものである。 その背景を考えて見ると、例えば配偶者を失ったときに起きる心の病いや、 自分が愛情を注いできた仕事を失ったときや、定年で急に老け込んだり、 大病にかかったりすることなどに見られる現象である。 大方の傾向としては、 一生懸命に仕事一筋に取り組んできて、趣味を持っていない様な人がなり やすいので、注意が必要である。 対象喪失症を乗り切って行くには、出来るだけ趣味を生かして、柔軟な発想 で自分自身の心をコントロールして行くよう心掛けるべきであると思う。
2011.05.26
コメント(0)
-
本当の意味での善行について
人のために善いことをするとき、善いことをすれば、人から喜ばれると 思ってするのは、悪いことをする人に比較すると、その悪いことより勝って いると思われるけれども、その善行は自分のことを思って人に尽くして いるのであれあば、本当の意味での善いことではない。 相手には気づかれなくても人のために善いことをし、将来的にも誰のため と言うことではなく、さりげなく人に尽くすことが本当の善行と言われている。 日常の生活の中で生かして行きたい事柄である。
2011.05.25
コメント(0)
-
日常の行いの大切さを学ぶ
論語から学ぶことは多いが、そのうち日常の行動の大切さに触れている 以下のような内容のものがある。 人は自分だけの利益のために行動をおこすと、怨恨の思いを抱かせて うまくいかないということである。 人間の本当の正しさは、礼節と同じように小事における行動に表れてくる ものである。 そして、小事における正しさは、道徳を根底にして生まれて 生まれてくる。 故に人を見るには、その人の日常の何でもない言動が どうかを注意して見る必要がある。 ヒントとして、いくら立派なことを言っても、日常の行いが良くないと人に 信用されないと言うことである。 普段の行動には注意して行くことが大切である。
2011.05.24
コメント(0)
-
健康を維持して行く努力を続けよう
健康を維持していくには、人それぞれに工夫と努力が必要と思う。 私の所属している「全国健称マラソン会」では、中高年の方を中心とした マラソンを楽しみながら健康な人生を目指しているグループである。 月例の練習会や全国大会に参加することによって、走友間の交流をはかる と共に健康的な話題に触れて元気をいただくことが多い。 昨日5月22日には、当会大阪支部の主催で近畿合同練習会が大阪舞洲にて 開催されて多くに方との触れ合いを楽しみ、幸せな一日を過ごすことが出来て 有り難く思っている。 来年 この場所で全国大会が開催されることになっているので、参加して 更に交流の輪を広げることを目指して日々のトレーニングに励むことにしている。 マラソンを楽みながら、健康管理につとめ、心身共に健全な無駄のない人生 をおくることを究極の目標としている。
2011.05.23
コメント(0)
-
物事の変化に素早く対応して行くことの必要性について
世の中に起こる色々な事象の変化に対応して、良い効果を上げて 行くには、自分の主義や主張に拘っていては、うまくいかない事が多い。 時と場合に応じて柔軟な姿勢で対処することが必要である。 自分の理想や考え方を前に出して、相手のことや情況を無視して、 強引に押し通すやりかたでは、うまく行かない。 自分の理想や目的は しっかりと決めておき、状況次第では左右に変化したり、一歩下がって 引いてみることも大事である。 この様な柔軟な考えと姿勢があってこそ、 物事はうまく進展していくものである。
2011.05.22
コメント(0)
-
感謝の心から穏やかな表情が生まれる
人の表情は心のもち方によって変動するものと言われている。 顔の相を作り出す心が変わると、自分の見る世界が変わってくることから、 いつも穏やかな心を持っていると、恵比須さんの様な穏やかな表情になるし、 いつも怒ったり、不平ばかり言ったり、人を陥れる事ばかり考えていると、人相 は恐ろしい鬼のよいな顔に変わってしまうものである。 人相は自分の心が つ作り出していることが分かる。 このようなことから、一日の終わりには、「今日も無事に生きることが出来て ありがとう」 と感謝の祈りを捧げることにより、心安らかに人生を歩んで行く ことにしたいものだ。
2011.05.21
コメント(0)
-
ほめすぎの効用を生かそう
この世の中には悪い人はいないのであって、自分と相性のいい人と、相性の 会わない人とに分けられるのではないだろうか。 気が会わない人であっても、褒めすぎの言葉で接することによりうまく対応して いけるものと思う。 ポイントになることは、いかにうまく接するかにある。 はじめから 「この人物 とはうまく行きそうにない」と思っていると、相手もその事をなんとなく感じて そのように反応してしまいがちである。 相性の合わない人ほど相手をほめて 見てはどうだろうか。 そうすることによって、相手も気分を良くして、話しかけて くれたり、自分の方もその気になって話しもうまく展開して行くはずである。 例えは、会議や討論をするときには、まず相手の意見を良く聞いて、認めたり、 褒めたりすることによって、だんだん気が合うようになって行くものである。 さらには、好きこのんで敵をつくってはいけない。 かえって敵と思われる人を 自分の中に取り込んで、勇気をもって対処することが必要である。 できる限りすべての人と平和に過ごすことが楽し人生への道へと つながるものと思う。
2011.05.20
コメント(0)
-
プラス思考で人生を乗り切ろう
人の行動は、心に描いたことが行動となって現れて来ると言われている。 仕事でも健康でも、あらゆることにおける力の源になっているのは、自分自身 の心の持ち方にあり、プラス思考で潜在意識を強化することにより、困難な 道を切り開くことが出来る。 潜在意識を積極的に取り入れていくには、常に声に出して自分自身に暗示を 掛けることにある。 気力が萎えてしまいそうなときでも、「私は元気だ」と言って いると、次第に現実もそのようになって行くものである。 ともかく、日常心掛けたいことは、「うまく行く」 「必ず勝つ」 「成功する」 「あの人が好きだ」 「私は元気だ」と繰り返し声に出して行くことにより、 プラス思考を高めて、人生のあらゆることに対処することにある。
2011.05.19
コメント(0)
-
叱り方には工夫が必要である
この話は子供だけではなく社会人に接するときにも通じることである。 工夫された良い叱り方は、叱る目的は行いしたその人自身の間違いを 気づかせて改めさせ、更にはその人に自信をもたせるようにすることに あると言われている。 ここにポイントとなることまとめて見た。 1.腹をたてない・・・親が叱るときは、ともかくも感情的になっている事が多い。 2.相手の身になる・・・相手に良くなって欲しい気持ちで、過ちは叱って行けない。 子供が自覚しているているときには、叱らないで、そのわけを教えることである。 3.叱ることを惜しむ・・・小言やぐちを慎み、愛情のこもった美し言葉で叱り、 後がカラットするように心掛けることである。 4.納得する工夫をする・・・原因を良く確かめる。 恥をかかせるようなしかり方は、 心を傷つける。「はか」 「グズ」 「のろま」 などの言葉ははかないことである。 5.時と場所をわきまえる・・・登校前、食事の前後、寝る前は絶対に叱らない。 食事は楽しく、夜は安らかに眠りの世界に入るべきである。 要は叱るときには、相手の人格形成に正しい効果をもたらすよう工夫が必要 である。
2011.05.18
コメント(0)
-
一日の終わりを大切に
一日の終わりを大切にしなければ、よい朝が迎えられないと言われている。 その日を良く終わることは、良く始まることにつながることなのである。 泣いたり怒ったりしたら、一日が良く終わることにはならない。 怒り疲れたり、 泣き疲れてそのまま寝てしまっては、気持ちにの上では、一日は終わって いないのだ。 一生のうちで一度しかない今日のこの日ために、ちゃんと 自分の心の中で描いて一日の終わりを締めくくりたいものだ。 ちゃんと締めくくりができないと疲れが取れない。 一日の最後を笑って 終われば、すっきりした心地で幸せが生まれてくるはずである。
2011.05.17
コメント(0)
-
世の中には欲張りすぎるとうまくいかないことが多い
何かを求めて必死になりすぎるとことによりかえってうまく行かず失敗すること があるように思える。 逆に、諦めて無欲になったときに、うまく行っていること がある。 出来事の現象からみることにする。 §名声や地位を得ようと今まで必死にやってきたことを止めたとき、両方とも手に していること。 §自分を良く見せたいということを止めたときに、その人は印象的な存在になって いること。 §何も見返りを求めていないのに、大きなものが手に入ってくること。 §子供や部下に口うるさいこと言うのを止めたときに、相手はその通りになって いること。 §自慢話や目立とうとすることを止めたときに、人から信頼される存在に なっているkと。 §権力や地位を利用した脅しを止めたとき、部下は従うようになっていること。 §有頂天のときは成長は期待できないが、打ちのめされたと感じたときに成長 がはじまること。 §こだわりすぎたりするとその奥に利己心が見え隠れしてうまくいかないこと。 ともかく 物事はあまり欲張らないでやるほうがうまくおさまるということである。
2011.05.16
コメント(0)
-
何事をなすにもその道の先生を見つけることが重要である
勉強でも、スポーツでも、その道を極めようとするならば、自己流でやって いても上達することは難しい。 やはり、何事でも、自分に適した先生を見つけて、 じっくりと基礎を身につけることから始めることが大切である。 仏教の教えでは、正しい師について、正しい教えを正しく聞くことから自分の 道を歩み始めよと説いている。 その中でポイントになるのは以下の通りである。 1.「善き師に出合うこと」・・・善き師に出合うためには縁故が必要であるが、 縁は向こうから勝手にやって来るものではないので、自分に求める心が必要 である。 2.「教えを正しく聞くこと」・・・正しく聞くことはとても難しいことである。 我欲があっては曲解していまう。 あらゆることを無にして聞き、その裏にある 真理をつかむ必要がある。 3.「聞いたことを真理に従って考えること」・・・ 頭で聞いていただけでは、 真理をつかむことは出来ない。 やはり、理論と実践は両天秤のようなものだから、 聞いたことは、行動の中でつかむことである。 先ず物事に取り組む第一歩を踏み出そうとするときには、人は人によって 磨かれて行くことを肝に命じておくべきである。
2011.05.15
コメント(0)
-
世話の意味するもの
「世話」と言う言葉の語源はインドのサンスクリット語の“セイバー”から来て いることをある会合で教えてもらった。 “セイバー”には、「横」という意味が あるそうですから、「世話をする」と言うことは、世話をする人も、世話を受ける 人も、横に並んだ同等の立場であるとうことだそうだ。 世話をしあうことで心の 安らぎを得ることが大切なことだ。 たとえ使い切れない程の財産があっても心の安らぎは得られるものではない。 心の安らぎを得るには、自分一人で生きているのではなく、、多くの人の力 によって支え合う中で「生かされている」と気づくことが大事なことである。 お互いに支え合い、世話し合って楽しい人生をおくって行きたいと思う。
2011.05.14
コメント(0)
-
楽しく生きることへの工夫
何も持たずに、ただひたすらに歩くことは理想的な全身運動になり、下半身 から来ることの多い老化現象を防止するのに最適だと言われている。 歩くことも、働くことも、楽しくやることによって効用があるのではないか。 疲れているときは、無理をしてジョギングをする必要はない。 仕事についても、 あまり体を使わずに、神経をすり減らしてしまうようなものが多いので、ストレス が溜まってくる。仕事が楽しくなるようにするためには、何か工夫が必要である。 楽しく生きて行くためには、自分の好きなことをすることが一番よい。 人は いつかは命はなくなるものと悟り切って、嫌なことがあってもいつまでも苦しむ ことなく、他の人の目を意識せずに、また、他の人と比較せずに、自分の生活 の中にユーモアとゆとりを取り入れることが、心の養生にとって大事なことだと 思う。
2011.05.13
コメント(0)
-
日頃心掛けたい素養をたかめる工夫について
簡単な事ではあるが、次の点を常に心掛けて行きたい。 1.どんなに苦しい場面に直面しても、いつも心のどこかで喜びを持つ。 2.どんなことに対しても感謝の気持ちを持つ。 3.常に人に知られない善行を目指して行くことにする。 簡単なことから始めて、常に素養を積んで、人格に磨きをかける取り組みを 継続していくことである。
2011.05.12
コメント(0)
-
人生を楽しく生きることを学ぶ
世の中には自分の思う通りにならないことが多い。 しかし、これを嘆くだけでは、ストレスが高まるばかりである。そこで、このような マイナス思考の生き方から、プラス思考に発想の転換をはかることによって、 この世を明るく楽しく生きることが大切ではないだろうか。 そのヒントとして 考えられのは以下の通りである。 1.足らないものを武器にする。 2.不利の裏にある長所を見つめる。 3.不足をベースにプラスを喜ぶ。 この世の生き方を表した教訓は、「徳川家康遺訓」より学ぶことが出来る。 「人の一生は重荷を負つて遠い道を行くようなものである。 急いではいけない。 不自由を常と思うと不足はない。心に望みが起これば困窮した時を思い出す べきである。堪忍は無事長久の基であり、怒りは敵と思え。勝つことばかり 知って負けることを知らなければ害はその身にふり掛かってくる。己を責めて 人を責めてはいけない。及ばないことは過ぎたことより勝っている」 ときには古典をひもとき人生の指針として行こう。
2011.05.11
コメント(0)
-
小さなことから始めて大きな成功を目指そう
最初からあまり大きなことを頼んでも、高い交換条件を持ち出されたり、 断られたたりすることが多い。 しかし、初めは小さなことを依頼して 引き受けてもらえば、次第次第に大きなことを依頼するようにすること によって、引き受けてもらう確率が高まって行く。このことは、心理学では、 小さな流れを「川」にして、「海」にするための「水路づけ」と言われて いるそうである。 初対面のお客様にアポイントメントをとるときに、「1時間お時間をいた だけませんか」とお願いするとなかなか承諾の返事をもらうことは難しいが、 「5分で結構ですから」と頼むと案外スムースに聞き入れてもらえるもの である。一旦会っていまうと、こちらの腕次第で時間を延ばすことも可能と なる。 何事をするにも、初めから大きな成果を期待せずに、まずは小さなことから 突破口を開くことによって、大きな成功へと展開して行くことが重要である。
2011.05.10
コメント(0)
-
やり過ぎには気をつけよう
物事は対極の形をとっているので、行き過ぎれば反対のものが出てきて 行動することに影響を及ぼすということである。 対極の例としては、善悪、長短、上下、明暗、貧富、美醜、強弱・・・・などである。 §儲けようと欲張り過ぎると、利己的になってお客は逃げてしまう。 §自分を捨てでもお客に尽くせば、その後には自然と利益や賞讃がついてくる。 §美しくなろうと必死になって頑張りすぎる人は、それ故に自分を醜くする。 §自慢ばかりする人は、その裏にある劣等感や不安がうすうす見えてくる。 §失敗したくないと慎重になりすぎると、時機をなくして結局は失敗する。 §本当のシンプルさを追いすぎると、その表現や実現は簡単でなく難しい。 §本当に人に優しくして行こうとすれば、そのため厳しさが必要になる。 §自分を磨くのに努力して苦労すれば、その後には喜びと楽しみが生まれる。 §部下や子供に干渉して説教しすぎると、逆に反発して良い結果を得られない。 以上のようなことから、物事に対応していくには再一見して取り組むべきだ。
2011.05.09
コメント(0)
-
友について考えて見よう
友の種類は大きく分けて4つあると言われている。 一つは、「華のような友」・・・・・何でも幸運なときには多くの人が寄って くるが、不運なときに本当に手助けの必要が出てくると去って行く人が ほとんどである。 このことから利害関係だけの友と言われている。 二つ目は、「はかりのような友」・・・・・財貨や身分などの軽量をいつも天秤に 掛けて、あっちについたりこっちについたりする人である。 三つ目は、「山のような友」・・・・・何を言わないでも、その人の傍らにいる たけで、心の優しさや暖かさが自然と伝わってくるような人のことである。 四つ目は、「地のような友」・・・・・このようにすれはどのくらいの見返りが 期待出来るとか、これだけすれば充分だとか計算づくめのことをするのではなく、 一方的に惜しみなく与えてくれる友のことである。 出来るだけ多くの良き友に巡り会って、良い仕事をしたりして、楽しい人生を おくりたいものだ。 そこで最も大事なことは、自分だけが求めるのではなく、人にとって自分が 良い友となるよう心掛けていくことが必要であると思う。
2011.05.08
コメント(0)
-
企業の繁栄と個人の幸せをつくり出すヒント
有名な作家堺屋太一氏の提唱されている企業づくりのための「理想」・ 「構想」・「独想」について考えてみた。 人間の本当の幸せは、自分の好んでいることを実現することにある。 働く時間にしても、一生懸命働いて高い収入を目指して行くことも、ゆとり を第一に考えて少ない所得に甘んじるのも、その個人に許された選択の 自由である。 職場として自分がその企業を好み、「働きたい」と願う人々 こそが、職員として集まる情況をつくり出すと言うことだ。 そのためには、先ず企業が何を目指しているか=「理想」を示すことが必要 である。 つぎには、それを実現するためにの手法=「構想」を明確にしておく必要が あるということだ。 そして、この理想が世の中にありふれた建前やきれい事でなく、その企業が 作り出す独自の説得力のある「独想」を伴っていなければならないということ である。 この「三想」を明確にして、これに賛同する職員を集めることが出来た企業は、 大いに有利になるという考え方である。 企業の経営へのヒントとして実践して行くべき価値があると思う。
2011.05.07
コメント(0)
-
人の生き方について
日本企業某有名人のヒントから「死に対する支度と言っても、何も暗く考える ことはない。どうせ皆死は避けられないものだからこそ、充実した人生をおくり たいと考える。 充実した人生とは、我々実業家の場合は、世の中の動き をよく見て、社会に対して何らかの有意義な仕事を成し遂げることにある。 その実感をもつことこそが、最高の幸福であり、実業家にふさわしい死の準備 だと思う。死の準備とは、人生に対する構えと言った観念論ではなく、毎日毎日 の生きる形にあるのではないだろうか。」と言われている。 人の生き方は、ゲーテよると「世俗的にはこの世を楽しく過ごそう。 すんだことはクヨクヨしない。 未来は神に任せ、つまらない言いがかりは 無視する」といったような楽天な人生観となっている。 他方、カントのように 「苦しんだ行為のみ善であり、愛を保証するものは犠牲である」と言った厭世的な 人生観がある。 基本的には楽天的に生きたいものだ。
2011.05.06
コメント(0)
-
未知のものに挑戦するときは前例の意識に拘るな
前例のない製品開発に挑戦し、前例のないマーケット方法を考案し、前例の ない活動を行い、成果を得るには、今までに前例があるかどうかに拘って いては、開発の妨げになる。 前例のない未知の市場に挑戦するのだからこそ、開発者にのみに与えられる 高い利益を手にするチャンスが生まれてくるのである。 ともかく、未知のものに挑戦するのは、リスクに挑むことであるから、従来の 思考方法で物事を判断していては成功への道に至るのは難しいと言える。 新しい自由な発想が成功へのカギを握っている。
2011.05.05
コメント(0)
-
心の持ち方次第で行動が左右される
人は「善いことができればいいなあ」と思えば体が良い方に向いて行き、 と同時に、悪いことを考えても、外からは見えないが、実際に行動しなくとも、 ふと思い浮かべることによって、知らず知らずのうちに体が悪い方向へ 向いてしまうと言われている。 人の行動を考えてみると、潜在意識として心にあることが、声を出すか 出さないかは別として言葉になり、それが神経を経て筋肉に伝わって行動に なるのだから、「何を思うか」ということが最も大切だということが分かる。 様々な事件が起こる中で、しばしば耳にすることは、「真面目な人だった のに・・・・・」ということである。 心の蔵には善悪併せ持っているので、 意識がふっと悪に触れたときに魔が差す状態になってしまうことになる。 だから、世の中で正しく生きるためには、心はいつも善いことをしようと 思っていることが必要である。
2011.05.04
コメント(1)
-
一日30分の運動で若さを保つには
一般的に「タバコの吸い過ぎの肺、酒の飲み過ぎの肝臓、運動をしない怠け者 の心臓」は病気になりやすいと言われている。 日本予防医学協会の話によおると、心臓の筋肉は、腕は脚と同じく横紋筋で 出来ており、動かさないと直ぐ細くなる。 それ故に心臓の機能が低下して、冠状 動脈の弾力性も落ちてきて、必要な量の血液が心臓に送られなくなる。 このことが、 狭心症の原因になる。 終日机に向かったまま、心臓に運動をさせない人は、狭心症の予備軍と見られて いる。 このことを予防するためには、怠け者から脱して、一日一回、時速60キロ位 の速さで歩くだけで良い。 ハードな運動をするひつようはなく、この程度の運動で 十分鍛錬されるようだ。 また、体重の60%前後は水分であり、水を一日180CCから2000CCくらい 飲むのも、健康と若さを保つ秘訣だそうである。
2011.05.03
コメント(2)
-
英語によることわざシリーズ1
現在 英語によることわざシリーズとしてまとめているので、 その一旦としてアップした。 「へたな職人は道具を責める」 “A bad workman quarrels with his tools” 17世紀頃から使われていたことわざで、道具や材料を やかましく言うのはヘタのしるしと言うことである。 我が国においては、能書家であった弘法大師は良い 筆を持たなくても書くことがうまかったので、つまるところ、 才能さえあれば書く手段に困ることはないと言っている。
2011.05.02
コメント(0)
-
ちょっとした気遣いの言葉を大切に
最近では、「こんにちは」 「失礼しました」 「ありがとう」 「またお合いしましましう」 などいった気遣いの言葉をあまり聞かなく なっているようだ。 また、電車などの乗り物の中で老人や体の不自由な人に席を譲らなかったり 足を投げ出して座ったり、乗客への迷惑もお構いなしで話し続けるひとも多く 見られる。 要するに、相手に対す労りや思いやりのなさに起因する問題だ言える。 ちょっと気遣いの言葉が自然と出るようになれは、世の中のは、 もっと 明るく過ごしやすくなるに違しがいない。
2011.05.01
コメント(0)
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- スーパーテクニック・シリーズ27.0(…
- (2025-11-17 14:10:39)
-
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- 蠍座の新月☆パワフルなリセット&変…
- (2025-11-17 18:25:15)
-