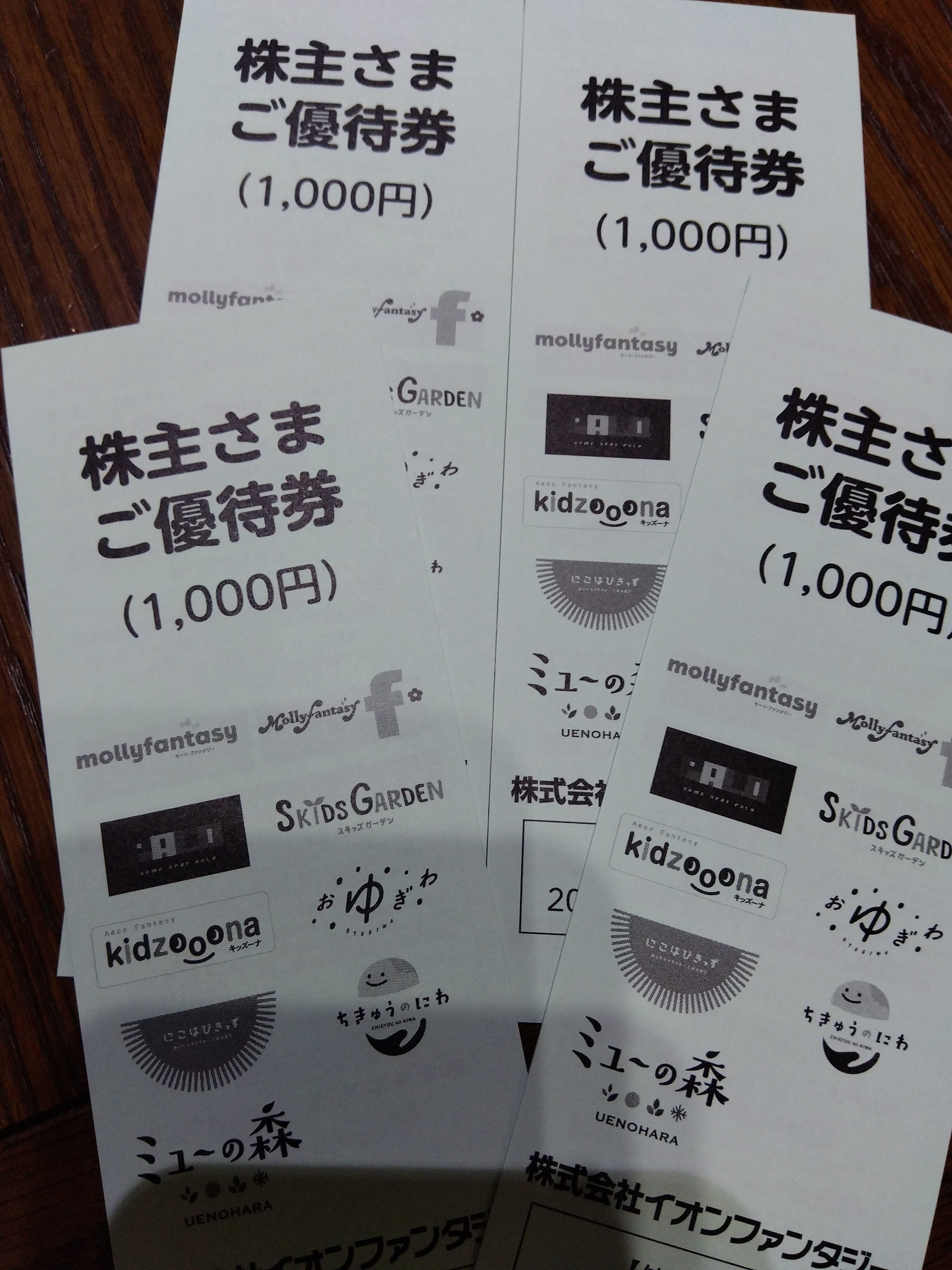2005年02月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
アジアを泳ぐように生きる
こうして上海に通うようになってみて改めて思うのは、「近いな」と。<地方の一部>という感覚にもなる。実際に、上海のオフィスに行くよりも国内の方が時間的に遠い場所は結構たくさんあるはず。おまけに航空運賃もほとんど変わらない…。そうなると、かつて昭和40年代に新幹線や国内線の利用が盛んになって、全国に<支店>や<営業所>が増えていったのと同じように、これからは、ヘンに「海外進出!」と気張る度合いが多少は減って、<支店><営業所>感覚に近くなっていくのかな、と。かつては、大企業だけが世界中に進出して、常に景気のいい国相手に商売ができた。しかし、これからは、中小企業でもこうして進出できるようになったのだから、素晴らしい。逆に大規模な工場などがいらない分、身軽に移動できる。考えてみれば、デフレの中での商売は大変な職種もあって、コスト争いに巻き込まれたら…体力が弱ってしまう。インフレな国や地域限定で商売をする…という手もある。または専門によっては逆も…ある。(ハゲタカファンド系など)企業によっては、そういう仕事を事業部ごとに振り分けてインフレとデフレの地域でバランスを取っていく…。人間も、インフレで大混雑系が好きな人もいれば、のびのびマイペースが好きな人もいる。景気は国を超えて移動していくから、それに合わせて人間も好きなところで暮らしたり仕事したり…そういうことを実際にしている人と出会うと「なるほど!」となる。極端な大金持ちであれば驚かないが、限りなく自営業に近い人で、実はひょうひょうとアジアを泳ぐように…というのが印象的だった。色んな生き方・価値観があるんですね、本当に。
2005/02/27
コメント(0)
-
念願の上海オフィスで活動開始!
日々進化する上海のサービス。90年代を知っている方々は、信じられないくらい良くなったと聞く。仕事で呼ばれて出張で通うのにはそろそろ限界が来た。きめ細かなサポートができないからである。本格的に腰をすえて仕事するために<オフィス>を借りることにした。宿泊を兼ねたマンションオフィスは卒業して。5年後に迫った上海万博に向けて市内でも様々な活動が活発化してきているし、F1も毎年開催されるし、テーマパークもできるし、色々なビジネスの機会がある。レジャーサービス的年代で考えてみると、70-80年代的なポジションだろうか。でも万博は60年代だから、日本の30年分を10年でやってしまう勢いだ。そうしたプロジェクトにも対応しつつ、ベースは、市内の商業施設を中心に運営コンサルタントとしての活動が中心になる。その中でも比重が最も高いのが人材育成のお手伝いだ。なぜ人材育成…俗に言う教育なのか?と言うと、最も違いが出やすいからである。あるレベルに育成するのに10年かかる会社もあれば1年でできてしまう施設もある。今の時代にこれほど「差」を出せる分野はそうあるものではない。これは個人に置き換えても同じこと。さらに貪欲に学習すれば、まだまだバージョンアップできるし、違った未来が切開ける可能性が高くなる。…ということで、当面はこちらから出向いて現場のお手伝いをしているプロジェクト仕事と、「スクール」あるいは「塾」のように通える場の提供と2つを中心に活動していきます!
2005/02/25
コメント(0)
-
上海おとこ祭り開催
トイレが流れない…。シャワーの排水が流れない…。…と、短期間に生活のインフラの大事さを学習しました。そして、今回はついに「停電」です。夜中の2:00に突然電気が全部止まりました(汗)。懐中電灯もロウソクも上海の部屋には用意してないのでまいったなぁ…と思っていると、唯一、明るい光が…そうです。ノートパソコンの画面の明かりでした。こうなると、パソコンのバッテリーが切れるまでの時間に何としてでも修理しなくてはならない、と。なぜなら、エアコンも止まって凄く寒かったからです。すかさずスキー用の靴下からエアテックのコートまでのフル装備に着替え、ライターとパソコンの明かりを頼りにブレーカーを探します。けれど、全然ダメ。バッテリーは段々減ってくるし…。こんな真夜中に誰かに電話して…も非常識だし…。さらに、こうしたトラブルに耐えうるだけの中国語力は全くないし…。一服しながらもアレコレ考えます。そんなことをしているとライターとパソコンのバッテリーの残量があとわずかとなり、意を決して電子辞書を片手にマンションの警備室にいざ出陣!24時間体制のはずだから。警備室をのぞくと「どうした?」とおじさんたち。「晩上好」とあいさつは言いとしてブレーカーが落ちたらしい。点検してもらいたい、なんて言えない。気がついたら「エアコンが没有(ない)」「テレビも没有(ない)」「あかりも没有(ない)」と「ない」を連発。おじさんたちは最初は「没有?????」「盗まれたのか?」と。「いや違うって。突然没有になったんだ」といったら、「あーなるほど、●□△×*」ということで、おじさんたち3人を引き連れて部屋に。部屋を確認するもやはりダメみたいで、外に出てなにやら電気室みたいなところでゴチャゴチャやっている。そのうちに「パッ」と電気が戻って来た。異国の地で冬の深夜の停電からの復活は予想以上にうれしかった。「謝謝」の連発で、ついでにお茶をいれて差し上げる。一応飲んでくれた。その時、復活したプロジェクターから壁一面に画画像が映し出された。実は停電の時、ちょっと息抜きで「PRIDE」のDVDを観ていた。それを観た中国人の3人のおじさんたちは「なんだこれは?」とかで、最初はちょっと残酷に見えたのか少ししかめ面をしたりしていたが、そのうちに「おお!」とか「やれ!」みたいな声援が狭い部屋に木霊した。さらにPRIDEのド派手な入場シーンには圧巻だったらしく、段々とのめり込んで行き、結局は、最後の試合まで全部見て帰っていった(笑)。「日本には凄い番組があるな」みたいな言葉を残して…。こうして<上海おとこ祭り>の幕は閉じた。もちろん、空はすっかり白かった。停電のお陰で中国に3人の格闘技仲間ができたのだから幸せもんだ(笑)。3月は<PRIDE29>を持参しなければ…。アジアの女性たちはヨン様でつながった。男たちはPRIDEや格闘技でつながる…のかなぁ?P.S.やはりミルコが人気だった(笑)。
2005/02/24
コメント(0)
-
楽しく勉強できるオフィス環境を
最近は、せっかく毎月上海に向かうのに飛行機に乗るから、できるだけ隣り合わせた人と話すようにしている。(迷惑そうならすぐにやめる:笑)中堅の商社に勤めていたKさんは現在、独立して起業して、上海にも進出しているらしい。正確には、上海の企業の仕事が多いから段々と上海に来る回数が増えて来た、と。日系企業と仕事をしているのかと思いきや、上海とか台湾の企業からの依頼が多い、と。どんな志やビジョンがあって独立したのか?興味津々に聞いてみると、「課長に昇進して残業代がつかなくなったから…」だった(笑)。なんともシンプルなご意見だった。こっから先は独立した方が得だな、と判断したとのこと。30代半ばでこういう思考の人は実は多いらしい。(Kさんの周囲には)その商社では、課長になると部下もたくさんいて、残業代がつかないけど、何しろ大変な労働時間とのこと。タダでたくさん働くんだったら独立した方がいい、そう考えたらしい。「そういう人がたくさんいたら社内に課長が少なくなりませんか?」と聞くと、「ハイ、たくさん辞めて少なくなりました。だから、課長は中途採用が多いんです」とのこと。それで収益が向上していればいいけれど、そうではないらしい。残業代もさておき、多分、重労働ばかりで憧れる存在に写らないのだろうと思った。ハードワークでも、なにやらかっこよく見えればそれはそれで憧れにもなるが、「給料も安くて大変そう…」では、誰もなりたいとは思わないはず。会社はこういう視点を忘れがちだし、課長個人も頑張って憧れるような仕事ぶりを見せなければいけない。会社も辛いままを放っておくからこうなる。または、課長も辛いなら勉強して視野を広げなければいけない。こういうご時勢だから、誰もラクな人はいないはず。ただし、勉強は辛いものでなく楽しくやりたい。(続かないから)日本には中間管理職のやりがいがたくさん詰まった「課長、島耕作」シリーズがある(笑)。(部長編、取締役編もある)今こそ、読み直してもらいたいものだ。真面目な話で、こうしたサラリーマン、会社員、OL系の漫画を社員が自由に読めるようにオフィスに全て揃えている会社がある。棚に並んでいる光景を見ると、日本にはこういうまじめな仕事系の漫画が本当にたくさんあるんだなぁ、と、ビックリする。映画でもテレビドラマでも、参考になるものはなんでも使う。日本は質の高い番組がたくさんある。「プロジェクトX系」から「ガイアの夜明け」とか、主人公の職場が「ホテルサービス系」もあれば「代理店」「レストラン」が舞台だったり…。そういうのを昼休みと言わず社員が見て勉強している。社員教育と言うと、何やら硬く考えがちだが、やわらかいものがあってもいい。本やテレビにDVDレコーダーなど、全員を定期的に研修に行かせることを考えれば遥かに格安である。(僕たちもこれを実践しています:笑)「○○業界」「企業経営…」「○○マネジメント」などのビジネス系もいいが、こういうユニークな環境もあるんだなぁと。ようするに楽しく元気に仕事をしてもらえればいいのだから…。
2005/02/22
コメント(2)
-
バブル時代のノウハウも役立つ
中国で仕事をしていると…「上海だから…」「中国人だから…」という議論になりがち。確かにそういう側面も多々あるのだろうけど、忘れがちになる視点もあって、上海のような「バリバリのインフレ」の地で、かれこれ10年間も「バリバリのデフレ」の思考では噛みあわないことが多いはず。イケイケゴーゴー!の上海ではスピードも求められるし、そこで日本のお家芸と言われるようなスタンプラリー型決済では「間に合わない」とか「じれったい」となるのは頷ける。イベントの企画だって、デフレ思考丸出しで、何しろ常に頭にコストを置いて、できるだけ小予算で…を合言葉にしていたら、やはり「やらない方がまし」ともなりかねない。人件費が高いから…DVDで…ではなくて、たくさんのダンサーに踊ってもらおう…などなど、日本ではできないことができたり。何よりも命中度が求められる日本では散弾銃のように「取りあえずやってみよう!」の上海と思考が噛み合わないシーンが多々ある様子。それがいきなり「中国人が…」となってしまうのは、こうした時代と経済の背景の違いが抜けてしまうからかな、と。「染み付いた10年は結構強力」ということかもしれない。けれど、落胆することはなくて、僕たちの引き出しには、あのバブリーなノウハウもギッシリ詰まっている。少しページをめくって熱かったあの時にのモードに頭を切り替えればよい。レジャーサービス業でも同様で、あの頃、何をしたかったのか?何が欲しかったのか?何かかっこよかったのか?…思い出すだけでも楽しい。考えようによっては飛行機で2時間半くらいでデフレとインフレの両方の仕事ができるのも楽しく貴重な体験だ。
2005/02/21
コメント(31)
-
自由へのパスポート
今回は、上海の人々がどんな風にケータイと接しているのか?改めてジックリ観察している。学生から20代くらいの女性たちの使い方は、なんとなく日本でみる光景と似ているような気がする。「話し好き」で「メール好き」それに「写真好き」と。どれを取っても日本のそれに負けないであろう…と実感できるほど生活の一部、手足のようにも写ってくる。ずーっとそういう観察をしていると、「着メロ」「メール」「写真」「壁紙」…と、日本の女性たちが「チョー、かわいい!」とかいいながら進化したソフトの威力を実感する。ケータイ自体はどこにでもあるものだが、付加価値(楽しさ、かわいさなど)を増幅させて新商品にして日本から世界に広まってしまうのだから恐れ入る。こういうのを企業内で会議室で企画しようと思ってもなかなか難しい。ヒントは街中にある…ということだろう。ケータイのボディにオリジナルなデザインして、マニキュアと合わせてしまう…ところまでいくと、つくづくユーザーが勝手に進化させていくユニークな商品だなぁと。もうすぐ中国も「3G」世代になるとか。約4億台弱に迫るケータイで本格的にインターネットが出来るようになると、これまたどのくらいの変化が起こるのか?人々の暮らしはどう変わるのか?情報の自由化はどのくらい進むのか?どのくらいのビジネスチャンスがあるのか?または衰退するのはどんな業種か?…ちょっと想像がつかないけど、ある意味で、中国の改革開放の総仕上げとなるインパクトを持つのがケータイかもしれない。いずれにしろ、ケータイは中国の人々にとっては、個人の自由へのパスポートにも見える。それほどの商品は他にないかも。
2005/02/20
コメント(0)
-
上海万博の後は…
上海は予想以上に寒い。まだ来たことがない時、上海は暖かいところだと思っていた(笑)。地名からなんとなくそんな想像をしていたのだ。寒いなら寒いできちんと寒い?北の方へ行ってみたいなぁと。寒さが絵になるというか、楽しめる所がいい。そうでなければ南の暖かい所へ少し避難したり…。都会の寒さって、あまり楽しいことがないからそんな心境になる。上海は冬寒くて夏は暑い…の幅が東京よりも大きい(体感的にも)から、これからのレジャー産業が楽しみな街だ。あれもやりたい、これもやりたいと、もう考えただけでも頭が一杯になる(笑)。人もたくさんいるし、活気もあるし、万博の後は商業が少し行き詰って、代わってエンターテイメントシティに変貌するのかな?
2005/02/19
コメント(0)
-
オリジナリティを表現する
最近、名刺交換するのが楽しい。知名度の高い大企業は別として、そのほとんどの企業の社名も仕事の内容もわからない。だから、中小の方々、自営業の方々の名刺には創意工夫が詰まっていることが多い。単にデザインだけかっこよくても、名刺ホルダーの中では「その他大勢」に埋まってしまうし。それでユニークな名刺をもらうと色々とヒアリングするようになった。名刺交換して、「どんなお仕事をされているんですか?」と聞かれるようでは、名刺の機能が弱いということになる。最近の僕の周辺のトレンドは、企業としての正式な名刺はそれはそれで持っているが、事業部ごとに仕事内容が人目でわかるような名刺も作成している企業が増えてきた。所属する「部署名と仕事」をあの名刺のスペースでどれくらいわかりやすく紹介するか?現場で働く方にはこれが大事になる。あるレジャー施設でも、事業部がいくつもあるから、事業部ごとに名刺がある。パソコンで作れるから、部署単位で工夫されていた。ポイントは、毎月「裏面が変わる」ことで、イベント情報なども入っている。施設の写真も入っている。それは見ていて楽しいし、すぐに覚えられる。この効果は絶大で、名刺交換後にメールのやり取りをする率が圧倒的に高くなった、とのこと。こんな小さな紙の世界だけど、その人たちの真のオリジナリティ度が現れている。「この人たちと仕事をしてみたいなぁ」と思ったり。こうした色んな創意工夫を目の前にすると、少し仕事の楽しさを再確認する気がする。僕らも見習って、新しい名刺を作りました。お会いしたら交換しましょう!(笑)
2005/02/18
コメント(0)
-
社内用語・専門用語の教育が違いを生む
社内教育が行き届いているのかどうか?の目安は「専門用語」「社内用語」をきちんと教えているか?がポイントになる。「社内の風通しをよく」「コミュニケーションこそ仕事の核」など、わかっちゃいるけど肝心なこと<共通言語>が放置されたままのところが目につく。(これでロスしている生産性は…恐ろしい)これは中国に通いだして、毎度のことながら言葉が単語がよくわからないで苦戦続きだから、特にそういうことに敏感になってきたのだと思う。それと、他社他施設に訪れると最初の打合せの時に実感できる。「???」が多いところと、「ちなみにここでは○○という意味でこの言葉を使っています」と丁寧なところ、と。それに加えて、多少の方言や職場の流行語、それに若者言葉?などが混ざり合うから国内でもより真剣に耳を傾けて、時には<一握りの勇気>を持って「○○ってどういう意味ですか?」と質問しないときちんとコミュニケーションできないことがほとんどだ。けれど、勇気の無い人や出しづらい人はそれは質問はできないから…「お前、なに聞いてたんだよぉぉぉぉぉ!(怒)」と罵声を浴びせる結末が待っていたりする。けれど、そういった配慮が行渡っている会社は、できるだけ専門用語は使わない配慮があったり、時に「用語集」を事前に配布しておいてくれたりするから、その<質>は天と地の差がある。当然、そうして行われた打合せから生まれるモノに大きな違いがることは言うまでもないかもしれない。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~仕事の生産性のアップのハウツウは色々あるが、その手前には、簡単だけど大事なことがあるんですね。これも生産性の向上には大変効果的で、それを測定するのは難しいけど、よーーーーく見てみると、膨大なんでしょうね、きっと。ある企業実験では、共通言語の徹底だけで、収益が120%もアップしたという事例があるくらいですから、あなどってはいけませんね。もちろん現場のサービスなどはさらに向上するでしょう。副産物としては、退職率の低下なども…。調べればもっと色々あるでしょう。なにしろ、新人さんにわからないこと、通じないことはお客さんにもきっと通じてないことが多いのだから、そういう意味では新入社員の教育ってもっと大きな視野でみないとならないのではないでしょうか。
2005/02/17
コメント(2)
-
両先端への投資
ブランド化というと、内装の質やデザイン、広告宣伝活動に重点が置かれてとかくこういうことが多い。そして、たいした効果を得ずに終わる。製造から販売サービスまでの流れにブランドを溶け込ませなければならないのに…。たいてい両端と言われる工場と販売サービスがおいて行かれる。対象外みたいな。そもそも両端という発想がどうなのかな、と。両先端ではないだろうか。なぜそうなるのか?と言うと、担当者が興味ある分野に走ってしまうことにある。真のブランド化目指して全体にどんなバランスで資源を投資するか?そういう視点に立てるようにならないければならない。
2005/02/15
コメント(0)
-
人気水族館を支える技術
●日本は水族館王国「人口一人当たりの水族館の数が世界一」沖縄に訪れる観光客の2人に1人が訪れる場所がある。沖縄県那覇市にある「美ら海水族館」・2002年開園・年間来場者数 280万人客を呼ぶのは世界一の巨大水槽。総水量、実に7500トン。まるで大きな海の底にいるような迫力は、まさに魚のテーマパークだ。しかし、未だ人気の衰えを知らない水族館人気カギは、ある男たちの熱い挑戦があった。上野動物園に日本初の水族館の記録が残っている。「うおのぞき(魚覧室)」1882年の開園と同時に、動物園の展示の一つとして、魚を見せる「うおのぞき」が誕生する今まで無かった生きた魚の見世物。しかし、それを一大集客施設に変えるあるアイデアを持った男が現れる。日本の映画に君臨した、日活の帝王、堀久作氏(元社長)だ。アイデアを思いついたのは江ノ島だという。場所は江ノ島当事まだ、人の寄り付かない漁村だった江ノ島。堀はこの江ノ島を一大観光地化する秘策を思いつく。その集客の目玉は「水族館」そこにはある秘策が。アメリカの映画スタジオで映画用のイルカを飼っているのを見ていた。「これだ!」と思ったんでしょうね。伊豆沖でイルカの捕獲が始まった(1956年)。江ノ島まで陸路およそ100km。イルカが箱根を越えた。寂しかった江ノ島に人々が溢れた。そして、堀氏の真骨頂は…、「イルカショー」映画人ならではの発想が、エンターテイメント性溢れる娯楽施設へと変えた。長嶋茂雄氏が現役選手を引退した1974年。水族館人気を不滅のものとする、画期的な水槽が造られた。360°水槽で囲んでしまうという、斬新なデザイン。(回遊水槽)ガラスでは不可能な形状を可能にしたのは、あるプラスチックメーカーだった。その名は「日プラ」使ったのは、最新のアクリル技術ガラスにはない「柔軟性」。どこまでぶ厚くしても保たれる高い透明度が高い水圧に耐える水槽を可能にした。客の減少が水族館は経営好調。挑戦者たちの戦いが今日も客を呼び続ける。~~~~~~~~~~~(テレビ東京:「ワールド・サテライト」より)ちなみに、この日プラという企業の技術のお陰で日本はもとより、アジア各国の水族館で回遊水槽で楽しむことができるようになった。そういえば、大連の水族館もあった。上海も…。素晴らしい日本の技術である。それにしても、水族館でも「映画業界」の出身者がその基盤を作ったんですね。やはり楽しませることにかけては映画業界の人々の功績は本当に大きいと実感します。
2005/02/13
コメント(30)
-
F1雑誌は発展途上中!
前回、上海に行った際にも大好きなF1雑誌を買いました。心の中では「中国だから…」と、紙の品質やらカラー写真もあまり期待はしていませんでした。だって、12元なんです。ところが、ビニール袋を開けてみると、意外や意外、日本の雑誌と遜色ないレベルの質で、さらに記事の構成なども見劣りしない。ちょっとビックリです。F1の記事はこれは書こうと思うと結構大変だし(何といっても知識がいる)インタビューを取り付けるのも、F1デビュー一年目の中国人ではなかなか大変だろうに、と。ところが、よくよくまじまじと表紙を眺めてみるとその理由がわかりました。やはりというか、日本のF1雑誌との提携だったんですね。どうりで…ね。ちなみに、この分野ではやはりモータースポーツ後進国なので、記者不足のようです。(自称記者はたくさんいるらしいけど…)中国国内の記事には信憑性がイマイチのようで。馬力とか最高速やドライビングのフィーリングなどもどこまでが本当なのか?と(笑)。なんど競争しても、POLOじゃフィットには勝てませんよ。いずれにしろ、雑誌もまさに発展途上のど真ん中といったところですね。ほとんどのジャンルではコアなファンは雑誌で育つから雑誌の進化がそのままそのスポーツの人気に影響します。中国人の記者の方々には頑張ってもらいたいものです。その他、Car雑誌も数冊買いまして、これもやっぱり提携でした。違いは、CDやらシールやらの付録が凄い。小学5年生の雑誌を買った気分でした(笑)。何しろ日本人にとってはお得感があるります。自動車王国だから、その周辺の産業にもこうしてチャンスがあるんですね。今年も上海GPが盛り上がりますように!(仕事的にもしっかり関わろうと虎視眈々です:笑)ということで、研究しまくってます。
2005/02/11
コメント(0)
-
採用基準「通勤距離」
採用の時、「できるだけ通勤距離の近い人を…」という選考基準が多い。これには別に悪気があるわけではなく、単純に近い方が「通勤がラク」で、シフト勤務の仕事では、早番、遅番と電車の時間を気にしながらの仕事は辛いだろう。それに、電車一本乗り遅れると、これまた遅刻しやすいし…、などの理由が大きい。あわせて、それにかかる<定期券代>が高額になる…という理由もあるだろう。ところが、この12年間、色んなお店や施設のお手伝いなど周囲を見渡していみてわかったことは、意外にも長距離通勤者の方が遅刻が少なくて勤怠がよい、安定している…ということである。近い人の方が、何かと遅刻をしたり欠勤したり…が多いようである。(そうでない人もいるが、比率として感じる)朝も長距離の人の方が早く出社して、さっさと掃除したりコーヒーいれたりして、後から出社する人々にとってはありがたい存在だったりする。勤怠の安定度では上かもしれない。(あくまでも人によるところが大きいが)なぜだろうか?それに、電車通勤を利用しての読書量が多かったり…で、こうなると、1万円くらい多くなる通勤費なんてあまり気にならなくなってくる。なにより、毎日確実に出社してくれる安心感には変え難いものがある。通勤定期代をケチっている場合じゃない。正確なその理由はわからないが、そういう事実があるので最近は採用の時に「距離は気にするのは辞めましょう」とアドバイスしている。それと、なんと言っても距離以前の問題として、コンディションが安定している人。もっと言えばタフな人を採用する方が重要かもしれない。面接の時には、「身心ともに健康です」とハキハキしておいて、入社して半年もすれば本当の病気とは違う、「ちょっと具合が悪いので…」と電話やメールで欠勤しだす人もいるので要注意である。よって、採用時の注意点はこちらに注がれる傾向にある。
2005/02/09
コメント(28)
-
バブル後の中国にかける人々
先日、ある人から中国人のビジネスマンを紹介してもらった。「所長さん、ユニークな人がいるよ」ということで短い時間だけどお会いしてみた。なにがユニークかというと、昨今の日本人と逆の発想をしている点である。その方、張さん(仮名)は、かつて日本に留学していて、そのまま日系企業へ就職。しばらしくして、親戚友人一同が「これからは中国の方が凄い。儲かる。チャンスがある」とのことで、退職し帰国。上海や蘇州でビジネスを展開していた。それでそれなりに儲かった。ところが、仕事をすればするほど疑問だらけになった、と。なぜか?と言えば、やはり日本で働いていたことが大きく影響しているらしい。つまり、張さんからみても中国の発展は「?」が多くて、儲かればそれでいい…というのがどうも納得できなくなってきて、日に日にそれは大きくなった。張さん曰く「中国で稼ぐのは、あまりにも簡単だった」と。どんどん集まってくる外資。買っては売れるマンション。いくらでも安く取替えがきく田舎の小姐たち。張さんは、このままでは2010年以後、本当にビジネスマンとして通用するのか?不安になったらしい。こんなのは日本やアメリカを相手に考えれば通用しないことばかりで、中国国内で成功しても、そのノウハウは世界には通用しないのでは?と。彼は実力指向なんですね、きっと。でも、ビックリするのは、同様に考えている人々が多数いるとのことです。それで、会社や財産を全部整理して(売って)日本企業に再就職して再来日したらしい。バブルの後の仕事の仕方を先に体験しつつ勉強しておきたい、と。さらに2010年以降の中国に必要な起業の準備も。日本にはバブル後の様々な事例がたくさんあるし、l省エネ技術も素晴らしいので、そういった視点で勉強しておくことが自分の未来にきっと役に立つということだった。そして、印象的だったのは、中国で起業するのは本当に簡単だし金儲けも難しくなかった。けれど、本当に社会に役立つ企業を作りたい、とのこと。これは難しいし、奥が深いと。当面は、そういう志のある日本企業を見つけたので入社し、その企業の運営や風土などをしっかり吸収したい、と。こんな人もいるんですね。こういう人にお会いすると「中国人って…」と言うのはあまりにも乱暴で考えてみれば13億人もいるのにワンパターンなはずないですね。いろんな人がいるわけです。お互いに(笑)。
2005/02/08
コメント(1)
-
日本が世界に誇るソフトとは…?
2010年の万博実現に向けて上海市がまずは最優先に取り組みだしたことは…警察の改革である。より「サービスと管理」を充実させよう、ということで、大変な努力をしているようだ。これは万博会場をどのようにするか?以前に最も大事なことで、市全体の安全性がなければ、とても開催できない。そこで、ニューヨーク市と同じように日本の警察のソフトを積極的に導入している。「110番」である。市民が110番通報をしたら、警察官がすぐに駆けつけてくれる。常に巡回をしていて、最もちかくにいるパトカーが急行する…。それだけではない。日本でも効力を発揮した「警視庁24時間」みたいな番組を真似して積極的に取材協力をしている…どころではなく、なんと警察署で番組制作をしているというから驚く。プロデューサーも警察官だ。視聴率も気にしているところが凄い。こういう番組で、新しい犯罪を市民に知らしめ注意を促すと同時に、「このくらい取締りを強化してるぞ!」というアピールにも威力を発揮しているらしい。日本と違うのは、そうした警察のサービスをありがたがる人もいれば、110番通報がエスカレートしてしまい、なんでもかんでもすぐに呼びだされる。駆けつけた時の態度も「遅いじゃないか!何やっているんだ!」と、段々調子に乗ってくることらしい。10年位前の警察からは考えられないくらい警察官の態度は良くなって喜ばしいはずなのに…と、ぼやきも聞こえてくる。それでも何しろ治安の安定こそが先進国への道とばかりに頑張る人々がいるわけです。日本のソフトはこんな所でも役に立っているんですね。ちなみに世界では日本の警察のこうしたソフトを真似している国や地域が増えてきているらしいです。
2005/02/07
コメント(0)
-
金メダルと万博の関係
かつての万博では、美術・家具・繊維・機械など部門別に審査され優秀な企業にはメダルが授与されていた。アドルフ・サックス氏は、自らが発明した楽器で1855年の万博でメダルを受賞。文字通り、サクソフォンである。俗にいう「サックス」。それがきっかけで世界中に広まっていった。今では、大変メジャーな楽器の一つとしての地位を築いている。さて、万博と近代オリンピックはどこでつながっているのか?そこには一人の人物の存在があった。フランス人のピエールド・クーダルダン男爵のちに「近代オリンピックの父」と呼ばれる人物。エッフェル塔建設で有名な、1889年の第4回パリ万博や1893年のシカゴ万博に関わった展示品の品質を競い合う万博にヒントを得て、スポーツの祭典オリンピックを思いついた…と言われている。彼の提唱により、第一回の近代オリンピックがアテネで開催されたのは1896年のこと。1900年の第2回パリ大会から1908年の第4回ロンドン大会まで万博と同時に開催された。オリンピックで勝者に与えられる金メダルは万博をヒントにしたものだったんですね。~~~NHKBS1の番組より~~~なんでもそうだけど、ルーツを調べてみると「へぇー!?」がたくさんあるものです。それが楽しいんだけど。実は知り合いの大先輩が北京オリンピック関連の仕事をしているので、最近、メダルとか当たり前にみていたことに興味があります。また、競技場の運営の研究にもはまってます(笑)。余談ですが、北京は黄砂やら埃、それに何しろ公害で空気があまりよい状態ではないので、選手は大変だろうな、と。それと、屋外競技の際の競技場のコンディションにも注意が必要のようです。滑ったりしないように…。だから、また新素材など、日本の技術が大活躍するみたいです。
2005/02/06
コメント(27)
-
レジャ研塾のきっかけ
30代目前の頃、あるアメリカ人のカレンさんというトレーナーと出会った。(アメリカの大学で心理学を教える傍ら、絵本作家だったらしい)素晴らしく楽しい研修を受けることができた。後日、そのカレンさんのマンションで勉強会が始まった。少人で数ほぼ毎週「サービスのこと」「トレーニングのこと」「表現力のこと」…なんと一年間続いた。まるで中学生時代通った「塾」のようだった。もちろん有料だったけど、生まれて始めて勉強が楽しいと思った。ある時はゲストを招いてのサロンのようでもあり、お茶を飲みながらカフェのようでもあり…。講師を聞いたりゲームをしたり、ビデオをみたり…。他社他業種の人たちと少数で参加して、勉強会が終了するといつも飲みに行って語り合った。年上が多かったせいで、社会勉強になった。その経験が現在の研修講師のベースになったのは間違いない。それ以来、なんとか協会が主催する「○○セミナー」にはあまり行かなくなった。(それまでは結構オタクだった:笑)ただ聞いているだけで、数十人の中に埋もれていてもあまり役に立たないと思ったから…。あれから十数年。大好きな格闘技をみていて気がついたことがある。かつては新日本プロレス、全日本プロレスという団体に選手は就職して、毎週のように巡業して練習して…とまるでサーカス団のようだった。ところが現在では、そういう団体はどんどん崩壊して、高田道場、吉田道場、○○キックジム…など、一流選手はジムや道場を主催して、次世代の選手や社会人、学生、子供たちに武道やレスリングとして指導している。もちろん自分自身もそこで鍛えている。さらに、お互い自信が他のジムや道場に稽古に通う。柔道やボクシングなど。(月謝を払って)それでいいざ「PRIDE」のような大きな大会やイベントがあると、出場していく…。なんとも素晴らしいシステムになっていった。そういうのを見ているうちにカレンさん宅で行われていた「塾」を思い出した。社会人になったからこそ、こういうのがもっとあればいいのに…と。学生時代とは比べ物にならないほど、学びたいことがたくさんあるし。(問題は次から次へと起こるし…)それで、自分たちも塾のようなものを始めてみようと…。そして、別の人の塾にも通ったり…。そういうことがしたいので、上海で始めてみた。少数でビデオをみたり他社事例を研究したり…。約20年。テーマパークやホテル、レストラン…などの文化・商業施設の計画とマニュアル作りとトレーニングをしてきたことが十分に活かせる場所があったら…と。塾なのか、サロンなのか、道場なのか…名称はさておき、こういうのは、色んな業種の人が立ち上げれば面白いのに…と。また来月も準備していきます!
2005/02/05
コメント(6)
-
今日の責任者は誰だ?
なにかしらの施設(お店とか○○センターとかホテルとか)を造ると支配人とか店長かと事業部長とか…そういうトップの人がいて、その下に副店長かとマネージャーとか副支配人とかそういうフォーメーションになる。それで、支配人の業務とは…マネージャーの業務とは…などの仕事の役割の分担みたいなものが必要になる。しかし、開けてみると意外といい加減なところが多い。ひとえにトップが総責任者だから、なかなか分担してくれないことが原因。こういう仕事は誰がOKすれば進めていいのか?クレームは誰が最終的に対応すればいいのか?返金などは誰の許可でいいのか?現場の仕事を進めていくと、様々なことが起きる。少なくとも全部をトップに了解を取る必要はない。けれど、たいていの場合後になって「なぜ、勝手に判断するんだ!オレは聞いてない!」となるから、皆怖がって、何でもかんでもトップのお伺い…となってしまう。だから、現場では支配人以外、誰も即決できない人ばかりが働いている…そういう施設は意外に多い。昨日までは「これでOK」と思っていたことが、次の日にはそれ以外の新しい出来事が起きる。では、支配人が休みの日にはどうするのか?休暇はいらないのか?そういう問題が出てくる。「そこは臨機応変に…」では、あまりにもアバウト過ぎる。臨機応変を口にしてはいけない。そこで、いつもアドバイスしていることは…、「その日当日の責任者を決めること」である。これはその下の副支配人でもマネージャーでもいい。何しろ当日起きたことや即決が必要なことは任せる。いちいち支配人に了解を得なくてもよい。(事後報告は必要)…というのも、施設によっては店長や支配人って、現場に出ていない人が多いから、即断即決できない人が多い。たいていは、来月、来シーズン、来年の仕事をしている。だから会議や打合せが多い。オフィスや本部にいる。それはそれで必要。つまり「もっといい未来を造る役割がある」けれど、毎日の運営やサービスは現場にいないから本当は良く知らない。メールなどパソコンでわかる範囲の報告ならわかるが…。当事にライブで起きることにすばやく対応するに現場にいる人に任せなければ一向にサービスは向上しない。野球で言えば、ベンチでしっかり見ている監督が指示を出すべきで、その上の本部にいちいちお伺いを立てている場合じゃない。それと同じこと。なので、今日来店来場しているお客さまにとってよりよいサービスを提供するには、当日の現場の総責任者を決めて「今日のことは任せる」体制になしかればならない。できれば3人は必要。そうしないと休みも休憩も取れなくなってしまう。「そうはいってもまだ任せられない」ではなく、しっかり指導して育成しておくことも支配人の仕事だ。そういうことをしっかりしないでおいて、いまだに新人が入社すると自分で育てようとしたり、かつての仲間を連れてこようとする人もいるから要注意である。これは、日本でも中国でも変わらないらしい。
2005/02/04
コメント(0)
-
上海サロン
つっちーさんのお誘いで市内某所で開催されているサロンに参加させて頂いた。場所は上海では知る人ぞ知る場所で、「こんな所もあるのか!」とタメ息が出るような素敵な場所だった。考えてみれば歴史的にみても、カフェやサロンが果たす役割は大変大きいに違いない。色々な立場の人々が集い、あーだ、こーだと議論を交わしながら…。何やら色んなモノが生まれて行く。その後はやはり居酒屋で今後はざっくばらんに議論が繰り返される。知識も身につくし、なんと言っても人付き合いが磨かれていく…そういう場なのかもしれない。
2005/02/03
コメント(0)
-
イベントに頼った店舗運営の結末は…
中国はもうすぐ新年。それで街中、色々とイベントの準備で大忙しの様子。こういうのは日本でも中国でも変わらない光景だと思う。その他にもクリスマスやバレンタイン、GW、ハロウィン…と年間を通じて、何かしらのイベントネタというのが存在する。それで、それに合わせて企画会議やら業者との打合せ。内装のデザインの検討や広告宣伝の…とおよそ一ヶ月前くらいからはその準備に追われることになる。そういう準備に走り回っている日に訪れたお客さんは…なんとも寂しい店内(施設)を味わう事になる。スタッフも何やらバタバタで、台本の練習をしていたり…、しきりに内線していたり…、どこか上の空な空気が漂う。それでイベントは大体、1週間から2週間で終わる。終わると「やったー!」と達成感から、飲んで騒いで、あとはグッタリ…。そこで働くスタッフも、イベントの時だけは燃えるが、普段は「電池切れ」みたいなサービスになる。こういうパターンにハマるとイベントのない日にはお客さんが来なくなる。イベントに全力だから、イベントのない日との落差が大きい。どうせならイベントのある日に行こう、となる。しかし、元々「もっと集客するには…」が目的にイベントなのに、結局、普段のお客さんを逃がしているのだからイタチゴッコである。大金と時間と労力をかけて…。本当は、特にイベントなんかしなくても普段のお客さんがコンスタントにたくさん来てくれるようにするべきなのに、誰もそれを言わなくなる。成功している所は、毎日がさもイベントのごとく、真剣に新鮮にサービスしている。飾りつけや内装もイベントのごとく毎日きれい…。持久力がある。その上にイベントがのってくるから集客も素晴らしい。ここにも、短距離走とマラソンランナーのような違いが存在するんだなぁと実感。
2005/02/02
コメント(0)
-
ブランディングの誤解
この数年間で身の回りの電化製品で故障したものがある。ここまで密着した生活をしていると、大変大きな不便さを実感するようになる。(海外で故障するとさらにきつい)僕の場合、そのほとんどが日本製だが、その故障によってもう買わなくなったメーカーがいくつかある。その時に味わった不便さがトラウマになってか、何しろもう買わない傾向にあるのかもしれない。それらのほとんどが現在はメイド・イン・チャイナだ。中国だから全部悪いわけでもなく、何年も快調に動くものもあれば、そうでないもののある。ようするに、工場や物流にどのくらい精魂込めて真剣に指導、管理に当たっているのか?が現れているのだ。<ぬるい>ところは二回続けて故障した。ここでメーカー側が「中国産なんで…」と言ってはいけない。その一方で、ブランディングだなんだと、広告宣伝ばかりやっきになっているように写る。しかし、どんなに宣伝されても壊れるものは嫌だから買わない。そもそもブランディングという言葉に酔ってしまって、ブランドイメージを維持でも守り抜く方の努力がおざなりになっているのだ。どんなに素敵なデザインでも故障ばかりではお話しにならない。CM大賞を狙うがごとく、一流のプロデューサーを呼ぼうが、コンマ1秒の画像にこだわった映像をCMに流したところで、それと同等、あるいはそれ以上の品質管理をしてもらいたいのがユーザー側の本音である。故障したり操作が分からない時に問い合わせるコールセンターも今ではほとんどアウトソーシングという外注である。カタカナ英語だとなにやらかっこいいように聞こえるのかもしれないが、ようは、クレームを外注に受けさせるのだから、覚悟が小さい。何でもかんでもDELLの真似をしなくても…。それが世界のグローバル企業のスタンダードなんです、という言い訳が聞こえてきそうだけど、そのスタンダードに乗って喜んでいるなら差別化への道は遠い。極端に言えば、性能が良くて、デザイン画素晴らしく故障しない…という商品ならば、黙っていても売れていく…、そういう商品開発と指導、管理を願いたいものだ。素晴らしい製品を開発する能力があるのだから、筋を通した売り方とサービスを…と。最後の1マイルで差をつけて欲しいし、手を抜かないで欲しい。ブランディングは広告宣伝のことではない。行動そのもののはずだ。頑張れ日系企業!
2005/02/01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1