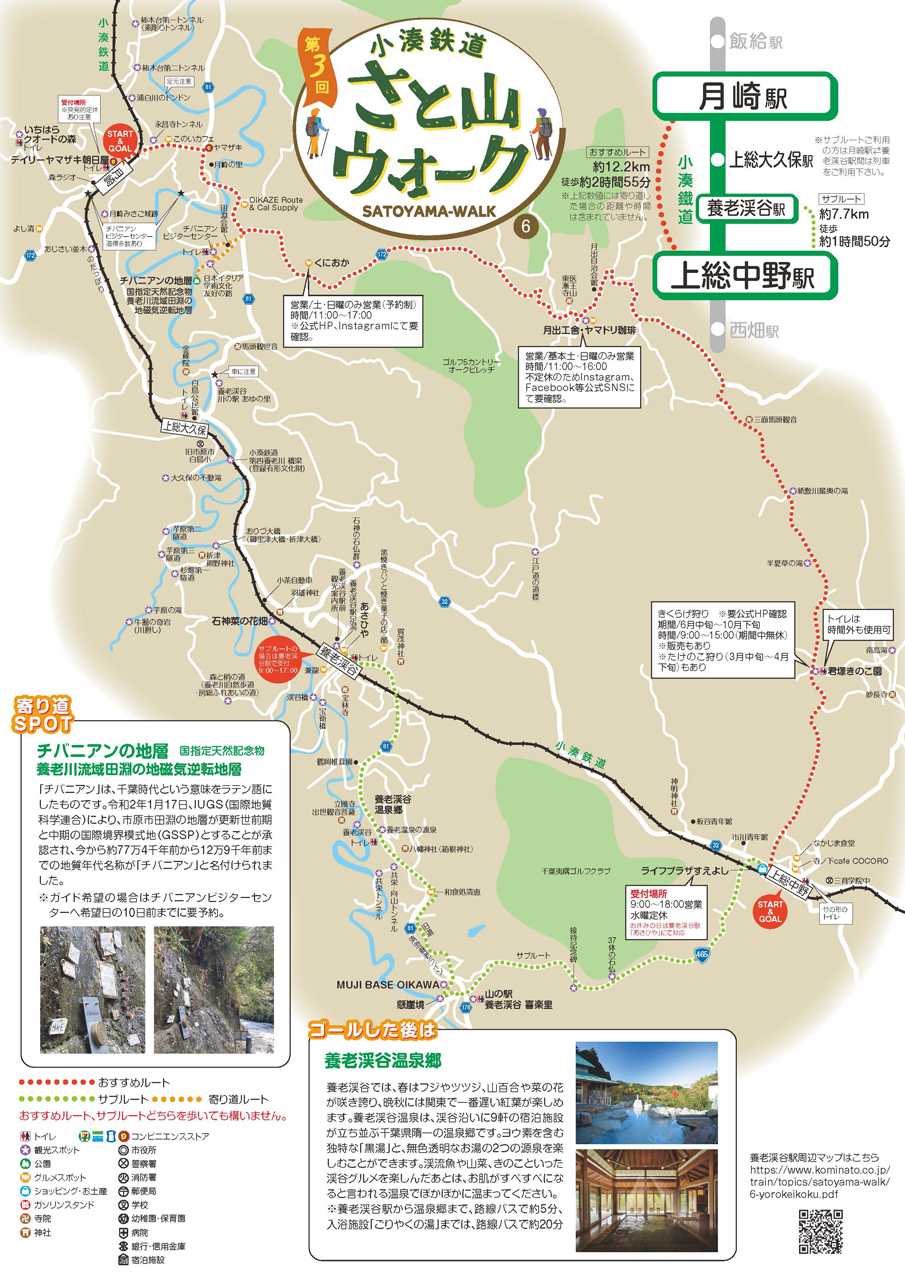2005年05月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
米国ディズニーで学んだ私の宝物~ディズニー大学へ行こう!~
数あるディズニー経験本の中でも数少ない20代の女性の著書。TDLの勤務経験者は全国で約20万人はいる、と言われるが、この木村美絵さんはTDLの経験はない。フロリダのディズニーワールドへ行き、そこで初めてディズニーのノウハウを現地で学んでいく。妙にビジネス書っぽくなく<教育本>ぽくないところが読みやすい。ご本人の素直な驚きや体験がきちんと記させている。業界慣れした人たちの本とは明らかに違う。下心や押し付け感が何もない。やたらに高学歴でも低学歴でもなく、大事件があったわけでもなく、やたらに執念めいたいモノがあったわけでもなく、一人の女性が「行きたい!」と思って学んできた、と。(最近、本の背景が重たいモノが多いので…:笑)他企業と無理やり比較したり、媚びたり批評もないく、「混じりっ気なし!」の純度の高い「学び本」だと思う。こんな本はなかなかあるものではない。多分、他業種の人々にとっては、この本は大変わかりやすく共感できるのではないだろうか。正真正銘の体験の記録として、参考になる。そして、ディズニーワールドでの業務終了後もディズニーのホスピタリティプログラムに参加して活動中で、自分のやりたい事が自然体で一貫しているところもいい。米国ディズニーのトレーニングの内容が知りたい人。ディズニーのインターンシップについて知りたい人。人事部で教育を担当している人。これから社会人になる人。サービスで行き詰っている人…。留学を考えている人。…などの方には特にお勧め!ビジネス書にありがちな、読んだ後にヘンなプレッシャーを感じることもないシンプルな良書です。【送料無料商品】米国ディズニーで学んだ私の宝物:ディズニー大学へ行こう!
2005/05/30
コメント(33)
-
【OJT】指示は指導の後で…
「安室さん、あれをセットしてお客さんに配って」と指示をする。しばらくして様子を見てみると、「なにやってるんだ!そんな配り方はないだろう(怒)よく考えてやれ!」と爆弾が投下されていたりする。こういう職場では、「所長さん、あいつらは何回指示してもできないんだよ。何かいい方法はない?」と聞かれる。一方で、「安室さん、ひとつ頼みたい仕事がある。よく見ててね。これをこうしてセットして、こうしてお客さんに配布してください」「ハイ」(安室さんがやってみる…)「そう、なかなかうまいね。あとはここを少しだけ…」と指導をする人もいる。こういう職場では「所長さん、あの子、覚えがはやいでしょう」と誇らしげである。同じ仕事でも言われる方の立場になれば、随分と印象が違うはずだ。前者は単なる<指示>だけど、後者はやり方を見せる、示すだけで<指導>になってしまう。当然、お客さんが受けるサービスにも小さな違いが生まれてくる。まさに<最後の一マイル>の差だ。わかりやすく言えば、これが<OJT>の基本。仕事しながら教えていく…。文章にすれば簡単だが、飛交うのは指示のままで、相変わらず指導が少ないのが現場の実態である。これが繰り返しきちんとできるようになったら、次からは指示を出せばよい。指導をカットすると…高くつきますよね(笑)。(結果として…)
2005/05/29
コメント(2)
-

アクアグライド
かつて、折畳みのカヌーが欲しかった。けれど、ヨットマンを知り合ってからは両方できたら良いなと思っていた。つまり両方できるものがあればなぁと。ところがあるんですね、こんなのが…。仕事道具も遊ぶ道具も折畳めるモバイルものが好きなんです。これからの季節は車のトランクにこんなのが入っていたら…いいなぁ。
2005/05/28
コメント(0)
-
ネーミングの研究中
最近、さまざまなシーンでネーミングを考える機会が多い。だからことあるごとにネーミングについて調べたりしている。社名や商品は、昔は個人名が多かったことがよくわかる。日本国内のものはわかりやすいが、海外モノはそれが個人名なのか?は知らなかったものがあって大変面白い。例えば、航空機のボーイングさん、ミシンのアイザック・シンガーさん通信社のポール・ロイターさんピストルを発明したサミュエル・コルトさん…などなど、本当にたくさんある。調べていくとなかなか楽しかったりもする。さらに単位などは<100ボルト×10アンペア=1キロワット>も全て個人名だから、日本名に置き換えれば<100小寺×10野村=1キロ斉藤>…というような感じだろうか。けれど、悔しいかな<1キロ斉藤>ではやはりしっくり来ない。そう考えると、現在の社名や商品名は本当によく考えられたものが多いということが良くわかる。それだけに…調べ過ぎるとなかなか決まらないものです(涙)。
2005/05/27
コメント(4)
-
モチベーションは憧れの人から
職場でのモチベーションには色々あるが、「あの人みたいになりたい!」これも大事な要素だ。つまり「憧れの人」である。少しカタカナが好きな人たち用には「キャリア・ターゲット」である。○○マネジメント論で抜けがちなことがコレ。憧れの人がいない、不在なことが前提になっているのか?何しろ論じられることが少ない。しかし、学問の世界とは違って、現場の世界では<憧れの人>が人を育てるしモチベーションにもなるし、定着率にも影響しているし…と、<不在>を前提にするわけにはいかないことが多い。反面、憧れの人がしっかりしているところは、○○マネジメント論はそんなに積極的でなくても構わない。(多少うすめでちょうど良い、となる)そして、<憧れの人>をどう採用するのか?見つけ出すのか?あるいは育てるのか?…というスキルに注目が集まる。これは当たり前のことで、店舗や施設、企業の生命線になるからだ。俗に「スターの育成」というやつだ。スターは色んなタイプがいていい。人のスターを全員が憧れるなんてことは芸能界でもあり得ない。時に<人事専門用語>の世界から離れて、こうした日常?用語で考えてみる事が大事だと思っている。ヒューマン・リソース・マネジメントとかなんとかの用語を連発しているとなんだか安心する人もいるが、実は皆よくわかっていない、理解していなかった…ということになる(笑)。こういう科学的な手法は、やはりその前に現場の現実があって、それを体系立て<論>としてまとめてあるから、実は<論>に適さない部分がうまく省略されている部分があるから要注意である。こうした手法が本当に適格なら、芸能プロダクションは簡単にもうかるし大盛況なはずである。芸能界でも現場でもスターは突然誕生したり、失速したり…でいつまで経っても奥が深い。人事も同様だ。「芸能界と一緒にするな」と言われたことがあるが、どちらも真剣勝負の世界である。参考になることは多々あると思っている。反対に「芸能界を舐めてませんか?」と。手前ミソで恐縮だが、少し前に上海で出会った留学生との会話で、その彼女は日本で学生時代TDLでアルバイトしていた。僕も働いていた時期があるが、いかんせん遠い昔で、年代からも全く共通の知り合いはいない…と思っていた。ところが「私の憧れは香取さんだった」と来たから二度ビックリ!(「社会人として大切なことはみんなディズニーランドに教わった」の香取くんです!)「一緒に働いていたの?」と聞くと、「いいえ、すでに退社されていましたけど、度々先輩たちから香取さんの仕事の話を聞いてファンになりました。それで憧れになっていったんです」ということ。「僕はその後の7年間、香取くんと一緒に働いていたんです」というとこれまた彼女も「えぇぇぇっ!」と三度目のビックリ(笑)。すでにもういない人までが憧れになるのだから、その影響力たるや、凄まじいものがあるなぁと実感した。先輩から聞く香取くんの噂話で彼女のやる気に火がついていたんだから、こうなると人事部の把握できる範囲ではない。ディズニー関連の本を読破したところで同じこと。奥行きはもっと深くて広がっていた。そして、これまた後日談だが、そういう彼女もまた後輩のスターだった。DNAはスターによって伝わっていくし運ばれていくんですね。(ここではディズニーさんのスピリット)こういう小さなスターがたくさんいる職場や企業はサービスの足腰が強いと言えるのかもしれない。憧れの人づくりもまた、企業にとっては大事な経営戦略になるんですね。
2005/05/26
コメント(0)
-
サービスのブランド化
●導入研修のススメ=======================================================「仕事の初日ほど、従業員が集中し、従順となり、学習意欲の高い日はない」ホルスト・シュルツィ:リッツカールトン・ホテル会長=======================================================多数の現場のスタッフを抱えている人は、この言葉の重さをズシーン!と実感するのではないだろうか?仕事柄、僕は本当に痛感している。リッツカールトンに限らず、ブランドイメージに相応しいサービスを提供しているところは、この<一日目>全知全能を注いでいるといっても過言ではない。考えようによっては「たった一度のチャンス!」とも言える。初日はたった1回しかないからだ。真剣勝負である。「何が一体違うんですか?」と聞かれることがあるが、「一日目の質です」ということになる。極端な例で言えば、まるで7時間のミュージカルのごとく綿密に造り込まれている。(たった1回きり上演のミュージカルみたいなもの)昨日まではひょっとしたら自社のお客さまだったかもしれない人をあっという間に<こちら側のスタッフ>に引き込む力がある。見る人が見れば、まさに<魔法の一日>である。「愛社精神を叩き込む」という類のレベルの内容ではない。わかりやすく言えば、「自社製品のファン」から「自社のファン、仕事のファン」に変身させてしまうようなもの。(私も踊ってみたい、唄ってみたい…と)「探してた仕事がここにあった!」とか、「これっとひょっとして自分に合うかも…」とか、なにしろ、「働いてみたい!」という意欲をかき立ててくれる。(フックがきちんとかかった状態)その上で、「こうやるとお客さんは喜んでくれます」とスキルを指導していくから、ガンガン吸収してくれる。覚えたくて仕方がないのだから、当然のこととなる。教育はスタートダッシュが大事とはよく言われることだが、慌てる事ではなく、最初から丁寧に…という意味だと思う。「丁寧」というと「甘やかす」みたいに考えてしまう人がいるが、丁寧に教えるから、丁寧な仕事をしてくれるようになるということで、甘やかす事とは次元が違う。ざっと教えておいて「だけど仕事は丁寧にやれよ」では、あまりにも無責任だ。ブランドイメージを行動(接客サービスなど)としてしっかり表現するには、「わが社のブランドは…」という講義だけでなくて、ブランドがイメージできるような「品」とか「楽しさ」とか「質」が伝わるような教育を行うことだと思っている。終わった後に「なるほどぉー!」と少しタメ息が出るような…(笑)。サービスのブランド化ってこういう舞台裏が必要なのかな、と。
2005/05/25
コメント(31)
-
憧れをセットで輸出する
<3人小姐のインタビュー:2>日本人と働くようになって少しがっかりするところがある、と。それは「働き過ぎ」というか、つまり「幸せそうに見えない」ことだそうだ。(そういう人を多くみかけることらしい)これはちょっとショックだった。(本当には大いにショックだったが少し見栄があった:笑)徐小姐曰く、中国人の管理について、日本人はあれこれと勉強しているかもしれないが、難しい能書きを横に置けば、お金持ちとかではなくても、幸せそうな上司がいればそれが一番とのこと。「成功=お金持ち」だけではなく、「成功=幸せそう」というのが最も大事だと。皆、そこそこのお金を持っているし素晴らしい製品を作っているのに、幸せそうに見えない…というのはなんかヘン?である、と。それで、製品には憧れるけど、日本人を真似しようとは思わない(思えない)し憧れない。日系企業で成功するには、「幸せそうな人を送り込むべきで、憧れがあれば…」という過激?で正直?とも言えるアドバイスを頂いた。====<所長の見解>======この件は日本にいる人ではなく、僕たちのように現地にいる人間の責任かもしれない。現に東京も元気だし、元気な人はたくさんいるから。現地にいる日本人がそう見えるのだろう。それと、憧れられる人が必要なのは日本でも一緒。けれどそういう人は少ないから社内にも滅多にいないから○○管理セミナーが流行る。ついでに言えば、某米国企業では、超有名ではないが、大変きれいな女優さんを講師として派遣して研修をしたらしい。(マナーとか、話し方とか…)ブランドイメージ作りの方法は広告宣伝だけではないんですね。「やるところは徹底的にやる」という典型的な例かな。========================そう言えば以前、上海のフォーラムで行った面接でも「幸せになりたいから…」という入社動機に驚いたことを思い出す。現実に、毎月の上海に滞在中に羨ましく思うことがある。それは食事風景だ。仲間やら家族やらで何しろワイワイと食べて飲んでいる。(平日でも)旺盛に見える食欲と共に、楽しいひと時に写ってしまう。一所懸命に働いて、大いに遊ぶ…。レジャ研だからこそこういうバランスに気をつけていたはずだが、上海に行くと、本当に反省する。気をつけないと、レストランと飲み屋やクラブしか知らない…となる。正直な話、どんなに根を詰めてもバランスが崩れるとロクな仕事の成果にならないし、結果クライアントにも迷惑をかけることになる。また、そうしたプライベートを大事にする姿勢が現在の、そしてこれからの中国のレジャー産業や観光産業の展望が明るくみえる原因でもある。この点では当面は世界的にも中国の天下だと思う。平均の利用者数も日本のように「2.3人」とかではなく、4人を超えることになるらしい。一人っ子政策でも、祖父祖母同伴が多いから。ちなみに王小姐は先日のGWに自分の家族と友人の計14人で旅行に行ったらしい。だからマイクロバスの需要が大きい。その点日本は一所懸命に働いても遊ぶ(楽しむ)時間が少ない…人が多くて、結果としてレジャー産業も苦しい…となる。GDPや所得がどんなに増えても、自由時間のない地域ではレジャーサービス業は寂しい限りだ。たまの連休は皆、無理してでも海外(ハワイ、グアムなど)だから、国内は厳しいままである。彼女たちから教えられたのは、お金も大事だけど、時間はもっと大事だと…。日本人は仕事の時間には厳しいが、プライベートの時間にはいい加減にみえる…。日本の経済は今でも好調だけど、人間が元気なくみえてしまう大事な理由だそうな。(個人的にも大いに反省するところだらけだった)両方できる人が尊敬されるし幸せ…ということなんでしょうね。肝に銘じて、<時間持ち>になれるようにがんばろう!(バランスが取れた状態の維持)と思いました。チャンチャン!
2005/05/24
コメント(0)
-
重慶より四国の松山が好き…
重慶生まれの20代後半の3人の女性スタッフ。じっくり話が聞きたい…と言われなぜかビックエコーに(笑)。防音で飲み放題食べ放題だからいいのだと。「だって、中国人はうるさいでしょう」という言葉には笑ってしまった。ちなみにビックエコーは中国の会社だと思っていたらしく、僕が「おお!ビックエコーかぁ、上海にもあるんだね」というと、「ええ!?日本にもあるの?」と(笑)。そこで、カラオケは日本人が発明したんだよということから話しが始まった。すると「うっそぉぉぉぉ!中国人が発明したんだよ。学校の先生が言ってた」…という逆襲にあう(汗)。まぁなんでもかんでもコピーの国だから、そういうことってたくさんあるんでしょうね。やたらに聞かれて答えるよりはこっちが聞きたいことがあるから、質問される度に、ブーメランのごとくさらりと質問を返してなんとか3人に話してもらう…という攻防が始まった。まずは、王さん(仮称)の話しからで、重慶生まれだからその歴史的背景から日本人は鬼だと思っていた。それが変わったのはなんと「東京ラブストーリー」だった。90年代に重慶でも放映されたらしい。そこでみる日本人は鬼どころか、カンチなんかはその逆で、「しっかりしろー!」とじれったかったらしい(笑)。リカは可哀そうだったけど可愛かった、と。それと、普通のサラリーマンとOLの生活だったけど、当時の中国よりもはるかにきれいでちゃんとしていることがわかった。それで、ガラガラ…とイメージが変わっていって「反日」的教えがあればあるほど逆に興味が湧いてしまって、大学卒業後に国営企業に就職するも、「このままではいけない」と思い、知人友人のネットワークを駆使して日本に留学の機会を得る。家族親戚の大反対の猛攻をかわしつつ日本へ。知人のいる四国の松山に向かう。上海から出発して関西空港に到着。その時に、あまりのきれいさに言葉が出なかった、と。なんて清潔な空港なんだろう。その後、松山に移動。ここでの生活が価値観を変えていった。田舎なのに「きれい」ということ。最初は水道の水を飲む人々に驚いたらしい。自分は相変わらず沸かして飲んでいた、と(笑)。近所に出かける時に、いちいち鍵を閉めない人もいる。中国の田舎=汚い、ボロい…なのに、ここは何しろきれいで清潔でいい人ばかりだった。どんなに探しても「鬼」はいなかった、と。しょっちゅう、村の色んな家に招待された夕食をご馳走になっていた。あまり日本語が話せないし、村人も中国が話せなかったけど、とても親切なのはよくわかった。それでおいしい日本食をたくさん食べて、これまたショックだった。中国料理が世界最高だと思っていたけど、こんなに芸術的な料理を食べていたる人たちがいたなんて。だから、今でもミソ汁を作ってのんでいるらしい。そして、村中の人々が朝から晩まで大変よく働くのにも驚いた。当時、国営企業の多かった重慶では考えられないことだった。だから戦後の日本の経済発展の正体を見た思いがした。「これじゃあ日本に勝てるわけがない」と。特に建築現場の大工さんたちが違うと思った。中国は出稼ぎ労働者、つまり臨時工みたいな人の仕事だけど、日本の建築現場の大工さんたちは皆プロだと思った。ものすごくきれいに丁寧に仕上げていくのに驚いた。メイドインジャパンが優秀なのが良くわかった、と。一年間の留学を終えて帰国する時は本当に悲しかった。多分、もう二度と来れないだろうと思ったから。「では、今、一番住みたいところはどこ?上海?重慶?松山?」と最後に意地悪な質問をしてみると、「もちろん松山」とあっさり(笑)。今では松山で商売ができるように計画を立てて働いているらしい。ちなみに、「松山かぁ、きれいだよねぇ」と相槌をうちながら、まだ一度も行った事がないことに気がついた(笑)。それにしても松山の観光協会の人が聞いたら泣いて喜ぶだろうな。TDLや秋葉原に連れて行かなくても、大好きになってくれるんだから。がんばれ観光協会!
2005/05/23
コメント(7)
-
中国:仕組みづくりで勝負が決まる
モチベーションをあげる方法はいくつもある。逆にみれば悪影響を及ぼしている原因もたくさんあるということ。その一つが現場のシフトと呼ばれる勤務スケジュールだ。<早番・遅番・公休>などを設定してスタッフが交代で勤務するように設定するわけだ。さらに当日の勤務で<ローテーション表>というものがある。これは全員が一斉に休憩したりはできないから、「王さんの次は陳さん、その後は徐さんの順番で休憩…」と休憩や食事を効率よく交代してとって行くためのもの。もう一つは、インフォメーション→レジ→休憩→販売コーナー→入口…と店内の業務を<ローテーション>で勤務していくもの。これを全員分作成しておく。(日本ではスタンダードになりつつある)多くの中国のお店では一日中レジだけ、インフォメーションだけ…と固定型が多い。だから当然ダラける。立ちっ放しのスタッフもいれば、座りっ放しのスタッフも…。何しろ一つの仕事を一人に担当させる…というものが多い。(10時間くらい連続で)だから、インフォメーションカウンターにお弁当を広げて食べてしまうことになる。(交代で休憩に行けないから)時に、店内のスタッフが皆カウンターでお弁当…ということにも。そこでローテーションの考えを教えてそれを作成するように指導するが、これがなかなか作成できない。仮に作成しても時間を守る規律がないとタダの紙切れと化す。さらに日本ほど人件費に対してシビアでないから、「そこまでして切り詰める必要が無い」となる。そうすると、日系企業としては人件費が安いと思って進出したのに、実は結構かかるな…ということになってしまう。そして、一人当たりの働き振りや生産性も低いし…。そうなると、わざわざ中国に進出しても意味が薄れてしまう…。こういうケースが結構あるようだ。確かに人件費は安いが、その分管理する人数は増えるわけだから、こうした管理方法を日本にいる時よりもきちん指導して活用しなければならない。それができれば儲かるとも言える。ところが、メーカー系の人はそういうのが得意だが、それ以外の企業の場合、「経験・勘・度胸が大好き」型な人が送り込まれてくるから、こうした大事な仕組みがなかなか定着しない。それで、「中国では利益が出ない」となって撤退に…というケースがある。だから、本当は<度胸型の人>に<仕組み型の人>をセットにして送り込まなければならない…というのがわかる。度胸型の人が切開いたビジネスチャンスをきちんと利益が出るように仕組み作って円滑に回るように出来る人の両方がいなければ成り立たない。日中関係ばかりに気を取られているとこうした小さくて当たり前の点を見逃してしまうからご用心である。
2005/05/22
コメント(0)
-
コンサルのコンサル
僕たち運営サービスに特化したコンサルタントをしている。だから普段は企業や施設、お店に出向いてアドバイスや支援を行う。しかし、そんな僕たちも社外の方々にアドバイスを頂く。もっとハッキリ言えば、コンサルしてもらう。意外に思われる人もいるかもしれないが、「社内でできること、できないこと」がわかっているからそうなる。あるいは「社内では見えないこと」がある。ヘンな風習が定着したりしないようにアドバイスを受けていく必要があるわけだ。考え方としては、スポーツ選手と似ていると思う。誰かしら専属のトレーナーがいて、「ここをもっと鍛えよう。そうするとフォームが安定する」とか、よりよい成績が出せるように叱咤激励しつつ、メニューを提供してくれる。または、「今度はこういう技を覚えよう。そうすればもっと得点できる」など。そういう存在なしで一流になるのは難しい。「サボる自分」「都合のいい自分」はどんな人の心にも住んでいると思う。(多かれ少なかれ)「この辺でいいや」「ここは自分流が一番」とか勝手に思い込みそうな時、「そんなのは自分流でもなんでもないよ」とビシッと指摘してくれたり…。または、定期的に健康診断を受けているような場合もある。「ここは相当ヘタってますね。直しましょう。お話になりません」と(笑)。こうして体調を整えたり、鍛えたりしながら、自分たちもプレーをする…。そういう流れが一番大事なんです。それと、世の中みなさん得意不得意があって、こうやってノウハウがグルグル回っているわけです。それでどんどん良いものが生まれるし進化する。これが外部で教えているばかりだと(出力ばかりで入力がない)、そのコンサルは「実は枯れている」「干上がっている」ことがある。故障したまま騙しだましプレーしているようなもの。選手寿命はこうして決まるのだと思う。いつも旬でいれるようにしたいなぁ。
2005/05/21
コメント(0)
-
中国が本当に脅威になるには
中国のスタッフ教育で最も労力の要するものはマネージャー教育である。(日本もところによっては同じようなものだが…:笑)どこぞの大学で経営学やら経済学を勉強していたりするとエリート意識に溢れている。もう教わる前から「任せて下さい!」と(笑)。大人しく聞いているとマネジメントでもマーケティングでも…みんなできるスーパーマンがたくさんいる。もしこれが全部本当なら、今頃の中国の経済成長はこんなものではないはず。日本はおろか、アメリカに肩を並べているのかもしれない。しかし、現実はそうではない。いくら上海の経済成長が凄いといっても、あくまでも外資の売上が大きい。メーカーの技術力に関しても、「もうすぐ日本を抜く」を息巻く人もいるが、そんなに簡単ではない。自動車のレベルで言えば、中国のメーカーのエンジンでまだ<F1GP>に出場することはできないだろう。もう10年くらいはかかりそうな感じがする。(あくまでも勘ですが…)日本は1960年代に出場していたから、そういう角度で見渡せば、まだ40-50年くらいの差がある。トヨタ2000GTで数々の世界記録を打ち立てたのもしかり。スカイラインGTRがポルシャを追い回す…などなど。ただし、もうそろそろ外野でワーキャー言うのは止めて出場してもらいたいと思う。言い訳の聞かない技術のオリンピックだから、時間はかかってもきっと大きな成長を遂げる事になると思う。人も技術も進化する。そういうイコールコンディションの世界で堂々と勝負することができたら、「世界の…」を名乗れる資格をもらったようなもの。せかっくここまで経済成長をして、かつての貧しさから脱しつつあるのだから、<体裁と外見重視>から中身のビシッと詰まった国に進化して欲しいものだ。現場のマネージャーを見てても、あるいは、上海のマンションつぶさに見て回ってもそれを象徴しているように思えてならない。反対に、そういうのをみていると、○○コンサルタントの先生方がおっしゃるほど、脅威な実感もない。本当に豊かで脅威な国になるかなれるかの本番はこれから…な気がする。
2005/05/20
コメント(26)
-
トレーナー・トレーニング
■「会社のきまりだから仕方ないだろう…」→「仕方ない…」と思っているうちは人に指導してはいけない。トレーニングに限らず日常の業務の中で、規則をきちんと指導しなければならないシーンに出くわすことがあります。その時に、伝書バトのように伝えていませんか?「上司が(本部が…社長が…)そう言っているんだから…」「誰かが提案したんだよ…」「オレだって納得してないよ…」などなど。仮にそれが本当だとしても、伝えているだけなら指導ではありません。単なる伝言係です。このように伝えていれば一見悪者にはなりませんが、信頼もされません。「自分の言葉」で伝えるべきです。時には意見がぶつかるかもしれないけれど、責任ある自分の言葉で指導するその姿勢はきっと信頼感を生みます。そして、その積み重ねがいずれ「自信」なってきます。結果として強いチームに進化します。【トレーナー(上司)はいつも心に“一握りの勇気”を持っている】====================================今日、一番大事に感じたこと。中国人のマネジメントって、古いボスキャラタイプが多いと聞くし、実際にそのようだ。ボスキャラでまとめるのは簡単だが、結果としてそれが<私物化>土台となっている。本当のマネジメントは、そういうパワーで抑える管理(徒弟制度)の先にある。がんばれ中国人のマネージャーたち!
2005/05/19
コメント(0)
-
少女が村を救う
随分前にガイアの夜明けで「少女が村を救う」という番組が放映された。可南省の田舎に住む18歳の少女が妹(二人)を大学に進学させられるように、と広東に出稼ぎに行く…。平日は工場で長時間労働でがんばる少女も、休日は仲間と連れ立って街に出る。写真を撮ったり楽しそう。街には年頃の少女の欲しいものがこれでもか!というほどに溢れている。けれど、少女は見ているだけで何も買わない。放映当時の月給は9000円。そのうち7500円は仕送り。残り1500円が自分のお小遣い。休日の残りの時間は4人部屋の寮で過ごす。洗濯掃除以外は本を読んで過ごす。今まであまりにも勉強不足だったから…と。…こういうドキュメンタリーは日本で研修などで鑑賞すると、中年でなくて新入社員の方々も感動したりする。さて、この10年くらい目覚しい発展の真っ只中の上海っ子はどんな反応をするのだろうか?あまり観たくない映像なのかもしれないし、興味が無いのかもしれないし、…と色々考えたりしたが、まぁ見せてみることにした。結果は…同年代の上海っ子(女性)スタッフは、「感想を聞かせてくれる?」と話を向けると、「ええ、わたしの感想は…(涙)」となって、何も話せなくなってしまった。噂にはそういうことは知ってはいても、こうしてきちんと観てしまうと、同年代で同じ国内…ということで、自分がいかに恵まれているのか、ビックリした様子だった。泣き止むと、「今すぐに彼女を救ってあげることはできないけど、恵まれた環境に甘えないで一所懸命に努力します」と真っ直ぐな眼差しだった。数日後、働き振りを見に行くと…少女ながらに真剣に働いていることが伝わってきた。中国は、村に限らず上海のような大都会も少女たちに救われているのかもしれない…。(目を凝らしてみてみるとそう思えてくる)それと少女が驚いたことはもう一つあって、日本のテレビで中国の田舎の少女を応援するような番組が放映されていることだ。しかも、番組の作りや映像がきれいで、少女を丁寧に扱っているのがわかったらしい。何か小さな変化が起こっているようだ。
2005/05/18
コメント(0)
-
アメリカ人の人気を利用する
昨日に続いて、「欧米企業に比べて日系企業は本当に人気が無い」という話。それはそれで「?」で、実際には、高収入だが大変なプレッシャーで「もう耐えられない」と日系企業に転職する中国人もいるから、これまた色々である。ということで、人気に関しては、最初(新卒)では欧米で、少し社会が分かってくると日系とイーブンになっているのかもしれない。(本音はわからないが、募集して誰も来ないことはないので)そんな中、大変したたかな社長さんにお会いした。その人は、中国に進出して利益を得るのは特別難しいと思わなかったらしい。はじめのうちは、「欧米が人気」とか、「アメリカ人に弱い」「日本人には横柄なことが多い」とかの噂を聞いていたので、「へぇー」と思った。そこで、「クソッ!」とムカついても仕方ないから、すぐに作戦変更で、現地でアメリカ人を数名雇った。もうバッチリ金髪の男女をバランスよく。思い切りキャリアウーマンらしくさせた。それで、中国企業や政府系との折衝や契約交渉などのシーンでは必ず同席させて、主役に仕立て上げてバンバンプレゼンさせていたらしい。結果は…「本当に弱いということがわかった(笑)」と。おもしろいように決まっていった。おまけに、日本人もアメリカ人もいる会社ということで、応募者が急増して採用には困らないとのこと。(中国人からみれば経済の2代大国である)けれど、これでOKになってしまうことがたくさんあるんだから、採用の考え方次第でいくらでも商売はできるとおっしゃる。こういうのはMBAとかの教科書にも載ってないんでしょうね、きっと(笑)。けれど、これはこれでノウハウの一部で、別に卑怯でもなければ騙したわけでもない。そのままちゃんと雇っているし。加えて、莫大な利益をあげるんだから、真似する人が現れても当然。なんと頭の柔らかい人なんでしょう。これもソフトな思考ですね。
2005/05/17
コメント(0)
-
日系企業の撤退の真相は…
「多くの日本企業は日本流で撤退(失敗)しているんですよ…」(欧米企業はうまいのに…と言いたいらしい)という声は、現地の中国人からも、そして日本人からも良く聞く。(もちろんマスコミ系の方々からも)そういうのって、よく調べてみると結構いい加減な情報であることがわかる。そもそも、撤退した日系企業と現地で成功している欧米企業の業種が違う。90年代に精密機械加工などで進出した中小企業の撤退があったが、それはビジネス感覚がどうのこうのではなく、単純に、その時点では中国で造る事ができなかった、という理由がある。(工員のレベル、材料の調達、電気、ガス、上下水道…設備の問題など)それから仮に同じ業界であっても、アメリカなら「この程度で大丈夫」と中国産でOKな商品も、日本人に売るには「不可」(厳しいから)だから、日本流云々が理由でないものもあるわけだ。もちろん本当にうまくいかなかったというケースもあるだろう。つまり日本流の問題ではなくて、中国には不向きだったビジネスもあるということ。あるいは、仕事のやり方が合わなかった、ヘタだった…も。単純に「良い商品が造れなかった」とか「まだ早過ぎた」が原因であるケースも多々ある。(だから失敗と書かれて憤慨している方がいた)第一、中国で成功してる企業や人もたくさんいる。成功した企業は日本流ではないのだろうか?失敗だけが日本流…というのもヘンな話だ。けれどそうしたことをきちんと調べずに、「日本流は…」とやるのが好きな人がいるから困ったものだ。それと、そういう情報を発信する人の一部には現地の日本人で日本の企業に見切りをつけて中国に来て仕事をしている場合、日系企業の苦戦がうれしい、という人もいる。(心情的には、ほーらね!と思いたいらしい)自分は現地に来てしまったのに、「やっぱり日本と日本企業は最高!」と手放しで喜ぶことは難しいのかもしれない。どの程度かは測定できないが、そういう心理も掛け算されて「見切り撤退」もいつしか「失敗」になってしまう。それが「日系流では…」と紙面を飾る原因の一部なんだなぁと、実感している。ご用心!
2005/05/16
コメント(32)
-
上半身シティ上海
上海の浦東空港からタクシーに乗ろうと思いきや…100mは優に超える行列が目に入った。17:00を過ぎたら上海政府ご自慢のリニアモーターも終了。そうなると…バスしかない。中国を代表する国際空港である。リニアで見栄を張りたい気持ちはわからないでもないが、何しろあまりにも貧弱な交通アクセスである。何しろ世界に向けて写真写りを意識したビルばかり建てまくって、肝心の鉄道や道路は貧弱だから、渋滞感は東京以上である。地下鉄の改札は、ディズニーランドなどで使われるバーを押して入る、ピープルカウンターが付いているから、大きなキャスターは引っかかってしまう。バスと地下鉄を乗り継いでキャスターを転がしながら歩いていると実感できるのが、これまた「ボコボコな歩道」。正確には「歩道らしきモノ」。または、「ゆくゆくは歩道にしたいと思っている」くらいな代物である。上海の出張を数回重ねると、キャスターは見事に悲鳴をあげだす。そして車輪周辺がギブアップしてしまう。だから半年に1回くらい買い換えている。マンションの近くのコンビニで水を買おうと立ち寄る。コンビニの前はたいていなぜか階段がある。荷物の多い出張族には辛い。(コンビニの商品の納品業者さんは大変だろうな)中国のショーケースとしての役割は果たしているが、「人に優しい街づくり」に関しては…スタートラインに立ったくらいか。上半身は立派?だが、下半身が貧弱な街…というのが正直なところ。(下水道や電気なんかも合わせて)だから「上半身シティ」と呼んでいる。なので、これからバンバン鍛えて頂きたい。そうこうして汗だくになりつつやっと部屋にたどり着いてみると東京の素晴らしさを身をもって実感できる。住みやすさの基準はたくさんあるが、「移動しやすい」というのはなんと素敵なことか。思うに、日本の経済力は人と物資の移動(運搬)のしやすさ(速さも)が支えているのかもしれない。しかも省エネだから恐れ入る。
2005/05/15
コメント(2)
-
次はインドへ…
初めて上海の仕事を紹介してくれた方から「あのーそろそろインドもお願いできますか?」と連絡があった。「いいですね。やってみたいです。いつからですか?」と聞くと、「それが来週からお願いできますか?」と。予定表を見るまでもなく、上海出張なので「参ったな…」状態に。喧々諤々の社内調整の結果、N美譲が行くことに。「○ィズニーストア出身の英語が堪能な彼女なら適任!」と決めたものの、誰もインドで仕事した経験者がいない。わからないことだらけだ。けれど、未知な分、新鮮だし熱が入るのも事実で、こういう感覚って大事にしたいなと思う。やがて何度か通ううちにワクワクドキドキ感が消えてしまうから…。前年ながら今回は上海からメールとチャットでのお手伝いになるが、近いうちに行ってみたいところである。それしても、中国に続きインドでもサービスマナーとかマインドが重要視されて来ているんですね。
2005/05/12
コメント(2)
-
少子化が問題になる人たち
少子化についての議論をあちらこちらで耳にする。それにしても「少子化=ヤバイ!」という展開にしたがる人が多い。マスコミの報道がそちら側が多いからか。いずれにしろ、少子化が「問題」になる人たちがいることは確かだ。しかし、反対側の人もいて、食糧問題の専門家になると「歓迎」となる。エネルギーの専門家も。考えてみれば、世界の人口はすでに60億人を超える。エネルギーも食料も理想を言えば20億人くらいが理想なのだから、遥かにオーバーしているわけだ。食料やエネルギーの分野から日本の適正人口を検証すると5000-7000万人くらいらしい。だから日本が少子化の見本を示して、そのソフトを世界中に輸出していこう、くらいの政策があってもいいのにな、と。これ以上、高速道路も鉄道もダムも空港も学校も…作らなくていい。もういらない。日本はすでに完備済みである。(四国には橋を四本もかけた。大阪には2つも空港を作った…)巨額なモノはすでに終わった。(ただし借金は十分にある:汗)中国などは、まだまだこれからで、天文学的な巨額な支出が待っている。それから高年齢者もそんなに貧乏な人ばかりじゃない。むしろ逆で、子供が面倒を見なくても食べていける人たちが多い。(蓄えがある)それから、定年退職ばかりかと思いきや、定年後に起業する人もいる。(よって定年はない)高齢者をお荷物としてみるには、あまりにも強引な印象を受ける。だから、人口が増えることで予算がもらえる人たちの議論に付き合うと疲れる。大事なのは、人口を強引に増やしたり減らしたりすることではなくて、人口が増える時の経済モデルを捨てて(ハコ物主義も捨てて)新しいモデルを作ることのはず…と考える。それと仕事柄、アルバイトや社員教育の現場で目にするにつけ、ちょっとお父さんお母さんの躾けの限界がきているのでは?と。(現場の表と裏で起きている事件をあげればキリがない…:汗)だからここは焦らず、まずは躾けのできる大人の育成に努める。(心の錆を落としてみる)そうすれば、少数でも立派に働こうとする子供が育って、人口は少なくとも無駄遣いの少ない節度ある質の高い社会が待っているように思う。少子化だけで終わらないで、その先の未来を創造する議論が欲しい。少なくとも、メリットデメリットの両方があるはずだから、メリットの方を大きく出来るように変革するしかない。21世紀は「ちょうどよい社会」を目指さなくてはならないのかもしれない。
2005/05/09
コメント(0)
-
上海のギター少年のお遊び
先日ギターを買った。と言っても上海で。つまり上海用ということで(笑)。何気ない商店街のお店にふらっと寄ったら、地元の若者が、ガシガシに弾いていた。楽器を手にした雰囲気というのは、どこも一緒ですね。照明が暗い古びた店だけど、活気があって楽しかった。奥の方では、いかにもそれなりのプロという雰囲気のおじさんが若者を集めてギターの弾き方を指導していた。そうこうしているうちに欲しくなってしまった。悪い病気である(汗)。ちょっと弾かしてもらおうとギターを手に取ると…、寄ってくること。「あの日本人、何を弾くのかな?」という感じで。そういう風にみられると弾けなくなるでしょう。うまくないんだから…。しかし、そこは「いざという時用の必殺の一曲」を演奏して、「へぇー!うまい!」と言わして日本代表?の面子を保つ(笑)。(これだけはまじめに練習してあるところが立派におやじ?である)すると「どうやるの?」と寄ってきて、ガシャガシャ始まる。こういうのって、楽器のいい所かな。言葉が不十分でも音とリズムで遊べること。それで、一時間くらい遊んで、ようやく気軽に引ける安いギターを買った。店の連中としっかり仲良くなったから、かなり値引いてくれた。「やはり音楽は国境を越えるんだ!」「音楽は年代を超えて友情を…」と意気揚々と帰国した。僕たちのオフィスは神保町だ。すぐ近くは御茶ノ水。楽器街である。さっき、ふとのぞくと、同じものが上海よりもさらに安く売っていた。世の中そんなもんである(泣)。つまり、遊ばれただけの日本のおじさん…だった。「おじさん遊びは国境を越える」のかもしれない(笑)。
2005/05/07
コメント(2)
-
タイトル・ホルダー
個人的に、仕事をしながらの楽しみがある。それは、タイトルホルダーの方々との出会いであり話を聴くことである。何も<オリンピック>とか<世界○○選手権大会>といったメジャーなものではなく、もっとローカルなもの。例えば…、ある会社では10年間<無遅刻・無欠勤>の方がいらした。<勤怠の鉄人>と女性にとってはあまり有難くないニックネームだったが、本当に10年間無遅刻・無欠勤を続けるには、様々な事件や出来事があることがわかった。そう、これを「続けようとする人」にとっては事件なのである。ところが、そうでない人たちにとっては取るに足らないことばかり。子供の発熱時の対応から、肉親の病気やご自身の体調管理まで、全てが小さくて丁寧なノウハウの固まりだった。通勤途中でお財布を忘れたことに気がついたら…。電車の中で具合の悪いおばあさんに出会ったら…。電車の事故があったら…。仮にだが、「10年間は絶対に遅刻も欠勤もしないように!」「もし、したら今後日本には永久に住めなくなります」とかなにか極端な罰則でもあれば、無遅刻・無欠勤の対策を真剣に考えるかもしれないが…。何しろ、継続は力なりと口で言うのは簡単だが、継続するための陰に隠された小さなノウハウは新聞に連載してもらいたいくらい面白かった。他にも、何しろ食器が好きで、あるレストランで皿洗いを15年間も続けた。その間にあらゆる食器の勉強をして、今ではその企業の食器の買い付けの担当部長に抜擢された方…など。けれど、出張の無い時には今でも皿洗いとやっているらしい。手で判断しているのだそうだ。洗い方は…もう職人というか、エンターテイメントの領域だった。食器が美しい上に大変衛生的だから、もちろん料理も美味しい。(食器で味は変わるらしい…)このように、職場の仲間や顧客が「あの人は○○をやらせたら…きっと社内一だ」のような人との出会いと話は大変勉強になる。インターネットの登場で、自分の売り方がうまい人たちは比較的有名になるのは難しくなくなったかもしれないが、このように自然発生的に人々の「推薦」「感謝」「尊敬」を集めている人との出会いは本当に貴重な体験である。このように周囲の人々から勝手につけられた周囲認定型<タイトルホルダー>が好きだ。今度、そういう人を呼んでお話を聞ける場を作りたいなぁ…(笑)。
2005/05/05
コメント(29)
-
【万博】混雑時のサービスの基本
5月4日には、愛・地球博の来場者数がおよそ15万人を記録した。関係者にとっては胸をなでおろすところだろう。ただ、それでお客さんは楽しめたのか?というと、満足度指数ではなかなか厳しい声が聞こえてくる。中には「取りあえず会場には行けた…」というレベルの人までいるから、今後の課題は、より多くのお客さんに楽しんで頂くためのレベルアップにつきる。ただし、これは100Mを12秒で走れるようになった人が11秒台を目指すくらい、努力がいる。GWでの分かりやすい反省点は、「品切れ」である。基本的には、手作り以外のお弁当持込をお断りしているのだから、夕方になると「品切れ」という、町中と同じ店舗運営ではお話しにならない。できるだけ持ち込まれたくないなら、せめて「選べる」ようにするのがサービスの基本である。どうしても「待ち」は発生してしまう。それで並んでやっと順番が来た時に「コレとコレとコレは品切れです」では、国際博覧会の看板が泣く。合格ラインとしては、並んだけど欲しいものが買えた…くらいには辿りつきたいところだ。その他、自動販売機も…雨天時の傘の販売も手を抜けない。そうでないと、お客さんに料金分の楽しさや快適さが提供できていないままになってしまい、間接的にはお客さんに借金してしまうことになる。(見方によっては…)しかし、借りた分を返すチャンスは数ヶ月しかない。ただ1回きりのお客さんがほとんどの万博の怖さはここにある。リベンジさせてもらう機会がほとんどないに等しい。(または志の低い人(スタッフ側)は、割り切ってしまう)それと、「特に大きな事故はなかった」との報道だが、それは会場運営の努力もさることながら、お客さんたちが、この数ヶ月に全国で起きた色んな事故のお陰で気をつけている、敏感になっている…ということが大きく関わっている。いずれにしろ、最後の勝負の夏に向けての反省材料が膨大に見つかったはずで、どんな改善をして7月に臨むのか?楽しみである。ということで、できれば後半の3ヶ月も足を運んでみると楽しさが倍増しているかもしれないから、ぜひ!
2005/05/04
コメント(0)
-
真実は権力よりも強し!
元ホンダF1総監督の桜井氏の話の中でもうひとつ強烈に印象的だったのは…エンジンの開発の過程で、先輩や上司との意見との対立を避け、そして威厳を持たせるために「本当はこの方が正しいのに…」というやり方を引っ込めてしまった。案の定、最終段階のテストで不具合が多発した。そして各メンバーが本田氏に呼ばれる。不具合の原因を初期段階から気がついていたことも白状した。メチャメチャに怒られると思った時に、ただひと言、凄まじい形相で「真実は権力よりも強いんだ!」と怒鳴られたらしい。それで頭の中が真っ白になった…。良い製品を作ること以外のことに賢くなりつつあった自分に気がついた。それからは、正しい意見を言い、聞き、よい製品を作るスペシャリストになっていった、とのこと。その後の活躍があの世界初のCVCCエンジンの開発→大衆車の16バルブDOHCエンジンの開発→1500ccのF1エンジンで1500馬力へとつながっているそうです。この言葉こそ一生忘れることなく胸に染み付いた、と。全ての社会でそのようになるかどうかは別として少なくともホンダの技術者の世界では本当にそうだったんでしょうね。自分の職場とか身近なところから実践したい大事なスピリットを教えて頂きました。
2005/05/02
コメント(2)
-
元ホンダF1総監督桜井氏が語るセナと本田宗一郎
桜井淑敏氏の講演を聞くのはうれしい。なんといっても個人的には、シティ・ターボシビックSIプレリュード…など当時、桜井氏が開発を手がけた車を一通り乗っていたくらいだから。どれも大変ユニークで魅力的な車だった。そうした市販車の開発を監修しつつ、F1チームの総監督までこなしていたんだから文字通りスーパービジネスマンだったと言っても過言ではない。しかも、その両方で記録を打ち立てたのだから頭の中を開けて覗いてみたい気がする。「セナとシューマッハはどちらが速いのか?」の質問に対する答えも「なるほどなぁ」とタメ息が出た。思うに、理系的なロジカルな思考と、文化芸術をこよなく愛する姿勢が見事にブレンドされた方だなぁと。セナと出会って、彼をホンダに乗せるために2チームにエンジンを供給することを選択する。そのためには予算の増額を獲得しなければならない。そこで全線テレビ中継の構想を掲げ、交渉に入る。テレビ局がつきやすくするために日本人ドライバー中島悟の起用を考える。それを天才セナに飲ませる。…などなど、F1の総監督って、エンジンなんかの開発指揮官的にしか思っていなかったので、その業務量と奥行きに驚いた。セナのエピソードでは、「センシング能力が高い」といこと。マシンがどんな挙動でどんな状態にあるのか?を瞬時に察する力が高い、と。そして、それをメカニックに的確に伝える力もあったらしい。当時エンジンの回転計のメモリは200回転ずつメモリがついていた。セナはそれを「50回転単位に変更して欲しい」と要求してきた。そんなに小さな単位でコントロールできないし意味が無いと思いつつ、セナの能力を試してみると、見事に「このコナーでは12550回転だった」と、言い当ててしまう。するとこちらも応えなければならなくなる。セナとの技術開発は楽しかった、と。こちらが改良するとすぐにそれに気がついてくれる。そして、その分、必ず速くなる。そういう関係が築けたことが素晴らしかった、と。氏の言葉で印象的なのは「初めての時が最大のチャンス!」ということ。初めて取り組む時に手を抜いたらそこでもう勝負あったである、と。それと本田宗一郎氏については、次から次へと変わるF1の規定について、ホンダバッシングがまさに最高潮に達した時についにターボエンジンの廃止が決まった。ホンダが勝つとすぐに規定が変わることにもう嫌気がさしてきた。ここまで来るともうF1から撤退するしかないと本田宗一郎氏に相談に行くと…、「なるほど。で、その規定はホンダだけに適用になるのか?」と本田氏。いくらなんでもそんなルールはなく、全てのチームが対象に決まっている。それを伝えると、「なんだ、あいつらはバカだなぁ。それじゃあ意味がないじゃないか。また、うちが勝つに決まっている。同じ土俵なら絶対に負けやしない。皆、同じ規制なら意味が無いじゃないか。ところで、相談ってなんだ?」「いいや、別に…。もういいです…」と部屋を出たらしい(笑)。なんとも凄まじくシンプルなスリピットが流れていたんですね。こういう時代だからこそ、以前よりもジーンと心に染み渡るお話しでした。
2005/05/01
コメント(2)
全23件 (23件中 1-23件目)
1