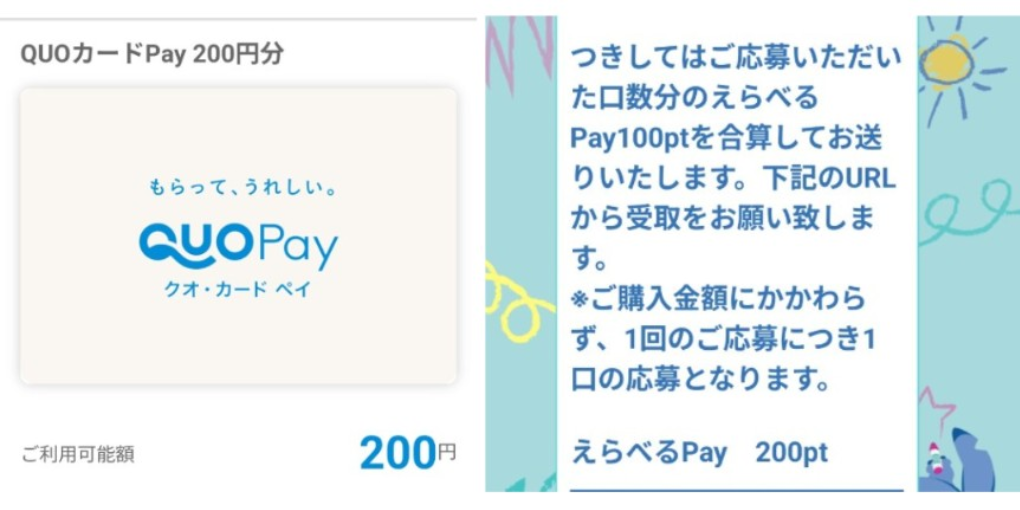2005年06月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
日本の中古品が活躍する上海の現場
道路工事の現場やビル建築の現場を丁寧?にのぞくと本当に日本製の機械や工具の多さに気がつく。クレーンやショベルカー、ミキサー車などは「○○工務店」とか「○○組」の名前が入ったままのものが多い。それと、現場を支える特殊工具(中国では)も、「○○組合」「○○商会」の文字が躍る。上海の発展には実は日本のバブルの崩壊があったからこそ、とも言える。日本に集まっていた世界の投資家たちのお金が行き場を失わずにそのまま上海を中心に中国に流れていった。さらに、日本の企業がリストラを繰り返し、優秀な人材が中国へ渡った。○イアールなど有名大手が積極的にハンティングしていった。そして何といっても、建設機械や工具などの中古品が膨大に余った。それを中国の各企業が格安値で買い叩いた。(あるいは譲った)それが一連の高層ビル建築や高速道路、あるいはその周辺の大工事に大いに役立った。人材も日本からたくさんやってきた。なんとボランティアで指導してくれる人たちもいた。それで発展が一気にフル加速状態になった。ということで、改めて現場をみるとそういうことが実感できる。上海からみれば、日本のバブル崩壊は天の恵みだったに違いない。しかし、<軍手>や<安全靴>くらいは自分たちで用意した方がいい。みていて危なっかしい…(汗)。
2005/06/27
コメント(1)
-
上海マンションバブル騒動
上海にいるのに朝からマンションに篭って企画書を作成していた。昼も過ぎていい加減空腹に耐えられなくなってきたので、近所を探索しつつ、お店を探していた。来る時の飛行機で隣になった上海人の実業家によれば、やはりマンションの値が下がり始めている、と。(場所によっては…だが)それで、そのおじさんはちゃっかり経営資産やらは少しずつ東京に移して2つの都市でバランスよく商売をするのがいい、というのが結論らしい。ご本人は昨年からコツコツ準備をしていたとのこと。お店を探す間に、不動産の店頭広告を見ながら歩いていた。昨年から見ているので、何となくわかりつつある。…とその時、いきなり後ろから大男が僕に向かって何やらまくし立ててくる。初めは「不動産屋が雇ったセールスマンかな?」と思ったりもしたが、顔を見ると目が血走っていて、そんなのん気なものではないことは直感でわかった。すかさず、わざと「私は日本人です。何を言っているのかわかりません」と日本語で答えた。するとその大男は「この店、この会社は詐欺集団です。買うのは絶対にやめなさい」…と、日本語で叫びだした。よくよく事情をきくとヨーロッパ人で上海ではあまりにも有名外資の巨大企業の元商社マンだったらしい。(社名と役職を聞けばエリートでした)何でも自分を初め紹介した知人友人同僚、そして親戚までもが相当な金額を騙されたらしい。どのように騙されたのか?彼らはどうなったのか?そこまでは会話ができなかった。というのも、いきなり店の中からヤバそうな風貌の方々が現れて、「まだいるのか!こいつ!どっかに行け!」とそのヨーロッパ人に食って掛かって行った。さすがにヤバいシチュエーションだと思い、「助けなきゃ」と考えていたら、今度はいきなり僕の方にかかってきて、「お前はこっちに来い!買え!」と店の中に引きづり込もうとしてきた。それで地面に倒された。こちらも黙っていてはまずいので、大胆に抵抗した…(笑)。(紳士な日記なのでご想像にお任せします:笑)結論から言えば、香港映画に出てくるほどのカンフーの達人はいなかった(笑)。ヨーロッパ人の彼に教えてくれたことにお礼をいい、その場を立ち去った。振り向くと、彼は持参したイスに座って、また<座り込み>を再開した。(良く見ると、大変みすぼらしい姿だった)色々な責任を取らされて今では退職して無職らしい。別れ際に「我々ヨーロッパ人は日本に進出してみて、これならアジアも大丈夫と思っていた。しかし、日本と他のアジアは全く違った。日本は唯一の約束を守る国(人々)だった。それがわからなかった私たちの勉強不足だった」と胸の内を教えてくれた。ただでさえ約束を守らないを言われる中国ビジネス。(もちろん全てではないが…)そこにかつてないほどのバブル景気が加わったのだから…その犠牲者は大変な人数なのかもしれない…。昨晩とは打って変って、身が引き締まる思いがした。
2005/06/26
コメント(4)
-
サボる人がいない職場
搭乗時間が遅れること30分。その後、機内に乗り込んでから待たされること1時間。そんなこんなで上海の到着が遅れ、一周年パーティの会場には15分くらい遅刻してしまった(泣)。けれど、上海の空港から向かう最中に「所長さん、今どこ?」「もうすぐ始まるよ」「見て欲しいから早く来てください」と何度も電話を頂く。着いてみるとちょうど始まったところ。ビデオカメラを回しながら中へ…。代表者による挨拶。その後、開業の準備、面接、トレーニング、一年前の式典、各種イベント…などの映像がBGMと共に流れる。(ちょっとジーンと来た)そして、スタッフ全員による合唱!続いてケーキカット!記念写真。そして、フロアを移動してからは立食のパーティ。そべてスタッフによる手作り感がいい。食べて飲んでスタッフとお客さんが何しろ楽しそう。本部から「こういうのをやりなさい」と押し付けられたイベントはなかなかこれほど盛り上がることはないと思う。しかし、「一周年のイベントを考えて実施してみなさい」だと積極的にお客さんのもてなそうとする。しかも自然体で。お客さんを招待してもてなす…。どっかのテーマパークと同じような。そういう時って、妙にマナーを押し付けるようなサービスはしない。「やぁ来てくれたんだ!」と。だから参加しやすい。僕もたくさんのスタッフの皆さんと再会できた。英語が上達していた人。日本語が上達していた人。何しろ身だしなみがきれいになってかっこよくなっていた人。後輩ができて先輩らしくなっていた人…。一年間でこんなに成長するんだなぁと感心してしまった。こういうシーンを見ていると、楽しんで働くのも大事な才能だな、と。どんなにマジメに働いていても、辛いことがあるとすぐに辞めてしまうならもったいない。それが転職癖になっていくし…。マジメを強制させる職場には必ず<サボる>人が出てくる。けれど、楽しい職場は楽しさをサボる人がないのがいい。勉強になった(笑)。
2005/06/25
コメント(0)
-
一周年記念で上海へ
昨年お手伝いしていた施設の一周年記念。スタッフの方が日本語で電話してきてくれた。なので、これから行って来ます!どんなパーティなのか?楽しみです。それと、実は…先週、上海のマンションに忘れ物をした。財布、免許証、銀行のカード、エアエッジ…。ということで、大変辛い一週間だった。おまけに、そういう時に限って、北海道から九州まで出張が入っていた(涙)。よく凌いだ…と自分を褒めてやりたい心境だ(笑)。というのも、現在、@成田空港で、財布の中身は…なななんと、あと千円!<肉うどう>を食べようかどうしようか?迷っている…。
2005/06/24
コメント(0)
-
「ていねい」への道
マナーがどうの、という話はなかなか伝わりづらい。それはきっと、「相手にとってどうなのか?」が問題であって、こちらが「決まった!(フッ…)」と自負するような仕草で応対したところで、相手にとって「大げさな…」「硬いんじゃないの」と思われたなら自己満足スキルみたいなものだ。中国人スタッフの言いたいことにも同感。そこで、少しずつバラして、「ていねいに…」をどう指導するか?これも人によりけりで色んな教え方があるでしょう。どれが一番良いのか?答えもまた人それぞれかも。僕たちは中国でも日本でも同じ用に伝えている。「誠心誠意」とかの心構えの解釈はこれまた人それぞれなので、具体的に。「一度に2つの動作を(作業も)しないこと」お店のカウンターでパソコンを打ちながら「いらっしゃいませ!」とやらない。<ながら族>はダメですよ、と。オフィスでも、人と話しながら携帯電話のメールチェックしたり…。日本でも中国でも<冷たく感じる人>の正体はコレが多い。いったん手を止めて、お客さんの方を見て「いらっしゃいませ!」が気持ちいい。これは職場の仲間でも一緒。<脱ながら…>だけで随分印象が変わる。お店の雰囲気も変わる。職場の雰囲気も…。中国だとそのことがリアルに実感できる(笑)。
2005/06/19
コメント(4)
-
中国人スタッフにマナーを指導するには…
中国人スタッフの前にすると「もっとていねいにできないかな」と思うことは多い。僕たちからみると何かと荒く見えてしまう。それで接遇講師なる方々が中国でも指導しているが、中には、なんだかピンとこないことがある。(そういう人がいる)それはなんでだろう?と思っていたが、最近わかってきた。「マナーが大事ですよ」とおっしゃるその方は確かに、決めの場面でのマナーはうまい。しかし、それ以外のシーンではなんだかいつもイライラカリカリしている。中国人スタッフ相手に仕草を見て「あんなのあり得なーい!」と。それでまたカリカリ…。だから教え方も厳しいというか、下手すると見下しても見えし…。けれど、きれいなマナーや仕草を身につけてみても、実はそれで結構ストレスになっているならあまり意味がないように思う。極端な話、よいマナーを身につけたら幸せになれるんだ…という希望が見えてこない。逆に幸せそうに見えない。言葉が通じない分だけ、滲み出ているモノには敏感なのだと思う。それなら多少荒くても、無邪気さを残した笑顔でノビノビ働いてもらいたいものだ。もし、指導するなら、そういう個性を残しつつ、マナーを身につけてもらえるにはどうしたらいいのか?それが創意工夫であり、ソフトだ。「無邪気さと引き換えるほどの魅力を感じなかった」というのが正直な感想である。
2005/06/18
コメント(2)
-
日系企業が不得意なもの
ことオフィス環境に関して言えば上海には大いに学ぶべきところがる。今までいくつかのオフィスを見せて頂いているが、多分だが、欧米系のよいところを真似ているのか?なにしろ一人当たりのデスク周りが広々で働きやすい。適度に音楽など流れていたり…で、多少自由な雰囲気が漂っている。決して最新のビルではなくても、それなりにセンスのある改装が施されていたりして、そこにいるのがかっこいい…と思わせたり。たまに知り合いや友人が訪ねてきても「どうだい?」と堂々とオフィスを見せられるらしい。案の定、日系企業の場合、あまり気を使わないから隣のデスクとピタッとくっついている…例のパターンが多い。(全ての企業とは言わないが…)これは多分、知人友人には見られたくない。(いかにもデスクの作業員…というイメージらしい)オフィスだけ見ていたら、上海であることを忘れる(笑)。(まるで東京にいるみたい:笑)この点は大いに反省するべき点がある。少し日系企業をかばうならば、戦後は特に工業が中心で伸びてきたから、オフィスを贅沢にするという発想が乏しかった。なにより工場現場を大事にした。しかし、工場を持たない企業の場合はオフィスが現場になる。その転換が少し遅れていたのかもしれない。そして、給料以外に環境は大変重要であることを再認識した。客観的にみても、遅刻早退欠勤が多いのは実は環境が大きく影響しているらしい。(かつて調べた方々がいた)「行きたくなる職場環境」があれば、必然的に勤態が安定する、定着率も…。そんなものだそうだ。おまけに人間関係にまで影響を及ぼすそうだから、人事部はオフィス環境づくりに真剣に取り組まなければならない。考えてみれば、自宅のマンションの部屋で仕事をした方がノビノビしていい…では、職場が自宅よりも環境が悪い証拠。(SOHOが増えるのも納得できる)昔は、自宅よりも会社のオフィスの方が上回っていたから会社に行きたくなれたらしい。これは日本でも中国でも一緒で、生産性をあげていくには見逃せない要素だな、と実感。社内のマガジンラックにオフィスの<空間デザイン>系の雑誌や本があるかないか?が会社選びの重要なポイントだとは…(汗)。日系企業が頑張れる余地は、まだふんだんにある!
2005/06/17
コメント(0)
-
ビデオ研修の目的
今回も「ディズニーランドのビデオがみたい!」というスタッフの皆さんのご要望にお応えしてかつてハンディカムで撮影した映像をDVDで持参してそれを見ながら研修した。まだ18-25歳くらいの人たちだからやはり楽しいのがいいに決まってる。(年取っても同じだけど…)けれど、今回は初めて見せた時とは違った。自分たちも一所懸命に接客しているから、「ああーていねい」「などほどなぁ…」など、驚嘆とタメ息が入り混じってそれを眺めている方も楽しかった。大きく瞳を見開いて、本当に瞬きが少なくなる(笑)。実はここがポイントで、上海に限らず日本でも、「なるほどなぁ…」となる人は大丈夫。逆に「でも、この辺はそんなに大した事ないじゃない」の場合は要注意。真剣に取り組んでいるかどうか?はこうした瞬間にすぐにわかる。真剣な時は、凄いモノに敏感になっているからすぐに気づく。何かしら盗んでやろうとか吸収してみようと。成長しつつあって、ちょうど心のコップが大きくなってきてるから、どんどん注げる。対して、半端者にはわからないから、何でも批評的に斜め目線で逃れようとしてしまう。コップがまだ小さいままだから、入れようとすると溢れてしまう…。その場合は、やたらにノウハウを指導する前に、コップが大きくなるような支援が必要。だから、こういうビデオ鑑賞は成長具合やコンディションを把握するのには持ってこいなのです。早く現地に連れて行ってあげたいものです!香港にもできるし…。(密かに計画中:笑)
2005/06/16
コメント(0)
-
上海のマンションバブルの臨界点
ついに上海のマンション相場がピークを迎えたらしい。まぁ正確には物件によって、あるいは地域によって違いはあるようだが。(だから住むために買う人にとっては良い状況がやってくる…)ただ、冷静になってみればほとんど東京のマンションと同じ値段というのはやはり…怖い。アメリカ人投資家たちは、散々稼いでおいて案の定、結構撤退しているらしい。(マンション投資では)「いや、上海はまだ大丈夫。万博までは絶対に伸びる」とか、「日本と違って政府がコントロールしているから二の舞は絶対にない」と言い張る人もいるが、「そうは言ってもやっぱり危ない」という中国人もいる。(意見はいろいろ)ただ、そうやって目くじら立てる人たちは楽して儲けたい人たちだから仕方がない。別に多少値下っても、それは段々と適正価格に近いづいていくわけだから本来は経済の揺り戻しの範疇かもしれない。僕が思う一番の懸念材料は「個人の借金」で、長びく上海バブルのお陰で、初めは慎重だった個人(平均所得者たち)も、「オレも…わたしも…」と、マンションやら車の購入やら株などに夢中になりだした。しかし、悲しい世の中の常で、平均所得者である個人が乗り出した頃というのはもうそろそろ…の時期で、そこからバブルが加速することはほとんどない。日本の場合、バルブが散ってそれはそれで大変だった人々もたくさんいるが、バブルの前の蓄えがあったし、両親、親戚など田舎に家や土地を持っていたりで肩代わりもできた。(これがある程度クッションの役割を果たした)大借金まみれの人もいれば、元に戻っただけの人もたくさんいた。ところが、上海の人々の場合、そうしたクッションが薄い。(極端な話、せんべい布団である)さらに借金の総額でも東京都民の借金の総額を抜いている。だから本当にバブルが散った時のインパクトは…あまり考えたくない…と。政府がついているから大丈夫…というか、政府は躍起になってゆっくりバブルを着陸態勢に持って行きたいはずだ。その証拠に、マンションの頭打ちがくる直前から外資の参入の法律を変えだし始めている。そのままだと、今度は日本で味をしめたハゲタカファンド軍団の来襲があるからだ。けれど、外資の参入がある程度持続できないと、これまたすぐに萎んでしまう。何より職場がなくなってしまう。ジレンマである。だから政府はA面とB面を激しく使い分ける。(バレているけど…)中国は今や世界の工場から消費市場になった、と言われるが、職場を失えば、消費もしぼんでしまう。さらに、こと世界の工場に関しては、ベトナムやインドが虎視眈々と中国の後釜を狙っていて全く油断できない状態にある。そう、中国も追われているのだ。
2005/06/15
コメント(2)
-
上海のスタバで課外授業
サービスについての指導の限界はお互いにいいと思っているサービスが違うこと。正確には、そんにいいサービスを受けたことがないから、「例えばスターバックスみたいな…」と話してもピン!と来ない人がいる。つまり、行ったことがないらしい。もちろん「ホテルでは…」とか「スチュワーデスは…」も同じことで、日本で言うなら旅館と修学旅行のバス電車くらいしか知らないスタッフに向かって青筋立てても仕方ない。「では…」ということで、課外授業が大事になる。初めて入るスタバでの表情を見ているだけでも楽しい。そして、真剣にスタッフの働き方を観察している姿にはちょっと感動。お互いに同じモノを見て、あーだこーだと語り合っておくことが必要。つまり「共通言語」を作り出すことになる。それと「基準」も。どう頑張っても「中国人と日本人」には変わらないから「こういう風にやろう」と共通の目標がバシッと決まらないと「中国人って…」「日本企業って…」の掛け合いに陥ってしまうから、結構大事な時間だと思っている。その証拠に、こうしてから働くと大きな見解の相違的なトラブルに発展する事は少ない。…なぁーんて言ってみたところで、日本国内でも「共通言語」や「基準」が不明確で「東京ものは…」「だいたい名古屋人は…」…となることがあるから、あまり変わらないのかもしれない(笑)
2005/06/14
コメント(0)
-
優秀な中国人の採用の秘訣
あるメーカーの方に伺った話によると中国人のオフィスワーカーは「チャット」が好きで「MSN」でチャットを立ちあげたまま仕事をしているらしい。上司の目を盗んでコッソリ…のうちは可愛かった。見かねてある会社に調査してもらったところ、オフィスワーカーのチャット時間は一日当たりの平均は1時間を超えたいたらしい。200人いれば…200時間/一日当たり、である。これにネットサーフィンが加わると…いくら人件費が安いからといっても、日本との差はあと少し…まで来ているのかもしれない、と。中国のPC普及台数が日本を超えたと大騒ぎしていても、圧倒的に会社の数、働く人数が違うから、職場のPCの台数が多い。それは当然の話で、現実は、まだ個人や自宅でPCを持っていない人が多い。だから人によってはオフィスで。ある人たちはネットバーに通うことになる。加えて、新聞でもテレビでも雑誌でも収集できる情報が限られているからネットにハマる気持ちはわからないでもない。しかし、そのネットも近々、政府に届出をしていないHPやブログは削除されてしまうらしいから、自由に情報を求める欲求はさらに高くなるのだろう。そうなると、チャットで生の情報をリアルタイムで交換したい、という展開なのかもしれない。そうは言っても、会社側はたまらない。「他部署との連絡に便利だから…」と立派な理由だが、毎日一時間もするくらいなら、「足を運ぶか電話しなさい」となる。現場の生産性をあげるのも大事だが、実はオフィスワーカーの生産性にはもっと膨大な伸びる余裕だらかもしれない。中国の大卒は優秀だとどんなに太鼓判を押してみても、人間なんて環境でどんどん変わる。「優秀」という言葉がどんどんサビていく人もいるはず…(涙)。優秀だった大学生の時みたいに真剣に働いてもらう仕組みを造ることが大事ですね。学歴だけで採用したんじゃないよ。その学歴を積み重ねたその勤勉さが欲しいんだ、と。採用面接の時は、そういう約束を忘れずに!
2005/06/12
コメント(4)
-
中国の未来は日本の省エネ技術次第
上海の街並みを見ていると、超大型の高層ビルやら橋やらリニア…などの超大型ハードは段々と整いつつあって、一時よりもクレーンの数も落ち着いて来たように写る。その後、マンションが続いて乱立しはじめて、それに庶民の投資も混ざってきて過熱気味…か。それも徐々に落ち着き始めると、いよいよ街の小売店舗が段々と充実してくることになる。遠目に観た上海は、未来都市を髣髴させるが、一件ごとの小売店舗は意外に過去形…で、古いモノが多い。もちろん古き良きもあるが、そうでないモノも大多数だ。そうなると、この辺からは日本の中小企業の出番かなと思う。何しろ、建物の造りがあまり良くないので、設計デザインの創意工夫が試される。かっこいいデザインは色々あるが、陳列技術や狭いながらの収納の工夫など、よいお店への道は日本に通ずる。さらに、照明などの電気周りからお店全体の省エネ設計にかけてはお手のもの。(省エネは電化製品と自動車だけではない)もうそろそろかっこいいだけでは済まされないはずだし…。(この分野では比較にならないほどの開きがある)商店街を支える味のある小売店舗の充実が、見た目は派手でも土台がユルユルの上海の都市の付加価値を高めることになるはず。きっともっと住みやすくなって、付加価値も上がるはず。上海バブルの暴落をやわらげる意味でも、その役割は大きい。もちろん大型商業施設もしっかりお願いしたい。日本人デザイナー、設計者たちがさらにどんな腕を見せてくれるのか?興味は尽きない。いろいろあるけど、中国の未来は電気と水次第だから、言い換えれば日本の省エネ技術次第である。それ以外の経済的要素を大型画面テレビのごとく見て楽しん議論してみても、結局は電気と水の問題が解決しないと、(それとその周辺の環境問題も)所詮は画質の小さい未来しか見えてこない。中国の未来は、緩やかな発展と省エネの進化のセットでしかあり得ないのだから、「抜かれる、抜かれない」の次元ではない。それに、なんと言っても地球温暖化防止のためにも大いに腕を奮って頂きたい!
2005/06/11
コメント(23)
-
エコノミストがしなければならないこと
@成田空港の本屋さんあるビジネス系の雑誌を見ていて「ふと…」じゃなくて、凄く疑問が湧いた。記事の内容は相変わらず「大丈夫か?日本経済」みたいなないようだったが、冷静に考えてみれば、大丈夫な業界や企業と大丈夫じゃない業界や企業がある。全部ダメでもないし、全部無事でもないはずだ。きっとそれなりに淘汰があって、そういうプラスマイナスがあって、ちょっと大丈夫くらいかな?と個人的は考えたりしている。しかし、そういう予測っぽいことを書きまくっている人たちは銀行系出身者、証券系出身者、生保系…となにしろ金融系が多い。対してメーカー系の人たちはあまりエコノミストになっていないということか。けれど、金融系は「まだまだ頑張れ」の業界で、決して世界最強ではない。この十数年の流れをみれば、結構苦しい業界で、(いや深刻に苦しい)メーカー系のGDPの合計には遠く及ばない。そういう人たちが、やれ「ソニーは…、ホンダは…」とメーカー系のことまで色々と書いているが、それは大きなお世話かもしれない。本業外の記事は、きちんと現場に足を運んで書いた方がいい。(現場が透けて見えない記事だった。多分、ネット&メールだな、きっと)逆に、足を運んで取材したモノは優先して掲載するべきだ。(そういう人もいるだろうし…)そんな暇があったら、何しろ本業をきちんと勉強して実践して世界を相手に戦える業界にして頂きたい…と。もっと世界をリードする商品を開発して人々に愛されなさい…とメーカー系でない僕でもたまにそんなことを考えてしまう。(けれど、以外に仕事はメーカー系が半分を占めるから気になる)それになんと言っても、予測が外れた時に、別に誰も謝罪しないし責任を取ったところをみたことがないから、(少なくとも僕は…)どこまで信じて良いのか?疑問だらけだ。どんなことでも、まずは自分の足元が大事でしょうね。
2005/06/10
コメント(2)
-
@上海:10-18日
今月の目的は、現場(店舗)のスタッフと管理職の研修と現場トレーニング。それに、借りているマンションの引越し。オフィスの近くに。何気にタクシー代がバカにならないし、雨の日のタクシーはつかまらないし…。(よって自転車マンと化す予定です。しかし、あくまでも予定ですよ:笑)サロン化して交流会や勉強会、それに僕の大好きな(自慢の)「ためになったテレビ番組試写会」(ご希望があれば格闘技系も…)などをしたいから…広いところに(笑)。
2005/06/09
コメント(2)
-
学問のプールから出て海で泳ごう!
最近、本屋さんで気がつくことは、「自分の気持ちを楽にする…」とか「今のままの自分でいい」とか「会社員は辞めよう」みたいな…。なにしろ癒し&自己啓発系、起業系の本が目立つように置かれている。これは俗に言う<五月病>のシーズンだからだろう、と。あれほど勢い良く入社したはいいけど…こんなはずじゃなかった…というタメ息が出始めているシーズンだから、本屋さんはそういうことをしっかり計算してこまめにレイアウトを変えたりしてる。考えてみれば、30-40年前と違って、どうしても食べていかなければならないような理由は少なくて、反対に「辞めたくなる理由」はたくさんあるからだろう、きっと。その時に「自分の本心に従って行動すればいい…(辞めちゃえば…)」とか甘いアドバイスをする人もいるが、本心がわかってないのに従えないのでは?と思うことがある。本心って、嫌なことや逃げたい時に「辞めちゃえ」というのが本心なのか?本当は、それを克服していく強い自分になりたいのが本心なのか?外野からはわからないはずだから、あまりアドバイスはしないようにしている。まぁ学生時代に教室で一所懸命勉強していても、社会に出ると「プールであれほど泳げたのに、海ではうまく泳げない…」というくらいの違いは誰でも実感しているのだと思う。それで退職して、大学院に行ったりMBA取得で留学…と、気がつけば30才。「今度こそ…」と思っても、プールが大きくなっただけで、プールはプールだった。職業的に明確な目的があれば別だが、あまり学問にしがみついて社会に出る事を先延ばしにしてしまうと、だんだんと怖くなってしまうんではないだろうか?というのも、それだけ勉強しても溺れる人はやっぱり溺れるから、やはり海に出るしかない。海は海の泳ぎ方や生き方があるから、多少溺れそうになっても海で練習した方がいいんじゃないかな…。(また学校に戻ると次は35才だぞ!Oくん)
2005/06/06
コメント(0)
-
商業施設はソフトビジネス
日本式…負けてませんね。北京でオープンしたイトーヨーカ堂は大健闘の様子です。一口にサービスと言っても、その内容は様々で何も接客だけではない。接客に関して言えば、それぞれの地域の事情や習慣、価値観もあるから一概に「○○が一番!」とは言えない。しかし、日本式がサービスで他国を大きく引き離す理由は接客以外の強さにある。「整理整頓」「陳列技術」「衛生的」「時間厳守」…とお客さんの快適で安全を維持するためのオペレーションが圧倒的に強い。わかりやすく言えば「準備」と「修復」と「後片づけ」。これは工場経営から学んでいるから当然かもしれない。それらが塵も積もると「気持ちいいサービス」となる。コンビニも健闘中だが、大型スーパーも…。考えてみれば、セブンイレブンやマクドナルドにディズニーランド…など、積極的に輸入して、その上で改良に改良を加えていく…のは、工業の分野だけではなく、サービスの分野でも先端を行っている。(たいてい本家を抜いてしまうところが素晴らしい)つまり、中国においても<ソフト>で商売をしているということ。商品は中国国内で仕入れているわけだから。(生産指導もしているから凄い)スーパーマーケットがパソコンだとしたら、サービス全般の仕組みがウィンドウズみたいなもの。だから、商業施設のソフトを輸出しているとも言える。(使い方も現地で指導している)中国との商売は工業製品の輸出入のことばかりが取上げられているし、新聞の見出しに「ソフトの輸出大国」とは出てこないけど、すでにそういう商売をしているのだから素晴らしい。DVDとか工業製品と違って、ちょっとやそっとでは盗まれないのがよい。盗んだつもりでも…サービスは品質がすぐにわかるし。これから、オリンピックと万博に向けて、さらにソフトの輸出ラッシュが始まると思う。(両方とも成功は日本次第かもしれない…)
2005/06/05
コメント(0)
-
新しいスペースマウンテン
ディズニーランド・パリには、ついにスペースマウンテン2がオープンした様子。(東京はまだなのに…)なんでも館内の映像は相当きれいらしく、さらに音楽とコースの起伏が連動していている…とのこと。これが本当なら乗ってみたい度が上がります!それにしても…ディズニーランドは、こうしたリニュアルがうまいですね。今まであったアトラクションを全部壊して新しくする…というのではなく、結構、何度もリニュアルして大事に育てていくあたりはさすがだなと。<イッツ・ア・スモールワールド>なんかもオープン以来何回かカラーリングなども変わっていて常に新しいモノに感じてしまうし。「昔のモノ=古い=ボロい」という構図にはならない。昔のモノに価値が増していくような…。うーん、これもブランドを育てていく底力なんでしょうね。
2005/06/04
コメント(4)
-
マニュアルレスの本当の意味
ある本の中で「マニュアルレスが大事」あって、マニュアルはいらない…とか書いてあった。いくつかの有名チェーン店を例に挙げていた。それを読んでいて、著者が業界シロートかどうかわかった。というのも、実例に挙げていたそのチェーン店はしっかりマニュアルが存在する。けれど、現場でマニュアルをいちいち読むことは少ない、ほとんどない。なぜか?それはトレーナーがその内容をきちんと教えてくれるからだ。トレーナーが熟読して内容を身につけているということ。マニュアルをテキストとして「読みモノ」になっているよりも「人が伝えるもの」になっている方が実践の効果が高い。つまりより良いサービスになる、ということ。マニュアルを渡されて、「はい、では28ページの説明をします…」だと、確かに暗記はできるかもしれないが、それだけで教わったスタッフは、世間で言われる「マニュアルのサービス」となってしまう可能性が高い。(テキストの文章が透けて見えてくるような…:笑)対して、あくまでもトレーナーという<人>から教わった人は言葉遣いから雰囲気まで伝わっているから<ぬくもり系>サービスになりやすい。(自分の言葉でサービスしているように聞こえる)これは「読み聞かせ」と似ている。そこに抑揚があったりして、人の気持ちが込められてくるから文字だけだとなんとも無機質だが、人が伝えてくれるとなにやら<バイブル>のような気がしてくるから不思議だ。<作業手順>だけならテキストでも伝わるが、そのお店、会社の理念やこだわり…といった<魂:スピリット>の部分は絶対に熱意を持った人が伝えた方がいい。だから、「あの職場がトレーニングはあるけどマニュアルはない…」(見たことない…)と言われるくらいでちょうど良いのだと思う。(まぁ職種にもよるけれど…)
2005/06/03
コメント(0)
-
読書でわかる心理状態
改めて本棚にある本を眺めて見ると、自分の興味のあるモノがよくわかる。(他人のも…)先日、本屋に立ち寄って20代半ばくらいの人たち3人がビジネス書のコーナーであれこれ本を手にとって話しているのが聞こえてきた。それは、まさに20代後半ー30代前半の僕の姿だった。当時は、いわゆる<管理職>になって気合が空回りで何をしても<カスる>状態だったので、(部下に相手にされないし、上司にはあてにされない…:涙)本を買い込み、セミナーや研修にまっしぐらな日々だった。それでバンバン買い込んで勉強した…はずだった。ところがある日、師匠と仰いでいたHさんが、僕の持参する本をみて、「いつも所長はいろんな本を参考に見せてくれるけど、あなたが重症であることがよくわかったわ」と言われた。「へっ!?なぜですか?」「だって、これって自分の上司やクライアントの管理職に対しての不満を確認しているような本の選び方よ」と。そう言われて冷静に考えてみると、「経営者の条件」とか「こんな管理職は…」「辞表を出せ管理職…」のようなタイトルの本ばかりになっていた。本当は、僕個人の啓発のために始めた読書が、いつも間にか、「ほーらね、ここにも書いてあるでしょう」「だからみなさんはダメなんですよ」「本当にできる管理職はこうなんです!}と言わんばかりに、周囲のおじさん管理職や経営者に対してのあてつけのごとくの読書に変わっていたのだ。そこでH先生は「本当は、上司がどうのではなくて、その上司に意見を聞いてもらえるようになるための本を買って勉強するはずだったんじゃないの?なんか嫌味な読書になってない?他人のアラを確認するためにお金使って何が楽しいの?あなたは今、ねじれてるわね」と単刀直入だった。「世間で言われる、上司が部下の意見に耳を傾けている、傾けていない…とかに踊らされてはダメよ。考えて御覧なさい。あの部長だって、部下が25人もいて、クライアントや取引先が50社くらいあるでしょう。部下一人当たりに耳を傾けられる時間なんてそんなにあるわけないでしょう。だから部下であるスタッフ方が、短い時間でスパッと意見や提案ができるスキルを身につけなければならないのよ。これは別に部長のせいじゃないの。あなたは部長をやったことがないからわからないだけ。そんなあてつけのための本を読むくらいだったら、コミュニケーションでもほうれんそうでも、そういう<自分ごとの本>をしっかり読んで練習しなさい!」と、おっしゃって頂いた。もうなにも言えないほど当たっていて、ひどい時は、本田宗一郎氏のことを持ち出して「それに比べてあの社長は…」と考えたりしていたのだから…(汗)。それに気がつくとH先生は「そうでしょう。それはたまらないはずよ、社長たちも。それを言ったら、経営者たちが32歳の所長とホンダの桜井さんと比べて所長は語学がまるっきりダメだ。それと集中力も桜井氏に比べて1/10しかない…とか。それと…○△×■、とやられたら嫌でしょう?同じことよ」そうです。一時期はこのように<嫌味な読書家>だったんです。あのようなスーパービジネスマンたちと比較されては堪らないと思いました。読書の仕方に心理状態が透けてしまうんですね。それ以来は自分にとって等身大の本を中心に読むようになりました(笑)。…ということで、「若者たちよ、自分のための本を買ってくれ…」と心の中で叫んでみた(笑)。
2005/06/02
コメント(4)
-
採用基準は「お勘定お願いします!」
一口に採用基準と言っても、職種や業種で多種多様で、「これが正解!」とはならない。(本ではあるようだけど…)「誠実は人」とか「意欲のある人」さらに「品が感じられる人」など印象を見るだけでも結構ある。最近、面白い事に気がついた。会社選びをしている人たちの意見が、「誠実な経営者がいること」「社風に品が感じられること」「人を大切にしていること」など、人事部の採用基準と似ていることである。まぁその他、待遇面やらいろんな項目があるけれど、このように似ている部分もしっかりあるんだなぁと。そして、それらの項目が選択肢にあがるということは、いかに「そうでない人」「そうでない会社」が多いか、ということの表れのような気がする。僕の場合も社内外問わず、人を見る時の癖がある。それは「お客さんの時の態度」である。仕事している時は、何らかのお客さんがいるもので、(取引業者さんなど)その際にきちんと応対していることは当たり前。これは社員でも部長でも社長でも…。素性に近い姿が見えやすいのが、食事などに行ったりした際の「お客側になった時の態度」である。別にお客さんなのに妙に気を使う必要もないけれど、威張り散らす必要もない。オーダーする時とかに微妙な「差」が出てくる。「お愛想!」と叫ぶのか、「ごちそうさま、お勘定お願いします!」と言えるかどうか?そう考えるようになったのにはワケがある。僕の初めてのボーナスで両親にご馳走した際に、いきがり小僧だった当時、初めての大枚はたいてのご馳走だから完全に舞い上がっていたのだと思う。で、「お愛想!」と勢いよく手をあげた。…ら、いきなりその手をバチーンッ!と叩かれ、「なんだいその偉そうな態度は(怒)!」と鬼の形相の母だった。「さっきから我慢してれば。店に入ってからずーっと店員さんに威張り散らして。どこでそんなことを覚えたんだい?えっ?」こうなるともう止まらない。「そういうのは心が錆びた人のやることなのよ!」結局、僕はお店の人に謝罪して、さらに代金は母が払った。出させてくれなかった。「こんな品のカケラもない食事なんか奢られたいわけないでしょう!」と。「それに…」と最後にひと言。「もし、このお店の店員さんがディズニーランドに来たらどうするの?どんな顔でサービスするつもりなの?そういうこと考えたことある?」「・・・・・(汗)」「それが社会生活なんだからね。覚えておきなさい」と。そんなことがあってからは、「ご馳走さま。お勘定お願いします!」と言う人に出会うと凄いなぁ、と思うようになった。ということで、今では僕も曲がりなりにもサービス業で食べさせてもらっているわけだから、できるだけ感謝を伝えたいなと思っています(笑)。
2005/06/01
コメント(4)
全20件 (20件中 1-20件目)
1