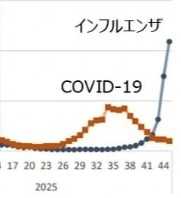2023年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
10年に一度クラスの寒波を迎えた仙台・宮城
ここ数年、雪のない1月に慣れきっているので、先週前半からの寒波襲来には驚いた人が多いだろう。とにかく気温が低い。25日には、仙台ではマイナス7.5度、石巻ではマイナス8.2度、登米市米山マイナス9.4度を記録したという。日中も気温が上がらず仙台のマイナス4.2度は過去2番目、気仙沼のマイナス7度は過去最低。10年に一度クラスの寒波と表現する報道があった。■関連する過去の記事 2月最高の気温を記録!(2016年02月15日) 山形で一番寒い大井沢の「ゆきんこ祭り」(2016年01月07日) 昭和22年以来の積雪を記録(2013年4月21日) 積雪最新記録を更新中(2013年02月25日) 釜石で35.6度(2022年06月26日) 9月の気温差 盛岡が世界2位(2012年10月15日) 積雪の一番は青森県(2012年03月03日) 今季一番の冷え込み(2012年01月29日) 異常低温の冬 仙台(2012年01月28日) 冬将軍頑張る(2011年1月30日) 薮川はもう氷点下3.8度!(2010年10月20日) 四月の雪を考える(2010年4月17日) 花と雪(同じ日) 9月に最高記録更新! 暑いぜ仙台(10年9月4日) 真夏日数が過去最高に(10年8月25日) 薮川が寒い理由(10年2月7日) 仙台の最低気温を考える(10年1月15日) 大雪の庄内(09年12月17日) 薮川で氷点下(08年9月29日) ダイナミックな寒暖の差(06年11月28日) マイナス10度の朝を迎えられるか(06年1月9日)
2023.01.29
コメント(0)
-
焼酎一杯グーイと鳴くセンダイムシクイ
鳥の鳴き声を人間の言葉に当てはめることを「聞きなし」という。ウグイスの「ホーホケキョ」など。国や地方によって異なる。センダイムシクイは、「焼酎一杯グーイ」なのだそうだ。また、別の聞きなしとして、「鶴千代君」がある。これを歌舞伎「伽藍先代萩」(めいぼくせんだいはぎ)の鶴千代君にちなんだことが、この鳥の和名の由来だという。■関連する過去の記事 江戸時代のビッグな御家騒動(2011年11月6日)(伊達騒動) 天下の三大お家騒動(2011年11月3日)(伊達騒動) 半田銀山と五代友厚(10年8月30日)
2023.01.24
コメント(0)
-
創作こけし日本一は何県?
伝統的なスタイルに捉われない自由なデザインの創作こけしの生産量は、群馬県が日本一。また、高崎だるまは年間約90万個の出荷で、全国シェアの半分を占める。こけしもだるまも、仙台・宮城の伝統工芸品。群馬と宮城、親近感わきますね~■参考 『群馬のトリセツ』2020年、昭文社■関連する過去の記事(群馬県) 日本三古碑と上野三古碑(2023年01月13日) 多賀城碑、壺の碑、日本中央碑について(2010年11月1日) 多賀城 壺の碑(08年9月15日) 日本の三古碑(07年8月22日)(多賀城の碑)
2023.01.19
コメント(0)
-
シンフォニックジャズ&ポップス
NHK-FM「吹奏楽のひびき」でオリジナルポップスを聴きながら、作業中。思い出すのは、もう5年ほど前か。文京シビックホールで、シンフォニックジャズ&ポップス全国大会を聴いた。当日券で飛び込んだのだった。わが宮城からは八巻先生率いる古川学園高校の堂々たる演奏もすばらしかった。この大会は、吹奏楽の新しい可能性を引き出すため創設されたのだという。ウインドの響きを重視しながら、マーチングや特殊な楽器編成などに走らず、ステージで演奏者たちの主体的な楽しさを感じてもらいたい、ということだろうか。思えば、今日の番組の冒頭に流れた岩井直溥さんの曲は、1975年の課題曲だ。あのころ、やはりポップス系の課題曲を提供した河辺公一さんが、いまの若者が軽音楽から離れていることに危機感を持っていたというのを、何かで読んだ気がする。東海林修のディスコ・キッドは、譜面が稚拙とかかなりの批判もあったが(バンドジャーナルに書かれていた気がする)、課題曲として採用した吹奏楽連盟も含めて、関係者は音楽と教育について、ほんとうに真剣だったのだと思う。
2023.01.15
コメント(0)
-
日本三古碑と上野三碑
上野三碑(こうづけさんぴ)は、国内最古の石碑群で、2017年ユネスコ世界記憶遺産に登録されている。高崎市の鏑川と烏川の合流点付近に、飛鳥・奈良時代に建てられた3つの石碑だ。このうち、多胡碑は、那須国造碑、多賀城碑とともに、日本三古碑に数えられる。・山上碑(やまのうえひ、681年)長利という僧がなき母の黒売刀自(くろめとじ)のため建てた石碑。完全な形で現存する日本最古の石碑。・金井沢碑(かないざわひ、726年)三家氏という一族が先祖供養と子孫繁栄、そして一族が仏の教えで結ばれ、仏に仕えることを誓った石碑。・多胡碑(たごひ、711年)既存の3郡から300戸を割いて新しく多胡郡がつくられた記念に建てられた。書体が美しく書道的価値も高い。上野三碑は3つの事実を伝えている。1つは多民族共生社会の形成。石碑文化はもともと中国から半島経由で伝来したもの。この地域には新羅系をはじめ多くの渡来人が居住しており、石碑もその協力で建立されたと考えられる。2つめは仏教の伝来と浸透。山上碑を建てた長利は、東国を代表する大寺院放光寺の僧であった。また、金井沢碑には三家(みやけ)氏一族が仏教信仰を誓う文が刻まれており、当時の上野国にも仏教が浸透していたことがうかがえる。3つめは日本語の基礎の芽生え。当時の公用文の漢文とは異なる日本独自の表記を編み出す努力が国内で続けられていた。その流れの中で、訓読みした漢字を日本語の語順に並べ替える方法が採用される。そのことがわかるのが山上碑だ。碑の53個の漢字はすべて日本語の語順に並べられており、山上碑はこの表記方法が完全な形で残る最古の石碑である。■参考 『群馬のトリセツ』2020年、昭文社■関連する過去の記事 多賀城碑、壺の碑、日本中央碑について(2010年11月1日) 多賀城 壺の碑(08年9月15日) 日本の三古碑(07年8月22日)(多賀城の碑) 記事リスト古代・中世の仙台・宮城もご覧ください。
2023.01.13
コメント(0)
-
温泉医学の権威 杉山尚
温泉の本を読んでいて、杉山尚(すぎやまたかし)東北大学名誉教授のことを知った。仙台市出身、2004年に89歳でご逝去。東北帝国大学医学部卒業後、東北大学附属温泉医学研究実験所教授、附属鳴子分院院長などを歴任。読んだ本の内容とは、次のような趣旨の内容だ。湯治は「一巡り」7日間が多いとされる。ホルモンの分泌、血圧、心臓の拍動数、基礎代謝量、血中中性脂肪や血糖値などが、およそ7日周期のリズムで正常化していくからだ。温泉療養で、疲労・倦怠感、眠気、食欲の増進や減退、下痢や便秘などの胃腸障害、頭痛、同期、めまい、発熱、発汗などの全身症状や歯痛、咽頭炎などの炎症症状がでることがあるが、湯あたり(温泉反応)と呼ばれ、冬至が盛んで一日に何度も入浴した時代にはよく見られた。杉山尚東北大名誉教授やドイツの研究によって、湯あたりは療養開始から7、14、21日前後に多いことが突き止められているが、一巡り7日の身体のリズムにのった失調現象なのである。(飯島裕一『温泉の秘密』海鳴社、2017年)◆関連する過去の記事 日本三大胃腸病の湯 峩々温泉(2023年01月02日)
2023.01.05
コメント(0)
-

仙台門松
正月の仙台市内で「仙台門松」を見かけた。かつて仙台城下で正月の風景だった門松を復元するというムーブメントがあるのだ。そして、よく見かける竹を三本斜めに切ったものとはかなり異なるものだ。(以下は手にしたパンフレットの記載から。)正月を代表する風景として門松があります。かつて仙台城下で飾られた門松は、現在よく知られている門松の形(斜めに切った三本の竹を藁で巻く)とは全く異なるものでした。それは、二本の柱に大きな松と笹竹を取りつけて、門のように造り上げ、しめ縄を巻き付けて、中央にケンダイと呼ばれるしめ飾りを取りつけ、鬼打木(おにうちぎ)という割り木を根本に添えるものでした。地域や家によって形や材料に少しずつ違いはありますが、このような門松はほぼ旧仙台藩領全域で飾られていたようです。しかし、明治時代以降、少しずつその数を減らし、特に第二次世界大戦中や高度経済成長期に激減し、個人宅でこのような門松を飾ることはほとんどなくなりました。◆仙台城の門松仙台城で飾られた門松は、五階松や七階松を使い、約4mの高さになる豪壮なものでした。寛文10年(1670)の古文書によると、そのころ仙台城と藩の施設で42組の門松が設置されていました。城下にある藩の関連施設の分も相当あったようです。こうした仙台城で飾られる門松の材料は、宮城郡根白石村(現在の泉区)から献納されるのが恒例となっていました。門松の材料を納める家は御門松上げ人(おんかどまつあげにん)と呼ばれる8軒に限られていました。◆仙台門松の復元旧仙台藩領で飾られていたこのような門松=仙台門松は、近代以降急速にその数を減らしました。しかし、仙台市博物館が調査を重ね、さらに仙台市泉区根白石で伝統的な門松を今も飾っている旧家の協力を得て、復元することができ、仙台市内の歴史系ミュージアムで復元・展示活動が行われています。このたび、一般社団法人心のふるさと創生会議では、仙台の歴史と文化を継承することを目的に、この仙台門松を多くの方に知っていただきたく、賛同いただいた企業・団体で展示を行っています。仙台藩で飾られた仙台門松をご覧いただき、仙台の歴史と文化の一端に触れていただければ幸いです。心のふるさと創生会議では、2019年に設置運動を始め、4年目の令和5年には17基の仙台門松が飾られている。そして、古文書に従い42基の設置を目指して活動をするのだそうだ。
2023.01.04
コメント(0)
-
シンコペーテッドな名前 再論
先日大船渡線のことを記事にした際に、ナベヅル線の形成に関わったとされる西磐井郡中里村(現在の一関市)出身の代議士柵瀬軍之佐(さくらいぐんのすけ)を知った。岩手県から衆議院議員当選6回、大正14年には加藤内閣の商工政務次官。64歳で没(1819-1932)。北上川にかかる橋に柵ノ瀬(さくのせ)橋があり、一関中心市街地から平泉方面に旧国道4号を北上すると、柵ノ瀬口というバス停があったような気がする。ここから国道を折れて東に田んぼの中の道を進むと、対岸の舞川にわたる柵ノ瀬橋に通じるのだ。往古の今泉街道につながったのだろうか。柵瀬をサクライと読むのは意外だが、北上川の狭窄部でもあり、橋の名に残る柵の瀬の地名と関連があるのだろう。そして、思い出したのは、以前に記事にしたシンコペーションな名前のこと。桜井 さくら・い佐倉井 さ・くら・い柵瀬 さく・らい見事だ。■関連する過去の記事 大船渡線の成り立ち(2022年12月22日) シンコぺーテッドな名前(06年12月22日)
2023.01.03
コメント(0)
-
日本三大胃腸病の湯 峩々温泉
本に書いていた。四万温泉(群馬県中条町)、湯平温泉(大分県由布市)と並んで、わが宮城県川崎町の峩々温泉が、日本三大胃腸病の湯と呼ばれるという。■参考 飯島裕一『温泉の秘密』海鳴社、2017年峩々温泉は、含石こうー重曹泉(ナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩)。飲泉とともに、湯船のわきに仰向けに横たわって備え付けの竹筒で浴槽内の熱い湯(源泉は58℃)を腹(胃や腸)の上にかける温治作法が伝わっている。かけ湯百回と言われる。六代目当主の竹内宏之さんは、「自然発生的に生まれたようだ、湯あたりを防ぐ知恵ともいえましょう」と説明する。(上掲書から)四万温泉は、近くの草津温泉の荒療治の帰途に、荒れた肌の手入れをする上がり湯として知られた。環境省による泉質月の飲泉適応症では、以下の通り。・塩化物泉 萎縮性胃炎、便秘・炭酸水素塩泉 胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常=糖尿病、高尿酸血症=痛風・硫酸塩泉 胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘・二酸化炭素泉 胃腸機能低下・含鉄泉 鉄欠乏性貧血・含よう素泉 高コレステロール血症・硫黄泉 耐糖能異常=糖尿病、高コレステロール血症
2023.01.02
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1