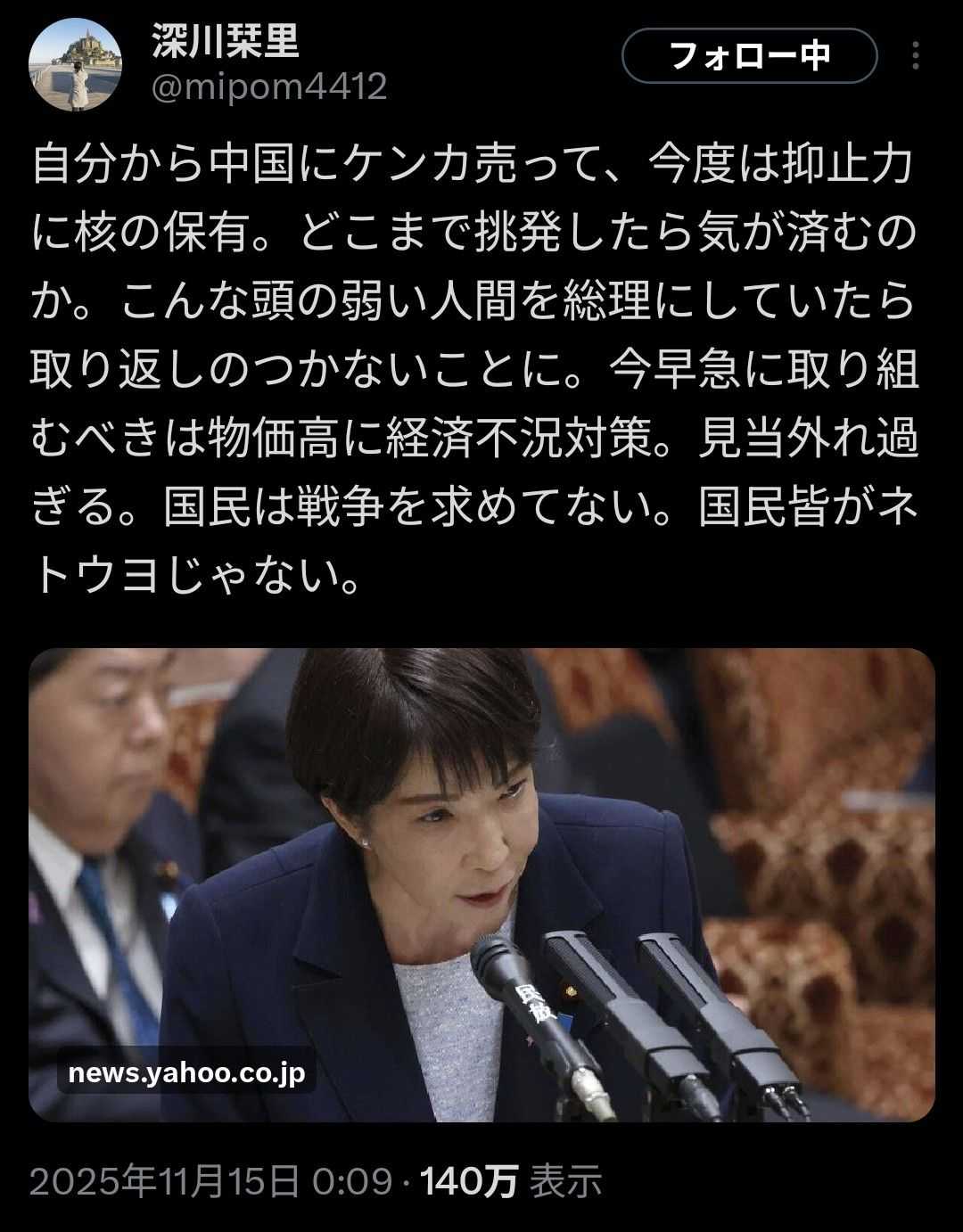2010年01月の記事
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-
川のランキングと東北
ズバリ日本の川の順位を言えますか。子供の頃、北上川は日本で4番目と教わったが、流域面積なのか長さなのか、混乱していて、実は良くわからない。国土交通省の説明によると、長さ(流路延長というらしい)では、1信濃川2利根川3石狩川4天塩川5北上川6阿武隈川7最上川8木曽川9天竜川10阿賀野川だそうだ。一方、流域面積では、1利根川2石狩川3信濃川4北上川5木曽川6十勝川7淀川8阿賀野川9最上川10天塩川となっている。東北の河川は、随分上位に入っている。北上や阿武隈は大河のイメージだが、山形県内で完結している最上川も、ベストテンに入っている。北海道をのぞき、単独の都府県を流れる川としては、日本最長だ。短い印象の淀川が、流域面積で阿賀野川に勝るのは意外だが、支流の多さのようだ。改めて感じるのは、宮城県が太平洋に注ぐ2本の大河で潤された土地であること。さらに、吉田川、鳴瀬川などの河川がひしめき、昔はさぞ水害に悩まされただろう。秋田県と青森県はベストテンに関係していない。秋田なら、雄物川と米代川が思い浮かぶが、いずも長さ130km台で、最上川より100kmも少ない。
2010.01.31
コメント(0)
-
大崎市にタンチョウが飛来
TVニュースによると、大崎市にカンガルーではなく、タンチョウが舞い降りたそうだ。宮城県内では1976年に伊豆沼で確認されてから34年ぶり。今月半ばから、大崎市や美里町の水田で目撃され、先週から蕪栗沼に居るそうだ。34年前には、県内に2年ほど生息していたそうで、今回もそっとしてやって欲しいということだった。子どものころは、タンチョウヅルと呼ぶのが普通だったと記憶しているが、北海道で見られるというイメージだ。今回は、中国大陸で飼育されているものが暖かい日本列島に飛来したのではないかとの見方もある。悪天候で迷い込んだ、との報道もあった。国の特別天然記念物で、国内生息数は昨年調査で600羽。やはり宮城県北部は、鳥たちの聖地なのか。動物には行政の区界も、人間社会のつまらぬ対立もお構いなし。それだけに、何だか、有り難いような気持ちになる。
2010.01.30
コメント(0)
-
庭の訪問者
今日は外は小雨。暖かささえ感じる。庭にツグミ君の訪問者。枝から下りて、まるで人のように、通路を歩いていた。春を踏みしめているように。
2010.01.30
コメント(0)
-
高卒者の就職の「厳しさ」 宮城の実情を考える
産経新聞の記事は興味深かった(宮城版、1月27日)。要約させいただくと、以下のとおり(構成は当ジャーナル。一部データ等を補足)。------------1 状況 宮城県の高卒者内定状況は、9月末時点で、23.6%で、全国でも3番目に悪い状況。12月末で、61.5%に回復したが、前年比ではマイナス14.4ポイントと開いた。しかし、他県と比較すると 宮城 61.5% 山形 80.1% 秋田 80.8%と、宮城は低い。なぜか。2 宮城県の内定率が低い理由 ある宮城県内高校の進路担当者は、地元志向の強さを挙げる。東北各県から就職希望者が仙台に集まるからだ。他県の高校では、優秀な生徒は仙台、次いで東京、名古屋、大阪と南下すると指摘。少なくなったパイを東北各県の高校生が奪い合っている。3 格差の実情 また、高校の学科別の格差を指摘する声も。県教委の調べでは、11月末時点で、 工業科 74.3% 商業科 46.2% 普通科 44.7% 農業科 44.2%であり、普通科は進学への切り替えもあるが、商業科の内定率の低さが例年より際だつという。 とりわけ女子の内定率が低く、優等生でも就職が決まらない。ある担当者は、企業の事務職は募集が減り、デパートのレジ係さえパートに代替されており、求人が少なくなっている、という。 また、商業科の学習指導要領が現実の企業ニーズと合わないとの指摘も。会社法の頻繁な改正や会計分野の変化に、教育が追いつかないという事情だ。最近では商業高校でも進学率が高まり、就職のための学校ではなくなった事情もあるという。------------最後に学習指導要領に話を持って行くのは、いかにも産経らしいと思うが、それはともかく、仙台を目指す各県の真剣な高校生に、地元の高校生がはじき出されているという話は、良く聞くことだ。■関連する過去の記事 仙台・宮城人怠け者論を考える(09年11月11日) がんばれ東北の高卒就職予定者!(09年1月18日)
2010.01.29
コメント(0)
-
バンクーバー五輪で輝け 小室選手
バンクーバー五輪に女子スケルトンで初出場する村田町出身の小室希さん(仙台大院)が、27日、母校の白石女子高校を訪れ、壮行会で応援してもらったというニュースがあった。白石女子高校は、4月から、白石高校と統合して、新しい白石高校としてスタートする。白高の男子学生やOB達も、「母校の先輩」として小室さんを応援してくれたら、どんなに素晴らしいことだろうと思う。さて、仙台大学のサイトには、堂々と五輪代表選手のコーナーがありました。ボブスレーやスケルトンの代表を輩出している仙台大学。わが宮城の誇りでもあります。冬季五輪と言えば、4年前は荒川静香さんの美しい滑りに魅了され、金メダルに歓喜しました。宮城の星が輝く世界の舞台。楽しみですね。■関連する過去の記事 スケルトン越さん 三たび五輪の舞台へ(10年1月10日 スケルトン越さん(06年2月18日)
2010.01.28
コメント(0)
-
困ったドライバー君
決して自分が優良ドライバーだとは思わないが、安全運転には努めていると思っている。日曜日の夜のことだ。いただいた仕事で遅い帰宅となったが、片側2車線の国道を走っていて、赤信号で停まろうと減速していたら、突然、右側のレーンから軽自動車が、私のいるレーンに割り込んできた。ほとんどぶつかりそうになったが、私が急ブレーキで停まったので、済んでのところで衝突は回避した。この軽自動車の運転者氏は、つまり脇を確認せずに、車線をヒョイっと変更したのだ。交差点を左折したかったからだろうが、極めて危ないことだ。私も、その交差点を左折するので、しばらく後を追う形となったが、夜間だから自由だと言わんばかりに、右に左にレーンをはみだすのも気にならないようで、そのうち、交差点をムダに大きく回って別道にへ去っていった。道路交通において、このようなドライバーは本当に困りものだ。若い御仁のようだったが、まわりの迷惑を考えて欲しい。秋田市の成人式で、進行を妨害する態度の悪い若者が問題となった。まったく困ったものだが、自分というものに自身がないからこそ、自己顕示をしたいのだろう。何か心に問題があるのだろうな。そんなことを、TVを見ながら娘たちと話をしていたら、我が家の娘によると、そういう子どもに育てたのは誰なんだヨ、と言われたが、それも道理だ。世の中全体で考えるべき問題なのかも知れない。人に迷惑を掛けてはいかん。他人の気持ちになれる人間でなければいけない。そんなことを、子ども達に話すが、果たして子ども達はどう受け取るのだろうか。今時の若者は、などという年になってしまったが、それこそ一昔前、我々の親の世代も、こうして悩んだのだろう。
2010.01.27
コメント(0)
-
各市の市長選挙を考える
日曜日(24日)に投開票が行われた市長選挙で、全国の話題となったのは、名護市と宮崎市だろう。名護市は、米軍普天間基地の移設受入に反対し、県外移転を求める元教育長の新人稲嶺さんが当選した。地元の意向を尊重するとしている鳩山内閣の判断に、影響が注目される。条件付き容認を唱え、2期目を目指す現職市長との接戦だった。 新人(社、共、民ほか推薦)17,950(当選) 現職(自、公支持) 16,362 投票率 76.96%宮崎市長選挙は、現職を破って当選したのが、合併前の町の町長さんだったというニュースで、印象に残った。4期務めた現職の引退を受けての選挙だが、当選した元町長は、前回の選挙でも現職に挑んで敗れた。姿勢の刷新を掲げて、後継者とされた新人を大差で破った。 新人・元町長 81,951(当選) 新人・元市議(民、公推薦)33,212 投票率 48.15%さて、東北でも市長選挙が行われた。当ジャーナルで3つの市長選挙に注目してみた。まず、福島県伊達市長選挙。無所属現職で2期目を目指す仁志田氏が、元伊達町長(冨田氏)、元梁川町議の2新人を破り再選。みを図ったが、わずかに及ばなかった。橘氏は地域農業の振興などを掲げたが、浸透しなかった。 現職 17,390(当選) 元町長 17,112 元町議 1,312 投票率65.30%この市長さんは、JRの車両所長をした方だそうで、保原町長を2期務めた。伊達市というと、保原の梁川の2つの核を連想する。今回の接戦も、この旧2町を代表した争いかと思いきや、惜敗の新人は元伊達町長さんだという。それにしても、300票足らずの接戦。河北新報は、現職が幅広い支持を集めたと表現しているが、どうなのだろう。地域的な構図か、現職の政策への批判か、かなり政治的な「中身」がありそうだ。朝日新聞によると、冨田氏は、小学校の改築などを例に旧保原町を中心とした利益配分だと批判したという。旧伊達町や旧梁川町の支持を集めたようだ。なお、朝日新聞は、伊達市の現職辛勝と、喜多方市の現職敗退、そして1週間前の南相馬市の現職敗退を含めて、平成の大合併のひずみと評している。南相馬は、民主支持の新人前市議が、現職をわずか700票差で破って当選していた。次に、喜多方市長選挙だ。ここは混戦で、現職が時点どころか3位に弾かれてしまった。 新人・元熱塩加納村長(山口氏) 12,502(当選) 新人・元県次長(飯野氏) 8,952 現職(白井氏) 6,553 新人・元市議(上野氏) 4,214 投票率 75.28%毎日新聞によると、山口氏は旧町村部を代表する形で地域間格差を指摘。経済人を中心に旧市域にも支持を広げた。陣営には渡部恒三議員の支持者らが加わった。自民が飯野、白井両陣営に割れたことも有利に働いた。飯野氏は、故伊東正義外相系の自民党組織が陣営の核となったが、世襲批判や知名度不足も響いた。この飯野氏は、現職白井氏の通算3期の後ろ盾役だった飯野陽一郎元市長の長男であり、白井氏は、後援組織の分裂を余儀なくされた。他には、花巻市長選挙だ。 現職(民主推薦) 30,954(当選) 新人(共産) 11,448 投票率 50.98%現職が堂々と2期目を決めたと言うことだが、共産党公認候補も結構票を取っていると見るべきではないか。投票率が前回から20ポイント近く下がっているから、基本的には無風だったのだろうが、批判票がやや多いようにも思う。
2010.01.26
コメント(0)
-
タロちゃん、タロウちゃん、そして「たろちゃん」
24日の河北新報には度肝を抜かれた。小沢一郎のことではなく、マリンピア松島水族館のオットセイの子どものこと。■関連する過去の記事 タロちゃん?タロウちゃん?(10年1月20日) 松島のタロちゃんを考える(10年1月19日) 宮城でも大いに盛り上がって、岩手との一体感、そして縄文時代から続くオホーツク文化圏を称揚しようではないか、と大げさにも考えていた。松島水族館では公開していないものの、皆さんの心配に配慮してか、ホームページ内の日記では、食欲も旺盛で、スイスイと華麗な泳ぎを見せているというので、安心している。度肝を抜かれたのは、河北の記事の見出し。タロちゃんでも、タロウちゃん(朝日新聞の表記)でもなく、「たろちゃん元気に」だった。こんなビッグな(?)東北のニュースについて大きな今まで沈黙を続けていた河北が、ついに報道したと思ったら、いきなり「たろちゃん」だ。タロとタロウとの区別は耳でもわかるが、表記がカタカナか平仮名かは、盲点だった。やられた、という思いだ。そして、冷静に考えれば、平仮名に思いが及ばなかったのは、この手のネーミングは、タマちゃんもウタちゃんもそうだが、当然カタカナだという思いこみが頭を固くしていたのだ。河北が悪いわけではない。硬直化した頭脳に、電光一閃、雷を落とされたような感じだ。これでタロちゃんネーミング騒動(当ジャーナルが勝手に騒いでいるだけですが。)に、東北に公称50万部の河北が参戦?、というわけで、混迷の色を濃くしている。
2010.01.25
コメント(0)
-
悲劇の天才彫刻家 高橋英吉
石巻文化センターには、石巻市出身の彫刻家高橋英吉の作品が展示されている。1911年(明治44年)石巻町湊本町の遠洋漁業を営む家に生まれ、石巻中学校、東京美術学校研究科(現在の東京芸大大学院)彫刻科木彫部へ。後輩となる佐藤忠良とも知り合う。親の反対を押し切っての上京だったようだ。壁を乗り越えようと、研究科を中退して鮎川から南洋捕鯨船に乗り込み、後の海の三部作制作の契機を得る。28歳の若さで、第3回文展において「潮音」が特賞を受賞し、将来を嘱望されたが、1941年戦地に応召し、41年ガダルカナル島で戦死。31歳。輸送船内で流木に彫った不動明王像が遺作とされる。81年、三部作の1つ「潮音」のブロンズ像が、日英豪3国協同建設のガダルカナル島平和公園に、シンボルとして建立された。ご令嬢の幸子さんも版画家として活躍されているのだそうだ。(石巻観光ガイドブック平成21年6月、石巻文化センターHP ほかから)
2010.01.24
コメント(0)
-
東北の「歩きたくなる道」
石巻市の観光パンフを読んでいたら、ハイキングで親しまれている旭山が、「美しい日本の歩きたくなる道500選」に選ばれているという。社団法人日本ウオーキング協会(編集部注:「オ」は拗音ではなく、通常のサイズです)が事務局となり、各界の有識者からなる推薦会議で、平成16年12月に選定した。■関連する過去の記事 やっぱりウ「オ」ークなのね(06年9月28日)さて、東北ではどのような道が選定されているだろうか。同協会のサイトから列挙させて頂く。----------○青森県1 津軽富士岩木山・高原のみち(弘前市、岩木町)2 世界遺産白神山地・暗門の滝を訪ねるみち(西目屋村)3 夕日海岸・津軽西浜のみち(深浦町)4 秘境・下北半島尻屋崎のみち(東通村)5 津軽こけしの里・虹の湖を巡るみち(黒石市)6 津軽鉄道・太宰文学を訪ねるみち(金木町)7 世界遺産白神山地・十二湖のみち(岩崎村)8 ふくち里山バーデパークのみち(福地村)9 種差海岸・渚と風のみち(八戸市)10 三内丸山・縄文の杜へのみち(青森市)11 十和田湖・奥入瀬渓流のみち(十和田市) ○岩手県1 奥の細道・平泉のみち(平泉町)2 渋民村・啄木と出会うみち(玉山村)3 イーハトーブの里 賢治と毘沙門天のみち(花巻市、東和町)4 遠野物語・土渕のみち(遠野市)5 壬生義士伝のまち・盛岡散策路(盛岡市)6 芭蕉最北の宿・一関、菜の花のみち(一関市)7 桜の名所北上展勝地のみち(北上市)8 アテルイの里・水沢散策路(水沢市)9 奥州街道 末の松山のみち(二戸市、一戸町)10 海と椿の碁石海岸を巡るみち(大船渡市)11 賢治と歩く小岩井農場を巡るみち(雫石町) ○宮城県1 杜の都仙台・広瀬川散策路(仙台市)2 眺望・釜房湖畔のみち(川崎町)3 水のまち・白石城下散策路(白石市)4 豊饒の大地・まほろばの里みち(大和町)5 塩釜から松島へ・絶景のみち(塩竈市、松島町)6 歴史街道・鳴子峡をたどるみち(鳴子町)7 蔵王連峰展望と千本桜のみち(大河原町)8 旭山・宝ケ峯遺跡のみち(河南町)9 陸中海岸・緑の真珠の散策路(気仙沼市)10 政宗ゆかりの磯浜を巡るみち(山元町)11 奥松島と縄文の村を訪ねるみち(鳴瀬町) ○秋田県1 神秘の湖・田沢湖畔のみち(田沢湖町)2 秋田市街と公園散策路(秋田市)3 松並木と清水の里を訪ねるみち(美郷町)4 縄文文化と伝説のみち(鹿角市)5 なまはげの男鹿半島のみち(男鹿市)6 奥の細道・九十九島象潟のみち(象潟町)7 のしろ・風の松原のみち(能代市)8 きみまちの里・二ツ井のみち(二ツ井町)9 大間越街道・松波公園へのみち(峰浜村、八森町)10 仁賀保・由利原高原のみち(由利町、仁賀保町) ○山形県1 寒河江眺望・長岡山へのみち(寒河江市)2 イザベラ・バード紀行・金山のみち(金山町)3 銀山温泉とブナ共生の森のみち(尾花沢市)4 羽黒山・修験のみち(鶴岡市)5 奥の細道・山刀伐(なたぎり)峠のみち(最上町)6 山形城下町歴史遊楽のみち(山形市7 陣峰市民の森から焼き物のみち(新庄市)8 出羽富士・鳥海山眺望のみち(遊佐町)9 鳥海山恵みの水と潮風のみち(酒田市)10 茂吉の上山・蔵王を訪ねるみち(上山市) ○福島県1 神秘の湖沼群・五色沼のみち(北塩原村)2 ふくしま信夫三山・自然のみち(福島市)3 塩屋崎灯台から薄磯と勿来海岸へのみち(いわき市)4 会津史跡巡りのみち(会津若松市)5 英世のふるさと・猪苗代のみち(猪苗代町)6 ほんとうの空がひろがるみち(二本松市)7 郡山・せせらぎこみちと渓谷を巡るみち(郡山市)8 白河市・南湖公園を巡るみち(白河市)9 柳津・只見川をたどるみち(柳津町)10 下野街道・大内宿をたどるみち(下郷町)----------何も、旅行商品やJRの小さな旅のように、無理に修飾語句をつけなくてもという感じもするが、美しい道や由緒を盛り込もうとする意気込みだろう。何かとせわしい世の中だ。小さいことは忘れ、悠久の歴史の積み重ねの中に先人が往来した足跡を、足の裏でしっかりと押さえて歩いてみるのも、いいだろう。
2010.01.23
コメント(0)
-
東北の学校・企業の略称を考える
ラジオのニュースで、「とりぎん文化会館」とか言うのを聞いたが、鳥取銀行のネーミングライツか何かだろう。要は、鳥取銀行を「とりぎん」と略称するようだ。そう言えば、鳥取大学を、鳥大(とりだい)と略称するのは聞いたことがある。たしかにそれが自然なのだろうが、慣れていない私には、一瞬それでいいのだろうか、と戸惑ってしまう。おそらく、鳥取県の名前が、「鳥」が先か「取」が先か迷ってしまうのと同類の感覚で、「トリ」ダイと耳で聴いても、「鳥」や「取」の文字がすぐに頭に連想できないからなのだろう。ところで、東北各県の大学の略称を考えてみる。 弘大 ひろだい(弘前大学) 岩大 がんだい(岩手大学) 秋大 しゅうだい(秋田大学) 山大 やまだい(山形大学) 福大 ふくだい(福島大学)この辺は、極めてオーソドックスだ。ただ、音読みにするか訓読みにするかは、定着がモノを言うのだろう。大学の「大」は音読みだし、そもそも略語は漢語風に読むべきだろうから、例えば、宮城県石巻高校を「石高 せきこう」と、また、白石高校を「はくこう」、秋田高校を「しゅうこう」と略称するように、音読みが正統派であり、とすれば、岩大や秋大は正統派で良いとしても、山大も「サンダイ」、弘大は「コウダイ」と読むべきだとも思われるが、これはもう定着次第であって、仕方ないだろう。もう少し考えてみる。 青大 あおだい(青森大学) 八大 はちだい(八戸大学) 盛大 もりだい(盛岡大学)青森と盛岡は、セイダイとは言わないようだ。いずれも都市名の発音通りの略称が定着したということだろう。ちなみに、歴史の古い「せいこう」(青森県立青森高校)とは対照的だ。それでは銀行の場合はどうだろうか。 青森銀行 あおぎん 岩手銀行 いわぎん 秋田銀行 あきぎん 山形銀行 やまぎんやっぱり、親しみやすい方をとるのだろう。ガンギンやシュウギンとは言わないようだ。以上から、新しい施設や親しみやすさを優先する場合などは、短縮する前のモトの読み方を踏襲するものと言えそうだ。ところで、電力会社はどうだろう。「とうでん」と言えば東京電力、「ほくでん」は北海道電力なので、わが東北電力は上手な略称を見いだせないようだ。たしかに、東北人は、日頃「電力」とだけ呼んで済ませているように思う。思えば、電力さんには失礼な話だ。固有名詞があるのだから、ちゃんと呼びたいが、できれば略称が欲しい。そこで、東北電力で、略称を一般公募してはどうだろうか。いや、難しいか。省略形としては「とうでん」も「ほくでん」も使えないとすれば、いきおい愛称パターンとなって、プロレスみたいに、みち電、などとなってしまうのだろうか。だから、やっぱり難しいだろう。
2010.01.22
コメント(0)
-
変な天気と政治情勢
仙台は夜が更けるに連れ、風が強くなってきた。アメダスを見ると、夜11時で、西北西の風15メートル。ちなみに、今日(21日)は、未明の1時が気温が最高で、13.9度。だんだん気温が下がり、正午で8.2度。夜11時で、1.1度。気温は下がって、風が強まってきた。明日朝は氷点下の冷え込みだそうだ。暖かさも一日だけで、急転直下の冷え込み。こんな天気もあるのか。帰りの車中では、仙台に暴風雪警報が発令された、とラジオで聞いた。そう言えば、自民党の参院選候補者は1人に決定したそうだが、発表はされていない。私でないことだけは確かだが、激戦だっただけに結果が注目される。民主党も、現職の桜井充氏の他もう1人を立てる方針だという。国会では、鳩山総理が、どう乗り切るか。今、あらためて仙台のアメダスを見たら、1時時点で、風は11メートル。明日(22日)は真冬に逆戻りか。
2010.01.21
コメント(0)
-
タロちゃん?タロウちゃん?
岩手から松島に来たオホーツクのタロちゃんの話の続きです。今日の県内各紙を賑わせているかと思ったら、まず、河北新報に出ていない。残念。朝日には、カラーで紹介されていたのだが、宮古市で保護された時の写真のようだ。そして、同行してきた宮古市の水産課長さんが、「タロウちゃんが3回くしゃみをした」と話したそうだ。あれ、「タロちゃん」じゃなかったのか。でも、昨日の各TV局の報道では、タロちゃんだったように思う。朝日は、17日の岩手県版でも、地元で「タロウちゃん」と呼ばれていると記していました。地元でも、タロウと呼んだり、タロと呼んだり、人によってさまざまなのでしょう。たしかに、戸籍もないだろうから、本名を確認しようもありません。ちなみに、テレビ朝日系列のIAT(岩手朝日テレビ)では、オットセイのタロちゃん、と表現していました。やっぱり、タロちゃんが主流のようです。ところで、松島水族館のサイトには、宮古市から保護の依頼があって、「タロちゃん」を飼育している、と出ていました。マリンピア日記に、タロちゃんの画像付きで、紹介されています。毎日新聞の宮城版によれば、タロちゃんは、人目につかない裏口の水槽に、まずは収容されているとか。シシャモを美味しそうに食べたそうです。今日の仙台は、午後は20度近くまで上がったようで、かなり暖かかったですね。タロちゃんは、大丈夫だったでしょうか。飼育のプロの方がいるので、安心ですね。
2010.01.20
コメント(0)
-
松島のタロちゃんを考える
仙台では各局がニュースで報じていた。岩手県宮古市で見つかったオットセイの赤ちゃん「タロちゃん」が保護されて、今日(19日)、松島水族館にやってきた。宮古市田老の河口付近で、今月15日に発見されたキタオットセイで、生後1年ほど。オホーツクから南下中に、群れからはぐれたという。発見されて5日経って衰弱が見られたため、飼育施設の整ったマリンピア松島水族館に運ばれた。田老のタロちゃん。早く回復して、海に帰ってもらいたいが、ちょっとだけでも良いから、子ども達が喜んだり、宮古や松島が盛り上がれば、と思う。そう言えば、ウタちゃんはどうなったのだろう。02年9月に、歌津町(現在は南三陸町)の伊里前川に姿を見せたワモンアザラシだ。ちょうど同年に東京多摩川で、タマちゃんが話題になったので、こちらもかなり有名になったと思う。さて、タロちゃんは岩手県側でも報道されている。岩手のローカルニュースでは、魚のエサに誘導されて移動用タンクに進むウタちゃんを見物する人が、大勢集まったそうだ。すっかりアイドルになって連日見物の人が絶えなかったのだから、見送りする市民が集まったのも当然だろう。市役所の人が、淋しい気もするが専門家に預けるのが一番、とコメントしているのが印象的だ。タロちゃんが無事松島に着いた、ということまでしっかり報道している。こうなったら、宮城県民も、岩手に負けず、タロちゃんを応援しよう。純情派の岩手県民に対して、軽薄で自分勝手と評される仙台・宮城の汚名返上のためにも。さて、私なら、松島タロちゃんセンベイでも売り出して、利益の10%を水族館に寄附してタロちゃんが元気に海に戻るための費用に充ててもらうとか。あるいは、 松島タロちゃん酒 オホーツクから来たタロちゃんかまぼこ タロちゃん牛タン カレーのコロちゃん、じゃなくてタロちゃん何でも考えられますね。子ども向けにタロちゃんのぬいぐるみなんか売り出したら、絶対に我が家の下の娘は夢中になるでしょう。
2010.01.19
コメント(0)
-
東北文教大学と再び東北各県の「東北」を探す
新聞を見ていたら、センター試験のシーズンらしく、各大学の広告が目に飛び込む。中で、東北文教大学という、私には新鮮な名称の学校があった。どこだろうか、と思って読むと、山形市で、今春開設なのだそうだ。山形短期大学、山形城北高校を運営している学校法人富澤学園が設置者だそうだ。人間科学部子ども教育学科90名で、小学校教諭、幼稚園教諭、保育士などの資格が取得できる。若者の希望や能力を最大限引き出すよう、特色のある高等教育機関が頑張って欲しい、と思う。ところで、山形県で東北を冠する大学といえば、芸術工科大と公益文科大学が思いつく。山形で3つめの「東北」アカデミアだ。東北は一つ。各地でどんどん「東北」を名乗って欲しいと思うのだが、改めて、宮城県以外で「東北」を探してみた。■関連する過去の記事 東北各県の「東北」を探す(07年11月29日)〔青森県〕 東北女子大学(弘前市) みちのく銀行〔岩手県〕 東北銀行 北日本銀行〔山形県〕 東北芸術工科大学(山形市) 東北公益文科大学(酒田市)〔福島県〕 日大東北高校(郡山市) 奥羽大学(郡山市) 東日本国際大学(いわき市) 東邦銀行(福島市) 大東銀行(郡山市)
2010.01.18
コメント(0)
-
プロが選ぶ東北の旅館など
山形新聞に出ていたが、「第35回プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」というのがあって、上山の古窯が総合3位。しかも、35年連続トップ10入りで、総合3位も5年連続というから、すごい。安ければいいと言う価値観しかない貧乏性の私なので、宿のグレードやおもてなし度の評価など、大してわからないのだが、古窯には10年以上も前に、お世話になったことがある。それと、総合10位の萬国屋さんにも数年前に家族でお世話になった。そう言えば、萬国屋さんでもらった「手形」を、東京のビジネスホテルで他の客のバッグに見つけて、笑ったことがある。このほか、上山の村尾旅館、赤湯の瀧波さんなどにも泊まったが、山形県には良い宿が多いと、たしかに思う。では、東北各県の旅館では、どこがランクインしているのだろうか。旅行新聞新社のサイトによる。○第35回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」 総合ベスト1003位 日本の宿古窯(山形県かみのやま温泉)10位 萬国屋(山形県あつみ温泉)11位 たちばなや (山形県あつみ温泉)16位 八幡屋(福島県母畑温泉)18位 南三陸ホテル観洋(宮城県南三陸温泉)20位 匠のこころ吉川屋(福島県穴原温泉)23位 ホテル華の湯(福島県磐梯熱海温泉)34位 結びの宿愛隣館(岩手県新鉛温泉)41位 伝承千年の宿佐勘(宮城県秋保温泉)56位 蔵王国際ホテル(山形県蔵王温泉)59位 八乙女(山形県由良温泉)64位 庄助の宿瀧の湯(福島県東山温泉)67位 月岡ホテル(山形県かみのやま温泉)68位 風望天流太子の湯山水荘(福島県土湯温泉)82位 蔵王四季のホテル(山形県蔵王温泉)83位 游水亭いさごや(山形県湯野浜温泉)88位 丸峰観光ホテル(福島県芦ノ牧温泉)95位 篝火の湯緑水亭(宮城県秋保温泉)なお、部門別というのがあるが、当然、上記の旅館が重複して登場してくる。そこで、総合ベスト100で登場していない宿だけに限って、以下に拾ってみた。○もてなし部門55位 ほほえみの宿滝の湯(山形県天童温泉)63位 鳴子観光ホテル(宮城県鳴子温泉)76位 亀や(山形県湯野浜温泉)80位 仙峡の宿銀山荘(山形県銀山温泉)83位 南部湯守の宿大観(岩手県つなぎ温泉)84位 湯瀬ホテル(秋田県湯瀬温泉)88位 ホテル紫苑(岩手県つなぎ温泉)96位 天童ホテル(山形県天童温泉)○料理部門40位 風望天流太子の湯山水荘(福島県土湯温泉)43位 浅虫観光ホテル(青森県浅虫温泉)51位 ホテル対滝閣(岩手県岩手湯本温泉)59位 男鹿グランドホテル(秋田県男鹿温泉郷)60位 大川荘(福島県芦ノ牧温泉)61位 古牧温泉青森屋(青森県古牧温泉)64位 松島ホテル一の坊(宮城県太古天泉松島温泉)68位 ホテル松島大観荘(宮城県松島海岸)72位 名湯の宿鳴子ホテル(宮城県鳴子温泉)81位 海と入り陽の宿帝水(秋田県戸賀温泉)89位 ホテルきよ水(宮城県秋保温泉)90位 いきかえりの宿瀧波(山形県赤湯温泉)94位 雨情の宿新つた(福島県いわき湯本温泉)96位 海辺のお宿一久(山形県湯野浜温泉)○施設部門19位 大川荘(福島県芦ノ牧温泉)58位 ホテル志戸平(岩手県志戸平温泉)70位 鷹泉閣岩松旅館(宮城県作並温泉)84位 ホテルグランメール山海荘(青森県鰺ヶ沢温泉)90位 遠刈田ホテルさんさ亭(宮城県遠刈田温泉)93位 ニュー村尾浪漫館(山形県かみのやま温泉)○企画部門49位 La楽リゾートホテルグリーングリーン(宮城県作並温泉)55位 ホテル王将(山形県天童温泉)59位 庭園の宿松渓苑(福島県岳温泉)73位 旅館玉子湯(福島県高湯温泉)79位 秋田温泉さとみ(秋田県秋田温泉)80位 金蘭荘花山(福島県磐梯熱海温泉)90位 ホテル森の風鶯宿(岩手県鶯宿温泉)100位 ホテルルーセントタカミヤ(山形県蔵王温泉)このほか、特別推薦として、小規模和風の宿が10軒選抜されている。東北からは、三ツ又温泉(秋田県三ツ又温泉)と吾妻屋(福島県高湯温泉)の2つ。こうしてあげてみると、意外と私も泊まった宿が多い。さらに、旅館以外に、プロが選ぶ土産物施設と優良観光バスもある。○プロが選ぶ観光・食事、土産物施設100選(発表は上位10施設)(観光・食事施設)5位 磐梯日光店(福島県・日光)6位 伊達の牛たん本舗(宮城県・仙台)9位 平泉レストハウス(岩手県・平泉)(土産物施設)3位 上杉城史苑(山形県・米沢)5位 庄内観光物産館ふるさと本舗(山形県・鶴岡)○プロが選ぶ優良観光バス30選(上位10社)5位 山交バス(山形市)6位 三八五バス(八戸市)
2010.01.17
コメント(0)
-
東北各県の最低気温はどうか
寒い日が続きます。昨日は仙台の最低気温を調べましたが、ところで、東北の各地はどうなのでしょうか。(昨日の日記 仙台の最低気温を考える(1月15日))各気象台のサイトなどから拾う。単位は度。各都市の最低気温です。正確には、日最低気温の最下位とか言うらしい。青森 -24.7(1931年2月23日)盛岡 -20.6(1945年1月26日)仙台 -11.7(1945年1月26日)秋田 -24.6(1888年2月5日)山形 -20.0(1891年1月29日)福島 -18.5(1891年2月4日)というわけで、実は仙台は随分と暖かい?ようだ。東北の6都市で最低の記録は盛岡かと思いきや、青森や秋田だったのは、意外だった。寒波は大陸から、か。
2010.01.16
コメント(0)
-
仙台の最低気温を考える
昨夜(14日)は帰りの車中で表示された外気温がマイナス6度だった。たぶんサーモの誤差で、本当はせいぜいマイナス3度くらいじゃないかと思うが、どっちにしても、暖冬続きの最近にしては、かなりの低温だ。今日(15日)も寒い一日。帰りの道路は雪化粧だった。週末にかけて、気温が下がるという。仙台でマイナス4度とか。九州でも積雪があったというが、不思議と昨日までは仙台は積雪がゼロだった。でも、寒波はやって来るらしい。暖房用の蓄熱レンガの電気は、入力も出力も最大にしておいた。子ども達がスムーズに起きて欲しいから。よく思い出すのだが、仙台に来て3年目の冬。寒い年で、雪も多く、また、毎朝氷点下の日が続いた。古いアパートだったから、風呂の水も凍るような部屋だった。朝の新聞配達に出かけるのが辛くて、コートをまとって、電気コタツで寝ていた。配達中にバイクで滑って転んだことも何度もあった。あれを思えば、今の生活は天国だ。最も昔。子供の頃は、今日のような氷点下の夜や朝は当然当たり前で、毎日雪をみて生活していたはずだが、人間楽な方にはすぐ慣れてしまい、厳しさはすぐ忘れてしまう。岩手県だから、たぶんマイナス10度近くの世界は経験していたはずだろうと思う。15日の宮城県はこの冬一番の寒さ。仙台で-4.6度、蔵王で-8.1度だったという。ところで、仙台が記録した最低気温は何度だろうか。仙台管区気象台のデータによると、最も低かったのは、-11.7度で1945年1月26日。また、月の平均気温で見ると、最も低いのは、やはり1945年の1月で、-3.0度。相当寒い新年だった。ベストテンは、1920年代、30年代がほとんどだが、唯一、7位に1977年1月の-1.5度がランクインしている。昭和52年だ。ちなみに、盛岡の最低気温は、昭和20年1月26日。仙台と同じ日だが、マイナス20.6度。すごい。
2010.01.15
コメント(0)
-
公衆浴場日本一の青森県
デーリー東北に大変ためになる記事があって、人口当たり公衆浴場数は、青森県が日本一なのだそうだ。以下、鹿児島県、大分県と続く。2位の鹿児島(10万人当たり19.3施設)に対して、24.5とダントツ。全国平均は4.9だそうだ。県内では、青森市52、八戸市45、弘前市30施設など。なぜ八戸に多いかという解説があって、1966年に水揚げ日本一となって以来、全国から集まった漁師で混雑したので、まだ自宅に風呂のない家も多かったご時世で、風呂屋が多くできたのだという。また、八戸では朝から営業している公衆浴場が多く、朝風呂が人気で、賑わっているそうだ。面白いですね。八戸の風呂屋さん。
2010.01.14
コメント(0)
-
仙台のカプセルホテルを考える
電車の広告に目を奪われた。ルー大柴が宣伝しているのだが、国分町に新しいカプセルホテルが出現したようだ。「サウナ&カプセル キュア国分町」というそうで、今なら、オープニング価格で、1900円で泊まれるそうだ。心が動かされる。さらに、1泊2食ビール付きのプランも、3780円だという。心が動かされる。ハッキリ言って、タクシーで帰るより、ずっと良い。貧乏性の私は、こう考えてしまう。ここ10年以上は、カプセルホテルにもサウナにも泊まったことはないが、独身時代は、仕事で遅い時などは帰宅するよりも経済合理的だから、カプセルをよく利用させていただいた。私は、決まって、国分町の交番脇の「リーブス」だ。一週間に3日か4日泊まったこともある。本当にお世話になった。今、改めてリーブスのサイトを見てみたら、料金は3300円。当時は確か、上段下段で差があって、3000円と2900円だったような記憶があるが。当時にないのが、ネット予約の200円割引。そして、面白いのが、チェックイン当日の宮城フルキャストスタジアム(表現が古いし、間違っていますが。)で行われたプロ野球チケット提示で、10%割引というもの。良い企画ですね。さて、仙台のカプセルホテルといえば、あとは「カプセルホテル本町」だろう。立地が抜群で、3150円。たぶん、仙台では、この3軒だと思う。
2010.01.13
コメント(0)
-
東北の小規模特認校を調べてみる
調べてみました。一覧表のような資料が見あたらないので、いろんな手がかりから、該当する学校を探して調べました。各指定校の小中学校のサイトでは、紹介・募集をしているようです。前回の宮城県の分を含めて、東北の一覧にしてみました■関連する過去の記事 宮城の小規模特認校(10年1月9日) 浦戸の小規模特認校を考える(10年1月8日)なお、県名の後に記した文科省調査の「学校選択制導入」自治体数は、特定地域選択制や自由選択制などを含めて、通学区域の特例を認めている場合の全体を拾っているため、小規模特認校制度の実施事例の数は、その内数となることになります。【青森県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校2自治体、中学校2自治体)1 十和田市立切田中学校 対象:十和田市内 平成12年度以来、毎年数名が入学しており、21年度は8名入学と記されています。 同校サイトで、青森県内で唯一の小規模特認校と標榜していることから、県内の実施例は、中学校一例だけと思われます。【岩手県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校2自治体、中学校1自治体) 実施例はないと思われる。【宮城県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校3自治体、中学校2自治体)1 東松島市 宮戸小学校 対象:原則として東松島市内 各学年とも在籍数を含めて定員16名(平成20年度全53名在籍) 通学費(ガソリン代)の補助制度有り2 白石市 小原小学校・小原中学校 平成20年度から。特認制度の在籍はゼロ(小中全体50名在籍)3 塩竈市 浦戸第二小学校・浦戸中学校 対象 市内市外を問わず。小中併せて5名程度の募集 平成17年度から実施。小中32人中、20人が学区の島外から船で通学。 7時15分にマリンゲートから乗船することが必要とされています。4 気仙沼市 月立(つきだて)小学校 平成19年度から。全31名で、特認制度の在籍は不明【秋田県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校4自治体、中学校なし) 不明です。【山形県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校2自治体、中学校2自治体)1 山辺町立作谷沢小中学校 在籍数 小中計23名。平成12年度から実施とのことだが、特認制度による在籍数不明2 山形市立双葉小学校 平成13年から実施 同校サイトによれば、県内では、上山市や八幡町、山辺町の小中学校、山形市では、双葉小学校と第一小学校、山寺小学校が特認校に指定、と記されています。もし平成18年時点の文科省調査が正しいとすれば、どこかで指定をやめたということになるのでしょうか。 なお、山形市のホームページには、通学区域や指定校変更などのの詳しい説明はあるものの、特認校については何も紹介されていませんでした。【福島県】(平成18年時点の文科省調査 学校選択制導入 小学校1自治体、中学校1自治体。いずれも自由選択制) 不明。ただし、文科省調査によれば、自由選択制の事例のみとされているため、特認校は平成18年では存在しないことになります。
2010.01.12
コメント(0)
-
今年の初滑り
手近なスキー場と言えば、ここです。快晴で無風に恵まれました。高速を手軽に使えることもあって、大変便利です。ゲレンデも、往年の混雑もなく、5時間のファミリー券で滑ってきました。
2010.01.11
コメント(4)
-
気になる朝日新聞の誤字
どうも気になっている。土曜日の朝日新聞(宮城)に、小学校の先生の紹介があって、良い内容なのだが、小学校名を誤って表記していた。富谷町の富ケ丘小学校を、「富ヶ岡」と表記していたのだ。(この際、ケとヶの区別は無視しましょう。)恐らく、紙面を手にした人は気づき、特に地元の方はガッカリしたのではないだろうか。もっと困るのは、大新聞だから誤りはないだろうと、これが正しいと信じている人がむしろ多数かも知れないことだ。私の勘違いかと思って何度も確認したが、やはり誤字だ。そして、昨日(日曜)も、わざわざ現物の紙面を読んでみたが、訂正などの説明はなかった。どこからか必ず連絡は入っていると思うのだが、敢えて訂正など書かないのだろうか。絶対に書くべきだ。義憤に駆られやすい若い頃なら、すぐ電話したところだが、さてどうしようか。
2010.01.11
コメント(0)
-
スケルトン越さん 三たび五輪の舞台へ
ついに決まるようだ。越和宏さんの3度目の冬季五輪。いいぞ、越さん。冬季五輪のスケルトン日本代表に、男子は越和宏、田山真輔、女子は小室希が内定したようだ。越さん、ソルトレークを沸かし、トリノで涙を流し、そして、3回目ですね。さりげない雰囲気と、あきらめ切れない(失礼)、いや、何度でも挑戦するその姿勢に、40代中年オヤジの私も共感(これまたセンエツで失礼!)していたものです。今度こそ最後の五輪ということですが(本当か)、その後の進退はともかく、大舞台です、思い切りやって下さい。頭から滑り降りるあんな危険な競技に、それこそ頭からのめり込んで、日本中を沸かせてくれるそのスピリットには、敬服しております。ボブスレーの名門仙台大学と、わが宮城の誇りでもあります。女子で内定した小室さんも仙台大学だそうで、バンクーバー五輪で、また仙台大学の名をとどろかせてやりましょう。越さん、頑張って下さい。■関連する過去の記事 スケルトン越さん(06年2月18日)
2010.01.10
コメント(0)
-
宮城の小規模特認校
昨日の記事の続き。浦戸の取組の他に、宮城県内や東北では、どこの自治体で、どのような小規模特認校があるのだろうか。■前回の記事 浦戸の小規模特認校を考える(2010年1月8日)昨日の記事に書いたように、学校選択制を実施している自治体について、東北の状況(平成18年度時点)は ○小学校 青森2 岩手2 宮城3 秋田4 山形2 福島1(福島だけ自由選択制) ○中学校 青森2 岩手1 宮城2 秋田0 山形2 福島1(同上)となっている。また、文科省の定義では、学校選択制には、特定地域選択制、自由選択制、小規模特認校などが含まれているが、小規模特認校は全国で小学校で88自治体、中学校で41自治体が導入している。文部科学省や各県のサイトに一覧表のような手がかりが見つからなかったが、各自治体のサイトから探ってみた。なお、少子化などの事情を踏まえた学校の統廃合や適正規模確保の論議が各地で行われているが、方向性の一つとして、特認校を含む学校選択制度について紹介や検討が行われているようだ。○東松島市 宮戸小学校で、定員16名 (宮戸小学校サイトに説明がある。なお、このホームページは素晴らしいです。)○白石市 小原小学校・小原中学校 平成20年度から (同市のサイトの説明)○塩竈市 浦戸第二小学校・浦戸中学校 (学校サイトに説明と募集案内。塩竈市外も可。7時15分にマリンゲートから船に乗れること。なお、こちらも素晴らしいホームページです。)ほかは、なかなか探せない。特認校だけではなく、学校選択制の事例も一覧を作ることができない。東北で唯一、福島県内で導入しているという自由選択制も、市町村がわからなかった。少し時間を掛けて、調べてみます。
2010.01.09
コメント(0)
-
浦戸の小規模特認校を考える
毎日新聞によると、塩竈市は、今月18日から小規模特別認定校(特認校)である市立浦戸第二小・浦戸中の児童生徒を募集するそうだ。浦戸諸島は、風光明媚、人情も食べ物も素晴らしく、一昔前に忘れ去られたような故郷の情景が凝縮されたような場所だ。さぞかし、心豊かな子どもに育つに違いない。■関連する過去の記事 寒風沢島に行きたい(2009年09月29日)募集人員は小中合わせ5人程度。応募者には来月上旬に体験入学を行う。学区外から子どもを受け入れる「浦戸特認校」の取組は、以前から聞いていたが、小規模特別認定校とは、一体どういう制度なのだろう。毎日新聞の記事では、特認校とは、特色ある小規模校に学区外からの転入学を認める小中一貫校的な教育システムで、05年度に浦戸が県内初の認定。現在は小学18人、中学14人。地元の浦戸4島は12人で、市営汽船で通う子が20人。教員12人教員が小中相互で授業を担当し、きめ細かい教育を続けているという。学校教育法に従い、市町村の教育委員会は、子どもが就学すべき小中学校を指定するのだが、その際の基準が、通学区域である。近年、弾力的な運用がなされており、例えば、隣接区域の学校を選択できる、あるいは通学区域を撤廃して自由選択とするなど、いわゆる学校選択制が導入されている場合が多くなってきた。法制上の根拠としては、学校教育法施行規則32条1項が、市町村教育委の判断により、あらかじめ保護者の意見を聴取することができることとされている(平成14年改正)。特認校制度とは、通学区域は残した上で、特定の学校についてだけ自由に就学を認める制度ということになる。従来でも、区域外就学や就学校の指定変更はあり、いじめなどの問題への対応として活用されていた。しかし、規制緩和の流れを背景に、選択機会の拡大や学校の個性多様化を容認する風潮が高まり、入学する公立小中学校を選択するシステムが、正面から取り上げられ、文部科学省もこれを普及する姿勢をとっている。文部科学省サイト「小・中学校における就学校の変更の状況について」(平成21年12月21日)によると、就学校の指定変更の全国統計が上げられている。学校選択制の状況については、「小・中学校における学校選択制等の実施状況について」(平成20年6月16日)があり、学校選択制に関しては(資料。なお平成18年時点)、 ○小学校 学校選択制導入 240自治体(14.2パーセント) 形態は、特定地域居住者にだけ認める「特定地域選択制」が最多(108)。「自由選択制」は24自治体。「特認校」は88自治体。 ○中学校 学校選択制導入 185自治体(13.9パーセント) 形態としては、「特定地域選択制」が最多(66)で、「自由選択制」は55自治体。「特認校」41自治体。東北の状況を見ると、 ○小学校 青森2 岩手2 宮城3 秋田4 山形2 福島1(福島だけ自由選択制) ○中学校 青森2 岩手1 宮城2 秋田0 山形2 福島1(同上)全国的には、やはり首都圏が圧倒的に多い。北海道、広島、福岡、鹿児島も取組が進んでいるようだ。頑張れ、浦戸の取組。そして、育て子どもたち。
2010.01.08
コメント(0)
-
チュニジアと石巻
今、盛岡の岩手県民会館で、カルタゴの歴史と文化を紹介する展覧会が行われているという。古代カルタゴの美術品やモザイクなど、ほとんどが日本初公開だそうだ。7日の開場式には、駐日チュニジア大使も臨席された。海洋民族フェニキア人の足跡や、ハンニバルの活躍など、古代の地中海文明を語る遺物に触れることができるのなら、是非私も足を伸ばしてみたい。岩手日報と岩手放送が共催しているようだが、それにしても、なぜ、盛岡で日本初が実現したのだろう。サイトをみると、あれ、昨年6月に仙台でもやっている。仙台会場が最初で、その後、金沢、東京、岡山、盛岡、京都、浜松、宮崎、名古屋と会場を変えて開催しているようだ。そうか、仙台が本当の日本初だったのか。聞いたこともあったような気もするが、機会を逸したのは迂闊だった。ところで、チュニジアと言えば、わが宮城県の石巻市(旧桃生町)が交流を深めている。カルタゴ通りがあると聞いたことがある。今日(7日)のニュースでは、ヌルディーン・ハシェッド駐日大使が6日亀山紘市長を表敬訪問し、同国のトレードマークで平和のシンボルでもあるオリーブの木を描いた、豪華な額を寄贈したそうだ。盛岡に来訪される足で、わざわざ石巻を訪問したのだろう。大使の訪問は、チュニジア国内の都市と石巻市の姉妹都市締結が狙いで、姉妹都市候補は、地中海に面した人口約3万人のリゾート地ハマム・スース市だそうだ。かつて常長がローマを目指して大海原に漕ぎ出した、世界に開かれた海の町石巻。候補とされる都市のことは、よくわからないが、遥かなる歴史に思いを馳せながら、海洋国家チュニジアとの縁を深めることが出来るのならば、意義も高いのではないだろうか。石巻に、誇りと潤いを取り戻したい。■関連する過去の日記 石巻の大いなる歴史2題(05年10月24日)
2010.01.07
コメント(0)
-
白石の連続放火を憂う
昨年10月から続いていた白石市の不審火。12月に収まったかと思っていたら、5日にまた市内の駐車場で、保育士さんの車が燃やされたという。警察も相当調べているとは思うが、是非頑張って検挙して頂きたい。同一の犯人かどうかわからないが(警察は同一犯と見ているとの報道もあり)、もちろん、犯人が悪いことに決まっている。しかし、こうして続発している以上、高まる一方の市民の不安を抑えるのは、やはり警察の捜査で犯人を検挙することに尽きる。これで、もう18件目だという。私は捜査に携わったことはないから、何も言える立場ではないのだが、一言。機材やデータやカネや何やら、それが警察にも必要なことは当然だが、おそらく捜査に最も重要なのは、人の力だろう。どんなに関係者や住民のデータが揃っていても、どんなに最新の分析器具が目の前にあっても、結局は大海の中から見えない糸をたぐって手がかりを引き寄せるのは、長年の経験に基づく、頭と目と鼻と耳と、そして足など、人の力のはずだ。そして、それは、時として寝食を忘れるくらいに、人のため世のために励んでいる警察の人たちが会得した、無形の力なのだろう。こうしている間にも、動いている。糸をたぐっている。検挙のニュースが近づいている。そう私は思う。
2010.01.06
コメント(0)
-
初詣の客数 やっぱり各県で減少
3が日の初詣の人出。山形(25寺社)は、83万人で昨年比8.7万人減。大雪の影響とみられる。トップは例年と同じく、県護国神社で12万人(1万人減)。以下、同市の鳥海月山両所宮8万人(同2万人減)、鶴岡市の荘内神社7万人(同増減なし)の順。(読売)岩手では、中尊寺が前年比36%減など、県南を中心に客が減少。中尊寺は、前年比約5.7万人減の約10万人、毛越寺は約1.4万人減の約6.9万人だった。雪と、高速道路通行止めの影響と見られる。盛岡八幡宮は、昨年とほぼ同数の約24万人。志和稲荷神社は約3万人減の約10万人。奥州市の水沢駒形神社は約7千人減の約10.5万人だった。(岩手日報)全国を見渡すと、新潟も2割減。逆に天候に恵まれた茨城は、30万人も増えてここ10年最高の371万人とのこと。
2010.01.05
コメント(0)
-
やっぱり少ない初詣の人出
仙台放送によると、今年の正月三が日の宮城県内の主な寺社(54か所)の初詣客は、去年より12万人少ない約142万人だった。県警のまとめ。塩竈神社44.3万人、竹駒神社44.2万人で、いずれも9千人ほど減少。大崎八幡は2万人増えて、9.7万人とのこと。強風が吹き荒れるなどの天候のため、近場で済ませる傾向があったと分析されている。私自身は、今回は実はどこにも行っていない。本当ならば、コタツに籠もった子ども達を連れて行き、人生のケジメの大切さを教え諭すべきだとは思うのだが、行かずに過ごしてしまった。反省。言い訳ではないのだが、やっぱり初詣の人出は減っていたようだ。■関連する過去の記事 県内では初詣に156万人(08年1月5日)
2010.01.04
コメント(0)
-
減少傾向の交通事故死者数
各紙が昨年一年間の各県の交通事故死者数などを報じている。各県警のリリースのようだ。福島民友によると、福島県内の死者数は101人(前年比マイナス12)で、昭和30年以降最少。また、発生件数、死者数、負傷者数の3項目がいずれも8年連続減少。これは全国でも福島県だけ、という。青森県は、1966年以来、過去最少の50人。2年連続の減少で、ピークの72年の5分の1近くまで減った。青森県の死者数は全国で9番目に少なく、東北では山形県に並び最少だった(デールー東北)。両県とも、県警がアピールポイントをしっかり伝えているようだ。河北新報には、管区警察局による6県の状況が出ていた。死者数438人は前年より10人減。2年連続で減少。事故件数は43,648件(前年比1,644件減)、負傷者数54,707人(1,970人減)といずれも6年連続の減少。県別の死者数は 福島 101(前年比 △12) 宮城 92(△3) 岩手 81(+12) 秋田 64(+3) 青森 50(△12) 山形 50(+2)で、福島、青森で大幅減の一方、岩手の増加が目立つとしている。宮城県については(河北新報)、死者数は前年より3人少ない92人で、減少は4年連続。ただし、仙台市内の死者が38人で12人増。県警や仙台市などが9月、街頭取締りなどの対策強化で、9月以降は前年同期に比べ4人減少した、と成果を説明している。死者数が増加した岩手、秋田、山形などは、報道が見あたらない。ひょっとして、アピールできる点が少ないとして、県警がリリースしていないのだろうか。全国では、交通事故死者4914人で、昭和27年以来57年ぶりに5千人を下回ったという(警察庁まとめ)。前年より241人減で、9年連続減少。厳罰化による飲酒運転減少やシートベルト着用などが要因と同庁はみているそうだ(日本経済新聞記事から)。■関連する過去の記事 東北の交通事故死者数をみる(06年1月5日)
2010.01.03
コメント(0)
-
龍泉洞の潜水調査が開始
寒気団の影響で、大晦日から強風や大雪が東北を襲っている。各地で、鉄道の運休や高速道の通行止めが相次いでいる。そんな地上の荒天をよそに、大晦日から始められたものがある。岩泉町の龍泉洞で始まった潜水調査だ。岩手日報の記事によると、31日に41年ぶりの潜水調査が開始した。日本洞穴学研究所が実施。初日は、観光ルート最奥部の第3地底湖からダイバーが潜水し、30から40メートル奥部まで調査した。前回1968年の潜水調査では、水中で隊員1人が死亡する事故が発生しており、今回は、最新器材を使用するなど安全面に配慮。安全なルート確保を最優先し、2月に測量を行う。同研究所は、05年から行った陸上調査と前回の潜水調査に基づく洞窟の図面に相違が生じたため、再度の潜水調査を決めた。地底湖の位置も含めて、今回の潜水調査で洞窟の構造を解明する。宇宙ロケットが飛ぶ時代に、我々の住む地表部分、それもわずか数十メートルの世界が、今なお未解明なのだ。地中の世界は、我々の想像以上に、多様で、複雑で、純粋で、奥深いのだろう。龍泉洞のブログに、潜水調査の様子が紹介されている。調査の安全と、実り多い成果を期待したい。■関連する過去の日記(龍泉洞) 龍泉洞 41年ぶりの潜水調査(09年12月10日) 神秘の地下洞窟 地質百選の龍泉洞(09年3月28日)ところで、龍泉洞が日本三大鍾乳洞の1つであることは知っていたが、他の2つとはどこだろう。子供の頃の私は、根拠もなく安家洞も1つだろうと思っていた。日本最長というのだから、当然だろう、と。とすると3つ目が、山口の秋芳洞か、という感覚。小学生の頃に、全国の奇洞マップみたいなもので、岩手には所在を示す黒丸が2つ並んでいたような、そんな記憶があるからだ。実際には、龍泉洞のほか、秋芳洞(山口県)、龍河洞(高知県)を指すそうだ。岩泉町の公式サイトの観光情報には、こう書いている。----------ここは森と水のシンフォニー「酸素一番宣言」のまち、岩泉町です。太古のロマンと神秘に満ち た洞窟、日本三大鍾乳洞に数えられる龍泉洞を筆頭として、わが岩泉の観光ポイントをご紹介いたし ます。雄大な北上山系に構える本州一広い町、岩泉の自然をまるごと体感してください。----------町のアピールポイントを盛り込んだ文章だが、やはり龍泉洞が筆頭扱い。安家洞も頑張れ、と応援したくなる。さて、悔しさのついでに、敵情視察。秋芳洞や龍河洞は、日本三大を名乗っているだろうか。得てして、日本n大何とか、というのはn番目にすべり込みたい側が標榜する一方で、当然に全国に冠たる地位を築いた側は、悠然として、n大何とかなどと俗な呼称はしないものだ。もし、三大を名乗っていないのなら、わが東北の龍泉洞に恐れと敬意を抱かぬ不届き千万、と東北人として怒り心頭の心境だ。ややオーバーだが。確認した。まず、山口県美祢市の秋吉台・秋芳洞観光サイト。この中の秋芳洞の解説には、何と、「東洋屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」は大正15年昭和天皇が皇太子の御時、本洞を御探勝になり、この名前を賜った」と表現されており、日本三大の文字はない。何とも大胆不敵。積年の恨み、会津に成りかわって、東北人として許し難いおごりぶり(オーバー)。秋芳洞は国の特別天然記念物。観光入り込みも年間85万人を誇る(平成20年山口県観光客動態調査結果)。もう1つ、高知の龍河洞。今日まで知らなかったぞ、そんな名前は。高知県香美市の公式サイトから、龍河洞を訪れると、「国指定の天然記念物及び史蹟になっており、古代人の遺した神の壺や弥生時代の住居跡、石筍や石柱など見どころは盛りだくさん。出口手前には二千年前の先住民の生活跡も残っています」と。残念。三大の文字は、こちらにもなし。国指定史跡・天然記念物。弥生時代の住居跡であることから史跡指定もされているそうだ。以上のような訳で、なんと、龍泉洞が相手にされていないではないか。確かに全国的にはメジャーではないかも知れないが、日本三大鍾乳洞の冠くらいは、一緒に付き合ってくれても良いと思うが。何とも残念でした。龍泉洞の入り込み数は、35万8千人(平成19年、岩手県の観光統計ページから)。頑張れ、龍泉洞。頑張れ、東北。
2010.01.02
コメント(0)
-
雪と陽ざしの庭 その2
怠惰に時を過ごしていると、仕事も世の中のこともすっかり忘れてしまいました。外は夜来の強風が吹き荒れています。ただ、空は真っ青の快晴。2日目のお日さまが元気に新春を照らしています。そんな訳で、思考停止中につき、昨日に引き続き庭の写真です。すみません。雪化粧の上に、新春の光。ただし、強風だけは画像に映りません。
2010.01.02
コメント(0)
-
雪と陽ざしの正月
皆様あけましておめでとうございます。仙台は昨夜から2年越しの雪ですが、朝はおさまり、陽ざしも出ております。それでも、タマに風も強くなり、吹雪と言うほどではないにしても雪が舞っております。画像は、2階から庭の一部を映してみました。雪と陽ざしの雰囲気が、出ているでしょうか。それでは、本年も おだずまジャーナル をよろしくお願いいたします。(編集長 小田島 樹成)
2010.01.01
コメント(4)
全34件 (34件中 1-34件目)
1