PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(86)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(72)演劇「劇場」でお昼寝
(3)映画「元町映画館」でお昼寝
(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(35)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(92)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(53)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(53)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(69)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(90)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(84)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(54)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(19)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(2)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(27)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(21)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(5)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(36)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(20)ベランダだより
(157)徘徊日記 団地界隈
(116)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(33)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(44)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(14)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(26)映画 香港・中国・台湾の監督
(38)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(57)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(27)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(17)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(44)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(30)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(104)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(3)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(11)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(15)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(7)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(2)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介
(17)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(3)週刊 読書案内 小野和子「あいたくて ききたくて 旅にでる」(パンプクエイクスPUMPQUAKES)
カレル・ゼマン「水玉の幻想」元町映画館no284
バーセル・アドラー他「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」シネリーブル神戸no305
エレネ・ナベリアニ「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」元町映画館no281
週刊 読書案内 井戸川射子「共に明るい」(講談社)
徘徊日記 大阪の狛犬 2025年2月17日(月) 「福島の天神さんの狛犬さん」 大阪・福島あたり
劇団MONO 「デマゴギージャズ」ABCホール
ベリコ・ヴィダク「キノ・ライカ 小さな町の映画館」元町映画館no283
徘徊日記 2025年2月18日(火)「寒いんですけど、梅が咲いてました!」団地あたり
コメント新着
キーワードサーチ
若桑みどり「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)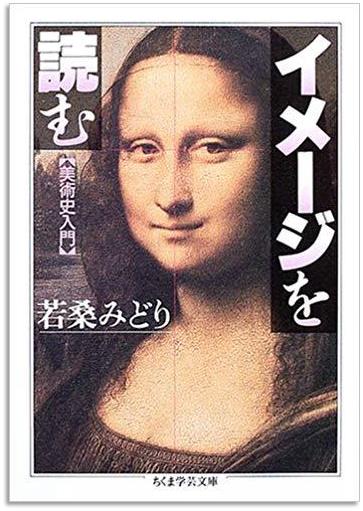 数年前、 中野京子さん
という方の 「怖い絵」(角川文庫)
という本が、ラ・トゥールの「いかさま師」の女の顔の絵を表紙にして出版されて以来、爆発的にヒットして、「高校生に」と思って図書館に揃えたのですが、全く反応がありませんでした。
数年前、 中野京子さん
という方の 「怖い絵」(角川文庫)
という本が、ラ・トゥールの「いかさま師」の女の顔の絵を表紙にして出版されて以来、爆発的にヒットして、「高校生に」と思って図書館に揃えたのですが、全く反応がありませんでした。
仕方がないので、自分で読みましたが、何故ヒットしているのかわかりませんでした。喜んで読んでくれたのは、読書に関して、悪食で大食漢(失礼)で評判の女性教員だけでした。
中野さん
の人気は衰えることなく続いているようでしたが、ぼくは図書館の先生をやめてしまいました。
「絵を見る」ということは、たとえば「本を読む」ということより簡単で万国共通のことだ。見ればわかるのだから。そんなふうに考えがちですが、果たしてそうでしょうか。
おそらく、上記の本はそんなふうに常識だと思い込んで暮らしているわれわれの思考の落とし穴を上手に利用している「名著(?)」だと思いました。「こわい」とか「かわいい」とか、「キモイ」なんていう新しい言葉もありますが、そういう、瞬間的な情動がフォーカスするに違いない「作品」を並べて、読者に新しい「わかった」や「知ってる」を与えてくれます。結果的に「小ネタ」的「教養」の獲得と「絵」を知っているという「自己満足」で納得するという仕組みになっているようですが、如何せん、底が浅いのではないでしょうか。紹介されている絵に関して、少し興味のある人なら、実は知っていることが、大げさに語られている印象でした。
そこで、思い出すのが、 若桑みどり
という美術史家のことです。彼女が高校生向けに書いた 「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)
という本があります。
この本はかつて 「ちくまプリマーブックス」
というシリーズの一冊として出版されていました。このシリーズの狙いは高校生の為の基礎教養の涵養だったと思います。「この程度のインテリジェンスは高校生には必要だ!」
まあ、そういうシリーズですね。ちなみに、シリーズは現在は150冊ほどで刊行がとまっていると思いますが、これをほんとに通読してしまえば大学入試の小論文など屁のようのもんだと思います。
さて、 「イメージを読む」
に戻りましょう。 若桑みどり
さんは絵画を見るときに必要な美術史学における三つの視点の大切さを説明しています。
「様式論」・「図像学(イコノグラフィー)」・「図像解釈学(イコノロジー)」
まず 「様式論」
とは一般に「ルネサンス様式」とか「バロック様式」とか説明されますが、その時代の「視覚の形式」を知ることですね。
次のその図柄のなかに描かれている人物や風景がどんな意味を持っていたのか 《表現されている図像の主題と意味を解明する》
方法である 「図像学」
の必要性が出てきます。
例えばヨーロッパの絵画はある時代、キリスト教の教会の聖画であったわけですから、描かれているのはいったい誰かということがわからないまま感動しても仕方が無いというわけです。
三つ目の 「図像解釈学(イコノのロジー)」
とは、たとえば 《何故15世紀ではものが平明に表現され15、17世紀には明暗のなかで表されたのか。》
を考えるためには、 《当時の時代精神とか、享受層(パトロン)とか、宗教思想とか、流行していた学問や風俗、戦争や疫病などの歴史的大事件など、あらゆるもの》
に目配りし、考察することだそうです。
つまり、一枚の絵を16世紀なら16世紀の社会の思想や感受性を凝縮した情報図像とし鑑賞することが出来るというわけです。
一枚の絵からあるイメージを受け取るというのは、ただ漠然と「美しい色」とか「細かい筆遣い」とか「大きなお尻やな」とか思い浮かべることでなく、しかるべき情報を読むことだと述べています。
「大きなお尻が描かれている」にはそれ相応の理由があるというわけです。
わたしたちは学者になるために絵を見るわけではないわけですから、研究はお任せするとしても、その成果を享受すること、情報の読み方を手ほどきしてもらうにこしたことはありません。作者の手ほどきは教科書の世界史なんかよりずっと面白いことはうけあってもいいですよ。
本論では「ミケランジェロ」「レオナルド・ダ・ヴィンチ」「デューラー」「ジョルジョーネ」という、ほぼ同時代、15世紀後半から16世紀初頭の画家たちが三つの方法論を駆使して解説されています。
たとえば 「レオナルド・ダ・ヴィンチ」
の章にこんな記述があります。
レオナルドは大変な植物の研究家でして、たくさんのデッサンを、葉脈であるとか雄しべ雌しべであるとか、あるいは潅木であるとか喬木であるとか、植物について植物学者のような写生を残しているのです。『岩窟の聖母』に描かれているすべての植物を分析してみた所、植物が非常に雄弁に、そして明確に意味を語っていることがわかりました。たとえば、イエス・キリストのそばに咲いているのはスミレです。スミレというのは謙遜の花であって、イエスの最大の美徳は謙遜なのです。 絵の主題を暗示する レオナルド・ダ・ヴィンチ の手法と教養、それに加えて、当時の宗教観が絵を観察しながら説明されていますね。
キリスト教のなかには七つの美徳と七つの悪徳があって、中世を通じて最大の美徳は謙遜で、最大の悪徳は傲慢です。ここでイエスは神の子、天の子でありながら、だれよりも低く地面に座っている。これこそ究極の謙遜です。
文庫本だから図像が全部白黒なのが残念ですが、文章が語り口調なので読みやすく、北大での授業の講義録の書き直しだそうですから内容は申し分ありません。
読んでしまえば世界が少し広がる?!ことは間違いありません。保証します、口だけですが。
ご安心ください、この本には「売らんかな!」の煽りはかけらもありませんから。
ボタン押してネ!
にほんブログ村


-
週刊 読書案内 山本陽子「入門 日本美… 2025.01.22 コメント(1)
-
週刊 読書案内 シャーロット・マリンズ… 2025.01.04 コメント(1)
-
週刊 読書案内 荒勝俊「日本狛犬大全」… 2024.11.20












