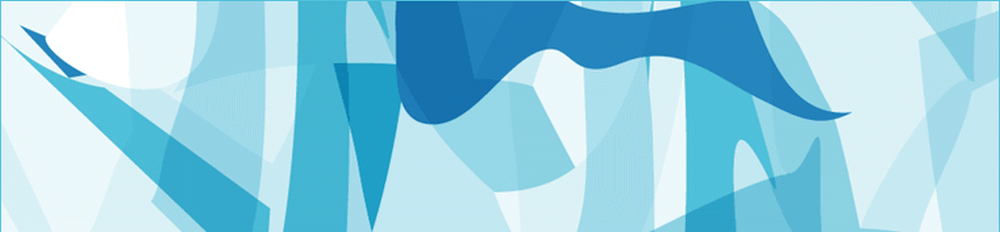2015年02月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
脱衣室が乾燥室に。
日中に家にいないことが多いので数年前に除湿機を購入した。冬でもこの除湿機をかけておくと5、6時間で洗濯物が乾く。ずっと窓の近くで洗濯ものを干していたのだけれど、なんか目ざわりで脱衣室にツッパリ棒を3本つけて、その下に除湿機をおいて、朝に洗濯をして除湿機をかけておくと仕事を終えて帰宅する頃にはもう洗濯物が乾いている。除湿機を使っても電気代はあまりかからないので、電気を使うのは嫌だけど除湿機は使っている。脱衣室に除湿機をおいておくとその熱ためか脱衣室の温度が下がりきらない。ヒートショックのために、入浴で体調を崩したり、場合によって脳卒中や心筋梗塞を起こす事故が増えていることもあって、脱衣室を乾燥室にすることもそうそう悪いことではなさそう。杉花粉が飛び始めているし、PM2.5のこともあり屋外に洗濯ものを干すことがためらわれ、ベランダにガラスの洗濯ものを干す部屋をつくることも出来ないので、電気を使うことについては心が痛むがいたしかたない。都市で生活するって、確かに便利だけど、その分消費量はドンドン増えるばかり。仕方ないのだけど、なんだかな、です。
2015年02月21日
コメント(2)
-
職場会議で、学習会のテーマとカルテシステムの改善を提案してみた。
先週に他のステーションに支援に出かけ、その事業所のカルテシステムが非常に合理的で、初めての患者さんでも全体像がすぐ把握でき何が要点か理解しやすい。今のステーションに異動してきた時、カルテについては法人全体での会議で検討されていたものだときいていたのでそんなもんかと思っていたが、別の事業所では違う方法でなされていた。支援から戻って、同僚にその話をしたらみんな変更すべきだという意見になった。賛同を得られたものと理解して、昨日の職場会議で提案してみたら後押しをする発言は皆無で賛成意見を求めたら一人だけ無難な発言をしてくれた。ふだんのよもやま話の中では、忌憚ない意見を言うのに、物事を決める職場会議で自分の意見を言うのをためらうのはどうしてなのだろう。特別な大きな会議ではなく、職場会議なのに。ちょっと拍子抜けしてしまった。結論としては、改善する方向にするということになったが、「ドンドン変えて行こう!」という元気な声は聞こえず、決まればそれに従うとか、そんな感じにしかならない。今の現状に不満でも、変わることに対しては消極的。そんな気分が蔓延している職場なのだと痛感。上司に意見を言うことに、消極的になったり、自分の意見を表明しなかったり、同意する意見に対しても賛意を積極的に表現しなかったり。公式の場で発言しなけらば、変わりようが無いのに。提案について疑問を持ったり、実行するうえで何が障害になるかなど、実行するうえで意見があればドンドン言えばいいのに。私は小さいときに、頑固一徹の父にすぐ上の姉が堂々と意見をしてその意見を認められたりする姿を見ていたこともあり、小さいころから自分の考えを両親や兄弟姉妹、先生に話すのは気にならないでいた。反対されたり否定されることも多いがそれはそれは意見の相違で止むをえないと受け止めていた。小学校4、5、6年の担任教師は戦後民主主義の申し子みたいな先生で、学級会議で論議し、決めたことを皆で実行するということをとことん教えてくれたので会議で自分の意見を表明するのは参加者の義務と信じてきた。授業中も学級会議でも、皆率先して手を上げてどんどん発言するのが普通だった。その先生の考えは、自主的に生きるというものだった。自分の意見を持ち、人に言われてするのではなく自分で考えたことを自主的に行う。マァ中学校に進んだら、担任になった教師からはすぐさまその考えは否定されてしまったが。そんな風に育ったので、これまで上司だからとか目上の人だから、なんと思われるかとか気にしたりすることなく、とりあえず自分の意見を主張することはしてきた。「かわいくない」「理想主義すぎる」「純粋ね」とか色々言われてきたけど、自分を偽るようなことだけはしてこなかったつもり。一人ひとり、考え方や生き方の価値観、行動の規範になるものは違うわけだから、他の人に自分の生き方を押しつけはしないけど、今の職場、所長だけが問題だけでなく、私を含めた組織そのもののあり方に課題があるのだろうと気づかされた昨日一日だった。
2015年02月20日
コメント(8)
-
三田での研修会。久々に充実した一日で体も心もすっきり。
訪問看護の仕事を続けていると、患者さんの生活の中に入らせていただくので、苦しそうだったり不自由だったりする患者さんの姿を間近に目にすることが多くとても心が痛む。どうしたら楽になるのか、悩んでも活字で勉強してもなかなか自分の知識や技術は高まらず、ここ10年ほどずっとずっと悩み続けている。リハビリの専門職と違って、身体の運動の仕組みや筋肉、骨、神経についての基礎的学問を殆ど学んでいないこともあって、体位変換とかポジショニングとか移乗や移動の介助方法についてなかなかうまく出来ない。看護師も患者さんの身体に接触をする仕事なので、病気のことだけでなく、身体運動の仕組みや働きについて学ばないと不適切なケアで「看護、介護関連障害」と言われている色々な障害を引き起こしてしまう。「愛護的なケア」とよく教科書に書いているのだけれど、このことを実践するとなると、そのための学習をしなければならない。ヨーロッパの福祉用具を輸入販売している会社が、そんな医療従事者の悩みを解決するために、実技を重視した研修会を開いている。受講料はお高いけど、それに見合うというよりも受講料の高いことも払拭するだけの研修内容なので経済的に許す限り、この会社の開く研修会には参加している。総花的な内容ではなく、研修に参加者が何を欲しているかをまず傾聴して、その要望に沿って自由自在に研修内容を組み立ててくださるので、もう明日から使えるような具体的な方法についてその根拠を含めて学ぶことができる。自分の悩みが解決されるのでとにかく研修が終わったときの爽快感は心地よい。今日は車いすのシーティング。骨格の変形や筋肉の低下に応じて体はそれに適応して変化していく。その変化によって食べにくくなったり動きが不自由になったりジョクソウができたり、呼吸が浅くなってしまうことで肺炎を起こしやすくなったり。そういった身体の機能低下を防ぐためにどう車いすの姿勢を整えていくかという内容。身体が変化していくことの原理を、自分身体感覚を研ぎ澄ませてちょっとした変化にも気がつくようになっていくので体の仕組みが腑に落ちるように理解できる。午前と午後に一時間ほどかけて受講生同士がペアになって実際にシーティングを体験するので、嘘のように理解が進む。午前中に試みた車いすの姿勢のまま、食事をしてみた。普段の私は早食いなので5分もかからず御飯を食べてしまうのに、体が後ろに傾いた姿勢になっただけで御飯をのみ込もうとしても米粒がのどを刺激して痛むしそもそも早く飲み込めない。弁当を食べ終わるのに35分もかかってしまった。ちょっとした姿勢の変化がこんなにも嚥下機能を低下させてしまうか身を持って知ることができた。たった1cm体が後ろに傾くだけで、腕の高さが上がるだけで、車いすの座面の形状を変えるだけで、などなどほんの少し変化が機能を高めたり低下させたり。受講生のほとんどは理学療法士や作業療法士で看護師は私一人。他の方はリハビリの専門家なので、もっともっと高いレベルの内容を希望していたのかもしれないけど、私にとっては本当に満足した内容。分からないこと、出来ないことに気づいて、その上にそのことが解決していく。研修ってこんな風に組み立てられると学習効果が高まることも実感。久しぶりの三田で、通りの間から東京タワーを眺めたり日本電気本社ビル前の「ひかり門」のモニュメントを始めてえ見たり。本当に今日は良い一日だった。
2015年02月15日
コメント(6)
-
ある研修会での歯科医の言動に違和感。現場で悩まないで簡単に胃ろうをつくってしまうのは誤解です。
昨日、ある研修会に参加した。 民間の会社が協賛しておこなったもので、講師が経鼻胃管(鼻から細い管を胃に入れて栄養剤を胃に入れる)や胃ろう造設について医科の現場でさも安易に行って経営に貢献しているといった話をされ会場に嘲笑が広がった。非常に不愉快になった。 高齢者が肺炎になった時、急性期の病院では短期間で治療を行わなければならないように医療保険の仕組みになっており、栄養状態が悪ければ末梢の血管(静脈)は出にくいので、中心静脈栄養か経鼻胃管で栄養状態を改善し、肺炎を治すために抗生剤の治療は必須になるのでどうしたって注射か胃管を使って治療しなければならない。 まず問題の一つとして、高齢になればなるほど嚥下機能は低下することについて高齢者の医療に携わる者(医科、歯科にかかわらず)が、日常の医療の一環として患者の口の中を診て口腔衛生やや嚥下機能の低下を予防する必要性を指導したり、歯科医が義歯を作成したとき嚥下機能を維持するために一生義歯を使い続ける重要性や口腔衛生について指導しているか、である。 歯が無くなって口から食べられなくなるのは、早くて50代頃から始まるだろうから、その世代の治療をする医科や歯科の医師が生涯の健康維持について「お口」の診察と教育をしなければならないであろう。内科疾患で、歯や嚥下について説明している医師はどのくらいいるだろう。 虫歯や歯周病に治療では口腔衛生につて必ず指導するだろうけど、生涯の問題としてパンフレットやDVDなどの映像で指導している医療機関はどのくらいあるのだろうか。 医科の急性期入院は、医療費削減の目玉になっているので、診断名に対応した治療を一週間とか10日間で退院させなければならない。しかも診断と治療がセットになった医療の枠が決められているので、口腔の問題があっても治療ができにくい保険の仕組みになっている。 胃の管を簡単に入れて肺炎を繰り返せば、簡単に胃ろうをつくって金もうけをしている、と揶揄するのは簡単だけど、あまりにも急性期の医療の実態を知らなさすぎる。その医師は、嚥下造影検査や嚥下内視鏡についても批判していた。 「平穏死」などという言葉を提唱している医師は60代を超えているし、昨日の講師も60代位。誤解されてしまうが高齢の医師は急性期の医療から離れているので、医療経済や厚生行政の仕組みに無理解で現場で働く医師を批判的にとらえたり否定しやすいように思う。 単純化した話は分かりやすいが誤解を与えやすい。 食べるための体の機能が低下した時のために、早期(せめて50代くらい)から一人ひとりが準備していく課題だと思う。肺炎は高齢者の死因の一位だし、肺炎になる前から、肺炎になっても口から食べるために、普段から何をしていくか是非知識を得て健康作りをしていってほしい。 胃ろうも胃管も一生その処置を受け続けなくてはならないものでなく、脳血管疾患の急性期から慢性期になって機能が改善すれば再び経口摂取ができるようになる。栄養状態を改善するために一時的処置にすぎないことも多いのだ。もちろん、その間リハビリと、嚥下機能の評価をしたうえでのことだが。 昨日の件の医師の話にも一理はあって、急性期の病院で口腔ケアと評して口腔内をガーゼでごしごしこすって、手当て出なく暴力的な方法をとっているといった批判はもっともで、手当てなら癒しを与えるようなケアの技術を身につけてほしいというのはその通りだと思う。 現在の医療の仕組みは、超急性期、急性期、亜急性期、回復期、慢性期と疾病の治療をする段階で医療機関の機能がはっきり分かれているので、自宅に戻るまで転々と入退院を繰り返さなければならない。 現場の医師も看護師も疲弊しきっているし、この問題を解決するには本当にややこしい。もっともっと横断的に専門職が協力して対応しなければならない課題だと思う。 介護の分野でも在宅医療でも経口摂取をするための知識と技術を高めなければならない。 でも残念ながら、訪問診察(いわゆる往診)でお口まで診察をする医師はどのくらいいるのだろう。床ずれがあっても全身の皮膚の診察をしないし、口や足をしっかり診る医師も少ない。肺炎になれば抗生物質を処方するけれど、呼吸器の診察は簡単に済ませてしまう。 私が看護師になったばかりのころの昔の医師は、全身を隈なく診察していたものだけど。現場はドンドン忙しくなってドンドン追い詰められて、そして、患者を総合的に診る医師が限られていく。 世の中が殺伐としてきて、「誰もが、どこにいても、必要な医療が受けられる」という皆保険の理念は失われ、「応能負担」(注)と称して医療保険の患者の負担割合はどんどん増えて行っている。経口摂取関することに限らないが、高齢者は目や耳、歯だけではなく身体の多臓器がトラブルに見舞われる。必要だと分かっていても、経済的な問題でそうそう医師にかからなくなるだろうし、歯無しになっても義歯を使わずにいる方も多い。 生活保護は税金の無駄使いと断言する人がいるくらいだから、高齢者の健康問題も自助努力で何とかしなさいって、行政としては無策でも平気なんだろうな。注;ぼちぼちむらさんのご指摘の通り「応能負担」ではなく、「応益負担」です。誤った記述をして大変失礼しました。
2015年02月14日
コメント(4)
-
職場管理者のキャラクターって、職場風土の大きな要因かもしれない。
法人内の訪問看護ステーションの同年齢の看護師が大腿骨頸部骨折で人工骨頭置換術の手術を受けたために、そのステーションに支援に半日だけ出向。 そのステーションの所長はまだ若い(30代後半)が、めちゃくちゃ明るくって声も大きいし笑い声も華やか。 ピリピリした雰囲気は全く無くって、特別に敬語を使うこともなく淡々とした話し方をするものの、要点はきっちり抑えている。面倒くさがらず、嫌なことは自分から率先して行うって雰囲気。 わが方の所長はいつも偉そうで、気にいらないと口調がきつくなったり分からなけらばその意味を糺さずただ分からなくって困ると言うばかり。 よその事業所と比較しても仕方が無いのだけれど、上司の性格でこんなにも職場の雰囲気が違うものかとビックリ。 ご自分の素のままで自然体でふるまうって大事なんだと。 現在勤めるステーションも人出不足なのだけれど、年度末の面接で異動希望を出そうかなとふと思う。 出向したステーションは大きな商店街の真ん中にあって、お野菜も一割くらい安いし、お魚屋さん、肉屋さん、花屋さん、蕎麦屋もラーメン屋もイタリアンレストランもあり、居酒屋も多い。 半日だけで十分な情報が得られるわけではないけど、第一印象は200点満点かな。 アーァ、異動したい!!
2015年02月13日
コメント(4)
-
口腔ケアが怖いって、どんなふうにケアをしているのだろう。
Tさんは88歳の温厚な紳士。2度の脳梗塞で言葉を話せなくなったが、廻りの状況や看護師の言動、ご自分の体の様子も良く分かっている方。35年間教職を勤めて、若い学生や看護学生を温かい目で見てくださる。よほどのことでも怒ったりすることはない。傑作なのは、看護師がちょっと手順を間違えたりすると大きく口を開けて大笑い。ちょっとしたミスを見逃さず笑う。この方がケアを拒否するってどういうことなのだろう。新メンバーIさんはもうこの方の訪問を何回もいっているのに、最近口腔ケアを希望されない、という看護記録が続いているので、訪問の時に何か不都合でもあるか、本人に尋ねてみたが特別な理由は言われなかった。誤嚥性肺炎は高齢者の死因の第一位でもあるしTさんは誤嚥性肺炎で2回も入院したことがある。この間口腔ケアをする際に、「お口には一億とか二億とか細菌が沢山住んでいるので口腔ケアをしたほうが娘さんを心配させないためにもお熱を出して辛い思いをするよりずっといいんですけど」と話しをして、「若い方はケアの希望をきくようにしているけど、口腔ケアは希望するしないの問題ではないように思うんですけど、どうして希望しないことがあるんですか」「口腔ケアの方法が何か問題があるんですか」と尋ねても笑っているだけ。良識がある方なので、多分正直に他のメンバーのことを話すことをためらわれたと思う。そして昨日、Iさんが訪問して「今日は受けるけど、怖いからこの次からは嫌だ」とIさんにはっきり話されたそう。実務経験が少ないのは若いから仕方が無いのだけれど、Iさんは自分はできると思い込んでいるので、他のメンバーにどういう方法でしたらよいか尋ねることをしない。実際訪問してから、分からない、できないことに直面して出来ないこと、分からないことがはっきりするようで、患者さんの前で手順書を見たりしてまごまごしている。それでも分からないと家族に聞いたりするのだという。これは、ご家族からの苦情で判明した。何度となく、患者宅に訪問してから手順書を眺めてケアを実施知るのはダメで、契約した限られた時間でやるべきことを行い、次の訪問まで患者さんの状態が安定して過ごせるように評価して必要なケアをするのが訪問看護の仕事だから、手順書を見る時間は契約時間の書かに入っているとは思わないで事前にケア内容を頭に叩き込んで行くようにしなければダメ、と私もIさんに話したし他のメンバーも話したという。このことは所長に話して、所長が面接したようだが、行動パターンは変わっていない。学びたい、技術をつけたい、よりよいケアをしたいと思っていれば些細なことも学習を繰り返すし、他者に尋ねることもする。ケアに時間がかかり、時間内に終わりそうもない患者さんに担当を指示するのは、きっちり指導をして看護師二人で訪問してIさんのケアをもう一人が見て必要なことが出来ているか評価して独り立ちしても大丈夫となったら一人で訪問するようにしたほうが良いと進言しても、体制の問題だからなどとの理由をつけてそのままにしている。きっと、どんどん苦情が増えるだろうな。一緒に訪問しないので、どういうやり方をしているかがブラックボックスなので対応に困るのだけど、とりあえず口腔ケアについては判明したので、この技術にはケアの指導をしてみようと思う。
2015年02月11日
コメント(4)
-
元気をもらえるのは、やっぱり患者さんの言葉です!!
ここ2年ほどお付き合いをしていただいている97歳のご婦人。耳は遠いものの、毎日新聞を読みイヤホンでTVを楽しんでおられる。番組選びは、朝刊のTV蘭を娘さんがチェックしお二人で何をみるか相談して決めている。父上もご主人もお医者さまで、女学校を卒業するまで買い食いをすることは全くなかったそうで、お金を使うことは殆どなくって、教師になってからやっとお金の使い方を学ばれたという。この方、本当にほめ上手で、何かケアをするたびに「ありがとう」と声をかけてくださる。看護学生さんを連れていくと「良い職業を選ばれたわね。苦労が多いことだろうけど頑張って長く働いて私たちを助けてくださいね」などと話しかけてくださる。こんな言葉をかけてくださる患者さんとの触れ合いは、学生さんにとってもとっても貴重な経験で「頑張って看護師になって働こう」という気持ちを強くするみたい。モンスターペイシャントなんて言葉が日常にあふれるようになってきた昨今だけど、看護学生や看護師に対して温かく見守る患者さんがいらっしゃることが本当に心強い。昨年の暮れから落ち込みがちな私だが、この方の訪問をすると何をしてもほめてくださるので、特別なことをしているわけではないのだけれど、ちょっと元気になってくる。人は認められることを望む動物だという。不自然に無理やりほめなくっても、ただ認めるだけで生き続けられるのだという。労うとか感謝するという言動も認めることの一つだと思う。どうかすると、できないことに目が行きがちだけど、できていること、毎日普通に続けていることも大切なことだと思う。今日の訪問はそんなことを考えさせてくれた。
2015年02月09日
コメント(6)
-
今季の冬支度大成功。
ここ数年、真冬の暖房費(ガスストーブ)が馬鹿にならない。フローリングなので、足元が冷えて冷えて膝掛けを使ったり、レッグウォーマーを二重履きにしたりいろいろ試したみたけど、関東の建物が断熱材をしっかり使うのは多分ここ15年前後のことなのだろうけど、我が家はこの断熱材を使っていそうもないほど冬の底冷えは酷い。窓が5つもあるので、南向きのお部屋と北向きのお部屋では室温が4度くらい違う。ここ2年ほど夏はエアコンを使わない暮らしにチャレンジしてみた。家の中に風が通り抜けるように扇風機とサーキュレーターを使って、アイスノンを三重使いにしたりして真夏の節電に成功。暑さにさらされていると汗腺が発達して良く汗をかくので体力もついたようでこの冬はインフルエンザの予防接種をしなかったけど風邪をひかず。窓からの冷気をシャットダウンすればよいかもしれないと考えて、東向きの出窓だけは何もせずに残りの窓には2重カーテンをつけて玄関と玄関の入り口にも同様に二重カーテン。天気の良い日は、南向きのカーテンを開けて日光を室内に入れると窓側のお部屋は真冬なのに20度くらいになる。昼間の室温が高いと部屋が暖まっているせいか夜中も14度くらい。北向きの居間にガスストーブを一番低い設定温度(14度位)にすると1時間もたたないうちに18度位になり、2重カーテンのおかげでこの室温が意外と保てる。朝になれば、出窓から朝日が射し込んでくるので、脳内時計も活性化してくるし、朝起きてもそうそう室温が低くないので(10度位)、朝起きるのもそうそう億劫ではないので、緑茶を一杯飲むと結構しっかり目覚めてくる。部屋着は一時ダウンとか着こんでみたけど妙に温かくなりすぎて不快なので、吸汗速乾下着+ヒートテック+メリノウール+綿のパーカー又はシャツ、下衣はヒートテック+暖パン+メリノウールのハイソックス。厚手のフリースとかもダウンと同じで暑すぎるし、直接ヒートテックだと何となく着心地が悪い。夏物の吸汗速乾下着が快適化に役立ってくれる。冬の間だけは、昇降式のテーブルを和卓位に低くして長座布団をひいて湯たんぽを足元に置いてフリースの膝掛けを掛けるともうポカポカ。今季の冬支度はまずまず成功。エアコンを使わないでいると、大概の公共場はエアコンなので何となく埃っぽく感じてしまう。関東の寒さは後一カ月半くらいで終わるので、そろそろ今年の夏対策も色々対策を練ろうと思う。居間狙っているのは、シャープの3D扇風機。そして、緑のカーテン。4月には準備を始めたほうがよさそうなので時々ホームセンターに行って色々物色中。こんなことを言えるのも関東に住んでいるからなのだけど。3.11以後、どうしても電気を使うのがためらわれて、でも電気を使わない生活はどだい無理で。出来る限りの節電をすることしかできないのだけれど。
2015年02月06日
コメント(12)
-
思いこみから脱するためには。
職場で感ずる色々な課題(問題)を、職場全体の課題として明確にしていくためにはどうしたらよいものだろうか。一人が感じている事柄を全員のものとしてみんなで取り組むためにはどういう道筋で共有していけばよいのか。自分が考えていることを他のメンバーに投げかけても、その場だけで過ぎ去っていく。霧や蒸気みたいに、すぐに消えていく。患者さんのケアをできるだけベストのものにしていくためにと問題提起してもピンと受け止めてもらえないのは、自分の提案の仕方に問題があったりするのではないかとここ一週間くらい考えこんでしまった。事態や状況についてどう受け止めるかについては、一人ひとりの考え方(突き詰めると職業観や人生観などの価値観)によることが大きいように思う。仕事をし始めたころ、良く面倒を見てくださった先輩から、最低一日一論文は目を通して学習をコツコツ続けていくことで10年、20年たてばその成果が自分の確信につながると教えられ、その教えを守ってきたつもり。少しずつ分かることが増えてくると、毎日の仕事の中で新たに発見することはいくつになってもあるもので、ケアを充実させていくことに終わりはないと思えてくる。実習に来る学生さんに話すとどんどん吸収していくのに、なぜ同僚に同じ話をしても何も変わっていかないのだろう。分からないことを分からないままにし、できないことをできないままにして仕事を続けていく様子が、不思議でならない。上司の問題が続いているのも、変わらないことを望んでいる職場風土があるのやも知れず。そして、そういう同僚に対して、皆と一緒に成長しようという私の気量が無かったからだとも思う。
2015年02月05日
コメント(8)
-
朝の45分間、心のリセット。
毎日色々嫌なことがあっても、朝には気分一新して心のリセット。 BSプレミアムの朝7時「ニッポンの里山」。日本各地の里山の情景を美しい映像で魅せてくれる。自然の厳しさがあってもその自然の特徴を生かして様々な暮らしが営まれている。そして人間も昆虫も鳥たちも自然の恵みにともに活かされている暮らし。都会で暮らしていると自然とのつながりは薄くなっているけれど、自然に感謝して暮らし続けているその日々の様子に心が洗われる。代々受け継がれている自然を生かし自然に生かされているその暮らし。 今森光彦さんの写真もとっても素敵。 7時10分からは「もう一度、日本」。この番組も日本各地の自然とそこで暮らす人々の暮らしが5分の映像で構成されている。自然の成り立ちの説明もあり、美しい日本の数々を魅せてくれる。厳しい自然の中で様々な撮影方法を駆使して自然を写しだしてくれる。 アーァ、日本で生まれて、地球で生まれて生きている素晴らしさを感謝してしまう。 そして「梅ちゃん先生」と「マッサン」。 時代の荒波にもまれても一生懸命生きていこうとする人々の生きていく姿勢に心がほんわかしたり勇気づけられたり。 朝の45分間で心をリセットして毎日出勤する私です。
2015年02月03日
コメント(4)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット
- 萬松山龍潭寺(りょうたんじ)~井伊…
- (2025-11-26 06:00:06)
-
-
-
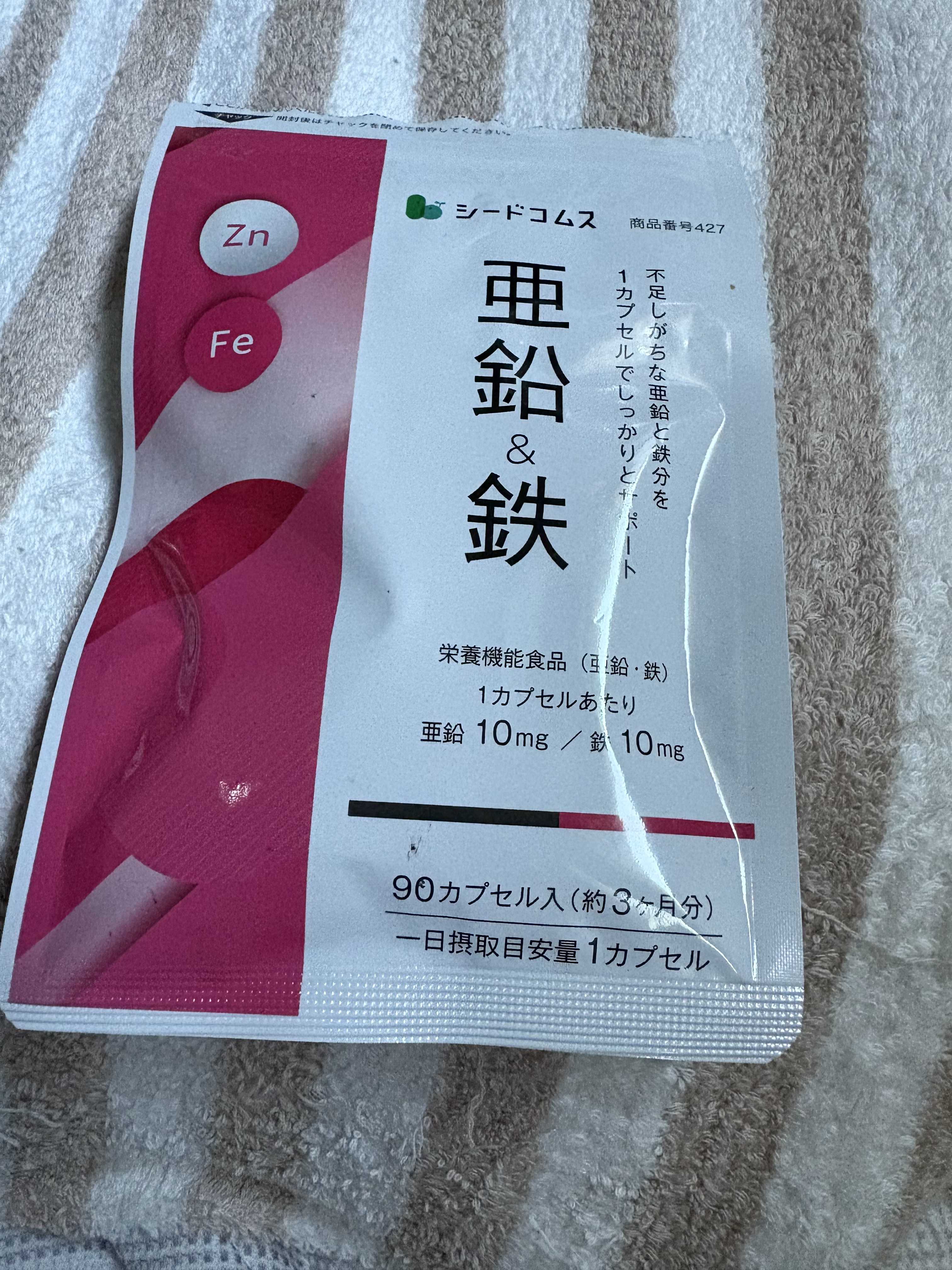
- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- チョコレート爆食やめれた理由は?
- (2025-11-26 08:22:49)
-
-
-

- 活き活き健康講座
- ☆トレーニングスリッパ☆
- (2025-09-22 20:40:58)
-