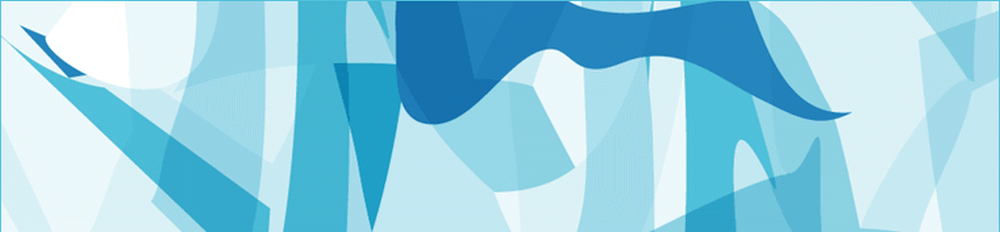2015年08月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
windows 10 の無料インストール終了。思った以上に快適です。
windows 10の無料インストールをどうしようかと迷っていたが、お知らせが来たのでダメもとでインストールしてみた。 PCが重くなっているので、起動時間は早くはならないが、フォトについてはすごく使いやすくなっていて6年前の写真がきれいに早く検索できる。写真も大きくなっていて、もうしばらくはノートパソコンでもいいかなと思ってしまう。 購入してからもう6年たってしまったので、そろそろ買い替えてもいいかなと思うのだが、スマホを使うことが多くなり、メールもLINEを使ったりしているので、PCでメールする頻度も減ってきたし、ブログと仕事関係の検索、写真の整理で使うくらいになってきたので、まだまだ使えそうだ。 写真に関しては、最近はデジカメとPCをつなぐコードを紛失してしまうし、メモリーカードを入れる場所に誇りがたまりすぎてSDカードから直接読み取れなくなってしまったり、朝の散歩もしなくなったのでブログに写真を載せなくなったりで、まぁなくてもいいかなと思ってしまう。 スマホは仕事中もいろいろな連絡で使うので、極力省エネモードで使っているのでゲームもしないし検索も最低限にしている。 結局、ノートパソコンとタブレット、スマホを持つと使う用途と頻度が分散されるので、パソコンだけに頼らなければならないということがなくなり、今程度の使い方なら、古いパソコンでも平気な気がする。 XPとかに比べれば、WINDOWS 7だってそうそう悪くはないのだけれども、10にしてとりあえずよかったというのが、今の気持ちです。
2015年08月26日
コメント(4)
-
なぁんだ、みんな興味があったんだ。看護師が行う関節可動域訓練。
今日の朝礼で、ケアマネージャーさんから看護師のケアで、リハビリ目的なのに少しもリハビリをしてくれない、との苦情があったとの報告があった。 看護師の基礎教育ではリハビリについては2時間くらい触れるだけなので、リハビリについて本格的に学ぼうと思ったら回復期リハビリとか急性期のICUとかで下測肺におおい肺炎予防とか、そういったことを重視している職場に配属されない限り学ぶ機会はない。 看護の基礎教育は、30年前の私の体験では、看護師が看護学生を教育するのではなく、看護とは何かにも興味も関心がない医師とか大学の講師とかが多くって、どういう看護を目指すから基礎科目の文学では何を学ぶとか、腰痛などの多い看護業務を乗り越えるためにどういう身体を作り上げるとかそんなことにはまったく触れられもせず、一般大学の教養科目と同じような内容で、他の大学の講義ノートを見れば試験にパスしてしまうような内容だった。 訪問看護のような慢性期や終末期の患者さんの看護ケアをするならば、その方その方の身体状況を適切に把握して、できるだけ消耗の少ないケアや合併症が進行しないようなケアを目指さなければならない。 急性期は、診断が確定されたらその疾病の治療が優先されるので、身体拘束をしたり薬物療法でせん妄や認知症症状を一定抑えなければならないことにもなる。 でも自宅での生活をする方には、ご本人が望む生活を実現するために、家族や訪問介護のヘルパーさんたちと協力して、本人や家族に負担がかからないようなケアをしたり、そのためにチームでその方のケアの標準化を目指したりとか、ケアの基本が大幅に変わってくる。 ずいぶん前には、30年前くらいのことだけど、50代で脳卒中になって片麻痺になると福祉用具が開発されていないのでベッドに寝たままで生活をすることになり、そのことで褥瘡ができたり関節拘縮が進んでしまったりと悲惨な方にお目にかかることが非常に多く、何もできない自分が口惜しく恨めしく、無力感を毎日感じていた。それでも褥瘡の処置に伺うことだけでもご家族は感謝されるのであった。なんともつらい仕事の毎日であまりにも辛すぎて、休日は寝たきりで過ごすことが多かったような。 その頃は在宅生活が可能な条件としてどんなものがあるかなどをテーマにすれば学会発表ができたくらいの、非常に遅れた日本の在宅看護の実情であった。 介護保険が始まって、多少ましになったものの、予防的ケアをどうすればよいのか、医師もケアマネージャーさんもそうだけど、看護師自身の認識がとっても届かなくって、褥瘡をどんどん大きくしても処置だけに関心を持つのだけれど、看護師が行う体位交換とか清拭とかのスキンケアとかそういったことも褥瘡の原因になることとわかっていない方がまだまだ多い。 患者さんにリラックスしていただかないと合併症がどんどん進むといっても、ケアの方法を変えない。ここ一年本当にどうしたものかと悩んでいたのだが、今朝の苦情の話で、やっとちょっと変えないといけないと認識してくれたようで、仕事が終わってからある人と勉強会をし始めたら、ほかの二人も自然に仲間になってくれて、みんなで勉強をして19時を迎えた。 やっと皆で学びあうことができ始めたと、ちょっと勇気が出てきた。 患者さんは一人ひとり違い、さらに機能の患者さんの状態や状況と明日の患者さんとは変化している。その時その時の状態に合わせて、どうケアをすればよいのか、それを考え実行できるようになるのが、自宅療養をされる患者さんを支援する看護師の役割なのだと思う。 そういう力を作り上げていくには、チーム全体でケアのあり方を検討したり、うまく言った方法を学びあうとかが絶対必要なので、やっとそんなことができ始めたようで、帰宅は遅くなったのだけど、ちょっとうれしい一日であった。
2015年08月24日
コメント(4)
-
二日連続、科博(国立科学博物館)通い。
8月初旬から、姉が東京で行われる森林インストラクター研修のために、我が家に滞在。 とりあえず姉が使えるように一室の掃除して、テーブルなども用意して、研修中は朝食の用意と、洗濯を毎日行ってほんの少しサポート。 普段は朝食は牛乳とコーヒーくらいだけど、講義形式の研修なので昼は軽く食べるというので、朝食は栄養バランスを考えて、たんぱく質を数種、野菜とコーヒーといつもよりしっかりと朝食を用意。朝の9時半から夕方の6時過ぎまでの講義なのですっかり疲れ切っているようで、夕食を用意できないときには近くの蕎麦屋さんやラーメン屋さんで食事。 夜も復習と予習で勉強し始めるものの、疲れ切っているようで、本を顔に乗せたまま寝入っている。朝は声をかけないと目を覚まさない日も。電車が混みあう前に家を出るので、7時半には出かけ、帰宅は夕方の7時半。 よくまぁ続くものだと感心してしまう。 生物多様性、とか普通のカラマツよりも2倍酸素を出すカラマツの開発とか。森林に関係しない生活をしていたものにとっては、一つ一つの講義が難解かつ新鮮で、姉はどんどん森林をはじめ、地球とか宇宙とかについての関心を広げているようだった。昨年もこの研修を受けたので、この一年で図書館に通い詰めたり、いろいろな森林に出かけたりして見聞を広めたようで、今年は講義の理解度も深まったと喜んでいた。 姉に影響されて、姉と一緒に科博に二日間通うことになった。 地球館はリニューアルされて、またまた素晴らしい展示になっている。地下2階の展示を見るだけで一日。地下一階の展示でも一日。 標本が素晴らしく、人間と始祖鳥の骨格展示があって、どちらも共通の仕組みになっているとか。 人間の解剖生理を勉強してきたのに、動物の一種としての人間がどのように進化の過程をたどってきたかなんて今までたいした興味がなかったのに、恐竜や象の骨格と人間のそれとの共通点を見つけながら食い入るように眺めていると昼過ぎには頭が痛くなって生あくび。 いったん屋上に行って外の空気をすって空を眺めて、おにぎりを食べてコーヒーを飲み一息ついたらまた展示室。 少しわかることが増えると、また見えてくる部分が増えて、一つの展示にかかる時間が増える。 科博は何回行っても飽きることがない。 リピーターパスを更新しようと思って友の会コーナーに行ったら、友の会への入会を勧められて、特別展示についても招待券が無料で入手でき、常設展は何回でも無料。音声ガイダンスは初回だけ310円払うとあとは何回でも無料。電車で一時間もかからないし、上野は好きだし、友の会に入会。 生命の大躍進の招待券を早速頂戴した。 自然教育園も無料で入園できるし、山に行く気力は今のところないので、せいぜい都内の植物園や公園で自然観察などを楽しもうと思う。
2015年08月23日
コメント(10)
-
2日連続の眠れぬ夜。
金曜日の夕方、肺がん末期の方を担当しているケアマネージャーが慌てて事務所に飛び込んできた。初めての訪問入浴の日で、本人もとても楽しみにしていたのに、ゼーゼーと息が荒く訪問入浴が始まる段になって口調が荒く興奮して入浴を拒否されたとのこと。 1週間前から咳で眠れぬ夜が続いているとも聞いていたので、ひょっとして肺炎? 心不全? 胸水の増加? と色々と気になり急遽、帰宅の道沿いにお家があるので雨の中寄ってみた。 ベッドに横たわっているものの、玄関を開けただけで ゼーゼーという荒い息づかいが聞こえてくる。全身汗がびっしょりで奥さまが体を拭いても拭いても汗が止まないという。 肺炎や心不全など胸郭内の臓器が障害を受けると、体を起す姿勢のほうが呼吸がしやすくなるので、ベッドの上で胡坐をかいていただき、背中に座布団をあててタオルケットを丸めたりして姿勢を整えた。10分、15分と経過するうちに呼吸が落ち着いてきてゼーゼーと荒い息づかいもなくなり、汗も完全にひいた。 やっと本人に笑顔が見られ、心配そうに眺めていた奥さまも少し安堵された様子だった。 「お風呂はもう金輪際嫌ですか」と尋ねてみると、「そうじゃないよ、今度は入りたいよ」との返事。 「呼吸が苦しくなって、血液の酸素の量が少なくなったことで脳に届く酸素の量が少なくなって、少し気分が変わってしまったのかもしれませんね」と説明すると「俺もそう思うよ」って。 両胸に手を当てると気管支の中を痰が移動するときに発生する振動が伝わってくるし、右肺の呼吸音が弱く、バリバリと音も聞こえる。 「ずっとベッドの上で座っているのは疲れてしまうので、疲れたら横になって、またゼーゼーしてきたら座って呼吸が落ち着くのを待ってくださいね。夜中、奥さまだけでは手に負えそうもないと感じた時には遠慮しないで携帯電話に連絡をください。すぐに飛んできますから。」と、駐輪場まで見送ってくださった奥様に念を押した。 あんなに苦しい呼吸状態なら、何が起きてもおかしくないし、夜中でも連絡があったらすぐ出かけるつもりで布団に横になったものの殆ど眠れないまま夜明けがきた。 二人で頑張って夜明けを迎えられたのかと思っていたときに、携帯電話が鳴った。息子さんからの電話で、「5時半に息がとまった。お袋が少し横になって眠っていた間に亡くなったようで、目が覚めたときにはもう息をしていなかった。呼吸が止まった時どんな様子だったか家族はだれも見守れなかったんです」と。 「御父様は昨夜は眠ることができたんでしょうか」と尋ねると、「いびきをかいて寝ていたようです」と返事が。 何日も眠れぬ夜が続いたので、最後の夜に奥さまがそばにいてぐっすり眠れたのなら、それはそれで良かったのかもしれないが、もう長くは無いと知っていたものの、そういう日を迎えたご家族の深い思いは計り知れないはず。 最期まで、おむつをつけずにトイレに行くことを希望していた。 脳梗塞、心筋梗塞、肺がんと辛い病気を色々されてきて、最後は進行がんで亡くなってしまわれた。 今年はどういうわけかお見送りする場面が多い。少しでもご本人やご家族が希望する自宅での生活を続けられるようにお手伝いをしたいが、生活全体を支えるような体制を整えたり、ご家族の介護方法の相談に適切に答えたりするのは非常に難しい。 そして日曜日(今日)の深夜、「咳が止まらない」と携帯電話に連絡が入った。分娩時の障害で脳性マヒで50年以上自宅療養をされている方のお母様。「痛いことはしないでほしい」と吸引機を購入したのに、目にしたくないと器械にカバーをかけてカーテンの陰にしまっておられる。「痰が多いんですね、お母さんとりあえず吸引をしましょう」と伝えて、電話を切る。 深夜2時半から4時まで。姿勢を整えたり、脈拍数と酸素飽和度をモニターしながら、吸引をしたり背中や腰をマッサージしたり。何とか呼吸数も脈拍数も落ち着いてまた午前に訪問することを約束して帰ってきた。この方も肺炎を起こしたようで、痰が動く時の振動も胸で触れるし、バリバリとした呼吸音もなくならない。 かかりつけのS病院なら入院をしてもいいけど、でも延命治療はしてほしくないし、わたし(母、83歳)が無くなる前にこの子を見送りたいし、どうしたらよいか結論を出すのは難しいわね。 と、迷っている様子。「また、連絡しますので、お母さんのお気持ちを一定整理しておいてくださいね」と話す。 午前中に訪問すると、深夜に比べると呼吸も脈拍も落ち着いているが、痰が貯留している状態は変わらず。 「明日に、往診を受けてどんな結果になるのか、入院するかどうかについてはもう少し考えたい」と。 終末期をどのように迎えるかについては、いろいろな議論があり非常に難しいが、癌に限らず色々な病気で終末期を迎える方に対して、食べられない、息が苦しい、痛い、吐き気がするなどなどさまざまな苦痛を和らげながら、のんびりゆったりと自宅で最期を迎えるような方法はきっとあるはず。 二日続けての眠られぬ夜だったけど、日々のケアの中でご本人やご家族からお話をよく聞く中で、どう暮らしていくかは、みつけられるはずとの思いを強くした。
2015年08月16日
コメント(2)
-
やっと、仕事が訪問看護と認識してくれた主治医。
一カ月に一回のメンタルクリニックの受診になってもう半年くらい。 2週間に一回だと、田舎にいる兄弟姉妹より接する機会も時間も多く、前回受診からの様子を伝えるのも普通になった。 今週の火曜日も受診日で、いつものように「どうだった?」って先生。 「イライラする頻度も時間も増えて、イライラが治まるまでの時間も長くなってきているんです」と私。 すると、「正当な理由があって怒っている感じ?」って。 「自分では、正当な理由だとは思えるんですけど、はたから見たらどうでしょうね。そうたいしたことでもないと思われるかもしれませんけど」 「正当な理由が無くても、怒りたくなることもあるよね。薬のせいかな? レキサプロはそういうことがあるけどね。でもパキシルのような強いものではないだろうし。サインバルタはそんなには怒りたくなりそうもないけど」 「怒鳴りたくなったり、暴力をふるいたくなるような激しいものではないんですけど。ちょっとイライラが長すぎるなぁって感じです。イライラしていることに気がついても、その後も続くのでちょっとイライラし過ぎのような感じがしてるんです」って私。 「マァ、人に迷惑をかけるようなものでなければ、大丈夫かな。梅雨明けからずっと暑くって大丈夫だった?」と先生。 へぇ、先生私の仕事をやっと覚えてくれたんだと思いつつ、「先週の金曜日は夕方に患者さんのおうちを出ても熱い湿った空気がまとわりついてきて、本当に疲れました。やっぱり、立秋を過ぎると少しずつ涼しくなってありがたいです」と私。 「今年はまた暑い日が長く続いたから大変だったね。次までまた同じ処方でも大丈夫そうだね」と先生。 いつものように、「元気でね」との先生の言葉で診察終了。 確かに立秋を過ぎたころからパタッと35度を超える日が続かなくなったし、夕方日が沈むのも6時半前になってきた。日没が早いと、夜になってからの涼しさが戻ってくるのが幾分早くなってきた感じ。 お盆中はずっと働くので、その前に二日間の連休が突然降ってわいてこの二日休みだったけど、映画を見たり自然番組を見たり、時々ビールで喉をうるおしたり、シャワーを浴びたり。ダラダラのんびり、好きなように時間を使い放題ってとっても贅沢!
2015年08月13日
コメント(4)
-
一生懸命なのはわかるけど、一つ一つ聞かれるとゆっくり休んでいられない。
ここ半年の間に、新しい看護師が4名増えて、ケアが複雑な患者さんに対しては、同行訪問を2回とか3回とか繰り返しているのだけど、なかなか仕事を覚えなくって、一々説明しないとケアが終わらないらしい。 Sさんのストーマは、腹筋に力を入れるような姿勢をするとすぐにストーマから大腸が15cmとか出てきてしまう。ストーマ脱と簡単に言ってしまうものも、このおかげでストーマを造設してから2年ほどは、ストーマ装具がしばしば外れてしまい便がベッドに広がってしまうとか様々なトラブルが続き、やっと今の方法で落ち着いた。 この方は、新しい看護師も高校生も看学生も教育的に見てくださるので、一人の患者として看護師や医師に望むことを率直だけどしかし愛情持って話してださる。 そんなSさんに甘え過ぎてしまったのだろうか、最近に就職してきた看護師は、仕事をしっかり覚えてケアに臨むのではなく、一々患者さんに聞いて仕事をしているらしい。 2回で覚えきらずに、自分なりの看護手順書をつくって、その方の家に行く前にイマージトレーニングをして、出来るだけ本人に負担をかけないようにケアをするようにはしていないようで、酷い時は「次は何をしたらよいですか」と訊くこともあるよう。 訪問看護計画でお約束した時間にお約束した内容を実施しなければならないので、いちいち聞かなくても済むように仕事の準備をするのが当たり前なのに、それをしていない。 スムーズにケアが進むか分からないし聞かれた時に起きていないといけないので、目を閉じていることもできなくって疲れてしまうという。「いろいろ注文を出すのは私がわがままだからいけないのよね」「教え方が悪いのね」とSさん。 どうしてこういう実態があるのか、患者さんから何回も教えてもらわないと分からないようでは、私たちが職場で教育していること自体に沢山の課題があるということなのだ。 「Sさんは我がままではないですよ。その方その方にとってふさわしい方法でケアをするのが看護なのですから、看護する側が患者さんに聞かなくては仕事ができないようにしか育てていない私たちがいけないのです」と伝えても、「私がわがままだから」としょんぼりしている。 入院患者さんなら、その入院期間に入院目的に沿ってしっかり決められたことをしなけらばならない。 在宅患者さんは、ケアの方法が一定完成していて、ほぼベストの方法になっているのだから、新しい職員はその方法をしっかり学ぶしかないのに、どうしてそういうことが分からないのだろうか。 ある看護師は汗かきなのに、鉢巻きもせず、首にタオルも巻かず、手に汗をかいても汗を拭かずに、患者さんのベッドに汗を垂らしてしまったそう。患者さんはそれを困って、その看護師のためにエアコンの設定温度を下げたのだという。 心をこめてその患者さんのケアをするのは看護師であって、患者さんからケアをされ、しかも患者さんにとって必要なエアコンの設定温度でないことを平気で見過ごしてしまうとは、だってリウマチで関節痛がある人なんですよ。 どうしてこういうことになってしまったのか。 新しい職員が入ってくるたびに、どうな風に職場で育てていくか話し合いをしましょう、しましょうと言っても一向に無頓着な上司。 猛暑のせいでイライラしていることもあるけど、新しい看護師たちに無責任な仕事の仕方に対しても腹が立って仕方がない。職場としての統一した方針が無いのだから、まとめようもない感じがして、今日はがっかりするやら、イライラするやら。 本当に、看護をするってことをどう考えているのだろう。 ウーム、分からない。
2015年08月10日
コメント(4)
-
立秋前日の7日の暑さには参った、37.7度体温を超えると応えますね。
7月末からずっと働きづくめだった。 今年の東京は梅雨明けから休む間もなくずっと暑さが続いた。 グリーンカーテンだけではあまり効果が無かったが、窓の外に遮熱スクリーンをかけてみたら、外気温以上に室内が高くならず、最高気温より-2度位は低い。 クーラーを使おうか使わまいかと悩んでいるのだけれど、何度までしのげるか実験中。 扇風機だけでなく、サーキュレーターと合わせて使ってとにかく室内の風の通りを良くして風を室内にとどまらせないようにしている。 7日には帰宅すると室温35度。帰宅直後窓と玄関を開け放して、ベランダの風が玄関から出ていくように風の流れをつくってみた。ベランダのゴーヤやなっぱ類にの鉢にも水を上げて約1時間で31.5度に下がった。 一晩中、扇風機は付けっ放しで、アイスノンをダブルで使い、熱くなったら反対側を使ってと繰り返していたら何とか夜が明けた。クーラーをやっぱり使うべきなんじゃないかと決意が覆りそうになったけど、8日は涼しく一日中寝放題。一日で疲れがとり切れず、今日も夕方までグッスリ。 猛暑続きで早々夏疲れ。 立秋が過ぎると幾分涼しくなりそうで、これからは8月上旬までの暑さが弱まってくれればよいのだけど。 熱中症については、ゴールデンウィークのころから患者さんやご家族にはその話をして、室温計と湿度計をまだ用意していないうちには用意していただき、エアコンの使い方や扇風機の併用についてお伝えしてきた。 まだ訪問患者さんには、熱中症で入院された方はいないが、これからどうなるやら。 長い夏はやはり疲れやすいし、睡眠を良くとり、汗をかいた分はしっかあり水分、塩分補給をしないと体調を崩す。 最近はまっている梅ジュースに一つまみのお塩のドリンク。色々飲み物はあった方が良いので、自分で経口保水液を作りその中にクエン酸を一つまみ。やっぱり飲みたいのは緑茶。体がすっきりして気持ちよい。 夜だけは時間が比較的にあるので温かく調理したものを最低3品は食べて、もちろん肉や魚は欠かさず。 立秋が過ぎたので、そろそろ涼しい日が時折やってきそう。台風の季節にもなりそうだけどね。
2015年08月09日
コメント(4)
-
一人でイライラしても仕方ないことは重々盛り過ぎているのだが、、、、。なんだかむっと来る日が続いていいる。
現在の職場は、患者数が90名近く居て、職員も9名なので、患者さん全体の状態を把握して適切なケアをしていくにほ、一人一人がその方の病態を丁寧に行って、患者さんや患者さん家族の話を丁寧に聞いて、病気の進行状態を予測しながら何をしていくことがベストなのか、患者さんと共に考えケアをすることが必要だ。 慢性の心不全の末期とか、腎不全の末期とかになれば、今後どのように症状が変化するかは予測がつくことも。患者さんの苦痛を最小限にするためには、床ずれの予防をすることなどは基本中の基本なのに、スキンケアについてのリスク要因の検討を全くしていない。 さまざまな癌の末期でも、痛み、吐き気、倦怠感、食欲不振、不眠、吐き気、血圧低下、便秘や下痢など身体全体の及ぶことがある。 患者さんの体のことなのだから。患者さんによく教えてもらえなければ対応が出来ない、それは当然のこと。 それなのに、医師や廻りの同僚に言われた処置だけしてくるとは何を考えているんだ!! と、喝を入れたくなる。 喝を入れただけで何もどう仕様もならないから、じっと我慢だけど。 職業人として、教育を受け、業務をすることに免許を与えられているということを真に受け止めているのだろうか。 看護師になって以来、指示を受けて仕事をするということは医師の診療ほ補助をするという任務に限って言えば必要な教務だが、その指示が患者の状態に適切ではないと判断したら、主治医に提案するのは、患者の健康を守っていく看護師としては当然の義務なのに。 さらに上肢の判断が間違っているときには、患者さんにとってそれが不利益なることなら、やはり進言すべきことなのだ。 マァ、そういう口うるさい看護師は煙たがられるし、患者さんのケアとして提案したことは受け入れないことも多い。 チーム医療、チーム医療と言われるが、病院施設内のチームも難しい面も多いが地域のチーム医療はさらに難しい。 さまざまな事業者が参加していると、その中でベストのケアをどうしていけばよいかというテーマをチームとして結集できなければどうしようもない。 今在宅医療に携わっている専門職の方々は、各職種の業務範囲に限定せず、その職種の技術が他の職種にとっても有効だと思うなら、ドンドン相互に教育をし合うことが必要だし、そのことで患者や家族の介護ケアの腕は上がっていくのだ。 自分の殻を破って、患者さんに近づいて行く。そういう専門職になりたい、
2015年08月06日
コメント(2)
-
同世代の同僚が介護のために退職していった!
診療所で一緒に働いて、新しい診療所の建設と新診療所での業務の構築で苦楽を共にした同僚の男性職員が両親の介護で退職していった。 福島の浜通りが実家なので、遠距離介護するのも難しく、結局長期休暇をとった間にどの程度公的サービスを使って両親二人の生活が可能なのか様子を見ていたそうだが、どう転んでも親たちだけの生活は無理の無理と判断して退職していった。 もう50代後半だから、地元に帰っていくのも年齢的には限界なんだろうなと思う。 ふだんは無口だが、恥ずかしそうにカラオケのマイクととるとすごい歌唱力で川島エイゴを、サザンとかさらっと歌い上げてしまう。 訪問看護を受けている患者さんの中にも、息子さんが仕事を辞めて介護にあたっている方も多い。それも年金受給前の年齢で、さまざまな節約を重ねて介護をしている。 男性の介護者とひとくくりでまとめるわけにはいかないのだけれど、仕事をしてきた経験が物を言うのだろうけど、業務基準を作成するように介護の仕事をまとめ上げて、必要度に応じて時間を決めて、一日、週間、月間と必要な介護業務を整理して淡々とこなしていく。 介護を始めたばかりだと、色々な情報を整理してその方にとってどのような介護が必要か説明していくとどんどん吸収されて必要なことを見につけていく。ご自分なりの仕事の仕方を身につけて行って、一旦それが完成してしまうと臨機応変ということが難しくなる方も中にはいらっしゃる。 医学も看護も日進月歩で、昨日は正しいと言われたことが今日になれば誤りになってしまうことがある。 男性の介護者にその訂正をしていただくときには、そもそもの解剖生理から、病態とか、新しい知見のポイントとかを論理的に説明しないと受け入れていただけない。 家族のためにというだけの、感情に訴えるだけの説明は殆ど通用しない。 息子さんだけではなく、ご主人も同じで、20年、30年と介護を続けていらっしゃると手技の変更をするのは非常に難しい。肺炎を起こしたり、尿路感染を起こしても、その感染症の原因と思われる介護の手技が明らかでもやっぱり訂正することは困難なことが多い。 介護度が重度になればなるほど、必要な時間も多くなるし、必要な物品も多い。使い捨てのプラスティック手袋も、医療の現場では一手技一手袋が原則なので排便の介助が終われば手袋を新しくして陰部洗浄をする、そして陰部洗浄が終わったらまたその手袋をはずす。 訪問看護で家族が用意した手袋を使うのは忍びなくって、自分は仕事用の手袋は沢山用意して訪問する。病院と違って家庭の物品の整理はその家庭ごとに違うし、その介助が終わるまでの必要物品がとりやすい位置にまとまっておいてあることも少ない。 ケアに当たる前に必要物品を用意するのだけれど、あれが足りないといったことが生ずると汚れた手袋で家具やシーツに触れたらそれだけで家族の仕事を増やすことになるので起こりうることをすべて予想して必要物品を用意するし、家族が用意できていないと思われる物品は自分の仕事鞄から出しておく。 20年も介護しているお宅に訪問した時に、排便介助で使った手袋を水で洗って乾かして使い回していることを知って驚いた。プラスティック手袋も左右100枚で1000円くらいなのだけど、月とか年とかの使用料をまとめていくと相当な額になるのだと思う。節約したくなるお気持ちが分からないわけでもない。 ノロウィルスとかインフルエンザとかの話が普及して手洗いが大事だということは常識になってきたので、訪問先で手を流水で洗わせていただくことは一般的になったが、それ以前は手を洗う時に流水で洗っていると水道の水の無駄使いと思われて御叱りを受けたことがある。10年も前のことではないのだ。先輩にもさっきの手洗いは何なの、って怒られたことも。 介護するご家族に、正しいことを根拠を踏まえて伝えていき、いずれ新しい知見が明らかになったら変更もあり得ると一々説明していくのは面倒なこともあるけど、でも手を抜くことは許されないのだと思う。 これからは、一人の子供さんのご家庭も多いので、息子さんでも娘さんでも一人のお子さんは両親を介護したり、配偶者の両親を介護していくことンも多くなるのだと思う。 こんなことを考えると家族に頼った高齢者社会の存続は無理と断言せざるを得ない。かといって有料の介護サービスの質が良くなって安心して介護を受けられる世の中になるかも ??。 数年前に、日本医師会の会長が準看護師は、精神科病院、介護施設、診療所などで地域医療を維持するうえで必要な職種であると言い切った。準看護師とは中学卒業後2年間の教育で都道府県の試験を受けて合格すれば業務に就くことができる。何が準なのか、良く分かっていない方も多いと思うが、簡単に言うと看護師の指示を受けて患者さんの療養上の介助をする職種なのだ。精神科の患者さんも障害者や高齢者の施設での介護も非常に難しいし、知識や技術が必要となる。 中卒後2年の教育でそういう仕事を自信を持って出来るようになるのだろうか。看護学校を卒業して30年以上もたっても、そういう分野の仕事は非常に難しく感じている。日本医師会のすべての分野も否定することは出来ないがこれほど準看護師の養成について頑固の賛成しているその意味が分からない。 そういう先生方は、準看護師中心の施設なんてもう日本には非常に少ないのだけど、そういう施設に入れるのか自問自答してほしい。安上がりの医療を推進することにすぎないのだと思ってしまうのは私だけだろうか。 超高齢化社会になって、安心して医療や介護を受ける世の中にしなければならないが、現実のいろいろを考えるとため息が止まらない。
2015年08月05日
コメント(4)
-
ここ最近、コーヒーや紅茶を飲まなくなったし喫茶店にも行っていない。夕方は、餃子にビールが平気になってしまった。
職場の近くにも住まいの近くにも喫茶店が少ない。どこの商店街でも、飲食店がつぶれれても居酒屋関係だけは店が増えていくという。 高校生のころはお金が無かったので、せいぜい自販機のコーラーを飲んだりパン屋さんとか雑貨屋さんで餡パンとかを食べるのがやっと。それでも友人たちとがやがやおしゃべりをしながら家路をたどるだけで十分楽しかった。 バイトをするようになってから自分で使えるお小遣いも増えて何かというと喫茶店で、ホットコーヒーだけで楽しめたし、働くようになったらマックとかイタリアンとかもう少しお金が払えるようになって色々なお店に行けるようになった。 でも、昼間からビールとラーメンとか、ビールとそばとか、そういうことはできなかったし、一人で寿司屋さんに行くなんてとんでもないという感じ。一杯千円のコーヒーを気取って飲んだこともあった。 仕事中も、昼休みもコーヒーを何杯も飲んだし、家でコーヒー豆を切らすことは無かった。 訪問の仕事をするようになって、患者さんのお宅のトイレを使わせていただくことは禁止されてから、いつしか職場でコーヒーを飲まなくなって、自宅のコーヒー豆も消えた。 50を過ぎ、一人でラーメンやにも入れるようになって、昼間のビールも人の目を気にせず飲めるようになって、いつしかコーヒーに何百円も使うよりビールのほうが良いと思うように。受験勉強とか、期限がある提出物とか、そういうものと縁が無くなってきたことも影響しているんだろうけど。 コーヒーを飲まなくなって、お菓子やケーキ類を自分のために買わなくなったし。お菓子を買うなら野菜や果物を買う方がいいと思うようになったし。 そんなわけで、最近は緑茶や健康茶とかを買っている。先月、ハリオの茶葉を入れて水だし緑茶が作れるというガラスのポットを買った。これが優れモノで、パックタイプの水だし茶よりずっとずっと美味しく、綺麗な緑色のお茶が仕上がり、ペットボトルに移して凍らせてもきれいな色を保てるし時間が経っても飲み口のさわやかさは消えない。 私の嗜好も年とともに変わってきた。生活の変化も影響して、何をどれだけ消費するかということも変化するものだと思う。
2015年08月03日
コメント(6)
-
25年振りの患者さんとの再会。
今の会社に就職したのは20代後半。 そのころは、まだ訪問看護が医療保険の対象になっていなく、外来看護師が仕事中に気になる患者さんを自分の時間を利用して訪問して、具合が悪くなっているから主治医に往診してほしいとか、とても自宅で過ごせそうもないから入院して治療を受けたほうがいいとかお話ししたのが訪問看護の始まりで、往診の合間に訪問看護をして床ずれの処置とか退院して間もない患者さんが無事で過ごしているかなど安否確認をしていた。 Zさんは30歳になったばかりで、ALSという難病と診断を受けて会社をしめざるを得なくなり、退職してしばらくしたら離婚して、次第に体の動きが悪くなって、階段昇降機を区と都の補助金で設置したり、呼吸困難になると入院して呼吸器を装着したり、体が不自由になるたびに新たな治療を受け入れて生活をされていた。 訪問看護の職場から透析室、診療所と移動していったが、Zさんが様々な治療を受け入れて自宅で生活をしていることは風の便りで知っていた。ヘルパーさんたちやボランティアの方々の手助けでコンサートに行ったり、お花見に行ったり、紅葉狩りに行ったりすることも。 どういうわけか、訪問看護の仕事に戻ってくると、Zさんは看護師に年齢制限の希望があって35歳以下ではないとダメとか、そんなわけで私はZさんの担当になることは無くここ7年過ぎてきた。 たまたま、今週は担当の看護師が家の事情で休みをとらざるを得なくなり、やむを得ず私が担当することになった。定期訪問の担当になるときには、何回か先輩の看護師と同行訪問して、マニュアルに記載できない細かなことの指導を受けて、ご本人から一人でも訪問しても大丈夫というお墨付きをもらって、やっと訪問看護ができるようになる。 今回はアテロームの切開手術後のガーゼ交換で毎日訪問看護の指示が出た。 35歳未満ではないし、事前の技術指導も受けていないし、どうしたものかと心配であったけど、私の名前も声も覚えていてくださって、眼球の動きで文字盤を追い介護福祉士さんが読みとるというコミュニケーション手段をとっているのだけれど、「懐かしいです。相かわらず、お優しいですね」と言ってくださった。 自分の20代のころがどんなだったかもう覚えていないけれど、そんな風に患者さんに受け止められて、久しぶりに看護師を続けていて良かったと思った。 同じ地域で仕事を続けていると、患者さんも一緒に年をとって行き、小児科のお子さんが大人になりまた自分の子供を診察で連れて来ていて、お会いできたりということもある。 看護師の仕事は特別に派手でもなく、名もなき仕事のうちの一つになると思うが、それでも時には患者さんやその家族の方が顔を覚えていてくれて懐かしい出会いをすることがある。 今年の東京は、梅雨明け以来暑い日が続いている。雲ひとつない青空とか、アスファルトから熱気がもうもうと顔に迫ってきたり、入道雲がモクモク湧いていたりとか、 アーァ、夏なんだなぁとしみじみと感じる。 小学生の頃、夏休みにアスファルトの道路を歩いて学校のプールまで。帰りの道でアスファルトの道に陽炎みたいに空気が流れていた。泳ぎ疲れたからだと冷たいアイスキャンディーと入道雲。 夏生まれのせいなのか、夏には桃とか李とか、冷えたキュウリやトマトとか。食べものの思い出が一杯で、夏は熱くても好き。もうアイスキャンディーを道路を歩きながら食べないけど、夕方のビールはとてつもなく美味しい。 Zさんの25年、私の25年。 それぞれがそれぞれの境遇で、一生懸命に生きてきたのだと思う。
2015年08月01日
コメント(2)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- ダイエット!健康!美容!
- 🌶️ 鶏肉と根菜のカレーソテー 香り…
- (2025-11-26 12:15:05)
-
-
-

- 今日の健康状態は?
- マヌカハニーのど飴、いろいろありす…
- (2025-11-21 18:05:52)
-
-
-

- 闘病記
- 長男🐻久しぶりの学校🏫へ🚗(在宅5日…
- (2025-11-26 12:00:06)
-