2006年01月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
消費者問題どこへいく~弁護士反撃 賠償ゲット
今日は少しいい話です。今日の朝日新聞に「ワンクリック詐欺 弁護士反撃賠償ゲット」という見出しでワンクリック詐欺を仕掛けられた弁護士が「威圧的な請求で精神的苦痛を受けた」としてサイト運営者に400万円の損害賠償を求めた訴訟で、サイト側に30万円の支払いを命じる判決が言い渡されたそうです。訴えた弁護士さんは「泣き寝入りする被害者が多い中、不正な請求に応じる必要がないばかりか、賠償も勝ち取れることを示した意義は大きい」と話しているそうです。このような詐欺の場合、相手も所在も掴めず(所在もわからない相手と契約しようがないはずです。そう考えても払わなくてもよいのです。)、訴訟や告訴がしにくい場合が多いがさすが弁護士さん。サイト運営者も相手が悪かったか。 でもその隣の記事は「保証金詐欺被害拡大66億円」昨年に比べオレオレ詐欺、架空請求詐欺の被害額は減ったが融資保証金詐欺だけは増加したそうです。こっちをたたけば、こっちがでっぱる。まだまだ続きそうです。くれぐれもご用心を。事務所ホームページが新しくなりました。週一で更新中です。ぜひご覧ください。消費者問題のページもあります。 藤田教育行政書士事務所のホームページはこちらから
Jan 31, 2006
コメント(0)
-
基本を制するものは試験を制する(2)~きょういく行政書士の受験講座~その2
「いくら基本だけしっかりやれと言ってもその基本だけでも大変なんだ。」とのお叱りの声をいただきました。おっしゃるとおりです。私の勉強している「法律」という分野も基本事項だけでも膨大な量です。それにほとんどの人は少ない時間を割いて受験勉強をなさっています。極端な話をしましょう。あなたは試験の数日前にこともあろうに今度受験する試験の問題用紙を拾ってしまいました。あなたならどうしますか(交番に届ける等のはなしではありません。)。私ならその問題の箇所だけ調べて答えを導き出し、それをしっかりおぼえて(覚える努力をしなくても頭に入ると思いますが。)試験会場に向かいます。試験問題がわかっていれば出題箇所だけしか勉強しませんよね。受験生は学問の追究したいのではなくて、試験に合格したいだけなので当然です。これが最小の試験勉強です。でも今回受ける問題が道端に落ちているわけありません。でも、昨年以降の問題なら本屋さんに売っています。そうです。過去問集です。過去問の研究で試験勉強の範囲を絞ることができます。最近は中学受験ですら過去問、過去問といっています。行政書士試験のご意見もいただきました。昨年の試験は「難問、奇問」連続だったとか。合格ラインが6割の試験で合格率が2、3パーセントとは、ちょっと聞いたことありませんね。この辺はじっくり研究して後日書きたいと思います。新会社法の施行が迫る中、勉強しなければならないことが多すぎる。事務所ホームページが新しくなりました。週一で更新中です。ぜひご覧ください。 藤田教育行政書士事務所のホームページはこちらから
Jan 30, 2006
コメント(0)
-
事務所ホームページ新しくしました。
以前はトップページのみでしたが個人ホームページと連動し、 「会社法務・許認可申請分野」 「家庭・教育分野」 「消費者問題分野」 の3つページができました。まだ、準備中の部分が多いですが週一回の更 新で盛りだくさんなHPになる予定です。どうぞごらんください。 藤田教育行政書士事務所のホームページはこちらから
Jan 29, 2006
コメント(0)
-
基本を制する者は試験を制す(1)~きょういく行政書士の受験講座~その1
中学受験から司法試験まで(因みに私は両試験とも不合格でした。)、各試験に関する情報は世の中に氾濫しております。皆さん、それに振り回されてはいけません。その問題ができなくても合否に影響のない「難問・奇問」を振りかざし、「さあ大変だ、もっと勉強しなければ・・・・。」ということもあります。要求された枝葉の知識までもれなく頭に詰め込み、試験会場に行ければいいのですが枝葉を追うことによって幹の部分(基本事項)がお留守になります。基本事項がしっかりしていれば「ここまで勉強していなかったけど、こうなるのではないか。」と応用も利きます。「試験場で考え、試験場で勉強する。」ことも可能なのです。ましてや合格ラインが6割~7割の試験ならば正答率の高い問題を確実にとっていくことが合格への大きな土台となります。枝葉の知識を問う問題にエネルギーを費やし(酷い時にはたった一問か二問のために。)、合格への土台となる基本問題を落としてしまっては合格はできません。「あんなに勉強したのに・・・・。」となるのではないでしょうか。
Jan 29, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その8~
法令分野「行政書士の業務に関し必要な法令等」がの出題数が増え、出題科目が減りました。出題数が40題から46題、出題科目が10科目から5科目(行政法関連は一つと数えました。)。おそらく記述式が6問、択一式が40問という分け方ではないでしょうか。記述式は憲法・行政法・民法の順で1・4・1か2・2・2。択一式は憲法・行政法・民法・商法・基礎法学の順で10・14・10・4・2。行政法・商法・基礎法学で10問をどう割り振るかでしょう。前回書いた流れから行くと基礎法学も案外増えるかもしれませんね。
Jan 28, 2006
コメント(0)
-
平成18年度より行政書士試験が変わります~その7~
今回の改正では業務分野が多岐にわたり特定されないという行政書士の特性等を鑑み、より一層法的思考力等を問うため、その判定になじみやすい基本法を中心に出題法令の限定を行ったそうです。ですから当然一つの法律科目からの出題数は増えることになります。ですから知識面だけでなく深い思考力が要求される問題が多くなると思われます。 平成15年の行政書士法改正で登録・入会後の行政書士については、資質向上のための研修の義務付けがなされました。今回の改正で行政書士業務と関わりが深い法律科目が削除されましたが、その修得は登録・入会後の研修等に委ね、試験では法的素養が試されるようです。試験により一定の法律的素養が実証された者であれば、個別法の修得も生ずることもないと考えられたようです。とはいっても行政書士の業務に関連する一般知識等において基本的な出題はされるようです。ここでも基本が試されます。
Jan 27, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その6~
行政書士試験の改正内容のつづきです。4 試験科目 (1)行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法(行政書士法 施行規則を含む。)「戸籍法」「住民基本台帳法」労働法及び「税 法」が削除された。(これらについては、「政治・経済・社会」又 は「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う 出題がなされうる。) (2)行政法の出題範囲を明確化するため、「行政法(行政法の一般的な 法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償 法及び地方自治法を中心とする。)」とされた。 (3)「一般教養」が「行政書士の業務に関連する一般知識等」に変更さ れ、その出題分野が、「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報 保護」及び「文章理解」と明記された。 「行政書士の業務に関連する一般知識等」に変更するなら個人的な意 見として数学的なこと必要だと思います。たとえば図形や測量的なも のなど。「政治・経済・社会」に削除された法令問題がどのような形 で姿をあらわすか。おそらくより基 礎的な問題になると思いま す。
Jan 24, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その5~
行政書士試験の改正内容のつづきです。3 出題数 「行政書士の業務に関し必要な法令等から40題、一般教養から20題」か ら「行政書士の業務に関し必要な法令等から46題、行政書士の業務に関連 する一般知識等から14題」に変更された。 私が受験生なら喜んでしまいますね。一般教養は苦手でしたから。4 試験科目 (1)行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法(行政書士法 施行規則を含む。)「戸籍法」「住民基本台帳法」労働法及び「税法」 が削除された。(これらについては、「政治・経済・社会」又は「情報 通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされ うる。) (つづく) ここは賛否両論のところでしょうか。実務から言えばみな重要な法令で す。「行政書士になるのに行政書士法を勉強しないの?」という人もいるで しょう。しかし、その次の括弧書きが曲者、(「政治・経済・社会」又は 「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなさ れうる。)。法令問題が増えた上に法令問題色の濃い一般知識問題が出題さ れるということですね。
Jan 23, 2006
コメント(0)
-
紙じゃないから印紙は入りません~電子公証制度~その2
電子公証制度だけでなく、「電子○○」「オンライン○○」はなるものはなにやらとっきつにくいものというイメージがあり、後回しにしていた私だかやり始めるとなかなか興味深いものばかり。先日参加した某研修会でも「実際に自分でやってみないとわからないし、やってみると意外と簡単。」と講師の方がおっしゃていたが正にそのとおり。まず、住民基本台帳カードも申請し、公的個人認証サービスも受けた。「なんで個人の電子証明書発行してもらうのに住基カードがいるねん。」と思っていたが仕組みがわかってみると「まあ、そりゃそうだわ。」という感じ。手数料も住基カード1000円、電子証明書の発行が500円と以外に安かった。「パスポートも電子申請で・・・。」とパンフレットにあったので早速試してみようと思ったが今のパスポートが2008年まで有効でした。
Jan 22, 2006
コメント(1)
-
紙じゃないから印紙は入りません~電子公証制度~その1
契約書・領収書等にその金額に合わせて収入印紙をはらなければなりませんが、「山があるから登るのさ」と同じように「書類があるから印紙をはるのさ」ということになっています。逆に「書類(紙)でなければ印紙はいらない」ということにもなります。「口約束」の契約には収入印紙は貼りようがないのです。 株式会社を設立するとき(現時点では有限会社も)、公証人にその定款を認証してもらわなければなりません。その際、公証人に払う費用が5万円と定款という書類に4万円の収入印紙を貼らなければなりません。しかし、「電子的記録の定款(電子定款)」の作成が認められ、書類(紙)ではない電子定款(フロッピー等に記録)の場合は4万円の収入印紙が不要になりました。この電子定款は行政書士が作成を代理することができます。といっても電子証明書を発行してもらったり、パソコンのソフト購入したりと一定のの準備は必要で私の事務所でも昨年その準備が完了してこの電子定款に対応できるようになりました。
Jan 21, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その4~
話が横道にそれてしまいましたので本題に戻しましょう。私の入手した財団法人行政書士試験研究センター発行の「平成18年度の試験から行政書士試験が変わります。」というパンフレットによると「行政書士試験の施行に関する定め」が平成17年9月30日に改正され、平成18年4月1日に施行されるとのことです。その内容は1 試験期日 試験日が毎年「10月の第4日曜日」から「11月の第2日曜日」に繰り下げられた。 試験時間が「午後1時から午後3時30分まで」から「午後1時から午後4時までに30分拡大された。2 合格発表日 試験の実施する日の属する年度の1月の「第三週」に属する日から同月の「第五週」に属する日に繰り下げられた。 (つづく)
Jan 18, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その3~
昨日の日記は都合により削除いたしました。本日、再掲載いたします。 平成3年度行政書士試験の論述試験のテーマは「ゴミ問題について論述せよ。」(正確な記憶ではありませんが出題の趣旨はこのようなものでした。)でした。現在は「ゴミ問題」というより地球環境問題として大きく採り上げられています。平成3年ですでに警笛が鳴らされていました。私も関心を持っていましたので「これは書けるな。」と内心喜びました。ですがただ知識を羅列しただけの答案だったなら私は合格しなかったかもしれません。私は当時市販されていた行政書士試験の論述試験の参考書(行政書士試験の参考書すら今の違って数少なかった時代、ましてや論述試験のみの参考書など多分その一冊だけだったと思います。)に書かれていた一番重要な点だけを頭において答案を書きました。それは「いかなるテーマであっても行政・企業・個人の役割を明確にして書きこと」です。私は企業の役割を中心に論述しましたが、行政・個人の役割もしっかりおさえた答案を書きました。試験終了後、合格できる答案かどうかより「行政・企業・個人」の役割をしっかりおさえた答案が書けたので満足でした。「行政・企業・個人」のこの視点は行政書士試験だけでなく、他の試験でも役立つと思います。覚えておいて損はないと思います。
Jan 18, 2006
コメント(1)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その2~
私は平成3年度に行政書士試験に合格しました。当時は今とほぼ同じ形式の択一試験と今ではなくなってしまった「論述試験」(論じて述べる試験、口述試験に対して書いて述べる試験。)がありました。私は法律科目では民法・行政法・憲法の順で得意なので、この3つの出題数が多い行政書士試験は正に私向きの試験でした。しかし、高校時代ラグビーに明け暮れた私にとって一般教養科目は法律科目の出来を帳消しにするぐらいのできの悪さだったのです。数的処理の問題はどう解いていいのかわからず、選択肢の数字を一つ一つ当てはめて解答を導き出す作業を時間をかけてやりました。同じに日に受験した友人にその話をしたら笑われ、「そんなことしているやつが合格するわけないよ。」と言われました(因みにその友人は不合格で私は合格しました。さて、法律科目での貯金を一気に使い果たした私は論述試験にかけるしかありませんでした。
Jan 16, 2006
コメント(0)
-
平成18年度から行政書士試験が変わります~その1~
1月14日、15日の日記は都合により削除しました。ここに再掲載いたします。 世の中不景気になると「資格ブーム」がやってくる(いや受験予備校がブームを作っているという人もいる。)。無責任に将来有望資格と行政書士をもちあげるものだから、周りの目は羨望(とまでいかないが)の眼差し、「すごいですね。事務所をお持ちですか。」となってくる。現実はトホホ・・である。先輩から「3年から5年は辛抱しないと・・・。」と言われ、何とか2年頑張ってきた。いよいよジンクスの3年目と胸躍らす今日この頃である。「開業1年目で○○万円」という類の本が何冊も出ているが「すごいな。」と読んでみると「開業新人セミナー」等の申込書がついている。「あれ、行政書士で儲かっているのでは・・・・。」 ブームのおかげか、私が開業したからか、受験生という方からのお話もいただきます。私は平成3年合格なので今と試験制度の違うのでなかなかアドバイスできないのですが、先日「今年から試験が変わるのですか。」との質問をいただいたので少し調べてみました。続きは明日
Jan 16, 2006
コメント(0)
-
まだ公布中、施行日未定の新会社法~その2~
1月10日の日記は都合により削除しました。同じ内容のものを再掲載いたします。 平成17年の第162回通常国会で成立(同年6月29日の参議院本会議で可決し、成立。)した「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(「整備法」と略してつかわれることが多い。)が同年7月26日に法律第86号、第87号として公布されています。(その1)でもお話した施行日(その法律の効力が生じる日)ですが法務省が発行している「新会社法」のパンフレット「使える・使おう会社法」には以下のように記されています。Q23 施行期日はいつですか。 会社法の施行につきましては、その公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとされています。具体的には、平成18年5月ころに施行される見通しです。 なお、いわゆる合併等対価の柔軟化に関する部分については、さらに、その1年後に施行することとされています(Q18参照)。 平成19年1月がタイムリミットですがやはり今年の五月に施行の見通しのようです。商業登記法等の通達もだされるはずです。
Jan 11, 2006
コメント(0)
-
私の中のヒーローたち~祝!伏見工業高校日本一
1月7日、全国高校ラグビーフットボール大会決勝戦で京都代表伏見工業高校が神奈川代表の桐蔭学園高校を破り、今年度の高校ラグビー日本一に輝きました(因みに我が母校の天理高校は2回戦敗退、残念)。私と伏見工業高校ラグビー部総監督山口良治先生とのつながりは私のホームページ「きょういく行政書士が行く」のカバチタレのプロジェクトXをご覧ください。上のアフィリエイトには関連商品が並んでおります。よろしくお願いいたします(これって便乗商法でしょうか。)
Jan 9, 2006
コメント(0)
-
初詣・初稽古
我が芦原会館田園調布支部は本日が初稽古。道場生の発案により近くの浅間神社までランニング、参拝の後、高台で基本稽古をした。運よく天候に恵まれ、寒い中にも清々しさが漂う初稽古だった。神社では他の少年スポーツ団体とも出くわしたが、こちらはほとんどが親子で会員なので子どもたちは誇らしげだった。ランニングで道場に戻り、手作りのお雑煮を食べ、今年1年の健康を祈った。ここでも子どもたちはおとうさん・おかあさんと一緒に稽古した後のお雑煮は格別だったようだ。
Jan 8, 2006
コメント(0)
-
まだ公布中、施行日未定の新会社法~その1~
平成17年の第162回通常国会で成立(同年6月29日の参議院本会議で可決し、成立。)した「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(「整備法」と略してつかわれることが多い。)が同年7月26日に法律第86号、第87号として公布されています。新会社法とは主にこの2つ法律を指しています。「公布」とは成立した法律等を広く国民に知らせることです。例えばその法律が成立した翌日から効力をもって「おまえは法律違反だ。何、知らない。今日国会で決まったんだ。」と言われても困ってしまいますよね。ですから法律を施行(効力をもたせる。)する前に広く国民に知らせ(公布)、国民に準備を促すのです。いくら国会で決まった法律でも不意打ちはルール違反です。この新会社法の施行日はまだ決まっていませんが今年の春を予定しているようです(4月か5月)。それまではいままでどおり商法の第2編や有限会社法等の法律が有効です。あまりマスコミで話題になっているのでもう新しい法律になったと思われている人もいるかもしれませんね。
Jan 6, 2006
コメント(0)
-
本年もよろしくお願い致します
明けましておめでとうございます。新しい年2006年は、景気回復の予兆がみられ、トリノ冬季五輪・サッカーワールドカップとスポーツのビックイベントが開催されます。明るい話題もありますがまだまだ減らない「振り込め詐欺」や「悪質商法」、多発する子どもたちを狙った事件と晴らさなければならない暗雲がたちこめています。そんな世情の中、三年目に入った我が事務所も本年より「藤田教育行政書士事務所」に改称し、家庭・教育相談、新会社法に関する相談、消費者問題を中心に少しでも皆様のお役にたてるよう精進してまいります。今年もよろしくお願いいたします。
Jan 5, 2006
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-
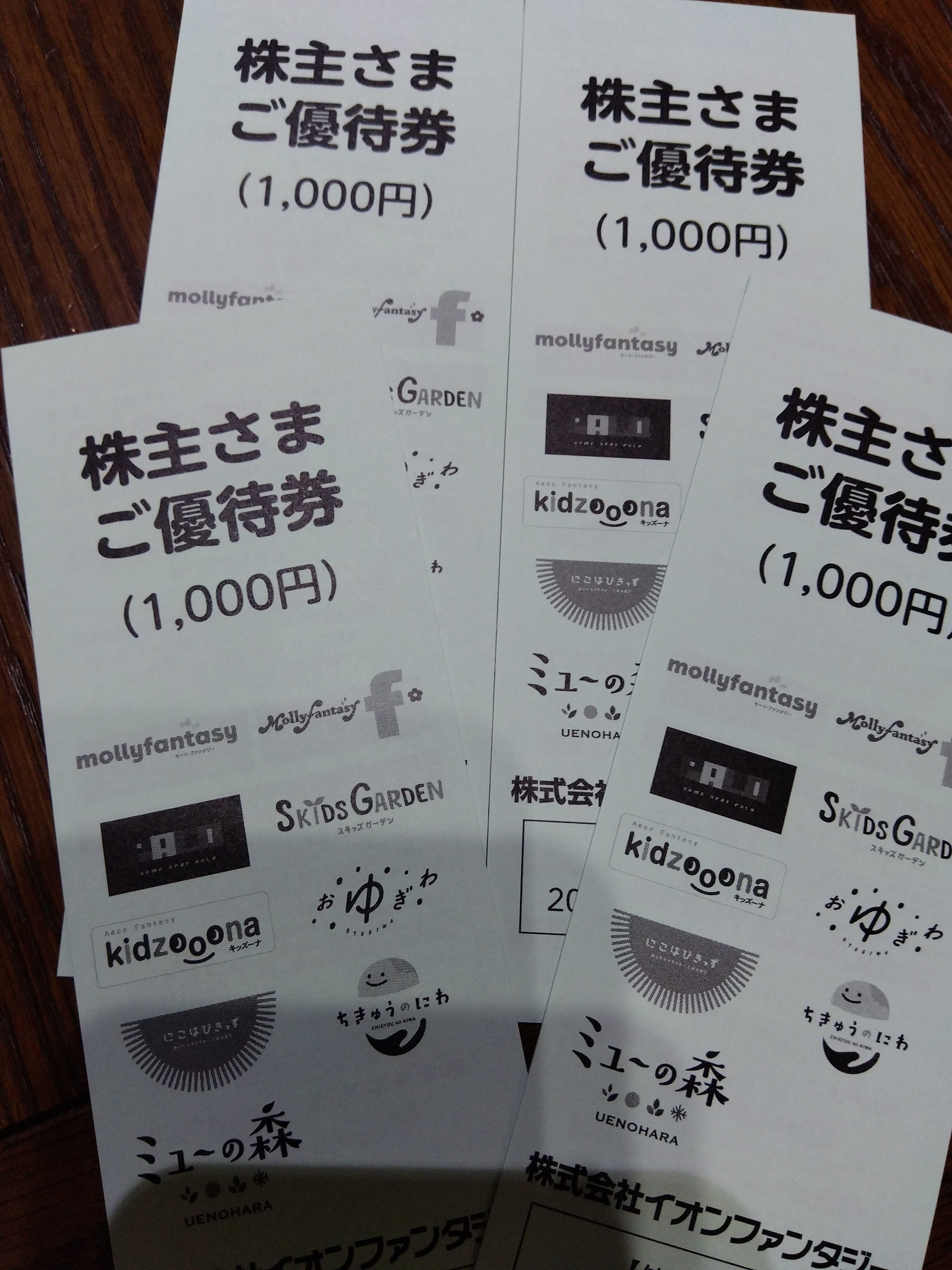
- 株主優待コレクション
- イオンファンタジーから株主優待が届…
- (2025-11-17 00:00:06)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…
- (2025-11-17 06:41:29)
-
-
-
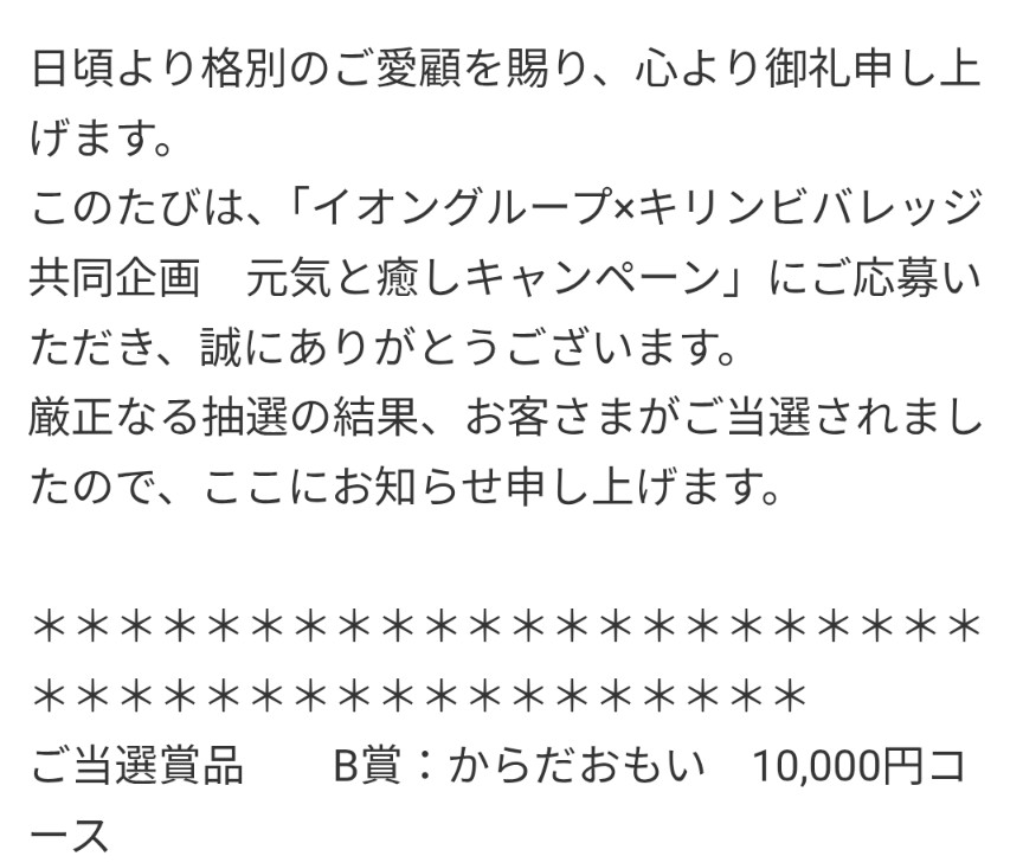
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-







