2007年07月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
マーボー情報が大人気になってきまいした。結構いいとこついていますよ!
平成19年7月29日【先週の概況】7月16日に北越沖大地震が発生し、先週は米国のサブプライム問題の揺り戻しで市場に大きな激震が発生した。サブプライム問題が表面化した当初は、小さな経済的現象で米市場では殆ど問題視されていなかった。6月の住宅関連指標の1つである中古住宅販売件数は前月比3.8%減と低迷している。金融機関のサブプライムローンも含めた住宅ローンに対する貸し渋りが常態化しており、住宅建築が増加することはあり得ない。既融資先の延滞・差し押さえが増加しているので、金融機関の損失が膨らんでいる。さらに、そのローンを束ねた住宅ローン債券に投資している投資家(ヘッジフアンド含む)が多大の損失を抱えており、国債等安全資産に資金を移しており、長期金利が4.7%程度に急低下している。所謂、信用リスクの回避である。大規模なM&A用資金も調達できなくなりつつある。実際、起債やローン実行の延期・中止が顕在化している。クライスラー、クリアチャネル、TXU等の大型案件が白紙になれば、影響は計り知れない。ニューズ社のDJ買収も1部株主の反対で雲行きが怪しくなっている。NYKダウは14,000$台まで一気に駆け上がってきたが、13,200$台まで急落して一週間を終えた。米大統領等政府要人は「経済のフアンダメンタルズ」は悪くないと言及しているが・・・。FRB発表の「ベージュブック」では6月~7月上旬について米景気拡大が続いているとの見解であり、4-6月のGDPは3.4%に回復している。FRBは、景気の減速とインフレ警戒の姿勢を崩していないが、サブプライムローン問題の影響を意識して金融政策を見直す必要がでてきている。4-6月の企業の業績発表は、市場心理に影響していない。強いて上げれば米アップルの好業績発表で逆行高が目立った程度である。GDPでは企業部門の好調さに反し、GDPの7割を占める消費が弱含みであることを注視すべきである。FRBは政策金利の引き下げ、流動性の供給を考えてもいいのではないか?さて、日本でも米国の株価調整とそれに伴う円高で、株価が大幅調整と同時に長期金利が急低下(週末で1.78%)した。参議院選挙での与党苦戦の予想も多少あったと思われるが・・・。企業業績発表の反響は吹き飛んだ。日経平均は24日以外総崩れの週であった。23日は筆者予想通り、先々週末の米国株安と円高で日経平均は190円強下げた。24日は、金融株主導で買われたが上値が重かった。この日、チャート分析で日経平均の5日移動平均が25日移動平均を下回った。「デッドクロス」で短期調整のシグナルである。25日は米国株不安定さと円高で下げた。26日は国内外の不透明さで、利益確定に押され下げた。そして、27日は月曜日~木曜日の下げの要因が集約された感じや外部要因に伴うリスクマネーの収縮の懸念が席巻し、幅広い業種に売りが売りを呼ぶ展開となり、全銘柄が下げた。先物の大口の裁定解消売りが下げ幅を大きくした。まさに「ブラックフライデー」の様相である。金融政策に影響する6月のCPI(0.1%下落・・5カ月連続)等全く度外視された格好。27日の「騰落レシオ」は70%を割り、反転の兆しのシグナルであるが・・・。【今週の予想】今週は参議院選挙の結果で始まる週である。与党大敗と先週の相場地合いを引きずり、週初は株価は調整するであろう。株価が安定するには選挙の後の政局流動化懸念と米国のサブプライム問題がこれ以上拡大せずに収束するのが前提である。米経済が安定に向かえば、「円借り取引」、個人の外債投資に伴う円売り需要で円安になり、輸出関連銘柄が持ち直して相場の底上げが期待できるが・・・。米国株は先週の混乱を引きずり、個別の材料に神経質な地合いになるであろう。サブプライムローン問題でフアンドが資金繰り難に陥り、今まで相場を牽引してきたM&Aが下火になると思われる。住宅問題が個人消費に悪影響する事態が懸念されており、経済統計に注目が集まる。株高による「資産効果」も剥げ落ちており、また、原油価格が77$/1バレルとひたひたと上昇しており、このあたりも個人消費減速をもたらす。今週発表になる「ISM製造業指数」と「雇用統計」に注目。4-6月の企業業績は個別銘柄には影響するが、相場全体に波及しないと考える。さて、日本の相場に戻ろう。参議院選挙結果の悪影響、円高、米国株に不透明感が漂う中で、好決算が予想される4-6月の業績と個別企業のM&Aと騰落レシオの指標が注目材料である。先ずは、円の動向であるが、米景気と株式相場に多大の影響を受ける。前述した米国の経済指標が発表になり米景気の趨勢が解る。各企業の社内レートは概ね115円に想定しているがまだ余裕がある。しかし、これ以上円高になると08年3月期の業績予想に悪影響し、株価の重しになる。収益のかなりの部分が円安に依存しているのが現状。もともと弱い内需関連株も引きずられるだろう。個人消費が伸び悩んでいるのも懸念材料。8月の日銀政策決定会合での政策金利据え置きの公算が大きくなったと考える。先週、国内のM&Aが発表となった。・ 伊勢丹と三越の資本提携。三越株急騰。・ プロミスが三洋信販にTOB。業界の収益悪化で必然の成り行き。業績悪化企業が、自社再建が不可能との判断がある。小売りでは、西友ストアーが3期連続赤字。ウオルマート傘下であるが、小売り再編の焦点になってくる。フランスのカルフール早期撤退でみた通り、外資小売りの日本進出は旨く行かないケースが多い。日米とも景気後退の懸念が強くなっている。以上
2007年07月30日
コメント(0)
-
マーボーは暑さに負けずがんばりました。
平成19年7月22日【先週の概要】7月16日(祝日)に新潟中越沖で大地震が発生した。最近、日本のあちこちで地震が発生している。お亡くなりになった方には心からご冥福を祈り、被災者の方々には早く立ち直られることを切に願います。この震災で産業界も甚大な被害を被った。先ず、東京電力の原発の1部火災、放射能に汚染された水の流出と大気中への微量の放射性物質の漏れで、当局から操業停止処分の指示を受けた。地震の規模が大きかったが、原発設備の地震に対する脆弱性が露呈された。これから、東電は発電量の代替設備による稼働等コストの増大に直面し、08年3月期の業績に多大な影響を及ぼすであろう。もう1つ、自動車産業も生産活動に大きな影響をきたした。多くの自動車会社が機材を発注している企業の操業開始見通しが立たなく、自動車生産を停止せざるを得ない事態になった。精密バネ大手のアドバネクス、エンジン関連部品製造のリケンとその子会社は操業再開の見通しが立っていない。自動車各社の年間生産計画に影響するか否か現状では不透明である。必然的に他の自動車関連部品生産会社も操業をストップしている状況。他に、被害を受けた企業として産業用ポンプ製造のウオシントン、三洋電機の半導体製造工場がある。リスクの分散と生産集中の効率化のどちらが重要か問われている。地震が発生した17日の株式市場では、地震関連で東京電力が下げ、自動車向けピストリング生産のリケンが4%強下落、トヨタ、ホンダも売られた。また、保険金支払いが増える保険株も軟調であった。逆に、復興需要があるとして、福田組等地場中堅ゼネコンが上昇した。日経平均は当日小幅安の▼21.68円で、04年10月発生した中越地震の時より影響は限定的であった。18日の日経平均は大きく201円強下げたが、地震の影響は限定的で、東京電力、リケンが下げ止まらない程度。市場が注視したのは、米国の株式相場の影響である。NYKダウは一時14,000ドル台をつけたが、現地取引終了後に発表された米インテルの4-6月の決算内容である。同社の利益率が悪化した。インテルへの期待感は失望に変わり、ハイテク株全体に影響を来すとの懸念が市場を席巻した。前にも述べた通り、ハイテク株の多いNASDAQ市場の動向を注視すべき時である。半導体のBBレシオ(受注対出荷の比率)の推移が重要である。米インテルが設備投資計画を引き下げた影響でアドテスト等日本の半導体製造装置関連が売られた。また、米サブプライムローン問題が日本にも飛び火し、野村証券が評価損をかかえている可能性を指摘され売られた。ただ、造船・鉄鋼株は逆行高であった。造船・海運・鉄鋼・原子力・航空機 関連銘柄は息の長い銘柄で、トレンドは調整があっても上昇基調を保つであろう。それと商社も見逃せない。海外資源への飽くなき投資で収益拡大の期待を抱かせる。翌日19日の日経平均は反発した。日本市場は米インテルショックがNYKダウ急落に繋がると懸念していたが、53ドル強の下げに収まったため安心感が台頭。昨日下げたハイテク関連銘柄が上昇。地震関連のトヨタ、信越化学も立ち直り上昇。消費者金融株が急伸した。プロミスと三洋信販の経営統合交渉に投資家は飛びつき、同業他社株に思惑買いが広がった。過払い金の返還に5%の利子を付ける判決で下げていた銘柄群であり、この業界はまだ再編がある。消費者金融業界は業績の下押しが確実で、経営環境も悪化の一途である。20日の市場で、地震関連の福田組の株価は急落した。一過性の話題に飛びつく投資家の存在が気になる。インサイダー取引で村上被告に東京地裁は厳しい判決を下した。M&Aが下火になる可能性があり、株価底上げのエネルギー源は乏しくなる。NYKダウは19日に終値で14,000ドル台を付けたが、20日には150ドル弱下落した。この日の下げの要因は2つ。キャタピラーの純利益が21%の大幅減、背景には米国内の住宅市場低迷が根幹にある。2つ目はサブプライム問題で、関連金融商品での損失を被る懸念がある金融株に売りが出たこと。日米とも、企業業績には目を離せない。【今週の予想】今週の株式相場は先週末のNYKダウ大幅反落の影響を受けて、週初は軟調な展開になるであろう。また、参議院議員選挙の与党過半数割れとの報道もあり、与党の過半数割れを市場は織り込みつつあるが、政局が不安定となり構造改革路線が先々不透明さを増した場合少なからず景気に影響を来す可能性がある。政治情勢に敏感な外国人投資家が売り姿勢に転じる可能性は否定できない。中越沖地震で、東京電力は他の電力会社からの供給や火力発電所の稼働増で供給に目途がついたものの2000億円のコスト増が見込まれている。予想連結経常利益の半分に相当し、今期は大幅減益が避けられない。自動車産業も本格生産が遅れれば今期の減益要因となる。一方、今週は企業の第一四半期決算の発表がピークを迎えるが、全体の08年3月期の予想利益は慎重な数字になると思われる。この様な要因で、今週の株式相場は上値の重い展開になると考える。こういう展開になると、目先明るい個別株を選別する傾向が強まって来る。・ 地震による保険金支払いが増加する生損保は売り材料。・ プロミスと三洋信販の経営統合で、消費者金融業界の再編期待。・ ホンダ、光発電に本格参入や米にジェットエンジン工場新設、中国向け専用車10年に発売等国内外での新規産業への積極展開。・ 地震特需関連業界。建設、建機業界等買い。・ 原油高・円安で青息吐息の製紙業界に再編期待。・ 日鉱金属 レアメタル9種類再利用100億円で大型設備建設。環境関連銘柄として要注目。・ 東レが汚れにくい水処理膜開発。海外での飛躍的需要拡大期待。研究開発力があり、市場開拓に積極的。・ 富士通、生体認証装置を米国で大量受注した。 等米国株式相場であるが、個別材料に一喜一憂する展開になりそうである。先週、米キャタピラーの利益率悪化でNYKダウは大きく下げた。今週もエクソンモービル、アップル等決算発表が相次ぐ。それと、サブプライムローン問題がまだ燻り、それが蒸し返されると、NYKダウは金融関連株を中心に大きく調整するであろう。27日に4-6月のGDP速報値が発表になる。基調的に1-3月の悪化を盛り返し、3%台であろうと予想されている。巡航速度の景気拡大を示すことになる。それと住宅関連指標も今週発表になる。何れも株価に大きく影響する。長期金利は日米とも低下しており、両国の株式相場に影響はないし金利差での円/ドル相場もおおきな変動は無いと見る。ただ、日本のCPIが発表されるが、大きく改善すれば、日銀の利上げ観測から、長期金利上昇・円の上昇も考えられる。CPIはマイナス圏から脱しないとみているが。今週は波乱の週となる。以上
2007年07月22日
コメント(0)
-
マーボーの経済指標 今月は絶対見逃さない!
平成19年7月16日【先週の概要】7月12日に参議院議員選挙が公示されて、7月29日投票日まで各候補者の戦いが始まる。この選挙の結果次第では、経済や景況感に多大な影響がある。市場ではこれから様子見気分が強まるであろう。11日と12日に日銀政策決定会合が開催され、政策金利は据え置きとされた。市場の予想通りであった。日銀は従前の「景気は今後も息の長い拡大を続ける」との見解を踏襲し、国内企業物価に関しては、「原油等国際商品価格の上昇を背景に、従来の見通しより上ぶれる」との見解である。ここで、消費者物価に言及がないのが疑問として残る。ミクロではガソリンが140円/1リットルに上昇していることや中国産食品の価格上昇(中国内需要増と安全チェック強化が主因)等消費者物価指数のコア指数ではないが、個々の商品の価格は上昇している。今後、総合消費者物価指数(コア指数に食料品、石油の数値を加算)も注視するべきだと筆者は考えている。8~9月に利上げの蓋然性は高いが、参議院選挙の結果はともかく、4-6月のGDPや米国経済の帰趨を注意深く見守る必要がある。5月の機械受注指標が前月比5.9%増加し、2カ月連続の増加である。9カ月程度先の設備投資の動向を示す指標だけに政策金利利上げに援軍であろう。一方、街角景気指数は3カ月連続悪化しており、6月の現状判断指数が46.0にとどまった。マクロの景況感がミクロへ広がっていないのが原因であろう。もう1つ気になる事象がある。日銀による「貸出・資金吸収動向」によると、民間銀行の貸し出しは前年同月比0.7%増えている。かたや、07年上半期の倒産件数は5,394件と前年同期比16.6%増えた。金融機関が与信管理を厳しくし、資金繰りが悪化した中小・零細企業が増えていることを示す。連鎖倒産が増幅している。ミクロの景気は悪化しつつあるのではないか。さて、株価については波乱の一週間であった。NYKダウは10日に大きく下げ、12日に283ドルと大きく上げた。日本の株価はそれに影響を受け、日経平均は11日に大幅下落し13日は大きく上げた。10日は、サブプライムローンの再燃からそれに関連する資産担保証券の格付けを格下げしなかった格付け会社ムーデイス社の株価が大幅下落し、S&P等大手格付け会社の株価が軒並み下げたことが相場の地合いを悪くした。その責任に矛先を向けた格好である。その余波が銀行株にも向かい金融株は総崩れした。11日の日経平均はNYKダウの下落と円高の影響で幅広い売りが先行し、先物の売りで下落幅を拡大した。日米とも「質への逃避」で国債に資金がシフトし、長期金利が急落(債券価格は上昇)した。一方、12日のNYKダウは283ドルと急騰した。要因は2つある。米主要小売り企業の6月売上高が2カ月連続して増加したこと。ウオルマートは2.4%増であった。ガソリン高とサブプライム問題の消費に対する影響が薄まった。2つ目は英豪資源大手リオ・テイントがカナダアルミ大手のアルキャン買収が決まったこと。TOBを仕掛けていたアルコア株も次のM&A標的になるとの連想買いで上昇した。M&Aが相場上昇力の源である。週末もNYKダウは連騰した。指標である米小売売上高6月が前月比0.9%減少(前年同月比3.8%増)であったにも拘わらず、長期金利低下、ドル買い戻し、GEの好決算、ミシガン大学の「消費者態度指数」が市場予想を上回ったことで堅調な展開であった。来週の日本の株価にどう影響するか。日本の個別銘柄では・ 米ボーイングが新中型機787を初公開。機体製造の三菱重工、東レ、川崎重工、ジャムコの需要拡大見込める。(長期的買い推奨)・ ブルドッグソースが買収防衛策発動で今期赤字の可能性。株価は値が付かない。・ ビックカメラ59%増益。販促策見直しが要因。・ キリン純利益、6月中間期21%減。ビール系出荷上期最低。趨勢的に市場縮小傾向。・ 原発関連で東芝、エネザーブ、宇徳運輸が急騰。木村加工は12連騰の後急落。その後原発関連売られる。・ フジテックエレベーター強度不足指摘で軟調。関連のJFE商HDも同様。行政処分の小林洋行も売られる。不祥事・事故の銘柄は容赦なく売られる。・ 消費者金融、グレイゾーン金利の返還問題で収益低迷。その期間利息も返還義務ありと最高裁判断。消費者金融業界は底なしの低迷を余儀なくされている。【今週の予想】今週は月曜日が祝日であり、市場開催日は4日しかない。29日の参議院選挙と第一四半期の企業業績発表前で投資家は様子見に徹するであろう。国内での重要な経済指標の発表もない。そうなると、外部環境に左右される相場展開になる。円相場、金利相場、米国の株式相場動向、原油相場等で相場展開が違ってくる。先ずは円相場であるが、週末の米国市場で、経済指標が市場予想を下回ったため円買いが優勢となり、121円85-95/ドルで引けている。日本市場の週末相場(122.38-41)より円高である。この円高傾向を意識し、火曜日の市場で長期金利上昇をもたらし、海外輸出関連銘柄が軟調となるリスクが顕在化するであろう。また、金利敏感銘柄(商社・不動産等)が揺さぶられるであろう。円売り取引や個人投資家の円売りで、円安に引き戻される可能性が濃厚である。もう1つの要因として米国の6月「住宅着工件数」が商務省から発表される。前月比横這いとの市場予想を下回れば、円買いが進む可能性があるが、一時的なものに留まるであろう。121円半ばから123円半ばでの推移であろう。長期金利は今までと同様に米国の相場に引きずられる展開になる。米国の「住宅着工件数」とともにCPI発表が予定されている。市場予想を下回ると米国景気後退懸念から米国長期金利が低下し、日本の長期金利も低下する。1.97%~1.94%と予想する。先週の米株式相場はサブプライムローンで一時調整したが、経済全体に波及することはないとの見方から持ち直した。今週は重要経済指標をこなしながら、高値のもみ合いになりNYKダウは一時的に14,000ドル付ける可能性がある。節目を抜けると日本の株価に好影響をもたらし、日経平均は18,000円を挟んだ膠着相場から抜けだし、18,500円を目指す展開になると思われる。石油相場が米国WTIが74ドル近くにひたひたと上昇傾向にある。78ドル/1バーレルの市場最高値を超えると、今までのシナリオが総崩れになり、日本の株価にも下圧力がかかる。個別銘柄を見ると・ エレベーター強度不足問題のフジテックとJFE商HDが引き続き売られる。・ ハイテク株の在庫調整が順調に進みつつあり物色の対象になってくる。今後NYKのナスダック相場を注視する必要あり。・ 任天堂は50,000円を突破しており、高値警戒感がでてくる可能性あり。・ 沖電気は、携帯電話での目による本人確認技術を開発し技術開発力で買われる。・ 原発、造船と航空機関連株は買い一巡により見送られる。長期的テーマであるため、目先は軟調か。・ ビール業界は市場縮小により、業績面での警戒感が漂う。・ 日産、カーナビ連動事故防止技術開発。今後の業績回復の一助となる。以上注意!2009年1月から株券のペーパーレス化が予定されている。タンス株券等お持ちの方、要注意です。
2007年07月16日
コメント(0)
-
マーボーの経済指標 前回ずばり的中 今回も慎重に記事にしました。
平成19年7月8日【先週の概況】4―6月の日銀短観が発表され、焦点である大企業製造業の景況感は横這いの23であった。これは市場の予想通りであり、設備投資も11。2%増加である。米国景気の減速、長期金利の上昇、原油上昇が景気に及ぼす影響等を横目に見ながら、日本経済は緩やかな景気拡大を印象付けた。大企業の業種別景況感を見ると、輸出関連業種の改善が際立っている。米国景気が減速しているが、新興国や資源国向けの輸出が拡大している。ただ、自動車は国内向けが不振で輸出にも陰りが見える。大企業非製造業の景況感も横這いである。運輸が世界的な物流拡大で大きく改善した。一方、個人消費関連は悪化している。また、中小企業については改善が足踏みしている。要因としては、大企業の景況感が横這いに留まり中小企業に裾野が広がっていないことを証明している。一方、ニッケル、タングステン等の非鉄金属や原油の高騰で企業収益を圧迫している。この資源高を川上から川下に転化できているのは極1部であり、日本の景気にとってリスク要因である。価格決定力が弱いのではないか、あるいは需要の減少を恐れているのが透けてみえる。消費関連企業の景況感も改善されない。企業のコスト削減策で収益を維持しているのが実態であろう。CPIが水面下にあるのが証明された。今後、この資源高騰が川下に浸透していけばCPIの改善にも繋がる。なお、設備投資の動向を示す「機械受注統計」の数値と日銀短観に於ける設備投資DIの差異は何を意味するのであろうか疑問が残る。さて、今回の日銀短観の結果を見て政策金利の利上げはどうなるか。市場関係者は7月見送り、8-9月利上げと予想しているが、資源の高騰を川下に転化できていない以上、利上げは年末とみる。企業のコスト削減努力で収益を維持している現状では、金利コスト上昇は企業収益に大きくマイナス作用となり、設備投資に牽引されている緩やかな景気拡大に水をさす結果になる。先々の景気過熱感を払拭するための利上げはまだ早いと筆者は考えている。さて、一週間の日経平均は薄商いの中で堅調であったが、週末に長期金利上昇懸念に押されて下げた。地合いは弱い。月末近くの参議院選挙結果と4-6月の企業第一四半期業績開示を控えて、市場は様子見気分で目先筋の短期売買が市場の主流が原因であろう。一方、NYKダウは堅調であった。長期金利の上昇、原油価格の急騰にも拘わらずM&Aが株価の上昇を支えていたのが実態である。投資フアンドカーライルが介護大手を、カナダの通信メデイアBCE、ブラックストーンのヒルトンホテル買収等々、枚挙にいとまがない。サブプライムローン問題や住宅市場の減速等をM&Aが相殺してなお余りあるのが現状である。経済統計(サプライマネジメント協会製造業景気指数の上昇、週末の雇用統計の予想を上回る雇用増)が株価上昇にとって相乗効果であった。米国M&Aに陰りが見えると言われるが、当面株価上昇の主因であり続けるであろう。日本のファーストステアリングが米国バーニーに買収提案したが、競合相手もおり、成立するか不透明感があり株価が下げた。M&Aに対する日米市場の評価が根本的に違う。【今週の予想】今週の株式相場も先週同様に薄商いの中上昇と下落拮抗し、日経平均が18,100円~18,200円程度で推移しそうである。市場は直近の材料難もあり、参議院選挙の結果と4-6月の企業業績四半期決算を見極めたいとして、様子見を継続しそうである。赤城農相の家賃問題が発覚し、ますます自民党の劣勢が顕在化しつつある。当落予想報道で、自民党の惨敗予想数字が出てくるとその時点で相場軟調になる可能性がある。今週のテーマは9日発表の「機械受注統計」と11,12日に開催される日銀の政策決定会合である。前者は材料視されないとみる。政策決定会合の議事録で、9人の委員の一部で利上げ提案があると8月利上げが現実味を帯びてくる。市場はある程度8月以降の利上げを織り込んでいるので、目先の大きな波乱は無いと思う。市場の注目点はむしろ米長期金利の動向であろう。米長期金利が5.3%を超えると、日本の長期金利にも波及し、株式相場にも影響を与えるであろう。外国為替であるが、日米の金利差を利用した円キャリー取引と個人投資家の外債投資に伴うドル買いで、円は上昇しにくくなっている。また、引き続きユーロが対円で最高値を更新し続けている。欧州への輸出依存度が高い企業には恩恵であろう。因みに、英国は先週政策金利を0.25%引き上げた。一方、米国では主要企業の4-6月の四半期決算が最大の注目点である。調査機関によると、企業の増益率は4%台に鈍化した模様である。しかし、先週発表の雇用統計で4-6月の非農業部門を除く雇用者数平均が148,000人増と堅調さを保ち、景気も上向いている。株式相場はサブプライムローン債権に拘わるヘッジフアンドの危機も乗り越えつつあるし、景気の上向き景気をおりこみながら、株価上昇基調は続くとみる。それを後押しするのがM&Aである。反対に、原油相場が72.81ドル/1バレルまで上昇しているが、リスク要因として持ち上がる懸念がある。ガソリン需要期にあること、産油国であるナイジュエリア治安悪化が主因である。貿易統計、小売り売上高等の経済指標も注目点である。今週の数値予想であるが、日経平均は18,200円弱、NYKダウは13,650ドル台、円は123円後半/ドル、日本の長期金利は1.9%前半と予想する。ところで、日本では奇数年の7月は株高のジンクスがあること皆さんは知っていますか?月足チャートの終値が始値を上回る「陽線」が、過去20年間でその確率が9割という高さであることです。今年は、参議院選挙でどうかな!以上
2007年07月10日
コメント(0)
-
0学相場分析追記
今月の相場注意日7月14日と17日 ここの日はどちらかにかなりの変化がある兆し注意銘柄の詳細追記楽天 それぞれの役職との相性がかなり来年から悪化の兆し ソフトバンク 宣伝効果が証してか今現在かなり高いがしかしながら 役職構成などからみるとかなり出費が多く出すぎる相性とでていて 果たして元に戻せるかが問題である。ヤフー J.ヤン効果がいまいちに見受けられる運命数からみても いまは本当に人をひきつける内容を提案すればかなりの効果はかわるが
2007年07月05日
コメント(2)
-
開始 0学ファイナンス銘柄分析!
注意銘柄楽天 ソフトバンク上昇見込み銘柄(2年先見込みで)製薬会社 (具体的には次回へ)
2007年07月02日
コメント(0)
-
マーボーも夏情報になっています。 必見!
平成19年7月1日【先週の概要】会期延長した通常国会も公務員法、社会保険庁問題の各法案を拙速は否めないが成立させ閉幕した。7月29日の参議院選挙に向け各党は選挙運動を展開するが、「年金問題」等で低い支持率の安部政権は負ける可能性が強い。そうなると政局不透明感から株価にも悪影響を及ぼし、特に外国人投資家は一時的に買いを控えると予想される。7月末~8月初にかけ選挙相場になる。さて、日経平均とNYKダウは軟調な展開であった。日経平均は後半持ち直して18,000円台を確保したが、薄商いの中相場の地合いは弱い。長期金利は28日に上げた以外は低下を続け、一時2%弱を付けた金利は1.865%まで下げた。この金利低下にも好反応を示していない。「質への逃避」と言え、リスク回避の投資家が多かったのかも知れない。一方、対ドルの円相場は27日に若干上昇したが、週末には123円ミドルまで円安に戻った。27日の日経平均大幅安の要因として、円高(たかが52銭円高)が市場心理に影響した。市場は円安が継続しなければ好材料にしない傾向がある。もっとも、当日は米国株安も要因であり、引けにかけ大口の株価指数の仕掛け的売りが下げ幅を拡大した感は否めない。米景気、金利、円相場が株式相場の方向を左右する3大要素であろう。25日の日経平均株下落の要因は前々週末の米国NYKダウの大幅下落が原因で利益確定売りを誘発した。直近の日経平均は長期金利の上下に影響されていない。今後、相場の地合いを悪くする要因として、70ドル台まで上昇した原油相場にも注視する必要がある。ところで、米国NYKの株式相場であるが、週間を通じて終値は上下幅の小さい相場であり大きく下落する日は無かった。しかし、相場の注目点は、サブプライムローンとその投資に失敗したヘッジフアンドを傘下に持つベアースターンズである。これは、「氷山の一角」ではないかと憶測する向きもあり、金融株の売りを誘っている。この問題が世界に拡散しないか懸念されるところである。ヘッジフアンドについては、運用リスクの他にも、金利上昇による資金調達が難しくなることや米当局の課税強化等外的圧力がある。資金流動性が細り大型のM&AやLBOが少なくなることが予想される。M&Aが今までの株高を牽引してきた事を考慮すると、先々株価の調整局面になり日本の株価に影響大である。日本でも証券委員会が、9月から全フアンド検査対象とする。日本の話題に移ろう。ほぼ、上場企業の株主総会は終焉した。物言う株主が以前より格段と増加し、特にサイレントマジョリテイーと言われた個人株主の存在感が目立った。不祥事のあった企業は陳謝し、企業防衛策も採択され、M&A対象企業は買収提案が否決された。今後、個別銘柄の株価は4-6月の四半期決算の状況に左右されることになる。【今週の予想】7月2日に「日銀短観」が発表される。ポイントの「大企業製造業業況判断指数」について、市場は前回比横這いと見ている。先週発表の鉱工業生産指数3カ月連続低下し前月比マイナス0.4%であったこと、5月のCPIは4カ月連続0.1%下落、完全失業率が3.8%と横這いであったこと、消費支出が前年同月比0.4%増加し5カ月連続上昇した事等強弱交錯している現状から筆者も横這いとみる。大きく上ぶれると、長期金利の上昇を誘発し、政策金利も8月利上げというシナリオが想定される。市場予想より弱い数字が出るようだと、利上げ延期も想定しうるし長期金利に低下圧力がかかる。短観の結果次第であるが、長期金利は、週間を通して1.8%~1.9%で推移すると見る。政府高官から、相場に影響する発言が出なければという前提であるが。円相場は例え長期金利が上昇しても、円高に振れないと見る。5日にECB(欧州中央銀行)、BOE(英中銀)の政策決定会合が開催され、景気過熱警戒感から政策金利利上げが予想できる。米長期金利も5.2%台で高止まりしている以上、日本との金利差から「円キャリー取引」が継続し、ボーナス時期でもあり個人の外債取引が旺盛となることから、円安傾向が続くと見る。最近、サムライ債(外国企業による円建て債)の発行が増加傾向にあることも円安に拍車をかける可能性がある。今週の円相場は122円~125円になると予想する。最近の株式相場は長期金利には反応薄で、円安・米国景気と同国長期金利に影響される。原油相場がひたひたと上昇し(70ドル/1バレル)、次に注視すべき要因である。米国の株価は値動きが荒い展開になりそうである。FOMCでは政策金利が据え置かれたが、景気判断は巡航速度である旨。ただし、インフレ懸念を引き続き堅持している。株価への懸念材料は2つある。1つは、原油価格の上昇である(インフレ懸念)。2つ目はベアースターンズ問題である。破綻の危機にあるヘッジフアンドが2社あるという。M&Aの1手法であるLBO(レバレッジバイアウト)の中止が相次いでおり、流動性の減少が予想される。FOMCは各機関にサブプライムローンについて緩和処置を要請している。何れにしても米国の株価は不安定であろう。米雇用統計の結果も要注意である。予想される米国株に影響される日本の株価であるが、内的要因としては「日銀短観」である。前述したが、大企業製造業業況判断指数がポイントである。しかし、筆者は大企業非製造業の判断指数も注視すべきだと考える。景気拡大の裾野の広がり、特に設備投資が顕著になりつつあるからである。もう1つ大企業の経常利益計画も注目点である。円安により堅調な数値を見込める。4-6月の四半期決算の先行指標とみることが出来る。好業績銘柄に物色がひろがるか?ただし、市場の予想より強い数値が出ると、政策金利上げの早期化を招く可能性がある。気がかりは、やはり米国株の動向と参議院選挙の行方である。自民党の惨敗との声もあり、政局流動化による外国人投資家の売りが表面化する。今週の日経平均は18,000円を挟んだ膠着相場と予想する。(個別業種では、原子力関連、商社、造船が業績拡大による推奨業種である)以上
2007年07月02日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 千葉市動物公園 じっと君のご飯タイ…
- (2025-11-19 00:00:07)
-
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- 終末ツーリング 第7話「つくば」
- (2025-11-19 00:07:47)
-
-
-
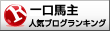
- 一口馬主について
- 所有馬近況更新(25.11.18)クールブ…
- (2025-11-18 20:52:43)
-







