2007年06月の記事
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-

昨日は三軒茶屋でイベント
今現在私は日本橋兜町と三軒茶屋で鑑定拠点を置いているが7月は伊東での鑑定も入っている。ただ、今後は兜町では株や相場の査定鑑定専門で 三軒茶屋では人生恋愛鑑定を専門でお話ができると良いと思っています。7月から金融部門ではメール情報鑑定でたくさんいい情報を提案していきたいと思います。対面鑑定は30分5000円 60分10,000円 これはどこも共通です0学占いにご興味があるかたどんどん連絡ください連絡先は 7月から公開されます。コメントいただいた方は先行予約として10分鑑定サービスをさせていただきます。これは三軒茶屋のブースです とても落ち着いた空間です。よろしくお願いいたします。
2007年06月29日
コメント(0)
-
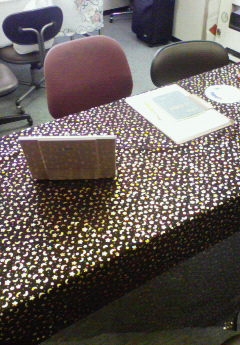
1日鑑定
今日はある大手生命保険会社で 1日鑑定イベントをしてきました。今日は幸せな方が多かったように感じます。みなさんが幸せになりますように
2007年06月27日
コメント(0)
-
今回こだわりを持ってつづりました。マーボーの経済誌 読みがい有り!
平成19年6月24日【先週の概要】先週の日経平均は週末に下げたが14日から6日連騰、18,000円台を達成した。円安進行以外日本独自の材料難の中、薄商い状況下での上昇であった。市場の矛先は個別銘柄物色に終始した。一方、米国のNYKダウは週間を通じて調整局面であった。今までの騰勢のスピード調整であろうか。それに、20日の株価調整は長期金利上昇に反応した相場であったが、週末の調整は、証券大手ベアースターンズ傘下のヘッジフアンドがサブプライム絡みの運用に失敗し資金難に陥っていることが嫌気された。サブプライムローン問題は収束観測がでていただけに不意を付かれた格好。損失規模等全容が見えないだけに、他のフアンドや金融機関に連鎖しないか等憶測を呼んだ。リスク回避する心理が急速に広がった。これに反し、大手買収フアンドブラックストーンが上場し値を上げた。今、米国当局は石油メジャーと共に、買収フアンドに対する課税強化を検討している。これを忌避する為の上場と憶測を呼んでいる。ヘッジフアンド、買収フアンドとも外部環境等変化に遭遇しつつある。一方、原油相場もじわりと上昇しつつあり、69ドル/1バレルにまで上昇した。米国のガソリン消費が膨らむシーズン到来とナイジェリアのスト、イランやパレスチナ問題での地政学リスクが主因である。労働単位コスト増勢も含めインフレ要因となる。FRBも注視するところである。一方、円安も顕著であり124円台/ドルまで下げた。円の独歩安であり、資源国通貨に対しても安値を更新続けている。日本と他国の金利差を求めた「円キャリー取引」と「日本の個人の外国投資信託購入」に伴う円売りが主因である。景気は日米とも、ほぼ堅調であると断言できる。緩やかな景気拡大基調を堅持している。日本政府発表の5月月例経済報告では消費上方修正・生産下方修正されたが、個別企業の投資・生産活動を見渡す限り、生産は弱含みと思えない。7月上旬の日銀短観次第で、ある程度状況把握ができると考える。個別に見ると・ 川崎重工業が、ボーイング新型航空機用に機体新工場建築(200億円投資)、中国で最大級造船所構築(600億円)予定。三菱重工業が国産ジェット機開発でボーイングと提携。また、同社は機体コスト減の材料を東レと新技術開発。航空機産業は業容拡大が見込まれる。両社株は連日高値を維持。・ 三菱商事が豪で鉄鉱石開発に3000億円投資。5商社で輸入の50%権益確保。・ 日新製鋼が自動車用鋼管製造用にインドで合弁加工事業に参入。・ 松下電器がプラズマパネル生産能力倍増。日本ビクターをケンウッドに売却する方向がようやく決まる。・ コマツ、日立建機が中国で建機リース会社設立。新興国での需要拡大に対応。・ 村田製作所が米電源事業会社を100億円で買収。・ 石川島播磨重工業が拠点を3箇所に拡大。ボーイング用GE向け好調で。・ 伊藤忠、インドネシアでLPG元売りの為、輸入基地建築(360億円投資)。・ 半導体DRAM価格下げ止まりで、エルピーダ、東エレク、アドテスト株価上昇。NAND型製造の東芝も株価上昇。半導体は一般的にシリコンサイクルと言われる好不調の波が周期的に訪れるので、これから好調になると考えていいのではないか。・ 旭ガラス、インドとロシアで自動車向け新工場建築。自動車産業の現地生産方向に向けた対応。・ JFEスチール、増産に向け電炉4社で大規模投資。このようにグローバルで勝ち残り、業績拡大に向けて積極投資が活発である。特に重工・商社が目立つ。【今週の予想】日経平均株価は需給環境改善で、18000円台を固める展開になる。18,500円も視野に入ってくる可能性がある。円と長期金利(米国の長期金利含む)および米国株式相場の状況次第で変わってくる。金利差に基づき、円は先週末に124円まで下落したが、じりじりと下落傾向を強めるであろう。126~127円程度に下落するのではないか。円安で輸出関連企業の業績拡大に繋がる。グローバルな設備投資と08年3月末収益予想の上方修正で株価に好影響をもたらす。長期金利は1.8%後半~1.9%前半で膠着しそうで、米国程、金利感応度は高くない。今週は日本サイドで5月の鉱工業生産指数、同月のCPIと家計調査が発表される。各指数とも先月と大差ないと思われるが、事前予想と大きく上ぶれると、日銀の早期利上げ観測が台頭する。となると長期金利も上昇するシナリオも確率は少ないがあり得る。一方米国では長期金利上昇が住宅市場への悪影響を懸念する声が出ており、5月の中古/新築住宅販売等住宅関連の指標と、27~28日開催のFOMCに注目が集まる。政策金利は据え置かれるだろうが、声明の内容が重要視される。日経平均株価に戻ろう。先週末のNYKダウの大幅下落で売り先行で始まる可能性がある。先週の日経平均は7年1カ月ぶりの水準まで上昇した。その達成感から、利益確定売りもでる可能性はあるが、株主総会集中日の時期は例年国内機関投資家の売りが減少する傾向が強い。6月中間決算を控えた外国人投資家も売りを手控えるであろう。日経平均は底堅い展開が続く可能性大である。個別企業の材料として・ 今年は猛暑と予想されているが、エアコン、ビール、冷凍食品、夏物衣料関係業種が売り上げを伸ばす可能性大である。・ 米国で原子炉30基増設されると発表されたが、東芝等原子力関連企業の受注が見込まれ、業績に寄与するであろう。・ 中国等新興国の経済成長により、建機・精密機械等に需要が拡大する。その為、設備投資の増加が期待される。・ 銀行界では、政策金利上げの見通しが立たず預貸金金利鞘増が見込めない。また、地方銀行の不良債権が残っており、県境を越えた合従連衡が進展する。・ 世界経済の拡大による流通活発化で海運関連は収益拡大する見通し。・ 百貨店三越営業益49%減益。製紙業界と同様に百貨店業界でもさらなるM&Aが持ち上がってくるであろう。NYKダウは、先週のヘッジフアンドの問題で大幅下落した影響が残り、調整局面が続く可能性がある。27~28日に開催されるFOMC見解に注目すべきである。政策金利は据え置かれるであろう。インフレ懸念もなく米国景気自体は堅調である。FOMCの見解が楽観視されれば、株価上昇が期待できる。また、住宅関連の指標も発表されるが、調整局面にある事は折り込み済みで、株価への影響はないと予想できる。以上
2007年06月25日
コメント(0)
-
コメントありがとうございます。
彷徨える虎さん コメントありがとうございます。まったくそのとおりです。今後ともまた何かありましたらコメントをお願いいたします。
2007年06月23日
コメント(1)
-
いろいろとコメントありがとうございます
先日友人からファンドの紹介がありました。1年で数十パーセントつくんだよでもそれは紹介紹介で回ってくるものですわたしから それは絶対に詐欺商法だから早く引き払ったほうが良いよと話したんだけど1年続いているんだから大丈夫でもわたしがだまされたケースは10年でしたからそれも説明したのに絶対大丈夫だってこんどあって話さないといけないですねみなさん金融監督庁に認可されていない会社でのお金やり取りはだれも保護してくれないし事件にもなりません。これがまさしくグレーゾーンの商法なんです。どんな商品にも責任を負うことができるものとの取引をすることと弁護士をたてても勝てる知識をもってから取引することが自分を守ることもなるしトラブルは回避できます。もう一度いいますが0学占星術の角度からの診断でも詐欺が横行すると確実にでています。いまお金をなくすことで後で働けばまたいいやなんて軽い気持ちは絶対のやめてくださいこれから経済はそうなかなかあのバブルの時代のようにはもどりませんから知識なくての取引は絶対にしないでくださいね。警告です
2007年06月21日
コメント(1)
-
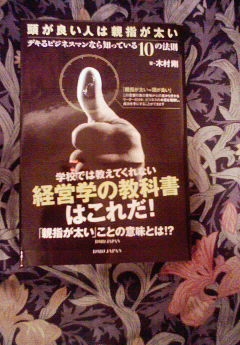
情報収集
今日は木村剛さんのお話を聞きに行きました。詐欺の話に熱が入っていたように感じました。詐欺にあっているようです。東大卒の木村さんすら見抜けないぐらい詐欺はかなり頭が良いようです。そしてまた、別の話では東大卒だけが世の中を動かしているわけではないという話もありましたが実際外資にも流れている東大卒が月のお給料が300万以上のようですこれはやはり頭がいいからだと思うのですが。どうなんでしょうか 皆さんはどう思われますか。ちなみに0学上から今後はさらにものすごい詐欺がでてくることはまちがいありません。皆さん本当にきよつけてくださいね。とりあえず参考になるかどうかはわかりませんが今日の収穫のお勧め本です
2007年06月19日
コメント(1)
-
お待たせ マーボーの経済分析 期待を裏切りません
平成19年6月17日【今週の概要】相場推移表6月11日 から 6月15日 月 日 曜日 日本 米国 日経平均 ドル/円 長期金利 NYKダウ NASDAQ6月11日 月 17834.48 121.60-62 1.905 13424.96 2572.15 55.39 -0.69 0.005 0.57 -1.396月12日 火 17760.91 121.65-67 1.93 13295.01 2549.77 -73.57 -0.05 0.025 -129.95 -22.386月13日 水 17732.77 122.28-30 1.96 13482.35 2582.31 -28.14 -0.63 0.03 187.34 32.546月14日 木 17842.29 122.93-95 1.955 13553.72 2599.41 109.52 -0.65 -0.005 71.37 17.16月15日 金 17971.49 123.3 1.915 13639.48 2626.71 129.2 -0.37 -0.04 85.76 27.3日経平均は、表の通り18,000円の大台を抜けなかった。対ドルで円安が進行し、週末には123円台をつけたが。一方NYKダウは12日に大幅調整したものの、上昇基調に変化はなく13,600ドル台をつけた。NYKダウは上下とも振幅が大きいのが最近の特徴である。今、グローバル的に長期金利が上昇している。NYKダウの調整は、米長期金利の上昇にある。長期金利の発端は中国の5月CPIが前年同期比3.4%上昇したことで、グローバルなインフレ圧力への警戒感が高まったため、米国長期金利が前日比0.14%高い5.29%となった。欧州の政策金利も利上げされたことも遠因であろう。急激な金利上昇がいかに株価への影響が大きいか実証された。日本の長期金利も米国金利上昇に影響され、1.9%台に上昇した。日経平均は円安効果が長期金利上昇に減殺されたため、上値が重たいのではないか。日本の景況感であるが1-3月のGDPが3.3%になり、速報値より上方修正された。企業の設備投資が堅調であることが主因である。PPI(企業物価)も前年同月比2.2%上昇した。週末の日銀政策金利決定会合で政策金利0.5%に据え置かれた。日銀総裁の発言で、今夏利上げの憶測を呼んでいる。あとは米国経済、消費、設備投資の確たる指標を求めているのが現状である。CPIであるが、トイレットペーパーやマヨネーズが値上げされているが、まだ水面下にある。値上げの波及効果も未知数である。企業の不祥事が頻発している。グッドウイルに続いて、英会話学校NOVAの強引商法が当局の指弾を受けた。グッドウイルは介護事業撤退の意向を表明し、人材派遣事業で存続すると発表しているが、業績縮小で株価が値下がり続けている。NOVAも今後の業績不安で株価の下落を招いている。三菱UFJ銀行も業務改善命令を受けた。企業のコンプライアンスはどうなっているのか。TOB合戦が長期化している楽天とTBSの株価が低迷している。M&Aが頻発しているが、松下電器が1兆円の資金でM&Aを狙っているし、シテイー銀行も4000億円の円建て社債発行を予定している。何時、大型のM&Aが発表されるか先が予見できない。【今週の予想】先週は急上昇した長期金利相場であった。しかし、日米とも長期金利警戒感が一巡したので、株価は堅調な展開になると予想する。18,000台を固める動きになる。その長期金利であるが、やはり米国の金利動向に大きく左右されるであろう。米国では19日に住宅着工件数が発表される。市場予想より下回れば、一部景況感の下ぶれ懸念で長期金利は落ち着くであろう。上ぶれば再び長期金利は上昇する可能性がある。従って、金利動向によってNYK株は左右されそうである。しかし、NYK市場はインフレ懸念が残っており、住宅着工件数の他、6月のフイラデルフイア連銀景気指数等の経済統計が材料視されるであろう。恐らくインフレ懸念は後退し、引き続き株価は増勢基調を保つ。日本の株価は、円安が最大の援軍である。ただし、米長期金利上昇やNYKダウの趨勢により、大きく変動する可能性がある。要は金利・円動向を注視すべき相場になるであろう。筆者は、日経平均は18,200円程度に上昇すると考えている。円相場は金利差による「円借り取引」が増勢を強めて、124円程度の円安になると予想する。市場では早期利上げ観測が後退し、円安の支援材料になる。要注目銘柄は次の通り。・ 松下電器子会社のビクターの売却交渉が米投資フアンドTPGと決裂し、ケンウッドと交渉に入った事で、ビクターの株は大幅下落した。ケンウッドとの交渉推移によって、ビクター株はさらに下落し、松下電器も調整する可能性がある。・ NECエレクは親子上場問題で、再編期待の上ぶれが期待できる。・ コムスン譲り受け候補でニチイ学館が、業容拡大期待でもっと買われる可能性がある。・ 東芝がフラッシュメモリー7割増産で業績拡大期待がもてる。・ フアナックが24年ぶり新工場新設。工作機械向け数値制御装置で高いシェアーを持ち、買い推奨株となろう。・ 長期金利上昇で、不動産株弱含みになり、銀行・保険は株価上昇する可能性がある。以上
2007年06月19日
コメント(0)
-
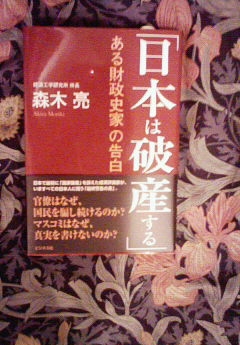
お勧め本を添付忘れたので
2007年06月16日
コメント(0)
-
とりあえず過去振り返り週間号はまとまりましたが
みなさんついていこれましたか。膨大な量を排出しました。これは以前も一緒に出していたマーボとのコラボレーションです。しばらく令菊のブログをお休みをしていましたがマーボーだけはまじめにため書きをしていのでこんな特集が組めることができました。過去を読むのも相場を見るのに大事なことが浮かび上がってくるものですよね。これを全部読まれた方は1行だけでもいいですので感想をお寄せください。あの森木先生の本のようにならないよう相場を読み経済を活気付けることが一番なんですがね。今後は 0学とのコラボレーションを7月から開始しますそれまでマーボーの経済誌が独占しますすごくいろんなことを貯めていたので楽しみにしてくださいね。これから長いお付き合いをよろしくお願いします。
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年6月10日 過去振り返り週間号
平成19年6月10日【先週の概要】先週の動きは政治的、経済的に大揺れの週であった。先進国首脳会議では、「温暖化ガス削減」がメインテーマであり、「京都議定書」後の新しい枠組みが合意された。環境問題について前進であった。しかし、この問題については中国とロシアの存在なしには語れない。両国の政治的、経済的影響力が増している。一方、国内では「年金問題」が大きな政治的、社会的問題となっている。社会保険庁の過去からの怠慢が問題視されている。天下り問題と絡めても、国民から怒りを買っている。次に、介護事業者「コムスン」の不正請求に伴う事業停止問題。余りに業容拡大に走り過ぎ、企業のコンプライアンスは二の次である。介護制度の法律もまだ不十分である事も要因の1つであろう。同社の親会社グッドウイルの株価が連日ストップ安まで売られている。業界全体に対しても、投資家の不信感が拭えないのではないか。企業不祥事といえば、目立っていないが富士通が「循環取引」で売り上げを不正嵩上げした事が発覚した。公正取引委員会の権限強化で次々と摘発される談合(官制談合含む)。社会公正の視点から常軌を逸脱している企業が多すぎる。さて、先週の日経平均は木曜日まで上昇気流に乗って18,000円台を回復したが、週末に274円安と大幅下げで大台を再び割ってしまった。国内経済指標の内、1-3月の法人企業統計(設備投資13.6%増、経常利益増益)、景気動向指数(一致指数50%超)は景況感改善を示す数値であったが、機械受注統計が2.2%と市場予想を下回った。この機械受注統計が市場予想を下回った事とNYKダウ3日大幅続落で、幅広い銘柄が売られた。それと、長期金利が週間を通じてじわりと上昇し、10年物国債指標銘柄が1.9%台をつけたことも要因であろう。120円台の円高も隠れた要因である。米国NYKダウ、ナスダックが火、水、木と3日連続大幅に下げたが、FRB議長のインフレ懸念発言と5月のIMS非製造業指数が市場予想を大幅に上回ったことが3連続安の発端である。政策金利引下げ期待が萎んでしまった。また、1-3月の単位労働コスト改定値が速報値を上方修正されたため、インフレ懸念が台頭し市場は金利に敏感になっている。この日株安の直接材料となったのは欧州ECBの政策金利利上げと追加利上げにも言及した事である。世界的金利上昇傾向と堅調な米景気をうけ、FRBの利上げ観測が台頭し、長期金利は5.1%まで上昇した。原油価格の上昇も輪をかけた。大型のM&Aも金利上昇から、なりを潜め株価上昇を牽引しなくなった。この世界的金利上昇の影響を受け、日本の金利上昇が上昇した。10年物国債が1.9%台をつけ(債券価格は下落)、2年債、5年債も上昇した。1部銀行も長期プライムレートを上げた。この金利上昇が企業業績に悪影響を来たす懸念が市場に台頭している。日米とも、金利上昇による株価の調整週であった。【今週の予想】今週の株式相場は海外市場の株価と金利動向に大きく左右されて、神経質な展開になりそうだ。米国の金利上昇と株安が一服すれば、大きく下落する局面はなくなるであろう。1-3月のGDP改定値等で国内景気の堅調さ(2.4%→3%台)が確認されれば、買いが入る可能性がある。もう1つの要因として、14日~15日に開催される日銀の金融政策決定会合が開催される。15日の総裁の発言内容が注目される。政策金利利上げが前倒しになる可能性を示俊すれば、短めの2年物・5年物・10年物の国債の金利が更に上昇し、10年物は2%に限りなく近づくであろう。12日に実施される新発5年物国債入札で需給が不調であれば、長期金利は更に上ぶれする可能性がある。金利上昇→企業業績下ぶれ予想→株価軟調というシナリオが予想される。その金利上昇の前に、設備投資資金等のため成長志向の強い企業は相次いで社債を発行している。米国の金利動向も少なからず、日本の金利に影響を与える。インフレ懸念から、米国の長期金利は1時5.24%まで上昇したが、さらに上ぶれると日本の金利上昇と株価下落に結びつく。米国は、前々週の雇用統計あたりから賃金と原油上昇からインフレ懸念が市場の大勢になりつつある。従って、米国株式相場は高値圏での値動きの荒い展開になりそうだ。今の米国株式相場は、経済のフアンダメンタル相場より、M&A相場である。今までは、米国投資フアンドの潤沢な資金による企業買収で市況は大きく動意づいた。リスクマネーでもあり、フアンドの規制が先進国首脳会議で議題になったこともあり、投資フアンドによるM&Aは減少していくのではないか。次に、円相場であるが、国内投資家に円売りも根強く続いているが、ヘッジフアンドによる円買いも出ており、方向感が出にくい展開になるであろう。120円を挟んだ展開になる。ただし、米国長期金利が下落か、日本の長期金利の更なる上昇によっては円高に振れる可能性がある。金利・為替・株価に影響する米国の経済指標が相次いで発表になる。13日のベージュブック、15日発表のCPIの結果によっては様相が大きく違ってくる。日本の個別銘柄では・ 下落し続けているグッドウィルの落ち着き所はどうなるか。・ 地方銀行の不良債権比率は4%台で改善していない。今後、地銀同士の合併が出てくる可能性がある。・ 商社株は積極的投資と資源関連で業績拡大が見込まれる。・ UCCがシャテイーにTOB、シャテイー株に買いが殺到するか。・ セブン&アイが赤ちゃん本舗を買収する。今後の株価への影響。・ 循環取引が発覚した富士通の株価への影響。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年6月3日 過去振り返り週間号
平成19年6月3日【先週の概況】日米の4月雇用統計が改善した。日本では完全失業率が3.8%と3%台に突入し、有効求人倍率も1.05倍となった。米国でも失業率4.5%と横這いながら、雇用者数が157、000人に増加した。(注)米国の雇用者数増加150、000人前後が景気善し悪しの判断材料となる。雇用面だけでは景気の判断材料にはならないが、日米とも緩やかな景気拡大していると判断できる。米国の景気減速懸念は、企業業績が思いのほか堅調であり懸念は薄らいでいる。逆にインフレ懸念が台頭してきている。日本の景気は、企業業績が海外需要と円安に支えられて堅調である。上場企業全体では、前期は経常収益が11%増加し、今期も3.5%増加見通しである。設備投資も内外で増える見込みである。問題は、個人消費とCPIである。4月の消費支出が前年同月比1.1%増加した。需給ギャップも10年ぶりに2四半期期連続プラス(0.7%)である。にも拘わらず、個人消費は盛り上がらない。企業の株主還元と設備投資で勤労者に企業利益が回っていないためである。どうやら、もう1つの要因がありそうである。それは、特別減税の廃止である。今年6月の住民税が上がる。国税・住民税の調整もあるが、特別減税廃止による増税である。消費者心理を萎縮させていると考える。個人消費が盛り上がらない要因をもう一度分析・調査する必要がある。企業サイドがいずれ息切れし、消費が盛り上がらなければ景気後退を余儀なくされる。消費はGDPの50%を占めているのだから。さて、日経平均であるが、やはり前々週のNYKダウと円安で週初は上昇した。中国株上昇にも買い安心感が広がった。このところの非鉄金属の相場が堅調な事を受けて鉄鋼・非鉄関連株が買われた。世界経済の堅調さ、資源高で商社株も堅調であった。もっとも、国内材料難の中、海外材料頼みが中心であった。水曜日には経済指標(鉱工業生産指数)の悪化で下げたが、木曜日は前日のNYKダウの大幅高で急騰した。結局、週間を通して477円余上昇して引けた。この1週間の騰落は外部要因によるところが大きかった。ところで、長期金利がじわりと上昇した。これは、早い時期の政策金利上げ観測の影響であるが、米国との金利差縮小で円高になるとの読みがあったがむしろ円安となった。週末の米国市場では122円まで円が下げた。この現象は日米の景況感格差に起因していると考えられる。【今週の予想】今週の株式相場は先週に引き続き堅調な展開になるであろう。米NYKダウの連日の高値更新が想定されるし、上海市場の下落にも感応度が薄れている。円安も継続しており、外部環境に恵まれており、18,100円台を試す展開になると予想する。個人投資家が市場に戻りつつあるのも支援材料である。ただし、今週は重要な経済指標が相次いで発表される。1-3月の法人企業統計、景気動向指数、機械受注統計である。これらの指標が良ければ、株価は上昇するであろう。しかし、政策金利の早期引き上げが想定されて長短金利の上昇をもたらされる危惧がる。金利の急騰は株式相場にはマイナスである。日米金利差縮小による円高が進む懸念がる。輸出関連株の収益に大きく影響する。米国の株価もM&Aに支えられており堅調さをたもっているが、7日発表のPPIが焦点である。何れは米国株の上昇気流が途切れて調整局面になるであろうが、その時は日本の株式市場にも大きく影響するであろう。日本の相場に影響する不安要因が政局の流動化である。農相の自殺、年金の問題等で安部政権の基盤が脆弱となり構造改革路線の継続が不透明化し、海外投資家の資金が日本市場から逃避することが懸念される。自民党が参議院選挙で敗北となると最悪のシナリオである。個別企業で先行き心配な企業は、3期連続赤字の三洋電機・電気商品リコールの松下電器・リストラ途上のJALである。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年5月27日 過去振り返り週間号
平成19年5月27日【先週の概況】今の日本の景気は拡大基調なのか後退傾向なのかあるいは一時的踊り場なのか不透明感が漂う。日銀の金利政策は間違っていないか?直近のGDPは2.4%(年率)成長であったが、成長の寄与は設備投資から個人消費と外需に変化した。主な予測機関の07年度のGDP予測値は2.2%である。1-3月の景気動向指数の一致指数が3カ月連続で50%割れ、3月の機械受注統計が前期比0.7%減であった。25日発表のCPIも前年同月比0.1%減少した。水面下にありデフレ脱却はしていない。(政府も認めている)となると、景気は後退局面の初期段階にあるのではないか。日銀の金利政策の誤りが原因ではないのか。昨年の量的緩和の解除、ゼロ金利の解除、金利引き上げの一連の政策が今になってボデイーブローのように効いてきている感がある。CPIが水面下でマイナスでも政策金利利上げとの日銀総裁の意図が理解出来ない。07年の企業収益が円安で潤って大幅利益を計上したが、政策金利上げにより円高となり、景気を牽引してきた企業部門が減益を余儀なくされる。また、金融機関の利上げによる減益も見込まれる。個人消費は微増であるが、低い一人当たり賃金は上昇していない中、需給ギャップの需要超過増大に赤信号が灯る。それと、円高になると輸入物価が下落しデフレに舞い戻る可能性があり、日銀はその点を看過している。日本のCPIが水面上に出てこない原因として原油動向と携帯電話使用料引き下げを上げているが説得力がない。原油や素材の上昇が企業の収益圧迫要因であるが、それが川下までなかなか波及しない。理由は企業の再編・リストラ等必死の努力でコストを吸収している。最近トイレットペーパーの値上げが発表になったが、その続きがない。競争の厳しいなか、企業がコスト増を消費者に転化できないからであろう。日本の株価が上昇しないのは以上のような原因である。さて、日本の株価であるが、先々週のNYKダウの上昇と円安で週初から水曜日まで上昇気流にのったが、週後半は下げに転じた。月曜日はNYKダウと円安をベースとし、日本時間の10:30分に開く上海市場の切り返しで上昇したもの。個別銘柄では、業績急回復したソニー、シャープ等電機銘柄が堅調。また、世界的需要増を見越した海運も堅調。一方今期の増益予想の企業(カプコン)は買われ、減益予想の企業(日ハム)は売られる展開は相変わらず。M&A相場での上昇株も見られた。(農産工、東京個別等)火曜日は内需関連株(建設・証券・銀行)に買いの矛先が向かった展開で日経平均は上昇。金曜日は、日経平均は前日のNYKダウの下落や若干の円高で見切り売りが相次ぎ大幅安で引けた。今や、日経平均はM&Aもさることながら、NYKダウと上海市場に大きく影響を受ける展開である。世界市場の堅調さに比べ日経平均は出遅れ感が鮮明である。NYKダウは先週調整したが、週末に66ドル余上昇した。4月の中古住宅販売が前月に比べ2.6%減少したが、M&A(NASDAQによる北欧のOMX買収やコカコーラによるエナジーブランズ買収)のニュースで相殺された格好であった。しかし、上海市場の株高がいつまで続くか霧の中であるが、急落した時は世界中の市場に強烈な影響を及ぼすであろう。【今週の予想】今週の株式相場は材料難の中冴えない展開になると予想する。先週の大手銀行で決算発表はほぼ一巡した。全般的に見て07年3月期の企業業績は好調であったが、08年度の業績予想は米国景気など不透明要素が多く慎重姿勢の企業が多かった。その為、決算発表期間中の市況は全般的に冴えなかった。電撃的に発表になるM&Aも対象銘柄のみの上昇で市場全体の底上げには繋がらない。欧米のM&Aは市場全体に影響する。市場の受け止め方の違いが鮮明である。材料難になると、市場は外部的要因に敏感に反応する相場展開になると思われる。米国景気・同国株式相場・円・上海株式相場動向に大きく左右される。・ 米国景気は、FRB高官の発言や強めの景気指標で利下げ観測が遠のいている。減速していた住宅産業は少しずつ回復している。従って、長期金利は4.8%後半まで上昇している。ガソリン高も3ドル台/1ガロンと高止まりしていることもインフレ懸念を増幅している。そのインフレに関して、今週の雇用統計とPCE(個人消費支出デフレーター)等指標が発表される。景気軟着陸か、インフレか先々の金融政策に影響を及ぼすことになる。・ 米国NYKダウ、ナスダック市場とも、発表される景気指標の市場予想との乖離に敏感に反応する。13500ドル台を維持しているNYKダウは調整局面に入る可能性がある。13000ドル台後半が底値とみる。・ 米国金利の長期金利上昇基調とそれにつられた日本の長期金利の上昇傾向(1.7%台前半)で若干円高に振れたが、金利差は歴然として残り円安基調は変化しない。一時的に123円台と円安になる可能性はあるが、米国の景気指標次第となる。・ 中国上海株式市況は連日最高値を更新し、中国当局の引き締め政策も全く効き目がない。バブルの様相を呈している。米国のグリンスパン前議長が言うように、いつかは大きな調整局面が来るが、時期は誰にも予測できない。日本市場の10:30以降の相場動勢を左右する。それだけ中国経済が成長を続けている証左でもある。最後に、筆者の勝手な予想であるが、米国週末のNYKダウと円安で、先週と同様に今週前半の日経平均は小高く推移する予感がする。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年5月20日 過去振り返り週間号
平成19年5月20日【先週の概況】5月17日に内閣府から発表された1-3月GDP速報値は実質2.4%成長であった。9期連続プラスであったが、その内容をみると今までとは様相が少し変化している。今まで成長を牽引してきた企業の設備投資が前期比マイナス0.9%となり増勢一巡となった。主に製造業の設備投資が国内で旺盛であったが、傾向として海外での設備投資に軸足が移ってきている。これは一過性ではなく、国内の設備投資は趨勢的に鈍化していくであろう。海外現地生産で貿易摩擦を事前に避ける行動と将来の円高対応の行動とみる。今後非製造業の設備投資が増加し製造業の減少分を一部穴埋めすると考えるが、それでも設備投資は現象していく。個別企業では生き残りをかけて増産を標榜するであろうが、そのことは需給ギャップが供給過剰となり、生産物価格が下落傾向となる。何れにしても、設備投資は成長の主役から今後降りる確率が高い。設備投資に代わって牽引役として躍り出たのは、GDPの50%程度を占める個人消費、外需(輸出-輸入)である。今まで、企業部門(設備投資)からなかなかバトンタッチできなかった個人消費であったが、ようやくバトンを渡せる地点まで来ている。今回のGDPで全体を0.6%押し上げた。外需は円安を背景に、輸出が伸びた分成長に寄与した。ただし、景気減速気味の米国の輸出は伸びが鈍化したものの、経済成長著しい中国や東南アジアへの輸出が増加し米国向けを補った。これも今までとは違っている現象である生活実感を示す名目成長率は年率1.2%と実質成長率を下回った。前期は名目が実質を上回りデフレ脱却かと思われたが、また元に戻ってしまった。その差は縮小傾向にあるが、政府が宣言している通りデフレ脱却はまだである。今後、緩やかな成長が続くか否かは個人消費が握っている。雇用は拡大しているが、1人当たりの所得が上向いていけば個人消費は堅調に推移し景気の持続に寄与する。日本経済は1%央~2%の潜在成長力を若干上回る実質成長を当面継続できそうである。日銀総裁は今回のGDPの内容を観て、想定の範囲内との旨。また、CPIが水面下すれすれで推移していても、マイナスでも政策金利引き上げの可能性はあると言及した。さて、株価であるが、相変わらず日経平均は脆弱である。15日と18日に大きく下げた。15日の下げの要因は1-3月の機械受注統計が前期比マイナス0.7%という数字であったことである。その指標が市場心理を冷やした結果利益確定売りに押された格好。新興株価指数が下げ止まらない中で、個人の逃げ足の早さが目に付いた。18日は円安にも拘わらず、実質GDP伸び悩み等足下の景気指標の鈍さを懸念する空気が強く、個別企業の07年度の好決算にも拘わらず、買いの手が伸びない。今まで検証した通り、各企業08年3月期決算の予想が慎重であることが、株価が上昇しない主因で景気指標の悪化がそれに輪をかけていることである。一方、NYKダウであるが、17日に微調整したが連日騰勢を維持し市場最高値を更新し続けている。FRBの政策金利が据え置かれ潤沢な資金が流れ込んでいる。住宅関連指標悪化も峠を越し他の経済指標(※)も順当な数値を示しているところに、世界的(日本も含む)M&Aが、買いを誘発しているのが現状。中国上海株の大幅下げにも、前回の世界連鎖安時と違って動じていない。いずれ調整局面に入るであろうが、日経平均はNYKダウの写真相場になっていない。※ 消費者物価前月比0.4%増 住宅着工前月比2.5%増 工業生産指数前月比0.7%増 【今週の予想】先ずは日本の企業業績に影響する円相場から話を進めよう。先週は121円台/ドルまで円安が進んだが、日米の景況感の差異に伴う金利差が大きく縮小する兆候がない。強いて上げれば、日本の4月CPI、同月の米国耐久財受注と新築住宅販売件数の数値によっては、市場が動意づく可能性は残る。何れにしても、120円を挟んだ膠着感漂う相場展開になる。概ね115円に社内レートを設定している日本の輸出企業にとって居心地の良い相場展開になる。1つだけ円高になる可能性が強い要因としては、米国に配慮して中国政策当局が元の変動幅を上下0.3%から0.5%に変更したことである。同じアジア通貨として、円が連れ高になることである。永続的か一時的になるか読めない。日銀は政策決定会合で政策金利を秋口まで据え置くであろうが、CPIの結果次第では長期金利上昇(価格下落)も考え得る。しかし、このシナリオは考えにくい。市場は1.6%台の金利が続くと見ており、先物金利も低下傾向にある。ただ、米国長期金利は前週末から上昇気味であり、日本の金利に波及する可能性も捨てきれない。最後に、株価について。NYKダウは13500円台を突破し騰勢基調は衰えていない。今週はビッグイベントが無く、28日が休日で薄商いの中動意の薄い展開となる。連日の騰勢でスピード調整の展開になる可能性はある。最近の景気指標もほぼ市場の予想通りであり、景気の減速もインフレの兆候も許容できる範囲内であり、市場には心地よい状況である。ここにM&Aが発表されるとさらに騰勢を強めるであろう。24日発表の新築住宅販売件数と耐久財受注は、余程市場予想と乖離しない限り影響はないと考える。日本の株価は、企業業績発表が一巡し、市場の目はマクロの経済指標と外部環境に映ってくる。世界的過剰流動性が円高や商品市況により流れの変調をきたし、日本の株式市況に悪影響を及ぼす可能性がある。世界的大型M&Aが新たに発表されても、個別銘柄または個別業種に一時的に反応するだけでそこから反発し騰勢を強めることはない。週末に発表されるCPIは大きく改善される可能性は少ないが、万一大幅改善して日銀による政策金利上げの思惑を生み円高となり輸出企業の業績に打撃となり、株価は軟調な展開となる。一方、中国上海市場、米国NYKダウの動向に注意が必要である。それにしても、個人投資家の見送り姿勢が強い。新興三市場指数の連日の下落が証左といえる。昨年初のライブドア事件が根っこにあるのか、会計不信を懸念しているのか?自国株価上昇による買い余力の増加した外国人投資家の買いが頼りである。17000円台前半で推移すると予想する。余談となるが、買収フアンドのM&Aに対する積極性と資金力には目を見張る物がある。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年5月13日 過去振り返り週間号
平成19年5月13日【先週の概況】先週の概況を記述する前に、GW週間のおさらいをしておこう。5月1日から3角合併が始まった。今後外資が日本の企業に買収を仕掛けることが法的に可能となった。いまや、世界中でM&Aが日常茶飯事である。先週は、日本では2日営業日しかなかったが、米ニューズ社がダウ社に買収提案した。先行きどうなるか不透明であるが、金融情報会社までM&Aの波が押し寄せている。日本では福岡フイナンシアルグループと九州親和ホールデイングの経営統合が発表された。実現すると、横浜銀行を抜いて地銀トップに躍り出る。3大メガバンクは公的資金返済が終わり、業績進展が顕著である。しかし、1部地銀は地域経済の不振から業績が低迷している。今後地域を越えた銀行の再編が進む可能性がある。信金・信組も含め金融機関数が多すぎる地域がある。日経平均は、5月1日に4月30日の米株安を受けて下落した。GW最中、様子見の投資家の買い控えが要因である。5月2日は円安を好感し反発した。日経平均は4月中旬以降、日替わりで騰落を繰り返している。この2日間はその典型である。連日、企業業績発表で好業績企業(※)が大半を占めるのに余り反応していない。米国NYKダウは4月30日に下落したものの、5月1日以降盛り返し連日最高値を更新した。米国経済指標について、4月30日発表の3月個人消費支出が前月比0.3%上昇したことと、5月4日発表の4月雇用統計は失業率4.5%に悪化、雇用者数が88,000人増となった。雇用拡大の勢いが鈍化している。FOMCでの主要な景気判断材料である。(※)好決算の企業 カシオ3期連続、ダイキン営業増益25%、日東紡経常益増22%、東エレク2期連続増益、さて、最初に個別銘柄・業界の業績から話題を始めよう。企業業績の発表は後半を迎え好業績が目立つ。・ 帝人16年ぶりの最高益・新日本科学経常益42%増・エイチワン経常益3倍増・森精機経常益55%増・曙ブレーキ純利益最高・オリンパス純利益最高・住友重機営業益最高・メネビア36%増益・出光興産経常益52%増・旭化成営業益最高・ユニシス純利益82%増・AOKIHD2期連続最高益・トヨタ営業益2兆円・NTTデータ経常益倍増・東レ純利益最高・特殊陶器営業益最高・海運3社経常増益・セコム経常益1000億円超す・オークマ最高益・武田薬品15期連続最高益・総合科学大手営業益最高・横河電機営業益最高・大日本インキ営業益最高・三菱地所2期連続で最高益・ニコン3期連続最高益・オリックス純利益最高・住友電気3期連続最高益・キーエンス純利益最高・日精工純利益最高・合繊大手5社純利益最高日経新聞が5月11日現在まとめた上場企業665社(金融除く)の利益は4期連続最高益で12.2%増加した。要因として新興国の経済成長、円安である。各社今までのリストラで損益分岐点が下がっており、利益が出易い体質になっている。また、各企業は今期以降の収益を慎重にみているが、積極的に次の一手を打っている。三菱重工は有機ELの量産体制を構築(有機ELは電気製品の一大変革製品)・郵船はブラジルのリオドセと20年傭船契約・ダイキンがエアコンの世界生産拡大・商船三井LNG新型船3隻1000億円規模で建造・NTTデータが中国、東南アジアに現地法人設立・東芝がベトナムに開発拠点設立・エルピーダ等半導体企業大手7社9700億円設備投資・トヨタが研究開発費6%増・三菱商事が特殊東海HDの筆頭株主に、製紙部門強化 世界的にM&Aも相変わらず突発的に発生している。・米のアルコアがカナダのアルキャンに対しTOB。再編の波が非鉄業界にも押し寄せている・米3Mが日本に拠点。3角合併の布石か?・日本の京都着物友禅株を香港のフアンドが株取得 ・トムソンがロイター買収を検討・ミタルが米鉄鋼会社大手を買収検討・学研が家庭教師派遣大手タートルを買収さて、平均株価の話題に移ろう。日経平均株価であるが、17700円台に上昇した日が2日程あったが、週末には16500円台に押し戻された。上値の重い展開であった。各企業が好業績を上げているにも拘わらず、週末には183円下落した。要因として前日のNYKダウの大幅下落を受けたためである。具体的には米半導体株指数が悪化したため、ハイテク株に安い物が目立った。今期の業績予想が期待外れの銘柄と急ピッチで上昇した海運、鉄鋼、不動産の利益確定売りも要因の1つである。一方、NYKダウは10日に大幅下落した。下落材料の1つは、米貿易赤字の拡大である。(3月10.4%増)貿易赤字が株価に影響されたのは最近では余り記憶にない。2つ目の材料として、落ち着いていた原油価格の上昇である。特に、ガソリンは3ドル台/1ガロンは消費を冷やす要因である。現に4月消費は前年同月比2.4%減少している。それでもなおNYKダウは最高値を更新している。一面では低金利を背景とした潤沢なマネーの存在がある。米国株は企業の好業績、相次ぐM&A等の好材料が上昇スパイラルを発生させている。市場に過熱感がでてきており、経済のフアンダメンタルズを反映していない。いずれ逆作用を起こすリスクを内在している。なお、5月9日開催のFOMCは市場の予想通り政策金利据え置きである。物価上昇回避の利上げか、景気減速(特に住宅)に対する利下げか両睨みである。日本の景気と金融政策はどうであろうか?現状は企業業績と設備投資が牽引しているが、消費は横這いである。実際CPIは低位横這いであり、日銀もそれを認めつつある。経済指標も弱含みの数値が出ている。景気動向調査の一致指数が3カ月連続50%割れ、街角景気指数が2カ月ぶり50%割れである。日銀の景気認識が誤っていないか?【今週の予想】先週末のNYKダウの大幅上昇と120円台をつけた円安で、日経平均は週初大幅高になりそうである。その上昇基調が続くかが問題である。各企業の決算発表がピークを迎え、市場の関心は08年度の収益予想となる。総じて、各企業の予想は慎重である。今後、上方修正した方が、市場の以外感から株価上昇を期待できるからだ。先週に業績見通しが市場予想を上回った住友鉱山が連日上場来高値を更新したが、市場予想を下回った企業(カシオと横河電機)が大幅下落に見舞われた例が典型的であり、そうした銘柄が相場に影響を与えるであろう。当然、米国の景気、景気指標及びNYKダウの状況に一喜一憂する場面もある。上海株式相場の上昇/下落にも左右される可能性もある。同市場は過熱気味であるのは事実。それと円相場の行方の影響も当然ある。先週、米国下院公聴会で「円安は日本の輸出補助金」との発言があった。週末にG8財務相会合が開催される。円安が議論の俎上に上れば、次の週の円動向に影響が及ぶ。今は円が元の存在に隠されている様相であるが!円は118円~122円と予想する。共同リースと三井リース統合により、地方銀行、リース業界、鉄鋼業界等M&Aの動向にも注意が必要である。それと、17日に発表予定の1-3月GDPも重要な注目材料である。市場予想(2.6%)を下回ると、デイフエンシブ銘柄が買われるが、景気下降もしくは踊り場として日経平均は調整する。日本株に影響する米国市場は海外情勢(上海株)と経済指標に左右される相場展開になる。15日に4月のCPI、16日は住宅着工件数が発表になる。インフレ、景気減退が確認されると株が売られる可能性が強い。NYKダウはサイコロジカル指数が大きくプラス(上げ日と下げ日の比率)で、そろそろ調整する局面に入るであろう。日米とも経済指標に目が離せない1週間である。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年4月29日 過去振り返り週間号
平成19年4月29日【先週の概要】ロシアのエリツイン前大統領が死去。元大統領のゴルバチョフと共に「民主化」と「市場経済化」に尽力し鉄のカーテンを取り除いた功績者である。世界の巨星がまた1人居なくなった。プーチン現大統領の政治的継続性を祈る。米国NYKダウが25日に13,000ドルを突破し、その後も13,120ドル台まで続伸した。25日は135ドル余上昇したが、要因は以下の4点に尽きる。1耐久財受注額が前月比3.4%増加したこと、資本財の受注が4.7%%伸びたことで民間設備投資の堅調さが確認された。2ベージュブックが発表されたが、内容はまちまちで余り材料視されなかった。3新築販売件数が予想に届かなかったが影響は限定的であった。4アマゾンドットコムやペプシコの好決算や、アルコアが1部事業の売却を発表したこと。アップル、ボーイングも大幅な増益である。住宅問題等に起因した米国の景気減速は1-3月期のGDP速報値が1.3%と前期比大幅低下したことで立証された。しかし、企業業績は堅調である。これは、企業がドル安を背景に海外部門での収益に依存しているのが真相である。米ドルの実効為替レートが過去最低になり、輸出競争力が向上していることや海外資金の流入という恩恵となっている。米国国内の景気は減速化のインフレ懸念、政策を誤ると「スタグフレーション」になるリスクをはらんでいる。利上げ再開か、利下げかFRBの舵取りは難しくなっている。欧州の景気は好調で、次回のECBでの利上げの可能性が明確であるのとは対照的である。一方、日本ではどうか。前半の前期企業業績は1部を除いて、営業益、経常益、純利益の数字が増益であった企業が圧倒的多数である。列挙してみると、新日本石油 国際石油開発帝石 ヤフー KDDI シャープ ホンダ 日本電産 ダイハツ リコー 日立建機 東芝 トヨタ系6社 任天堂 京セラ 資生堂 松下電器 三菱電機 富士フイルム JR3社 JT スズキ 信越化学 大手5商社 等※日産自動車は国内、海外とも販売不振で、減収・減益のためリストラ開始。前期の業績が最高値を達成した企業が多いにも拘わらず、株価は低調である。26日は前日のNYKダウの大幅高や、当日のアジア株の上昇を受けて大幅に上昇したが、17,500円に近づくと戻り待ちの売りに阻まれる展開であった。2月の世界同時株安から他国の市場は戻しているが、日本株は立ち直りが遅れている。外国人投資家の買いは継続しているものの個人投資家の動きが鈍い。新興株3市場の平均株価が続落し続けており、個人投資家は損失を被って投資余力が低下しているのが原因である。前日25日の大幅下げは材料不足で下げた。日本株の基調は弱いの一言に尽きる。企業の前期業績が好調でも今期予想が慎重であることが、株価上昇の弱い基調の要因でもあるのか。一方、日本のマクロ経済指標は弱い。CPI3月は前年同月比0.3%下落した。原油安や携帯電話料金下落が主因である。鉱工業生産指数は3月マイナス0.6%であった。消費関連指標はプラスを維持しているものの景気の基調は弱い。日銀展望レポートでも07年度のCPIを0.5%から0.1%に下方修正した。当年度の実質GDPが2.0%となり、08年度のCPIを0.5%と想定した。現行の政策金利も0.5%に据え置いた。先々需給ギャップが引き締まり緩やかな成長が続くシナリオである。政策金利の利上げも視野に入れている。筆者は、景気が踊り場に差し掛かっているとみる。企業の設備投資は確かに堅調である。鉄鋼各社の合計設備投資は8,600億円を予定している。確かに企業業績と設備投資は堅調である。しかし、消費に火が付かない。このまま推移すると、供給サイドの増加で需給ギャップが緩んで、デフレのリスクが顕在化してくると想定できる。従って、政策金利上げは来年であるべきである。金利先物は参院選後の利上げを睨み、買われているが一時的に過ぎない。日銀のシナリオ通りには行かないと筆者は観る。【今週の予想】今週の日本はGWで営業日は5月1日と2日の2日間しかない。市場参加者は少なくなるであろう。従って、海外の相場に左右される可能性が強い。ポイントはNYKダウの動向と日銀展望レポートの結果である。NYKダウは13,000ドル台を突破して、連日市場最高値を更新している。好調な企業業績が底上げした。主要企業の業績発表も後半を迎えており、市場の関心は金融政策に移ってくるであろう。景気減速とインフレ懸念が混在する中で、FRBはどう舵取りをするか。今週末の雇用統計が来週のFOMCの政策判断を占う判断材料となる。となると、今週の日本の株価への影響は限定的となる。急ピッチで上昇したNYKダウのスピード調整が1週間の間にあるか、ドル/円の為替相場の推移に影響されるであろう。それと海外版M&Aが突発的にあると、業界再編の思惑から日本の株価に対する影響大である。売買高が少ない中で、2日間の日経平均は17,500円弱の横這いで推移すると読む。焦点は来週以降の相場展開である。5月の日経平均は外国人投資家の売買動向に左右される傾向が過去3年間続いているので要注意。日本企業の今期予想が慎重なこと、欧米ヘッジフアンドが5月中間決算で売りを出すことが多い事が要因。円相場であるが、116~118円台で推移すると考える。日本サイドでは売買材料に乏しい一方、米国では景気を占う経済指標の発表が相次ぐ。米国3月の個人消費支出、労働生産性、雇用統計である。GDPが1.3%と低下しており、これらの指標が低い水準となれば政策金利下げの期待感が顕在化する。一方、日銀は政策金利利上げ姿勢を崩していないため金利差縮小観測から、円借り取引の先細りを誘い円高になると予想する。薄商いの中、突発的要因で相場が急変する可能性があることに要注意。ユーロは対ドル、対円とも高止まりすると予想する。堅調な景気と金利先高予想により買われる傾向が続く。日本の長期金利は1.6%台と低位安定するであろう。ただ、欧米の金利動向に影響を受ける可能性に要注目。最後に、世界中で頻発するM&Aと構造改革である。英国バークレイズ銀行が和蘭のABN-AMRO銀行を買収されることが正式発表された。一波乱ありそうであるがーーー。日本でも、第一三共製薬が製造2社売却・米フアンドが東京スター銀行株売却・松下電工が印度の配線器具大手会社を買収・古川電工が米国内光部品会社売却・ダビンチがTOCへTOB提案・ドトールコーヒーと日本レストランシステム経営統合・セントラルフアイナンスが三井住友グループの傘下に入る(UFJ東京三菱グループからの脱退)・任天堂がバンダイナコムの開発子会社買収・洋菓子プレシアがタカラブネを買収 等非常に多くなっている。業界の市場が縮小している企業群など要注目。変化の激しい時代である。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年4月22日 過去振り返り週間号 その前の1週間おやすみしました。
平成19年4月22日【先週の概況】日米で大きな凶弾事件が続発。銃に倒れた方々の冥福を祈る。日本では銃所有規制があるにも拘わらず、何故銃弾による事件が起こるのか。警察当局の徹底した規制強化を望む。さて、景気・株価・金利の動きはどうであったか?日経平均は週間を通じて行きつ戻りつの値動きで、結局90円弱の上昇に留まり基調は弱い。今月下旬からの各企業前期決算発表まで投資家は様子見気分で商いを見送っていた。一方米国NYKダウは強気一辺倒の相場で週末に153.35ドル上昇し、12,900ドルを超えて終えた。日経平均が大きく下げた19日の要因は、米国ハイテク株安が発端となり夕刻発表の中国の経済成長率が高すぎるとの憶測から、同国の金融引き締め観測→アジア株安と2月末世界同時株安を連想させて市場心理を弱気にさせたことにある。先物の大口売りや円高も拍車を駆けた。それにしても中国の経済成長率は高い。週後半に発表された同国のGDP1-3月期は実質11.1%の成長率であった。貿易黒字の予想を超える拡大、固定資産投資特に不動産投資の増勢が主因である。このままでは不動産バブルが懸念される。同国政策当局の規制・政策金利上げも景気急減速を恐れて対策が小出しであり有効性に乏しい。この結果当日の上海株式市場は4.5%下げた。政治的・軍事的・経済的に同国の影響力は増しており、中国の情勢は投資家にとって目が離せない。上海株式市場の動勢は世界に伝播する存在になっている。さて、米国株価であるがFRBの政策金利利下げは遠のいたが、インフレと景気減速の端境にある。投資家の目は1-3月期の企業業績に移っている。週初発表の小売り売上高が前月比0.7%増で市場予想を上回ったことを発端として上昇基調が固まった。インテル等企業全般が1-3月期の業績の好調さを維持していることで、市場の雰囲気を明るくした。マクロの経済指標のCPI(前月比0.6%増)、住宅着工(前月比0.8%増)、工業生産指数(0.2%減)はあまり市場には影響しなかった。日米とも企業業績一点を凝視している格好だが、発表が先行している米国の堅調さが目立った。外国為替であるが、欧州の堅調な経済と金利先高感で対ドル、対円とも急進した。対円では162円台と市場最高値を大幅更新した。欧州向け輸出が多い企業にとって業績上ぶれ要因である。ドル/円は117円~119円台で推移しており、大きなインパクトになっていない。「円借り取引」も復活しており、現行の金利差が続く限りこの程度の為替相場が続くであろう。日本の金利であるが、翌日物金利は政策誘導金利0.5%前後で推移しているが、長期金利(10年)は1.6%後半~1.7%前半で推移しており、大きな変動は無かった。ただ、27日発表の「展望レポート」により政策金利早期利上げの思惑が働き、中短期の金利が上昇し超長期金利が下落する現象で期間別金利差が縮小傾向にある。いずれにしても、金利の激変は考えられず景気に対する影響はさほどない。政策金利上げも来年までないと予想する。◎要注目 東芝、事業の選択と集中が活発。業績回復傾向に拍車。音楽・映像ソフトから撤退証券会社決算減益。個人投資家の取引先細りが主因三菱重工、石炭ガス発電機米で攻勢。同社の積極経営際立つ電炉大手、1割減産。原料高騰と鋼材需要急増のため海外新薬の承認短縮化。研究・開発競争激化と薬品業界の淘汰表面化HOYA、ペンタックスの買収が混迷。TOBになる可能性楽天、TBS株買い増しシェアー20%へ。買収防衛策の決定を攪乱。TBS株高騰丸紅、カリブの電力事業買収へ。このところ、商社の積極経営目立つ【今週の予想】今週から07年3月の決算発表が本格化する。ハイテク・自動車・鉄鋼・商社・薬品等主要業種の増益基調が確認できれば、株価は堅調に推移する可能性が高い。だが、株価は将来の業績を見極めて動く傾向があるため、同時に発表される08年度の業績見通しも大事である。市場は増益基調を予想する向きが大勢であるが、期初の予想を低めに見通すことが多いため悲観論が台頭し、株価が調整する可能性がある。4月~5月に株価が調整するのはこのためである。M&Aの標的にされるリスクを避けるため慎重な予想をする経営者が多いのが事実。単なる慎重さだけなのか、客観的事実に基づく予想なのか見極める必要がある。一定規模以上の企業について市場予想と企業側の予想が大きく乖離すれば株価が大きく下落するパターンが過去にも観られた。企業予測のベースとなる事項として需要動向、円の動向、原材料特に原油価格動向、米国の景気減速、中国の景気過熱がある。何れにしても先々の不透明さが企業を慎重にさせている。需給面では個人投資家の動向が注目材料である。JASDAQ平均株価が8日続落している。新興市場が下げ止まらないと、市場全体の心理を冷え込ませる可能性が捨てきれない。株価指数先物裁定現物買い残の思惑的大口売りもあり、市場を大きく上下させる可能性もある。また、経済統計も株価を左右する。3月の鉱工業生産指数、CPI、日銀の「経済・物価情勢の展望」である。今後の金融政策を占う重要な材料であり、株価に大きく影響するであろう。筆者は、利上げは年明けと予想するがーー。今週の日経平均は17,000円台前半を予想する。米国NYKダウは、13,000ドル台を突破すると予想する。確かに、米景気への先行き懸念も根強く、経済指標に瞬間的に反応し下押しする局面もあるが、良好な企業業績が押し返すと考える。13,200ドル程度まで上昇すると予想する。(経済指標:3月の耐久財受注、1-3月のGDP速報) 以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年4月8日 過去振り返り週間号
平成19年4月8日【先週の概況】4月2日、日銀短観が発表された。市場がポイントとしてみる「大企業製造業」の景況感は前回に比べ1年ぶり2ポイント低下した。その背景はこの調査期間が2月後半から3月30日までであるため、世界株価連鎖安の発生と住宅問題を抱える米経済に不安の増幅した事と、円が115円まで上昇した時期と重なった事である。大企業非製造業はほぼ横這い、設備投資も増勢を失っていない、雇用環境は人手不足の数値がでているので、今回の調査結果は一時的と考える。ただ、小売り、サービスには明るさが見える。この様な結果に当日の株式市場はじわりと反応した。先物裁定現物売りに押されて大きく下落したことが主因であるが、「短観」の結果で買い控えに繋がった。業種別銘柄では鉄鋼、造船、非鉄金属の業況判断DIが大幅悪化を示したため、大きく値を下げた。ところが、一変翌日は先物裁定買いが入り、前日のNYKダウの上昇が主因で日経平均は215円高で引けた。さらに翌日(4日)日経平均は300円台と大きく上げた。要因として、NYKダウ高、円安、原油安という外部要因である。要するに、「短観」というイベント等に日経平均は左右されるが、それ以外の日は米国景気、NYKダウ、円に左右される構図である。需給関係では、売買高の60%程度を占める外国人売買と先物裁定売買が値幅を増幅する。個別銘柄では、・ エデイオン、ビッグカメラ統合撤回で株価が大きく下落した。・ 日本国内での06年度新車販売が前年比8.3%減った。輸出依存状態が顕著である。普通自動車が軽自動車に押されているのが現状。因みに軽の分野では、ダイハツがスズキを販売面で追い抜いた。軽自動車依存が顕著である。・ 灰色金利問題で三洋信販が801億円赤字に転落した。・ ケンウッドが、07年度純利益が87%減ったにも拘わらず、米国の無線システムジートロンの買収を発表。今後の業績展開は不透明。・ 野沢屋と合併する大丸が6期連続最高益であった。合併により、収益基盤が益々確固たるものになる。・ 任天堂07年度62%増益。ゲーム機がソニー製品を大きく凌駕した。・ 新日鉄07-08年度投資3000億円上積みし、自社株買いも活発である。株主重視政策である。ただし、他の設備産業と同様に今年度は税制改正(原価償却費増)で利益が圧迫される。・ 日本の設備投資を反映し、森精機が07年度の営業益47%増。【今週の予想】日経平均に影響するのは、先ずは円/ドル相場である。その前に米国景気に関するニュースである。FOMCの議事録が発表される。FRB議長発言は「景気減速と物価上昇」両睨みの姿勢である。住宅減速とサブプライムローンおよび企業業績の減速で景気後退懸念がある一方、原油先物(WTI)の上昇や労働単価の上昇によるインフレ懸念である。一部市場では利下げ期待があるがもう少し様子見姿勢を続けるであろう。政策を誤ると、スタグフレーション(景気後退下のインフレ)に陥る可能性も意識されつつある。そうなると、最悪のシナリオとなる。先週末の米国雇用統計では失業率が4.4%に改善し、雇用は18万人増と好調な数字であった。円も119円まで下落した。まだ、米国経済は巡航速度を保っていると言える。当日米国はイースター休暇で、米株式市場に対する影響は週初にでてくる。景気指標はまだら模様であり、はっきりした姿は不明瞭である。従って、市場は比較的慎重になる可能性がある。一応、足下は118円~119円と円安傾向が強いので、日本では輸出株を中心として好影響を及ぼすであろう。ただし、13日に開催されるG7の7カ国財務相・中央銀行総裁会議で円安をテーマとした議題がでてくると様相がかなり違ってくる。円高に振れる可能性がある。日本の株式相場は、米国の雇用統計と円安で堅調に推移する見通しが立つ。週末はSQ算出日であるが、そう大きく波乱材料にならないであろう。しかし、翌週から07年度企業業績発表、米国も四半期の決算発表が控えており、市場は様子見の姿勢を強める可能性も捨てきれない。商いが細る可能性がある。小売業の2月期決算が迫っているが、決算数値が対計画比下回り、かつ今期の業績予想が市場予想を下回る可能性があり売られる可能性がある。概ね各企業は好業績を確保した模様であり、今期の予想の法が株価への影響が大きい。経済指標では11日に「機械受注」が公表されるが、若干前月比マイナスとなり予想の範囲内で大きく株価に影響しないと予想する。9日、10日の金融政策決定会合が開かれるが、利上げはないと断言できる。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年4月1日 過去振り返り週間号
平成19年4月1日【先週の概況】先週は2006年期末の週であった。筆者の青春時代のシンボル的存在であった植木等が享年80歳で死去された。心臓の持病をもちながら最後まで頑張ったとの旨。男子本懐でありご冥福を祈る。もう1つ、能登半島で強度な地震が発生し、多くの被害をもたらした。今のところ企業群の工場は正常稼働しており、日本の景気への悪影響は無い模様。被災者の早い立ち直りを切に希望する。日経平均は26日の配当取り最終日まで、先週からの上昇基調を保ち17,500円台を維持していたが、結局期末には17,283円で終わった。27、28日両日の下げが響いた。27日は、5日間で777円上昇したことで高値警戒感が強くなり、NYKダウが一時大幅下落したことも追い打ちをかけた。配当落ちで高配当銘柄が売られた。28日は117円台に1円近く円高となったのが主因である。やはり日経平均株価は円高が強まると下げる。この日の円高は、米国の経済指標(3月の米消費者信頼感指数の悪化、新築住宅販売軒数が7年ぶり低水準)が弱く、米景気に対する悲観的見方が市場を支配した。中東情勢に対する懸念もドル売りに拍車をかけた。さて、日本の景気であるが、緩やかであるが成長過程が継続している。増益基調にある企業業績、旺盛な設備投資と海外実需が牽引している。最大の懸案である個人消費も持ち直す兆しがある。しかし、まだ機関車の動力車輪にはなり得ていない。確かに、団塊世代の消費が少しずつ増えている。多額の退職金を自分の趣味に回す消費である。一方、完全失業率も4.0%と勤労者も増えている。しかし、消費は今一つ冴えない。雇用者所得は毎年平均1%伸びているのに、1人当たり賃金は伸びていない。(1月は2年連続マイナス)結局今までの消費の支えは雇用者が増えた要因である。企業側の労働分配率の低さに原因があることは今更言うまでのこともない。企業は、配当・自社株買いで株主に報い、残りのキャッシュは設備投資に回している。一方リスクは米国の景気と円高である。米国はインフレか景気後退の端境にあり、FRBの政策は難しい選択を迫られている。住宅問題を抱えて政策金利引き下げの期待もあるのだがーー。個別の銘柄については・ 伊勢丹・東急百貨店の提携が、情報力等で軌道に乗っていくかが命運を制する。・ 新日鉄がミタルと提携を拡大。同社の世界戦略が試されている。また、同社はインドで生産へ。経済が高度成長しているBRICSへの自動車等需要家の進出が影響した。・ 加ト吉、架空取引の疑いが発覚。巧妙な手口での粉飾であるが、企業の法令遵守が改めて問われている。・ 不二屋が山崎パンの傘下に入り、山崎パンは1兆円企業が展望できる。・ オリコが2,900億円増資。ミズホHDと伊藤忠が出資。・ 三洋電機人事混乱収拾へ。業績回復には相当の時間がかかる。・ 第一興商、ヤクルト、三菱電機、三井造船、住友不動産、ニコン各社決算最高値。・ 大手銀行、株の含み益が8.6兆円。貸し出し金利引き上げ遅れをカバー。【今週の予想】4月2日から新年度入りで、株式市場も名実ともに新年度入りする。新聞記事コラムに記載してあったが、4月の株式相場は機関投資家の新年度資金の流入に伴う上昇が期待されるが、2003年以降の平均は1.98%の下落だそうである。理由は、主要企業が3月期決算と同時に発表する業績予想が慎重で失望売りが出やすいためである。ただし、03年、05年は4月急落後年末までに40~47%上昇した。今年度も先例通りになるか?さて、今週の相場はどうか?上述したように機関投資家の新規資金の流入が期待でき、また仕掛け的株価指数先物の裁定取引の現物売りもボリュームは大きくなく、需給面は問題なしと思う。4月3日に「日銀短観」が発表される。ポイントである大企業製造業の景況感である。市場の大方の予想は弱冠の低下であるが、強めにでると日経平均を大きく押し上げる要因となる。しかし消費者物価が弱い。2月消費者物価指数が前年同月比マイナス0.1%であった。消費支出は1.3%増であったが、消費関連がまだ弱い。もう1つの要因としては、やはり米景気の行方と円高である。この要因は市場に対してネガテイブに作用するであろう。米景気は企業業績の減速感、サブプライム住宅ローン機関の破綻、同問題の影響による消費減速、イラン問題の地政学リスク等景気後退や市場心理悪化の要因が山積みである。FRB議長はまだ、景気後退とインフレリスク両睨みの姿勢である。先月の議長の議会発言で、市場は利下げを待望していただけに株式の大幅下落を招いた。3月の新車販売、小売り大手売り上げ、雇用統計が発表されるので、その指標によってNYKダウは値動きの荒い展開になると予想する。円相場は米の経済指標の動向で、一進一退の展開になるであろう。レンジとして116~120円を予想する。仮に、115円より円高が進むと日本の株価が輸出産業を中心に下押しするであろう。結局円相場も米景気次第となる。日経平均は日米景気睨み、膠着感が強い相場展開になると予想する。突発的M&Aがあると業界再編期待で株価を押し上げる要因も忘れてならない。参考であるが、企業業績に影響を与える税制改革が控えている。減価償却期間の短縮と償却限度の変更である。(取得価格の95%→100%)減益要因であると同時に減税である。その分設備投資増加の余力が生まれる。もう1つ参考であるが、業界を一変させる商品が実用化されようとしている。有機ELという商品である。薄くて形が変幻自在になる照明で、将来9兆円の市場になると予想されている。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年3月25日 過去振り返り週間号
平成19年3月25日 【先週の概況】先週は日経平均とNYKダウとも続伸を続けた。2回の世界連鎖安を経てようやく市場心理も落ち着き、内外の投資家はリスクテイク余力が高まった。金利の安い円を借り、新興国や資源産出国に投資をする「円借り取引」が再開し、円が117円~118円台前半と落ち着いている。輸入企業のドル買いと個人による外為証拠金取引の活発さも円の安定に寄与している。現に、豪ドル、英ポンド(資源国通貨)が対円、対ドル共に上昇しているではないか!原油も米国のWTIで3日続落後57ドル台/1バーレルから61ドル台まで上昇してきている。世界中を駆け巡る余資がリスク資産を求めて積極的になっている。先週はFOMCでFF金利利上げが見送りとなった。会合終了後の声明で利上げ再開の表現を修正し、今後の情勢次第で利上げ、利下げのどちらにでも柔軟に動く姿勢を示した。ポイントは「サブプライムローン」問題を意識した文言である。このローンの取り扱い業者が借入れ者の破綻や延滞で業績が悪化し、既に業務停止が20社を超えた。この業界に融資している金融機関にもいずれ波及する懸念がある。FRB当局も大きなリスク要因と視たと思われる。FOMC後NYK株は159ドル高と急伸した。市場の1部の予測では利下げの可能性もあったが、CPI上昇も配慮し利下げはなかった。さて、日本でも日銀政策金利決定会合が開催されて、当然ながら利上げ見送りとなった。FOMCの決定が市場に大きな影響があったが、日銀の決定は影が薄かった。日本の株価の推移は米国の景況感や株価の上昇、円安、株価指数先物裁定買残の減少の好材料が重なり4連続上昇した。円安、米国の景況感、NYK株価が日本の株価(特に輸出値がさ株)に反映した。現行、日本の株価の需給構造は期末配当取りの個人の買い、アジア勢の買い、欧米投資家の売りの構図である。国内の景気であるが、消費とCPIがポイントである。早く景気の機関車を設備投資と海外要因から個人消費に移行させる必要がある。上場企業の株主配当が純利益の半分を占めるとある。勤労者に配分を多くしてもよいはずである。M&Aに備えた防衛策の一環であろう。個別の企業、業界では・ 電力業界で原子力事故の事実が表面化している。事故の大小に拘らず、大きな社会問題化しつつあり、投資家の懸念を招く可能性。・ 森精機が米国の工作機械販社を買収。米国での売上拡大期待が大きい。・ 土地の公示価格が全国平均で0.4%と16年ぶりに上昇(3大都市圏中心)したが、不動産株の株価に大きなインパクトを与えず翌日には反落した。・ 日立がリストラを加速。HDD小田原工場の生産中止、メキシコ工場の4,500人解雇。市場がリストラ策を評価し、株価上昇。・ 富士通をはじめ、大手企業が子会社評価損を計上。年度末決算への影響度合い不透明。・ マツダ、15年ぶりに100万台販売計画。強気な計画である。・ 中外製薬、タミフル問題で販売・収益計画に狂い。市場はどうみるか?・ 信越化学工業、直江津工場火災により同工場の操業停止へ。業績に対する影響必至。・ 日産の販売不振続く。今後、どういう計画で業容拡大を図るか?・ 14地銀システム共同開発へ。コスト削減と将来の合併のし易さを注視。・ 米GEが三洋クレジット買収。三洋電気再建にリストラ加速。・ ペンタックスの株が急騰。HOYAとの合併を控え、合併比率見直される可能性大。・ シチズンが携帯用カメラ部品、小型液晶から撤退で、特損100億円計上。電子部品価格競争激化で計画達成不可能と判断。・ ヤマハ、西部HDと同様にリゾート4施設売却。リストラの一環。・ 2009年3月期からリース物件を強制的に貸借対照表に計上義務化。リース業界に影響大である。【今週の予想】日経平均の先週4日間の上昇幅は736円に達した。2回の世界連鎖安から戻りが急速であったことに警戒感が強まっている。スピード調整が必要な場面であろう。17,500円前後まで上昇すると、戻り待ち売りがでてくる可能性がある。年度末までに日経平均が18,000円台を伺うと筆者は予想と期待していたが実現するか微妙である。あと600円程度上昇すれば、18,000円台に到達する。その為には、細り気味な商いが25億株以上、売買代金で3兆円以上の大商いが続くと、筆者の期待に沿うかもしれない。しかし、現在は連鎖安からちょうど半値返しにあり、25日移動平均に近い水準あたりである。このことから相場が乱高下しない可能性大である。26日は配当権利付き最終売買日であり、配当狙いの買いと国内フアンドの運用成績改善を狙った買い程度しか期待出来ない。指数先物の裁定買い残がかなり減少しているので、裁定解消売りでの大幅下落はないと予想する。売り越し状態にある外国人投資家の買いにも期待したい。30日にCPI発表があるが、マイナスの予想が多い。利上げを云々する時期ではない。米国の株価は、引き続き連鎖安からの戻りを試す展開になる可能性がある。先週は5連騰であり、2月の住宅着工件数が前月比9%増であったことから、完全に市場心理は改善している。FOMCで利下げ期待が展望できることも市場にはプラスである。マクロの経済指標の改善に素直に反応する展開になる。今後、住宅販売件数、耐久財新規受注額、消費者信頼感指数が発表され、敏感に反応するであろう。NYKダウは12,550ドル前後まで上昇する可能性大である。日経平均はドル/円と米国経済に左右されるが、最近の北朝鮮問題が地政学リスクとして要注意である。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年3月18日 過去振り返り週間号
平成19年3月18日【先週の概況】 先週1週間の日経平均は従前と同じく、山あり谷ありの荒れ相場であった。山は低く谷は深い様相である。2月の後半から、それまで18,200円台で上昇気流に乗っていたのが嘘のようである。市場心理の繊細さは、1方向に傾くと雪崩のように一気に流れてしまう。前回の同時世界株安は中国上海市場の大幅下落が発端であったが、今回の大幅下落はNYK発である。日本を含めたアジア、欧州と全面安が連鎖した訳であるが、日本に限ってみると、円高と米景気の動向が市場心理を不安定にしている。円高は「円借り取引」の巻き戻しでの円買いに因るものである。今まで、安い金利の円を借り他通貨に替えて運用していたが、運用を回収しその資金を円に戻しているため円買いが発生している。市場推計では「円借り取引」は20兆円程度と踏んでいる。株式市場の下落を受けて、その資金は債券に流れ、長期金利(新発10年物国債利回り)が1.5%後半まで低下している。(国債価格は上昇)一方、米国の景気はどうか?現在、日本の株価は、NYKの株価より米国の景気そのものに影響を受けている。米国景気はGDPが2%台で推移しており比較的安定している。問題は、「サブプライム住宅ローン」問題がじわじわと顕在化しており、住宅市場冷え込みの影響が経済全体に波及するとの不安である。NYSE(NYK証券取引所)が破綻や延滞により経営悪化した同住宅ローン大手を上場廃止したことが、ますます、景気悪化懸念を現実なものとして嫌気された。いずれ、大手銀行の経営にも影響すると懸念されている。2月の小売売上高が前月比0.1%増と低水準であったことも、景気悪化懸念を増幅することとなった。もっとも、週末発表のCPIは前月比0.4%上昇、3か月連続上昇である。米国の経済指標は強弱入り乱れており先が不透明である。市場心理が一点に集中し過ぎていないか?日本では、株価は調整局面であるが、昨年の10-12月のGDP改定値が5.5%と大幅上昇しており、内需主導の成長が続いている。ただし、国内物価の動きを示すGDPデフレーターはマイナス0.5%と速報値と変化無く、デフレの脱却とは言えない。次に、国内外でのM&A、企業不祥事、業績不振が頻発している。・ 日興株、一転上場維持となりシテイーグループのTOB価格が1,700円/株に引き上げられた。日興株大幅高。・ 日立の子会社日本サーボを日本電産に売却。日立の決算は最悪で、選択と集中の一環。・ 大日本印刷、個人情報863万件流出した。情報管理に関し上層部の認識が甘い。・ 大丸・松坂屋9月統合。日本最大のデパート誕生(伊勢丹を売上高で凌駕する)。・ 薬品のエーザイ、純利益最高(アルツハイマー治療薬が海外で堅調)、一方中外薬品がタミフル副作用問題で株売られる。・ 三菱重工が米国の原子力発電所2基受注。重工と関連部品会社に恩恵が大きい。・ 損保10社、不払い問題で一定期間業務停止処分。いつまで続く生/損保の不払い発覚。・ 電力各社で原子力機器の障害隠蔽工作。法令順守精神の欠如。・ 日産、3工場で減産。ゴーン体制で復活後の販売不振建て直しの戦略は?【今週の予想】2週連続で下落した日経平均の今週の焦点は、やはり米国経済と円高である。米国では20日、21日にFOMCが開催される。FF金利は据え置かれるであろうが、サブプライム住宅ローン問題が益々深刻となり、一縷の利下げの可能性がある。現在の米国景気はGDPが2%台で推移しており、巡航速度を保っている。しかし、前FRB議長が「年後半に景気減速に陥る」と発言したが、住宅不況が回復せずにこのまま横這いまたは下落したら、その発言が現実なものになる。あながち無視出来ない発言といえる。景気は、今ある悪材料に適切に対応しておかないと数ヶ月先に悪く変化するものである。住宅産業は裾野が広く、他の産業分野に影響をきたし、じわじわと地を這うように影響する。今週に相次いで発表される住宅関連指標が最大の注目材料である。かたや、先週末発表のあったCPI(0.4%上昇)でインフレ懸念が顕在していると考えられれば、FRBはどう舵をとるか難しい判断を迫られる。会合後の声明の表現を注視する必要がある。さてドル/円相場であるが、「円借り取引」は残高が20兆円あると推定されているが、巻き戻しが一巡したのではないか?欧州のECBが利上げして、ユーロがドルと円に対しユーロ高になったように米国の景気と日米の金利差に着目し直すのではないか。117円~119円での動きだと考える。さて、日本の景気と株価はどうであろうか?06年10~12月のGDPは年率5.5%と好調さを保っている。景気拡大最長記録を達成しているが、良好な企業業績、堅調な設備投資と海外輸出に支えられている。しかし、CPIと個人消費が他項目に比べて弱い。大手電機、鉄鋼等が1,000円(渋い金額)賃上げ実施といわれているが、この賃上げが中小企業に波及しなければ消費増に直ぐには結びつかない。それに賃上げ実施は7月であろうから、秋口以降にしか消費は改善しないであろう。ここに、景気の現状に対し、不気味な現象が現れている。短期金利と長期金利の金利差が縮小している。政策金利上げと円借り取引巻き戻しによる安全資産(国債)逃避による長期金利低下が要因である。期間別金利を結んだ曲線(イールドカーブ)が平らになると、景気後退のシグナルと言われている。さて、日経平均株価であるが、日米の景気動向を睨みながらの売買が交錯する展開であろう。米国減速懸念の強まり、円高と各企業の期末決算予想、公示地価(22日発表)と外部環境に振り回される。この要因がどうなるかで日経平均は決まってくるといっても言い過ぎではない。19~20日に開催される日銀の金融政策決定会合では、政策金利は据え置きであろうが、議長の発言内容によっては株価に対する影響が出てくる。外国人売りと期末配当狙いの個人投資家の買いが綱引きをしながら、17,000円を目指す展開となると考える。注目銘柄では、三菱重工 東芝 大日本印刷 日立 東芝 大丸 松坂屋 損保業界 電力業界 日産 テルモ キッコーマン 明治海運以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年3月11日 過去振り返り週間号
平成19年3月11日【先週の概況】先週の株式市場は先々週の世界市場の連鎖安に引きずられた大幅反落の地合いを引き継ぎ、週初まで安値を更新し、日経平均は16000円央まで落ち込んだ。その後、3月7日に調整したが安値の更新は一服し、17100円台まで回復して今週を終えた。ボリュームの比較的小さな香港市場の下げが全世界の市場を震撼させた訳であるが、ヘッジフアンド等のリスクマネーの逃避を誘発した。その原因は「円借り取引」の手仕舞いである。フアンドが金利の低い円を借りて、ドルや高金利の資源国市場に投資していたその資金を回収し、原資を今までとは逆に円に交換し(円買)借りていた円を返済した訳である。その証拠に、日本での銀行間取引市場で外国銀行の借り入れ意欲が減退した。また、米国の長期金利が下落(価格は上昇)した。リスクテーカーがリスクを避け安全資産に逃避した。この状況を引き起こした原因のルーツは日銀の政策金利引き上げではないか?逆にこの連鎖安を断ち切った要因として、ECB(ユーロ中央銀行)の利上げではないか。日本の円相場はあくまで他通貨との金利差で決定されていたため、日本の政策金利利上げが今回の世界連鎖安のマグマを貯めていたのである。米国の貿易収支赤字幅の減少もドル/円相場には大勢を決める要因になっていない。一時115円台まで急進し114円台まで上昇すると思われたが、週末NYKマーケットでは118円まで戻している。3月期末を迎える企業(特に輸出関連企業)にとって、この円安にはほっとしたのではないか。円安が収益押し上げ要因であるためである。米国のNYKマーケットも株連鎖安にみまわれたが、日本だけでなく全世界の経済を牽引している米国経済はまだ、ソフトランデイングの見極めが付かない。3月7日発表されたベージュブック(9地区FRBの地域経済の集約報告)は弱冠弱含みの景気認識であり、3月8日発表の小売り売上高も2.5%と伸びが鈍化したのがマイナス要因であるが、週末発表の雇用統計は比較的堅調であった。懸念されるのは住宅関連の指標と「サブプライム」の破綻、焦げ付きの増加である。当面、FF金利は据え置きであろう。個別銘柄・業種では、・ コマツが4期連続最高益。優良企業の首位にも選ばれた。・ 日興コーデイアルにCITYグループが最大のTOB実施。日興の他大口株主のフアンドが価格面で難色。(2000円/株が適正価格では?)・ シオンがダイエー、マルエツ株取得へ。群雄割拠の小売業界再編加速。今後は百貨店、スーパー、コンビニ等の業界同士の競争になる。専門小売りでもAOKIがマルフルにTOBを実施予定。・ 後発医薬品大手で、自社薬品普及遅れで在庫水準高まり、収益圧迫要因。・ 松下電器がビクター売却を入札制へ。最大のネックであるビクターを売却し、目標の売上高営業利益率10%に一歩近づく。【今週の予想】NYKダウが先週末小幅上昇、アジア諸国株価市場の落ち着きから、日経平均は大きく下落することはないと考える。また、円は118円から120円近辺に落ち着く可能性、先物裁定買い残が減少傾向にあることも援軍である。投資家心理も落ち着いており、企業業績好調で投資環境も良好になっている。急騰し、18000円台にすぐ戻すことはないが、じわじわと上値を更新する展開となるのではないか。戻りは鈍いかもしれないがー。さて、日本の景気と相場に影響を与える米国であるが、先ず、FF金利の次回利上げはない。企業業績と設備投資は堅調であるが、小売り、雇用面での指標が鈍化している。それと住宅関連が底を打ったもののまだ復調に至っていない。それに伴う高金利住宅ローン金融機関の破綻・延滞が増加傾向にある。今は大きな問題になっていないが不安要因である。元来、米国では住宅の価格が担保価格以上になると、余った価値相当分を借り換え消費に回す傾向にあり消費の堅調さを保っていた。13日発表の小売り売上高と16日のCPIの指標によって、市場はどう観るか(インフレ懸念か、軟着陸か)?何れにしても、米国の景気が良好でないと輸出主導で好景気を持続している日本の景気に多大の影響がある。日本の話題にもどるが、次の政策金利利上げはいつか?足下のCPIは0%付近を這っている。先々、CPIを押し上げる要因はない。筆者は次の利上げは来年の春先ではないかと考えている。理由は労働収益分配率が少し上昇しているが、今回の賃上げと来春の賃上げがどの程度の数字になるかを見極める必要がある。住民税の増税や税額控除廃止が控えているのでその影響はどうか?好景気は企業収益・設備投資がもっており、GDPの50~60%を占める個人消費にバトンタッチしないと好景気持続が息切れしてくる懸念がある。早く個人消費が盛り上がり、内需主導の好景気持続が望まれる。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年3月4日 過去振り返り週間号
平成19年3月4日【先週の概況】先週の株式市場は、週央の上海株の急落を発端とした世界中の株式連鎖安に尽きる。その余波はNYK、日経ともまだ続いている。日経平均は絶好調で18,200円台を回復したのが26日(月)で、市場が宴を謳歌していた直後猛烈な嵐に襲われた。27日(火)は、昨年来高値を更新し続けたため、日経平均は高値警戒感と利益確定売りに押されて約95円下げた。市場ではスピード調整と見ていた。比較的楽観視していたその翌日に世界同時株安に見舞われた。原因として中国上海市場で過去最大の下落したことである。中国政策当局の政策変更の思惑が原因である。中国の市場の脆弱性が見て取れる。見方を変えれば、中国の経済・市場が世界の相場に影響する程になったのか?欧州は別として、米国と日本は相場に影響する問題点が燻っていたタイミングだったため大きく波及したと考える。米国では景気軟着陸に対する不透明感がでてきたし、グリンスパーン前FRB議長の「景気後退の可能性」発言、住宅関連指標の悪化と「サブプライム」という高めの金利で低所得者層向けに貸し出す住宅ローン金融機関の破綻が増加、イランに拘る地政学リスク、GDP確定値の下方修正等(2.2%)である。おまけに市場取引の急増に対する市場システムの脆弱さも誘発した。「サーキットブレイカー」(株価の急激な動きに対し市場を一定時間休止すること)という言葉も久し振りに聞いた。FRBは様子見気分であるが、利下げも視野にいれておく必要があると考える。一方、日本では企業業績と期末決算予想の数字で順調に値上がりしてきたが、いっぺんに吹き飛んだ。日本独自の要因では、会計・監査不信問題(日興・三洋電気・ソフトバンクと会計監査会社「みすず」の解散)、過去最高水準にある先物裁定残高の累積、円高である。円高はいわゆる「円借り取引」の巻き返しである。円高は円安で潤ってきた特に輸出関連企業の業績に大きく影響する。日米とも投資資金がリスクを恐れて安全資産に逃避したのであり、日本の長期金利(10年物国債利回り)が一時1.5%台まで低下(債券価格上昇)した。株価に焦点が当たって目立たなかったが、重要な経済指標が発表された。1月の鉱工業生産指数が横ばい、CPIも0%と横ばいであった。消費支出が0.6%増であったものの、生産・消費サイド双方とも冴えない数字である。2月の利上げは正しかったのか?このような情勢下、個別業種・企業をみると、・ 日興コーデイアル上場廃止されるか分水嶺に差し掛かっている。・ 丸紅が、純利益63%増・ 名古屋地下鉄談合ゼネコン5社告発されるが、株価に影響大。・ 積水ハウス経常益41%増・ アドテスト営業益23%増・ 大手銀行は、政策金利引き上げ、債券価格上昇は収益増要因であるが、期末での株式と円の評価損益に不透明さがでてきた。【今週の予想】今週も先週のグローバルな株安を引きずるかどうか?趨勢的にみて、今週以降も株安が続くとみる。焦点はやはり、円/ドルの動向と米国経済である。先ずは円/ドル相場である。先週前半まで、121円台であった円/ドル相場が世界同時株安時を境に116円台まで円が急騰した。市場別でみると日本に比べ欧米市場で円高進行が急激である。この事実は欧米のヘッジフアンドが「円借り取引」を解消していることに起因している。回収したドル等を自国の債券に移しているので、長期金利が低下していることになる。一方日本では、輸入関連企業の先物ドル買い、個人の外為証拠金取引によるドル買いが継続しているためである。どちらが強いかは不明であるが、筆者は「円借り取引」解消のドル買い戻しが強く、暫くは円高に拍車がかかり115円/ドルを突破すると考える。一方、米国の景気は軟着陸するか不透明になってきている。米国も含めて世界経済への懸念が高まり、米国自身の景気先行きの見方が不安定になりつつある。GDPの確定値も2%台で巡航速度の3%半ばには遠いし、利上げによりサブプライム住宅ローン貸し出し金融機関に焦げ付きが増えていることが深刻度合いを増している。今週末に発表される雇用統計、貿易統計が発表されるが、過去のデーターであり、今回の株安後の景気、株式相場の変化に影響を与えないであろう。利下げに舵をきる局面だと考える。日本でも、円/ドル相場が焦点である。円高になると、輸出関連企業の収益に負の影響があり、国内関連企業には影響がないとしても、輸出で回復してきた日本経済に暗雲が漂う。その他にも、株式相場に影響する懸念材料が目白押しである。SQ算出を控え、累積している裁定取引先物売り圧力、押し目買い資金獲得するための国内勢の換金売り、悪材料に敏感に反応する市場心理、個別企業の会計不信、ゼネコンの談合問題、個別企業の製品欠陥発生(レノボの三洋電機製リチュームの欠陥等)、株式取得機構の三菱商事、任天堂株売り出し等等、波乱要因が多い。それと、マクロの景気指標のうちCPIが0%であったこと、鉱工業生産指数の低下、米国景気の不透明さも不安定要素として追加せねばならない。日米とも株価調整、長期金利低下傾向が今週も含めて続く可能性大である。3月決算前で全ての面で上昇基調が望まれる。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年2月25日 過去振り返り週間号
平成19年2月25日【先週の概況】先週のビッグイベントは、20日と21日に開催された日銀政策決定会合で政策金利である無担保翌日物金利(俗称「無担保コール取引」と呼ばれ、毎日、各銀行が資金過不足調整する市場の金利)が0.25%引き上げられて、即日実施されたことである。まさに3度目の正直である。今回は表だった政治的圧力は無かった。前週発表の昨年10-12期のGDP(国内総生産)速報値が4.8%増加と決定打になったと思う。消費と消費者物価にまだ弱い面があるのも事実であるが、今後趨勢的に強くなると踏んだと思われる。もう1つの判断材料は米景気のソフトランデイングが見通せるようになったことである。今後、銀行の預金金利と貸し出し金利(短プラレート)が引き上げられる。緩和的環境維持と金利調整はゆっくり進めて行くとの総裁発言が強烈な印象を与え、マーケットは冷静そのものであった。それまで、マーケットでは利上げを60%程度見込んでいたが、投資家心理は気迷い気分であった。視界が晴れ、日経平均は翌日から大きく買われ、週末は終値で18,100円台をつけた。東証TOPIX(株価指数先物)は15年3カ月ぶりに1、800台をつけた。当日は売買高が30億株を超えて大商いであった。一方、円高になると予想されたが、欧米との金利差は依然として大きく、むしろ利上げ決定前より円安方向に進んだ(週初119円台→週末121円台/ドル)。円借り取引(円を調達し、ドル転して外貨で運用する取引――「円キャリー取引」といわれている)も再開されている。輸出関連企業にとって円安効果は変わらない。ユーロは160円にせまっている。また、利上げは、中小・零細企業にとって影響が顕在するが、財務体質が健全な大企業にとっては軽微な影響で済む。家計にとっても、金利上昇の恩恵で消費にはプラスとなる可能性がある。企業はM&Aに備え、設備投資と株主配当を厚くしているが、従業員への給与への配分を増やせば、もっと消費が伸びるのだがーー。個別各社の話題に移ろう。相変わらずM&Aと不祥事が目に付く。・ 前週発表された大丸・松坂屋の統合計画発表により、両社の株価急騰。・ 山崎製パンが不二屋との救済の延長として、製造・販売も提携。山崎製パンの拡大路線か?・ パイロット営業益52%増。地味ではあるが、堅実さが売り物。・ JALの減益率拡大。どこまで落ちるのか?何かアクシデントが発生したら大混乱に陥る。・ 東京鐵鋼、大阪製鐵傘下入り否決。個人株主の影響力大。以前は、個人株主はサイレントマジョリテイであったが、時代の変化を感ずる。・ 積水ハウス、今期も最高益。・ 三洋、不適切損失処理の疑い。膿を出しきらないと再生は難しい。・ ヤマハ発動機、中国に不正輸出。(外国為替管理法違反)・ 消費者金融、信販会社 返還請求引き当てで今期業績一段と悪化。【今週の予想】今週は18,000円台まで上げた日経平均に影響しそうなのが、米国の経済と調整局面のNYKダウと予想される。NYKダウは先週央から下げ基調になって、週間で120ドル下落した。その要因として、ここにきてインフレ懸念が再燃してきたことである。21日に発表されたCPIはコア指数(エネルギーと食品除く指数)が前月比0.3%上昇と昨年6月以来の伸びを示した。市場は再び政策金利の利下げを意識しつつあっただけに、お門違いの数値で驚いた。1月末のFOMC議事録で、インフレ懸念が大勢であったことが判明し、その数値を裏付けた格好。そこにイランの核開発問題(地政学リスク)、住宅市場の悪化懸念、原油高が輪をかけた。以上がNYKダウ(ナスダック含む)の調整局面の主要因である。今週3月1日に発表されるPCE(個人消費支出物価指数)の発表が焦点になる。また、27,28日に発表になる住宅関連数値によっても株価が左右される。米国経済のソフトランデイングが望まれるが。米国経済とNYKダウに影響を受ける可能性がある日経ダウはどうか。基調的には先週の地合いを引き継ぐ公算が大きい。先週の政策金利利上げにも拘わらず、投資環境は影響されなかったし、金利も低位安定を保った。為替はむしろ円安になった。市場は、次回金利上げは当面無い(参議院選挙以降)との予測が買い安心感を誘った感が否めない。ただ、需給面で裁定買い残が空前の約5兆6千億円まで積み上がっており、裁定解消売りに押される局面があり、相場全体の過熱感と相俟って大きく調整する可能性も捨てきれない。円安基調がいつまで続くかも不透明である。日経ダウは18,000円台を挟む動きと予想する。気になる銘柄は、業績低迷のJAL、不適切経理処理の三洋、提携先模索中の日興コーデイアル、外国為替管理法違反のヤマハ発動機、業績一段悪化が見込まれる消費者金融、信販会社各社である。食品・薬品・鉄鋼各業界でのM&A(業務提携含む)が国内外で発表される可能性には要注目。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年2月18日 過去振り返り週間号
平成19年2月18日【先週の概況】先週のハイライトは、昨年10-12月期のGDPである。実質で前期比年率4.8%増であった。市場予想の実質年率3.7-3.8%の予想を大きく上回った。引き続き企業の設備投資が堅調に伸び、前期に大幅に落ち込んだ個人消費が2期ぶりにプラスに転じた。前期の外需主導の成長から内需主導の成長に戻った感がある。GDPの50%を占める個人消費の寄与度が大きい。ただ、GDPデフレーターは-0.5%とマイナス幅は縮小しているものの原油高の一服が主因であり、物価指数はまだ水面上下すれすれであり、基調としては弱い。企業物価(卸売物価)は1月で前年同月比2.2%伸びているのに、なかなか川下に流れて来ない。これは、増益基調の企業部門が設備投資、株主配当に資金を振り向けて従業員に配分しないのが要因である。街角景気も好調ではない。さて、国内株式市況であるが、12日は休日で市場はお休みであったが、週末を除いて高値を更新し続けた。この要因として、好調な企業業績、円安、米国NYKダウの高値更新である。週末は急ピッチな上昇から利益確定売りと円高(119円台)による売りが優勢であったが下げ渋り、小幅安で引けた。連日の売買高が3兆円超(10日間)とマーケットボリュームが大きかった(大商い)。株価指数先物の買いが株価を大きく引き上げたのも特徴である。また、M&Aが散発しており、良好な市場心理となっている。米系投資フアンド ステイールがサッポロに買収提案、ゼンショーがサンデイサンにTOBを提案したこと、東京鐵鋼、大阪製鐵傘下に入る可能性等である。良好な企業業績発表がピークアウトしている中でネガテイブな銘柄も散見される。・ 西友5期連続赤字。ウオルマートの支援も無力である。・ カルソカンセ純利益95%減。・ オリコ赤字2000億円超で無配に転落、株急落。筆頭株主である伊藤忠商事の業績に悪影響必至。・ 沖電気最終赤字380億円。半導体不振と繰り延べ税金資産の取り崩しが原因。(注)繰り延べ税金資産――期末において、貸し倒れ有税引き当てした不良債権が実際に回収不能となった場合税金が返却される。戻る予定の税金を処理する資産勘定科目。相手勘定科目として株主資本に計上する。【今週の予想】先週末に明らかになった大丸・松坂屋の統合計画、一方米国でもクライスラーとGMの提携交渉と、国内外で広義の大型M&Aが連鎖的に発表されている。この事は、個別銘柄や関連業界の株価の押し上げ要因となる。規模のメリットや効率化による収益増加を期待できる。週初に、大丸・松坂屋の統合計画は日経平均の上げ要因となる。また、米シテイーグループがJDR(預託証券方式)で東証に上場する予定と報じられた。メリットとして、東証の株式市場がグローバル化し、より市場の厚みが増すこと。デメリットとして、投資資金の希薄化を通じ株価押し下げ要因として浮上してくる。さて、相場見通しに戻ろう。先ずは米国NYKダウであるが、先週のFRBパーナンキ議長の議会証言で「インフレ無き緩やかな経済成長」の表現が好感され、NYKダウが続伸している。市場の注目点は先月のFOMC議事録の内容発表であろう。先々の金融政策動向が推察できるからだ。21日発表のCPIも注目点である。現在の懸念材料は住宅関連指標の低迷と急激な原油高であろう。次に、日本の株価水準はどうなるであろうか。BOJ(日銀)の金融政策の内容が大きな焦点である。前週発表のGDPが年率4.8%であったが、その数字だけで政策決定が左右される訳ではない。中身を分析すると、GDP中50%を占める消費関連がまだ弱いことと、GDPデフレーターの数値から物価水準が水面すれすれである。先月発表のCPIの数字も含め、まだ利上げには早すぎる感が否めない。今回のGDPは7-9月GDPの反動増の声もある。国内総需要が総供給を上回っているが、決定的要因ではない。政府の間接的圧力も予想され、利上げなしと筆者は推測する。もし、利上げが決定された場合は、先ず円高傾向となり輸出関連株、有利子負債の多い不動産や電力株が利益確定売りで売られるであろう。逆に、利鞘拡大期待から金融関連が買われるであろう。一時的に株価調整局面になる可能性がある。利上げ見送りの場合は現行円相場が維持されて、金利敏感株を中心に物色される。ドル/円相場は米国政策金利に左右される。最後に東京三菱UFJ、日興コーデイアル、不動産投信(REIT)ダビンチ、電力関連の書類改竄等、個々の企業の不祥事が頻発し業務停止命令が頻発している。株価に影響するだけに、企業側のコンプライアンス重視姿勢を示して欲しい。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2007年2月11日 過去振り返り週間号
平成19年2月11日【先週の概況】阿倍政権は大丈夫か?指導力のなさ、政府税制調査会長の辞任、1部大臣の政治資金問題、厚生労働省大臣の「生む機械発言」、それに支持率の低下と枚挙に暇がない。経済運営に心細さを感じる。年央の参議院議員選挙に勝てるか?一方、1月の政策金利は据え置かれたが、政府サイドの日銀に対する圧力を感ずる。しかし、景気牽引部門が、企業部門から消費部門にバトンタッチできておらず、CPIは水面上すれすれである。政策金利を上げる局面にないと筆者は考える。2月発表のGDPにおける消費部門の力強さが、金利引き上げのポイントであろう。さて、日本の株式相場であるが、日経平均は5日と7日に大幅下落した。先週あたりから、先物裁定買い残が大幅に増加していたため、先物の仕掛け的売りが下げを増幅させた。原因として、円高反転リスク、政局不安が相場の地合いを悪くした。7日の下げも同じようなもので、他に利益確定売りや持ち高調整も下げの要因として上げられる。各企業の第三四半期や4-12月の経常利益(または純利益)の発表がピークを迎えている。大筋では好業績をあげているが(上場企業、経常益6.5%増)、ネガテイブな銘柄は日産である。ゴーン体制になって初の減益である。日立(純利益77%減)、NECの大幅減益、日航の赤字も際立つ。日航は年央の資金繰りも懸念される程である。関係機関が早く手を打たないと債務超過になる懸念もある。一方、M&Aや業務提携も相変わらず発表されており、関係する該当銘柄の押し上げ要因になっている。「アサヒビール」と「カゴメ」、「エデイオン」と「ビッグカメラ」各々が業務および資本提携すると発表。お互いの弱点を補完しあう提携であろう。鉄鋼業界、流通業界を中心に今後も合従連衡があると予想する。今年央に三角合併も解禁されることから、グローバルなM&Aも頻発しよう。(注)三角合併――外国企業が日本法人を設立し、日本企業と合併させ被合併日本企業の株主には外国企業の株式を割り当てられること。9日は日経平均が大幅上昇した。SQ(special quotation)算出を無難に通過した事と弱冠の円安が主因。円安で潤う国際優良株が買われた。売買代金が7日連続3兆円を超えており、市場の厚みが実証され、今後の相場の地合いの良さが好材料となる。【今週の予想】今週の焦点は15日発表の10-12月のGDPである。企業の業績発表はピークアウトしており、平均株価への影響力は弱くなりつつある。先週の経済指標も相場は反応薄であった。 先週発表の経済指標 景気一致指数 61%(3カ月連続50%超)街角景気指数 50%割れ(3カ月連続)機械受注 2%増GDPの数値が日経平均の高値を誘うか否かの鍵を握る。市場の予想は実質前期比3.8%である。予想の範囲内であれば株は買い進まれる可能性大である。市場予想を下回れば景気後退感から失望売りを誘う。逆に予想より大幅に上回れば、翌週の日銀金融政策決定会合における政策金利上げの思惑から、高配当銘柄や不動産株が売られるであろう。逆に金融株が利鞘拡大期待で買われる。もう1つ注目材料は消費項目である。景気拡大を何時までも企業部門が牽引していてはいずれ景気下降局面に入る。もう1つのポイントは円安の持続である。先週末の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)で、ユーロ圏からの円安に対する不満がうっ積しており、共同声明に織り込まれる可能性があったが織り込まれなかった。米国発の経済のフアンダメンタルズに基づく旨の意見が利いた結果である。これで、ドル/円が120~123円程度、ユーロ/円で158円~160円程度となり、輸出産業に対する好材料となる。為替差益が収益に対する神風となる。個別銘柄の上昇要因では、業界再編のサプライズである。最近の業界再編は週2~3件発表される傾向があり、薬品、流通、鉄鋼各業界の動きが要注意。最後に需給面では、裁定買残が5兆円強と積み上がっていること、アートネーチャー等6社が新規株式公開を予定していること等が悪材料である。なお、来期から全国市町村職員共済組合連合会がリスクをとる施策に転換し、積立金の1部(現在残4千500億円)を国内株式へ倍増させる予定であることを銘記しておく。需給面から明るい材料である。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
年が明けました 2007年2月3日から過去振り返り週間号
平成19年2月3日【先週の概況】前年後半から政治・社会・経済各分野において数多くの変化、イベント、事故があった。9月の阿部政権の発足、問題発言による閣僚の更迭、官製談合の発覚、知事等による汚職・収賄、米国での民主党勝利等等である。経済界においても、不二家の製品期限問題、日興コーデイアル証券の粉飾決算問題、東電の原発偽装工作、パロマの製品安全性等今も経済界を震撼させている。もう1つ忘れてならないのは、企業間のM&Aである。個々の企業の優勝劣敗でその関係企業の株価が大きく変動している。グローバルなM&Aも頻発している。過去の経験則によれば、猪年と米国大統領選前年の株式相場は勝つ(上昇)確率が高い年である。今年末の状況は如何に?先週央から、各企業の第三四半期の決算状況と平成6年度期末の決算予想が報道されているが、1部の企業(ソニー等)を除けば増収・増益である。優良企業は大幅増益の企業もある。IT関連の在庫調整の懸念もあるが、この好決算の大きな要因として円安と石油等資源価格の下落によるコスト減の2点に要約される。逆に資源高で潤った企業には逆風である。円も対ドル、対ユーロで各120円、157円程度であれば、輸出企業にとって安泰である。日経平均は31日(水)に比較的大きく下げた。これは、日興コーデイアルの不正経理問題が市場心理を悪化させ、先物の売りで下げ幅を大きくした。他の日は、企業の良好な四半期決算に素直に反応し小幅上昇に終始した。一方、NYKダウは週末こそ小幅下落したが、1月31日(水)に98ドル強と大きく上昇した。これは、FOMCで政策金利が5回連続据え置かれたこと、実質GDPも3.5%成長に回復したことが要因。住宅市場の1部にまだ懸念が残るものの、米景気の持ち直しと物価上昇圧力は緩和しつつあるとの判断である。日本の景気には好材料である。米国の景気と中国の経済成長が日本の景気にとって欠くべからざる存在であると断定できる。【今週の予想】日本の政策金利利上げが毎月のように燻ぶる。1月も利上げ見送りであったが、発表される経済指標がまだら模様で判断しにくいのが現状であろう。CPIが水面上すれすれの0.1%であり、本当にデフレは脱却できたか懐疑的な声も聞こえてくる。景気も本当に拡大基調であろうか?タクシーの乗車率の低下、飲み屋の客足減少と店じまい、各ハローワークの求職者で混み合い、中小企業の倒産等ミクロ面で景気の実感として悪いと思う。確かに企業部門の収益状況は絶好調である。景気循環において、景気牽引役が企業部門からGDPの60%を占める個人部門にバトンタッチしないのは、企業収益の労働分配率が低いのが主要因であるが、定率減税の廃止、年金保険料の引き上げで個人の消費マインドが萎縮している。失業率の改善(12月4.1%)、有効求人倍率1.08倍と好調であるが、家計調査の消費支出は減少、毎月勤労統計現金収入では僅か0.2%増である。これでは消費に火が付かない。このような状況下、株価はどう展開するであろうか?第三四半期決算発表がピークを迎えつつあり、今週はトヨタ、三菱地所が控えている。トヨタはグループ各企業が増益基調であったので、最高益になるであろう。三菱地所は3月の基準地価発表で増益基調は崩れず、買われるであろう。その他電子機器、輸出関連企業、内需企業は増益で買われると予想する。問題企業としては、減益を発表したソニーと日産である。両社とも製品政策の失敗が原因であり、戦略を立て直さないと株価は低位に甘んじる。不正経理問題で管理ポストにある日興コーデイアルは、当局の対応次第では上場廃止になる可能性がある。発覚時から株価は続落して、その後100円程度値上がりしたが、買いにくい銘柄である。不二家は山崎製パンの救済で持ち直す。東電の原発偽装工作も問題の拡大で売られる可能性がある。これは他の電力株にも連鎖するかもしれない。需給関係では、裁定買い残高の積みあがりによる影響や、先物の特別清算指数算出を控えた先物の仕掛け売りがでる可能性があるので要注意。もっとも、連日の3兆円を越える売買高が示すように相場の厚み・地合いは悪くないので、悪材料を吸収する余力があると考える。今週末に次週の株価に影響するイベントが2つある。1つは国内GDPの発表。2つ目はG7での円安に対する言及。(その結果次第で円高に振れて、輸出産業の収益に暗雲をもたらす)次週の株価は特に注意を要する。NYKダウは、好調な企業業績、景気のソフトランデイング、いわゆるインフレ無き経済成長が経済指標で示され、NYKダウは引き続き最高値を更新するであろう。ただ1つ懸念は原油先物が50ドルを切るまで値下がりしていたWTIが、57ドル/1バレルまで値上がりしたことである。いずれにしても、日経株には今のところ、影響を来たさないであろう。 以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年11月27日 過去振り返り週間号
平成18年11月27日【先週の概況】先週23日(木)は日本で「勤労感謝の日」、米国で「感謝祭」の祝日であった。米国では当日または翌日、クリスマス商戦のスタートでもある。小売りの売上高がピークになる期間である。マクロの指標でもある「小売り売上高」に影響し、景気の大きな判断材料でもある。さて、日経平均であるが、週初と週末に大きく売り込まれた。NYKダウは同じく週初と週末に下げたが、12、300ドル台を維持している。NYKダウの上げ潮に対し、日経平均はこの1カ月ブラックマンスである。週初の下げは国内景気の先行き不透明さを背景に内外投資家の利益確定売りが主因である。まして、各企業の業績先行きに慎重であるのが市場の心理悪化を招いている。その上、あおぞら銀行新規上場、トヨタの増資等市場需給の希薄化で市場心理を冷やした。おまけに、株式取得機構が保有株式を放出する愚行を犯している。先物買残も積み上がっており、潜在的売り要因として控えている。政府が、株式譲渡益課税を現行施策前に戻す(譲渡益と配当に対する税率を10%から20%へ)とアナウンスしたことも影響している。経過処置をとるとの発言があったがーー。何ともはや時期が悪い。22日に経過処置発言で、日経平均は180円上昇したが、祝日明けの翌日大きく値を下げた。この要因としては、円高である。週末のロンドンではドルは115円まで値を下げた。この水準は輸出企業の採算ラインであり、輸出関連企業の今期の業績に影響大である。輸出が牽引してきた国内景気に影をさす。また、大手メガバンクの中間期決算の収益は最大であったが、貸し倒れ引当金の戻りが大半である。本来業務の収益(業務純益)は減少している。(国内の貸し出し残高は減少しており、預貸利鞘も貸し出し金利引き上げが思うように進んでいない)日本の景気は戦後最長を更新しているように思えるが、年度内政策金利利上げの思惑がみえる。日銀の強気は正しいのか。景気各指標は景気減速を示しているし、長期金利が6.5%台であり、景気減速の象徴ではないのか。先行き景気不透明感を市場が織り込みつつある。利上げは来秋以降にずれ込む可能性がある。【今週の予想】最近、「TOB」「MBO」「業務提携」「資本提携」が国内外で頻発している。USエアーのデルタ航空を買収、キリンがメルシャンをTOB提案、日本製紙がレンゴーと、東海パルプと特殊製紙、豪カンタス航空等の買収等である。その度に、その国の市場のムードを明るくし、上げ基調を保っている。NYK、アジア諸国等の株は上昇基調を保っている。だが、日本では企業同士の合併・統合等何処吹く風である。日本の市場では何か基本を忘れてないか?日経平均は週末には15,700円台で引けた。一方、NYKダウは週末46ドル台下げた。最近の傾向として、NYKダウの週末の下げは、ほぼ次週の日経平均の下げに繋がっている傾向がある。従って、週初は下げる可能性がある。ついでに、過去1回あった現象であるが、米国の住宅関連指標が減速したが、NYKダウには直接影響しないで、日経平均の株価に直接影響したことである。やはり、海外輸出産業が日本の景気をリードしている証左であろう。今週は、下値を固める週であろう。その下値は15,000円とみる。騰落レシオが売られすぎの70%割れ寸前、PER(株価収益率)も割高感が薄れてきており、徐徐に買い上げてきて、16,000円台を回復するであろう。ただ、景気、企業業績に好影響を及ぼす大きな材料が欲しいところ。29日発表の鉱工業生産指数が注目材料。市場予想は「―」なので、株価が大きく値崩れする心配はない。むしろ、懸念材料は円高であり、これ以上の円高は企業の通期の収益にマイナス作用で株価が調整する。今の円高局面は、日米間の金利差で動いており、極端な円高にならないと考える。米国では、今週に先行き景気を占う経済指標が相次ぎ発表となり、住宅産業を中心に景気後退がよりはっきりすれば、株価も調整する。日米とも、景気が分水嶺に差し掛かっている。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年11月20日 過去振り返り週間号
平成18年11月20日【先週の概要】先週号は休刊にしたため、11月6日~11月10日分も含め記述します。2週間を通じて日経平均は調整局面であり、NYKダウは堅調そのものであった。日米とも日本は4-9月の中間決算発表、米国は7-9月の四半期決算発表の最終局面です。両国の各企業とも業績は好調であった。日本の上場企業の業績は経常利益2桁増である。しかし、日経平均は企業収益の好調さを材料視していない。問題は各企業の通期見通しが不透明であることである。各企業とも慎重姿勢である。市場は先々の不透明さを最も嫌う。そうした中で10日発表された7-9月の機械受注が11.9%減少や景気動向指数のうち先行指数が3カ月連続50%割れと景気下振れ懸念で株価が下落し、先物の裁定解消売りが振れを大きくしている。最近内外でM&AやMBOという単語が頻発している。米国のホテルや薬品のM&A、ヘッジフアンドによる明星食品のTOB、JFEの日立造船事業買収、ホンダが八千代工業にTOB、USエアーがデルタ航空を買収提案、キリンがメルシャンをTOB等である。こういう個別銘柄が相場全体を牽引するが、日本の場合はまさに線香花火である。日経平均が大きく上昇したのは、14日GDPが実質2.0%上昇した日のみで以降はじり貧で17日週末には辛うじて16000円台を保った。NYKダウは連日最高値を更新し、12,300ドル台で終えた。米国中間選挙で民主党が勝利したが、薬価引き下げと最低賃金の引き上げ政策がどう展開するか注目である。また、原油相場、CPI等の指標、住宅産業の業況指標が注目点でもある。現在はアジア株も全面高であり、日本の株式市況のみが取り残されている。【今週の予想】最近は日本の相場に影響しない米国相場であるが、今週は経済指標発表等特に無い。23日が祭日でデイーラーが長期休暇を取るため、薄商いの中高値圏で平穏な相場展開になるであろう。ただし、M&A等突発的な事象が出れば大きく動意付く可能性がある。先週の経済指標を見る限り、住宅産業の落ち着きさえ確認できれば、FF金利の据え置きとともに景気の軟着陸が展望でき、暫くは相場の期待に沿った景況感になると予想する。さて、日本の株価であるが、米国は堅調、アジア株も全面高の中で日本だけが蚊帳の外にある。今週も上値の重い展開になるであろう。日米とも週後半に休暇であるため、持ち高整理の売りに押される可能性がある。日本の相場では外国人がシェアーの50%超であり、1つの材料で大きく売る。米国株高で外国人投資家はリスク許容度が増しているはずであるが、日本株に対し先物を中心に売り姿勢である。それとは対称的に日本の個人投資家のシェアーは少なくなっている。大型株上昇と小型株下落の構図である。今週は銀行の中間決算の発表がある。業績は好調であるが、業務純益は減少している。通期の予想によって相場動向は違ってくる。ヘッジフアンドの決算期による利益確定売りもでてくる可能性がある。円は117~119円台で膠着しており引き続き海外関連企業は買われる。内需関連株は景況感が悪化するか否かで株価は左右されるであろう。日銀は景気に対し強気であるが、日本の景気は牽引役が設備投資から完全に個人消費に移っていない。GDPのGDPデフレーターのマイナスは縮小しているが、デフレを完全に脱しきれていないのではないか。今後の適切な運営が望まれる。(政策金利上げは、年内実施は難しい)以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年11月6日 過去振り返り週間号
平成18年11月6日【先週の概況】先週の日経平均、米国NYKダウとも冴えない展開であった。米国NYKダウは先週木曜日まで12,000ドル台を堅持していたが、米国7-9月のGDPが前期比1.6%増とかなり低い数字になったことが発端でダウが73ドル強下げた。そのGDPの数字で、NYKダウは先々週の金曜日から6日連続落である。その余波が週初10月30日(月)の日経平均に端的に現れた。317円も下げた。この下げの要因は米国GDPの低下による米景気軟着陸期待が修正を迫られたこと、かつ1円強の円高/ドル安になったこと、日本の鉱工業生産指数(9月)が前月比0.7%低下したことである。悪材料が重なった。株価指数先物、裁定買残の解消売りが全体の下げを加速した。当然ながら米国に大きく依存している輸出関連株中心に売られた。最近の相場を牽引してきた個別企業の9月中間決算収益も消し飛んでしまった。各経営者も通期の2ケタ増益の言質をあたえないので、牽引力が弱くなっている傾向がある。10月31日に自立反発狙いで上げたが、週間を通じて弱気な相場展開であった。相場からそれるが、31日発表になった日銀の展望レポートの内容がかなり楽観的であるのに筆者は驚きを隠さない。景気が息の長い拡大を続けるという前提で、GDP・CPIを予測しているが、筆者は米景気の不透明感、IT分野の在庫増等来年春先までに景気は調整局面に入ると予想する。確かに9月の失業率4.2%、有効求人倍率1.08倍と好調だが、なかなか消費に火が付かない。企業の設備投資と海外需要に頼っているのが現状。原因は企業部門の労働分配率の低さにある。『個別業種と銘柄』・ 携帯電話番号ポータビリテイは現在のところKDDI(AU)が優位。ソフトバンクは、表示方法等で公正取引委員会に指摘される失態等で話題性はあるが、獲得台数は伸びていない。・ 三菱重工がGEと提携交渉中であり、交渉成立すると重工の大きな飛躍につながる。・ アコム赤字2,821億円の赤字。ノンバンクの収益悪化は一過性でなくなり、企業の淘汰が始まると考える。・ スズキが経常益1,300億円となり、燃費のよい軽自動車業界は利益の押し上げと株価の先高が見込める。・ 丸井、純利益68%増。株価の上昇に結びつくか?【今週の予想】先週と同じパターンになる可能性がある。先々週の週末にNYKダウが73ドル強下げた後、先週初の日経平均は大きく下げた。ただ、先週末のNYKダウの下落は32ドル強と比較的小さい下げであったことと、円が118円/ドルと円安になったことが相違点である。しかし軟調な展開を予想する。米国雇用統計(10月)の強さ(失業率4.4%)が雇用面からみると強い数字であり、FF金利の利下げが当面ないとの悲観論でNYKダウは下げた。10月の消費者信頼感指数、製造業景況感指数が悪化し、住宅産業の減速を配慮し、むしろ利下げの可能性を予見していたが、この雇用統計でその思惑は外れて株価が軟調になった。米国NYKダウは、7日の中間選挙を境に流れが変わる可能性がある。共和党、民主党どちらが勝とうが、流れがどうなるか推し量れないがーー。先週の雇用統計でインフレ警戒感が意識されて、軟調に推移するであろう。11,800ドルが下値の壁か。一方、日経平均は軟調な展開になると予想する。一時的に16,000円を割る可能性がある。最も株価上昇要因である各企業の中間決算発表のピークであるが、通期の決算予想の増益率を慎重にみている企業が多い。従って、大きく株価を動かす要因として迫力に乏しい。むしろ大企業のTOB、MBO、業務提携等が相場を上昇させる要因となりやすい。今週はトヨタ、武田薬品等の国際優良株の決算発表がある。通期収益予想によって株価が大きく左右される。経済指標としては、9月の機械受注統計がある程度。受給面では、個人投資家は方向感出るまで様子見に徹し、海外投資家は自国相場の軟調でリスク許容度が低下し、残る国内機関投資家がどう出るかにかかっている。最後に、5兆円に残高が積み上がった裁定買い残の解消売りが需給面の懸念の一つになりつつある。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年10月30日 振り返り週間号
平成18年10月30日【先週の概況】米国FOMC、3回連続FF金利据え置き!米国、GDP成長率1.6%(7月―9月)に減速!日本のCPI前年同月比0.2%上昇米国NYKダウは先週12,000$を突破しなお史上最高値を更新し続けていたが、週末の朝方発表されたGDP成長率の減速で反落した。前回の成長率2.6%をさらに下回った。要因として、やはり裾野の広い住宅産業の落ち込みであろう。住宅産業の米国経済に占めるウエイトが大きいことの証左である。米国のGDP成長率の巡航速度は3%強とされ、景気減速のハードランデイングにならないだろうか?ただし設備投資と個人消費は堅調であった。2年間続いたFF金利利上げも終止符を打ち、次回以降のFOMCでは利下げの局面になる可能性がある。米国経済の軟着陸を期待する。日本の経済と株価に影響大であるからである。月~木曜日のNYKダウ続伸は企業の4半期決算の好調さとインフレ懸念の後退が要因である。さて、日経平均は週初の上げを週末の下げが帳消しにして、先週末比ほぼ横這いで終わった。週初の日経平均上げは、根強い企業業績の上方修正期待と円安、原油安が主因であった。この日決算発表した信越化学、円安効果期待の輸出関連株、空き部屋率低下、マンション販売好調による不動産株が上昇した。一方、週末の下げはCPIの数値が市場の予想を下回ったのが主因であり、高値警戒感、週末、月末とあり、利益確定売りが先物主導で売られた。個別銘柄・業界のトピックスでは・ 軽自動車、国内販売200万台になる。石油高による燃費のよい軽自動車が買われている。近い将来、普通自動車と肩を並べる日が来るかも。・ 不動産REIT主導による不動産売買の拡大、マンション販売好調、賃貸物件の空き部屋率の低下、一部地域の基準地価の上昇等により、総じて不動産各社の業績は好調。・ 携帯電話のナンバーポータビリテイー制度発足で、NTTドコモ、AU、ソフトバンクモバイルが熾烈な客争奪戦。今のところ、ソフトバンクモバイルが価格破壊をスローガンに優位に立っている。・ NEC、決算発表遅れ。日本基準財務諸表変更に手間取る。(株急落要因)・ 東証2部の明星食品に米国ヘッジフアンドからTOBしかけられる。経営陣が拒否。・ 日本ハム、プロ野球日本一にも株価軟調。【今週の予想】今週の日経平均は特に内外の経済指標に影響を受ける展開になる。米国NYKダウが先週末に、4連騰の後反落した。これはGDPが1.6%と市場予測よりかなり低い数値であったのが主因。特に住宅投資が17.4%と大幅鈍化した。FRBは前回FOMCで利上げを据え置いたが、今後利下げに転換する可能性がある。現在は企業の設備投資とGDPの60%を占める個人消費が景気を引っ張っているのが現状。インフレ懸念など市場関係者の頭の中にない。今週は個人消費支出(PCE)と雇用統計が金融政策に影響を与える材料となる。7―9月の企業業績は好調ではあるが、NYKダウは1週間12,000円を挟んだもみ合いに終始すると予想する。米国の金利が低下すると、日米の金利差に影響を受ける$高が円高になる可能性が高い。先週GDPショックで金利が低下するとの連想から、119円台/$から117円台/$と円高に振れた現象である。社内レートを110円台に設定してあるのでまだ貯金があるが、このまま円高傾向が強まると輸出産業の下期収益に影響する。一方日本の金融政策であるが、CPIが0.2%と市場予想より低く、変動の激しい食料品とエネルギーを除くとマイナスである。日銀が31日に発表する「経済・物価情勢の展望」は物価に関しては弱含みの表現になるし、9月の鉱工業生産指数は前月比1%下落と予想される。日本経済は踊り場に差し掛かったのではないか!主要企業の中間決算は総じて2ケタ増であるが、現状の経済状況と企業決算状況の綱引きで一進一退ではなかろうか。受給関係では先物の買い玉の積み上がりが気になるところ。個別業種・企業では・ 東証2部の明星食品に対するTOBの経過と同社の株価推移。・ 携帯電話3社の勝敗は11月末頃見えて来る。ソフトバンクモバイルの勝利か?・ ソニーの営業益91%減。この先増収策が見えて来ない。・ 王子製紙のTOBから始まった製紙業界の今後の再編劇は?紙は輸入物も含め供給過剰。・ 薬価改定、来春は見送りの予定。製薬会社の収益に朗報。・ NEC決算発表遅れ。真相は?以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年10月22日 過去振り返り週間号
平成18年10月22日【先週の概況】米国NYKダウ12,000ドル突破!NYKダウは、先週19日に12,000ドルを突破しました。週末には少し調整しましたが、12,000ドル台をキープしております。先週末あたりから市場最高値を更新続け、その兆候はありました。大きい要因は、企業の好決算への期待感である。それに、長期金利の低下が追い討ちをかけた。17日の調整はPPIが前月比0.6%上昇し、インフレ懸念が台頭したことである。翌日はIBM46%増益発表とCPIコア指数0.2%、住宅着工件数が6%増と企業増益期待とインフレ懸念の後退が株価を押し上げた。12,000ドル突破はコカコーラの7-9月の決算が市場予想を上回つたように、優良企業の好決算が相次ぎ、買われた。フイアデルフィア連銀の景気指数悪化、OPECの日量120万バレル減産決定も市場に影響しなかった。因みに米国WTI原油は週末1バーレル56ドル台である。24、25日に開催されるFOMCでは利上げなしであろう。米国の景気軟着陸が十分予想される。一方、日経平均は16,000円台を抜けることはなかった。週初と週末に上昇したが、米国の経済ソフトランデイングを期待した各国の株価指数先物の上昇による海外投資家のリスク許容度増による買いが目立ち、円安や新興市場の持ち直しで買われた。勿論、NYKダウの12,000ドル台突破も市場の雰囲気を明るくした。今後の相場展開に影響しそうなニュースでは、証券税制(譲渡益軽減税率10%適用)の期限切れ後どう決まるのか。廃止か継続か?投資家への心理的影響が少なくない。北朝鮮は複数回核実験を実施すると公表しているが、その懸念が相場の重しとなっている。個別業種・企業については、・ ソニーのリチュウム電池問題。東芝がソニーに対し損害賠償を提起する方向であり、他の企業も同調すると、ソニーの損失は底なしである。ソニーブランドも地に落ちている。・ 24日から、携帯電話の番号ポータビリテイー制度がはじまるが、KDDI社は30%シェアー確保と強気である。NTTドコモ、AU、ソフトバンクいずれが勝つか?・ リース産業は業界再編が見込まれ、株高を演出している。これは、企業会計上の変更(リース物件も資産計上し減価償却する必要がある)が発端である。・ 米ボーイング787の受注が好調で、収益押し上げ要因として浮上。その代表企業が東レで、炭素繊維が寄与。機体製造や素材供給に日本企業が深く関わり、来年以降関連企業に恩恵が広がる。【今週の予想】このところ円安に歯止めがかり、先週は119円台から118円台に円が切りあがり118円台でもミドルにまで円高になっている。円キャリー取引に日銀が注目し始めたこと、ロシアが外貨準備のうち円の比率を上げると発表したことが挙げられる。日本の政策金利利上げ予想で日米の金利差縮小の思惑等により117円後半まで円が上昇すると予想する。これでも、日本の輸出産業への円安恩恵がある。日米の株式相場であるが、両国とも中間決算、7-9月の決算内容で方向性がきまる。米国NYKダウは12,000ドル台を回復し、高値を追う展開になろう。企業収益は13四半期連続で2桁増益を確保しそうである。ただ、26-27日に9月の耐久財受注、戸建住宅販売、GDP(速報)が発表される。市場予想を上回ると相場下げの要因となる。また、下降気味な原油相場の動向が気になるところ。企業業績も先週末のキャタピラーの決算発表が市場予想を下回ると、相場全体も調整する相場展開である。日経平均は、国内企業の中間決算の発表に一喜一憂の展開になると予想する。好業績銘柄には買いが入るが、高値警戒感、北朝鮮問題、円高傾向が売りを誘う可能性あり。また、裁定取引に伴う買い残の積みあがりも売り要因として気になるところ。これまで軟調であった中小型株にも買いが広がりつつあることは好材料。今週は松下、ホンダの中間決算発表が続く。新日鉄が3,000億円調達、出光興産の新規上場が市場にどう影響するか?相場の予想とそれるが、政府税制調査会の会長に本間大阪大学教授が選出された。経済成長論者で今までの会長と違って、企業寄りの減税に軸足を置く人物である。企業にとっては朗報である。「経済成長なくして、財政改革なし」以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年10月15日 過去振り返り週間号
平成18年10月15日【先週の概況】先週の日経平均、米国NYKダウの流れをみると、NYKダウは週後半に過去最高値を更新したこと。それに吊られて日経平均も16,500円台を達成したことである。北朝鮮の核実験があったにも拘らず、その日のNYKダウは小反発したし、日経平均は朝方少し調整したものの、大勢に影響は無かった。核実験予告で市場に織り込まれていたし、「地政学リスク」も市場が意識しなかったようである。日中、日韓首脳会談は成功裏に終わったが、今後の経済の緊密さが促進される可能性も市場は看過した。現状ではやはり、日銀短観の景況感等経済の現状、企業の収益に着目している。勿論、両方の見通しも大切である。もう1つ、両国の政策金利の動向も焦点である。両国間の金利差が縮まらないため、円相場は120円/1ドル近辺まで下落し、円安と設備投資の増勢が景気を引っ張っている構図である。NYKダウの推移と商品相場(原油)の下落(1バーレル60ドル近辺)も忘れてはなるまい。その政策金利であるが、米国FOMCのFF金利は年内利上げなしと予想する。むしろ利下げという議論も出てくる。原油価格は落ち着いているし、裾野の広い住宅関連指標が弱いからである。一方、日本の政策金利は、総裁の定例記者会見で「ゆっくりと」と表現しており、足元の景況感をみると、設備投資の増勢が緩んでいるしIT在庫増が気になる現象である。設備投資の先行指標である8月の機械受注が6.7%増と市場予想よりかなり下回った。マクロ的にみると、年明け以降景気は踊り場に突入する可能性が大きい。米国の景気もインフレ懸念は後退したが、巡航速度であるGDP3・5%を大きく割り込み2・5~2.6%である。米国の景気減速が日本の景気の機関車である輸出産業に大きく影響する。もっとも、米貿易赤字8月分が最大となり米国景気は堅調と読むアナリストもいるが、その主因は対中国であり、日本の景気とは無関係と筆者は考える。先週1週間の株価は、日米とも堅調な要因として企業業績によるところが大きかった。【今週の予想】政治的側面であるが、国連安全保障理事会で北朝鮮への制裁決議案が賛成多数で可決された。これで、もう一度核実験を強行すると、臨検の強化等政治的緊張感が高まり、相場に対する影響が出てくるであろう。北朝鮮は世界的に孤立を助長する愚挙には出ないと考えるが。もうひとつ、衆議院神奈川16区、大阪9区の補欠選挙が告示された。この補選で自民党の劣勢が伝えられると、日経平均に少なからず影響する。日本の株式市場に影響するNYK株は主要企業の7-9月期の決算発表を睨む展開になる。先週のNYKダウが連日最高値を更新したが、過熱感がでており潜在的なスピード調整で下押し圧力がある。決算内容が悪いと利益確定売りで表面化し、株価は下押しするであろう。17日(PPI)、18日(CPI)に発表されるインフレ指標も焦点で、コア指数が上昇していると、早期利下げ期待が後退し、NYKダウは調整する可能性がある。ベージュブックは各地区の景気がまだら模様を呈しており、FRBメンバーの中にはまだ、インフレ警戒論が残っている。今週はインテル等ハイテク企業の決算発表がある。ハイテク企業は相場牽引力が強く相場への影響力が大である。もっともNYKダウは最高値を更新したが、NASDAQはまだピーク時の半分まで到達したに過ぎない。このあたりの歴然とした差異はどう考えるか。さて、日経平均はこれから各企業の中間決算発表の本格化を控え、暫く材料に乏しく、買いが手控えられて様子見の投資家が増える可能性がある。売買代金が2兆円を下回る日が続く可能性がある。そうなると、NYKダウの動向に神経質な展開になる。需給関係では、先週後半から中小型株にも物色の矛先がようやく向かった。今週もその流れが続く可能性はある。楽天の下落傾向は底なしであったのが象徴的である。個別銘柄では、・ 信越化学は連結営業利益が30%増、減価償却期間短縮と報じられ、将来に亘って増益基調が続く。・ 流通業界では業界内各企業が増益基調の中、三越だけ減益である。将来、M&Aの対象になるのでは。一方丸紅を中心としたダイエー再建グループのイオン、マルエツは国内最大の小売グループ企業となり、合理化等で各企業の収益力が増す。・ 失態続きのソニーの回復期待は後退した。現場力が欠如。・ 日立はクラリオンを買収。収益構造の変化が見込まれる。・ 出光興産、24日東証に上場。2,500億円。市場全体の需給に足かせとならないか。・ 大正製薬、2回目の業績予想下方修正で大幅続落。・ 三井住友FGと住友商事各系列リース会社合併。経理基準の変更(予定)で体質強化。 ※経理基準変更――リース物件も資産に計上する必要。押しなべて、日経平均は15,000円から16,000円で一進一退であろう。※ 株に関する諺「秋に買って、春に売ると効率的」以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年10月8日号 過去振り返り週間
平成18年10月8日号【先週の概況】先週の相場を動意つけた要因は3つあった。A日銀短観 1 対ドル、対ユーロとも円安2 米NYKダウの過去最高値更新B日銀短観では、企業の景況感が2期連続改善した。特に市場が重視する大企業製造業のDI(デフュージョンインデックス)が3ポイントも上昇した。大企業非製造業は横ばいであるが、DIの数値は低くない。設備投資も前回より拡大し中堅・中小企業にも裾野が拡がりつつある。雇用も拡大しており人手不足が常態化しつつある。ただ3カ月先の景況感には陰りが見えるがーー。日本の景気の足下は巡航速度で持続力がついている。● 円が安い。先週末のNYK為替相場は1ドル119円をつけ、対ユーロでは150円近辺で推移している。これは、各国の金利差が主因と言わざるを得ない。米国は政策金利であるFF金利の利上げを中断しているが、EUでは先週0.25%引き上げた。一方日銀は、年内再利上げに対し躊躇している。投資家は金利差を利用して円を借り海外に投資している。(キャリー・トレードという)国内投資家は外貨を買い、海外に投資している。海外中央銀行は円の外貨準備を減らしている。円安は当面(恐らく120円台半ばになる時期)続くであろう。輸出企業にとって収益嵩上げ要因となりフォローの風が吹いている。● 米国NYKダウは週初、週末に微調整したものの堅調そのものであり、週央には過去最高値を更新した。この要因は、原油が1バレル60ドル(WTI)を割り込みインフレ懸念が後退したことで米景気が軟着陸に向かうと期待が高まったこと。唯一の懸念は住宅産業の減速感が強まっていることである。このような環境を受け、日経平均は4日には下落したものの、5日は大幅高となった。4日は北朝鮮の地下核実験実施するとのアナウンスを意識され(地政学リスク)、大口の先物売りで一段安となった。5日は米国NYKダウの連日の最高値更新、円安が主導し、自動車・電機等主力株に買われ、全面高となつた。週末は小反落して終えた。【今週の予想】先ずは日本の相場に影響する米国NYK株から。先週の相場は週末こそ雇用統計により、調整したが、連日過去最高値を更新し続けた。景気軟着陸、物価安定、FF金利利上げ打ち止め観測が要因である。さらに上昇するか否かは、9月のFOMC議事録の内容が焦点である。市場はFF金利の利下げも意識しつつある。先週末発表の雇用統計で9月の雇用者増が5万人と大幅減であったが、8月の統計が大幅に修正された結果を市場がどう読むか。次の焦点は、7-9月期の企業業績である。11日のFOMC議事録、12日の地区連銀によるベージュブックの結果もポイント。さて、日本の相場であるが、米国NYKダウの大幅な上下に影響を受けるのは至極当然である。円安、国際商品市況(特に原油)の下落、中間決算内容に対する期待感から外国人投資家が買いを継続し、大商いの中上値を試す展開になると予想する。16800円程度に上げてくるのではないか。因みに円は1ドル124~125円程度の円安になると思われる。懸念されるのは、北朝鮮が地下核実験を実行した場合の地政学リスクと、10日に発表される「機械受注統計」がさらなる悪化した場合である。前回この統計の悪化により株式が大きく調整した引き金になった。市場予想の11%増が目安になるであろう。毎回記述するが、株価指数先物の思惑的売買が大きく膨らむと値幅が大きくなる。日本の現景気拡大は最長を更新することはまず間違いない。最後に阿部政権の行動であるが、中国、韓国を最初にタイミングよく訪問したことは非常によかった。「政経分離」と言われつつも、両国との関係緊密化は経済にとってプラスである。小異を捨てて大同につく関係を筆者は望む。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年10月1日号 過去振り返り週間
平成18年10月1日号【先週の概況】9月25日~29日阿部内閣が26日発足した。「美しい国」をスローガンの1つに掲げているが、足元では官製談合、地方自治体による裏金問題等美しくない事態が頻発している。本当に「美しい国」が実現できるか。一方、「構造改革なくして経済成長なし」の所信表明は評価できる。新閣僚の布陣、官邸主導の補佐官人選等から期待が持てる。さて、先週の株式相場であるが、週前半は先々週末から3日連続の続落であった。25日(月曜日)の日経平均はほぼ横ばいであったが、26日は下落した。この日の下げの主因は9月中間期の権利・配当落ち、10月以降の下期運用を睨んだ機関投資家の銘柄入れ替えや換金売りと、阿部内閣の顔ぶれを見極めたいと積極的売買を控える投資家が多かったためである。それでも、前場は比較的堅調な地合いを保っていたが、その地合いを大きく崩したのが株価指数先物の大口売りであった。またしても、先物に振り回された格好である。翌日はまったくその逆の展開であった。前日の米国NYKダウの上昇、期末特有のお化粧買い、阿部政権の改革に向けた期待で上昇基調を辿っていたが、日経平均先物の買いが大きく相場の上げ幅を広げた。毎度繰り返すが、最近の相場は薄商い、材料に対する鈍い反応の中で日経平均先物が振れを大きくしている。ただ、各個別銘柄では、業績(予想)に対し素直に反応している。29日にCPIの発表があったが、前年同月比0.3%上昇であって、市場は余り反応しなかった。雇用統計も失業率4.1%で反応が薄かった。主な個別銘柄・業種の動向は・ ソニーのリチューム電池問題。リコールが世界中に広がりをみせており、その費用がどの程度拡大するか業績への影響も見通せない。・ 日産・ルノーがGMと提携交渉中。合意すればかなりの相互メリットがあり、評価できる。また、日産は日産デイーゼルをボルボに売却した。連結業績面の足かせが取れた。・ ソフトバンク、携帯事業を証券化。金利低下による先々の業績にプラス要因。【今週の予想】10月2日~10月6日米国NYKダウは、2,000年につけた過去最高値(11,722ドル)に迫るまで上昇し、その数値を一時上回ったが、終値ベースで高値更新には至らなかった。利上げ休止と原油安で景気軟着陸期待から高値挑戦域まで上昇したが息切れしてしまった。今後雇用統計等重要な経済指標発表が続くが、高値でのもみ合いになるであろう。ただ、2日発表の米サプライマネージメント協会指数は、景況感悪化を示すと予想される。予想通りだと、企業収益悪化懸念から株価下押し要因として働く。長期金利が一時4.5%まで下がり、長短金利が逆転している現状から、FF金利下げも視野に入ってくる。天然ガス先物への投資失敗で巨額損出を計上したヘッジフアンド(56億ドル損失)の件が投資家心理に響いてくる可能性がある。さて、日経平均について気の長い話であるが、中間決算の発表が始まる11月頃に決算発表と通期予想の結果によって、今期の株価の趨勢が決定されるだろう。今まで、景気を引っ張ってきた企業業績、設備投資が息切れせず、個人消費にバトンタッチされれば、良好な景況感で投資家心理を強気にさせる。翌年3月末までに1回程度利上げがある可能性があると予想する。ただし、阿部政権が利上げに対し慎重であるので、日銀が強行突破できるか疑問も残る。足元の相場であるが、2日に日銀短観(7~9月)発表がある。大企業製造業の景況感が前回(4~6月)と比べて横ばいか微増と市場は予想している。大きく下ぶれると、景気悪化懸念から株価下押しするであろう。長期金利が1.6%台、為替が1ドル117円程度と企業にとって業績に好環境であるが。3日野村不動産ホールデイングのIPO(株式新規上場)がある。公募と売り出しで、1、645億円の資金を吸い上げる。一時的にしろ、需給悪化懸念がある。(24日には出光興産のIPOがある)また、もう1つの需給悪化懸念として、4月に仕込んだ信用取引の決済期日が近づいていること。含み損を抱えている個人投資家が換金売りすれば、当然需給悪化に繋がる。先週、16,000円台を回復した日経平均は、週間を通して、NYKダウの影響を受けながら、16,500円台を試す展開になると予想する。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年9月24日号 振り返り週間記事
平成18年9月24日号【先週の概況】19日~22日台風13号が日本の九州地方を直撃し、大きい被害をもたらした。その後秋らしい清々しい天気が続いているが、日経平均株価は小雨模様であった。先々週13日にチャート分析上、日経平均の五日移動平均が二十五日移動平均を上から下に突き抜けて「デッドクロス」を形成した。経験則上、そのシグナルは調整が長引くと書いたが、その通りとなった。日々山谷があったが、週末を通じて日経平均は232円余下落し1万5634.67円で引けた。もう1つ経験則で、過去の株式相場の歴史で9月は株価が安くなる月だそうです。これは、バブル時代以降の現象で、米国もその傾向があると言われています。この原因として海外の機関投資家、株式投信の決算時期が10月、11月に集中しているため、利益確定売りが9月に出てくることだそうです。日本の株式市場で海外投資家のシェアーが大きいため、その売りで相場が軟調になると予想されます。20日の日経平均の下げは、前日の米国NYKダウの株安やタイのクーデターを嫌気した売りが先行し、終日安値で推移した。それに株価指数先物に左右される展開も加わり、下げが加速する場面もあれば、買われて下げ渋る場面もあった。阿部新総裁が選出されたが、ほぼ織り込み済みで、時間の関係もあり動意付かなかった。22日の下げの要因は、前日の米国NYKダウの反落と外為相場で円安が一服したことが嫌気されたことと、やはり株価指数先物の売りが下げを加速した展開であった。輸出関連株は円安で収益が嵩上げされるので株価が値上がりする傾向がある。この相場展開は1カ月余続いており、9月末までに日経平均は15,000円台を意識する可能性がある。中間決算を控え、銀行の決算に対する影響が懸念される。注目すべき業種として・ 国土交通省が発表した基準地価で3大都市圏の地価が上昇した結果、不動産関連株は19日の相場で上げたが、同日結局安くなった。地価で動意付く局面は終わった。むしろ空部屋率の低下による不動産関連投資信託の買いを推奨。・ 信越化学が5連騰。外国人投資家が好感して飛びついた格好。悪材料銘柄は手仕舞い、好材料には飛びつく外国人の投資姿勢を示す。【今週の予想】25日~29日米国のFF金利は8月に続いて利上げなしであったが、インフレ警戒より景気減速をFRBが懸念し始めたと予想する。世界的に商品相場が下落し、原油・金が2割近い安値を付けた。(原油はWTIで1バーレル60ドル台)日米とも景気の先行きに不透明感が漂う中で、内外投資家の様子見が強まれば、今までと同様、株価指数先物に左右される相場展開になる。現在の市場は悪材料に敏感に反応する地合いである。米国も同じ様な状況である。先週フイラデルフィア連銀発表の製造業指数が低水準になると、相場が大きく下げに転じた。住宅市場も弱含んでおり、これまで相場の下支えであった企業業績の先行き懸念も投資心理を冷やしている。また、あるヘッジフアンドが天然ガス先物で巨額損失を出したことも相場波乱要因として懸念されている。商品相場で売られた資金は安全資産である国債に向かっており、日米とも長期金利の金利が低下している。(10年物国債の価格上昇)米国では戸建住宅販売の指標、日本では8月の鉱工業生産指数、CPIが発表されその指標が10月以降の景気の先行きを暗示し株式相場を左右する。注目銘柄、業種として、・ 銀行株は下落基調となるであろう。金利がここまで下げると収益的にマイナス要因。・ サハリン2工事指し止め。ロシアの資源外交の強硬姿勢が散見されるが、この件もその一環である。工事に投資している三井物産、三菱商事の収益に対する影響度合いは。・ 商品相場下落した結果、原料値上げ交渉中の企業群の対応如何に。・ クーデター後のタイの政情はどうなるか。進出企業の業績に対する影響は。・ JFEが中国に新工場建設。新日鉄に追随。業績と株価の反応は。・ ネット関連株軒並み下落の中、SNSミクシーの株価落ち着きどころは。・ 阿部政権となり、構造改革の行方は(補佐する陣容により方向が決まる)。・ いすず営業益32%増。今週の株価の動向は。・ ソニーのプレイステーション3の、欧米販売時期延期、売り出し前の値下げ等企画力欠如。任天堂との競争力。・ 住友化学、殺虫剤会社を合併。今後の増益体制の一環か。・ デンソーとショウワが米国拠点を拡充。自動車メーカーの米国での販売好調さに追随か。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年9月17日 週間振り返り
平成18年9月17日号【先週の概況】先週の日経平均も冴えなかった。やはり16,000円の壁は厚い。一方、ニューヨークダウは木曜日に小幅安であった以外は堅調そのものであった。原油先物(WTI)の下落が主因である。日経平均は週初286円余いきなり下げた。木曜日に192円余上げたが、結局先週末は16,000円台を堅持できなかった。ドル・円は117円台と円安方向であるのに輸出関連株は動意つかなかった。4-6月のGDPは年率1.0%に上方修正されたし、民間設備投資も足元は堅調である。ただし、6~9カ月先の設備投資の動向を占う「機械受注統計」が市場予想を大幅に下回ったのが(16.7%減)、週初の大幅下げの発端で、設備投資関連銘柄の売りを誘った。外部環境も含め好材料には動意薄で、悪材料には敏感に反応する相場展開である。買い材料不足の中、先物に翻弄され易い市場展開が続いている。9月12日には1カ月振りの安値をつけた。この日は売買代金が久し振りに2兆円と膨らんだが、実需の売りが殆どであって、9月末中間決算に向けての利益確定売りが中心である。中間決算配当取りの買いは少数派なのであろうか。9月13日にSNSのミクシーがマザースに上場したが、初値が公募価格より大幅に高く、9月14日には終値で312万円を付けた。まさに驚異の人気銘柄である。楽天株が続落しているのに対峙している。このままの堅調さが続くのか。【今週の予想】今週の日経平均は先週に引き続き上値の重い展開であろう。9月中間決算の配当権利取りの買いがでる可能性はあるが、電力株等1部の銘柄に限られ、相場を力強く引っ張る力はない。チャート分析でみても、先週13日に日経平均の五日移動平均が二五日移動平均を上から下に突き抜けるデッドクロスを形成した。相場が下降局面に転じたシグナルである。4月下旬と同様の現象でその後調整した記憶が残っている。CPIが基準の見直しで0.2%に落ち、「機械受注統計」が市場予想より大幅に数値が下落した。政府は、9月の月例経済報告で「デフレ」の文字を削除する意向であるが、マクロの経済は、完全にデフレから抜けたのか疑問である。証左として、指標銘柄である10年物国債が1.6~1.7%と低位安定しているではないか。景気が悪くなると、長期金利が低くなるのが(国債の値上がり)経済の基本原理である。その辺を政府がどう見ているのか。ミクロでは、各企業の業績は至極順調である。(日立製作所を除く)9月中間期の実績と通期の見通しが明確になるまで、日経平均は大きく上に動意つかないであろう。また、4月以降に膨らんだ信用取引が期日前に整理されてくると、相場に大きな重しとなる可能性がある。政治面では9月20日に総裁選がある。阿部官房長官が順当であるが、相場に織り込み済みである。以外だったのは、竹中氏が参議院議員を辞職することである。構造改革を引っ張り、経済をここまで良くした最大の功労者である。今後の改革実践者がいなくなる。最後に米国のニューヨークダウであるが、原油先物の下落が支えている感がある。経済指標では労働コストが高めの数値である以外の各指標は景気減速の数値である。20日のFOMCは引き続き利上げ停止となる。従って、NYKダウは堅調に推移すると予想する。この堅調さが日経平均に伝播するといいのだがーー。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
2006年9月10日からUPします 過去を振り返り後半戦の相場を見ていきましょう
平成18年9月10日号《先週の概況》先週9月4日ライブドアー事件の初公判があった。大きな意味で日本の実業界を震撼させた経済事犯であり、今後公判が進捗するに従ってどんな新事実が出てくるか見ものである。さて、紀子様に第3子が生まれた。男の子であり、皇室に男子が生まれるのは41年ぶりだとか。これで、政府の皇室典範の改正議題は20年以上議論されないであろう。株式相場は皇室での慶事には全く左右されずに、事前に織り込まれていたのか利益確定売りに押された格好。唯一久し振りに市場が活況であったことだけである。日本全体の経済効果は1500億円であるとか。次に株式相場である。週初は16,300円を超えたが、日を追うに従い16,000円台を辛うじて保った動き。16,000円を大きく超えるのは難しい。ここ数週間続いている先物への思惑的売買と、NYKダウの影響から抜け切れない。週初に発表された法人企業統計(4-6月)の企業設備投資が前期比16.6%増および全産業経常益10.1%増の2つの好材料も泡のように消え去って行ってしまった。また、製造業の損益分岐点比率が77.5%と収益力が高まっている事実も材料視されていない。売った資金は何処へ行ったか。特に個人投資家の資金は4方向ある。1 金利差に着目して外債投資に 2 国内債券投資へ(10年物国債金利が1.6%台と値上がりしている)3 都心の空部屋率低下(2.98%)と賃料値上げ攻勢から不動産REITに 4 待機資金として預貯金へ目立った個別銘柄・業種の動き。・ 住友鉱 銅価格の急騰が収益を押し上げ、中間決算の営業利益2.5倍へ・ コスモ石油が反落。米原油先物下落と過去のガス漏れ1部隠蔽・ 新日鉄が韓国ポスコと資本、業務提携拡大によるグローバルな企業再編に備え・ 国が三菱重と初の国産ジェット旅客機の生産計画を固めた 将来の収益拡大期待・ ソニー、欧州でプレステ3販売開始再延期 ブランドイメージにダメージ大きい同社はネガテイブな事実が頻発《今週の予想》今週は、予想の前に外国為替のことを整理しておこう。無論、経済および株価に影響あるからである。一定年齢以上の方はご存知であろうが、1985年9月22日、米国のプラザで開催されたG5(先進5カ国財務省・中央銀行総裁会議)で円安ドル高是正政策が合意され、急激に79円/ドル台まで円高が進んだ。この合意は米国貿易収支赤字の解消が目的である。現行は、円は対ドル、対ユーロともに安く、対ドルで116円~117円、対ユーロで150円程度である。現在は貿易収支ではなく各国の金利差で動いている。本来、為替は各国の経済のフアンダメンタルズで決まる。16日に開催されるG7で日本の円安問題が議論されると円高へと傾く可能性がある。そうなると日本の輸出企業の収益に影響し、株安となる。さて、株式相場の話題に移ろう。先ず、日本の株式市場に影響するNYK株式市場から。NYKのWTI原油先物は67ドル台/1バーレルに値下がりしているが、今は、他の経済指標が注目されている。ベージュブックによると各地区の経済状況は減速基調を強めているし、住宅関連指標が全て下ぶれている。景気減速かインフレか、実像は大分見えてきた。ただ、企業の労働コストが上昇している。こうした現状で、今週は8月の小売上高、CPIの発表が週後半にある。これらの数値が市場の予想と乖離していると、株価に波乱を起こす。しかし、次回FOMCでFFきりは休止継続であり、NYKダウは堅調に推移するであろう。日本の日経平均は米国の相場変動に左右されながら、ソニー等一部銘柄を除き堅調に推移するであろう。ただし、過去の経験則から外国人投資家は秋口に売る傾向にあるので、実需面で下押し圧力となる可能性がある。また、経済指標では、4-6月のGDP改定値と7月の機械受注統計が発表となる。GDP改定値は0.2ポイント上方修正されると予測、機械受注は6月の大幅増の反動で減少する見通し。2数値とも市場の見込みと大きく下方乖離すると日経平均株価が下ぶれする可能性がある。従来通り、株価指数先物に左右されるとでこぼこの相場展開になる。個人投資家を中心に中間配当取り目的の買いも予想される。要するに、各企業の業績は良好であることを前提として、国内外の外的要因には左右されるが需給は少しずつ改善し、好循環により相場展開は9月末に向けて良好になると予想する。以上
2007年06月16日
コメント(0)
-
今までためていた過去ログを大公開 つぎつぎ発表するか
ものすごいいきよいで過去ログを披露みんなついてこれるかな
2007年06月16日
コメント(0)
-
森木先生出版バーティー 「日本は破産する」
すごいタイトルでももうかなり前から言われていたことまだ読んではいないけど出席者がそうそうたるメンバー NHKの海老沢会長筆頭にすごくむしろ本の内容が怖く感じてきたこともあった。本当に近じか現実になるのでは 近いのではなんていうように皆さんもぜひよんでみてください。
2007年06月16日
コメント(0)
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 静岡旅行2024(13)掛川城跡
- (2025-11-18 19:00:05)
-
-
-

- 鉄道
- 大井川バックの国鉄特急色「タイプP」
- (2025-11-18 19:32:32)
-







