2015年02月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

化女沼にて
久しぶりに化女沼に行って来ました。カモは少しいましたが、小鳥の姿が見えませんでした。沼の周りで出会った小鳥たちです。ダイサギカシラダカウスタビガアオサギネコヤナギカワウ
2015年02月21日
コメント(3)
-

風たちぬ
宮崎 駿監督のアニメ「風立ちぬ」を一昨年子供たちと一緒に見ました。今日テレビ放送がるといことで子供たちから教えられて見ています。 (一昨年書いたものです)我がふるさとが舞台(堀辰雄の風立ちぬ)になっています。 「風立ちぬ、いざ生きめやも」 (ポール・ヴァレリーの詩から) 主題歌 ひこうき雲 この作品はゼロ戦の設計者・堀越二郎と堀辰雄の「風立ちぬ」を重ねたものです。ふるさとの町の病院は高原の空気の澄んだ場所で、 当時は不治の病と言われた結核の療養のために多くの文人が来ていました。 横溝正史、竹久夢二、堀辰雄、尾崎喜八、正木不如丘などです。 堀辰雄の「風立ちぬ」ではここで療養していたのは節子です。(彼の作品に「菜穂子」もあります) 私の母もこの病院で事務をしていて堀辰雄に東京に出て来ないかと言われたとのこと。 (どんな意味で言われたのかは本人のみしかわかりませんがネ)今はそんな面影をみじんも感じさせないところがさびしいですね。(笑) 母のアルバムから高原サナトリウム本館玄関前で、当時のお医者さん、看護婦さんと一緒の写真を見つけました。前にいる方々は?久しぶりに若い頃に読んだ堀辰雄の風立ちぬを青空文庫で読んでみました。ふるさとの子供の頃の思いでが眼に浮かびました。 時代が僕に追いついた 2013/7 宮崎駿「風立ちぬ」は 「火垂るの墓」への回答
2015年02月20日
コメント(0)
-
朝背負い(故郷の原風景)
昨日の続きです。義父が朝早く目覚めたときに、原稿用紙に書き留めたものを私が冊子にしたものからです。ここは仙台市北部の根白石です。義父が生まれ育った場所です。明治~昭和の初めころまで、どこの山村でも見られた光景でしょうか。朝背負い (韮畠 山村(やまむら)のくらし) 根白石は中世に山村と呼ばれていたそうです。 お正月となると、私たちはよく朝背負いということをよくやりました。一年中ただ働きに働いて勤労の美徳を発揮していますが、お正月だけはゆっくりしました。でも本当にゆっくりするのは元旦、二日、三日の三日間だけです。この三日だけは本当に改まった気持ちでお正月をしました。後の日は休むには休みますが朝背負いということをやります。「夜あけるぞ。起きろよ。」と姉たちに静かに起こされてみると本当に夜が明けはなれようとしています。あまり音を立てないようにして着物を着替えて庭に下り立ちます。着物というと当時は平常は「長衣装」(襦袢)を着て帯を締め、その上に「短か衣装」(紐のない羽織のようなもの)を着ていました。働きに出かけるときはこの短か衣装だけを着て、帯をきりりと締めていました。もちろん股引きを穿いたのです。庭に下り立って足袋に草鞋をつけます。そして蓑を着て荷縄を持って皆に遅れないように出かけます。もう兄や姉たちはもう道路に出ています。道路に出てみると泉や、橋本、馬場あたりの人々までの人々が急ぎ足で山に向います。「お早やかス」とお互いが挨拶します。この辺のならわしとして黙って通り過ごす人はほとんどいません。私どももそれに見習いました。道路はコリコリと凍っています。道路の両側には雪が一杯です。道路の真ん中だけが雪がとけています。その道には足跡がついていて、そこには水がたまっていて、その上に氷が張っています。この氷をパリパリと踏みつけながら山へ山へと急ぎます。学校の前を通って駐在所のところから右折して北畠、館を通るとまもなく高梨沢というところがありました。小さな沢でした。この沢を上り下りして沢蟹をとったものです。茶褐色の小さな蟹を五匹も六匹もとって握っていた掌をウズウズさせていたこと、食べると少し塩辛い味がしたことなど思い出だされますが、この沢に小さな土橋がかけてありました。この土橋を通って新家(あたらしえ)という、うちの前から左折して田んぼを通って、いよいよ山道です。もうこの頃になると山の方から一杯薪を背負った人々が下ってきます。「お早やかス」とお互い挨拶しながら私たちは道をよけて重い荷物を背負った人々を通してやりました。山について私たちも薪や柴木を背負って山を下りました。子供の私たちは芝木でまるった「芝まる」を二つ位重ねて背負いました。いそいそと山道のよい足場を選んで転ばないように背負った荷をぐらつかせないように慎重に坂道を下ります。もう汗ばんで来ます。ところどころに道路の片側に高い土堤があったりして荷を背負ったまま具合よく休めるところがありました。皆そこで列を作って休みました。五、六分もするとまた歩き出しました。疲れるとまた休みました。このようにして途中三、四回位休んで家に着きます。兄や姉たちは太い木をたくさん背負ってました。「デガン、デガン、ガチャ」と音を立てながら荷を下ろします。私たちは「モサリ、モサリ」と芝まるを下ろします。荷を下ろした私たちは汗を拭いて足を洗って顔を洗って家の中に入ります。すがすがしい朝でした。働いて気持ちのいい朝でした。もうお餅も焼けていて、お汁粉だのお雑煮だの、納豆餅だのがちゃんと出来ていました。楽しい楽しいお正月の食膳でした。
2015年02月16日
コメント(1)
-
冬の生活(日本の原風景)
私の義父は仙台市の北部にある根白石の生まれです。2004年に放送されたNHK連続テレビ小説『天花』のロケ地になりました。私の故郷を思い起こすような自然豊かな山村です。義父が40年前に書いた子供の頃の思い出を私が冊子にして兄・姉様方に配りました。その中から「冬の生活」です。これを読むと私の子供の頃の故郷の情景がよみがえります。今のように必要なものはコンビニで買うなんってできませんでしたから(店もないし、お金もないですからね)必要なものは自分で作りましたね。草履や縄を綯うのは必須でしたね。竹の雪落としもよくやりました。大雪の夜には雪の重みで竹の折れる音が聞こえました。冬の生活 (「韮畠」 山村のくらし 2007年発行より)冬になると、たくさん雪が降りました。もう正月から二月にかけては、降った雪が消えないで積もって尺余りに達していました。道路も人や馬が通るところだけが黒く雪が消えていました。冬になっても部落の人々は休みませんでした。男の人々はハバキ(脛巾)というものを脛にあてツマゴ草靴を履いてスカリに山刀や鋸やまさかりを入れて山へ出かけました。私たちは炭出しや炭の背負い出しに動員されました。女の人々はうちにおって蓆織りなどをしました。母などはよく機織りなどもしてました。年寄りたちまでが藁靴を作ったり、草履(ぞうり)を作ったり、縄をなったりしました。私たちも縄をないました。縄をなうと一把いくらということで小遣いを貰いました。外に積んである藁を運んで来て、その藁をすぐって槌棒と称するもので藁を打って軟らかくして、よく縄をないました。藁靴も作りました。つまごも編みました。草履も作りました。その合間を凧揚げもして遊びました。その竹も、竹を切って来てヒゴを作って障子紙を張って自分で作りました。長い長い糸を手繰りながら凧揚げは楽しいものでした。でもしばし遊ぶと、またうちへ帰って藁を打って縄をないをしました。物置から簀を持ち出して籾をまいてバッタリを作って雀とりを仕掛けたりしました。これはほとんど毎日のようにしました。でもとったことはありませんでした。馬の尾毛でワナを作って、よく雀の集まるところへ仕掛けましたが、これも成功しませんでした。吹き矢も作って雀を狙いましたが、これも駄目でした。成功したことのあるのはうさぎワナです。細い針金を丸めてわなを作って唐山へ行って兎の通り道に仕掛けました。二、三匹とった経験がありましたが、でも子供である私たちには無理な遊びでした。大きな藁屋根には大きな垂氷がたくさん下がっていました。それに朝日があたるととてもきれいでした。お昼近くになると、これが解けてポチャリポチャリと軒下に落ちました。屋敷の南側には竹林がありました。これに雪が一杯積もって、その重さに堪えかねて折れるものもありました。私たちはこの雪落としもしました。竹は雪の重みで曲げられて地べたにその梢をつけていました。朝の雪はきも私たちの仕事でした。故郷の雪はなつかしく深く思い出の中にあります。雪を転がして雪だるまを作ったこと、その眉と目と鼻と口は炭屑を拾ってきて作りました。氷すべりもしましたが、これは太い竹を割って下駄のようにし、こわごわすべりました。友達の中には下駄にカスガイを打って上手に走る人もありましたが、それも田舎者の自己流の域を脱していませんでした。*つまご(瓜子) 雪道に用いる草鞋(わらじ)につける藁製の覆い。
2015年02月15日
コメント(0)
-

庭の鳥
今日も午前は晴れていたのですが、午後からは雪が降り出しました。今日も庭には子飼いの鳥たちが勢ぞろいしました。ツグミ、ヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、スズメ
2015年02月14日
コメント(1)
-

ホオジロ
近くの江合川の葦の中で飛んでいた鳥はホオジロでした。
2015年02月13日
コメント(1)
-
換 暦
【今日は何の日】かでツイートに出ていたことです。 今まで何の日かさっぱり知りませんでしたが‥。 暦について知りえてよかったです。また換暦も便利です。 今日は「建国記念日」ではなく「建国記念の日」です。 日本が建国された日というわけではなく、 どこかにあったはずの建国の日を、今日、祝いましょうという意味。 神武天皇が即位された日がBC660年2月11日ということによります。 「辛酉年春正月庚辰朔」、 今、世界の国々では西暦を使いますが、これは「グレゴリオ暦」です。 ユリウス暦を改良したものがグレオリオ暦です。 (ユリウス暦は閏年を4年に1度入れる、グレゴリオ暦は400年に3回ずつ省く) ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えは1582年10月4日(木曜日)の翌日を、 (10日間省いて)1582年10月15日(金曜日)とする。 日本の切り替えは明治5年12月2日の翌日を明治6年1月1日(1873年1月1日)とする。 和暦、グレゴリオ暦、ユリウス暦、ユリウス日などの変換ツール 【換暦 和暦 神武1年1月1日 → グレゴリオ暦 紀元前660年2月11日 西暦には0年がないから(紀元前1年の翌年は紀元1年)、 BC660年は皇紀1年、BC1年は皇紀660年、AD1年は皇紀661年、AD1940年は皇紀2600年です。 紀元2600年記念行事が盛大に行われた1940年(昭和15年)生まれの方に、 「悠紀夫」とか「悠紀子」などの名前が多いそうです。(現在74歳) 同姓同名は 全国で?名 名字だけ、名前だけでも検索できます。 電話帳登録者なので、特に子供や女性は実際の数を反映していません。目安です。 。
2015年02月11日
コメント(0)
-

雪の日の庭
今日は雪です。庭に来た鳥たちです。
2015年02月09日
コメント(0)
-

マガン
化女沼近くの田んぼでガンが餌を食べているのを見かけました。まだガンは残っているんですね。このように皆なが立ち上がって一方向を見ているのは警戒姿勢のようです。
2015年02月08日
コメント(1)
-

スズメ
江合川沿いの葦に群がっていたスズメたちです。ベニマシコオオジュリン?
2015年02月07日
コメント(0)
-

立春
今日は立春で満月です。 国立天文台 今日の暦一昨日の江合川には、強い風の中に多数の白鳥とカモがいましたが、打って変って、今日は静かでした。カモと言ってもカルガモばかりになっていました。川辺で春の息吹を探しました。ネコヤナギが銀色の穂をつけ始め、カシラダカが…
2015年02月04日
コメント(1)
-
節分
(一昨年と同じ内容です) 季節の始まり[立春・立夏・立秋・立冬]の前日を、季節を分けるという意味で節分といいます。 一年の始まりの意をこめて特に立春の前日を指すようになりました。 季節的には今日が大晦日、あすが1年の始まりの元旦です!! 豆をまくと、後始末が大変なので口に入れました。 豆まきは、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられ、それを追い払うために行われた宮中の年中行事と寺社の豆打ちが融合したもののようです。 呪文の言葉は 豆をまいて「鬼は外、福は内」ですが鬼とは病気、災害、災難、不運など全ての不幸のもとを含めた言葉です。 現在色々な鬼が暴れまわっています。 鬼を近づけないようにしたいものですが、 鬼は鬼の面をかぶっていないので見分けるのが大変です。こんな暗い、不安な世の中ではせめて美しい映像を見て心を慰めたいものです。美しい画像を集めました。これを見て和んでください!!*美しいオーロラの写真(動画) オーロラ アイスランド、ノルウェー、カナダなど。*ノルウェーの美しい風景の写真集 美しきノルウェー *世界の棚田の写真集 世界の棚田 (場所は写真の右下のsourceをクリック)*日本の火山 デスクトップ壁紙用火山カレンダー 日本の火山
2015年02月03日
コメント(1)
-

江合川にて
今日は近くの江合川に行きました。まだ川辺は残雪が残って歩きにくいです。今日は風の強い日でしたが、白鳥(ほとんどオオハクチョウ)とカモ(ほとんどオナガカモ)が集結し整然と行進?していました。 江合川にて
2015年02月02日
コメント(0)
-

ムクドリ
今日も雪が薄く積った我が家の庭に来た小鳥たちです。今日は久しぶりのムクドリたちです。羽が黒い物の中に、こげ茶色のもがいました。常連はキジバト、ヒヨドリ、ツグミ、スズメ撮影は部屋の中からガラス越しです。キャノンEOSズーム 庭の小鳥2ツグミ
2015年02月01日
コメント(2)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 政治について
- 許しがたいこと。辞任してから言え!
- (2025-11-15 10:41:51)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【2025年11月】お買い物マラソ…
- (2025-11-15 11:01:26)
-
-
-
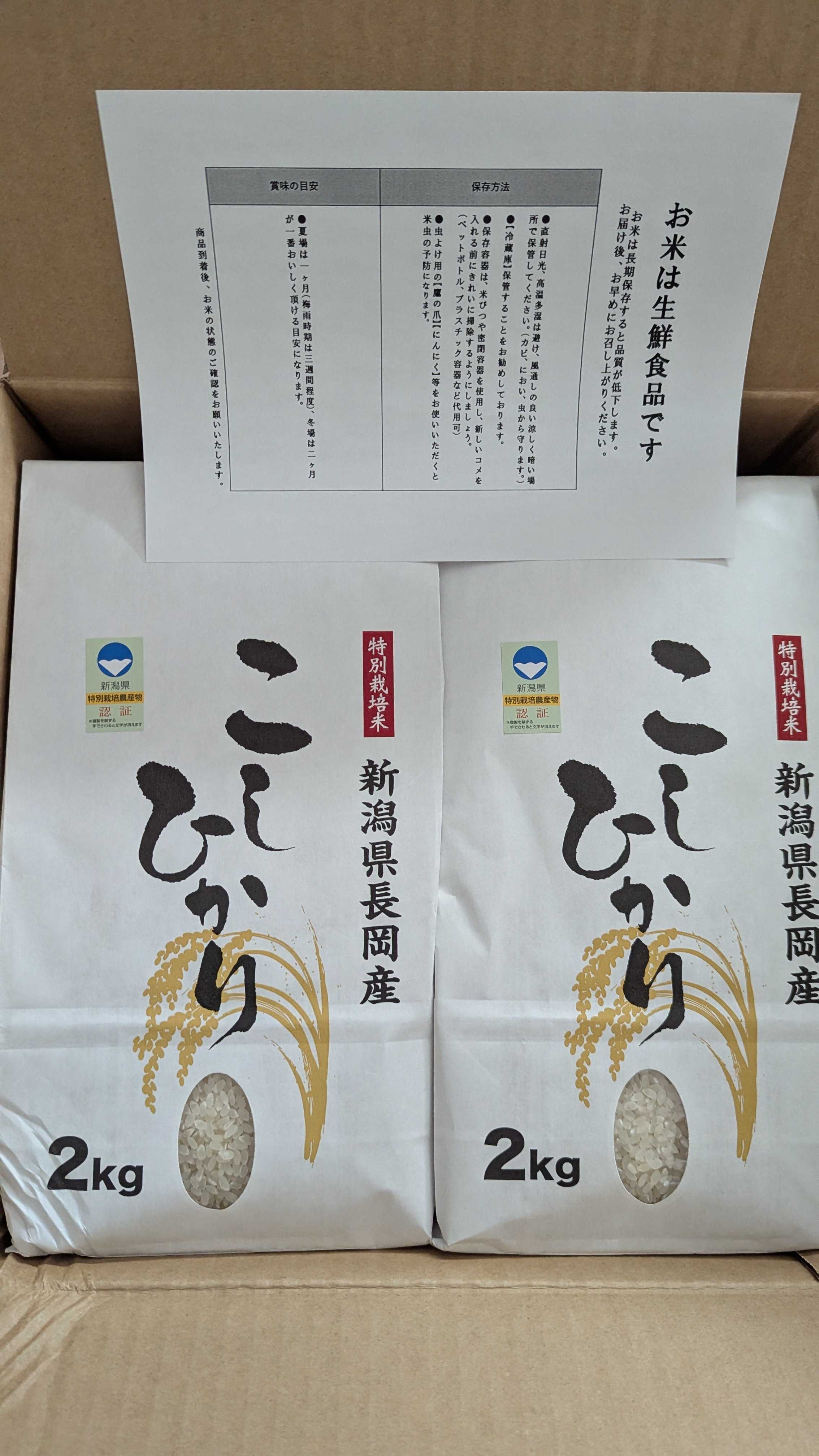
- 株主優待コレクション
- 株主優待品到着 8566 リコーリース
- (2025-11-15 13:10:04)
-






