2011年11月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
絵本 “An Angel for Solomon Singer", "When I Was Young in the Mountains" by Cynthia Rylant
子どもの絵本とは思えない内容です。ニューヨークのさびれたホテルでひっそりと暮らすSolomon は暖かい故郷の思い出を抱いて日々生きています。ある時故郷の街の名前に似たカフェにふらっと立ち寄った事で日々が輝く様になって行きます。メニューに書かれていた一言、"dream"を彼はひっそりと心の中で注文し続けて。すてきな言葉が溢れています。これを声を出して読むとほっこりと暖かくなります。これもシンシア・ライラントさんの絵本です。Audible.comの朗読がしみじみしています。シンシアさんの子ども時代のお話だと思います。子ども時代は祖父母とともに、山の中で暮らしたということです。そんなに大昔ではないのですが、本当に質素な暮らしです。電気もなくランプの光で食事をし、井戸水を汲み風呂に入ります。蛇の入って来るような池でも気にせず水遊びをしたり。でも満ち足りた幸せな子ども時代です。シンシアさんの絵本は子ども向けなのでしょうが、どれも大人も感動する物ばかりです。この2冊は特に大人こそが解る絵本だと思います。
2011.11.29
-

古いブログからの転載-9(2008年5月4日) 映画「最高の人生の見つけ方」
最高の人生の見つけ方?-?goo?映画期待以上に面白かったです。死を主題にした映画ですが、とても温かい気分になる映画です。主人公は正反対の人生を送って来た2人。ただ一つの共通点はガンで余命半年と宣告されたこと。これだけ聞けばきっと涙涙の感激ストーリーかと思いますが、大笑いのコメディーでした。でも、ほんのちょっとほろり,とさせられます。邦題は「最高の人生の見つけ方」ですが、英語のタイトルは"The Bucket List" 棺桶に入る前にやっておきたい事のリストという意味のようです。まじめなカーター(モーガン・フリーマン)が書いていたまじめなリストに、大金持ちのエドワードがどんどんリストを書き足してそれを実行してしまいます。エドワード(ジャック・ニコルソン)の大金持ちぶりが半端ではなく痛快です。自家用飛行機で世界を飛び回ります。エドワードと秘書との会話もしゃれていてユーモアたっぷりです。アメリカ英語で2人とも老人のせいか、ゆっくりしゃべってくれて聞きやすく、ちょっと英語が上達した気分になりました。最近,意識してイギリス英語を聞く様にしているのですが、やっぱり、アメリカ英語がわかりやすい。映画を見ていて台詞がわかるとうれしくなります。でもやっぱりイギリス英語、もっとがんばらなくっちゃ、です。
2011.11.29
-
古いブログからの転載-8(2008年5月19日) 映画 「ラベンダーの咲く庭で」「ムッソリーニとお茶を」「マンデラの名もなき看守」
Judi DenchとMaggie Smithが主演している映画と言えば、もう、きっと良い映画という印象で見て、すっかり虜になってもう3回目見ました。2回は字幕付きの日本向けのDVDで。どうしても手元に置きたくて、買おうと思ったのですが、日本版は高かったので、UK Amazonから買いました。送料込みで2000円ですから,日本版よりずっと安く入手できました。でも普通の日本向けDVDプレーヤーでは再生できませんが、イギリス版はパソコンでは見られます。アメリカ版はパソコンのリージョンを変えれば見られます。 という訳でイギリス版ですから、今回は英語字幕付きで見ました。ほんとにすてきな映画です。コーウォールの海岸の近くで引退生活を送る姉妹。ある日、海岸に流れ着いた若者を救助し,自宅に滞在させる事になります。 天才的なバイオリン奏者の若者と微妙な恋のの感情を抱くJudi Denchが演じる妹。ほんとに少女のようなかわいらしさです。 村の風景、村人の素朴ながら豊かな生活、イギリスの田舎の美しさがちりばめられています。 すばらしいバイオリンの演奏も堪能しながら、見終わった後,ちょっとの涙と、でも、ほのぼのとした暖かい気持ちになります。 これも,何回も見てます。映画館で見て、テレビでも見て、ビデオでも見て、その後何年かして,DVDを借りようとしたら,置いてなくて、やっぱり,買いました。中古でしたから,安かったです。 昨日,久しぶりに早く帰った息子が私のコレクションからこれを見始めたので見る事に。ストーリーがすべて分かっていても、台詞もほとんど分かっているのに、楽しめるのです。台詞がユーモアいっぱい。老婦人パワー全開です。イギリス人の笑ってしまうようなプライドの高さ。シェークスピアや午後の紅茶への頑固な誇り、嫌みにならず、ほほましく感じます。 映画の最後でスコットランド兵が「イギリス人だから,通訳はいらないね。」というと、主人公のルカが言います。「いや、言葉が通じないかもしれない。命令は通じない。」と言います。誇り高いレディー・へスターが「イタリア軍も、ドイツ軍も私たちをう動かせなかったのに、なんで,スコットランド兵が、、、」と言う台詞、ユーモアたっぷりです。 「世界中から,私達が選んだフィレンツェ」という言葉がこの女性達がいかにイタリアを,フィレンツェを愛していたかがよくわかります。実話をもとにしている様です。ネタばれにならない様に書くのは難しい。マンデラの名もなき看守 - goo 映画映画館で見た映画です。ネルソン マンデラ大統領がノーベル平和賞受賞者であることや、南アフリカ共和国での初めての黒人大統領であったことなど、新聞や報道で知識として知っているだけでしたが、映画となって見て、ネルソン・マンデラの崇高な人間性が伝わってきました。 しかし、この映画の主人公は看守グレゴリーです。グレゴリーが当時の南アフリカの白人としては当然である黒人に対する見方、言動には違和感はあります。彼の妻も当時の女性としては当たり前の言動なのでしょうが、神様の言葉も都合良く解釈してしまいます。 グレゴリーが看守として直接マンデラに接して、信念や哲学を知り、少しづつ変わって行きます。心配する妻に「マンデラに会えばわかる!」と言います。マンデラはそういう人だったのですね。マンデラにあった人は彼の魂に触れ人間性を呼び覚まされて行きます。 人間のどうしようもないおろかさを思い知らされるとともに、人間の強さや、すばらしさも教えてくれました。
2011.11.23
-
児童書 "Because of Winn-Dixie"
今日の散歩でBecause of Winn-Dixieを聞き終わりました。ずっと前に一度読んだのですが、聞いた方がずっと感動します。すばらしい朗読です。南部の小さなさびれた田舎街が舞台です。小さい時にママが家を出てしまい、パパと2人暮らしのオパール。パパの仕事はpreacher、教会の牧師さんです。パパの仕事で引っ越しが多く友達がいないオパールは、ある時街のWinn-Dixieというスーパーマーケットで野良犬と出会い連れ帰ります。犬につけた名前がWinn-Dixie。スーパーマーケットがそのまま犬の名前になったのです。その日から不思議なほど人との出会いが始まります。さびれた図書館の司書さん、犯罪歴があるとうわさの男、魔女だと怖がられている目の不自由の女性、寂しげな少女、みんなどこかに寂しさを感じさせます。Winn-Dixieが結びつけてくれた人とのつながりがオパールとその人々も少しずつ変えて行きます。南部なまりの発音で朗読されますが、それがまたいい雰囲気です。この朗読の俳優さんが映画でも演じたらきっとすてきだろうな、と思います。
2011.11.23
-
古いブログからの転載-7(2008年5月9日)"Homeless Bird" "The Fire-Eaters"
児童書ですから、難しい単語も少なくて読みやすいのですが、内容は深刻です。インドの、それほど昔ではないらしい時代の女性の結婚制度の犠牲になった少女の話です。 持参金目当てに病気の少年と結婚させられてしまった少女が、悲惨な状況の中で自立して行く様子が明るく語られます。少女の作るキルトが希望を開いてくれます。とてもさわやかで元気の出る作品です。1962年アメリカとソ連が今にも核戦争を勃発しかねない状況にまでせまっていたキューバ危機、その年のイギリスの田舎町の少年の日常を描いた作品です。何気ない生活の中に忍び寄る不安が、不思議な曲芸師McNulty、原因不明の病気を抱えた父親との会話の中で浮かび上がってきます。Bobbyの純粋さに心うたれます。戦争の危機を感じながら、世界を救うためなら,自分を犠牲にして下さい、と祈ります。Skelligの作者David Almondの2004年の作品です。--------------------------------------現在の感想(2011年11月19日)どちらも強烈なイメージが残っています。Homeless Birdは大人の会員さんに人気です。
2011.11.19
-
古いブログからの転載-6(2008年5月4日)映画 「つぐない」
つぐない?-?goo?映画映画の写真からみて、センチな恋愛映画かな、っと思いきや、とんでもない。見終わってから、しばらく映画の場面が頭から消えず、ずっと考え続けてしまいました。なぜ? なぜ? あまりに悲しい、あれでいいの?と。 今年の一番の映画でした。原作も絶対読みたいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー今でも鮮明に覚えています。もう一度見たい映画です。
2011.11.19
-
古いブログからの転載-5(2008年4月18日) "Family Honor"
ひさしぶりにミステリーと言うか,探偵物を読みました。Amazonの書評が良かったのでだいぶ前に買って,ちょっ読んで、やめたらしい。途中迄読んで、これ読んだ事あったっけ、と気がついたのですが、なぜかやめたか不明です。 今回はわりとスイスイ読んだのですが、最後まで読んでも、やっぱり,あまり好きはなれないタイプの小説である事が判明しました。暗黒の世界、裏の世界、殺人があまりに簡単に行われるのが納得いきません。 日本のミステリーでは夏樹静子や宮部みゆきをたくさん読みましたが、アメリカのものにはなかなか好きな物に出会えません。日本語で読んだ時も同じ様に感じた感じたのでやっぱり,好きではないのかもしれません。 まだまだ未読本があるので、児童書とPBと混ぜながら楽しんで行きます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー今日の感想(2011年11月19日)どんなストーリーだったのか、覚えていません。書いておかないとまた同じ本に手を出してしまいそうです。
2011.11.19
-
古いブログからの転載-4、2008年3月29日 "Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe" by Fannie Flagg
初めて映画を見たのはもう10年以上前、子ども達が学校へ行っている隙間時間に、知人からたまたまもらった無料券で全く予備知識もなく見に行って大感激し、その日は一日中映画の余韻に浸っていました。その当時はこの本が読めるなんて思ってもいませんでした。100万語くらいのころに思いつきでDVDと本を買って、DVDは見ましたが、映画の内容からして難しいだろうと本箱に置いてはや4年、ふとした事で読むきっかけがやってきました。 1週間くらいこの本に取り憑かれてました。先へ進みたいけど、読み終わるのはもったいない、でも読みたいと、とうとう今日読み終わりました。もう大感激でした。映画よりもずっと細かい人間描写、たくさんの登場人物、それぞれがみんな生き生きして、登場人物がみな主人公の様です。 現代(といっても1986年ごろ)と1920年~40年ごろを行ったり来たり、老人ホームで暮らすNinnyが中年女性のEvelynに語る昔語りという形式で物語が進みます。その間に昔の新聞記事やEvelynの現在の問題などが入ります。最初は年代を確認ししたり、たくさんの登場人物の関係が混乱したりしましたが、映画がよみがえって来て読みやすくなってきました。だんだん映画と違うところが多くなって来て、それが面白くて読むスピードが上がってきました。 昔の南部の生活が懐かしく語られますが、その中に人種問題があり、大不況の時代あり、ウーマンリブの話があり、サスペンスあり、ロマンスあり、本当にいろんな問題が語られています。料理もその一つ、カフェで出されるメニューがとてもおいしそうで食べたくなります。読みながら,いい香りがただよおってきそうでした。きっと読む人みんながそう思うのでしょう。本の最後のページはカフェのメニューのRecipeが載っています。フライドグリーントマトを作るには緑の熟していないトマトが必要なのですが、いつか作ってみたいものです。
2011.11.16
-
小学生クラスの一緒読み Folk and Fairy Taleシリーズ
小学生クラスは70分レッスンの最初20~30分は自由多読です。その後に全員一緒に同じ本を読む「一緒読み」をしています。6年生のクラスでは今、Scholastic社のFalk and Fairy Tales、Easy Readersのシリーズを読んでいます。10分くらいで1冊をゆっくり読みます。繰り返しが多く最初の2~3ページを一緒に声を出して読むと後は一人でも読める様になってしまいます。読みながらQAしたり英語で発話させながら読みます。最近6年生たち、スラスラ読める様になって来て感激しています。今日読んだのはMartina the Cockroachというお話です。これは何とCockroachさんがドレスを着て、香水をつけてさあ、これでお婿さんを探そう、というお話なんですが、これにはみんなあきれてしまってました。14cm×14cmサイズの小さい絵本が15冊が一組、私が持っているのはそれが5組は行った物です。4人が最高人数のこの教室ではちょうどいい数です。
2011.11.15
-
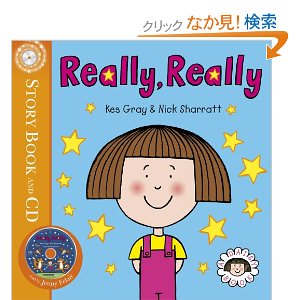
新着絵本 "Really, Really" by Kes Grag & Nick Sharrat
何とも楽しいNick Sharattさんのイラストです。おかっぱ頭のDaisyちゃんのシリーズはどれもあんまりいい子のお話ではないんですね。でも、こんなだったら楽しいな、というお話です。お母さんがお出かけ、イギリスでは子どもを一人置いて外出したら行けない法律があるという事です。そんな時はBabysitterさんがやってきます。Daisyはこのときとばかりに普段でできない事をやってしまいます。お母さんから渡されたリストなんて無視して自分の好きな物ばかり食べて、夜更かしして。いつも何時に寝るの?12時よ。Really?Really, really.パジャマ着て!いつも服のままで寝るの。Really?Really, really.いつも真夜中までビデオ見るの。Really?Really, really.fibbed Daisy. と繰り返されます。ここで私,初めてfibを知りました。こんな悪い子きっとお母さんにしかられるし、Babysitterさんだってこれじゃあ,困った物よね。きっとお給料ももらえないよね。さあ,結果はどうなるでしょう。お楽しみに!新しい絵本のかごに入っています。
2011.11.15
-
古いブログからの転載-3 フィンランドの教育の本 2008年3月18日
英語多読の本ではありませんが、最近では一番感心のあることなので、書いておきたいと思います。フィンランドの教育が日本とは大きな違いがある事は予想通りですが、あまりの違いにショックでした。基本的に違う事はだれでもどこでもほぼ無料で教育を受ける事ができるということ。日本でも建前ではそれが保証されているはずですが、実際は教育は大変お金のかかる事になっています。 2冊目の本では具体的な教室の様子が多くのページを割かれて書かれています。小学校から中学校まで先生の指導技術が高度な物である事が分かります。一斉授業でないので、大変な注意力やコントロール力が必要とされるようです。 教科書の内容は日本に比べるとかなり量は少なく、授業時間もかなり少ないのに最終的には学力が高いという事は、今日本で、授業時間を増やせば学力が上がると世間で言われている事はいったいどういうことなのでしょう。 これからの子ども達、日本の未来を考えると無関心ではいられない問題です。
2011.11.14
-
古いブログからの転載-2 "When My Name was Keoko" 2008年2月29日
【送料無料】When My Name Was Keokoずっと前に読んだ本ですが、とても印象に残っている本です。Korean Americanである作者の母親世代の経験に基づいて書かれたという事です。日本の植民地として日本の教育を強制され、日本語を話す事を強制され、日本名を強制された人々の日常が淡々とした子どもの日記の形で描かれています。 教科書的な知識では知っていたことですが、英語多読のおかげで、考える機会を与えてもらった本でした。児童書ならではの子どもの視点で描かれているのが救いです。だからこそ、切なさが伝わってきます。
2011.11.14
-
古いブログからの転載-1 "Butterfly Lion" 2008年2月28日
最初に開いたブログがあるのですが、有料でずっとお金を払っているのに全く書いていないので、閉じる事にしました。主に趣味の映画や読書の事を書いていたので、このブログと2本建てにしようとしていたのですが、こちらに映画の事も書く様になったので閉じる事にしました。それに際して記録のためにこちらに転載いたします。しばらく古い記事ばかり続く事になります。読んでくださっている方ごめんなさい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一番最初の本の紹介に大好きなこの本を書く事にしました。もう3年以上前にBBC7のBig Toeの音源を聞いたのが最初でした。MP3プレーヤーに入れて聞いたのですが、これがすばらしく、今迄に何回も聞いています。アマゾンでも音源は買えるようです。その後本も買って読みましたが、やっぱり聞く方がすばらしいです。散歩中に聞いて、涙がでて困ってしまい、ベンチに座ってしばらく物語の世界にひたっていました。"Bitterfly Lion" イギリスの寄宿制の学校から逃げ出した「私」が古い館の前で出会った老婦人から聞いた話。遠い昔を懐かしむように「私」に話してくれた白いライオンと少年の物語です。アフリカの広大な自然と、イギリスの古い館や学校が目の前に浮かんでくるようです。
2011.11.14
-

映画 ゴーストライター
ゴーストライター?-?goo?映画映画「ゴーストライター」を見てきました。久しぶりにハラハラドキドキする映画を堪能しました。最後までいったい誰が陰謀の人物なのかわからず、目が離せません。イギリスの元首相のラング氏の自伝を書くという仕事を請け負ったユアンマグレガー扮する主人公。今気がついた、この人名前なんだっけ、名乗っていなかったような。自己紹介の時"I'm a ghost."と言ってたような。ゴーストライターですから。サスペンスの主人公ですから、さぞかっこいい活躍をするのかと思ったのですが、ユアンマグレガーはなんか情けない感じのゴーストライターです。自分が意図していないのに巻き込まれてしまいます。また首相役の007のピアーズブロンソンもあんまりかっこ良く見えない。ブレア元首相がモデルとも言われています。こんな2人ですが、話の規模は大きいのです。前任者が不審な死に方をしている。元首相もなんだか怪しいし、その妻も愛人のような秘書も。CIAも出てくるし、テロもからんでいる。サスペンスが好きな人にお勧めの映画です。
2011.11.12
-
繰り返し読んでほしい絵本たち
絵本には2種類あると思います。大人がそばにいて子どもに読み聞かせると言う設定で書かれている絵本、いわゆる人に読んでもらう絵本、かなり難しいものもあります。もう一つは、幼稚園や小学校の低学年の子どもが語数の少ない物から少しずつ自力読み出来る様になるための絵本です。簡単な語彙、少ない語数で書かれています。大人の方が、さあ多読を始めよう、絵本から、と前者の難しい絵本を開いて、ショックを受けるという事はよくある事です。そんな絵本の中にはさすが名作、子どもが大好きになる様に、繰り返しが多く、韻を踏んでいて、文法的にも勉強になる物がいっぱいあります。そういう絵本は1回読んでおもしろかった、おしまい、ではもったいないと思います。たくさんある中から、私の独断で「繰り返し読んでほしい本」をかごに集めました。また完成はしていませんが、徐々に増やして行きます。繰り返し読んでいつの間にか覚えてしまったとなってくれたらと思います。日本語の絵本も子どもは繰り返し読んでどんどん語彙が増えて行きます。それと同じだと思います。今日の所かごに入っている絵本 これらの絵本はどれもリズムののいい、一緒に声を出すと楽しい絵本ばかりです。大人の方もぜひ、声を出して読む事をお薦めします。
2011.11.09
-
"War Horse" by Michael Morpurgo
多読初期の頃に出会った"Butterfly Lion"以来ずっと大好きな作家のMichael Morpurgoの作品を出来るだけ読もうと思っています。あれこれ探していたら、出会ったのがこのWar Horseです。今War Horseで検索すると映画のTrailerが出てきます。そして、もう何年か前からLondonの劇場で演劇として上演されていたという事も知りました。今度行ったら絶対みたい。もうすぐ日本でも映画が公開になります。スピルバーグ監督で来年3月公開です。映画公開の前に読まなくては思って読み始めたら、私の多読始まって以来の難しさ!Audibleの音源で聞き読みをしてみましたが、Unabridgedのはずなのに所々単語が違ってるし、倒置が多くて戸惑ってしまいました。で、やぶれかぶれ、ただ聞くだけにしてみました。そしたら、何と不思議、スイスイと頭に入ってくるのです。文章が馬の語りという形で書かれているせいなのか、とても読みにくかったのですが、聞いているとそれが気にならないのです。多分、分からない所を気にしている暇がないのでしょう。朗読はかなり訛の強い、いかにもイギリスの田舎のような尻上がりのアクセントとくせの強い発音です。でも味わいのあるいい朗読です。という訳で、映画公開の前に投げ出さずに読めてよかった!感動の要素が詰まっています。少年、動物(馬)戦争、ほのかな恋、絶対泣けます。第一次世界大戦のころにはあったに違いないストーリーです。
2011.11.07
-
教室の英語まんが本が増えました。
世界的にも大人気の日本の漫画です。世界のあちこちから漫画で日本語を習得した人たちの話が聞こえてきます。まず現地語で書かれた漫画を読み、その後は日本語の原作を読み、アニメを見て会話を修得していき、最近では日本語の簡単な物語を読むという日本語多読も徐々に広がり始めています。その反対に英語の習得にも漫画は有効なはずです。以前から漫画は教室においていますが、円高の今が購入チャンスと、またどっと増やしました。教室にある英語漫画本をご紹介します。One Piece1巻~5巻 nodame 1巻~7巻 doraemon1巻~10巻 Case Closed(名探偵コナン) 1巻~4巻最近入った漫画本from me to you(君に届け) 1巻~5巻) Kiki's Delivery Service(魔女の宅急便)全4巻 honey and clover(ハチミツとクローバー) 1巻~4巻この他にアメリカの漫画ですが、snoopyも10冊ほどあります。この中で一番簡単なのは「魔女の宅急便」です。画像が映画の写真そのままでとってもきれいで、せりふ(英語)が少なく読みやすいです。どうぞ、どんどん読んでください。
2011.11.06
-
"The Little Old Lady Who Was Not Afraid of Anything"
ハロウィーンレッスンは先週でしたが、小学生クラスは今週も絵本の読み聞かせはハロウィーン系です。怖い物知らずのLittle Old Ladyが森にハーブやナッツを摘みにお出かけ、暗くなって来てしまいました。何にも怖くないおばさんの後ろに何やら奇妙な音がします。Clomp, Clomp,靴が付いてくるのです。その後はズボンが付いて来たり、シャツが付いて来たり、でもおばさんは、ずっとこう言い続けます。"Get out of my way, I am not afraid of anything"この部分を生徒全員に一緒に言ってもらいました。それぞれの擬音をまねしたり、台詞を言ってもらったり、おばさんはどうしたらいいと思う、と問いかけてみたりとかなりActing Outを取り入れた読み聞かせをしています。この絵本はそれにはぴったりの絵本です。最後の最後が楽しい絵本です。ハロウィーンが終わったと思ったら街にはクリスマスソングが流れています。冬の絵本とクリスマス絵本も再来週には出します。
2011.11.04
-
"Weedflower" by Cynthia Kadohata
先週からまた読み(聞き)始めて今日の散歩で聞き終わりました。もう最後には歩きながら泣きそうでした。朗読が本当にすてきです。パールハーバーの後、日系アメリカ人の生活は一変。それまで築いて来た物をすべて失い、収容所に移動。そこでの日系アメリカ人のたくましさの物語は最近ではテレビドラマでも取り上げられていましたが、少女の目を通して、もっと直感的な、普遍的な友情とか理不尽な物への怒りが静かな言葉な描かれています。なおさら悲しさ、怒りが伝わってきます。収容所の近くに住むインディアンの少年との友情と恋もすてきです。もし現実にこんな事があったとしたらきっと2人は文通し戦後再会を果たした事でしょう。無気力になって行く大人たち、ワイルドになって行く子どもたち、アメリカ兵として戦争に行くもの、N0-no boyとなって移送させられて行く人々。すみ子は現実を忘れる様に庭作り、花作りに没頭して行きます。すみ子にとって草花は希望だったのです。朗読の最後の方には作者のCynthia Kadohataさんの生の声でインタビューが入っています。今までハードカバーしかなかったので、ペーパーバックを買い足し会員さんにも音源付きで読んでもらえる様にしました。
2011.11.03
-
もう、年末!
もう2011年も2ヶ月なんて早すぎる!11月~12月のスケジュールを載せました。上のHOMEの「教室のスケジュール」をクリックして下さい。11月中は何も変化はありません。通常のカレンダー通りです。祭日の特別オープンもありません。木曜日午前中の多読クラブは10日と24日の2回です。このごろ午前中の会が充実して来ています。大人の会員さん15人ほどのうち、午前中の多読クラブに来ている方は5人くらいです。毎回来られる方、夜と午前中時々の方などさまざま。午前中は中高生がいないので、ゆっくりじっくり読んでいただく事が出来ます。絵本や薄っぺらいピンクレベルや赤レベルの本は教室で読むのが一番です。
2011.11.01
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天お買い物マラソンで“買いすぎ”迷…
- (2025-11-25 12:00:06)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🍚 My Healthy Life, Part 2: Trying…
- (2025-11-25 12:10:09)
-







