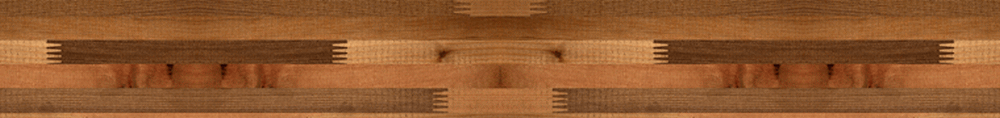2011年03月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その6
こんにちはenoです。 "動的筋力"プログラムの最も大きな欠点としては、これらの運動を行うなかで、背筋や膝を痛める選手が出てきたことだ。 これらの運動そのものが障害の原因というより、もともと障害を抱えていたところがこれらの運動でさらに悪くなったと思われる。 私には選手の痛みが、我慢できる(障害に結びつかない)痛さなのか、障害の警告としての痛さなのかがわからなかった。 少々の痛みで音(ネ)を上げるなんて、スポーツ選手としては甘いという考え方が私にあって、例えば、30回という回数を全員一律でやらせてしまうときの危険性がこのときにはわからなかった。 こうした経緯の中で、単純に体力だけでなく、体の構造そのものにも個人差があるだということが次第にわかってきた。 それにともない、スポーツ医学にも興味を持つようになった。 "動的筋力"プログラムは、結局ケガの心配から行わなくなり、良き詰りの結果、筋力トレーニング・プログラムを一切行わない時期があった。 技術練習のみとなったわけであるが、今考えてみると、筋力トレーニング的要素を含んだ練習がその時に行われており、それは十分に成果をあげた方法だったと言えると思う。 それは、規定の重さよりも重くしたボールを使っての練習である。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月30日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その5
こんにちはenoです。 ゴムチューブによる"静的筋力"トレーニングの欠点は、筋力がどれくらいアップしているか分からないし、「何かをやり遂げた!」という達成感が無いことだ。 確かに上級生と新人を比べると、保持できるチューブの伸びや時間に差がある。 トレーニングの効果はあるのだろうが、実感としてそれが感じられない。何か変化と達成感のあるプログラムが欲しいと思った。 そこで、動きの中で筋力強化をしようと考えて作ったのが、"動的筋力"プログラムである。 "静的筋力"という言葉あるのなら、"動的筋力"という言葉があってもいいじゃないかと勝手に命名した。 これは、腕立て、腹筋,背筋、懸垂、スクワット、サイドキック、ハーキー・ジャンプ、モモ上げ、等々、従来から一般的に行われている各種の運動に変化をつけて、筋力強化プログラム化したものである。 この"動的筋力"プログラムは、徒手で行うと、慣れてくれば回数を多くこなせるようになり、技術練習の時間を食われるようになるので、ダンベルや砂袋を使って負荷をかけて行うことにした。 ところが、このプログラムも、慣れてくるとただ単に回数をこなすだけという惰性的になりやすい面が感じられた。 また、どの程度効果が上がっているのかが、具体的にわからないという不満が私自身にもあった。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月25日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その4
こんにちはenoです。 これまで作ったトレーニング・プログラムの中に、"静的筋力"と"動的筋力"というプログラムがある。 "静的筋力"プログラムは、自転車のゴムチューブを利用したもので、いわば、ゴムチューブを利用した「アイソメトリック・トレーニング」である。 今ではアイソメトリックという言葉はスポーツの世界で一般的なものになっているが、私がこの方法を初めて知ったのは今から40年以上も前のことで、その時の言葉が"静的筋力"だった。 器具を使わずに、手と手を押し合わせたり、引っ張ったりするだけで筋力がアップするという話を聞き、画期的な方法だと思った。 その後、当時のチームに早速この静的筋力トレーニングを行うことにした。 最初は、器具なしで行うプログラムを色々考えてみたが、上手くいかないので縄跳びのロープを使うことにした。 ところが選手にとっては、変化の全くない状態でジッとしているのはつまらないということと、最大限の力でロープを引っ張るので、ロープが手に食い込み痛いという欠点があった。 そこで、動きに多少変化があり、同じような効果を狙えるものとして、自転車のゴムチューブを利用することにした。 このゴムチューブによる"静的筋力"プログラムを半年間続けたが、この方法の欠点は、筋力がどれくらいアップしているか分からないし、トレーニング中も「何かをやり遂げた!」という達成感が無いことだ。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月23日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その3
こんにちはenoです。 日頃より「 Basketball is my life 」をご愛読頂き、誠にありがとうございます。 皆様もご存知のとおり、東北地方で大きな地震がありました。 いまだ十分な情報もなく、混乱した状態ではございますが、皆様とご家族のご無事と被害が最小であられますことを心よりお祈り申しあげます。 このような状況ではございますが、普段通りメールをお届けする事が、私ができる唯一の貢献ではないかと考え、配信することにいたしました。 ------------------------------ コーチ自身が面白くないと考えているものを、選手には面白いと思えというのは説得力を持たない。これこそが、コーチングの悪い見本のようなものなのである。 筋力トレーニングと楽しさ(面白さ)は両立するか? 振り返って見ると、私はこの問題を常に抱えながら、しかもより安全で有効な方法を目指して指導してきたのだと思う。 結果は、紆余曲折、失敗の連続である。 一体、何が失敗の要因だったのだろうか? 成功した一面もあるが、それは突き詰めると、なぜよかったのか? 私の筋力トレーニング"紆余曲折史"の中から幾つかの例を取り上げて、これらの点を考えてみたいと思う。 そして、それが、読者の皆さんの"近道"の第一歩になればと思う。 これまで作ったトレーニング・プログラムの中に、"静的筋力"と"動的筋力"というプログラムがある。 "静的筋力"プログラムは、自転車のゴムチューブを利用したもので、いろいろな姿勢のなかでゴムチューブを引き伸ばし、その状態を保つ。 いわば、ゴムチューブを利用した、「アイソメトリック・トレーニング」である。 アイソメトリック・トレーニングとは、 筋肉の活動の仕方には2種類あり、ひとつは筋肉が伸び縮みする活動(アイソトニック運動)で、腕立て伏せやベンチプレスなどをしているとき。もうひとつは、筋肉が伸び縮みしない活動(アイソメトリック運動)は、腕立伏せで静止している時とか、ビルの壁を腕で押そうとしている時などである。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月21日
コメント(0)
-
楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング (番外)
こんにちはenoです。 大変なことが起こってしまいました。まさか日本でこれほどの地震があるとは・・・私自身、丁度大阪へクリニックに行くため、駅へ向かう時に、この地震は起きました。思わず気分が悪くなったのかと思いましたが、次の瞬間倒れてしまいました。此れは如何したのかと周りを見渡したら何人かの人が膝をついていました。駅の高架の部分に居たために揺れも大きかったのでしょうが、驚きました。そんな訳で全ての電車は止まり、帰ってTVを観たらこれまた驚きで、大変なことが起きていると言うのが実感されてきました。 今は少し吾が方も落ちついてきましたが、ブログの更新は今しばらくお待ち願いたいと思います。 PS. 被災地の皆さん、頑張ってください。
2011年03月14日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その2
こんにちはenoです。 スポーツをするからには楽しくなければ言葉の意味がない。いわゆる、猛練習主義とスポーツを楽しむことは矛盾しない。 スポーツを行うものの気持ちの持ち方、"練習する心"が大切なのである。 苦しみを自分で選ぶかどうかで、それが楽しさにも変わるし、ただつらいだけの練習にもなる。 当たり前のこと(そしてこれが以外と無視されがちなこと)だが、選手個人々の意識が最も大切なのである。 このことは、考え方を変えれば、選手個々がそうした意識を持てるような状況をつくるのが大切だということである。 そしてコーチの仕事として、このことが最も難しい仕事なのだと考えるのは私一人ではないと思う。 さて、上記の"猛練習"という言葉を、"筋力トレーニング"に置き換えて考えてみよう。 私たちは筋力トレーニングを、単調で面白くないもの、苦しいだけのものと感じてはいないだろうか? 自戒の念を込めて言えば、私はそう感じている一人である。 コーチ自身が面白くないと考えているものを、選手には面白いと思えというのは説得力を持たない。 これこそが、コーチングの悪い見本のようなものなのである。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月07日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その1
こんにちはenoです。 猛練習と楽しさは両立するか? 猛練習というと、「辛い」「苦しい」などのイメージがある。 また、鬼コーチによってシゴかれるというのも、これらのイメージとセットになったイメージと言えるだろう。 猛練習というのは、シゴかれて、辛いばかりのものなのだろうか・・・ 私の恩師である畑龍雄先生が書いた文章の一筋に、"楽しく猛練習を"というくだりがある。 少し長くなるが、その部分を引用してみたい。 『 困難があるから練習するのである。だから練習することはやりにくいことが多いに決まっているし、やりにくいことには気が進みにくいことも事実である。どんなに気が進まなくとも、実際にやる以上は、「よーし!やるぞ!」という自分の積極的な決心に立て直して始めて練習というものである。気が進まないことでも進んでやる。それが練習の心である。進んで身に受けた苦しみは、楽しんですることが出来る。これが苦しい練習も楽しくやってのけるスポーツの楽しみ方である。スポーツをするからには楽しくなければ、というのはこの言葉の意味である。いわゆる、猛練習主義とスポーツを楽しむことは矛盾しない。』 文章の一部の抜粋なので文章を理解しにくい面もあると思うが、要はスポーツを行うものの気持ちの持ち方、"練習する心"の大切さを言っている。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年03月03日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1