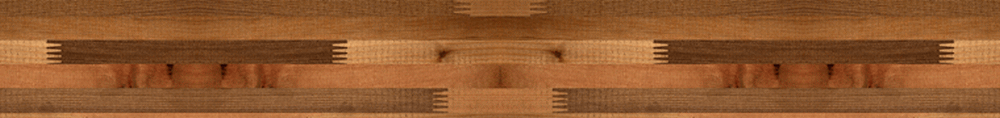2011年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

トレーニングは進化する その7
こんにちはenoです。 中・高校時代から障害を抱えている選手は、それを持病と決め込んであきらめている選手が多いのではないか。 しかし、適切なケアをトレーニングによって、こうした障害もある程度克服できることが多い。 ベスト・コンディションをつくるための選手の意識の改革も、トレーニングの重要な課題と言える。 今後のトレーニング課題として、トレーニングに限らないが、スポーツを実際に指導するうえで、分からない点は多い。 そして、私たちコーチには、常に現実的な対処法、解決の手段が求められる。 ここでは、日立戸塚で抱えていたトレーニングの課題の中から、重要な点をいくつか挙げていこうと思う。 前回でも少し述べたが、単に基礎体力を伸ばすというのではなく、バスケットボールという競技にとってのウェイト・トレーニングはどうあるべきなのか?どのような種目で、どれくらいまで最大筋力を高めればよいのか?スピード・トレーニングの重要性は?重要だとすればどういう内容がよいのか?さらにシーズン中のウェイト・トレーニングの内容はどうあるべきか? 別に完璧な答えを求めていたわけではないが、確かな指針、実際的な手引きとなるようなものが当時はあまりなかったのでる。 バスケットボール以外の競技でも、同様な問題があるのではないだろうか・・・ ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月23日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その6
こんにちはenoです。 私1人であれば、選手を思い切って休ませることが出来なかっただろうし、その選手に対する個人メニューを作り、それを指導するということも難しかっただろう。 また、選手にしても、トレーナーのいるチーム体制で育ってきていたので、練習を休むことに対してのいたずらな不安や焦りもなく、その後の競技復帰のためのトレーニングに対しても理解が早くスムーズに進んだと言えよう。 トレーナーの仕事について具体例と共に紹介していくと、話が長くなってしまうので、1つ例を挙げると、足関節のテーピングは特に必要と考える選手以外は、なるべく巻かないようにしたということである。 これは、足関節のテーピングを行ったために他の部分に負担がかかって痛めてしまう危険性があるのでは無いかと言うことである。 また、無理に「テーピングに依存する習慣」をつけないようにするためだ。 さらに、「外せるテーピングはなるべく外す!」と言うのが、日立戸塚のトレーナーの方針であった。 もう1つ、トレーナーが挙げている課題として、新入部員に対して、ケガに対する"意識"をも持たせるということがあった。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月19日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その5
こんにちはenoです。 日立戸塚を"卒業(私は引退ではなく卒業と言っている)した選手で、木塚という選手などは、その後6年間プレーを続けたが、6年目が体力的にも最も充実していたし、動きもシャープだった。 "上級生"になるほど技術、体力ともに充実させていける理由は、大きく分けて2つある。 1つは、トレーナーの加入で、選手の健康管理体制が、年ごとに充実してきていること。 もう1つは、やはりトレーニング・コーチの加入で、より質の高い充実したトレーニングが可能になったことだ。 前年度のシーズン中のトレーニングの成功で、チームの"トレーニングの歴史"は、さらに一段高いレベルに達したと思っている。 トレーニングについて語るうえで、選手の健康管理、つまりトレーナーの役割は重要だ。先の試合中に腰を痛めた選手の場合でも、トレーナーの果たした役割は大きい。 こうしたケガでは、基本的に医師の診断団を受けて、それをもとに競技復帰の計画を立てるわけであるが、ケガをしたら必要な休養を取るとともに、チームとは別メニューでトレーニングをこなすというシステムが確立してきたと思う。 この選手の短期間の復帰も、まさにそうしたチーム体制があったからこそだと言えよう。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月16日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その4
こんにちはenoです。 シーズン中のトレーニングを行った効果は、予期せぬところにも表れた。 3月一杯で公式戦を終えて、2週間の休みの後、新シーズンの練習に入ったが、例年であれば、シーズン中は4~5ヵ月間トレーニングを行わないため、落ちた体力を取り戻すためにかなりの期間を要する。 ところが、この年の新シーズンはその体力を戻す期間が非常に短かった。 というより、入部2年目の選手などは、シーズン中に試合に出なかった分だけレギュラー選手よりもトレーニングを十分に行った。 メニューを渡し、週4~5回のトレーニングを行わせたので、前年度のシーズンオフの時期よりも体力(最大筋力や持久力)などが著しく向上していた。 つまり、シーズン中のトレーニングは、次のシーズンのスタート時点の体力をも高める効果があると言えるのではないだろうか。 特に、それまでトレーニングをあまり行っていなかった選手にとっては、その効果は事のほか大きい。 当時、日立戸塚では、"上級生"になるほど、技術だけでなく、体力もレベル・アップする。 昔のチームであれば"上級生"にあたる4~5年目の選手は、相対的に練習量を落とさざるをえなかった。 何故かと言えば、いわゆる「ロートルは体にガタがきていて頑張れない。」が、当たり前であったからである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月12日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その3
こんにちはenoです。 球技の場合、タイムや距離を競う種目に比べると、トレーニングの効果を競技成績と結び付けて語るのは難しいが、1986年度のシーズン中のトレーニングの効果として最も大きな点は、シーズン中のケガが非常に少なかったということだ。 足関節の捻挫以外に、大きなケガはなかったが、ある試合中のアクシデントで腰を痛めた選手がいた。 試合後2日間は痛くて歩けないほどで、これまで選手のケガを見てきた私の経験からは1週間後の試合には無理ではないかと感じられたが、驚異的に回復できた。 不幸中の幸いだったと言えようが、シーズン中のトレーニングで体力が高いレベルで維持できていたことが、この"幸い"を招いたような気がする。 実際、体力チェックのデーターを見ても、シーズンオフに高めた体力が、シーズン中も維持できていたのが分かる。 大きなケガが無く、選手が無理を押して試合に出るということが、当年度のシーズンはほとんど無くて済んだ。 何よりもこのことが、チーム力にとっての大きなプラスだったと言えるだろう。 さらに言えば、シーズン中も維持できたその体力が、それぞれの動きに反映されたと思うし、選手の体力的な自身は試合にも積極的なプレーとなって現れていたようだ。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月09日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その2
こんにちはenoです。 今回試みたシーズン中のトレーニングについて、その成果を振り返ってみると、まず、トレーニングの内容について簡単に触れておこう。 日曜日が試合として、1週間のスケジュールを、基本的に次のように行った。 月曜日:休養日。火曜日:水曜日:どちらかの日に、ウェイト・トレーニング+ランニング・ドリル。木曜日:休養日。金曜日:ウェイト・トレーニング。土曜日:調整日 トレーニング時間は、練習の終りに30分間程度。週の前半のトレーニングは、ウェイト・トレーニングトランニングを組み合わせたスーパー・サーキット・トレーニングの方式で行った。 方法は、まず選手を2組に分けて、Aグループがマシーン(カイザーカム・2)でトレーニングしている間、Bグループが体育館の縦を往復する。そして、それぞれのトレーニングを交替してすぐに次のセットを開始するというもの。 マシーンは空気圧だが、最大の50%くらいの負荷にして、ランニング・グループと交替するまでの間、出来るだけ早いスピードで行う。 1種目のウェイト・トレーニングを1セットとして、10セット行うように行った。 金曜日のウェイト・トレーニングは高負荷・低回数制で3セット行った。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月05日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その1
こんにちはenoです。 前回の最後のところで、私が監督をしていた日立戸塚バスケットボール部のトレーニングは、過去のトレーニングの歴史の上に成り立っているという意味の事を書いた。 大げさな言い方だが、つまり、トレーニングが決して同じことの繰り返しではなく、試行錯誤の中で発展していくものであるという事を言いたかった。 そのチームが持つ固有な条件の中で、トレーニングも"進化"していくのである。 今回は、日立戸塚の過去のシーズンを振り返りながら、その"進化"の状況を紹介してみたい。 以下に、トレーナー、トレーニング・コーチとともに話し合った内容の要点をお伝えする。 1986年のシーズンのトレーニングで、これまでともっと大きく変わった点は、シーズン中(公式試合期間中)も、週3回の計画的なトレーニングを入れたことである。 これまでもシーズン中に全くトレーニングを行わなかったわけではないが、きちんとプログラムを組み、継続的に行ったのは初めてであった。 これには、3年前からトレーナーやトレーニング・コーチがチームに加わり、チームの指導体制が充実してきたことによるところが大きい。 こうした専門スタッフがいることは、やはりチームにとって大いにプラスである。 それぞれのチームで事情はあるだろうが、なんとか工夫してコーチングの役割分担をすることを奨めたい。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年09月02日
コメント(1)
全7件 (7件中 1-7件目)
1