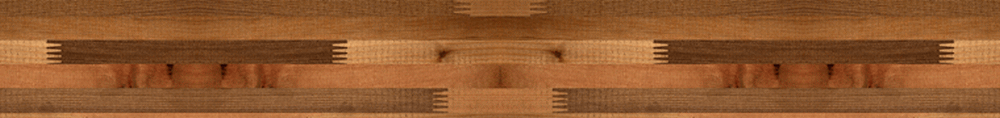2011年08月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

コーチと選手のギャップ その8
こんにちはenoです。 バスケットボールのためのコンディショニングという言葉を使ったが、そのための具体的な、確かたる内容があるわけではない。 よく考えてみると、私たちの周りには分からないことだらけで、経験的により良いと思われる方法を私たちは行っている。 例えば、ウェイト・トレーニングにしても、どういう種目で、どのようなプログラムで行えばよいのか?最大筋力はどこまで伸ばしていけばよいのか?選手の個人差をどのように考えればよいのか?分からないことだらけだ。 完全で効果的な方法を前提として、試行錯誤を繰り返して行かざるを得ない。その試行錯誤の積み重ねが、日立戸塚のトレーニングとなって残っていった。 従って毎年同じトレーニング計画ではあり得ないし、トレーニングにも"歴史"がある。 大げさにいえば、日々のトレーニングの歴史の上に立って、これからの新たなトレーニングが始まっていく。 こうして得られた成果が、広くバスケットボールのために、そしてスポーツ全般にとって役立つものになればと願っている。 この章 END ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月31日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その7
こんにちはenoです。 バランスのとれた体力をレベル・アップしていけば、当然、バスケットボールの競技力向上にもつながる。 実際、日立戸塚では、以前よりもケガや障害の発生は少なくなっていたし、他のチームに比べて少なかったと思う。 1番目の質問で、自分が教える立場になったとしてトレーニングをどの程度入れるかという問いに対して、選手があまり積極的な考えを持っていないのはなぜかと書いた。 それは、選手にケガや障害の予防という考え方がないことが、理由の一端として挙げられるかもしれない。 単に体力アップしてプレーのレベルを上げようというのであれば、「シーズン・オフに適当にやれば・・・」程度に考える気持ちも分かる。 日立戸塚では、専任のトレーニング・コーチやトレーナーが付いていたので、選手が意識しなくてもより良いコンディショニングについてカバーしている面が大きいが、本来は選手自身がもっと考えるべきだと思う。 実業団というトップ・レベルにいるから特別なトレーニングが必要なのではなく、バスケットボールならバスケットボールという競技を行う上で必要な体つくりを、競技レベルに応じて適切に行うことが重要なのである。 こういう考え方は、出来るだけ早いうち(中学や高校)に身につけておいたほうが、よりよい選手生活、またはスポーツへの取り組みが出来ると思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月29日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その6
こんにちはenoです。 重要なのは、練習にかけた時間ではなく、集中した時間である。 しかも、内容のある練習をいかに行うか。それが試合に表われる。 少なくとも週に1日は、選手・コーチとも体を休め、同時にその日を、次の練習・試合を計画するために使ったらどうだろうか。 今と同じだけの成果を、いやそれ以上の成果を、週に1日休みを入れても挙げられるはずである。 中学や高校なら、週7日の練習は当たり前という選手の"常識"は、今後変えていくべきだと思う。 選手の意識としてもう1つ興味深く感じたのは、「何のためにトレーニングするのか?」という単純な質問に対する選手の答えだ。 その答えは「バスケットボールの競技力向上のため」ということに集約される。 つまり、より良いプレーをするためのパワー・アップであり、ダッシュ力やスタミナなどのアップだ。 当然といえる答えだが、1つ気がついたのは、体全体のコンディショニング(競技に適したバランスのとれた体力づくりの意でこの語を使う)を行い、ケガや障害の予防をするという答えが1つもなかったことだ。 私としては、もちろん競技力向上ということが前提にあるが、バスケットボールを行うためのコンディショニング、ケガや障害をなるべく起こさないようにするためのトレーニングが重要だという気持ちが強い。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月26日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その5
こんにちはenoです。 なぜ彼女達は、自分が指導する立場になったとしたときに休みを入れないと言うのか? それは要するに、彼女達が高校時代に週7日の練習(試合も含む)でやってきたし、それをこなせたからである。 つまり、「自分達にできたから」という発想だ。 それでは、なぜ週7日の練習が無理だと感じなかったのかというと、練習内容の密度が低いからだと考えられる。 例えば、チームの人数が多くて、ランニング・シュート1つするにしても待つ時間が長いことがよくある。 こうした待ち時間の長い練習では、仮に3時間の練習をしても、選手が実質的に動いているのはごくわずかということもある。 まして、レギュラーがコートを主に使い、他の選手はコートの周りで立って声を出しているだけという場合などは、チーム全体でみると練習の密度はなおさらに低いと言える。 その他にもチームそれぞれで事情があるだろうし、指導するコーチが忙しいために練習内容を合理的に進めていく時間が無いということもあるだろう。 しかし、そうした色々な事情はあるにしても、週7日の練習というのは、選手にとっても、コーチにとってもあまりにも余裕がなさすぎる。 トレーニング効果だけでなく、スポーツそのものや毎日の生活を楽しむという意味においても、弊害が大きすぎると思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月24日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その4
こんにちはenoです。 続いて、「練習休み」の日をどの程度入れるか?と、いう質問に対しては、「高校では練習時間が短いし、教えることが沢山あるから休日は最低限入れない」という意見が多数であった。 彼女達のこうした考え方は、大部分、自分達の高校で行ってきた練習の中から培われてきたもので、ある程度強いレベルにいた選手に共通するものと言えるかもしれない。 最初の質問に関して言えば、トレーニングは必要なものだから是非とも取り入れたいという積極的な姿勢が無い。 トレーニングの必要性を彼女達がそれほど感じていない? というか、この点は、3番目の質問と併せてもう一度考えてみたい。 2番目の質問に関しては、選手に対してさらに質問を重ねてみた。 「それでは、現在の日立戸塚の練習休みも必要ないと言えるか?」と聞いてみたところ、「今の練習だと休みが無いと体力的に無理。」「休みが無いと、頭の中が練習のことで一杯になって整理できなくなる。」などの答えが返ってきた。 つまり、現在はそれだけ集中的な練習を行っているので、休養日がどうしても必要という訳だ。 これは、彼女達が楽をしたい(怠けたい)から言っているわけではないと私は思っている。"休養もトレーニングのうち"と言えるだけのトレーニングを実際に行っていたからである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月22日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その3
こんにちはenoです。 選手達は、2年目、3年目と経験を重ねるに従い、トレーニングの効果を身を持って知るようになるわけだ。 逆に言えば、選手が自らモチベーション持って、より効果的なトレーニングを行っていくには、これだけの時間がかかっていると言える。 実際、ウェイト・トレーニングを例に取ってしても、3年目、4年目の選手で筋力の伸びが頭打ちになりそうな選手が、1・2年目の選手に負けないような筋力伸びをみせることも珍しくない。 トレーニングも、意識・技術のレベルで上達していくものだということが伺える。 さて、前置きの説明が長くなったが、このようにトレーニングの効果をある程度実感している選手達に、「君たちが仮に高校のバスケットボールの指導者になったとして、体力トレーニングをどの程度行うか?」と質問してみた。 選手達の答えの主なものは、 「 トレーニングはやらせたいと思うが、高校では練習時間が短いし、 トレーニングの設備が無いから・・・ 」 「 シーズンオフ中心にトレーニングを行い、シーズン中はボール練習のみ。」 「 できれば、特別にトレーニング時間を取らなくても、ボール練習の中に 体力強化も組み込めるような種目を行いたい。」 等々であった。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月17日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その2
こんにちはenoです。 今回(当時の日立戸塚チーム)の意見を聞いた選手は、その年に入部した選手と2年目、3年目の選手達で、チーム体制の中で育ってきた選手達である。 彼女らは、実業団チームの一員として、日本の多くの女子バスケットボールの選手の中ではトップクラスにあたる。 その意味では、体力・技術共に高いレベルにあると言える。 しかし、特にトレーニングに関しては、本格的に始めたのは日立戸塚に入ってからといえるだろう。 日立戸塚では、4月から夏にかけてのシーズンオフは、練習に占める体力トレーニングの比重がかなり大きい。 おそらく、他のチームに比べてボールを使った練習の割合は少ないに違いない。 「トレーニングばっかりやっていていいのかな?」と言うのが、入部して1年目だった選手の感想だ。 しかも、日立戸塚では2年目、3年目と上級生になるに従って体力的に高いレベルになるので、1年目の選手にとって、特に、春から夏にかけての時期は、チームの練習についていくのがやっとであった。 ところが、夏以降になると、上級性の動きにも何とかついていけるようになってきて、トレーニング効果を意識し始める。 2年目、3年目の選手達にしても、こうした経験を経て、さらに練習や試合での動きが以前よりも良くなってくるのを実感していく。 その中から、パワー、スタミナなど、他のチームの選手に負けないという自信が出て来るようだ。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月16日
コメント(0)
-

コーチと選手のギャップ その1
こんにちはenoです。 コーチは選手のことを何でも知っている・・・・・わけではない。 トレーニングについても、実際に行うのは選手であり、選手がどう感じ、何を考えているかまで、全てのことがコーチに分かるわけではない。 それに、トレーニングはただ頑張ってやりさえすればよいという割り切り方で、(つまり苦しいほどやらせればよい)、選手の気持ちを改めて考えているコーチは少ないのではないだろうか。 そこで試みに、選手の意識、意見を聞く場をつくり、トレーナー、トレーニング・コーチも交えてトレーニングに関して話し合ってみた。 トレーニングに対する選手の意識には、やっぱりと思うことが多かった半面、予想もしなかった意見も聞かれて面白かった。 以下に、私にとって非常に興味深かった話題をいくつか紹介したい。 「君がもし、高校の指導者になったとしたら?」 当時の日立戸塚バスケットボール部(以下、日立戸塚と略)では、1日の練習は3時間、2日練習して1日休み。 例えば、日曜日が試合だとしたら、(月)休み、(火)・(水)練習、(木)休み、(金)・(土)練習、のパターンを基本にしていた。 シーズンオフのトレーニングだけでなく、シーズン中のトレーニング計画、プログラムを組んで、専任のトレーニング・コーチの指導の下に行っていた。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月13日
コメント(0)
-

練習時間を短くするための提案 その7
こんにちはenoです。 コート(グラウンド)以外のところでも選手に教える機会を作ることが、練習時間の短縮に結びつくし、より効果的である。 具体的には、ミーティングの機会をもっと多く持ち、活用すべきである。 また、選手1人1人に練習ノートをつけさせて、それに指導者がコメントをつけることで選手・指導者間の伝達を図っておけば、練習がもっとスムーズに運ぶことになる。 指導者は立って練習に臨むこと・・・ 長時間の練習を選手に課して平気でいられるのは、考えてみると指導者自身が運動するわけではないからでもある。 私自身も選手と共に運動するわけではないが、その代わり、練習中は立ったままでいることにしている。(現在もクリニックなどの場では、立ったままで指導している) とは言ったものの、ずっと立ちっ放しでいることは身体的には結構つらいことで、慣れないうちは腰が痛くなったりして集中力が無くなることも少なくなかった。 ましてや選手は厳しい運動を行っているわけで、選手の心身の状態を私なりに推し測る意味でも、練習中立っていることが"最低限守るべき態度"だと自分に課している。 たまに、椅子に座ってタバコを吸いながら練習を指導するコーチがいるが、あれでは長時間の練習も楽なものに思えてしまうのではないだろうか。 それ以前に、一生懸命頑張っている選手に対して無礼であると思う。 長時間練習を避ける戒めの意味でも、指導者は立って練習に臨むべきである。 * * * 練習時間を短くするための提案、アドバイスについて思いつくままに記したが、出来れば前回の文章と併せてお読みいただきたい。 練習時間を短くする方法としては、バスケットボールに限っていえばもっと詳しく挙げられるが、各競技に共通する問題のみを取り上げたので具体性に欠ける面が多々あると思われる。 足りないところは、読者の皆さんの創意工夫で補っていただければ幸いです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月10日
コメント(0)
-

練習時間を短くするための提案 その6
こんにちはenoです。 残りの数秒、数mでも全力を出させる。 例えば、20mとか、30mのダッシュを行う場合、最後まで全力を出さずに半分過ぎくらいから力を抜いて流しているようなことが多い。 同様に30秒間のドリルを行ったとき、最後の10秒間くらいは力を抜くということが習慣化しているというようなことはよくあるはずだ。 1本1本のドリルを最後までやれば、それだけ少ない本数でも効果的だし、時間も節約できる。また、集中力の向上にも役立つ。 何度も同じ注意ばかりを繰り返していないか? あるプレーが出来ない選手がいるとする。何度注意しても分からない。 こうした時、分からせようと指導者がその選手の練習にこだわることは、時間的に大きなロスになるばかりでなく、その他の選手のやる気、集中力を損なうことになる。 出来ない選手にその場で必要なことを指摘しておくことは大切だが、そこで指導者が感情的に流されるべきではない。 あくまでチーム全体の練習を進め、その選手には練習後の冷静な状態で説明する。選手にとってもその方が受け入れやすいことが多い。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月08日
コメント(0)
-

練習時間を短くするための提案 その5
こんにちはenoです。 選手はみんな上手くなりたい、強くなりたいと思っている。そして指導者はそれに応える責任がある。 20人の選手がいれば、20人の個性の上に練習が成り立つべきである。 1つ1つの練習種目にもそれが反映されるべきで、決してパターンにハメ込もうとするべきではない。 大原則として、練習始めの心身共にフレッシュな時には習得すべき重要な練習を、練習の最後には復習すべきドリルなどを持ってくる。 また、時間手の節約として、練習の流れがスムーズにいくようなプログラムを作る。 例えば、スタンディング・ストレッチをやっている間にマネージャーがボールを各選手の足元に用意してボールを使う練習が2人1組になる。 余ったボールをマネージャーが片づけていくという方法(日立戸塚の例)だと、ボールの用意、片付けで練習が途切れることが無い。 この他、全般的にユックリズム(ユックリ+ismの俗語)を無くすこと、つまり時間の使い方に無駄をなくすように選手1人1人に徹底させることが大切。 例えば、種目と種目の間は素早く走るとか、何かの合図にすぐに反応して動作に移れるように意識を集中させることなどは、練習を効率よく短くするうえで役立つ。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月04日
コメント(0)
-

練習時間を短くするための提案 その4
こんにちはenoです。 コーチをしていた日立戸塚では、コートが半面しか使えなかったとき、4m四方のエリアの中でのドリルを考え、そのエリア練習を4つ作った。 選手は3人1組とし、2人がプレーして1人が休み(見学)という形でローテーションしていく。 また、バスケットボール・リングが2つしかなくて、シュート練習に時間がかかるときには、リングに見立てたポールを何本か立てて、模擬シュート練習が行える場所を作った。 そして、6人1組に分かれたグループがその場所をローテーションしていくのである。 これらはほんの一例だが、各競技、各チームの置かれている状況に応じて、色々な工夫が可能だと思う。 選手のグループ分けの話が出たついでに話しておくと、色々な練習種目に応じて選手をグループ分けするとき、上手い選手と下手な選手をあえて組み合わせる。 そうすることで練習に緊張感が出て来るし、上手い選手が下手な選手に教えることが出来る。 指導者はとにかく上手い選手ばかり見ることが多く、"レギュラー・クラス選手だけの練習"になってしまいがちである これは、その他の選手のやる気をスポイル(台無し)するし、チームとしてのロスが大きいので効率的な練習とはいえない。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年08月01日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1