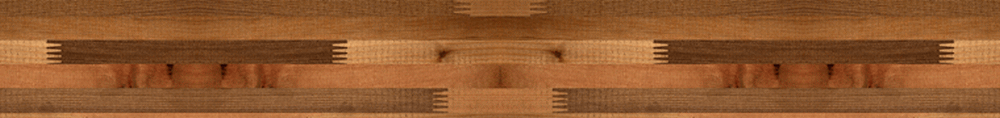2011年06月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

スローガン 「長~い練習、大きなマイナス」 その2
こんにちはenoです。 なぜ練習時間が長くなるのか。 練習時間を出来るだけ短く、しかも効果的に行うことがコーチの役割だと私自身は思っている。 同じ効果が得られるのならば、練習時間は短いにこしたことはないし、長ければ長いだけ選手の集中力は無くなる。また、長くなれば練習が楽しくなくなるのは当然である。 そして、もう一つの重要な点は、長すぎる練習(いわゆる練習のし過ぎ)は、ケガに結びつきやすいということである。(こうしたマイナスの側面については、後でまた取り上げる) さて、それでは、我々コーチは、練習時間を長くしてしまいがちなのだろうか。 私の経験から、原因として思いつくところをいかに挙げてみよう。 【1】まず、長期的な練習計画がたてられていないこと。 年間の練習計画の中で、どの時期にどのようなトレーニングや技術練習を行い、その目標をどの程度に置くかを決めておかないと、いつもただ無目的に精一杯努力しなければならなくなる。 当然ながら、そこで設定される目標は、選手個々の能力を十分に考慮したものでなければならない。 無闇に高すぎる目標を設定することは、かえってモチベーションの低下につながるし、いたずらに練習を長引かせることになる。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月27日
コメント(0)
-

スローガン 「長~い練習、大きなマイナス」 その1
こんにちはenoです。 理想的な練習時間は? 1日1日の練習を精一杯やること、出来るだけ充実した内容にすることを我々コーチは望むし、選手にしても基本的にはそれは同じであろう。 その結果、練習はできる限り長くなる。 長時間の練習を行うことが、"精一杯やったこと"、"充実した練習"の証となるわけである。 しかし、本当にそうだろうか? 長時間の練習で何を精一杯やったのだろうか。何が充実していたのだろうか。 理想的な練習時間というものを考えた場合、長時間の練習はその条件にあてはまるのだろうか。 もちろん、競技種目や選手のレベル、またはチームの置かれている条件(時間、環境、スタッフ)などによって有効な練習時間は異なるのだろうが、私自身は、「長時間の練習=充実した練習」とする考え方は間違っていると思う。 理想的な条件としては、むしろ練習時間を出来るだけ短くすることではないだろうか。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月24日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その11
こんにちはenoです。 今回は、「健康日報」」のことを中心に、選手の健康対策のことを紹介したが、当時の日立戸塚チームには、専属のトレーナーが一人、そしてチーム・ドクターとして二人(内科、整形外科、各1名)に協力していただいていた。 こうしたスタッフに支えられ、以下のような健康管理対策も行っていることを最後に付け加えておきたい。 入部時に・・・ ◇既往歴病気やケガの既往歴60項目について調査する。 ◇スポーツ整形外科医メディカルチェック関節の痛みや下肢の"アライメント"(調整すること)をチェック。これは、外傷、障害の予防に役立たせるのが目的。 ◇血液・尿・視力・エックス線等のテスト毎年4月に実施。 ◇心電図検査安静時心電図検査を実施。 ◇診察禄ドクターに診察してもらったときの記録を個人ごとにファイル。その記録を見て分からない点はドクターに質問できるし、チーム・ドクターがチームに来て診てくれる場合もデーターとなる。 以上に述べたような項目が基礎としてあり、そのうえで「健康日報」が機能してくると言えよう。 そして、こうした選手の健康管理を取りまとめる役目として、日立戸塚にはトレーナーがいた。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月22日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その10
こんにちはenoです。 「健康日報」は、コーチやトレーナー(マネージャー)の側から言えば、選手個人の状態を知る有効な手がかりとなるとともに、チーム全体としての情報も得ることが出来る。 例えば、ハードな練習が続きオーバー・トレーニング気味になると、痛みを記入する選手が多くなるし、痛みの部分も多くなってくる。 つまり、選手の疲れを見るバロメーターになるし、練習量を調節する材料になる。 女子選手では、トレーニング量が増えたり、試合前になったりすると、月経がなくなる選手がいる。 そうした微妙な体調の変化も、「健康日報」によって理解しやすい。 また、試合が近づくと痛みに対して敏感、ナーバスになる選手など、選手個人の性格が現われる点も面白い。 選手は自分の体調を毎日書くので、自然に自分のコンディションを考える習慣がつくのである。 「健康日報」には空欄があり、痛みについてだけではなく、日誌代わりになんでも思いついたことを書き込めるようにしてある。 そして彼女達が選手を辞めてチームを去るときにファイルされた「健康日報」を各自に思い出として渡すようにしている。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月20日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その9
こんにちはenoです。 60%の痛みを、練習に参加できるかどうかの境界にしたので、58%とか59%の痛みを記入する選手が多く出た。 痛みはあるが練習には出たい。または出なければならないと考えている選手がこういう数字を書く。 要するに選手自身も迷っているわけである。 その選手に練習をさせるべきか、止めさせるべきかを決める判断がトレーナー(マネージャー)に重要になるのはこういう場合である。 ついでに言えば、練習を休むこと、休養することは練習をさぼることではない。休養はマイナスではなく、プラス要素だということ。 これを上手に取ることは最高のトレーニングだという価値観の転換が必要だと思う。 ただし、「健康日報」から以上のような判断を下すのは、ケガの治療などをしていない選手に対してである。 例えば、膝のケガをして、それが重度のケガの場合は手術を受けて長期的なリハビリテーションを行っている選手は、最初からチームの練習とは別メニューのトレーニングを行う。 「健康日報」に痛みを記す場合、1日に数回の練習があれば、午前中には青、午後(昼間)は赤、夜は黒として、一つのイラストに色分けして記入することとした。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月18日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その8
こんにちはenoです。 選手によっては80%、100%という場合も出てきて私を驚かせた。 私としては、100%の痛みというのは死んでしまうような究極的な痛みをイメージしていたからである。 これでは混乱が大きいので、その歯止めとして、60%の痛みという基準を設けた。 この60%というのは、痛くて練習が満足に行えない、行うことで支障が出るというポイントで、60%と書いた選手は基本的にチームの練習を休ませることにした。 「健康日報」のつけ方、使い方として、練習前に選手各自が記入して、トレーナー(マネージャでも良い)がそれぞれをチェックする。 また、毎日の「健康日報」は個人ごとにファイルされ、練習の時にはコート・サイドに置いておく。 こういう方法を採ることで、まずトレーナー(マネージャー)が練習前に選手の状態をある程度把握できるし、必要とあればその選手のケア、特別なトレーニング・メニューの作成などを行える。 また、私自身も練習中の選手の動きがおかしい?体に異常があるのではないか?と感じられたとき、この「健康日報」を見ることで、選手の状態を確認できたのである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月15日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その7
こんにちはenoです。 健康日報記入の注意事項 【2】その他 ◇ 痛みについてはなるべく詳しく記入する。(筋肉痛であるのかどうかも部分的にハッキリと。) ◇ 新たな痛み、または持続的な痛みについても変化があった時はトレーナーに報告すること。 ◇ 記入するときは、午前は青色、午後は黄色、夜は黒色とする。 ◇ 痛みについて午前と午後が同じ場合は、午前に書いたところを( )で囲む。%が増した場合はハッキリと数字を書くこと。 ◇ 体重はバスケットシューズを除く衣服を着用したそのままの数字を書くこと。 ◇ 平常脈は1分間のものを書くこと。 ◇ Q6についてひどいものは、二重マル、そうでないものには一重マルで囲む。 ◇ 健康日報は1ヶ月ごとに外してファイルして前日の上に重ねていく。 ◇ なるべく丁寧に記入漏れの内容に書くこと。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月13日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その6
こんにちはenoです。 健康日報記入の注意事項 【1】 痛みのパーセンテージと練習への影響 9%以下 痛みの感覚 : ほとんど気にならない程度。練習への影響 : 練習するうえで影響はない。 10~19%痛みの感覚 : 何かの時にフッと痛みを感じる。練習への影響 : 同上 20~29%痛みの感覚 : 明らかに特別な動作で痛みを感じる。(走る、ストップ、ジャンプ、等)練習への影響 : 同上 30~39%痛みの感覚 : じっとしていても痛みを感じたり、気になったりする。練習への影響 : 同上 40~49%痛みの感覚 : 練習中に意識の中に痛みを感じることが多い。練習への影響 : 練習中に気になることがある。 50~59%痛みの感覚 : 特定の動作について常に痛みが感じる。練習への影響 : 練習は出来るが特定のメニューについては出来ないものがある。 60~64%痛みの感覚 : 特定の動作のみならず痛みを感じることが多い。練習への影響 : 練習は何とかできるが自分の動作をセーブしなくてはならない。 65~69%痛みの感覚 : 同上練習への影響 : 練習種目を限定して行う。 70~79%痛みの感覚 : 日常生活の上でも支障が多くスムーズな動作に欠ける。練習への影響 : ストレッチ、支障のある部分以外のトレーニングのみを行う。 80~100%痛みの感覚 : 常に痛みが伴う。練習への影響 : 完全休養。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月11日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その5
こんにちはenoです。 自分がチームから離れていた時の選手の状態、戻ってきたその日の選手の状態をすぐに判断できる材料があることは私にとって予想外の喜びであり、収穫だった。 また、使っていくうちに、仮にチームから離れていなくても、分からなかったような点が色々と見えてきた。 そして、最早ナショナル・チームのための実験的なものでなく、日立戸塚チーム自身のために「健康日報」は必要なものになっていった。 (ナショナル・チームでは、昭和56~57年まで、私がヘッド・コーチを務めた2年間にこれを用いた。) "痛み"をパーセンテージで書かせてみた。 「健康日報」の最大の特徴は何かと言うと、選手自身に自分の主観で痛みのパーセンテージを書き込ませるということである。 体を前から見たところと、後ろから見たところのイラストがあり、痛みのあるところに印をつけて痛さの度合いをパーセンテージで表す。 私たちの習慣として、痛さをこらえて練習することが当たり前になっているので、この弊害をなくすために考えたことだ。 ところが、最初は、どういう程度の痛みが何%かと言う基準を設けていなかったので、当然ながら選手それぞれの痛みに対する基準があまりにもバラバラになってしまった。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月08日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その4
こんにちはenoです。 選手の健康状態を把握していないと効果的なトレーニングは組めないし、逆にマイナスになることだってある。 ナショナル・チームの合宿はごく短期的なだけに」、練習の中で選手の健康状態を十分に把握していくことは難しいし、選手のことをよく知らないまま練習をさせることになる。 そこで、病気やケガの既往歴(過去の病歴、健康状態に関する記録)や、現在の状態を選手自身に書き込んでもらう「健康日報」のようなものを作ってはどうかと考えた。 このアイディアは、すぐにはナショナル・チームで実現できず、まずは日立戸塚チームで実験的に行ってみることになった。 選手に記入してもらう質問内容、質問様式などをどうするか?そこから決めなくてはならなかったので、周囲の人達に協力してもらい、何種類かの質問(記録)用紙を作った。 前回(その3)で示した健康日報(省略版)にあるのはその中の1つで、その後改良が重ねられていった。 こうした経緯で、「健康日報」を自分のチームでつけるようになり、意外な発見をさせられることがある。 実際、自分のチームについては選手を毎日みているので、「健康日報」はあまり必要ないと考えていた。 しかし、私がナショナル・チームの仕事で外出する機会が増えるにつれ、当初ナショナル・チームのためにと考案し、行ってきたことが実は自分のチームに対して役立つ結果となったのである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月08日
コメント(1)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その3
こんにちはenoです。 選手のケガや痛みをコーチはどうやって知るか? 日立戸塚チームでは、次に示すような「健康日報」を、選手1人1人に毎日つけさせていた。 ≪ 健康日報 ≫・・・(省略版) Q1,期日Q2,体重Q3,気温、気圧、湿度Q4,生理 (有、無)、××日目・症状Q5,各所の状態(人体絵図)で説明Q6,自分の症状を○で囲む 頭・・・・・・・・・痛い・重い、~他 首、肩、背・・首筋がこる、~他 胸・脇・・・・・・重苦しい、動悸、~他 腰・・・・・・・・・冷える、しびれる、~他 腹・・・・・・・・・腹痛、消化不良、~他 胃・・・・・・・・・食欲不振、胸やけ、~他 全身・・・・・・・不眠、疲労倦怠感、~他 手・足・・・・・・冷える、痛い、~他 のど・・・・・・・せき、たん、声のかれ、~他 目・・・・・・・・・コンタクト(有・無)、充血、~他 耳・鼻・・・・・・耳鳴り、鼻づまり、~他 口/舌・・・・・渇く、口臭、~他 尿、便・・・・・・○○回、スッキリ、~他 その他・・・・ この「健康日報」を作るきっかけは、今から30数年前、私がナショナル・チームのコーチとしてチームを見るようになったときのことである。 自分のチームの選手のことは毎日見ているである程度は分かっていたつもりだが、色々なチームから選ばれてくる選手についてはデーターがほとんど無い。 その選手が現在ケガをしているのかどうか?ケガの程度は?ケガをしたばかりか治りかけか?慢性的な障害を抱えているか?など、分からないことばかりである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月06日
コメント(0)
-

健康あってこそトレーニングが生きる その2
こんにちはenoです。 競技スポーツは、色々な意味で体がより良い状態で動くことが要求される。 病気やケガが大きなマイナス要因になるのは言うまでもない。 いくら効果的なトレーニングを行っても、ケガや障害があれば効果は半減するだろうし、かえってそれらを悪化させることにもなりかねない。 トレーニングが選手にとってのプラスの要素だとするなら、病気やケガはマイナスの要素である。 プラス要素を追求する一方で、マイナス要素は出来るだけ少なくする必要がある。 つまり、選手が健康な状態にあってこそ、トレーニングの効果も最大限に生きてくるし、試合でも良いプレーが出来るということである。 当たり前といえば当たり前のことであるが、マイナス要素をいかに少なくするかという努力は、意外に見落とされているのではないだろうか。 前置きが長くなったが、以上のような観点から、今回は選手管理の1方法として、日立戸塚チームで使っていた「健康日報」を中心に紹介しよう。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年06月03日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1