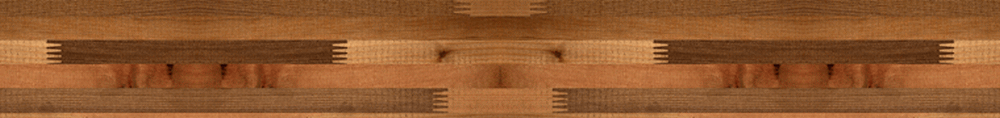2011年10月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

競技復帰はどこまで可能になったか その7
こんにちはenoです。 【記者】:以前に座談会や、佐藤さんに書いていただいた前十字靱帯損傷と競技復帰関する記事のなかで、手術後だいたい3カ月くらい入院してリハビリテーションを行い、その後通院しながらのリハビリテーションが8か月目まで続くということでしたが、こうした機関も含め、実際の復帰までの期間に一番辛かったことというのはどういうことですか。 【宮永】:最初の説明で、1年経てば何とかやれるようになるというふうに聞いていたのですが、手術後7~8カ月以後、チームの練習に少しずつ参加し始めて、自分としてはもっとやれると思うのにやらせてもらえなかったことが辛かった。 病院にリハビリテーションに行っている時はいいのですけれど、体育館でみんなが練習をしているのを見ながら、陰で自分1人トレーニングをしているのはとても辛いことでした。 時間がたてば何とかなると思ってはいましたが、やはり自分1人遅れていくような気がして・・・・・。 それに,ケガをしたときには下級生だったので、ボール集めなど下級生の仕事をしなくてはならないという気持ちもあって、なおさら辛い感じでした。 【佐藤】:今は、ケガをした選手はチームから離れて個人メニューでトレーニングをすることが当たり前になっていますが、マツがリハビリテーションを行っている頃は私がトレーナーとしてチームを見始めた年だったので、チームにそういうシステムが整っていなかったということがあります。 マツの前にも前十字靱帯の手術をした選手がいたのですが、リハビリテーションのほぼ最初の時からトレーナーとして私が見ることができたのはマツが初めてで、そういう意味では、監督・コーチがいて、チーム・ドクター、トレーニング・コーチ、トレーナーがいて、というチーム体制が出来つつある大きな変革の時期だったと思います。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月31日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その6
こんにちはenoです。 【榎本】:本人にしてみれば、他の選手も手術を受けているという安心感があるし、私達にしても手術を奨める以上は、本人を不安がらせるより、勇気づける事を言っていたので、手術を受ける時点ではそれほど悩みはなかったのかもしれない。 しかし、本人に手術を奨めるまでには、我々としては大変に思い悩むわけです。 例えば、手術後、復帰したとして、「その選手をどういうふうに使うつもりか」「どのくらいの頻度でその選手をゲームに出すつもりか」「その選手以外の新人が力をつけてきたらどうするのか」など、現実的な色々な問題を含めて、増島先生や佐藤トレーナーと話し合います。 これはマツの場合に限らず、他の選手の場合もおなじです。 手術をするとなれば、なるべく早いほうがいいので、夜遅く電話で増島先生と話したこともあった。 そうやって話していくうちに、これだけみんなで考えた末のことだから、「責任を持って復帰まで持って行くぞ!」という意気込みたいなものも、我々の中に新たに生まれてきたように思います。 日立戸塚の場合、手術を受けた選手の復帰は上手くいっているけれど、それは、選手本人はもとよりドクターも含め、我々みんなのコミュニケーションが上手くいったことが大きいのではないかと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月28日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その5
こんにちはenoです。 【榎本】:本人がどうしても手術をしたいと言っても、私やチーム・ドクター、トレーナーなどの判断で、手術を思いとどまらせるように説得したことも過去に会った。 その選手の場合、すでに引退に近い年齢だったし、日常生活を送るのには必ずしも手術する必要が無かったからです。 【佐藤】:増島先生は、目的のはっきりしない手術はしないという方針です。 何のために手術をするのか、復帰のためか、それとも一般の生活をするためか、まずその目的をはっきり持ったうえで話し合う。 引退した選手で、両膝とも前十字靭帯を損傷したために、それでは日常生活にも支障があるので、プレーには復帰しないことを前提に手術をした選手もいます。 【記者】:宮永さん自身は、手術をすることに対して、どういう考えだったんですか。 【宮永】:私の場合、日立戸塚に入って1年目に前十字靭帯を切ったのと、私の前に結城さんという先輩が手術をしていたので、当然という雰囲気で、手術を受けることにしました。 その頃は前十字靭帯損傷というのがどういうものか全然知らなくて、ケガをしてそれを切ると当然手術を受けなくてはいけないと思っていたし、また1年くらい経てば復帰できるということくらいしか考えていませんでした。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月26日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その4
こんにちはenoです。 "手術に踏み切るまで"(座談会より要約・抜粋) 榎本:今日は、前十字靱帯損傷の手術から復帰まで、特にチーム戻ってトレーニングを始めて、実際に試合に出るまでの話を中心に話を進めたいと思います。 マツ(座談会に出席した宮永選手の愛称)にはこの機会に、手術を経験した選手として、本当の痛みとか辛さについて語ってもらえればと思います。 まず、前十字靱帯損傷の診断や治療が進んできたとはいっても、実際にその手術を受けることを決めるまでに、我々は大いに悩みます。 例えば、専属のチーム・ドクターがまだ在籍してなかったときのことです。 選手が膝の手術をすることになり、その担当のドクターに、手術の内容などについて詳しく教えてもらおうと思っても、医師の道義上の問題とかで教えてもらえないことがあった。 選手に手術を受けさせるということは、私にとっても大きな問題で、手術の内容や成功の可能性、復帰の見通しなど、色々な事を監督の立場として考えざるを得ない。 知らなかった、分からなかったでは済まされないのである。 現在は、チーム・ドクターの増島先生、佐藤トレーナーがいるので、彼らと色々な角度から手術すべきかどうかを話し合うだけでなく、もちろん本人やその両親とも十分話し合ったうえで決めるようにしている。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月22日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その3
こんにちはenoです。 私は前十字靱帯損傷の診断や治療の進歩が、競技復帰に役立たないと言っているわけでは決してない。 逆に、日立戸塚では、その進歩の恩恵を最大限に受けていたと言ってよい。 しかし、だからこそ一層、競技復帰の困難さが分かるし、それを皆さんに訴えたいと思う。 それは前十字靱帯損傷を起こさないようにすること、つまり予防の重要性を知っていただきたいからである。 前置きが長くなったが、次回より、日立戸塚において得た、”前十字靱帯損傷と競技復帰”の情報を紹介したい。 内容は、以前、雑誌の取材のため、前十字靱帯損傷の再手術から復帰した1人の選手、宮永美和を交えた「座談会からの要約・抜粋」である。 彼女の前にも前十字靱帯損傷の手術を受けた選手はいたが、チーム・ドクターやトレーナーの管理・指導が行きとどいた状態での競技復帰は彼女が初めてだったと言ってよいと思う。 座談会の出席者は他に、トレーナーの佐藤利香、記者のK氏、そして私である。 競技復帰と一口に言うが、そこに至るまでの長い過程で、当時の選手自身やトレーナーが何を考え、何をしたのか、チームの事情はどうだったのかなどをなるべく具体的に知っていただきたいと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月19日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その2
こんにちはenoです。 前十字靱帯損傷とはどういうケガか、今回のこの話の中では、前十字靱帯損傷の手術からの競技復帰をテーマに、当時指導していた日立戸塚女子バスケットボール部(以下、日立戸塚と略)の例をお話ししたいと思う。 前十字靱帯損傷の診断や治療はここ数十年急速に進歩してきて、競技復帰が可能な段階にまできているが、それでも実際には、選手が競技復帰を果たすまでには多くの困難がある。 「診断や治療が確立してきたからケガをしても大丈夫」というわけにはとてもいかない。 むしろ、前十字靱帯損傷は、やはり選手にとって致命的なケガだと考えざるを得ない。 スポーツ医学を理解するドクターが増えてきたとは言っても、前十字靱帯損傷の手術が行える専門的な病院はそれほど多くないと思われる。 運よくそこで治療が受けられ、手術が上手くいったとしても、本格的な競技復帰までには1年以上は優にかかるであろう。 (現在、競技復帰までのリハビリテーションの期間が短縮されつつあるという) 仮に高校の選手を考えた場合、1年とか1年半のブランクがその選手にとってどういう意味を持つかは容易に想像がつくと思う。(社会人チームの場合も、事情はさして変わらない) ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月17日
コメント(0)
-

競技復帰はどこまで可能になったか その1
こんにちはenoです。 すでにご存じの方も多いと思うが、膝の致命的なケガとして、前十字靱帯損傷がある。 この靱帯は、ストップやターンを行うのに重要な役割を果たすため、これが切れてしまうと、それらの動きがうまく行えなくなる。 また、無理してプレーを続けると、ひどい痛みや腫れが起きるばかりでなく、半月板やその他の靱帯などまで傷めてしまうこともある。(ケガしたほうの脚をかばいながらプレーすることで、反対の脚を傷めることもある。) この前十字靱帯損傷は、器械体操やバスケットボールの女子選手に特に多いといわれている。 そして、女子バスケットボール選手に関して私が知る限り、この前十字靱帯損傷の断裂は、意外と簡単に起きてしまうことがある。 致命的なケガが、あっけないほど簡単に起きるのである。 また、前十字靱帯損傷の診断や治療に関して、十数年前までは確立されていなかったために、今から考えればおそらく前十字靱帯損傷だったと思われる選手が、"治らない膝の痛み"を抱えたまま引退することも珍しくなかった。 現在では、スポーツ医学を勉強するドクターが増えてきたので、前十字靱帯損傷に対する適切な治療が受けられるようになってきた。 それでもなお、前十字靱帯損傷とは知らないまま、"治らない膝の痛み"を抱える選手は数多いのではないかと思われる。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月12日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その9
こんにちはenoです。 トレーニング・コーチが加わったことで、これまでは基礎体力を中心としたトレーニングを行ってきたが、シーズンの目標として、特にジャンプ力に強化を入れた。 バスケットボールにとってジャンプ力強化は重要な問題だが、これまであえて強化目標として入れなかった。 それは、このトレーニングばかりが先行すると、かえって障害を招きかねないと思ったことが理由の1つだ。 そういう意味では、日立戸塚がジャンプ力強化という専門トレーニングに取り組める段階に、やっと来たと言えたのである。 以上のように書き出してみると、日立戸塚のトレーニングが遅々とした歩みでしかないと改めて感じさせられる。 しかし、私1人で指導していた時代に比べれば、トレーナーや、トレーニング・コーチが加わっての歩みは何倍も速いし、その足取りは確かなものになっていったと思っている。 この章 END 次回からのテーマとして、女子バスケットボール選手の前十字靭帯損傷について述べていきたいと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月07日
コメント(0)
-

トレーニングは進化する その8
こんにちはenoです。私たちが欲しいのは、日本のスポーツの環境、日本のスポーツ選手に合った具体的な答えである。シーズン中のトレーニングついて成功したと書いたが、その内容は全くの試みの段階で、今後の検討、改良の余地が多く残されている。日立戸塚のウェイト・トレーニングは、マシーンによるものが主体であった。これまでにも、バーベルやダンベルを使ったトレーニングを試みてきたが、結局、安全に簡単にできるという点で、マシーンのトレーニングが定着していた。しかし、フリー・ウェイトの良さもぜひ取り入れたいと思っていたので、シーズンオフの時期に、ベンチ・プレスやスクワットなど他種目を行わせた。スクワットについては、パワー・ラックやスクワット・ラックを購入して行ったが、数か月行ってみた感想としては、やはりフリー・ウェイトは難しいということだ。安心して見ていられるようなフォームの習得は、とても1ヵ月や2ヶ月では無理だと感じられた。我々の教え方にも問題があるのだろうが、よほどウェイト・トレーニングの指導に精通した人が十分な時間をかけないと、「安全で効果的」なレベルまで持っていくのは難しいと思う。フリー・ウェイトをもっと安全に効果的に行うための導入はないものだろうか?また、高校や大学などでウェイト・トレーニングを始め、適切なフォームの習得も出来ていないのに、重い重量を挙げることの危険性を感じる。フリー・ウェイトの習得は、まだまだ大きな課題であると思う。■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年10月04日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…
- ホークスを日本一に導いた小久保監督…
- (2025-11-13 22:51:08)
-
-
-

- タイガース党
- 背番号31は永久欠番確定か!?
- (2025-11-22 13:02:51)
-
-
-
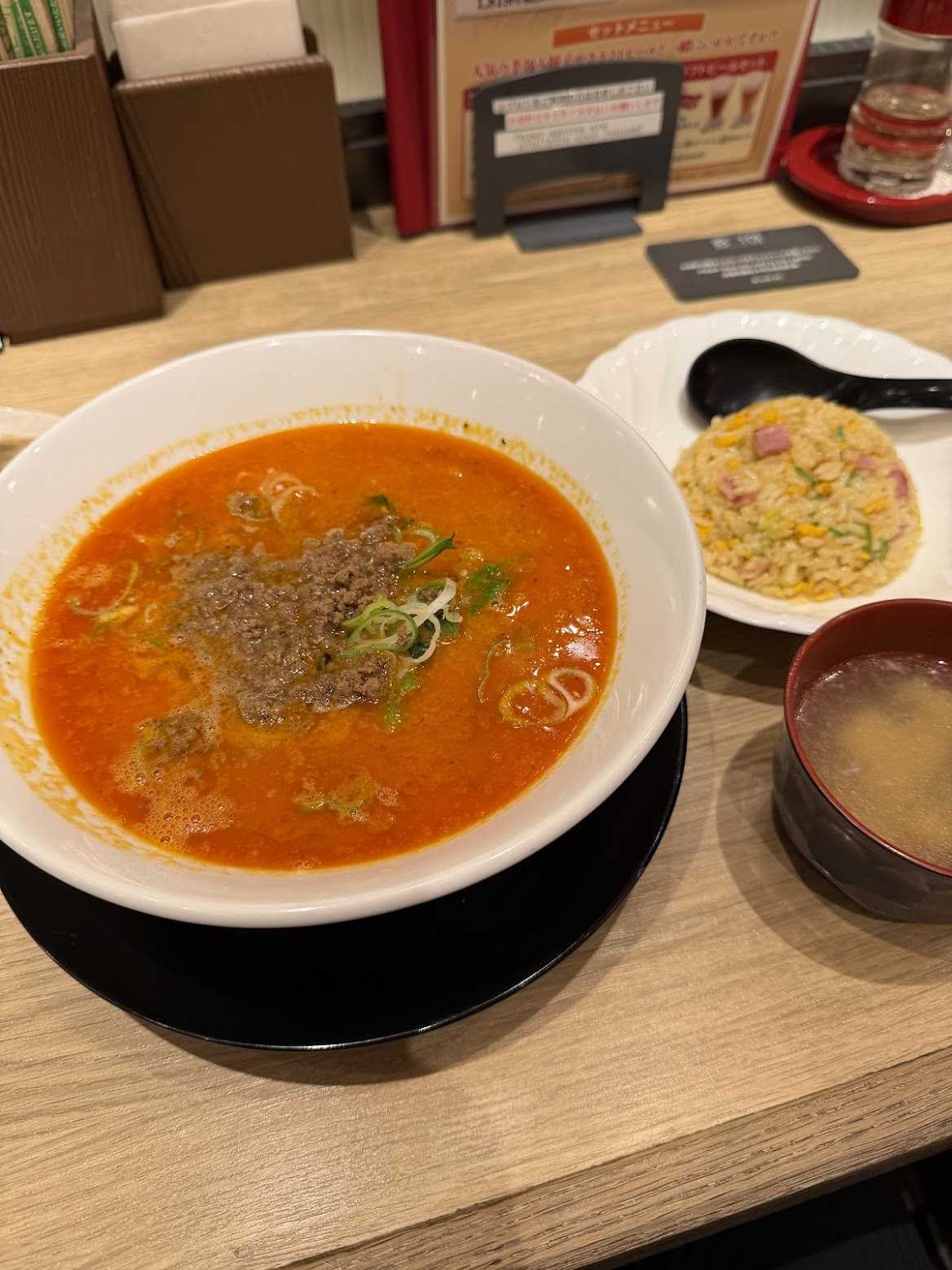
- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…
- 育成1位は俊足巧打
- (2025-11-23 06:59:38)
-