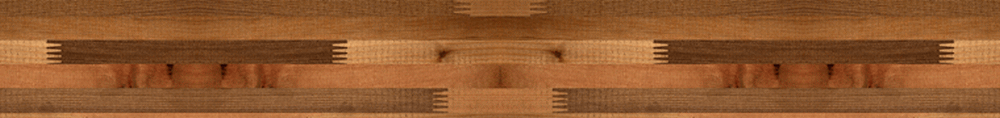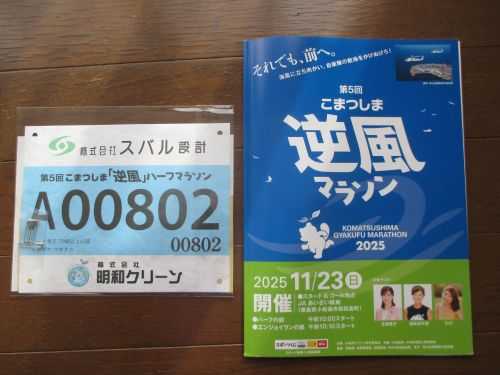2011年04月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

コーチング is イメージ・トレーニング その6
こんにちはenoです。 十数年も前のことだが、チームの要となる選手で、感情の起伏の大きい選手がいた。 チームとして日本リーグの初優勝を目指している時期で、私個人としてもガムシャラにコーチ業をやった大変な時期だった。 その選手はミスしたり、精神的に落ち込むようなことがあると、すぐに泣いてしまう。練習の雰囲気は当然悪くなる。 その選手1人のために最悪のムードで練習を終えることになることが度々あった。 私は練習を何とかみんなが笑顔で終われるようにと、練習の最後の10分間は、その泣き虫な選手の気分を出来るだけ盛り上げるようなストーリーを毎日イメージした。 次の日の練習に希望を持たせ、気持ちよく練習を終えられるかどうかは、コーチの"イメージ・トレーニング"にかかっていると思う。 どうだろうか? さて、スポーツの中でも、球技は特に試合での作戦が勝敗に大きく影響する。 バスケットボールはその中でも特に、作戦は重要といえるのではないかと思う。 相手チームのことを細部までイメージして試合の流れを組み立てるのである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月27日
コメント(0)
-

コーチング is イメージ・トレーニング その5
こんにちはenoです。 どうやったら練習が盛り上がるのか? 私がコーチとしてのイメージの大切さに気がついたきっかけは、どうやったら練習が盛り上がるかをあれこれ工夫していたことによる。 これまでに述べてきた中で、音楽を使った練習ということも、練習を盛り上げるには?という問いへの1つの答えである。 スムーズに気持ちよく練習に入っていける要素は何か? その後の盛り上がり(選手の気分的なノリ)、そして明日へつなげて気持ちよく練習を終わるには? 練習の流れに滞りのない、無駄のないプログラムの組み立て方は? 毎日の練習の細部にまで注意を払いながら、選手の動きや表情までイメージして練習を計画し、何度も成功・失敗を繰り返していった。 いわば、"練習のストーリー"作りを行った。 単にプログラムを並べて数時間の練習が出来上がるのではなく、"ストーリー"をイメージするのである。 また、選手をどういう状況で褒めるか、もしくは叱るかといったことも、具体的に(前もって)イメージするようにした。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月25日
コメント(0)
-

コーチング is イメージ・トレーニング その4
こんにちはenoです。 コーチは脚本家であり、演出家であれ。 コーチというのは、演劇の世界でいえば、脚本家であり、演出家(または映画監督)であると思う。 ところが、日本では特に、コーチの仕事として、"演出"の部分ばかりに力を入れていることが多いのではないだろうか? 脚本が無いと芝居が成立しないという単純な事実を考えてみていただきたい。 それも、よい芝居には、よい脚本が不可欠だということを。 コーチは、自ら脚本を作り、自ら演出する。競技種目によってその脚本や演出は様々である。 それぞれのチーム、選手に応じてもそれらが変わってくるだろう。 私はバスケットボールのコーチをしていたわけだが、私自身の"脚本" "イメージトレーニング"に関するこれまでの歩みを、これから数回に分けて、簡単に述べていくので、参考にしていただければと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月23日
コメント(0)
-

コーチング is イメージ・トレーニング その3
こんにちはenoです。 勝つための道筋、条件をどれだけ具体的にイメージできるか、コーチの仕事というのは、本来、こうした具体的なイメージの上に成り立っているべきだと思う。 長期的なトレーニング計画、試合に向けての調整、試合の作戦、次の日の練習内容・・・ 何から何まで、イメージによる"予想図" "完成図"があってこそ、より充実した練習、試合が行えるのではないか。 勿論、イメージした通りに物事すべて運ぶわけではない。 人間(選手)が相手のことだから、むしろイメージ通りに進まないことの方が多いと言えるかもしれない。 しかし、イメージがあってこそ進むべき方向が決まるのであり、その方向が間違っていれば修正が出来る。そこにまた新たなイメージが生まれてくる。 イメージのない動きや練習というのは、舵のない船のようだと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月20日
コメント(0)
-

コーチング is イメージ・トレーニング その2
こんにちはenoです。 コーチングにおいて重要な点とは、色々な考え方が出来るだろうが、私が第1に挙げたいのは、コーチがどれだけイメージを持てるかということである。 チームや個々の選手であるべき姿をイメージし、それに到達できるような道筋をより具体的にイメージする。そして、その"設計図"を選手達に渡す。 どれだけの具体的なイメージを持てるか? ここでいうイメージとは、言い換えれば、想像力豊かに発想するということである。 ごく単純な例を挙げてみよう。 試合に勝つためには、まず勝ちたいと思う必要がある。勝ちたいと思うところから、勝つためのアプローチが始まる。 勝ちたいという願望を、勝てるという自信につなげていくのは、イメージの力でもあるはずだ。 その為には、勝つための道筋、条件をどれだけ具体的にイメージできるかが鍵となる。 イメージは具体的であればあるほどよい。 コーチの仕事というのは、本来、こうした具体的なイメージの上に成り立っているべきだと思う。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月18日
コメント(0)
-

コーチング is イメージ・トレーニング その1
こんにちはenoです。 あなたは、どれだけ具体的なイメージが持てるか? 最近、イメージ・トレーニングとか、メンタルトレーニングと言われる言葉がよく使われるようになってきた。 心理面をもトレーニングの対象として捉えるこうした方法は、世界のスポーツの流れであろうし、心理的プレッシャー弱いとされる日本選手の課題として、最近特に重視されてきたようだ。 イメージ・トレーニングが正確には、どういう内容を指すのかは知らないが、心理面を重視することには私も賛成である。 そして、今回私が言いたいことは、イメージ・トレーニングが選手に対してだけでなく、コーチにも必要だということ。 むしろコーチこそがイメージ・トレーニングが非常に重要ではないかということである。 (ここではイメージ・トレーニングという言葉を 私なりの解釈で勝手に使った。 本来の"イメージ・トレーニング"のカテゴリーには 入らないかもしれないのであらかじめご了承いただきたい) コーチングにおいて重要な点は何だろうか? 色々な考え方が出来るだろうが、私が第1に挙げたいのは、コーチがどれだけイメージを持てるかということである。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月15日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その11
こんにちはenoです。 筋力トレーニングに関して私自身の意見、反省点とは... ◇ 前回までのトレーニングの例にはバーベルを使ったプログラムが出てこないが、それは安全上、また技術的に難しかったからである。 その後、トレーニング・コーチが入ったので、バーベルを使った種目もプログラムに徐々に入れていった。 バーベルはトレーニング・マシーンに比べ、意識をより集中する必要があるし、バランスを取ることも要求されるので、トレーニング・マシーンとはまた違った面の有効性があると思う。 一方、トレーニング・マシーンはまず安全で、初心者でも行いやすい。 ◇ 当時の私のチームには、アシスタント・コーチ、トレーニング・コーチ、トレーナーがいたが、役割の分担化(細分化)がトレーニングを含め、練習の質を向上させることに大きな意味を持つと思う。 ◇ 最後に私自身の結論的なことを1つ。 コーチが苦手なことは、選手も苦手ということ。 苦手な部分にどう対処するかは、選手だけの問題でなく、コーチ自身の問題でもある。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月11日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その10
こんにちはenoです。 筋力トレーニングに関して私自身の意見、反省点とは… ◇ 私自身は、楽しさ、やる気を非常に重視して練習を組み立てているつもりだが、(音楽を多く用いるのもそのため)、筋力トレーニングを計画する際にはそれがかえってマイナスに働いた面があると思う。 つまり、楽しさ、やる気に重点を置くあまり、"シュート・サーキット"のように、筋力トレーニングの部分が中途半端になってしまったという例がある。 猛練習と楽しさが矛盾しないという言い方を借りれば、ウェイト・トレーニングの単調さと、楽しさも矛盾しないと言えるだろう。(単調という表現が適当でないのかもしれないが…) その単調さを紛らわす方法よりも、それを克服する状況づくりを行う必要があったように思う。 ◇ 重いボールを使った練習は、楽しさ、やる気を志向した、良い面が出た例だと思う。 コーチや監督はどうしても技術や作戦などのほうに関心が高いので、そういう意味ではこれは当然なことといえる。 逆に言えば、コーチや監督は、技術や作戦以外のところ、基礎体力作りの面に関しては関心が低いので、良い指導が出来にくいということでもある。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月09日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その9
こんにちはenoです。 筋力トレーニングとして非常に中途半端になってしまった最大の失敗原因は何か? 筋力トレーニングに関して、その後の大きな変化といえば、まずトレーニング・マシーンを買い揃えていったこと。(カイザー・カム・2 という空気圧のマシーンを5台揃えた) それと、数年前からトレーニング・コーチを入れて、週に何度か見てもらっていた。この2つは、いわばこれまでの反省をもとに対処した改善策である。 筋力トレーニングに関して私自身の反省点、または若干の意見をまとめると次の通り。 ◇ 私自身の最大の失敗は、本格的な筋力トレーニング、ウェイト・トレーニングを熟知していなかったこと。またそれに対して楽しさ(面白さ)を見出していなかったこと。 冒頭のところで述べたように、コーチの面白いと思っていないものを、選手に面白いと思わせることは難しい。別な表現をすれば、苦手なことを教えるのは難しいということ。 ◇ チームではコーチは私1人でずっとやってきたので、苦手な部分を克服するだけの余裕はなかったこと。 技術練習とトレーニング全般(筋力トレーニングを含む)を、1人で見ることそのものに無理があったと思う。 トレーニング・コーチに入ってもらったのはこの理由による。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月06日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その8
こんにちはenoです。 A)シュート・サーキット B)ミドル・シュート・サーキットC)スーパー・シュート・サーキット この3つのプログラムは、筋力トレーニングの内容がそれぞれ異なる。 A)は徒手的なもの、B)はダンベルを使ったもの、C)はアポロ・エクササイザーとダンベルを使ったものである。 (アポロ・エクササイザーとは)アイソメトリックスとアイソキネティックス(アイソカイネティックス)というトレーニング方法の組み合わせである。 アイソメトリックスとは力を入れた状態で数秒間静止するというもので、今でも軽いトレーニングやリハビリなどで使われる。 アイソキネティックス(アイソカイネティックス)は筋肉の可動範囲を、時間をかけて動かすというものである。 バーベルなどでは軽く感じる場所と重く感じる場所が出るので、非効率だという理屈だからである。 これらのシュート・サーキットは要するに、シュートの練習と筋力トレーニングを同時に行える点と、さらにタイムを取って競うという競技性を狙ったもので、選手には好評なプログラムであった。 しかし、このプログラムの欠点を言えば、選手がシュートのほうにばかり意識を集中して、筋力トレーニングが付け足しになってしまったことである。 筋力トレーニングとしては非常に中途半端なものになってしまった。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月04日
コメント(0)
-

楽しさ、やる気にこだわる筋力トレーニング その7
こんにちはenoです。 バスケットボールというのはボールを扱う競技であるから、ボールを重くすればそれに必要な筋力が強化できると考え、既定のボールと性能(弾み)が変わらず、かつ思いボールを特別に作ってもらった。 あまり重すぎるのはオーバー・アクションになってよくないので、結局100g思いボールを、シーズン中もシーズン・オフも毎日使った。 既定のボールを使っての練習ももちろん行い、両者の時間的割合は色々と工夫した。 この思いボールを使ったことによって、スローイングもシュートも飛距離が大きく伸びた。 現在は3点シュートのラインがあるが、それより更に外側からからでも楽にシュート出来るほどである。 "静的筋力"や"動的筋力"のプログラムが、いわば基礎的筋力トレーニングだったとすれば、この重いボールでの練習は、専門的筋力トレーニングとして位置づけることが出来るのではないかと思う。 その後、新たな筋力トレーニング・プログラムとしてできたのが、一連の"シュート・サーキット"である。 これは2人1組になって筋力トレーニング・メニューとシュート(20本)を交互にこなしていくというもので、3セットのタイムを計り、各組対抗でそのタイムを競う。 "シュート・サーキット" "ミドル・シュート・サーキット""スーパー・シュート・サーキット"の3つのプログラムがある。 3つとも筋力トレーニングとシュートを交互に繰り返すのは変わらないが、筋力トレーニングの内容がそれぞれ異なる。 ■ 読者様からの一言が、何よりも励みになります。♪ この記事のコメントお寄せください。■ 榎本のメルマガ(当ブログと内容が違います) 『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年04月01日
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1