2011年09月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

鳩づくし
『皇嘉門(こうかもん)』 横道発見! こういう細道を見つけっと、入ってみたくなんだよね。 で、こっそり入ってみた。 立ち入り禁止の札もないし、ちゃんと道が通ってるから、だいじだよね。 建物を囲むように建てられた塀。 黒に細かい細工が施されている。 「鳩の彫り物が おおいなー」 ずっと続く塀の彫り物は、みんな鳩なんだ。 なんか、場違いな場所へ入り込んじまったみたい。 後で調べてわかったんだどもな。この回廊は『鳩づくしの回廊』って言うんだって。 そういえば。鳩は平和のシンボルだべ。東照宮の『眠り猫と雀』も平和の印。 もしかして。真似たのかな。 ドキドキしながら、先へと進む。 豪華な門。 「入っていいんかな? いいんだよね?」 そろそろと、足を踏み入れる。 「なんだべな、こりゃ? 竜宮城さ、来ちまったんけ?」 立ち止まって見上げた門は、浦島太郎の物語の挿絵にそっくり。 これが『皇嘉門』だど。 中国の建築様式で、竜宮造りっていうんだって。別名『竜宮門』。 この奥に家光公の墓所、奥院がある。 だども、この先は立ち入り禁止。柵でがっちりおおわれて、侵入は不可能。 だども『皇嘉門』が見られただけで、文句なし。 陽明門に比べれば小さい門だけんど、こっちも見ごたえは十分。 満足、満足! (栃木弁:注)だいじ=大丈夫にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.29
コメント(1)
-

4つの門
『門』 大猷院には4つの大きな門があんだ。 1つ目は「仁王門(におうもん)」。密迹金剛(みつしゃくこんごう)と那羅延金剛(ならえんこんごう)の仁王像が守衛替わり。 2つ目は「二天門(にてんもん)」。後水尾天皇の書いた「大猷院」の額が目印だべ。 門を守っているのは、「持国天(じこくてん)、広目天(こうもくてん)。裏は風神、雷神と4人が受け持つ。 3つ目が「夜叉門(やしゃもん)」。東西南北を表す4体の夜叉が担当。 そして4つ目が「唐門(からもん)」。ここには守護の像はないけんど、細かい細工や彫り物がびっしりと埋め尽くしている。 この奥に 拝殿があんだ。 だども、あんまし観光客はいないみたい。 たまたまかな? 東照宮と違って、静かな落ち着いた雰囲気。いいなあ。落ち着くど。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.28
コメント(0)
-

後方支援
『大猷院』 「大猷院」は徳川家光(3代将軍)の墓所だど。 「死んだ後も、東照権現さまにお仕えする」と遺言を残したため、この場所に祀られたとか。 入ってすぐに小さな橋があった。 流をたどってみっと、小さな滝があったべ。 流を見ながら、小休止。 滝は三途の川。 橋を渡った先は、あの世を現しているんだって。 これは手や口を清めるための、御水舎。 白と金を基調に、黒で縁取られた東照宮に比べて、大猷院は金と黒を基調に、赤の縁取り。 金箔も赤身を帯びたものを使ってんだと。 大猷院は、派手さや豪華さはない。 だども、落ち着いた雰囲気で、東照権現さまを背後からそっと見守っているような、心強さを感じたべ。 正面の仁王門の前にも階段があったけんど、先の二天門までにも階段がある。 山の急斜面を利用して建てられてっからな。階段や坂道はしゃーないな。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.26
コメント(1)
-

歴史も、敷地も、奥が深いんだど~
『日光二荒山神社』 日光山内では東照宮が有名なんだけんど、二荒山神社のほうが古くて歴史があんだど。 奈良時代に勝道上人が、四本竜寺を建てたんがはじまりなんだって。 そうそう。正式名称は、二荒山神社って言うんだ。二荒山神社は「ふたらさん じんじゃ」と読むんだよ。 ところが。 栃木県宇都宮市に、二荒山神社っていう神社があんだ。こっちは「ふたあらやま じんじゃ」って読むんだ。 だども、漢字で書くとどっちも「二荒山神社」。 だもんで、区別するために、本や雑誌で紹介すっときは、日光と付けてるんだって。 ややこしいべ~。 東側の参道から入ると、楼門が見える。入母屋造りというらしい。 奥に見えるのが二荒山神社の拝殿。 この時、雨が降って来たんだ。だから、他の場所は見ないで、急いで通りすぎちゃったんだ。 神社もちらっと見ただけで、通り過ぎた。 ブログを書くために調べて見たら、拝殿の奥に、見どころがたくさんあったみたいなんだ。 日枝神社とか、朋友神社とか、化け燈籠とか。 「ああ!悔しい!」 う~ん。これは、もう一度、見にいかなくっちゃぁなんないかな。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.24
コメント(0)
-

なにが でるかな?
「上神道:二荒山神社」 上神道は東照宮と二荒山神社を結ぶ道だど。 左右には石の燈籠が立っている。 高い石塀と赤塗の塀が、燈籠の奥を固めてる。 他には何にもない。と、思うかもしんないけんど、よく見るといろんなものがあるんだど。 真っ直ぐに伸びた、杉の木、とか。 足元の石と歩いた時の感触、とか。 石塀の石に触ってみる。雨が降って、冷たいかな? それとも、日に当たって暖かい? その日だけしか見れない景色が、たくさんあるど。 「塀の向こうは、どんなかな」 と思ったら、首を伸ばして、覗いてみんのも、おもしろいっぺ。 表からは見えない神社が、見られっかもしんないど。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.23
コメント(1)
-
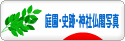
幻の「鳴かない龍」
「本地堂」 陽明門を入って左側の大きな建物が本地堂。 東照宮の御際神・薬師如来を祀るお堂だど。 鳴龍って聞いたことあんべ? 龍の下で手を打つと、龍が鳴いているように聞こえるっていうやつだど。 今は、宮司さんらしい案内役のかたがいらして、説明付きで、龍の鳴き声を効かせてくれるんだ。 拍子木を「こーん」と鳴らすと「ふぉーおおん」って感じで反響すんだ。 だども、この鳴龍。昔は鳴かなかったんだって。 っつうのも、床が畳敷だったため音がわかりにくかったんだな。 鳴いているような音がする、って気が付いたのは、明治のはじめごろなんだって。 ってことは。 社参に訪れた将軍さまたちは、龍の鳴き声を聞けなかったってことなのかな。 うわー。もったいないなー。 それからな、話はかわるけんどもな。 本地堂の建物は、昭和36年3月15日の火災で焼失しちゃったんだと。 今見ている建物は、昭和43年に再建されたものなんだって。 「えっ、それじゃあ、江戸時代に立てられたものじゃあないの?」 って驚くかもしんないけんど、変わってしまったものは建物だけじゃぁないんだよ。 鳴龍の絵も別物なんだ。 今の絵は、「堅山南風」という画伯が描いたもの。 黒い墨で書かれた、ちょっとおどろおどろした迫力のある龍なんだ。 そんで、元の絵は「狩野安信」っていう方が描いたもの。 赤や緑を使った、優しげというか、落ち着いた感じの龍。 東照宮のあちこちにいる龍を想像してもらえると、かなり近いど。 「狩野安信」のほうが、東照宮の龍って感じがするな。 うーん。現物が見れないってのは残念だべ。 昔の龍を見たい方は、宝物館で売っている「日光東照宮」っていう写真集をごらんください。 16ページに、焼失前の龍の写真が載ってるど。 ぜひ、今と昔の龍を見比べてほしいべな。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.21
コメント(0)
-

こまいぬ三昧
「奥社」 短い階段を上がると、拝殿の正面にでる。 拝殿は、黒漆塗に金箔の細工。東照宮と比べっと、地味だな感じだど。 だども、威厳はかわんない。っつうか、こっちの方が迫力があって、好きだな。 拝殿を堪能したら、案内板に従って、裏にまわる。 ちょうど拝殿の裏っ側に、門が見えた。 鋳抜門。青銅制の平唐門だべ。 門の前にも、こまいぬらしき丸い背中が見えた。「むむ、遠くて良く見えねえど!」 目が悪いって、損だべな・・・ もっと近くで見たいけど、砂利の上に造られた木造の通路は、鋳抜門のそばを通らない。 しゃーねーから、写真を一枚。あとでじっくり鑑賞しよう。 これがそん時の写真だべ。 奥にあんのが、権現様の宝塔。 宝塔の前には鶴ともうひとつ、小さな背中が見えたど。 鶴といえば、亀。だども、どうもちがうみたいだべ。 ぐるっと回って、反対側から覗いてみた。 遠くてはっきり見えないけんど、こまいぬみたいだべな。 ここでも写真を一枚。と思ったんだけんど、どうにも角度がよくない。 塀が邪魔っ気で、肝心のこまいぬらしき像が、うんまく写真におさまんない。 後ろから、他の観光客も迫ってきた。 いつまでも突っ立って、占領してるわけにもいかねえかんな。 写真はあきらめて、先にすすんだ。 さて、帰りは無事に帰れっか。またまた、階段だべよ~。 (栃木弁:注) しゃーねー =仕方がない。しょうがない。 うんまく =じょうずに。うまく。いい具合に。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.20
コメント(0)
-

1×1=無敵?
『奥社拝殿のこまいぬ』 階段を登りおえる。足はがくがくして、もう限界だべ。 頂上には親切にも、ベンチとお茶の自動販売機が設置してあった。 まずは休憩して、息をととのえる。「みんなばてるんだなー」って、ちょっと安心したよ。 水飲み場もあった。いや、清めの水だべか。 ふと見上げると、石で作られたこまいぬが2匹、おでむかえ。いんや、不審者が入ってこないように、睨みをきかせてんだべな。 だども、可愛くって、見入っちゃうど。 もしかして。可愛い魅力で、誘惑して、先に進ませないって作戦け? 右側のこまいぬ。角はない。 左側のこまいぬ。角がある。 毎日手入れしてんのかな? 苔も生えてない。綺麗すぎて、ちょっと残念。古めかしいほうが、昔を感じられていいんだけんどなー。 この先に、拝殿と東照権現さまの宝塔がある。 もう一息。「よいしょっ」と掛け声とともに、腰を上げる。 あっ、まだ階段があった。 しばし、立ち尽くす。 足腰が鍛えられるなあー。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.19
コメント(1)
-

207
『再び東照宮の話』 「眠り猫」を拝観した後、奥に進む。参道への登り道。登り口に坂下門がある。 「坂下門」と呼ばれるようになったのは江戸時代の中期頃からで、昔は「御奥院御登り口」と呼ばれていたんと。 江戸時代には、将軍社参の時にしか開かれなかったので、「開かずの門」とも言ったみたいだべ。 写真も乗せたかったんだけんど、あんまし良く写ってなかったんで、勘弁しとこれね。 これは坂下門を抜け、奥社へ向かう参道の入り口。 石段は、全部で207段あんだって。 まだまだ先は長い。ひょいっと左側に目を向けると、東照宮の本殿と拝殿らしき屋根が見た。見とれた振りしてひとやすみ。 木々の隙間から覗き見る東照宮も、趣があんべ? 振り返ると、まっつぐな道。 このあと、落っこちそうな急斜面の石段を登っていく。 なんとかがんばって、やっと奥社まで、たどりついたんだ。 ベンチに座って、しばらく休憩。「やー、体力ないなー」としばらく落ちこんじゃったど。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.17
コメント(0)
-
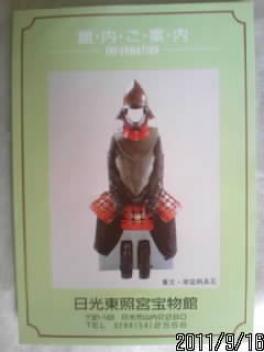
「日光東照宮宝物館」
下新道を進んでいくと、「日光東照宮宝物館」っつう建物にたどり着く。 大正4年に開館した宝物館には、国宝や重要文化財に指定された品物がたくさん展示されてんだ。 これは宝物館のパンフレット。表紙に使われてんのは南蛮胴具足。 徳川家康公が、関ヶ原の合戦で着用したと伝えられてるもんだど。もちろん重要文化財だっぺ。 納められた品々は、東照宮の祭神「徳川家康公」の遺愛品や、朝廷からの寄進品、歴代の将軍や諸大名が奉納品ものだど。 家康公が集めた、舶来品も、いっぺえある。 たとえば、渾天儀。天体や星の動きを調べるときに使うんだ。見たところ地球儀に似てっけど、渾天儀に日本とか阿蘭陀とかは、載ってない。 星の動きだけ。そだな。宇宙の向こう側から眺めた地球周辺を、再現したって言えば、わかっかな。 編鐘も、展示されるど。楽器としても使えるし、音律を合わせるときにも使うんだと。 門の形の板に細い棒を渡して、小さい鐘をたくさん吊るしたものなんだ。 どちらも残っている数が少なく、とっても貴重な品なんだって。 だども、一番の見どころは、20分の1の縮尺で再現された東照宮の模型だべな。 展示室の一室が、ほぼ模型で埋め尽くされてんだ。そこいらの模型とは、迫力が違うど。 屏風絵や彫刻部分まで、精巧に再現されてて、いまさっき散策した、東照宮の全体が見渡せる。 歴史に興味ない人でも、思わず引き込まれっちゃうよ。 それから、宝物館で買える「東照宮再発見」高藤晴俊・著 は、おすすめの本。 著者は、東照宮の禰宜を務めている方なんだ。 綺麗な写真や、東照宮の裏話なんかが載ってて、おもしろいど。 そだ。余談だけんど、宇都宮市にある「栃木県立博物館」にも、ガラスでできた東照宮の模型があんだよ。 ちょっと精巧さには欠けるけんど、綺麗だかんね。ぜひ一度、見てほしい逸品だべな。 (栃木弁:注) いっぺえ=いっぱい。たくさん。 いまさっき=さっき。ちょっと前。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.16
コメント(0)
-

まっつ~ぐ~に~♪
今日は無駄話は無し。写真だけだど。 場所は大猷院から東照宮の横を抜けて、石鳥居まで抜ける下新道っつう道だべ。 まっつぐに伸びる道。それだけで、わくわくしっちゃうな~。 木の幹や苔を眺めながら、てくてくと歩いていく。いい気分。 山内の神社めぐりで疲れた目や神経を沈めるには、もってこいの場所だど。 (栃木弁:注)まっつぐ=真っ直ぐ。一直線。の意味。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.15
コメント(1)
-

「恐悦至極にございます」
「石垣越えなんて、楽勝!楽勝!」 軽々と着地を決める獅子。 日光東照宮の、陽明門の前にいんだ。んで、これは右側の獅子。 こっちは左側の獅子。柵に遮られて見ずらいけんど、びしっと着地を決めている。 「飛び越えの獅子」またの名を「恐悦飛越えの獅子」。 寛永13年に参拝した、徳川家光公に褒められ、「恐悦至極にございます」と答えたから「恐悦」の名が付いたと言われてる。 逆立ちしてるとこ以外にも、見て欲しいとこがあんだどもな。実はこの獅子たち、後ろの石柵と同じ一本の石から彫られてるんだ。 くっついてるみたいに見えるんじゃあなくって、本当にくっついてんだよ。そこんとこ、よーく見てほしいんだべ。可なり高度な技術が必要だど。「嘘だー」って思う人。ぜひ、東照宮に言って、じっくりと観察してみとこれね。 但し。この獅子たちは、重要文化財に指定されてっから、お触りは厳禁だど。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.14
コメント(2)
-

石? 石! 石・・・
東照宮の大階段前。道沿いにあった石。 奥宮の道沿いにあった石。 大猷院の道沿いにあった石。 なんか不思議だべ。なんだろなーと思って写真に撮ってきたんだ。 んで、調べて見たら、祝祭などで使う幡を建てるための礎石なんだって。 史跡じゃあなくって、がっかり。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.13
コメント(2)
-

燈籠
写真は、日光東照宮の表門を入ったところにある、燈籠たちだべ。 燈籠は江戸時代に大名たちが奉納したものなんだ。 たとえば。伊達正宗。島津家久。藤堂高虎。井伊直孝。福島正則。などなど。大勢の大名たちの名がならんでる。 境内に現存する燈籠は121基、石造りが101基、銅製17基、鉄製2基、石造り五重塔が1基あって、表門前に6基、表門から陽明門下大石段までに90基、陽明門前に24基、陽明門内に1基となってる。 すごい数だんべ。さすが東照権現さま、って感じだど。 燈籠の順番も決まってんだ。陽明門の直下は譜代大名。陽明門大石段下は外様大名。陽明門内に東福門院さまが納めたとされる1基がある。 陽明門内にある1基は銅製燈籠で「1本燈籠」と呼ばれているんだ。 この燈籠は、東福門院(2代将軍秀忠公の娘・後水尾天皇の中宮)の奉納と言われてきたんだどもどうやら違うって意見もあるらしいど。 『元禄御道具帳』っつう資料には「禁裏様御奉納」と書いてあって、他の資料でも「後水尾天皇の奉納」と書いてあったんだって。だもんで、今は、後水尾天皇が奉納した燈籠じゃあないか、って説が強いんだと。 ずらりと並んだ燈籠群に、お気に入りの武将たちの姿を重ねて見る。さて、何がおこるかな。宴会か。手柄自慢か。それとも戦の続きかな。 建物を見るだけじゃなくって、建物に縁のある人たちを想像してみる。 こんな楽しみかたも、おもしろかんべ?にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.11
コメント(1)
-

ちょこっとだけ、振り向いて
日光の東照宮は、山内で一番人気がある場所だど。観光客もたくさんいて、写真を撮るのも一苦労だべ。 入場料は1,300円。これで陽明門と眠り猫と鳴竜がみられんだ。 さてと。東照宮内で見られる建物と主な彫刻は 三神庫 (象) 神厩舎 (三猿) 陽明門 (子供、仙人、龍 など) 坂下門 (眠り猫と雀) 本地堂 (鳴竜) ってとこかな。 陽明門、眠り猫、三猿は、日光に行ったことがない人でも、「ああ、あれか」ってわかるぐらいに有名だ。だがら、説明はいんないね。 こんなかだと、像の彫刻が見逃しそうかな。 象は表門を潜ってすぐ。目の前に見える三神庫の屋根の下にいんだ。 だども、見逃される理由はもう一つある。 「想像の象」って呼ばれる白と黒の象たちは、ちょうど神厩舎の反対側に位置してんだ。 神厩舎には三猿がいっぺ? 皆そっちさ見とれて、わいわいと通り過ぎっちゃーから、見逃しっちゃうんだ。 実は、私も見逃したんだ。帰り道でふと見上げたら「想像の象」が目にはいって、やっと気が付いた。 「こんなとこに、いたっ」って驚いちゃったよ。 この象が彫られたころは、まだ象が日本にはいなかったんだ。だから、狩野探幽さんは一生懸命想像して描いたんだな。ようく見ると、耳の形や尻尾の辺りが、今の象とは、ちょこっと違うんだ。 高い位置にいっから、見え辛いんだけんど。じっくり見て、違いを感じてほしいな。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.10
コメント(0)
-

日光山内散策に出発!
9月6日(火)に、日光山内を歩いてきたど。そん時に見たもの感じたことを、ちょこっとづつ書いていこうとおもいます。 東照宮と大猷院を中心に、あちこち写真を撮ってきたけんど、携帯が古いのか、撮影者の腕の限界か。ボケボケの写真ばっかし。 だもんだから、見どころの場所は、ほかの方のブログやホームページに乗ってっから、そっちさ見とこれね。 今回は車で行ったんだ。長距離ドライブで、くったくた。一休みした後で出発だっぺ。 日光山内には、あちこちに看板や案内板が立ってっから、ガイドブックがなくっても、迷うことはない。ゆっくりと散策できっと。 東照宮に向かう参道を歩いていると、水の流れる音がする。昨日からの台風の影響かな? ときょろきょろ辺りをみまわした。 参道の脇に水路を発見。近寄ってみると、澄んだ水が流れてる。緑の苔と石が、水の流れと共演して、いい音色を奏でていた。 東照宮へ向かう途中で、ほっと一息。緊張がほぐれたど。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.08
コメント(0)
-

飛山城 倉庫跡かな? 兵士詰所かな?
林に囲まれた広場に復元された、中世の竪穴建築物だべ。 2棟あって、一つは真っ直ぐな形、もう一つはL字形になってる。 入り口は板をかぶせたもの。持ち上げて中に入る。建物の中に入るというよりは、地面の中にもぐりこむって感じだべ。もちろん中は真っ暗だど。 竪穴建築は、地面に深く穴を掘って、屋根を付けたような建物だから、壁がない。地面が壁の役割もしてるんだな。その分雨や風には強そうに見える。 こっちの建物は横から入り込む形式。食糧なんかの貯蔵用に使われたと考えられてる。地面の下は気温も保ちやすいだろうから、食べ物を保管するにはちょうどよかったんだろうな。 中には兵士の詰所かも。という意見もある。だども、こんなとこさ何人も籠ったら、窒息しないんだろうか。中で喧嘩とかはじまったら? 閉所恐怖症の人がいたら? さて、建物の中では実際どんなことが起こっていたのか。どんな使い方をされていたのか。 写真を見ながら考えてみるのも、散歩の後の楽しみになってきた、今日このごろだっぺ。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.07
コメント(0)
-

飛山城 烽家
飛山城には2つに復元された建物があんだ。一つがこれ。こないだ、ちょこっと書いた「烽家(とぶひや)」の建物。狼煙の管理を任された、役人たちの住居だったみたいだべ。 こっちが正面。建てられたのは平安時代のころらしいど。飛山城が築かれるずっと前の建物っつうのは、間違いないんだと。 発掘品の中に、「烽家」と書かれた墨書土器が見つかってる。そこで、専門家の調査では8世紀から9世紀ごろのものと言われてる。 これは裏側。でっぱってんのはカマドの裏側。こっから外に煙が抜けるようになってる。 カマドの裏側って見たことなかったんだども、こんな風になってたんだね。 狼煙の制度は799(延暦18)年に、一部の地域を覗いて停止または廃止されたらしい。 飛山の「烽家」が廃止の対象になってたんかどうかは、わかっていない。 けんど、実際に住んでいた人はいた。 復元とはいえ、昔の建物を眺め、中を覗いていると、どんな人たちがどんな生活をしていたのか。空想が広がるど。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.04
コメント(0)
-

飛山城 謎の建築物の正体は・・・
飛山城で一番広い6番の曲輪。ここでも建物跡が確認されたらしい。この辺りで確認された建物は小規模なものが多いみたいだ。 今は芝生が植えられたり、紫陽花が群生してたりして、散歩や遊び場にはうってつけって感じの広場になってたど。 広場の片隅にある、謎の建築物。説明版がないのでなんだかわからない。 一見、物見櫓にも見えるんだけど、実は、建築物の正体は狼煙台なんだ。 飛山城跡の入り口にある「とびやま歴史体験館」に詳しく説明があんだけど、飛山に城が築かれる前。「烽家」という狼煙を管理する設備があったことがわかったんだ。 この建築物は、狼煙の煙が本当に信号として役にたつのか実験したときに、復元されたもの。「ハネツルベ式」っつって、夜間に火をあげるときに使うんだと。 写真では見ずらいんだけんど、真すぐ上に伸びた棒が立っている。 その先に、紐で束ねた藁や生柴をしばって吊るす。藁に火をつけ棒を高く掲げると、20K先からも見えるらしい。だども、実験のときには約5Kぐらい先からしか、見えなかったんだって。天候とか、空気なんかも昔と違うから、しゃあないべな。 鬼怒川を挟んで反対側には東山道っつう、昔の街道が通っていたらしい。街道を通る人々からは、飛山がよく見えた。 飛山は、城を築かれる前から、重要な拠点として、活用されていたんだべ。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.02
コメント(0)
-

飛山城 北側の曲輪
2号堀の入り口だど。正面の橋を渡れば、北側の曲輪に入れるんだ。 だども、この日は危険のため立ち入り禁止。 鬼怒川の河川から、撮った写真。崖の上がちょうど1号堀に囲まれた曲輪のあたり。その奥に3号堀がある。 崖が崩れてる。地震の影響があったみたいだ。立ち入り禁止なのは、崖崩れのせいかもしんないな。 3号堀はL字形をしていて、部分的に堀残しがあるため、虎口として使われていた可能性があんだと。堀からは木橋が確認でき、「横矢掛け」ができる作りになってんだ。 「横矢掛け」っていうのは、侵入者に対して横から矢を射かけられるように、土塁や塀を作って待ち伏せできる仕掛けのこと。前に写真を載せた枡形と同じ仕掛けだべ。 3号堀に囲まれた曲輪では、掘立柱建物が1棟確認されてる。また、1号堀、3号堀の近くの崖は昔は今よりも広かったらしいんだ。 その崩れた部分に、主人の住居があったのかもしれない。 主人の住居跡が発見されて、復元されていたら、見応えがあったんべなー。にほんブログ村にほんブログ村
2011.09.01
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1










