2011年11月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

自慢の逸品 『干瓢ふくべ一刀彫』 (栃木県上三川町)
「干瓢ふくべ一刀彫」 前にちょこと書いたけんど、上三川町には「ふくべ」っていう、干瓢の実を使った特産品があんだ。(前の記事。干瓢の実の写真はこちら だど) 古くは戦国時代。 炭を入れる器として使われてたみたいなんだ。 【送料無料】【smtb-kd】【茶器/茶道具・炭道具】瓢(ふくべ) 炭斗 白価格:12,600円(税込、送料込) これは楽天市場で検索して見つけたもの。 干瓢じゃなくって、瓢箪みたいだどもな。 たぶん、干瓢の炭入れも、こんな感じだったんだべな。 本格的な細工物が生まれたのは、江戸時代になってから。 正徳2年(1712)に近江国水口藩から国替えになった鳥居忠英が、下野国壬生藩に伝えたんが、栽培のはじめなんだと。 ふくべに色を塗って、面を造り始めたんも、この頃みたいだど。 大きな目と、丸く口を開いた鬼の面は、藤原秀郷が退治したという「百目鬼」っていう鬼がモデルでな。 魔除けになるんだと。写真があると、わかりやすいんだどもな。いい写真がみっかんなかんたんだ。 気になる人は「ふくべ細工」で検索しとこれね。(追記:ふくべ細工写真だど。参考に、しとこれね) 面の他に、小物もあるど。 小さなふくべは、花瓶や小物入れ、だるまのような置物などに細工されて、土産物としても、よろこばれてる。 だども、最高作品は「ふくべ一刀彫」っていう彫り物だべな。 上三川町の故・渡辺孝一さんというかたが、考案されたんだと。《上三川町ホームページ・ふくべ一刀彫の写真はこちら》 この作品の作者は、誰かわかんないけんど、見事だべ。「干瓢ふくべ一刀彫」は、上三川町だけでしか見られない、自慢の芸術品なんだど!ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.30
コメント(2)
-
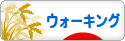
『上三川落城物語・歴史編 3』
『上三川落城・歴史篇』《その3・落城後の影響》 慶長2年(1597)5月2日。上三川城は、落城した。 城主・今泉高光は自害。今泉家は滅亡したことになる。 だども、話はここで終わりじゃぁないんだ。 今日は、その後の出来事を、ちょこっとだけ、書いてみっかんな。 まずは、宇都宮城。 宇都宮国綱(うつのみや くにつな)は、一族内の騒動を納められなかったという理由で、改易。 所領は没収。備前国(岡山県)の宇喜多秀家のもとへ配流となったんだっぺ。 改易の理由は、所領の石高を偽って、豊臣秀吉の怒りを買ったって説も、あるんだどもな。 他にも、勢力を広げ始めた宇都宮氏の威力を、削ぐためだって話も、聞いたど。 はっきりとした理由は、わかってないみたいだべ。 次は、多功城。 13代城主・多功綱朝(たこう つなとも)は上三川落城には関係していなかった。 だども、宇都宮氏の改易と供に、宇都宮一族の勢力は弱まり始めた。 多功城も、その一つで、だんだんと威力をなくし、廃城となった。 最後は、芳賀城。今は真岡城っていわれてるとこだど。 騒動を起こした、芳賀高武(はが たかたけ)はどうなったかって言うとな。 芳賀城も、宇都宮氏の改易に伴って、勢を弱めていったんだ。 高武は上杉景勝に身柄を預けられ、伊勢神宮に宇都宮家の再興を願ったりしている。 没年も、ちょっとあやふやだけんど、高武が最後の芳賀城主だったってことは、間違いないようだど。 最後は、宇都宮城以外の城は廃城になって、姿を消しちまった。 ・・・さびしいもんだな。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.28
コメント(2)
-
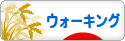
『上三川落城物語・歴史編 2』
『上三川落城・歴史篇』《その2・事件のあらまし》 上三川落城の2年前。 落城の、きっかけと言える事件が、起こったんだ。 慶長元年(1595)。豊臣秀吉の朝鮮出兵から戻った国綱に、養子の話が来きたんだ。 相手は浅野長政の次男・長吉。進めてきたのは、豊臣秀吉。 国綱には、後継ぎがいなかったから、ちょうどいいと思ったんだべな。 困った国綱は、大阪詰め宇都宮家 家老・北条松庵と上三川城主・今泉高光に相談したんだと。 松庵と高光は賛成した。んだがら、国綱は、養子の話をうけることにしたんだ。 ここで話が済めば、上三川城は落城しなかったかも、しんないけんどな。 そうは、いかねかったんだべ。 養子受け入れの話を聞きつけた、芳賀高武が、苦情を言ってきた。 高武は、宇都宮一族以外から、養子を入れることが、気にいらなかったらしいんだ。 養子をとるなら、芳賀家から取るって、約束していたって噂も、あんだ。 もし、ほんとに約束してたとしたら、高武に相談しないで、養子話を進めちまった宇都宮氏は、怒られてもしゃーないべな。 だども、実際は、なんで高武が怒ったんか、よくわかってないらしいど。 とにかく。怒った高武は 秀吉の腹心・石田三成を通じて、養子話を解消しちまった。 んで、帰りがけに、京都四条河原で、北条松庵を、斬り殺しちまったらしい。 高武の怒りは、そんだけ激しかったってことだべな。 そして、慶長2年(1597)5月2日。 芳賀高武は、上三川城へ、夜襲をかける。 養子話に賛成した今泉高光が、許せなかったらしいんだ。 高光は、同じ宇都宮一族の高武が、攻め込んでくるなんて、考えてなかったみたいでな。 応戦したんだけんど、高光の勢いに負け、長泉寺へ逃げ込んだ。 長泉寺は、上三川城の北にあって、今泉家の菩提寺でもあんだど。 そして、今泉高光は、長泉寺で自害。 上三川城は、落城、したんだ。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.26
コメント(0)
-
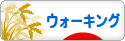
『上三川落城物語・歴史編 1』
『上三川落城・歴史篇』 《その1・人物紹介》 昨日は「片目のどじょう」っていう伝説側から、上三川城の最後を書いた。 なんで、今日は、歴史側から見てみようと思う。 ええと、時代は1597年。豊臣秀吉が、全国を統一したころの話。 おもな登場人物は 22代・宇都宮城 城主・宇都宮 国綱(くにつな 1568~1608) 14代・上三川城 城主・今泉 高光(たかみつ 1548~1597) 24代・芳賀城(真岡城) 城主・芳賀 高武(たかたけ 1572~1612) の三人だど。 他にも、豊臣秀吉とか浅野長政とかもでてくるけんど、説明はいんないねw。 おっと、ここで、3つの城があった場所さ、書いとくな。 大まかな説明だから、詳しくしりたい人は、地図さ見とこれね。 宇都宮城は、下野国の真ん中より、少し北側。 今でいうと、宇都宮駅と東武駅の間辺りに、あったんだ。 そこから、南に下がって石橋駅の辺りに、多功城があった。 多功城から、東側に進むと上三川城があったとこだど。 この辺りは、目印になるもんが、ないんだよな。 上三川町の中心部ってことに、しとくべか。 上三川城から、東へまっすぐ行って、今の真岡駅があるあたりが、芳賀城があったとこになる。 わかるかな? で、この3人の関係だけんど、ちょこっと、ややこしい。 宇都宮氏が主人(本家)で、今泉氏と芳賀氏は、家臣って立場になってるみたいだべ。 上三川城を築いた横田氏は、宇都宮氏の出で、1380年ごろに、今泉って名前に替わったんだ。 なんで、家系をたどって行くと、宇都宮氏にたどり着く。宇都宮一族なんだよ。 代々宇都宮氏に仕え、信頼も厚い間柄だったみたい。 そんで、芳賀氏。 一品舎人親王(いっぽんとねりしんのう)が祖といわれる一族なんだども、婚姻関係やらなにやらあって、宇都宮氏の重臣として、活躍したらしい。 23代城主・高継(たかつぐ)には子供がいなかったので、高武を養子にしたんだ。 んで、この高武は国綱の弟なんだっぺ。 3人の関係さ、わかったかな? 落城事件は、国綱に後継ぎがいなかったことが、原因のひとつになってんだけんどな。 これで、今泉氏と芳賀氏が、宇都宮氏の後継ぎ問題に係わってきた理由が、わかったかな?ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.25
コメント(0)
-

『片目のどじょう・ 上三川落城伝説』(栃木県 上三川町)
『片目のどじょう・上三川落城伝説』 澄んだお堀の水の中に、鯉がいた。 目を凝らしてみると、小さい魚のようなもんが、泳ぎ去っていった。 「めめっこいな~」 ほげほげ~ っと見入っちゃったっぺ。 古い場所や、昔からのこる地名には、面白い伝説や悲しい言い伝えってのがあるもんなんだけど、上三川城にもあんだよ。 上三川城落城に関わる、伝説なんだど。 ただな。途中で、変な伝わりかたをしたみたいでな。 内容が、まちまちなんだ。 歴史に残っている事実と、同じだったり、違うとこもあんだどもな。 まあ、このへんは伝説だから、ちょこっと目をつぶって、大目に見とこれね。 でな。どんな話かっていうとな。《その1》「片目のどじょう」 慶長2年(1597)上三川城に、めんこい姫君がいたんだ。 真岡城主・芳賀高武、が嫁に欲しいって言って来たんだけんどな。 姫君には、好きな人がいたんで、ことわったんだと。 そこに宇都宮氏の、跡継問題が持ち上がったんだ。 で、養子をとるって話になった。 真岡城の芳賀高武は、反対派。上三川城の今泉高光は、賛成派。 意見が食い違って、揉め事になっちまった。 姫君のこともあって、怒った芳賀高武は、上三川城に夜襲を掛け、落城さしちまったんだっぺ。 姫君は、刃物で首を突いて、死のうとしたんだども、手元さくるっちまってな。片目を突いちまった。 その後、お堀に身を投げて、自害したんだと。 それ以来。 お堀のどじょっこは、みんな片目になっちまったって、言い伝えなんだ。 他には、姫君の婚礼の日に、高武が攻め込んできた、ってのもある。 最後もな。好きな武士と一緒に、お堀に身を投げた、って説も、あるんだど。《その2》「片目のどじょう」 話の主人公は、姫君じやなくって、今泉高光の奥方さまだった、って話だべ。 あとの部分は、ほぼ同じ。 最後は、高光と供に、御堀に飛び込んだっ、てことになってる。《その3》「片目の魚」 主人公は、姫君。 んで、内容は、ほぼ《その1》と同じなんだどもな。 攻め込んできた芳賀高武の軍勢と、姫君が一騎打ちするって話なんだ。 姫君は、なぎなたを振り回して、応戦。 片目を弓矢で射抜かれて「無念!」とか言って、御堀に飛び込んだんだと。 《その3》は、造り話だべな~。 せめて、姫君を守る武士、ってことにしとけばよかったのに。 これじゃあ、伝説じゃなくって、コメディ時代劇になっちゃーべ。 題名も「どじょう」から「魚」に変更されちまってるしな。 どじょっこも、魚だけんどな~。 だども、お堀の魚っつったら、鯉が思い浮かぶんじゃないかな。 そんじゃあ、だめだんべ~。 「当事者のどじょっこは、どう思ってっかな」 って、御堀の中を覗いてみたけんど、片目のどじょっこは、姿を見せてくんなかった。 鯉が、口をぱくぱくさせてるだけだったっぺ。 (栃木弁:注) めめっこい=かわいい(県北) めんこい=かわいい(県南) ほげほげ=ぼけっと どじょっこ=泥鰌にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.24
コメント(4)
-

崩れかけた 巨石たちの魅力
『崩れかけた 巨石たちの魅力』 今日は、上三川城で見っけた、不思議な石っこを、紹介すっと。 まずは、本丸広場。 東の隅っこにある、舞台みたいなとこにあったんだ。 石垣の一部かな? だども、上三川城に石垣が残ってるって話は、聞いてないべ。 草が生えてるし、石の間に詰まってんのは土。 セメントで固めた、偽物じゃあないど。 ってことは、公園化に伴ってこさえられた、偽物の可能性は低いべな。 第一、表門の石垣と比べっと、造りが雑だど。 だども、自然石には見えない。 なんだべな~。 こういうとこにこそ、説明板が欲しいもんだどもな。 気になんな~。 次は、土塁の外側。 北側の堀のあたりだど。 どうだべ? 明らかに、土塁の土止めって感じだべ。 崩れた土が、堀を埋めちまわないように、作られた壁に、見えないけ? これも、草が生えてて、土が詰まってた。セメント跡はないよ。 「これこそ、ほんとの石垣の跡け?」 って思っても、変じゃあないべ。 お城好きの人なら、知ってると思うけんど、石垣でお城を囲むってのは、珍しくない。 大阪城とか名古屋城とか、有名どころの城には、背中がそっくりかえっちまうような、高くて見事な石垣がつきもんだ。 やっぱし、お城へ行ったら、石垣はぜったい、みたいもんだんべ? だども、この石たちも、本物の石垣跡か、確信はないど。 公園化に伴って作られたもんじゃないってことは、確かだけんど、戦国時代の物かどうかは、わかんないかんな。 それに、ちょっと、近代っぽい雰囲気もあんだよな。 専門家じゃないから、勘、だけんどな。 ほんとのとこは、どうなんだべな。 最後は、正面の門近く。 公園化で造られた石垣の東側の隅っこだど。 よ~く、みとこれね。 整然とつくられた石垣の隣に、崩れた山みたいなもんがあるべ。 「これこそ、ほんもんの、石垣跡だべ!」 うれしくってな~。写真撮りまくっちゃったどw。 だって、崩れてるし。 でも、よ~くみると、積んだ石みたいにも、見えるんだ。 隣の石垣が、年月とともに崩れて、風化して、土に埋もれた・・・って想像して、みとこれな。 どうだべ? ますます石垣っほく、みえないけ? 「うん!これは、絶対に、石垣の跡だど!」 って、勝手に決めつけちまったけんど。 皆はどうだい? 石垣跡だって、思わないけ?にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.22
コメント(0)
-

土塁の上から・後篇
『土塁の上から・後篇』 上三川城の土塁は、高さが3メートル近くあんだ。 どのぐらいの高さかっていうと、こんな感じ。 写真の場所は、北西の角んとこ。ちょっとした広場になってて、休憩用の椅子があったよ。 んでな。柵のぎりぎりまで近寄って、土塁の下を覗き込んでみたんだ。 下に水堀があるせいかな。本丸広場側よりも、深く見えたど。 上三川城には、奥方さまが、御堀に身を投げ自害したって伝説があんだどもな。「ここなら、可能、だべな」 ってな。怖くなっちまって、そろそろと、後ずさりで撤退したんだ。 西側の土塁の壁は、東側とくらべっと、なだらかだな。 昨日書いた、東側の土塁では「ふくべ」を見っけたけんど、西側は住宅地になってんだ。 何の変哲もない、住宅地だべ。 だども、近すぎてな~。土塁の写真を撮るんも一苦労だったんだど。 土塁の高さが、低いからかな。 気を付けないと、覗きになっちまうんだよ。 「あやしいやつが、いるど」 って、通報されたくないかんな。 この辺は、ゆっくり見学できなかったんだ。 さらに歩いていくと、突き当りに休憩所があった。 場所は、南西の角っこだよ。 さっきの崖と、この休憩場がある角っこには、見張りの櫓か、小屋のようなものが建ってたって、考えられてんだって。 ってことは、遠くまでよく見える場所ってことだべな。「どんな景色が、みえんのかな~」 って、楽しみにしてたんだ。 ところが、木の枝が邪魔で、周りが良く見えない。 あちこちと、首を巡らして、やっと遠くに、山が見える場所を発見したど。 絶景~! 筑波山かな~。 あとは一面に広がる、家の屋根。 もうちょっと、木の枝が少ないと、辺りがよく見えたんだどもな~。 だども、十分に満足したっぺ。 これだから、土塁登りは、やめらんないね。にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.19
コメント(0)
-

土塁の上から・前篇
『土塁の上から・前篇』 上三川城の土塁は、階段が付いている。 だから、遠慮なく、上に登ってみたど。 綺麗な石を引きつめた通路があったべ。 歩きやすいようにって考えたんだろうけんど、実際は歩きにくかったな。 なんでか、っつうとな。石は滑るんだ。 写真を撮った場所は、広いからいいけんど、狭い場所もある。 柵は腰より低いとこにあってな。 転んだら、土塁を転がって、下の御堀に「ぽちゃん!」ってはまっちまいそうだったんだど。 おまけに、散歩にいった前日は、大雨だったべ? 木の日陰になっている場所は、濡れた落ち葉が、石の通路でさらに、滑るんだ。 で、滑る足元を気にしながら、のろのろと進んでいたら、こんなものが見えた。 びっくりしたど! 下向いてたかんな。目の視点も合ってなかったんで、ぼけっとしててな。 一瞬、しゃれこうべ かと思っちまったよ。 「そんなもんが、裏庭にあるはずあんめ」 ってな。見直したっくれ、正体がわかったべ。 これは「ふくべ」ってんだ。「ぶくべ」は夕顔の実の中身をくりぬいて、乾燥させたもんなんだ。 夕顔ってのは、くるくると剥いて干すと、干瓢になんだよ。 上三川町は、干瓢の生産地なんだ。 夕顔の白い花は、上三川町の花になってるぐらい、有名だっぺ。 んでな。「ふくべ」は色を塗ったり、彫刻をしたりすっと、芸術品にかわるんだど。 町の民芸品に、なっててな。昔は、あちこちで見たんだどもな~。 今は、どこで売ってんだべな。 下野新聞に、趣味で「ふくべの彫刻」をやっている人の作品が載ってな。 ぶったまげたど~。 木に彫刻したっていっても、わかんねかったんじゃないかな。 牡丹か菊だったか、ちょっと忘れちまったけんど、細かいとこまで繊細に彫られた花は、見事だったべ~。 日光東照宮の彫刻にも、負けないっていったら、大げさだべか。 いんや! 負けてない! と、思うど! 上の写真の「ふくべ」からは、ちょっと想像できねえかも、しんないな。 だども、「ふくべの彫刻」は機会があったら、ぜひ見てほしい一品だど! (栃木弁:注) ぶったまげた=おどろいたにほんブログ村にほんブログ村
2011.11.18
コメント(2)
-

上三川城と多功城の関係
『上三川城と多功城』 (写真は北側からみた本丸広場。遠くに大手口がみえるべ) 上三川城は、建長元年(1249)に横田頼業が築城した城なんだど。 最初は、宇都宮の兵庫塚あたりにあった、横田城にいたんだどもな。 政策や防御を考えて、上三川に移ったらしいんだ。 頼業は、宇都宮城主5代目・宇都宮頼綱の次男でな。 弟(頼綱の4男)には、多功城の初代城主・宗朝がいんだ。 宗朝は、多功城を築いた人でもあるんだよ。 多功城は、栃木県河内郡上三川町多功 にあった城だど。 なんで、多功城の話なんか、持ち出したかっていうとな。 上三川城と多功城は、宇都宮城の南側の守りを固める、重要な城だったんだ。 何度も、力を合わせて、戦に勝利してんだよ。 たとえば。 永禄元年(1558)の「多功の戦い」。 越後の上杉謙信が、上野から下野に進行、宇都宮城を狙ったときの話だべ。 上三川城の城主は、こんとき、今泉って名乗ってたんだどもな。 今泉・真岡・児山の3氏が多功氏と力をあわせて、上杉軍を追い払ったんだど。 それどころか、たくさんの武将の首を取ったとか。 その後も、上三川城と多功城は、宇都宮城の要として、活躍したんだって。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.17
コメント(2)
-

階段もいろいろあんだね。
『土塁の階段』 何日か前のブログに「土塁に階段なんか作ったら、城好きに怒られるかも」 って書いたけんど、怒られなくって、すむかもしんない。 土塁には、上に登るための階段が、こさえられることがあるってわかったんだ。 そこで、上三川城にあった階段を、本に載っていた階段と、比べてみたっぺ。 これは、北側の土塁に作られた石段。 戦国時代の城に作られた石段は「雁木(がんぎ)・雁木坂」ていって、土塁の上に直接上がれるようになってんだよ。 その「雁木坂」に良く似てた。 これは、東側の階段。門の側から、斜めの状態で、上に登れるようになってんだ。 壁に沿うように作られた石段は「合板(あいさか)」っていうらしいど。 反対側にも、同じように上がれる階段があんだ。 こっちも、本に載っていた「合坂」の写真と、よく似てた。 でもな~。 上三川城に残ってんのは、戦国当時のものじゃないかもしんないべ。 だって、階段跡が残ってたって話は、聞いてないかんな。 だども、石の古い感じとか、石段一つの幅の狭さは、新しくこさえたようには見えなかったな。 実際に登り降りしてみっと、坂も急で、落っこちそうになったっぺ。 公園用に作ったとしたら、危険度が高いと思うど。 復元ものかな。 だったとしても、周りの土塁に溶け込んでて、雰囲気が出てる。 この階段なら、城好きさんでも 文句はいわない・・・といいなあ。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.16
コメント(0)
-

昔は土居(どい)・土手(どて)っていったんだって。
『土塁の話』 面積250平方メートル、ほぼ正方形の形をした本丸広場を、ぐるっと取り巻いている土の壁。 これが上三川城址の見どころ。土塁だど。 入口は南に面した大手口ってとこと、小さい門が構えてある2か所だけ。 西側と東側に、一つづつ、こしゃえてあんだ。 だもんで、どこをみても、土の壁になってんだよ。 高さは、約3メートルあんだって。 芝が植えてあって、なだらかな斜面だな。 壮観な眺めだど~♪ この感じは、実際に見て感じてほしいな~。 この写真は、外側の堀横からみたもんだど。 上三川城は、平らな場所につくられた平城なんだよ。 だから、土塁の外側も見られんだ。 山城みたいな、崖っぷちに築かれた城じゃあ、危なくって、素人は見にいけないべ? 上三川城の場合は、堀に面して遊歩道が設置されてっから、安全に見学出来っと。 こういうとこが、公園化のいいとこだべな。 土塁の外っ側は、目の前がすぐに住宅地になってんだ。 城内が静かな分、堀の側を歩いていると、些細な物音が五月蠅いって感じるかもしんない。 だどもな。こればっかしは、しゃーないな。街中だかんな。 おや? そういえば。 本丸広場にいっときは、騒音さ聞こえなかったど。 土塁って、音消しの役目も、すんのかな。にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.15
コメント(0)
-

本丸広場を探検
『本丸跡』 本丸広場を眺めていると、端っこに、井戸を発見。 近づいてみた。だども、井戸ではなかったみたいだべ。 湧水とか書いてあったな。だども、今は水はなかったよ。 石碑もあったんだどもな。こういうのは苦手だべ。 よくわからなかったんで、そのまま通りすぎちゃった。 本丸跡の周辺は、通路がこしゃえてあった。 石で綺麗な模様が絵描かれてたりしてな。歩きやすいど。 子供や御年寄りのかたでも、安心して歩けんな。 だども、城好きから見ると、減点対象になんだべな。 本丸中央は芝が植えられてっから、通路は広場の周りを土塁にそってぐるっと廻ってる。 土塁の上に上る階段がみえた。 石でこしゃった階段は、ちょこっと苔が生えてたりしてな。いい感じだな~。 のんびり公園散策派としては、点数加算対象なんだどもな。「土塁に階段をつくるなんて、けしからん!」 と、城好きさんに、怒られそうだな。 日光浴を楽しみながら歩いていくと、神社があった。お稲荷さまらしい。 横に倒れた木の板には、「なんとか姫稲荷神社」ってかいてあったんだけんど、忘れたべ。 メモしとくんだったな~。 姫といえば。 上三川城の落城に係わる伝説に「片目の魚伝説」ってのがあんだ。 お稲荷さまは、この伝説に出てくる姫さまなんじゃあないか と思う。 ところがな。帰ってきてから調べてみたら、話はちょっと違ってたみたいなんだ。「片目の魚」じゃあなくって「片目のどじょう」らしいんだよ。 それに、伝説に出てくる人は、姫君でなくって、奥方さまらしい。 伝説がおこった時期とか、背景なんかは、同じなんだどもな。 う~ん。悩んじゃうど。 だから、この辺りは、もうちょっと調べて、はっきりしてから、書くかんね。 この稲荷神社の信憑性も、ちょこっと薄まっちまったな。 昔からのもんなのか。話題づくりのために、こしゃえたんか。 どっちにしても、もうちっと、手入れしたほうが、いいんじゃないかな。 割れたガラスとか、倒れた木の標識が、おいたわしかったど。 (栃木弁:注) こしゃる=作る。にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.14
コメント(0)
-

そうだ! 上三川城址公園へ行こう!
『上三川城址公園』 11月12日。 秋なのに夏のような陽気に、じっとしていられなくなった。 そこで、ちょこっと散歩に行ってきたど。 場所は、栃木県河内郡上三川町にある『上三川城址公園』だべ。 上三川町は、北側が宇都宮、西と南側が下野市、東側を真岡市に囲まれた町なんだどもな。 知ってる人は、どんぐらいいるのかな。 有名な観光場所はないから、知らないかな。 上三川城址についてはな。見る人によって意見がわかれてんだ。 お城好きのかたたちのホームぺ―ジでは、良かったという人もいれば、整備のしすぎって意見もあったべな。 載ってる写真も、城跡って感じじゃあなかったし。あんまし、広くないみたいだし。 上三川城は、本丸跡と、周りの土塁しか残っていないんだ。 周り水掘りがあるけど、これは昔っからのもんなのか、ちょっと疑問だな。 町の真ん中に、残った平城だかんな。 ほとんどの部分は、開発でなくなっちまってるんが、普通だべ? 公園化したとしても、本丸を囲む土塁が、ほどんど全部残ってるってだけでも、いいんじゃないかな。 つうことで、城址としてはあんまし期待しないで、散歩気分で出かけたんだ。 これが城跡入口。 「う~ん。こりゃあ、だめなほうに、1票、だべな」 入口の石壁は、素人の目で見ても、酷い。 復元物じゃあなくって、にせて作っただけだもんな。セメントで固めてあったど。 だもんで、気分が一気に、さがっちゃった。 だども、ここまできたら、全部見ねばなんねなって、先に進んだ。 いきなり、本丸跡広場にでた。 「おお。これは、いいほうに、1票!」 本丸跡は、広かった。ほんと、今までみた城の中では一番広いど。 天気が良かったせいか、さらに広々と見えた。 どれぐらい広いかっていうと、そうだべな。野球が出来るかもしんないな。 それにな。周りを囲む土塁も、いい感じだど。 気分がだんだんと、盛り上がって来た。「さあ、探検に出発! だべ!」 さてっと。この続きは、また明日にすっかな。にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.13
コメント(0)
-
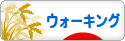
ブログの写真は なぜ ぼけぼけなのか?
えびねっこのブログの写真は、なぜ ぼけぼけなのか?《理由1》 デジカメを 持ってないから。 昔は 持ってたんだどもな。使いこなせなかったんだ。 電池代ばっかし かかっちゃってな。 リサイクルしちゃったw。《理由2》 携帯の カメラを使いたかったから。 カメラ付携帯電話を 買ったんだどもな。ほとんど使ってなかったんだ。 なんとか使いこなせないかな~、って思ったんだどもな~ 機会がなくって。 最近になって、やっと使い方がわかってきたど。《理由3》 みんなが 綺麗な写真を撮っているから。 ブログを見てっとな。みんな綺麗な写真 ばっかしなんだ。 「あんなにきれーな写真は 撮れねえな~」って思ってな。 写真の技術じゃあ、絶対かなわないから。 「このままでいいや!」って、な。 《結果》 気楽に写真が 撮れるようになった。 それにな。ぼけぼけ写真だと 想像力が湧くようになったど。 「ここは、どんなとこだったかな」とか、写真を見ながら思い出してるうちにな。 いろんな考えが浮かんでくるようになったんだ。 頭の体操にもなるし。わかんないとこさ出てきたら、調べるって楽しみも増えた。 それによ。あんまし綺麗すぎる写真てのも、困ったとこがあんだよ。 TVとか見て、現地にいって、がっかりしたこと、ないけ? 映像が綺麗すぎちゃってな~。期待が大きくなりすぎちゃったんだべな。 ぼけぼけ写真なら、期待はずれってことはないど。 だって、ほんもののほうが、いいんだかんな。 それに、な。 「ぼけぼけ」と「ほげほげ」 ちょこっと似てて、いい感じだべ? ほげほげブログには、ぴったりじゃあないかな。(栃木弁:注) ほげほげ=のんびり。ぼけっとしてる。 にほんブログ村にほんブログ村
2011.11.10
コメント(0)
-
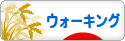
たまには 雑談でも、どうだべ?
おばんでやんす。 これは、昔の栃木弁で、「こんばんは」って意味だど。 明治時代ぐらいまでは、使われてたらしいんだけんどな。 今は「おばんです」って言ってんな。 今日は「えびねっこ」について、ちょこっと書いてみっかんな。 「えびねっこ」は、このブログを書いてる人のことだど。 生まれも育ちも、栃木県。 最近「栃木弁っておもしろいな~」って勉強し始めた、おばさん・・・いんや、おねーさんなんだw。 ええと、そんでな。まずは名前の由来から、いってみっべかな。 エビネって花を知ってっけ? 東洋蘭の一種で、山や里の木の下に咲く花なんだ。 日陰が好きなんだどもな。 品種改良された園芸種の中には、いい香りを放つ、匂いエビネってのもある。 地味で小さな花だけんど、愛好者もたくさんいるんだど。 この花が大好きなんで、「エビネ」に「っこ」を付けて、栃木弁風にしてみたんだよ。 栃木弁ではな。可愛いものに「っこ」って付けるんだど。 たとえば、「ねごっこ(猫)」「いぬっこ(犬)」「うまっこ(馬)」って感じだな。 「えびねっこ」。なかなかいい感じだべ? 気に入ってんだ。 栃木弁も気にいってる。 まだまだ、勉強し始めたばーりだかんな。 ごじゃっぺなとこもあんだけんど、これからも、ごじゃっぺ栃木弁でブログさ、書いてこうって思ってる。 最近は、歴史の勉強や城跡めぐりも始めてな。 まずは地元、栃木の歴史を探ってっとこだど。 おんもしれー話さ見っけたら、ブログさ書くかんな。 気が向いたときにでも、読んどこれね。(栃木弁:注) ごじゃっぺ=嘘。でたらめ。ここでは、曖昧って感じ。 ばーり=ばかり おんもしれー=おもしろい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと 押してね。にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.09
コメント(2)
-

宇都宮城 東側の守り・「田川」
『田川』(注:写真は宇都宮城と復元された堀の一部です) 宇都宮城の東っ側を守っているのは、田川。宇都宮市の真ん中辺りを、北から南に流れる川なんだ。 宇都宮駅の前にある「宮の橋」は、田川にかかる橋なんだども、有名な場所なんだ。 現在の宇都宮城は、本丸周辺の一部しか残っていない。 だもんで、公園として整備された城址からは、田川の流は見えないんだ。 あいだに建物も建ってっしな。 だども、古い地図を見っとな。 本丸の周りに二の丸、三の丸と、それらを囲む堀があってな。 堀の外っ側から、田川の近くまで、侍屋敷が広がってたってことがわかってる。 本丸から田川まで、大体400mぐらいかな。 川はくねってるかんな。おおざっぱな距離だども、な。 さて。 田川は日光から宇都宮市を流れ、小山市辺りで鬼怒川に合流する支流なんだ。 鬼怒川に比べたら、半分ぐらいの川幅なんだども、「暴れ川」って言われるぐいらい、氾濫したんだと。 下流にあたる宇都宮藩は、度々田川の洪水に、悩まされてんだよ。 第39代城主・松平忠祇さまの時代には、「源之丞洪水」ってのがあってな。 宝暦7(1757)年、明和元年(1764)年、明和3(1766)年と、3度も大洪水に見舞われてる。 使者が、118人も出たって話もあんだよ。 堤防も作った。幕府の手伝いで、灌漑用水も造られたんだどもな、なかなかしぶとくってな。 やっと、収まったのは、二宮尊徳さんが「宝木用水(新川)」を造ってからなんだ。 そういえば、尊徳さんの用水路跡か記念碑があったべな。 真岡市(旧・二宮町)には、尊徳さんの住んだ建物も残ってんだよな。 そのうち、行ってみっかな。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと 押してね!にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.08
コメント(0)
-

勝山城・飛山城の守り川 「きぬ川」
『鬼怒川』 鬼怒川は栃木県の北、日光の先にある鬼怒沼から流れて来る川だど。 栃木県の北から南に流れ、利根川に合流する一級河川なんだ。 これは勝山城の西側を防衛する鬼怒川。 こっちは飛山城の西側を防御する鬼怒川。 位置は勝山城が上流で、ずっと下ってきた崖の上に飛山城が築かれてるんだど。 鬼怒川は「鬼が怒る川」っていわれてっけど、平安時代は「衣川」っていったんだべ。 江戸時代でも「衣川」「絹川」っていって、怒るどころか、静かな流れの川なんだよ。 鬼怒は明治時代になってから、当てられた文字なんだ。 さて。鬼怒川の歴史で、忘れちゃいけない出来事があるんだどもな。 それは、江戸時代前期・1590年ごろから始まった「利根川東遷事業」だど。 利根川・ 荒川・渡良瀬川の流を変えて、江戸周辺の水害を減らそう、っていう大工事。 詳しく書くと、ブログじゃぁたんなくなっちゃうから、おおざっぱにいうけどな。 利根川と荒川と渡良瀬川を接続させて、鬼怒川に水を分水させっちゃうべ、ってことだべな。 下流に流れる水の量が減れば、洪水になる確率も下がるもんな。 だども、鬼怒川にも、いいことがあったんだよ。 利根川とくっつくことで、川を下って、江戸まで直接船で行けるようになったんだ。 この方法だと、途中で荷物を積み替える手間が省けるし、時間もかなり節約されたはずだ。 以前は、川が途切れるたんびに、荷物を積み替えて、陸と川を行ったりきたりしてたはずだかんな。 御蔭で、江戸と下野が、一気に近くなったんだ。 これって、いいことだんべ? おおっと。最後になっちまったけんど。「利根川東遷事業」なんて、でっけえこと考えた人のことも、書いとかなくっちゃな。 それは、徳川家康公、だど。 こないだの、水戸城周辺の工事も、家康公だったべね? 戦国武将っていうと、戦ばっかししてたイメージがあっけど、違ったんだな。 なんか、もっと、すごいことも、していそうな気がしてきたど。 歴史って、あんまし興味がなかったんだけんど、なぁんか、家康公に、興味がわいてきたど。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと 押してね。にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.07
コメント(0)
-

那珂川の話・栃木編
『那珂川 2』 今日は、栃木県側の那珂川だど。 那珂川は関東でも3つの指に入る大河なんだ。 関東でも1,2を争う清流で、鮎釣りで有名。鮎釣りがはじまると、大勢の釣り好きが那珂川に集まってくるんだど。 鮭も獲れるんだと。 江戸時代には献上品として、水戸藩に送られてたっつうから、極上の鮭が獲れたんだべな~。 これは、黒羽城の本丸跡にあったもの。石で囲まれた小さな場所は、枯れた池みたい。 ネットで調べて見たら、池の後で間違いなかったんだけど、いつの時代のものかは、わかんなかったんだ。 「ここに、那珂川に水さ、入れて、鑑賞したんかな」 小さい池だかんな。鮎は入らないだろうけんど、水辺の草とか植えたら、風流だべな。 黒羽城の北を流れる那珂川は、水流も多く、離れていても音が聞こえるぐらい勢いも強い。 だども、もっと北へ行くと、どんどんと石が多くなってきて、場所によっては姿を隠しちまう。 伏流水っていってな。川の流れが、地面の下にもぐっちまう現象なんだって。 地上部分は河原のようになっていて、大小さまざまな大きさの石っころが、広がってるんだ。 大雨が降ると、地上に姿を現して、川になるんだと。 この上流辺りを、那須野ヶ原っていってな。約4万haの扇状地なんだ。 日本で最大の広さだど。 だども、この辺りの人たちは、飲み水が確保できなくってな。 4km離れた箒川まで桶を抱えて、水汲みにいったんだって。 川はみんな地面の下さはいっちまうかんな~。 井戸は10m~100m掘らないと水が出なかったんだと。 この間、近場の大田原藩・黒羽藩は、なにも対策が出来なかったみたいだべ。 っつうか、対策を考えたとしても、だど。禄高が1万ちょいぐらいしかない小藩だかんな。 手出しが出来なかったんだな。 那須地方の水不足が解消に向かったのは、明治18(1885)年になってから。 那須疏水っつってな。那珂川上流の西岩崎ってとこから、水を引いて来たんだって。 この那須疏水は「日本三大疏水」に数えられてんだ。 那須地方の うんまいお米「なすぞだち」が作れんのは、那須疏水のおかげなんだど。 那珂川は、上流では水不足、下流では大洪水を引き起こす。 真ん中辺りは、鮎釣りや鮭が獲れて大賑わい。 困りもんだけんど、自然がいっぱい残ってて、今も綺麗な流れを湛えている、雄大な川なんだど。 黒羽城本丸跡の池が、水たまりみたいに見えっちゃうくらいにな。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと おしてね。にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうごさいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.06
コメント(0)
-

黒羽城・西の守り
『那珂川』 那珂川は栃木県の那須岳から、茨城県の太平洋へと流れる川だど。 黒羽城の西側を守っている川でもあんだ。 本丸の土塁を上がっていくと、那珂川の流れが見える、はずなんだども、立ち入り禁止区域なんで、見れなかった。 だども、ごうごうと流れる川の音は、はっきりと聞こえたど。 本丸御殿に住んだ殿さまたちも、那珂川の流れを聞いて、楽しんだんかな。 那珂湊って知ってっけ? 茨城県にある、魚市場みたいなとこなんだども、那珂川の河口そばにあるんだよ。 新鮮な魚が安く買えて、その上、うんまい。 たしか、おいしいお寿司屋さんもあったど。魚好きには、もってこいの場所なんだ。 だども、昔の那珂川は、水害が多くってな。 特に上流の栃木県で大雨が降ると、全部茨城県に流れてきちゃうかんな。 那珂川の氾濫は何度もあったみたいだど。 んで、 困ったんは水戸藩だ。 水戸城は北側を中川(今の那珂川)、南側を千波湖が守ってる。 これが、一度に氾濫したっくれ、城下町はあっというまに水浸しだかんな。 そこで、徳川家康が関東郡代・伊奈忠次に命じてつくらせたんが、備前掘。 慶長15(1610)年に完成した備前掘。洪水調節と周辺の水供給に役だったんだそうだど。 これが、那珂川開発の始まりなんだべ。 他にも、小場江用水路ってのがあって、今でも大事に使われてんだそうだ。 ・・・? あれ? 栃木県の話さするつもりだったんだども、茨城県の話になっちゃったど。 ま、いっか。お隣県だもんな。 しかし、那珂川って、黒羽城だけでなくって、水戸城の守りもしてたんだね。 とすると、黒羽城跡で聞いた、ごうごうという流れも、水戸城跡でも、聞けんのかな。 なんだか、水戸城に、親近感が湧いてきたど。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと 押してね。にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.05
コメント(0)
-

昔を語る マンホール
『黒羽』 黒羽城址公園内を散策していたら、こんなもんを見っけたべ。 これは黒羽町のシンボルを模した、下水道のマンホールだど。 杉の木・やまゆり・うぐいす の三つが彫り込んであんだ。 黒羽町ってのは、黒羽城を中心にした地域の町。元・黒羽藩のことだよ。 黒羽藩は、代々大関氏が城主を務めてきたんだ。 だども、初代から続いていた大関氏は、大田原氏に攻め込まれ、お家を乗っ取られちゃったんだよ。 天文11(1542)年ごろ、13代藩主・大関増次を打ち取った大田原資清は、12代藩主・宗増に長男の高増を養子にだし、次の藩主にさせたんだ。 ちなみに、資清は二男も同じ方法で、福原家に養子にだし、福原家も乗っ取った。 そして、次の狙いは那須氏・・・と続いてくんだけんど、これは別の話になっちゃうんで、やめとくど。 戦国時代には、他にも戦や揉め事があったみたいだけんど、黒羽藩は平和な時期が多かったみたいだべ。 江戸時代には、改易や転封もなく、大関氏が黒羽藩を納めてたんだと。 そして明治時代のころ。黒羽藩から黒羽県に替わり、黒羽町になったんだっぺ。 だども、黒羽町は、今はもう、ないんだど。 2005年に大田原市と合併したんで、黒羽町は大田原市になっちゃったんだ。 だから、黒羽城の住所も、黒羽町から大田原市になったんだよ。 あれ? これって、なにか不思議だね。 合併した理由は知らないど、大田原市の陰謀ってわけじゃあ、ないよね? 大田原と黒羽って、何か因縁があんのかな~。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぽちっと 押してね。にほんブログ村にほんブログ村 最後まで読んでくれて ありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011.11.02
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- お勧めの本
- 「海のてがみのゆうびんや」海で迷子…
- (2025-11-16 19:10:04)
-








