2012年01月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

裏表ありすぎな土塁 2
「左側の土塁」 今度は左側の土塁を探検! と思ったら、階段が、ない。 でも、上に柵がこさえてあっから、どっか上に上がれる場所があるはずなんだ。 うろうろ。 うろうろ。 歩き回った結果、やっと見っけたど! 場所はこないだの『玄門』とこを、さらに、奥に進んだとこ。 花壇の奥の、奥~のほうに、あった! 「花壇に、はいっちゃいげません」 って、言われてっけど、他に道がない。 それに、はいるなって看板もないし・・・いいべな。 ドキドキしながら、花壇の中さ、突入~!だどw。 階段を登ると、左手は藪だった。 手すりんとこまでいけば、正面の門が見えるんだけど・・・危険なんで、断念。 道と崖の区別がつかないぐらい笹が茂ってっかんな。 ふみ外して怪我したら、危ねえもんな。 左手側は、比較的、綺麗で、歩けるだけの道がある。 木の枝を避けながら、歩いていくと、突き当りは、公民館の壁だったど。 なんて~んかな。林の向こうは、きれいな壁ってのは、変な気分だべ。 せっかくいい気分で、探検してたのに、一気に覚めっちゃったっぺ。 ず~っと、壁を見ててもつまんないんで、引きかえす。 帰り道は、こんな道。急な坂になってんだ。 転ばないように、ゆっくりと歩いていると、堀が見えた。 左側の土塁は、上から見ると、Z字のように曲がってんだ。 ここは昔のまんまの形って聞いてるけど、この形には理由があんのかな。 さてっと。 短いけんど、楽しい土塁歩きは、おしまい。 堪能さしていただきました。 満足、満足。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.31
コメント(0)
-

裏表ありすぎな土塁
「右側の土塁」 公園内をぐるっと回って、土塁のとこに戻ってきたど。 これは、入口からみて、右側の土塁を本丸跡から見たとこ。 さらに近づく。 表っ側と、ぜんっぜん、ちげ~っぺ! だども、こっちのほうが、好み。 (表側の写真は、こちら) 土塁の側面を覗いてみる。 わ~い! 土だ~! って当り前だべ! いや、前にもかいたけんどな。 壬生城の土塁は公園化で整備されちゃったって聞いたから。 自然のまんま残ってるって感じが、うれしかったんだっぺw。 さらに、うれしいことがあったんだど。 壬生城の土塁は、上に登れんだ。 木でできた階段を登って行くと・・・ 土塁の上は、土の道。 ここには、公園化の手は伸びてないみたい。 柵もあっけど、道幅は狭くって、落ちそうだべな。 ・・・でも。こんな道が、好き。 階段をゆっくりと降りて、右側の土塁探検は終了。 残っている部分が少ないから、あっという間に終わっちまったよ。 だども、十分満足だど~。 壬生城、来てよかった~。 さて、次は左っ側だべな。 ええ~っと、どっから、登んかな?ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.30
コメント(0)
-

壬生城の歴史に 触れちゃったっぺ
「本丸跡 2」「他に見っとこ、あっかな~」 郷土資料館を後にして、公園内をぐるっと見回す。 右手に『公民館』がある。 ここは昔、中学校があったんだっと。 学校が移転した跡地を役場にしたって、話だど。 おんや? 建物の向こうに、変なもんが見える。オブジェかな? 公園内には、小さな彫刻が飾ってあったから、彫刻作品かもしんないな。 近づいてみると。 彫刻じゃなかった。説明板がある。どれどれ。 これは『吾妻岩屋古墳』の『玄門』ってものらしいど。『玄門』っていうのは、 古墳の中にある玄室の、出入り口近くに付けられる、石のこと。 説明板によると。 明治初年のころ、壬生藩主だった、鳥居忠室が古墳から掘り出して、 隠居場所の『上稲葉赤御堂』ってとこに、移築されてたんだって。 古墳が好きな殿さまだったんかな? 昭和63年になってから、地元の関係者の手で、城址公園に移築されたとか。 石とか岩を見ると、なでなでしたくなるんだけんど、 触るなって看板はないからいいべな~。ってな。 思う存分、なでなでしちゃったW。『玄門』には、くっきりと、昔の人が掘った四角い跡が残ってたよ。 って、ことは。昔の人と、同じ石を触ってんだね~。 もしかしたら、鳥居忠室公も、触ったんだべか? わ~お! だったら、すごいな~。 いったい、どんぐらいの時代の人たちが、触ったんだべな~。 今は、そんなかに、えびねっこの手形も混ざってんだよWWW。 やったべ~!! ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.29
コメント(1)
-

本物は、むりだべな~。
「本丸跡」 壬生城の本丸跡は、公園になってんだ。 入って中央部分には、巨大な噴水。 周りを囲むように、通路とベンチがこさえてあって、近所のかたが、くつろいでいたど。 全部が本丸跡なんかな? 思ってたより、広~いべ。 公園も、もっと、こじんまりしてんだべっ、て思ってたんだどもな。 すっきりしていて、居心地良さそう。 手入れもよくされてんだべな。ゴミなんか落ちてなかったど。 公園の奥に建物が見える。 左っ側が『図書館』。右っ側が『歴史民俗資料館』だど。 資料館は、城址散歩の楽しみの一つ。 ここは、建物もきれいで入りやすそうなんで、さっそく足を運んでみたど。 壁には、武将らしい人物。 これは、中の展示物も、期待できそうだべな。 んで、さっそく入館・・・と、思ったら、休館ですって? なんでだべ? 張り紙さ、よ~く見だら、次の展示会の準備があんだと。 そういえは。 公園入口の掲示板に、ポスターが張ってあったっぺ。 『壬生城本丸御殿と徳川将軍家』 そうそう。 今日(1月28日)の下野新聞にも、展示会の記事が載ってたよ。 下野新聞によると、4代将軍・家綱が、1663年に壬生城に宿泊したんだと。 んで、そん時の本丸御殿を、模型で再現してんだって。 (下野新聞の記事は、こちら) 模型を作っているのは、図書館勤務で壬生城を研究している、笹崎明さん。 制作途中の写真も載ってんだけんど、細かいとこまでしっかり作ってあるんだよ。 そして、大きい! これは、見に行かなくっちゃなんないな~。 企画展『壬生城本丸御殿と徳川将軍家』は、2月4日から3月1日までやってんだって。 楽しみが、増えたど~w。ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.28
コメント(1)
-

あれに見えるは~ 土の壁~♪
「土橋と土塁」 門の中に入ると、広い駐車場がある。 通路の右側と左側に、それぞれ30~40台の車がが止められそうな広さだど。 この辺りは、二の丸があった場所らしいべ。 大名が暮らす御殿も、この辺りにあったんだって。 残念ながら、それらしい雰囲気は、ぜんぜんない。 駐車場が広いから、楽に駐車できて、うれしかったけんどね。 道路に沿って歩いていくと、橋が出現。 同時に目に入ってきたんが、今回のお楽しみ。 壬生城に唯一残っている遺構、土塁だど。 これが右側。 んで、こっちが左側だど。 あんまし期待していなかったせいかな。 なかなかいい感じに思えたど。 堀を渡る橋は、『土橋』っていってな。 堀の中に土を入れて、渡れるようにした橋なんだ。 だども、舗装されて、偽物っぽい欄干がこさえてある。 堀自体も、石で固められちゃって、柵で囲んであったよ。 この辺りは公園として、安全面を重視したんだべな。 残念だけんど、まあ、しゃあないな。 土塁の表面は、笹が植えてあった。崩れないようにしたんだな。 芝を植えてある土塁は見たことあっけど、笹ってのも、いい雰囲気を出してるど。 うん。ちょこっと、林ん中さ入りこんだ気分だべ。 土塁の下には細い道があって、ぐるりと土塁を囲ってる。「あとのお楽しみだな♪」 ってことで、中に入った。 本丸跡は、噴水があって、遊具があって、いろんな建物も建ってるって聞いたど。 さて。どんなかな。 ドキドキすんな~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.27
コメント(1)
-

壬生城址公園へ行ってきたど (栃木県 壬生町)
「壬生城址公園」 2012年1月26日。 壬生城跡公園へ行ってきました。 場所は、栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目。 壬生城は、日光社参の際に、将軍さまの常宿とされた城なんだど。 ええと・・・ ここで、お城好きのかたには、残念なお知らせだべ。 壬生城の遺構は、開発によってほとんど、なくなっちゃってんだ。 残っているのは、本丸の正面にあたる土塁と、堀の跡だけなんだと。 ネットで調べても、公園がメインみたいなんで、あんまし期待しないで行ってみたよ。 これは、入口に復元された門だっぺ。 二の丸にあった門なんだと。 鹿沼市に移築された高麗門を参考にして建築された、『木造本瓦葺高麗門』なんだって。 門が建てられた場所は、道路の関係で、ちょこっと位置が違うらしいんだけど、 なかなかいい雰囲気だんべ。 扉も頑丈。 本物も、こんな感じだったんかな。 将軍さまが、お泊りになったっつうぐらいだから、 こんぐらいしっかりしてないと、だめなんだべな。 さてさて。 いよいよ、公園内に侵入すっと。 なにが、あっかな? ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.26
コメント(1)
-
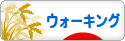
昔の名前で でています♪
「町名」 宇都宮城と二荒山神社の周辺には、昔の面影を残した町名が、いっぱいあんだ。 たとえば、宇都宮城から西の方角にある、『材木町』。 ここは、材木問屋があって、城中の御用も務めてたんだと。 その北にあんのが『伝馬町』。 ここには問屋場があって、にぎやかなところだったんだっぺ。 他国の使者が来たときに、面接する『対面場』も、ここにあったらしいど。 他には、曲物師が多く住んでいた『曲師町』。 明神様の馬場先ってことから付いた『馬場町』ってのも残ってる。 二荒山神社は『馬場町』にあんだよ。 で、宇都宮城があるとこは、なんて言う場所かっていうとな。『本丸町』っていうんだ。 そのまんま、だべなw。 他にも『鉄砲町』とか『茂破町』『新宿町』って面白そうな名前もあったんだどもな。 地図で確認できなかったんだ。 他の地域と合併したり、名前が変わったりしちゃんたんだべな。 道なんかも、どんどん開発されちまって、昔の通りを探すにも、苦労するんだ。 だども、まだまだ、昔のまんま。面影を残した名前が、残っでる。 こういうのって、いいっぺな~。 名前さ聞いただけで、昔はどんな建物があったのか、 どんな場所だったかってことが、想像でっきっぺ? 最近は、町や市の合併で、昔の地名が、どんどん無くなってるんだどもな。 それって、ちょっと寂しい。 他の県でも、同じなんかな? 時代に合わせるためには、しゃーないことなんかな? だども、やっぱし、この先もずっと、昔の名前さ、残していきたいべな~。 歴史がある、名前だもんな。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.24
コメント(1)
-

イチョウの精子?
「世界で初めて、精子の撮影に成功したイチョウ」 これは二荒山神社の、右側にあるイチョウ。 どこにでもある、イチョウなんだけんどな。 ちょっと、違うんだ。 根元んとこに、石碑が立ってた。 これによると、『世界で初めて、精子の撮影に成功したイチョウの木』なんだと。 へえ~。イチョウに雄株と雌株があるってことは、知ってたけんど、精子もあったんだ。 知らなかったべ~。 イチョウの精子を発見したのは、平瀬作五郎という人。 1894年に銀杏の中から、発見したらしいべ。 この発見をきっかけに、1894年には、池野成一郎がソテツの精子を発見してる。 当時の日本では、大発見といわれた出来事だったんだって。 実際に、精子研究に使われたイチョウが、東京大学の小石川植物園に残ってるそうだど。 ってことは、二荒山神社にあるイチョウは、実際の研究には、関係してないんかな? ちょっと、石碑が読みづらくってな。わかんなかったんだどもな。 ネットで調べた限りでは、イチョウの話のなかに、二荒山神社の名前が出てこない。 どういう経緯があったんだべな。 う~ん。謎だっぺ。 楽天市場で、こんな本を見っけた。【送料無料】「イチョウ精子発見」の検証価格:2,415円(税込、送料別) これに、詳しく載ってっかな? ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.23
コメント(1)
-
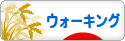
天明鋳物 (栃木県 佐野市)
「天明鋳物」 栃木県佐野市の名産品に、『天明鋳物』ってのがあんだ。 鋳物ってのは、溶かした金属を型に流し込んで作った製品のことだっぺ。 お寺にある鐘も、鋳物だべ。 佐野市の『天明鋳物』の歴史は古く、平安時代にまで、さかのぼれる。 鋳物が作られるようになったのは、あの藤原秀郷が、きっかけなんだよ。 天慶2年(939)藤原秀郷は、河内国丹南郡(現・大阪あたり)から、鋳物師を5人連れてきたんだど。 この時の鋳物師は、中国のほうから渡ってきた、職人だったみたいなんだ。 んで、5人の鋳物師を、金屋寺岡(現・足利市)に住まわせて、武器をこさえたんが、最初らしいべ。 鋳物の香炉を作って、天皇に献上したって噂も、どっかで聞いたよ。 高度な技術を持ってたんだね。 室町時代になっと、天明宿(現・佐野市)に『尾嶋天明衆』『嶋田天明衆』と言われる鋳物師の集団が出来たんだ。 『天明鋳物』の天明は、この地名から付いたみたいだど。 今では、お寺の鐘や灰皿などの工芸品の他、機会部品なとも作ってるんだって。 佐野のお寺にいったら、平安時代から伝わる技術に、ちょこっと思いを馳せてみてね。 《参考》 佐野天明鋳物のホームページは、こちらランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.19
コメント(1)
-
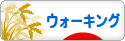
歩くときに 大切なもの
『靴』 月に一回の、ほげほげ散歩さはじめて、思ったんだどもな。 靴って、だいじだべ。 前にこんな出来事さ、見掛けたんだけどな。 場所は日光山内・大猷院だど。 行ったことある人は、わかっと思うけんど。 日光山内のほとんどの場所は、歩きやすいように、舗装されてんだ。 でもな。 あの辺りは、山さ切り開いて神社や寺を築いたとこなんで、坂や階段ばーりなんだっぺ。 そこへ、観光らしい若いカップルがやって来た。 男性のほうは、普通なんだども、女性のほうがなんか、変。 男性の後から、よろよろと歩いてくんだ。 なんかな。追いつくだけで、必死って顔してた。 具合が悪いんかな。 って、様子さ見てたんだどもな。足元さ見て、呆れっちまったべ。 ヒールの高い靴さ、履いてんだかんな。 それも、爪先しか地面につかねえべ、ってくらい高いやつだど。 街中でなら、かっこいいんだろうけどな。 山ん中で履くもんじやねえべな。 そういやあ、サンダル履きで、山の階段さ登ってる人も、見たごどあんな。 危ないなって、思わないんかな? 高価な登山靴を買え、っていってんじゃ、ねえど。 行く場所に合わせた靴を、履いたほうがいい、って言いたいんだ。 そのほうが、足元も安定するし、事故や怪我の可能性も減るべ。 ゆっくりと、景色や花や史跡を、楽しめると思うんだけどな~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.14
コメント(1)
-

攝社(せっしゃ)ってなんだべな?
「二荒山神社攝社(せっしゃ)下之宮」 二荒山神社の外で、小さな神社を見つけたど。 場所は、神社前の道路を渡って目の前にある、百貨店の入口んとこ。 最初は、百貨店に関係した神社かな、って思ったんだどもな。『二荒山神社攝社下之宮』って書いてある。 ってことは、二荒山神社に関係あるものだべな。 ここは、手水舎みたいだな。 お浄めしようかな、って覗いてみたら、水がなかった。 これが、神社の正面なんだけど、がっちりと柵で覆われでだ。 な、なんか、変な神社だべ~。 百貨店の真ん前なんで、居づらくってな。 早々に、退散しちまったっぺよ。 帰って来てから調べたら『攝社』ってのは、本社に縁故の深い神をまつった神社のことなんだって。 んで、『二荒山神社攝社下之宮』の場合は、二荒山神社発祥の地として、建てられたもんなんだと。 昔は『荒尾崎』って言われた場所らしいべ。 で、二荒山神社の本殿がある山が『臼ヶ峰』。 この辺りは、一続きの山だったんだと。 周辺の開発によって、山も丘もなくなっちまってな。 場所もちょこっと移動したみたいだけんど、神社は今も、大切にされてるようだど。 祀られている神様は、本社と同じで『豊城入彦命』。 近くさ行ったら、こっちの神様も、ぜひお参りしとこれね。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.11
コメント(0)
-

神さまが、おられる場所
「本殿と拝殿」 お浄めも終わったし、今度は本殿へお参りに行くことにしたど。 手前には、初詣客用に、特別に設えた赤と白の幕が引いてあってな。 ここさ、御賽銭を入れんだべ。 神社に入って、正面にある大きな建物なんだどもな。 ここは『拝殿』っていって、お祓いをしてもらったり、神様と対面する場所なんだ。 大抵の神社は、神様がおられる『本殿』と、お祓いを受けるための場所『拝殿』とあってな。『本殿』は奥まった場所にあって、普通の人は入れないんだと。 知んなかったな~。勉強になったっぺ。 んで、こっちが『本殿』だど。 中は見れないけんど、建物は見えるんだ。 がっちり、ガードされてるって感じだな。 ここに祀られている神様は、『豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)』。 他にも、市神さまとか、お酒に関係ある神様が居られたかな。 奥のほうには、初振稲荷神社っていう、赤い門が並んだお稲荷さんもあったど。 鳥居のあいだには、ちっこいお狐さまが、並んでお出迎えしてくれっと。 神社内には、他にもたくさん神様が祀ってあるんで、ゆっくり散策してみっといいべな。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.10
コメント(3)
-

枝源五郎寄進の水盤
「手水舎(てみずしゃ。ちょうずや)」 神社にお参りする前に、まずやることは、手や口を清めることだべな。『神門』を潜って、辺りを見回すと、左手に立派な『手水舎』があった。 みんなと並んで、さっそくお浄めしたど。 ひんやりとした水が、きもちいがったべ~。 これが、二荒山神社の手水舎の水盤。 龍の口んとこから、水が流れて来るようになってんだ。 実は、今回、二荒山神社さ来た理由は、2っつあってな。 1つは初詣なんだけんど、もう一つは、この『水盤』だったんだ。 一見、普通の『水盤』に見えんべな。 うん。作りが特別ってわけじゃあ、ないんだど。 なにが特別なんか、っていうとな。『水盤』を寄進した人が特別なんだ。 横んとこに、名前さ掘ってあんだ。『枝源五郎・天明5年』ってなってんだけど、わかっかな。『枝源五郎』って人はな。 1750年ごろに、宇都宮に存在した侠客で、旅籠屋『松屋』の倅なんだどもな。 仁義に厚く、困っている人を見かけると、放っておけなくなる人だったんだ。 その性格を見込まれて、目明しにもなったんだど。 後に、江戸へ行ったらしいんだどもな。 ここでも、大親分と呼ばれる大人物になったって、言われてるんだ。 いろいろな逸話が、残ってんだどもな。 歴史的な資料は、少なくってな。生没年もはっきりしてないんだよ。 宇都宮に残ってんのは、二荒山神社に寄進した水盤と、慈光寺ある生前墓だけ。 ところが、この『水盤』も、本物じゃあないんだと。 戊辰戦争で焼けちまって、のちに醸造替えされたもんなんだって。 う~ん、残念だべな。 そうそう。『枝源五郎』の逸話で、一番有名な話はな。 慈光寺の入口に、大きな赤い門をこさえたことだっぺ。 これは、書いとかなくっちゃな。 安永4年(1775)宇都宮城下で万人講を作って資金を集め、3年がかりでこさえたんだと。 だども、本物は1945年の第2次世界大戦で焼けちまってな。 今あんのは、復元されたもんなんだ。 『赤門』って呼ばれる門は、真っ赤な大門なんだと。 当時の様子をしっかり残して、作られたみたいでな。 そっちも、いつか見にいきたいべ。 って、ことで。 二荒山神社にある『水盤』は、『枝源五郎』に関する数少ない貴重な証拠なんだってことが、わかってもらえっかな。 もし、二荒山神社さお参りに行く機会があったら、ぜひ、じっくりと、見とこれね。《参考》【送料無料】宇都宮城物語価格:1,575円(税込、送料別) ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.08
コメント(1)
-

『菊花心に三つ巴』って、知ってっけ?
「神紋(しんもん)」 昨日のブログに、書いた紋がこれ。 門の柱んとこに、あったんだ。菊の花みたいだべ。 こっちは、門の扉んとこにあった紋。 やっぱし、菊の花みたいだべ。 菊の御紋というと、天皇とか、高貴な方々が思い浮かぶんだどもな。 なんか、関係があんのかな。 ちょこっと、調べてみたんだどもな。 神社には、『神紋』っていってな。神社特有の紋が、あんだって。 個人の家でいう『家紋』みたいなもんなんだべな。 んで、『二荒山神社』の『神紋』はどんなかっていうと、2つあってな。 1つは普通の『三つ巴』。もう一つは『菊花心に三つ巴』ってやつなんだ。 ここに付いてんのが、『菊花心に三つ巴』だべ。 菊の花の中心、花心の部分が『三つ巴』の紋になってんだ。 珍しい紋だべ? 初めて見たど。『三つ巴』といえば。 宇都宮城さ納めてた、宇都宮氏の紋が『三つ巴』じゃなかったかな。 うん。そだ、そだ。『右三つ巴』ってやつだど。 宇都宮氏は二荒山神社を信仰してたんで、神紋の一つ『三つ巴』の紋を頂いたらしいんだ。 そんでな。宇都宮氏の一族は、みんな『三つ巴』の変化型の紋をもってるみたいだど。 右周りだの左周りだの、いろいろあるみたいなんだどもな~。 よぐわがんないど。 『紋』かあ。 いままで興味がなかったんで、ぽけっと見てたけんど、調べてみると、面白いかもしんないな。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.07
コメント(2)
-

階段を登っていくと・・・
「神門」 長くて高い階段を登ると、目の前に巨大な門が現れる。 二荒山神社の入口、『神門』だべ。 階段のすぐ上にあっから、写真さ撮るだけでも、一苦労なんだ。 全体さ写そうとすっと、階段からおっこっちゃうんだど。 階段の数は、数えなかったんだけんど、50段はあんべな。 急だし、落ちたら、大けがじゃすまねえべ。 隅っこの手すりにつかまって、バランスさ崩さないように、慎重に撮ったんだ。 うんまく写ってっけ? 門の右っ側。 塀の向こう側、神社内は、休憩所になってんだ。 ふと見上げると、繊細な彫刻が彫ってあった。 よく見ると、門のあちこちにも、細かい細工が彫ってある。 家紋っていうんかな。 神社の紋らしき、菊の形に似た模様が、いくつかあったよ。 んで、こっちは中側。門の左側んとこなんだども、見えっかな。 屋根の内側の細工だべ。屋根は複雑な木の組み合わせで、支えられてんだ。 建築関係は、さっぱしわかんないから、技術がどうこう、って言えないけんど。 ほれぼれしちゃうな。 境内は、初詣客がいっぱい。お祓い待ちらしき、団体さんの姿もあったど。 若い人も結構いたんだけんど、門の横には誰もいなくてな。 おかげで、ゆっくりと、屋根の下を観察できたどw。 変な人ってみられたかな? だども、せっかく行ったんだし、こんなに立派な『神門』だもん。 じっくり見なくちゃ、損だべな。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.06
コメント(2)
-

「ふたあらやまじんじゃ」 (栃木県 宇都宮市)
「二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ)」 1月5日に、二荒山神社へ行って来たど。 場所は栃木県宇都宮市。 宇都宮駅を出て、西側の大通りをまっつぐ行くとあんだ。 ビルにまぎれて、見えないけんどな。 南の方向には、宇都宮城があんだど。 二荒山神社は、宇都宮氏とも、深い関係がある神社なんだ。 大きな鳥居の後ろの森が、全部神社の境内だど。 昔は階段の近くまで、ビルが建っててな。 神社へ上がる階段も、もっと急で、落ちそうになった記憶があんだどもな。 最近になって建て替えたみたいだべ。 鳥居も綺麗だし、階段も登りやすくなってるど。 二荒山神社は、藤原秀郷も戦勝祈願に立ち寄ったっていう話が残ってるぐらい、古い神社なんだ。 見どころもいっぱいあっから、一度、お参りしてみっといいど。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.05
コメント(1)
-

下野国の武士団
「下野の武士団」 今日はこの本を参考に、ちょこっと書いてみるべ。【送料無料】下野の中世を旅する価格:1,890円(税込、送料別) 下野国に武士団が現れたんは、10世紀ごろなんだと。 ちょうど『平将門の乱』が起こったころだべな。 下野国の押領使・藤原秀郷を子孫とした一族が、南の地域に勢力を伸ばしていったんが、最初らしいべ。 んでな。下野国の武士団は、主に4つの勢力に分かれんだどもな。 まずは、北の地域を支配した、『那須氏の一族』。 場所は、今でいうと、那須・黒磯・大田原の辺りかな。 有名な武人で那須の与一って人がいっけど、与一はここ、北の那須一族の出なんだど。 前にブログに書いた『黒羽城』の大関氏が北に入るっぺ。 次は、中央部と東を納めた、『宇都宮氏』。 場所は、宇都宮駅の周辺から、真岡の辺りかな。 宇都宮氏が納めていたころは、多功(多功氏)や上三川(上三川氏)にも一族の城があってな。 真岡(芳賀氏)ともつながりがあったんだ。 ブログに書いた『宇都宮城』と『上三川城』がここに入るっぺ。 他に『勝山城』と『飛山城』も宇都宮氏の出城みたいなもんでな。 重臣や宇都宮一族が、納めていたんだと。 次は、西だべな。ここの代表は、『佐野氏』だな。 ほかにも『足利氏』とか『皆川氏』もいるど。 場所は、佐野・足利・栃木辺りも入んだべな。 ええと、この地域は、まだ勉強し始めたばーりなんで、ちっとわかんないんだどもな。 有名武人は、なんつっても、『藤原秀郷』だべな。『唐沢山城』が西地区の代表だど! さて、最後は南の地域。ここは『小山氏』だな。 場所は、小山駅の辺りなんだけんどな。 小山氏については、まだぜんぜん勉強してないんだ。『小山城(祇園城)』を拠点にしてて、系統をたどっていくと、『藤原秀郷』に行き当たるんだと。 あとは、『宇都宮氏』の仇敵ってとこかな。 宇都宮氏と小山氏は、供に巨体な勢力を誇ってた一族でな。 何かと揉めごとを起こしては、戦になってたみたいなんだ。 さて。これらの下野武人団は、16世紀ごろに活躍したんだどもな。 織田信長が亡くなって、豊臣秀吉の時代になったころに、ほとんどの一族が、勢力を無くしちまったんだと。 中には、滅亡しちまった一族も、あんだど。 ほとんどの武士団が、大名になれなかったみたいだど。 まだ本も、読み始めたばーりだかんな。 読み進めたら、もっと面白いことが、わかっかもしんないど。 ってことで。 今年は、16世紀ごろ。中世って言われてる時代を中心に、勉強しようと思うんだ。 さて、どんな話さ出てくっか。 楽しみだべな♪ ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.03
コメント(1)
-
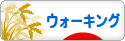
新年だべな。
「新年の挨拶」 あけまして おめでとうございます。 今年も、どうか、よろしくお願いします。だべ。 1月1日。 新しい1年の始まりだな。 さて、どんな、年にしたいかな~。 まずは、城址散歩に行くべ。 栃木には、まだまだ、ほげほげと散歩できる城址があんだど。 んで、写真さ撮って、ブログに乗せる。 ブログのほうも、もうちっと手を加えて、読みやすくしたいな。 そんで、たくさんの人に読んでもらえると、うれしいな。 まだ、具体的な案さ、ないんだけんど。 ま。のんびりと、やっぺ。 あと、体力さ、付けないとな。 食生活も、そろそろ気を付けないと。 最近では、お腹とお尻が、重たくなってきてな。 歩いてっと、地面につまずいたりしちゃーんだ。 後は、夜更かしだべか。 これも、健康さ、よくないな。 遠くへ出かけるには、早起きと朝から動ける行動力も、付けないといけないべ。 他にも、歴史の勉強もしたいし、文章も上手くなりたい。 やりたいことや、変えたいことさ、いっぱいだな~。 だども、今年のブログも、栃木弁でいくど。 慣れない人には、読み辛いかもしんないけんど、これが、えびねっこ流だかんな。 ここだけは、変えらんないべ。 ってことで。 今年も、下手な栃木弁と、栃木の話ばっかするえびねっこを、どうぞよろしくお願いします。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村
2012.01.01
コメント(1)
全18件 (18件中 1-18件目)
1










