2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
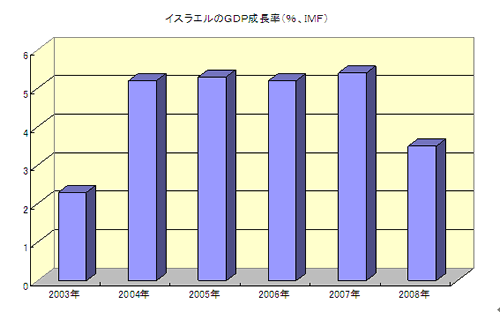
第120回 イスラエルの経済
今日のまとめ 1、全体としてイスラエルの経済は好調である 2、財政政策は保守的であり収支は改善している 3、為替の安定がインフレを比較的低く抑えている ■イスラエルのGDP成長率 近年イスラエルの経済は好調に推移しています。2006年にイスラエル北部はレバノンとの紛争で経済が混乱しました。それにもかかわらず、2006年から2007年にかけてのGDP成長率は5.25%としっかりした成長を記録しています。IMFの予想では今年のイスラエル経済は世界経済の減速の影響で3.5%程度の成長にとどまるとみられています。これは近年の5%を超える成長率からすれば少し低いですが、それでも立派な水準だと言えると思います。イスラエル政府は財政収支改善を目指しており、公共部門での支出を抑え気味にしています。それにもかかわらず、経済が好調だったのはその他の部門がまんべんなく成長に寄与したためであると言えるでしょう。 ■イスラエルの財政政策 近年のイスラエル経済の好調で税収は高水準でした。その一方で支出を抑えたため、イスラエルの財政収支は下のグラフに見られる通り随分改善してきています。イスラエル政府は政府の負債を圧縮することに努めています。目標としては2015年までに負債比率を60%にまで下げていく計画です。 ■イスラエルの失業率 イスラエル企業の業績はおおむね堅調で、バランスシートもどんどん強固になっています。こうした民間部門の好調を受けてイスラエル企業は雇用に対して積極的であり、失業率は着実に下がってきています。 ■インフレ イスラエルは過去にハイパー・インフレを経験しています。その苦い経験を生かして保守的な財政政策を採用したためイスラエルの通貨の安定感は最近増してきています。このところイスラエル・シェケルが強かったため輸入品の価格が安定し、これが物価上昇を比較的低く抑えることに貢献しました。 ■政策金利 バンク・オブ・イスラエル(イスラエル中央銀行)は政策金利を2006年10月のピークである5.5%から2007年6月には3.5%にまで下げてきました。その後、2007年12月にはインフレ率が3.4%に上昇したため利上げに転じ、2007年8月から3度に渡り利上げしました。2008年1月の時点での政策金利は4.25%になっています。 ■貿易収支 今後、世界各国経済がスローダウンすることが考えられるためイスラエルの輸出も減速すると考えられます。このため貿易収支は若干悪化すると予想されています。
2008年02月21日
-
第119回 イスラエルの歴史
今日のまとめ 1.イスラエルには世界からユダヤ人の人材が集まった 2.在外ユダヤ人のネットワークがイスラエル企業の強みである 3.防衛産業から派生した企業が多く活躍している ■若くて歴史の複雑な国 イスラエルの歴史を語ろうとする場合、その背景の複雑さからどうしても色々な見解の相違や対立が生じざるを得ません。ここでは皆さんが株式投資をするにあたって最低限知っておくべき予備知識としてのイスラエル史にのみ言及したいと考えています。 イスラエルは1948年5月14日に独立が宣言された若い国家です。しかしパレスチナの土地にはそれよりずっと以前からユダヤ教、イスラム教、キリスト教などの宗教が織り成す歴史が脈々と流れており、それがこの土地の地政学に極めて複雑な影響をもたらしていると言えます。パレスチナの地にユダヤ人の国家を再興しようという、所謂、シオニズム運動が本格的に勢いを持ち始めたのは1791年にフランス国内でのユダヤ人の解放が失敗したことが始まりでしょう。さらに1894年のアルフレッド・ドレフュスの裁判を巡る経緯から、反ユダヤ感情が欧州の社会に根強く存在することが印象付けられたこともシオニズム運動の加速を促したといえます。 1896年にハンガリー人のテオドール・ヘルツルがユダヤ人の国家を建設することを主張する『ユダヤ人国家』という本を出版しました。当初は国家建設を構想したと言うよりは、パレスチナの土地の中に自給自足の入植地を作り、ユダヤ文化の再興を期すというのがその意図するところだったとも言われています。ヘルツル自身は入植地の場所としてウガンダになっても仕方ないという考えを持っていましたが、東ヨーロッパのユダヤ人達はパレスチナでないと駄目だと主張しました。ロシアの社会運動家で東ヨーロッパにおけるユダヤ人弾圧を逃れた若者を中心にシオニズム運動を推進しようという機運が高まりました。ダビッド・ベングリオンはそんな中のひとりでしたが1906年にパレスチナに来ると、このグループのリーダーとなり抜群の指導力と強固な意志でシオニズム運動の組織化を指揮しました。■イギリスの日和見主義 第一次世界大戦の頃、英国のマンチェスター大学で化学を教えていたハイム・ヴァイツマン博士は巧みな交渉でシオニストの利益を推進しました。当時英国は戦争を有利に進めるためアラブ諸国から同盟関係を得たいと考えていました。1915年のメッカのシャリフ・フセインと英国のエジプト総督サー・ヘンリー・マクマホンとの間で交わされた書簡(所謂マクマホン宣言)の中で英国は大まかに言って現在のシリアの地中海沿岸地域からレバノン北部に位置する土地におけるアラブ人の独立を約束しました。 しかしその後、1917年11月に英国はバルフォア宣言によって「パレスチナの土地にユダヤ人の祖国を作る」ことを認めるとともに「パレスチナに居住する非ユダヤ人の市民権と宗教の自由を擁護する」という態度を表明します。こうした英国の日和見主義ともとれる一連の約束が後々までパレスチナ問題に影を落とすわけです。■国連の決議 その後、第二次世界大戦の際のユダヤ人迫害に至るまでパレスチナへのユダヤ人の入植は着実なペースで進みました。第二次世界大戦の際のユダヤ人虐殺では600万人にのぼるユダヤ人が命を落としたとされます。これがパレスチナの入植地を国家として承認しようという動きを加速させたことは言うまでもありません。パレスチナへ移住したがるユダヤ人の数は増えましたが、当時パレスチナを管理していた英国はアラブ先住民とのバランスをとるためにユダヤ人の移民を制限しようとしました。 こうした緊張の高まりから英国はもはや独自の判断だけではパレスチナの政策を決められないと考え、国連総会にパレスチナ問題の討議を預けます。国連はニューヨーク郊外のフラッシング・メドウズにおける会議で1947年11月29日にパレスチナの土地を複雑なユダヤ人居留地とアラブ人居留地に区分けすることを決定します。アラブ最高委員会はこの国連の決議を不服とし紛争が始まりました。■建国と相次ぐ戦争 1948年5月14日にはイスラエルの建国が宣言され、翌日、アラブの軍隊がイスラエルに侵攻(第一次中東戦争)しました。この戦争は多大な犠牲を伴いましたが、1949年の1月までにはイスラエルは戦争前の線引きよりもより拡大した土地を支配下におさめることに成功し、停戦ラインが折衝されました。この後の主な紛争としては1956年スエズ運河地方での衝突(第二次中東戦争)、1967年6月の第三次中東戦争(六日間戦争)でイスラエルがゴラン高原、シナイ半島、ガザ地区、東エルサレム、ヨルダン川西岸を獲得したこと、1973年の第四次中東戦争(ヨム・キプル戦争)などが挙げられます。このうち1973年の戦争は緒戦でイスラエルが劣勢だったのでそれまでの常勝神話が崩れ、与党である労働党の衰退の原因となりました。1977年のリクード党の躍進はそういう背景のもとに実現したのです。 1979年には米国のジミー・カーター大統領の斡旋でエジプトとイスラエルがキャンプ・デービッドにて平和条約を締結しました。これはエジプトがアラブ国家としてはじめてイスラエルと和解したことを意味し、画期的な出来事でした。■変質するイスラエル社会 イスラエル国内のユダヤ人はスペインやポルトガルをルーツとするセファルディム、中欧や東欧をルーツとするアシュケナジム、そして北アフリカや中東からのオリエント系ユダヤ人などいくつくかのルーツに分かれており、経済的、社会的地位の面ではアシュケナジムが支配的です。これが緊張のひとつの原因となっています。さらに労働シオニズム運動の考え方ではイスラエルに入植したユダヤ人は皆平等にキブツなどで労働に従事することを主張していますが、最近ではアラブ人が単純労働を担うケースが多く、社会の階層化が見られ始めています。■防衛負担はイスラエルの宿命イスラエルは国家安全保障上の理由から軍隊が非常に重要な役割を果たしています。男子の場合は3年間、女子の場合は21ヵ月の徴兵制度があります。イスラエルは最新の兵器を開発する必要から防衛産業が発達しており、武器輸出は外貨獲得の重要な源泉となっています。1987年にインティファーダと呼ばれるパレスチナ人の抵抗運動がはじまってからはイスラエルの軍隊が政治にもだんだん影響力を及ぼすようになってきました。ヨルダン川西岸ならびにガザ地区に住むパレスチナ人はイスラエルの支配に対抗すべく、独自の自衛軍を組織するとともに経済、社会面でも反対運動を組織していきます。そして教育や食糧の分配、管理や医療面での支援などを通じてコミュニティー活動に従事しました。 インティファーダの運動家の中にはPLO(パレスチナ解放機構)やハマス(イスラム原理運動)のメンバーも一部含まれていると考えられます。インティファーダが始まって以来、イスラエルは様々な方法でヨルダン川西岸ならびにガザ地区のパレスチナ人の生活に制限を加えました。インティファーダを鎮圧するために1989年当時イスラエルが費やした費用はアメリカ政府の試算では月間で1.3億ドルとも言われ、観光収入の激減ともあいまってイスラエルの国庫負担を増加させました。 この当時のイスラエルの経済的困難は新イスラエル・シッケルの13%の切り下げ、5.5億ドルに上る政府予算の削減、食糧、燃料などへの補助金の廃止、公的部門におけるレイオフの発表、ハイパー・インフレなどにつながりました。また最近では2006年にヒズボラ(急進的シーア派組織)がイスラエル兵2名を拉致したことをきっかけにイスラエルがヒズボラの活動拠点となっているレバノン南部に侵攻するという事件が起きています。■イスラエル史のまとめ イスラエルはその建国の経緯から世界各地からいろいろなユダヤ人が集まってきて出来た国です。その分、いろいろな才能を持った人材のバラエティーに富んでいるという風にも考えられます。また世界に散らばったディアスポラと呼ばれる在外ユダヤ人のネットワークがあり、これがイスラエルの企業活動に国際色を与えています。ウォール街に対するコネが強いのもそのためです。 イスラエルにとって防衛産業というのは重要な分野でした。このため防衛や情報に絡むビジネスではイスラエル企業は世界最先端のノウハウを持っているところが少なくありません。
2008年02月19日
-
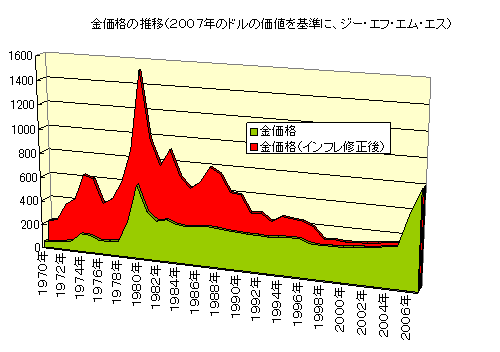
第118回 金鉱株の近況
今日のまとめ 1.ドルのファンダメンタルズの悪化が金価格高騰の一因 2.需給関係面から見ても金価格は先高観が強い 3.操業上の問題などが産金各社の株価の明暗を決めている ■1000ドルを窺う金価格 このところ金価格は堅調に推移しています。去年前半675ドルから725ドルのレンジで取引されていた金価格は9月から上昇トレンドに入り、現在911ドルに達しています。ゴールドの市場の調査会社として定評のあるジー・エフ・エム・エス社は今年の或る時点で金価格が1000ドルをつけるだろうと予測しています。それでは何故金価格がこのように堅調に推移しているのか、その背景を考えてみましょう。■蝕まれたドルゴールドに投資家の関心が向かう最初の理由はドルに対する不信感だと思います。近年、イラク戦争への戦費投入やポーク・バレリングと呼ばれる既得権益に絡む予算の奪い合いなどでアメリカの財政は悪化しました。実はこのような放埓な金融財政政策には前例があります。 1961年、ケネディー大統領はベトナム戦争の戦費調達をやりやすくするためFEDに金融を緩和しろと圧力をかけました。同時に大型減税案を打ち出します。このときは議会がそれを阻止しました。ところが1963年にケネディー大統領が暗殺されてしまい、アメリカ人は強烈なショックを受けます。副大統領だったリンドン・ジョンソンはケネディーの後を受けて大統領に就任すると「ケネディーの遺志を継ぐ」という事を宣言し、ケネディーのやり残したイニシャチブを全部実行に移します。それまで健全財政などの見地からケネディーに反対していた反対派はケネディーに同情する圧倒的な世論の高まりに負けて大型減税を通してしまうのです。そればかりではなく、メディケアなどの社会福祉制度もこのケネディー暗殺後の、アメリカ国民がエモーショナルになっているときに相次いで可決します。 これはちょうど9・11の同時多発テロの後にアメリカの世論が右傾化し、財政の悪化を招いた過程と酷似しています。ジョンソン大統領は低金利維持を最優先の政策とします。FRBはどんどんドル紙幣を増刷し、アメリカの国際収支は悪化しました。こうした、「不況のときにはどんどん財投をした方が良い」という考え方は経済学者ジョン・メイナード・ケインズの理論であり、それを信奉する人たちはケインジアンと呼ばれます。ジョンソン大統領のこの政策は当初成功を収めます。そこで米国の雑誌、『タイム』はWe are all Keynesians now.、つまり「我々は皆、ケインズ派だ!」と宣言するわけです。 ところで相場の世界では『タイム』の表紙に載る様なアイデアはそれがピークで、後は下り坂になるというジンクスがあります。ケインズ派がわが世の春を謳歌したのも、やはり束の間のことでした。なぜなら1971年の8月にはジョンソン大統領の後を継いだニクソン大統領がドルの切り下げを発表せざるを得なくなってしまったからです。さらにベトナム戦争遂行に絡む放埓な金融政策ならびに財政政策がインフレの芽を世界経済にしっかり植えつけてしまいました。その後、1973年にOPECのカルテルによる原油価格引き上げが世界的なインフレの直接的なきっかけになるわけですけど、上で見てきたようにもうそれ以前にインフレになる環境は整っていたわけです。ケインズ派は「ベトナム戦争さえなければ我々の実験は大成功を収めていたのに」と嘆きました。 でもそれは物事の順序を勘違いしていると思います。ベトナム戦争を遂行せんがためにケネディーはケインジアン的なレシピーを取ることを決めたわけであり、そもそも戦争やケネディーの暗殺という事件が無ければこういう展開にはならなかったのです。今回、ベトナム戦争をイラク戦争に置き換えてやるだけで1970年代初頭の資本市場のおかれた環境と今の環境が酷似していることがわかると思います。これはアメリカが70年代に経験したスタグフレーションがもう一度起こるリスクが高くなっていることを示唆していると思います。これまでのアメリカ、ヨーロッパ、日本などの経済成長を振り返ってみると、サブプライム・ローンに代表される新しい金融商品が仕掛け人となって経済成長や需要が創造されてきた部分が大きいです。でも、マネー・ゲームに打ち興じた時代は終わりを告げようとしているのです。このことはゴールドのような実物資産の価値が上昇することを意味します。現在の金価格はインフレ修正後の価値に直して考えるとまだまだ1980年の高値より遥かに安い水準にあります。■供給側からの説明 次に金の需給関係から最近の金相場の高騰の原因を考えてみましょう。ゴールドの需給関係をタイトにしているひとつの理由は生産が余り伸びていないことによります。下のグラフでもわかるようにゴールドの供給のうち最も大きな部分を占めるのは金鉱からの金の生産です。 しかし世界の金鉱からのゴールドの生産高はここ10年余り頭打ちが続いています。その理由は主要金山の埋蔵量が枯渇していること、金鉱がどんどん深くなり採掘コストが上昇していることなどによります。 主要な金生産国の中での生産高の変化を見てみると中国が近年生産高を伸ばしていることが注目されます。その反面、これまで成長のエンジンの役割を果たしてきたペルーは落ち込みを見せています。さらに歴史的に大きな生産高を誇ってきた南アフリカも近年どんどん凋落しています。■需要側からの説明 さて、需要の方に目を転じてみましょう。ゴールドの消費の中に占める最大の需要先はジュエリーのファブリケーション(加工)です。 ジュエリーのファブリケーション需要の増減を見ると最近原油高で好景気に沸いている中東からの需要が大幅に増えていることがわかります。これに加えて中国や、伝統的にファブリケーションの需要の多いインドなどからの引き合いが伸びていることがわかります。 金の需要で最近注目されているのはETFを通じた金投資からの需要です。ETFというのは上場投資信託のことを指しますが、投資家が株式市場を通じてこれらのゴールドETFを購入した場合、その購入額に相当する金の延べ棒をETF証券の発行根拠として指定信託銀行に保管する必要があります。従って金ETFの売買代金とETF向けの延べ棒の需要には或る一定の相関関係があります。ETFが人気になればなるほど現物の延べ棒への需要も増えることは言うまでもありません。ゴールドのETFはニューヨーク証券取引所や大阪証券取引所をはじめ世界の株式市場に存在します。とりわけ最近ではインドなどの新興国の株式市場でのゴールドのETF上場が計画されており、今後もETFの人気は持続すると考えられます。 ゴールドの需給関係からの最近の金価格高騰の説明をまとめると、近年、金の掘り尽しからだんだん生産が困難になっている状況にあって、中東、インド、中国などの新興国が豊かになることで需要が増えていて、さらにETFのような利便性の高い投資商品の開発によって新しい需要が生じたことが原因であるとまとめることが出来るでしょう。■金価格と金鉱株の株価のデカップリングこうした長期での強気要因に加えて最近、南アフリカで電力が不足し、操業上の理由から金鉱の生産が相次いで停止に追い込まれたことも逼迫間を煽りました。このため金価格が上昇する一方で操業停止に追い込まれた産金会社の株式は売られるというデカップリングが進行中です。 こうした状況を反映して現在の産金会社各社の株価は主に操業面での安定度、若しくはキャッシュ・フローの予測の立てやすさを切り口として序列が決まってきている印象があります。その観点からは最大手であるバリック・ゴールド(ABX)や財務管理に定評のあるゴールドコープ(GOLD)などが「勝ち組」として人気を博しています。その反面、南アの老舗の産金会社であるハーモニー(HMY)やゴールド・フィールズ(GFI)は最安値近辺をウロウロしています。南アの発電キャパシティーの不足は新しい発電所が完成するまで今後も慢性的に続くと思われます。それを断った上で、現在はこれらの金鉱は操業を再開しており、目先の業績に対する影響は一時的なものであると認識されています。 また、ゴールドのみならずプラチナなどの値段も騰がっていますから、生産量で予想を下回った分はある程度市況価格の上昇で取り返せます。一方、アジアに目を転ずるとモンゴルのオユ・トルゴイ鉱山を所有するアイヴァンホー(IVN)の株価は最近の金価格の上昇に余り反応していません。これは同社の鉱山が未だ生産を開始していない準備段階であることに加えて、同社とモンゴル政府との間で締結される投資契約(Investment Agreement)がまだ調印に至っていない事を投資家が問題視していることによると思います。今年の6月にモンゴルの総選挙が予定されており、その投票の後に調印が持ち越される公算が高いです。モンゴルのバヤル首相はアイヴァンホーとその事業パートナーであるリオチント(RTP)の両社に対しては好意的であり、これまでに作成された投資契約の草案の条件を変更することなく早急に契約調印をすべきだと演説しています。 また最近行われたモンゴルの国民に対するアンケートでも国民の79.5%はこのプロジェクトを支持するという意向を表明しています。オユ・トルゴイの所有権(エクイティー・インタレスト)に関しては現行の比率を改変すべきだという野党の声もありますがその一方で「あまりアイヴァンホーとリオチントに不利な条件にすると将来、どの企業もモンゴルのプロジェクトに参加したがらなくなる」ということを懸念する声も強いです。結局のところIAのエコノミクス(政府、参加企業のコスト負担比率ならびに分け前の分配比率)は現在の草案と余り大差ない水準で最終的に妥結するものと考えられます。これとは別に2月の上旬にリオチントは同社の現場責任者としてはエース級のキース・マーシャル氏をモンゴル担当にすると発表しています。リオチント社にとってモンゴルのプロジェクトの重要さを物語る人事だと思います。オユ・トルゴイからの本格的な生産開始は2011年にずれ込むことはほぼ避けられない状況ですが、それは既に現在の株価水準に織り込み済みだと思います。
2008年02月15日
-
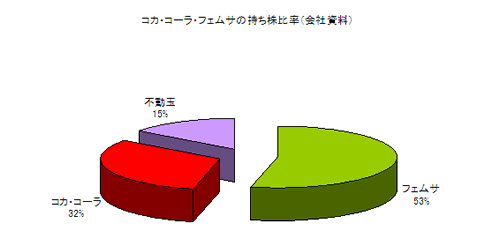
第117回 メキシコの株式市場(その2)
今日のまとめ 1. コカ・コーラ・フェムサのビジネスは景気後退に強い 2. イカの受注残は過去最高水準 3. ホーメックスは持ち家奨励政策の恩恵を蒙る 4. 空港管理会社の株は景気後退による旅客数の減少に注意 前回に続いてメキシコの代表的なADRを紹介してゆきます。■コカ・コーラ・フェムサ(KOF) 同社はラテン・アメリカを中心とするコカ・コーラのボトラーです。コカ・コーラのボトラーとしては世界第2位の規模です。同社はメキシコを代表する飲料の企業、フェムサと米国のコカ・コーラの合弁企業で1979年に創業されました。 ニューヨーク証券取引所への上場は1993年と比較的古く、このためアメリカの投資家にも馴染みのある銘柄となっています。2003年にはライバルのパナメリカン・ベバレッジ社を買収し南米最大のコカ・コーラのボトラーとなりました。同社は「コカ・コーラ」の他にも「ファンタ」、「リフト」などのブランドのソフトドリンクを販売しています。国別の出荷量は下のグラフのようになっており、過去4年間の平均年間成長率は4.1%です。国別ではベネズエラ、アルゼンチン、ブラジルが最も急激な成長を見ています。 同社の業績は清涼飲料のボトリングという比較的ディフェンシブ(景気変動に強い)な性格を反映して安定的に推移しています。過去10年間の年率平均EBITDA(税・償却・利払い前利益)は17%程度で成長しています。 このためパナメリカン社を買収したときに背負い込んだ負債も順調に返済中であり、2003年の時点で28億ドルあった負債は現在18億ドルまで圧縮されています。■イカ(ICA) イカはメキシコを代表する建設・エンジニアリング会社です。同社は道路建設や土木工事に加えて米国のフルアー(FLR)社とのジョイント・ベンチャーによるエンジニアリング部門を抱えています。さらに住宅建設や空港の建設ならびに運営管理を行っています。カルデロン政権はインフラストラクチャー整備を政策の目玉に据えており、向う5年間に2350億ドルにものぼるプロジェクトを計画しています。これはメキシコとしては異例の高水準の公共投資額です。具体的には水力発電所、高速道路、空港などの建設がそれです。このため同社のバックログ(受注残)は過去最高の水準に達しています。 歴史的にイカは建設やエンジニアリングに特化していたのですが、最近では有料道路や空港のコンセッション(運営管理)のビジネスに力を入れています。これは安定的な通行料金や空港使用料の収入の割合が増えることで、これまでの同社の業績の特徴であった好況・不況時の売上高激増・激減をある程度、均す効果をもたらすと期待されます。反面、自社のバランスシートを積極的に活用したこれらのコンセッション事業は資本市場の環境が急変した場合、思わぬ資金繰りリスクを招くことになりかねません。 同社の負債は外貨建てが30%です。一方、同社の収入は外貨建てが33%であり、収入の通貨と負債の通貨のマッチングはきちんと出来ています。■ホーメックス(HXM) ホーメックスは1989年に創業されたメキシコ最大の宅建業者です。同社は廉価な一戸建て住宅を専門としています。米国屈指の不動産投資家、サム・ゼルが出資していることから米国の投資家にも知られています。メキシコの人口のうち6割は30歳以下であり今後住宅を購入する必要のある国民は多いです。また現在、メキシコでは年間約65万世帯の住宅が新規に必要になると試算されています。メキシコでは近年の金利の低下で住宅ローンを組める消費者の数が激増しました。これを反映して住宅ローン承認件数も順調に伸びています。 メキシコの住宅ローン市場はアメリカのように証券化に依存していませんのでサブプライム問題に絡む証券化市場の機能不全の悪影響は軽微です。カルデロン政権は国民の持ち家促進を政策の柱にしており、同政権の打ち出した持ち家奨励プランで新たに100万世帯が住宅取得可能になると試算されています。ホーメックスはローン審査がおりて、手付金を払った住宅購入希望者からの注文だけに応じて建設を始めるという極めて保守的な方針を堅持しています。また、建設手順の標準化、規格化を通じて低コスト化、建設作業の効率化を徹底的に追求しています。今年の売上成長ガイダンスは+16~18%、EBITDA(利払い、税金、償却前利益)マージンのガイダンスは24~25%です。 ■メキシコの空港管理会社株 メキシコのADRとしてギャップ(PAC)、アスール(ASR)、オーマ(OMAB)という3つの空港管理会社の株式がアメリカの株式市場に上場されています。このうちギャップはグアダラハラ、プエルト・バジャルタ、ティファナ、ロス・カボスを中心とした太平洋側の空港のコンセッションを所有しています。年間の利用客は約2000万人です。アスールはカンクン、コスメル、オアハカなどのメキシコ湾沿岸の空港のコンセッションを所有しており、年間の利用客は約1400万人です。オーマはモンタレー、アカプルコなどのコンセッションを所有しており、年間1200万人の利用者があります。メキシコの旅客数は年間13%程度で成長しています。成長の原動力になっているのは安売り航空会社の進出です。但し旅客数の伸びは景気に比較的敏感であるため、このところの米国経済の減速には十分気をつける必要があると思われます。またジェット燃料の高騰で航空会社の運航費用が高騰していることも懸念材料のひとつです。メキシコの空港管理会社を巡る中期での材料としてはメキシコ・シティーに第二の国際空港が近く建設される可能性が高い点です。このコンセッションが近く入札にかけられるという憶測もあり、これが具体化すれば各空港管理会社も積極的に応札するものと思われます。
2008年02月04日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 日経平均株価、先物上昇、サイバー株…
- (2025-11-21 00:00:02)
-
-
-

- 楽天市場
- 【楽天ランキング1位】【送料無料】…
- (2025-11-21 00:05:45)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-







