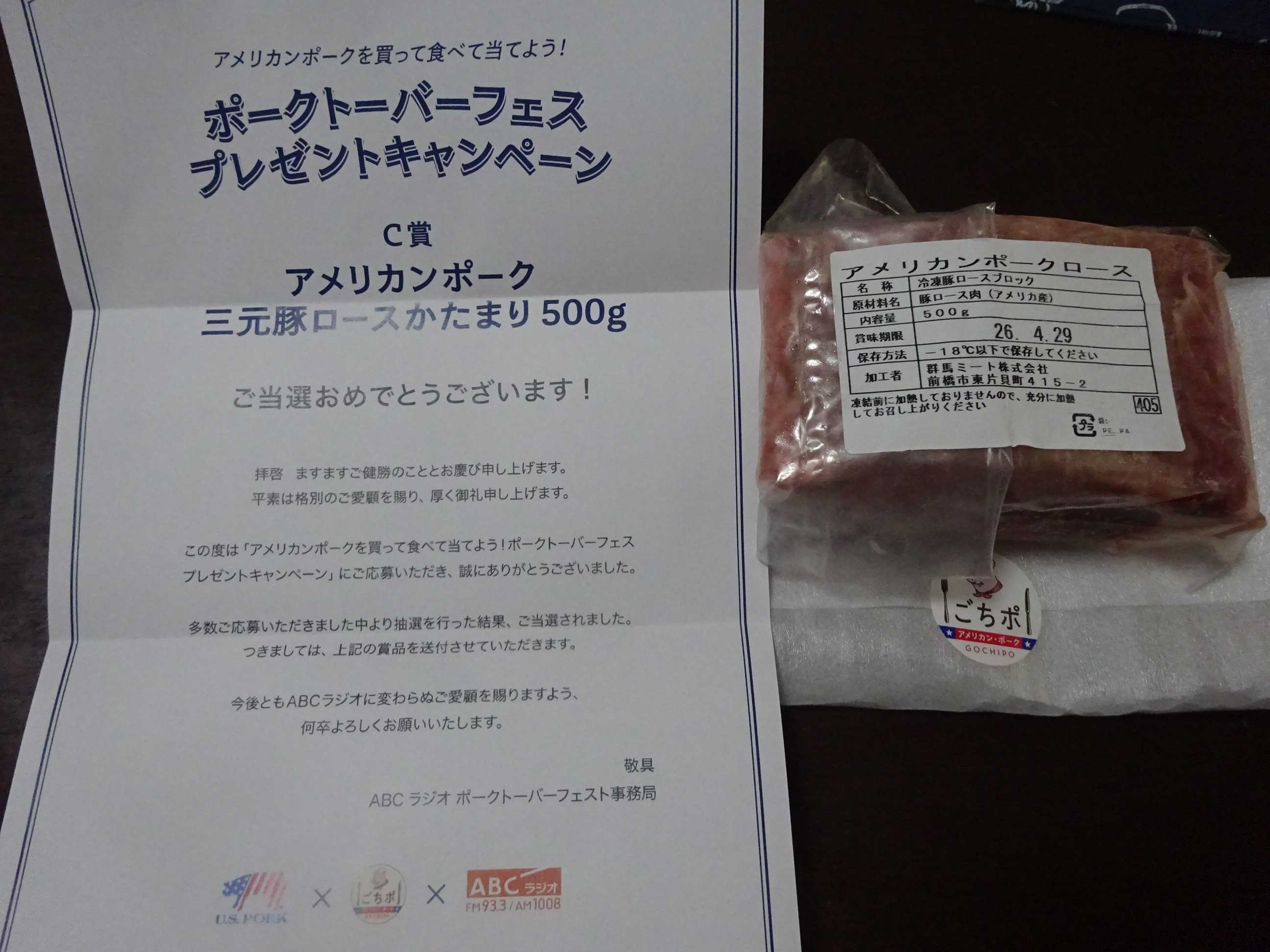2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年06月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
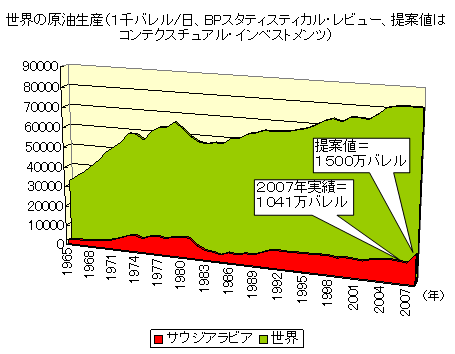
第132回 サウジアラビアの増産について
今日のまとめ 1. サウジは1500万バレル/日までの増産の可能性を示唆 2. 需給統計は石油価格を占う上で限界がある 3. 中国、インドの現在の消費量との比較ではインパクトがある数字と言える ■原油価格抑制に向けたジッダ会議 高騰を続ける原油価格を抑えることを目的にサウジアラビアのジッダに産油国ならびに消費国の閣僚が集合し対策会議が開かれました。その結果サウジは7月中にも20万バレル/日の増産に踏み切り、生産能力を970万バレル/日に引き上げるとともに2009年までにはこれを1250万バレル/日、そして必要であれば(実現の可能性はともかく)1500万バレル/日まで生産を拡大すると公約しました。今日はこの増産が世界の原油の需給関係の中でどういうインパクトを持つのかについて考えてみたいと思います。まず世界の原油生産高とサウジアラビアの原油生産高を、つい先週刊行されたばかりの2008年度版『BPスタティスティカル・レビュー』を元にグラフ化してみました。 なお、サウジアラビアの政府は現在の生産能力を950万バレル/日としているのですが、BPの統計では既にサウジアラビアは1000万バレルを生産しており、統計に齟齬があります。こうした食い違いはめずらしいことではありません。2007年の生産実績である1041万バレル/日で計算するとサウジアラビアが世界の原油生産に占める比率は12.6%になります。サウジアラビアが生産高を1500万バレルに引き上げたとすると増産分は550万バレル/ 日になりますが、それをBPによる世界の現在の石油生産高(8153万バレル/日)に加算し、世界合計を8703万バレル/日とした上で増産分の世界合計に占める割合を計算すると6.3%ということになります。 ■生産と消費 BPの統計では過去の世界の原油生産と消費の数字は必ずしも一致していません。下のグラフを見ると1980年頃からは消費の数字の方が常に多くなっていることがわかります。それ以前は生産の方が消費を上回っていました。 この食い違いの部分だけをグラフ化したものが下のチャートです。これで見ると原油価格が急騰した1970年代を通じて石油生産は消費を上回っていたことが判りますし、原油価格が長期に渡って低迷した90年代にはずっと生産が消費を下回っていたことになります。つまりこのデータ・ポイントからだけで原油価格を予想しようとするのはムリがあるわけです。 ■大口需要国の需要規模との比較次に今回サウジアラビアが公約している550万バレル/日の増産がどの程度の規模なのかを中国やインドの原油消費量と比較してみます。BPによると2007年の中国の原油消費量は786万バレル/日、インドは275万バレル/日でした。すると今回の増産公約はこれらの国の消費量を合計したものの約50%に相当するわけです。
2008年06月23日
-
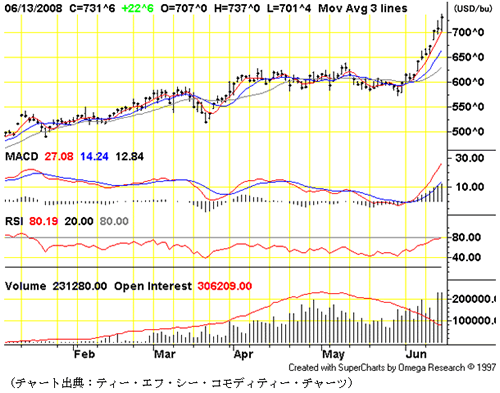
第131回 米国中西部の豪雨と穀物市場への影響
今日のまとめ 1. 米国中西部の豪雨は記録的な水準である 2. トウモロコシ、大豆の不作が予想される 3. 飼料の高騰は食肉業者のマージンを圧迫する 4. エタノール業者にとってもコスト増は悪材料 ■米国中西部の豪雨 このところ米国の穀倉地帯である中西部では記録的な豪雨が続いています。過去1ヵ月の降雨量は平年の4倍にものぼり、1993年の記録的な豪雨以来の悪天候です。影響を受けている地域はアイオワ、イリノイ、ウィスコンシン、ミズーリ州などです。 ■一過性? 一般論として株式市場の投資家は自然災害のもたらす短期的な市場価格の変動に対してはあまり直情的に動かない方が得策です。今回の災害に関しても性急な動きは控えた方が良いでしょう。それを断った上で今回の災害がマーケットに与える影響について考えてみたいと思います。まずトウモロコシは今が蒔いた種がちょうど芽を出す大事な時期です。この時期に土壌の水分が多すぎると根がしっかり張らず、収穫量が減ります。その意味ではこの時期の豪雨は今年の収穫に対しては「取り返しのつかない」ダメージを既に与えてしまったと言えます。これを受けて米国農務省は先週、今年のトウモロコシの収穫予想をこれまでの121.3億ブッシェルから117.4億ブッシェルへ下方修正しました。117,4億ブッシェルというのは去年の収穫実績より10%ほど少ないです。一方、大豆ですが、こちらは降雨で地中の窒素が流されてしまった可能性があります。窒素は作物の育成促進に必要ですので窒素肥料の需要は増えることが予想されます。 ■市場への影響 既にトウモロコシや大豆の価格は急騰しています。トウモロコシ(シカゴ・ボード・オブ・トレード、フロアー・セッション)大豆(シカゴ・ボード・オブ・トレード、フロアー・セッション) これらの作物は家畜の飼料としても重要ですので養豚や養鶏のコストが上昇することが考えられます。既に格付け機関ムーディーズは養豚業者、スミスフィールズ・フーズ(ティッカー:SFD)の見通しを引き下げるかもしれないと発表しています。また養鶏業者、ピルグリムズ・プライド(ティッカー: PPC)の株価は6月に入ってから29%も下落しました。 一方、トウモロコシを原料としているエタノール業者の株価も売り叩かれています。ヴェラサン(ティッカー:VSE)の株価は今月に入って28%下落しました。またアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ティッカー:ADM)は豪雨の影響により物流面でかなり悪影響が出ていると発表しています。トウモロコシを原料としてコーン・シロップを作っているコーン・プロダクツ(ティッカー:CPO)の株価も下がっています。 ■風が吹けば桶屋が儲かる? 一方、米国中西部の天候不順が有利に働く企業も当然あります。窒素肥料を作っているテラ・インダストリーズ(ティッカー:TRA)はその一例です。また飼料の高騰でチキンの値段が上がれば今回影響を受けなかったブラジルの養鶏業者、サディア(ティッカー:SDA)ならびにペルディゴン(ティッカー: PDA)にとっては輸出市場での競争力が増す事を意味します。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドと似た業態の穀物メジャーであるブンゲ(ティッカー: BG)はブラジルに生産の重点をシフトしていたのでADMほど影響を受けていません。ブンゲ(BG:黒)とアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM:茶色)の株価
2008年06月16日
-
第130回 グローバル経済のアンバランスと通貨危機の可能性について
今日のまとめ 1. ベトナム市場は変調をきたしている 2. これはベトナムだけの問題ではなく、グローバルな問題だ 3. 輸入が突然止まる危険がある 4. インフレ退治が待ったなしになる 5. ホットマネーが向かっている投資先は避ける 6. ドル高のシナリオも想定に入れておくこと ■新しい頭痛の種 サブプライム問題は喉元を過ぎた感じで、ゆっくり時間をかけながら傷を癒す段階に入っています。しかし世界の資本市場にとって新しい頭痛の種が生じました。それはベトナムの通貨市場が不穏な動きになっているという事です。先週、ベトナム・ドンの自由市場のレートが17700あたりまで急激にドン安に振れました。公式レートは16060です。これを受けてベトナム政府は一日の為替の値幅制限を一気にこれまでの2倍の2%に拡大しました。ベトナムの通貨市場の変調は未だ先週はじまったばかりですから、これが大きな混乱につながるかどうかは未だ判然としません。しかしこの問題は注意深く観察する必要があります。 ■グローバル経済のアンバランスこそが発端 ベトナム市場の変調はともすれば「あれはベトナム固有の問題だ」ないしは「こんな事になったのは全てベトナムの政府や金融当局に責任がある」という風に考えられがちです。でもその認識は間違っています。なぜならベトナムの通貨の健全性が損なわれた背景にはグローバル経済のアンバランス(英語ではアンバランスとは言わず、Macroeconomic imbalancesという言い方をします)という問題が存在するからです。それではグローバル経済のアンバランスとは一体何を指しているのでしょうか?。私の定義ではそれはBRICsに代表されるこんにちのグローバル経済の「勝ち組」と、低成長に苦しむ先進国という「負け組み」の色分けが余りに明快に出来上がってしまって、「勝ち組」の方に世界の投機資金が集まる現象を指します。世界から投資資金が集まると自ずとその国の経済は「金余り」の様相を呈してきますし、それが不動産価格や株価の上昇という形で一層それらの国々に住む人々の金回りを良くし、それが経済成長を一段と後押しするという好循環を生むわけです。この好循環自体は悪いことではないと思いますが、バランスを取りながら手堅く成長する途を選ばず、横着をすると、とんでもない失敗をする危険もどんどん増すのです。 ■イージー・マネー(あぶく銭)の落とし穴 それでは具体的にどんな落とし穴があるのでしょうか?。先ず自国通貨のオーバー・バリュエーション(過大評価)という問題があります。海外から投機資金がどんどん入ってくるとその国の通貨が押し上げられます。自国通貨が余り強くなり過ぎると、輸出競争力は段々衰えます。これは通常、貿易収支の数字に顕れるわけですが、それに国際間の資金の移動を加味した数字である経常収支の数字は往々にして海外からの投機資金の流入に助けられて輸出競争力が劣化した後も黒字が続く場合が多いです。これを放置すると或る日突然海外の投資家が「この国の輸出競争力は衰えているぞ」という事に気付くと、急いで投資資金を引いてしまいますから、突然、経常収支も悪化するわけです。経常収支が悪化しはじめると国内に滞留したガイジンの投資資金が出てゆく際、換金に応じる毎に外貨準備が費消されるというパターンになるわけです。外貨準備が底をついてしまえば、換金に応じられなくなるわけですから、海外の投資家は先を争うように出口に殺到するという事が起こるわけです。 ■輸入にブレーキがかかるとき 経常赤字が急速に拡大しはじめると、それをすばやく食い止めるのに効果的な方法はひとつしかありません。それは「輸出が振るわないのなら、輸入も絞り込むしかない」ということです。大体、ホットマネーがどんどん飛び込んでくるような国は国内消費の需要も旺盛である場合が殆どです。輸入は国内消費と直結していますから、輸入を押さえ込むには消費を或る程度、殺さないといけなくなるわけです。これには国内の信用成長を抑制したり金利を引き上げるという方法が用いられます。 ■インフレ イージー・マネーのいまひとつの落とし穴はインフレです。海外からの投機資金の流入は国内の資産価格のインフレを招きます。若し、銀行がこのブームに乗ってガードを緩めて杜撰な与信審査でどんどん融資を拡大すれば、政策金利が引き上げられた際に思わぬ不良債権を大量に抱え込むはめに陥るでしょう。また生活必需品や食品のインフレが発生した場合は所得水準の比較的低い国ほどすぐに政情不安やストライキなどに発展します。 ■コンテージョン(伝染) さて、通貨危機が怖い本当の理由は問題が起きてしまった当該国に投資している人だけが損害を蒙るのではなく、多くの場合、比較的健全な国にすら様々な惨禍の火の粉が降りかかるところにあります。例えば上の説明で通貨危機に見舞われた国が「輸入を絞り込むしかない」という判断に達したとします。するとその国と沢山商売している相手国も突然、輸出不振に陥ることは想像に難くないと思います。ここ数年はイントラ・アジア、つまりアジア域内貿易がとても盛んでした。ベトナムもそのメンバーのひとりとしてこのブームに組み込まれていたわけですから、若しベトナムがアジア域内貿易のブームから脱落するようだとベトナムとの貿易相手国も景気が悪くなるわけです。 ■関係ない国までもが巻き添えを食う? しかしもっと怖いのは一見、通貨危機に見舞われた国とは貿易上のつながりが薄く、経済のファンダメンタルズもぜんぜん違う国ですら、とばっちりを受ける可能性があるという事です。例えばタイランドのバーツ危機に端を発したアジア通貨危機ではインドネシアや香港など、タイランドとは殆ど貿易をしていない国までもが巻き添えになりエコノミストを驚かせました。また、経済のファンダメンタルズで言えばシンガポールや香港や韓国のように比較的国民所得の高い国もフィリピンのような比較的所得の低い国と分け隔てなく投機筋の売り崩しのターゲットにされました。 農業主体の国であろうが、工業国であろうが関係なかったこと、タイランドと商売していようと、していまいと関係なかったこと、リッチな国であろうと、貧しい国であろうと関係なかったこと、、、これらの事実を目の当たりにして当時の国際金融の関係者やエコノミストはコンテージョンの気まぐれさに頭を抱えてしまったのです。 ■今後のシナリオを模索する それでは若しベトナムの問題が深刻化した場合(未だそうと決まったわけではありません。でも細心の注意が必要だと思います)、グローバル・エコノミーのシナリオにどういう影響が出るのでしょうか?。この問題はとても複雑ですから、私にも結論は出ていません。でも思いつくままにチェックすべき項目を列挙すると: ◆ ホットマネーが介入している国や資産(たとえば石油)は資金が突然引くかもしれないので注意を要する ◆ 工業セクターや海運セクターはスローダウンするかもしれない ◆ アジア通貨危機の局面ではドルは基本的には強かったので、今回もこれがドル高要因にならないか注意する必要がある などになると思います。
2008年06月02日
全3件 (3件中 1-3件目)
1