2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年04月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
第126回 インド株式市場の投資チャンスについて(その3)
今日のまとめ 1. 銀行株の調整はきつかったが内容は決して悪くない 2. ITアウトソーシングの決算はまちまちと言ったところ 3. 長期でみた同セクターの成長率の鈍化は顕著 ■銀行株 最近、インフレ懸念が高まっていることからインド準備銀行は先週キャッシュ・リザーブ・レシオ(CRR)を0.5%引き上げ8%とすると発表しました。インドの株式市場、とりわけ銀行株は今回の引き締めを予期していたのでこのニュースは株価に織り込み済みだと思います。 インドの銀行株は1月の高値からHDFC銀行(ティッカー:HDB)の場合で23%、ICICI銀行(ティッカー:IBN)の場合で39%の調整となっています。これは(1)ICICI銀行がサブプライム絡みの市場の混乱で債券ならびデリバティブ部門が含み損を抱えていると公表したこと、(2)貸付の焦げ付きの増加するのではないかという懸念、(3)融資成長率が鈍化していること、などが原因とされています。 まずICICI銀行の含み損に関してですが同行は直接サブプライム・ローンに関連する投資対象には投資していません。含み損はあくまでも市場全般の混乱が原因です。また含み損の金額は同行の規模から考えれば取るに足らない額です。 貸付の焦げ付きに関してはICICI銀行の場合、融資全体に占めるノン・パフォーミング・ローン(NPL)の比率は3%程度であり、これは去年までの数字より大幅に改善しています。さらに焦げ付きに対する引当金に関しても以前は引き当てが不十分だったのですが最近ではだいぶ改善してきています。 資産内容が良いことで知られているHDFC銀行に関しては融資全体に占めるノン・パフォーミング・ローン(NPL)比率は1.5%に過ぎず、引当金のカバレッジも120%と十分です。 次に融資成長率に関しては去年までの融資成長率が余りに高すぎたのでむしろ今の成長率(ICICI銀行の場合は約20%、HDFC銀行の場合は約25%)の方が安心して見ていられる無理の無い成長率だという気がします。 インドの銀行セクターはインド株式市場のいろいろなセクターの中でとりわけ業績成長率が安定的に推移しています。大体、年率18~20%程度の成長をコンスタントに出せています。このペースは今後も当分変わらないでしょう。 ■ITアウトソーシング ITアウトソーシングのセクターは主要銘柄の決算が続々出ているところです。全体の印象としては、まちまちと言ったところだと思います。ただ一部の投資家が懸念していたように「2008年はサブプライム問題の影響を受けてひどい年になる」という懸念はどうやら杞憂に終わったと言えるでしょう。そこで各社の内容を見ると: ■インフォシス(ティッカー:INFY) 3月期決算は売上高、EPSともにコンセンサスと同じでした。しかし来期、ならびに今年通年のガイダンスはコンセンサスより少し低くなっています。因みに今年(FY09年)の売上高ガイダンスは49.7~50.5億ドル(約20.2%成長)、EPSガイダンスは$2.31~$2.35です。同社の場合、売上高の約3分の1を銀行などの金融サービス業の顧客に依存しており、サブプライム問題の影響をとりわけ受けやすいと懸念されていました。しかしこのセクターからは今のところキャンセルは1件もありません。顧客のうち上位100社に対して行ったアンケートでは76%から回答が寄せられていますが回答のあった全ての顧客が今年の予算を現状維持か、ないしは拡大しています。しかし回答の無い、今年の予算の策定が遅れている顧客に関しては不確実性を残しているとも言えるでしょう。営業戦略としては顧客の所在する国(例えば米国や欧州)での役務比率をなるべく下げ、その分、コストの安いインドでの役務比率を上昇することによって顧客が倹約できるように提案してゆきたいとしています。この場合、インフォシスにとってはインドでの役務比率が高まると見かけ上売上成長にマイナス要因になります。しかし、逆にマージンという点ではインドにおける役務提供の方がマージンは高いです。従って均してみるとこういう提案をすることは同社の不利益にならないとしています。 ■ウィプロ(ティッカー:WIT) 3月期決算は売上高、EPSともにコンセンサスと同じでした。ウィプロのIT部門のFY08年通年の売上成長率実績は+18.3%でした。これは他社に比べて低い成長率です。6月期の売上高ガイダンスは買収で新しく加わった部分を除くと前年同期比で+26%成長を見込んでいます。また今年後半にかけてだんだん売上成長が良くなる、所謂、バックエンド・ローデッド型の業績推移を同社は想定しています。なおインフォシスに比べるとウィプロのガイダンスは信頼度が低いと一般に投資家は考えているようです。 ■サティヤム(ティッカー:SAY) 3月期決算は売上高、EPSともに市場予想を若干下回りました。3月期の売上高成長率は+18.5%とこのところ好調な同社としては意外に伸び悩みました。同社の今年(FY09年)の売上高ガイダンスは+24~26%成長です。6月期の売上成長率は控えめなガイダンスです。それでも6月期の落ち込みはライバルのインフォシスやウィプロよりは軽微です。また他社同様、年後半にかけてだんだん売上高のモメンタムは強まると見ています。 先進国の景気後退という目下の懸念事項をひとまず棚上げしておいて、一歩さがって巨視的にインドのITアウトソーシングの業界全体の成長率を見た場合、やはり2年前くらいまでは楽々年率30~40%近い成長が出せていたのに、最近では上に見たようにそれが20%台に下がってきているのはまぎれもない事実です。勿論、株価の方もそれに呼応する形でこのところずっとダラダラ安が続いています。つまり期待も株価水準も両方ともリーズナブルな水準と考えられ、ホームランをかっ飛ばすというよりはシングル・ヒット狙いのような投資スタンスになるかと思います。
2008年04月23日
-
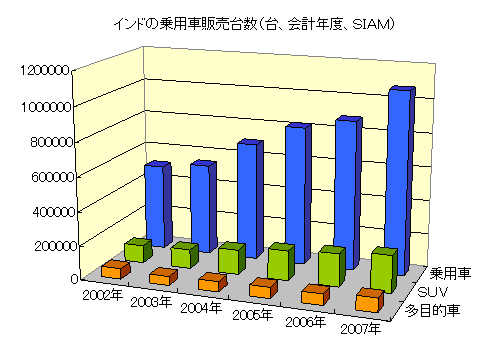
第125回 インド株式市場の投資チャンスについて(その2)
今日のまとめ 1. インドの自動車株は成長の盛りにある 2. 販売台数は金利に敏感 3. タタ・モータースの『NANO』が話題に 4. ジャガー・ランドローバーはタタ・グループの買収戦略を踏襲 ■自動車業界 インドの自動車業界は急成長の過程にあります。 単純に台数ベースで言うとオートバイが多いのですが、カテゴリーとして重要なのは乗用車と軽商用車ならびに中・大型商用車だと思います。乗用車のマーケット・シェア・リーダーはマルチで市場占有率は54.6%です。第2位は現代自動車で16.8%のシェアです。第3位はタタ・モータース(ティッカー:TTM)でシェアは15.4%です。乗用車市場はこの3社の寡占となっており他のメーカーは余り重要ではありません。また上位3社のマーケット・シェアは比較的安定的に推移しています。軽商用車の市場はタタ・モータースが強く、65.4%のマーケット・シェアを誇っています。第2位はマヒンドラ&マヒンドラで24.3%の占有率です。中・大型商用車の市場ではテルコ(市場占有率62.8%)とアショク・レイランド(同27.9%)が圧倒的に強いです。 ■インドの自動車市場の特徴 インドの自動車市場を中国のそれと比べた印象としては、中国の場合、実力の拮抗した中途半端な規模のメーカーが乱立し、激しくシェア争いを演じているのに対してインドの市場はメーカーの数が限られている上、先行企業がしっかり基盤を固めてしまっているため、余り劇的な序列の変化は無いということが挙げられます。自動車産業が典型的なスケール・メリットの働くビジネスであることを考えると中国よりインドの競合状況の方が好ましいという風にも言えます。 ■金利と自動車販売高の関係 一方、インドと中国の自動車業界に共通する点というのもあります。その最たるものは需要が金利に極めて敏感であるという点です。下のグラフは各車種別の販売台数成長率の推移を示したものですが、政策金利の上がり始めた2006年に中・大型商用車、乗用車、SUV(スポーツ多目的車)などの高額な車種を中心に販売台数成長率が落ち込んだことがわかります。 現在のインドの金利を見るとプライム・レートは13%です。インフレ・プレッシャーは未だ残っているのですが、暫くはこの金利水準が維持されると予想されます。インド経済がソフトランディングして金利が下落基調に転ずるとオート・ローンが組みやすくなるという思惑から自動車株が人気になると考えられます。 ■超低価格車 乗用車のカテゴリーで話題になったのはタタ・モータースが発表した『NANO』だと思います。『NANO』は10万ルピー(約27万円)という超低価格で、新しいマーケット・セグメントを創出しようという試みです。この超低価格車のコンセプトには他社も対抗する商品を企画しはじめており、いずれ新しいカテゴリーとして定着すると思われます。 ■タタ・モータースのジャガー・ランドローバー買収 タタ・モータースはフォードの傘下にあった英国の名門ブランド、ジャガーならびにランドローバーを23億ドルで買収しました。この買収に関しては「安物のクルマを作っているインドのメーカーがジャガーのような高級ブランドを買収してもイメージを損ねるだけだ」という風に批判的な声が強いです。しかし我々投資家が先ず理解しなければならない点はインドの経営者、とりわけタタ財閥は財務のソロバンの立つ担当者がこの買収を仕掛けているという点だと思います。実際、タタ・グループ企業が過去に行った大型買収としてはタタ・コミュニケーションズ(旧ヴィデッシュ・サンチャ・二ガム)のタイコム(もともとはAT&Tの海底ケーブル事業)買収やタタ・スチールのコーラス(旧ブリティッシュ・スチール)などがあり、いずれの場合も世界的なブルーチップ企業を極めて有利なバーゲン価格で買収しています。つまり純投資として考えた場合でも十分採算に見合う案件にしか手を出していないのです。実際、ジャガー・ランドローバーの場合、フォードの傘下にあった間にフォードは通算で100億ドルに近い設備投資をこの部門に投下しています。 ■買収のタイミングに関する考察 もうひとつの特筆すべき点は今回の買収がジャガーの新製品サイクルとちょうどタイミング的に合致している点だと思います。『ジャガーXF』という新しいモデルはちょうどショールームに並び始めたタイミングです。フォードは既にリストラにより2004年から2006年にかけてフォード・ランドローバーの従業員の17%を削減済みであり、この面でもタタ・モータースがやらなければいけない仕事は限られていると思います。買収時期に関しての投資家の懸念としてはこれから先進国経済が景気後退局面に入っていく過程にあり、高級車の売り上げは景気敏感なので業績悪化が心配されるという点が挙げられます。 ■その他の懸念材料 またジャガー・ランドローバー部門がタタ・モータースの全社売り上げの5割にも上る計算になるので純粋なインド株としての性格が失われると見る投資家もいます。加えてタタ・モータースの乗用車部門の主力ブランドである『インディカ』は登場以来10年を数える古い商品ラインであり、フルモデルチェンジが必要です。その設備投資費用をどう捻出するのかが懸念されています。
2008年04月09日
-
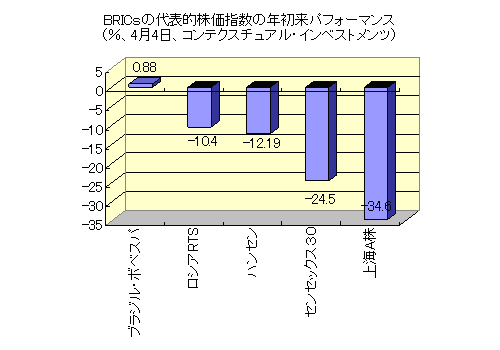
第124回 インド株式市場の投資チャンスについて(その1)
今日のまとめ 1. 年初来のインド株式市場の調整幅はBRICsの中で特に大きい 2. 本年度予算に対する失望も売られた一因 3. ウンター・パーティー・リスクの見地からPノーツの人気は一巡 4. 経済はちょうどいい湯加減になっている 5. プレミアム縮小でADRの妙味は増している ■調整局面のインド株 インド株が最近冴えません。BSEセンセックス30指数は年初来-24.5%の調整となっており、我々日本人投資家が投資しにくい中国本土のA株指数を除けばBRICs4カ国の中で最悪のパフォーマンスとなっています。 そこで今日はインド株の内容が本当にそんなに悪いのか検証してみたいと思います。 ■ユニオン・バジェット(本年度予算)に対する失望 2月29日にユニオン・バジェット(本年度予算)が発表されましたが、その内容は株式市場の投資家に冷淡な内容でした。今年の予算のハイライトは: 1. 零細農家に対する借金(去年3月までに貸し出され去年年末に期限が来た分)の減免 2. 道路建設などのインフラ投資の推進 3. 乗用車・二輪車の消費税の減額(16%から12%へ) 4. 短期キャピタル・ゲイン税率を10%から15%へ引き上げ 5. デリバティブ商品への課税強化などです。このうち零細農家の借金を棒引きにする案に関しては借金が帳消しにされることは明確に示されているのですが、それでは損を蒙る銀行へはどういう風に補償するのか?という点が不明瞭でした。最近、銀行株が嫌気されている原因のひとつはここにあります。また、株式市場という見地からは短期キャピタル・ゲインの増税はマイナス要因でした。さらにデリバティブ商品への課税強化も投資家は嫌気しました。その理由はインド議会が所謂、Pノーツによる外人投資家のインド株購入を制限する立法を提出する可能性があるからです。 ■Pノーツ問題のその後 このPノーツとはパーティシパトリー・ノーツの略でデリバティブの一種です。インドでは外人投資家はちゃんと政府から免許を受けないと直接インド株を買うことは出来ません。でもちゃんと政府の指示通りインド投資専門の法人をモーリシャスなどに設置し、登記するだけで多額の弁護士費用がかかります。そこでヘッジファンドなどの投資家はPノーツによる代理投資で済ませてしまうという方法をしばしば用いて来ました。 証券会社はインドで投資できる免許を持っているし、国内の投資家とのつながりもあります。そういう経路から株式を調達してきて自分で保有します。そして外人投資家にはPノーツを発行するのです。Pノーツは「この契約はアナタのために株券をうちの証券会社が一時預かっていることを証するものである。うちで預かっているアナタの株が値上がりしたら、値上がり益はアナタのもの。値下がりしたら、損はアナタが被ること」という確認書です。証券会社がなぜこのビジネスをやるか?というとそれは手数料を沢山取れるからです。 こうした商品がどういう弊害をもたらすかですが、先ず外人の投資を制限する法律がザル法になってしまいます。さらに流入する流動性の把握が困難になります。一説には現在の外人投資家のインド株購入の約半分がこうしたPノーツによる購入であるとも言われています。 Pノーツ規制が去年最初に話題になった際、株式市場は急落しました。そこで即時禁止にするとインパクトが大き過ぎるということで、とりあえず新規のPノーツの組成は禁止され、既に流通しているものに関しては来年の4月をメドにゆっくり終わらせてゆく方向にあります。しかしそうした政府からの規制を待たずPノーツは最近、自然に下火になりつつあるのではないでしょうか?その理由は、米国の証券会社がサブプライム問題で大きな損を出すなど、カウンター・パーティー・リスク(=商売をする相手を選ぶ際、相手が信用に足るかどうかのリスク)への関心が高まっているからです。 ■GDP成長率は若干下方修正 次に実態経済がどうなっているかについて見てみます。インドの2007年12月期の実質GDP成長率は8.4%でした。2008年3月に年度末を迎える2008会計年度の通年の実質GDP成長率は8.6%程度に落ち着くものと見られます。さらに来年3月に締切られる2009会計年度の実質GDP成長率の予想数字は8.2%程度と予想されます。確かに数字は少し下がったのですけど昔のインドに比べれば景気の振幅はかなりマイルドになるものと予想されます。この理由はインドの経済規模自体が大きくなったのでそれだけ安定感が増したことに加えてインド準備銀行の機先を制する経済政策がソフトランディングの可能性を高めたことによります。 ■建設・製造業の動向 建設と製造業は既に去年の秋からスローダウンしています。12月期の実質設備投資成長率は前年比+15.7%でした。これは9月期の+17.4%より若干減速しています。中でもインフラストラクチャー向け投資の減速が目を引きます。インドの設備投資は民間企業による投資が中心で、その点、企業の資本調達コストは相変わらず比較的低いし、企業のキャッシュフローも潤沢ですから今後は設備投資の数字は余り下がらないと思います。従ってこの15%前後の成長率というのは今後も維持できると思います。一方、一月の工業生産は+5.3%とスローダウンしています。これは最近の過去のレンジの下限あたりです。この数字も、もう今の水準より余り下がらないと思います。 ■サービス・個人消費の動向サービス業は比較的安定的に推移しています。一方個人消費も12月期で前年比+7.2%と極めて安定的に推移しています。インドの個人消費は余り金利には敏感ではありません。これは銀行サービスの経済への浸透度が低いからです。消費者信用成長率(住宅ローン+個人向け融資)は去年の年末の時点で大体+20%程度の成長率に下がっています。これは2006年の40%近い成長率からかなりスローダウンしています。逆の見方をすれば2年前の成長率が少し高すぎたと思うのです。むしろこのくらいの数字の方が好ましいと思います。 ■信用・物価の動向マネー・サプライ(M3)は+24%と最近では最も急成長しています。これは少し高すぎる気がします。インドの3月22日の週の卸売物価指数は7%でした。これは2004年12月4日の週の7.07%以来の高い数字です。ただ、まだ過去のレンジの範囲内に収まっているという意味では異常な水準とは言えません。インド政府は物価の高騰を押さえ込む為に食物油の輸入関税を撤廃したり、お米の輸出を禁止したりしています。 ■金利政策インドは2004年からリバース・レポ・レートを引き上げ始め、2007年上半期までには一連の金利引き上げを完了しました。今はその利上げが経済を冷やすのをじっと待つ展開です。既に消費者物価には若干の沈静化が見られていますから最近の卸売物価指数の急伸でもそれほど慌てる必要は無いと思います。 ■貿易収支・為替の動向原油価格の高騰は輸入原油の代金の膨張を招き、これが貿易収支を悪化させていますけど、原油を除くとその他の貿易収支は極めて安定しています。また最近ルピーがドルに対して若干弱含むなど、為替の面でも良い展開になっています。 ■マクロ経済は悪くないこれらの点をまとめてみるとインドの経済は確かに減速しているけれども、それはむしろ今までが過熱し過ぎていたわけで、このくらいの成長が実は一番湯加減が良いと言えると思います。確かに来年(2009年3月に締切る会計年度)のGDP成長率の予想は0.2%程度下がってはいますけれど、それでも8.2%という成長率は素晴らしい数字だと思います。私の考えではBRICsの4カ国の中でインドが最初に経済のソフトランディング(軟着陸)に成功する国になると思うのです。 ■ADRは随分安くなりましたさて、一昔前のインドのADRは恒常的に本国市場の株価に対してプレミアムで取引されていました。2000年から2005年までのADRのプレミアムは単純平均で17%程度でした。それが最近では単純平均で4%を切る水準になっており、かなりプレミアムが剥げました。
2008年04月07日
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 「”決断”の差は”責任”の差」
- (2025-11-20 21:40:08)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 11/20 20時〜数量限定‼️もち吉『ブラ…
- (2025-11-20 21:59:07)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-







