2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年05月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
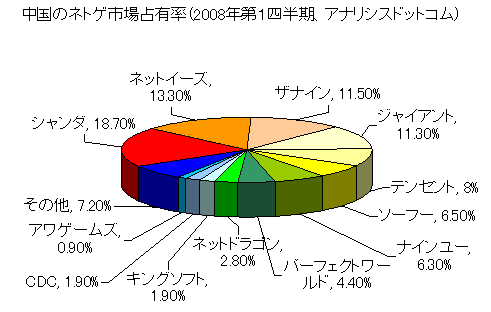
第129回 中国のオンライン・ゲーム市場の近況
今日のまとめ 1. オンライン・ゲーム市場の第1四半期は好調だった 2. オンライン・ゲーム株は依然低い株価評価に甘んじている 3. 収益見通しの安定につながる様々な変化があった 4. セクター全体の株価評価の底上げも期待できる 中国のオンライン・ゲーム市場は関係者の予想よりもかなり早いペースで急成長しています。市場調査会社、アナリシス・インターナショナルによると2008年の第1四半期の中国のオンライン・ゲーム市場は去年の第4四半期から14%も成長し、5.7億ドルの売上があったそうです。第1四半期の各社の市場占有率は下のグラフのようになっています。 今年のオンライン・ゲーム市場の成長率は約37%と予想されています。これはポータルのブランド広告市場の成長率である約40%にほぼ匹敵します。もちろん、中国のネット関連ビジネスにはサーチエンジン(100%成長)やB to B(50%成長)など、オンライン・ゲーム市場より急激に伸びているビジネスもあります。でも37%というのはたいへん立派な成長率だと思います。 各社の売上成長率は下のグラフのようになっています。見やすいようにオンライン・ゲーム関連企業はピンク色にしておきました。 次に各社の株価収益率(PER)を示すと下の図のようになります。これを見るとオンライン・ゲームの株は例外なく株価収益率が低いことがわかります。 さらに株価収益率をEPSの成長率で割り算した、所謂、PEG(PE to growth)レシオで見ると下のグラフのようになります。一般に「PEGレシオが1以下であれば割安」という風に解釈されています。 これで見るとシナ(ティッカー:SINA)以下はPEGで1を割っており、割安だということです。とりわけパーフェクト・ワールド(ティッカー: PWRD)、ジャイアント・インタラクティブ(ティッカー:GA)、ザナイン(ティッカー:NCTY)の3社はポータルのブランド広告関連企業やB to B関連銘柄に匹敵する売上高成長率があるにもかかわらず株価的には極めて低い評価に甘んじていることが分かると思います。 このようにオンライン・ゲームの株の評価が低い理由は幾つか挙げられます。先ず同セクターには圧倒的な強さを誇るリーダー企業が存在せず、実力の拮抗した多くの企業が割拠している状況を挙げることができるでしょう。マーケット・シェアも比較的変動しやすく、目が離せません。 次にヒット作に依存する体質であるという先入観がなかなか払拭できない点も重要でしょう。実際、オンライン・ゲームの運営会社が海外で製作された人気ゲームを高いライセンス・フィーを払って購入して中国でサービス開始するというシナリオ下で、若し期待通りにそのタイトルにファンがつかなければ、喩えて言えば売れ残った携帯電話の在庫を評価損で落とすのと同じような感覚でインペアメント・チャージを計上する必要があります。最近の例ではザナインのライセンス導入した『ギルド・ウォーズ』がその憂き目にあいました。 ただ、一時懸念されていたほどヒット・タイトルの寿命は短くなく、或る程度の人気が出たヒット作には2年目、3年目に入っても勢いが衰えないものも少なからずあります。これは拡張パックやキャンペーンなどでファンをつなぎとめるノウハウが向上したことも影響していると思われます。 さらに昔はサブスクリプション方式と言ってユーザーがゲームを楽しむ時間に対して課金する方法が一般的でしたが、最近ではアイテム課金方式も定着してきています。このような課金方式の多様化は運営会社の裁量の余地を拡大し、結果として経営の安定が図りやすくなったと評価できるでしょう。 それから以前はひとつのヒット作に依存していた運営会社の多くが複数のタイトルを展開することができるようになり、「当たり外れ」のリスクが分散されてきたように思います。 冒頭で述べた通り今年の中国のオンライン・ゲーム市場は素晴らしいスタートを切りました。場合によってはアナリストの予想を大幅に超える成長を見る可能性も高いです。直近では四川省の大地震で業界全体として3日間、営業を自粛するという発表があり、オンライン・ゲーム株は押し目を作っています。そういう短期的なネガティブ要因を除けば業界のファンダメンタルズはすこぶる好調と言えるでしょう。もともとキャッシュフローや利幅という面では素晴らしい業界のことですから、今後、セクター全体の株価評価が底上げ(マルチプル・エクスパンション)することも十分考えられます。
2008年05月21日
-
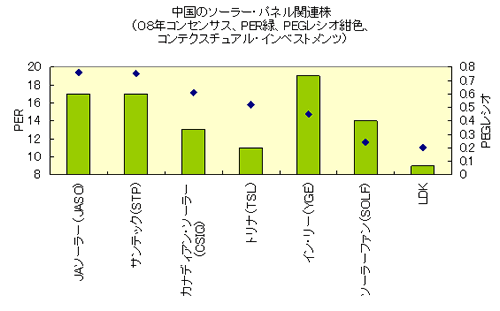
第128回 太陽光発電市場の近況
今日のまとめ 1. 太陽光発電のセクターは一見すると割安のように見える 2. 制度面、景気面でのリスクを忘れてはならない 太陽光発電のセクターは中国株ADRのひとつの投資カテゴリーとしてすっかり定着した観があります。各社とも急激な売上成長の下で順調に業績を伸ばしており、今年の売上目標に関しても強気に見ている企業が殆どです。いま、各社の株価収益率(PER)を見ると下のグラフのようになっており割高感はありません。PERをEPS成長率で割り算した、所謂、PEGレシオで見ると各銘柄とも1以下です。 しかし太陽光発電株の表面的な割安感は同セクターのマクロ・リスクとバランスを取りながら評価されるべきであると思います。 先ず同セクターは偏った需要に成長を依存しています。下のグラフは今年の国別のソーラー・パネルの需要を示しています。ドイツとスペインの2国だけに需要の6割以上が集中していることは健全ではありません。 ドイツやスペインにはフィード・イン・タリフという制度があります。これは昼間ソーラー・パネルから生産される余剰電力を個人が電力会社へ売り戻すことを保証する制度です。この電力会社による強制買取りが個人にとって実質的な補助金となっており、それがソーラー・パネル普及に大きく貢献しました。しかし今後もこのソーラー・パネル設置者を優遇する制度が維持されるかどうかについては若干の不透明感も出ています。 具体的にはドイツでは議会が補助金の見直しに関して討論を始める見通しであり、場合によっては3割近く補助金が削減されるかもしれません。スペインではフィード・イン・タリフの補助金の予算が去年、達成されてしまい、補助制度の延長期間に入っているのですが、今年の秋にそれが見直される見通しです。 そうした制度面での不透明要因に加えて景気要因も見逃せません。スペインは近年、空前の建設ブームによってソーラー・パネルの設置需要も喚起されました。従って住宅建設ブームが終わるとソーラー・パネルの需要にも悪影響が出ると思われます。 ソーラー・パネルのビジネスは上記の要因に加えてシリコンの品不足の問題があります。さらに最終製品価格は未だ他の発電方法より割高であるため、中・長期では更に製品単価が下がることが必要です。このことはマージン縮小圧力が今後も恒常的に存在することを示唆しています。近年のソーラー・ブームで無数の企業が乱立し、それらの大半が特別な差別化戦略も無いままに無秩序な拡張戦略をとっていることも過当競争を招く危険を孕んでいます。
2008年05月19日
-
第127回 中国の娯楽・レジャー産業(その2)
■中国南方航空(ティッカー:ZNH) 同社は機体キャパシティー、旅客数などの指標で見ると中国最大の航空会社です。また安全運行のトラックレコードでも中国で第1位です。同社は広州と北京をハブ空港としています。売上高構成比は国内旅客が74.9%、海外旅客が14.1%、貨物が6.8%、香港・マカオ旅客が2.0%、その他2.2% となっています。 2006年から2007年にかけての旅客運行キロ数(RPK)は17.5%成長し817億RPKに達しています。一方、キャパシティーの指標である座席キロ数(ASK)は同期間に13.1%成長し1097億ASKに達しています。キャパシティーの増加より旅客運行キロ数の伸びの方が高かった為、ロードファクター(稼働率)は2006年の71.7%から2007年は74.5%へと改善しています。さらに顧客単価を加味したイールドで見ると2007年は 0.61人民元/RPKと2006年の0.60人民元/RPKより若干改善しています。 つまり同社は中国の経済成長そのものよりかなり早いペースで業容を拡張しているわけですが、その拡張に合わせて旅客数もきちんと増えており、収益を犠牲にしていないということです。同社の営業費用のうちフライト運行費用は54.9%を占めており、その中でもジェット燃料費は63%を占めて最大の支出項目です。2006年から2007年にかけてのジェット燃料費の増加は13.1%であり、便数の増加などを考えた場合、この増加率は極めて低い気がします。その理由は中国政府がジェット燃料を価格統制している為であり、国際市況の実勢とはかけ離れていると考えられます。ただ今後、原油価格が若し下落し、ジェット燃料の国際市況も沈静化すれば大幅な価格改定で収益性が損なわれるリスクが減ることから同社の株価にとってはプラスに働くと考えられます。 ■チャイナ・デジタルTV(ティッカー:STV) 同社はケーブルテレビのデジタル化を促進するアクセス制限ソフトウエアを作っている会社です。中国ではケーブルテレビ自体は既にかなり普及しています。現在1.48億世帯がケーブルテレビに加入しており、毎年、少なくとも1000万世帯程度この数字は増えています。しかしそれらの多くはデジタル対応になっていません。デジタル対応の普及率は7%に過ぎません。中国政府は2015年までにデジタル化を完了し、アナログ放送を終わらせる計画です。北京五輪はデジタル化を促進するひとつの契機です。 デジタル化するには放送局の側の、所謂、ヘッドエンドと呼ばれる機器をアップグレードするとともに各家庭のセットトップ・ボックスにデジタル信号を解読するスマートカードを差し込む必要があります。同社はヘッドエンド側の装置とスマートカードの両方を作っていますが売上の9割はスマートカードから発生します。 現在、同社のマーケットシェアは51%で圧倒的に首位です。スマートカードの価格は安定的に推移しています。同社の営業マージンは54%であり、これは近年の数字に照らしてやや見劣りする数字です。販売管理費などの急増がマージン悪化の原因です。この他エレクトロニック・プログラム・ガイドのビジネスを立ち上げるためにその分野での研究開発費を積み増したりしているのもマージンを圧迫しています。同社の場合、売上成長の数字は顧客であるケーブルTV 会社のデジタル化計画が事前にわかっているため比較的予想しやすいです。従って費用をいかに厳格に管理するかが経営のポイントになります。 ■シー・トリップ(ティッカー:CTRP) 同社は旅行の予約サービスをオンラインならびにオフラインで提供する会社です。顧客が同社のウエブサイトなどを経由してホテルや航空券を予約した場合、一定のコミッションを受け取るビジネス・モデルです。12月期の決算では総売上高は54%成長、ホテル予約は42%成長、航空券予約は72%成長、パッケージ・ツアーは71%成長でした。ホテル予約コミッションは売上の53%、航空券予約コミッションは売上の39%、パッケージ・ツアーは売上の6% 程度を占めています。 ホテル予約部門では予約全体の約半分が大都市のホテル、残りの半分が地方都市のホテルの予約です。成長率で言うと地方都市の予約の成長の方が高い成長を示しています。このため当面は地方都市での業務提携先を積極的に拡充する戦略をとっています。いまのところ約6000のホテルと提携関係にあります。 一方、中国の航空業界自体は年率15%程度で成長しています。従ってシー・トリップの成長率はエア・トラベル自体の成長よりかなり早いスピードで成長しているわけです。現在同社は内外の75のエアラインと提携しています。 同社のウエブサイトに登録している顧客数は4200万人であり、これは2006年年末の3600万人から増えています。同社のグロスマージンは 81%で、これは去年の80%から若干改善しています。同社は特に営業費用などの管理が行き届いています。今期の税率は7%と通常よりかなり低かったです。但しこの税率は今後また上昇する可能性もあります。なお心配された豪雪の影響はほとんどありませんでした。但し今年の旧正月はとりわけ寒かったので例年より旅行自体が若干低調だったと報告されています。今日紹介した銘柄のうちシー・トリップだけが新高値を更新中です。
2008年05月07日
-
第127回 中国の娯楽・レジャー産業(その1)
今日のまとめ 1. オリンピックは資本集約的なレジャー産業の出現を可能にする 2. オリンピックは「起点」であって「終点」ではない 3. 娯楽・レジャー株は割安に放置されている ■北京五輪は娯楽・レジャー株を見直す好機 日本で『観光白書』が創刊されたのは東京オリンピックの年、つまり1964年です。これはオリンピックのような国家の行事が娯楽・レジャー産業にどういう影響を与えるかを考える上で示唆に富む出来事だったと思います。 もちろん、オリンピック以前の日本人だって余暇を楽しんでいただろうし、年配の方なら楽しい思い出もいろいろあると思います。戦後の娯楽やレジャーに関する社会現象を思いつくままに書き出してみると、例えば1940年代後半には競輪・競馬のブームがありました。民放が最初にテレビ放送を開始したのは 1953年です。1950年代後半になると麻雀がブームになり、深夜喫茶、歌声喫茶などが繁盛しました。 しかしオリンピックの直前・直後あたりからの日本のレジャーの在り方はそれまでとは少し違った様相を呈し始めます。例えばこの頃からホテルの建設ブームが始まりました。そして1968年には最初の海外団体パック旅行の『ルック』が発売されました。それらの新しいレジャーはいずれも高速道路や空港などの社会的インフラストラクチャーが整備されて初めて実現可能なサービスや商品です。また娯楽が「レジャー産業」として事業化される必要が出てきたのはそれらのビジネスが以前に比べて資本集約的、つまり初期投資に巨額の資金を必要とするようになったからに他なりません。オリンピックのようなイベントはそういう巨額の投資を採算的に可能にする「特需」を創り出すという意味でレジャー産業の産婆の役割を果たしているわけです。 いま中国株に目を向けると、まさしくそういう新しい産業が飛躍しようとしています。それらの多くの企業は北京五輪を前に株式市場で資金を調達し、施設や設備を購入し、それらの先行投資の果実の収穫の機会を待ち構えている局面です。この場合、それらのビジネスは北京五輪という需要機会を想定してキャパシティーを設定していますから、現時点では必ずしも稼働率や価格の面で所期の需要をフルに享受しているとは言えないケースもあります。しかしオリンピックが終わってしまったら、それらのビジネスも終わりになるのかと言えば、それはそんなことはありません。日本の例を見てもわかる通り、五輪は「終点」ではなく、「起点」なのです。 その意味では現在の中国の娯楽・レジャー関連株というのは大変興味深い立場に置かれています。なぜなら株式を公開した当初の興奮が去って、人気の圏外に放置されている銘柄が多いからです。今日はそんな人気離散している企業の幾つかに焦点を当ててみたいと思います。 ■ホーム・インズ&ホテルズ(ティッカー:HMIN) 同社はビジネス・ホテルのフランチャイズを展開しています。同社のホテルのモットーは便利なロケーションにリーズナブルな価格のホテルを展開するという事です。現在、中国の66都市で266のホテルを展開しています。これを2011年頃までに1000ホテルにまで伸ばすというのが同社の長期の経営計画です。 しかし目下のところ同社の株価は低迷しています。その理由は去年の11月に買収した「トップスター」ホテル・チェーンのパフォーマンスが芳しくなく、ホーム・インズの経営陣のM&Aの手腕に投資家が疑問を抱いていること、それから積極的な地方都市への展開が客室単価、マージン、客室稼働率などの経営指標を短期的に押し下げていることなどが原因です。 「トップスター」チェーンは去年の第4四半期の客室稼働率が56%しかありませんでした。これはホーム・インズの92%に比べると大変悪い数字です。買収が発表された時点での客室稼働率のガイダンスより、実際の買収後の数字が悪化していた事も投資家が動転した理由です。しかしこれはもともと第4四半期がホテルのビジネス自体が低調な時期であるという季節要因に拠るところが大きく、買収後の統合に失敗したという風に結論付けるのは性急過ぎると思います。また「トップスター」買収に絡む特別損失が計上されていますが、その大部分は「トップスター」チェーンのホテル会計・予約システムのソフトウエアを廃棄処分にし、代わりにホーム・インズのシステムに組み込むための、最初から予想された費用であり、この損はあくまでもノン・キャッシュ、つまり評価上の損失であり、実損ではありません。 ホーム・インズ本体の話に戻ると地方都市への積極進出はマージンの悪化を招いています。この理由は地方で好立地のホテルを買収し、部屋の内装や看板をホーム・インズのブランドにリニューアルする際に必要となる改装費は都市でも地方でも一定であることが主な理由です。地方は客室単価が安いので自ずとマージンは悪くなってしまいます。また、全社的な客室単価(RevPAR)が圧迫を受けているのは大都市での客室料金が値下げプレッシャーを受けているからではなくて、地方への展開で客室単価の比較的安い物件が同社のポートフォリオにどんどん追加されていることが原因です。 ホーム・インズの足許の業績は第1四半期に中国を襲った記録的な豪雪の影響でかなり悪くなると思われます。従ってウォール街の投資家は目先、同社株を敬遠しています。ただ、記録的な豪雪というのは一時的な要因であって同社の長期的な財務的健全性とは何の関係もない材料です。 ■メルコPBLエンターテイメント(ティッカー:MPEL) 同社はオーストラリアのPBLと香港のメルコとの間のカジノ・ジョイント・ベンチャーでマカオにおける事業に特化しています。同社の現在の主力カジノは『クラウン・マカオ』です。タイパ島に位置する同カジノは主にハイ・ローラーと呼ばれる裕福層をターゲットにした施設です。これとは別にコータイ通り沿いの、ラスベガス・サンズ(ティッカー:LVS)の『ベネチアン・マカオ』の真向かいに『シティ・オブ・ドリームス』という巨大カジノを現在建設中であり、こちらの方は来年の春に開業の予定です。 同社の『クラウン・マカオ』はロケーションが悪いこと、中途半端な規模であることなどの理由から相当苦戦するだろうと思われてきました。メルコ PBLの経営陣はそうした懸念に応えるため、すぐに『クラウン・マカオ』をハイ・ローラー向けに特化したカジノへと改装し、同時にジャンケット(団体ツアー)のオペレーターと提携し徹底的な集客戦略を展開しました。その結果、『クラウン・マカオ』はとりわけハイ・ローラーのセグメントでは強く、現在第1 位の市場占有率(VIPで21%)を誇っています。この結果、同社はマカオで「一番駄目な会社」から「最もマークすべき強敵」へと変身しました。メルコ PBLの株式は上場以来全く良いところ無しの展開でしたが、今はマカオで一番勢いのあるカジノになっているので株価的にも期待して良いと思います。
2008年05月07日
全4件 (4件中 1-4件目)
1










