2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年07月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
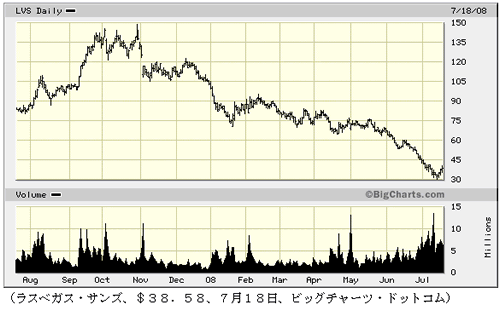
第135回 マカオ関連銘柄の近況
今日のまとめ 1. マカオ関連株低迷の一因は米国カジノ業界の変調にある 2. ツアー業者への手数料割戻し競争の激化が不健全な経営環境を作っている 3. マカオ政府が規制に乗り出した為、過当競争は沈静化すると思われる ■安値を更新するマカオ関連株 マカオ関連株が冴えません。代表銘柄であるラスベガス・サンズ(LVS)やメルコ・クラウン・エンターティメント(MPEL)は軒並み新安値を更新しています。 ■アメリカ本国のカジノの低迷 マカオ関連株が低迷している理由は幾つか考えられます。先ずマカオに進出してきているアメリカのカジノ業者は本国アメリカにおける経営環境の暗転に直面していることが挙げられます。下のグラフはマカオ、ラスベガス、アトランティック・シティーの各都市におけるギャンブル収入の前年同期比の推移を示したものです。これを見るとマカオの今年上半期のギャンブル収入は今年に入ってから毎月、前年同期比で30~70%も伸びていることがわかります。その反面、ラスベガスとアトランティック・シティーは前年比割れの月が多いです。 現在のラスベガスやアトランティック・シティーの低迷は9・11の同時多発テロの直後の落ち込みよりも、もっとひどい状況です。これはサブプライム問題に端を発した米国の景気後退の影響を受けていること、原油価格の高騰で行楽客の足が遠のいたこと、ラスベガスの不動産バブルが弾けたことでカジノ熱が冷めたこと、マカオの本格的な稼動でアジアからの旅行者がマカオに奪われてしまったこと、長年の過剰投資でオーバー・キャパシティー気味になっていること、などが影響していると思われます。このため米国市場に上場されているカジノ株は軒並み大幅な調整を余儀なくされています。銘柄名52週高値からの下落幅ウィン・リゾーツ-50.02ペン・ナショナル・ゲーミング-54.94メルコ・クラウン-65.17ラスベガス・サンズ-74.07MGM-74.13(コンテクスチュアル・インベストメンツ) ■マカオの直面する問題 それではマカオのカジノ産業が全然問題を抱えていないかと言えば、それはそうではありません。先ずVIPと呼ばれる、一度に多額のお金を賭ける顧客への依存度が高すぎる問題があります。マカオのギャンブル・ライセンスがこれまでのスタンレー・ホーによる独占から6社に拡大された背景にはマカオをラスベガス型の大衆的で健全なマス・マーケット志向のリゾートに方向転換しようとする意図がありました。これに基づいてメルコ・クラウンの『クラウン・マカオ』、ラスベガス・サンズの『ベネチアン・マカオ』などの新しい施設が開業したわけです。しかし、いまのところこれらのカジノの収入は依然、VIPに大きく依存しています。またVIPの顧客を引っ張ってくるツアー業者(=彼らのことをジャンケット・オペレーターと呼んでいます)への手数料の割戻し競争が激化しました。ジャンケット・オペレーターへの手数料の割戻しは各社の競争の都合などから内容が不透明である場合が多く、投資家を混乱させています。さらに手数料割戻しはカジノにとってはマージン圧迫要因でもあります。 ■マカオ政府の対応こうした問題に応えてマカオ政府は次のような対応策を提示しました:1.ジャンケット業者への手数料は掛け金総額の1.25%を超えてはならない2.新規のカジノの建設ならびにギャンブリング・テーブルの数に制限を加える3.中国本土の一部の特権的な階層がマカオに入り浸ることを抑制するためビザの発給に制限を加える これらの一連の措置は短期的にはマカオのカジノ各社の売上にはマイナスの影響を与えると思います。とりわけメルコ・クラウンのようにVIPへの依存度が高い企業にとってはきついと思われます。その反面、手数料の割戻し競争に制限が加えられるということは各社のマージンにとってはプラスです。またギャンブリング・テーブルの野放し的な増加に制限が加えられたことは過当競争の心配が減ったことを意味すると思います。 ■カジノ業者の資金調達面からの考察 去年まではカジノに対する銀行やウォール街の融資姿勢は極めて積極的で、ハラーズ・エンターテイメントなどの大手がLBOにより非公開化されました。従ってカジノ業者の多くは比較的多額の負債を抱えています。そこへサブプライム問題が襲ったため、いまは以前ほど簡単に融資がおりなくなっています。また、先週、SJMが香港に上場されましたが、この公募は不人気の為、当初計画の約半分程度の募集規模となりました。こうした一連の信用の緊縮化は無秩序な拡張が今後ある程度抑制されることを意味すると思います。
2008年07月22日
-
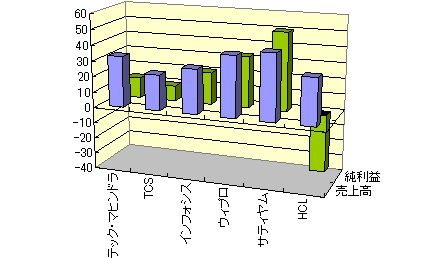
第134回 インドITアウトソーシング業界の近況
今日のまとめ 1、インフォシスの決算は市場予想を上回った 2、先週の米国金融市場の不安が投資家の期待を下げた 3、インド・ルピー安の恩恵だけでは上値は追えない ■決算シーズンが始まる インドのITアウトソーシング企業の決算発表のシーズンが到来しました。下のグラフは2009年度第1四半期(=つまり2008年6月期)のインドの主要ITアウトソーシング企業のコンセンサス予想を示したものです。このうち先陣を切って既に決算を発表したインフォシス(ティッカー:INFY)に関しては予想値ではなく、実績の数字を示してあります。 ■インフォシスの決算を吟味する 先週金曜日に発表されたインフォシスの決算は市場予想を上回る内容でした。銘柄名インフォシスティッカーINFY6月期売上高実績11.6億ドルコンセンサス予想11.5億ドル6月期EPS実績54セントコンセンサス予想51セント9月期売上高ガイダンス12.15から2・25億ドルコンセンサス予想12.1億ドル9月期EPSガイダンス55~56セントコンセンサス予想56セント08年売上高ガイダンス49.7~50.5億ドルコンセンサス予想50.3億ドル08年EPSガイダンス$2.32~2.36コンセンサス予想$2.31(出典:コンテクスチュアル・インベストメンツ) しかし、好決算にも関らず金曜日の立会ではインフォシスのADRは▼13.3%も急落しました。これは来期以降のガイダンスが投資家の当初の期待ほど引き上げられなかったのが原因です。このところのインド・ルピー安で「インドのITアウトソーシング企業は少し為替面で楽になっている」という見方が支配的でした。先月までのインフォシスの経営陣の口ぶりもそういう楽観的な見通しを反映したものでした。しかし先週、ファニー・メイ(FNM)、フレディ・マック(FRE)、リーマン・ブラザーズ(LEH)などの株価が急落し、再び米国の金融サービス・セクターの経営の健全性に対する不透明感が台頭しています。そういうニュアンスを微妙に反映し、インフォシス経営陣が今後の見通しをトーン・ダウンしたことが嫌気されたのだと思います。 ■北米の金融サービスへの依存 インフォシスは引き続き銀行や保険などの金融サービス業の顧客に対する依存度が高いです。下の表は同社の顧客業種別売上高ですが、6月期の売上高に占める銀行業の比率は27.7%でした。通信の比率が下がっているのはインフォシスの最大顧客であるブリティッシュ・テレコムのビジネスが減っているからです。ブリティッシュ・テレコムの総売り上げに占める割合は10.3%から7.9%へと下がりました。インフォシスの顧客業種別売上比率 (%) 07年6月(LTM)2008年3月2008年6月保険7.276.8銀行3026.927.7製造業13.316.418.4小売10.311.912.2通信20.422.519.7公共・エネルギー5.25.25.4運輸2.22.82.4サービス業7.85.55.5その他3.61.81.9(出典:インフォシス) また地域別では北米への依存度が62%と高いです。この地域別売上構成は近年、余り変動していません。 一方、役務内容別で見るとアプリケーションの開発、保全、ならびにコンサルティング&パッケージ・インプリメンテーションが高い比率を占めています。インフォシスの役務内容別売上シェア (%) 07年6月(LTM)2008年3月2008年6月アプリケーション開発22.521.821.4アプリケーション保全24.623.422BPO566.3コンサルティング2224.123.7パッケージ・インプリメンテーションインフラ管理4.74.65.7製品エンジニアリング1.51.82.2システム統合2.533.1テスティング7.27.27.4その他6.24.44.3プロダクツ3.83.73.9(出典:インフォシス) ブリティッシュ・テレコムからのビジネスが減少しているので大口顧客の成長が鈍化しているように見えますが、実際はブリティッシュ・テレコムを除いたトップ10顧客の今期の成長は3月期比+3.8%と堅調でした。またトップ10以外の顧客の成長率も+3.9%と確りしています。インフォシスは年間売上高のうち約46%を上半期に達成するだろうと予想しています。これは売上の54%が下半期に集中することを示唆しているわけです。しかし下半期の方が上半期より売上が多いのは例年のパターンであり、今年だけが特別下半期への依存度が高いわけではありません。 今期は49の新規顧客が追加されました。これは最近のトレンドより若干多い数字であり、全体としてITアウトソーシングのビジネスがまだまだ健全であることの証拠だと言えます。今期のハイライトとしては製造業、小売業などの顧客からの引き合いが強かった点です。とりわけ製造業はドル安で景気が良かったのが活発な引き合いの理由と考えられます。インフォシスのコストの管理は全般に上手く行っていると言えるでしょう。43.3%のグロスマージンは平常通りと言えます。従業員の給与引き上げのプレッシャーも上手く管理出来ていると思います。一方、役務単価は極めて安定しており、値引きプレッシャーのようなものはありません。 ■インドの他のITアウトソーシング企業の見通し インド・ルピーは今後も弱いと考えられることからITアウトソーシング企業にとっては好ましい環境が続きます。インフォシスの経営陣の談話では独立系のBPOは苦しんでいるところが多く、今後、それらの独立系BPOが大手ITアウトソーシング企業に買収されるケースが多発するだろうとのことです。顧客から受注した役務をインド国内の従業員を担当につけることでこなしてゆくという、所謂、グローバル・デリバリー・モデルをインフォシスは提唱しています。今後、このような顧客への価値提案が増えると考えられます。
2008年07月10日
-

第133回 70年代といまを比較すると
今日のまとめ 1、緩和的な金融・財政政策がインフレの種を蒔いた2、実質金利マイナスは憂慮すべき共通点 3、賃金インフレに対する期待が日本、米国で低いことが救い 4、インフレが或る一定の水準を越えると株式のバリュエーションは陥没する ■出発点は緩和的な金融・財政政策 原油高が続く今日と1970年代のオイルショックの頃を比較すると共通点がみられます。まず両方の時代とも長年にわたる米国の低金利政策が災いの種を蒔いたという点が似ています。その話をするためにはオイルショックに揺れた70年代より10年ほど遡って、1960年代から話を始める必要があります。 1961年、ケネディー大統領はベトナム戦争の戦費調達がやりやすいように金融緩和政策を取るようにFEDに圧力をかけました。また、大型減税を政策として打ち出しました。しかし、当時のアメリカは財政的には保守的で、ケネディーの減税策は議会を通りませんでした。 ところが1963年にケネディー大統領が暗殺されてしまい、アメリカ人は強烈なショックを受けます。副大統領だったリンドン・ジョンソンはケネディーの後を受けて大統領に就任すると「ケネディーの遺志を継ぐ」という事を宣言し、ケネディーのやり残したイニシャチブを全部実行に移します。それまで健全財政などの見地からケネディーに反対していた反対派はケネディーに同情する圧倒的な世論の高まりに負けて大型減税を通してしまうのです。そればかりではなく、メディケアなどの社会福祉制度もこのケネディー暗殺後の、アメリカ国民がエモーショナルになっているときに相次いで可決しています。これはちょうど9・11の同時多発テロの後にアメリカの世論が右傾化し、軍事費の増加と減税で財政の悪化を招いた過程と酷似しています。 (出典:ニューヨーク・タイムズ=左はケネディー暗殺、右は同時多発テロを伝える事件翌日の第一面) ジョンソン大統領は低金利維持を最優先の政策とします。FEBはどんどんドル紙幣を増刷し、アメリカの国際収支は悪化しました。こうした、不況のときにはどんどん財投をした方が良いという考え方は経済学者ジョン・メイナード・ケインズの理論であり、それを信奉する人たちはケインジアンと呼ばれます。ジョンソン大統領のこの政策は当初成功を収めます。そこで米国の雑誌、『タイム』は「我々は皆、ケインズ派だ!」と宣言するわけです。しかしケインズ派がわが世の春を謳歌したのは束の間のことでした。なぜなら1971年の8月にはジョンソン大統領の後を継いだニクソン大統領がドルの切り下げを発表せざるを得なくなってしまったからです。ベトナム戦争遂行に絡む放埓な金融政策ならびに財政政策はインフレの芽を世界経済にしっかり植えつけてしまったのです。その後、1973年にOPECのカルテルによる原油価格引き上げが世界的なインフレの直接的なきっかけになるわけですけど、いままで見てきたようにもうそれ以前にインフレになる種は蒔かれていたわけです。今回、ベトナム戦争をイラク戦争に置き換えてやるだけで1970年代初頭の資本市場のおかれた環境と今の環境が酷似していることがわかると思います。 ■オイルマネーの還流と実質金利 第一次オイルショックで突然、沢山のドルを稼ぎはじめた中東などの産油国はシティバンクやチェイス・マンハッタンなどのマネーセンター・バンクにそれをごっそり預金しました。そしてマネーセンター・バンクはそのお金を石油を輸入に頼っている新興国に貸し付けるというカタチで還流したのです。また石油が眠っていると考えられるラテンアメリカなどの国には石油探索、増産に向けた信用供与が盛んに行われました。この潤沢な融資により実質金利はマイナスで推移しました。シンジケート・ローンやユーロ・ダラーの活用などといった金融技術面での進歩もそういう時代背景の下に進んだのでした。翻って現代を見るとソヴリン・ウエルス・ファンド(SWF)が注目を浴びている現状というのは当時の「ペトロダラー」がもてはやされた状況とイメージがダブります。もっと重要な事は今回も少なからぬ国々で実質金利がマイナスに維持されており世界各国のイールドカーブの形はインフレを根絶するような断固としたスタンスになっていないという点です。 ■投資家の慢心 さて、ここで興味深いのは第一次オイルショックが起きた後も、米国の金融界ではインフレが慢性的な問題になると考えていた投資家やエコノミストは少数派で、多くの投資家は既にインフレは峠を越したと考えていた点です。従って当時のカーター政権もインフレ抑制とともに経済成長をも追及する、所謂、二兎を追うどっちつかずの政策を平気で続けていたわけです。 投資家が新興国へどんどん「ペトロダラー」を還流させる事の内包するリスクに対して鈍感になっていたひとつの理由は1973年からはじまり1979年まで続いたGATTの東京ラウンドで世界貿易の場で関税を引き下げるなど成長促進する取り決めが議論され、投資家が新興国に寄せる期待が高かったためです。いまGATT東京ラウンドをWTO加盟とか北京オリンピックに置き換えると、そういう投資家の期待は現在のマーケットにもそのままあてはまります。 ■危機のクライマックス 1978年のインフレは重要なレベルである6.8%を1月に突き抜け、4月には7.4%、クリスマスには9%へと昂進します。そして1979年1月にはイランでイスラム原理革命が起こり、アヤトラ・ホメイニ師が登場、とうとうインフレ率は二桁に達するわけです。ここで興味深いのは10年債の利回りは1975年頃の、比較的債券市場が小康状態を保っていた頃の水準とたいして変わらないレベルで依然取引されており、その後襲いかかる狂乱インフレを全く予期していなかった点です。 ところが夏にはアメリカのガソリン・スタンドに行列が出来始めました。インフレは12%につっかけ始めるし、景気指標は景気後退の兆候を示し始めました。「もうボヤボヤしていられない」と考えたカーター大統領は7月に閣僚を入れ替え、FRB議長をビル・ミラーからポール・ボルカーに交代します。 10月23日に10年債が11%をつけると金融市場はパニックの様相を呈し始め、ボルカーはIMFミーティングでベルグラードにいたのですが、会議を中座し米国に飛びかえり、その週末の臨時FOMCミーティングでマネー・サプライを大幅に減らす「世紀の大決断」をします。これは当然、景気を犠牲にする方法ですので失業率は9%へ、市中金利は20%に突入しました。この直後の同年11月にはイランのアメリカ大使館に学生が乱入し、大使館で働く職員たちを444日間に渡って監禁する事件が起き、危機はクライマックスを迎えます。そしてひとたび原油安に転ずると、今度は実質金利が急上昇し世界的な不況が来たわけです。 ■現代が70年代と違う箇所 ここで注意しないといけないのはインフレには世界中をぐるぐる回る、伝播しやすいものと、そうでないものがあるということです。原油価格や穀物価格は極めて伝播しやすいです。その反面、サービス(たとえばレストランのウエイトレスのチップ)や給与はそれぞれの国によって地域差があります。これは人はモノのように世界を自由に流通しないから当然です。実はこの部分の期待が新興国と先進国では極めて異なるのです。つまり新興国の国民の多くは自分の暮らしぶりが自分の親の世代よりは本人の世代の方がよくなると思っているし、子供の世代はもっとよくなるという期待を抱いている人が多い。これは突き詰めて言えば給与がベースアップするという期待があるわけです。 反面、アメリカや日本ではどんどん給料が上がると思っている人は余り居ません。実際、アメリカではドットコム・バブル崩壊後、2003年頃から景気が上向いてきたわけですけど、今回の景気拡大サイクルでは労働者の所得は殆ど上昇しませんでした。これはアメリカの歴史の中では異例なことです。つまり2年前、アメリカの景気が良かったときでさえ、アメリカの一般の庶民で株などの資産を余り持っていなかった人々は暮らしぶりという点ではうつむき加減だったのです。今ならアメリカの国民はもっと厳しいと感じているに違いありません。だから賃上げへの期待は低いです。同じことが日本にも言えて、インフレだからというだけの理由で給与のベースアップを今か今かと待っている日本のサラリーマンは居ないと思います。 アメリカや日本で賃金に関する国民の期待がしっかりアンカー(投錨)されているということは70年代のような酷いことにならない期待を我々に与えていると解釈できるでしょう。その反面、アメリカや日本が低金利を維持することで新興国の中央銀行のインフレ退治の作業が一層難しくなっているとも言えるのです。つまりブレーキを思いっきり踏み込むというリスクは新興国の方が遥かに高いわけです。 ■米国の株式のバリュエーション 現在のS&P500のPERは15倍程度で、これは一見、割安に見えます。ただし、気をつけないといけないことがあるのです。それは若しインフレが上に書いた70年代のようにどんどん動き出したら、15倍程度というPERが適正であるというモノサシ自体が使えなくなるからです。アメリカ株のPERが15倍くらいならOKという考え方はあくまでも過去20年間の平均値を取ったに過ぎないのです。この20年間は米国のCPIは1%から5%のレンジの中にきれいに納まってきました。ドットコム・バブルの時期を除けば、そのくらいのインフレ率ならアメリカ株のPERは大体14倍~21倍のPERに収まって呉れる、するとその中値は17.5倍だから今の15倍というのは平均値より安いという感覚になるわけです。ところが過去に米国のインフレ率が6%を越えたら、PERのレンジはいきなり7倍~14倍へとガクンと下がりました(下のグラフの70年代のPERにご注目下さい)。すると現在の15倍というPERはとても割高なわけです。このように今は米国の株式のバリュエーションが底抜けするかどうかの瀬戸際なのです。 新興国の株式市場は歴史が浅い上に70年代当時と今とでは上場企業数や指数構成などがぜんぜん異なりますので、上に書いたような過去との比較は意味がありません。しかしアメリカの株式市場でバリュエーションの「底抜け」が起きてしまうと、新興国の株式市場もその余波を被ることは想像に難くありません。
2008年07月03日
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 楽天市場
- 【楽天ランキング1位】【送料無料】…
- (2025-11-21 00:05:45)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 「”決断”の差は”責任”の差」
- (2025-11-20 21:40:08)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 日経平均株価、先物上昇、サイバー株…
- (2025-11-21 00:00:02)
-







