2015年05月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
2016 県立入試予想 理科
来年の県立入試の物理分野の大問、出題予想は現在学校で学習中の「運動とエネルギー」です。これ、一択。先日の進学研究会の説明会では「磁界」というのが挙がってました。確かに「磁界」も出ていませんが、26年「光」(1年分野)→27年「電流」(2年分野) と来ましたので、現在の3年生の学年は、3年学習分野の「運動とエネルギー」なのではと私個人的には考えます。今年は直前予想をすべて的中させましたが、来年はよりいっそう精度を上げたいと思います。何がどういう形で出るかまで突っ込むつもりです。新指導要領で入ってきた仕事や仕事率までしっかり習得しておきたいところです。こちらは期末テスト範囲ですかね。「磁界」は小問にまわるような気がします。anyway、物理は差がつくので、よーく理解しておく必要があります。それと、物理にかぎらないのですが、グラフは縦軸と横軸に何がとられているか、よく考えてから書くことがたいせつです。等速直線運動で縦軸に距離をとったときに横線を書いたら、そりゃ運動してませんから。またしても、くどいくらい注意しておきました。
2015.05.30
コメント(0)
-
茨城県立高校入試研究5 国語を勘ぐる
成績優秀者で実力テストの国語だけ成績が安定しない生徒は少なくない。選択肢問題の配点が5点と高いので、何問か連続して間違えるとボコボコにされてしまう。 今年のつくば秀英高校の国語の問題は、県立入試と全く同じ形式、分量で行われたのであるが、塾では軒並み30台、40点台だったので、生徒や保護者は直前期にちょっとした恐慌をきたした。 いったい、どういうことなのかと思って問題を解いてみたところ、選択肢がどれも難しい。それも4択で2つまで絞れて、さあどっちかというのではなくて、「ア」かもしれないし、「イ」かもしれないし、「ウ」かもしれないし、「エ」かもしれないという問題である。今年の秀英入試の場合、あまり深く考えずになんとなくの勘で真っ直ぐ答えを選びに行った方が結果的には良かったように思うのだが、当塾の生徒の場合、すべての選択肢の1語、1語を真剣に検討して矛盾するものは消去していくので、同じ内容で微妙に言い換えられているような場合などは、かえって出題者の術中に嵌まってしまうようである。 悪問といわけでは全くないのだが、このタイプの問題は現場で緊張して、いつもより頭が固くなっている生徒にとっては誤答が誘発されやすい。 個人的には県立入試で、こういう問題を作ってもいいのではないかと思う。 しかし、現実の県立入試はそうはなっていない。4択なら3つが誤りなのが判別でき、残りの正しい選択肢を1つ選べる問題がほとんどである。 そこで、まず、生徒と保護者には落ち着いてもらうことにした。県立入試の国語は選択肢の正解率が75%を超える問題が多いこと、例年の結果をみても、平均点が高いうえに、5教科の中で極端に標準偏差が小さい(差がつきにくい)から、そんなに低い点数にはなりようがない、それなら他の科目で十分に合格できるから心配しないでいいことを説明した。これまでの年度でも、直前の実力テストが50点程度で本番で80点〜90点の点数が取れたことは何度もある。 やはり、今年も本番では80点から90点の点数が取れたようで国語が合格を支えるカタチになった。国語の点数が高くなりがちだといってもさすがに90近くま持ってこれれば科目別順位も上位なのは間違いない。 なぜ、茨城県がこういう問題を作っているのか考えてみたのだが、どうも国語の成績で合否を左右させたくないというのが本音なのではないだろうか。 国語で点数が左右されると、問題によっては、数学の大問8の(2)が解ける生徒や英語で100点近く取れる生徒が土浦一や水戸一に落ちてしまう危険性がある。 この辺の生徒は漏れなく合格者として取りたいのが本音なのではないか。 深読みし過ぎかもしれないが、そんなことを思う。 といって国語を真面目にやらないと実力テストの順位も模試の偏差値も上がらないことは間違いないので真剣にとりくんでほしい。
2015.05.29
コメント(0)
-
残念な漢字
当塾では、国語の時間の終わりに必ず漢字の読み書き20問をやっている。 しかし、この目的は入試対策ではなく、中学生の教養を身につけることである。 茨城県立入試の場合、漢字が6問しか出題されず、配点もきわめて低く、他県に比べると漢字そのものの入試での重要性は低い。 また出題される漢字の多くが小学4年生あたりで履修するものなので漢字で差をつけてやろうとするのは無理がある。 漢字問題の位置づけは、数学でいうところの2➖8といった問題と同じで、お助けの「点くれ問題」である。 坂東市は検定試験に力を入れているので、漢検だけでなく、読解能力を試す「読検」のようなものがあればと思うのである。ほんと読めない。読めないことが他の4教科に甚大な影響を与えていることに誰も気づかない。
2015.05.27
コメント(0)
-
塾からみた良い中学校の先生とは
これから書くことは学校の先生の悪口ではないことを断っておきます。真剣に考えてほしい、かなり真面目な話です。塾から見た良い学校の先生というのは、ずばり、「標準的な進度から遅れない人」です。もう、これに尽きます。たとえば教科書が5単元あれば、1学期の中間テストではきちんと第1単元で問題を作れ、期末テストでは第2単元までで問題が作れる人です。学校の先生の場合、運動会をきちんとやるとか、部活で県大会に出場するとかいったことは、外観的に明らかになるのできちんとなされる人が多いのですが、学習進度(深度)については怪しい人がたくさんいます。今回の中間テスト、ある中学校では、数学の試験範囲が「式の展開、展開の公式1~4に対応する因数分解、2段階の因数分解、置き換えをしての因数分解、連続する整数や図形など因数分解の応用まで」(学校の授業そのものはもう平方根に入っている)なのに対して、別の中学校では、もっとも基本的な因数分解にさえ入れないところがあります。今まで数学の点数が40点や50点程度だった生徒まで100点が狙えるくらいに練習を積んだのに、ちょっとかわいそうです。こんなテストで、提出物だけ提出して通知表「5」をもらってもしかたありません。茨城県が高校入試の選抜で内申書に重きを置かない理由もこんなあたりなのでは。「そんなの、塾の都合でしょ?」いう話ではありません。このあと、中3生は、平方根、2次方程式、2次関数、円周角、相似、中点連結定理、三平方の定理・・・・・と受験までにマスターしなければならないことが山積みなのに、1学期の中間テストで最も基本的な因数分解も出題できないのだとすれば、迷惑被って高校入試に落ちて泣きを見るのは生徒と保護者です。最終段階で「志望校を1つ下げた方がいいです。」といっても1つ下げると、この地区は偏差値で10も15も吹っ飛ぶわけです。 9月は運動会の練習で授業も進まないし、今年もまたズルズルといってしまって塾が負担を被るのだろうなと思うと今から憂鬱でなりません。最近、英語の教員でTOEIC、730ポイント以上の人が多いか少ないかの県別ランキングというのが出ていましたが、そんなことはどうでもよくて、現実は各教科とも教員の学力以前の話なんです。きとんとした進度を取れるかどうか。昔に比べて、教員の方は強く管理されて業務が激増しているという話を聞きますが、力の入れ所が大いにずれてるんじゃないかと思うわけです。今年は英語については、どの中学校も現在完了の3用法まで来ているので、まずまず順調です。実は新指導要領で進度的には英語は一番楽なんです。チンタラやっていても、秋までに履修範囲そのものは終えられるのは英語くらいでしょうか。ただ、いずれにせよ中学校の授業が高校入試に直結せず、ふだんの学習と県立入試の距離が最も遠いのも英語です。通塾していない人は長文などは、どうやって学習してるんでしょうか。英作文が必出なのですが誰が添削してあげてるんでしょうか。社会は順調に進んでいたとしても、現代史の学習が中2から中3に移動してきて、公民を圧迫するので非常にきついです。それなのに、県立入試では公民の最終単元の経済分野の出題が多いのが嫌らしいところです。高校入試の試験委員は、同じ茨城教員なのに、ここで書いたようなことを顧慮しているとは思えませんね。まあ、土浦一高とか水戸一高とか受ける人には中学校がどうのこうのといったのと別の学力を求めているのは当然ですが。
2015.05.26
コメント(0)
-

茨城県歴史館2 給食
県立歴史館に保存されている旧水海道小学校の内部は公開されていて、茨城の教育に関する歴史や変遷がわかるような展示がいろいろとなされています。その一つが給食です。私が小学校に入学して何がもっとも辛かったかというと、この写真のものです。わかりますか。脱脂粉乳。アルミのポットに入っていて、各自のアルミの容器に注がれるのですが、これが見た目は牛乳なのに、形容が困難なとんでもない味で、世の中にこんな不味いものがあるのかと思ったものです。市内の同学年の人に聞いたところ、「そんなの知らねえよ」というし、私たちも小学2年生からは瓶の牛乳になりましたので、終戦後からの名残りのこの飲み物を飲んだことがある最後の世代なのかと思います。
2015.05.26
コメント(0)
-

茨城県歴史館 1 水海道小学校
茨城統一テストの総会で水戸に行ったので、県の歴史館に寄ってみました。まず、玄関の脇に移築された水海道小学校があり、中が公開されています。なんと、このおしゃれな建物が明治14年(1881年)に完成しているので、びっくりです。町の人が出資しての建設だったようで、当時の水海道の人々の財力が伺われます。貴重なものなので、水戸に移築して茨城県の方で管理してるようです。つくったのは、羽田甚三氏。水海道出身の女優、羽田美智子さんの高祖父だそうです。
2015.05.24
コメント(0)
-
修学旅行帰り
岩井中生は修学旅行帰りのためかボーとしています。 この期間の中学校のホームページの閲覧数は新記録のようで、保護者の方は、「京都で楽しんでるかな」とか「どこをどう回ってるんだろ」、「どんなとこに泊まったの」「食事の様子はどうかな」といったことに興味があるようです。 ただ、どうも塾の生徒たちは、「楽しかったなあ」というよりは「学校行事の1つをこなした」という感じで「さしま少年自然の家」の宿泊学習とあまり変わらなかったようです。(笑)。 とにかく岩井中学校の場合、大人数なので、学校行事は「全体に無意識に乗ってく」という生徒が多いように思います。 しかし、先生は事故やトラブルにないようにということや生徒の体調など、とてもたいへんだったのではなかと思います。どうも私は心配性で多人数を預かる学校の先生には向きません。「自分も楽しんじまえー。」ってくらいじゃないとやっていけないのかとも思ったりもします。 京都の真ん中にあんな大人数が泊まれる旅館があるとはビックリしました。確か、自分も新京極をブラブラした覚えがあるので、そのあたりに泊まったのかもしれませんが。
2015.05.22
コメント(0)
-
我々は既に英語を話せているのでは?
開隆堂の中学英語教科書をみると出てくる単語のほとんどは既に日本語として取り入れられていることに気づく。 中2のプログラム1から教科書に出てくる単語を挙げていくと、バケーション、スタイル、ロック、トラディショナル、ディッシュ、ウィークエンド、サイエンス、アワー、ビレッジ、ダンス、ホビー、アンダー、チェリー、ハンティング、レイク・・・ これほど外来語に日本語が侵食されていたとは驚くばかりである。 だから、英語を話せないということではなくて、英語は話せているのである。 しかし、野球部の高校生がfirst、second、third(ファースト、セカンド、サード)が書けなかったり、サッカー部の高校生が教科書上では、near(ニア)、far(ファー)の意味がわからなかったりする。 under18代表を目指す生徒が、教科書でunderが出てくると、もうわからない。書くとandaaなどとなってしまう。 小学校から英語授業が導入されたり、高校の英語の授業では英語しか使わなかったりと、いろいろ偉い人たちは考えるようであるが、単語をつないでデタラメな言葉を話せるようになっても、読み、書きは全く向上しないと思う。 明治時代になるまでは学校がなく、また明治になってからも小学校に行かなかった人は多くて、ついこの前まで、日本語の読み書きができない日本人はたくさんいた。野口英世の母の手紙を見ればわかる通り平仮名で手紙を書くことさえ苦労だったのだ。 では、その人たちが日本語を話せなかったかというとそんなことは全くない。 語学学習は「必要性」と「論理的な学習」の両方がたいせつだ。現在の日本の小中高生のように日常生活上の必要がない上に論理的な学習は「めんどくせー」となれば、英語の学力が引き続き上がらないだろうことは予測がつく。 小学校からやるからどうのという問題ではないと思う。早く始めたらいいだろうという考え方は短絡的である。まあ、日本の有識者は昨日の国立競技場建設見直しのニュースなんかをみても、みな行き当たりばったりで短絡的なんだけれども。 興味があるのは相撲取りの日本語の読み書き能力である。話す能力はインタビューなど聞くと、助詞の使い方などまで含めて特級である。 琴欧洲などは日本人の親方よりも日本語能力が高い。
2015.05.20
コメント(0)
-
各教科の曖昧さをどうするか
私の塾での伸び率が最も大きいのは数学である。私は数学に関しては門外漢であるにもかかわらず。これは、使っているテキストが非常によく効く薬だということが大きい。 しかし、それでは、私が数学を教えるにあたって中学レベルでわからないことがあるかというと公立高校の入試に関してはない。 なぜ、そのような答えになるかを明確に説明することができる。生徒がわからないということがわかる私が完璧にわかるのだから(わかりなくい日本語ですが)、一年間どうやって持っていくか、どこをつつけば成績が上がるがか、どこで滞るか、その乗り越え方は、といったあたりは十分なノウハウが積み上がってきた。 問題は理科である。これ、分野によっては学校の理科の先生もごまかしているところがあるんじゃないかなあと思うのですよ。生徒たちが、そう言っている。 中学生の、しかもかなり成績の良い生徒が疑問を感じるポイントは確かにいくつかある。聞いてみると、もっともな疑問である。いま、学習中の斜面を下るときの台車の速さと力なんか、そうですね。確かに台車の重力の斜面に沿った分力は斜面のどこにあっても傾きが同じなら一定なのは図を書いても説明がつく。しかし、「スピードが上がっていくのに力は変わらない。」というのは、生徒たちにとっては違和感があるらしい。違和感があるがゆえに、かえってテストでは間違わないが、煮え切らないモヤモヤ感は頭に残ったままのようである。 私も評価の高い先生の授業なんかをYouTubeで見てみたりするのだが、私が授業でやっているのと大差ないので隔靴掻痒である。結局、試験にできれば、それでいいのか。 本当に芯から理解している先生を一個一個真剣に問い詰めて、スッキリしたいことは実はたくさんある。たぶん、全分野は無理だ。 社会も地理、歴史、公民を全部網羅するのは困難のはず。公民だけでも、経済があったり、憲法があったり、会社法があったり、証券投資論があったり、国際関係論があったりで、これを全部本格的にカバーする人は、そういないはずである。社会で1人の先生にすべての問題を問い詰めるのは酷である。 私は、日本史で大学を受験し、政治経済学部に入った。一通り、政治学も経済学も頭に入っている。専攻は「社会経済地理学」というやつで地理である。公務員試験のために憲法や行政学を、そのあと、会社員を経て、資格試験のために、民法なんかも何年も勉強した。 本気で深いところから教えようとしたら、中学校の社会は範囲が広いゆえに、いろいろ難しいことばかりである。知り過ぎているのも教え加減が難しい。中学生が中学校の教科書(特に歴史)が理解しずらいのは、よく理解できる。間違いは慎重に回避されているものの、微妙なところは、うまくごまかされてしまう。
2015.05.18
コメント(0)
-
修学旅行を覚えてますか
来週から市内の中学3年生は各中学校入れ替わりで奈良、京都に修学旅行です。 塾日程としては苦しいところですが、中学の修学旅行も一生に一度しかないことですから生徒のみなさんには楽しんできてほしいものです。 京都市内は数人のグループでタクシー観光なので、金閣寺や銀閣寺といった定番を外して、意外と風変わりなところを見てくる生徒も多いようです。 京都はどこに行ってもおもしろいし、どこに行かなくてもおもしろいです。大人だと博物館とか美術館とかもいいです。 私は中学のときは京都、奈良、伊勢と行ったはずなのですが、どこに行って何を見たか、ほとんど何も覚えていません。奈良から伊勢への近鉄電車が山深いところを走っていたことだけは、なぜか強くイメージに残っています。 下妻一高で島根、鳥取に行って蒜山高原で焼肉を食べた人は私の同期です。前年と違ったところへということで広島からバスで中国山地を縦断したのですが、不評で翌年は取りやめになりました。あとから、ふりかえれば松江城、鳥取砂丘、玉造温泉、姫路城となかなか渋いコースを廻ったようです。 このときについても個々の場所の記憶はほとんどなく、ひたすら山の中をバスに乗っていたことくらいしか覚えていません。 一番印象に残っているのが、友人のK君が洋式便器の使い方がわからず、様式便器を和式スタイルで利用して驚いたという修学とは全く関係のないことです。 ちょうど高校から大学にかけての時期が日本人の生活スタイルの入れ替わりの時期だったんです。 当時は飛行機禁止だったので、沖縄や外国という選択肢は、ありませんでした。 下妻の周りの中学校は、ほとんどの生徒が中学時代に京都、奈良に行っていたので、高校では広島(必須)、そこからは年によってオプションという感じでした。ただ、一部の人は中学時代に富士、箱根で結局、修学旅行で京都に行かずじまいの人もいました。 みなさんの修学旅行はどんなものだったでしょうか。
2015.05.16
コメント(0)
-
5月、6月、7月 塾講師が忘れがちな視点
学習塾の講師で、朝の6時に起床している人は、いないはずである。本来、人間は、朝日を拝むことから始まるべきであるが、塾の講師で日の出が何時なのわかっている人は少ないはずである。まして、朝の7時からグランドを5周走ったりしている人はいない。塾講師の場合、 通常勤務時間は午後からのはずである。「勤務時間9:00~23:00」などという求人票を出したら労働基準法に違反してしまう。 しかし、生徒の方は夏の間、生活時間が長い。塾に来るのは、部活の朝練から始まる非常に長い一日の諸々をすべてこなした後ということになる。そのあたりをよく考えないといけないと思うのである。「気合いが足りない。」とか「集中力に欠けている。」というのは簡単だけれども、生徒の一日の中の余力・余裕という点からも考えなければいけない。特に1学期の塾は、効率と効果という視点もとてもたいせつである。 私の塾は祝日営業なのだが祝日の集中力は平日に比べて高い。学校で頭を使ってないからなのかもしれないが、頭も遊んでしまいそうな祝日が一番勉強が進むというのは、初めは、やや意外なことであった。
2015.05.14
コメント(0)
-
野山をかけまわらない田舎の人
坂東市のように、電車が走っておらず、バスもないというような田舎だと、都会の人は日常生活のために野山を歩き回っている印象があるかもしれないが全く反対である。 私など50メートル以上の距離は車移動である。 そのため、たまに上京して、30分も電車の中に立っていて、それから地下鉄の階段を登って路上に出て、さらに目的地まで5分も6分も歩くというようなことを一日何度か繰り返して地元に戻ってくるとヘトヘトになる。足腰が痛い。太腿やふくらはぎが張る。 田舎の人からみると、都会の人は駅までの往復や階段の昇り降りだけでも、十分に運動していると思う。 子どもたちは徒歩か自転車通学なので運動面での不足はないと思うけれども、外に遊ぶ場所がないので、部活以外は家にこもってゲームばかりしがちになる。特に小学生は部活がないのでそうなりがちである。学校か家か。お出かけは通常は親と一緒に車でということになる。 大人は意識的に歩いている人が非常に多い。私の自宅の周りも時間を問わず常に誰かが歩いている。県内あちこち出かけるが、こんなにウォーキングが好きで継続されている市もそうないと思う。市が特別に呼びかけたようなことは一度もないはずだから、自発的な健康留意の意識は素晴らしい。 その点、子どもたちには特に外出モチベーションがないので、部活には引きこもり防止という機能もあるのかもしれない。塾も同様か。
2015.05.13
コメント(0)
-
電子教科書でどうなる?
私は超アナログ人間である。本は装丁や質感もあってこそだと思うし、音楽も可能であればLPレコードに戻りたいくらいである。 しかし、医院があっという間に電子カルテになったことを見ても、学校の方も教科書や定期テストが電子化されるのは、そう遠いことではないかもしれない。一度、導入されると速そうである。理科は教科書に動画が盛り込めたり、教科書上で自分で実験できたりすると、どの分野の学習においても、かなり有用な気がする。数学はどうなんだろう。空間図形や動点なんかは、かなり変わりそうだ。それが能力の向上につながるのかどうかは、よくわからない。現在、数学で「上の上の成績」の生徒は紙の上に書かれた立体の見取り図をみて自分の頭の中を電子化できる生徒なわけで、そこに余計な補助が入ってしまうとすれば、そのせいで何か欠けてきてしまう能力もあるのかもしれないと思うのである。
2015.05.12
コメント(0)
-
セカンドオピニオンにほっとする
昨日のブログで書きました通り、先週、「ポリープ様声帯」で、一ヶ月様子見て状態が変わらなければ手術と言われて、「えー、これから一ヶ月も声が出ないの?そんで、それから手術?」と内心、冷や汗タラタラ、「どうすっかなあ」(どうしたらよいのだろう)と困惑、混乱した週末を過ごしたのですが。。 今日は、あれこれと十分に調べて検討した上で、つくばの某クリニックにセカンドオピニオンを聞きにいってみました。 こちらは、前回のドクターのようにご自分だけで画像をみて一方的に状態を告げるのではないようです。 ファイバースコープを入れたあと、画面をこちに向けてくれ、一緒に画像を見ながら、「はい、深呼吸してください。」「止めてください。」「エーと言ってみてください。」と声帯の形をいろいろに動かし、画像を止めたり拡大したりしながら丁寧な説明がありました。 診断は風邪による感染で声帯が腫れてるだけ(ただし、ひどく腫れていて真っ赤、赤)とのことでした。確かに声帯はビロビロしてるらしいのですが、菌を撃退して腫れが引けば、普通の声は出るし、問題はないということで、ホッとしました。 薬も前医院でのステロイドから抗生物質と消炎剤に変わりました。やれやれ。 とにかく塾生、特に3年生には迷惑をかけたくないというのが一番で。あまり、ふだん意識していなくて、自分でいうのも変なのですが、今回、改めて、かなり真面目に来年の入試に向けて取り組んでいるらしいということを自覚したしだいです。 あと、4、5日お聞き苦しいかと思いますがご理解のほどをお願いします。 入試が済んで、それまでは異様なくらいに衛生に神経質だったのですが、新学年になり、やはり、うがい、手洗いなどに油断がありました。
2015.05.11
コメント(0)
-
実はいろいろとありまして
実はいま、市内比較なら、格段に耐震性と断熱、空調などの快適性に優れた平屋鉄骨構造の塾を建設中なのですが。 そんな中、実は声の調子が良くなくて、明日というか今日、セカンドオピニオンを聞きに2軒目に診察にいきます。 喉のポリープ様声帯という症状で、名前とは異なり、ポリープがあるわけではなくて、声帯全体が使い古し状態でひどく、水ぶくれでブヨブヨらしい。専門医がファイバースコープで診察しているので、誤診はありえないと思うけど、1軒目では、程度と見通しを聞けなかったので、その辺を確認してきます。 腫瘍とかそういうわけではなく、ズルズル放置してる人もいるらしいので、私も、とりあえず声を戻して、それからじっくり考えたいのだけど。。 7年前の声帯結節のときのように、いつの間にか治った(わけではないのだが) 発声に支障がなくなれば。
2015.05.11
コメント(0)
-
中3 理科・社会
今日は、理科と社会で実力テスト仕様=県立入試仕様の問題をやってもらいました。理科の大問4の合力と分力、斜面上の台車の問題は、そのまま中間テストにも使える問題です。解説しましたが、しっかり復習しておいてください。 今日の問題は圧力や湿度の問題も出ました。このあたりは、新研究などで、ここだけ抜き出して早めに学習しておくと実力テストの順位が上にいきます。全体正答率が非常に低い分野です。
2015.05.09
コメント(0)
-

母子密着世代
5月4日の日経新聞の記事によると、男子高校生の2人に1人が母親の勧めをきっかけに化粧水を使い始めるという。 40半ばから50半ばの女性は息子とよく買い物に出かけ息子に服を買ってあげるのが好きらしい。 母親と娘は立ち位置が対等で友達のような関係なのに対して、息子は母親に主導権を握られているとのこと。 つい最近も書いたけれども、地方だと物理的に母親の援助なしには高校生活が成り立たないのが現実である。都市部と比べても、より一層母子密着が強いかしれない。
2015.05.05
コメント(0)
-
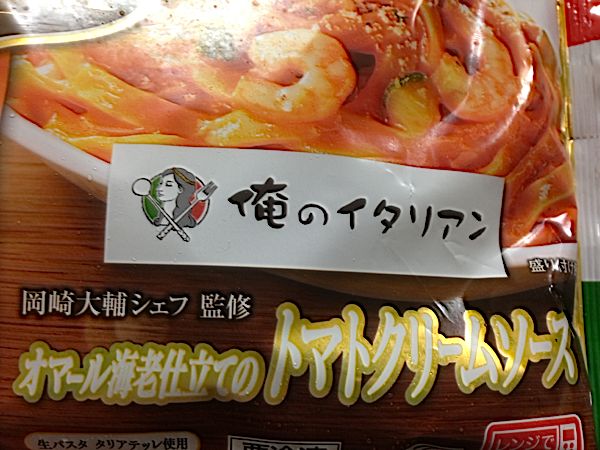
俺の・・・
日清食品冷凍 『俺のイタリアン』 新潮新書 『俺の日本史』 塾名を「俺の塾」にしようかしらん。
2015.05.03
コメント(0)
-
いろいろな人が
今日は所用で午前中に上京。 帰りのつくばエクスプレスの車中で女子高生が這いつくばって、あっち向いたり、こっち向いたりしてるので、「何、やってんだろ。それにしてもちょっと衛生的でないなあ。」と見ていたら、どうも何か落し物を探していて見つからないらしい。その子が座っていた隣の席の女性に「あなたのバッグの中に落ちてませんか?」というようなことになって、その女性もバッグの中を捜させられたりして、ちょっと困惑気味でした。 結局、落し物というのは、コンタクトレンズなんかもそうですが、思わぬ方角で発見するもので、彼女も探していたのとは反対方向の遠くの床上から無事に拾い上げたピアスを自分の左耳におさめることができました。 私は守谷駅で下車。車に乗り換え、塾に向かっていると常総線の踏切で引っかかりました。何気なくバックミラーで後ろの車を見たら、アンチャンが絶叫中でした。ハンドルのところには紙を押さえつけています。どうも歌詞のようです。しきりにそちらに目をやっては顔が歪んだり、頭や肩が揺れたりするので可笑しくなりました。 自分の歌に酔っているというよりは、その曲をかなり一生懸命練習中らしく、上手く歌えない箇所を何度も繰り返しているようです。ずっとシャウトしながら私の車の後ろをついてきました。 昼に休憩に入ったお店では、喫煙スペースしか空いていないと言われて、まあ昔は煙モクモクの中にいたのだから大丈夫だろうと思って、そちらに行ったら、猛烈に気分が悪くなって頭がクラクラクラして早々に退散しました。ほとんどの場所が禁煙になったことで、こんなにも煙に弱くなっているんだということを改めて感じました。 さして重要でない一日でも、あれこれあるものです。
2015.05.02
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 楽天市場
- 楽天ブラックフライデーセール!
- (2025-11-22 01:03:03)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 楽天ブックスで買えたSwitch2本体
- (2025-11-22 00:05:02)
-
-
-
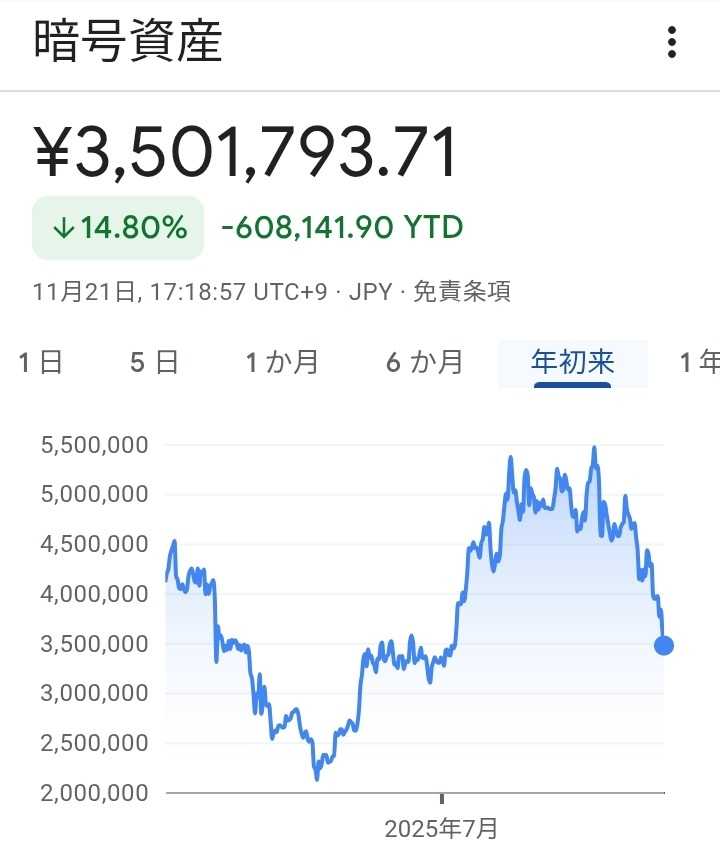
- 株式投資日記
- 久しぶりに日本株資産が増加したが、…
- (2025-11-21 19:50:51)
-







