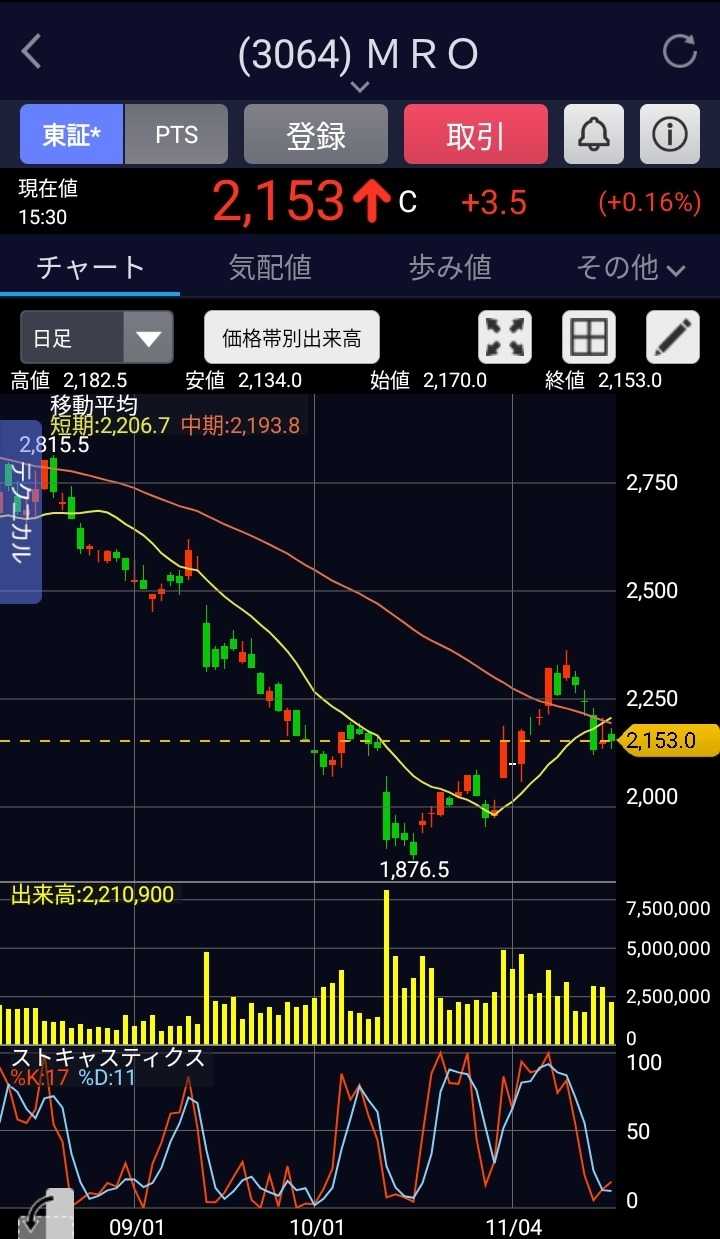2009年10月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
独学者とトンデモ説の親和性、または権威主義的性格について
以前、サルトルの 『嘔吐』 に出てくる 「独学者」 なる人物にふれて、「サルトルの 『嘔吐』 をちらちらと読み返してみた」 なる雑文を書いたことがある。そこで引用した 『嘔吐』 の箇所をもう一度ひいてみる。なお、引用文中の 「彼」 とは、この 「独学者」 を指している。彼は目で私に問いかける。私はうなづいて賛意を評するのだが、彼がいくらか失望したということ、彼が欲したのは、もっと熱狂的な賛同だったということを感じる。私に何ができようか。彼が私に言ったことのすべての中に、人からの借り物や引用をふと認めたとしても、それは私が悪いのだろうか。言葉を質問形にするのは癖なのである。じっさいには断定を下しているのだ。優しさと臆病の漆は剥げ落ちた。彼がいつもの独学者であるとは思われない。彼の顔つきは、鈍重な執拗性をあらわしている。それは自惚れの壁である。 ウェブにはこの種の人は珍しくない。なにしろ、ちょっとした手間と暇さえかければ、誰でも簡単にネット上にホームページやブログを作成して、そこになにやら 「独創的」 な研究成果を発表するぐらいのことはできるからだ。正直に言うと、昔、傾倒していた人を扱ったこの手の 「論文」 を見かけ、いささか感じたことがあったため、しばらくメールでやりとりしたこともある。 最初から、表面上はていねいな言葉の中に、なにか傲慢さを感じさせる 「慇懃無礼」 な雰囲気があって、???という気もした。なので、そこでやめとけばよかったのだが、ついつい疑問点をいくつか並べて書き送ったところ、いきなり 「あなたはまだまだ勉強が足りないようですね」 といった類の傲岸不遜な返事が返ってきた。どうやら、その人の自尊心をいたく傷つけてしまったようであった。 別に、「独学者」 一般を誹謗するつもりはないし、勉学や研究の環境が整わない中で 「独学」 を続けるということは、むろん賞賛さるべきことではある。しかし、サルトルも指摘しているように、「独学者」 にはしばしば 「夜郎自大」 という痼疾がついてまわる。いったい、それはなぜなのか。 以前の記事では、「それは 「独学」 という行為が必然的に孤独な作業であることから来るものだろう」 と書いたが、どうもそれだけではなさそうだ。じっさい、すべての 「独学者」 がそのように夜郎自大というわけではない。むしろ、それは個々の 「独学者」 が 「独学」 を続けているモチーフ、それもおそらくはその人自身も気づいていない、もっと奥の秘められたところ、一言でいえば 「自尊心」 の満足ということにあるような気がする。 「自尊心」 というものは、たしかにだれもが有するものであり、その満足は人間の本源的な欲求のひとつでもある。そして、「独学者」 にとって、もっともその 「自尊心」 を満足させることはなにかといえば、おそらく 「独創的」 であることだろう。たしかに、「独創的」 であることは 「独創的」 でないことよりも評価される。だが、いうまでもなく、「独創的」 な研究などというものは、そう簡単に生まれるものではない。 極端な例を出せば、1+1の答は誰が計算しても2である(2進法の場合は除く)。少々難しい方程式だって、それを理解できる人が正しい解法を用いて、間違いを犯さずに計算すればみな答は同じになる。たしかに、ややこしい問題とかであれば、その過程で多少の独創性が発揮される場面もないわけではあるまいが、答は一緒なのだから、その意味では「独創性」 が発揮される場面などはない。 だから、一般的に言うなら、「独創性」 が必要とされ、また 「独創性」 が発揮されるのは、「未知の領域」 ということになる。だが、「未知の領域」、すなわちいまだ解決されざる問題を見つけるには、その分野において、現時点でどこまでが既知であり、問題がどこまで解決されているかをまず知らなければならない。 「独創性」 を発揮すべき 「未知の領域」 とは、いわば雲の上に突き出ている富士山の頂上のようなものだ。だが、そこまでたどりつくには、えっちらおっちらと麓から自分の足で登っていかなければならない。ヘリコプターでいきなり頂上に降り立ったところで、それは富士を征服したことにはならない。だから、それはそう簡単なことではない。 「独学者」 の多くが、ときにはトンデモ学説ですらあるような、世間の 「常識」 から離れた説に引き付けられがちなのは、おそらくそのためだろう。それは、本当の 「独創性」 を発揮するための前提として必要な、自分が 「知らない」 ということを知るための努力を不要にしてくれるだけでなく、自分が世間の常識を超越しており、したがって世間の人々より上にいるかのごとき勘違いによって、自尊心の満足にも役立つという非常に便利なツールでもある。 たとえば、「常識を疑え」 という人たちは、コペルニクスはプトレマイオスの天動説を疑った、ガリレオはアリストテレスの運動論を疑った、ラボアジェはフロジストン説をひっくり返した、ウェゲナーは大地は動かないという常識に挑戦した、などという例を持ち出す。たしかに、それまでの常識をひっくり返したこの種の 「大発見」 は、科学の歴史にはことかかない。科学の進歩とはそういうことだ。 しかし、彼らにそれが可能だったのは、それまでの 「常識」 では説明できぬ未知の問題にぶつかったからであり、あるいは 「常識」 であり、解決済みであるとされていたことに、じつは未解決の問題が潜んでいるのに気づいたからだろう。どちらにしても、それにはそれまでの 「常識」 について、ふかく理解することがまずは前提になる。そこで必要なのは、「常識」 なるものを無批判に受け入れることでもなければ、頭ごなしに否認し、ただ投げ捨てることでもない。 さて、興味深いのは、このように 「世の常識」 や 「学界の常識」 とかに挑戦している人らの多くが、じつは彼らなりの固有の 「神」 を持っているという事実である。それはたとえば、政治・社会関係であれば副島隆彦や宮台真司であったりするのだが、同じような 「神」 は、医療や看護関係にも、物理学や宇宙論といった分野にも、また史学や思想・哲学といった分野にもいるだろう。最近では、こういった神様もじつに多様である。 むろん、それらはピンからキリまであり、十把一絡げに扱うわけにはいかない。「神様」 扱いされてるからには、それなりの力量や資格、実績を備えている人もむろんいるだろうし、馬鹿な弟子がいるからといって、それがすべて師匠の責任というわけでもない。どんなに偉いお師匠さんにも、師の教えを理解できずに誤解したり、ただの無意味な呪文にしてしまったりする不肖の弟子というのはいるものだ。それは、かの親鸞さんについてすら言える。 ただ、このことからは、そのような人の多くが、じつはフロムの言う 「権威主義的性格」 を備えているのではという印象を強く受ける。一般に 「権威主義的性格」 は、権威への服従を好むマゾヒスティックな性格と、権威を振りかざすことを好むサディスティックな性格の統合というように理解されている。これがただの小物であれば、自己の服属する権威のもとで、その権威を振りかざしたがる、いわゆる 「虎の威を借るキツネ」 ということになる。しかし、その一方で、フロムは次のようなことも指摘している。 権威主義的性格には、多くの観察者を誤らせるようなもう一つの特徴がある。権威に挑戦し、「上から」 のどのような権威にも反感をもつ傾向である。時にはこの挑戦がすみずみまでいきわたり、服従的傾向は背景に退くこともある。このタイプの人間はつねにどのような権威にも ―― じっさいにはかれの利益を助長し、抑圧の要素をもたない権威にも反逆する。ときには権威に対する態度が分裂する。すなわちある権威に ―― とくにその無力に失望した権威には抵抗するが、やがてより大きな力と約束によって、マゾヒズム的な憧憬をみたしてくれるように思われる、他の権威には服従する。...... かれらは内的な強さと統一性によって、自由と独立を妨げる力と戦う人間であるかのように見える。しかし権威主義的性格の権威に対する戦いは、本質的に一種のいどみに過ぎない。それは権威と戦うことによって、かれ自身を肯定し、かれ自身の無力感を克服しようとしている。そして他面では意識的であれ、無意識的であれ、服従へのあこがれが残っているのである。権威主義的性格は 「革命的」 ではない。私は彼を 「反逆者」 とよびたい。『自由からの逃走』 このフロムの著書はナチズムの分析を主題にしたものだが、この指摘は、たとえば反権力や反権威、超俗性などをかかげた組織や集団の中に、しばしば、彼らが挑戦しているはずの権威とそっくりの 「対抗的権威」 が形成されるのはなぜかも説明してくれる。
2009.10.25
コメント(1)
-
風と桶屋の関係、またはバタフライ効果
気象学にバタフライ効果という言葉がある。Wikipediaによると、これはエドワード・ローレンツという人が1972年にアメリカ科学振興協会でおこなった講演のタイトル、『予測可能性-ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか』 に由来するということだ。 これはむろん一種の比喩であり思考実験なのであって、どこかでの蝶のはばたきが、実際につねにどこかに竜巻を引き起こすというわけではあるまい。だいいち、そんなことがあちこちでしょっちゅう起きていては、たまったものではない。 難しい数学はちんぷんかんぷんだが、ようするにカオス理論なるものによれば、「カオスな系では、初期条件のわずかな差が時間とともに拡大して、結果に大きな違いをもたらす。そしてそれは予測不可能」 ということらしい。いや、そういうふうに言われても、やっぱりよく分からない。 昔の人は、「風が吹けば桶屋が儲かる」 と、なかなか洒落たことを言った。これは、「大風で土ぼこりが立つ → 土ぼこりが目に入って盲人が増える → 盲人は三味線を買う → 三味線に使う猫皮が必要になりネコが殺される → ネコが減ればネズミが増える → ネズミは桶を囓る → 桶の需要が増え桶屋が儲かる」 ということらしい(ネコさん、ごめんなさい)。 世界は様々な事象で満ちている。無から有はけっして生じないのだから、いかなる事象も、必ずどこかに原因を有する。上の命題は 「風が吹く」 で始まっているが、その風だって、吹いたのには、誰かが大きな口をあけてふーと吹いたか、吸い込んだか、あるいは台風の接近だとか、なんらかの原因によって気圧の差が生じたことによる。 そういう因果の連鎖をたどっていけば、それこそ宇宙がドカンと誕生したというビッグバンにまで遡るだろう。それに、風が吹いた結果のほうも、「桶屋が儲かる」 で終わるわけではない。たとえば、「桶屋が儲かると、近在にその噂が広まる → 噂を聞いて盗人が押し込みにくる」 などというように、その結果はさらに未来に向かって続いていくだろう。 いや、それだけではない。あるひとつの事象を決定する原因はたったひとつではない。ボールが窓に当たったとしても、それで実際に窓が割れるかどうかは、ガラスの厚さや強度、当たったボールの硬さや速度にも左右される。 それに、ひとつの事象から、枝分かれするようにいろいろな結果が同時に生まれることもあるだろう。世界の中では、いまここで風が吹いているだけでなく、その横ではカラスがカーと鳴き、ネコがニャーと鳴いているかもしれない。田中さんの家では夫婦喧嘩の真っ最中だが、公園では若いカップルがいちゃいちゃしているかもしれない。 世界の中では、つねに複数の事象がたがいに関連しながら、あるいは独立しながら、同時多発的に発生している。そして、そのような事象は、場合によってはたがいに影響を及ぼしながら、時系列にそって発生し、変化し、あるいは消滅する。これはまさに混沌とした世界である。 たとえば、17世紀にオランダにいた哲学者のスピノザはこんなことを言っている。定理28 あらゆる個物、あるいは有限でかぎられた存在を持つあらゆるものは、自分と同じように有限でかぎられた存在を持つ他の原因から、存在や作用へと決定されることによって、はじめて存在することができるし、また作用へと決定されることができる。さらにこの原因も同じように有限でかぎられた存在を持つ他の原因から、存在や作用へと決定されることなしには、存在することもできないし、また作用へと決定されることもできない。このようにして無限に進む。『エティカ』 第一部 「神について」 より だが、このようにすべての事象が因果関係の連鎖でつながっているとしても、そのことはただちに、すべての事象が必然性によってつながれた必然的に発生したものであるということは意味しない。長い因果の連鎖をへて、いまここで発生した事象のすべてが、いかなる偶然性も含まない完全な必然性によって生じたというには、すべての因果の連鎖が、最初のドカンという宇宙誕生(スピノザなら 「神」 というだろうが)の時点において、すでに決定されていたと言わなければならない。 そのような長大で、しかも相互に絡み合っている複雑な連鎖の計算は、どんなに巨大な計算機をもってしても不可能だという技術的理由はともかくとして、すべての事象の連鎖が世界が誕生した時点で決定されていたと考えるのは、どう考えても無理だろう。結果から原因を探ることは可能だとしても、因果によって生じる結果なるものは、つねに一義的とは限らない。そこにはつねにいくらかの幅や揺らぎが存在する。もっとも、全能の神様ならば、そのすべてを予見していたかもしれないが。 それに、いったん成立した個々の事象や存在は、ただ外的要因によって左右されるだけでなく、程度の差はあれ、自律的な自らの 「本性」 も持っている。煌々とともる電灯に集まってくる蛾や蚊のみなさんには、光の誘惑に抵抗するだけの自由はないのかもしれないが、彼らとて、たんなる刺激に対する反応によってのみ生きているわけではないだろう。 話はがらっと変わるが、のちにスターリンによって 「右翼的偏向」 と批判され、最後には 「裏切者」 の汚名を着せられて処刑されたブハーリンは、『過渡期経済論』 の中でこんなことを書いている。恐慌は拡大し、波のごとく伝わるが、これは、体制内の一部分における均衡破壊が、ちょうど電信線によって伝わるみたいに、その各部分へと不可避的に拡がるからである。世界経済の諸条件のもとでの戦争が ― 一か所における均衡破壊を意味したものが ― 不可避的に、体制全体の大動揺に、世界戦争に転化した。 これが書かれたのは、ニューヨークはウォール街での株暴落を原因とする世界恐慌が勃発した9年前のこと。彼がのちのような 「右派」 ではなく、レーニンの主張する屈辱的な対ドイツ講和に反対していた 「左派」 だった頃の著作である。なので、その主張には極左的な単純化傾向がいささか強い。 世界経済のネットワーク化とは、つまり世界中の地域経済の相互依存が極大に達することだ。その結果、ブハーリンが指摘した、ネットワークを通じた危機の伝播と増幅という傾向もたしかに生じはするが、それと同時に、リスクの拡散と危機の局所的爆発の回避というそれとは反対の傾向も存在する。ある時点においてどちらの傾向が強いかは、一概には言えない。 しかし、たとえば、いまここで1000円を支出してなにかを購入した場合、その1000円はどこへどのように流通し、どのように分割され、最終的にどこにどのような影響を与えるか、それは市場の専門家などでない限り、ほとんど誰にも分からない。 むろん、たとえその結果がわからぬとしても、たった一人によるたった一回きりの行為であるなら、たいした影響はないかもしれない。しかし、それと同じ行為を1000人、10000人、いや10万人の人が毎日繰り返したなら、いったいどこにどのような結果が生じるのか。 その結果、たしかに誰かは儲かるだろうが、その反対に、どこかの店が倒産し、誰かが職を失うといったことが絶対に生じないとは、たぶん誰にも断言できぬだろう。これもまた、冒頭で引用したバタフライ効果のようなものである。われわれは、まことに混沌とした世界に生きている。 それはまるで、次の一歩を右脚から踏み出すか、左脚から踏み出すかに、世界の存亡がかかっているといった妄想に突然とりつかれた結果、その場に立ち尽くし、ついに一歩も動けなくなったという狂人が住んでいる世界のようなものである。 だが、それでも人は生きていかなければならないとしたら、そのようにただ立ち尽くしているというわけにはいかない。結果がどうなるか分からないからといって、次の一歩を右脚から踏み出すのか、それとも左脚から踏み出すのかの決断を、永遠に回避し続けるわけにはいかない。できることは、せいぜい可能な限り、自己の行為が及ぼす結果について事前に考え、予測しておくといったことにすぎないだろうが。 ところで、スピノザというと、「空中に投げられた石にもし意識があれば、自分の自由意志で飛んでいると思うだろう」 と言ったとかいう話があり、これは人間の意志の自由を否定したものと解釈されている(中公版の 『エティカ』 にはたしかに石を使った比喩はあるのだが、この言葉は見つからなかった。はて?)。 しかし、彼は人間の自由というものをすべて否定したわけではない。実際、『エティカ』 には、「自由な人間はなによりも死について考えることがない。そして彼の知恵は、死についての省察ではなく、生きることについての省察である」 というような定理もある。 彼は、その第三部 「感情の起源と本性について」 の定理2の長い注解の中で、「人々が自由であると確信している根拠は、彼らは自分たちの行為を意識しているがその行為を決定する原因については無知であるという、ただそれだけのことにある」 と述べている。 それはつまり、人はなんらかの行為を行ったとき、あるいは行わないとき、それを決定した自分の意志をただ無根拠に 「自由」 と称するのではなく、それがいかなる原因によって生じたものか、いかなる根拠によって制約されたものか、それをまずは省みよ、ということだろう。彼の言う人間の自由とは、おそらくその先に見えてくるものなのだ。 「限界」 を超えるための前提は、まずその 「限界」 がどこにあるかを知ることだ。同様に、自分が抱えている 「偏見」 や 「偏向」 から自由になるために必要なのは、そのような 「偏見」 や 「偏向」 をまず自覚することだ。それは、無意識の抑圧の意識化による解消という、フロイト先生が提唱した 「精神分析」 でもたぶん同じことだろう。追記:バタフライ効果をネタにした一日違いの記事を発見 暴力も責任も地続きなので線引きしましょう
2009.10.21
コメント(0)
-
あれやこれやの雑感
鳩山内閣が誕生してはや一ヶ月である。長かった自公政権の後始末がたいへん、というのは分かるのだが、予算やら事業の見直しやらと、まだまだ前途は多難のようだ。鳩山由紀夫という人については、いまひとつよく分からないのだが、なんとなくやはり昔の細川護煕氏と同じ、育ちのよさからくる軽さが感じられる。いや、人の良さからくる能天気さのほうは、むしろ細川氏以上なのかもしれない。 たしかに、内閣のメンバーを見れば、前の内閣などにくらべて、なかなかの論客と実力者ぞろいのようだ。だが、そのことがかえって内閣のアキレス腱になるおそれというのもなくはない。つまり、はたして今の鳩山氏に、論客であり野心もあるであろう人がおおぜいそろっている内閣をまとめるだけの力があるのだろうかという疑問だ。国民新党の静香ちゃんなどは、どう見ても首相より大きな顔をしている(物理的な意味だけじゃなく)。 どこに書いてあったかは忘れたが、かつてE.H.カーは、レーニン率いるボルシェビキ政権について、「ヨーロッパで最も知的水準が高い政府」 と評したことがある。当時のボリシェビキ政府には、レーニンとトロツキーをはじめとして、多士済々の人材がそろっていた。その多くが長い外国生活の経験があり(むろん、昨今のようなのんきな留学などではなく亡命を強いられたことによる)、何ヶ国語も自由にあやつることができる国際人であり、また科学から文学や歴史まで高い教養も有していた。 そういう一言居士のようなうるさ型の船頭ばかりの政権が一つにまとめられたのは、内外からの脅威は別にすれば、むろん卓越した指導者としてのレーニンの権威によるものだが、そのレーニンですら、ドイツとの屈辱的な講和をめぐっては反対派の執拗な抵抗に悩まされ、「そんなこと言うなら、おれは辞めるぞー」 といって、党を脅さなければならないことがあったくらいだ(なんだか、小沢さんみたい)。 それは維新直後の明治政府でも同じで、薩長のほかに土佐・肥前、旧公卿などからなる政府が、かつての主君であった島津久光のような頭の固いお殿様や、随所に残る頑迷な攘夷派などの抵抗を押し切って、その後の発展の基礎をすえた改革を進められたのには、なんといっても、維新後いったん帰郷しながらも、大久保らの説得を受けて政府に戻った西郷の存在が大きいだろう。 さて、「男だったら流れ弾のひとつやふたつ 胸にいつでもささってる」 というのは、31歳で自殺した沖雅也が主演していたTVドラマの主題歌、「男たちのメロディ」 の一節であり、「男は誰もみな 無口な兵士」 とは、オーディションで合格したばかりの薬師丸ひろ子が14歳でデビューした映画、「野性の証明」 の主題歌 「戦士の休息」 の台詞である。また、沢田研二はヒット曲 「サムライ」 の中で、「男は誰でも不幸なサムライ」 と歌っている。 とはいえ、それは別に男だけにいえる話ではない。なので、そこで 「男は~」、「男は~」と連呼されると、いささか鼻白むむきもいるかもしれない。たしかに 「男のロマン」 がどうしたとか、「どうせ女には~」 などとやたらと言いたがる人というのは、たいていはただの 「自己陶酔」 型の人間か、「自己慰謝」 の好きな甘ったれた人間である。それに、そもそもそういうことは、上の歌にもあるとおり、それまでよほど運が良く、また恵まれていた人でない限り、誰にでもあてはまることである。 つまるところ、あえて口に出そうが出すまいが、何十年も生きていれば、たいていの人は脛とか背中とかに、触れるとまだ痛むような 「傷」 のひとつやふたつは負っているということだ。そして、そういう 「傷」 は良い悪いに関係なく、重ければ重いほど、その人にとっての不可欠な一部となる。それは、その人にとって肉体の一部であり、積み重ねられてきた経験の一部であり、長い間に堆積された時間の証でもある。 ただし、えてしてそういう 「傷」 は、気づかないうちに社会や他者に対する認識、そしてむろん自己についての認識にも、なんらかの 「偏向」 をもたらすことが多い。それは普段はそれほどでなくとも、そのような 「傷」 にどこかで触れるような問題にぶつかった場合に、突如として発動されたりもする。 たしかに、人間の認識に必要な意識とは、それ自体主観的な作用であり、ただの鏡やカメラの中のフィルム(古い!)ではないのだから、それもある程度はしかたない。だが、ただの借り物の言葉を振り回すような人はともかく、たとえばけっして愚かとは思えないような人とかが、自分の言葉がブーメランとなって、そのまま話者自身にはねかえっているのに気づかないのには、たぶんそういう理由があるからなのだろう。 しかし、誰を相手にしているのか知らないが、「あなたたちとは違うんです!」 みたいな 「優越感」 ゲームをネット上でやっている人とかを見ると、「おいおい」 などと思ってしまう。どんな分野であれ、専門的な知識や経験とかは 「素人」 の皆さんに分け与えるものであって(むろん、すべて無償でとまでは言わないが)、「素人」 に対してふんぞり返る 「自己正当化」 のために持ち出すものではない。 で、そういう「対立」 みたいなものをさらにややこしくしているのが、「敵の敵は味方だ!」 とか 「敵の味方は敵だ!」 というような単純かつ粗雑な論理で、勝手に 「敵」 認定や 「味方」 認定をしている人。 勝手な 「敵」 認定が迷惑なのはもちろんだが、勘違いした勝手な 「味方」 認定というのも、たぶんそれにおとらず迷惑なものである。どこをどう読んだら、その人が自分の 「味方」 だと認定できるのか、はたで見ているとさっぱり分からない場合もあるのだが、そういう人は、そもそも根本的に理解力や読解力に難があるのだろう。 なにを勘違いしたのか、自分が 「敵」 認定している人とほとんどかわらぬことを、ただし反対側からとか、ちょっとばかし異なる発想やレトリックを使って言っているにすぎないような人を、勝手に 「味方」 認定している人もいれば、どう考えても、あなたが考えているほど単純な人ではないよという人を、自分の 「味方」 だと思っているような人もいる。 たぶん、そういう人は、勝手に 「味方」 認定して、すりすりと擦り寄った相手が、実は画面の向こうでしんそこ困った顔やうんざりした顔をしていたり、ときには腹の中で 「お前が言うなー」 とか 「それはお前のことだよ」 などと思っているかもしれないなんてことは考えもしないのだろう。もっとも、「敵の敵は味方だ!」 なんて粗雑な発想をする人は、そもそも頭の中が最初から粗雑なのだろうからこれまたしかたあるまいが。 最後はまったくの余談だが、安保だの沖縄だのといった問題を全面展開したあげく、「君はどうするんだ? 許すのか、許さないのか」 みたいな論法でせまるのは、たしかに昔からよくあったオルグ作法のひとつである。このような論法が、ときとして 「詐術」 めいて聞こえるのは、たぶんある特定の問題へのコミット、つまり、そのような問題に対する責任の引き受けということが、いつの間にか○○同盟だの○○派だのといった、特定の政治的立場へのコミットということにすり替えられているからだろう。 そういうすり替えというのも、多くの場合、オルグしている本人自身が気づいていない。つまり、そういう論法を使う人自身が、頭の中で上にあげた二つの問題の違いに気づかず、無意識に等置しているということだ。しかし、この二つを等置し混同することは、その意図がどうであれ、結局は自派の勢力拡大のために個別の問題を利用するという 「政治的利用主義」 の現れにすぎない。 かりに、ある人がそのような責任を認めたとしても、それをどのような形で引き受けるかは、それぞれが自己の責任で判断すべきことである。ある問題について、自己の責任の存在を認めるか否かということと、その責任を個人がどのような形で引き受けるか、ということとはいちおう別の問題なのである。私はだれか? めずらしく諺にたよるとしたら、これは結局、私がだれと 「つきあっているか」 を知りさえすればいいということになるはずではないか?アンドレ・ブルトン 『ナジャ』 の冒頭より
2009.10.16
コメント(2)
-
「認知的不協和」またはイソップのキツネ
「認知的不協和」(cognitive dissonance)とは、人が自身の中で互いに矛盾する認知を同時に抱えた状態だとか、そのときに覚える不快感を表す社会心理学の用語で、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガー(1919-1989)という人が提唱したのだそうだ。 この人によれば、「認知的不協和」 が存在すると、その不協和を軽減し除去するための心理的圧力が生じ、その結果、どちらかといえば不都合な一方の要素が無意識のうちに修正されて、「不協和」 な状態が軽減されたり除去されるということだ。 この理論の説明でよく言及されるのが、イソップ寓話にある 「キツネとブドウ」 の物語である。これは誰でも知っているだろうが、ある日、美味しそうなブドウがなっているのを見つけたキツネが、一生懸命とびあがって獲ろうとしたものの、どうしても届かない、それで最後に 「どうせあのブドウは酸っぱいんだ」 といって諦めたという話である。 キツネとしては、一方に 「渇いたのどを潤したい」 という欲求があり、他方に 「美味しそうなブドウ」 が樹になっているぞ、という認知がある。ところが、どうしても届かないため、「美味しそうなブドウ」 という認知を 「すっぱいブドウ」 という認知に変えることで、ブドウに対する欲求を断念したというわけだ。 この場合、キツネとしてはどうしても手に入らないブドウのことでいつまでもうじうじしているよりも、さっさと諦めて、別のものを探したほうが現実的であり生産的でもある。なので、「それは現実逃避だ!」、「事実から目をそらした自己正当化だ!」 などといってことさらに非難する必要はあるまい。 そもそも人間、なんでもかんでも可能なわけではないのだから、理屈がどうであれ、そのような心理的機制によって、かなえられない欲望がおさまり、心理的な安定が得られるのであれば、それはそれでよい。これに限らないが、人間の心というものはなかなかよくできている。 しかし、問題は 「認知的不協和」 の対象がブドウのような物ではなく、「他者」 という人である場合。その場合、これはしばしば過大な 「自己評価」 の幻想による維持を意味し、その結果、「他者」 とのコミュニケーション不全をもたらすおそれも出てくる。 人間にとっては、たしかに自己の精神的安定が第一なのだから、競争や争いに負けたときに、「本気じゃなかったんだよ」 とか 「おれだってやればできるんだよ」 などといって自分を慰めるのはしかたあるまい。ただ、そういうことはあくまで内心にとどめておくべきで、公言してしまっては恥ずかしい。 吉本新喜劇の池乃めだかの 「今日はこれぐらいにしといたるわ」 というギャグが受けるのは、それがただの 「負け惜しみ」 であることが誰の目にも明白だからだが、よく考えると、たいていの人はそれと大差ないことをどこかでやっている。 自分が人から批判されるのは、彼らがわたしを妬んでいるからだ、という理屈で自分を納得させるのもそうだし、自分が誰にも相手にされないのを、自分はみなに一目置かれているのだというようにすりかえて自分を慰めるのもそうだ。こうなると、もはや病膏肓の域に近づいてくる。これは、もはやただの 「自我肥大」 か 「自意識過剰」 にすぎない。 これが意味するのは、自己と自己をめぐる状況について客観視ができないということだ。そして、そのような 「自己客観視」 の不能は、ただの自己正当化による 「認知的不協和」 の解消にますます拍車をかけることになる。その結果、ニワトリとタマゴのような関係が生じ、どっちが原因でどっちが結果なのか、もはや分からない状態になってしまう。 これはとくに自尊心の高い人ほど陥りやすいものだが、そのことはつまり、この 「病」 はかならずしもたんなる 「劣等感」 の所産とは限らないということ、言い換えると、それなりに高い才能や能力を有する人でも、このような 「病」 に罹患するおそれはあるということを意味する。実際、漱石や芥川のような才人であっても、こういう 「病」 から完全に逃れることはできなかったのだから。 漱石と並べるわけではないが、最近で言うなら、五輪招請の失敗をめぐる、石原都知事のブラジルとフランスなどとの裏取引を示唆するかのごとき発言もそうだろう。彼の過去の発言を振り返ると、招請失敗の最大の責任は彼自身にあるとしか思えないのだが、結局、彼はそういった事実や現実を認めたくないために、無意識に 「認知」 の修正をやって、責任をよそに転嫁しているにすぎないように思える。 ところで、今日10月10日は中国では双十節と呼ばれ、1911年に長江中流の都市、武昌(現在は対岸の漢口との合併によって武漢となっている)で、政府による鉄道国有化政策をきっかけとして軍隊の蜂起が起こり、全国に波及して清王朝が倒れた辛亥革命が始まった日でもある。 以下は、「日本改造法案大綱」 を書いて陸軍を中心にした青年将校らに影響を与えたため、2.26事件の首謀者として処刑された北一輝の 『支那革命外史』 序からの引用である。相抱いて淵に投じた二人の中、一人は眠りから覚めなんだ。一人は蘇生した。蘇生した一人が倒幕革命の一幕を終わってむなしく墓前に哭した時、頭をめぐらせばすでに十有余年の夢である。不肖また支那の革命にくみして十有余年、まことに一夢のごとし。ろくろく何事をもなすあたはざりし遺憾は盟友らの墓石に対するもこころよくない。清朝転覆の一幕、盟友らにとりて何程のことであらう。非命にたおれた宋教仁・范鴻仙君らの悽慘な屍を巻頭に弔らひ掲げて、ひとり暗涙をのみつつ、筆を執っていた六年前の不肖自身の心中が悲しまれる。 文中、「相抱いて淵に投じた二人」 とは、薩摩藩の開明的藩主島津斉彬が急死したのち、錦江湾にともに身を投げた西郷隆盛と僧月照のことを指しているのだろう。月照は安政の大獄で幕府から終われる身となり、西郷とともに京都から薩摩に逃亡したが、斉彬の死による藩政の変化により追放を命じられたたため、悲観して西郷とともに身を投げたということだ。 北のこの書のすぐれている点は、列強の進出に苦しむ 「後進地域」(今ふうに言えば 「第三世界」)における革命運動が、ときとして排外的でもあるナショナリズムの高揚を伴うことの必然性を理解していたところにある。それは、いうまでもなく幕末の倒幕運動が攘夷からはじまったことの意味を、彼が正確に認識していたからでもある。 彼が、アメリカかぶれの孫文を評価せず、その最大のライバルであった宋教仁を支持したのはそのためだが、その結果、上海で起きた宋教仁暗殺の黒幕を、袁世凱ではなく孫文だとしたのはいただけない。しかし、それもまた、イソップのキツネと同じ 「認知的不協和」 のもたらしたものなのかもしれない。関連記事: 「自己イメージ」 の歪み、あるいは 「認知的不協和」 について
2009.10.10
コメント(2)
-
伊勢湾台風の再来か
台風18号は、古来の南海道の鼻先をかすめて愛知県南部に上陸した。その後、本州を縦断して、東北から太平洋に抜けたとのことだ。同じようなコースをたどり、大きな被害をもたらした台風といえば、誰もが伊勢湾台風を思い起こすだろう。報道でも、伊勢湾台風との比較がさかんに行われている。 伊勢湾台風が襲来したのは1959年9月26日ということだから、その記憶はまったくない。なにしろまだ三歳にも満たぬころだから。ただ、伊勢湾台風は阪神大震災が起こるまでは、戦後最大の被害をもたらした自然災害だった。阪神大震災の死者は6,434人、行方不明者3人、負傷者43,792人ということだが、伊勢湾台風による死者は4,697人、行方不明者401人、負傷者38,921人にのぼっている。 むろん、現代では、当時にくらべ河川の改修や河口付近の防潮堤の整備、それになによりも上陸のはるか前からの正確な進路予報のおかげで、台風のためにそのような甚大な被害が出ることはないだろう。とはいえ、すでに2名の死者と59名の負傷者が出たということだ。もちろん近親に死者を出した人にとっては、その数の大小など関係のない話ではある。 ところで、洪水神話といえば当然 『創世記』 にある 「ノアの箱舟」 の話が連想される。ノアの箱舟は、トルコと旧ソ連との国境に近いカフカス山中の山、アララト山に漂着したとされているが、あんな巨大な箱舟が実際に作られたとはとうてい思えないので、これは眉唾な話だろう。おそらくは、「伝説」 を作った人々にとって、アララト山が彼らの知る最も高い山だったということにすぎまい。 この洪水説話そのものは、それよりはるかに古いメソポタミアの神話が原型だそうだが、そのひとつ、最古の文明であるシュメールの伝説的な王にして英雄ギルガメシュを歌った 「ギルガメシュ叙事詩」 では、洪水の場面がこんなふうに描かれている。六日七夜、風と洪水が大地を襲った。嵐は大地を平らにした。七日目になると、嵐は去り、洪水は苦悶する女のように自らと格闘した。大洋は静まり、悪風は治まり、洪水は退いた。私は一日中あたりを見回した。沈黙があたりを支配していた。すべての人間が粘土に戻っていた。大地は屋根のように平らだった。(中略)七日目になって、私はハトを放した。ハトは飛んでいったが、戻ってきた。休み場所が見つからなかったので、戻ってきたのだ。私はツバメを放した。ツバメは飛んでいったが、戻ってきた。休み場所が見つからなかったので、戻ってきたのだ。私はカラスを放した。カラスは飛んでゆき、水が退いたのを見た。カラスはついばみ、身繕いし、頭を動かしたが、戻ってこなかった。そこですべての鳥を四方に放ち、犠牲をささげた。「11枚目の粘土板」 より これを読むと、アメリカに多いらしいID(インテリジェント・デザイン)論者のような 「聖書」 原理主義者には悪いが、たしかに 『旧約聖書』 の物語のほうはただのパクリだとしか思えなくなってくる。 さて話は全然かわるが、ネットなどの公共の場での議論では、しばしば 「中学生にも分かる話」 と 「中学生には分からない話」 が対立することがある。言い換えると、これは基本だけを教える 「初級編」 と、それを前提にし、さらにその上のことを学ぶ「上級編」の対立ということだ。 「上級編」 では、「初級編」 で一般的に教えられたにすぎない原則がより厳密に定義されたり、原則を制限する条件や状況について教えられたりする。その結果、それまでの原則に反するかのごとき 「例外」 が教えられることもある。初級者にとって 「原則」 は唯一にして絶対だが、上級者にとっては必ずしもそうではない。 また、たいていの分野では原則はひとつではなく、互いに対立することもある。その結果、「初級編」 での教えと 「上級編」 の教えとは、しばしば対立し相反するかのように見えることになる(ただし、カルト教団などでしばしば見られる、教祖に絶対忠誠を誓った特定の信徒のみに内密で伝授される 「高度の教え」 なるものは、これとは別の話である)。 たとえば、小学生の算数では 「引く数」 は 「引かれる数」 より小さくなければならない。そうでなければ、引き算そのものが成立しない。しかし、中学生になると、この原則が簡単にひっくり返される。それは、言うまでもなく、負の数が導入されるからだが、ここで 「なんでやー」 と躓くと、その先には進めないことになる。 当然のことだが、「中学生には分からない話」 を理解できる人の数は、「中学生にも分かる話」 を理解できる人よりも少ない。ただし、そこの段差がさほど大きくなければ、「中学生には分からない話」 を理解できる人もそれなりにおり、「中学生にも分かる話」 しか理解できないという人はそれほど多くはないだろうから、さして問題とはならないだろう。 困るのは、この差がいささか大きく、そのため、「中学生には分からない話」 も理解できるという人の数があまり多くなく、結果的に 「中学生にも分かる話」 しか理解できない人のほうが多数を占めるといった場合である。 実際の中学生ならば、「自分はまだ中学生だから、これはまだ理解できないんだ。もっと勉強して理解できるようになろう!」 ですむのだが、あいにくと 「公共」 の議論に参加する人たちは、みな自分は立派な大人だと思っていて、本当はまだ中学生にすぎないということを自覚していなかったりする。 なので、そのような場では、しばしばただの 「基本編」 にすぎない 「中学生にも分かる話」 のほうが正しく、「中学生には分からない話」 は間違っているかのように見え、結果として多数を制してしまうという、へんてこりんなことが起きてしまう。 「科学」 や 「学問」 のように、それなりの知識を必要とし、参加資格が実質的に制限されていたり、暗黙のうちに序列化(それがつねに適切だとは限らないが)されているような場なら、そういうことはあまり起きない。しかし、建前上、すべての人に開かれている 「公共」 の議論では、こういうことがあちこちでけっこう起きる。 「公共」 の議論に参加する者の資格を制限するわけにはいかないので、これはしょうがないのだが、そういうところを実際に目にしたりすると、いささか脱力してしまう。勝ち誇ったような身振りで、「原則論」 をとうとうとのたまう人がいたりすると、「そんなことは分かってるよ」 とか、「いや、そういうことを最初から言ってるのだけど」 などと言いたくもなるという話である。 ところで、今日は10月8日、つまり、今から42年前に、戦争下にあった南ベトナムの首都サイゴンを訪れようとした当時の佐藤栄作首相に対し、「三派全学連」 と呼ばれたグループの学生らが空港近くでデモを行い、機動隊と衝突した結果、山崎博昭という京大の学生が死亡した日である。 彼は1948年生まれだったそうだから、生きていれば来月で61歳ということになる。評論家の橋本治や糸井重里、作家の立松和平らと同じ世代。とくに糸井とは、誕生日がわずか2日しか違わないらしい。注: 念のために、付け加えておきますが、文中で 「中学生」 という言葉を使ったのはあくまで比喩なので、もしそれが不愉快だという方がいれば、適当に 「高校生」 とか 「大学生」 などの言葉に置きかえてください。 また、だから 「公共」 の場の議論への参加には、資格制限をつけるべきだなどということを言っているわけでもありません。
2009.10.08
コメント(0)
-
我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか
ゴッホとの共同生活が破綻したゴーギャンがフランスからタヒチへと逃亡したのは、ゴッホと別れてから三年後の1891年のことである。タヒチが 「発見」 されたのは18世紀半ばで、最後にはハワイで先住民に殺された、かのキャプテン・クックことジェームズ・クックも、金星観測のため、1769年にタヒチを訪れている。 むろん、この 「発見」 とはヨーロッパ人と彼らの世界にとってのことにすぎない。タヒチは、おそらくはアジアのどこかから船出し、その後、ハワイからイースター、さらにニュージーランドにまで航海を続けた人々らによって、そのはるか以前に発見されていたのである。いうまでもなく、それはいわゆる 「新大陸」 の場合でも同じことだ。 タヒチなどの島々の 「発見」 が、当時のヨーロッパの知識人らにどのような影響を与えたかは、たとえば革命前のフランス啓蒙思想家の一人であるディドロが、航海から帰国した同国人のブーガンヴィルについて、『ブーガンヴィル航海記補遺』 という書を書いていることからもうかがえる。彼はその中で、次のように書いている。ああ!ブーガンヴィル氏よ、あなたは無邪気で仕合せなタヒチ人のすむ岸辺からあなたの船を遠ざけるがいい。彼らは幸福でいるのに、あなたはただ彼らの幸福を損なうだけであろうから。彼らは自然の本能に従うのに、あなたはこの荘厳神聖な性格を抹消しようとしている。いっさいは万人に所属するのに、あなたは我のもの、汝のものという不祥な区別を彼らの中に持ち込もうとしている。ついに、あなたはタヒチを去る。......すでに夜明けの時刻から、彼らはあなたが船に帆を上げるのを認める。彼らはあなたのもとに殺到し、あなたを抱擁して涙を流す。泣くがいい、哀れなタヒチ人よ。しかしお前たちの流す涙はこれらの野心に満ちた、腐敗した、邪悪な人間の到着を悼む涙であっても、決して出発を悼む涙であってはならない。いつか、お前たちは彼らの正体を知るに違いない。いつか、彼らは片手に十字架、片手に短剣を握って到来し、お前たちを虐殺したり、お前たちに無理やりに彼らの習俗や見解を採用させたりするに違いない。いつか、お前たちは彼らの足もとにひれ伏して、彼らとほとんど変わらない不幸な状態に陥るにちがいない。 ディドロの予言どおり、タヒチはその後、太平洋における英仏の覇権争いに巻き込まれ、1842年にはフランスの保護領、さらに1880年にはその植民地となり、現在は、共和国フランスの自治権を与えられた 「海外領土」 ということになっている。ちなみに、タヒチに近いムルロア環礁で、フランスの核実験が行われたことは、まだ記憶に新しい。 このような、いわゆる 「善良なる未開人」 の発見が近代ヨーロッパの思想に及ぼした影響については、言うをまたない。世界各地での 「未開人」 の発見は、やがて 「人類学」 なる学問の誕生に導き、ヨーロッパという 「文明諸国」 の遠い過去との比較であるとか、また人類の文化と社会の「発展段階」論といった壮大な理論もいろいろと提出された。 それはともかくとして、一般的に言うなら、自然科学であれ人文・社会科学であれ、「人間」 という生物についての科学が発達することは、人間を 「神」 の似姿という神聖な座から引きずりおろすことを意味する。 われわれ人間が、人間自身を客観的で合理的な冷たい認識の対象とするとき、人間はもはやかつての伝統的な 「キリスト教神学」 で信じられていたような、神と同じ理性を分有し、神から特別なご愛顧を受けた、他の生物とは別格の生き物ではあり続けられない。「進化論」 がもたらした衝撃とは、まさにそういうものである。 われわれは、すでに人間の 「意識」 というものが、神から授けられた、神と同じ 「理性」 などではなく、進化によって生まれた脳という器官の産物にすぎないことを知っている。だが、具体的な意識は、身体とそれを取り巻く、他者を含めた 「世界」 との関係の中で成立するのであり、したがってたんに脳の中にのみ局在しているのではない。 それは自己の身体を貫き、身体をすっぽり覆うと同時に、身体からはみ出したものとしても存在する。たとえば、熟練者が道具や機械を操作するときのように。それは、いわば 「延長された身体」であり、「二乗された身体」 でもある。そして、その結果、「身体」 の側にも、「精神」 の中に取り込まれ、「精神としての身体」 に変容するという妙な状況が生じることになる。 なんの因果かは知らないが、人間は、巨大な大脳を含む特異な身体組織を得ることで、「自己意識」 というややこしいものを持ち、言葉をしゃべるようになった。おかげで、人間はわけのわからぬさまざまな 「観念」 を生み出し、悩まされるようにもなってしまった。もっとも、それがどのようにして発生したかは、すでに遠い記憶の彼方であるから、もはや誰にも分からない。 たとえば、呪術の力を信じる 「未開人」 は、呪いをかけられたと思うと、それだけで死にいたるという。だが、それは、彼が 「愚昧」 であるがために起こるのではない。そうではなく、それは彼もまたわれわれと同じ、「観念」 という病にとりつかれているがゆえに起きるのだ。 そこに違いがあるとすれば、それはせいぜい、とりつかれる 「観念」 の違いにすぎない(どちらが高級であるかは、あえて問わない)。つまるところ、魔法や呪術を信じる 「未開人」 もまた、多少の程度の差はあれ、われわれと同じ立派な 「文化」 的存在なのである。 途中ははしょるが、結局のところ、自然史という地球の歴史への登場以来、われわれ人間はみな、究極的にはこの奇妙な 「心身」 という 「下部構造」 による規定をつねに受けている。そして、そのような 「下部」 と、その上に立つ歴史や社会、文化といった 「上部」 をつなぐ配線は、たしかに明瞭ではないが(完全に明瞭になることはありえないだろう。それはつまり人間が「自由」でもあるからだ)、なんらかのイデオロギーによってことさらにつながなくとも、すでにそこにあるものである。 したがって、そのような 「配線」 の存在を意識することは、なんらかの 「価値」、たとえば白色人種、とりわけアーリア人種の優越といった怪しげな 「理念」 や、特定の民族や社会層に対する差別を正当化するために、「遺伝学」 だとか 「生理学」 だとか、つねにひとつの暫時的な仮説でしかないなんらかの 「科学」 によって、怪しげな 「配線」 をすることとはまったく別のことだ。 それはまた、なんらかの 「下部構造」 から直接に、「価値」 だとか 「理念」 だとかを導き出そうという話なのでもない。むろん、そのような 「配線」 の存在を認識することは、人間の自由をすべて否定することでもない。ただ、その 「絶対性」 が否定されるだけのことだ。だが、絶対的に自由な人間など、地上に存在しえぬことなど、ほとんど自明のことにすぎまい。 しかし、「上部構造」 に対する否定的制約としてであれ、その成立を可能とする肯定的条件としてであれ、人間の 「本性」 や 「生活世界」 といった具体的な 「下部」 による規定を無視して、自らを 「普遍的」 と称する理念が大手を振って歩き回るなら、そこに生じるのはつまるところ 「啓蒙の暴力」 であり、せんじつめれば、現に近現代史の中でしばしば生じたような、「普遍性」 の名による 「テロル」 ということにしかなるまい。 「行動主義心理学」 を提唱したワトソンは、かつて、「もし自分に生後間もない健康な子供を預けてくれるならば、その子供をどんな性格にでも、どんな職業人にでも育て上げてみせる」 と豪語したという。むろん、これはおそらく当人も承知の、宣伝をかねた一種のハッタリにすぎないだろう。 だが、そのような人間の 「本性」、すなわち "human nature" そのものの存在をいっさい否定する論理こそが、「革命」 や 「党」、「国家」 といった大義の前には、親や家族、親しい友人らも売り渡すことが正しい行為だとして称揚された 「スターリニズム」 の論理を生んだのであり(むろん、それだけが原因ではないが)、それが最後に行き着く先はオーウェルの描いた 『1984』 ということになるだろう。 現代の社会が、いわゆるグローバル資本主義を経済としての 「下部構造」 としているとしても、われわれを規定しているのはそれだけではない。経済としてのグローバル資本主義は、自己に照応する複雑な 「上部構造」 を必要とする、それ自体が一つの巨大で複雑なシステムであり、それをもって社会を最下段で規定する 「下部構造」 であると単純にみなすことはできない。 そのような世界の変容は、むろん無視し得ない現実であるし、世界経済をかつてのような相互に孤立した国民経済へと分断することが可能なわけでもない。とはいえ、人間という存在を最終的に規定しているのは、われわれ自身の 「心身」 と 「生活世界」 とでも言うべき具体的な現実ではあるまいか。 まだ若かったマルクスが言った、「現実的な諸個人による物質的生活の生産」 とは、まずはそのような具体的な世界のことを指しているのであり、それはたんなる経済や経済学の問題なのではない。あらゆる人間歴史の最初の前提は、もちろん生きた人間的諸個人の存在である。それゆえ、最初に確認すべき事態は、これら諸個人の身体的組織、およびそれによって与えられる彼らのそれ以外への自然への関係である。『ドイツ・イデオロギー』 ついでに引用すると、マルクスの同時代人であったシュティルナーは、キリスト教の神とは、類としての人間の本質が疎外されたものであり、人間はそのような神として自ら疎外した自己の本質を取り戻さなければならないと説いたフォイエルバッハに対して、彼はただ神の代わりに、「人間」 なるものをその座につけたにすぎないと批判している。 なぜなら 「神の精神」 はキリスト教的見解によれば、また「われわれの精神」 でもある。......それは天にもわれわれのうちにも住む。哀れなるわれわれはその 「住居」 である。そしてフォイエルバッハが進んでその天上の住居を破壊し、そのすべてをわれわれのうちに移そうとするなら、そのときわれわれ ―― その地上の住居 ―― は著しく混雑をきわめるであろう。『唯一者とその所有』 人間と社会の 「基底」、いいかえれば、われわれを規定している 「心身」 を含めた人間が有する 「自然」 を承認することは、つまるところ、人間がけっして神ではないということ、そしてまた、たとえわれわれが神を殺したとしても、人間はけっして神にはなれないということを明確に承認し、自覚することでもある。 結論はしごく当然な話になってしまったが、言いたいのはようするにそういうこと。なお、タイトルはむろんゴーギャンの有名な絵からのパクリである。
2009.10.02
コメント(4)
全6件 (6件中 1-6件目)
1