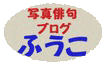2013年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

高大26日目
今日は、高大26日目。午前中は鶴島先生のエッセイの授業、午後はクラスミーティングだった。放課後はマジック同好会の集まりに参加した。エッセイは、宿題だった「寒波」の文を読み、先生から指導・コメントを受けるという形式で全員の分が終った。いつものことだが、先生のコメントは短いが鋭い。文の冗長さ、不要な言葉、導入、締めくくりの文のよしあし、テーマのよしあしなどみんなが成程ということを指摘される。生徒の作品も「寒波」に関連する想い出を書いたものが多かったが、気象の寒波ではなく人生の荒波を寒波に見立てた作品もあり、十人十色で面白かった。次回の宿題は「青春」だ。ミーティングでは、修学旅行の行き先について議論した。各班から候補地が推薦され、多数欠を取ったところ5班と8班の案が同数。さらに2案を決戦採決したところまたも同数となった。しかし5班が辞退したため結局8班の案に決定した。各班の案と票数は次のとおり。1、3班 淡路島へ花を見に行く。 5 2班 姫路へ城と花を見に行く。 3 4版 明治村へ 5 5版 紀州3名園とフィッシャーマンズワーフ10 6班 金熊寺の梅林と黒江塗の町 6 7班 なばなの里、長島温泉 1 8班 津の結城神社の梅園と関宿 10写真は白板に書かれた各班の行き先案と票数。マジックは、これまでの復習をした。一度覚えても実際にやらないと忘れてしまうものだ。なお、マジック同好会の会合は今年度はこれで終り。
2013.01.31
コメント(0)
-

一日中家で過ごす 不断桜
今日は、一日中家にいて、エッセイの宿題「寒波」を書いたり、句会資料を作成したり、俳句を考えたり、本を読んだり、句集を読んだり、テレビを見たりしながら過ごした。今日の写真は昨日、霊山歴史館で見かけた梅と不断桜。この不断桜は10月ごろから4月ごろまでずっと花を付けているのだそうだ。
2013.01.30
コメント(0)
-

「八重の時代」展を見る
今日は、昼前から出て京都に行き、霊山歴史館で開催されている「会津の武士道 八重の時代」展を見に行った。一月から放送が始っている大河ドラマ「八重の桜」の予備知識を得るためである。展示の規模は大きくはなく、全体で100点ほどだった。うち新島八重・新島襄・同志社大に関するものは24点、松平容保や会津藩に関するものが15点、あとは、新撰組に関するもの22点、竜馬に関するもの12点、鳥羽伏見の戦に関するもの14点、戊申戦争に関するもの9点だった。その他、八重に関する映像、電動紙芝居が各1点映写されていた。1時間ほどかけて、一通り見て回り、八重や兄の覚馬、夫の襄などの生涯や功績について大体のことは分かった。もう少し資料があればいいのにと思ったが、今回の展示は第1期であり、残りの資料は第2期で展示されるのだそうだ。画像は、パンフレットより。左:戊申戦争の絵、右:松平容保の和歌、孝明天皇の御染筆(忠誠)、新島襄古写真、電子紙芝居、3D立体映像、新島八重写真、女紅場之創始・槙村正直筆。
2013.01.29
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は句会資料のプリント、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の結果は上出来で、5句のうち4句が先生から選ばれた。しかし、一句は誰からも選ばれなかった。句会のあと新年会に参加した。今日、先生から選ばれたのは次の句。 〇探梅行出歩くことに意義あつて こっぱん (先生ほか6票) 〇寒月に心の中を見透かさる こっぱん (先生ほか4票) 〇鷽替の最後の最後巫女と替ふ こっぱん (先生ほか2票) 〇氷柱より雫の落つるよき間合 こっぱん (先生ほか2票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎鷽替ふる回り回つて同じ人 慈子 (先生特選ほか3票) ◎鷽替の替へてまた替へ吉を追ふ 光祐 (先生特選ほか2票)今日、最高得票を得たのは、上記こっぱんの探梅行の句。先生の句で、今日一番人気だったのは次の句。 ◎垂るること宿命にして長氷柱 塩川雄三先生 (5票)新年会は、17時から南森町の「大陸風」で行われた。先生や句友との親睦を深め今年も俳句道に精進することを誓い合った。写真はその新年会にて。
2013.01.28
コメント(0)
-

淀川探鳥会に参加
今日は、朝から淀川探鳥会に参加した。今年一番の寒波が来ているということで、参加者はいつもの常連だけだったが、天気はよく鳥はいろいろな種類を見ることができた。帰宅後は、午前中に取っておいたビデオを見たりして過ごした。今日一番初めに見たのはイソヒヨドリ。きれいな色をしていた。多くの数を見たのはツグミ。木の枝、土の上さらに干潟にまでたくさん来ていた。オオジュリンも鳴き声とともに多く見られ、ベニマシコも見られた。干潟ではケリ、イソシギが見られた。また、最後にカワセミを見ることが出来たのもラッキーであった。しかし、今日は珍しく、アオサギ、ダイサギ、コサギなどサギの種類は見かけなかったし、猛禽類も見なかった。いつも多いカワウやユリカモメも少なかった。今日見た鳥は次の通り。ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、オオバン、ケリ、イソシギ、ユリカモメ、セグロカモメ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ベニマシコ、ホオジロ、アオジ、オオジュリン。37種。写真は、カモの群れ、イソヒヨドリ、カモの飛翔、ユリカモメ、オナガガモ、オオバン、ケリ、オオジュリン、ツグミ。
2013.01.27
コメント(0)
-

河東碧悟桐についての講演を聴く
今日は、午前中は、エッセイの宿題の構想を考えたり雑事で過ごし、午後は、伊丹の柿衛文庫で開催された講演会「碧悟桐と子規・虚子」に参加した。講演会は、現在開催されている展示会「寄贈コレクションによる俳句のあゆみ2 山頭火、碧悟桐、秋桜子、誓子、草田男」の関連行事として行われたもので、講師は坪内稔典氏だった。最初に展示会を見て、講演会を聴き、そのあとまた展示会を見た。展示会には、5俳人とその弟子の色紙・短冊の作品および句集など330点が展示されていた。講演は13時30分から15時まで行われ、碧悟桐の俳句、書の紹介、子規との師弟関係、虚子との交友関係についていろいろな事例を交えて説明された。興味深かったのは、1.碧悟桐の俳句で一番有名な句は、 赤い椿白い椿と落ちにけり (23才の作) で、2番目に有名な句はないということ。2.碧悟桐は俳句より書の方が有名であること。 弟子も同じような字を書いた。3.新聞社「日本」で俳句欄を担当し、選者をしていた。4.虚子は守旧派、碧悟桐は新傾向。5.自由律俳句の祖。6.松瀬青々の娘と結婚。7.「引退の辞」を書いて引退した。 煎餅屋をしたかったが果せず死去。画像は、パンフレット、講演配付資料、講演会スナップなどより。左より、中村草田男「降る雪や」、種田山頭火「木の芽や」、河東碧悟桐「梅遠近」、同「踏んで来た」、同「猫図」、山口誓子「海に出て」、種田山頭火「こうろぎに」、水原秋桜子「機の音」、河東碧悟桐「山をやく」。
2013.01.26
コメント(0)
-

オペラ「フィデーリオ」を見る
今日は、午前中は、DVDでオペラ「フィデーリオ」を見、午後からはK病院へ診察に行った。帰りに阪急百貨店に寄って加賀物産展をはじめ店内を見た。オペラ「フィデーリオ」はベートーベンの唯一のオペラ作品。音楽はベートーベンらしい曲想で、特に第2幕エンディングの合唱は、交響曲第九番第4楽章合唱付きのエンディングとよく似ている。無実の罪で投獄されている男プロテスタンを救うため、その妻レオノーレが男装してフィデーリオと名乗り看守として就職する。門番ヤキーノは看守長ロッコの娘マルツェリーネに恋しているが、マルツェリーネはフィデーリオに恋する。プロテスタンを罪に陥れた刑務所長のピッツァロはロッコに対しプロテスタンを殺せと命令する。以下略すが、最後は地下牢から無事救い出すという物語。フィデーリオのソプラノ、プロテスタンのテノール、ロッコのバス、ピッツァロのバス・バリトン、どの声優の歌声も演技も素晴らしかった。画像は、映像のキャプチャー及び説明書より。コヴェント・ガーデン王立歌劇場、説明書表紙、DVDのメニュー画面、第1幕ロッコ、マルツェリーネ、フィデーリオの三重唱、第1幕のフィナーレ束の間の日差しを喜ぶ囚人たち、第2幕プロテスタンの妄想、ピッツァロにピストルを突きつけるフィデーリオ、救出されたプロテスタン、手錠を外すフィデーリオ。
2013.01.25
コメント(0)
-

高大28日目
今日は、高大28日目。午前中は久しぶりでエッセイの講義、午後は共通講座で「大阪のものづくり」の話、その後、マジック同好会の新年会がこう行われた。エッセイの時間の前半は、前回書いたエッセイのうち優秀な作品11編が紹介された。みんな巧い。文章が巧い前の題材の選び方が素晴らしい。みんなが興味を持つだろうと思う題材を選んだり、変った切り口で論じたりしているのである。平凡な題材を平凡に書いたのでは誰も読んでくれない。後半は、題名を与えて即興で5行(100字)の文章を書くこと。これは制限時間10分。全員が順次読んだが、先生は「短い文にするとみんないいエッセイになっている。この調子で永井エッセイを書くようにすればよい」との指導があった。エッセイの講義の中で、Tさんが読んだ横尾忠則の「病の神様」の中の「日常と非日常あるいは生と死」や、Mさんが読んだ木津川計の「ことばの身づくろい」の中の「ことばのリズム」も朗読が素晴らしくよく内容が理解できた。午後の共通講座の前に同窓会の説明があり、その席上に貴乃花氏が現れ、大阪場所の支援を頼んでいた。そのあとの講演では、阪大経済学部教授の沢井実氏が、「大阪のモノ作りの歴史をふりかえる」と題して、明治中期から昭和初期までの大阪の製造業の歴史を整理して話された。当時は東京、名古屋を引き離して、日本最大の工業都市だったが、戦後次第に東京、名古屋に抜かれた経緯や、大阪にあった懐かしい会社の話に興味深く聴き入った。その後、マジック同窓会の新年会が近くの店で行われ、村本先生はじめ6人が集まった。写真は、エッセイ教室の授業前、貴乃花氏、沢井氏の講演、マジックの新年会。
2013.01.24
コメント(0)
-

梅はまだ咲かず
今日は、午前中はパズルを考えたり、俳句を作ったり、寺社の本を読んだり、メールを書いたりなど雑事で過ごし、午後から図書館に行ったあと、大阪城の梅林に行った。図書館では、オペラ「フィデーリオ」と「トスカ」のDVDを借りた。まだ見ていない。梅林は、例年なら一月の下旬になれば2分くらいは咲いているのだが、今年は寒さが厳しく今日はまだ数本の梅に花がちらほら咲き始めた程度だった。梅林に来ている人も殆どいなかった。(但しロウバイは満開)。咲いている梅は、寒紅という紅梅と香篆という白梅だけだった。梅はダメだったが、堀にはユリカモメやカモをたくさん見ることができた。写真は、青屋門から見た大阪城、梅見茶屋から見た大阪城、ロウバイと大坂城、梅林の様子、紅梅、白梅、キンクロハジロ、ユリカモメ、同。
2013.01.23
コメント(0)
-

歌川国芳展へ
今日は、午前中は、寺社紀行の本を読んだり、俳句を作ったりし、昼前から出掛け神戸大丸で開催されている「歌川国芳展」を見に行った。国芳展は2年前に大阪市立美術館で開催されたが、今回はそれ以来2年振りの開催。その時は初めての大規模(400点)で本格的な国芳展で、作品の奇抜さに驚いたが、今回は作品は120点と少なかったものの迫力のある作品ばかりで、2年前の興奮がまた蘇えった。じっくり説明も読みながら見て回ったが、出て来ると2時間半も掛かっていた。展示は次の5つに分類されていた。第1章 花のお江戸のファッション・グルメ 国芳もよう正札付現金男野晒悟助、春の虹蜆など21点第2章 季節を楽しむ江戸っ子のレジャー 新板こども遊びの内すもふのまなびなど21点第3章 国芳の江戸散歩 東都富士見三十六景昌平坂の遠景、東都名所佃嶋など17点第4章 江戸のコミカルワールド 猫の当字ふぐ、人をばかにした人だ、てるてる坊主おひよりおどり、朝比奈小人嶋遊、道外化けもの夕涼、流行猫の曲手まり、おぼろ月猫の盛など32点第5章 英雄たちの大冒険 讃岐院眷属をして為朝を救ふ図、本朝水滸伝八百人一個尾形周馬寛行、大物之浦海底之図、相馬の古内裏など29点国芳の絵は一枚の絵を見れば見るほどいろいろな発見があり、興味が湧いてくる。いろいろな隠しものがあったり、人物の表情がよかったり、絵が細かく技巧的であったりで、一枚一枚感心しながら見て行った。画像はパンフレットより。讃岐院眷属をして為朝を救ふ図(部分)、国芳もよう正札付現金男野晒悟助、新板こども遊びの内すもふのまなび(部分)、春の虹蜆、 てるてる坊主おひよりおどり。左:猫の当字ふぐ、人をばかにした人だ、本朝水滸伝八百人一個尾形周馬寛行、東都富士見三十六景昌平坂の遠景、大物之浦海底之図、右:朝比奈小人嶋遊(部分)、東都名所佃嶋(部分)、道外化けもの夕涼(部分)、流行猫の曲手まり(部分)、おぼろ月猫の盛(部分)、相馬の古内裏(部分)
2013.01.22
コメント(0)
-

オペラ「リゴレット」を見る
今日は、午前中は、昨日留守録しておいた「日曜美術館」などのビデオを見たり、昨日のパズル会と句会の資料を整理したりしながら過ごし、午後は、図書館で借りたDVDでオペラ[リゴレット」を見た。ヴェルディのオペラ「リゴレット」は名前は有名で、第3幕ででテノールが歌う「女心:風の中の羽根のように」も有名だ。しかしどんなストーリのオペラか今まで見たことも聴いたこともがなかった。大変悲しい物語であることを始めて知った。リゴレットは一人娘を誘拐した公爵に復讐をしようと殺し屋に頼むが、殺し屋は前金を受け取った上、公爵の替わりに娘を殺して残金を受け取る。娘が自分から望んで公爵の身代わりになったのだった。ほんに女心は分からないものだ。画像は、映像および解説書より。チューリーッヒ歌劇場、解説書表紙、DVDのメニュー画面、第1幕怒るモンテーロ伯爵、第1幕リゴレットと娘ジルダ、第1幕ジルダ、第2幕リゴレット、第3幕殺し屋に前金を払うリゴレット、第3幕虫の息のジルダ。
2013.01.21
コメント(0)
-

関西ぱずる会宿泊例会2日目、俳句21新年会
今日は、関西ぱずる会宿泊例会の2日目。朝食のあと、9時から例会が始った。参加者は広島や三重県、福井県からの者を含め24人。先ず、Y氏から恒例の年賀パズルの紹介があり、氏が受け取った36通の年賀状のパズルを解いた結果の発表があった。難問パズルを除いて毎年殆どすべての問題を解いている。続いて各自自分の年賀パズルの趣旨と回答状況の説明がされた。その後、各自の発表に移り、昨夜披露されたものを含め多くのパズル関連玩具、図書、資料等が配付、回覧された。発表は12時時点でまだ続いていたが、私はあとの予定があるため、後ろ髪を引かれる思いで、12時過ぎに会場をあとにした。写真は、関西ぱずる会例会の模様と回覧されたパズル関連玩具、図書などの一部。例会を出てすぐに南海電車に飛び乗り、千里中央の句会会場に駆け付けた。出句だけをすませ、駅構内にあるレストランで昼食を取った。句会の成績はあまりよくはなかったが、投句4句のうち2句がなんとか選ばれた。次の2句。 〇初夢の中だけにある隠しごと こっぱん 〇ビル群が迎ふ難波の大初日 こっぱん今日、人気を得ていた句は次の句で、10人中6人が選んでいた。 ◎こころ根は採点されず大試験 明子句会のあと、新年会が行われ9人が出席した。
2013.01.20
コメント(0)
-

関西ばする会の宿泊例会
今日は、午前中は、俳句の月例投句、課題句会投句、句集の感想文なとを作成・送付にかかり、その後、明日の「俳句21」句会に出句する句を作ったり、パズル会への資料を準備したりしながら過ごした。14時に家を出て、関ぱ宿泊例会の場所である石津川のホテルには15時に到着した。順々に会員は集まり、早速机上にパズルが並べられ、各自思い思いのパズルを手にして夕食までの時間を過ごした。夕食時には、例年のようにU氏から干支に因んだ箸置きがプレゼントされた。夕食後は、M氏の「面積迷路」の出題があり、先着正解者3名に著書が贈られたが、私の問題にはミスプリントがあり、回答不能だった。Tの字4つを正方形の枠に入れるパズルや、キノコの形5個を正方形に入れるパズル、6片のピースを並べて正方形と正五角形を作るパズルを解いたり、動く絵、立体に見える絵、錯視、トリック写真、不可能物体などを見たりしながら、夜が更けるのを忘れてパズルに興じた。写真は、例会の様子、夕食の様子、以下並べられてパズルの例。ほんの一部。中央はヘビの箸置き。
2013.01.19
コメント(0)
-

「昭和原風景ジオラマ館」へ
今日は、午前中は句集の感想文を書き、午後は図書館へ行ったあと、高島屋で開催されている「昭和原風景ジオラマ館」を見に行った。「昭和原風景ジオラマ館」は昭和37年東京生れのジオラマ作家山本高樹の作品を集めたもので、懐かしく心温まる作品ばかりだった。展示は次のように4つに分類されていた。下記3のセットは、梅ちゃん先生のタイトルバックで流れていた映像に使われたもの。このジオラマを使い、船や指導者や人間を少しずつ動かしながら撮影し、動画にしたのだそうだ。0.新世界・通天閣1.東京幻風景 凌雲閣、銀座、有楽町のガード下、浅草の縁日、三社祭、池の端の伊豆栄、上野不忍池、新宿ゴールデン街、夢町楽天地など9点。2.懐かき日々 額縁ショウの帝都座、井戸広場の本郷、サムライ紹介の横浜、神保町の古本屋街、電気キネマ会館、駄菓子屋、深川界隈、色町向島、明神湯雪谷など10点。3.梅ちゃん先生の町 ドラマテーマ曲バックの風景、蒲田の新世界。4.懐かしの情景 ひかり幼稚園(熊本人吉)、長野飯山の大根干し、山古志村の民家、隠れ里の温泉、雪国の越後十日町、尾道のガウディハウス、見世物小屋の立つ縁日、橋の下の廓舟、川っぺりの町など9点。一つひとつが細かくしっかり作られていて、撮影すると本物と変らない迫力がある。なくなりつつある日本のよき町並みがこういう形で保存されていけばいいと思った。このジオラマの面白いところは、町並みや建物の模型だけでなく人物を大勢登場差せているところだ。祭りでは数百人の人形が作られそれぞれ服装が描かれているし、遊郭では客引きをはじめ各部屋での遊びの場面がリアルに作られている。銭湯では、男湯、女湯の様子が分かる。裏街の家の壁には猥褻な落書きもある。図はパンフレットより。左:梅ちゃん先生の町、右:梅ちゃん先生の町、モダン都市銀座、雪国の市越後十日町、新宿ゴールデン街、凌雲閣の怪人、梅ちゃん先生の町。
2013.01.18
コメント(0)
-

高大27日目
今日は高大27日目、今年初めての受講日で第3学期の初日である。午前中は田中新一先生の川柳の講義、午後はクラスミーティングだった。川柳の先生は川柳結社「番傘」の幹事長で、朝日新聞なにわ柳壇、やまと柳壇の選者を務める。講義は「川柳の味わい方作り方」と題して、川柳の起源、川柳の歴史、川柳と俳句の違い、川柳の基礎知識、川柳の持ち味(うがち、滑稽、軽味、ドラマ性、句品)などの説明を聞いたあと、川柳の作り方として、1.句材の見付け(写生、人間関係、好きなこと、社会、本音、意外性、ドラマ、詩性など)と、2.技巧(省略、比喩、擬人など)を学んだ。最後に今年の朝日新聞なにわ柳壇の昨年一年間の最優秀句と十秀の紹介があった。最優秀句は次の句だった。 ◎万能細胞神はどこまで許すのか 上嶋幸雀午後のミーティングでは、本日返却された各自のエッセイ2題と川柳の作品を班内で廻し読みし、お互いに批評しあった。楽しい時間だった。今日は写真を撮らなかったので、昨日京都鴨川で撮った鳥の写真を上げる。場所は塩小路橋。右上の山は比叡山で雪を被っている。鳥はダイサギ、アオサギ、ヒドリガモ、ホシハジロ、カラスなど。
2013.01.17
コメント(0)
-

「十二天像と密教法会」展と「豆皿、帯留、ぽち袋」展
今日は、京都へ展覧会2つを見に行った。京都国立博物館で開催されている「十二天像と密教法会の世界 併催方丈記」展と、JR伊勢丹で開、催されている「美しき日本の小さな心~豆皿、帯留、ぽち袋」展である。そのあと、大学の同窓会の幹事会に参加し、駅前の喫茶店で、5月に予定している旅行の打合せを行った。「国宝十二天像と密教法会の世界 併催方丈記」展は、1300年前から宮中で行われている御七日の御修法という行事とそれに使われる絵「十二天像」「山水屏風」など70数点を展示したものである。展示は次のように分類されていた。第1部 十二天像と後七日後修法 第1章 国宝十二天像 十二天像12幅、五大尊像2副など3点。 第2章 空海帰朝 弘法大師像、宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱など8点。 第3章 後七日御修法のはじまり(正月行事) 年中行事絵巻、十二天像3幅など3点。 第4章 後七日御修法の荘厳(飾り付け) 両界曼荼羅図、両部大壇具など11点。 第5章 後七日御修法のあゆみ 後七日差図「真言院」、同「金剛界」など19点。第2部 灌頂とその荘厳 山水屏風と十に天像を中心に 十二天像屏風、山水屏風など27点。ここまで見るのに1時間半かかった。続いて「方丈記」展を見た。「方丈記」展では、方丈記全一巻が全部拡げて展示されていて、長さは約5メートルくらいだった。「イク河ノナガレハタヘズシテ・・・」で始まる方丈記の全文である。その他、方丈記に出て来る事柄に関連するものとして18点の史料や絵図が展示されていた。画像は、パンフレットより。左:国宝十二天像(拡大図は水天)と方丈記、右:国宝十二天像のうち風天、十二天像のうち4幅、国宝宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱、国宝山水屏風、国宝飢餓草紙、方丈記。画像は、関連サイトより。国宝五大尊像のうち軍荼利明王像、弘法大師像(秘鍵大師像)、国宝金剛般若経開題、五鈷鈴、三鈷杵、金銅六器「東寺」銘、両部大壇具のうち胎蔵界大壇具、国宝灌頂暦名、十二天像のうち帝釈天、賀茂御祖神社絵図。展示を見終ると11時半。京都駅まで歩き昼食をとり、12時半から「美しき日本の小さな心~豆皿、帯留、ぽち袋~」展を見た。貴道裕子という女性が集めたもので、展示品は小さいものだがその数の多さに驚いた。係の人に聞くと、約3500点だということだった。しかもそのどれもが素晴らしいものばかりなのである。豆皿の文様は、吉祥、唐草、木の葉、花、富士、寿、人物、山水、色釉、霊獣、魚介などに分類されていたが、分類されていない物も1000個ほど並べられていた。帯留は数は数100点くらいだったが、非常に精巧な作りで、見事なものだった。ぽち袋のデザインは、大入袋、歌舞伎隈取、役者、十八番、家紋、火消、浮世絵、面、江戸小唄、年中行事、食道楽、郷土玩具、人形、大津絵、お化け、艶もの、アールデコ、トランプ、異国情緒、滑稽物、伊勢詣、絵馬、民謡、都おどり、浪速名所、浄瑠璃、源氏香、花、うさぎ、仕掛け物、八景ものなどに分類されてそれぞれ数十点が展示されていた。画像は、パンフレットより。左:上ー帯留、左ーぽち袋、右ー豆皿、右 上ー豆皿、中ー帯留、下ーぽち袋、右下ーてっさい堂。同窓会の打合せは幹事4人が喫茶店に集まって話し合い、仕事の分担を決めた。2月上旬にでも現地の下調べに行く予定。
2013.01.16
コメント(0)
-

トリックアート展
今日は、午前中は、写真や動画の整理と、写真のスライドショウや動画をDVDにする方法を勉強し、午後から、近鉄阿倍野で開催されている「トリックアート展」を見に行った。DVDには、「Media Impression」というソフトを使えばなんとか作ることができることがわかった。DVDプレヤーにかけると自動的に映像が再生される。DVDーRだけではなく、CD-Rにも焼くことができるがこの場合はCDプレヤーやDVDプレヤーでは再生できないことも分かった。容量が無駄にはなるが、やはり配付用としてはDVDに焼くべきであろう。「トリックアート展」は一昨日行って「50分待ち」の満員だったので、あきらめたもの。今日は一転してガラガラだった。作品は40点展示されていたが、どれも大同小異で、額縁から動物たちが飛び出るものである。実は、絵も額縁もすべて壁面に描かれたもので、絵や額縁に手で触って分かる通り、額縁の凹凸はまったくない。館内は撮影自由で、むしろ展示されている絵と一緒に人物を写真に撮ることによって、会場での体験以上の臨場感を得ようとするものである。実際みんなカメラで友達同志、親子同志と撮りあっていた。画像は、パンフレット。画像は、展示の一部。
2013.01.15
コメント(0)
-

梅田散策
今日は、午前中は句会資料の挿絵を選んだり、年賀パズルを考えたり、雑用で過ごし、昼前から梅田に出て昼食。その後、デパートなどを散策した。帰宅後は、俳句を考えたり、写真を整理したり、大学同窓会の旅行の計画を考えたりして過ごした。今日は、写真を撮らなかったので、一昨日「くらしの今昔館」で見た「昭和のレトロ家電展」を紹介する。この展示会は増田健一氏の20年に渡るレトロ・コレクション500点を家電を中心に展示するもの。主に昭和30年代のものが多く集められている。展示は次のような構成になっていた。1.増田家は昭和レトロ家電で一杯。2.三種の神器ーテレビ・洗濯機・冷蔵庫3.うんちくレトロ家電ー宇宙時代・美容ブーム・一粒で二度おいしい4.河合さあまって美しさ100倍ーデザイン家電5.住まいと暮らしの家電6.懐かしの生活雑貨・ポスターコレクション画像はパンフレットより。左:家電コレクター増田氏、資生堂の粉石鹸、松下のトースター、東芝のホームスタンド、八欧電機の14インチテレビ、東芝の真空管ラジオ、松下の電球の看板、松下の自動ポット、松下の電気冷蔵庫、早川のトランジスタラジオ、右:増田氏と白黒テレビ、早川のトランジスタラジオ、日立の卓上扇風機、分割内鍋、三種の神器。
2013.01.14
コメント(0)
-

「酒と食のうつわ展」と「杉良太郎の絵画展」た
今日は、午前中はテレビを見たり、雑事をしたりして過ごし、午後は、天王寺の大阪市美術館で開催されている「酒と食のうつわ展ー杯の中の小さな世界」を見たあと、上六の近鉄百貨店で開催されている「杉良太郎絵画展ー杉良太郎が描く日本の四季」を見に行った。「酒と食のうつわ」というタイトルだが、展示品約260点の230点は酒器それも盃、杯だった。細密な絵が書かれていてざっと見て回るだけで1時間半かかった。展示は、七福神・仙人・唐子などの人物、四季の草花・鳥、季節の祭り、鶴亀に代表される吉祥、名所絵などに分類されていて分かり易かった。画像は、左:パンフレット、右:サイトより。群鶴蒔絵杯春正作銘、魚介蒔絵杯羊遊斎銘、三方に伊勢海老蒔絵杯花一房銘、猿猴舟遊び蒔絵杯、寿老人蒔絵杯天明五乙巳孟冬製、山水松蒔絵三つ組杯・杯台齋藤「仙吉」銘。杉良太郎は俳優・歌手として活躍するかたわら福祉活動にも力を入れている。また、1991年から独学で絵を画き始め、年々腕をあげ各種賞を受けるまでになっている。今回の展示は風景画を中心に春夏秋冬に分け100点を展示したもの。意外に大作が多かった。初期の作品はややきこちなさが見られたが、最近の絵には風格が出て来たように思う。画像はパンフレットより。左:新生、右:朝焼けの富士、秋桜、小さな田園、鷲、ポピーの語らい近鉄阿倍野店で開催されている「トリックアート展」にも行く予定であったが、会場は満員で入場まで50分待ちということだったので諦めた。
2013.01.13
コメント(0)
-

クラリネットリサイタル、町家寄席、琴の演奏会
今日は、午前中は大阪城スクエアで加藤京子クラリネットリサイタルを聴き、午後は、大阪くらしの今昔館で桂出丸と桂福車の落語を聴き、夜はATCサンセットホールで琴の演奏を聴いた。クラリネットリサイタルは、11時から開演でピアノ伴奏は川口容子だった。曲目は以下の通り。 1.フランツ・シュトラウス:ノクターン作品7 2.シュトックハウゼン:友情を込めて 3.門田展弥:クラリネットとピアノのためのソナタ第3番 4.バルトーク:ルーマニア民族舞曲 5.ラヴェル:ハバネラ形式の小品どの曲も初めて聴くものだったが、2を除いてみんなきれいな曲だった。2は前衛音楽でクラリネット独奏だったが、演奏が難しい割にはあまり楽しい曲ではなかった。画像は、パンフレット、ポスター、プログラム、会場風景、最後の挨拶、同。リサイタルのあと、天満橋OMM地下で昼食をとり、天六のすまいの今昔館へ向った。町家寄席の今日の演目は桂出丸が「子ほめ」、桂福車が「辞世の句」だった。「子ほめ」はよく聴く話だが、「辞世の句」は初めて聞いたように思う。「いまわの際のことば」を「今川焼きとビワとおそば」と聞き違えるのを初め、いろいろな辞世の句を間違えるのが面白かった。画像は、左:ポスター、右上:桂出丸、右下:桂福車。落語を聴き終ったあと、展示室で企画展「レトロ家電」を見た。そのあと、南港のATCへ向った。今日のプログラムは正月らしく題名も「和で奏でる初春の調べ」として、琴の重奏を主に、ソロや三味線との合奏もあり、楽しい演奏会だった。出演は、菊春友莉絵と菊聖優涼可の二人。プログラムは下記の通り。1.吉沢検校:千鳥の曲 琴デュエット2.宮城道雄:さらし風手事 琴デュエット3.唯是震一:神仙調舞曲 琴ソロ4.石川勾当:新青柳アンコール曲 長澤勝俊?:花吹雪画像は、パンフレット、プログラム、開演前のホール、演奏中の二人。
2013.01.12
コメント(0)
-

一日中家で過ごす
今日も、一時マンションの周りを散歩した以外は一日中家で過ごした。年賀状の整理、ジパング倶楽部イベントへの申し込み、読書(句集)、ビデオ鑑賞、年賀パズル解き、写真の整理、(ほか何をしたか覚えていない)などをした。夜はテレビの金曜劇場で「コクリコ坂」を見た。 高大から来年の入学許可書が来た。もう一年、高大で学ぶことができそうだ。今日の画像は、マンションの周りで今咲いている花。山茶花全盛で、ほかの花はあまり多くない。
2013.01.11
コメント(0)
-

黛まどか句集「てつぺんの星」を読む
今日は一日中家にいて、黛まどかの第7句集「てつぺんの星」を読み、佳句を抜きだしたりしたり、録画した番組を見たり、雑事をしたりして過ごした。黛まどかは1994年「B面の夏」で俳人デビューした女流俳人。5,6年前に読んだことがあるが、お色気たっぷりの句が多かった。その後の「京都の恋」も読んだが、その後の句集は読んでいなかった。B面の夏の句には次のような句があった。 ・水着選ぶいつしか彼の眼となつて まどか ・星涼しここにあなたのゐる不思議 ・会いたくて逢いたくて踏む薄氷 ・夕焼の中に脱ぐもの透きとほる ・うしろからふいに目隠しされて秋 「てつぺんの星」は昨年3月の発刊で彼女の第7句集で、第6句集「忘れ貝」発刊後5年間の344句が収められている。黛まどかは読売新聞主催のおしゃれ句会の選者をしていて私も5年前の9月に一度だけ参加したことがある。「B面の夏」のような句ばかりでなく、分かりやすく馴染みやすい句を作る人だという印象を持った。今回の句集もそうした本格的な句が多かった。例えば、 ・囀りの中に母呼ぶ子の声も まどか ・七夕の竹に願ひの混み合へる ・しまひ湯に浮んで柚子の疵だらけ ・初景色スカイツリーを加へたる ・エッフェル塔収まり切れず初写真画像は、第1句集から第7集までの表紙。B面の夏、夏の恋、花ごろも、くちづけ、京都の恋、忘れ貝、てつぺんの星。最後は薬師寺でのおしゃれ句会のときのまどかさん。
2013.01.10
コメント(0)
-

春麗句会に参加
今日は、午前中はK病院へ診察に行ったあと、帰りに堀川戎の宵戎に参詣し、午後は春麗句会に参加した。堀川戎は笛、鉦、太鼓、三味線の音が境内に響き渡り、巫女が10人並んで参拝客に笑顔を振り播いていた。みんなそれぞれの福笹に縁起物をいろいろ付け、今年の運を呼んでいた。写真は堀川戎の宵戎の模様。春麗句会の句会は、まずまずの成績で、先生から4句選ばれうち2句が特選だった。特選に選ばれたのは次の句。 ◎寒牡丹対話のできる距離で見る こっぱん(先生特選ほか1) ◎門松の左右の違ひ観察し こっぱん(先生特選)選に選ばれたのは次の句。 〇初詣初立ち飲みとなりにけり こっぱん(先生選ほか1) 〇巫女たちの笑顔の並ぶ宵戎 こっぱん(先生選)
2013.01.09
コメント(0)
-

わいわいパソコンの例会、なにわの語り部劇場
今日は、午前中は昨日の句会のまとめを行い、午後は、わいわいパソコンの例会に参加、夜はなにわの語り部劇場を鑑賞した。わいわいパソコン例会は今月は梅田の生涯学習センターで行われ、インターネットを利用したパソコン利用例についてN氏から紹介があった。その中で、フリーソフト「craving Explorer」を用いたYou Tubeなどからの動画や音楽のダウンロードは大変使いやすいものだった。いろいろな音楽や落語、テレビ番組などが簡単にダウンロードできるので、時間の許す限り楽しんだ。例会後、新年会に途中まで参加して、「なにわの語り部劇場」の会場ガスビルへ急いだ。このイベントは大阪ガスエネルギー・文化研究所の主催で、大阪の歴史・文化を伝えるため、テーマごとに映像と音楽と朗読を組み合わせた作品を発表しているもの。これまで、曾根崎心中、大阪モダニズム、道頓堀・心斎橋、淀川ものがたり、織田作之助の世界などを上演して北が、今日のテーマは「通天閣」だった。会は18時30分に始まり、木全研究所所長の挨拶、栗本主席研究員の趣旨説明につづいて「通天閣ものがたり」が上演された。出演は語り:栗本智代、ピアノ:宮川真由美、ヴァイオリン:西村恵一、パーカッション:池田安友子の4人だった。内容は、初代通天閣の建設に至る経過、ビリケンの歴史、建設後のルナパーク、新世界の繁栄、戦時中の火災・倒壊、戦後の2代目通天閣の建設運動、100年を迎えた現在の通天閣などで、豊富な映像資料と分かり易い解説朗読と音楽演奏により、楽しく鑑賞することができた。途中、フル演奏されたモンティのチャルダッシュは見事だった。写真は、上:例会風景と「Craving Explorer」の画面例。下:なにわの語り部劇場の模様。
2013.01.08
コメント(0)
-

今日は句会
今日はいきいき俳句会の初句会の日、午前中は資料のプリントのあと5句の選定の最後の推敲を行った。句会に成績はあまり振るわなかったが、先生からは2句選ばれ、うち一句は特選だった。先生に選ばれたのは次の句。 ◎食べ過ぎてつい飲み過ぎて寝正月 こっぱん(先生特選ほか1票) 〇若者に席ゆづられし初電車 こっぱん(先生ほか1票)今日、先生の特選にえらばれたのは、上記のほか次の句。 ◎遠耳に大きな声の御慶かな 隆司(先生特選)今日最高得票を得たのは先生の句だが他には次の句。 〇初夢の何かを見しが忘れけり 昇一(先生ほか4票) 〇口紅の色少し変へ初鏡 愛子(先生ほか4票) 〇先づ健康夫の挨拶屠蘇祝ふ 茲子(先生ほか4票) 〇動かざる生駒稜線初茜 洋子(先生ほか4票) 〇毎年の繰り言なれど今年こそ 光祐(先生ほか4票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎年新た特に決意もなかりけり 塩川雄三先生(6票)写真は中央公会堂を背景に句会風景。
2013.01.07
コメント(0)
-

新春カモ観察会、築港俳句会新年会
今日は、、午前中は大阪自然環境保全教会主催の新春カモ観察会に参加し、午後は築港俳句会の新年会に参加した。新春カモ観察会は毎年参加しているが、寒い日が多い。しかし今日は穏やかな日で絶好の観察日和であった。カモ観察会という名称だが、カモ以外の鳥もいろいろ見ることができた。イソヒヨドリ、ベニマシコ、オオジュリン、コチドリ、ハマシギ、ミサゴなどを見ることができた。また、カワウの500羽くらいの群れが飛ぶのも見た。写真は、阪神淀川駅前に集まった参加者、カモの群れ、岩場で休むカモの群れ、カワラヒワとベニマシコ、カワラヒワ、オオジュリン、百合鴎、ハマシギ、コチドリ。カモ観察会を終え、食事をしてから法円坂の築港俳句会の新年会会場に駆け付けた。新年会には毎年参加しているが、句会の成績はいつも悪い。今日も5句のうち先生からは一句も選ばれず、仲間から3句が選ばれ、2句はだれからも選ばれなかった。句会のあとは新年祝賀会となった。会では、挨拶のあと、鶴首表彰が行われた。写真は、S氏による乾杯、塩川雄三主宰の挨拶、祝賀会風景、課題句会優秀者の表彰、事前投句優秀者の表彰、当日句会優秀者の表彰、祝賀会風景、参加者ひとこと挨拶、同。
2013.01.06
コメント(0)
-

オペラ「タンホイザー」を見る
今日は、午前中に図書館へ行き、午後は借りて来たオペラ「タンホイザー」を見た。名前は聞いたことがあるが見るのは初めてであった。「タンホイザー」はワーグナーの作品で初演は1845年。3幕3時間の長いオペラ。先日見た「魔笛」も宗教色の強いものだったが、「タンホイザー」はさらに宗教色が強いあ。主役タンホイザーは若気の至りで過ちを冒すが、懺悔と苛酷な難行・苦行を行ったにも拘わらず許されず遂に恋人とともに死んでいくという悲劇である。エンディングでは「これで二人とも天国へ行ける」と賛美する。画像は、ビデオおよび解説本より。上中はバイエルン国立歌劇場、中下はオペラの舞台となったヴァルトブルグ城
2013.01.05
コメント(0)
-

年賀パズル、ビデオ鑑賞など
今日は、一時散歩に出たほかは殆んど家で過ごし、年賀パズルを考えたり、正月の間に録ったビデオを見たりしながら過ごした。ビデオは「楽吉左衛門」や「佐々木監督と漫画雑誌編集長」など。写真は、十日戎の準備の整った堀川戎神社。
2013.01.04
コメント(0)
-

買初め
今日は午前中はテレビやビデオを見て過ごし、午後から外出し、ヨドバシカメラでBD-Rなどを買初めしたあと、デパート廻りをした。BD-Rは昨年買ったときは10枚1500円くらいだったが、今日は830円とかなり安くなっていた。一枚25ギガで83円だから、DVDーR一枚4.3ギガで30円と較べても割安な記録媒体だと思う。その他、延長コード、電球などを買ったり、買い替えのためのテレビや洗濯器を物色した。デパートは伊勢丹三越、大丸、阪急、阪神を見て回った。どのデパートも満員だったが特に阪急の混雑度は凄かった。今日の写真はマンションのベランダからの今日の日の出。大阪の日の出時刻は7時7分だが、この写真は7時19分。生駒山の高さの分だけ遅れるのだ。ビルはOBPのビル群、右の↓の下は大阪城。
2013.01.03
コメント(0)
-

初詣、義母の見舞い
今日は、午前中は、大晦日に録画した「第九」を見たあと大阪天満宮へ初詣、午後は、介護施設に義母を見舞った。天満宮は2日だったことと午前中であったこととで、昨日とは打って変って静かな境内だった。来年から初詣は2日に来ることにしよう。古い破魔矢を納め、参拝をし、新しい破魔矢を買って帰った。写真は今日午前の境内の模様。義母は今年数え年で99歳となった。認知症が少しあり言葉が聴き取りにくいが、こちらのいうことが理解できるので、何とかコミュニケーションはできる。車椅子依存の生活だが、身体は元気で食欲は旺盛である。いろいろな話をしたり、車椅子を押して館内を回ったりした。帰宅後は、テレビで「白虎隊」を見た。
2013.01.02
コメント(0)
-

謹賀新年
新らしい年2013年が明けました。おめでとうございます。今年もどうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。私の年賀状をお届けいたします。左は切手収集仲間用、右はパズル愛好家用です。以下日記今日から新年、昨夜は紅白が終ってから就寝し、今朝は6時半に起床した。テレビで「苔寺の四季」を見ながら、お屠蘇とお節を味わった。10時に郵便箱を見・に行ったら年賀状が来ていたので、一通り目を通す。受け取ったが出していない人に賀状を書く。例年午前中に済ませる大阪天満宮への初詣への出発が正午を過ぎてしまった。例年人出は多いが30分くらい並べば入れていたが、今日行って驚いた。長い列が道路一杯に広がって数十メートル続いていた。しばらく行列に並んでいたが遅々として進まないので、今日は参詣をあきらめた。明日に延期することにした。帰宅後は、届いた年賀パズルの問題を解きながら、テレビを見て過ごした。夜はウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサートを楽しんだ。写真は、マンションのベランダから見た初日の出。
2013.01.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1